「津田青楓」管見(その二) [東洋城・豊隆・青楓]
(その二) 『明暗(夏目漱石著・岩波書店)』(「装幀・青楓画」)・「漱石山房と其弟子達」(青楓画)・「婦人と金絲雀鳥(津田青楓画)」・「「出雲崎の女(津田青楓画)」周辺
E3808D.jpg)
「津田青楓・自撰年譜(大正六年~大正十二年)」(『書道と芸術(津田青楓著)』所収)
https://dl.ndl.go.jp/pid/2459907/1/76
※大正六年(一九一七) 三十八歳
『明暗(夏目漱石著・岩波書店)』の装幀を為す。

「装幀(津田青楓)/『明暗(夏目漱石著・岩波書店)』/大正六年(一九一七)」(『漱石と十弟子(津田青楓著・芸艸堂刊)』(昭和四十九年)の口絵写真の冒頭のもの=モノクロ)
https://www.bungakukan.or.jp/item/3342/
https://yahan.blog.ss-blog.jp/2023-12-17
※大正七年(一九一八) 三十九歳
「俳画展」に「漱石と十弟子」と題する二曲屏風半双を為す。(この作品今小山店主の主の有也。) 画中の人物、安倍能成・寺田寅彦・鈴木三重吉・阿部次郎・小宮豊隆・森田草平・野上臼川・赤木桁平・岩波茂雄・松根東洋城の十氏なり。
[ 蕉門の十哲といふ絵を見たことがある。芭蕉のお弟子十人を蕪村が俳画風にかいたものなのだ。私は大正七年ある人の主催で現代俳画展なるものの催のあつたとき、慫慂されたので、蕪村にならつて漱石と十弟子を思ひついて、二曲屏風半双を描いて出陳した。
それはいい工合に今度の空襲で灰になつてしまつた。当時は生存中の十人を一人々々写生し張りきつて描いた。それにもかかはらず後になつてみると随分未熟で見られなかつた。機を見てかき直しませうと、当時の持主に約束してゐたが、其の後戦争が勃発して持主の家も什器も焼けてしまつた。私は安心した。(後略) ](『漱石と十弟子(津田青楓著・芸艸堂刊)』)

『漱石と十弟子(津田青楓著・芸艸堂刊)』所収「漱石と十弟子」(津田青楓画)→C図

「漱石山房と其弟子達(津田青楓画)」→A図(「日本近代美術館蔵」)
https://obikake.com/column/10092/
https://blog.goo.ne.jp/torahiko-natsume/e/6ad1c4767dddc3568e6b34e7d727b501

「漱石と十弟子(津田青楓画)」昭和51(1976)年/紙本著色/A4判用(縦30.9cm×横22.0cm×厚さ0.04cm)→B図(「漱石山房記念館蔵」)
https://soseki-museum.jp/user-guide/museum-shop/
※ 上記の「A図」と「B図」については、下記のアドレスで紹介している。
https://yahan.blog.ss-blog.jp/2023-09-08
※大正十年(一九二一) 四十二歳

「ホトトギス(「表紙」絵・大正十年)
http://www.kyoshi.or.jp/j-eitopi/kanpo/040.pdf

「ホトトギス(「目次」・大正十年)(抜粋)
http://www.hototogisu.co.jp/
※「ホトトギス(300号記念号)の「表紙絵」を担当したのは津田青風にとっては、その「挿絵」を担当した「小川芋銭・石井柏亭・森田恒友・小川千甕」ともども、一つのエポックであったことであろう。
[(補記・「ウィキペディア」など)
小川芋銭(「1868年3月11日(慶応4年2月18日) - 1938年(昭和13年)12月17日)は、日本の画家。19世紀から20世紀前半にかけて活躍した日本の日本画家。」)
石井柏亭(「石井柏亭(1882-1958)は、洋画家として油彩画だけでなく、水彩画、版画、日本画と幅広いジャンルの作品を残しました。さらに、歌人、詩人、批評家、著述家、教育者としても活躍をしました。」)
森田恒友(「1881-1933(明治14-昭和8))、1906(明治39)年、東京美術学校西洋画科卒業。文展に出品。14~15(大正3~4)年に渡欧、帰国後水墨画の制作を始める。22(大正11)年、岸田劉生らと春陽会を創立、以後春陽会を中心に作品を発表。29(昭和4)年、帝国美術学校西洋画科の教授となる。セザンヌほかに学び油彩画を描いたが、一方で南画の理解と制作に励み、特に関東平野の風土をモチーフとして独自の詩情にあふれた水墨画を描いた。)」
小川千甕 (「1882年10月3日 - 1971年2月8日)は、京都市出身の仏画師・洋画家・漫画家・日本画家。本名は小川多三郎。後に、自由な表現できる日本画である「南画」を追求。多くの作品を発表し、戦後にかけて文人への憧れから「詩書画」を多く手掛けるようになる。) 」
※大正十一年(一九二二) 四十三歳

https://www.shiryodo.jp/shiryo_pcard_d.html
※「第九回二科展へ『黒き文庫』」「舞子の顔」等を出品す。」(『書道と画道 (市民文庫 ; 第106)』)(「国立国会図書館デジタルコレクション」)
※大正十二年(一九二三) 四十四歳
.gif)
「婦人と金絲雀鳥(津田青楓画)/1920/油彩/116.7×73.0/(モデルは敏子)」(「東京国立近代美術館」蔵)
https://www.momat.go.jp/collection/o00277
[ 一九二三年(大正十二)の第十回二科会出品作。文庫本を手に椅子にかける洋装の女性が描かれている。後ろに置かれた衝立は、岩場に立つ鶴が立つ鶴が描かれた作品(※別記)と同図柄であり、当時の妻山脇敏子をモデルに描いた作品である。画面の構成上、足下に鳥籠があれば良いと思い、自分好みのかたちのものを見つけるまでに随分苦労し、完成までに長い時間がかかったようだ。青楓は、ここに描かれた鳥籠が中国製だといい、椅子は中国の坊主がかけるような椅子と表現する。青楓のもつ中国趣味垣間見える。(K=喜多孝臣)](『背く画家 津田青楓とあゆむ明治・大正・昭和/津田青楓 著/喜多孝臣 編・解説)』所収「作品132解説」)
-2e89e.jpg)
「出雲崎の女(津田青楓画)/ 1923/96.5×146.5(モデルは「出雲崎の宿(『くまき』の娘))」/「東京国立近代美術館」蔵))
[ 一九二三年(大正十二)の第十回二科会出品作。新潟出雲崎は良寛の出生地である。一九二二年(大正十一)、青楓は良寛開堂式に招かれ、ここをはじめて訪れた。本作のモデルは、そのときに泊まった宿屋の娘で、「顔かたちにとても特殊的な感覚をもつてゐる」ことに惹きつけられ、モデルをお願いし、描いたという。壺や団扇、開いて置かれた本、足下にいる黒猫など、細部の道具立てへのこだわりや、モデルの肌の茶味を帯びた渋い独自の色彩表現は、その後の青楓の油絵にもしばしば見受けられる。(K=喜多孝臣)](『背く画家 津田青楓とあゆむ明治・大正・昭和/津田青楓 著/喜多孝臣 編・解説)』所収「作品133解説」)
(参考「「着衣のマハ」(左)と「裸のマハ」(右)との関連)
E3808DE381A8E3808CE8A3B8E381AEE3839EE3838F(E58FB3)E3808D.jpg)
「着衣のマハ(左)」と「裸のマハ(右)」(「フランシスコ・デ・ゴヤ」作)
[(着衣のマハ」=「ウィキペディア」=『着衣のマハ』(ちゃくいのマハ、スペイン語: La maja vestida)は、スペインの画家フランシスコ・デ・ゴヤによって描かれた油絵である。マドリードのプラド美術館所蔵。『裸のマハ』の直後に描かれている。その真意は、製作依頼者であるマヌエル・デ・ゴドイの19世紀初めの自宅改装の際の『裸のマハ』に関するカモフラージュであると考えられている。)](「ウィキペディア」)
(再掲) 寺田寅彦の随筆「震災日記より
https://yahan.blog.ss-blog.jp/2023-11-09
[ 寺田寅彦の随筆「震災日記より」(旧字・旧仮名) (抜粋)
http://sybrma.sakura.ne.jp/394torahiko.shinsainikki.html
九月一日。(土曜)
朝はしけ模樣で時々暴雨が襲つて來た。非常な強度で降つて居ると思ふと、まるで斷ち切つたやうにぱたりと止む、さうかと思ふと又急に降り出す實に珍らしい斷續的な降り方であつた。雜誌「文化生活」への原稿「石油ラムプ」を書き上げた。雨が收まつたので上野二科會展招待日の見物に行く。會場に入つたのが十時半頃。蒸暑かつた。フランス展の影響が著しく眼についた。T君(※津田青楓)と喫茶店で紅茶を呑みながら同君の出品畫「I崎の女」(※津田の作品「出雲崎の女)に對する其モデルの良人からの撤囘要求問題の話を聞いて居るうちに急激な地震を感じた。椅子に腰かけて居る兩足の蹠を下から木槌で急速に亂打するやうに感じた。多分其前に來た筈の弱い初期微動を氣が付かずに直ちに主要動を感じたのだらうといふ氣がして、それにしても妙に短週期の振動だと思つて居るうちにいよいよ本當の主要動が急激に襲つて來た。同時に、此れは自分の全く經驗のない異常の大地震であると知つた。其瞬間に子供の時から何度となく母上に聞かされてゐた土佐の安政地震の話がありあり想出され、丁度船に乘つたやうに、ゆたりゆたり搖れると云ふ形容が適切である事を感じた。仰向いて會場の建築の搖れ工合を注意して見ると四五秒程と思はれる長い週期でみしみしみしみしと音を立てながら緩やかに搖れて居た。それを見たとき此れなら此建物は大丈夫だといふことが直感されたので恐ろしいといふ感じはすぐになくなつてしまつた。さうして、此珍らしい強震の振動の經過を出來るだけ精しく觀察しようと思つて骨を折つて居た。
主要動が始まつてびつくりしてから數秒後に一時振動が衰へ、此分では大した事もないと思ふ頃にもう一度急激な、最初にも増した烈しい波が來て、二度目にびつくりさせられたが、それからは次第に減衰して長週期の波ばかりになつた。
同じ食卓に居た人々は大抵最初の最大主要動で吾勝に立上つて出口の方へ驅出して行つたが、自分等の筋向ひに居た中年の夫婦は其時は未だ立たなかつた。しかも其夫人がビフテキを食つて居たのが、少くも見たところ平然と肉片を口に運んで居たのがハツキリ印象に殘つて居る。併し二度目の最大動が來たときは一人殘らず出てしまつて場内はがらんとしてしまつた。油畫の額はゆがんだり、落ちたりしたのもあつたが大抵はちやんとして懸かつて居るやうであつた。此れで見ても、さう此建物の震動は激烈なものでなかつたことがわかる。あとで考へて見ると、此れは建物の自己週期が著しく長いことが有利であつたのであらうと思はれる。震動が衰へてから外の樣子を見に出ようと思つたが喫茶店のボーイも一人殘らず出てしまつて誰れも居ないので勘定をすることが出來ない。それで勘定場近くの便所の口へ出て低い木柵越しに外を見ると、其處に一團、彼處に一團といふ風に人間が寄集つて茫然として空を眺めて居る。此便所口から柵を越えて逃出した人々らしい。空はもう半ば晴れて居たが千切れ千切れの綿雲が嵐の時のやうに飛んで居た。その内にボーイの一人が歸つて來たので勘定をすませた。ボーイがひどく丁寧に禮を云つたやうに記憶する。出口へ出ると其處では下足番の婆さんが唯一人落ち散らばつた履物の整理をして居るのを見付けて、預けた蝙蝠傘を出して貰つて館の裏手の集團の中からT畫伯を捜しあてた。同君の二人の子供も一緒に居た。其時氣のついたのは附近の大木の枯枝の大きなのが折れて墜ちて居る。地震の爲に折れ落ちたのかそれとも今朝の暴風雨で折れたのか分らない。T君に別れて東照宮前の方へ歩いて來ると異樣な黴臭い匂が鼻を突いた。空を仰ぐと下谷の方面からひどい土ほこりが飛んで來るのが見える。此れは非常に多數の家屋が倒潰したのだと思つた、同時に、此れでは東京中が火になるかも知れないと直感された。東照宮前から境内を覗くと石燈籠は一つ殘らず象棋倒しに北の方へ倒れて居る。大鳥居の柱は立つて居るが上の横桁が外れかゝり、しかも落ちないで危く止つて居るのであつた。精養軒のボーイ達が大きな櫻の根元に寄集つて居た。大佛の首の落ちた事は後で知つたがその時は少しも氣が付かなかつた。池の方へ下りる坂脇の稻荷の鳥居も、柱が立つて桁が落ち碎けて居た。坂を下りて見ると不忍辨天の社務所が池の方へのめるやうに倒れかゝつて居るのを見て、なる程此れは大地震だなといふことが漸くはつきり呑込めて來た。
無事な日の續いて居るうちに突然に起つた著しい變化を充分にリアライズするには存外手數が掛かる。此日は二科會を見てから日本橋邊へ出て晝飯を食ふつもりで出掛けたのであつたが、あの地震を體驗し下谷の方から吹上げて來る土埃りの臭を嗅いで大火を豫想し東照宮の石燈籠のあの象棋倒しを眼前に見ても、それでも未だ晝飯のプログラムは帳消しにならずそのまゝになつて居た。併し辨天社務所の倒潰を見たとき初めて此れはいけないと思つた、さうして始めて我家の事が少し氣懸りになつて來た。
辨天の前に電車が一臺停つたまゝ動きさうもない。車掌に聞いても何時動き出すか分らないといふ。後から考へると此んなことを聞くのが如何な非常識であつたかゞよく分るのであるが、其當時自分と同樣の質問を車掌に持出した市民の數は萬を以て數へられるであらう。
動物園裏迄來ると道路の眞中へ疊を持出して其上に病人をねかせて居るのがあつた。人通りのない町はひつそりして居た。根津を拔けて歸るつもりであつたが頻繁に襲つて來る餘震で煉瓦壁の頽れかゝつたのがあらたに倒れたりするのを見て低濕地の街路は危險だと思つたから谷中三崎町から團子坂へ向つた。谷中の狹い町の兩側に倒れかゝつた家もあつた。鹽煎餅屋の取散らされた店先に烈日の光がさして居たのが心を引いた。團子坂を上つて千駄木へ來るともう倒れかゝつた家などは一軒もなくて、所々唯瓦の一部分剝がれた家があるだけであつた。曙町へはいると、一寸見たところでは殆ど何事も起らなかつたかのやうに森閑として、春のやうに朗かな日光が門並を照して居る。宅の玄關へはいると妻は箒を持つて壁の隅々からこぼれ落ちた壁土を掃除して居るところであつた。隣の家の前の煉瓦塀はすつかり道路へ崩れ落ち、隣と宅の境の石垣も全部、此れは宅の方へ倒れて居る。若し裏庭へ出て居たら危險なわけであつた。聞いて見ると可なりひどいゆれ方で居間の唐紙がすつかり倒れ、猫が驚いて庭へ飛出したが、我家の人々は飛出さなかつた。此れは平生幾度となく家族に云ひ含めてあつたことの效果があつたのだといふやうな氣がした。ピアノが臺の下の小滑車で少しばかり歩き出して居り、花瓶臺の上の花瓶が板間にころがり落ちたのが不思議に碎けないでちやんとして居た。あとは瓦が數枚落ちたのと壁に龜裂が入つた位のものであつた。長男が中學校の始業日で本所の果迄行つて居たのだが地震のときはもう歸宅して居た。それで、時々の餘震はあつても、その餘は平日と何も變つたことがないやうな氣がして、ついさきに東京中が火になるだらうと考へたことなどは綺麗に忘れて居たのであつた。
その内に助手の西田君が來て大學の醫化學敎室が火事だが理學部は無事だといふ。N君が來る。隣のTM敎授が來て市中所々出火だといふ。縁側から見ると南の空に珍らしい積雲が盛り上つて居る。それは普通の積雲とは全くちがつて、先年櫻島大噴火の際の噴雲を寫眞で見るのと同じやうに典型的の所謂コーリフラワー狀のものであつた。餘程盛な火災の爲に生じたものと直感された。此雲の上には實に東京ではめつたに見られない紺靑の秋の空が澄み切つて、じりじり暑い殘暑の日光が無風の庭の葉鷄頭に輝いて居るのであつた。さうして電車の音も止り近所の大工の音も止み、世間がしんとして實に靜寂な感じがしたのであつた。
夕方藤田君が來て、圖書館と法文科も全燒、山上集會所も本部も燒け、理學部では木造の數學敎室が燒けたと云ふ。夕食後E君と白山へ行つて蠟燭を買つて來る。TM氏が來て大學の樣子を知らせてくれた。夜になつてから大學へ樣子を見に行く、圖書館の書庫の中の燃えて居るさまが窓外からよく見えた。一晩中位はかゝつて燃えさうに見えた。普通の火事ならば大勢の人が集つて居るであらうに、あたりには人影もなく唯野良犬が一匹そこいらにうろうろして居た。メートルとキログラムの副原器を收めた小屋の木造の屋根が燃えて居るのを三人掛りで消して居たが耐火構造の室内は大丈夫と思はれた。それにしても屋上に此んな燃草をわざわざ載せたのは愚な設計であつた。物理敎室の窓枠の一つに飛火が付いて燃えかけたのを秋山、小澤兩理學士が消して居た。バケツ一つだけで彌生町門外の井戸迄汲みに行つてはぶつかけて居るのであつた。此れも捨てゝ置けば建物全體が燒けてしまつたであらう。十一時頃歸る途中の電車通は露宿者で一杯であつた。火事で眞紅に染まつた雲の上には靑い月が照らして居た。
九月二日。曇
朝大學へ行つて破損の狀況を見廻つてから、本郷通を湯島五丁目邊迄行くと、綺麗に燒拂はれた湯島臺の起伏した地形が一目に見え上野の森が思ひもかけない近くに見えた。兵燹といふ文字が頭に浮んだ。又江戸以前の此邊の景色も想像されるのであつた。電線がかたまりこんがらがつて道を塞ぎ燒けた電車の骸骨が立往生して居た。土藏もみんな燒け、所々煉瓦塀の殘骸が交つて居る。焦げた樹木の梢が其儘眞白に灰をかぶつて居るのもある。明神前の交番と自働電話だけが奇蹟のやうに燒けずに殘つて居る。松住町迄行くと淺草下谷方面はまだ一面に燃えて居て黑煙と焰の海である。煙が暑く咽つぽく眼に滲みて進めない。其煙の奧の方から本郷の方へと陸續と避難して來る人々の中には顔も兩手も癩病患者のやうに火膨れのしたのを左右二人で肩に凭らせ引きずるやうにして連れて來るのがある。さうかと思ふと又反對に向ふへ行く人々の中には寫眞機を下げて遠足にでも行くやうな呑氣さうな樣子の人もあつた。淺草の親戚を見舞ふことは斷念して松住町から御茶の水の方へ上つて行くと、女子高等師範の庭は杏雲堂病院の避難所になつて居ると立札が讀まれる。御茶の水橋は中程の兩側が少し崩れただけで殘つて居たが駿河臺は全部焦土であつた。明治大學前に黑焦の死體がころがつて居て一枚の燒けたトタン板が被せてあつた。神保町から一ッ橋迄來て見ると氣象臺も大部分は燒けたらしいが官舎が不思議に殘つて居るのが石垣越しに見える。橋に火がついて燃えて居るので巡査が張番して居て人を通さない。自轉車が一臺飛んで來て制止にかまはず突切つて渡つて行つた。堀に沿うて牛が淵迄行つて道端で憩うて居ると前を避難者が引切なしに通る。實に色んな人が通る。五十恰好の女が一人大きな犬を一匹背中におぶつて行く、風呂敷包一つ持つて居ない。浴衣が泥水でも浴びたかのやうに黄色く染まつて居る。多勢の人が見て居るのも無關心のやうにわき見もしないで急いで行く。若い男で大きな蓮の葉を頭にかぶつて上から手拭でしばつて居るのがある。それから又氷袋に水を入れたのを頭にぶら下げて歩きながら、時々その水を煽つて居るのもある。と、土方風の男が一人繩か何かガラガラ引きずりながら引つぱつて來るのを見ると、一枚の燒けトタンの上に二尺角くらゐの氷塊をのつけたのを何となく得意げに引きずつて行くのであつた。さうした行列の中を一臺立派な高級自動車が人の流れに堰かれながら居るのを見ると、車の中には多分掛物でも入つて居るらしい桐の箱が一杯に積込まれて、その中にうづまるやうに一人の男が腰をかけてあたりを見廻して居た。
歸宅して見たら燒け出された淺草の親戚のものが十三人避難して來て居た。いづれも何一つ持出すひまもなく、昨夜上野公園で露宿して居たら巡査が來て○○人の放火者が徘徊するから注意しろと云つたさうだ。井戸に毒を入れるとか、爆彈を投げるとかさまざまな浮説が聞こえて來る。こんな場末の町へまでも荒して歩く爲には一體何千キロの毒藥、何萬キロの爆彈が入るであらうか、さういふ目の子勘定だけからでも自分にはその話は信ぜられなかつた。
夕方に駒込の通へ出て見ると、避難者の群が陸續と瀧野川の方へ流れて行く。表通の店屋などでも荷物を纏めて立退用意をして居る。歸つて見ると、近所でも家を引拂つたのがあるといふ。上野方面の火事がこの邊迄燒けて來ようとは思はれなかつたが萬一の場合の避難の心構だけはした。さて避難しようとして考へて見ると、どうしても持出さなければならないやうな物は殆ど無かつた。たゞ自分の描き集めた若干の油繪だけが一寸惜しいやうな氣がしたのと、人から預つて居たローマ字書きの書物の原稿に責任を感じたくらゐである。妻が三毛猫だけ連れてもう一匹の玉の方は置いて行かうと云つたら、子供等がどうしても連れて行くと云つてバスケットかなんかを用意して居た。
九月三日(月曜)曇後雨
朝九時頃から長男を板橋へやり、三代吉を賴んで白米、野菜、鹽などを送らせるやうにする。自分は大學へ出かけた。追分の通の片側を田舎へ避難する人が引切なしに通つた。反對の側は未だ避難して居た人が歸つて來るのや、田舎から入込んで來るのが反對の流れをなして居る。呑氣さうな顔をして居る人もあるが見ただけで隨分悲慘な感じのする人もある。負傷した片足を引きずり引きずり杖にすがつて行く若者の顔には何處へ行くといふあてもないらしい絶望の色があつた。夫婦して小さな躄車のやうなものに病人らしい老母を載せて引いて行く、病人が塵埃で眞黑になつた顔を仰向けて居る。
歸りに追分邊でミルクの罐やせんべいビスケットなど買つた。燒けた區域に接近した方面のあらゆる食料品店の店先はからつぽになつて居た。さうした食料品の缺乏が漸次に波及して行く樣が歴然とわかつた。歸つてから用心に鰹節、梅干、罐詰、片栗粉等を近所へ買ひにやる。何だか惡い事をするやうな氣がするが、二十餘人の口を託されて居るのだからやむを得ないと思つた。午後四時にはもう三代吉の父親の辰五郎が白米、薩摩芋、大根、茄子、醬油、砂糖など車に積んで持つて來たので少し安心する事が出來た。併し又この場合に、臺所から一車もの食料品を持込むのはかなり氣の引けることであつた。
E君に靑山の小宮君(※小宮豊隆)の留守宅の樣子を見に行つてもらつた。歸つての話によると、地震の時長男が二階に居たら書棚が倒れて出口をふさいだので心配した、それだけで別に異狀はなかつたさうである、その後は邸前の處に避難して居たさうである。
夜警で一緒になつた人で地震當時前橋に行つて居た人の話によると、一日の夜の東京の火事は丁度火柱のやうに見えたので大島の噴火でないかと云ふ噂があつたさうである。 (昭和十年十月) ]
E3808D.jpg)
「津田青楓・自撰年譜(大正六年~大正十二年)」(『書道と芸術(津田青楓著)』所収)
https://dl.ndl.go.jp/pid/2459907/1/76
※大正六年(一九一七) 三十八歳
『明暗(夏目漱石著・岩波書店)』の装幀を為す。

「装幀(津田青楓)/『明暗(夏目漱石著・岩波書店)』/大正六年(一九一七)」(『漱石と十弟子(津田青楓著・芸艸堂刊)』(昭和四十九年)の口絵写真の冒頭のもの=モノクロ)
https://www.bungakukan.or.jp/item/3342/
https://yahan.blog.ss-blog.jp/2023-12-17
※大正七年(一九一八) 三十九歳
「俳画展」に「漱石と十弟子」と題する二曲屏風半双を為す。(この作品今小山店主の主の有也。) 画中の人物、安倍能成・寺田寅彦・鈴木三重吉・阿部次郎・小宮豊隆・森田草平・野上臼川・赤木桁平・岩波茂雄・松根東洋城の十氏なり。
[ 蕉門の十哲といふ絵を見たことがある。芭蕉のお弟子十人を蕪村が俳画風にかいたものなのだ。私は大正七年ある人の主催で現代俳画展なるものの催のあつたとき、慫慂されたので、蕪村にならつて漱石と十弟子を思ひついて、二曲屏風半双を描いて出陳した。
それはいい工合に今度の空襲で灰になつてしまつた。当時は生存中の十人を一人々々写生し張りきつて描いた。それにもかかはらず後になつてみると随分未熟で見られなかつた。機を見てかき直しませうと、当時の持主に約束してゐたが、其の後戦争が勃発して持主の家も什器も焼けてしまつた。私は安心した。(後略) ](『漱石と十弟子(津田青楓著・芸艸堂刊)』)

『漱石と十弟子(津田青楓著・芸艸堂刊)』所収「漱石と十弟子」(津田青楓画)→C図

「漱石山房と其弟子達(津田青楓画)」→A図(「日本近代美術館蔵」)
https://obikake.com/column/10092/
https://blog.goo.ne.jp/torahiko-natsume/e/6ad1c4767dddc3568e6b34e7d727b501

「漱石と十弟子(津田青楓画)」昭和51(1976)年/紙本著色/A4判用(縦30.9cm×横22.0cm×厚さ0.04cm)→B図(「漱石山房記念館蔵」)
https://soseki-museum.jp/user-guide/museum-shop/
※ 上記の「A図」と「B図」については、下記のアドレスで紹介している。
https://yahan.blog.ss-blog.jp/2023-09-08
※大正十年(一九二一) 四十二歳

「ホトトギス(「表紙」絵・大正十年)
http://www.kyoshi.or.jp/j-eitopi/kanpo/040.pdf

「ホトトギス(「目次」・大正十年)(抜粋)
http://www.hototogisu.co.jp/
※「ホトトギス(300号記念号)の「表紙絵」を担当したのは津田青風にとっては、その「挿絵」を担当した「小川芋銭・石井柏亭・森田恒友・小川千甕」ともども、一つのエポックであったことであろう。
[(補記・「ウィキペディア」など)
小川芋銭(「1868年3月11日(慶応4年2月18日) - 1938年(昭和13年)12月17日)は、日本の画家。19世紀から20世紀前半にかけて活躍した日本の日本画家。」)
石井柏亭(「石井柏亭(1882-1958)は、洋画家として油彩画だけでなく、水彩画、版画、日本画と幅広いジャンルの作品を残しました。さらに、歌人、詩人、批評家、著述家、教育者としても活躍をしました。」)
森田恒友(「1881-1933(明治14-昭和8))、1906(明治39)年、東京美術学校西洋画科卒業。文展に出品。14~15(大正3~4)年に渡欧、帰国後水墨画の制作を始める。22(大正11)年、岸田劉生らと春陽会を創立、以後春陽会を中心に作品を発表。29(昭和4)年、帝国美術学校西洋画科の教授となる。セザンヌほかに学び油彩画を描いたが、一方で南画の理解と制作に励み、特に関東平野の風土をモチーフとして独自の詩情にあふれた水墨画を描いた。)」
小川千甕 (「1882年10月3日 - 1971年2月8日)は、京都市出身の仏画師・洋画家・漫画家・日本画家。本名は小川多三郎。後に、自由な表現できる日本画である「南画」を追求。多くの作品を発表し、戦後にかけて文人への憧れから「詩書画」を多く手掛けるようになる。) 」
※大正十一年(一九二二) 四十三歳

https://www.shiryodo.jp/shiryo_pcard_d.html
※「第九回二科展へ『黒き文庫』」「舞子の顔」等を出品す。」(『書道と画道 (市民文庫 ; 第106)』)(「国立国会図書館デジタルコレクション」)
※大正十二年(一九二三) 四十四歳
.gif)
「婦人と金絲雀鳥(津田青楓画)/1920/油彩/116.7×73.0/(モデルは敏子)」(「東京国立近代美術館」蔵)
https://www.momat.go.jp/collection/o00277
[ 一九二三年(大正十二)の第十回二科会出品作。文庫本を手に椅子にかける洋装の女性が描かれている。後ろに置かれた衝立は、岩場に立つ鶴が立つ鶴が描かれた作品(※別記)と同図柄であり、当時の妻山脇敏子をモデルに描いた作品である。画面の構成上、足下に鳥籠があれば良いと思い、自分好みのかたちのものを見つけるまでに随分苦労し、完成までに長い時間がかかったようだ。青楓は、ここに描かれた鳥籠が中国製だといい、椅子は中国の坊主がかけるような椅子と表現する。青楓のもつ中国趣味垣間見える。(K=喜多孝臣)](『背く画家 津田青楓とあゆむ明治・大正・昭和/津田青楓 著/喜多孝臣 編・解説)』所収「作品132解説」)
-2e89e.jpg)
「出雲崎の女(津田青楓画)/ 1923/96.5×146.5(モデルは「出雲崎の宿(『くまき』の娘))」/「東京国立近代美術館」蔵))
[ 一九二三年(大正十二)の第十回二科会出品作。新潟出雲崎は良寛の出生地である。一九二二年(大正十一)、青楓は良寛開堂式に招かれ、ここをはじめて訪れた。本作のモデルは、そのときに泊まった宿屋の娘で、「顔かたちにとても特殊的な感覚をもつてゐる」ことに惹きつけられ、モデルをお願いし、描いたという。壺や団扇、開いて置かれた本、足下にいる黒猫など、細部の道具立てへのこだわりや、モデルの肌の茶味を帯びた渋い独自の色彩表現は、その後の青楓の油絵にもしばしば見受けられる。(K=喜多孝臣)](『背く画家 津田青楓とあゆむ明治・大正・昭和/津田青楓 著/喜多孝臣 編・解説)』所収「作品133解説」)
(参考「「着衣のマハ」(左)と「裸のマハ」(右)との関連)
E3808DE381A8E3808CE8A3B8E381AEE3839EE3838F(E58FB3)E3808D.jpg)
「着衣のマハ(左)」と「裸のマハ(右)」(「フランシスコ・デ・ゴヤ」作)
[(着衣のマハ」=「ウィキペディア」=『着衣のマハ』(ちゃくいのマハ、スペイン語: La maja vestida)は、スペインの画家フランシスコ・デ・ゴヤによって描かれた油絵である。マドリードのプラド美術館所蔵。『裸のマハ』の直後に描かれている。その真意は、製作依頼者であるマヌエル・デ・ゴドイの19世紀初めの自宅改装の際の『裸のマハ』に関するカモフラージュであると考えられている。)](「ウィキペディア」)
(再掲) 寺田寅彦の随筆「震災日記より
https://yahan.blog.ss-blog.jp/2023-11-09
[ 寺田寅彦の随筆「震災日記より」(旧字・旧仮名) (抜粋)
http://sybrma.sakura.ne.jp/394torahiko.shinsainikki.html
九月一日。(土曜)
朝はしけ模樣で時々暴雨が襲つて來た。非常な強度で降つて居ると思ふと、まるで斷ち切つたやうにぱたりと止む、さうかと思ふと又急に降り出す實に珍らしい斷續的な降り方であつた。雜誌「文化生活」への原稿「石油ラムプ」を書き上げた。雨が收まつたので上野二科會展招待日の見物に行く。會場に入つたのが十時半頃。蒸暑かつた。フランス展の影響が著しく眼についた。T君(※津田青楓)と喫茶店で紅茶を呑みながら同君の出品畫「I崎の女」(※津田の作品「出雲崎の女)に對する其モデルの良人からの撤囘要求問題の話を聞いて居るうちに急激な地震を感じた。椅子に腰かけて居る兩足の蹠を下から木槌で急速に亂打するやうに感じた。多分其前に來た筈の弱い初期微動を氣が付かずに直ちに主要動を感じたのだらうといふ氣がして、それにしても妙に短週期の振動だと思つて居るうちにいよいよ本當の主要動が急激に襲つて來た。同時に、此れは自分の全く經驗のない異常の大地震であると知つた。其瞬間に子供の時から何度となく母上に聞かされてゐた土佐の安政地震の話がありあり想出され、丁度船に乘つたやうに、ゆたりゆたり搖れると云ふ形容が適切である事を感じた。仰向いて會場の建築の搖れ工合を注意して見ると四五秒程と思はれる長い週期でみしみしみしみしと音を立てながら緩やかに搖れて居た。それを見たとき此れなら此建物は大丈夫だといふことが直感されたので恐ろしいといふ感じはすぐになくなつてしまつた。さうして、此珍らしい強震の振動の經過を出來るだけ精しく觀察しようと思つて骨を折つて居た。
主要動が始まつてびつくりしてから數秒後に一時振動が衰へ、此分では大した事もないと思ふ頃にもう一度急激な、最初にも増した烈しい波が來て、二度目にびつくりさせられたが、それからは次第に減衰して長週期の波ばかりになつた。
同じ食卓に居た人々は大抵最初の最大主要動で吾勝に立上つて出口の方へ驅出して行つたが、自分等の筋向ひに居た中年の夫婦は其時は未だ立たなかつた。しかも其夫人がビフテキを食つて居たのが、少くも見たところ平然と肉片を口に運んで居たのがハツキリ印象に殘つて居る。併し二度目の最大動が來たときは一人殘らず出てしまつて場内はがらんとしてしまつた。油畫の額はゆがんだり、落ちたりしたのもあつたが大抵はちやんとして懸かつて居るやうであつた。此れで見ても、さう此建物の震動は激烈なものでなかつたことがわかる。あとで考へて見ると、此れは建物の自己週期が著しく長いことが有利であつたのであらうと思はれる。震動が衰へてから外の樣子を見に出ようと思つたが喫茶店のボーイも一人殘らず出てしまつて誰れも居ないので勘定をすることが出來ない。それで勘定場近くの便所の口へ出て低い木柵越しに外を見ると、其處に一團、彼處に一團といふ風に人間が寄集つて茫然として空を眺めて居る。此便所口から柵を越えて逃出した人々らしい。空はもう半ば晴れて居たが千切れ千切れの綿雲が嵐の時のやうに飛んで居た。その内にボーイの一人が歸つて來たので勘定をすませた。ボーイがひどく丁寧に禮を云つたやうに記憶する。出口へ出ると其處では下足番の婆さんが唯一人落ち散らばつた履物の整理をして居るのを見付けて、預けた蝙蝠傘を出して貰つて館の裏手の集團の中からT畫伯を捜しあてた。同君の二人の子供も一緒に居た。其時氣のついたのは附近の大木の枯枝の大きなのが折れて墜ちて居る。地震の爲に折れ落ちたのかそれとも今朝の暴風雨で折れたのか分らない。T君に別れて東照宮前の方へ歩いて來ると異樣な黴臭い匂が鼻を突いた。空を仰ぐと下谷の方面からひどい土ほこりが飛んで來るのが見える。此れは非常に多數の家屋が倒潰したのだと思つた、同時に、此れでは東京中が火になるかも知れないと直感された。東照宮前から境内を覗くと石燈籠は一つ殘らず象棋倒しに北の方へ倒れて居る。大鳥居の柱は立つて居るが上の横桁が外れかゝり、しかも落ちないで危く止つて居るのであつた。精養軒のボーイ達が大きな櫻の根元に寄集つて居た。大佛の首の落ちた事は後で知つたがその時は少しも氣が付かなかつた。池の方へ下りる坂脇の稻荷の鳥居も、柱が立つて桁が落ち碎けて居た。坂を下りて見ると不忍辨天の社務所が池の方へのめるやうに倒れかゝつて居るのを見て、なる程此れは大地震だなといふことが漸くはつきり呑込めて來た。
無事な日の續いて居るうちに突然に起つた著しい變化を充分にリアライズするには存外手數が掛かる。此日は二科會を見てから日本橋邊へ出て晝飯を食ふつもりで出掛けたのであつたが、あの地震を體驗し下谷の方から吹上げて來る土埃りの臭を嗅いで大火を豫想し東照宮の石燈籠のあの象棋倒しを眼前に見ても、それでも未だ晝飯のプログラムは帳消しにならずそのまゝになつて居た。併し辨天社務所の倒潰を見たとき初めて此れはいけないと思つた、さうして始めて我家の事が少し氣懸りになつて來た。
辨天の前に電車が一臺停つたまゝ動きさうもない。車掌に聞いても何時動き出すか分らないといふ。後から考へると此んなことを聞くのが如何な非常識であつたかゞよく分るのであるが、其當時自分と同樣の質問を車掌に持出した市民の數は萬を以て數へられるであらう。
動物園裏迄來ると道路の眞中へ疊を持出して其上に病人をねかせて居るのがあつた。人通りのない町はひつそりして居た。根津を拔けて歸るつもりであつたが頻繁に襲つて來る餘震で煉瓦壁の頽れかゝつたのがあらたに倒れたりするのを見て低濕地の街路は危險だと思つたから谷中三崎町から團子坂へ向つた。谷中の狹い町の兩側に倒れかゝつた家もあつた。鹽煎餅屋の取散らされた店先に烈日の光がさして居たのが心を引いた。團子坂を上つて千駄木へ來るともう倒れかゝつた家などは一軒もなくて、所々唯瓦の一部分剝がれた家があるだけであつた。曙町へはいると、一寸見たところでは殆ど何事も起らなかつたかのやうに森閑として、春のやうに朗かな日光が門並を照して居る。宅の玄關へはいると妻は箒を持つて壁の隅々からこぼれ落ちた壁土を掃除して居るところであつた。隣の家の前の煉瓦塀はすつかり道路へ崩れ落ち、隣と宅の境の石垣も全部、此れは宅の方へ倒れて居る。若し裏庭へ出て居たら危險なわけであつた。聞いて見ると可なりひどいゆれ方で居間の唐紙がすつかり倒れ、猫が驚いて庭へ飛出したが、我家の人々は飛出さなかつた。此れは平生幾度となく家族に云ひ含めてあつたことの效果があつたのだといふやうな氣がした。ピアノが臺の下の小滑車で少しばかり歩き出して居り、花瓶臺の上の花瓶が板間にころがり落ちたのが不思議に碎けないでちやんとして居た。あとは瓦が數枚落ちたのと壁に龜裂が入つた位のものであつた。長男が中學校の始業日で本所の果迄行つて居たのだが地震のときはもう歸宅して居た。それで、時々の餘震はあつても、その餘は平日と何も變つたことがないやうな氣がして、ついさきに東京中が火になるだらうと考へたことなどは綺麗に忘れて居たのであつた。
その内に助手の西田君が來て大學の醫化學敎室が火事だが理學部は無事だといふ。N君が來る。隣のTM敎授が來て市中所々出火だといふ。縁側から見ると南の空に珍らしい積雲が盛り上つて居る。それは普通の積雲とは全くちがつて、先年櫻島大噴火の際の噴雲を寫眞で見るのと同じやうに典型的の所謂コーリフラワー狀のものであつた。餘程盛な火災の爲に生じたものと直感された。此雲の上には實に東京ではめつたに見られない紺靑の秋の空が澄み切つて、じりじり暑い殘暑の日光が無風の庭の葉鷄頭に輝いて居るのであつた。さうして電車の音も止り近所の大工の音も止み、世間がしんとして實に靜寂な感じがしたのであつた。
夕方藤田君が來て、圖書館と法文科も全燒、山上集會所も本部も燒け、理學部では木造の數學敎室が燒けたと云ふ。夕食後E君と白山へ行つて蠟燭を買つて來る。TM氏が來て大學の樣子を知らせてくれた。夜になつてから大學へ樣子を見に行く、圖書館の書庫の中の燃えて居るさまが窓外からよく見えた。一晩中位はかゝつて燃えさうに見えた。普通の火事ならば大勢の人が集つて居るであらうに、あたりには人影もなく唯野良犬が一匹そこいらにうろうろして居た。メートルとキログラムの副原器を收めた小屋の木造の屋根が燃えて居るのを三人掛りで消して居たが耐火構造の室内は大丈夫と思はれた。それにしても屋上に此んな燃草をわざわざ載せたのは愚な設計であつた。物理敎室の窓枠の一つに飛火が付いて燃えかけたのを秋山、小澤兩理學士が消して居た。バケツ一つだけで彌生町門外の井戸迄汲みに行つてはぶつかけて居るのであつた。此れも捨てゝ置けば建物全體が燒けてしまつたであらう。十一時頃歸る途中の電車通は露宿者で一杯であつた。火事で眞紅に染まつた雲の上には靑い月が照らして居た。
九月二日。曇
朝大學へ行つて破損の狀況を見廻つてから、本郷通を湯島五丁目邊迄行くと、綺麗に燒拂はれた湯島臺の起伏した地形が一目に見え上野の森が思ひもかけない近くに見えた。兵燹といふ文字が頭に浮んだ。又江戸以前の此邊の景色も想像されるのであつた。電線がかたまりこんがらがつて道を塞ぎ燒けた電車の骸骨が立往生して居た。土藏もみんな燒け、所々煉瓦塀の殘骸が交つて居る。焦げた樹木の梢が其儘眞白に灰をかぶつて居るのもある。明神前の交番と自働電話だけが奇蹟のやうに燒けずに殘つて居る。松住町迄行くと淺草下谷方面はまだ一面に燃えて居て黑煙と焰の海である。煙が暑く咽つぽく眼に滲みて進めない。其煙の奧の方から本郷の方へと陸續と避難して來る人々の中には顔も兩手も癩病患者のやうに火膨れのしたのを左右二人で肩に凭らせ引きずるやうにして連れて來るのがある。さうかと思ふと又反對に向ふへ行く人々の中には寫眞機を下げて遠足にでも行くやうな呑氣さうな樣子の人もあつた。淺草の親戚を見舞ふことは斷念して松住町から御茶の水の方へ上つて行くと、女子高等師範の庭は杏雲堂病院の避難所になつて居ると立札が讀まれる。御茶の水橋は中程の兩側が少し崩れただけで殘つて居たが駿河臺は全部焦土であつた。明治大學前に黑焦の死體がころがつて居て一枚の燒けたトタン板が被せてあつた。神保町から一ッ橋迄來て見ると氣象臺も大部分は燒けたらしいが官舎が不思議に殘つて居るのが石垣越しに見える。橋に火がついて燃えて居るので巡査が張番して居て人を通さない。自轉車が一臺飛んで來て制止にかまはず突切つて渡つて行つた。堀に沿うて牛が淵迄行つて道端で憩うて居ると前を避難者が引切なしに通る。實に色んな人が通る。五十恰好の女が一人大きな犬を一匹背中におぶつて行く、風呂敷包一つ持つて居ない。浴衣が泥水でも浴びたかのやうに黄色く染まつて居る。多勢の人が見て居るのも無關心のやうにわき見もしないで急いで行く。若い男で大きな蓮の葉を頭にかぶつて上から手拭でしばつて居るのがある。それから又氷袋に水を入れたのを頭にぶら下げて歩きながら、時々その水を煽つて居るのもある。と、土方風の男が一人繩か何かガラガラ引きずりながら引つぱつて來るのを見ると、一枚の燒けトタンの上に二尺角くらゐの氷塊をのつけたのを何となく得意げに引きずつて行くのであつた。さうした行列の中を一臺立派な高級自動車が人の流れに堰かれながら居るのを見ると、車の中には多分掛物でも入つて居るらしい桐の箱が一杯に積込まれて、その中にうづまるやうに一人の男が腰をかけてあたりを見廻して居た。
歸宅して見たら燒け出された淺草の親戚のものが十三人避難して來て居た。いづれも何一つ持出すひまもなく、昨夜上野公園で露宿して居たら巡査が來て○○人の放火者が徘徊するから注意しろと云つたさうだ。井戸に毒を入れるとか、爆彈を投げるとかさまざまな浮説が聞こえて來る。こんな場末の町へまでも荒して歩く爲には一體何千キロの毒藥、何萬キロの爆彈が入るであらうか、さういふ目の子勘定だけからでも自分にはその話は信ぜられなかつた。
夕方に駒込の通へ出て見ると、避難者の群が陸續と瀧野川の方へ流れて行く。表通の店屋などでも荷物を纏めて立退用意をして居る。歸つて見ると、近所でも家を引拂つたのがあるといふ。上野方面の火事がこの邊迄燒けて來ようとは思はれなかつたが萬一の場合の避難の心構だけはした。さて避難しようとして考へて見ると、どうしても持出さなければならないやうな物は殆ど無かつた。たゞ自分の描き集めた若干の油繪だけが一寸惜しいやうな氣がしたのと、人から預つて居たローマ字書きの書物の原稿に責任を感じたくらゐである。妻が三毛猫だけ連れてもう一匹の玉の方は置いて行かうと云つたら、子供等がどうしても連れて行くと云つてバスケットかなんかを用意して居た。
九月三日(月曜)曇後雨
朝九時頃から長男を板橋へやり、三代吉を賴んで白米、野菜、鹽などを送らせるやうにする。自分は大學へ出かけた。追分の通の片側を田舎へ避難する人が引切なしに通つた。反對の側は未だ避難して居た人が歸つて來るのや、田舎から入込んで來るのが反對の流れをなして居る。呑氣さうな顔をして居る人もあるが見ただけで隨分悲慘な感じのする人もある。負傷した片足を引きずり引きずり杖にすがつて行く若者の顔には何處へ行くといふあてもないらしい絶望の色があつた。夫婦して小さな躄車のやうなものに病人らしい老母を載せて引いて行く、病人が塵埃で眞黑になつた顔を仰向けて居る。
歸りに追分邊でミルクの罐やせんべいビスケットなど買つた。燒けた區域に接近した方面のあらゆる食料品店の店先はからつぽになつて居た。さうした食料品の缺乏が漸次に波及して行く樣が歴然とわかつた。歸つてから用心に鰹節、梅干、罐詰、片栗粉等を近所へ買ひにやる。何だか惡い事をするやうな氣がするが、二十餘人の口を託されて居るのだからやむを得ないと思つた。午後四時にはもう三代吉の父親の辰五郎が白米、薩摩芋、大根、茄子、醬油、砂糖など車に積んで持つて來たので少し安心する事が出來た。併し又この場合に、臺所から一車もの食料品を持込むのはかなり氣の引けることであつた。
E君に靑山の小宮君(※小宮豊隆)の留守宅の樣子を見に行つてもらつた。歸つての話によると、地震の時長男が二階に居たら書棚が倒れて出口をふさいだので心配した、それだけで別に異狀はなかつたさうである、その後は邸前の處に避難して居たさうである。
夜警で一緒になつた人で地震當時前橋に行つて居た人の話によると、一日の夜の東京の火事は丁度火柱のやうに見えたので大島の噴火でないかと云ふ噂があつたさうである。 (昭和十年十月) ]
「津田青楓」管見(その一) [東洋城・豊隆・青楓]
(その一)「漱石の死に顔のスケッチ(津田青楓画)」周辺
.jpg)
「漱石の死に顔のスケッチ(津田青楓画)」(『漱石写真帖/著者・松岡譲 編/出版者・第一書房/出版年月日・昭和4』)(「国立国会図書館デジタルコレクション」)
https://dl.ndl.go.jp/pid/1688827/1/135
[漱石の十三回忌を記念し、漱石の長女筆子と結婚した松岡譲によって編まれた写真帖。漱石の生涯をたどることができるよう父祖から遺族の写真まで数多くの写真によって構成されている。ここに青楓による漱石の死に顔のスケッチが掲載されている。一九一六年(大正五)十二月十日葬送の折、棺蓋を開いて最後の別れをした際に写生したものである。スケッチそのものは門下の俳人東洋城が所蔵していたが、一九二三年(大正十二)の関東大震災の折に消失した。(K=喜多孝臣)](『背く画家 津田青楓とあゆむ明治・大正・昭和/津田青楓 著/喜夛孝臣 編・解説)』所収「資料32解説」)
[ 津田君の画には技巧がないと共に、人の意を迎へたり、世に媚びたりする態度がどこにも見えません。一直線に自分の芸術的良心に命令された通り動いて行くだけです。だから傍から見ると、自棄(やけ)に急いでゐるやうに見えます。又何うなつたつて構ふものかといふ投げ遣りの心持も出て来るのです。悪く云へば知恵の足りない芸術の忠僕のやうなものです。命令が下るか下らないうちに、もう手を出して相手を遣つ付けてしまつてゐるのです。従つてまともこのでもあります。(中略) 利害の念だの毀誉褒貶の苦痛だのといふ。一切の塵労俗累が混入してゐないのです。さうして其好所を津田君は自覚してゐるのです。―――夏目漱石「津田青楓氏」(「美術新報」一四巻一二号、一九一五年一〇月) ](『背く画家 津田青楓とあゆむ明治・大正・昭和/津田青楓著/芸艸堂刊』)
[ 津田君は嘗て桃山に閑居して居た事がある。其処で久しく人間から遠(ざ)かつて朝暮唯鳥声に親しんで居た頃、音楽といふ者は此の鳥の声のやうな者から出発すへき物ではないかと考へた事があるさうである。津田君が今日其作品に附する態度は矢張これと同じやうなものであるらしい。―――寺田寅彦「津田青楓君の画と南画の芸術的価値」(「中央公論」三十三巻八号、一九一八年八月) ](『背く画家 津田青楓とあゆむ明治・大正・昭和/津田青楓著/芸艸堂刊』)
(再掲) 「[漱石・十二月九日、漱石没(五十歳)。5月~12月、「明暗」。]
https://yahan.blog.ss-blog.jp/2023-10-18
2452 春風や故人に贈る九花蘭(「九花蘭」は五月頃に芳香のある黄緑色の花を開く。)
2453 白梅にしぶきかゝるや水車(2483までの三十一句は「手帳に記された句」。)
2454 孟宗の根を行く春の筧(かけひ)哉(同上)
2455 梅早く咲いて温泉(ゆ)の出る小村哉(同上)
2456 いち早き梅を見付けぬ竹の間(同上)
2457 梅咲くや日の旗立つる草の戸に(同上)
2458 裏山に蜜柑みのるや長者振(同上)
2459 温泉に信濃の客や春を待つ(同上)
2460 橙も黄色になりぬ温泉(ゆ)の流(同上)
2461 鶯に聞き入る茶屋の床几哉(同上)
2462 鶯や草鞋(わらじ)を易(か)ふる峠茶屋(同上)
2463 鶯や竹の根方に鍬の尻(同上)
2464 鶯や藪くゞり行く蓑一つ(同上)
2465 鶯を聴いてゐるなり縫箔屋(ぬいはくや)(同上。「縫箔屋」=衣服模様を業とする)
2466 鶯に餌をやる寮の妾かな(同上)
2467 温泉の里橙山の麓かな(同上)
2468 桃の花家に唐画を蔵しけり(同上)
2469 桃咲くやいまだに流行(はや)る漢方医(同上)
2470 輿(こし)に乗るは帰化の僧らし桃の花(同上)
2471 町儒者の玄関構や桃の花(同上)
2472 かりにする寺小屋なれど梅の花(同上)
2473 文も候(そろ)稚子(ちご)に持たせて桃の花(同上)
2474 琵琶法師召されて春の夜なりけり(同上)
2475 春雨や身をすり寄せて一つ傘(同上)
2476 鶯を飼ひて床屋の主人哉(同上)
2477 耳の穴掘つてもらひぬ春の風(同上)
2478 嫁の里向ふに見えて春の川(同上)
2479 岡持の傘にあまりて春の雨(同上)
2480 一燈の青幾更ぞ瓶の梅(同上)
2481 病める人枕に倚れば瓶の梅(同上)
2482 梅活けて聊(いささ)かなれど手習す(同上)
2483 桃に琴弾くは心越禅師哉(同上)
2484 秋立つや一巻の書の読み残し(「芥川龍之介宛書簡」九月二日)
2485 蝸牛や五月をわたるふきの茎(「画賛九月八日」)
2486 朝貌にまつはられてよ芒の穂(同上)
2487 萩と歯朶に賛書く月の団居哉(「夏目漱石遺墨集・第三巻」の画賛の句)
2488 棕櫚竹や月に背いて影二本(「自画賛九月八日」)
2489 秋立つ日猫の蚤取眼かな(「画賛九月」)
2490 秋となれば竹もかくなり俳諧師(同上)
2491 風呂吹きや頭の丸き影二つ(前書「禅僧二人宿して」、「十月」)
2492 煮て食ふかはた焼いてくふか春の魚(「画賛十月」)
2493 いたづらに書きたるものを梅とこそ(「自画賛十一月」)
2494 まきを割るかはた祖を割るか秋の空(「鬼村元成宛書簡」、「十一月十日」)
2495 饅頭に礼拝すれば晴れて秋(「富沢敬道宛書簡」、「十一月十五日」)
2496 饅頭は食つたと雁に言伝よ(同上)
2497 吾心点じ了りぬ正に秋(同上。前書「徳山の故事を思ひだして 一句」)
2498 僧のくれし此饅頭の丸きかな(同上。「無季」の句)
2499 瓢箪は鳴るか鳴らぬか秋の風(同上。前書「瓢箪はどうしました」)
(東洋城・三十九歳。虚子は大正二年、俳句に復活したが、四月、東洋城に無断で「国民俳壇」を手に入れた。爾後、虚子及び「ホトトギス」と絶縁し、「渋柿」によつて芭蕉を宗とし俳諧を道として立った。)
※怒る事知つてあれども水温む(前書「有感(大正五年四月十七日国民俳壇選者更迭発表の日)」)
[※「大正五年、虚子が俳句に復活し、四月十七日、東洋城はついに国民俳壇の選者を下りた。それというのも、国民新聞の社長・徳富蘇峰が、選者を下りてほしい旨、手紙を送ってきたためであった。東洋城はかねてより、社長からなにか言ってくるまで辞めないつもりだったが、読むと、かなり困って書いてきたものだとわかった。「仕方がない、社長は大将だ。ここまで書いてくるのは、よほどのことなのであろう」と、ついに下りることを承諾した。そして、
有感(感有リ)
いかること知つてあれども水温(ぬる)む
という句をつくり、以後虚子とは義絶した。九月には母の上京を促すため、帰郷した。末弟の宗一(そういち)が東京高商に入学するため上京し、以後、宇和島で独り住まいになっていた母の面倒を見るのは長男(※嫡男)の務めだと思い、同居の説得に行ったのだった。この年、東洋城にとって肉親の死にも等しい哀しいできごとがあった。十二月九日、漱石が死亡したのである。」(『渋柿の木の下で(中村英利子著)』) ]
用ふべき薬も絶えし火桶かな(前書「黒き枠の中より(「漱石先生の死))六句」)
木枯に深山木折るゝ音を聞け(同上)
埋火は灰の深きに消えにけり(同上)
祖父も父も繕ひし土塀冬日さす(同上)
ともし火に枯荷の月を観じけり(同上)
元日や人の心の一大事(同上)
[「東洋城はかって、父が亡くなるときにもこうして末期の水を捧げたが、師の漱石にも同じことをしていると思いながら、あと筆を進めず漱石の顔を見た。この時の東洋城の心には、師とか文豪などというものはなく、父を失ったときと同じ悲しみがあった。「先生、先生」、呼んだ後、漱石はふ―っと息を吐いたが、その後はもう続かない。真鍋が夫人に「お目を」と言い、夫人は手で静かに漱石の目をつむらせたが、初めから開いていないのをそうしたのは、永遠に安らかに瞑目させようとしたものだった。阿部学士検脈。真鍋学士検脈。退いて「すでに」と言う。部屋の中は、しのび泣きや声を上げて泣く声で満ちた。時に午後六時五十分。曇った日はすでに暮れ、闇の中に寒風がさみしく吹いた。
( 東洋城はこのあと、一連の葬儀に関して仕切り役ともいうべき重要な働きをした。しかし、それにもかかわらず、弟子たちのあいだに軋轢が生じた。」(『渋柿の木の下で(中村英利子著)』) ]

「夏目漱石の娘 愛子さん(「父漱石の霊に捧ぐ」より)」
http://enmi19.seesaa.net/article/463137651.html
(寅彦・三十九歳。十一月、東京帝国大学理科大学教授となる。十二月、胃潰瘍のため医者より絶対安静を命じられる。十二月九日、夏目漱石死亡。) →[『寺田寅彦全集/文学篇/七巻』には収載句は無い。
(以下略) ]
.jpg)
「津田青楓像」(寺田寅彦画)
https://yahan.blog.ss-blog.jp/2023-12-17
[「寺田寅彦の描いたスケッチ」(上=松根東洋城、下右=小宮豊隆、下左=津田青楓、昭和2年9月2日、塩原塩の湯明賀屋にて) (『寺田寅彦全集第十二巻』・月報12・1997年11月)のうち]
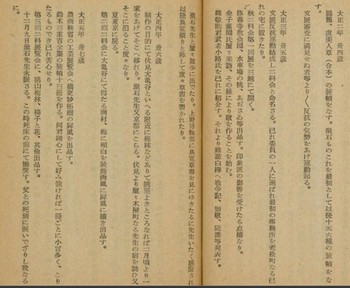
「津田青楓・自撰年譜(大正二年~大正五年)」(『書道と芸術(津田青楓著)』所収)
『書道と芸術(津田青楓著)』所収「自撰年譜」(「国立国会図書館デジタルコレクション」)
https://dl.ndl.go.jp/pid/2459907/1/75
※大正二年(一九一三) 三十四歳
六月 父西川源兵衛没
八月 長男安丸生まれる。漱石が名付け親となる。
十月 文展に落選し、漱石よりなぐさめの言葉が書かれた手紙を受け取る。
※大正三年(一九一四) 三十五歳
六月 文展に抗し、有島生馬、石井柏亭らと二科会を結成。
※大正四年(一九一五) 三十六歳
七月 京都桃山から東京小石川区老松町に移住する。
九月 次女「ふよう」生まれる。
十一月 師・谷口香嶠逝去
※大正五年(一九一六) 三十七歳
七月 長男安丸疫痢にて死す。
十二月九日 夏目漱石逝去。死床にて慟哭す。(※『背く画家 津田青楓とあゆむ明治・大正・昭和/津田青楓著/芸艸堂刊』所収「津田青楓年譜」抜粋)
.jpg)
「漱石の死に顔のスケッチ(津田青楓画)」(『漱石写真帖/著者・松岡譲 編/出版者・第一書房/出版年月日・昭和4』)(「国立国会図書館デジタルコレクション」)
https://dl.ndl.go.jp/pid/1688827/1/135
[漱石の十三回忌を記念し、漱石の長女筆子と結婚した松岡譲によって編まれた写真帖。漱石の生涯をたどることができるよう父祖から遺族の写真まで数多くの写真によって構成されている。ここに青楓による漱石の死に顔のスケッチが掲載されている。一九一六年(大正五)十二月十日葬送の折、棺蓋を開いて最後の別れをした際に写生したものである。スケッチそのものは門下の俳人東洋城が所蔵していたが、一九二三年(大正十二)の関東大震災の折に消失した。(K=喜多孝臣)](『背く画家 津田青楓とあゆむ明治・大正・昭和/津田青楓 著/喜夛孝臣 編・解説)』所収「資料32解説」)
[ 津田君の画には技巧がないと共に、人の意を迎へたり、世に媚びたりする態度がどこにも見えません。一直線に自分の芸術的良心に命令された通り動いて行くだけです。だから傍から見ると、自棄(やけ)に急いでゐるやうに見えます。又何うなつたつて構ふものかといふ投げ遣りの心持も出て来るのです。悪く云へば知恵の足りない芸術の忠僕のやうなものです。命令が下るか下らないうちに、もう手を出して相手を遣つ付けてしまつてゐるのです。従つてまともこのでもあります。(中略) 利害の念だの毀誉褒貶の苦痛だのといふ。一切の塵労俗累が混入してゐないのです。さうして其好所を津田君は自覚してゐるのです。―――夏目漱石「津田青楓氏」(「美術新報」一四巻一二号、一九一五年一〇月) ](『背く画家 津田青楓とあゆむ明治・大正・昭和/津田青楓著/芸艸堂刊』)
[ 津田君は嘗て桃山に閑居して居た事がある。其処で久しく人間から遠(ざ)かつて朝暮唯鳥声に親しんで居た頃、音楽といふ者は此の鳥の声のやうな者から出発すへき物ではないかと考へた事があるさうである。津田君が今日其作品に附する態度は矢張これと同じやうなものであるらしい。―――寺田寅彦「津田青楓君の画と南画の芸術的価値」(「中央公論」三十三巻八号、一九一八年八月) ](『背く画家 津田青楓とあゆむ明治・大正・昭和/津田青楓著/芸艸堂刊』)
(再掲) 「[漱石・十二月九日、漱石没(五十歳)。5月~12月、「明暗」。]
https://yahan.blog.ss-blog.jp/2023-10-18
2452 春風や故人に贈る九花蘭(「九花蘭」は五月頃に芳香のある黄緑色の花を開く。)
2453 白梅にしぶきかゝるや水車(2483までの三十一句は「手帳に記された句」。)
2454 孟宗の根を行く春の筧(かけひ)哉(同上)
2455 梅早く咲いて温泉(ゆ)の出る小村哉(同上)
2456 いち早き梅を見付けぬ竹の間(同上)
2457 梅咲くや日の旗立つる草の戸に(同上)
2458 裏山に蜜柑みのるや長者振(同上)
2459 温泉に信濃の客や春を待つ(同上)
2460 橙も黄色になりぬ温泉(ゆ)の流(同上)
2461 鶯に聞き入る茶屋の床几哉(同上)
2462 鶯や草鞋(わらじ)を易(か)ふる峠茶屋(同上)
2463 鶯や竹の根方に鍬の尻(同上)
2464 鶯や藪くゞり行く蓑一つ(同上)
2465 鶯を聴いてゐるなり縫箔屋(ぬいはくや)(同上。「縫箔屋」=衣服模様を業とする)
2466 鶯に餌をやる寮の妾かな(同上)
2467 温泉の里橙山の麓かな(同上)
2468 桃の花家に唐画を蔵しけり(同上)
2469 桃咲くやいまだに流行(はや)る漢方医(同上)
2470 輿(こし)に乗るは帰化の僧らし桃の花(同上)
2471 町儒者の玄関構や桃の花(同上)
2472 かりにする寺小屋なれど梅の花(同上)
2473 文も候(そろ)稚子(ちご)に持たせて桃の花(同上)
2474 琵琶法師召されて春の夜なりけり(同上)
2475 春雨や身をすり寄せて一つ傘(同上)
2476 鶯を飼ひて床屋の主人哉(同上)
2477 耳の穴掘つてもらひぬ春の風(同上)
2478 嫁の里向ふに見えて春の川(同上)
2479 岡持の傘にあまりて春の雨(同上)
2480 一燈の青幾更ぞ瓶の梅(同上)
2481 病める人枕に倚れば瓶の梅(同上)
2482 梅活けて聊(いささ)かなれど手習す(同上)
2483 桃に琴弾くは心越禅師哉(同上)
2484 秋立つや一巻の書の読み残し(「芥川龍之介宛書簡」九月二日)
2485 蝸牛や五月をわたるふきの茎(「画賛九月八日」)
2486 朝貌にまつはられてよ芒の穂(同上)
2487 萩と歯朶に賛書く月の団居哉(「夏目漱石遺墨集・第三巻」の画賛の句)
2488 棕櫚竹や月に背いて影二本(「自画賛九月八日」)
2489 秋立つ日猫の蚤取眼かな(「画賛九月」)
2490 秋となれば竹もかくなり俳諧師(同上)
2491 風呂吹きや頭の丸き影二つ(前書「禅僧二人宿して」、「十月」)
2492 煮て食ふかはた焼いてくふか春の魚(「画賛十月」)
2493 いたづらに書きたるものを梅とこそ(「自画賛十一月」)
2494 まきを割るかはた祖を割るか秋の空(「鬼村元成宛書簡」、「十一月十日」)
2495 饅頭に礼拝すれば晴れて秋(「富沢敬道宛書簡」、「十一月十五日」)
2496 饅頭は食つたと雁に言伝よ(同上)
2497 吾心点じ了りぬ正に秋(同上。前書「徳山の故事を思ひだして 一句」)
2498 僧のくれし此饅頭の丸きかな(同上。「無季」の句)
2499 瓢箪は鳴るか鳴らぬか秋の風(同上。前書「瓢箪はどうしました」)
(東洋城・三十九歳。虚子は大正二年、俳句に復活したが、四月、東洋城に無断で「国民俳壇」を手に入れた。爾後、虚子及び「ホトトギス」と絶縁し、「渋柿」によつて芭蕉を宗とし俳諧を道として立った。)
※怒る事知つてあれども水温む(前書「有感(大正五年四月十七日国民俳壇選者更迭発表の日)」)
[※「大正五年、虚子が俳句に復活し、四月十七日、東洋城はついに国民俳壇の選者を下りた。それというのも、国民新聞の社長・徳富蘇峰が、選者を下りてほしい旨、手紙を送ってきたためであった。東洋城はかねてより、社長からなにか言ってくるまで辞めないつもりだったが、読むと、かなり困って書いてきたものだとわかった。「仕方がない、社長は大将だ。ここまで書いてくるのは、よほどのことなのであろう」と、ついに下りることを承諾した。そして、
有感(感有リ)
いかること知つてあれども水温(ぬる)む
という句をつくり、以後虚子とは義絶した。九月には母の上京を促すため、帰郷した。末弟の宗一(そういち)が東京高商に入学するため上京し、以後、宇和島で独り住まいになっていた母の面倒を見るのは長男(※嫡男)の務めだと思い、同居の説得に行ったのだった。この年、東洋城にとって肉親の死にも等しい哀しいできごとがあった。十二月九日、漱石が死亡したのである。」(『渋柿の木の下で(中村英利子著)』) ]
用ふべき薬も絶えし火桶かな(前書「黒き枠の中より(「漱石先生の死))六句」)
木枯に深山木折るゝ音を聞け(同上)
埋火は灰の深きに消えにけり(同上)
祖父も父も繕ひし土塀冬日さす(同上)
ともし火に枯荷の月を観じけり(同上)
元日や人の心の一大事(同上)
[「東洋城はかって、父が亡くなるときにもこうして末期の水を捧げたが、師の漱石にも同じことをしていると思いながら、あと筆を進めず漱石の顔を見た。この時の東洋城の心には、師とか文豪などというものはなく、父を失ったときと同じ悲しみがあった。「先生、先生」、呼んだ後、漱石はふ―っと息を吐いたが、その後はもう続かない。真鍋が夫人に「お目を」と言い、夫人は手で静かに漱石の目をつむらせたが、初めから開いていないのをそうしたのは、永遠に安らかに瞑目させようとしたものだった。阿部学士検脈。真鍋学士検脈。退いて「すでに」と言う。部屋の中は、しのび泣きや声を上げて泣く声で満ちた。時に午後六時五十分。曇った日はすでに暮れ、闇の中に寒風がさみしく吹いた。
( 東洋城はこのあと、一連の葬儀に関して仕切り役ともいうべき重要な働きをした。しかし、それにもかかわらず、弟子たちのあいだに軋轢が生じた。」(『渋柿の木の下で(中村英利子著)』) ]

「夏目漱石の娘 愛子さん(「父漱石の霊に捧ぐ」より)」
http://enmi19.seesaa.net/article/463137651.html
(寅彦・三十九歳。十一月、東京帝国大学理科大学教授となる。十二月、胃潰瘍のため医者より絶対安静を命じられる。十二月九日、夏目漱石死亡。) →[『寺田寅彦全集/文学篇/七巻』には収載句は無い。
(以下略) ]
.jpg)
「津田青楓像」(寺田寅彦画)
https://yahan.blog.ss-blog.jp/2023-12-17
[「寺田寅彦の描いたスケッチ」(上=松根東洋城、下右=小宮豊隆、下左=津田青楓、昭和2年9月2日、塩原塩の湯明賀屋にて) (『寺田寅彦全集第十二巻』・月報12・1997年11月)のうち]
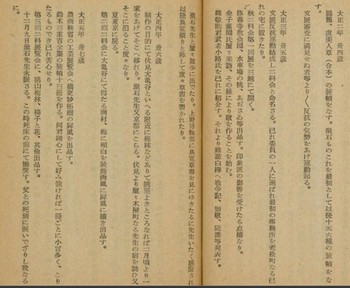
「津田青楓・自撰年譜(大正二年~大正五年)」(『書道と芸術(津田青楓著)』所収)
『書道と芸術(津田青楓著)』所収「自撰年譜」(「国立国会図書館デジタルコレクション」)
https://dl.ndl.go.jp/pid/2459907/1/75
※大正二年(一九一三) 三十四歳
六月 父西川源兵衛没
八月 長男安丸生まれる。漱石が名付け親となる。
十月 文展に落選し、漱石よりなぐさめの言葉が書かれた手紙を受け取る。
※大正三年(一九一四) 三十五歳
六月 文展に抗し、有島生馬、石井柏亭らと二科会を結成。
※大正四年(一九一五) 三十六歳
七月 京都桃山から東京小石川区老松町に移住する。
九月 次女「ふよう」生まれる。
十一月 師・谷口香嶠逝去
※大正五年(一九一六) 三十七歳
七月 長男安丸疫痢にて死す。
十二月九日 夏目漱石逝去。死床にて慟哭す。(※『背く画家 津田青楓とあゆむ明治・大正・昭和/津田青楓著/芸艸堂刊』所収「津田青楓年譜」抜粋)
東洋城・寅彦、そして、豊隆」(漱石没後~寅彦没まで)俳句・連句管見(その二十) [東洋城・寅日子(寅彦)・蓬里雨(豊隆)]
その二十「昭和十年(一九三五)」(続き)」
.jpg)
「渋柿(寺田寅彦追悼号の巻頭頁)」(第262号、昭和11年2月)(『寺田寅彦全集第十二巻』)
[ありし日の寺田寅彦 /A ペンを措きて /B 心明るく /C 家居 /D 晴れたる野]
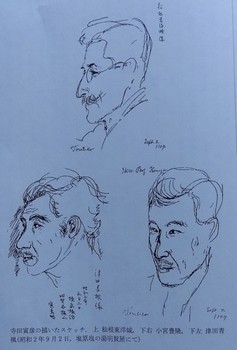
「寺田寅彦の描いたスケッチ」(上=松根東洋城、下右=小宮豊隆、下左=津田青楓、昭和2年9月2日、塩原塩の湯明賀屋にて) (『寺田寅彦全集第十二巻』・月報12・1997年11月)
※ 上記の寺田寅彦の写真四葉は、寅彦が亡くなった(昭和十年十二月三十一日没)翌年の昭和十一年(一九三六)二月号の「渋柿」(寺田寅彦追悼号)の巻頭頁に掲載されたものである。
そのページに掲載された文面([ありし日の寺田寅彦 /A ペンを措きて /B 心明るく /C 家居 /D 晴れたる野])は、おそらく、「渋柿」主宰者の「松根東洋城」が記述したもののように思われる。
この写真四葉(「A/B/C/D」)を、生前の「寺田寅彦」の四つ顔とすると、「A=ペンを措きて=画人/B=心明るく=科学者/C=家居=文人/D=晴れたる野=音楽家」と、「B=心明るく=科学者」と「C=家居=文人」との写真は、よく見掛けるもので、これをベースにして、「A=ペンを措きて=画人」と「D=晴れたる野=音楽家」とは、珍しい写真なので、「俳諧師・東洋城」に敬意を表して、俳諧(滑稽)的な「見立て」(「対象を、他のものになぞらえて表現すること」)の一つとして提示をして置きたい。
※ 次の「寺田寅彦の描いたスケッチ」(上=松根東洋城、下右=小宮豊隆、下左=津田青楓、昭和2年9月2日、塩原塩の湯明賀屋にて)は、『寺田寅彦全集第十二巻』(月報12・1997年11月)に、「資料」(「渋柿(寺田寅彦追悼号・昭和十一年二月)」)の「寺田博士(西岡十四王稿)」の中に所収されているもので、この「寺田寅彦の描いたスケッチ」もまた、「渋柿」主宰者の「松根東洋城」が、この「寺田博士(西岡十四王稿)」の中に、掲載をしたように思われる。
そして、何よりも、この「寺田寅彦の描いたスケッチ」(上=松根東洋城、下右=小宮豊隆、下左=津田青楓)は、下記のアドレスで紹介した、[「昭和二年(一九二七)八月、小宮豊隆、松根東洋城、津田青楓と塩原温泉に行き、連句を実作する」(「寺田寅彦年譜」)の、その塩原温泉でのものと思われる。]と合致する。
(再掲)
https://yahan.blog.ss-blog.jp/2023-12-04
[※ 歌仙(昭和十一年十一月「渋柿(未完の歌仙)」)
オ
(八月十八日雲仙を下る)
霧雨に奈良漬食ふも別れ哉 蓬里雨
馬追とまる額の字の上 青楓
ひとり鳴る鳴子に出れば月夜にて 寅日子 月
けふは二度目の棒つかふ人 東洋城
ぼそぼそと人話しゐる辻堂に 雨
煙るとも見れば時雨来にけり 子
ウ
皹(アカギレ)を業するうちは忘れゐて 城
炭打くだく七輪の角 雨(一・一七)
胴(ドウ)の間に蚊帳透き見ゆる朝ぼらけ 子 (※茶の「胴炭」からの附け?) 恋
葭吹く風に廓の後朝(キヌギヌ) 城 恋
細帯に腰の形を落付けて 雨(六・四・一四) 恋
簾の風に薫る掛香 子(八・二八) 恋
庭ながら深き林の夏の月 城(七・四・一三) 月 ](『寺田寅彦全集 文学篇 第七巻』)
※ この「四吟(蓬里雨・青楓・寅日子・東洋城)歌仙(未完)」は、当時の「東洋城・寅日子・蓬里雨・青楓」の、この四人を知る上で、格好の「歌仙(未完)」ということになる。
この歌仙(未完)の、「表六句と裏一句」は、「昭和二年(一九二七)八月、小宮豊隆、松根東洋城、津田青楓と塩原温泉に行き、連句を実作する」(「寺田寅彦年譜」)の、その塩原温泉でのものと思われる。
その塩原温泉(栃木県)での歌仙の、その発句に、「八月十八日雲仙を下る」の前書を付しての「霧雨に奈良漬食ふも別れ哉(蓬里雨)」の、この前書にある「雲仙(温泉)」(長崎県)が出て来るのはどういうことなのか(?) ――― 、この句の背景には、次のアドレスの「作家を求める読者、読者を求める作家――改造社主催講演旅行実地踏査――(杉山欣也稿)」(金沢大学学術情報リポトロジKURA)で記述されている「雲仙温泉」で開催された「改造社主催講演会」に、その講師として、小宮豊隆の名が出てくるのである。
file:///C:/Users/user/Downloads/CV_20231201_LE-PR-SUGIYAMA-K-203.pdf
[雲仙の温泉岳娯楽場を会場に、八月十七日~二十二日に開催された九州地区のそれは、やはり新聞各紙の広告によって宣伝が重ねられた。講師は、小宮豊隆・阿部次郎・木村毅・藤村成吉・笹川臨風に、課外講演として京大教授・川村多二(「動物界の道徳」というタイトル)が演壇に立った。「長崎新聞」の紙面から、ここも大盛況であったことが分かる。]
[この八月十七日の翌日(八月十八日)、雲仙温泉での講演を後にして、その帰途中に「東洋城・寅彦・青楓」と合流して、その折りの塩原温泉(四季の郷・明賀屋、近郊に、東洋城の「両面句碑」が建立されている)での一句のように解せられる。
そして、裏の二句目の「炭打くだく七輪の角・雨(一・一七)」は、昭和六年(一九三一)一月十一日付けの、文音での、蓬里雨の付け句のように思われる。それに対して、「胴(ドウ)の間に蚊帳透き見ゆる朝ぼらけ・子」(寅日子・裏三句目)と「葭吹く風に廓の後朝(キヌギヌ)・城」と付け、同年の四月十四日に「細帯に腰の形を落付けて・雨」(蓬里雨・裏四句目)」、続く、同年の八月二十八日に「簾の風に薫る掛香・子」(寅日子・裏五句目)と付けて、その翌年の昭和七年(一九三二)四月十三日に「庭ながら深き林の夏の月・ 城」(東洋城・裏六句目)」のところで打ち掛けとなっている。
実に、昭和二年(一九二七)の八月にスタートした歌仙(連句)は、その五年後の、昭和七年(一九三二)の四月まで、未完のままに、そして、寅彦が亡くなった、翌年の、昭和十一年(一九三六)十一月号の「渋柿」に公開されたということになる。 ]
※ この「寺田寅彦の描いたスケッチ」(上=松根東洋城、下右=小宮豊隆、下左=津田青楓)は、下記のアドレスで紹介した、[「昭和二年(一九二七)八月、小宮豊隆、松根東洋城、津田青楓と塩原温泉に行き、連句を実作する」(「寺田寅彦年譜」)の、この時、「東洋城(本名・豊次郎)・寅彦(寅日子)」(五十歳)、「豊隆(蓬里雨)」(四十四歳)]、そして、「津田青楓(本名・亀治郎)」(四十六歳)で、この頃が、この四人の、激動時代の、一時の心休まる時でもあったであろう。
この年(昭和二年)の七月に、漱石門の「 芥川龍之介」が睡眠薬を多量に飲んで自殺した後で、さらに、この塩原温泉は、明治四十一年(一九〇八)の、漱石門の「森田草平」の『煤煙』(「心中未遂事件」)に関わる所でもあり、この漱石門の四人(東洋城・寅彦・青楓・豊隆)に取っては、忘れ得ざる因縁の土地でもあったことであろう。
それらに付け加えることとして、この年に、東洋城は、この塩原(四季の郷・「塩の湯・明賀屋」近傍)に、下記アドレスなどで紹介している「両面句碑」を建立し、そのお祝いを兼ねてのものであったというように思われる。
https://yahan.blog.ss-blog.jp/2023-11-26
(再掲)

「塩原両面碑の松根東洋城(昭和二年七月、両面碑・西面)」)(『東洋城全句集中巻』)
https://yahan.blog.ss-blog.jp/2023-11-17
[【碑文】
「さまみえて土になりゐる落葉哉」表
「すずしさやこの山水に出湯とは」裏 (塩原四季郷より)
http://hotyu.starfree.jp/historicalspots/bungakuhi/bungakuhi.html ]
.jpg)
(追記その一)『自撰年譜(津田青楓編集兼発行者)』(昭和十五年九月二十五日刊・非売品)周辺
https://dl.ndl.go.jp/pid/1905748/1/52
『自撰年譜(津田青楓編集兼発行者)』所収「昭和十年・十一年」(抜粋)(「国立国会図書館デジタルコレクション」)
https://dl.ndl.go.jp/pid/1905748/1/4
※ 寅彦が亡くった「昭和十年 五十六歳」の末尾の「一、十二月廿日寺田寅彦氏永眠さる」は、「十二月三十一日」の誤記であろう。その文面中の、「仕事の唯一の理解者を喪ひしことまことにさびしき心地す」は、青楓の、この時の実感であろう。
ひとときの/ほかにはあらじ/相見たる/ひとときたこそを/いのちとぞ思ふ
津田青楓は、寅彦と同様に、和歌(短歌)にも精通していた。
この「昭和十年 五十六歳」に続く、「昭和十一年 五十七歳」は、所謂、「二・二六事件」勃発の記述である。
受話器おき/雪を蹴立てて/町にいづ/二・二六日/ひるかたぶきぬ
.jpg)
『自撰年譜(津田青楓編集兼発行者)』所収「青楓画伯像 河上肇写」
https://dl.ndl.go.jp/pid/1905748/1/3
※ この『自撰年譜(津田青楓編集兼発行者)』の冒頭に出て来る、この「青楓画伯像 河上肇写」は、漱石没後、「関東大震災」(「大正十二年=一九二三」)で京都移住後、青楓が心酔した、「河上肇」([1879~1946]経済学者・社会思想家。山口の生まれ。京大教授。マルクス(主義)経済学の研究・紹介に努め、大学を追われた。のち、日本共産党に入党、検挙されて入獄。著「資本論入門」「経済学大綱」「貧乏物語」「自叙伝」など)その人が、青楓をスケッチした当時のその青楓の実像である。このスケッチ画に見られる絵画を通しての二人交遊は、青楓の「研究室に於ける河上肇像」として、大正十四年(一九二五)の「第十三回二科美術展覧会」の出品作となっている。
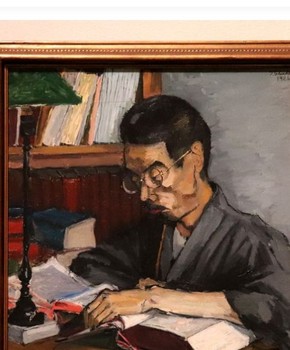
津田青楓画「研究室に於ける河上肇像」(「京都国立近代美術館蔵」)
https://rakukatsu.jp/tsuda-seifu-20200323/
そして、これらが、続く、当時の、津田青楓画の傑作、《疾風怒濤》(1932、笛吹市青楓美術館蔵)、そして、《犠牲者》(1933、東京国立近代美術館蔵)との連作を生んで行く。
これら連作の生まれた、昭和七年(一九三二)、そして、昭和八年(一九三三)当時には、津田青楓は、京都から、再び、東京へと移住し、昭和十年(一九三五)の、寅彦が亡くなる頃は、その左翼運動から身を引いて、同時に、絵画活動の拠点であった「二科会」とも訣別し、これまでの「洋画)」から、「日本画」へと、軸足を進める時でもあった。
なお、寺田寅彦の青楓(津田亀次郎)宛て書簡は、寅彦が亡くなる昭和十年(一九三五)三月十一日付けものが最後で、そこに、「先日は第二画集を難有う御坐いました。益々油が乗つたやうで実に見事なものであります。天下一品とは此事でありましよう」とある。(『寺田寅彦全集 文学篇 第十七巻』)

津田青楓画《疾風怒濤》(1932、笛吹市青楓美術館蔵)
https://bijutsutecho.com/magazine/review/21974

津田青楓画《犠牲者》(1933、東京国立近代美術館蔵)
https://note.com/azusa183/n/n7f1fab27c7e2
https://bunka.nii.ac.jp/db/heritages/detail/107539
[津田青楓 (1880-1978)/ツダ、セイフウ/昭和8年/1933/油彩・キャンバス・額・1面/193.0×95.4/26回白日会展 東京都美術館 1950
犠牲者/The Victim/1933年/油彩・麻布 193.0×95.4㎝
津田は、1933年7月19日、官憲による家宅捜査をうけたのち、一時拘留された。このとき制作中だったのが、この《犠牲者》である。31年第18回二科展に出品された《ブルジョア議会と民衆の生活》(出品時には、「新議会」と改題させられた。現在、この作品の習作が当館に所蔵されている。)は押収されたものの、この作品は幸い残すことができた。当時、官憲によるプロレタリア思想弾圧は、日増しに激しくなっていた。
とくに京都時代に知己となった河上肇は京都帝国大学教授を辞職した後、日本共産党に加入し地下に潜行していたが、この年1月に検挙された。津田の検挙も、かねてから上記の作品によって官憲の注目をあつめ、また河上の潜行をたすけたという容疑によるものであった。
この《犠牲者》は、同年2月の小説家小林多喜二の獄死に触発されて描かれたもので、津田自身は、「一見拷問の残忍性を物語る酸鼻に堪へないやうなもの」だが、「十字架のキリスト像にも匹敵するやうなものにしたいといふ希望を持つて、この作にとりかかつた」(『老画家の一生』)と後に記している。
拷問をうけ、吊り下げられた男、そして左下の窓を通してかすかにみえる議事堂、この簡潔な構図に弾圧に対する告発がこめられていることは確かだ。ただし、津田とプロレタリア思想との関係は、社会的 な義憤と河上との親交による共感からのものであり、多分に同伴者的なものであった。
しかし、当時のプロレタリア美術が不毛であったなかで、直接的な社会性を持った作品として評価されている。](「文化遺産オンライン」)

津田青楓画《犠牲者》(1933、東京国立近代美術館蔵)の下部(「窓」の部分)拡大図
この下部(「窓」の部分)拡大図に、昭和十一年(一九三六)に竣工された、「新議会(※新国会議事堂)の、その竣工前の屋根の部分が描かれている。
.jpg)
「ブルジョワ議会と民衆生活」 下絵(津田青楓/1931)(「東京国立近代美術館」蔵)
[素材・技法=油彩、コラージュ/ 作品サイズ=125.8×80.3 ]
https://www.momat.go.jp/collection/o00276
(追記その二) 『漱石・寅彦・三重吉(小宮豊隆著・岩波書店)』所収「『明暗』の材料/129」
(「津田青楓」と離婚した「山脇敏子」)周辺
『漱石・寅彦・三重吉(小宮豊隆著・岩波書店)』の、「『明暗』の材料/129」の中に、次のような一節がある。
https://dl.ndl.go.jp/pid/1127319/1/79
[『明暗』第三十一囘で、藤井が醉つて、小林だの津田だの相手に、「昔は女の方で男に惚れたけれども、男の方では決して女に惚れなかつた」その理由が何所にあるかを說明する。
是は恐らく大正五年三月中旬に書かれた、「ポセッション」と題する、漱石の日記の中の一節から來てゐる。「私はいくら女を戀しても一直線に其方へ進む譯には行かないのです」/「何故」「女が自分で自分を所有してゐないと思ふからです」/「ぢや女は誰が所有してゐます」/「旣婚の女は無論夫の所有でせう。少くとも夫はさう認めてゐるでせう」/「さうです」/「未婚の處女は兩親の所有でせう。少くとも父母はさう認めてゐるでせう。父母〔の〕許諾がなくて嫁に行く女はまあないからです」といふのが、それである。
(中略)
同じやうな戀愛問題に關する會話が、大正五年の三月中旬以後四月上旬以前に書かれたらしい、漱石の日記の中にある。「我一人の爲の愛か」と題して「私はそんな氣の多い人は嫌です。自分一人を愛して吳れる人でなくつては」/「外の人は全く愛せずに自分丈に愛の量を集めやうといふのですね」/「さうです」/「すると其男に取つて貴女以外の女は丸でなくなるので原原すな」/「えゝ」/「何うしてそれが出來ます」/「完全の愛はそんなさうでせう。其所迄行かなくつちや本當の愛を感ずる譯には行かないぢやありませんか」/「然し考へて御覽なさい。あなた以外の女を女と思はないで、あなた丈を女と思ふといふ事は理性でも悟性でもに訴へて出來る事でせうか」/「感情の上では出來る筈ぢやありませんか」/「然しあなた丈を女と思ふといふと解し得られる樣ですが外の女を女と思ふなといふと想像出來なくなるやうです。(中略)
さうして是は、もし私の記憶に誤がないならば、當時の津田靑楓の妻君、今の山脇敏子と漱石との對話の要點を記錄したものであつた。漱石は是を『明暗』第百三十囘の、お秀とお延との對話に用ひる。]
『漱石・寅彦・三重吉(小宮豊隆著・岩波書店)』所収「『明暗』の材料/129」(抜粋)
.gif)
「婦人と金絲雀鳥(津田青楓画)/1920/油彩/116.7×73.0/(モデルは敏子)」(「東京国立近代美術館」蔵)
https://www.momat.go.jp/collection/o00277
[山脇敏子(「ウィキペディア」)
1887年(明治20年) 広島県呉市の医師の家庭に生まれ、竹原市で育つ。
1899年(明治32年) 竹原市立東野小学校を卒業して上京。
1905年(明治38年) 女子美術学校(現・女子美術大学)日本画科卒業。日本画の手ほどきは、殆ど河鍋暁翠から習ったという。女子美術学校の卒業生として、初の文部省留学生に選ばれ渡欧。洋画も学ぶ。
1907年(明治40年) 夏目漱石と親交のあった津田青楓と結婚。漱石を中心に集まる内田百閒や鈴木三重吉ら「木曜会」の作家や、寺田寅彦やセルゲイ・エリセーエフらの学者、また文展に不満を持つ藤島武二や南薫造ら若い芸術家と親交を持った。漱石の絶筆『明暗』のモデルともされる。
1918年(大正7年) 二科美術展覧会に洋画入選。
1919年(大正8年) 他の女流画家たちと日本で初めての女子洋画団体「朱葉会」を結成。命名はやはり創立委員だった与謝野晶子。
1923年(大正12年) 西村伊作が創設した文化学院の講師。まもなく農商務省の委嘱で婦人副業視察に再び渡欧、フランスに1年滞在。この間青楓に愛人ができ1926年(大正15年)離婚。傷心の敏子は画家を諦め、自立への道を服飾に賭けた。三度渡欧し昼は手芸、夜は裁断を二年間必死に勉強。また経済的窮地をパリを訪れていた細川侯爵夫人に救われた。これが縁で後に学習院・常磐会で手芸や洋裁を教えた。
1929年(昭和4年) 東京麹町内幸町に「山脇洋裁学院」(現・山脇美術専門学院)を開設。また日本のオートクチュールの草分け、洋裁店「アザレ」を銀座に開店。官家や知名人の服飾を手がけ格調あるモードは高い評価を得た。
1935年(昭和10年) 陸軍被服廠嘱託。文化服装学院講師。
1947年(昭和22年) 戦後の洋裁ブームの中「山脇服飾美術学院」を設立、理事長・院長となる。
1952年(昭和27年) 文部省教材等調査研究会委員。
1956年(昭和31年) 日本伝統の織物や文様を積極的に取り入れ、アイヌ文様を主題にパリで開いた服飾個展は、パリ市から賞を受けた。のちにブームとなった日本モードの先駆けでもあった。
1960年(昭和35年) 脳出血で死去。小平霊園に眠る。 ]
※ 青楓と敏子との結婚生活は、明治四十年(一九〇七)から大正十二年(一九二三)の、十六年間、その間に、二男(?)三女をもうけた。
※長女(「あやめ=原あやめ」=明治四十四年生れ=敏子の跡を継ぎ「山脇美術専門学院」理事長・学院長。平成二十年没。)
長男(「安丸=漱石命名」=大正二年生れ、大正五年病没。)
※次女(「ふよう」=大正四年生れ、平成六年没。)
次男(「庸」=大正九年没。?)
三女(「ひかる」=大正十年生れ、昭和五年没。)
敏子が、「洋裁研究」のため渡仏したのは、大正十一年(一九二二)で、この時には、男の子は二人とも病没し、長女(十二歳)・次女(八歳)・三女(二歳)の三人を、青楓に預けてのものであった。敏子が帰国したのは、関東大地震のあった翌年の、大正十三年(一九二四)で、この時には、「青楓・あやめ・ふよう・ひかる」が神戸港に出迎えている。
そして、青楓と敏子が離婚したのは、大正十五年(一九二六)、その年の十二月二十五日に大正天皇が崩御し、昭和元年となる。この時には、「青楓・あやめ・ふよう・ひかる」は、青楓の実家のある京都市(東山区)に移住し、「敏子」は東京を居住地として、昭和四年(一九二八)に、現在の「山脇美術専門学院」の前身の「山脇洋裁学院」を東京銀座に開設することになる。
これらの「青楓・敏子・あやめ(長女)」の生涯は、下記アドレスの「千草会会報追悼号」(平成21年2月発行) の年譜に記されている。
https://yamawaki.ac.jp/pdf/chigusa_tsuitou.pdf

「千草会会報追悼号」(平成21年2月発行)
https://yamawaki.ac.jp/pdf/chigusa_tsuitou.pdf
この年譜に、青楓が、昭和十五年(一九四〇)九月二十五日に発刊(非売品)した、下記アドレスの「自撰年譜」を重ね合わせることによって、「青楓と敏子」との、そのドラマというのは浮かび上がってくる。
さらに、それられに付け加えて、「青楓と敏子」との、その「敏子」が亡くなった昭和三十五年(一九六〇)以後の、昭和四十九年(一九七四)七月に刊行された『漱石と十弟子(津田青楓著・芸艸堂刊)』の、その「新序文」(昭和四十九年七月一日付け)の中の、「私の娘婿Hは丁度銀座裏の陋屋(ロウオク)で細々と出版業をやっていた」と重ね合わせると、「青楓と敏子」と、その長女(あやめ)夫妻(「原愿雄=H」と「原あやめ)」とのドラマとが重ね合わさってくる。
その「新序文」の「私の娘婿H=原愿雄」は、上記の「千草会会報追悼号」の年譜によると、「太平洋戦争」の終戦の前年(昭和十九年=一九四四)に亡くなっている。すなわち、この『漱石と十弟子(津田青楓著・芸艸堂刊)』の新訂前の、『漱石と十弟子((津田青楓著・世界文庫刊・昭和二十四年=一九四九)』は、「私の娘婿H=原愿雄」は眼にしていないであろう。
そして、この『漱石と十弟子(津田青楓著・世界文庫刊・昭和二十四年=一九四九)』の、その刊行前の、昭和二十二年(一九四七)に、「私の娘婿H=原愿雄」が亡き、その「長女・原あやめ」が、「母・敏子の仕事を手伝うべく、神田駿河台に山脇服飾美術学院開設、副院長に就任」にした、「亡き夫・H=原愿雄」と「実母・山脇敏子の『山脇服飾美術学院開設』の、その『副院長』就任」を祝してのものと解することも、青楓の、その「漱石と十弟子(津田青楓著・世界文庫刊)』(昭和二十四年=一九四九)と、その新訂後の「漱石と十弟子(津田青楓著・芸艸堂刊)』(昭和四十九年(一九七四))の、その著者(「津田青楓」)に対して、その面子を汚すこともなかろう。
さらに、この『漱石と十弟子(津田青楓著・芸艸堂刊)』(昭和四十九年(一九七四)に、「(山脇)敏子」は、「百合子」の名で、漱石在世中の「青楓と敏子(そして、その家族)」の姿が活写されている。(ちなみに、青楓の『自撰年譜』の「昭和四年(一九二九)」には、「山脇(※敏子)無断で子供等を東京へつれ去る」とあり、当時の「青楓と敏子」との関係は、相当に深刻なものがあったことであろう。)
そして、『漱石と十弟子(津田青楓著・芸艸堂刊)』に出てくる「百合子」(「(山脇)敏子」)とは、青楓が漱石亡き後の心の拠り所とした「河上肇」(経済学者。啓蒙的マルクス経済学者として大正,昭和初期の左翼運動に大きな影響を与えた)とも深く関与している「中條百合子・宮本百合子」(日本の左翼文学・民主主義文学、さらには日本の近代女流文学を代表する作家の一人)の、その「百合子」と解することも、これまた、その「漱石と十弟子(津田青楓著・世界文庫刊)』(昭和二十四年=一九四九)と、その新訂後の「漱石と十弟子(津田青楓著・芸艸堂刊)』(昭和四十九年(一九七四))の、その著者(「津田青楓」)に対して、その面子を汚すこともなかろう。

「装幀 津田青楓 大正六年(一九一七)」(『漱石と十弟子(津田青楓著・芸艸堂刊)』(昭和四十九年)の口絵写真の冒頭のもの=モノクロ)
https://www.bungakukan.or.jp/item/3342/
この「装幀 津田青楓 大正六年(一九一七)」(『漱石と十弟子(津田青楓著・芸艸堂刊)』(昭和四十九年の口絵写真の冒頭のもの=モノクロ)に、終戦後(昭和二十一年=一九四六)の「宮本百合子を巡る婦人群像」の、それぞれをの一人ひとりを、重ね合わせたい。

「1946年3月18日、婦人民主クラブが結成された。加藤シヅエ、厚木たか、宮本百合子、佐多稲子、櫛田ふき、羽仁説子、関鑑子、藤川幸子、山室民子ら。」
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AE%AE%E6%9C%AC%E7%99%BE%E5%90%88%E5%AD%90#/media/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:Modern-History-of-Women-14.png
.jpg)
「渋柿(寺田寅彦追悼号の巻頭頁)」(第262号、昭和11年2月)(『寺田寅彦全集第十二巻』)
[ありし日の寺田寅彦 /A ペンを措きて /B 心明るく /C 家居 /D 晴れたる野]
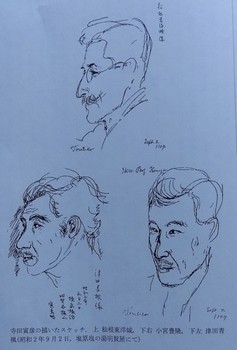
「寺田寅彦の描いたスケッチ」(上=松根東洋城、下右=小宮豊隆、下左=津田青楓、昭和2年9月2日、塩原塩の湯明賀屋にて) (『寺田寅彦全集第十二巻』・月報12・1997年11月)
※ 上記の寺田寅彦の写真四葉は、寅彦が亡くなった(昭和十年十二月三十一日没)翌年の昭和十一年(一九三六)二月号の「渋柿」(寺田寅彦追悼号)の巻頭頁に掲載されたものである。
そのページに掲載された文面([ありし日の寺田寅彦 /A ペンを措きて /B 心明るく /C 家居 /D 晴れたる野])は、おそらく、「渋柿」主宰者の「松根東洋城」が記述したもののように思われる。
この写真四葉(「A/B/C/D」)を、生前の「寺田寅彦」の四つ顔とすると、「A=ペンを措きて=画人/B=心明るく=科学者/C=家居=文人/D=晴れたる野=音楽家」と、「B=心明るく=科学者」と「C=家居=文人」との写真は、よく見掛けるもので、これをベースにして、「A=ペンを措きて=画人」と「D=晴れたる野=音楽家」とは、珍しい写真なので、「俳諧師・東洋城」に敬意を表して、俳諧(滑稽)的な「見立て」(「対象を、他のものになぞらえて表現すること」)の一つとして提示をして置きたい。
※ 次の「寺田寅彦の描いたスケッチ」(上=松根東洋城、下右=小宮豊隆、下左=津田青楓、昭和2年9月2日、塩原塩の湯明賀屋にて)は、『寺田寅彦全集第十二巻』(月報12・1997年11月)に、「資料」(「渋柿(寺田寅彦追悼号・昭和十一年二月)」)の「寺田博士(西岡十四王稿)」の中に所収されているもので、この「寺田寅彦の描いたスケッチ」もまた、「渋柿」主宰者の「松根東洋城」が、この「寺田博士(西岡十四王稿)」の中に、掲載をしたように思われる。
そして、何よりも、この「寺田寅彦の描いたスケッチ」(上=松根東洋城、下右=小宮豊隆、下左=津田青楓)は、下記のアドレスで紹介した、[「昭和二年(一九二七)八月、小宮豊隆、松根東洋城、津田青楓と塩原温泉に行き、連句を実作する」(「寺田寅彦年譜」)の、その塩原温泉でのものと思われる。]と合致する。
(再掲)
https://yahan.blog.ss-blog.jp/2023-12-04
[※ 歌仙(昭和十一年十一月「渋柿(未完の歌仙)」)
オ
(八月十八日雲仙を下る)
霧雨に奈良漬食ふも別れ哉 蓬里雨
馬追とまる額の字の上 青楓
ひとり鳴る鳴子に出れば月夜にて 寅日子 月
けふは二度目の棒つかふ人 東洋城
ぼそぼそと人話しゐる辻堂に 雨
煙るとも見れば時雨来にけり 子
ウ
皹(アカギレ)を業するうちは忘れゐて 城
炭打くだく七輪の角 雨(一・一七)
胴(ドウ)の間に蚊帳透き見ゆる朝ぼらけ 子 (※茶の「胴炭」からの附け?) 恋
葭吹く風に廓の後朝(キヌギヌ) 城 恋
細帯に腰の形を落付けて 雨(六・四・一四) 恋
簾の風に薫る掛香 子(八・二八) 恋
庭ながら深き林の夏の月 城(七・四・一三) 月 ](『寺田寅彦全集 文学篇 第七巻』)
※ この「四吟(蓬里雨・青楓・寅日子・東洋城)歌仙(未完)」は、当時の「東洋城・寅日子・蓬里雨・青楓」の、この四人を知る上で、格好の「歌仙(未完)」ということになる。
この歌仙(未完)の、「表六句と裏一句」は、「昭和二年(一九二七)八月、小宮豊隆、松根東洋城、津田青楓と塩原温泉に行き、連句を実作する」(「寺田寅彦年譜」)の、その塩原温泉でのものと思われる。
その塩原温泉(栃木県)での歌仙の、その発句に、「八月十八日雲仙を下る」の前書を付しての「霧雨に奈良漬食ふも別れ哉(蓬里雨)」の、この前書にある「雲仙(温泉)」(長崎県)が出て来るのはどういうことなのか(?) ――― 、この句の背景には、次のアドレスの「作家を求める読者、読者を求める作家――改造社主催講演旅行実地踏査――(杉山欣也稿)」(金沢大学学術情報リポトロジKURA)で記述されている「雲仙温泉」で開催された「改造社主催講演会」に、その講師として、小宮豊隆の名が出てくるのである。
file:///C:/Users/user/Downloads/CV_20231201_LE-PR-SUGIYAMA-K-203.pdf
[雲仙の温泉岳娯楽場を会場に、八月十七日~二十二日に開催された九州地区のそれは、やはり新聞各紙の広告によって宣伝が重ねられた。講師は、小宮豊隆・阿部次郎・木村毅・藤村成吉・笹川臨風に、課外講演として京大教授・川村多二(「動物界の道徳」というタイトル)が演壇に立った。「長崎新聞」の紙面から、ここも大盛況であったことが分かる。]
[この八月十七日の翌日(八月十八日)、雲仙温泉での講演を後にして、その帰途中に「東洋城・寅彦・青楓」と合流して、その折りの塩原温泉(四季の郷・明賀屋、近郊に、東洋城の「両面句碑」が建立されている)での一句のように解せられる。
そして、裏の二句目の「炭打くだく七輪の角・雨(一・一七)」は、昭和六年(一九三一)一月十一日付けの、文音での、蓬里雨の付け句のように思われる。それに対して、「胴(ドウ)の間に蚊帳透き見ゆる朝ぼらけ・子」(寅日子・裏三句目)と「葭吹く風に廓の後朝(キヌギヌ)・城」と付け、同年の四月十四日に「細帯に腰の形を落付けて・雨」(蓬里雨・裏四句目)」、続く、同年の八月二十八日に「簾の風に薫る掛香・子」(寅日子・裏五句目)と付けて、その翌年の昭和七年(一九三二)四月十三日に「庭ながら深き林の夏の月・ 城」(東洋城・裏六句目)」のところで打ち掛けとなっている。
実に、昭和二年(一九二七)の八月にスタートした歌仙(連句)は、その五年後の、昭和七年(一九三二)の四月まで、未完のままに、そして、寅彦が亡くなった、翌年の、昭和十一年(一九三六)十一月号の「渋柿」に公開されたということになる。 ]
※ この「寺田寅彦の描いたスケッチ」(上=松根東洋城、下右=小宮豊隆、下左=津田青楓)は、下記のアドレスで紹介した、[「昭和二年(一九二七)八月、小宮豊隆、松根東洋城、津田青楓と塩原温泉に行き、連句を実作する」(「寺田寅彦年譜」)の、この時、「東洋城(本名・豊次郎)・寅彦(寅日子)」(五十歳)、「豊隆(蓬里雨)」(四十四歳)]、そして、「津田青楓(本名・亀治郎)」(四十六歳)で、この頃が、この四人の、激動時代の、一時の心休まる時でもあったであろう。
この年(昭和二年)の七月に、漱石門の「 芥川龍之介」が睡眠薬を多量に飲んで自殺した後で、さらに、この塩原温泉は、明治四十一年(一九〇八)の、漱石門の「森田草平」の『煤煙』(「心中未遂事件」)に関わる所でもあり、この漱石門の四人(東洋城・寅彦・青楓・豊隆)に取っては、忘れ得ざる因縁の土地でもあったことであろう。
それらに付け加えることとして、この年に、東洋城は、この塩原(四季の郷・「塩の湯・明賀屋」近傍)に、下記アドレスなどで紹介している「両面句碑」を建立し、そのお祝いを兼ねてのものであったというように思われる。
https://yahan.blog.ss-blog.jp/2023-11-26
(再掲)

「塩原両面碑の松根東洋城(昭和二年七月、両面碑・西面)」)(『東洋城全句集中巻』)
https://yahan.blog.ss-blog.jp/2023-11-17
[【碑文】
「さまみえて土になりゐる落葉哉」表
「すずしさやこの山水に出湯とは」裏 (塩原四季郷より)
http://hotyu.starfree.jp/historicalspots/bungakuhi/bungakuhi.html ]
.jpg)
(追記その一)『自撰年譜(津田青楓編集兼発行者)』(昭和十五年九月二十五日刊・非売品)周辺
https://dl.ndl.go.jp/pid/1905748/1/52
『自撰年譜(津田青楓編集兼発行者)』所収「昭和十年・十一年」(抜粋)(「国立国会図書館デジタルコレクション」)
https://dl.ndl.go.jp/pid/1905748/1/4
※ 寅彦が亡くった「昭和十年 五十六歳」の末尾の「一、十二月廿日寺田寅彦氏永眠さる」は、「十二月三十一日」の誤記であろう。その文面中の、「仕事の唯一の理解者を喪ひしことまことにさびしき心地す」は、青楓の、この時の実感であろう。
ひとときの/ほかにはあらじ/相見たる/ひとときたこそを/いのちとぞ思ふ
津田青楓は、寅彦と同様に、和歌(短歌)にも精通していた。
この「昭和十年 五十六歳」に続く、「昭和十一年 五十七歳」は、所謂、「二・二六事件」勃発の記述である。
受話器おき/雪を蹴立てて/町にいづ/二・二六日/ひるかたぶきぬ
.jpg)
『自撰年譜(津田青楓編集兼発行者)』所収「青楓画伯像 河上肇写」
https://dl.ndl.go.jp/pid/1905748/1/3
※ この『自撰年譜(津田青楓編集兼発行者)』の冒頭に出て来る、この「青楓画伯像 河上肇写」は、漱石没後、「関東大震災」(「大正十二年=一九二三」)で京都移住後、青楓が心酔した、「河上肇」([1879~1946]経済学者・社会思想家。山口の生まれ。京大教授。マルクス(主義)経済学の研究・紹介に努め、大学を追われた。のち、日本共産党に入党、検挙されて入獄。著「資本論入門」「経済学大綱」「貧乏物語」「自叙伝」など)その人が、青楓をスケッチした当時のその青楓の実像である。このスケッチ画に見られる絵画を通しての二人交遊は、青楓の「研究室に於ける河上肇像」として、大正十四年(一九二五)の「第十三回二科美術展覧会」の出品作となっている。
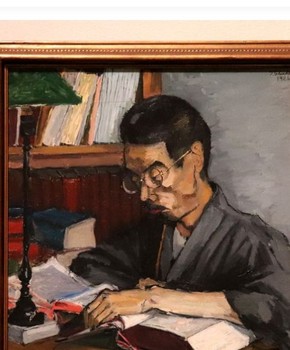
津田青楓画「研究室に於ける河上肇像」(「京都国立近代美術館蔵」)
https://rakukatsu.jp/tsuda-seifu-20200323/
そして、これらが、続く、当時の、津田青楓画の傑作、《疾風怒濤》(1932、笛吹市青楓美術館蔵)、そして、《犠牲者》(1933、東京国立近代美術館蔵)との連作を生んで行く。
これら連作の生まれた、昭和七年(一九三二)、そして、昭和八年(一九三三)当時には、津田青楓は、京都から、再び、東京へと移住し、昭和十年(一九三五)の、寅彦が亡くなる頃は、その左翼運動から身を引いて、同時に、絵画活動の拠点であった「二科会」とも訣別し、これまでの「洋画)」から、「日本画」へと、軸足を進める時でもあった。
なお、寺田寅彦の青楓(津田亀次郎)宛て書簡は、寅彦が亡くなる昭和十年(一九三五)三月十一日付けものが最後で、そこに、「先日は第二画集を難有う御坐いました。益々油が乗つたやうで実に見事なものであります。天下一品とは此事でありましよう」とある。(『寺田寅彦全集 文学篇 第十七巻』)

津田青楓画《疾風怒濤》(1932、笛吹市青楓美術館蔵)
https://bijutsutecho.com/magazine/review/21974

津田青楓画《犠牲者》(1933、東京国立近代美術館蔵)
https://note.com/azusa183/n/n7f1fab27c7e2
https://bunka.nii.ac.jp/db/heritages/detail/107539
[津田青楓 (1880-1978)/ツダ、セイフウ/昭和8年/1933/油彩・キャンバス・額・1面/193.0×95.4/26回白日会展 東京都美術館 1950
犠牲者/The Victim/1933年/油彩・麻布 193.0×95.4㎝
津田は、1933年7月19日、官憲による家宅捜査をうけたのち、一時拘留された。このとき制作中だったのが、この《犠牲者》である。31年第18回二科展に出品された《ブルジョア議会と民衆の生活》(出品時には、「新議会」と改題させられた。現在、この作品の習作が当館に所蔵されている。)は押収されたものの、この作品は幸い残すことができた。当時、官憲によるプロレタリア思想弾圧は、日増しに激しくなっていた。
とくに京都時代に知己となった河上肇は京都帝国大学教授を辞職した後、日本共産党に加入し地下に潜行していたが、この年1月に検挙された。津田の検挙も、かねてから上記の作品によって官憲の注目をあつめ、また河上の潜行をたすけたという容疑によるものであった。
この《犠牲者》は、同年2月の小説家小林多喜二の獄死に触発されて描かれたもので、津田自身は、「一見拷問の残忍性を物語る酸鼻に堪へないやうなもの」だが、「十字架のキリスト像にも匹敵するやうなものにしたいといふ希望を持つて、この作にとりかかつた」(『老画家の一生』)と後に記している。
拷問をうけ、吊り下げられた男、そして左下の窓を通してかすかにみえる議事堂、この簡潔な構図に弾圧に対する告発がこめられていることは確かだ。ただし、津田とプロレタリア思想との関係は、社会的 な義憤と河上との親交による共感からのものであり、多分に同伴者的なものであった。
しかし、当時のプロレタリア美術が不毛であったなかで、直接的な社会性を持った作品として評価されている。](「文化遺産オンライン」)

津田青楓画《犠牲者》(1933、東京国立近代美術館蔵)の下部(「窓」の部分)拡大図
この下部(「窓」の部分)拡大図に、昭和十一年(一九三六)に竣工された、「新議会(※新国会議事堂)の、その竣工前の屋根の部分が描かれている。
.jpg)
「ブルジョワ議会と民衆生活」 下絵(津田青楓/1931)(「東京国立近代美術館」蔵)
[素材・技法=油彩、コラージュ/ 作品サイズ=125.8×80.3 ]
https://www.momat.go.jp/collection/o00276
(追記その二) 『漱石・寅彦・三重吉(小宮豊隆著・岩波書店)』所収「『明暗』の材料/129」
(「津田青楓」と離婚した「山脇敏子」)周辺
『漱石・寅彦・三重吉(小宮豊隆著・岩波書店)』の、「『明暗』の材料/129」の中に、次のような一節がある。
https://dl.ndl.go.jp/pid/1127319/1/79
[『明暗』第三十一囘で、藤井が醉つて、小林だの津田だの相手に、「昔は女の方で男に惚れたけれども、男の方では決して女に惚れなかつた」その理由が何所にあるかを說明する。
是は恐らく大正五年三月中旬に書かれた、「ポセッション」と題する、漱石の日記の中の一節から來てゐる。「私はいくら女を戀しても一直線に其方へ進む譯には行かないのです」/「何故」「女が自分で自分を所有してゐないと思ふからです」/「ぢや女は誰が所有してゐます」/「旣婚の女は無論夫の所有でせう。少くとも夫はさう認めてゐるでせう」/「さうです」/「未婚の處女は兩親の所有でせう。少くとも父母はさう認めてゐるでせう。父母〔の〕許諾がなくて嫁に行く女はまあないからです」といふのが、それである。
(中略)
同じやうな戀愛問題に關する會話が、大正五年の三月中旬以後四月上旬以前に書かれたらしい、漱石の日記の中にある。「我一人の爲の愛か」と題して「私はそんな氣の多い人は嫌です。自分一人を愛して吳れる人でなくつては」/「外の人は全く愛せずに自分丈に愛の量を集めやうといふのですね」/「さうです」/「すると其男に取つて貴女以外の女は丸でなくなるので原原すな」/「えゝ」/「何うしてそれが出來ます」/「完全の愛はそんなさうでせう。其所迄行かなくつちや本當の愛を感ずる譯には行かないぢやありませんか」/「然し考へて御覽なさい。あなた以外の女を女と思はないで、あなた丈を女と思ふといふ事は理性でも悟性でもに訴へて出來る事でせうか」/「感情の上では出來る筈ぢやありませんか」/「然しあなた丈を女と思ふといふと解し得られる樣ですが外の女を女と思ふなといふと想像出來なくなるやうです。(中略)
さうして是は、もし私の記憶に誤がないならば、當時の津田靑楓の妻君、今の山脇敏子と漱石との對話の要點を記錄したものであつた。漱石は是を『明暗』第百三十囘の、お秀とお延との對話に用ひる。]
『漱石・寅彦・三重吉(小宮豊隆著・岩波書店)』所収「『明暗』の材料/129」(抜粋)
.gif)
「婦人と金絲雀鳥(津田青楓画)/1920/油彩/116.7×73.0/(モデルは敏子)」(「東京国立近代美術館」蔵)
https://www.momat.go.jp/collection/o00277
[山脇敏子(「ウィキペディア」)
1887年(明治20年) 広島県呉市の医師の家庭に生まれ、竹原市で育つ。
1899年(明治32年) 竹原市立東野小学校を卒業して上京。
1905年(明治38年) 女子美術学校(現・女子美術大学)日本画科卒業。日本画の手ほどきは、殆ど河鍋暁翠から習ったという。女子美術学校の卒業生として、初の文部省留学生に選ばれ渡欧。洋画も学ぶ。
1907年(明治40年) 夏目漱石と親交のあった津田青楓と結婚。漱石を中心に集まる内田百閒や鈴木三重吉ら「木曜会」の作家や、寺田寅彦やセルゲイ・エリセーエフらの学者、また文展に不満を持つ藤島武二や南薫造ら若い芸術家と親交を持った。漱石の絶筆『明暗』のモデルともされる。
1918年(大正7年) 二科美術展覧会に洋画入選。
1919年(大正8年) 他の女流画家たちと日本で初めての女子洋画団体「朱葉会」を結成。命名はやはり創立委員だった与謝野晶子。
1923年(大正12年) 西村伊作が創設した文化学院の講師。まもなく農商務省の委嘱で婦人副業視察に再び渡欧、フランスに1年滞在。この間青楓に愛人ができ1926年(大正15年)離婚。傷心の敏子は画家を諦め、自立への道を服飾に賭けた。三度渡欧し昼は手芸、夜は裁断を二年間必死に勉強。また経済的窮地をパリを訪れていた細川侯爵夫人に救われた。これが縁で後に学習院・常磐会で手芸や洋裁を教えた。
1929年(昭和4年) 東京麹町内幸町に「山脇洋裁学院」(現・山脇美術専門学院)を開設。また日本のオートクチュールの草分け、洋裁店「アザレ」を銀座に開店。官家や知名人の服飾を手がけ格調あるモードは高い評価を得た。
1935年(昭和10年) 陸軍被服廠嘱託。文化服装学院講師。
1947年(昭和22年) 戦後の洋裁ブームの中「山脇服飾美術学院」を設立、理事長・院長となる。
1952年(昭和27年) 文部省教材等調査研究会委員。
1956年(昭和31年) 日本伝統の織物や文様を積極的に取り入れ、アイヌ文様を主題にパリで開いた服飾個展は、パリ市から賞を受けた。のちにブームとなった日本モードの先駆けでもあった。
1960年(昭和35年) 脳出血で死去。小平霊園に眠る。 ]
※ 青楓と敏子との結婚生活は、明治四十年(一九〇七)から大正十二年(一九二三)の、十六年間、その間に、二男(?)三女をもうけた。
※長女(「あやめ=原あやめ」=明治四十四年生れ=敏子の跡を継ぎ「山脇美術専門学院」理事長・学院長。平成二十年没。)
長男(「安丸=漱石命名」=大正二年生れ、大正五年病没。)
※次女(「ふよう」=大正四年生れ、平成六年没。)
次男(「庸」=大正九年没。?)
三女(「ひかる」=大正十年生れ、昭和五年没。)
敏子が、「洋裁研究」のため渡仏したのは、大正十一年(一九二二)で、この時には、男の子は二人とも病没し、長女(十二歳)・次女(八歳)・三女(二歳)の三人を、青楓に預けてのものであった。敏子が帰国したのは、関東大地震のあった翌年の、大正十三年(一九二四)で、この時には、「青楓・あやめ・ふよう・ひかる」が神戸港に出迎えている。
そして、青楓と敏子が離婚したのは、大正十五年(一九二六)、その年の十二月二十五日に大正天皇が崩御し、昭和元年となる。この時には、「青楓・あやめ・ふよう・ひかる」は、青楓の実家のある京都市(東山区)に移住し、「敏子」は東京を居住地として、昭和四年(一九二八)に、現在の「山脇美術専門学院」の前身の「山脇洋裁学院」を東京銀座に開設することになる。
これらの「青楓・敏子・あやめ(長女)」の生涯は、下記アドレスの「千草会会報追悼号」(平成21年2月発行) の年譜に記されている。
https://yamawaki.ac.jp/pdf/chigusa_tsuitou.pdf

「千草会会報追悼号」(平成21年2月発行)
https://yamawaki.ac.jp/pdf/chigusa_tsuitou.pdf
この年譜に、青楓が、昭和十五年(一九四〇)九月二十五日に発刊(非売品)した、下記アドレスの「自撰年譜」を重ね合わせることによって、「青楓と敏子」との、そのドラマというのは浮かび上がってくる。
さらに、それられに付け加えて、「青楓と敏子」との、その「敏子」が亡くなった昭和三十五年(一九六〇)以後の、昭和四十九年(一九七四)七月に刊行された『漱石と十弟子(津田青楓著・芸艸堂刊)』の、その「新序文」(昭和四十九年七月一日付け)の中の、「私の娘婿Hは丁度銀座裏の陋屋(ロウオク)で細々と出版業をやっていた」と重ね合わせると、「青楓と敏子」と、その長女(あやめ)夫妻(「原愿雄=H」と「原あやめ)」とのドラマとが重ね合わさってくる。
その「新序文」の「私の娘婿H=原愿雄」は、上記の「千草会会報追悼号」の年譜によると、「太平洋戦争」の終戦の前年(昭和十九年=一九四四)に亡くなっている。すなわち、この『漱石と十弟子(津田青楓著・芸艸堂刊)』の新訂前の、『漱石と十弟子((津田青楓著・世界文庫刊・昭和二十四年=一九四九)』は、「私の娘婿H=原愿雄」は眼にしていないであろう。
そして、この『漱石と十弟子(津田青楓著・世界文庫刊・昭和二十四年=一九四九)』の、その刊行前の、昭和二十二年(一九四七)に、「私の娘婿H=原愿雄」が亡き、その「長女・原あやめ」が、「母・敏子の仕事を手伝うべく、神田駿河台に山脇服飾美術学院開設、副院長に就任」にした、「亡き夫・H=原愿雄」と「実母・山脇敏子の『山脇服飾美術学院開設』の、その『副院長』就任」を祝してのものと解することも、青楓の、その「漱石と十弟子(津田青楓著・世界文庫刊)』(昭和二十四年=一九四九)と、その新訂後の「漱石と十弟子(津田青楓著・芸艸堂刊)』(昭和四十九年(一九七四))の、その著者(「津田青楓」)に対して、その面子を汚すこともなかろう。
さらに、この『漱石と十弟子(津田青楓著・芸艸堂刊)』(昭和四十九年(一九七四)に、「(山脇)敏子」は、「百合子」の名で、漱石在世中の「青楓と敏子(そして、その家族)」の姿が活写されている。(ちなみに、青楓の『自撰年譜』の「昭和四年(一九二九)」には、「山脇(※敏子)無断で子供等を東京へつれ去る」とあり、当時の「青楓と敏子」との関係は、相当に深刻なものがあったことであろう。)
そして、『漱石と十弟子(津田青楓著・芸艸堂刊)』に出てくる「百合子」(「(山脇)敏子」)とは、青楓が漱石亡き後の心の拠り所とした「河上肇」(経済学者。啓蒙的マルクス経済学者として大正,昭和初期の左翼運動に大きな影響を与えた)とも深く関与している「中條百合子・宮本百合子」(日本の左翼文学・民主主義文学、さらには日本の近代女流文学を代表する作家の一人)の、その「百合子」と解することも、これまた、その「漱石と十弟子(津田青楓著・世界文庫刊)』(昭和二十四年=一九四九)と、その新訂後の「漱石と十弟子(津田青楓著・芸艸堂刊)』(昭和四十九年(一九七四))の、その著者(「津田青楓」)に対して、その面子を汚すこともなかろう。

「装幀 津田青楓 大正六年(一九一七)」(『漱石と十弟子(津田青楓著・芸艸堂刊)』(昭和四十九年)の口絵写真の冒頭のもの=モノクロ)
https://www.bungakukan.or.jp/item/3342/
この「装幀 津田青楓 大正六年(一九一七)」(『漱石と十弟子(津田青楓著・芸艸堂刊)』(昭和四十九年の口絵写真の冒頭のもの=モノクロ)に、終戦後(昭和二十一年=一九四六)の「宮本百合子を巡る婦人群像」の、それぞれをの一人ひとりを、重ね合わせたい。

「1946年3月18日、婦人民主クラブが結成された。加藤シヅエ、厚木たか、宮本百合子、佐多稲子、櫛田ふき、羽仁説子、関鑑子、藤川幸子、山室民子ら。」
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AE%AE%E6%9C%AC%E7%99%BE%E5%90%88%E5%AD%90#/media/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:Modern-History-of-Women-14.png
「東洋城・寅彦、そして、豊隆」(漱石没後~寅彦没まで)俳句・連句管見(その十九) [東洋城・寅日子(寅彦)・蓬里雨(豊隆)]
その十九「昭和十年(一九三五)」
[東洋城・五十八歳。「満二十年記念号」刊。湘南大会挙行。伊予鹿島に句碑建つ。十二月三十一日、寺田寅彦没。]
.jpg)
「松山市北条鹿島にある石碑(東洋城句碑)」(「伊達博(伊達博物館)通信」)
「鹿に聞け /潮の秋する/ そのことは/東洋城」
http://datehaku.blogspot.com/2011/12/blog-post_29.html
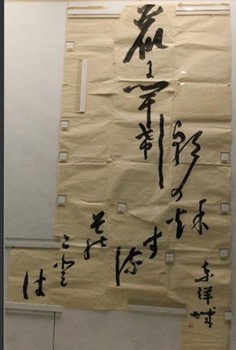
「松山市北条鹿島にある石碑(東洋城句碑)下書き(石の曲がりに合わせてつぎはぎをしている下書き/非常に珍しい物である)」(「伊達博(伊達博物館)通信」)
「鹿に聞け /潮の秋する/ そのことは/東洋城」
http://datehaku.blogspot.com/2011/12/blog-post_29.html
涼しさや山の墓また海の墓(前書「伊予鹿嶋に吾が句碑建つ。野州塩原のと東西二碑なり」)
風薫れ島神へさてともがらに(前書「鹿島の句碑除幕式に祝電」)
※ 「野州塩原の碑」は、下記のアドレスの「松根東洋城両面碑(塩原温泉・四季郷)」であろう。
https://yahan.blog.ss-blog.jp/2023-11-26
https://yahan.blog.ss-blog.jp/2023-11-17
(再掲)
〇松根東洋城両面碑 塩湧橋先
【碑文】
「さまみえて土になりゐる落葉哉」表
「すずしさやこの山水に出湯とは」裏 (塩原四季郷より)
http://hotyu.starfree.jp/historicalspots/bungakuhi/bungakuhi.html
「病寅日子君を慰む 五句」
秋雨や人の病にわが病(前書「君は腰を余は風邪を」)
足腰に三つの湯婆(トウバ)や冬を待つ(※「湯婆(タンポ)」=「湯タンポ」)
仰(「アオ(ムケ)」)に寝て秋の空見る遥かかな
まがつみの背骨にからむ寒さかな(※「まが」=「禍」=「禍罪」=災難)
時雨(シグ)るゝ夜(ヨ)歌仙の夢もありぬべし
「『寺田寅彦追悼号』より 三句」(昭和十一年)
山茶花の白きに凍る涙かな
山茶花の久の曇りや今日よりは
枯菊や心の富を痩せたまひ
[寅彦(寅日子)・五十八歳。昭和十年(一九三五)。十二月三十一日没。
2月19日、地震研究所談話会で「水準線路の昇降と温泉の分布」(宮部と共著)を発表。3月12日、帝国学士院で“Hot Springs and Deformation of Earth’s Crust. PartⅡ”(with N. Miyabe)を発表。4月16日、地震研究所談話会で「コロイドと地震学(第一報)」を発表。5月23日、理化学研究所学術講演会で「割れ目と生命(第二報)」(渡部との共著)および「墨汁の諸性質(第五報)」(山本・渡部と共著)を発表。
6月12日、帝国学士院で“Cataphoresis of Chinese Ink in Water Containing Deuterium Oxide”(with R. Yamamoto)および“Relation between Topography and Vertical Displacement of Earth’s Crust”(with N. Miyabe)を発表。7月4日、『文学』の座談会(「日本文学に於ける和歌俳句の不滅性」)に出席。9月17日、地震研究所談話会で「浅間火山爆発実見記」を発表。10月1日、従三位に叙せられる。
11月19日、理化学研究所学術講演で「墨汁の諸性質(第六報)」(山本・渡部と共著)を発表。11月、島薗博士の診察を受ける。疼痛は身体各所に現われるようになる。12月3日、日本学術振興会第四特別委員会委員を委嘱される。12月17日、地震研究所談話会で「宮古—青森間地殻の垂直変動」(宮部と共著)を発表。
12月31日、病勢次第に募り、午後零時28分死去。病は転移性骨腫瘍。
「夢判断」、『文芸春秋』、1月。
「新春偶語」、『都新聞』、1月。
「新年雑俎」、『一橋新聞』、1月。
「追憶の医師達」、『実験治療』、1月。
「西鶴と科学」、『日本文学講座』、改造社、1月。
「自由画稿」、『中央公論』、1〜5月。
「Hakari no Hari」、『RS』、1月。
「相撲」、『時事新報』、1月。
「蛆の効用」、『自由画稿』、2月。
「颱風雑俎」、『思想』、2月。
「詩と官能」、『渋柿』、2月。
「鴉と唱歌」、『野鳥』、2月。
「映画雑感」、『セルパン』、2月。
「人間で描いた花模様」、『高知新聞』、2月。
「一般人の間へ」、普及講座『防災科学』、岩波書店、3月。
「最近の映画に就て——俳諧的な情味などを」、『帝国大学新聞』、4月。
「映画雑感」、『渋柿』、4月。
アンケート「古事記全歌謡の註釈と鑑賞」、『文学』、4月。
「土井八枝『土佐の方言』序文」、春陽堂、5月。
「物売りの声」、『文学』、5月。
「伯林大学(1909‐1910)」、『輻射』、5月。
「五月の唯物観(A)——ホルモン分泌の周期」、『大阪朝日新聞』、5月。
「五月の唯物観(B)——ホルモン分泌の数式」」、『大阪朝日新聞』、5月。
「清少納言の健康——五月の唯物観(C)」、『大阪朝日新聞』、5月。
「映画雑感」、『映画評論』、5月。
「箱根熱海バス紀行」、『短歌研究』、6月。
「随筆難」、『経済往来』、6月。
「映画雑感」、『渋柿』、6月。
「『漱石襍記』——豊隆の新著について」、『帝国大学新聞』、6月。
「Neko sanbiki」、『RS』、6月。
「『万華鏡』再刊添え書」、岩波書店、6月。
「『物質と言葉』再刊添え書」、岩波書店、6月。
『蛍光板』、岩波書店、7月。
「B教授の死」、『文学』、7月。
「災難雑考」、『中央公論』、7月。
「僕流の見方」、『映画と演芸』、7月。
「海水浴」、『文芸春秋』、8月。
「糸車」、『文学』、8月。
「映画と生理」、『セルパン』、8月。
「映画雑感」、『渋柿』、8月。
「静岡地震被害見学記」、『婦人之友』、9月。
「高原」、『家庭』、9月。
「小浅間」、『東京朝日新聞』、9月。
アンケート「ローマ字綴方に関する諸家の意見」、『言語問題』、9月。
「映画雑感」、『渋柿』、10月。
「雨の上高地」、『登山とスキー』、10月。
「日本人の自然観」、岩波講座『東洋思潮』、10月。
「俳句の精神」、『俳句作法講座』、改造社、10月。
「小爆発二件」、『文学』、11月。
「三斜晶系」、『中央公論』、11月。
「埋もれた漱石伝記資料」、『思想』、11月 ]
なつかしや末生(ウラナリ)以前の青嵐(「渋柿七月」)
「手帳の中より、十年八月一日グリーンホテル三句」
鶯や夏を浅間のから松に(八月一日松根豊次郎氏絵葉書「軽井沢より」)
白樺の窓松の窓風薫る(「同前」)
萱草(カンゾウ)や浅間をかくすちぎれ雲(※「寅彦」の絶句とも?)
※ この「八月一日松根豊次郎氏絵葉書『軽井沢より』」の全文は次のとおり。
[八月一日 木 長野県北佐久郡軽井沢千ケ瀧グリーンホテルより品川区上大崎一ノ四七〇松根豊次郎氏へ(絵葉書 署名の「寅」に輪を施しあり)
今夜はグリーンホテルへ泊つて原稿を書いてゐる。午後は星野へ下りてそれから子供等と附近や軽井沢を歩いてゐる。今年は天気に恵まれて高原の涼気を満喫することが出来て仕合せです。星野にゐると人の出入りがしげくて仕事は出来ないが此処は実に閑寂で先般来の神経の疲れも十二分に休める事が出来さうです。
白樺の窓松の窓風薫る
鶯や夏を浅間のから松に 寅 ]
[豊隆(蓬里雨)・五十二歳。昭和十年(一九三五)。一月『能と歌舞伎』出版。五月『漱石襍記』出版。七月合著『西鶴俳諧研究』出版。十二月寺田寅彦が死んだ。]
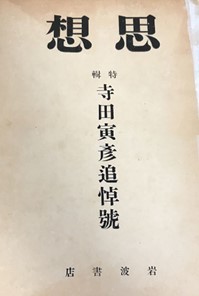
『思想 特輯 寺田寅彦追悼號』(特集 寺田寅彦追悼号) 岩波書店 昭和11年(1936年) 3月号初版(表紙)
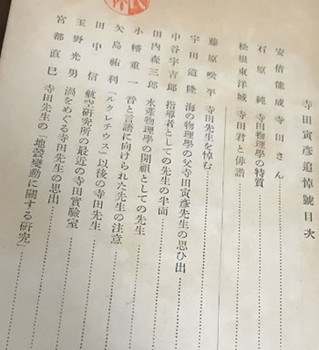
『同上』(目次)
※ 上記の「目次」を見ると、「安倍能成(寺田さん)・石原純(寺田物理学の特質)・松根東洋城(寺田君と俳諧)/藤原咲平(寺田先生を悼む)・宇田道隆(海の物理学の父寺田寅彦先生の思ひ出)・中谷宇吉郎(指導者としての先生の半面)・田内森三郎(水産物理学の開祖としての先生)・小幡重一(音と言語に向けられた先生の注意)・矢島祐利(「ルクレチウス」以後の寺田先生)・田中信(航空研究所の最近の実験室)・玉野光男(渦をめぐる寺田先生の思出)・宮沢直巳(寺田先生の「地殻変動の研究」)」が、その名を連ねている。
ここに、当然に名を連ねるべき「小宮豊隆(蓬里雨)」の名がない。これらに関して、上記の追悼文の中で、「中谷宇吉郎(指導者としての先生の半面)」は、下記のアドレスで閲覧することが出来る。
https://www.aozora.gr.jp/cards/001569/files/53224_49846.html
[「「指導者としての寺田先生(中谷宇吉郎)」(抜粋)
先生の臨終の席に御別(おわかれして、激しい心の動揺に圧(おさ)れながらも、私はやむをえぬ事情のために、その晩の夜行で帰家の途に就いた。同じ汽車で小宮(こみや)さんも仙台へ帰られたので、途中色々先生の追想を御伺いする機会を与えられた。三十年の心の友を失われた小宮さんは、ひどく力を落された御(ご)様子でボツリボツリと思い出を語られた。常磐線(じょうばんせん)の暗い車窓を眺めながら、静かに語り出される御話を伺っている中(うち)に、段々切迫した気持がほぐれて来て、今にも涙が零(こぼれ)そうになって困った。小宮さんが先生の危篤の報に急いで上京される途次、仙台のK教授に御(お)会いになったら、その由を聞かれて大変愕(おどろ)かれて、「本当に惜しい人だ、専門の学界でも勿論(もちろん)大損失だろうが、特に若い連中が張合いを失って力を落すことだろう」といわれたという話が出た。その話を聞いたら急に心の張りが失せて、今まで我慢していた涙が出て来て仕様がなかった。(以下略) ) ]
ここに出て来る、「三十年の心の友を失われた小宮さんは、ひどく力を落された御(ご)様子でボツリボツリと思い出を語られた」の、この「小宮さん」こと、これが、当時の「小宮豊隆(蓬里雨)」の実像で、その知己(「岩波茂雄・和辻哲郎・阿部次郎」など)の携わっていた、その「思想」の、その「追悼号」に、一文を遺さず、その「三十年の心の友」の「寺田寅彦(寅日子)」への追悼句は、何と、亡くなる最晩年(東洋城が没する昭和三十九年=一九六四)に近い、「昭和三十七年十一月二十五日 寺田寅彦忌 二句」(七十九歳)として、その『蓬里雨句集』に収録されている。
柿一つ残る梢に時雨かな(前書「寺田寅彦忌/十月二十五日/二句」)
もごもごと苺を喰ひし君が口(同上)
(追記その一) 「破門」(『漱石・寅彦・三重吉(小宮豊隆著・岩波書店)』所収)周辺
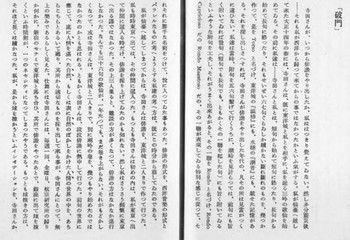
「破門」(『漱石・寅彦・三重吉(小宮豊隆著・岩波書店)』(「国立国会図書館デジタルコレクション」)
https://dl.ndl.go.jp/pid/1127319/1/147
太平洋戦争が勃発した翌年の昭和十七年(一九四三)に、小宮豊隆は、『漱石・寅彦・三重吉(小宮豊隆著・岩波書店)』を刊行する。これは、豊隆の「漱石・寅彦・(鈴木)三重吉・(芥川)龍之介」に関する回想録ともいうべきもので、その内容(目次)は、次のとおりである。
[目次
漱石と戀愛/1
漱石二題/15
漱石と讀書/32
漱石と畫/39
漱石と烟草/49
決定版『漱石全集』/56
僞物/60
靈夢/72
「かな」と「がね」と/78
ラヂオの『坊ちやん』/89
『坊ちやん』とそのモデル/93
『三四郎』の材料/103
『行人』の材料/112
『明暗』の材料/129
漱石二十三囘忌/144
休息している漱石/152
日記の中から/184
修善寺日記/203
雪鳥君の『修善寺日記』/248
『腕白時代の夏目君』はしがき/256
『藪柑子集』の後に/261 → 大正十二年一月二十六日
『冬彦集』後語/264 → 大正十一年十二月二十日
『萬華鏡』/267 → 昭和四年八月六日
『觸媒』/270 → 昭和九年十二月二十五日
『寅彦全集』/275 → 昭和十二年九月
「破門」/278 → 昭和十一年一月二十三日
『橡の實』のはじめに/286 → 昭和十一年二月二十一日
『囘想の寺田寅彦』序/297 → 昭和十二年八月一日
三重吉の思ひ出/307
鈴木三重吉/312
三重吉のこと/324
『三重吉童話全集』序/339
芥川龍之介の死/345
一插話/358 ]『漱石・寅彦・三重吉(小宮豊隆著・岩波書店)』(「国立国会図書館デジタルコレクション」)
『思想 特輯 寺田寅彦追悼號』(特集 寺田寅彦追悼号) 岩波書店 昭和11年(1936年) 3月号の、「松根東洋城(寺田君と俳諧)」の追悼文中の、「『小宮の所謂破門』的爆弾(「渋柿」寅彦追悼号所載)の、その全文は、上記目次の[「破門」/278→ 昭和十一年一月二十三日]で収載されている。
(再掲)
https://yahan.blog.ss-blog.jp/2023-11-30
[豊隆(蓬里雨)・昭和七年(一九三二)、三十三歳。]
『漱石 寅彦 三重吉(小宮豊隆著・岩波書店)』(昭和十七年初版)の中に、「破門」(昭和十一年一月二十三日「渋柿(寺田寅彦追悼号)」初出)という、豊隆が寅彦より「もう君とは俳諧をやらない」と、「東洋城・寅彦・蓬里雨」の三吟俳諧(連句)の座から「破門」されたという内容のものがある。
[(前略)
―― 或時、たしか京橋の竹葉で三人(※「東洋城・寅彦・蓬里雨」)一緒に飯を喰つてゐた時だった。寺田さんは急に眞顔になつて、私に、もう君とは一緒に俳諧をやらないと言ひ出した。―― 君のやうに不熱心ではしやうがない。僕はうちの者の機嫌をとつて、うちで会をしてゐる。それなのに君は一向真面目に句を作らない。雑談計りしてゐる。それでなければ昼寝をする。君のやうな不誠実な人間は破門する。――
(中略)
―― 是が寺田さんと私との長いつき合ひの間に、寺田さんから叱られた唯一の思ひ出である。寺田さんと話をしてゐると、時々横つ面を張り飛ばされるやうに感じる事がある。然しそれは、大抵こつちが何等の点で、馬鹿になつてゐる時、いい気にゐる時である。その際寺田さんの方では、別にこつちの横つ面を張り飛ばさうと意図してゐる訳ではなく、寺田さんから言へば、ただ当り前の事を言つてゐるのが、此方では横つ面を張り飛ばされて感じるのである。然し是はさうではない。寺田さんはほんとに叱る積りで叱つたのである。然もよくよく考へて見ると、寺田さんの叱つたのは、私の俳諧のみではなかつた。私の仕事、私の学問、私の生活。
―― いつまでたつても「後見人」を必要とするやうな私の一切を、寺田さんは是で叱つたのだといふ気が、段段して来る事を、私は禁じ得ない。これは或は私の感傷主義であつたとしても、少くとも寺田さんの俳諧に対する打ち込み方、学問に対する打ち込み方、生活に対する打ち込み方、――人生の凡てののもを受けとる受けとり方を、最も鮮やかに代表してゐるものであつたとは、言ふ事が出来るのである。 ](『漱石 寅彦 三重吉(小宮豊隆著・岩波書店)p278-285』 )
この[「東洋城・寅彦・蓬里雨」の三吟俳諧(連句)の座から「蓬里雨破門」]関連については、『寺田君と俳諧』(『東洋城全句集(下巻)』所収)で、東洋城は、次のとおり記述している。
[ 始め連句は小宮君が仙台から上京するを機会とし三人の会で作つてゐた、それで一年に二度来るか三度来るかといふ小宮君を待つてのことだから一巻が中々進行しない。其上小宮君の遅吟乃至不勉強が愈々進行を阻害する。一年経つも一巻も上がらぬ、両人で癇癪を起し、仕舞には小宮君が上京しても三人会は唯飯を食ふ雑談の会として連句のことは一切持出さないことにしてしまつた。そこで余との両吟に自ら力が入つて来、屡(シバシバ)二人会合するやうになつた。昭和四年・五年は少なく、両吟・三吟各一連に過ぎなかったが、六年に至っては俄然増加して、両吟七、三吟一歌仙を巻きあげた。](『東洋城全句集(下巻))』所収「寺田君と俳諧」) ]
(追記その二) 『思想 特輯 寺田寅彦追悼號』(特集 寺田寅彦追悼号) 岩波書店 昭和11年(1936年) 3月号の、「松根東洋城(寺田君と俳諧)」周辺
[(オ)
蝸牛やその紫陽花を樹々の底 東洋城
むつと湿りの暑い土の香 寅日子
表戸を下ろした後の潜りにて 城
暈(カサ)着た月の晴れて行く空 蓬里雨 月
張り切つて纜(トモヅナ)ゆるゝ望の潮 子
一つの鯔(イナ)の三段に飛ぶ 城
(ウ)
ものゝふの戈(ホコ)を横へ詠(ヨ)へる哉 城
流沙(ルサ)の果に紺碧(コンペキ)の山 子
群鴉(カラス)人里やがて見え初(ソ)めて 子
土橋の札(フダ)の勧化(カンゲ)断り 城
足音に濁り立(タ)てたる河の魚 子
袖肌寒う二人寄り添ふ 城 恋
中門の忍び草の月の影 子 恋 月
(昭和十年五月十七~八月三十日 軽井沢への車中) ]
※ 『思想 特輯 寺田寅彦追悼號』(特集 寺田寅彦追悼号)所収「松根東洋城(寺田君と俳諧)」の末尾に「作りかけの歌仙一つ。―――」として、上記の未完の「歌仙」(昭和十年五月十七~八月三十日 軽井沢への車中) が掲載されている。それに続いて、次の寅彦の「東洋城宛書簡」と東洋城のメモが記されている。
[ 十三日は学術振興会のある事を忘れてゐて、朝思出し電話をかけた。悪しからず。信州から帰つてから足を痛め、びつこ引いて歩いてゐたら、その為か腹の筋が引きつつて起居が不自由で、その上胃の具合まで狂つて弱つてゐるが寝込む程でもないので、よぼよぼしながら出勤してゐる。少しヒカンした。からだが不自由だと癇シヤクが起つて困る。
中門の忍び車の月の影
読めば昔は美しの恋
では如何哉
今週金曜は多分大丈夫のつもりです。
九月十六日(※昭和十年)
本郷曙町 寺田寅彦
今朝映画雑感を送りました
―――(最後の書簡)
「付句秋季でなくちやいけないぢやないか」と言ひかけて口をつぐむ。(※「東洋城」のメモ書きで、「『秋の月』の付句は『秋季』の句がルールと、何時ものクセが口を突いたが、またまた、寅日子に癇シャクをくらってはと、口をつぐんだ」というよう意であろう) ](「昭和十一年三月、思想第一六六号」)
※ この末尾の「作りかけの歌仙一つ。―――」の前に、寅彦が亡くなる前後のことについて、東洋城は、次のように記述している。
[ 余(※東洋城)は親しく病歴に持した。その病漸く重きに至つて苦悩をまさしく見、その末期の水を与へ、最後の一息を見極め、その棺に釘打つ際の面への訣別をなし、葬儀万端に列し、野辺の送りをなし、その焼け尽くした熱灰に対し、その白骨を拾ひ、壺に納めて携へて帰つた。彼の肉体の遂にまざまざと滅亡に帰したこと、これより明々歴々なことはない。余が眼疑ふことは出来ず、余が心誤るにはあまりに明らかだ。既に十日祭を過ぎ、二十日祭を過ぎた或夕、用を以て新宿に来、用を了つてふと思ひ立ち、ありし昔をなつかしくモナミの地下へもぐつた。八月九日(※東洋城と寅日子の最後の「モナミ」での両吟の日)以来だから、丁度五月(※五ケ月)を経てゐる。(中略)
そこに、余には一つの奇跡が起つた。自分の前の空席に寺田君がゐる。正に居る、勿論形は無い。その姿はないが温容が迫る、その声はないが話が聞こえる。明に空席であるが、寺田君が居る。(中略)
此時以来、余には寺田君は死んでゐないことになった。(中略)
さうして余は今後、金曜日には君の霊と一しよに連句を作るべく、時々モナミの夕を一人で過ごさうと心にきめた。ふと一句口を衝いて出たが、急にシャンデリアの明るさを強く感じた。
君が席のけふは留守なる冬夜哉 ](『東洋城全句集(下巻))』所収「寺田君と俳諧」)
[ 寺田寅彦は昭和十年十二月三十一日、東京市本郷曙町二十四番地の自邸で、五十七歳二カ月の生涯を終えた。病名は転移性骨腫瘍であった。剖検記録はない。
告別式は、昭和十一年一月六日、谷中斎場で行われた。寺田家のしきたり通り神式であった。葬儀委員長は理化学研究所所長、子爵大河内正敏が務めた。夏目漱石の『三四郎』に描かれているように青年時代の大河内と寅彦は、穴蔵のような理科大学の地下室でともに研究生活を送っている。弔辞は東京大学総長長与又郎、同地震研究所所長石本巳四雄、友人総代安倍能成、門弟代表藤原平が読んだ。
小林勇氏は『回想の寺田寅彦』の「告別式」で「これらの弔辞が寂としたあたりの中へ響いて行く時人々は咳一つせず沈黙の底に沈んでゐたが、安倍教授の弔辞が進むに従って、会葬者の席からあちらこちらにすすり泣きの声が聞え始めた」と記している。 ](『寺田寅彦覚書(山田一郎著・岩波書店)』)
(追記その三) 「俳句の精神」(初出「俳句作法講座(改造社)」1935(昭和10)年10月)
https://www.aozora.gr.jp/cards/000042/card2513.html
一 俳句の成立と必然性
二 俳句の精神とその修得の反応(抜粋)
[ 風流とかさびとかいう言葉が通例消極的な遁世的《とんせいてき》な意味にのみ解釈され、使用されて来た。これには歴史的にそうなるべき理由があった。すなわち仏教伝来以後今日まで日本国民の間に浸潤した無常観が自然の勢いで俳句の中にも浸透したからである。
しかし自分の見るところでは、これは偶然のことであって決して俳句の精神と本質的に連関しているものとは思われない。仏教的な無常観から解放された現代人にとっては、積極的な「風流」、能動的な「さび」はいくらでも可能であると思われる。
日常劇務に忙殺される社会人が、週末の休暇にすべてを忘却して高山に登る心の自由は風流である。営利に急なる財界の闘士が、早朝忘我の一時間を菊の手入れに費やすは一種の「さび」でないとは言われない。日常生活の拘束からわれわれの心を自由の境地に解放して、その間にともすれば望ましき内省の余裕を享楽するのが風流であり、飽くところを知らぬ欲望を節制して足るを知り分に安んずることを教える自己批判がさびの真髄ではあるまいか。 ]
[東洋城・五十八歳。「満二十年記念号」刊。湘南大会挙行。伊予鹿島に句碑建つ。十二月三十一日、寺田寅彦没。]
.jpg)
「松山市北条鹿島にある石碑(東洋城句碑)」(「伊達博(伊達博物館)通信」)
「鹿に聞け /潮の秋する/ そのことは/東洋城」
http://datehaku.blogspot.com/2011/12/blog-post_29.html
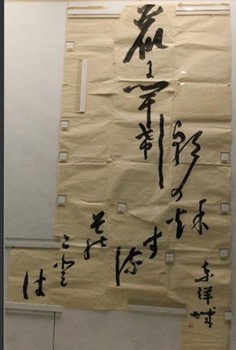
「松山市北条鹿島にある石碑(東洋城句碑)下書き(石の曲がりに合わせてつぎはぎをしている下書き/非常に珍しい物である)」(「伊達博(伊達博物館)通信」)
「鹿に聞け /潮の秋する/ そのことは/東洋城」
http://datehaku.blogspot.com/2011/12/blog-post_29.html
涼しさや山の墓また海の墓(前書「伊予鹿嶋に吾が句碑建つ。野州塩原のと東西二碑なり」)
風薫れ島神へさてともがらに(前書「鹿島の句碑除幕式に祝電」)
※ 「野州塩原の碑」は、下記のアドレスの「松根東洋城両面碑(塩原温泉・四季郷)」であろう。
https://yahan.blog.ss-blog.jp/2023-11-26
https://yahan.blog.ss-blog.jp/2023-11-17
(再掲)
〇松根東洋城両面碑 塩湧橋先
【碑文】
「さまみえて土になりゐる落葉哉」表
「すずしさやこの山水に出湯とは」裏 (塩原四季郷より)
http://hotyu.starfree.jp/historicalspots/bungakuhi/bungakuhi.html
「病寅日子君を慰む 五句」
秋雨や人の病にわが病(前書「君は腰を余は風邪を」)
足腰に三つの湯婆(トウバ)や冬を待つ(※「湯婆(タンポ)」=「湯タンポ」)
仰(「アオ(ムケ)」)に寝て秋の空見る遥かかな
まがつみの背骨にからむ寒さかな(※「まが」=「禍」=「禍罪」=災難)
時雨(シグ)るゝ夜(ヨ)歌仙の夢もありぬべし
「『寺田寅彦追悼号』より 三句」(昭和十一年)
山茶花の白きに凍る涙かな
山茶花の久の曇りや今日よりは
枯菊や心の富を痩せたまひ
[寅彦(寅日子)・五十八歳。昭和十年(一九三五)。十二月三十一日没。
2月19日、地震研究所談話会で「水準線路の昇降と温泉の分布」(宮部と共著)を発表。3月12日、帝国学士院で“Hot Springs and Deformation of Earth’s Crust. PartⅡ”(with N. Miyabe)を発表。4月16日、地震研究所談話会で「コロイドと地震学(第一報)」を発表。5月23日、理化学研究所学術講演会で「割れ目と生命(第二報)」(渡部との共著)および「墨汁の諸性質(第五報)」(山本・渡部と共著)を発表。
6月12日、帝国学士院で“Cataphoresis of Chinese Ink in Water Containing Deuterium Oxide”(with R. Yamamoto)および“Relation between Topography and Vertical Displacement of Earth’s Crust”(with N. Miyabe)を発表。7月4日、『文学』の座談会(「日本文学に於ける和歌俳句の不滅性」)に出席。9月17日、地震研究所談話会で「浅間火山爆発実見記」を発表。10月1日、従三位に叙せられる。
11月19日、理化学研究所学術講演で「墨汁の諸性質(第六報)」(山本・渡部と共著)を発表。11月、島薗博士の診察を受ける。疼痛は身体各所に現われるようになる。12月3日、日本学術振興会第四特別委員会委員を委嘱される。12月17日、地震研究所談話会で「宮古—青森間地殻の垂直変動」(宮部と共著)を発表。
12月31日、病勢次第に募り、午後零時28分死去。病は転移性骨腫瘍。
「夢判断」、『文芸春秋』、1月。
「新春偶語」、『都新聞』、1月。
「新年雑俎」、『一橋新聞』、1月。
「追憶の医師達」、『実験治療』、1月。
「西鶴と科学」、『日本文学講座』、改造社、1月。
「自由画稿」、『中央公論』、1〜5月。
「Hakari no Hari」、『RS』、1月。
「相撲」、『時事新報』、1月。
「蛆の効用」、『自由画稿』、2月。
「颱風雑俎」、『思想』、2月。
「詩と官能」、『渋柿』、2月。
「鴉と唱歌」、『野鳥』、2月。
「映画雑感」、『セルパン』、2月。
「人間で描いた花模様」、『高知新聞』、2月。
「一般人の間へ」、普及講座『防災科学』、岩波書店、3月。
「最近の映画に就て——俳諧的な情味などを」、『帝国大学新聞』、4月。
「映画雑感」、『渋柿』、4月。
アンケート「古事記全歌謡の註釈と鑑賞」、『文学』、4月。
「土井八枝『土佐の方言』序文」、春陽堂、5月。
「物売りの声」、『文学』、5月。
「伯林大学(1909‐1910)」、『輻射』、5月。
「五月の唯物観(A)——ホルモン分泌の周期」、『大阪朝日新聞』、5月。
「五月の唯物観(B)——ホルモン分泌の数式」」、『大阪朝日新聞』、5月。
「清少納言の健康——五月の唯物観(C)」、『大阪朝日新聞』、5月。
「映画雑感」、『映画評論』、5月。
「箱根熱海バス紀行」、『短歌研究』、6月。
「随筆難」、『経済往来』、6月。
「映画雑感」、『渋柿』、6月。
「『漱石襍記』——豊隆の新著について」、『帝国大学新聞』、6月。
「Neko sanbiki」、『RS』、6月。
「『万華鏡』再刊添え書」、岩波書店、6月。
「『物質と言葉』再刊添え書」、岩波書店、6月。
『蛍光板』、岩波書店、7月。
「B教授の死」、『文学』、7月。
「災難雑考」、『中央公論』、7月。
「僕流の見方」、『映画と演芸』、7月。
「海水浴」、『文芸春秋』、8月。
「糸車」、『文学』、8月。
「映画と生理」、『セルパン』、8月。
「映画雑感」、『渋柿』、8月。
「静岡地震被害見学記」、『婦人之友』、9月。
「高原」、『家庭』、9月。
「小浅間」、『東京朝日新聞』、9月。
アンケート「ローマ字綴方に関する諸家の意見」、『言語問題』、9月。
「映画雑感」、『渋柿』、10月。
「雨の上高地」、『登山とスキー』、10月。
「日本人の自然観」、岩波講座『東洋思潮』、10月。
「俳句の精神」、『俳句作法講座』、改造社、10月。
「小爆発二件」、『文学』、11月。
「三斜晶系」、『中央公論』、11月。
「埋もれた漱石伝記資料」、『思想』、11月 ]
なつかしや末生(ウラナリ)以前の青嵐(「渋柿七月」)
「手帳の中より、十年八月一日グリーンホテル三句」
鶯や夏を浅間のから松に(八月一日松根豊次郎氏絵葉書「軽井沢より」)
白樺の窓松の窓風薫る(「同前」)
萱草(カンゾウ)や浅間をかくすちぎれ雲(※「寅彦」の絶句とも?)
※ この「八月一日松根豊次郎氏絵葉書『軽井沢より』」の全文は次のとおり。
[八月一日 木 長野県北佐久郡軽井沢千ケ瀧グリーンホテルより品川区上大崎一ノ四七〇松根豊次郎氏へ(絵葉書 署名の「寅」に輪を施しあり)
今夜はグリーンホテルへ泊つて原稿を書いてゐる。午後は星野へ下りてそれから子供等と附近や軽井沢を歩いてゐる。今年は天気に恵まれて高原の涼気を満喫することが出来て仕合せです。星野にゐると人の出入りがしげくて仕事は出来ないが此処は実に閑寂で先般来の神経の疲れも十二分に休める事が出来さうです。
白樺の窓松の窓風薫る
鶯や夏を浅間のから松に 寅 ]
[豊隆(蓬里雨)・五十二歳。昭和十年(一九三五)。一月『能と歌舞伎』出版。五月『漱石襍記』出版。七月合著『西鶴俳諧研究』出版。十二月寺田寅彦が死んだ。]
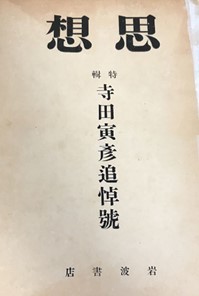
『思想 特輯 寺田寅彦追悼號』(特集 寺田寅彦追悼号) 岩波書店 昭和11年(1936年) 3月号初版(表紙)
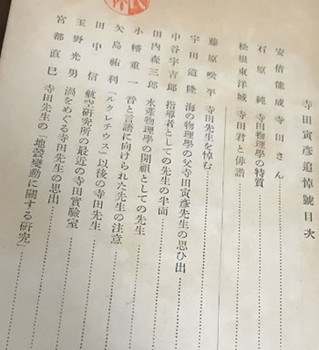
『同上』(目次)
※ 上記の「目次」を見ると、「安倍能成(寺田さん)・石原純(寺田物理学の特質)・松根東洋城(寺田君と俳諧)/藤原咲平(寺田先生を悼む)・宇田道隆(海の物理学の父寺田寅彦先生の思ひ出)・中谷宇吉郎(指導者としての先生の半面)・田内森三郎(水産物理学の開祖としての先生)・小幡重一(音と言語に向けられた先生の注意)・矢島祐利(「ルクレチウス」以後の寺田先生)・田中信(航空研究所の最近の実験室)・玉野光男(渦をめぐる寺田先生の思出)・宮沢直巳(寺田先生の「地殻変動の研究」)」が、その名を連ねている。
ここに、当然に名を連ねるべき「小宮豊隆(蓬里雨)」の名がない。これらに関して、上記の追悼文の中で、「中谷宇吉郎(指導者としての先生の半面)」は、下記のアドレスで閲覧することが出来る。
https://www.aozora.gr.jp/cards/001569/files/53224_49846.html
[「「指導者としての寺田先生(中谷宇吉郎)」(抜粋)
先生の臨終の席に御別(おわかれして、激しい心の動揺に圧(おさ)れながらも、私はやむをえぬ事情のために、その晩の夜行で帰家の途に就いた。同じ汽車で小宮(こみや)さんも仙台へ帰られたので、途中色々先生の追想を御伺いする機会を与えられた。三十年の心の友を失われた小宮さんは、ひどく力を落された御(ご)様子でボツリボツリと思い出を語られた。常磐線(じょうばんせん)の暗い車窓を眺めながら、静かに語り出される御話を伺っている中(うち)に、段々切迫した気持がほぐれて来て、今にも涙が零(こぼれ)そうになって困った。小宮さんが先生の危篤の報に急いで上京される途次、仙台のK教授に御(お)会いになったら、その由を聞かれて大変愕(おどろ)かれて、「本当に惜しい人だ、専門の学界でも勿論(もちろん)大損失だろうが、特に若い連中が張合いを失って力を落すことだろう」といわれたという話が出た。その話を聞いたら急に心の張りが失せて、今まで我慢していた涙が出て来て仕様がなかった。(以下略) ) ]
ここに出て来る、「三十年の心の友を失われた小宮さんは、ひどく力を落された御(ご)様子でボツリボツリと思い出を語られた」の、この「小宮さん」こと、これが、当時の「小宮豊隆(蓬里雨)」の実像で、その知己(「岩波茂雄・和辻哲郎・阿部次郎」など)の携わっていた、その「思想」の、その「追悼号」に、一文を遺さず、その「三十年の心の友」の「寺田寅彦(寅日子)」への追悼句は、何と、亡くなる最晩年(東洋城が没する昭和三十九年=一九六四)に近い、「昭和三十七年十一月二十五日 寺田寅彦忌 二句」(七十九歳)として、その『蓬里雨句集』に収録されている。
柿一つ残る梢に時雨かな(前書「寺田寅彦忌/十月二十五日/二句」)
もごもごと苺を喰ひし君が口(同上)
(追記その一) 「破門」(『漱石・寅彦・三重吉(小宮豊隆著・岩波書店)』所収)周辺
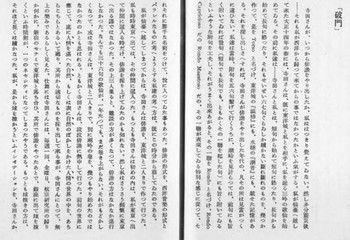
「破門」(『漱石・寅彦・三重吉(小宮豊隆著・岩波書店)』(「国立国会図書館デジタルコレクション」)
https://dl.ndl.go.jp/pid/1127319/1/147
太平洋戦争が勃発した翌年の昭和十七年(一九四三)に、小宮豊隆は、『漱石・寅彦・三重吉(小宮豊隆著・岩波書店)』を刊行する。これは、豊隆の「漱石・寅彦・(鈴木)三重吉・(芥川)龍之介」に関する回想録ともいうべきもので、その内容(目次)は、次のとおりである。
[目次
漱石と戀愛/1
漱石二題/15
漱石と讀書/32
漱石と畫/39
漱石と烟草/49
決定版『漱石全集』/56
僞物/60
靈夢/72
「かな」と「がね」と/78
ラヂオの『坊ちやん』/89
『坊ちやん』とそのモデル/93
『三四郎』の材料/103
『行人』の材料/112
『明暗』の材料/129
漱石二十三囘忌/144
休息している漱石/152
日記の中から/184
修善寺日記/203
雪鳥君の『修善寺日記』/248
『腕白時代の夏目君』はしがき/256
『藪柑子集』の後に/261 → 大正十二年一月二十六日
『冬彦集』後語/264 → 大正十一年十二月二十日
『萬華鏡』/267 → 昭和四年八月六日
『觸媒』/270 → 昭和九年十二月二十五日
『寅彦全集』/275 → 昭和十二年九月
「破門」/278 → 昭和十一年一月二十三日
『橡の實』のはじめに/286 → 昭和十一年二月二十一日
『囘想の寺田寅彦』序/297 → 昭和十二年八月一日
三重吉の思ひ出/307
鈴木三重吉/312
三重吉のこと/324
『三重吉童話全集』序/339
芥川龍之介の死/345
一插話/358 ]『漱石・寅彦・三重吉(小宮豊隆著・岩波書店)』(「国立国会図書館デジタルコレクション」)
『思想 特輯 寺田寅彦追悼號』(特集 寺田寅彦追悼号) 岩波書店 昭和11年(1936年) 3月号の、「松根東洋城(寺田君と俳諧)」の追悼文中の、「『小宮の所謂破門』的爆弾(「渋柿」寅彦追悼号所載)の、その全文は、上記目次の[「破門」/278→ 昭和十一年一月二十三日]で収載されている。
(再掲)
https://yahan.blog.ss-blog.jp/2023-11-30
[豊隆(蓬里雨)・昭和七年(一九三二)、三十三歳。]
『漱石 寅彦 三重吉(小宮豊隆著・岩波書店)』(昭和十七年初版)の中に、「破門」(昭和十一年一月二十三日「渋柿(寺田寅彦追悼号)」初出)という、豊隆が寅彦より「もう君とは俳諧をやらない」と、「東洋城・寅彦・蓬里雨」の三吟俳諧(連句)の座から「破門」されたという内容のものがある。
[(前略)
―― 或時、たしか京橋の竹葉で三人(※「東洋城・寅彦・蓬里雨」)一緒に飯を喰つてゐた時だった。寺田さんは急に眞顔になつて、私に、もう君とは一緒に俳諧をやらないと言ひ出した。―― 君のやうに不熱心ではしやうがない。僕はうちの者の機嫌をとつて、うちで会をしてゐる。それなのに君は一向真面目に句を作らない。雑談計りしてゐる。それでなければ昼寝をする。君のやうな不誠実な人間は破門する。――
(中略)
―― 是が寺田さんと私との長いつき合ひの間に、寺田さんから叱られた唯一の思ひ出である。寺田さんと話をしてゐると、時々横つ面を張り飛ばされるやうに感じる事がある。然しそれは、大抵こつちが何等の点で、馬鹿になつてゐる時、いい気にゐる時である。その際寺田さんの方では、別にこつちの横つ面を張り飛ばさうと意図してゐる訳ではなく、寺田さんから言へば、ただ当り前の事を言つてゐるのが、此方では横つ面を張り飛ばされて感じるのである。然し是はさうではない。寺田さんはほんとに叱る積りで叱つたのである。然もよくよく考へて見ると、寺田さんの叱つたのは、私の俳諧のみではなかつた。私の仕事、私の学問、私の生活。
―― いつまでたつても「後見人」を必要とするやうな私の一切を、寺田さんは是で叱つたのだといふ気が、段段して来る事を、私は禁じ得ない。これは或は私の感傷主義であつたとしても、少くとも寺田さんの俳諧に対する打ち込み方、学問に対する打ち込み方、生活に対する打ち込み方、――人生の凡てののもを受けとる受けとり方を、最も鮮やかに代表してゐるものであつたとは、言ふ事が出来るのである。 ](『漱石 寅彦 三重吉(小宮豊隆著・岩波書店)p278-285』 )
この[「東洋城・寅彦・蓬里雨」の三吟俳諧(連句)の座から「蓬里雨破門」]関連については、『寺田君と俳諧』(『東洋城全句集(下巻)』所収)で、東洋城は、次のとおり記述している。
[ 始め連句は小宮君が仙台から上京するを機会とし三人の会で作つてゐた、それで一年に二度来るか三度来るかといふ小宮君を待つてのことだから一巻が中々進行しない。其上小宮君の遅吟乃至不勉強が愈々進行を阻害する。一年経つも一巻も上がらぬ、両人で癇癪を起し、仕舞には小宮君が上京しても三人会は唯飯を食ふ雑談の会として連句のことは一切持出さないことにしてしまつた。そこで余との両吟に自ら力が入つて来、屡(シバシバ)二人会合するやうになつた。昭和四年・五年は少なく、両吟・三吟各一連に過ぎなかったが、六年に至っては俄然増加して、両吟七、三吟一歌仙を巻きあげた。](『東洋城全句集(下巻))』所収「寺田君と俳諧」) ]
(追記その二) 『思想 特輯 寺田寅彦追悼號』(特集 寺田寅彦追悼号) 岩波書店 昭和11年(1936年) 3月号の、「松根東洋城(寺田君と俳諧)」周辺
[(オ)
蝸牛やその紫陽花を樹々の底 東洋城
むつと湿りの暑い土の香 寅日子
表戸を下ろした後の潜りにて 城
暈(カサ)着た月の晴れて行く空 蓬里雨 月
張り切つて纜(トモヅナ)ゆるゝ望の潮 子
一つの鯔(イナ)の三段に飛ぶ 城
(ウ)
ものゝふの戈(ホコ)を横へ詠(ヨ)へる哉 城
流沙(ルサ)の果に紺碧(コンペキ)の山 子
群鴉(カラス)人里やがて見え初(ソ)めて 子
土橋の札(フダ)の勧化(カンゲ)断り 城
足音に濁り立(タ)てたる河の魚 子
袖肌寒う二人寄り添ふ 城 恋
中門の忍び草の月の影 子 恋 月
(昭和十年五月十七~八月三十日 軽井沢への車中) ]
※ 『思想 特輯 寺田寅彦追悼號』(特集 寺田寅彦追悼号)所収「松根東洋城(寺田君と俳諧)」の末尾に「作りかけの歌仙一つ。―――」として、上記の未完の「歌仙」(昭和十年五月十七~八月三十日 軽井沢への車中) が掲載されている。それに続いて、次の寅彦の「東洋城宛書簡」と東洋城のメモが記されている。
[ 十三日は学術振興会のある事を忘れてゐて、朝思出し電話をかけた。悪しからず。信州から帰つてから足を痛め、びつこ引いて歩いてゐたら、その為か腹の筋が引きつつて起居が不自由で、その上胃の具合まで狂つて弱つてゐるが寝込む程でもないので、よぼよぼしながら出勤してゐる。少しヒカンした。からだが不自由だと癇シヤクが起つて困る。
中門の忍び車の月の影
読めば昔は美しの恋
では如何哉
今週金曜は多分大丈夫のつもりです。
九月十六日(※昭和十年)
本郷曙町 寺田寅彦
今朝映画雑感を送りました
―――(最後の書簡)
「付句秋季でなくちやいけないぢやないか」と言ひかけて口をつぐむ。(※「東洋城」のメモ書きで、「『秋の月』の付句は『秋季』の句がルールと、何時ものクセが口を突いたが、またまた、寅日子に癇シャクをくらってはと、口をつぐんだ」というよう意であろう) ](「昭和十一年三月、思想第一六六号」)
※ この末尾の「作りかけの歌仙一つ。―――」の前に、寅彦が亡くなる前後のことについて、東洋城は、次のように記述している。
[ 余(※東洋城)は親しく病歴に持した。その病漸く重きに至つて苦悩をまさしく見、その末期の水を与へ、最後の一息を見極め、その棺に釘打つ際の面への訣別をなし、葬儀万端に列し、野辺の送りをなし、その焼け尽くした熱灰に対し、その白骨を拾ひ、壺に納めて携へて帰つた。彼の肉体の遂にまざまざと滅亡に帰したこと、これより明々歴々なことはない。余が眼疑ふことは出来ず、余が心誤るにはあまりに明らかだ。既に十日祭を過ぎ、二十日祭を過ぎた或夕、用を以て新宿に来、用を了つてふと思ひ立ち、ありし昔をなつかしくモナミの地下へもぐつた。八月九日(※東洋城と寅日子の最後の「モナミ」での両吟の日)以来だから、丁度五月(※五ケ月)を経てゐる。(中略)
そこに、余には一つの奇跡が起つた。自分の前の空席に寺田君がゐる。正に居る、勿論形は無い。その姿はないが温容が迫る、その声はないが話が聞こえる。明に空席であるが、寺田君が居る。(中略)
此時以来、余には寺田君は死んでゐないことになった。(中略)
さうして余は今後、金曜日には君の霊と一しよに連句を作るべく、時々モナミの夕を一人で過ごさうと心にきめた。ふと一句口を衝いて出たが、急にシャンデリアの明るさを強く感じた。
君が席のけふは留守なる冬夜哉 ](『東洋城全句集(下巻))』所収「寺田君と俳諧」)
[ 寺田寅彦は昭和十年十二月三十一日、東京市本郷曙町二十四番地の自邸で、五十七歳二カ月の生涯を終えた。病名は転移性骨腫瘍であった。剖検記録はない。
告別式は、昭和十一年一月六日、谷中斎場で行われた。寺田家のしきたり通り神式であった。葬儀委員長は理化学研究所所長、子爵大河内正敏が務めた。夏目漱石の『三四郎』に描かれているように青年時代の大河内と寅彦は、穴蔵のような理科大学の地下室でともに研究生活を送っている。弔辞は東京大学総長長与又郎、同地震研究所所長石本巳四雄、友人総代安倍能成、門弟代表藤原平が読んだ。
小林勇氏は『回想の寺田寅彦』の「告別式」で「これらの弔辞が寂としたあたりの中へ響いて行く時人々は咳一つせず沈黙の底に沈んでゐたが、安倍教授の弔辞が進むに従って、会葬者の席からあちらこちらにすすり泣きの声が聞え始めた」と記している。 ](『寺田寅彦覚書(山田一郎著・岩波書店)』)
(追記その三) 「俳句の精神」(初出「俳句作法講座(改造社)」1935(昭和10)年10月)
https://www.aozora.gr.jp/cards/000042/card2513.html
一 俳句の成立と必然性
二 俳句の精神とその修得の反応(抜粋)
[ 風流とかさびとかいう言葉が通例消極的な遁世的《とんせいてき》な意味にのみ解釈され、使用されて来た。これには歴史的にそうなるべき理由があった。すなわち仏教伝来以後今日まで日本国民の間に浸潤した無常観が自然の勢いで俳句の中にも浸透したからである。
しかし自分の見るところでは、これは偶然のことであって決して俳句の精神と本質的に連関しているものとは思われない。仏教的な無常観から解放された現代人にとっては、積極的な「風流」、能動的な「さび」はいくらでも可能であると思われる。
日常劇務に忙殺される社会人が、週末の休暇にすべてを忘却して高山に登る心の自由は風流である。営利に急なる財界の闘士が、早朝忘我の一時間を菊の手入れに費やすは一種の「さび」でないとは言われない。日常生活の拘束からわれわれの心を自由の境地に解放して、その間にともすれば望ましき内省の余裕を享楽するのが風流であり、飽くところを知らぬ欲望を節制して足るを知り分に安んずることを教える自己批判がさびの真髄ではあるまいか。 ]
「東洋城・寅彦、そして、豊隆」(漱石没後~寅彦没まで)俳句・連句管見(その十八) [東洋城・寅日子(寅彦)・蓬里雨(豊隆)]
その十八「昭和九年(一九三四)」
[東洋城・五十七歳。栃木、桐生、佐野にて俳句大会。満州各地を遍歴すること月余に及ぶ。大連にて「東洋城百短冊展」開催。「満州行」連載。「句作問答」始まる。「俳句研究」創刊。品川区上大崎一丁目四七〇へ移転。]
「『満州行』」より二百十一句]中の十句
青嵐しづかに汽船の左舷かな(前書「神戸出港」)
夏海へ今関門の若葉かな(前書「玄海」)
アカシヤの花や大陸第一歩(前書「大陸上陸」)
三伏を奉天城の繁華かな(前書「奉天」)
掘り下げて地獄の道や日の盛(前書「撫順」)
あはれむや塀の崩れに夏柳(前書「柳条溝」)
浴衣着てそぞろに行けば日本かな(前書「新京銀座の夜店」)
楡並木ロシヤ女の夏着かな(前書「哈爾濱」)
夜を秋や七星落ちて七山に(前書「蒙古七山の一の玻璃山遠望」)
峡川につづく水車や夏柳(前書「顧望満州」)
※ この「満州行」で、東洋城が日本を離れていた時に、俳誌「渋柿」の主要同人が「渋柿」を離脱して、新たに「あら野」という俳句結社を作るという、東洋城にとっては、予期しない大きな出来事があった。この主要同人は、「小杉余子(よし)」「上甲平谷(へいこく)」「星野石木」「南仙臥(せんが)」らで、これらの主要同人は、東洋城が最も頼りしていた、謂わば、「渋柿」という俳句結社の中枢を担っていたメンバーでもあった。
この「あら野」については、『俳文学大辞典(角川書店)』では、次のように記述されている。
[ あら野 俳誌
昭和十年(一九三五)一月(創刊)。月間。編集発行人は上甲保一郎(上甲平谷)、選者小杉余子・星野石木。「一に風雅の誠を貫いて平等無礙(むげ)なる方人悦楽の王土を現ずる」を理念とする。昭和十九年の雑誌統合により、「渋柿」に合併。(以下略) ]
小杉余子と上甲平谷とについても、『俳文学大辞典(角川書店)』に記述されているが、「デジタル版 日本人名大辞典+Plus」などでは、次のとおりである。
[小杉余子( こすぎよし) 1888-1961 明治-昭和時代の俳人。
明治21年1月16日生まれ。銀行勤務のかたわら,松根東洋城に師事して大正4年「渋柿」に参加。昭和10年東洋城のもとをはなれ,「あら野」の創刊にくわわる。平明な写生句で知られた。昭和36年8月3日死去。73歳。神奈川県出身。本名は義三。句集に「余子句集」「余子句選」。](「デジタル版 日本人名大辞典+Plus」)
[上甲平谷(じょうこうへいこく)
明治25年4月10日愛媛県生れ。昭和61年8月29日歿。早稲田大学文学部哲学科卒。初め村上霽月、のち河東碧梧桐、次いで松根東洋城の門に入る。俳誌「澁柿」、「あら野」を経て、昭和13年「俳諧藝術」を創刊(のち「火焔」と改題)。句集三冊。
芭蕉俳諧 ( 昭和24年4月10日 冨山房 )
紀行文集 無明一杖 ( 昭和63年7月5日 谷沢書房 )
俳諧襍稿 遊戯三昧 ( 平成4年4月10日 谷沢書房 ) ](「近代文献人名辞典β」)
この「渋柿」離脱と「あら野」の創刊は、結果的には、昭和十三年(一九三八)に、上甲平谷が、新たに「俳諧芸術」を創刊して、内部分裂の結果、昭和十九年(一九四四)の用紙統制による雑誌統合などにより、「渋柿」へと吸収され、事実上姿を消して行くことになる。
何故、このような主要同人の離脱と、新たなる俳誌「あら野」の創刊になったのかという、その要因の一つに、寅彦の言葉ですると、「連句の道の要諦は、銘々が自分の個性を主張すると同時に他者の個性を尊重し受容して御互に活かし合ひ響き合ふ處にある。此れは或意味での則天去私に外ならない、處が君はどうも自分の個性だけで一色にしてしまはうとするので困る」(「大正十五年(一九二六)二月十三日付け松根豊次郎宛書簡」)という、「東洋城の『自我の強さ』『狷介(自分の意志をまげず、人と和合しないこと)』『非妥協・潔癖・厳格・守節・守拙』等々の、その「東洋城個人主宰誌」的な「俳誌運営」からの脱却ということが挙げられるであろう。
そして、そのことは、「あら野」の俳句理念の「平等無礙(むげ)なる方人悦楽の王土を現ずる」という、「平等無礙(むげ)・自由闊達」に、「俳諧道場」(「芭蕉を宗とし俳諧を道として立つ」=「渋柿・東洋城」の理念)ではなく、「俳諧悦楽」(芭蕉を宗とし俳諧を楽(楽しみ)として相互に共有する)ということからも、その一端が覗い知れる。
それと同時に、この時に「渋柿」から離脱した主要同人達には、「渋柿」(東洋城主宰)が、謂わば、「本城」で、その一つの「出城」として、その裾野を拡げるような意味合いもあったことであろう。
しかし、この「渋柿」からの離脱と「あら野」の創刊は、後の、昭和四十八年(一九七三)に刊行された『風狂俳人列伝』(石川桂郎著)によって、「東洋城スキャンダル」の一つとして、次のとおりに記述されることになる。
[ 過日、東洋城がY邸に泊まった折のこと、夫人が別室に床をのべていたときであろうか、暴力をもって東洋城が夫人を犯そうとした。それを知ったYが短刀をつきつけてその無礼をなじり謝罪させたという。Yは東洋城と絶交状態となっていたのだ。Yが新誌に走ると彼についていた多くの弟子もこれに従ってしまい、迎えた側にとってはこの上ない喜びとなった。](『風狂俳人列伝 (石川桂郎著) 』)
この「Y」が、「小杉余(Y)子」であることは、当時の俳人達には容易に想像され得ることであったろう。しかし、この「Y」が、仮に「小杉余(Y)子」としても、余子は、東洋城の生存中の、昭和三十六年(一九六一)に亡くなっており、この『風狂俳人列伝』(石川桂郎著)は目にしていない。
また、水原秋櫻子に俳句の手ほどきをしたという「南仙臥」も、昭和四十四年(一九六九)に他界し、東洋城と、明治三十八年(一九〇五)の「京大・三高俳句会」以来の仲間で、「渋柿」で共に「俳諧(連句)」の研鑽を積んだ同士でもあった「星野石木」も、昭和三十五年(一九六〇)も、東洋城在世中に亡くなっている。
とすると、『風狂俳人列伝(石川桂郎著)』の著者(石川桂郎)に、「ある人から東洋城を書いてみないかと意外な資料を送られ、小説の主題、俗世間にザラにある事件だが、俳句の鬼のような彼に、これほどの女好きな、人間くさい面のあるのを知って、この列伝に加える気になった」という、この「意外の資料を送った人」とは、「上甲保一郎(上甲平谷)」ということになることは、当の「上甲平谷」も、そこまでは考えが及ばなかったのかも知れない。
.jpg)
『風狂俳人列伝(石川桂郎著)』(「中公文庫」)
この『風狂俳人列伝(石川桂郎著)』(「中公文庫」)の帯文の「俳句に憑かれた人びと」の中に、著者(石川桂郎)がいう「俳句の鬼」のような「彼(松根東洋城)」を取り上げることは、著者(石川桂郎)の一つの眼識なのかも知れない。
しかし、「これほどの女好きな、人間くさい面のある」のかという、この一方的な興味本位の見方というのは、「漱石・東洋城・寅彦(寅日子)・豊隆(蓬里雨)」の書簡などからすると、やや飛躍しているという見方も拭えない。
確かに、東洋城の「母(敏子)・妹(房子)、姪(柳原白蓮=血縁関係ではない)」等々に対する「フェミニスト(女性に優しく接する男性)」であることは、その[東洋城全句集(上・中・下)]からして窺い知れるところである。
と同時に、その「子供好き」などを加味するすると、単に、「フェミニスト(女性に優しく接する男性)」というよりも、より「雲上人(クモショウニン・クモノウエノヒト)」(東洋城をよく知る「鈴木三重吉」の「東洋城」あだ名)のように、「普通人(フツウジン)」の「石川桂郎(「桂郎自身も酒食と放言を好む風狂の人」=「ウィキペディア」)」)にとっては、「風狂俳人」というよりも、同根の「風狂の鬼」の「忘れえざる俳人」の一人であったことであろう。
[寅彦(寅日子)・五十七歳。昭和九年(一九三四三)。
1月9日、日本学術振興委員を委嘱され第四部常置委員会委員となる。1月12日、帝国学士院で“On Physical Properties of Chinese Black Ink”(with R. Yamamoto and T. Watanabe)を発表。1月16日、地震研究所談話会で「東北地方の地形に就て」を発表。2月12日、帝国学士院で“On a Regularity in Topographical Features of North-East Japan”を発表。
2月20日、地震研究所談話会で「粉末堆層の破壊に関する実験」を発表。3月12日、帝国学士院で“On the Modes of Fracture of a Layer of Powder Mass”(with T. Watanabe)および“On the Physical Meaning of Periodic Structure in Earth’s Crust”を発表。4月17日、地震研究所談話会で「大陸で収縮する?」および「中国の地形」を発表。
5月12日、帝国学士院で“Revision of Precise Levelling along R. Tenryu from Simosuwa to Kakegawa, 1934”(with N. Miyabe)および“On the Stability of Continental Crust”を発表。5月24日、理化学研究所学術講演会で「墨汁の諸性質(第三報)」(山本・渡部と共著)および「割れ目と生命」を発表。
6月19日、地震研究所談話会で「日本海の深さ」を発表。7月3日、地震研究所談話会で「地殻変動と温泉」を発表。7月12日、帝国学士院で“Hot Springs and Deformation of Earth’s Crust”を発表。
10月24日、水産試験場の海洋学談話会で「日本海海底の変化」を講演。11月12日、帝国学士院で“Results of Revision of Precise Levelling in Tohoku Districts”(with N. Miyabe)を発表。11月15日、理化学研究所学術講演会で「墨汁の諸性質(第四報)」(山本・渡部と共著)および「二三の生理光学的現象」(山本・渡部と共著)を発表。11月20日、地震研究所談話会で「珊瑚礁に就て」を発表。12月12日、帝国学士院で“Vertical Movement of Earth’s Crust and Growth of Coral Reef”を発表。
「初冬の日記から」、『中央公論』、1月。
「猫の穴掘り」、『大阪朝日新聞』、1月、『東京朝日新聞』、1月。
「思出草」、『東炎』、1月。
「踊る線条」、『東京朝日新聞』、1月。
「徒然草の鑑賞」、『文学』、1月。
「雑記帖より」、『文体』、2月。
「本当の旅の味「ギリシャとスカンデイナヴィヤ」安倍能成氏の紀行記」、『帝国大学新聞』、
2月。
「ある探偵事件」、『大阪朝日新聞』、2月。
アンケート「ドイツ芸術の独白性について」、『カスタニエン』、2月。
「変つた話(四題)」、『経済往来』、3月。
「俳諧瑣談」、『俳句研究』、3月。
「学位に就て」、『改造』、4月。
「ジャーナリズム雑感」、『中央公論』、4月。
「科学に志す人へ」、『帝国大学新聞』、4月。
「『西洋拝見』を読んで」、『東京朝日新聞』、4月。
「函館の大火に就て」、『中央公論』、5月。
「マーカス・ショーとレビュー式教育」、『中央公論』、6月。
「庭の追憶」、『心境』、6月。
「映画雑記」、『キネマ旬報』、6月。
「“豆”と哲人——ピタゴラスの最期」、『東京日日新聞』、7月。
「御返事(石原純君へ)」、『立像』、7月。
「「山中常磐」の映画的手法」、『セルパン』、7月。
「夕凪と夕風」、『週刊朝日』、8月。
「鷹を貰い損なった話」、『行動』、8月。
「観点と距離」、『文芸春秋』、8月。
「喫煙四十年」、『中央公論』、8月。
「初旅」、『旅と伝説』、8月。
「雑記帖より」、『文学』、8月。
「ゴルフ随行記」、『専売協会誌』、8月。
「子規自筆の根岸地図」、『東炎』、8月。
「Rokugwatu no Hare」、『RS』、8月。
「星野温泉より」、『渋柿』、8月。
「藤棚の蔭から」、『中央公論』、9月。
「鳶と油揚」、『工業大学蔵前新聞』、9月。
「明治丗二年頃」、『俳句研究』、9月。
「映画雑感」、『文学界』、9月。
「地図を眺めて」、『東京朝日新聞』、9〜10月。
「疑問と空想」、『科学知識』、10月。
「映画雑感」、『映画評論』、10月。
「室戸の奇現象」、『土陽新聞』、10月。
「小泉八雲秘稿画本『妖魔詩話』」、『帝国大学新聞』、10月。
「破片」、『中央公論』、11月。
「天災と国防」、『経済往来』、11月。
「俳句の型式と其進化」、『俳句研究』、11月。
「青楓の果実蔬菜描写」、津田青楓『線描蔬菜花卉第二画集』、11月。
アンケート「ほんとほん」、『帝国大学新聞』、11月。
『触媒』、岩波書店、12月。
「家鴨と猿」、『文学』、12月。
「鴫突き」、『野鳥』、12月。
「追憶の冬夜」、『短歌研究』、12月。 ]
蝉鳴くや松の梢に千曲川(「八月十五日小宮豊隆氏宛絵葉書」の中より)
嶺すでに麓へぼかす紅葉哉(「十月一日松根豊次郎氏宛絵葉書」の中より)
※この「八月十五日小宮豊隆氏宛絵葉書」は、「長野県北佐久郡沓掛星野温泉旅館」よりのもので、例年、寺田寅彦家族は、避暑でこの星野温泉旅館などを利用していたことが、[寺田寅彦全集文学篇第十七巻(「書簡集三)」などから分かる。
寅彦が亡くなる昭和十年(一九三五)の八月・九月の小宮豊隆氏宛の書簡などから、「寅彦家・豊隆家・安倍能成家・野上豊一郎家・東洋城(独身)」が、家族ぐるみの交遊関係にあったことが覗える
[ 八月二十日 火 長野県北佐久郡軽井沢千ケ瀧グリーンホテルより仙台市北二番丁六八小宮豊隆氏へ(葉書、「寺田正二・寺田弥生・寺田雪子」・「安倍能成・安倍道子・安倍浩二・安倍亮・安倍恭子」の寄書き)
(赤鉛筆にて)
千ケ瀧グリーンホテルの露台より 寅彦
今朝軽井沢から来襲寅彦先生の実行力なきを憐れんで居る 成(※能成)
(黒インキにて) 「寄書き(省略)」
八月二十一日 水 長野県北佐久郡軽井沢千ケ瀧グリーンホテルより長野県北軽井沢法政大学村増田山荘、安倍能成・同夫人・同令息・同令嬢諸氏へ(絵葉書、松根豊次郎・寺田正二・寺田弥生・寺田雪子署名の寄書き)
昨日は失礼、今日は東洋城来襲、午後例のべランダでシューベルトのリンデンバウムを歌って聴かせました。御一同に聴かせなかつたのは恨事であります。
※ 八月二十日に、「軽井沢千ケ瀧グリーンホテル」に滞在中の「寅彦一家」の所に、北軽井沢法政大学村増田山荘」の「能成一家」がやって来て、ここで、寅彦は正二(次男)のピアノ伴奏で、シューベルトの「リンデンバウム(菩提樹)」を御披露する予定であったが、その日は「千ケ瀧グリーンホテル」の茶和会にぶつかっていて、その御披露は実現しなかった。翌日(八月二十一日)、東洋城が突然やって来て、昨日、叶わなかった、寅彦の「リンデンバウム(菩提樹)」の独唱を聴かせたというものである。
九月一日 日 長野県北軽井沢法政大学村より仙台市北二番丁六八小宮豊隆氏へ(絵葉書、松根豊次郎・野上豊一郎・野上八重子・寺田正二・寺田弥生・寺田雪子との寄書き)
(表に)
雨のふる中を北軽井沢へ遊びに来て、松根君に案内して貰つて、野上荘を驚かし、唯今クラブで少憩中であります。 寅彦
昨日東京から同車、連句をやり乍ら軽井沢で別れてこヽへ。今日雨襲来各知人を驚かす。城(※東洋城)
寺田先生や東洋城師がお嬢さんやお坊ちやんと御いつしよに入らつしやいました。あなたのお噂をみんなでいたしております。弥生子(※野上弥生子)
生れてはじめて彌生子さんのお顔を見ました。長谷川君にどうぞよろしく。正二、弥生・雪子(※「長谷川君」は「正二」の学友で、豊隆の東北帝大に職を得ている。)
(裏に)
君も厄介な仕事を引受けさせられて大変だね来年は此山へ又おみこしを上げないか 豊一郎(※野上豊一郎・野上臼川) ]
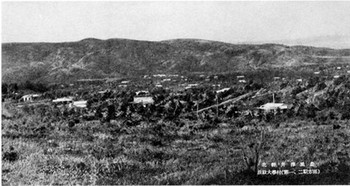
「長野県北軽井沢法政大学村」(北軽井沢「法政大学村」~その1~)
https://www.hosei.ac.jp/hosei/daigakugaiyo/daigaku_shi/museum/2011/110720/?auth=9abbb458a78210eb174f4bdd385bcf54
「法政大学村の第1期、第2期分譲地方面(『大学村七十年誌』より転載)。山荘はすべて、法政大学の校舎も手がけた蒲原重雄司法省技師が設計した。10坪から15坪前後の山荘は、1戸1戸外観・間取りが異なり、幾何学模様を多用したセセッション様式を取り入れた、素朴でエキゾチックな雰囲気だった。開村時は電気も水道もない生活だったが、都会からやってきた村民は、かえって原始的な暮らしを珍しがり楽しんだという。」
※ この「北軽井沢法政大学村」の産みの親は、当時の法政大学の「予科長・学監」の「野上豊一郎」教授(昭和八年=一九三三に「法政騒動」により休職・免職になるが、昭和十六年=一九四一に復職、後に、総長などを歴任する)であるが、上記の、「東洋城・寅彦とその家族」が、「北軽井沢法政大学村」の「野上豊一郎(臼川)・弥生子」山荘を訪れた頃は、いわゆる、「法政騒動」「1933 - 1934年(昭和8 - 9年)に法政大学で発生した学校騒動」)の余燼の中にあり、それぞれが、それぞれに激動の中にあった。

「法政騒動」「1933 - 1934年(昭和8 - 9年)に法政大学で発生した学校騒動」)に関する「朝日新聞」の記事(「ウィキペディア」)
この「法政騒動」については、下記のアドレスの、「昭和八、九年の「法政騒動(宮永孝稿)」(「法制大学学術機関リポジトリ」)が、その全容を伝えている。
file:///C:/Users/user/Downloads/59-4miyanaga2.pdf
この「法政騒動」は、上記の「朝日新聞」の記事にあるとおり、「漱石門」の「野上豊一郎」(学監兼予科長)を、「漱石門」の「森田草平」(教授、豊一郎が招聘した)が「関口存男(後に公職追放)らの右派の革新教授」に担ぎ上げられて、恰も、漱石門の「野上豊一郎(臼川)と森田草平」との確執によるものという、それが、クローズアップされての報道に力点が置かれたという一面も有している。
この「野上豊一郎」(学監兼予科長)解任要求の、その「反野上派は四つのスローガン」は次のようなものであった。(「ウィキペディア」)
一 学長問題(他の有力な人物を学長に推すべきだとの声が一部にあった)
二 隣接地購入問題(大学の隣の旧陸軍用地を購入できないのはなぜか)
三 財政問題(松室致前学長が残した巨額の負債をどうするのか)
四 人事行政問題(法政大学出身者をもっと教員に採用せよとの動きもあった)
この「人事行政問題(法政大学出身者をもっと教員に採用せよとの動きもあった)」は、これは、そっくり、同時期(「1933 – 1934・5年(昭和8 – 9・10年)))に勃発した、東洋城の主宰する俳誌「渋柿」における、「主要同人の『渋柿』脱退と新俳誌『あら野』の創刊」の背後に蠢いていた、その「『渋柿』出身者をもつと重視すると同時に、その主要同人の他者(社・派)との自由交流を認めよ」という、そういう面で、「野上豊一郎((臼川))」の「法政騒動」と、「松根東洋城」の「主要同人の『渋柿』脱退と新俳誌『あら野』の創刊」というのは、これは飛躍した見方も知れないが、こと、上記の、「寅彦」書簡の、「寅彦(一家)・東洋城・安倍能成(一家)・野上一家」(「臼川と弥生子」一家)・豊隆一家(仙台在住))などからすると、そういうことは、やはり、付記して置くべきものと思われる。
[豊隆(蓬里雨)・五十一歳。二月『巴理滞在記』『黄金虫』出版。]
木菟(ミミヅク)を雀の笑ふ麗らかかな(昭和九年「渋柿・五月号」)
草木国土花咲く春も暮れにけり(昭和九年「渋柿・七月号」)
瓜もみをいつ喰ひ初めて河童哉(昭和九年「渋柿・八月号」)
広々と道一筋や冬の霧 (昭和九年)
小宮豊隆の俳句については、昭和四十七年(一九七二)刊行の『蓬里雨句集』(私家版)がある。そのうちの「昭和九年作」の四句である。

木下杢太郎装丁、多色刷木版画、 小宮豊隆『黄金虫』(小山書店、 昭和9年)
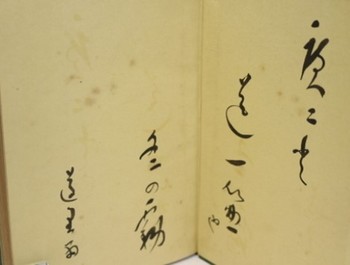
小宮豊隆『黄金虫』(小山書店、 昭和9年)の「献呈本」に書かれた「蓬里雨筆の一句/広々と道一筋や冬の霧(蓬里雨)」
この『黄金虫』は、寺田寅彦の『柿の種』(昭和八年初版・小山書店)の姉妹本で、寅彦の『柿の種』が、東洋城の「渋柿」の巻頭言(「無題」・「曙町より」)をまとめたものとすると、その豊隆の「渋柿」の巻頭言(「仙台より」をまとめたもので、その「序」で、「寅彦の「柿の種」は富有柿だが、自分(小宮)のは貧寒瘦地の渋柿」と記している。(この『黄金虫』は、ドイツ留学時の記述が主となっている。)
(付記)
[短章 その一
棄てた一粒の柿の種
生えるも生えぬも
甘いも渋いも
畑の土のよしあし ] (『柿の種(寺田寅彦著)』)
『巴里滞在記』については、下記アドレスの「国立国会図書館デジタルコレクション」で閲覧することが出来る。
https://dl.ndl.go.jp/pid/1235730/1/7
(補記)
俳諧瑣談(寺田寅彦)
https://www.aozora.gr.jp/cards/000042/card1690.html
子規自筆の根岸地図(寺田寅彦)
https://www.aozora.gr.jp/cards/000042/card24419.html
明治三十二年頃(寺田寅彦)
https://www.aozora.gr.jp/cards/000042/card24397.html
俳句の型式とその進化(寺田寅彦)
https://www.aozora.gr.jp/cards/000042/card2512.html
[東洋城・五十七歳。栃木、桐生、佐野にて俳句大会。満州各地を遍歴すること月余に及ぶ。大連にて「東洋城百短冊展」開催。「満州行」連載。「句作問答」始まる。「俳句研究」創刊。品川区上大崎一丁目四七〇へ移転。]
「『満州行』」より二百十一句]中の十句
青嵐しづかに汽船の左舷かな(前書「神戸出港」)
夏海へ今関門の若葉かな(前書「玄海」)
アカシヤの花や大陸第一歩(前書「大陸上陸」)
三伏を奉天城の繁華かな(前書「奉天」)
掘り下げて地獄の道や日の盛(前書「撫順」)
あはれむや塀の崩れに夏柳(前書「柳条溝」)
浴衣着てそぞろに行けば日本かな(前書「新京銀座の夜店」)
楡並木ロシヤ女の夏着かな(前書「哈爾濱」)
夜を秋や七星落ちて七山に(前書「蒙古七山の一の玻璃山遠望」)
峡川につづく水車や夏柳(前書「顧望満州」)
※ この「満州行」で、東洋城が日本を離れていた時に、俳誌「渋柿」の主要同人が「渋柿」を離脱して、新たに「あら野」という俳句結社を作るという、東洋城にとっては、予期しない大きな出来事があった。この主要同人は、「小杉余子(よし)」「上甲平谷(へいこく)」「星野石木」「南仙臥(せんが)」らで、これらの主要同人は、東洋城が最も頼りしていた、謂わば、「渋柿」という俳句結社の中枢を担っていたメンバーでもあった。
この「あら野」については、『俳文学大辞典(角川書店)』では、次のように記述されている。
[ あら野 俳誌
昭和十年(一九三五)一月(創刊)。月間。編集発行人は上甲保一郎(上甲平谷)、選者小杉余子・星野石木。「一に風雅の誠を貫いて平等無礙(むげ)なる方人悦楽の王土を現ずる」を理念とする。昭和十九年の雑誌統合により、「渋柿」に合併。(以下略) ]
小杉余子と上甲平谷とについても、『俳文学大辞典(角川書店)』に記述されているが、「デジタル版 日本人名大辞典+Plus」などでは、次のとおりである。
[小杉余子( こすぎよし) 1888-1961 明治-昭和時代の俳人。
明治21年1月16日生まれ。銀行勤務のかたわら,松根東洋城に師事して大正4年「渋柿」に参加。昭和10年東洋城のもとをはなれ,「あら野」の創刊にくわわる。平明な写生句で知られた。昭和36年8月3日死去。73歳。神奈川県出身。本名は義三。句集に「余子句集」「余子句選」。](「デジタル版 日本人名大辞典+Plus」)
[上甲平谷(じょうこうへいこく)
明治25年4月10日愛媛県生れ。昭和61年8月29日歿。早稲田大学文学部哲学科卒。初め村上霽月、のち河東碧梧桐、次いで松根東洋城の門に入る。俳誌「澁柿」、「あら野」を経て、昭和13年「俳諧藝術」を創刊(のち「火焔」と改題)。句集三冊。
芭蕉俳諧 ( 昭和24年4月10日 冨山房 )
紀行文集 無明一杖 ( 昭和63年7月5日 谷沢書房 )
俳諧襍稿 遊戯三昧 ( 平成4年4月10日 谷沢書房 ) ](「近代文献人名辞典β」)
この「渋柿」離脱と「あら野」の創刊は、結果的には、昭和十三年(一九三八)に、上甲平谷が、新たに「俳諧芸術」を創刊して、内部分裂の結果、昭和十九年(一九四四)の用紙統制による雑誌統合などにより、「渋柿」へと吸収され、事実上姿を消して行くことになる。
何故、このような主要同人の離脱と、新たなる俳誌「あら野」の創刊になったのかという、その要因の一つに、寅彦の言葉ですると、「連句の道の要諦は、銘々が自分の個性を主張すると同時に他者の個性を尊重し受容して御互に活かし合ひ響き合ふ處にある。此れは或意味での則天去私に外ならない、處が君はどうも自分の個性だけで一色にしてしまはうとするので困る」(「大正十五年(一九二六)二月十三日付け松根豊次郎宛書簡」)という、「東洋城の『自我の強さ』『狷介(自分の意志をまげず、人と和合しないこと)』『非妥協・潔癖・厳格・守節・守拙』等々の、その「東洋城個人主宰誌」的な「俳誌運営」からの脱却ということが挙げられるであろう。
そして、そのことは、「あら野」の俳句理念の「平等無礙(むげ)なる方人悦楽の王土を現ずる」という、「平等無礙(むげ)・自由闊達」に、「俳諧道場」(「芭蕉を宗とし俳諧を道として立つ」=「渋柿・東洋城」の理念)ではなく、「俳諧悦楽」(芭蕉を宗とし俳諧を楽(楽しみ)として相互に共有する)ということからも、その一端が覗い知れる。
それと同時に、この時に「渋柿」から離脱した主要同人達には、「渋柿」(東洋城主宰)が、謂わば、「本城」で、その一つの「出城」として、その裾野を拡げるような意味合いもあったことであろう。
しかし、この「渋柿」からの離脱と「あら野」の創刊は、後の、昭和四十八年(一九七三)に刊行された『風狂俳人列伝』(石川桂郎著)によって、「東洋城スキャンダル」の一つとして、次のとおりに記述されることになる。
[ 過日、東洋城がY邸に泊まった折のこと、夫人が別室に床をのべていたときであろうか、暴力をもって東洋城が夫人を犯そうとした。それを知ったYが短刀をつきつけてその無礼をなじり謝罪させたという。Yは東洋城と絶交状態となっていたのだ。Yが新誌に走ると彼についていた多くの弟子もこれに従ってしまい、迎えた側にとってはこの上ない喜びとなった。](『風狂俳人列伝 (石川桂郎著) 』)
この「Y」が、「小杉余(Y)子」であることは、当時の俳人達には容易に想像され得ることであったろう。しかし、この「Y」が、仮に「小杉余(Y)子」としても、余子は、東洋城の生存中の、昭和三十六年(一九六一)に亡くなっており、この『風狂俳人列伝』(石川桂郎著)は目にしていない。
また、水原秋櫻子に俳句の手ほどきをしたという「南仙臥」も、昭和四十四年(一九六九)に他界し、東洋城と、明治三十八年(一九〇五)の「京大・三高俳句会」以来の仲間で、「渋柿」で共に「俳諧(連句)」の研鑽を積んだ同士でもあった「星野石木」も、昭和三十五年(一九六〇)も、東洋城在世中に亡くなっている。
とすると、『風狂俳人列伝(石川桂郎著)』の著者(石川桂郎)に、「ある人から東洋城を書いてみないかと意外な資料を送られ、小説の主題、俗世間にザラにある事件だが、俳句の鬼のような彼に、これほどの女好きな、人間くさい面のあるのを知って、この列伝に加える気になった」という、この「意外の資料を送った人」とは、「上甲保一郎(上甲平谷)」ということになることは、当の「上甲平谷」も、そこまでは考えが及ばなかったのかも知れない。
.jpg)
『風狂俳人列伝(石川桂郎著)』(「中公文庫」)
この『風狂俳人列伝(石川桂郎著)』(「中公文庫」)の帯文の「俳句に憑かれた人びと」の中に、著者(石川桂郎)がいう「俳句の鬼」のような「彼(松根東洋城)」を取り上げることは、著者(石川桂郎)の一つの眼識なのかも知れない。
しかし、「これほどの女好きな、人間くさい面のある」のかという、この一方的な興味本位の見方というのは、「漱石・東洋城・寅彦(寅日子)・豊隆(蓬里雨)」の書簡などからすると、やや飛躍しているという見方も拭えない。
確かに、東洋城の「母(敏子)・妹(房子)、姪(柳原白蓮=血縁関係ではない)」等々に対する「フェミニスト(女性に優しく接する男性)」であることは、その[東洋城全句集(上・中・下)]からして窺い知れるところである。
と同時に、その「子供好き」などを加味するすると、単に、「フェミニスト(女性に優しく接する男性)」というよりも、より「雲上人(クモショウニン・クモノウエノヒト)」(東洋城をよく知る「鈴木三重吉」の「東洋城」あだ名)のように、「普通人(フツウジン)」の「石川桂郎(「桂郎自身も酒食と放言を好む風狂の人」=「ウィキペディア」)」)にとっては、「風狂俳人」というよりも、同根の「風狂の鬼」の「忘れえざる俳人」の一人であったことであろう。
[寅彦(寅日子)・五十七歳。昭和九年(一九三四三)。
1月9日、日本学術振興委員を委嘱され第四部常置委員会委員となる。1月12日、帝国学士院で“On Physical Properties of Chinese Black Ink”(with R. Yamamoto and T. Watanabe)を発表。1月16日、地震研究所談話会で「東北地方の地形に就て」を発表。2月12日、帝国学士院で“On a Regularity in Topographical Features of North-East Japan”を発表。
2月20日、地震研究所談話会で「粉末堆層の破壊に関する実験」を発表。3月12日、帝国学士院で“On the Modes of Fracture of a Layer of Powder Mass”(with T. Watanabe)および“On the Physical Meaning of Periodic Structure in Earth’s Crust”を発表。4月17日、地震研究所談話会で「大陸で収縮する?」および「中国の地形」を発表。
5月12日、帝国学士院で“Revision of Precise Levelling along R. Tenryu from Simosuwa to Kakegawa, 1934”(with N. Miyabe)および“On the Stability of Continental Crust”を発表。5月24日、理化学研究所学術講演会で「墨汁の諸性質(第三報)」(山本・渡部と共著)および「割れ目と生命」を発表。
6月19日、地震研究所談話会で「日本海の深さ」を発表。7月3日、地震研究所談話会で「地殻変動と温泉」を発表。7月12日、帝国学士院で“Hot Springs and Deformation of Earth’s Crust”を発表。
10月24日、水産試験場の海洋学談話会で「日本海海底の変化」を講演。11月12日、帝国学士院で“Results of Revision of Precise Levelling in Tohoku Districts”(with N. Miyabe)を発表。11月15日、理化学研究所学術講演会で「墨汁の諸性質(第四報)」(山本・渡部と共著)および「二三の生理光学的現象」(山本・渡部と共著)を発表。11月20日、地震研究所談話会で「珊瑚礁に就て」を発表。12月12日、帝国学士院で“Vertical Movement of Earth’s Crust and Growth of Coral Reef”を発表。
「初冬の日記から」、『中央公論』、1月。
「猫の穴掘り」、『大阪朝日新聞』、1月、『東京朝日新聞』、1月。
「思出草」、『東炎』、1月。
「踊る線条」、『東京朝日新聞』、1月。
「徒然草の鑑賞」、『文学』、1月。
「雑記帖より」、『文体』、2月。
「本当の旅の味「ギリシャとスカンデイナヴィヤ」安倍能成氏の紀行記」、『帝国大学新聞』、
2月。
「ある探偵事件」、『大阪朝日新聞』、2月。
アンケート「ドイツ芸術の独白性について」、『カスタニエン』、2月。
「変つた話(四題)」、『経済往来』、3月。
「俳諧瑣談」、『俳句研究』、3月。
「学位に就て」、『改造』、4月。
「ジャーナリズム雑感」、『中央公論』、4月。
「科学に志す人へ」、『帝国大学新聞』、4月。
「『西洋拝見』を読んで」、『東京朝日新聞』、4月。
「函館の大火に就て」、『中央公論』、5月。
「マーカス・ショーとレビュー式教育」、『中央公論』、6月。
「庭の追憶」、『心境』、6月。
「映画雑記」、『キネマ旬報』、6月。
「“豆”と哲人——ピタゴラスの最期」、『東京日日新聞』、7月。
「御返事(石原純君へ)」、『立像』、7月。
「「山中常磐」の映画的手法」、『セルパン』、7月。
「夕凪と夕風」、『週刊朝日』、8月。
「鷹を貰い損なった話」、『行動』、8月。
「観点と距離」、『文芸春秋』、8月。
「喫煙四十年」、『中央公論』、8月。
「初旅」、『旅と伝説』、8月。
「雑記帖より」、『文学』、8月。
「ゴルフ随行記」、『専売協会誌』、8月。
「子規自筆の根岸地図」、『東炎』、8月。
「Rokugwatu no Hare」、『RS』、8月。
「星野温泉より」、『渋柿』、8月。
「藤棚の蔭から」、『中央公論』、9月。
「鳶と油揚」、『工業大学蔵前新聞』、9月。
「明治丗二年頃」、『俳句研究』、9月。
「映画雑感」、『文学界』、9月。
「地図を眺めて」、『東京朝日新聞』、9〜10月。
「疑問と空想」、『科学知識』、10月。
「映画雑感」、『映画評論』、10月。
「室戸の奇現象」、『土陽新聞』、10月。
「小泉八雲秘稿画本『妖魔詩話』」、『帝国大学新聞』、10月。
「破片」、『中央公論』、11月。
「天災と国防」、『経済往来』、11月。
「俳句の型式と其進化」、『俳句研究』、11月。
「青楓の果実蔬菜描写」、津田青楓『線描蔬菜花卉第二画集』、11月。
アンケート「ほんとほん」、『帝国大学新聞』、11月。
『触媒』、岩波書店、12月。
「家鴨と猿」、『文学』、12月。
「鴫突き」、『野鳥』、12月。
「追憶の冬夜」、『短歌研究』、12月。 ]
蝉鳴くや松の梢に千曲川(「八月十五日小宮豊隆氏宛絵葉書」の中より)
嶺すでに麓へぼかす紅葉哉(「十月一日松根豊次郎氏宛絵葉書」の中より)
※この「八月十五日小宮豊隆氏宛絵葉書」は、「長野県北佐久郡沓掛星野温泉旅館」よりのもので、例年、寺田寅彦家族は、避暑でこの星野温泉旅館などを利用していたことが、[寺田寅彦全集文学篇第十七巻(「書簡集三)」などから分かる。
寅彦が亡くなる昭和十年(一九三五)の八月・九月の小宮豊隆氏宛の書簡などから、「寅彦家・豊隆家・安倍能成家・野上豊一郎家・東洋城(独身)」が、家族ぐるみの交遊関係にあったことが覗える
[ 八月二十日 火 長野県北佐久郡軽井沢千ケ瀧グリーンホテルより仙台市北二番丁六八小宮豊隆氏へ(葉書、「寺田正二・寺田弥生・寺田雪子」・「安倍能成・安倍道子・安倍浩二・安倍亮・安倍恭子」の寄書き)
(赤鉛筆にて)
千ケ瀧グリーンホテルの露台より 寅彦
今朝軽井沢から来襲寅彦先生の実行力なきを憐れんで居る 成(※能成)
(黒インキにて) 「寄書き(省略)」
八月二十一日 水 長野県北佐久郡軽井沢千ケ瀧グリーンホテルより長野県北軽井沢法政大学村増田山荘、安倍能成・同夫人・同令息・同令嬢諸氏へ(絵葉書、松根豊次郎・寺田正二・寺田弥生・寺田雪子署名の寄書き)
昨日は失礼、今日は東洋城来襲、午後例のべランダでシューベルトのリンデンバウムを歌って聴かせました。御一同に聴かせなかつたのは恨事であります。
※ 八月二十日に、「軽井沢千ケ瀧グリーンホテル」に滞在中の「寅彦一家」の所に、北軽井沢法政大学村増田山荘」の「能成一家」がやって来て、ここで、寅彦は正二(次男)のピアノ伴奏で、シューベルトの「リンデンバウム(菩提樹)」を御披露する予定であったが、その日は「千ケ瀧グリーンホテル」の茶和会にぶつかっていて、その御披露は実現しなかった。翌日(八月二十一日)、東洋城が突然やって来て、昨日、叶わなかった、寅彦の「リンデンバウム(菩提樹)」の独唱を聴かせたというものである。
九月一日 日 長野県北軽井沢法政大学村より仙台市北二番丁六八小宮豊隆氏へ(絵葉書、松根豊次郎・野上豊一郎・野上八重子・寺田正二・寺田弥生・寺田雪子との寄書き)
(表に)
雨のふる中を北軽井沢へ遊びに来て、松根君に案内して貰つて、野上荘を驚かし、唯今クラブで少憩中であります。 寅彦
昨日東京から同車、連句をやり乍ら軽井沢で別れてこヽへ。今日雨襲来各知人を驚かす。城(※東洋城)
寺田先生や東洋城師がお嬢さんやお坊ちやんと御いつしよに入らつしやいました。あなたのお噂をみんなでいたしております。弥生子(※野上弥生子)
生れてはじめて彌生子さんのお顔を見ました。長谷川君にどうぞよろしく。正二、弥生・雪子(※「長谷川君」は「正二」の学友で、豊隆の東北帝大に職を得ている。)
(裏に)
君も厄介な仕事を引受けさせられて大変だね来年は此山へ又おみこしを上げないか 豊一郎(※野上豊一郎・野上臼川) ]
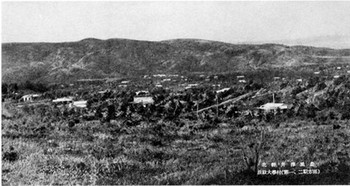
「長野県北軽井沢法政大学村」(北軽井沢「法政大学村」~その1~)
https://www.hosei.ac.jp/hosei/daigakugaiyo/daigaku_shi/museum/2011/110720/?auth=9abbb458a78210eb174f4bdd385bcf54
「法政大学村の第1期、第2期分譲地方面(『大学村七十年誌』より転載)。山荘はすべて、法政大学の校舎も手がけた蒲原重雄司法省技師が設計した。10坪から15坪前後の山荘は、1戸1戸外観・間取りが異なり、幾何学模様を多用したセセッション様式を取り入れた、素朴でエキゾチックな雰囲気だった。開村時は電気も水道もない生活だったが、都会からやってきた村民は、かえって原始的な暮らしを珍しがり楽しんだという。」
※ この「北軽井沢法政大学村」の産みの親は、当時の法政大学の「予科長・学監」の「野上豊一郎」教授(昭和八年=一九三三に「法政騒動」により休職・免職になるが、昭和十六年=一九四一に復職、後に、総長などを歴任する)であるが、上記の、「東洋城・寅彦とその家族」が、「北軽井沢法政大学村」の「野上豊一郎(臼川)・弥生子」山荘を訪れた頃は、いわゆる、「法政騒動」「1933 - 1934年(昭和8 - 9年)に法政大学で発生した学校騒動」)の余燼の中にあり、それぞれが、それぞれに激動の中にあった。

「法政騒動」「1933 - 1934年(昭和8 - 9年)に法政大学で発生した学校騒動」)に関する「朝日新聞」の記事(「ウィキペディア」)
この「法政騒動」については、下記のアドレスの、「昭和八、九年の「法政騒動(宮永孝稿)」(「法制大学学術機関リポジトリ」)が、その全容を伝えている。
file:///C:/Users/user/Downloads/59-4miyanaga2.pdf
この「法政騒動」は、上記の「朝日新聞」の記事にあるとおり、「漱石門」の「野上豊一郎」(学監兼予科長)を、「漱石門」の「森田草平」(教授、豊一郎が招聘した)が「関口存男(後に公職追放)らの右派の革新教授」に担ぎ上げられて、恰も、漱石門の「野上豊一郎(臼川)と森田草平」との確執によるものという、それが、クローズアップされての報道に力点が置かれたという一面も有している。
この「野上豊一郎」(学監兼予科長)解任要求の、その「反野上派は四つのスローガン」は次のようなものであった。(「ウィキペディア」)
一 学長問題(他の有力な人物を学長に推すべきだとの声が一部にあった)
二 隣接地購入問題(大学の隣の旧陸軍用地を購入できないのはなぜか)
三 財政問題(松室致前学長が残した巨額の負債をどうするのか)
四 人事行政問題(法政大学出身者をもっと教員に採用せよとの動きもあった)
この「人事行政問題(法政大学出身者をもっと教員に採用せよとの動きもあった)」は、これは、そっくり、同時期(「1933 – 1934・5年(昭和8 – 9・10年)))に勃発した、東洋城の主宰する俳誌「渋柿」における、「主要同人の『渋柿』脱退と新俳誌『あら野』の創刊」の背後に蠢いていた、その「『渋柿』出身者をもつと重視すると同時に、その主要同人の他者(社・派)との自由交流を認めよ」という、そういう面で、「野上豊一郎((臼川))」の「法政騒動」と、「松根東洋城」の「主要同人の『渋柿』脱退と新俳誌『あら野』の創刊」というのは、これは飛躍した見方も知れないが、こと、上記の、「寅彦」書簡の、「寅彦(一家)・東洋城・安倍能成(一家)・野上一家」(「臼川と弥生子」一家)・豊隆一家(仙台在住))などからすると、そういうことは、やはり、付記して置くべきものと思われる。
[豊隆(蓬里雨)・五十一歳。二月『巴理滞在記』『黄金虫』出版。]
木菟(ミミヅク)を雀の笑ふ麗らかかな(昭和九年「渋柿・五月号」)
草木国土花咲く春も暮れにけり(昭和九年「渋柿・七月号」)
瓜もみをいつ喰ひ初めて河童哉(昭和九年「渋柿・八月号」)
広々と道一筋や冬の霧 (昭和九年)
小宮豊隆の俳句については、昭和四十七年(一九七二)刊行の『蓬里雨句集』(私家版)がある。そのうちの「昭和九年作」の四句である。

木下杢太郎装丁、多色刷木版画、 小宮豊隆『黄金虫』(小山書店、 昭和9年)
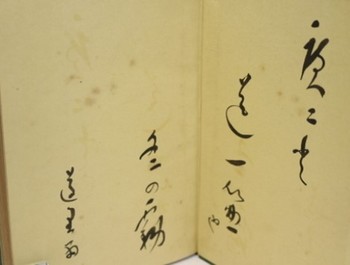
小宮豊隆『黄金虫』(小山書店、 昭和9年)の「献呈本」に書かれた「蓬里雨筆の一句/広々と道一筋や冬の霧(蓬里雨)」
この『黄金虫』は、寺田寅彦の『柿の種』(昭和八年初版・小山書店)の姉妹本で、寅彦の『柿の種』が、東洋城の「渋柿」の巻頭言(「無題」・「曙町より」)をまとめたものとすると、その豊隆の「渋柿」の巻頭言(「仙台より」をまとめたもので、その「序」で、「寅彦の「柿の種」は富有柿だが、自分(小宮)のは貧寒瘦地の渋柿」と記している。(この『黄金虫』は、ドイツ留学時の記述が主となっている。)
(付記)
[短章 その一
棄てた一粒の柿の種
生えるも生えぬも
甘いも渋いも
畑の土のよしあし ] (『柿の種(寺田寅彦著)』)
『巴里滞在記』については、下記アドレスの「国立国会図書館デジタルコレクション」で閲覧することが出来る。
https://dl.ndl.go.jp/pid/1235730/1/7
(補記)
俳諧瑣談(寺田寅彦)
https://www.aozora.gr.jp/cards/000042/card1690.html
子規自筆の根岸地図(寺田寅彦)
https://www.aozora.gr.jp/cards/000042/card24419.html
明治三十二年頃(寺田寅彦)
https://www.aozora.gr.jp/cards/000042/card24397.html
俳句の型式とその進化(寺田寅彦)
https://www.aozora.gr.jp/cards/000042/card2512.html
「東洋城・寅彦、そして、豊隆」(漱石没後~寅彦没まで)俳句・連句管見(その十七) [東洋城・寅日子(寅彦)・蓬里雨(豊隆)]
その十七「昭和八年(一九三三)」
[東洋城・五十六歳。足利にて俳句大会。奈良、京都に遊ぶ。母の遺骨を宇和島に埋葬。「渋柿句集」春夏秋冬四巻・宝文館刊。]

「松根東洋城・大洲旧居」(大洲城二の丸金櫓跡に「俳人松根東洋城 大洲旧居」があった。)
http://urawa0328.babymilk.jp/ehime/oozujou.html

「大洲城本丸」
http://urawa0328.babymilk.jp/siroato/oozujou-4.jpg
[ 東洋城は本名を松根豊次郎といい、明治11年(1878年)2月25日、東京の築地に松根権六(宇和島藩城代家老松根図書の長男)を父に、敏子(宇和島藩主伊達宗城の次女)を母に長男として生まれた。
明治23年(1890年)10月父権六が、大洲区裁判所判事として、大洲に赴任するに伴って東洋城も大洲尋常高等小学校に転校して来た。当時、この屋敷が裁判官判事の宿舎で、明治31年(1898年)10月、権六が退官するまで、約8年間、松根家の人々はここに居住した。
東洋城は明治25年、大洲尋常小学校を卒業すると、松山の愛媛県尋常中学校(のちの松山中学校)に入学した。
4年生の時、夏目漱石が英語教師として赴任し、ふたりの運命的出会いが、その後の東洋城の生き方に大きな影響を及ぼすことになった。
俳人東洋城は俳誌『渋柿』を創刊(大正8年)、多くの同人を指導し、大洲にもしばしば訪れた。昭和8年(1933年)この「大洲旧居」にも立ち寄り「幼時を母を憶ふ」と次の句を詠んでいる。
淋しさや昔の家の古き春 東洋城
また大洲の東洋城の句碑には、如法寺河原に
芋鍋の煮ゆるや秋の音しずか 東洋城
がある。大洲史談会により平成5年(1993年)建立された。
東洋城は戦後、虚子と共に芸術院会員となり昭和39年(1964年)10月28日東京で87歳で死去した。墓は宇和島市金剛山大隆寺にある。
なお、ここの家屋(平屋建)は、明治2年(1869年)4月、大洲城二の丸金櫓跡に建てられたもので、江戸時代末期の武家屋敷の遺構が一部のこされている。]
「亡母と西下 六十二句」中の十句
淋しさや昔の家の古き春(前書「大洲旧居(幼時を母を憶ふ)」)
柴門は三歩の春の蒲公英かな(前書「大洲にて」)
山(サ)ン川(セン)の何も明ろき木の芽かな(前書「庵主の吟『荘にして何か明るき時雨かな』に和す」)
如法寺を寝法師と呼ぶ霞かな
朧とや昔舟橋あのほとり
春愁や夜の蒲公英をまぼろしに(前書「大洲を出で立つとて」)
蓋とりて椀の蕨に別れかな(前書「大洲甲南庵留別」)
神代こゝに神南山(カンナンザン)の霰かな(前書「若宮平野にて」)
伊予富士の丸きあたまや春の雨(前書「今出の浜四句」のうち)
海を見てゐてうしろ田や春の雨(前書「今出の浜四句」のうち)
E3808D.jpg)
「松根東洋城句碑(宇和島市宇和津町・大隆寺)」
http://urawa0328.babymilk.jp/ehime/22/dairyuuji-3.jpg
[黛を濃うせよ/草は芳しき/東洋城(句意=黛は眉のこと。若草がいっせいに萌えだして芳しい春の天地の中、あなたの眉墨をも濃くおひきなさい。若草さながら芳しく。)/平成13年(2001年)2月25日、松根敦子建立。]
[寅彦(寅日子)・五十六歳。昭和八年(一九三三)。
1月12日、帝国学士院で“Distribution of Terrestrial Magnetic Elements and the Structure of Earth’s Crust in Japan”および“Kitakami River Plain and Its Geophysical Significance”を発表。1月17日、地震研究所談話会で「四国に於ける山崩の方向性」および「日本のゼオイドに就て」を発表。4月11日、航空評議会臨時評議員になる。4月12日、帝国学士院で“Result of the Precise Levelling along the Pacific Coast from Koti to Kagosima, 1932”を発表。5月16日、地震研究所談話会で「統計に因る地震予知の不確定度」を発表。5月25日、理化学研究所学術講演会で「墨汁皮膜の硬化に及ぼす電解質の影響」(内ヶ崎と共著)、「墨汁粒子の毛管電気現象」(山本と共著)および「藤の実の射出される物理的機構」(平田・内ヶ崎と共著)を発表。6月12日、帝国学士院で“On a Measure of Uncertainty Regarding the Prediction of Earthquake Based on Statistics”を発表。10月12日、帝国学士院で“Luminous Phenomena Accompanying Destructive Sea-Waves”を発表。11月17日、理化学研究所学術講演会で「墨汁粒子の電気的諸性質(続報)」(山本・渡部と共著)を発表。11月21日、地震研究所談話会で「相模湾底の変化に就て」を発表。12月11日、航空学談話会で「垂直に吊された糸を熱するときに生ずる上昇力と之に及ぼす周囲の瓦斯の影響」(竹内能忠と共著)を発表。
「鐘に釁る」、『応用物理』、1月。
「北氷洋の氷の破れる音」、『鉄塔』、1月。
「Image of Physical World in Cinematography」、『Scientia』、1月。
「重兵衛さんの一家」、『婦人公論』、1月。
「鉛をかじる虫」、『帝国大学新聞』、1月。
「鎖骨」、『工業大学蔵前新聞』、1月。
「ニュース映画と新聞記事」、『映画評論』、1月。
「書翰」、『アララギ』、1月。
「短歌の詩形」、『勁草』、1月。
「自然界の縞模様」、『科学』、2月。
「藤の実」、『鉄塔』、2月。
「銀座アルプス」、『中央公論』、2月。
「珈琲哲学序説」、『経済往来』、2月。
談話「不連続線と温度の注意で山火事を予防」、『報知新聞』、2月。
「空想日録」、『改造』、3月。
「地震と光り物——武者金吉著『地震に伴ふ発光現象の研究及び資料』紹介」、『東京朝日
新聞』、3月。
「映画雑感」、『帝国大学新聞』、3月。
「物質群として見た動物群」、『理学界』、4月。
「病院風景」、『文学青年』、4月。
「猿の顔」、『文芸意匠』、4月。
「「ラヂオ」随想」、日本放送協会『調査時報』、4月。
「Opera wo kiku」、『Romazi Zidai』、4月。
「測候瑣談」、『時事新報』、4月。
「ことばの不思議 二」、『鉄塔』、4月。
「津波と人間」、『鉄塔』、5月。
「耳と目」、『映画評論』、5月。
※『柿の種』、小山書店、6月。
「蒸発皿」、『中央公論』、6月。
「記録狂時代」、『東京朝日新聞』、6月。
「言葉の不思議(三)」、『鉄塔』、7月。
「感覚と科学」、『科学』、8月。
「涼味数題」、『週刊朝日』、8月。
「錯覚数題」、『中央公論』、8月。
「神話と地球物理学」、『文学』、8月。
「言葉の不思議(四)」、『鉄塔』、8月。
アンケート「最近読んだ日本の良書愚書」、『鉄塔』、8月。
「学問の自由」、『鉄塔』、9月。
「試験管」、『改造』、9月。
「軽井沢」、『経済往来』、9月。
「科学と文学」、岩波講座『世界文学』、9月。
アンケート「記・紀・万葉に於けるわが愛誦歌」、『文学』、9月。
『物質と言葉』、鉄塔書院、10月。
「科学者とあたま」、『鉄塔』、10月。
「浅間山麓より」、『週刊朝日』、10月。
「沓掛より」、『中央公論』、10月。
「二科展院展急行瞥見記」、『中央美術』、10月。
「KからQまで」、『文芸評論』、10月。
「科学的文学の一例——維納の殺人容疑者」、『東京朝日新聞』、10月。
「猿蟹合戦と桃太郎」、『文芸春秋』、11月。
「俳諧瑣談」、『渋柿』、11月。
「人魂の一つの場合」、『帝国大学新聞』、11月。
『地球物理学』、岩波書店、12月。
『蒸発皿』、岩波書店、12月。
「伊香保」、『中央公論』、12月。
「異質触媒作用」、『文芸』、12月。 ]
哲学も科学も寒き嚏(クサメ)哉(二月「渋柿」)
※清けさや色さまざまに露の玉(四月二十二日付け「松根豊次郎宛書簡」)
※薫風や玉を磨けばおのづから(同上)
※ 上記の四月二十二日付け「松根豊次郎宛書簡」は、次のとおり。
[四月二十二日 土 本郷区駒込曙町二四より牛込区余丁四一松根豊次郎氏への「はがき」
昨日はとんだ失礼、朝出がけ迄に御端書も電話もなかつたが念の為に五時数分前にモナミへ行つて見廻したが御出なく,矢張未だ御帰京ないものと考へて銀座の方へ出てしまつたのでありました。
「無題」の集録も本文の校正は出来たが、装幀などが中々手間がとれて進行せず、併し五日中位には出来る事になると存候
――――――――――――――――――――――――――――
友人の葡萄の画に賛を頼まれて考案中「清けさや色さまざまに露の玉」などは如何や御斧正を乞ふ。
又学士院受賞者に祝の色紙を頼まれ苦吟中「薫風や玉を磨けばおのづから」では何の事か分かるまじく候、御高見御洩らし被下度祈候
四月廿二日 ](『寺田寅彦全集 文学篇 第十七巻』)
※ 上記の書簡中の「『無題』の集録も本文の校正は出来たが、装幀などが中々手間がとれて進行せず、併し五日中位には出来る事になると存候」は、上記の年譜中の、「※『柿の種』、小山書店、6月。」で刊行されたもので、その初出のものは、「渋柿」の「巻頭言(寅彦の「無題」)」の、その集録が主体になっていることを意味している。
この『柿の種』(「小山書店」刊=小山久二郎(「小山書店主」)はは安倍能成の甥で、岩波書店勤務を経て創業)には、小宮豊隆も深く関わっている。
また、書簡中の「モナミへ行つて見廻したが御出なく」のその「モナミ」は、「帝都座の地下室のモナミ」(「新宿3丁目交差点にあった帝都座(現在の新宿マルイ本館)の地下」)の、「モナミ(大食堂)」で、ここが、東洋城と寅彦との連句の制作現場である。

TEITOZA「新宿 モナミ大食堂」
https://tokyomatchbox.blogspot.com/2022/03/blog-post_06.html
[ 寺田君は午後四時頃航空研究所を出て小田急で新宿駅に下車し、すぐモナミへ来る。僕の方が後になる事が多い為君はいつも待合室の長椅子で夕刊か何か読んでゐる。夕刊を読んでしまふと欧文原稿の校正などをしてゐる。僕が側へ腰を掛けて少し話をすると、「行かうか」とか「飯食はうか」というて立上がる。例の古い外套だ。そして左脇に風呂敷(時に大きなカバン)をかかへ右手に蝙蝠傘を杖いてサツサと食堂の方へ行く。ボックスがあいていればボックス、あいてゐなければ柱の蔭か棕櫚の蔭かになるやうな一卓に陣取る。さうして、何か一品註文する。(中略) それからソロソロと仕事にとりかかる。両人が汚い手帖を取り出して前回の附けかけの各自受持ちのところを出す。僕が小さい季寄せを提袋から出すと君がポケットから剥ぎ取りのメモを出し二三枚ちぎつて僕に呉れる。附くと見せ合つて対手が承知すると両方の手帖に記入する、不承知だとダメを出して考へ直す。(以下、略) ] (『東洋城全句集(下巻)』所収「寺田君と俳諧」)
[豊隆(蓬里雨)・五十歳。昭和八年(一九三三)。一月合著『新続芭蕉俳諧研究』出版。十月『芭蕉の研究』出版。]
※ 小宮豊隆が、東北帝大法文学部(独逸文学)の教授として仙台(仙台市北二番丁六八)に移住したのは、大正十四年(一九三五)の四月、その翌年に「芭蕉俳諧研究会」(阿部次郎・太田正雄(木下杢太郎)・山田孝雄・岡崎義恵・土井光知・小牧健夫・村岡典嗣など)が始まり、この会は、昭和二十一年(一九四六)に、豊隆が東京音楽学校校長として仙台を去るまで続いた。その間の、大正十五年(昭和元年・一九二六)から昭和八年(一九三三)にかけての豊隆の論考は、昭和八年九月九日の「序」を付しての『芭蕉の研究(岩波書店・十月初版)』として結実を遂げている。
(再掲)
https://yahan.blog.ss-blog.jp/2023-11-27
『芭蕉の研究』(小宮豊隆著・岩波書店)
https://dl.ndl.go.jp/pid/1213547/1/1
[目次
芭蕉/1 → 昭和七年十一月四日(論文)
不易流行説に就いて/56 → 昭和二年四月五日(論文)
さびしをりに就いて/107 → 昭和五年八月七日(論文)
芭蕉の戀の句/139 → 昭和七年五月二十日(論文)
發句飜譯の可能性/167 → 昭和八年六月五日(論文)
『冬の日』以前/175 → 昭和三年十二月七日(論文)
『貝おほひ』/199 → 昭和四年三月三日(論文)
芭蕉の南蠻紅毛趣味/231 → 昭和二年二月(論文)
芭蕉の「けらし」/261 → 大正十五年七月(論文)
芭蕉の眞僞/290 → 昭和六年十月十五日(論文)
二題/296 → 昭和三年九月九日(「潁原退蔵君に」)
→ 昭和七年八月二十三日(「矢数俳諧」)
『おくのほそ道』/303 → 昭和七年一月十四日(論文)
立石寺の蟬/326 → 昭和四年八月二十日(「斎藤茂吉」との論争)
芭蕉の作と言はれる『栗木庵の記』に就いて/330 →昭和六年七月七日(論文)
『おくのほそ道』畫卷/375 → 昭和七年六月十九日(論文)
芭蕉と蕪村/379 → 昭和四年十月(論文)
附錄
蕪村書簡考證/419 → 昭和三年六月二十八日(論文)
西山宗因に就いて/452 → 昭和七年九月二十日(論文)
宗因の『飛鳥川』に就いて/489 →昭和八年二月十二日(論文) ](「国立国会図書館デジタルコレクション」)
その「序」で、豊隆は、「考えて見ると、私は、少し芭蕉に狎(ナ)れすぎたやうな気がする。是は決して、研究にとつて、好ましい事ではないない」と記述している。
この「序」の、「少し芭蕉に狎(ナ)れすぎた」という想いは、寅彦の「東洋城・寅日子・蓬里雨三吟の座」からの「蓬里雨破門」は、年長(六歳年上)の「兄事」する「漱石最側近」の「東洋城・寅日子」両人に対する「 狎(ナ)れすぎ」(「もたれすぎ」)という想いが、豊隆にとっては去来したことであろう。
この寅彦の「東洋城・寅日子・蓬里雨三吟の座」からの「蓬里雨破門」は、その後の、この三者の交遊関係は、いささかも変わりなく、逆に、年少者の豊隆が、年長者の「東洋城・寅日子」を、陰に陽に支え続けていたということが、『寺田寅彦全集文学篇(第十五・十六・十七巻=書簡集一・二・三)・岩波書店』の、寅彦からの「豊隆・東洋城・安倍能成・津田青楓など」宛ての書簡から読み取れる。
[※ 歌仙(昭和十一年十一月「渋柿(未完の歌仙)」)
オ
(八月十八日雲仙を下る)
霧雨に奈良漬食ふも別れ哉 蓬里雨
馬追とまる額の字の上 青楓
ひとり鳴る鳴子に出れば月夜にて 寅日子 月
けふは二度目の棒つかふ人 東洋城
ぼそぼそと人話しゐる辻堂に 雨
煙るとも見れば時雨来にけり 子
ウ
皹(アカギレ)を業するうちは忘れゐて 城
炭打くだく七輪の角 雨(一・一七)
胴(ドウ)の間に蚊帳透き見ゆる朝ぼらけ 子 (※茶の「胴炭」からの附け?) 恋
葭吹く風に廓の後朝(キヌギヌ) 城 恋
細帯に腰の形を落付けて 雨(六・四・一四) 恋
簾の風に薫る掛香 子(八・二八) 恋
庭ながら深き林の夏の月 城(七・四・一三) 月 ](『寺田寅彦全集 文学篇 第七巻』)
※ この「四吟(蓬里雨・青楓・寅日子・東洋城)歌仙(未完)」は、当時の「東洋城・寅日子・蓬里雨・青楓」の、この四人を知る上で、格好の「歌仙(未完)」ということになる。
この歌仙(未完)の、「表六句と裏一句」は、「昭和二年(一九二七)八月、小宮豊隆、松根東洋城、津田青楓と塩原温泉に行き、連句を実作する」(「寺田寅彦年譜」)の、その塩原温泉でのものと思われる。
その塩原温泉(栃木県)での歌仙の、その発句に、「八月十八日雲仙を下る」の前書を付しての「霧雨に奈良漬食ふも別れ哉(蓬里雨)」の、この前書にある「雲仙(温泉)」(長崎県)が出て来るのはどういうことなのか(?) ――― 、この句の背景には、次のアドレスの「作家を求める読者、読者を求める作家――改造社主催講演旅行実地踏査――(杉山欣也稿)」(金沢大学学術情報リポトロジKURA)で記述されている「雲仙温泉」で開催された「改造社主催講演会」に、その講師として、小宮豊隆の名が出てくるのである。
file:///C:/Users/user/Downloads/CV_20231201_LE-PR-SUGIYAMA-K-203.pdf
[雲仙の温泉岳娯楽場を会場に、八月十七日~二十二日に開催された九州地区のそれは、やはり新聞各紙の広告によって宣伝が重ねられた。講師は、小宮豊隆・阿部次郎・木村毅・藤村成吉・笹川臨風に、課外講演として京大教授・川村多二(「動物界の道徳」というタイトル)が演壇に立った。「長崎新聞」の紙面から、ここも大盛況であったことが分かる。]
この八月十七日の翌日(八月十八日)、雲仙温泉での講演を後にして、その帰途中に「東洋城・寅彦・青楓」と合流して、その折りの塩原温泉(四季の郷・明賀屋、近郊に、東洋城の「両面句碑」が建立されている)での一句のように解せられる。
そして、裏の二句目の「炭打くだく七輪の角・雨(一・一七)」は、昭和六年(一九三一)一月十一日付けの、文音での、蓬里雨の付け句のように思われる。それに対して、「胴(ドウ)の間に蚊帳透き見ゆる朝ぼらけ・子」(寅日子・裏三句目)と「葭吹く風に廓の後朝(キヌギヌ)・城」と付け、同年の四月十四日に「細帯に腰の形を落付けて・雨」(蓬里雨・裏四句目)」、続く、同年の八月二十八日に「簾の風に薫る掛香・子」(寅日子・裏五句目)と付けて、その翌年の昭和七年(一九三二)四月十三日に「庭ながら深き林の夏の月・ 城」(東洋城・裏六句目)」のところで打ち掛けとなっている。
実に、昭和二年(一九二七)の八月にスタートした歌仙(連句)は、その五年後の、昭和七年(一九三二)の四月まで、未完のままに、そして、寅彦が亡くなった、翌年の、昭和十一年(一九三六)十一月「渋柿」(寺田寅彦追悼号)に公開されたということになる。

「作家を求める読者、読者を求める作家――改造社主催講演旅行実地踏査――(杉山欣也稿)・抜粋」(金沢大学学術情報リポトロジKURA)
ここで、寅彦の「東洋城・寅日子・蓬里雨三吟の座」からの「蓬里雨破門」は、何時の頃かというと、下記の「(参考)「寅彦が詠んだだ連句(歌仙)」(年・連句(歌仙)数・歌仙名・連衆)」のとおり、昭和六年(一九三一)の「※短夜の」(「東・寅・豊」の三吟、昭和六年十月「渋柿」)以降のことのように思われる。
(参考)「寅彦が詠んだだ連句(歌仙)」(年・連句(歌仙)数・歌仙名・連衆)
1925(T14) 1 「水団扇」(東・寅)
1926 (T15/Sl) 4 「昔から」(東・寅)/ 「炭竈と」(東・寅)/ 「雲の蓑」(東・寅・豊)/
「けふあす の」(東・寅)
1927(S2) 4 「あすよりは」(東・寅・豊)/「鎖したれど」(東・寅・豊)/「霜降り
る」(東・寅)/「文鳥や」(東・寅)
1928(S3) 5「露けさの」(東・寅・豊)/「簾越に」(東・寅・豊)/「うなだれて」(東・寅)/「コスモスや」/「旅なれは」(東・寅)
1929 (S4) 1 「花蘇枋」」(東・寅)
1930(S5) 1 「かはかはと」(東・寅・豊)
1931 (S6) 8 「翡翠や」(東・寅)/「あのやうに」(東・寅)/「淡雪や」(東・寅)/
「※短夜の」(東・寅・豊)/「咲きつづく」(東・寅)/「飛ぶ蝶や」(東・
寅)/「乗合は」(東・寅)/「如月や」(東・寅)
1932(S7) 8 山里や」(東・寅)/「くさびらに」(東・寅)/「風も無き」(東・寅)/
「末枯や」(東・寅)/「武蔵野は」(東・寅)/「裏山や」(東・寅)/
「葭切や」(東・寅)/「夕立や」(東・寅)
1933 (S8) 6 「翡翠や」(東・寅)/「牡丹や」(東・寅)/「白露や」(東・寅)/
「するすると」(東・寅)/「晴れまさる」(東・寅)/「一裏や」(東・
寅)
1934 (S9) 4 「鷽の琴」(東・寅)/「静けさや」(東・寅)/「秋風や」/(東・寅)/「十
ばかり」/(東・寅)
1935(Sl0) 5 「その頃の」(東・寅)/「まざまざと」(東・寅)/「蝉鳴くや」(東・
寅)/「冬空や」(東・寅)/「山の戸や」(東・寅)
※未完は除く
(追記その一)「津田青楓」周辺
https://yahan.blog.ss-blog.jp/2023-10-18
[9 津田青楓(つだせいふう)=明治13(1880)~昭和53(1978)年。画家。『道草』や『明暗』など漱石の本の装丁を手がけた。また、漱石に絵画の手ほどきをした。(「漱石十大弟子の一人」、実兄は「去風流七代・西川一草亭」、漱石側近の画家、後に「左翼」に転向。)]
https://yahan.blog.ss-blog.jp/2023-09-08

「漱石山房と其弟子達」(津田清楓画)→A図
https://blog.goo.ne.jp/torahiko-natsume/e/6ad1c4767dddc3568e6b34e7d727b501
≪「上段の左から」→則天居士(夏目漱石)・寅彦(寺田寅彦)・能成(阿部能成)・式部官(松根東洋城)・野上(野上豊一郎)・三重吉(鈴木三重吉)・岩波(岩波茂雄)・桁平(赤木桁平)・百閒(内田百閒)
「下段の左から」→豊隆(小宮豊隆)・阿部次郎・森田草平/花瓶の傍の黒猫(『吾輩は猫である』の吾輩が、「苦沙弥」先生と「其門下生」を観察している。)
「則天居士」=「則天去私」の捩り=「〘連語〙 天にのっとって私心を捨てること。我執を捨てて自然に身をゆだねること。晩年の夏目漱石が理想とした心境で、「大正六年文章日記」の一月の扉に掲げてあることば。」(「精選版 日本国語大辞典」)
「天地人間」(屏風に書かれた文字)=「天地人」=「① 天と地と人。宇宙間の万物。三才。② 三つあるものの順位を表わすのに用いる語。天を最上とし、地・人がこれに次ぐ。
※落語・果報の遊客(1893)〈三代目三遊亭円遊〉「発句を〈略〉天地人を付ける様な訳で」(「精選版 日本国語大辞典」)→「2096 空に消ゆる鐸のひびきや春の塔(漱石・「前書」=「空間を研究せる天然居士の肖像に題す」)→「空間に生れ、空間を究(きわ)め、空間に死す。空たり間たり天然居士(てんねんこじ)噫(ああ)」(『吾輩は猫である』第三話)
↓
https://www.konekono-heya.com/books/wagahai3.html ≫
(追記その二) 「柿の種」周辺
https://www.aozora.gr.jp/cards/000042/files/1684_11274.html

[子猫が勢いに乗じて高い樹のそらに上ったが、おりることができなくなって困っている。
親猫が樹の根元へすわってこずえを見上げては鳴いている。
人がそばへ行くと、親猫は人の顔を見ては訴えるように鳴く。
あたかも助けを求めるもののようである。
こういう状態が二十分もつづいたかと思う。
その間に親猫は一、二度途中まで登って行ったが、どうすることもできなくて、おめおめとまたおりて来るのであった。
子猫はとうとう降り始めたが、脚をすべらせて、山吹やまぶきの茂みの中へおち込んだ。
それを抱き上げて連れて来ると、親猫はいそいそとあとからついて来る。
そうして、縁側におろされた子猫をいきなり嘗なめ始める。
子猫は、すぐに乳房にしゃぶりついて、音高くのどを鳴らしはじめる。
親猫もクルークルーと恩愛にむせぶように咽喉を鳴らしながら、いつまでもいつまでも根気よく嘗め回し、嘗めころがすのである。
単にこれだけの猫のふるまいを見ていても、猫のすることはすべて純粋な本能的衝動によるもので、人間のすることはみんな霊性のはたらきだという説は到底信じられなくなる。
(大正十一年六月、渋柿)

[ルノアルの絵の好きな男がいた。
その男がある女に恋をした。
その女は、他人の眼からは、どうにも美人とは思われないような女であったが、どこかしら、ルノアルの描くあるタイプの女に似たところはあったのだそうである。
俳句をやらない人には、到底解することのできない自然界や人間界の美しさがあるであろうと思うが、このことと、このルノアルの女の話とは少し関係があるように思われる。
(大正十三年三月、渋柿) ]
[三毛の墓
三毛みけのお墓に花が散る
こんこんこごめの花が散る
小窓に鳥影小鳥影
「小鳥の夢でも見ているか」
三毛のお墓に雪がふる
こんこん小窓に雪がふる
炬燵蒲団こたつぶとんの紅くれないも
「三毛がいないでさびしいな」 ] (昭和三年二月、渋柿)

[東洋城・五十六歳。足利にて俳句大会。奈良、京都に遊ぶ。母の遺骨を宇和島に埋葬。「渋柿句集」春夏秋冬四巻・宝文館刊。]

「松根東洋城・大洲旧居」(大洲城二の丸金櫓跡に「俳人松根東洋城 大洲旧居」があった。)
http://urawa0328.babymilk.jp/ehime/oozujou.html

「大洲城本丸」
http://urawa0328.babymilk.jp/siroato/oozujou-4.jpg
[ 東洋城は本名を松根豊次郎といい、明治11年(1878年)2月25日、東京の築地に松根権六(宇和島藩城代家老松根図書の長男)を父に、敏子(宇和島藩主伊達宗城の次女)を母に長男として生まれた。
明治23年(1890年)10月父権六が、大洲区裁判所判事として、大洲に赴任するに伴って東洋城も大洲尋常高等小学校に転校して来た。当時、この屋敷が裁判官判事の宿舎で、明治31年(1898年)10月、権六が退官するまで、約8年間、松根家の人々はここに居住した。
東洋城は明治25年、大洲尋常小学校を卒業すると、松山の愛媛県尋常中学校(のちの松山中学校)に入学した。
4年生の時、夏目漱石が英語教師として赴任し、ふたりの運命的出会いが、その後の東洋城の生き方に大きな影響を及ぼすことになった。
俳人東洋城は俳誌『渋柿』を創刊(大正8年)、多くの同人を指導し、大洲にもしばしば訪れた。昭和8年(1933年)この「大洲旧居」にも立ち寄り「幼時を母を憶ふ」と次の句を詠んでいる。
淋しさや昔の家の古き春 東洋城
また大洲の東洋城の句碑には、如法寺河原に
芋鍋の煮ゆるや秋の音しずか 東洋城
がある。大洲史談会により平成5年(1993年)建立された。
東洋城は戦後、虚子と共に芸術院会員となり昭和39年(1964年)10月28日東京で87歳で死去した。墓は宇和島市金剛山大隆寺にある。
なお、ここの家屋(平屋建)は、明治2年(1869年)4月、大洲城二の丸金櫓跡に建てられたもので、江戸時代末期の武家屋敷の遺構が一部のこされている。]
「亡母と西下 六十二句」中の十句
淋しさや昔の家の古き春(前書「大洲旧居(幼時を母を憶ふ)」)
柴門は三歩の春の蒲公英かな(前書「大洲にて」)
山(サ)ン川(セン)の何も明ろき木の芽かな(前書「庵主の吟『荘にして何か明るき時雨かな』に和す」)
如法寺を寝法師と呼ぶ霞かな
朧とや昔舟橋あのほとり
春愁や夜の蒲公英をまぼろしに(前書「大洲を出で立つとて」)
蓋とりて椀の蕨に別れかな(前書「大洲甲南庵留別」)
神代こゝに神南山(カンナンザン)の霰かな(前書「若宮平野にて」)
伊予富士の丸きあたまや春の雨(前書「今出の浜四句」のうち)
海を見てゐてうしろ田や春の雨(前書「今出の浜四句」のうち)
E3808D.jpg)
「松根東洋城句碑(宇和島市宇和津町・大隆寺)」
http://urawa0328.babymilk.jp/ehime/22/dairyuuji-3.jpg
[黛を濃うせよ/草は芳しき/東洋城(句意=黛は眉のこと。若草がいっせいに萌えだして芳しい春の天地の中、あなたの眉墨をも濃くおひきなさい。若草さながら芳しく。)/平成13年(2001年)2月25日、松根敦子建立。]
[寅彦(寅日子)・五十六歳。昭和八年(一九三三)。
1月12日、帝国学士院で“Distribution of Terrestrial Magnetic Elements and the Structure of Earth’s Crust in Japan”および“Kitakami River Plain and Its Geophysical Significance”を発表。1月17日、地震研究所談話会で「四国に於ける山崩の方向性」および「日本のゼオイドに就て」を発表。4月11日、航空評議会臨時評議員になる。4月12日、帝国学士院で“Result of the Precise Levelling along the Pacific Coast from Koti to Kagosima, 1932”を発表。5月16日、地震研究所談話会で「統計に因る地震予知の不確定度」を発表。5月25日、理化学研究所学術講演会で「墨汁皮膜の硬化に及ぼす電解質の影響」(内ヶ崎と共著)、「墨汁粒子の毛管電気現象」(山本と共著)および「藤の実の射出される物理的機構」(平田・内ヶ崎と共著)を発表。6月12日、帝国学士院で“On a Measure of Uncertainty Regarding the Prediction of Earthquake Based on Statistics”を発表。10月12日、帝国学士院で“Luminous Phenomena Accompanying Destructive Sea-Waves”を発表。11月17日、理化学研究所学術講演会で「墨汁粒子の電気的諸性質(続報)」(山本・渡部と共著)を発表。11月21日、地震研究所談話会で「相模湾底の変化に就て」を発表。12月11日、航空学談話会で「垂直に吊された糸を熱するときに生ずる上昇力と之に及ぼす周囲の瓦斯の影響」(竹内能忠と共著)を発表。
「鐘に釁る」、『応用物理』、1月。
「北氷洋の氷の破れる音」、『鉄塔』、1月。
「Image of Physical World in Cinematography」、『Scientia』、1月。
「重兵衛さんの一家」、『婦人公論』、1月。
「鉛をかじる虫」、『帝国大学新聞』、1月。
「鎖骨」、『工業大学蔵前新聞』、1月。
「ニュース映画と新聞記事」、『映画評論』、1月。
「書翰」、『アララギ』、1月。
「短歌の詩形」、『勁草』、1月。
「自然界の縞模様」、『科学』、2月。
「藤の実」、『鉄塔』、2月。
「銀座アルプス」、『中央公論』、2月。
「珈琲哲学序説」、『経済往来』、2月。
談話「不連続線と温度の注意で山火事を予防」、『報知新聞』、2月。
「空想日録」、『改造』、3月。
「地震と光り物——武者金吉著『地震に伴ふ発光現象の研究及び資料』紹介」、『東京朝日
新聞』、3月。
「映画雑感」、『帝国大学新聞』、3月。
「物質群として見た動物群」、『理学界』、4月。
「病院風景」、『文学青年』、4月。
「猿の顔」、『文芸意匠』、4月。
「「ラヂオ」随想」、日本放送協会『調査時報』、4月。
「Opera wo kiku」、『Romazi Zidai』、4月。
「測候瑣談」、『時事新報』、4月。
「ことばの不思議 二」、『鉄塔』、4月。
「津波と人間」、『鉄塔』、5月。
「耳と目」、『映画評論』、5月。
※『柿の種』、小山書店、6月。
「蒸発皿」、『中央公論』、6月。
「記録狂時代」、『東京朝日新聞』、6月。
「言葉の不思議(三)」、『鉄塔』、7月。
「感覚と科学」、『科学』、8月。
「涼味数題」、『週刊朝日』、8月。
「錯覚数題」、『中央公論』、8月。
「神話と地球物理学」、『文学』、8月。
「言葉の不思議(四)」、『鉄塔』、8月。
アンケート「最近読んだ日本の良書愚書」、『鉄塔』、8月。
「学問の自由」、『鉄塔』、9月。
「試験管」、『改造』、9月。
「軽井沢」、『経済往来』、9月。
「科学と文学」、岩波講座『世界文学』、9月。
アンケート「記・紀・万葉に於けるわが愛誦歌」、『文学』、9月。
『物質と言葉』、鉄塔書院、10月。
「科学者とあたま」、『鉄塔』、10月。
「浅間山麓より」、『週刊朝日』、10月。
「沓掛より」、『中央公論』、10月。
「二科展院展急行瞥見記」、『中央美術』、10月。
「KからQまで」、『文芸評論』、10月。
「科学的文学の一例——維納の殺人容疑者」、『東京朝日新聞』、10月。
「猿蟹合戦と桃太郎」、『文芸春秋』、11月。
「俳諧瑣談」、『渋柿』、11月。
「人魂の一つの場合」、『帝国大学新聞』、11月。
『地球物理学』、岩波書店、12月。
『蒸発皿』、岩波書店、12月。
「伊香保」、『中央公論』、12月。
「異質触媒作用」、『文芸』、12月。 ]
哲学も科学も寒き嚏(クサメ)哉(二月「渋柿」)
※清けさや色さまざまに露の玉(四月二十二日付け「松根豊次郎宛書簡」)
※薫風や玉を磨けばおのづから(同上)
※ 上記の四月二十二日付け「松根豊次郎宛書簡」は、次のとおり。
[四月二十二日 土 本郷区駒込曙町二四より牛込区余丁四一松根豊次郎氏への「はがき」
昨日はとんだ失礼、朝出がけ迄に御端書も電話もなかつたが念の為に五時数分前にモナミへ行つて見廻したが御出なく,矢張未だ御帰京ないものと考へて銀座の方へ出てしまつたのでありました。
「無題」の集録も本文の校正は出来たが、装幀などが中々手間がとれて進行せず、併し五日中位には出来る事になると存候
――――――――――――――――――――――――――――
友人の葡萄の画に賛を頼まれて考案中「清けさや色さまざまに露の玉」などは如何や御斧正を乞ふ。
又学士院受賞者に祝の色紙を頼まれ苦吟中「薫風や玉を磨けばおのづから」では何の事か分かるまじく候、御高見御洩らし被下度祈候
四月廿二日 ](『寺田寅彦全集 文学篇 第十七巻』)
※ 上記の書簡中の「『無題』の集録も本文の校正は出来たが、装幀などが中々手間がとれて進行せず、併し五日中位には出来る事になると存候」は、上記の年譜中の、「※『柿の種』、小山書店、6月。」で刊行されたもので、その初出のものは、「渋柿」の「巻頭言(寅彦の「無題」)」の、その集録が主体になっていることを意味している。
この『柿の種』(「小山書店」刊=小山久二郎(「小山書店主」)はは安倍能成の甥で、岩波書店勤務を経て創業)には、小宮豊隆も深く関わっている。
また、書簡中の「モナミへ行つて見廻したが御出なく」のその「モナミ」は、「帝都座の地下室のモナミ」(「新宿3丁目交差点にあった帝都座(現在の新宿マルイ本館)の地下」)の、「モナミ(大食堂)」で、ここが、東洋城と寅彦との連句の制作現場である。

TEITOZA「新宿 モナミ大食堂」
https://tokyomatchbox.blogspot.com/2022/03/blog-post_06.html
[ 寺田君は午後四時頃航空研究所を出て小田急で新宿駅に下車し、すぐモナミへ来る。僕の方が後になる事が多い為君はいつも待合室の長椅子で夕刊か何か読んでゐる。夕刊を読んでしまふと欧文原稿の校正などをしてゐる。僕が側へ腰を掛けて少し話をすると、「行かうか」とか「飯食はうか」というて立上がる。例の古い外套だ。そして左脇に風呂敷(時に大きなカバン)をかかへ右手に蝙蝠傘を杖いてサツサと食堂の方へ行く。ボックスがあいていればボックス、あいてゐなければ柱の蔭か棕櫚の蔭かになるやうな一卓に陣取る。さうして、何か一品註文する。(中略) それからソロソロと仕事にとりかかる。両人が汚い手帖を取り出して前回の附けかけの各自受持ちのところを出す。僕が小さい季寄せを提袋から出すと君がポケットから剥ぎ取りのメモを出し二三枚ちぎつて僕に呉れる。附くと見せ合つて対手が承知すると両方の手帖に記入する、不承知だとダメを出して考へ直す。(以下、略) ] (『東洋城全句集(下巻)』所収「寺田君と俳諧」)
[豊隆(蓬里雨)・五十歳。昭和八年(一九三三)。一月合著『新続芭蕉俳諧研究』出版。十月『芭蕉の研究』出版。]
※ 小宮豊隆が、東北帝大法文学部(独逸文学)の教授として仙台(仙台市北二番丁六八)に移住したのは、大正十四年(一九三五)の四月、その翌年に「芭蕉俳諧研究会」(阿部次郎・太田正雄(木下杢太郎)・山田孝雄・岡崎義恵・土井光知・小牧健夫・村岡典嗣など)が始まり、この会は、昭和二十一年(一九四六)に、豊隆が東京音楽学校校長として仙台を去るまで続いた。その間の、大正十五年(昭和元年・一九二六)から昭和八年(一九三三)にかけての豊隆の論考は、昭和八年九月九日の「序」を付しての『芭蕉の研究(岩波書店・十月初版)』として結実を遂げている。
(再掲)
https://yahan.blog.ss-blog.jp/2023-11-27
『芭蕉の研究』(小宮豊隆著・岩波書店)
https://dl.ndl.go.jp/pid/1213547/1/1
[目次
芭蕉/1 → 昭和七年十一月四日(論文)
不易流行説に就いて/56 → 昭和二年四月五日(論文)
さびしをりに就いて/107 → 昭和五年八月七日(論文)
芭蕉の戀の句/139 → 昭和七年五月二十日(論文)
發句飜譯の可能性/167 → 昭和八年六月五日(論文)
『冬の日』以前/175 → 昭和三年十二月七日(論文)
『貝おほひ』/199 → 昭和四年三月三日(論文)
芭蕉の南蠻紅毛趣味/231 → 昭和二年二月(論文)
芭蕉の「けらし」/261 → 大正十五年七月(論文)
芭蕉の眞僞/290 → 昭和六年十月十五日(論文)
二題/296 → 昭和三年九月九日(「潁原退蔵君に」)
→ 昭和七年八月二十三日(「矢数俳諧」)
『おくのほそ道』/303 → 昭和七年一月十四日(論文)
立石寺の蟬/326 → 昭和四年八月二十日(「斎藤茂吉」との論争)
芭蕉の作と言はれる『栗木庵の記』に就いて/330 →昭和六年七月七日(論文)
『おくのほそ道』畫卷/375 → 昭和七年六月十九日(論文)
芭蕉と蕪村/379 → 昭和四年十月(論文)
附錄
蕪村書簡考證/419 → 昭和三年六月二十八日(論文)
西山宗因に就いて/452 → 昭和七年九月二十日(論文)
宗因の『飛鳥川』に就いて/489 →昭和八年二月十二日(論文) ](「国立国会図書館デジタルコレクション」)
その「序」で、豊隆は、「考えて見ると、私は、少し芭蕉に狎(ナ)れすぎたやうな気がする。是は決して、研究にとつて、好ましい事ではないない」と記述している。
この「序」の、「少し芭蕉に狎(ナ)れすぎた」という想いは、寅彦の「東洋城・寅日子・蓬里雨三吟の座」からの「蓬里雨破門」は、年長(六歳年上)の「兄事」する「漱石最側近」の「東洋城・寅日子」両人に対する「 狎(ナ)れすぎ」(「もたれすぎ」)という想いが、豊隆にとっては去来したことであろう。
この寅彦の「東洋城・寅日子・蓬里雨三吟の座」からの「蓬里雨破門」は、その後の、この三者の交遊関係は、いささかも変わりなく、逆に、年少者の豊隆が、年長者の「東洋城・寅日子」を、陰に陽に支え続けていたということが、『寺田寅彦全集文学篇(第十五・十六・十七巻=書簡集一・二・三)・岩波書店』の、寅彦からの「豊隆・東洋城・安倍能成・津田青楓など」宛ての書簡から読み取れる。
[※ 歌仙(昭和十一年十一月「渋柿(未完の歌仙)」)
オ
(八月十八日雲仙を下る)
霧雨に奈良漬食ふも別れ哉 蓬里雨
馬追とまる額の字の上 青楓
ひとり鳴る鳴子に出れば月夜にて 寅日子 月
けふは二度目の棒つかふ人 東洋城
ぼそぼそと人話しゐる辻堂に 雨
煙るとも見れば時雨来にけり 子
ウ
皹(アカギレ)を業するうちは忘れゐて 城
炭打くだく七輪の角 雨(一・一七)
胴(ドウ)の間に蚊帳透き見ゆる朝ぼらけ 子 (※茶の「胴炭」からの附け?) 恋
葭吹く風に廓の後朝(キヌギヌ) 城 恋
細帯に腰の形を落付けて 雨(六・四・一四) 恋
簾の風に薫る掛香 子(八・二八) 恋
庭ながら深き林の夏の月 城(七・四・一三) 月 ](『寺田寅彦全集 文学篇 第七巻』)
※ この「四吟(蓬里雨・青楓・寅日子・東洋城)歌仙(未完)」は、当時の「東洋城・寅日子・蓬里雨・青楓」の、この四人を知る上で、格好の「歌仙(未完)」ということになる。
この歌仙(未完)の、「表六句と裏一句」は、「昭和二年(一九二七)八月、小宮豊隆、松根東洋城、津田青楓と塩原温泉に行き、連句を実作する」(「寺田寅彦年譜」)の、その塩原温泉でのものと思われる。
その塩原温泉(栃木県)での歌仙の、その発句に、「八月十八日雲仙を下る」の前書を付しての「霧雨に奈良漬食ふも別れ哉(蓬里雨)」の、この前書にある「雲仙(温泉)」(長崎県)が出て来るのはどういうことなのか(?) ――― 、この句の背景には、次のアドレスの「作家を求める読者、読者を求める作家――改造社主催講演旅行実地踏査――(杉山欣也稿)」(金沢大学学術情報リポトロジKURA)で記述されている「雲仙温泉」で開催された「改造社主催講演会」に、その講師として、小宮豊隆の名が出てくるのである。
file:///C:/Users/user/Downloads/CV_20231201_LE-PR-SUGIYAMA-K-203.pdf
[雲仙の温泉岳娯楽場を会場に、八月十七日~二十二日に開催された九州地区のそれは、やはり新聞各紙の広告によって宣伝が重ねられた。講師は、小宮豊隆・阿部次郎・木村毅・藤村成吉・笹川臨風に、課外講演として京大教授・川村多二(「動物界の道徳」というタイトル)が演壇に立った。「長崎新聞」の紙面から、ここも大盛況であったことが分かる。]
この八月十七日の翌日(八月十八日)、雲仙温泉での講演を後にして、その帰途中に「東洋城・寅彦・青楓」と合流して、その折りの塩原温泉(四季の郷・明賀屋、近郊に、東洋城の「両面句碑」が建立されている)での一句のように解せられる。
そして、裏の二句目の「炭打くだく七輪の角・雨(一・一七)」は、昭和六年(一九三一)一月十一日付けの、文音での、蓬里雨の付け句のように思われる。それに対して、「胴(ドウ)の間に蚊帳透き見ゆる朝ぼらけ・子」(寅日子・裏三句目)と「葭吹く風に廓の後朝(キヌギヌ)・城」と付け、同年の四月十四日に「細帯に腰の形を落付けて・雨」(蓬里雨・裏四句目)」、続く、同年の八月二十八日に「簾の風に薫る掛香・子」(寅日子・裏五句目)と付けて、その翌年の昭和七年(一九三二)四月十三日に「庭ながら深き林の夏の月・ 城」(東洋城・裏六句目)」のところで打ち掛けとなっている。
実に、昭和二年(一九二七)の八月にスタートした歌仙(連句)は、その五年後の、昭和七年(一九三二)の四月まで、未完のままに、そして、寅彦が亡くなった、翌年の、昭和十一年(一九三六)十一月「渋柿」(寺田寅彦追悼号)に公開されたということになる。

「作家を求める読者、読者を求める作家――改造社主催講演旅行実地踏査――(杉山欣也稿)・抜粋」(金沢大学学術情報リポトロジKURA)
ここで、寅彦の「東洋城・寅日子・蓬里雨三吟の座」からの「蓬里雨破門」は、何時の頃かというと、下記の「(参考)「寅彦が詠んだだ連句(歌仙)」(年・連句(歌仙)数・歌仙名・連衆)」のとおり、昭和六年(一九三一)の「※短夜の」(「東・寅・豊」の三吟、昭和六年十月「渋柿」)以降のことのように思われる。
(参考)「寅彦が詠んだだ連句(歌仙)」(年・連句(歌仙)数・歌仙名・連衆)
1925(T14) 1 「水団扇」(東・寅)
1926 (T15/Sl) 4 「昔から」(東・寅)/ 「炭竈と」(東・寅)/ 「雲の蓑」(東・寅・豊)/
「けふあす の」(東・寅)
1927(S2) 4 「あすよりは」(東・寅・豊)/「鎖したれど」(東・寅・豊)/「霜降り
る」(東・寅)/「文鳥や」(東・寅)
1928(S3) 5「露けさの」(東・寅・豊)/「簾越に」(東・寅・豊)/「うなだれて」(東・寅)/「コスモスや」/「旅なれは」(東・寅)
1929 (S4) 1 「花蘇枋」」(東・寅)
1930(S5) 1 「かはかはと」(東・寅・豊)
1931 (S6) 8 「翡翠や」(東・寅)/「あのやうに」(東・寅)/「淡雪や」(東・寅)/
「※短夜の」(東・寅・豊)/「咲きつづく」(東・寅)/「飛ぶ蝶や」(東・
寅)/「乗合は」(東・寅)/「如月や」(東・寅)
1932(S7) 8 山里や」(東・寅)/「くさびらに」(東・寅)/「風も無き」(東・寅)/
「末枯や」(東・寅)/「武蔵野は」(東・寅)/「裏山や」(東・寅)/
「葭切や」(東・寅)/「夕立や」(東・寅)
1933 (S8) 6 「翡翠や」(東・寅)/「牡丹や」(東・寅)/「白露や」(東・寅)/
「するすると」(東・寅)/「晴れまさる」(東・寅)/「一裏や」(東・
寅)
1934 (S9) 4 「鷽の琴」(東・寅)/「静けさや」(東・寅)/「秋風や」/(東・寅)/「十
ばかり」/(東・寅)
1935(Sl0) 5 「その頃の」(東・寅)/「まざまざと」(東・寅)/「蝉鳴くや」(東・
寅)/「冬空や」(東・寅)/「山の戸や」(東・寅)
※未完は除く
(追記その一)「津田青楓」周辺
https://yahan.blog.ss-blog.jp/2023-10-18
[9 津田青楓(つだせいふう)=明治13(1880)~昭和53(1978)年。画家。『道草』や『明暗』など漱石の本の装丁を手がけた。また、漱石に絵画の手ほどきをした。(「漱石十大弟子の一人」、実兄は「去風流七代・西川一草亭」、漱石側近の画家、後に「左翼」に転向。)]
https://yahan.blog.ss-blog.jp/2023-09-08

「漱石山房と其弟子達」(津田清楓画)→A図
https://blog.goo.ne.jp/torahiko-natsume/e/6ad1c4767dddc3568e6b34e7d727b501
≪「上段の左から」→則天居士(夏目漱石)・寅彦(寺田寅彦)・能成(阿部能成)・式部官(松根東洋城)・野上(野上豊一郎)・三重吉(鈴木三重吉)・岩波(岩波茂雄)・桁平(赤木桁平)・百閒(内田百閒)
「下段の左から」→豊隆(小宮豊隆)・阿部次郎・森田草平/花瓶の傍の黒猫(『吾輩は猫である』の吾輩が、「苦沙弥」先生と「其門下生」を観察している。)
「則天居士」=「則天去私」の捩り=「〘連語〙 天にのっとって私心を捨てること。我執を捨てて自然に身をゆだねること。晩年の夏目漱石が理想とした心境で、「大正六年文章日記」の一月の扉に掲げてあることば。」(「精選版 日本国語大辞典」)
「天地人間」(屏風に書かれた文字)=「天地人」=「① 天と地と人。宇宙間の万物。三才。② 三つあるものの順位を表わすのに用いる語。天を最上とし、地・人がこれに次ぐ。
※落語・果報の遊客(1893)〈三代目三遊亭円遊〉「発句を〈略〉天地人を付ける様な訳で」(「精選版 日本国語大辞典」)→「2096 空に消ゆる鐸のひびきや春の塔(漱石・「前書」=「空間を研究せる天然居士の肖像に題す」)→「空間に生れ、空間を究(きわ)め、空間に死す。空たり間たり天然居士(てんねんこじ)噫(ああ)」(『吾輩は猫である』第三話)
↓
https://www.konekono-heya.com/books/wagahai3.html ≫
(追記その二) 「柿の種」周辺
https://www.aozora.gr.jp/cards/000042/files/1684_11274.html

[子猫が勢いに乗じて高い樹のそらに上ったが、おりることができなくなって困っている。
親猫が樹の根元へすわってこずえを見上げては鳴いている。
人がそばへ行くと、親猫は人の顔を見ては訴えるように鳴く。
あたかも助けを求めるもののようである。
こういう状態が二十分もつづいたかと思う。
その間に親猫は一、二度途中まで登って行ったが、どうすることもできなくて、おめおめとまたおりて来るのであった。
子猫はとうとう降り始めたが、脚をすべらせて、山吹やまぶきの茂みの中へおち込んだ。
それを抱き上げて連れて来ると、親猫はいそいそとあとからついて来る。
そうして、縁側におろされた子猫をいきなり嘗なめ始める。
子猫は、すぐに乳房にしゃぶりついて、音高くのどを鳴らしはじめる。
親猫もクルークルーと恩愛にむせぶように咽喉を鳴らしながら、いつまでもいつまでも根気よく嘗め回し、嘗めころがすのである。
単にこれだけの猫のふるまいを見ていても、猫のすることはすべて純粋な本能的衝動によるもので、人間のすることはみんな霊性のはたらきだという説は到底信じられなくなる。
(大正十一年六月、渋柿)

[ルノアルの絵の好きな男がいた。
その男がある女に恋をした。
その女は、他人の眼からは、どうにも美人とは思われないような女であったが、どこかしら、ルノアルの描くあるタイプの女に似たところはあったのだそうである。
俳句をやらない人には、到底解することのできない自然界や人間界の美しさがあるであろうと思うが、このことと、このルノアルの女の話とは少し関係があるように思われる。
(大正十三年三月、渋柿) ]
[三毛の墓
三毛みけのお墓に花が散る
こんこんこごめの花が散る
小窓に鳥影小鳥影
「小鳥の夢でも見ているか」
三毛のお墓に雪がふる
こんこん小窓に雪がふる
炬燵蒲団こたつぶとんの紅くれないも
「三毛がいないでさびしいな」 ] (昭和三年二月、渋柿)

「東洋城・寅彦、そして、豊隆」(漱石没後~寅彦没まで)俳句・連句管見(その十六) [東洋城・寅日子(寅彦)・蓬里雨(豊隆)]
その十六「昭和七年(一九三二)」
[東洋城・五十五歳。秋田、象潟、榛名、箱根に遊ぶ。松山俳諧道場、東京俳諧道場。十二月、母没す。]
草摘(ツム)や畔をたがへて俳門(うかれびと)
寿(いのちなが)母生(あ)れし日の弥生かな(前書「草屋春風」)
恰(アタカ)もの柿の頃なり法隆寺(前書「『柿食へば鐘が鳴るなり』の句を思ひ出づれど、柿は買はず」)
その後(ア)トや前立仏(マエダチブツ)に秋の暮(前書「夢殿秘仏」)
いや静(シ)づに御魂(オミタマ)まもれ落葉共(ドモ)(前書「母を失ふ」)
※ 東洋城の俳句の「読み」というのは、「俳門(うかれびと)」とか「寿(いのちなが)」とか、東洋城独特の「読み」があり、東洋城が期待しているとおりの「読み」をするというのは難しい。
ちなみに、「恰(アタカ)もの」などの「読み・意味」するものは、その「前書」から類推する他はない。「後(ア)ト」は、「ト」のルビがあり、その「前立仏(マエダチブツ・マエダテブツ)」から、「五・七・五」音からすると、「その後(ア)トや」という読(詠)みになる。
そして、前書に「母を失ふ」とある「いや静づに御魂まもれ落葉共」をどう読(詠)むかとなると、「五・七・五」音の読(詠)みから、「いや静(シ)づに御魂(オミタマ)まもれ落葉共(ドモ)」として置きたい。
『東洋城全句集(中巻)』の「昭和八年(五十六歳)」に、「亡母と西下 六十二句」が収載されているが、『東洋城全句集(上巻)』の、「明治三十七年(二十七歳)」に、母を句にした次の句がある。
瓶のものに水仙剪るや四方の春(前書「床に掛軸餅は据ゑたれど瓶に花忘れたり、けさとなりて母上庭に下り立ち水仙を剪り給ふ」)
この東洋城の句は、東洋城が「病臥(腸チフス)」で癒えた時の「快癒句録 八句」の、そのうちの一句である。
瓶のものに水仙剪るや四方の春(前書「床に掛軸餅は据ゑたれど瓶に花忘れたり、けさとなりて母上庭に下り立ち水仙を剪り給ふ」)
いや静(シ)づに御魂(オミタマ)まもれ落葉共(ドモ)(前書「母を失ふ」)
この二句の間に、東洋城の、その生涯の、その半世紀(五十年)に亘る、東洋城の「母と子」との歴史が刻まれているということになる。
(再掲) 「東洋城家族」(「俳誌『渋柿(昭和四十年(一九六五)の一月号(「松根東洋城追悼号」)」所収「青春時代を語る / 東洋城 ; 洋一/p54~73」)
https://yahan.blog.ss-blog.jp/2023-10-08

「東洋城家族」(「俳誌『渋柿(昭和四十年(一九六五)の一月号(「松根東洋城追悼号」)」所収「青春時代を語る / 東洋城 ; 洋一/p54~73」)
https://dl.ndl.go.jp/pid/6071686/1/41
[左から「父・権六/伯母・初子(柳原前光(伯爵)夫人・白蓮の養母・東洋城の母の姉)/母・敏子/弟・卓四郎/弟・新八郎/親族/弟・宗一」(明治四十一年七月三十一日写)
(追記) ※上記のアドレスでは、「松根東洋城」家族として、「弟・卓四郎/弟・新八郎/親族/弟・宗一」としたのだが、『松根東洋城年譜』(『東洋城全句集中巻』)では、「明治二十年(一八八七)/十歳/弟貞吉郎生まる」とあり、「弟・新八郎(明治十八年生れ)」と「弟・卓四郎(明治二十五年生れ)」との間に、「弟貞吉郎(明治二十年生れ)」があり、それらを加味して、上記の写真を解読する必要があろう。
(再掲)
https://yahan.blog.ss-blog.jp/2023-10-12

(裏面に、「明治四十二年九月四日写之、秋風やこぼつときめてきめて撮す家」と認めてある宇和島の宏壮な郷邸で、私の推定では敷地三千坪もあつたろうか。大半を町へ売られ、跡は町立病院が建った。残った二百坪程度の敷地に七間位の邸を建てられ、私どもはそこへ通つた。それも戦火に罹つて炎上、今は唯「我が祖先(おや)は奥の最上や天の川」の句碑一基を残すのみである。徳永山冬子)
「青春時代を語る / 東洋城 ; 洋一/p54~73」)」(「俳誌『渋柿(昭和四十年(一九六五)の一月号) 』 (「松根東洋城追悼号」)」
https://dl.ndl.go.jp/pid/6071686/1/37
※ この「宇和島の松根家の邸宅と家族」(明治四十二年九月四日写)については、右から、「父・権六と母・敏子」、中央の三人「新八郎(次弟)・東洋城(継嗣・豊次郎)・房子(妹)」、
左から「宗一(末弟)・卓四郎(四弟)・貞吉郎(三弟)」という見方もあるのかも知れない。
[寅彦(寅日子)・ 55歳。
1月12日、帝国学士院で“Cracks Produced on the Surface of Dielectrics by Gliding Spark”(with M. Hirata and R. Yamamoto)および“Deformation of the Rhombic Base Lines at Mitaka and Earthquakes in Kwanto”を発表。1月19日、地震研究所談話会で「地震と漁獲」(渡部哲と共著)を発表。3月12日、帝国学士院で“Earthquakes and Fisheries”を発表。5月12日、帝国学士院で“Change of Depth in the Bay of Tosa”を発表。5月17日、地震研究所談話会で「興津より串本に至る水準点検測成果」および「土佐沿岸海底の変化」を発表。5月25日、理化学研究所学術講習会で「椿の花の落ち方に就て」(内ヶ崎と共著)および「水晶玉の打撃像」(平田・山本と共著)を発表。6月6日、航空学談話会で「中空紡錘状流水水柱の生成」(田中・伊東彊自と共著)を発表。6月21日、地震研究所談話会で「半島の傾斜と地殻の剛性」(宮部と共著)および「地震の分布と観測所の分布」を発表。7月12日、帝国学士院で“Tilting and Strength of Earth’s Crust”(with N. Miyabe)を発表。10
月18日、地震研究所談話会で「地磁気の分布と日本の構造」を発表。11月12日、帝国学士院で“On the Result of Revision of Precise Levelling along the Pacific Coast from Okitu to Kusimoto, 1932”および“The Result of the Recent Revision of Precise Levelling on the Route from Tokyo to Huzimi via Takasaki and Suwa”(with N. Miyabe)を発表。12月17日、勲二等に叙せられ瑞宝章を授けられる。12月20日、地震研究所談話会で「北上川に就て」および「地磁気の分布と日本の構造(続報)」を発表。
「音楽的映画としてのラブ・ミ・トゥナイト」、『キネマ旬報』、1月。
「読書今昔談」、『東京日日新聞』、1月。
「物理学圏外の物理的現象」、『理学界』、1月。
談話「山火事の警戒は不連続線」、『日本消防新聞』、1月。
※「俳諧 二つ折」、『渋柿』、1月。
「郷土的味覚」、『郷土読本』、2月。
「映画の世界像」、『思想』、2月。
「『手首』縦横録」、『中央公論』、3月。
「映画「三文オペラ」その他」、『帝国大学新聞』、3月。
「Propfessor Takematu Okada」、『Geophysical Magazine』、3月。
「千本針」、『セルパン』、4月。
談話「シベリアの大山火事」、『日本消防新聞』、4月。
「俳味あるフランス映画——「自由を我等に」を見て」、『帝国大学新聞』、5月。
『続冬彦集』、岩波書店、6月。
「工学博士末広恭二君」、『科学』、6月。
「生ける人形——文楽の第一印象」、『東京朝日新聞』、6月。
談話「喫茶店に書斎を求む」、『帝国大学新聞』、6月。
「チューインガム」、『文学』、8月。
「映画芸術」、岩波講座『日本文学』、8月。
「教育映画について」、『文学』、8月。
「天文と俳句」、『俳句講座』、改造社、8月。
「烏瓜の花と蛾」、『中央公論』、10月。
「札幌まで——熊に逢はなかつた話」、『鉄塔』、11月。
「俳諧の本質的概論」、『俳句講座』第三章、改造社、11月。
「音楽的映画としての「ラヴ・ミ・トゥナイト」、『キネマ旬報』、11月。
「ステッキ」、『週刊朝日』、11月27日。
「Kasu no Simatu」、『Romazi no Nippon』、11月。
「ロプ・ノール其他」、『唯物論研究』、12月。
「夏目漱石先生の追憶」、『俳句講座』第八巻、改造社、12月。
「田丸先生の追憶」、『東京帝国大学理学部会誌』、12月。
「言葉の不思議(わらふとべらぼう)」、『鉄塔』、12月。 ]
上記の年譜の「※「俳諧 二つ折」、『渋柿』、1月。」周辺のことに関連して、「大正十五年補遺」(『寺田寅彦全集 文学篇 第十七巻』)に、次のとおりの、寅彦から東洋城への「俳諧二つ折」離脱(?)の書簡がある。
[大正十五年(一九二六)二月十三日 土 本郷駒込曙町十三より牛込区余丁町世十一松根豊次郎氏へ(「はがき」表の署名に「寅」とあり。)
さう一々故障を入れられては興味がぬけてしまつて困ります。壁泥は泥壁とはちがひます。又小生の二枚折のプロットは歌仙とは少しちがひます。「背景」はそんなに変化しないで、其前に一二の焦点が出来る方が「絵」としては効果があるのです。それで壁泥は撤回しない事にします。(中略)
此の二枚折は君の独吟に願ひます。附句の内容を指図するのは連句の根本義に背くと思ひます。二枚折はいやになつたからやめます。独りでやり玉へ。失敬
大正十五年(一九二六)二月十三日 土 本郷駒込曙町十三より牛込区余丁町世十一松根豊次郎氏へ(「はがき」表の署名に「寅」とあり。)
連句の道の要諦は、銘々が自分の個性を主張すると同時に他者の個性を尊重し受容して御互に活かし合ひ響き合ふ處にある。此れは或意味での則天去私に外ならない、處が君はどうも自分の個性だけで一色にしてしまはうとするので困る。それでは連句にならないで独吟になつてしまう。芭蕉の頭の大きかつた証拠はあらゆる個性を異にした弟子達のちがつた世界を包容してそれぞれを発達させた点にあるかと思ふ。どんなまづいと思ふ附け方で活かす事が面白くありませんか。繰返していゝますが、内容の注文は連句の根本義に背きます。
東洋城先生もつて如何となす?! ?! ?!
大正十五年(一九二六)二月十五日 月 本郷駒込曙町十三より牛込区余丁町世十一松根豊次郎氏へ(「封筒なし」)
少々過激派の端書を出し、あとで内々恐縮して居た處昨夜御手紙でいよいよ以て恐縮どうか御寛容を祈ります。
二枚折は種々な型式が可能なうちで其の一つ第一号型式として前半を大部分「自然」特に長句を「自然」にして短句の方に一つか二つ位人事を入れ、後半に入りて逆に長句の方を人事、短句にボツボツ自然を入れ最後の一二句で又自然に点じ此れが冒頭の自然に、それとなく対立(同じ景色ではなく、しかも調和するもの)して、一幅の背景を完成するといふのよいかと思そます (以下、略) ](『寺田寅彦全集 文学篇 第十七巻』)
https://yahan.blog.ss-blog.jp/2023-11-15
(再掲)
▽「俳諧 二つ折(『渋柿』、9月)」は、「六つ物」(六句形式)を「二つ折」(「表と裏」の十二句)」を基本とするもの。「俳諧 二枚折(『渋柿』、7月)」は、「俳諧 二つ折」(十二句)を二枚続けて、「(六句・六句)+(六句・六句)=二十四句」を基本とするもの。「俳諧 二枚屏風(『渋柿』、12月」)は、「俳諧 二つ折」(十二句)を二枚続けて、「(六句・六句)+(六句・六句)=二十四句」を、「二曲一双」屏風のように、「一枚目屏風(六句+六句)=右隻」と「二枚目屏風(六句+六句)=左隻」と、「対(主題)」の仕立てにする形式のもの。これは、「六曲一隻(六句+六句+六句+六句+六句+六句)」ものなど、様々なバリエーションのものがあろう。
[豊隆(蓬里雨)・昭和七年(一九三二)、三十三歳。]
『漱石 寅彦 三重吉(小宮豊隆著・岩波書店)』(昭和十七年初版)の中に、「破門」(昭和十一年一月二十三日「渋柿(寺田寅彦追悼号)」初出)という、豊隆が寅彦より「もう君とは俳諧をやらない」と、「東洋城・寅彦・蓬里雨」の三吟俳諧(連句)の座から「破門」されたという内容のものがある。
[(前略)
―― 或時、たしか京橋の竹葉で三人(※「東洋城・寅彦・蓬里雨」)一緒に飯を喰つてゐた時だった。寺田さんは急に眞顔になつて、私に、もう君とは一緒に俳諧をやらないと言ひ出した。―― 君のやうに不熱心ではしやうがない。僕はうちの者の機嫌をとつて、うちで会をしてゐる。それなのに君は一向真面目に句を作らない。雑談計りしてゐる。それでなければ昼寝をする。君のやうな不誠実な人間は破門する。――
(中略)
―― 是が寺田さんと私との長いつき合ひの間に、寺田さんから叱られた唯一の思ひ出である。寺田さんと話をしてゐると、時々横つ面を張り飛ばされるやうに感じる事がある。然しそれは、大抵こつちが何等の点で、馬鹿になつてゐる時、いい気にゐる時である。その際寺田さんの方では、別にこつちの横つ面を張り飛ばさうと意図してゐる訳ではなく、寺田さんから言へば、ただ当り前の事を言つてゐるのが、此方では横つ面を張り飛ばされて感じるのである。然し是はさうではない。寺田さんはほんとに叱る積りで叱つたのである。然もよくよく考へて見ると、寺田さんの叱つたのは、私の俳諧のみではなかつた。私の仕事、私の学問、私の生活。
―― いつまでたつても「後見人」を必要とするやうな私の一切を、寺田さんは是で叱つたのだといふ気が、段段して来る事を、私は禁じ得ない。これは或は私の感傷主義であつたとしても、少くとも寺田さんの俳諧に対する打ち込み方、学問に対する打ち込み方、生活に対する打ち込み方、――人生の凡てののもを受けとる受けとり方を、最も鮮やかに代表してゐるものであつたとは、言ふ事が出来るのである。 ](『漱石 寅彦 三重吉(小宮豊隆著・岩波書店)p278-285』 )
この[「東洋城・寅彦・蓬里雨」の三吟俳諧(連句)の座から「蓬里雨破門」]関連については、『寺田君と俳諧』(『東洋城全句集(下巻)』所収)で、東洋城は、次のとおり記述している。
[ 始め連句は小宮君が仙台から上京するを機会とし三人の会で作つてゐた、それで一年に二度来るか三度来るかといふ小宮君を待つてのことだから一巻が中々進行しない。其上小宮君の遅吟乃至不勉強が愈々進行を阻害する。一年経つも一巻も上がらぬ、両人で癇癪を起し、仕舞には小宮君が上京しても三人会は唯飯を食ふ雑談の会として連句のことは一切持出さないことにしてしまつた。そこで余との両吟に自ら力が入つて来、屡(シバシバ)二人会合するやうになつた。昭和四年・五年は少なく、両吟・三吟各一連に過ぎなかったが、六年に至っては俄然増加して、両吟七、三吟一歌仙を巻きあげた。](『東洋城全句集(下巻))』所収「寺田君と俳諧」)

(左から「松根東洋城・寺田寅日子・小宮蓬里雨」=「東洋城・蓬里雨」→「みやこ町役場 歴史民俗博物館・漱石快気祝い」、「寅日子」→「ウィキペディア」)
※ 「寅日子の蓬里雨破門」の頃の「東洋城・寅日子・蓬里雨」の三吟歌仙(昭和六年十月「渋柿」)
歌仙(「短夜の」巻・「東洋城・寅日子・蓬里雨」の三吟歌仙(昭和六年十月「渋柿」)」)
オ
短夜の旅寝なりしが別れかな 蓬里雨
蚊帳の釣手に濱の朝風 寅日子
長文に積荷の事も書きそへて 東洋城
将棋に声のつのる辻侍 雨
色々にものなまぐさき河岸の月 子 月
あれほどの虫鳴かずなりけり 城
ウ
汽車の中夜寒の人の寄合うて 雨
熊にとられし女うつくし 子
輿入れのその白無垢の潔く 城 恋
障子に映る影のさまざま 雨 恋
水の国真菰の里とうたはれて 子
人若かりし万葉の頃 城
どこまでも一筋道の夏の月 雨 月
名物なれば鮎の早鮓 子
なまなかに塗りたる箸の處禿げ 城
手拭掛のたたく戸袋 雨
先生を花見にさそふはかりごと 子 花(※先生=漱石のイメージ?)
春の朝寝を起されてゐる 城
ナオ
處狭(セ)く傘干す庭の陽炎ひて 雨
しぶきの玉を散らすカナリヤ 子
琴の手の一手々々にもゆる胸 城 恋
肩の細りをつゝむ縮緬 雨 恋
鳴きつれし千鳥もしばし絶えて憂き 子 恋
雲より下の雪の荒海 城
絶頂の鬼の窟(イワヤ)の夜もすがら 雨
鸚鵡(オウム)石とはこれをいふらん 子
聞き及ぶ十八番の七(ナナ)ツ面(メン) 城
あいた片手に尻をからげる 雨
宿まではついに一足の月の土手 子 月
暗いところで秋の行水 城
ナウ
コスモスの姿さまざま花つけて 雨
日限(ヒギリ)間近き仕事もちけり 子
べたくたと口のまめなる家の老 城
雀くはへて帰り来る猫 雨
絲桜根岸に寮をしつらひて 子 花
網代垣とは春深き雨 城
(補記)
俳諧の本質的概論
https://www.aozora.gr.jp/cards/000042/card2471.html
夏目漱石先生の追憶
https://www.aozora.gr.jp/cards/000042/card2472.html
田丸先生の追憶
https://www.aozora.gr.jp/cards/000042/card2473.html
[東洋城・五十五歳。秋田、象潟、榛名、箱根に遊ぶ。松山俳諧道場、東京俳諧道場。十二月、母没す。]
草摘(ツム)や畔をたがへて俳門(うかれびと)
寿(いのちなが)母生(あ)れし日の弥生かな(前書「草屋春風」)
恰(アタカ)もの柿の頃なり法隆寺(前書「『柿食へば鐘が鳴るなり』の句を思ひ出づれど、柿は買はず」)
その後(ア)トや前立仏(マエダチブツ)に秋の暮(前書「夢殿秘仏」)
いや静(シ)づに御魂(オミタマ)まもれ落葉共(ドモ)(前書「母を失ふ」)
※ 東洋城の俳句の「読み」というのは、「俳門(うかれびと)」とか「寿(いのちなが)」とか、東洋城独特の「読み」があり、東洋城が期待しているとおりの「読み」をするというのは難しい。
ちなみに、「恰(アタカ)もの」などの「読み・意味」するものは、その「前書」から類推する他はない。「後(ア)ト」は、「ト」のルビがあり、その「前立仏(マエダチブツ・マエダテブツ)」から、「五・七・五」音からすると、「その後(ア)トや」という読(詠)みになる。
そして、前書に「母を失ふ」とある「いや静づに御魂まもれ落葉共」をどう読(詠)むかとなると、「五・七・五」音の読(詠)みから、「いや静(シ)づに御魂(オミタマ)まもれ落葉共(ドモ)」として置きたい。
『東洋城全句集(中巻)』の「昭和八年(五十六歳)」に、「亡母と西下 六十二句」が収載されているが、『東洋城全句集(上巻)』の、「明治三十七年(二十七歳)」に、母を句にした次の句がある。
瓶のものに水仙剪るや四方の春(前書「床に掛軸餅は据ゑたれど瓶に花忘れたり、けさとなりて母上庭に下り立ち水仙を剪り給ふ」)
この東洋城の句は、東洋城が「病臥(腸チフス)」で癒えた時の「快癒句録 八句」の、そのうちの一句である。
瓶のものに水仙剪るや四方の春(前書「床に掛軸餅は据ゑたれど瓶に花忘れたり、けさとなりて母上庭に下り立ち水仙を剪り給ふ」)
いや静(シ)づに御魂(オミタマ)まもれ落葉共(ドモ)(前書「母を失ふ」)
この二句の間に、東洋城の、その生涯の、その半世紀(五十年)に亘る、東洋城の「母と子」との歴史が刻まれているということになる。
(再掲) 「東洋城家族」(「俳誌『渋柿(昭和四十年(一九六五)の一月号(「松根東洋城追悼号」)」所収「青春時代を語る / 東洋城 ; 洋一/p54~73」)
https://yahan.blog.ss-blog.jp/2023-10-08

「東洋城家族」(「俳誌『渋柿(昭和四十年(一九六五)の一月号(「松根東洋城追悼号」)」所収「青春時代を語る / 東洋城 ; 洋一/p54~73」)
https://dl.ndl.go.jp/pid/6071686/1/41
[左から「父・権六/伯母・初子(柳原前光(伯爵)夫人・白蓮の養母・東洋城の母の姉)/母・敏子/弟・卓四郎/弟・新八郎/親族/弟・宗一」(明治四十一年七月三十一日写)
(追記) ※上記のアドレスでは、「松根東洋城」家族として、「弟・卓四郎/弟・新八郎/親族/弟・宗一」としたのだが、『松根東洋城年譜』(『東洋城全句集中巻』)では、「明治二十年(一八八七)/十歳/弟貞吉郎生まる」とあり、「弟・新八郎(明治十八年生れ)」と「弟・卓四郎(明治二十五年生れ)」との間に、「弟貞吉郎(明治二十年生れ)」があり、それらを加味して、上記の写真を解読する必要があろう。
(再掲)
https://yahan.blog.ss-blog.jp/2023-10-12

(裏面に、「明治四十二年九月四日写之、秋風やこぼつときめてきめて撮す家」と認めてある宇和島の宏壮な郷邸で、私の推定では敷地三千坪もあつたろうか。大半を町へ売られ、跡は町立病院が建った。残った二百坪程度の敷地に七間位の邸を建てられ、私どもはそこへ通つた。それも戦火に罹つて炎上、今は唯「我が祖先(おや)は奥の最上や天の川」の句碑一基を残すのみである。徳永山冬子)
「青春時代を語る / 東洋城 ; 洋一/p54~73」)」(「俳誌『渋柿(昭和四十年(一九六五)の一月号) 』 (「松根東洋城追悼号」)」
https://dl.ndl.go.jp/pid/6071686/1/37
※ この「宇和島の松根家の邸宅と家族」(明治四十二年九月四日写)については、右から、「父・権六と母・敏子」、中央の三人「新八郎(次弟)・東洋城(継嗣・豊次郎)・房子(妹)」、
左から「宗一(末弟)・卓四郎(四弟)・貞吉郎(三弟)」という見方もあるのかも知れない。
[寅彦(寅日子)・ 55歳。
1月12日、帝国学士院で“Cracks Produced on the Surface of Dielectrics by Gliding Spark”(with M. Hirata and R. Yamamoto)および“Deformation of the Rhombic Base Lines at Mitaka and Earthquakes in Kwanto”を発表。1月19日、地震研究所談話会で「地震と漁獲」(渡部哲と共著)を発表。3月12日、帝国学士院で“Earthquakes and Fisheries”を発表。5月12日、帝国学士院で“Change of Depth in the Bay of Tosa”を発表。5月17日、地震研究所談話会で「興津より串本に至る水準点検測成果」および「土佐沿岸海底の変化」を発表。5月25日、理化学研究所学術講習会で「椿の花の落ち方に就て」(内ヶ崎と共著)および「水晶玉の打撃像」(平田・山本と共著)を発表。6月6日、航空学談話会で「中空紡錘状流水水柱の生成」(田中・伊東彊自と共著)を発表。6月21日、地震研究所談話会で「半島の傾斜と地殻の剛性」(宮部と共著)および「地震の分布と観測所の分布」を発表。7月12日、帝国学士院で“Tilting and Strength of Earth’s Crust”(with N. Miyabe)を発表。10
月18日、地震研究所談話会で「地磁気の分布と日本の構造」を発表。11月12日、帝国学士院で“On the Result of Revision of Precise Levelling along the Pacific Coast from Okitu to Kusimoto, 1932”および“The Result of the Recent Revision of Precise Levelling on the Route from Tokyo to Huzimi via Takasaki and Suwa”(with N. Miyabe)を発表。12月17日、勲二等に叙せられ瑞宝章を授けられる。12月20日、地震研究所談話会で「北上川に就て」および「地磁気の分布と日本の構造(続報)」を発表。
「音楽的映画としてのラブ・ミ・トゥナイト」、『キネマ旬報』、1月。
「読書今昔談」、『東京日日新聞』、1月。
「物理学圏外の物理的現象」、『理学界』、1月。
談話「山火事の警戒は不連続線」、『日本消防新聞』、1月。
※「俳諧 二つ折」、『渋柿』、1月。
「郷土的味覚」、『郷土読本』、2月。
「映画の世界像」、『思想』、2月。
「『手首』縦横録」、『中央公論』、3月。
「映画「三文オペラ」その他」、『帝国大学新聞』、3月。
「Propfessor Takematu Okada」、『Geophysical Magazine』、3月。
「千本針」、『セルパン』、4月。
談話「シベリアの大山火事」、『日本消防新聞』、4月。
「俳味あるフランス映画——「自由を我等に」を見て」、『帝国大学新聞』、5月。
『続冬彦集』、岩波書店、6月。
「工学博士末広恭二君」、『科学』、6月。
「生ける人形——文楽の第一印象」、『東京朝日新聞』、6月。
談話「喫茶店に書斎を求む」、『帝国大学新聞』、6月。
「チューインガム」、『文学』、8月。
「映画芸術」、岩波講座『日本文学』、8月。
「教育映画について」、『文学』、8月。
「天文と俳句」、『俳句講座』、改造社、8月。
「烏瓜の花と蛾」、『中央公論』、10月。
「札幌まで——熊に逢はなかつた話」、『鉄塔』、11月。
「俳諧の本質的概論」、『俳句講座』第三章、改造社、11月。
「音楽的映画としての「ラヴ・ミ・トゥナイト」、『キネマ旬報』、11月。
「ステッキ」、『週刊朝日』、11月27日。
「Kasu no Simatu」、『Romazi no Nippon』、11月。
「ロプ・ノール其他」、『唯物論研究』、12月。
「夏目漱石先生の追憶」、『俳句講座』第八巻、改造社、12月。
「田丸先生の追憶」、『東京帝国大学理学部会誌』、12月。
「言葉の不思議(わらふとべらぼう)」、『鉄塔』、12月。 ]
上記の年譜の「※「俳諧 二つ折」、『渋柿』、1月。」周辺のことに関連して、「大正十五年補遺」(『寺田寅彦全集 文学篇 第十七巻』)に、次のとおりの、寅彦から東洋城への「俳諧二つ折」離脱(?)の書簡がある。
[大正十五年(一九二六)二月十三日 土 本郷駒込曙町十三より牛込区余丁町世十一松根豊次郎氏へ(「はがき」表の署名に「寅」とあり。)
さう一々故障を入れられては興味がぬけてしまつて困ります。壁泥は泥壁とはちがひます。又小生の二枚折のプロットは歌仙とは少しちがひます。「背景」はそんなに変化しないで、其前に一二の焦点が出来る方が「絵」としては効果があるのです。それで壁泥は撤回しない事にします。(中略)
此の二枚折は君の独吟に願ひます。附句の内容を指図するのは連句の根本義に背くと思ひます。二枚折はいやになつたからやめます。独りでやり玉へ。失敬
大正十五年(一九二六)二月十三日 土 本郷駒込曙町十三より牛込区余丁町世十一松根豊次郎氏へ(「はがき」表の署名に「寅」とあり。)
連句の道の要諦は、銘々が自分の個性を主張すると同時に他者の個性を尊重し受容して御互に活かし合ひ響き合ふ處にある。此れは或意味での則天去私に外ならない、處が君はどうも自分の個性だけで一色にしてしまはうとするので困る。それでは連句にならないで独吟になつてしまう。芭蕉の頭の大きかつた証拠はあらゆる個性を異にした弟子達のちがつた世界を包容してそれぞれを発達させた点にあるかと思ふ。どんなまづいと思ふ附け方で活かす事が面白くありませんか。繰返していゝますが、内容の注文は連句の根本義に背きます。
東洋城先生もつて如何となす?! ?! ?!
大正十五年(一九二六)二月十五日 月 本郷駒込曙町十三より牛込区余丁町世十一松根豊次郎氏へ(「封筒なし」)
少々過激派の端書を出し、あとで内々恐縮して居た處昨夜御手紙でいよいよ以て恐縮どうか御寛容を祈ります。
二枚折は種々な型式が可能なうちで其の一つ第一号型式として前半を大部分「自然」特に長句を「自然」にして短句の方に一つか二つ位人事を入れ、後半に入りて逆に長句の方を人事、短句にボツボツ自然を入れ最後の一二句で又自然に点じ此れが冒頭の自然に、それとなく対立(同じ景色ではなく、しかも調和するもの)して、一幅の背景を完成するといふのよいかと思そます (以下、略) ](『寺田寅彦全集 文学篇 第十七巻』)
https://yahan.blog.ss-blog.jp/2023-11-15
(再掲)
▽「俳諧 二つ折(『渋柿』、9月)」は、「六つ物」(六句形式)を「二つ折」(「表と裏」の十二句)」を基本とするもの。「俳諧 二枚折(『渋柿』、7月)」は、「俳諧 二つ折」(十二句)を二枚続けて、「(六句・六句)+(六句・六句)=二十四句」を基本とするもの。「俳諧 二枚屏風(『渋柿』、12月」)は、「俳諧 二つ折」(十二句)を二枚続けて、「(六句・六句)+(六句・六句)=二十四句」を、「二曲一双」屏風のように、「一枚目屏風(六句+六句)=右隻」と「二枚目屏風(六句+六句)=左隻」と、「対(主題)」の仕立てにする形式のもの。これは、「六曲一隻(六句+六句+六句+六句+六句+六句)」ものなど、様々なバリエーションのものがあろう。
[豊隆(蓬里雨)・昭和七年(一九三二)、三十三歳。]
『漱石 寅彦 三重吉(小宮豊隆著・岩波書店)』(昭和十七年初版)の中に、「破門」(昭和十一年一月二十三日「渋柿(寺田寅彦追悼号)」初出)という、豊隆が寅彦より「もう君とは俳諧をやらない」と、「東洋城・寅彦・蓬里雨」の三吟俳諧(連句)の座から「破門」されたという内容のものがある。
[(前略)
―― 或時、たしか京橋の竹葉で三人(※「東洋城・寅彦・蓬里雨」)一緒に飯を喰つてゐた時だった。寺田さんは急に眞顔になつて、私に、もう君とは一緒に俳諧をやらないと言ひ出した。―― 君のやうに不熱心ではしやうがない。僕はうちの者の機嫌をとつて、うちで会をしてゐる。それなのに君は一向真面目に句を作らない。雑談計りしてゐる。それでなければ昼寝をする。君のやうな不誠実な人間は破門する。――
(中略)
―― 是が寺田さんと私との長いつき合ひの間に、寺田さんから叱られた唯一の思ひ出である。寺田さんと話をしてゐると、時々横つ面を張り飛ばされるやうに感じる事がある。然しそれは、大抵こつちが何等の点で、馬鹿になつてゐる時、いい気にゐる時である。その際寺田さんの方では、別にこつちの横つ面を張り飛ばさうと意図してゐる訳ではなく、寺田さんから言へば、ただ当り前の事を言つてゐるのが、此方では横つ面を張り飛ばされて感じるのである。然し是はさうではない。寺田さんはほんとに叱る積りで叱つたのである。然もよくよく考へて見ると、寺田さんの叱つたのは、私の俳諧のみではなかつた。私の仕事、私の学問、私の生活。
―― いつまでたつても「後見人」を必要とするやうな私の一切を、寺田さんは是で叱つたのだといふ気が、段段して来る事を、私は禁じ得ない。これは或は私の感傷主義であつたとしても、少くとも寺田さんの俳諧に対する打ち込み方、学問に対する打ち込み方、生活に対する打ち込み方、――人生の凡てののもを受けとる受けとり方を、最も鮮やかに代表してゐるものであつたとは、言ふ事が出来るのである。 ](『漱石 寅彦 三重吉(小宮豊隆著・岩波書店)p278-285』 )
この[「東洋城・寅彦・蓬里雨」の三吟俳諧(連句)の座から「蓬里雨破門」]関連については、『寺田君と俳諧』(『東洋城全句集(下巻)』所収)で、東洋城は、次のとおり記述している。
[ 始め連句は小宮君が仙台から上京するを機会とし三人の会で作つてゐた、それで一年に二度来るか三度来るかといふ小宮君を待つてのことだから一巻が中々進行しない。其上小宮君の遅吟乃至不勉強が愈々進行を阻害する。一年経つも一巻も上がらぬ、両人で癇癪を起し、仕舞には小宮君が上京しても三人会は唯飯を食ふ雑談の会として連句のことは一切持出さないことにしてしまつた。そこで余との両吟に自ら力が入つて来、屡(シバシバ)二人会合するやうになつた。昭和四年・五年は少なく、両吟・三吟各一連に過ぎなかったが、六年に至っては俄然増加して、両吟七、三吟一歌仙を巻きあげた。](『東洋城全句集(下巻))』所収「寺田君と俳諧」)

(左から「松根東洋城・寺田寅日子・小宮蓬里雨」=「東洋城・蓬里雨」→「みやこ町役場 歴史民俗博物館・漱石快気祝い」、「寅日子」→「ウィキペディア」)
※ 「寅日子の蓬里雨破門」の頃の「東洋城・寅日子・蓬里雨」の三吟歌仙(昭和六年十月「渋柿」)
歌仙(「短夜の」巻・「東洋城・寅日子・蓬里雨」の三吟歌仙(昭和六年十月「渋柿」)」)
オ
短夜の旅寝なりしが別れかな 蓬里雨
蚊帳の釣手に濱の朝風 寅日子
長文に積荷の事も書きそへて 東洋城
将棋に声のつのる辻侍 雨
色々にものなまぐさき河岸の月 子 月
あれほどの虫鳴かずなりけり 城
ウ
汽車の中夜寒の人の寄合うて 雨
熊にとられし女うつくし 子
輿入れのその白無垢の潔く 城 恋
障子に映る影のさまざま 雨 恋
水の国真菰の里とうたはれて 子
人若かりし万葉の頃 城
どこまでも一筋道の夏の月 雨 月
名物なれば鮎の早鮓 子
なまなかに塗りたる箸の處禿げ 城
手拭掛のたたく戸袋 雨
先生を花見にさそふはかりごと 子 花(※先生=漱石のイメージ?)
春の朝寝を起されてゐる 城
ナオ
處狭(セ)く傘干す庭の陽炎ひて 雨
しぶきの玉を散らすカナリヤ 子
琴の手の一手々々にもゆる胸 城 恋
肩の細りをつゝむ縮緬 雨 恋
鳴きつれし千鳥もしばし絶えて憂き 子 恋
雲より下の雪の荒海 城
絶頂の鬼の窟(イワヤ)の夜もすがら 雨
鸚鵡(オウム)石とはこれをいふらん 子
聞き及ぶ十八番の七(ナナ)ツ面(メン) 城
あいた片手に尻をからげる 雨
宿まではついに一足の月の土手 子 月
暗いところで秋の行水 城
ナウ
コスモスの姿さまざま花つけて 雨
日限(ヒギリ)間近き仕事もちけり 子
べたくたと口のまめなる家の老 城
雀くはへて帰り来る猫 雨
絲桜根岸に寮をしつらひて 子 花
網代垣とは春深き雨 城
(補記)
俳諧の本質的概論
https://www.aozora.gr.jp/cards/000042/card2471.html
夏目漱石先生の追憶
https://www.aozora.gr.jp/cards/000042/card2472.html
田丸先生の追憶
https://www.aozora.gr.jp/cards/000042/card2473.html
「東洋城・寅彦、そして、豊隆」(漱石没後~寅彦没まで)俳句・連句管見(その十五) [東洋城・寅日子(寅彦)・蓬里雨(豊隆)]
その十五「昭和六年(一九三一)」
[東洋城・五十四歳。「渋柿二百号記念号」刊。改造社の『俳句講座』に執筆。能成(※安倍能成)の寄稿始まる。]
.jpg)
「俳誌・渋柿(600号/昭和39・4)・『渋柿』六百号記念号」所収「六百号に思ふ / 安倍能成/p7~7」
https://dl.ndl.go.jp/pid/6071677/1/6
[扉(一句) / 野村喜舟
六百号に思ふ / 安倍能成/p7~7
四方の花(百句) / 野村喜舟/p8~13
Variétés 1 さよりと水母 / 松根東洋城/p49~49
Variétés 2 幼い詩情 / 松根東洋城/p55~55
Variétés 3 照葉狂言 / 松根東洋城/p61~61
Variétés 4 国語問題 / 松根東洋城/p67~67
Variétés 5 声と寺 / 松根東洋城/p73~73
Variétés 6 真珠貝供養 / 松根東洋城/p79~79
巻頭句 / 野村喜舟/p14~48
澁柿六百号を語る ≪座談会≫ / 水原秋櫻子 ; 秋元不死男 ; 安住敦 ; 楠本憲吉/p50~54,56~60,62~66,68~70
俳句における音韻的音調 / 西岡十四王/p71~72,74~78,80~82
たなごゝろを合せること / 礒部尺山子/p83~86
芭蕉覚書(2) / 渡部杜羊子/p87~92
空白の雄弁性 / 島田雅山/p93~93
もののあはれ / 三輪青舟/p94~97
寺田寅日子雑感 / 牧野寥々/p98~101
渋柿の立場 / 田中拾夢/p106~108
日曜随想 / 吉本杏里/p108~113
自然性の一考察 / 青木誠風/p113~115
五つの話 / 火野艸/p115~119
顔 / 高畠明皎々/p120~121
渋柿一号より六百号までの主要論文とその要旨 / 不破博/p122~127
巻頭句成績累計表 / 牧野寥々/p128~130
俳誌月且(1) / 不破博/p131~131
四月集 / 青舟 ; 十四王 ; 鬼子坊 ; 尺山子 ; 壺天子 ; 春雨/p102~103
新珠集 / 村上壺天子/p104~105
無題録 / 野口里井/p143~143
各地例会だより/p132~136
巻頭句添削実相/p136~136
処々のまとゐ/p137~137
栃木の伝統を語る 座談会 / 栃木同人/p138~142
選後片言 / 野村喜舟/p144~145
東洋城近詠(病院から)/p146~146 ]
※ この「俳誌・渋柿(600号/昭和39・4)・『渋柿』六百号記念号」が刊行された、その年の十二月二十七日に、松根東洋城は、その八十七年の生涯を閉じる。その最後の、「俳誌・渋柿(600号/昭和39・4)・『渋柿』六百号記念号」の、その巻頭言は、「阿部能成」(評論家、哲学者、教育家。愛媛県出身。夏目漱石門下。京城帝国大学教授。一高校長。第二次大戦後、文相、学習院院長を歴任。主著に「西洋近世哲学史」。明治一六~昭和四一年(一八八三‐一九六六)で、その「渋柿」でのデビューは、「昭和六年(一九三一)」の、「渋柿二百号記念号」ということになる。
阿部能成は、昭和十年(一九三五)十二月に、寺田寅彦が没した時に、友人総代として弔辞を読む。そして、昭和三十九年(一九六四)十月に、松根東洋城の没した時にも、友人総代として弔辞を捧げている。
東洋城の没後の、昭和四十一年(一九六六)に、『東洋城全句集(上・中・下巻)』の刊行に際して、編者(「安倍能成・小宮豊隆(友人代表)、野村喜舟(「渋柿」代表)、松根宗一(親族代表)」)の一人として名を連ね、その完成(昭和四十一年八・十月、昭和四十二年一月)を待たずに、その年の五月に、小宮豊隆、その一か月後の六月に、安倍能成も没している。
我影の丈高ければ冴えにけり(前書「自笑」)
読み耽る花五百首や春の夜半(前書「渋柿句集を撰む日々夜々たり 二句」)
人々やわが春睡の諫め役(同上)
付句今何の起情の霞かな
坂の渇きまこと濡らしけり汗の玉(前書「登山」)
駒形でどじようくひけり梅雨のうち(前書「俳諧消息」)
広重の絵の具の空や秋の暮(前書「墨江鐘ヶ淵にて」)
この里の人情歌へ高灯籠(前書「旅」)
初汐と或(アルイ)はいふや秋出水(前書「月明墨江下る」)
一くらみ又しきる雪に急ぎけり(前書「旅」)
[寅彦(寅日子)・五十四歳。
1月15日、幸田露伴を初めて訪問。
2月17日、地震研究所談話会で「三島町の被害に就て」(宮部と共著)を発表。2月18日、雑誌『科学』創刊号につき、編集主任石原純、相談にあずかる(寺田も編集者の中の一人)。
3月9日、航空学談話会で「パラヂウム膜の亀裂に就て(第二報)」(田中と共著)を発表。3月17日、地震研究所談話会で「島弧の曲率に就て(第二報)」および「三島町の被害に就て」を発表。
4月13日、帝国学士院で“On the Curvature of Islands Arc and Its Relation to the Latitude”および“On Heterogeneous Distribution of Houses Destroyed by Earthquake”(with N.Miyabe)を発表。4月21日、地震研究所談話会で「地震と雷雨との関係」を発表。4月、服部報公会常置委員を委嘱される。
5月28日、理化学研究所学術講演会で「火災の物理的研究(第一報)」(内ヶ崎と共著)および「固体の破壊に関する二三の考察」を発表。6月12日、帝国学士院で“Analogy of Crack and Electron”を発表。6月16日、地震研究所談話会で「ワレメに就て」を発表。
7月7日、地震研究所談話会で「地震群に就て」を発表。
8月、この頃から玉を突くようになる。
9月15日、地震研究所談話会で「深川に於けるメタン瓦斯湧出地」(宮部と共著)を発表。10月15日、アーレニウス『史的に見たる科学的宇宙観の変遷』(寺田訳、岩波文庫)が出版される。
11月12日、帝国学士院で“Relation between Frequencies of Earthquake and Thunderstorm”を発表。11月17日、地震研究所談話会で「三鷹菱形基線の変化の地震頻度」を発表。11月25日、理化学研究所学術講演会で「硝子板の割目(Ⅰ)」(平田・山本龍三と共著)および「山林火災と不連続線」(内ヶ崎と共著)を発表。
12月15日、地震研究所談話会で「三鷹菱形基線の変化と関東地方の頻度との関係(続報)」を発表。この年、しきりに連句を試みる。
「時事雑感」、『中央公論』、1月。
「火山の名に就て」、『郷土』、1月。
「女の顔」、『渋柿』、1月。
談話「地震に伴ふ光の現象」、『日本消防新聞』、1月。
「『芭蕉連句の根本解説』に就て」、『東京朝日新聞』、1月。
「曙町より」、『渋柿』、2月〜1935年11月。
「連句雑俎」、『渋柿』、3〜12月。
「日常身辺の物理的諸問題」、『科学』、4月。
「映画雑記より」、『文芸春秋』、5月。
「風呂の寒暖計」、『家庭』、6月。
「映画雑記」、『時事新報』、6月。
「青衣童女像」、『雑味』、9月。
翻訳アーレニウス『史的に見たる科学的宇宙観の変遷』、岩波書店、10月。
「量的と質的と統計的と」、『科学』、10月。
「映画雑感」、『中央公論』、10月。
「天然の芸術——「アフリカ」は語る」、『帝国大学新聞』、11月。
「カメラに掲げて」、『大阪朝日新聞』、11月。
「蓑田先生」、『東京帝国大学理学部会誌』、12月。
「こはいものの征服」、『家庭』、12月。
「ラヂオ・モンタージュ」、日本放送協会『調査時報』、12月。
「青磁のモンタージュ」、『雑味』、12月。 ]
(十二月十八日小宮豊隆氏宛手帳の中より二句)
小春日やにげた小鳥は何処の空
霜の朝鳥は逃げたる小鳥籠
(十二月二十六日小宮豊隆氏宛絵端書の中より)
子供等に歳聞かれけりクリスマス
![小宮豊隆宛 [年賀絵はがき].jpg](https://yahan.c.blog.ss-blog.jp/_images/blog/_f2e/yahan/m_E5B08FE5AEAEE8B18AE99A86E5AE9BE380805BE5B9B4E8B380E7B5B5E381AFE3818CE3818D5D.jpg)
明治42年(1909) 一月一日 (金) 小宮豊隆宛 [年賀絵はがき]/寺田寅彦 / 明治42年一月一日(1909)/書簡 / 書簡(みやこ町歴史民俗博物館/WEB博物館「みやこ町遺産」)
https://adeac.jp/miyako-hf-mus/viewer/mp200010-200020/061v2/
この明治四十二年(一九〇九)の「年賀絵はがき」の全文は、『寺田寅彦全集 文学篇 第十五巻』に収載されている。
[一月一日 金 午前七時~八時 小石川区原町一〇より本郷区森川町一小吉館小宮豊隆氏へ (新年絵はがき)
思ひ切つたハイカラの御年賀申上候。此れは多分原口君のデザインになりたるものと存じ候美祢子嬢へも同様のを差出すつもり
三四郎 様 ](『寺田寅彦全集 文学篇 第十五巻』)
※ この「三四郎 様」の「三四郎」は、明治四十一年(一九〇八)、「朝日新聞」の九月から十二月にかけて連載され、翌年五月に春陽堂から刊行された、『それから』『門』へと続く前期三部作の一つ『三四郎』の主人公の名で、その「三四郎」は、小宮豊隆がモデルとされている。ちなみに、寺田寅彦は、「三四郎の先輩(三四郎より7歳ほど年上)」の「野々宮宗八」のモデルとされている。また、この文面中の「原口君」の「原口」のモデルは「黒田清輝」、「美祢子嬢」のモデルは「平塚雷鳥」とされている。(「ウィキペディア」)

(2014.11.26朝日新聞より)
https://blog.goo.ne.jp/takimoto_2010/e/f12d9e288c77b8a84f604562b9c0e488
[豊隆(蓬里雨)・昭和六年(一九三一)、四十八歳。二月合著『続続芭蕉俳諧研究』出版。]
※寺田寅彦と小宮豊隆が、東洋城が主宰する「渋柿」に毎号執筆(「巻頭言」)するようになったのは、大正九年(一九二〇)、東洋城・寅彦(四十三歳)、豊隆(三十七歳)の頃である。
この頃の、「寺田寅彦の小宮豊隆宛書簡(はがき二葉)」に、次のような、寅彦の「変体詩」がある。
![小宮豊隆宛 [はがき二葉]一.jpg](https://yahan.c.blog.ss-blog.jp/_images/blog/_f2e/yahan/m_E5B08FE5AEAEE8B18AE99A86E5AE9BE380805BE381AFE3818CE3818DE4BA8CE891895DE4B880.jpg)
大正9年(1920) 十月八日 (金) 小宮豊隆宛 [はがき二葉]/寺田寅彦 / 大正9年十月八日(1920)/書簡 / 書簡(みやこ町歴史民俗博物館/WEB博物館「みやこ町遺産」)
https://adeac.jp/miyako-hf-mus/viewer/mp200550-200020/594/
![小宮豊隆宛 [はがき二葉]二.jpg](https://yahan.c.blog.ss-blog.jp/_images/blog/_f2e/yahan/m_E5B08FE5AEAEE8B18AE99A86E5AE9BE380805BE381AFE3818CE3818DE4BA8CE891895DE4BA8C.jpg)
大正9年(1920) 十月八日 (金) 小宮豊隆宛 [はがき二葉]/寺田寅彦 / 大正9年十月八日(1920)/書簡 / 書簡(みやこ町歴史民俗博物館/WEB博物館「みやこ町遺産」)
https://adeac.jp/miyako-hf-mus/viewer/mp200550-200020/594/
[ 変体詩 其一
歯ぐきが脹れて耳が鳴る
網膜の上をデカルトの渦が躍り廻る
冷たい物質と物質が
熱い血の中を喰ひ合つて居る
歯ぐきでも耳でも胃袋でも
歯ぐきよ胃袋よさようなら
空腹の生んだ科学も
性慾の生んだ芸術も
さようならさようなら
米と塩はあるかい
それでいゝさようなら Alles pech! Alles pech!
変体詩 其二
鶏頭が倒れかゝつて居る
起こしてくれ、おれは歯が痛い
蜻蛉の群れが
夥しい蜻蛉の群れが
隊を立てゝ飛んで居る
蜻蛉よ
少しじつとして居てくれ
おれは今歯が痛い
十月八日作 フズドールスキー (以上はがき一)
変体詩 其三
林檎が棚からおつこつた
星の欠けらを一寸なめた
オムレツカツレツガーランデン
カントにヘーゲル、アインシュタイン
みゝずの眼玉は見付けたが
碧い瞳に一寸ほれた
フアウスト、ハムレット、バーベリオン
ドンナーウェターパラプリユイ
――――――――――――――――――――――――――――
ひとりでにこんなものが出来ましたから御笑草に御目にかけます。弱陽性といふのが案外持続してとれないで居ます。もうそろそろよくなるでしやう。
十月八日
今計って見たら七度八分ある、多分歯齦(はぐき)の熱でしやう。
此んな事ばかり書いて強いて憐みを乞ひたくはないがし方ない。やつぱり黙って居るのは苦しいから許してくれ玉へ (以上はがき二) ](『寺田寅彦全集 文学篇 第十五巻』)
(補記)
「『芭蕉連句の根本解説』に就て」、『東京朝日新聞』、1月。
『寺田寅彦全集 文学篇 第十八巻』に、寺田寅彦の「書籍批評」が収載されている。なお、『芭蕉連句の根本解説(太田水穂著)』については、次のアドレスで閲覧することが出来る。
https://lab.ndl.go.jp/dl/book/1088431?page=3
なお、『芭蕉連句の根本解説(太田水穂著)』は、下記のアドレスで閲覧することが出来る。その目次は次のとおりである。
https://dl.ndl.go.jp/pid/1880003/1/1
[目次
序/1
冬の日
狂句木枯の卷/3
はつ雪の卷/49
つゝみかねの卷/96
炭賣の卷/138
霜月の卷/182
曠野
雁がねの卷/225
ひさご
木のもとの卷/263
猿みの
鳶の羽の卷/299
市中の卷/339
灰汁桶の卷/378
炭俵
梅が香の卷/421
空豆の卷/451
振賣の卷/478
續猿みの
八九間の卷/515
猿みのの卷/549
夏の夜の卷/582
連句索引/615
内容索引/637 ](「国立国会図書館デジタルコレクション」)
「連句雑俎」、『渋柿』、3〜12月。
https://aozora.binb.jp/reader/main.html?cid=2461
『芭蕉の研究』(小宮豊隆著・岩波書店)
https://dl.ndl.go.jp/pid/1213547/1/1
[目次
芭蕉/1 → 昭和七年十一月四日(論文)
不易流行説に就いて/56 → 昭和二年四月五日(論文)
さびしをりに就いて/107 → 昭和五年八月七日(論文)
芭蕉の戀の句/139 → 昭和七年五月二十日(論文)
發句飜譯の可能性/167 → 昭和八年六月五日(論文)
『冬の日』以前/175 → 昭和三年十二月七日(論文)
『貝おほひ』/199 → 昭和四年三月三日(論文)
芭蕉の南蠻紅毛趣味/231 → 昭和二年二月(論文)
芭蕉の「けらし」/261 → 大正十五年七月(論文)
芭蕉の眞僞/290 → 昭和六年十月十五日(論文)
二題/296 → 昭和三年九月九日(「潁原退蔵君に」)
→ 昭和七年八月二十三日(「矢数俳諧」)
『おくのほそ道』/303 → 昭和七年一月十四日(論文)
立石寺の蟬/326 → 昭和四年八月二十日(「斎藤茂吉」との論争)
芭蕉の作と言はれる『栗木庵の記』に就いて/330 →昭和六年七月七日(論文)
『おくのほそ道』畫卷/375 → 昭和七年六月十九日(論文)
芭蕉と蕪村/379 → 昭和四年十月(論文)
附錄
蕪村書簡考證/419 → 昭和三年六月二十八日(論文)
西山宗因に就いて/452 → 昭和七年九月二十日(論文)
宗因の『飛鳥川』に就いて/489 →昭和八年二月十二日(論文) ](「国立国会図書館デジタルコレクション」)
[東洋城・五十四歳。「渋柿二百号記念号」刊。改造社の『俳句講座』に執筆。能成(※安倍能成)の寄稿始まる。]
.jpg)
「俳誌・渋柿(600号/昭和39・4)・『渋柿』六百号記念号」所収「六百号に思ふ / 安倍能成/p7~7」
https://dl.ndl.go.jp/pid/6071677/1/6
[扉(一句) / 野村喜舟
六百号に思ふ / 安倍能成/p7~7
四方の花(百句) / 野村喜舟/p8~13
Variétés 1 さよりと水母 / 松根東洋城/p49~49
Variétés 2 幼い詩情 / 松根東洋城/p55~55
Variétés 3 照葉狂言 / 松根東洋城/p61~61
Variétés 4 国語問題 / 松根東洋城/p67~67
Variétés 5 声と寺 / 松根東洋城/p73~73
Variétés 6 真珠貝供養 / 松根東洋城/p79~79
巻頭句 / 野村喜舟/p14~48
澁柿六百号を語る ≪座談会≫ / 水原秋櫻子 ; 秋元不死男 ; 安住敦 ; 楠本憲吉/p50~54,56~60,62~66,68~70
俳句における音韻的音調 / 西岡十四王/p71~72,74~78,80~82
たなごゝろを合せること / 礒部尺山子/p83~86
芭蕉覚書(2) / 渡部杜羊子/p87~92
空白の雄弁性 / 島田雅山/p93~93
もののあはれ / 三輪青舟/p94~97
寺田寅日子雑感 / 牧野寥々/p98~101
渋柿の立場 / 田中拾夢/p106~108
日曜随想 / 吉本杏里/p108~113
自然性の一考察 / 青木誠風/p113~115
五つの話 / 火野艸/p115~119
顔 / 高畠明皎々/p120~121
渋柿一号より六百号までの主要論文とその要旨 / 不破博/p122~127
巻頭句成績累計表 / 牧野寥々/p128~130
俳誌月且(1) / 不破博/p131~131
四月集 / 青舟 ; 十四王 ; 鬼子坊 ; 尺山子 ; 壺天子 ; 春雨/p102~103
新珠集 / 村上壺天子/p104~105
無題録 / 野口里井/p143~143
各地例会だより/p132~136
巻頭句添削実相/p136~136
処々のまとゐ/p137~137
栃木の伝統を語る 座談会 / 栃木同人/p138~142
選後片言 / 野村喜舟/p144~145
東洋城近詠(病院から)/p146~146 ]
※ この「俳誌・渋柿(600号/昭和39・4)・『渋柿』六百号記念号」が刊行された、その年の十二月二十七日に、松根東洋城は、その八十七年の生涯を閉じる。その最後の、「俳誌・渋柿(600号/昭和39・4)・『渋柿』六百号記念号」の、その巻頭言は、「阿部能成」(評論家、哲学者、教育家。愛媛県出身。夏目漱石門下。京城帝国大学教授。一高校長。第二次大戦後、文相、学習院院長を歴任。主著に「西洋近世哲学史」。明治一六~昭和四一年(一八八三‐一九六六)で、その「渋柿」でのデビューは、「昭和六年(一九三一)」の、「渋柿二百号記念号」ということになる。
阿部能成は、昭和十年(一九三五)十二月に、寺田寅彦が没した時に、友人総代として弔辞を読む。そして、昭和三十九年(一九六四)十月に、松根東洋城の没した時にも、友人総代として弔辞を捧げている。
東洋城の没後の、昭和四十一年(一九六六)に、『東洋城全句集(上・中・下巻)』の刊行に際して、編者(「安倍能成・小宮豊隆(友人代表)、野村喜舟(「渋柿」代表)、松根宗一(親族代表)」)の一人として名を連ね、その完成(昭和四十一年八・十月、昭和四十二年一月)を待たずに、その年の五月に、小宮豊隆、その一か月後の六月に、安倍能成も没している。
我影の丈高ければ冴えにけり(前書「自笑」)
読み耽る花五百首や春の夜半(前書「渋柿句集を撰む日々夜々たり 二句」)
人々やわが春睡の諫め役(同上)
付句今何の起情の霞かな
坂の渇きまこと濡らしけり汗の玉(前書「登山」)
駒形でどじようくひけり梅雨のうち(前書「俳諧消息」)
広重の絵の具の空や秋の暮(前書「墨江鐘ヶ淵にて」)
この里の人情歌へ高灯籠(前書「旅」)
初汐と或(アルイ)はいふや秋出水(前書「月明墨江下る」)
一くらみ又しきる雪に急ぎけり(前書「旅」)
[寅彦(寅日子)・五十四歳。
1月15日、幸田露伴を初めて訪問。
2月17日、地震研究所談話会で「三島町の被害に就て」(宮部と共著)を発表。2月18日、雑誌『科学』創刊号につき、編集主任石原純、相談にあずかる(寺田も編集者の中の一人)。
3月9日、航空学談話会で「パラヂウム膜の亀裂に就て(第二報)」(田中と共著)を発表。3月17日、地震研究所談話会で「島弧の曲率に就て(第二報)」および「三島町の被害に就て」を発表。
4月13日、帝国学士院で“On the Curvature of Islands Arc and Its Relation to the Latitude”および“On Heterogeneous Distribution of Houses Destroyed by Earthquake”(with N.Miyabe)を発表。4月21日、地震研究所談話会で「地震と雷雨との関係」を発表。4月、服部報公会常置委員を委嘱される。
5月28日、理化学研究所学術講演会で「火災の物理的研究(第一報)」(内ヶ崎と共著)および「固体の破壊に関する二三の考察」を発表。6月12日、帝国学士院で“Analogy of Crack and Electron”を発表。6月16日、地震研究所談話会で「ワレメに就て」を発表。
7月7日、地震研究所談話会で「地震群に就て」を発表。
8月、この頃から玉を突くようになる。
9月15日、地震研究所談話会で「深川に於けるメタン瓦斯湧出地」(宮部と共著)を発表。10月15日、アーレニウス『史的に見たる科学的宇宙観の変遷』(寺田訳、岩波文庫)が出版される。
11月12日、帝国学士院で“Relation between Frequencies of Earthquake and Thunderstorm”を発表。11月17日、地震研究所談話会で「三鷹菱形基線の変化の地震頻度」を発表。11月25日、理化学研究所学術講演会で「硝子板の割目(Ⅰ)」(平田・山本龍三と共著)および「山林火災と不連続線」(内ヶ崎と共著)を発表。
12月15日、地震研究所談話会で「三鷹菱形基線の変化と関東地方の頻度との関係(続報)」を発表。この年、しきりに連句を試みる。
「時事雑感」、『中央公論』、1月。
「火山の名に就て」、『郷土』、1月。
「女の顔」、『渋柿』、1月。
談話「地震に伴ふ光の現象」、『日本消防新聞』、1月。
「『芭蕉連句の根本解説』に就て」、『東京朝日新聞』、1月。
「曙町より」、『渋柿』、2月〜1935年11月。
「連句雑俎」、『渋柿』、3〜12月。
「日常身辺の物理的諸問題」、『科学』、4月。
「映画雑記より」、『文芸春秋』、5月。
「風呂の寒暖計」、『家庭』、6月。
「映画雑記」、『時事新報』、6月。
「青衣童女像」、『雑味』、9月。
翻訳アーレニウス『史的に見たる科学的宇宙観の変遷』、岩波書店、10月。
「量的と質的と統計的と」、『科学』、10月。
「映画雑感」、『中央公論』、10月。
「天然の芸術——「アフリカ」は語る」、『帝国大学新聞』、11月。
「カメラに掲げて」、『大阪朝日新聞』、11月。
「蓑田先生」、『東京帝国大学理学部会誌』、12月。
「こはいものの征服」、『家庭』、12月。
「ラヂオ・モンタージュ」、日本放送協会『調査時報』、12月。
「青磁のモンタージュ」、『雑味』、12月。 ]
(十二月十八日小宮豊隆氏宛手帳の中より二句)
小春日やにげた小鳥は何処の空
霜の朝鳥は逃げたる小鳥籠
(十二月二十六日小宮豊隆氏宛絵端書の中より)
子供等に歳聞かれけりクリスマス
![小宮豊隆宛 [年賀絵はがき].jpg](https://yahan.c.blog.ss-blog.jp/_images/blog/_f2e/yahan/m_E5B08FE5AEAEE8B18AE99A86E5AE9BE380805BE5B9B4E8B380E7B5B5E381AFE3818CE3818D5D.jpg)
明治42年(1909) 一月一日 (金) 小宮豊隆宛 [年賀絵はがき]/寺田寅彦 / 明治42年一月一日(1909)/書簡 / 書簡(みやこ町歴史民俗博物館/WEB博物館「みやこ町遺産」)
https://adeac.jp/miyako-hf-mus/viewer/mp200010-200020/061v2/
この明治四十二年(一九〇九)の「年賀絵はがき」の全文は、『寺田寅彦全集 文学篇 第十五巻』に収載されている。
[一月一日 金 午前七時~八時 小石川区原町一〇より本郷区森川町一小吉館小宮豊隆氏へ (新年絵はがき)
思ひ切つたハイカラの御年賀申上候。此れは多分原口君のデザインになりたるものと存じ候美祢子嬢へも同様のを差出すつもり
三四郎 様 ](『寺田寅彦全集 文学篇 第十五巻』)
※ この「三四郎 様」の「三四郎」は、明治四十一年(一九〇八)、「朝日新聞」の九月から十二月にかけて連載され、翌年五月に春陽堂から刊行された、『それから』『門』へと続く前期三部作の一つ『三四郎』の主人公の名で、その「三四郎」は、小宮豊隆がモデルとされている。ちなみに、寺田寅彦は、「三四郎の先輩(三四郎より7歳ほど年上)」の「野々宮宗八」のモデルとされている。また、この文面中の「原口君」の「原口」のモデルは「黒田清輝」、「美祢子嬢」のモデルは「平塚雷鳥」とされている。(「ウィキペディア」)

(2014.11.26朝日新聞より)
https://blog.goo.ne.jp/takimoto_2010/e/f12d9e288c77b8a84f604562b9c0e488
[豊隆(蓬里雨)・昭和六年(一九三一)、四十八歳。二月合著『続続芭蕉俳諧研究』出版。]
※寺田寅彦と小宮豊隆が、東洋城が主宰する「渋柿」に毎号執筆(「巻頭言」)するようになったのは、大正九年(一九二〇)、東洋城・寅彦(四十三歳)、豊隆(三十七歳)の頃である。
この頃の、「寺田寅彦の小宮豊隆宛書簡(はがき二葉)」に、次のような、寅彦の「変体詩」がある。
![小宮豊隆宛 [はがき二葉]一.jpg](https://yahan.c.blog.ss-blog.jp/_images/blog/_f2e/yahan/m_E5B08FE5AEAEE8B18AE99A86E5AE9BE380805BE381AFE3818CE3818DE4BA8CE891895DE4B880.jpg)
大正9年(1920) 十月八日 (金) 小宮豊隆宛 [はがき二葉]/寺田寅彦 / 大正9年十月八日(1920)/書簡 / 書簡(みやこ町歴史民俗博物館/WEB博物館「みやこ町遺産」)
https://adeac.jp/miyako-hf-mus/viewer/mp200550-200020/594/
![小宮豊隆宛 [はがき二葉]二.jpg](https://yahan.c.blog.ss-blog.jp/_images/blog/_f2e/yahan/m_E5B08FE5AEAEE8B18AE99A86E5AE9BE380805BE381AFE3818CE3818DE4BA8CE891895DE4BA8C.jpg)
大正9年(1920) 十月八日 (金) 小宮豊隆宛 [はがき二葉]/寺田寅彦 / 大正9年十月八日(1920)/書簡 / 書簡(みやこ町歴史民俗博物館/WEB博物館「みやこ町遺産」)
https://adeac.jp/miyako-hf-mus/viewer/mp200550-200020/594/
[ 変体詩 其一
歯ぐきが脹れて耳が鳴る
網膜の上をデカルトの渦が躍り廻る
冷たい物質と物質が
熱い血の中を喰ひ合つて居る
歯ぐきでも耳でも胃袋でも
歯ぐきよ胃袋よさようなら
空腹の生んだ科学も
性慾の生んだ芸術も
さようならさようなら
米と塩はあるかい
それでいゝさようなら Alles pech! Alles pech!
変体詩 其二
鶏頭が倒れかゝつて居る
起こしてくれ、おれは歯が痛い
蜻蛉の群れが
夥しい蜻蛉の群れが
隊を立てゝ飛んで居る
蜻蛉よ
少しじつとして居てくれ
おれは今歯が痛い
十月八日作 フズドールスキー (以上はがき一)
変体詩 其三
林檎が棚からおつこつた
星の欠けらを一寸なめた
オムレツカツレツガーランデン
カントにヘーゲル、アインシュタイン
みゝずの眼玉は見付けたが
碧い瞳に一寸ほれた
フアウスト、ハムレット、バーベリオン
ドンナーウェターパラプリユイ
――――――――――――――――――――――――――――
ひとりでにこんなものが出来ましたから御笑草に御目にかけます。弱陽性といふのが案外持続してとれないで居ます。もうそろそろよくなるでしやう。
十月八日
今計って見たら七度八分ある、多分歯齦(はぐき)の熱でしやう。
此んな事ばかり書いて強いて憐みを乞ひたくはないがし方ない。やつぱり黙って居るのは苦しいから許してくれ玉へ (以上はがき二) ](『寺田寅彦全集 文学篇 第十五巻』)
(補記)
「『芭蕉連句の根本解説』に就て」、『東京朝日新聞』、1月。
『寺田寅彦全集 文学篇 第十八巻』に、寺田寅彦の「書籍批評」が収載されている。なお、『芭蕉連句の根本解説(太田水穂著)』については、次のアドレスで閲覧することが出来る。
https://lab.ndl.go.jp/dl/book/1088431?page=3
なお、『芭蕉連句の根本解説(太田水穂著)』は、下記のアドレスで閲覧することが出来る。その目次は次のとおりである。
https://dl.ndl.go.jp/pid/1880003/1/1
[目次
序/1
冬の日
狂句木枯の卷/3
はつ雪の卷/49
つゝみかねの卷/96
炭賣の卷/138
霜月の卷/182
曠野
雁がねの卷/225
ひさご
木のもとの卷/263
猿みの
鳶の羽の卷/299
市中の卷/339
灰汁桶の卷/378
炭俵
梅が香の卷/421
空豆の卷/451
振賣の卷/478
續猿みの
八九間の卷/515
猿みのの卷/549
夏の夜の卷/582
連句索引/615
内容索引/637 ](「国立国会図書館デジタルコレクション」)
「連句雑俎」、『渋柿』、3〜12月。
https://aozora.binb.jp/reader/main.html?cid=2461
『芭蕉の研究』(小宮豊隆著・岩波書店)
https://dl.ndl.go.jp/pid/1213547/1/1
[目次
芭蕉/1 → 昭和七年十一月四日(論文)
不易流行説に就いて/56 → 昭和二年四月五日(論文)
さびしをりに就いて/107 → 昭和五年八月七日(論文)
芭蕉の戀の句/139 → 昭和七年五月二十日(論文)
發句飜譯の可能性/167 → 昭和八年六月五日(論文)
『冬の日』以前/175 → 昭和三年十二月七日(論文)
『貝おほひ』/199 → 昭和四年三月三日(論文)
芭蕉の南蠻紅毛趣味/231 → 昭和二年二月(論文)
芭蕉の「けらし」/261 → 大正十五年七月(論文)
芭蕉の眞僞/290 → 昭和六年十月十五日(論文)
二題/296 → 昭和三年九月九日(「潁原退蔵君に」)
→ 昭和七年八月二十三日(「矢数俳諧」)
『おくのほそ道』/303 → 昭和七年一月十四日(論文)
立石寺の蟬/326 → 昭和四年八月二十日(「斎藤茂吉」との論争)
芭蕉の作と言はれる『栗木庵の記』に就いて/330 →昭和六年七月七日(論文)
『おくのほそ道』畫卷/375 → 昭和七年六月十九日(論文)
芭蕉と蕪村/379 → 昭和四年十月(論文)
附錄
蕪村書簡考證/419 → 昭和三年六月二十八日(論文)
西山宗因に就いて/452 → 昭和七年九月二十日(論文)
宗因の『飛鳥川』に就いて/489 →昭和八年二月十二日(論文) ](「国立国会図書館デジタルコレクション」)
「東洋城・寅彦、そして、豊隆」(漱石没後~寅彦没まで)俳句・連句管見(その十四) [東洋城・寅日子(寅彦)・蓬里雨(豊隆)]
その十四「昭和五年(一九三〇)」
[東洋城・五十三歳。毎週金曜日、寅彦と会合して連句を作る。浦賀で海上大会。]
[ 塩原両面碑に立ちて 十五句
わが句碑の端とはなるゝ寒さかな
碑の我が句最も冬を知れるかな
我が句碑の冬の句驕れ山容(スガタ)
凩の四方八方来(ク)や句碑我に
碑撮(ウツ)すや却て冬の山相(スガ)タ
あはれむや碑撮す人の指の凍(イテ)
碑の冬や塩の湯道の口をなし
あはれむや句碑のぐるりに枯るゝ葦
句碑の句の冬とはをかし温泉(ユ)に遊び
この凍(イ)てを我が句碑の上と思ふかな(前書「旅宿寒夜」)
あくまでに澄みて鋭(スル)ドや冬の水(前書「冬の塩原」)
門前も古町も鄙や古正月
此の荘のあるじの留守や冬木立
タツツケに羽子(ハネ)つく子等や古正月
山川の音こそものの冬夜かな

「塩原両面碑の松根東洋城(昭和二年七月、両面碑・西面)」)(『東洋城全句集中巻』)
https://yahan.blog.ss-blog.jp/2023-11-17
[【碑文】
「さまみえて土になりゐる落葉哉」表
「すずしさやこの山水に出湯とは」裏 (塩原四季郷より)
http://hotyu.starfree.jp/historicalspots/bungakuhi/bungakuhi.html ]
[寅日子(寅彦)・五十三歳。
1月21日、地震研究所談話会で「本邦火山活動の緯度分布に就て」および「温泉の熱に就て」を発表。2月12日、帝国学士院で“Crustal Disturbance in Kwanto Districts”(with N. Miyabe)および“On the Relation between the Disvergence of Horizontal Displacements of Trigonometrical Points and the Vertical Displacements of the Earth Crust”を発表。
2月17日、航空学談話会で「パラヂウム膜の亀裂に就て」(田中と共著)を発表。2月18日、地震研究所談話会で「三角点移動の意義に就て」を発表。
4月12日、帝国学士院で“Further Studies on Periodic Columnar Vortices Produced by Convection”(with M.Tamano)を発表。4月15日、地震研究所談話会で「山崩れに就て(第二報)」(宮部と共著)を発表。
6月12日、帝国学士院で“Preliminary Experiments on the Modes of Propagation of Surface
Combustion”を発表。6月17日、地震研究所談話会で「土地の垂直運動と地形との関係」(宮部と共著)を発表。
9月15日、正四位に叙せられる。9月16日、地震研究所談話会で「山崩れの調査(第三報)」(宮部と共著)を発表。
10月29日、理化学研究所学術講演会で「火山灰の吸着作用(Ⅱ)」(平田・内ヶ崎直郎と共著)を発表。
12月12日、帝国学士院で“On Luminous Phenomena Accompanying Earthquakes”を発表。12月16日、地震研究所談話会で「地震に伴う光の現象」を発表。
談話「火災研究の基本材料」、『日本消防新聞』、1月。
「二つの正月」、『文芸春秋』、2月。
「LIBER STUDIORUM」、『改造』、3月。
「高浜さんと私」、『現代日本文学全集』、月報、4月。
「地図をたどる」、『大阪朝日新聞』、7月。
「夏 暑さの過去帳(上)(下)」、『東京朝日新聞』、8月。
「映画時代」、『思想』、9月。
「震生湖より」、『渋柿』、10月。
「映画雑感(一)(二)」、『帝国大学新聞』、11〜12月。
「レーリー卿(Lord Rayleigh)」、岩波講座『物理学及び化学』、12月。
「研究者の対立」、『東京朝日新聞』、12月。
談話「大地震と光り物」、『報知新聞』、12月 ]
忙しや金が入る出る歳の暮(十二月二十四日松根豊次郎宛封緘端書の中より)
※ この句は、『寺田寅彦全集 文学篇 第十六巻』に、その全文が収載されている。
[ 十二月二十四日 水 午後零時~四時 神田より牛込区余丁町四一松根豊次郎氏へ(封緘はがき 速達便)
正直へ神の恵みの落しもの (城)(※東洋城)
石も長閑に笑ふ狛犬
花の山うかうか越えし此処は何処
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
それから先日の「女の顔」の中へ左を加えたし
ロゼチの腺病質の女の事の次へ、音楽会見初めの件の前に
「それから又グリューズの「破瓶」の娘の顔も好きらしかつた。ヴォラプチュアスだと評して居た。先生の虞美人草かなんかの中に出て来るヴォラプチュアスな顔のモデルは即ち此れである」
右校正の時御入れ下さい
十二月二十四日
忙しや金が入る出る歳の暮 ]
この二日後の「十二月二十六日付け小宮豊隆宛寺田寅彦書簡」がある。
[十二月二十六日 金 仙台市北二番丁六八小宮豊隆氏へ
(前略)
虚子(※高浜虚子)より大兄(※小宮豊隆)と安倍君(※安倍能成)上京の期聞合せ参り居候、御上京草ゝつかまる事と存候、一夕大にメートルをあげて昔を偲び度と楽しみ居候、御出京の日取決定の上御一報願上候
松根大将(※松根東洋城)小生へも続々厳談、折柄震研の仕事でテンテコ舞の処を督促され、何をかいわんやら分からない程のデタラメを書送り候処、今度は又至急に連句を一巻無理やりに上げろとの事にて電車中にて呻吟、速達で送ると、すぐ電話で附句を申越し、速刻又次の二句をつづけろとの事、当日は理研・震研・文部省・丸善・三越と東奔西走の間にやつと製造途中で封緘葉書を求め速達で発送、それに大将があげ句をつければ落成するのだから、それきり受け取つとたとも何もなくしーんとしてしまつて颱風一過の後の如き有様に有之候、尤も大分奮闘して居るらしいので同情も致居候、しかし少生の如き重宝至極、何時でも即刻に金玉の名文章やダイアモンドルビーの如き句を手の平からもみ出す手品師のやうな軽便なる友人をもつ東洋城も亦仕合せ果報者かと存ぜられうたゝ羨望の感に堪えず候 (後略) ]
[豊隆(蓬里雨)・昭和五年(一九三〇)、四十七歳。二月合著『続芭蕉俳諧研究』出版。]
(追記)「自画像(寺田寅彦)」周辺
.jpg)
「母の像(寺田寅彦画)」 (『寺田寅彦画集(中央公論美術出版)』)
[制作年月=大正一〇・二/種別=油彩/基材=板/大きさ=33.0×24.0㎝]
.jpg)
「つるばら(寺田寅彦画)」(『寺田寅彦画集(中央公論美術出版)』)
[制作年月=大正一〇・二/種別=油彩/基材=板/大きさ=32.8×23.8㎝]
(E5AFBAE794B0E5AF85E5BDA6E794BB).jpg)
「自画像(A)(寺田寅彦画)」(『寺田寅彦画集(中央公論美術出版)』)
[制作年月=大正一三/種別=油彩/基材=カンバスボード/大きさ=32.5×23.5㎝]
[自画像 寺田寅彦
https://www.aozora.gr.jp/cards/000042/files/2438_10299.html
四月の始めに山本鼎(やまもとかなえ)氏著「油絵のスケッチ」という本を読んで急に自分も油絵がやってみたくなった。去年の暮れに病気して以来は、ほとんど毎日朝から晩まで床の中で書物ばかり読んでいたが、だんだん暖かくなって庭の花壇の草花が芽を吹き出して来ると、いつまでも床の中ばかりにもぐっているのが急にいやになった。同時に頭のぐあいも寒い時分とは調子が違って来て、あまり長く読書している根気がなくなった。今までは内側へ内側へと向いていた心の目が急に外のほうへ向くと、そこには冬の眠りからさめて一時に活気づいた自然界が勇み立って自分を迎えてくれるような気がした。ちょうどそこへ山本氏の著書が現われて自分の手をとって引き立てるのであった。
中学時代に少しばかり油絵をかいてみた事はある。図画の先生に頼んで東京の飯田(いいだ)とかいううちから道具や絵の具を取り寄せてもらって、先生から借りたお手本を一生懸命に模写した。カンバスなどは使わず、黄色いボール紙に自分で膠(にかわ)を引いてそれにビチューメンで下図の明暗を塗り分けてかかるというやり方であった。かなりたくさんかいたが実物写生という事はついにやらずにしまった。そして他郷に遊学すると同時にやめてしまって、今日までついぞ絵筆を握る機会はなかった。もと使った絵の具箱やパレットや画架なども、数年前国の家を引き払う時に、もうこんなものはいるまいと言って、自分の知らぬ間に、母がくず屋にやってしまったくらいである。
その後都へ出て洋画の展覧会を見たりする時には、どうかすると中学時代の事を思い出し、同時にあの絵の具の特有な臭気と当時かきながら口癖に鼻声で歌ったある唱歌とを思い出した、そうして再びこの享楽にふけりたいという欲望がかなり強く刺激されるのであった。しかし自分の境遇は到底それだけの時間の余裕と落ち着いた気分を許してくれないので実行の見込みは少なかった。ただ展覧会を見るたびにそういう望みを起こしてみるだけでも自分の単調な生活に多少の新鮮な風を入れるという効果はあった。
中学時代には、油絵といえば、先生のかいたもの以外には石版色刷りの複製品しか見た事はなかった。いつか英国人の宣教師の細君が旧城跡の公園でテントを張って幾日も写生していた事があった。どんなものができているかのぞいてみたくてこわごわ近づくと、十二三ぐらいの金髪の子供がやって来て「アマリ、ソバクルト犬クイツキマース」などと言った。実際そばには見た事もないような大きな犬がちゃんと番をしているのであった。
それから二十何年の間に自分はかなり多くの油絵に目をさらした。数からいえばおそらく莫大(ばくだい)なものであろう。見ているうちに自分の目はだんだんにいろいろに変わって来た。そして芸術としての油絵というものに対する考えもいろいろにうつって行った。ただその間に不断にいだいていた希望はいつか一度は「自分のかいた絵」を見たいという事であった。世界じゅうに名画の数がどれほどあってもそれはかまわない。どんなに拙劣でもいいから、生まれてまだ見た事のない自分の油絵というものに対してみたいというのであった。
このような望みは起こっては消え起こっては消え十数年も続いて来た。それがことしの草木の芽立つと同時に強い力で復活した。そしてその望みを満足させる事が、同時に病余の今の仕事として適当であるという事に気がついた。
それでさっそく絵の具や筆や必要品を取りそろえて小さなスケッチ板へ生まれて始めてのダップレナチュールを試みる事になった。新しいパレットに押し出した絵の具のなまなましい光とにおいは強烈に昔の記憶を呼び起こさせた。長い筆の先に粘い絵の具をこねるときの特殊な触感もさらに強く二十余年前の印象を盛り返して、その当時の自分の室から庭の光景や、ほとんど忘れかかった人々の顔をまのあたりに見るような気がした。
まず手近な盆栽や菓子やコップなどと手当たり次第にかいてみた。始めのうちはうまいのかまずいのかそんな事はまるで問題にならなかった。そういう比較的な言葉に意味があろうはずはなかった。画家の数は幾万人あっても自分は一人しかいないのであった。
思うようにかけないのは事実であった。そのかわり自分の思いがけもないようなものができてくるのもおもしろくない事はなかった。とてもかけそうもないと思ったものが存外どうにか物になったと思う事もあり、わけもないと思ったものがなかなかむつかしかったりした。それよりもおもしろいのは一色の壁や布の面からありとあらゆる色彩を見つけ出したり、静止していると思った草の葉が動物のように動いているのに気がついたりするような事であった。そして絵をかいていない時でもこういう事に対して著しく敏感になって来るのに気がついた。寝ころんで本を読んでいると白いページの上に投じた指の影が、恐ろしく美しい純粋なコバルト色をして、そのかたわらに黄色い補色の隈くまを取っているのを見て驚いてしまってそれきり読書を中止した事もある。またある時花壇の金蓮花(きんれんか)の葉を見ているうちに、曇った空が破れて急に強い日光がさすと、たくさんな丸い葉は見るまにすくすくと向きを変え、間隔と配置を変えて、我れ勝ちに少しでも多く日光をむさぼろうとするように見えた。一つ一つの葉がそれぞれ意志のある動物のように思われてなんだか恐ろしいような気もした。
手近な静物や庭の風景とやっているうちに、かく物の種がだんだんに少なくなって来た。ほんとうは同じ静物でも風景でも排列や光線や見方をちがえればいくらでも材料にならぬ事はないが、素人(しろうと)の初学者の自分としては、少なくもひとわたりはいろいろちがった物がかいてみたかった。いちばんかいてみたいのは野外の風景であるが今の病体ではそれは断念するほかはなかった。それでとうとう自画像でも始めねばならないようになって来た。いったい自分はどういうものか、従来肖像画というものにはあまり興味を感じないし、ことに人の自画像などには一種の原因不明な反感のようなものさえもっているのであるが、それにもかかわらずついに自分の顔でもかいてみる気になってしまった。
それである日鏡の前にすわって、自分の顔をつくづく見てみると、顔色が悪くて頬(ほお)がたるんで目から眉(まゆ)のへんや口もとには名状のできない暗い不愉快な表情がただようているので、かいてみる勇気が一時になくなってしまった。そのうちにまた天気のいい気分のいいおりに小さな鏡を机の前に立てて見たら、その時は鏡の中の顔が晴れ晴れとしていて目もどことなく活気を帯びて、前とは別人のような感じがした。それでさっそくいちばん小さなボール板へ写生を始めた。鉛筆でザット下図をかいてみたがなかなか似そうもなかった、しかしかまわず絵の具を付けているうちにまもなくともかくも人の顔らしいものができた。のみならずやはりいくらかは自分に似ているような気もした。顔の長さが二寸ぐらいで塗りつぶすべき面積が狭いだけに思ったよりは雑作(ぞうさ)なく顔らしいものができた、と思ってちょっと愉快であった。それでさっそく家族に見せて回ると、似ているという者もあり、似ていないというものもあった、無論これはどちらも正しいに相違なかった。
この始めての自画像を描く時に気のついたのは、鏡の中にある顔が自分の顔とは左右を取りちがえた別物であるという事である。これは物理学上からはきわめて明白な事であるが写生をしているうちに始めてその事実がほんとうに体験されるような気がした。衣服の左前なくらいはいいとしても、また髪の毛のなでつけ方や黒子(ほくろ)の位置が逆になっているくらいはどうでもなるとしても、もっと微細な、しかし重要な目の非対称や鼻の曲がりやそれを一々左右顛倒(てんとう)して考えるという事は非常に困難な事である。要するに一面の鏡だけでは永久に自分の顔は見られないという事に気がついたのである。二枚の鏡を使って少し斜めに向いた顔を見る事はできるだろうがそれを実行するのはおっくうであったし、また自分の技量で左右の相違をかき分ける事もできそうになかった。そんな事を考えなくてもただ鏡に映った顔をかけばいいと思ってやっているうちに着物の左衽(ひだりおくみ)のところでまたちょっと迷わされた。自分の科学と芸術とは見たままに描けと命ずる一方で、なんだか絵として見た時に不自然ではないかという気もするし、年取った母がいやがるだろうと思ったので、とうとう右衽(みぎおくみ)にごまかしてしまったが、それでもやっぱり不愉快であった。
この自画像.「No.1」は恐ろしくしわだらけのしかみ面(づら)で上目に正面をにらみつけていて、いかにも性急なかんしゃく持ちの人間らしく見えるが、考えてみると自分にもそういう資質がないとは言われない。
それから二三日たってまた第二号の自画像を前のと同大の板へかいてみた。今度は少し顔を斜めにしてやってみると、前とは反対にたいへん温和な、のっぺりした、若々しい顔ができてしまった。妻や子供らはみんな若すぎると言って笑ったが母だけはこのほうがよく似ていると言った。母親の目に見える自分の影像と、子供らの見た自分の印象とには、事によったら十年以上も年齢の差があるかもしれない。それで思い出したが近ごろ自分の高等小学校時代に教わったきりで会わなかった先生がたの写真を見た時にちょっとそれと気がつかなかった。写真の顔があまり若すぎて子供のような気がしたからである。よくよく見ているとありありと三十年前の記憶が呼び返された。これから考えるとわれわれの頭の中にある他人の顔は自分といっしょに、しかもちゃんときまった年齢の間隔を保存しつつだんだん年をとるのではあるまいか。
同じ自分が同じ自分の顔をかくつもりでやっていると、その時々でこのようにいろいろな顔ができる、これはつまり写生が拙なためには相違ないがともかくもおもしろい事だと思った。No.1にもNo.2にもどこか自分に似たところがあるはずであるが、1と2を並べて比較してみると、どうしても別人のように見える。そうしてみると1と2がそれぞれ自分に似ているのは、顔の相似を決定すべき主要な本質的の点で似ているのでなくて第二義以下の枝葉の点で似ているに過ぎないだろうと思われる。
これについて思い出す不思議な事実がある。ある時電車で子供を一人連れた夫婦の向かい側に座を占めて無心にその二人の顔をながめていたが、もとより夫婦の顔は全くちがった顔で、普通の意味で少しも似たところはなかった。そのうちに子供の顔を注意して見るとその子は非常によく両親のいずれにも似ていた。父親のどこと母親のどことを伝えているかという事は容易にわかりそうもなかったが、とにかく両親のまるでちがった顔が、この子供の顔の中で渾然こんぜんと融合してそれが一つの完全な独立なきわめて自然的な顔を構成しているのを見て非常に驚かされた。それよりも不思議な事は、子供の顔を注視して後に再び両親の顔を見比べると、始め全く違って見えた男女の顔が交互に似ているように思われて来た事である。このような現象を心理学者はどう説明するだろうか。たしかにおもしろい問題にはなるに相違ないと思った。それからまた一方では親子の関係というものの深刻な意味を今さらのように考えたりした。もう一つ、これはK君の話だが、同君の友人の二男が、父親よりも生母よりもかえって、父の先妻、しかもなくなった先妻にそっくりなので、始めて見たK君は、一種名状のできないショックを感じたそうである。K君の認めた相似が全くオブジェクティヴだとすると、現在の科学はこの説明を持てあますだろうと思われる。
いったい二つの顔の似ると似ないを決定すべき要素のようなものはなんであろう。この要素を分析し抽出する科学的の方法はないものだろうか。自分は自画像をかきながらいろんな事を考えてみた。同じ大きさに同じ向きの像を何十枚もかいてみる。そしてそれを一枚一枚写真にとって、そのおのおのを重ね合わせて重ね撮とり写真をこしらえる。もしおのおのの絵が実物とちがう「違い方」が物理学などでいう誤差の方則に従っていろいろに分配せられるとすれば重ね撮りの結果はちょうど「平均」をとる事になってそれが実物の写真と同じになりはしまいか。もしそれが実物と違えばその相違は描き手に固有ないわゆる personal equation を示すか、あるいはその人の自分の顔に対する理想を暴露するかもしれない。それはとにかく何十枚の肖像をだいたい似ている度に応じて二つか三つぐらいの組に分類する。そうしてその一つ一つの写真を本物の写真と重ねてみてよく一致する点としない点とをいくつかの箇条に分かって統計表をこしらえる。こんな方法でやれば「顔の相似」という不思議な現象を系統的に研究する一つの段階にはなりそうである。
自画像は「No.2」でしばらくやめてまた静物などをやっているうちに一日画家のT君が旅行から帰ったと言ってわざわざ自分の絵を見に来てくれた。ありたけの絵をみんな出して見てもらっていろいろの注意を受け、いろいろなおもしろい事を教わってたいへんに啓発されるような気がした。自画像の二枚については、あまり色が白すぎるというのと、もっと細かに見て、色や調子を研究して根気よくかかなければいけないというのであった。なるほどそう言われてみると自分のかいた顔は普通の油絵らしくなくて淡彩の日本画のように白っぽいものである。もっとも鏡が悪いために実際いくぶん顔色が白けて見えたには相違ないが、そう言われて後に鏡と絵と比べてみると画像のほうはたしかに色が薄くて透明に見えて、上簇期じょうぞくきの蚕のような肌はだをしていた。そしていかにもぞんざいで薄っぺらなものに思われて来た。それからT君はいろいろの話の内にトーンというものの大切な事を話した。目を細くしてよく見きわめをつけてから一筆ごとに新しく絵の具を交ぜては置いて行くのだそうである。ある人は六尺もある筆の先へちょっと絵の具をくっつけて、鳥でも刺すようにして一点くっつけてはまたながめて考え込むというのである。この話を聞いているうちになんだか非常に愉快になって来た。そういう仕事をしている画家と、非常にデリケートな物理の実験をやって敏感なねじをいじってはめがねをのぞいている学者と全く兄弟分のような気がしておもしろくなって来た、そしてどういうわけか急におかしくなって笑い出すとT君もいっしょに笑い出してしまった。
それから二三日たってT君の宅へ行って同君の昔かいた自画像を二枚見せてもらった。それは小さな板へかいた習作であったがなるほど濃厚な絵の具をベタベタときたならしいように盛り付けたものであった。しかし自分ののっぺりした絵と比べて見るとこのほうが比較にならぬほどいきいきしていてまっ黒な絵の具の底に熱い血が通かよっていそうな気がした。
もっとも考えてみるとこのくらいの事は今始めて知ったわけではない。この自分の自画像がもし他人の絵であったとしたらおそらく始めからまるで問題にならないで打っちゃってしまうほどつまらないものかもしれない。ただそれが自分のかいたのであるがためにこんなわかりきった事がわからないでいたのをT君の像をながめているうちにやっとの事で明白に実認したに過ぎない。いったい自分は、多くの人々と同様に、自分の理解し得ないものを「つまらない」と名づけたり、自分と型のちがった人を「常識がない」と思ったりするような事がかなりありそうであるが、幸いにあるいは不幸にして、自分の絵を一つの単純な絵として見て黒人くろうとのと比較する時に、自分のほうがいいと思いうるほどの自信がないと見えて、T君の絵と説とにすっかり感心してしまった。そうして頭を新しく入れ換えて第三号の自画像に取りかかる事にした。
T君のすすめに従って今度はカンバスへやることにした。六号という大きさの画布を枠わくに張ったのを買って来た。同時に画架も買って来てこれに載せた。なんだかいよいよ本式になって来たと思うと少し気味の悪いような気もしてすぐには手をつけられなかった。居間のすみの箪笥たんすのわきにある鏡台の前へすわって左から来る光に半面を照らさせ、そして鏡に映っているものは画架でも背後の箪笥でもその上にある本や新聞でも、見えるだけのものはみんなそのままにかいてみようと思ってやり始めた。
今度はなるべく顔を大きくするつもりで下図を始めたのであるが、どういうものか下図をかいているうちに思ったより小さくなってしまった。自分が大きくしようと思っているのに手と鉛筆とがそれを押え押えて顔を縮めて行くようにも思われた。実物に近いほどに書くつもりのがいつのまにか半分足らずぐらいのものになった。実物と思って見ているのが実は鏡の中の虚像で鏡より二倍の距離にあるから視角はかなり小さくなっている。それに画布のほうは手近にあるものだから、たとえ映像と絵と同じ視角にしても寸法は実物の半分以下になるわけだと思われる。それにしても人が鏡を見て自分の顔というものの観念をこしらえているが、左右顛倒(てんとう)の事実は別として顔の大きさというものに対しても正当な観念を得る事はおそらく非常に困難だろうと思われだした。つまりわれわれはほんとうの自分の顔というものは一生知らずに済むのだという気さえした。自分の事は顔さえわからないのだ。だれかが「自分の背中だけは一生触れられない」と言った事を思い出す。
下図をすっかり消してかき直すのもめんどうであったし、またこのくらいの大きさのも一枚あっていいと思ってそのまま進行する事にした。妻と長女とに下図を見せて違った所を捜させるとじきにいろいろな誤りが発見された。他人が見ればそんなにたやすく見つかるような間違いが、かいている自分にはなかなかわからないのであった。
下図はとうとうあまりよく似ないままで絵の具をつけ始めた。かいて行くうちによくなるだろうと思ったが、なかなかそう行かない事はあとでだんだんにわかって来た。
もちろん顔から塗り始めた。始めにだいたいの肉色と影をつけてしまった時には、似てはいないがたいへん感じのいいような顔ができたのでこれは調子がいいと思って多少気乗りがして来た。そしてだんだんに細かく筆を使って似せるほうと色の調子とに気を配り始めるとそろそろむつかしくなる事が予覚されるようになって来た。まず第一に困った事は局部局部を見て忠実に写しているといつのまにか局部相互の位置や権衡が乱れてしまう。右の目の格好を一生懸命にかいてだいたいよくなったと思って少し離れて見るとその目だけが顔とは独立に横に脱線したりつり上がりねじれなどした。どうも右をかいている時と左をかいている時とで顔の傾斜が変わる癖があるらしかった。そのために左右の目は互いに自由行動をとってどうしても一つの顔の中に融和しない、しかたがないからいずれか一方をきめてから他の一方を服従させるほかはないと思ってまず比較的似ているらしい向かって右の目を標準にする事に決めた、そして左をかく時は一生懸命に右との関係を考え考えかいて行った。
コンパスや物差しを持って来て寸法の比例を取ったりしたが、鏡が使ってあるだけにこの仕事は静物などの場合のように簡単でない。なにしろほんとうの顔と鏡の顔と、ほんとうの物差しと鏡の中の物差しとこの四つのもののうちの二つを比較するのだから時々頭の中が錯雑して比較すべき物を間違えたりする。それからもう一つ鏡のぐあいの悪い事は、静物などと同じつもりで、目を細くして握った手のひらの穴からのぞくと、鏡の中の顔もそのとおりまねをするから結局目の近辺をかく時にはこの方法は無効になるのであった。
右の目を標準にしてだんだんに進行して行くうちにまもなく鼻から顔全体の輪郭まで大改造をやらなければならない事がわかって来たのでこれはたいへんだと思った。顔全体がだいぶ傾斜しなければならぬ事になるらしい。それでは困るから結局かんじんの右の目をもう一ぺん打ちこわして、すっかり始めからやり直すほかはないと思うとはりつめた力が一時に抜けて絵筆を投げ出してしまいたくなった。ひとまず中止としてカンバスを室のすみへ立てかけて遠方からながめて見ると顔じゅう妙に引きつりゆがんで、始めに感じのよかった目も恐ろしく険相な意地悪そうな光を放ってにらんでいるので、どうもそのままにしてあすまで置くのは堪えられないような気がした。それで、もうだいぶ肩が凝って苦しくなって来たけれども奮発して直し始めた。
それからほとんど毎朝起きて部屋(へや)の掃除(そうじ)がすむとすぐにこの自画像「No.3」に手を入れる。あまり凝りすぎてもからだにさわるから午前だけにしたいと思ったが、午前中に一段片付けたつもりで昼飯を食いながらながめていると間違った所が目について気になりだす、もう一筆と思ううちにとうとう午後の時間が容赦なくたってしまう。
それでも少しずつは似てくるようであった。時としては描きながら近くで見ると非常によくなって、ほとんどもう手をつける所がないような気がして愉快になる。しかし画架からはずして長押(なげし)の上に立てかけて下から見上げるとまるで見違えるような変な顔になっているのでびっくりする。どうかすると片方の小鼻が途方もなくたれ下がっているのを手近で見る時には少しも気づかなかったりする。
不思議な事にはこのように毎日見つめている絵の中の顔がだんだんに頭の中にしみ込んで来てそれがとにかく一人の生きた人間になって来る。それは自分のようでもあるしまた他人のようでもある。時としては絵の顔のほうがほんとうの自分で鏡の中のがうそのような気がする。特に鏡と画面とから離れて空で考える時には、鏡の顔はいつでも影が薄くて絵の顔のほうが強い強い実在となって頭の中に浮かんで来るのである。これではだめだと思った。絵を見つめる時間をなるべく減じて鏡を見る時を長くしなければいけないと思った。
絵の中にいる人間とかいている自分との間には知らず知らずの間に一種の同情のようなものが生じて来るような気がしだした。画像が口をゆがめて来ると、なんだか自分も口をゆがめなくてはいられなくなるようであった。自分が目を細くしていると画像もいつのまにかそうするように思われた。絵の顔が気持ちのいい日はなんだか愉快であるが、そうでない日は自分もきげんがよくなかった。
調子のごくごくいい日にはいいかげんに交ぜる絵の具の色や調子がおもしろいようにうまくはまって行く。絵の具のほうですっかり合点(がてん)してよろしくやってくれるのを、自分はただそこまで運んでくっつけてやっているだけのような気がする。こんな時にはかなり無雑作むぞうさに勢いよく筆をたたきつけるとおもしろいように目が生きて来たり頬ほおの肉が盛り上がったりする。絵の具と筆が勝手気ままに絵をかいて行くのを自分はあっけに取られて見ているような気がするのである。こんな時には愉快に興奮する。庭を見ても家内の人々の顔を見ても愉快に見え、そうして不思議に腹がよくへって来る。
これに反してぐあいの悪い日は絵の具も筆も、申し合わせて反逆を企て自分を悩ますように見える。色が濃すぎたと思って直すときっと薄すぎる。直しているうちに輪郭もくずれて来るし、一筆ごとに顔がだんだん無惨に情けなく打ちこわされて行く。その時の心持ちはずいぶんいやなものである。早く中止すればいいと思わない事はないが、そういう時に限って未練が出てやめるに忍びない。ちょうど来客でもあってやむを得ず中止する時には、困ったという感じと、ちょうどいい時に来てくれたという考えとがいっしょになる。客が帰るとできそこなった絵をすぐに見ないではいられない。
あまり自分が熱中しているものだから、家内のものは戯れに「この絵は魂がはいっているから夜中に抜け出すかもしれない」などと言って笑っていた。ところがある晩床の中にはいって鴨居(かもい)にかけた自画像をながめていると、絵の顔が思いがけもなくまたたきをするような気がした。これはおもしろいと思って見つめるとなんともない。しかし目をほかへ転じようとする瞬間にまたすばやくまたたくように見えた。これはたぶん有りがちな幻覚かもしれない。プーシキンの短編にもカルタのスペードの女王がまたたきをする話があるが、とにかくわれわれの神経が特殊な状態に緊張されると、こんな錯覚が生じるものと見える。それよりも不思議な錯覚は、夜床の中で目をねむって闇やみの中を見つめるようにすると、そこに絵の顔が見えて来る事である。始めて気のついた時はハルシネーションのようにはっきり見えたが、その後はただぼんやり、しかしそれが画像の顔だという事がわかるくらいに現われたり消えたりした。生理光学でよく研究されている残像ナハビルドという現象はあるが、それは通例実物を見つめた後きわめて少時間だけにとどまるし、また通例陽像ポジチーフと陰像ネガチーフとが交互に起こるものである。このように長時間の後に残存してしかも陽像のみ現われるというのはまだ読んだ事も聞いた事もなかった。おそらくこれは生理的ではなくて、病理的に神経の異常から起こるハルシネーションの類だろうが、それにしても妙なものである。人殺しをしたものが長い年月の後に熱病でもわずらった時に殺した時の犠牲者の顔をありあり見るというが、それはおそらく自分の見た幻覚と類した程度のものが見えるのではあるまいかと思った。
もう一つ不思議な錯覚のようなものがあった。ある日例のように少しずつ目をいじり口元を直ししているうちに、かいている顔が不意に亡父の顔のように見えて来た。ちょうど絵の中から思いがけもなく父の顔がのぞいているような気がして愕然がくぜんとして驚いた。しかし考えてみるとこれはあえて不思議な事はないらしい。自分はかなりに父によく似ていると言われている、自分はそうとは思わないがどこかによく似た点があるに相違ない。自分の顔のどこかを少しばかりどうか修正すれば父の顔に近よりやすい傾向があるのだろう。それで毎日いろいろに直したり変えたりしているうちには偶然その「どこか」にうまくぶつかって、主要な鍵かぎに触れると同時に父の顔が一時に出現するのであろう。
それから考えてみるに自分が毎日筆のさきでいろいろさまざまの顔を出現させているうちには自分の見た事のない祖先のたれやそれの顔が時々そこからのぞいているのではないかという気がしだした。実際時々妙に見たような顔だという気のする事さえある。
人間の具体的な個々の記憶や経験はそのままに遺伝するものではないだろうが、それらを煎せんじつめた機微なある物が遺伝しているので、そのためにこのような心持ちを起こさせるのではあるまいか。漱石先生の「趣味の遺伝」はまさにこういう点に触れたもののようにも思われる。ラフカディオ・ハーンの書いたものの中にもこのような考えが論じてあった。われわれの祖先を千年前にさかのぼると、今の自分というのはその昔の二千万人の血を受け継いでいる勘定だそうである。そうしてみると自分が毎日こしらえているいろいろの顔は、この二千万人のだれかの顔に相当するかもしれない。こんな事を考えておかしくも思ったが、同時に「自分」というものの成り立ちをこういう立場から、もう一度よく考えてみなければならないと思った。なんだか独立な自分というものは微塵みじんに崩壊ほうかいしてしまって、ただ無数の過去の精霊が五体の細胞と血球の中にうごめいているという事になりそうであった。
この第三号の自画像はまずどうにか、こうにか仕上げてしまった。ほんとうの意味ではいつまでかかっても「仕上がる」見込みのない事がわかって来たから、ここらでまず一段落ついた事にしてしばらく放置してみる事にした。バックに緑色の布のかかった箪笥たんすがあって、その上に書物や新聞の雑然と置いてあるのがいかにもうるさくて絵全体を俗悪にしてしまうから、あとからすっかり塗りつぶしてそのかわりに暗緑色の幕をたれたようなぐあいに直してみた。そうしたら顔が急に引き立って浮き上がって来た。のみならずそれまでは雑誌の口絵にでもありそうな感じのあった絵が、この改造のためにいくらか落ちついた古典的といったような趣を生じた。そして色の対照の効果で顔の色の赤みが強められるのであった。しかしまた同時に着物がやはり赤っぽく見えだして気に入らなくなったが、もうそれを直すだけの根気がなくなってそのままにしてしまった。
すぐに第四号の自画像を同大の画布にやり始める事にした。今度はずっと顔を大きくしてそして前よりも細かく調子を分析してやってみようと思った。ところが下図をかき始めにはかなり大きくかいたのが、目や鼻を直し直ししているうちに知らず知らずだんだんに顔が縮小して行くのが実に不思議であった。だいたいできたころに寸法をとってみるとやっと実物の四分の三ぐらいのものになっている事がわかった。それをもう一度すっかり消してやり直す勇気がなかったから今度もまたそのままでやり続けた。
最初の日は影と日向ひなたとを思い切って強く区別してだいたいの見当をつけてみた。その時にできた顔は不思議に前の第三号の顔に似ていた。何かしら自分の頭の奥にこびりついた誤謬(ごびゅう)が強い力で存在を主張していると見える。
この絵はとうとう二十日(はつか)余りいじり回したが、結局やはり物にならないで中止してしまわねばならなかった。顔の面積が大きくなっただけに困難は前よりもいっそう大きかった。局部にとらわれて全体の権衡を見失う事もいよいよ多かった。セザンヌが「わかりますか、ヴォラール君。輪郭線が見る人から逃げる」と言ったほんとうの意味はよくはわからぬが、全くそういったような気のする事がしばしばあった。右の頬ほおをつかまえたと思う間に左の頬はずるずる逃げ出した。ずっと前にいつかある画家が肖像をかいているのを見た事がある。その時に画家の挙動を注意していると素人しろうとの自分には了解のできないような事がいろいろあった、たとえば肖像の顋あごの先端をそろそろ塗っていると思うとまるで電光のように不意に筆が瞼まぶたに飛んで行ったりした。油断もすきもならないといったふうに目を光らせて筆をあちらこちらと飛ばせていた。羊の群れを守る番犬がぐるぐる駆け回って、列を離れようとする羊を追い込むような様子があった。今になって考えてみるとあれはやはり輪郭線や色彩が逃げよう逃げようとするのを見張っていたのだと思われた。こういうふうにやらなければならないとなるとなかなかたいへんだと思った。
実際輪郭線がわずかに一ミリだけどちらかへずれても顔の格好がまるで変わってしまうのは恐ろしいようであった。ある場所につける一点の絵の具が濃すぎても薄すぎても顔がいびつに見えた。そのような効果は絵に接近して見ていてはかえってわからなくて少し離れて見ると著しく見えた。六尺の筆を使う意味が少しわかりかけたのである。
どうにか顔らしいものができた時にはそれが奇妙にも自分の知っている某○学者によく似ていた。そうとも知らず家内のある者がこの絵を見て「大工か左官のような顔だ」といった。
それから毎日いろいろと直して変化させている間に、いつのまにかまたこの同じ大工の顔がひょっくり復帰して来るのが不思議であった。会いたくないと思ってつとめて避けている人に偶然出くわすような気がしばしばした。ある日思い切って左の頬ほおをうんと切り落としてから後はこの不思議な幽霊に脅かされる事は二度となくなった。
いつまでやってもついにできあがる見込みはなさそうに思われだした。ある日K君にこのごろ得たいろいろの経験を話しているうちに同君が次のような事を注意した。「いったい人間の顔は時々刻々に変化しているのをある瞬間の相だけつかまえる事は第一困難でもあるし、かりにそれを捕えて表現したとしても、それはその人の像と言われるだろうか」というような意味であった。そういうふうに考えてみると、単に早取り写真のようなものならば技巧の長い習練によって仕上げられうるものかもしれないが、ある一人の生きた人間の表現としての肖像は結局できあがるという事はないものだとも思われた。あるいはその点に行くとかえって日本画の似顔とかあるいは漫画のカリカチュアのほうが見込みがありそうに思われた。それほどではなくてもまつ毛一本も見残さずかいた、金属製の顔にエナメルを塗ったような堅い堅い肖像よりは、後期印象派以後の妙な顔のほうが少なくもねらい所だけはほんとうであるまいかと思われてくる。この考えをだんだんに推し広げて行くと自然に立体派や未来派などの主張や理論に落ちて行くのではあるまいか。
仕上がるという事のない自然の対象を捕えて絵を仕上げるという事ができるとすれば、そこには何か手品の種がある。いったい顔ばかりでなく、静物でもなんでも、あまり輪郭をはっきりかくと絵が堅すぎてかえって実感がなくなるようである。たとえばのうぜんの葉を一枚一枚はっきりかいてみると、どうもブリキ細工にペンキを塗ったような感じがする。これは自分の技巧の拙なためかと思うが、しかし存外大家の描いたのでもそんなのがありやすい。これに反してわざと輪郭をくずして描くと生気が出て来て運動や遠近を暗示する。これはたしかに科学的にも割合簡単に説明のできる心理的現象であると思った。同時に普通の意味でのデッサンの誤謬(ごびゅう)や、不器用不細工というようなものが絵画に必要な要素だという議論にやや確かな根拠が見つかりそうな気がする。手品の種はここにかくれていそうである。
セザンヌはやはりこの手品の種を捜した人らしい。しかしベルナールに言わせると彼の理論と目的とが矛盾していたために生涯しょうがい仕上げができなかったというのである。それにしてもセザンヌが同じ「静物」に百回も対したという心持ちがどうも自分にはわかりかねていたが、どうしてもできあがらぬ自分の自画像をかいているうちにふとこんな事を考えた。思うにセザンヌには一つ一つの「りんごの顔」がはっきり見えたに相違ない。自分の知った人の中には雀すずめの顔も見分ける人はあるが、それよりもいっそう鋭いこの画家の目には生きた個々のくだものの生きた顔が逃げて回って困ったのではあるまいか。その結果があの角ばったりんごになったのではあるまいか。
こんなさまざまの事を考えながら、毎日熱心に顔を見つめてはかいていると、自分の顔のみならず、だれでも対している人の顔が一つの立体でなくて画布に表われた絵のように見えて来た。人と対話している時に顔の陰影と光が気になって困った。ある夜顔色の美しい女客の顔を電燈の光でしみじみ見ていると頬ほおや額の明るい所がどうしてもまだかわかぬ生の絵の具をべっとり盛り上げたような気がしてしかたがなかった、そしてその光った所が顔の運動につれていろいろに変わるのを見とれているうちに、相手の話の筋道を取りはずしそうになる事が一度ならずあった。その後に、ある日K君と青山の墓地を散歩しながら、若葉の輝く樹冠の色彩を注意して見ているうちに、この事を思い出して話すと、K君は次のような話をしてくれた。ゴンクールの小説に、ある女優が舞台を退いて某貴族と結婚したが、再びもとの生活が恋しくなるというのがある。その最後の条に、夫が病気で非常な苦悶くもんをするのを見たすぐあとで、しかも夫の眼前で鏡へ向かってその動作の復習をやる場面がある。夫がそれを見てお前は芸術家だ、恋はできないと言って突きとばすのでおしまいになっている。K君はこれを読んだ時にあまりに不自然だと思ったが、自分の今の話を聞くとそんな事もないとは限らないような気がすると言った。このような特殊な場合だけ考えると、実際世間で純粋な芸術が人倫に廃頽的はいたいてき効果を与えるといって攻撃する人たちのいう事も無理でないと思われて来る。しかしそういう不倫な芸術家の与える芸術その物は必ずしも効果の悪いものばかりとは思われない。つまり、こういう芸術家やこれとよく似た科学者らは、極端なイーゴイストであるがために結果においてはかえって多数のために自分を犠牲にする事になる場合もあるだろう。そういう時にいつでも結局いちばん得をするのは、こういう犠牲者の死屍ししにむちうつパリサイあたりの学者と僧侶(そうりょ)たちかもしれない。こんな事を考えているうちに、それなら金もうけに熱中して義理を欠く人はどうかという問題にぶつかって少しむつかしくなって来た。
毎日同じ顔をいじり回しているうちに時々は要領にうまくぶつかる事もあった。なんだか違っているには相違ないが、どう違っているかわからないで困っていたような所が、何かの拍子にうまく直って来る時には妙な心持ちがした。楽器の弦の調子を合わせて行ってぴったりと合ったような、あるいははまりにくい器械のねじがやっとはまった時のような、なんという事なしに肩の凝りがすうっと解けるような気がするものである。
そういうふうにうまく行った所はもう二度といじるのが恐ろしくなる。それをかまわず筆をつける時にはかなりヒロイックな気持ちになる。しかしそれをやるときっと手が堅くなっていじけて、失敗する場合が多い。進歩という事にさえかまわなければ手をつけないでそのままに安んじておくほうがいわゆる処生の方法とも暗合して安全であるかもしれない。
それで自画像第四号もとうとう仕上げずにやめてしまった。第三号は第一号のように意地の悪い顔であったがこの第四号は第二号のように温厚らしくできた。二重人格者の甲乙の性格が交代で現われるような気がした。
今度は横顔でもやってみようと思って鏡を二つ出して真横から輪郭を写してみたら実に意外な顔であった。第一鼻が思っていたよりもずっと高くいかにも憎々しいように突き出ていて、額がそげて顋あごがこけて、おまけに後頭部が飛び出していてなんとも言われない妙な顔であった、どこかロベスピールに似ているような気がした。とにかく正面の自分と横顔の自分を結びつけるのがちょっと困難に思われた。かつて写真屋のアルバムで知らぬ人の顔について同じような経験をした事はあったが、生まれて四十余年来自分の肩の上についている顔についてこんな経験をしようとは思わなかった。
これから思うと刑事巡査が正面の写真によって罪人を物色するような場合には、目前にいる横顔の当人を平気で見のがすプロバビリティもかなりにありそうだと思った。場合によっては抽象的な人相書きによったほうがかえって安全かもしれない。あるいはむしろ漫画家のかいた鳥羽絵(とばえ)がいちばん有効かもしれない。上手(じょうず)なカリカチュアは実物よりも以上に実物の全体を現わしているから。
これと連関して自分が前からいだいている疑問は、人間の顔が往々動物に似たり、反対に動物の顔がある人を思い出させる事である。実際らくだに似た人やペリカンに似た人がある。ふぐ、きす、かまきり、たつの落とし子などに似た人さえある。古いストランド雑誌にいろんな動物の色写真をうまくいろいろの人間に見立てたのがあった。ある外国人は日本の相撲すもうの顔を見ると必ず何かの動物を思い出すと言ったが、その人の顔自身がどうも何かの獣に似ているのであった。レヴィンのかいたトルストイの顔などはどうしても獅子ししの顔である。
そうしてみるとわれわれが人の顔を見る時に頭の中へできる像は決してユークリッド幾何学的のものではないと思われる。ただある、割合に少数な項目の、多数な錯列パーミュテーションによっていろいろの顔の印象ができている。その中に若干「相似」を決定するために主要な項目の組み合わせがあってこれだけが具備すれば残りの排列などはどうでもいいのだろう。この主要の組み合わせを分析するという事はかなりおもしろいしかしむつかしい問題だろうと思ったりした。渾天(こんてん)に散布された星の位置を覚えるのに、星の間を適当に直線で連ねていろいろの星座をこしらえる。それを一度覚えてしまえばいつ見てもそれだけの星がまとまって見えるし、これとだいたいに似た点の排列を見ればそれが実際にはかなりいびつになっていてもすぐにそれと認められる。われわれの顔に対する記憶もこれと似たものではあるまいか。星座の連結法はむしろ任意的だが顔の場合にはそれが必然的ですべての人間に共通であるとすればこれも一つの不思議な問題になる。
いろいろの「学」と名のつく学問、ことに精神的方面に関したもので、事物の真を探究するとは言うものの、よく考えてみると物の本来の面目はやはりわからないで、つまりは一種の人相書きか鳥羽絵(とばえ)をかいている場合も多いように思われるが、そのような不完全な「像」が非常に人間に役に立って今日の文明を築き上げたと思うと妙な気持ちがする。ただ甲乙二人の描いた人相書きがちがう場合にどっちも自分のかいたほうが「正しい」と言って、主張するのはいいとしてもおしまいにはにがにがしいけんかになるのはどんなものだろう。物理学では相対原理の認められた世の中であるのに。
横顔はとにかく中止として今度はスケッチ板へ一気呵成(いっきかせい)に正面像をやってみる事にした。二十日(はつか)間苦しんだあとだから少し気を変えてみたいと思ったのである。今度は似ようが似まいがどうでもいいというくらいの心持ちで放胆にやり始めてただ二日で顔だけはものにしてしまった。ところがかえってこのほうがいちばん顔が生きていてそしていちばん芸術的に見えた。その上これが今までのうちで最もよく似ているという者もあった。なんだかあまりあっけなくて、前の絵にいつまでもかじりついていたのがばかばかしいような気がしたが、実はやはり前の絵で得た経験の効果がこのスケッチに現われたかもしれない。
第一号から最後の五号までならべて見ると、ずいぶんいろいろな顔である。そしていずれも偶然の産物である。この偶然の行列の中から必然をつかまえるのは容易な事ではないと思った。すべてに共通なのは目が二つあるとかいうような抽象的な点ばかりかもしれない。もっとも顔自身の日々の相が偶然のものではあろうが。
毎日変わっている顔の歴史を順々にたぐって行けば赤ん坊の時まで一つの「連続コンチニウム」を作っているが、これを間断なく見守っていない他人に向かって子供の時の顔と今の顔とを切り離して見せてそれが同人だという事を科学的理論的に証明しようとしたらずいぶん困難な事だろう。何十年来一つ家に暮らした親にでも、自分がある夜中に突然入れ換わったものでないという事を「証明」しなければならないとしたら困るだろう。第一自分自身にさえ子供の時と今との連鎖を完全に握っている人はありそうもない。こんな「証明」の必要はめったに起こらないから安心しているだけである。しかしたとえば生まれたばかりで別れて三年後に会った自分の子供を厳密な意味で確認しうる人があるだろうか。しあわせな事には世の中では論理的の証明はわりに要求されないで、オーソリティの証言が代用されそのおかげで物事が渋滞なく進捗しんちょくするのであろう。
自画像をかきながら思うようにかけない苦しまぎれに、ずいぶんいろんな事を考えたものである。それをもう一ぺん復習するようなつもりで書いてみるとずいぶんくだらない事を考えたものだと思う事もあるが、また中にはもう少し深く立ち入って考えてみたいと思う事もないではない。(大正九年九月、中央公論) ]
[東洋城・五十三歳。毎週金曜日、寅彦と会合して連句を作る。浦賀で海上大会。]
[ 塩原両面碑に立ちて 十五句
わが句碑の端とはなるゝ寒さかな
碑の我が句最も冬を知れるかな
我が句碑の冬の句驕れ山容(スガタ)
凩の四方八方来(ク)や句碑我に
碑撮(ウツ)すや却て冬の山相(スガ)タ
あはれむや碑撮す人の指の凍(イテ)
碑の冬や塩の湯道の口をなし
あはれむや句碑のぐるりに枯るゝ葦
句碑の句の冬とはをかし温泉(ユ)に遊び
この凍(イ)てを我が句碑の上と思ふかな(前書「旅宿寒夜」)
あくまでに澄みて鋭(スル)ドや冬の水(前書「冬の塩原」)
門前も古町も鄙や古正月
此の荘のあるじの留守や冬木立
タツツケに羽子(ハネ)つく子等や古正月
山川の音こそものの冬夜かな

「塩原両面碑の松根東洋城(昭和二年七月、両面碑・西面)」)(『東洋城全句集中巻』)
https://yahan.blog.ss-blog.jp/2023-11-17
[【碑文】
「さまみえて土になりゐる落葉哉」表
「すずしさやこの山水に出湯とは」裏 (塩原四季郷より)
http://hotyu.starfree.jp/historicalspots/bungakuhi/bungakuhi.html ]
[寅日子(寅彦)・五十三歳。
1月21日、地震研究所談話会で「本邦火山活動の緯度分布に就て」および「温泉の熱に就て」を発表。2月12日、帝国学士院で“Crustal Disturbance in Kwanto Districts”(with N. Miyabe)および“On the Relation between the Disvergence of Horizontal Displacements of Trigonometrical Points and the Vertical Displacements of the Earth Crust”を発表。
2月17日、航空学談話会で「パラヂウム膜の亀裂に就て」(田中と共著)を発表。2月18日、地震研究所談話会で「三角点移動の意義に就て」を発表。
4月12日、帝国学士院で“Further Studies on Periodic Columnar Vortices Produced by Convection”(with M.Tamano)を発表。4月15日、地震研究所談話会で「山崩れに就て(第二報)」(宮部と共著)を発表。
6月12日、帝国学士院で“Preliminary Experiments on the Modes of Propagation of Surface
Combustion”を発表。6月17日、地震研究所談話会で「土地の垂直運動と地形との関係」(宮部と共著)を発表。
9月15日、正四位に叙せられる。9月16日、地震研究所談話会で「山崩れの調査(第三報)」(宮部と共著)を発表。
10月29日、理化学研究所学術講演会で「火山灰の吸着作用(Ⅱ)」(平田・内ヶ崎直郎と共著)を発表。
12月12日、帝国学士院で“On Luminous Phenomena Accompanying Earthquakes”を発表。12月16日、地震研究所談話会で「地震に伴う光の現象」を発表。
談話「火災研究の基本材料」、『日本消防新聞』、1月。
「二つの正月」、『文芸春秋』、2月。
「LIBER STUDIORUM」、『改造』、3月。
「高浜さんと私」、『現代日本文学全集』、月報、4月。
「地図をたどる」、『大阪朝日新聞』、7月。
「夏 暑さの過去帳(上)(下)」、『東京朝日新聞』、8月。
「映画時代」、『思想』、9月。
「震生湖より」、『渋柿』、10月。
「映画雑感(一)(二)」、『帝国大学新聞』、11〜12月。
「レーリー卿(Lord Rayleigh)」、岩波講座『物理学及び化学』、12月。
「研究者の対立」、『東京朝日新聞』、12月。
談話「大地震と光り物」、『報知新聞』、12月 ]
忙しや金が入る出る歳の暮(十二月二十四日松根豊次郎宛封緘端書の中より)
※ この句は、『寺田寅彦全集 文学篇 第十六巻』に、その全文が収載されている。
[ 十二月二十四日 水 午後零時~四時 神田より牛込区余丁町四一松根豊次郎氏へ(封緘はがき 速達便)
正直へ神の恵みの落しもの (城)(※東洋城)
石も長閑に笑ふ狛犬
花の山うかうか越えし此処は何処
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
それから先日の「女の顔」の中へ左を加えたし
ロゼチの腺病質の女の事の次へ、音楽会見初めの件の前に
「それから又グリューズの「破瓶」の娘の顔も好きらしかつた。ヴォラプチュアスだと評して居た。先生の虞美人草かなんかの中に出て来るヴォラプチュアスな顔のモデルは即ち此れである」
右校正の時御入れ下さい
十二月二十四日
忙しや金が入る出る歳の暮 ]
この二日後の「十二月二十六日付け小宮豊隆宛寺田寅彦書簡」がある。
[十二月二十六日 金 仙台市北二番丁六八小宮豊隆氏へ
(前略)
虚子(※高浜虚子)より大兄(※小宮豊隆)と安倍君(※安倍能成)上京の期聞合せ参り居候、御上京草ゝつかまる事と存候、一夕大にメートルをあげて昔を偲び度と楽しみ居候、御出京の日取決定の上御一報願上候
松根大将(※松根東洋城)小生へも続々厳談、折柄震研の仕事でテンテコ舞の処を督促され、何をかいわんやら分からない程のデタラメを書送り候処、今度は又至急に連句を一巻無理やりに上げろとの事にて電車中にて呻吟、速達で送ると、すぐ電話で附句を申越し、速刻又次の二句をつづけろとの事、当日は理研・震研・文部省・丸善・三越と東奔西走の間にやつと製造途中で封緘葉書を求め速達で発送、それに大将があげ句をつければ落成するのだから、それきり受け取つとたとも何もなくしーんとしてしまつて颱風一過の後の如き有様に有之候、尤も大分奮闘して居るらしいので同情も致居候、しかし少生の如き重宝至極、何時でも即刻に金玉の名文章やダイアモンドルビーの如き句を手の平からもみ出す手品師のやうな軽便なる友人をもつ東洋城も亦仕合せ果報者かと存ぜられうたゝ羨望の感に堪えず候 (後略) ]
[豊隆(蓬里雨)・昭和五年(一九三〇)、四十七歳。二月合著『続芭蕉俳諧研究』出版。]
(追記)「自画像(寺田寅彦)」周辺
.jpg)
「母の像(寺田寅彦画)」 (『寺田寅彦画集(中央公論美術出版)』)
[制作年月=大正一〇・二/種別=油彩/基材=板/大きさ=33.0×24.0㎝]
.jpg)
「つるばら(寺田寅彦画)」(『寺田寅彦画集(中央公論美術出版)』)
[制作年月=大正一〇・二/種別=油彩/基材=板/大きさ=32.8×23.8㎝]
(E5AFBAE794B0E5AF85E5BDA6E794BB).jpg)
「自画像(A)(寺田寅彦画)」(『寺田寅彦画集(中央公論美術出版)』)
[制作年月=大正一三/種別=油彩/基材=カンバスボード/大きさ=32.5×23.5㎝]
[自画像 寺田寅彦
https://www.aozora.gr.jp/cards/000042/files/2438_10299.html
四月の始めに山本鼎(やまもとかなえ)氏著「油絵のスケッチ」という本を読んで急に自分も油絵がやってみたくなった。去年の暮れに病気して以来は、ほとんど毎日朝から晩まで床の中で書物ばかり読んでいたが、だんだん暖かくなって庭の花壇の草花が芽を吹き出して来ると、いつまでも床の中ばかりにもぐっているのが急にいやになった。同時に頭のぐあいも寒い時分とは調子が違って来て、あまり長く読書している根気がなくなった。今までは内側へ内側へと向いていた心の目が急に外のほうへ向くと、そこには冬の眠りからさめて一時に活気づいた自然界が勇み立って自分を迎えてくれるような気がした。ちょうどそこへ山本氏の著書が現われて自分の手をとって引き立てるのであった。
中学時代に少しばかり油絵をかいてみた事はある。図画の先生に頼んで東京の飯田(いいだ)とかいううちから道具や絵の具を取り寄せてもらって、先生から借りたお手本を一生懸命に模写した。カンバスなどは使わず、黄色いボール紙に自分で膠(にかわ)を引いてそれにビチューメンで下図の明暗を塗り分けてかかるというやり方であった。かなりたくさんかいたが実物写生という事はついにやらずにしまった。そして他郷に遊学すると同時にやめてしまって、今日までついぞ絵筆を握る機会はなかった。もと使った絵の具箱やパレットや画架なども、数年前国の家を引き払う時に、もうこんなものはいるまいと言って、自分の知らぬ間に、母がくず屋にやってしまったくらいである。
その後都へ出て洋画の展覧会を見たりする時には、どうかすると中学時代の事を思い出し、同時にあの絵の具の特有な臭気と当時かきながら口癖に鼻声で歌ったある唱歌とを思い出した、そうして再びこの享楽にふけりたいという欲望がかなり強く刺激されるのであった。しかし自分の境遇は到底それだけの時間の余裕と落ち着いた気分を許してくれないので実行の見込みは少なかった。ただ展覧会を見るたびにそういう望みを起こしてみるだけでも自分の単調な生活に多少の新鮮な風を入れるという効果はあった。
中学時代には、油絵といえば、先生のかいたもの以外には石版色刷りの複製品しか見た事はなかった。いつか英国人の宣教師の細君が旧城跡の公園でテントを張って幾日も写生していた事があった。どんなものができているかのぞいてみたくてこわごわ近づくと、十二三ぐらいの金髪の子供がやって来て「アマリ、ソバクルト犬クイツキマース」などと言った。実際そばには見た事もないような大きな犬がちゃんと番をしているのであった。
それから二十何年の間に自分はかなり多くの油絵に目をさらした。数からいえばおそらく莫大(ばくだい)なものであろう。見ているうちに自分の目はだんだんにいろいろに変わって来た。そして芸術としての油絵というものに対する考えもいろいろにうつって行った。ただその間に不断にいだいていた希望はいつか一度は「自分のかいた絵」を見たいという事であった。世界じゅうに名画の数がどれほどあってもそれはかまわない。どんなに拙劣でもいいから、生まれてまだ見た事のない自分の油絵というものに対してみたいというのであった。
このような望みは起こっては消え起こっては消え十数年も続いて来た。それがことしの草木の芽立つと同時に強い力で復活した。そしてその望みを満足させる事が、同時に病余の今の仕事として適当であるという事に気がついた。
それでさっそく絵の具や筆や必要品を取りそろえて小さなスケッチ板へ生まれて始めてのダップレナチュールを試みる事になった。新しいパレットに押し出した絵の具のなまなましい光とにおいは強烈に昔の記憶を呼び起こさせた。長い筆の先に粘い絵の具をこねるときの特殊な触感もさらに強く二十余年前の印象を盛り返して、その当時の自分の室から庭の光景や、ほとんど忘れかかった人々の顔をまのあたりに見るような気がした。
まず手近な盆栽や菓子やコップなどと手当たり次第にかいてみた。始めのうちはうまいのかまずいのかそんな事はまるで問題にならなかった。そういう比較的な言葉に意味があろうはずはなかった。画家の数は幾万人あっても自分は一人しかいないのであった。
思うようにかけないのは事実であった。そのかわり自分の思いがけもないようなものができてくるのもおもしろくない事はなかった。とてもかけそうもないと思ったものが存外どうにか物になったと思う事もあり、わけもないと思ったものがなかなかむつかしかったりした。それよりもおもしろいのは一色の壁や布の面からありとあらゆる色彩を見つけ出したり、静止していると思った草の葉が動物のように動いているのに気がついたりするような事であった。そして絵をかいていない時でもこういう事に対して著しく敏感になって来るのに気がついた。寝ころんで本を読んでいると白いページの上に投じた指の影が、恐ろしく美しい純粋なコバルト色をして、そのかたわらに黄色い補色の隈くまを取っているのを見て驚いてしまってそれきり読書を中止した事もある。またある時花壇の金蓮花(きんれんか)の葉を見ているうちに、曇った空が破れて急に強い日光がさすと、たくさんな丸い葉は見るまにすくすくと向きを変え、間隔と配置を変えて、我れ勝ちに少しでも多く日光をむさぼろうとするように見えた。一つ一つの葉がそれぞれ意志のある動物のように思われてなんだか恐ろしいような気もした。
手近な静物や庭の風景とやっているうちに、かく物の種がだんだんに少なくなって来た。ほんとうは同じ静物でも風景でも排列や光線や見方をちがえればいくらでも材料にならぬ事はないが、素人(しろうと)の初学者の自分としては、少なくもひとわたりはいろいろちがった物がかいてみたかった。いちばんかいてみたいのは野外の風景であるが今の病体ではそれは断念するほかはなかった。それでとうとう自画像でも始めねばならないようになって来た。いったい自分はどういうものか、従来肖像画というものにはあまり興味を感じないし、ことに人の自画像などには一種の原因不明な反感のようなものさえもっているのであるが、それにもかかわらずついに自分の顔でもかいてみる気になってしまった。
それである日鏡の前にすわって、自分の顔をつくづく見てみると、顔色が悪くて頬(ほお)がたるんで目から眉(まゆ)のへんや口もとには名状のできない暗い不愉快な表情がただようているので、かいてみる勇気が一時になくなってしまった。そのうちにまた天気のいい気分のいいおりに小さな鏡を机の前に立てて見たら、その時は鏡の中の顔が晴れ晴れとしていて目もどことなく活気を帯びて、前とは別人のような感じがした。それでさっそくいちばん小さなボール板へ写生を始めた。鉛筆でザット下図をかいてみたがなかなか似そうもなかった、しかしかまわず絵の具を付けているうちにまもなくともかくも人の顔らしいものができた。のみならずやはりいくらかは自分に似ているような気もした。顔の長さが二寸ぐらいで塗りつぶすべき面積が狭いだけに思ったよりは雑作(ぞうさ)なく顔らしいものができた、と思ってちょっと愉快であった。それでさっそく家族に見せて回ると、似ているという者もあり、似ていないというものもあった、無論これはどちらも正しいに相違なかった。
この始めての自画像を描く時に気のついたのは、鏡の中にある顔が自分の顔とは左右を取りちがえた別物であるという事である。これは物理学上からはきわめて明白な事であるが写生をしているうちに始めてその事実がほんとうに体験されるような気がした。衣服の左前なくらいはいいとしても、また髪の毛のなでつけ方や黒子(ほくろ)の位置が逆になっているくらいはどうでもなるとしても、もっと微細な、しかし重要な目の非対称や鼻の曲がりやそれを一々左右顛倒(てんとう)して考えるという事は非常に困難な事である。要するに一面の鏡だけでは永久に自分の顔は見られないという事に気がついたのである。二枚の鏡を使って少し斜めに向いた顔を見る事はできるだろうがそれを実行するのはおっくうであったし、また自分の技量で左右の相違をかき分ける事もできそうになかった。そんな事を考えなくてもただ鏡に映った顔をかけばいいと思ってやっているうちに着物の左衽(ひだりおくみ)のところでまたちょっと迷わされた。自分の科学と芸術とは見たままに描けと命ずる一方で、なんだか絵として見た時に不自然ではないかという気もするし、年取った母がいやがるだろうと思ったので、とうとう右衽(みぎおくみ)にごまかしてしまったが、それでもやっぱり不愉快であった。
この自画像.「No.1」は恐ろしくしわだらけのしかみ面(づら)で上目に正面をにらみつけていて、いかにも性急なかんしゃく持ちの人間らしく見えるが、考えてみると自分にもそういう資質がないとは言われない。
それから二三日たってまた第二号の自画像を前のと同大の板へかいてみた。今度は少し顔を斜めにしてやってみると、前とは反対にたいへん温和な、のっぺりした、若々しい顔ができてしまった。妻や子供らはみんな若すぎると言って笑ったが母だけはこのほうがよく似ていると言った。母親の目に見える自分の影像と、子供らの見た自分の印象とには、事によったら十年以上も年齢の差があるかもしれない。それで思い出したが近ごろ自分の高等小学校時代に教わったきりで会わなかった先生がたの写真を見た時にちょっとそれと気がつかなかった。写真の顔があまり若すぎて子供のような気がしたからである。よくよく見ているとありありと三十年前の記憶が呼び返された。これから考えるとわれわれの頭の中にある他人の顔は自分といっしょに、しかもちゃんときまった年齢の間隔を保存しつつだんだん年をとるのではあるまいか。
同じ自分が同じ自分の顔をかくつもりでやっていると、その時々でこのようにいろいろな顔ができる、これはつまり写生が拙なためには相違ないがともかくもおもしろい事だと思った。No.1にもNo.2にもどこか自分に似たところがあるはずであるが、1と2を並べて比較してみると、どうしても別人のように見える。そうしてみると1と2がそれぞれ自分に似ているのは、顔の相似を決定すべき主要な本質的の点で似ているのでなくて第二義以下の枝葉の点で似ているに過ぎないだろうと思われる。
これについて思い出す不思議な事実がある。ある時電車で子供を一人連れた夫婦の向かい側に座を占めて無心にその二人の顔をながめていたが、もとより夫婦の顔は全くちがった顔で、普通の意味で少しも似たところはなかった。そのうちに子供の顔を注意して見るとその子は非常によく両親のいずれにも似ていた。父親のどこと母親のどことを伝えているかという事は容易にわかりそうもなかったが、とにかく両親のまるでちがった顔が、この子供の顔の中で渾然こんぜんと融合してそれが一つの完全な独立なきわめて自然的な顔を構成しているのを見て非常に驚かされた。それよりも不思議な事は、子供の顔を注視して後に再び両親の顔を見比べると、始め全く違って見えた男女の顔が交互に似ているように思われて来た事である。このような現象を心理学者はどう説明するだろうか。たしかにおもしろい問題にはなるに相違ないと思った。それからまた一方では親子の関係というものの深刻な意味を今さらのように考えたりした。もう一つ、これはK君の話だが、同君の友人の二男が、父親よりも生母よりもかえって、父の先妻、しかもなくなった先妻にそっくりなので、始めて見たK君は、一種名状のできないショックを感じたそうである。K君の認めた相似が全くオブジェクティヴだとすると、現在の科学はこの説明を持てあますだろうと思われる。
いったい二つの顔の似ると似ないを決定すべき要素のようなものはなんであろう。この要素を分析し抽出する科学的の方法はないものだろうか。自分は自画像をかきながらいろんな事を考えてみた。同じ大きさに同じ向きの像を何十枚もかいてみる。そしてそれを一枚一枚写真にとって、そのおのおのを重ね合わせて重ね撮とり写真をこしらえる。もしおのおのの絵が実物とちがう「違い方」が物理学などでいう誤差の方則に従っていろいろに分配せられるとすれば重ね撮りの結果はちょうど「平均」をとる事になってそれが実物の写真と同じになりはしまいか。もしそれが実物と違えばその相違は描き手に固有ないわゆる personal equation を示すか、あるいはその人の自分の顔に対する理想を暴露するかもしれない。それはとにかく何十枚の肖像をだいたい似ている度に応じて二つか三つぐらいの組に分類する。そうしてその一つ一つの写真を本物の写真と重ねてみてよく一致する点としない点とをいくつかの箇条に分かって統計表をこしらえる。こんな方法でやれば「顔の相似」という不思議な現象を系統的に研究する一つの段階にはなりそうである。
自画像は「No.2」でしばらくやめてまた静物などをやっているうちに一日画家のT君が旅行から帰ったと言ってわざわざ自分の絵を見に来てくれた。ありたけの絵をみんな出して見てもらっていろいろの注意を受け、いろいろなおもしろい事を教わってたいへんに啓発されるような気がした。自画像の二枚については、あまり色が白すぎるというのと、もっと細かに見て、色や調子を研究して根気よくかかなければいけないというのであった。なるほどそう言われてみると自分のかいた顔は普通の油絵らしくなくて淡彩の日本画のように白っぽいものである。もっとも鏡が悪いために実際いくぶん顔色が白けて見えたには相違ないが、そう言われて後に鏡と絵と比べてみると画像のほうはたしかに色が薄くて透明に見えて、上簇期じょうぞくきの蚕のような肌はだをしていた。そしていかにもぞんざいで薄っぺらなものに思われて来た。それからT君はいろいろの話の内にトーンというものの大切な事を話した。目を細くしてよく見きわめをつけてから一筆ごとに新しく絵の具を交ぜては置いて行くのだそうである。ある人は六尺もある筆の先へちょっと絵の具をくっつけて、鳥でも刺すようにして一点くっつけてはまたながめて考え込むというのである。この話を聞いているうちになんだか非常に愉快になって来た。そういう仕事をしている画家と、非常にデリケートな物理の実験をやって敏感なねじをいじってはめがねをのぞいている学者と全く兄弟分のような気がしておもしろくなって来た、そしてどういうわけか急におかしくなって笑い出すとT君もいっしょに笑い出してしまった。
それから二三日たってT君の宅へ行って同君の昔かいた自画像を二枚見せてもらった。それは小さな板へかいた習作であったがなるほど濃厚な絵の具をベタベタときたならしいように盛り付けたものであった。しかし自分ののっぺりした絵と比べて見るとこのほうが比較にならぬほどいきいきしていてまっ黒な絵の具の底に熱い血が通かよっていそうな気がした。
もっとも考えてみるとこのくらいの事は今始めて知ったわけではない。この自分の自画像がもし他人の絵であったとしたらおそらく始めからまるで問題にならないで打っちゃってしまうほどつまらないものかもしれない。ただそれが自分のかいたのであるがためにこんなわかりきった事がわからないでいたのをT君の像をながめているうちにやっとの事で明白に実認したに過ぎない。いったい自分は、多くの人々と同様に、自分の理解し得ないものを「つまらない」と名づけたり、自分と型のちがった人を「常識がない」と思ったりするような事がかなりありそうであるが、幸いにあるいは不幸にして、自分の絵を一つの単純な絵として見て黒人くろうとのと比較する時に、自分のほうがいいと思いうるほどの自信がないと見えて、T君の絵と説とにすっかり感心してしまった。そうして頭を新しく入れ換えて第三号の自画像に取りかかる事にした。
T君のすすめに従って今度はカンバスへやることにした。六号という大きさの画布を枠わくに張ったのを買って来た。同時に画架も買って来てこれに載せた。なんだかいよいよ本式になって来たと思うと少し気味の悪いような気もしてすぐには手をつけられなかった。居間のすみの箪笥たんすのわきにある鏡台の前へすわって左から来る光に半面を照らさせ、そして鏡に映っているものは画架でも背後の箪笥でもその上にある本や新聞でも、見えるだけのものはみんなそのままにかいてみようと思ってやり始めた。
今度はなるべく顔を大きくするつもりで下図を始めたのであるが、どういうものか下図をかいているうちに思ったより小さくなってしまった。自分が大きくしようと思っているのに手と鉛筆とがそれを押え押えて顔を縮めて行くようにも思われた。実物に近いほどに書くつもりのがいつのまにか半分足らずぐらいのものになった。実物と思って見ているのが実は鏡の中の虚像で鏡より二倍の距離にあるから視角はかなり小さくなっている。それに画布のほうは手近にあるものだから、たとえ映像と絵と同じ視角にしても寸法は実物の半分以下になるわけだと思われる。それにしても人が鏡を見て自分の顔というものの観念をこしらえているが、左右顛倒(てんとう)の事実は別として顔の大きさというものに対しても正当な観念を得る事はおそらく非常に困難だろうと思われだした。つまりわれわれはほんとうの自分の顔というものは一生知らずに済むのだという気さえした。自分の事は顔さえわからないのだ。だれかが「自分の背中だけは一生触れられない」と言った事を思い出す。
下図をすっかり消してかき直すのもめんどうであったし、またこのくらいの大きさのも一枚あっていいと思ってそのまま進行する事にした。妻と長女とに下図を見せて違った所を捜させるとじきにいろいろな誤りが発見された。他人が見ればそんなにたやすく見つかるような間違いが、かいている自分にはなかなかわからないのであった。
下図はとうとうあまりよく似ないままで絵の具をつけ始めた。かいて行くうちによくなるだろうと思ったが、なかなかそう行かない事はあとでだんだんにわかって来た。
もちろん顔から塗り始めた。始めにだいたいの肉色と影をつけてしまった時には、似てはいないがたいへん感じのいいような顔ができたのでこれは調子がいいと思って多少気乗りがして来た。そしてだんだんに細かく筆を使って似せるほうと色の調子とに気を配り始めるとそろそろむつかしくなる事が予覚されるようになって来た。まず第一に困った事は局部局部を見て忠実に写しているといつのまにか局部相互の位置や権衡が乱れてしまう。右の目の格好を一生懸命にかいてだいたいよくなったと思って少し離れて見るとその目だけが顔とは独立に横に脱線したりつり上がりねじれなどした。どうも右をかいている時と左をかいている時とで顔の傾斜が変わる癖があるらしかった。そのために左右の目は互いに自由行動をとってどうしても一つの顔の中に融和しない、しかたがないからいずれか一方をきめてから他の一方を服従させるほかはないと思ってまず比較的似ているらしい向かって右の目を標準にする事に決めた、そして左をかく時は一生懸命に右との関係を考え考えかいて行った。
コンパスや物差しを持って来て寸法の比例を取ったりしたが、鏡が使ってあるだけにこの仕事は静物などの場合のように簡単でない。なにしろほんとうの顔と鏡の顔と、ほんとうの物差しと鏡の中の物差しとこの四つのもののうちの二つを比較するのだから時々頭の中が錯雑して比較すべき物を間違えたりする。それからもう一つ鏡のぐあいの悪い事は、静物などと同じつもりで、目を細くして握った手のひらの穴からのぞくと、鏡の中の顔もそのとおりまねをするから結局目の近辺をかく時にはこの方法は無効になるのであった。
右の目を標準にしてだんだんに進行して行くうちにまもなく鼻から顔全体の輪郭まで大改造をやらなければならない事がわかって来たのでこれはたいへんだと思った。顔全体がだいぶ傾斜しなければならぬ事になるらしい。それでは困るから結局かんじんの右の目をもう一ぺん打ちこわして、すっかり始めからやり直すほかはないと思うとはりつめた力が一時に抜けて絵筆を投げ出してしまいたくなった。ひとまず中止としてカンバスを室のすみへ立てかけて遠方からながめて見ると顔じゅう妙に引きつりゆがんで、始めに感じのよかった目も恐ろしく険相な意地悪そうな光を放ってにらんでいるので、どうもそのままにしてあすまで置くのは堪えられないような気がした。それで、もうだいぶ肩が凝って苦しくなって来たけれども奮発して直し始めた。
それからほとんど毎朝起きて部屋(へや)の掃除(そうじ)がすむとすぐにこの自画像「No.3」に手を入れる。あまり凝りすぎてもからだにさわるから午前だけにしたいと思ったが、午前中に一段片付けたつもりで昼飯を食いながらながめていると間違った所が目について気になりだす、もう一筆と思ううちにとうとう午後の時間が容赦なくたってしまう。
それでも少しずつは似てくるようであった。時としては描きながら近くで見ると非常によくなって、ほとんどもう手をつける所がないような気がして愉快になる。しかし画架からはずして長押(なげし)の上に立てかけて下から見上げるとまるで見違えるような変な顔になっているのでびっくりする。どうかすると片方の小鼻が途方もなくたれ下がっているのを手近で見る時には少しも気づかなかったりする。
不思議な事にはこのように毎日見つめている絵の中の顔がだんだんに頭の中にしみ込んで来てそれがとにかく一人の生きた人間になって来る。それは自分のようでもあるしまた他人のようでもある。時としては絵の顔のほうがほんとうの自分で鏡の中のがうそのような気がする。特に鏡と画面とから離れて空で考える時には、鏡の顔はいつでも影が薄くて絵の顔のほうが強い強い実在となって頭の中に浮かんで来るのである。これではだめだと思った。絵を見つめる時間をなるべく減じて鏡を見る時を長くしなければいけないと思った。
絵の中にいる人間とかいている自分との間には知らず知らずの間に一種の同情のようなものが生じて来るような気がしだした。画像が口をゆがめて来ると、なんだか自分も口をゆがめなくてはいられなくなるようであった。自分が目を細くしていると画像もいつのまにかそうするように思われた。絵の顔が気持ちのいい日はなんだか愉快であるが、そうでない日は自分もきげんがよくなかった。
調子のごくごくいい日にはいいかげんに交ぜる絵の具の色や調子がおもしろいようにうまくはまって行く。絵の具のほうですっかり合点(がてん)してよろしくやってくれるのを、自分はただそこまで運んでくっつけてやっているだけのような気がする。こんな時にはかなり無雑作むぞうさに勢いよく筆をたたきつけるとおもしろいように目が生きて来たり頬ほおの肉が盛り上がったりする。絵の具と筆が勝手気ままに絵をかいて行くのを自分はあっけに取られて見ているような気がするのである。こんな時には愉快に興奮する。庭を見ても家内の人々の顔を見ても愉快に見え、そうして不思議に腹がよくへって来る。
これに反してぐあいの悪い日は絵の具も筆も、申し合わせて反逆を企て自分を悩ますように見える。色が濃すぎたと思って直すときっと薄すぎる。直しているうちに輪郭もくずれて来るし、一筆ごとに顔がだんだん無惨に情けなく打ちこわされて行く。その時の心持ちはずいぶんいやなものである。早く中止すればいいと思わない事はないが、そういう時に限って未練が出てやめるに忍びない。ちょうど来客でもあってやむを得ず中止する時には、困ったという感じと、ちょうどいい時に来てくれたという考えとがいっしょになる。客が帰るとできそこなった絵をすぐに見ないではいられない。
あまり自分が熱中しているものだから、家内のものは戯れに「この絵は魂がはいっているから夜中に抜け出すかもしれない」などと言って笑っていた。ところがある晩床の中にはいって鴨居(かもい)にかけた自画像をながめていると、絵の顔が思いがけもなくまたたきをするような気がした。これはおもしろいと思って見つめるとなんともない。しかし目をほかへ転じようとする瞬間にまたすばやくまたたくように見えた。これはたぶん有りがちな幻覚かもしれない。プーシキンの短編にもカルタのスペードの女王がまたたきをする話があるが、とにかくわれわれの神経が特殊な状態に緊張されると、こんな錯覚が生じるものと見える。それよりも不思議な錯覚は、夜床の中で目をねむって闇やみの中を見つめるようにすると、そこに絵の顔が見えて来る事である。始めて気のついた時はハルシネーションのようにはっきり見えたが、その後はただぼんやり、しかしそれが画像の顔だという事がわかるくらいに現われたり消えたりした。生理光学でよく研究されている残像ナハビルドという現象はあるが、それは通例実物を見つめた後きわめて少時間だけにとどまるし、また通例陽像ポジチーフと陰像ネガチーフとが交互に起こるものである。このように長時間の後に残存してしかも陽像のみ現われるというのはまだ読んだ事も聞いた事もなかった。おそらくこれは生理的ではなくて、病理的に神経の異常から起こるハルシネーションの類だろうが、それにしても妙なものである。人殺しをしたものが長い年月の後に熱病でもわずらった時に殺した時の犠牲者の顔をありあり見るというが、それはおそらく自分の見た幻覚と類した程度のものが見えるのではあるまいかと思った。
もう一つ不思議な錯覚のようなものがあった。ある日例のように少しずつ目をいじり口元を直ししているうちに、かいている顔が不意に亡父の顔のように見えて来た。ちょうど絵の中から思いがけもなく父の顔がのぞいているような気がして愕然がくぜんとして驚いた。しかし考えてみるとこれはあえて不思議な事はないらしい。自分はかなりに父によく似ていると言われている、自分はそうとは思わないがどこかによく似た点があるに相違ない。自分の顔のどこかを少しばかりどうか修正すれば父の顔に近よりやすい傾向があるのだろう。それで毎日いろいろに直したり変えたりしているうちには偶然その「どこか」にうまくぶつかって、主要な鍵かぎに触れると同時に父の顔が一時に出現するのであろう。
それから考えてみるに自分が毎日筆のさきでいろいろさまざまの顔を出現させているうちには自分の見た事のない祖先のたれやそれの顔が時々そこからのぞいているのではないかという気がしだした。実際時々妙に見たような顔だという気のする事さえある。
人間の具体的な個々の記憶や経験はそのままに遺伝するものではないだろうが、それらを煎せんじつめた機微なある物が遺伝しているので、そのためにこのような心持ちを起こさせるのではあるまいか。漱石先生の「趣味の遺伝」はまさにこういう点に触れたもののようにも思われる。ラフカディオ・ハーンの書いたものの中にもこのような考えが論じてあった。われわれの祖先を千年前にさかのぼると、今の自分というのはその昔の二千万人の血を受け継いでいる勘定だそうである。そうしてみると自分が毎日こしらえているいろいろの顔は、この二千万人のだれかの顔に相当するかもしれない。こんな事を考えておかしくも思ったが、同時に「自分」というものの成り立ちをこういう立場から、もう一度よく考えてみなければならないと思った。なんだか独立な自分というものは微塵みじんに崩壊ほうかいしてしまって、ただ無数の過去の精霊が五体の細胞と血球の中にうごめいているという事になりそうであった。
この第三号の自画像はまずどうにか、こうにか仕上げてしまった。ほんとうの意味ではいつまでかかっても「仕上がる」見込みのない事がわかって来たから、ここらでまず一段落ついた事にしてしばらく放置してみる事にした。バックに緑色の布のかかった箪笥たんすがあって、その上に書物や新聞の雑然と置いてあるのがいかにもうるさくて絵全体を俗悪にしてしまうから、あとからすっかり塗りつぶしてそのかわりに暗緑色の幕をたれたようなぐあいに直してみた。そうしたら顔が急に引き立って浮き上がって来た。のみならずそれまでは雑誌の口絵にでもありそうな感じのあった絵が、この改造のためにいくらか落ちついた古典的といったような趣を生じた。そして色の対照の効果で顔の色の赤みが強められるのであった。しかしまた同時に着物がやはり赤っぽく見えだして気に入らなくなったが、もうそれを直すだけの根気がなくなってそのままにしてしまった。
すぐに第四号の自画像を同大の画布にやり始める事にした。今度はずっと顔を大きくしてそして前よりも細かく調子を分析してやってみようと思った。ところが下図をかき始めにはかなり大きくかいたのが、目や鼻を直し直ししているうちに知らず知らずだんだんに顔が縮小して行くのが実に不思議であった。だいたいできたころに寸法をとってみるとやっと実物の四分の三ぐらいのものになっている事がわかった。それをもう一度すっかり消してやり直す勇気がなかったから今度もまたそのままでやり続けた。
最初の日は影と日向ひなたとを思い切って強く区別してだいたいの見当をつけてみた。その時にできた顔は不思議に前の第三号の顔に似ていた。何かしら自分の頭の奥にこびりついた誤謬(ごびゅう)が強い力で存在を主張していると見える。
この絵はとうとう二十日(はつか)余りいじり回したが、結局やはり物にならないで中止してしまわねばならなかった。顔の面積が大きくなっただけに困難は前よりもいっそう大きかった。局部にとらわれて全体の権衡を見失う事もいよいよ多かった。セザンヌが「わかりますか、ヴォラール君。輪郭線が見る人から逃げる」と言ったほんとうの意味はよくはわからぬが、全くそういったような気のする事がしばしばあった。右の頬ほおをつかまえたと思う間に左の頬はずるずる逃げ出した。ずっと前にいつかある画家が肖像をかいているのを見た事がある。その時に画家の挙動を注意していると素人しろうとの自分には了解のできないような事がいろいろあった、たとえば肖像の顋あごの先端をそろそろ塗っていると思うとまるで電光のように不意に筆が瞼まぶたに飛んで行ったりした。油断もすきもならないといったふうに目を光らせて筆をあちらこちらと飛ばせていた。羊の群れを守る番犬がぐるぐる駆け回って、列を離れようとする羊を追い込むような様子があった。今になって考えてみるとあれはやはり輪郭線や色彩が逃げよう逃げようとするのを見張っていたのだと思われた。こういうふうにやらなければならないとなるとなかなかたいへんだと思った。
実際輪郭線がわずかに一ミリだけどちらかへずれても顔の格好がまるで変わってしまうのは恐ろしいようであった。ある場所につける一点の絵の具が濃すぎても薄すぎても顔がいびつに見えた。そのような効果は絵に接近して見ていてはかえってわからなくて少し離れて見ると著しく見えた。六尺の筆を使う意味が少しわかりかけたのである。
どうにか顔らしいものができた時にはそれが奇妙にも自分の知っている某○学者によく似ていた。そうとも知らず家内のある者がこの絵を見て「大工か左官のような顔だ」といった。
それから毎日いろいろと直して変化させている間に、いつのまにかまたこの同じ大工の顔がひょっくり復帰して来るのが不思議であった。会いたくないと思ってつとめて避けている人に偶然出くわすような気がしばしばした。ある日思い切って左の頬ほおをうんと切り落としてから後はこの不思議な幽霊に脅かされる事は二度となくなった。
いつまでやってもついにできあがる見込みはなさそうに思われだした。ある日K君にこのごろ得たいろいろの経験を話しているうちに同君が次のような事を注意した。「いったい人間の顔は時々刻々に変化しているのをある瞬間の相だけつかまえる事は第一困難でもあるし、かりにそれを捕えて表現したとしても、それはその人の像と言われるだろうか」というような意味であった。そういうふうに考えてみると、単に早取り写真のようなものならば技巧の長い習練によって仕上げられうるものかもしれないが、ある一人の生きた人間の表現としての肖像は結局できあがるという事はないものだとも思われた。あるいはその点に行くとかえって日本画の似顔とかあるいは漫画のカリカチュアのほうが見込みがありそうに思われた。それほどではなくてもまつ毛一本も見残さずかいた、金属製の顔にエナメルを塗ったような堅い堅い肖像よりは、後期印象派以後の妙な顔のほうが少なくもねらい所だけはほんとうであるまいかと思われてくる。この考えをだんだんに推し広げて行くと自然に立体派や未来派などの主張や理論に落ちて行くのではあるまいか。
仕上がるという事のない自然の対象を捕えて絵を仕上げるという事ができるとすれば、そこには何か手品の種がある。いったい顔ばかりでなく、静物でもなんでも、あまり輪郭をはっきりかくと絵が堅すぎてかえって実感がなくなるようである。たとえばのうぜんの葉を一枚一枚はっきりかいてみると、どうもブリキ細工にペンキを塗ったような感じがする。これは自分の技巧の拙なためかと思うが、しかし存外大家の描いたのでもそんなのがありやすい。これに反してわざと輪郭をくずして描くと生気が出て来て運動や遠近を暗示する。これはたしかに科学的にも割合簡単に説明のできる心理的現象であると思った。同時に普通の意味でのデッサンの誤謬(ごびゅう)や、不器用不細工というようなものが絵画に必要な要素だという議論にやや確かな根拠が見つかりそうな気がする。手品の種はここにかくれていそうである。
セザンヌはやはりこの手品の種を捜した人らしい。しかしベルナールに言わせると彼の理論と目的とが矛盾していたために生涯しょうがい仕上げができなかったというのである。それにしてもセザンヌが同じ「静物」に百回も対したという心持ちがどうも自分にはわかりかねていたが、どうしてもできあがらぬ自分の自画像をかいているうちにふとこんな事を考えた。思うにセザンヌには一つ一つの「りんごの顔」がはっきり見えたに相違ない。自分の知った人の中には雀すずめの顔も見分ける人はあるが、それよりもいっそう鋭いこの画家の目には生きた個々のくだものの生きた顔が逃げて回って困ったのではあるまいか。その結果があの角ばったりんごになったのではあるまいか。
こんなさまざまの事を考えながら、毎日熱心に顔を見つめてはかいていると、自分の顔のみならず、だれでも対している人の顔が一つの立体でなくて画布に表われた絵のように見えて来た。人と対話している時に顔の陰影と光が気になって困った。ある夜顔色の美しい女客の顔を電燈の光でしみじみ見ていると頬ほおや額の明るい所がどうしてもまだかわかぬ生の絵の具をべっとり盛り上げたような気がしてしかたがなかった、そしてその光った所が顔の運動につれていろいろに変わるのを見とれているうちに、相手の話の筋道を取りはずしそうになる事が一度ならずあった。その後に、ある日K君と青山の墓地を散歩しながら、若葉の輝く樹冠の色彩を注意して見ているうちに、この事を思い出して話すと、K君は次のような話をしてくれた。ゴンクールの小説に、ある女優が舞台を退いて某貴族と結婚したが、再びもとの生活が恋しくなるというのがある。その最後の条に、夫が病気で非常な苦悶くもんをするのを見たすぐあとで、しかも夫の眼前で鏡へ向かってその動作の復習をやる場面がある。夫がそれを見てお前は芸術家だ、恋はできないと言って突きとばすのでおしまいになっている。K君はこれを読んだ時にあまりに不自然だと思ったが、自分の今の話を聞くとそんな事もないとは限らないような気がすると言った。このような特殊な場合だけ考えると、実際世間で純粋な芸術が人倫に廃頽的はいたいてき効果を与えるといって攻撃する人たちのいう事も無理でないと思われて来る。しかしそういう不倫な芸術家の与える芸術その物は必ずしも効果の悪いものばかりとは思われない。つまり、こういう芸術家やこれとよく似た科学者らは、極端なイーゴイストであるがために結果においてはかえって多数のために自分を犠牲にする事になる場合もあるだろう。そういう時にいつでも結局いちばん得をするのは、こういう犠牲者の死屍ししにむちうつパリサイあたりの学者と僧侶(そうりょ)たちかもしれない。こんな事を考えているうちに、それなら金もうけに熱中して義理を欠く人はどうかという問題にぶつかって少しむつかしくなって来た。
毎日同じ顔をいじり回しているうちに時々は要領にうまくぶつかる事もあった。なんだか違っているには相違ないが、どう違っているかわからないで困っていたような所が、何かの拍子にうまく直って来る時には妙な心持ちがした。楽器の弦の調子を合わせて行ってぴったりと合ったような、あるいははまりにくい器械のねじがやっとはまった時のような、なんという事なしに肩の凝りがすうっと解けるような気がするものである。
そういうふうにうまく行った所はもう二度といじるのが恐ろしくなる。それをかまわず筆をつける時にはかなりヒロイックな気持ちになる。しかしそれをやるときっと手が堅くなっていじけて、失敗する場合が多い。進歩という事にさえかまわなければ手をつけないでそのままに安んじておくほうがいわゆる処生の方法とも暗合して安全であるかもしれない。
それで自画像第四号もとうとう仕上げずにやめてしまった。第三号は第一号のように意地の悪い顔であったがこの第四号は第二号のように温厚らしくできた。二重人格者の甲乙の性格が交代で現われるような気がした。
今度は横顔でもやってみようと思って鏡を二つ出して真横から輪郭を写してみたら実に意外な顔であった。第一鼻が思っていたよりもずっと高くいかにも憎々しいように突き出ていて、額がそげて顋あごがこけて、おまけに後頭部が飛び出していてなんとも言われない妙な顔であった、どこかロベスピールに似ているような気がした。とにかく正面の自分と横顔の自分を結びつけるのがちょっと困難に思われた。かつて写真屋のアルバムで知らぬ人の顔について同じような経験をした事はあったが、生まれて四十余年来自分の肩の上についている顔についてこんな経験をしようとは思わなかった。
これから思うと刑事巡査が正面の写真によって罪人を物色するような場合には、目前にいる横顔の当人を平気で見のがすプロバビリティもかなりにありそうだと思った。場合によっては抽象的な人相書きによったほうがかえって安全かもしれない。あるいはむしろ漫画家のかいた鳥羽絵(とばえ)がいちばん有効かもしれない。上手(じょうず)なカリカチュアは実物よりも以上に実物の全体を現わしているから。
これと連関して自分が前からいだいている疑問は、人間の顔が往々動物に似たり、反対に動物の顔がある人を思い出させる事である。実際らくだに似た人やペリカンに似た人がある。ふぐ、きす、かまきり、たつの落とし子などに似た人さえある。古いストランド雑誌にいろんな動物の色写真をうまくいろいろの人間に見立てたのがあった。ある外国人は日本の相撲すもうの顔を見ると必ず何かの動物を思い出すと言ったが、その人の顔自身がどうも何かの獣に似ているのであった。レヴィンのかいたトルストイの顔などはどうしても獅子ししの顔である。
そうしてみるとわれわれが人の顔を見る時に頭の中へできる像は決してユークリッド幾何学的のものではないと思われる。ただある、割合に少数な項目の、多数な錯列パーミュテーションによっていろいろの顔の印象ができている。その中に若干「相似」を決定するために主要な項目の組み合わせがあってこれだけが具備すれば残りの排列などはどうでもいいのだろう。この主要の組み合わせを分析するという事はかなりおもしろいしかしむつかしい問題だろうと思ったりした。渾天(こんてん)に散布された星の位置を覚えるのに、星の間を適当に直線で連ねていろいろの星座をこしらえる。それを一度覚えてしまえばいつ見てもそれだけの星がまとまって見えるし、これとだいたいに似た点の排列を見ればそれが実際にはかなりいびつになっていてもすぐにそれと認められる。われわれの顔に対する記憶もこれと似たものではあるまいか。星座の連結法はむしろ任意的だが顔の場合にはそれが必然的ですべての人間に共通であるとすればこれも一つの不思議な問題になる。
いろいろの「学」と名のつく学問、ことに精神的方面に関したもので、事物の真を探究するとは言うものの、よく考えてみると物の本来の面目はやはりわからないで、つまりは一種の人相書きか鳥羽絵(とばえ)をかいている場合も多いように思われるが、そのような不完全な「像」が非常に人間に役に立って今日の文明を築き上げたと思うと妙な気持ちがする。ただ甲乙二人の描いた人相書きがちがう場合にどっちも自分のかいたほうが「正しい」と言って、主張するのはいいとしてもおしまいにはにがにがしいけんかになるのはどんなものだろう。物理学では相対原理の認められた世の中であるのに。
横顔はとにかく中止として今度はスケッチ板へ一気呵成(いっきかせい)に正面像をやってみる事にした。二十日(はつか)間苦しんだあとだから少し気を変えてみたいと思ったのである。今度は似ようが似まいがどうでもいいというくらいの心持ちで放胆にやり始めてただ二日で顔だけはものにしてしまった。ところがかえってこのほうがいちばん顔が生きていてそしていちばん芸術的に見えた。その上これが今までのうちで最もよく似ているという者もあった。なんだかあまりあっけなくて、前の絵にいつまでもかじりついていたのがばかばかしいような気がしたが、実はやはり前の絵で得た経験の効果がこのスケッチに現われたかもしれない。
第一号から最後の五号までならべて見ると、ずいぶんいろいろな顔である。そしていずれも偶然の産物である。この偶然の行列の中から必然をつかまえるのは容易な事ではないと思った。すべてに共通なのは目が二つあるとかいうような抽象的な点ばかりかもしれない。もっとも顔自身の日々の相が偶然のものではあろうが。
毎日変わっている顔の歴史を順々にたぐって行けば赤ん坊の時まで一つの「連続コンチニウム」を作っているが、これを間断なく見守っていない他人に向かって子供の時の顔と今の顔とを切り離して見せてそれが同人だという事を科学的理論的に証明しようとしたらずいぶん困難な事だろう。何十年来一つ家に暮らした親にでも、自分がある夜中に突然入れ換わったものでないという事を「証明」しなければならないとしたら困るだろう。第一自分自身にさえ子供の時と今との連鎖を完全に握っている人はありそうもない。こんな「証明」の必要はめったに起こらないから安心しているだけである。しかしたとえば生まれたばかりで別れて三年後に会った自分の子供を厳密な意味で確認しうる人があるだろうか。しあわせな事には世の中では論理的の証明はわりに要求されないで、オーソリティの証言が代用されそのおかげで物事が渋滞なく進捗しんちょくするのであろう。
自画像をかきながら思うようにかけない苦しまぎれに、ずいぶんいろんな事を考えたものである。それをもう一ぺん復習するようなつもりで書いてみるとずいぶんくだらない事を考えたものだと思う事もあるが、また中にはもう少し深く立ち入って考えてみたいと思う事もないではない。(大正九年九月、中央公論) ]
「東洋城・寅彦、そして、豊隆」(漱石没後~寅彦没まで)俳句・連句管見(その十三) [東洋城・寅日子(寅彦)・蓬里雨(豊隆)]
その十三「昭和四年(一九二九)」
[東洋城・五十二歳。松山及び宇和島にて俳諧道場、東京にて屋外早天道場、出羽荘内に訪ふ。改造社版『現代日本文学全集』に作品を寄す。]
[ 出羽荘内を訪ふ 十四句
葭切(ヨシキリ)や荘内小田のこゝを鳴く(鶴岡駅から俥にて三里余、車上口占)
月山の雪や車上の青嵐
田植女や真白き足を戻り来る
なつかしき出羽荘内の田植かな
葭切に備前守(ビゼンノカミ)の入部かな(「記」には、我祖先光広、松根の城へ移り、名字を改めて、松根備前守と申しけるなりと)
鮎川や鮎とらなくに里閑(シズ)か(途、一大急流を超ゆ、赤川といふ)
田植人黒川能の事聞かん(松根邑は今、黒川村の一字をなせり)
語り出す元和その頃の事や窓涼し(旧事に明るき一老を求め得て、語り伝へるところを聴く)
夏川の流(ナガレ)の急に見入りけり(備前守の城趾、今は河中となり了し、僅にその一部を残す)
角櫓(スミヤグラ)こゝにありしと若葉かな
濠 (ホリ・シロ) 跡といふでふ葭の茂りかな
青嵐三百年の無沙汰かな(中祖伊予に移りて二百五十年、この旧郷を訪ふものなし)
故郷(フルサト)の故郷淋し閑古鳥(帰路車上。郭公を聞く)
郭公(カッコウ)のあちらこちらはなかりけり ]
(再掲)
https://yahan.blog.ss-blog.jp/2023-11-10
http://sp.mogamiyoshiaki.jp/?p=log&l=143960

[(松根備前守光広/まつねびぜんのかみあきひろ)~俳人・松根東洋城の先祖~
義光の弟である義保の子。義保は長瀞城主。兄の片腕となって出羽南部の平定に尽力したが、天正19年(1591)に戦死。ときに光広は3歳の幼児だった。義光がこれを哀れんで、息子同然にいつくしみ育てたと、宇和島市に残る古記録は伝えている。
光広は成人の後は山形市漆山に居住したこともあったが、西村山の名門白岩家の名跡を継いで「白岩備前守」を名乗る。
慶長5年(1600年)の関が原合戦、長谷堂合戦のときは12、3歳だったから、まず戦陣の経験はなかっただろうと思われる。元和2年(1616)、庄内櫛引郷に居城松根城を築いて松根姓を名乗る。一1万2千石、一書に1万3千石とある。
義光に育てられたことに対する報恩の気持ちからか、最上家を思う心が人一倍厚い人物だったようだ。
熊野夫須美神社に、那智権現別当あて、年次無記8月20日付、光広の書状が一通ある。
「最上出羽守義光が病につき、神馬一疋ならびに鳥目(銭)百疋を奉納いたします。御神前において御祈念くださるようお頼みします」という内容である。
「白岩備前守光広」の署名からみて、松根移転以前であることは明らか。義光の病が重くなった慶長18年(1613)のものと推定される。出羽からははるかに遠い紀州那智に使者を遣わして、病気平癒の祈りをささげたのである。あるいは、光広はそのころ上京中だったかもしれない。
義光が亡くなり、跡を継いだ駿河守家親も3年後の元和3年ににわかに亡くなり、その後を12歳の少年、源五郎家信が継ぐ。とかく問題行動を起こしがちな幼い主君に、家臣たちは動揺する。
家を守りたてるべき重臣たちのなかには、義光の四男山野辺光茂こそ山形の主にふさわしいとして、鮭延越前、楯岡甲斐らの一派が公然と動きはじめる。
かくてはならじ、お家のためになんとかせねばと、光広は「山野辺一派が策謀をめぐらし当主家親を亡きものにした」と幕府に直訴した。幕府でも一大事とばかり徹底的に究明したが、事実無根と判明。偽りの申し立てをした不届きの所業として、光広は九州柳川の立花家にあずけられてしまう。彼はここ柳川でおよそ五十年を過ごす。藩主立花宗茂との親交を保ちつつ、寛文12年(1672)84歳の生涯を終える。
その子孫が四国宇和島の伊達家につかえ、家老職の家柄を伝えて維新を迎えた。
高名な俳人松根東洋城(本名豊次郎1878~1964)は、この家の9代目にあたる。宮内省式部官などを勤めながら夏目漱石の門下として俳壇で活躍、のち芸術院会員となった。
昭和4年6月、父祖の地である庄内の松根から白岩をおとずれた東洋城は、昔をしのんで次のような句を残した。
故里の故里淋し閑古鳥
青嵐三百年の無沙汰かな
出羽の最上から九州柳川へ、そして更に四国の宇和島へ。先祖のたどった長い長い3百年の道程だった。宇和島市立伊達博物館の庭には、「我が祖先(おや)は奥の最上や天の川」の句碑がある。
最上家の改易で会津・蒲生氏により接収破却された松根城の跡には、最上院がある。光広の妻が晩年に住んだという松根庵には、彼女の墓碑が寂しくたっている。(片桐繁雄稿)]
(「最上義光歴史館」) ]
[寅日子(寅彦)・五十二歳。
3月12日、帝国学士院で“Ignition of Combustible Gases with Three-Part Spark”(with K. Yumoto and R. Yamamoto)を発表。3月19日、地震研究所で「砂層の崩壊に関する実験」(宮部と共著)を発表。
4月1日、水産講習所の嘱託を解かれ、新たに出来た水産試験場において物理学および海洋学に関する調査を嘱託される。4月16日、地震研究所談話会で「火山の形(第二報)」を発表。
5月12日、帝国学士院で“On the Effects of the Vapours of Halogen Compounds upon the Form and Structure of Long Sparks”(with U. Nakaya and R. Yamamoto)を発表。6月12日、“On the Form of Volcanos”を発表。
6月17日、航空学談話会で「金属薄膜に関する二三の実験」(田中信と共著)を発表。6月18日、地震研究所談話会で「丹後震災地付近に於ける地殻の変動」(宮部と共著)を発表。
7月3日、理化学研究所で脳貧血を起す。
10月12日、帝国学士院で“Deformation of the Earth Crust and Topographical Features”(with N. Miyabe)を発表。10月15日、地震研究所談話会で「桜島の地形変化」(宮部と共著)および「石油の生成と火山作用」を発表。
11月19日、理化学研究所学術講演会で「火山灰の接触作用」(平田森三と共著)を発表。
12月17日、地震研究所談話会で「関東地方に於ける地殻変動」(宮部と共著)を発表。この頃からしきりに映画を見るようになった。
「年賀状」、『東京朝日新聞』、1月。
「化物の進化」、『改造』、1月。
『万華鏡』、鉄塔書院、4月。
「数学と語学」、『帝国大学新聞』、4月。
「藤原博士の『雲』」、『新愛知』、6月。
「験潮旅行断片」、『大阪朝日新聞』、7月。
「デパートの夏の午後」、『東京朝日新聞』、8月。
「さまよへるユダヤ人の手記より」、『思想』、9月。
「野球時代」、『帝国大学新聞』、11月。 ]
荒海やこゝに静かな草の庵(七月二十八日)
※ この句については、『寺田寅彦全集 文学篇 第十六巻』に、その全文が収載されている。
[ 七月二十八日 千葉県安房郡千倉町より牛込区余丁町四一松根豊次郎氏へ(絵葉書)
子供を送りて昨日参り一泊致候
涼しいといふことは暑いといふことの一つの相に過ぎず
荒海やこゝに静かな草の庵
七月二十八日 ]
この葉書の前に、次のような、三吟(東洋城・寅日子・蓬里雨)」の文音連句(書簡による連句の付け合い)のものがある
[ 五月二十三日 京橋区銀座不二家より牛込区余丁町四一松根豊次郎氏へ(はがき、小宮豊隆との寄せ書=小宮氏の文面省略)
今夜不二屋で左記
(ギンザフジヤ)
クリームの溶けあし見るや五月雨 豊(※蓬里雨)
苺の色を奪ふ口紅 寅(※寅日子)
あとあとよろしく
五月二十三日 ](※仙台の豊隆が上京して、銀座の不二屋で、寅彦と、やりかけの連句の付け合いを作り、それを東洋城に回送したものであろう。)
[豊隆(蓬里雨)・昭和四年(一九二九)、四十六歳。三月合著『芭蕉俳諧研究』出版。]

みやこ町歴史民俗博物館/WEB博物館「みやこ町遺産」
https://adeac.jp/miyako-hf-mus/catalog-list/200020
上記の右端の「速達便」(大正七年十一月五日付け)は、『寺田寅彦全集 文学篇 第十六巻』に収載されている。
[十一月五日 火 午前八時~九時 本郷区駒込曙町一三より赤坂区青山南町六ノ一〇八小宮豊隆氏へ (はがき 速達便)
御端書難有う
小生も木曜の方が都合が宜しう御坐います
しかし水曜でも都合のつかぬ事はありませんが少し遅くなります、どうぞよろしく
十一月五日 ]
※ 当時の小宮豊隆は、「漱石全集」の編纂に全力を投入していて、その資料収集に関する寅彦との書簡のやり取りが多い。そして、「木曜」は、「木曜会」(漱石生前の漱石門の面木―の集まり、漱石没後は命日の「九日会」)の、豊隆が当番の時に、寅彦は参加する場合が多かったようである。東洋城は、「渋柿」の編集に追われて「九日会」には、顔を出さなかったように、当時の書翰から窺える。
.jpg)
「東大構内(寺田寅彦画)」(『寺田寅彦画集(中央公論美術出版)』)
[制作年月=大正八・九/種別=墨に淡彩/基材=和紙/大きさ=25.0×15.0㎝]
20(E5AFBAE794B0E5AF85E5BDA6E794BB).jpg)
「姉妹(A) (寺田寅彦画)」(『寺田寅彦画集(中央公論美術出版)』)
[制作年月=大正八・九/種別=墨に淡彩/基材=和紙/大きさ=34.0×23.3㎝]
※ 「大正七年一月十四日付け小宮豊隆宛寺田寅彦書翰」に、「小生は近頃少し気が狂つて徘(原・ママ=俳)句を作つて見たり畫いて見たりして居ます しかし一向物にならないので余り永くは続くまいかと思居候 今日は青楓(※津田青楓)君と野上(※野上豊一郎)君とが来て宅の掛物を見て貰ひました」などとあり、主として、東洋城からの依頼の「渋柿」に搭載する「俳句」や、津田青楓を師として、絵画制作などに没頭するようなことが、しばしば書翰に見られてくる。しかし、この当時は、文音による「俳諧」(連句)関係の書簡は見受けられない。
(参考) 「三四郎」の遺族が漱石の書簡寄贈 福岡・みやこ町に(「日本経済新聞社」)
[夏目漱石の弟子で、小説「三四郎」のモデルとなったドイツ文学者、小宮豊隆の遺族が、漱石から受け取った手紙や写真など計477点を小宮の出身地の福岡県みやこ町に寄贈した。「吾輩は猫である」の猫の死を伝える「死亡通知」など貴重な内容。みやこ町が13日までに明らかにした。
小宮は1905年に東京帝国大に入学。身元保証人になった漱石に弟子入りして交流を深め、小説の校正も手伝った。
みやこ町によると、漱石の手紙は122点。「猫の死亡通知」は1908年9月14日付で、死んだ状況や埋葬の様子を伝え「主人(漱石)は三四郎執筆中で忙しいので、会葬には及びません」とユーモアあふれる。
幼くして父親を失った小宮は、漱石を父親のように慕っていた。1906年12月22日付の手紙で漱石は「僕をお父さんにするのはいいが、大きな息子がいると思うと落ち着いて騒げない」とつづっている。
ほかに漱石の漢文紀行「木屑録(ぼくせつろく)」や、千円札の肖像になった写真、同じく弟子だった物理学者、寺田寅彦の手紙226点もある。いずれも東京都杉並区在住で三女の里子さんが「故郷で生かしてほしい」と寄贈した。
町歴史民俗博物館の川本英紀学芸員は「小説からは見えない師弟関係が伝わってくる」と話している。同博物館で、手紙など約10点を14~26日に展示する。〔共同〕 ]
[東洋城・五十二歳。松山及び宇和島にて俳諧道場、東京にて屋外早天道場、出羽荘内に訪ふ。改造社版『現代日本文学全集』に作品を寄す。]
[ 出羽荘内を訪ふ 十四句
葭切(ヨシキリ)や荘内小田のこゝを鳴く(鶴岡駅から俥にて三里余、車上口占)
月山の雪や車上の青嵐
田植女や真白き足を戻り来る
なつかしき出羽荘内の田植かな
葭切に備前守(ビゼンノカミ)の入部かな(「記」には、我祖先光広、松根の城へ移り、名字を改めて、松根備前守と申しけるなりと)
鮎川や鮎とらなくに里閑(シズ)か(途、一大急流を超ゆ、赤川といふ)
田植人黒川能の事聞かん(松根邑は今、黒川村の一字をなせり)
語り出す元和その頃の事や窓涼し(旧事に明るき一老を求め得て、語り伝へるところを聴く)
夏川の流(ナガレ)の急に見入りけり(備前守の城趾、今は河中となり了し、僅にその一部を残す)
角櫓(スミヤグラ)こゝにありしと若葉かな
濠 (ホリ・シロ) 跡といふでふ葭の茂りかな
青嵐三百年の無沙汰かな(中祖伊予に移りて二百五十年、この旧郷を訪ふものなし)
故郷(フルサト)の故郷淋し閑古鳥(帰路車上。郭公を聞く)
郭公(カッコウ)のあちらこちらはなかりけり ]
(再掲)
https://yahan.blog.ss-blog.jp/2023-11-10
http://sp.mogamiyoshiaki.jp/?p=log&l=143960

[(松根備前守光広/まつねびぜんのかみあきひろ)~俳人・松根東洋城の先祖~
義光の弟である義保の子。義保は長瀞城主。兄の片腕となって出羽南部の平定に尽力したが、天正19年(1591)に戦死。ときに光広は3歳の幼児だった。義光がこれを哀れんで、息子同然にいつくしみ育てたと、宇和島市に残る古記録は伝えている。
光広は成人の後は山形市漆山に居住したこともあったが、西村山の名門白岩家の名跡を継いで「白岩備前守」を名乗る。
慶長5年(1600年)の関が原合戦、長谷堂合戦のときは12、3歳だったから、まず戦陣の経験はなかっただろうと思われる。元和2年(1616)、庄内櫛引郷に居城松根城を築いて松根姓を名乗る。一1万2千石、一書に1万3千石とある。
義光に育てられたことに対する報恩の気持ちからか、最上家を思う心が人一倍厚い人物だったようだ。
熊野夫須美神社に、那智権現別当あて、年次無記8月20日付、光広の書状が一通ある。
「最上出羽守義光が病につき、神馬一疋ならびに鳥目(銭)百疋を奉納いたします。御神前において御祈念くださるようお頼みします」という内容である。
「白岩備前守光広」の署名からみて、松根移転以前であることは明らか。義光の病が重くなった慶長18年(1613)のものと推定される。出羽からははるかに遠い紀州那智に使者を遣わして、病気平癒の祈りをささげたのである。あるいは、光広はそのころ上京中だったかもしれない。
義光が亡くなり、跡を継いだ駿河守家親も3年後の元和3年ににわかに亡くなり、その後を12歳の少年、源五郎家信が継ぐ。とかく問題行動を起こしがちな幼い主君に、家臣たちは動揺する。
家を守りたてるべき重臣たちのなかには、義光の四男山野辺光茂こそ山形の主にふさわしいとして、鮭延越前、楯岡甲斐らの一派が公然と動きはじめる。
かくてはならじ、お家のためになんとかせねばと、光広は「山野辺一派が策謀をめぐらし当主家親を亡きものにした」と幕府に直訴した。幕府でも一大事とばかり徹底的に究明したが、事実無根と判明。偽りの申し立てをした不届きの所業として、光広は九州柳川の立花家にあずけられてしまう。彼はここ柳川でおよそ五十年を過ごす。藩主立花宗茂との親交を保ちつつ、寛文12年(1672)84歳の生涯を終える。
その子孫が四国宇和島の伊達家につかえ、家老職の家柄を伝えて維新を迎えた。
高名な俳人松根東洋城(本名豊次郎1878~1964)は、この家の9代目にあたる。宮内省式部官などを勤めながら夏目漱石の門下として俳壇で活躍、のち芸術院会員となった。
昭和4年6月、父祖の地である庄内の松根から白岩をおとずれた東洋城は、昔をしのんで次のような句を残した。
故里の故里淋し閑古鳥
青嵐三百年の無沙汰かな
出羽の最上から九州柳川へ、そして更に四国の宇和島へ。先祖のたどった長い長い3百年の道程だった。宇和島市立伊達博物館の庭には、「我が祖先(おや)は奥の最上や天の川」の句碑がある。
最上家の改易で会津・蒲生氏により接収破却された松根城の跡には、最上院がある。光広の妻が晩年に住んだという松根庵には、彼女の墓碑が寂しくたっている。(片桐繁雄稿)]
(「最上義光歴史館」) ]
[寅日子(寅彦)・五十二歳。
3月12日、帝国学士院で“Ignition of Combustible Gases with Three-Part Spark”(with K. Yumoto and R. Yamamoto)を発表。3月19日、地震研究所で「砂層の崩壊に関する実験」(宮部と共著)を発表。
4月1日、水産講習所の嘱託を解かれ、新たに出来た水産試験場において物理学および海洋学に関する調査を嘱託される。4月16日、地震研究所談話会で「火山の形(第二報)」を発表。
5月12日、帝国学士院で“On the Effects of the Vapours of Halogen Compounds upon the Form and Structure of Long Sparks”(with U. Nakaya and R. Yamamoto)を発表。6月12日、“On the Form of Volcanos”を発表。
6月17日、航空学談話会で「金属薄膜に関する二三の実験」(田中信と共著)を発表。6月18日、地震研究所談話会で「丹後震災地付近に於ける地殻の変動」(宮部と共著)を発表。
7月3日、理化学研究所で脳貧血を起す。
10月12日、帝国学士院で“Deformation of the Earth Crust and Topographical Features”(with N. Miyabe)を発表。10月15日、地震研究所談話会で「桜島の地形変化」(宮部と共著)および「石油の生成と火山作用」を発表。
11月19日、理化学研究所学術講演会で「火山灰の接触作用」(平田森三と共著)を発表。
12月17日、地震研究所談話会で「関東地方に於ける地殻変動」(宮部と共著)を発表。この頃からしきりに映画を見るようになった。
「年賀状」、『東京朝日新聞』、1月。
「化物の進化」、『改造』、1月。
『万華鏡』、鉄塔書院、4月。
「数学と語学」、『帝国大学新聞』、4月。
「藤原博士の『雲』」、『新愛知』、6月。
「験潮旅行断片」、『大阪朝日新聞』、7月。
「デパートの夏の午後」、『東京朝日新聞』、8月。
「さまよへるユダヤ人の手記より」、『思想』、9月。
「野球時代」、『帝国大学新聞』、11月。 ]
荒海やこゝに静かな草の庵(七月二十八日)
※ この句については、『寺田寅彦全集 文学篇 第十六巻』に、その全文が収載されている。
[ 七月二十八日 千葉県安房郡千倉町より牛込区余丁町四一松根豊次郎氏へ(絵葉書)
子供を送りて昨日参り一泊致候
涼しいといふことは暑いといふことの一つの相に過ぎず
荒海やこゝに静かな草の庵
七月二十八日 ]
この葉書の前に、次のような、三吟(東洋城・寅日子・蓬里雨)」の文音連句(書簡による連句の付け合い)のものがある
[ 五月二十三日 京橋区銀座不二家より牛込区余丁町四一松根豊次郎氏へ(はがき、小宮豊隆との寄せ書=小宮氏の文面省略)
今夜不二屋で左記
(ギンザフジヤ)
クリームの溶けあし見るや五月雨 豊(※蓬里雨)
苺の色を奪ふ口紅 寅(※寅日子)
あとあとよろしく
五月二十三日 ](※仙台の豊隆が上京して、銀座の不二屋で、寅彦と、やりかけの連句の付け合いを作り、それを東洋城に回送したものであろう。)
[豊隆(蓬里雨)・昭和四年(一九二九)、四十六歳。三月合著『芭蕉俳諧研究』出版。]

みやこ町歴史民俗博物館/WEB博物館「みやこ町遺産」
https://adeac.jp/miyako-hf-mus/catalog-list/200020
上記の右端の「速達便」(大正七年十一月五日付け)は、『寺田寅彦全集 文学篇 第十六巻』に収載されている。
[十一月五日 火 午前八時~九時 本郷区駒込曙町一三より赤坂区青山南町六ノ一〇八小宮豊隆氏へ (はがき 速達便)
御端書難有う
小生も木曜の方が都合が宜しう御坐います
しかし水曜でも都合のつかぬ事はありませんが少し遅くなります、どうぞよろしく
十一月五日 ]
※ 当時の小宮豊隆は、「漱石全集」の編纂に全力を投入していて、その資料収集に関する寅彦との書簡のやり取りが多い。そして、「木曜」は、「木曜会」(漱石生前の漱石門の面木―の集まり、漱石没後は命日の「九日会」)の、豊隆が当番の時に、寅彦は参加する場合が多かったようである。東洋城は、「渋柿」の編集に追われて「九日会」には、顔を出さなかったように、当時の書翰から窺える。
.jpg)
「東大構内(寺田寅彦画)」(『寺田寅彦画集(中央公論美術出版)』)
[制作年月=大正八・九/種別=墨に淡彩/基材=和紙/大きさ=25.0×15.0㎝]
20(E5AFBAE794B0E5AF85E5BDA6E794BB).jpg)
「姉妹(A) (寺田寅彦画)」(『寺田寅彦画集(中央公論美術出版)』)
[制作年月=大正八・九/種別=墨に淡彩/基材=和紙/大きさ=34.0×23.3㎝]
※ 「大正七年一月十四日付け小宮豊隆宛寺田寅彦書翰」に、「小生は近頃少し気が狂つて徘(原・ママ=俳)句を作つて見たり畫いて見たりして居ます しかし一向物にならないので余り永くは続くまいかと思居候 今日は青楓(※津田青楓)君と野上(※野上豊一郎)君とが来て宅の掛物を見て貰ひました」などとあり、主として、東洋城からの依頼の「渋柿」に搭載する「俳句」や、津田青楓を師として、絵画制作などに没頭するようなことが、しばしば書翰に見られてくる。しかし、この当時は、文音による「俳諧」(連句)関係の書簡は見受けられない。
(参考) 「三四郎」の遺族が漱石の書簡寄贈 福岡・みやこ町に(「日本経済新聞社」)
[夏目漱石の弟子で、小説「三四郎」のモデルとなったドイツ文学者、小宮豊隆の遺族が、漱石から受け取った手紙や写真など計477点を小宮の出身地の福岡県みやこ町に寄贈した。「吾輩は猫である」の猫の死を伝える「死亡通知」など貴重な内容。みやこ町が13日までに明らかにした。
小宮は1905年に東京帝国大に入学。身元保証人になった漱石に弟子入りして交流を深め、小説の校正も手伝った。
みやこ町によると、漱石の手紙は122点。「猫の死亡通知」は1908年9月14日付で、死んだ状況や埋葬の様子を伝え「主人(漱石)は三四郎執筆中で忙しいので、会葬には及びません」とユーモアあふれる。
幼くして父親を失った小宮は、漱石を父親のように慕っていた。1906年12月22日付の手紙で漱石は「僕をお父さんにするのはいいが、大きな息子がいると思うと落ち着いて騒げない」とつづっている。
ほかに漱石の漢文紀行「木屑録(ぼくせつろく)」や、千円札の肖像になった写真、同じく弟子だった物理学者、寺田寅彦の手紙226点もある。いずれも東京都杉並区在住で三女の里子さんが「故郷で生かしてほしい」と寄贈した。
町歴史民俗博物館の川本英紀学芸員は「小説からは見えない師弟関係が伝わってくる」と話している。同博物館で、手紙など約10点を14~26日に展示する。〔共同〕 ]
「東洋城・寅彦、そして、豊隆」(漱石没後~寅彦没まで)俳句・連句管見(その十二) [東洋城・寅日子(寅彦)・蓬里雨(豊隆)]
その十二「昭和三年(一九二八)」
[東洋城・五十一歳。「東洋城百詠」刊。渋柿大会開催。新那須温泉、大平山に遊ぶ。東洋城百茶碗が作られた。]

[歌舞伎十八番之内『勧進帳』 明治23年 豊原国周(1835年-1900年)筆]
http://yagi.la.coocan.jp/image1/kanjincho_01509.gif
「歌舞伎十八番の内 勧進帳 百十一句」(東洋城作)の十句(抜粋)
歌舞伎十八番勧進帳や春茲に(前書「開幕 舞台面」)
白梅やすこし藍さす白よけれ(前書「富樫(左団次)の顔」)
桜貝義経は若うつくりけり(前書「義経(宗十郎)の出」)
どんじりに弁慶田螺ひかへけり(前書「弁慶(羽左衛門)の出」)
薄霞む安宅の関へかゝりけり(前書「いざ通らんと旅衣」)
春浅き勧進帳の白紙かな(前書「固より勧進帳のあらばこそ」)
九字の真言春郭然と説かれけり(前書「夫れ九字の真言と云つぽ」)
春見張る団十郎の眼や昔(前書「元禄見得」)
打擲(チョウチャク)す笠の音なり春霰(前書「思へば憎しや」)

https://enmokudb.kabuki.ne.jp/repertoire/673/
【左】[左から]源義経(坂田藤十郎)、武蔵坊弁慶(市川團十郎)、富樫左衛門(松本幸四郎) 平成24年10月新橋演舞場
【右】[左から]駿河次郎(市川高麗蔵)、亀井六郎(大谷友右衛門)、武蔵坊弁慶(松本幸四郎)、片岡八郎(中村鴈治郎)、常陸坊海尊(松本錦吾)、富樫左衛門(市川團十郎) 平成24年10月新橋演舞場
唄の喉※伊十郎とはうらゝかな(前書「つひに泣かぬ弁慶も」、※=長唄・芳村移十郎)
寄り離れ小貝と春の浪とかな(前書「判官御手をとり給ひ」)
春淋しきさだめと人の嘆きけり(前書「いかなれば義経は」)
舞ひ舞ふや扇と数珠と皆うらゝ(前書「たえずとうたり」)
一飛び二飛びや東風に遠かる(前書「虎の尾を踏み毒蛇の口を」)
袖巻きの見得やすくりと松余寒(前書「幕切(富樫舞台真中へ)」)
[寅日子(寅彦)・五十一歳。1月17日、地震研究所談話会で「関東地震に関係せる地殻の
移動に就て」(宮部と共著)を発表。
2月12日、帝国学士院で“On the Vertical Displacement of the Sea Bottom in Sagami Bay Discovered after the Great Kwanto Earthquake of 1923”, “On the Horizontal Displacements of the Primary Trigonometrical Points Discovered after the Kwanto Earthquake”(with N. Miyabe)および“On the Geophysical Significance of the Crustal Movement Found after the Great Earthquake of 1923”を発表。
3月12日、帝国学士院で“On an Irregular Mode of Spherical Propagation of Flame”(with K. Yumoto)を発表。3月20日、地震研究所談話会で「丹後地震に於ける地殻変動に就て」(宮部と共著)および「関東地震と海面」(山口生知と共著)を発表。
3月21日、測地学委員会の用件で酒田へ向かう。4月12日、帝国学士院で“On Gustiness of Winds”を発表。4月23日、航空学談話会で「Convectionに依る渦流」を発表。
4月24日、地震研究所談話会で「丹後地震と地殻変動」(宮部との共著)を発表。
5月12日、帝国学士院で“Effect of an Irregular Sucession of Impulses upon aSimple Vibrating System—Its Bearing upon Serismometry”(with U. Nakaya), “Relation betweenHorizontal Deformation and Postseismic Vertical Displacement of Earth Crust which Accompanied the Tango Earthquake”(with N. Miyabe)および“Postseismic Slow Vertical Displacement of Earth Crust and Isostasy”(with N. Miyabe)を発表。
5月22日、地震研究所談話会で「丹後地方地殻変動」(宮部・東庄三郎と共著)および「火山の形に就て」(東と共著)を発表。5月頃から、バイオリンを水口幸麿について習うようになる。
6月12日、帝国学士院で“Vertical Displacements of Sea Bed off the Coast the Tango Earthquake District”(with S. Higasi)を発表。
6月19日、地震研究所談話会で「気圧と海水面」および「地震と海底変動」を発表。
7月3日、同談話会で「横圧に依る砂層の崩壊」(宮部と共著)および「島弧の形状に就て」を発表。7月12日、帝国学士院で“On a Characteristic Mode of Deformation of Sea Bed”(with S. Higasi)を発表。
9月25日、地震研究所談話会で「地震史料の調査(第一報)」および「地震帯に就て」を発表。10月12日、帝国学士院で“Ignition of Gas by Spark and Its Dependency on the Nature of Spark”(with K. Yumoto)および“On the Effect of Cyclone
upon Sea Level”(with S. Yamaguti)を発表。
11月26日、航空学談話会で「液体に浮遊する粉末と液との相対運動に就て」(玉野と共著)を発表。
談話「ロンドン大火と東京火」、『日本消防新聞』、1月。
「日本楽器の名称と外国との関係」、『大阪朝日新聞』、1月。
「土佐の地名」、『土佐及土佐人』、1月。
詩「三毛の墓」、『渋柿』、2月。
「比較言語学に於ける統計的研究法の可能性に就て」、『思想』、3月。
「最上川象潟以後」、『渋柿』、4月。
「夏目先生の俳句と漢詩」、『漱石全集』第13巻、月報、5月。
「羽越紀行」、『渋柿』、5月。
「子規の追憶」、『日本及日本人』、9月。
「スパーク」、『東京帝国大学理学部会誌』、9月。
「ルクレチウスと科学」、岩波講座『世界思潮』、9月。
「雑感」、『理科教育』、11月。
「二科狂想行進曲」、『霊山美術』、11月。
※[「夏目先生の俳句と漢詩」、『漱石全集』第13巻、月報、5月。]
https://yahan.blog.ss-blog.jp/archive/c2306351243-1
※[「子規の追憶」、『日本及日本人』、9月。]
https://www.aozora.gr.jp/cards/000042/card24418.html
※「小宮豊隆宛寅彦書翰」の句など(大正十一年・一九二四~昭和三年・一九二八)
(大正十一年・一九二四)
物言へど猫は答へぬ寒さ哉(「日記の中より 二句」、一月三十一日)
冰(コオ)る夜や顔に寄り来る猫の鬚(ヒゲ) (同上)
(大正十二年・一九二五)
春の江は靄(モヤ)に暮れ行く別れ哉(「小宮豊隆氏送別の句(錦水にて)」、三月)
(大正十四年)
葉がくれに秋にうなづく柘榴哉(「小宮豊隆氏宛手紙の中より」、九月三十日)
(大正十五年・昭和元年・一九二六)
狼の群に入らばや初時雨(「小宮豊隆氏宛端書の中より」、一月十四日)
(昭和二年・一九二七)
稍(ヤヤ)寒く余白の※出来し(※再案=のこりし)手紙哉(小宮豊隆氏宛手紙、九月二十五日)
(付記)「寺田寅彦年譜」の「昭和二年(一九二七)」に、「八月、小宮豊隆、松根東洋城、津田青楓と塩原温泉に行き、連句を実作する」とあるが、この時の連句は、『松根東洋城全句集(下巻)』にも『寺田寅彦全集・文学篇・第七巻』にも収載されていない。また、この年の七月に、「十八日仙台に行き、十句日小宮豊隆と松島に遊んだ。瑞巌寺、五大堂を見てパークホテルに投じ月を待つて連句を作つた」(『寺田寅彦全集・文学篇・第七巻』)とあるが、この連句も収載されていない。なお、この時の俳句は、昭和二年に、次のとおり、四句収載されている。
島は暮れて残る明りの海と空(七月十九日松島、三句)
塩釜は夕立するらん沖夕映(同上)
涼風や寝起の心よみがへる(同上)
波に飛ぶ蛍を見たり五大堂(「松島より一句」・「渋柿(九月)」)
(昭和三年・一九二八)
※ 上記の年譜に「3月21日、測地学委員会の用件で酒田へ向かう。」とあるが、これは、寅彦の「羽越紀行」(昭和三年五月「渋柿」)で、さながら、寅彦の「奥の細道」(句入りの散文)でまとめられている(『寺田寅彦全集・文学篇・第七巻』)。
「羽越紀行」(昭和三年五月「渋柿」)一部抜粋
[ 昭和三年三月二十一日
夜の九時半上野駅を出で立つ。(中略)
駅の名の峠と呼ぶや雪の声
粉雪やいづこ隙間を漏るゝ風
生来五十余年未だ北国の冬を知らず、(中略)
雪の国もんぺ(モンペ)の国へ参りける(「出羽の国=山形・秋田」の山形の米沢?)
やがて赤湯を過ぐ。
温泉の町は雪に眠りて旭日哉(赤湯温泉)
新庄にて乗換ふ。
雪の汽車北と西とへ別れ哉
雪国の自然には暖国の人の思ひ及ばざる現象もありけり。
雪の原穴の見ゆるは川ならめ
最上川は雪解の水を集めたり。(中略)
山の根の雪を噛む濁り哉(最上川)
右岸既に春をきざせど、左岸は日を背にして未だ厳冬の鎖し難く。
あのやふに曲がりて風の氷柱哉
山は左右に開けて汽車日本海岸に近づく。(中略)
荘内の野に日は照れど霰哉(荘内平野)
酒田の町になにがしの役場をたづねて後、(中略)
しべりあ(シベリア)の雪の奥から吹く風か(坂田)
渡船は帆を巻きおろす霰哉(同上)
やふやふ(ヨウヨウ)に舟岸につく霰かな(同上)
明くる朝まだき象潟に赴く。(中略)
象潟は陸になりける冬田哉(象潟)
しんかんと時雨るゝ松や蚶満寺(同上)
やよ鴉汝(ナレ)もしぐれて居る旅か(同上)
有耶無耶の関の跡此のあたりかと汽車の窓より眺めて過ぐれとさだかならす、(中略)
有耶無耶の関は石山霰哉
あの島に住む人ありて吹雪哉
終日海岸を西へ南へ越後に下る。途上温海といへる温泉の町に一汽車の暇を立ち寄る。(中略)
自動車のほこり浴びても蕗の薹(温海温泉)
日本海は悠久の「地の悲み」を湛へて沖の彼方に遠く消え去るを見る。
雪霰帆一つ見えぬ海淋し
荒海に消え入る雲の何ともな
(前略) 翌朝阿賀川の峡谷を遡る。
残雪や名のない山の美しう(阿賀川)
(前略) 会津の野を過ぎて猪苗代に近づく、磐梯山は神々しく碧空に輝きてめでたく。
御山雪裾野芝原蕗の花
眠るかや湖(ウミ)をめぐらす雪の山
旅三日雪の国々めぐりて再び武蔵野に入れば、(中略)
しばらくの留守をたづねて来た春か
飛行機と見えしは紙鳶(タコ)に入る日かな
旅は愛し侘し、天下の広き、(中略)
三毛よ今帰つたぞ門の月朧
三日の留守も三年の旅も「量」こそかはれ「質」は変らじ。
珍らしや風呂も我家の朧月
さればこそ旅は楽しく面白けれ。(中略)
蝸牛の角がなければ長閑かな
又想ふ。
蝸牛の角があつても長閑かな
[豊隆(蓬里雨)・昭和三年(一九二八)、四十五歳。四月翻訳シュニツラー『アナトール』(岩波文庫)出版。]
http://karatsujuku.com/wp-content/uploads/2022/06/karatsujuku_lecture147_resume.pdf
[「寺田寅彦の俳諧と物理学(大嶋 仁)」(抜粋)
「東洋城・寅日子・蓬里雨の三吟」
雪の蓑ひとつ見ゆるや峡(かひ)の橋 東洋城
空はからりと晴れわたる朝 蓬里雨
⼊営を見送る群の旗立てて 寅日子
酒にありつく人のいやしき 城
後の月用もないのに台所 雨
飛んで出でしは竈馬(いとど)なり 子
(「渋柿」1926 所収の歌仙の初6句)
松根東洋城は漱石に英語を習う。漱石や高浜虚子と異なり連句を目指す。
小宮豊隆は漱石に英文学を習った独文学者で蕉風復興を目指す。
寺田寅彦は上記二者と仲がよく、共に連句制作をした。
「寅彦の連句論」
連句の一句の顕在的内容は、やはりその作者の非常に多数な体験のかなめである。そうしてその多くの潜在的思想の網が部分的に前句と後句に引っかかっているのである。
もちろん前句には前句の作者の潜在思想の網目がつながっているのであるが、付け句の作者の見た前句にはまたこの付け句作者自身の潜在的な句想の網目につながるべき代表的記号が明瞭に現われているのである。
そうしてまたこの二つの句を読む第三者がこの付け合わせを理解し評価しうるためにはこの第三者の潜在思想中で二句が完全に連結しなければならないのである。しかもこの際読者の網目と前句作者の網目と付け句作者の網目とこの三つのものが最もよく必然的に重なり合い融け合う場合において、その付け合わせは最もすぐれた付け合わせとして感ぜられるのである。このような機巧によって運ばれる連句の進行はたしかにフロイドの考えたような夢の進行に似ているのである。
しかし夢の場合はそれが各個人に固有なものであって必ずしもなんらの普遍性をもたなくてもよい。しかし連句においては甲の夢と乙の夢との共通点がまた読者の多数の夢に強く共鳴する点において立派な普遍性をもっており、そこに一般的鑑賞の目的物たる芸術としての要求が満足されているのである。 (「連句雑俎」1931)
映画と連句とが個々の二つの断片の連結のモンタージュにおいてほとんど全く同一であるにかかわらず、全体としての形態において著しい相違のあるのは、いわゆる筋が通っているのと通っていないのとの区別である。多くの映画は一通りは論理的につながったストーリーの筋道をもっているのに、連句歌仙の三十六句はなんらそうした筋をもたないのである。
(…)しかし「アンダルーシアの犬」と称する非現実映画(往来社版、映画脚本集第二巻)になるともはやそういう明白な主題はない。そのモンタージュは純然たる夢の編成法であり、しかもかなりによく夢の特性をつかんでいる。
たとえば月を断ち切る雲が、女の目を切る剃刀を呼び出したり、男の手のひらの傷口から出て来る蟻の群れが、女の脇毛にオーバーラップしたりする。そういう非現実的な幻影の連続の間に、人間というものの潜在的心理現象のおそるべき真実を描写する。この点でこの種の映画の構成原理は最も多く連句のそれに接近するものと⾔わなければならない。 (「映画芸術」1932) ]
[東洋城・五十一歳。「東洋城百詠」刊。渋柿大会開催。新那須温泉、大平山に遊ぶ。東洋城百茶碗が作られた。]

[歌舞伎十八番之内『勧進帳』 明治23年 豊原国周(1835年-1900年)筆]
http://yagi.la.coocan.jp/image1/kanjincho_01509.gif
「歌舞伎十八番の内 勧進帳 百十一句」(東洋城作)の十句(抜粋)
歌舞伎十八番勧進帳や春茲に(前書「開幕 舞台面」)
白梅やすこし藍さす白よけれ(前書「富樫(左団次)の顔」)
桜貝義経は若うつくりけり(前書「義経(宗十郎)の出」)
どんじりに弁慶田螺ひかへけり(前書「弁慶(羽左衛門)の出」)
薄霞む安宅の関へかゝりけり(前書「いざ通らんと旅衣」)
春浅き勧進帳の白紙かな(前書「固より勧進帳のあらばこそ」)
九字の真言春郭然と説かれけり(前書「夫れ九字の真言と云つぽ」)
春見張る団十郎の眼や昔(前書「元禄見得」)
打擲(チョウチャク)す笠の音なり春霰(前書「思へば憎しや」)

https://enmokudb.kabuki.ne.jp/repertoire/673/
【左】[左から]源義経(坂田藤十郎)、武蔵坊弁慶(市川團十郎)、富樫左衛門(松本幸四郎) 平成24年10月新橋演舞場
【右】[左から]駿河次郎(市川高麗蔵)、亀井六郎(大谷友右衛門)、武蔵坊弁慶(松本幸四郎)、片岡八郎(中村鴈治郎)、常陸坊海尊(松本錦吾)、富樫左衛門(市川團十郎) 平成24年10月新橋演舞場
唄の喉※伊十郎とはうらゝかな(前書「つひに泣かぬ弁慶も」、※=長唄・芳村移十郎)
寄り離れ小貝と春の浪とかな(前書「判官御手をとり給ひ」)
春淋しきさだめと人の嘆きけり(前書「いかなれば義経は」)
舞ひ舞ふや扇と数珠と皆うらゝ(前書「たえずとうたり」)
一飛び二飛びや東風に遠かる(前書「虎の尾を踏み毒蛇の口を」)
袖巻きの見得やすくりと松余寒(前書「幕切(富樫舞台真中へ)」)
[寅日子(寅彦)・五十一歳。1月17日、地震研究所談話会で「関東地震に関係せる地殻の
移動に就て」(宮部と共著)を発表。
2月12日、帝国学士院で“On the Vertical Displacement of the Sea Bottom in Sagami Bay Discovered after the Great Kwanto Earthquake of 1923”, “On the Horizontal Displacements of the Primary Trigonometrical Points Discovered after the Kwanto Earthquake”(with N. Miyabe)および“On the Geophysical Significance of the Crustal Movement Found after the Great Earthquake of 1923”を発表。
3月12日、帝国学士院で“On an Irregular Mode of Spherical Propagation of Flame”(with K. Yumoto)を発表。3月20日、地震研究所談話会で「丹後地震に於ける地殻変動に就て」(宮部と共著)および「関東地震と海面」(山口生知と共著)を発表。
3月21日、測地学委員会の用件で酒田へ向かう。4月12日、帝国学士院で“On Gustiness of Winds”を発表。4月23日、航空学談話会で「Convectionに依る渦流」を発表。
4月24日、地震研究所談話会で「丹後地震と地殻変動」(宮部との共著)を発表。
5月12日、帝国学士院で“Effect of an Irregular Sucession of Impulses upon aSimple Vibrating System—Its Bearing upon Serismometry”(with U. Nakaya), “Relation betweenHorizontal Deformation and Postseismic Vertical Displacement of Earth Crust which Accompanied the Tango Earthquake”(with N. Miyabe)および“Postseismic Slow Vertical Displacement of Earth Crust and Isostasy”(with N. Miyabe)を発表。
5月22日、地震研究所談話会で「丹後地方地殻変動」(宮部・東庄三郎と共著)および「火山の形に就て」(東と共著)を発表。5月頃から、バイオリンを水口幸麿について習うようになる。
6月12日、帝国学士院で“Vertical Displacements of Sea Bed off the Coast the Tango Earthquake District”(with S. Higasi)を発表。
6月19日、地震研究所談話会で「気圧と海水面」および「地震と海底変動」を発表。
7月3日、同談話会で「横圧に依る砂層の崩壊」(宮部と共著)および「島弧の形状に就て」を発表。7月12日、帝国学士院で“On a Characteristic Mode of Deformation of Sea Bed”(with S. Higasi)を発表。
9月25日、地震研究所談話会で「地震史料の調査(第一報)」および「地震帯に就て」を発表。10月12日、帝国学士院で“Ignition of Gas by Spark and Its Dependency on the Nature of Spark”(with K. Yumoto)および“On the Effect of Cyclone
upon Sea Level”(with S. Yamaguti)を発表。
11月26日、航空学談話会で「液体に浮遊する粉末と液との相対運動に就て」(玉野と共著)を発表。
談話「ロンドン大火と東京火」、『日本消防新聞』、1月。
「日本楽器の名称と外国との関係」、『大阪朝日新聞』、1月。
「土佐の地名」、『土佐及土佐人』、1月。
詩「三毛の墓」、『渋柿』、2月。
「比較言語学に於ける統計的研究法の可能性に就て」、『思想』、3月。
「最上川象潟以後」、『渋柿』、4月。
「夏目先生の俳句と漢詩」、『漱石全集』第13巻、月報、5月。
「羽越紀行」、『渋柿』、5月。
「子規の追憶」、『日本及日本人』、9月。
「スパーク」、『東京帝国大学理学部会誌』、9月。
「ルクレチウスと科学」、岩波講座『世界思潮』、9月。
「雑感」、『理科教育』、11月。
「二科狂想行進曲」、『霊山美術』、11月。
※[「夏目先生の俳句と漢詩」、『漱石全集』第13巻、月報、5月。]
https://yahan.blog.ss-blog.jp/archive/c2306351243-1
※[「子規の追憶」、『日本及日本人』、9月。]
https://www.aozora.gr.jp/cards/000042/card24418.html
※「小宮豊隆宛寅彦書翰」の句など(大正十一年・一九二四~昭和三年・一九二八)
(大正十一年・一九二四)
物言へど猫は答へぬ寒さ哉(「日記の中より 二句」、一月三十一日)
冰(コオ)る夜や顔に寄り来る猫の鬚(ヒゲ) (同上)
(大正十二年・一九二五)
春の江は靄(モヤ)に暮れ行く別れ哉(「小宮豊隆氏送別の句(錦水にて)」、三月)
(大正十四年)
葉がくれに秋にうなづく柘榴哉(「小宮豊隆氏宛手紙の中より」、九月三十日)
(大正十五年・昭和元年・一九二六)
狼の群に入らばや初時雨(「小宮豊隆氏宛端書の中より」、一月十四日)
(昭和二年・一九二七)
稍(ヤヤ)寒く余白の※出来し(※再案=のこりし)手紙哉(小宮豊隆氏宛手紙、九月二十五日)
(付記)「寺田寅彦年譜」の「昭和二年(一九二七)」に、「八月、小宮豊隆、松根東洋城、津田青楓と塩原温泉に行き、連句を実作する」とあるが、この時の連句は、『松根東洋城全句集(下巻)』にも『寺田寅彦全集・文学篇・第七巻』にも収載されていない。また、この年の七月に、「十八日仙台に行き、十句日小宮豊隆と松島に遊んだ。瑞巌寺、五大堂を見てパークホテルに投じ月を待つて連句を作つた」(『寺田寅彦全集・文学篇・第七巻』)とあるが、この連句も収載されていない。なお、この時の俳句は、昭和二年に、次のとおり、四句収載されている。
島は暮れて残る明りの海と空(七月十九日松島、三句)
塩釜は夕立するらん沖夕映(同上)
涼風や寝起の心よみがへる(同上)
波に飛ぶ蛍を見たり五大堂(「松島より一句」・「渋柿(九月)」)
(昭和三年・一九二八)
※ 上記の年譜に「3月21日、測地学委員会の用件で酒田へ向かう。」とあるが、これは、寅彦の「羽越紀行」(昭和三年五月「渋柿」)で、さながら、寅彦の「奥の細道」(句入りの散文)でまとめられている(『寺田寅彦全集・文学篇・第七巻』)。
「羽越紀行」(昭和三年五月「渋柿」)一部抜粋
[ 昭和三年三月二十一日
夜の九時半上野駅を出で立つ。(中略)
駅の名の峠と呼ぶや雪の声
粉雪やいづこ隙間を漏るゝ風
生来五十余年未だ北国の冬を知らず、(中略)
雪の国もんぺ(モンペ)の国へ参りける(「出羽の国=山形・秋田」の山形の米沢?)
やがて赤湯を過ぐ。
温泉の町は雪に眠りて旭日哉(赤湯温泉)
新庄にて乗換ふ。
雪の汽車北と西とへ別れ哉
雪国の自然には暖国の人の思ひ及ばざる現象もありけり。
雪の原穴の見ゆるは川ならめ
最上川は雪解の水を集めたり。(中略)
山の根の雪を噛む濁り哉(最上川)
右岸既に春をきざせど、左岸は日を背にして未だ厳冬の鎖し難く。
あのやふに曲がりて風の氷柱哉
山は左右に開けて汽車日本海岸に近づく。(中略)
荘内の野に日は照れど霰哉(荘内平野)
酒田の町になにがしの役場をたづねて後、(中略)
しべりあ(シベリア)の雪の奥から吹く風か(坂田)
渡船は帆を巻きおろす霰哉(同上)
やふやふ(ヨウヨウ)に舟岸につく霰かな(同上)
明くる朝まだき象潟に赴く。(中略)
象潟は陸になりける冬田哉(象潟)
しんかんと時雨るゝ松や蚶満寺(同上)
やよ鴉汝(ナレ)もしぐれて居る旅か(同上)
有耶無耶の関の跡此のあたりかと汽車の窓より眺めて過ぐれとさだかならす、(中略)
有耶無耶の関は石山霰哉
あの島に住む人ありて吹雪哉
終日海岸を西へ南へ越後に下る。途上温海といへる温泉の町に一汽車の暇を立ち寄る。(中略)
自動車のほこり浴びても蕗の薹(温海温泉)
日本海は悠久の「地の悲み」を湛へて沖の彼方に遠く消え去るを見る。
雪霰帆一つ見えぬ海淋し
荒海に消え入る雲の何ともな
(前略) 翌朝阿賀川の峡谷を遡る。
残雪や名のない山の美しう(阿賀川)
(前略) 会津の野を過ぎて猪苗代に近づく、磐梯山は神々しく碧空に輝きてめでたく。
御山雪裾野芝原蕗の花
眠るかや湖(ウミ)をめぐらす雪の山
旅三日雪の国々めぐりて再び武蔵野に入れば、(中略)
しばらくの留守をたづねて来た春か
飛行機と見えしは紙鳶(タコ)に入る日かな
旅は愛し侘し、天下の広き、(中略)
三毛よ今帰つたぞ門の月朧
三日の留守も三年の旅も「量」こそかはれ「質」は変らじ。
珍らしや風呂も我家の朧月
さればこそ旅は楽しく面白けれ。(中略)
蝸牛の角がなければ長閑かな
又想ふ。
蝸牛の角があつても長閑かな
[豊隆(蓬里雨)・昭和三年(一九二八)、四十五歳。四月翻訳シュニツラー『アナトール』(岩波文庫)出版。]
http://karatsujuku.com/wp-content/uploads/2022/06/karatsujuku_lecture147_resume.pdf
[「寺田寅彦の俳諧と物理学(大嶋 仁)」(抜粋)
「東洋城・寅日子・蓬里雨の三吟」
雪の蓑ひとつ見ゆるや峡(かひ)の橋 東洋城
空はからりと晴れわたる朝 蓬里雨
⼊営を見送る群の旗立てて 寅日子
酒にありつく人のいやしき 城
後の月用もないのに台所 雨
飛んで出でしは竈馬(いとど)なり 子
(「渋柿」1926 所収の歌仙の初6句)
松根東洋城は漱石に英語を習う。漱石や高浜虚子と異なり連句を目指す。
小宮豊隆は漱石に英文学を習った独文学者で蕉風復興を目指す。
寺田寅彦は上記二者と仲がよく、共に連句制作をした。
「寅彦の連句論」
連句の一句の顕在的内容は、やはりその作者の非常に多数な体験のかなめである。そうしてその多くの潜在的思想の網が部分的に前句と後句に引っかかっているのである。
もちろん前句には前句の作者の潜在思想の網目がつながっているのであるが、付け句の作者の見た前句にはまたこの付け句作者自身の潜在的な句想の網目につながるべき代表的記号が明瞭に現われているのである。
そうしてまたこの二つの句を読む第三者がこの付け合わせを理解し評価しうるためにはこの第三者の潜在思想中で二句が完全に連結しなければならないのである。しかもこの際読者の網目と前句作者の網目と付け句作者の網目とこの三つのものが最もよく必然的に重なり合い融け合う場合において、その付け合わせは最もすぐれた付け合わせとして感ぜられるのである。このような機巧によって運ばれる連句の進行はたしかにフロイドの考えたような夢の進行に似ているのである。
しかし夢の場合はそれが各個人に固有なものであって必ずしもなんらの普遍性をもたなくてもよい。しかし連句においては甲の夢と乙の夢との共通点がまた読者の多数の夢に強く共鳴する点において立派な普遍性をもっており、そこに一般的鑑賞の目的物たる芸術としての要求が満足されているのである。 (「連句雑俎」1931)
映画と連句とが個々の二つの断片の連結のモンタージュにおいてほとんど全く同一であるにかかわらず、全体としての形態において著しい相違のあるのは、いわゆる筋が通っているのと通っていないのとの区別である。多くの映画は一通りは論理的につながったストーリーの筋道をもっているのに、連句歌仙の三十六句はなんらそうした筋をもたないのである。
(…)しかし「アンダルーシアの犬」と称する非現実映画(往来社版、映画脚本集第二巻)になるともはやそういう明白な主題はない。そのモンタージュは純然たる夢の編成法であり、しかもかなりによく夢の特性をつかんでいる。
たとえば月を断ち切る雲が、女の目を切る剃刀を呼び出したり、男の手のひらの傷口から出て来る蟻の群れが、女の脇毛にオーバーラップしたりする。そういう非現実的な幻影の連続の間に、人間というものの潜在的心理現象のおそるべき真実を描写する。この点でこの種の映画の構成原理は最も多く連句のそれに接近するものと⾔わなければならない。 (「映画芸術」1932) ]
「東洋城・寅彦、そして、豊隆」(漱石没後~寅彦没まで)俳句・連句管見(その十一) [東洋城・寅日子(寅彦)・蓬里雨(豊隆)]
その十一「昭和二年(一九二七)」
[東洋城・五十歳。塩原に句碑建立。伊予に遊ぶ。芥川龍之介自殺。「添削実相」掲載始まる。]

〇松根東洋城両面碑 塩湧橋先
【碑文】
「さまみえて土になりゐる落葉哉」表
「すずしさやこの山水に出湯とは」裏 (塩原四季郷より)
http://hotyu.starfree.jp/historicalspots/bungakuhi/bungakuhi.html
『東洋城全句集(上巻)』の「昭和二年」には、「塩原・四季郷」と題して、三十二句が収載されている。また、『東洋城全句集(中巻)』には、「昭和二年七月、塩原四季郷両面碑(西面)前にて」と題しての、当時の東洋城の肖像写真が掲載されている。この時の句に、上記の「両面句碑」の句に似た、次のような句がある。
涼しさや橋の下なる碧き山
涼しさや街道一つみえゐる灯(前書「瞰(かん) 流亭」)
径(ミチ)岐(キ)していづれか深き落葉かな
[寅彦=寅日子・五十歳
file:///C:/Users/user/Downloads/%E5%AF%BA%E7%94%B0%E5%AF%85%E5%BD%A6%E5%B9%B4%E8%A1%A8.pdf
3月10日、前年12月に辞職希望を申し出ていたが、理学部勤務を免ぜられ、地震研究所所員専任となる。3月12日、帝国学士院で“On Thermoelectric and Electrothermal Properties of Bismuth Single Crystal”(with T. Tsutsui)を発表。3月15日、地震研究所談話会で「砂の崩れ方の話」(宮部直巳と共著)を発表。
4月2日、数学物理学会で“Some Experiments on Periodic From of Convection Currents”(with Second Year Students)を発表。4月12日、帝国学士院で“On Thermoelectric Phenomena of Thin Metallic Films”(with S. Tanaka and S. Kusaba)を発表。4月19日、地震研究所談話会で「地球の激震帯と其長周期移動」(宮部と共著)を発表。
5月11日、帝国学士院“On a Long Period Fluctuation in Latitude of the the Macroseismic Zone of the Earth”(with N. Miyabe)を発表。5月17日、地震研究所談話会で「弾性波の実験(第二報)」(坪井と共著)および「日本海沿岸の島列に就て」を発表。5月30日、航空学談話会で「風の短周期変化に就て」(玉井光男と共著)。
6月21日、地震研究談話会で「沿岸島列に就て」および「島弧の生成に関する実験」(宮部と共著)を発表。7月12日、帝国学士院で“On the Vortical Motion of Fluid Produced by Rotating Body”(with K. Hattori)を発表。
9月20日、地震研究所談話会で「土佐南海岸の汀線変化に就て」(岸上冬彦・小平孝雄と共著)および「統計地震学に於けるSchwankung の理論の応用」(岸上・河角広と共著)を発表。
10月12日、帝国学士院で“Formation of Periodic Columnar Vortices by Convection”および“Residual Thermoelectric Phenomena of Apparently Homogeneous Wire”(with T. Tsutsui and M.Tamano)を発表。10月14日、水産講習所の海洋調査担当官会議で「大気の運動に就て」を講演。
10月18日、地震研究所談話会で「弾性波の実験(第三報)」(坪井と共著)、「微動遮断に関する堀の効果」(坪井と共著)および「砂の崩壊に就て」(宮部と共著)を発表。11月15日、地震研究所談話会で「本邦に於ける近年の山崩の分布」を発表。
12月12日、帝国学士院で“On the Mechanism of Formation of Step-Faults in Sand Layers—A Possible Analogy with Slip Bands in Deformed Metallic Crystals”(with N. Miyabe)を発表。この年の秋頃よりアイヌ語、マレイ語などの辞典から土佐の地名の語源を捜すことを試みる。
「断片」、『明星』、1月。
「備忘録」、『思想』、9月。
「Odisin no Okorikata ni kwansuru hitotuno Syukisei」、『RS』、9月。
「松島より」、『渋柿』、9月。
「怪異考」、『思想』、11月。
「昭和二年の二科会と美術院」、『霊山美術』、11月。
「人の言葉—自分の言葉」、『東京帝国大学理学部会誌』、12月。 ]
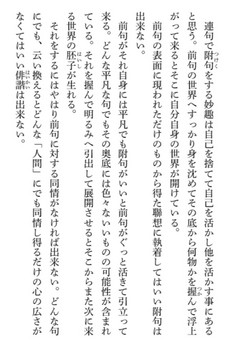
「断片」、『明星』、1月。(抜粋)
https://aozora-dev.binb.jp/reader/main.html?cid=42221
[豊隆(蓬里雨)・昭和二年(一九二七)、四十四歳。七月翻訳ストリンドベリ『父』出版。十二月翻訳ストリンドベリ『幽霊曲』(岩波文庫)出版。]
「歌仙『みちのく人の巻』(昭和二年二月「渋柿」)」
オ
送別
あすよりはみちのく人や春の雨 東洋城
まだ雪のこる西側の山 蓬里雨
沈丁花こぼるゝ里に移り来て 寅日子
筧は口をつけぬならはし 城
庭の木に梟来て啼く明けの月 雨 月
納豆うれしき肌寒の朝 子
ウ
年々を脚気の癒ゆる露深み 城
あすからかゝる約束の本 雨
切貼の馴れぬ手振もうら若く 子
母子(オヤコ)小町と唄はれにけり 城
一々に値上げ煙草の詫をいひ 雨
蠅取紙に光る秋の日 子
鰡(ボラ)鰯秋刀魚のきほふ魚の棚 城
蹇(アシナエ)の子のギス飼うてゐる 雨
針程のことを兎角に言ひつのり 子
白いうなじをふるはせて泣く 城 恋
斵(キ)れて来て見付通れば花に月 雨 花・月・恋
誰が捨てたか土手の猫の子 子
ナオ
蠶(コ)の頃の苗代の頃の忙しさ 城
家出の兄のよこす長文 雨
繰り言も浮世長屋の隣同士 子
箍(タガ)のはじけた桶提げて行く 城
大木の榎実こぼるゝ塀の前 雨
流れにまかせ葦を刈る船 子
悲しきは謡の中の秋の風 城
義理立たねばとあかで別るゝ 雨 恋
腰掛に一夜仮寝の夢覚めて 子 恋
朝のうちからわかる雷 城
先ず孫に月見団子をわけてやり 雨 月
白い紅いはおしろいの花 子
ナウ
秋の空丘の丸きに家建ちて 城
踏切越せば税関がある 雨
夜もすがら何処の鍛冶屋の鎚(ツチ)の音 子
幾日の果ての葬(ホフリ)悲しき 城
此度は花見にさとの母連れて 雨 花
小鮎の鰭(ヒレ)にいさゝかの色 子
※ この三吟歌仙で目立つのは、「二花三月」の「月・花の定座」を、脇句作者の「蓬里雨」が独占しているということである。
(オ「五句目」)
庭の木に梟来て啼く明けの月 蓬里 雨→月(「梟」=冬、冬の月、定石は秋の月。)
(ウ「十一句目」)
斵(キ)れて来て見付通れば花に月 蓬里雨→花・月・恋(「斵(キ)れる」=「女との縁を切る」、「見付」=「見付遊郭」、「花」=春で「春の月」、定石は夏の月。)
(ナオ「十一句目」)
先ず孫に月見団子をわけてやり 蓬里雨→月(「月見団子」=秋、「人情自」の秋の月。)
(ナウ「五句目」)
此度は花見にさとの母連れて 蓬里雨→花(「花見」=春。「人情自他半」の花。)
三吟の場合は、「A→B→C」の順を繰り返すと、「B」が「二花三月」を独占するので、宗匠・主宰(「捌き」)が、「A=発句と月、B=花と月、C=花と月」などと、「月花一句」(「月と花の句は、一人で独占しないで、他の連衆にも配分する)というルール」で、捌いていくのだが、その配慮は、ここでは完全に無視されている。
これらを肯定的に解するると、仙台(東北帝大)に赴任する「蓬里雨(連衆=芭蕉俳諧研究家・独逸文学者・漱石門」への最大限の餞として、「東洋城・寅日子・蓬里雨」座の、「東洋城(俳諧宗匠・『渋柿』主宰・漱石門)と寅日子(連衆=俳諧研究家・物理学者・漱石門)・との二人が、意図的に、送別する「脇=蓬里雨」に、この連句の「月の座・花の座」の、いわゆる、「花を持たせる」という進行をしたと解することもできよう。
(参考)「『3、月の句の心得』・『4.花の句の心得』・『5.恋の句の心得』・『6.特別扱いの句』・『7.句の続け方』・『8.季移り』・『9.付け順』・10.『「付け」と「転じ」』周辺(抜粋)
http://hakuhyodo.my.coocan.jp/kuzu/renku.html
[3.月の句の心得
(1) 月の句は春夏秋冬いずれの月を出してもよい。
(2) ただし、発句が秋季の場合には、第五句目の定座の月を「引き上げ」て、三句目までに月の句(これは秋の月とする)を詠むのが原則。
(3) 月の定座で、「月」や「有明」という語を出すのがまずい場合には、月の異名・(「桂男」とか「玉兎」など)を用いる。どういうのがまずいのかというと、表六句のうちに、「月」を含む言葉が使われており、定座で「月」を出すと「月」がだぶる場合、たとえば発句に如月とか霜月(これを月並の月という)などが出た場合。つまり、空の月は moon で、月並の月は month というわけ。
(4) 月の定座では落月や無月の句はできるだけ慎む。
(5) 秋の句が三句~五句続く場合、その中のどこかで必ず月の句を詠む。この月がないのを素秋(すあき)といって嫌う。
(6) 「星月夜(ほしづくよ)」は秋の季語であるが、星の光が月のように明るい夜をさし、直接月を詠んだ言葉ではない。そこで、この語が発句に出たら、それに続く秋の句には月を詠み込まず素秋にする。そのかわり、他の季の句中に「有明」など月のかわりになるものを詠み込む。
(7) どうしても月を詠まねばならぬのに、前句の具合で付けにくい場合は、実際空に浮かぶ月だけではなく、想像上の月を付ける方法もあり、これを「思いあわせの月」という。
(例)
堪忍ならぬ七夕の照り 利平
名月のまに合せ度(たき)芋畑 芭蕉
上の例では、名月は実際の月ではなく、名月の料理に間に合せたいということで、「照り」と「月」の不調和を避けております。
(8) 月の字を一種の助字(「かな」「や」の類)として用いることがあり、これを「投げこみの月」という。
(例)
革足袋(かはたび)に地雪踏(ぢせつた)重き秋の霜 洒堂
伏見あたりの古手屋の月 芭蕉
4.花の句の心得
花といえば、春の桜とだいたい相場が決っております。特定銘柄の老舗だけに、格式も高く、あだやおろそかには扱えません。定座に用いる花の句には、桜の花を詠んでも「桜」といってはならず、必ず「花」という言葉を用います。もちろん、「桜」という言葉を使うこともありますけれども、それは正式な「花」の句としては認められず、同様に、「豆の花」なども正式の花にはなりません。つまり、歌の世界では、桜はもはや単に植物としての存在を超えたものとしてあるわけです。
(1) 四句目には特に軽い句を出すべきだから、花の句のように大切なものは出さない。
(2) 月と花とを一句のうちに詠み込むのは、一座に一句と限る。こういう句の季は、花にひかれて春となる。
(例)
月と花比良の高ねを北にして 芭蕉
(3) 花に桜をつけることは、特別の場合には許される。
(例)
辛崎の松は花より朧(おぼろ)にて 芭蕉
山はさくらをしをる春雨 尚白
例の発句は松を詠んだものであり、花は実体のない「根なしの花」だから、脇に桜を出してもかまわないとする。
(4) 一句の中に花と吉野を同居させるのはかまわないが、「花」に「吉野」を、「吉野」に「花」を付けてはいけない。(同様に「宇治」に「茶」を付けてはいけ ない)
(5) 短句(七七)には、好んで「花」を持ち出さない。(五七五のほうに詠みなさいということ)
(6) 月花一句のこと、つまり俳諧ではひとりの作者が月や花の句を独占してはならない。みんなに「花」を持たせるよう、適当に按配するのである。
(7) 花前の句は、花の句が詠みやすいように配慮する。つまり、花の定座の前では、「秋」の字や、恋の句は控えて、軽い句を作る。
5.恋の句の心得
蕉門俳諧の恋の句の特徴は、ことばそのものよりも恋の情や気持を大事にするところにあります。蕉風以前には、式目書なる便利なものを参考にして、恋のことばを選べばそれでよしとする風があり、その中には、「そひふし」「人妻」「若後家」「男狂」「長枕」などという中年好みのことばも多かったようです。しかし、芭蕉がそんなことばをむき出しで使うはずはなく、
ものいへば扇子に顔をかくされて 芭蕉
きぬぎぬのあまりかぼそくあてやかに 芭蕉
と、さすがに品のよい中にも強烈な印象を与える色香が漂っております。面白いのは、芭蕉俳諧ではもともと恋の句を出す回数が少なかったのですけれども、晩年にむかってその傾向は顕著となり、まず一巻中一句が普通になったことです。
(1) 初折の裏の第一句目、つまり折立(おったて)に恋句を出すことを、昔は「待兼(まちかね)の、恋」といって嫌ったが、蕉門ではそれにこだわらない。
(2) 付句に恋の句をさそうような含みのある句を「恋の呼び出し」といい、恋の句に続いて付けると恋になるが、一句独立しては恋の意を持たぬものを「恋離れ」という。また、前句が恋とも恋ともつかぬような句である時には、必ず恋の句を付けて、前句ともども恋にすべきである。
(例)
(a) 砧(きぬた)うたるゝ尼達の家 曽良
(b) あの月も恋ゆゑにこそ悲しけれ 翠桃
(c) 露とも消ね胸のいたきに 芭蕉
(d) 錦繍(きんしう)に時めく花の憎かりし 曽良
上の例では、(a)が恋なのかどうかはっきりしない句、つまり「恋の呼び出し」にあたり、それを受けた翠桃は原則通り恋の句を付けている。また、(d)は(c)が恋句であるからはじめて恋になるという意味で「恋離れ」に相当する。
(3) 花の定座の前には恋句を出さぬこと。これは「花の句」の項で説明したとおり、花の句の前にはなるべく軽い句を出すことから。ただし、恋句自体の中に花や月を詠みこむのは自由である。
6.特別扱いの句
歌仙三十六句のうち、最初から三番目までと最終の句とは、特別の名称でよばれ、またその取り扱いにもきまりがあります。その他の句は全部平句(ヒラク)といいます。
(1) 第一句 …… 発句または立句(たてく)。これには、歌仙興行の季節にかなった季語をもち、完全に独立した形と内容をそなえていることが要求される。ふつう、「や」とか「かな」という切字(きれじ)を用いるが、それは絶対条件ではなく、あくまでも内容が問われる。歌仙全体の気分を左右しかねないので、あまりに重々 しいものや、縁起の悪いものは嫌われる。
(2) 第二句 …… 脇句(わきく)または脇。「客発句、亭主脇」ということばがあり、一座の賓客格が発句を出し、亭主格がそれに脇を付ける慣習があった。いわば、挨拶を交す心である。脇句はぴったりと発句の調子・用語に付け、発展させすぎてはいけない。季節、題材、発句にあわせるのが原則である。体言留めが多い。
(例)
市中(まちなか)は物のにほひや夏の月 凡兆
あつしあつしと門々の声 芭蕉
(3) 第三句 …… 第三。脇句が発句にぴったりと付くのに対して、第三は転句にあたり、変化をもたらす。発句・脇が初春の句ならば、第三では中春か晩春というふうに、季節にも気を配るのはもちろん、内容も思い切って離れるのである。
留め方にもきまりがあって、ふつうは「に」「て」「にて」「らん」「もなし」などで留める(例外あり)。ただし、発句・脇の腰(終りの五文字、または七文字)に「て」の字があれば、第三には「て」留めを用いず、発句が「かな」留めの場合には、第三では「にて」留めを用いない。また、発句の切字に推量・疑問の助詞・助動詞を用いた場合は、第三では「らん」留めは用いない。
(4) 第四句 …… 特別の名称はないが、四句目は軽く付けるのが昔からの習い。
(5) 第三十六句 …… 挙句(あげく)。挙句はあっさりとつけるのをよしとする。挙句は発句の作者や脇句の作者(亭主)が作らず、一座の最初の一巡に執筆の句が入っていない場合には、執筆が作る。また、ここでは季を変えない。
7.句の続け方
連句には句数(くかず)と去嫌(さりきらい)というルールがあります。句数というのは、春なら春の句を最低何句続けねばならず、また何句以上続けてはいけないというきまりです。また、去嫌とは、たとえば同季の句が三句続いた場合、つぎに同じ季の句を出すには最低五句は隔てなければならない(これを「同季五句去り」という)というふうに、類似したものの接近を嫌うというきまりです。
(1) 春・秋は句数は三句から五句まで。同季五句去りとする。
(2) 夏・冬は句数は一句から三句まで(ふつうは二句)。同季二句去り。
(3) 神祇・釈教(神社仏閣、神道・仏教に関係するもの)は、句数一句より三句、二句去りとする。
(4) 恋は句数二句から五句まで。三句去り。
(5) 述懐・無常(懐古・遁世・老い・うき世、死・葬儀・霊魂など)は、句数一句から三句。三句去り。
(6) 山類(さんるい)・水辺(すいへん)(山・峰・岡・谷・麓、海・浦・川・池・湖・水・氷の類)は、句数は一句から三句。三句去り。ただし、異山類・異水辺(山と谷、海と川など)は打越(うちこし)、つまり一句去りでもよい。
(7) 人倫(人間生活に関すること)は二句去り。ただし、実際は句数・去嫌ともかなり自由に付けている。
(8) 国名・名所は、句数一句から二句。二句去り。
(9) 生類(生き物)は、句数一句から二句。同種なら二句去り、異種なら打越を嫌わず。
(10) 木類・草類は、句数一句から二句。二句去りだが、木と草とは打越を嫌わず。
(11) 降物(ふりもの 雨・露・雪など)・聳物(そびきもの 雲・霞・虹など)は、句数一句から二句。二句去りだが、降物と聳物とは打越を嫌わず。
(12) 時分(朝・昼・夕など)は、句数一句から二句。同時分なら三句去りだが、異時分なら打越を嫌わず。(夜分二句去り、ただし打越を嫌わぬものあり、とあるが、どれが夜分の句かということになると煩雑に過ぎるので、省略する)
8.季移り
俳諧ではある季から他の季に移る場合、ふつうその間に雑(ゾウ)とよばれる、特定の季に属さない句を入れます。なるほど、これはうまい工夫です。中間に、どちらの季節にあってもおかしくない句を挿入しておけば、ごく自然に進行するはずですから。
(例)
(a) 雲雀なく小田に土持比(ツチモツコロ)なれや (春)
(b) しとぎ祝うて下されにけり (雑)
(C) 片隅に虫歯かゝへて暮の月 (秋)
すこし脇道にそれますが、「しとぎ」というのは、水につけて軟らかくなった生米を、ペースト状の粉にしてからまるめたもので、神仏へのお供えなどに用いられるものです。
ところが、中間に雑の句をはさまず、直接季を転じて付けることもあり、これを「季移り」といいます。これは、露のように春・夏・秋三季にわたるものや、月のように四季にわたるもの、その他特定の季の季語になってはいても一年中あっておかしくないものを巧みに利用するわけです。季移りは、秋から冬へ、冬から秋へというような二季移りが普通ですけれども、三季移り(ただし、歌仙では一箇所に限られる)もあります。
(例1)
(a) 放(ハナチ)やるうづらの跡は見えもせず (秋)
(b) 稲の葉延(ハノビ)の力なきかぜ (夏)
前句は「鶉(うづら)」で秋、付句は「稲の葉延」で夏(晩夏)。この例の場合、(a) の秋の鶉を、(a)(b)の両句でかもしだされる景色を味わう際には夏の鶉と見かえて解釈します。鶉は夏にもいるから、不自然はないとするのです。
(例2)
(a) 露とも消ね胸のいたきに (秋)
(b) 錦繍に時めく花の憎かりし (春)
「露」は秋の季語ですが、三季にわたるので春の情景としてもおかしくないというわけです。
なお、雑すなわち無季の句は、句数・句去りの制約を受けません。ただし、むやみに雑の句ばかりを出して、歌仙一巻の調和を破壊することがあってはいけません。
9.付け順
複数の人間が集まって歌仙を興行する際に、どういう順で句を続けていくのか、これには「出勝(でがち)」と「膝送り」というふたつのやり方があります。
出勝は「付勝(つけがち)」ともいって、まずは発句以下ひとりひとり句を付けて、一巡したら、その後は各句ごとに連衆全員が付句を考え、早くできた人が句を執筆に言うか短冊に書いて提出します。それを宗匠が、必要なら指導を加えたうえで、次の付句を促すのです。いわば、早いもの順ですから、腕のいい人にはかなわないわけです。芭蕉の俳席では、このやり方はあまり採用されなかったようです。
膝送りは、一定の順序によって付け進めていくやり方で、人数(芭蕉の俳席では、ふつう二人から六、七人)によって、次のように決っております。なお、カッコ内は、月花の定座を示し、「』」は初折・名残の折それぞれの表・裏の区切りを示します。なお、七吟以上では定まった順番を見いだし難く、六吟には基本的な順序はあるものの、付け順はいろいろだそうです。また、ぼくたちが真似事をするにしても、五吟くらいが関の山でしょうから、ここでは両吟から五吟までについて解説します。独吟の順序は、……わかりますね。
(1) 両吟(二人)
A,B,B,A,A(月),B』
B,A,A,B,B,A,A,B(月),B,A,A(花),B[折端]』
B[折立],A,A,B,B,A,A,B,B,A,A(月),B』
B,A,A,B,B(花),A』
これは一見でたらめのように思われるかも知れないが、実は月・花、長句・短句がきわめて公平に配分されている。
(2) 三吟
基本的には、A,B,C,A,B,Cを最後まで繰り返すのだが、それではBが月・花の句を独占してしまう。実際には、Aは発句、BとCは花を一句ずつ、月の句はひとり一句を理想とするが、一人二句のこともある。この辺は座のなりゆきと、宗匠の判断によるのだろう。
(3) 四吟
各人が四句おき、二句おきに出るように(「二飛び四飛び」という)、
A,B,C,D-B,A,D,C
を繰返す。これだと、Aには発句と花・月ひとつずつ、Bには月二つ、Cには花ひとつがあたるけれども、Dには定座があたらない。そこで、月の座を引き上げたり、後半で順序を変更している例もある。
(4) 五吟 三十六句を五人で割れば一句あまるので、最初の一巡の後で執筆がその一句を担当して数を合せる。執筆をFとすれば、
A,B,C,D,E(月),F』
B,A,D,C,A,E,C,B(月),E,D,B(花),A』
D,C,A,E,C,B,E,D,B,A,D(月),C』
A,E,C,B,E(花),D』
これではAとCには月・花の定座はあたらないので、やはり座を引き上げたりして調節しているようだ。
10.「付け」と「転じ」
すでに見たように、俳諧ではAにBを付け、BにCを付け、しかもAとBで構成される世界は、BとCとで新たに構成される世界によって「転じ」られることになります。こうして、付けることによって転じられるという「変化」が生ずるわけです。
「付け」については、蕉風よりはるか以前から様々の分類がなされておりますが、それを細かに検討することは即席入門の範囲を越えますので、ここでは触れません。『去来抄』にいう「物付」、「心付」、「匂い付」は、ふつうそれぞれ貞門、談林、蕉風にあてはめられております。しかし、貞門の付合(ツケアイ、寄合ともいい、付け方のこと)のすべてが物付で、蕉風ならば匂い付とするのは間違いで、貞門にも心付志向あれば、蕉風にも物付の例はあります。
(1) 物付 …… 宇治なら茶というふうに、前句のことばや物に縁のあることばを用いて付けていくやりかた。
(例)
歌いづれ小町をどりや伊勢踊 貞徳
どこの盆にかおりやるつらゆき 同
上の例では、「小町」「伊勢」から「貫之」、「踊」から「盆」が出ている。
(2) 心付 …… 前句のもつ意味や心持に応じて付ける(句意付)やりかた。
(例)
子をいだきつゝのり物のうち 宗因
度々の嫁入するは恥知らず 同
子供を抱きながら乗り物に乗っている女を、子持ちの再婚ととらえて、からかっている。
さて、肝心の匂い付ですが、広く言えば心付に含まれるとも考えられ、蕉門の場合は、前句の意味に即して付けるというよりも、前句の持つ気分・余情を把握した上で、それに響きあう内容の句を付けることが多い(当然句意付もあるわけです)と考えればよいでしょう。
「付合」が付けの種類をいうことばなら、付けの手法・態度を「付心」といい、その結果得られる効果を「付味」といいます。 ]
[東洋城・五十歳。塩原に句碑建立。伊予に遊ぶ。芥川龍之介自殺。「添削実相」掲載始まる。]

〇松根東洋城両面碑 塩湧橋先
【碑文】
「さまみえて土になりゐる落葉哉」表
「すずしさやこの山水に出湯とは」裏 (塩原四季郷より)
http://hotyu.starfree.jp/historicalspots/bungakuhi/bungakuhi.html
『東洋城全句集(上巻)』の「昭和二年」には、「塩原・四季郷」と題して、三十二句が収載されている。また、『東洋城全句集(中巻)』には、「昭和二年七月、塩原四季郷両面碑(西面)前にて」と題しての、当時の東洋城の肖像写真が掲載されている。この時の句に、上記の「両面句碑」の句に似た、次のような句がある。
涼しさや橋の下なる碧き山
涼しさや街道一つみえゐる灯(前書「瞰(かん) 流亭」)
径(ミチ)岐(キ)していづれか深き落葉かな
[寅彦=寅日子・五十歳
file:///C:/Users/user/Downloads/%E5%AF%BA%E7%94%B0%E5%AF%85%E5%BD%A6%E5%B9%B4%E8%A1%A8.pdf
3月10日、前年12月に辞職希望を申し出ていたが、理学部勤務を免ぜられ、地震研究所所員専任となる。3月12日、帝国学士院で“On Thermoelectric and Electrothermal Properties of Bismuth Single Crystal”(with T. Tsutsui)を発表。3月15日、地震研究所談話会で「砂の崩れ方の話」(宮部直巳と共著)を発表。
4月2日、数学物理学会で“Some Experiments on Periodic From of Convection Currents”(with Second Year Students)を発表。4月12日、帝国学士院で“On Thermoelectric Phenomena of Thin Metallic Films”(with S. Tanaka and S. Kusaba)を発表。4月19日、地震研究所談話会で「地球の激震帯と其長周期移動」(宮部と共著)を発表。
5月11日、帝国学士院“On a Long Period Fluctuation in Latitude of the the Macroseismic Zone of the Earth”(with N. Miyabe)を発表。5月17日、地震研究所談話会で「弾性波の実験(第二報)」(坪井と共著)および「日本海沿岸の島列に就て」を発表。5月30日、航空学談話会で「風の短周期変化に就て」(玉井光男と共著)。
6月21日、地震研究談話会で「沿岸島列に就て」および「島弧の生成に関する実験」(宮部と共著)を発表。7月12日、帝国学士院で“On the Vortical Motion of Fluid Produced by Rotating Body”(with K. Hattori)を発表。
9月20日、地震研究所談話会で「土佐南海岸の汀線変化に就て」(岸上冬彦・小平孝雄と共著)および「統計地震学に於けるSchwankung の理論の応用」(岸上・河角広と共著)を発表。
10月12日、帝国学士院で“Formation of Periodic Columnar Vortices by Convection”および“Residual Thermoelectric Phenomena of Apparently Homogeneous Wire”(with T. Tsutsui and M.Tamano)を発表。10月14日、水産講習所の海洋調査担当官会議で「大気の運動に就て」を講演。
10月18日、地震研究所談話会で「弾性波の実験(第三報)」(坪井と共著)、「微動遮断に関する堀の効果」(坪井と共著)および「砂の崩壊に就て」(宮部と共著)を発表。11月15日、地震研究所談話会で「本邦に於ける近年の山崩の分布」を発表。
12月12日、帝国学士院で“On the Mechanism of Formation of Step-Faults in Sand Layers—A Possible Analogy with Slip Bands in Deformed Metallic Crystals”(with N. Miyabe)を発表。この年の秋頃よりアイヌ語、マレイ語などの辞典から土佐の地名の語源を捜すことを試みる。
「断片」、『明星』、1月。
「備忘録」、『思想』、9月。
「Odisin no Okorikata ni kwansuru hitotuno Syukisei」、『RS』、9月。
「松島より」、『渋柿』、9月。
「怪異考」、『思想』、11月。
「昭和二年の二科会と美術院」、『霊山美術』、11月。
「人の言葉—自分の言葉」、『東京帝国大学理学部会誌』、12月。 ]
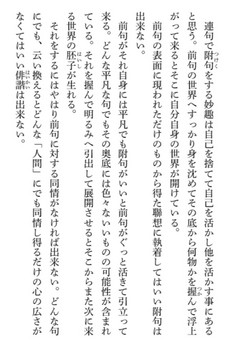
「断片」、『明星』、1月。(抜粋)
https://aozora-dev.binb.jp/reader/main.html?cid=42221
[豊隆(蓬里雨)・昭和二年(一九二七)、四十四歳。七月翻訳ストリンドベリ『父』出版。十二月翻訳ストリンドベリ『幽霊曲』(岩波文庫)出版。]
「歌仙『みちのく人の巻』(昭和二年二月「渋柿」)」
オ
送別
あすよりはみちのく人や春の雨 東洋城
まだ雪のこる西側の山 蓬里雨
沈丁花こぼるゝ里に移り来て 寅日子
筧は口をつけぬならはし 城
庭の木に梟来て啼く明けの月 雨 月
納豆うれしき肌寒の朝 子
ウ
年々を脚気の癒ゆる露深み 城
あすからかゝる約束の本 雨
切貼の馴れぬ手振もうら若く 子
母子(オヤコ)小町と唄はれにけり 城
一々に値上げ煙草の詫をいひ 雨
蠅取紙に光る秋の日 子
鰡(ボラ)鰯秋刀魚のきほふ魚の棚 城
蹇(アシナエ)の子のギス飼うてゐる 雨
針程のことを兎角に言ひつのり 子
白いうなじをふるはせて泣く 城 恋
斵(キ)れて来て見付通れば花に月 雨 花・月・恋
誰が捨てたか土手の猫の子 子
ナオ
蠶(コ)の頃の苗代の頃の忙しさ 城
家出の兄のよこす長文 雨
繰り言も浮世長屋の隣同士 子
箍(タガ)のはじけた桶提げて行く 城
大木の榎実こぼるゝ塀の前 雨
流れにまかせ葦を刈る船 子
悲しきは謡の中の秋の風 城
義理立たねばとあかで別るゝ 雨 恋
腰掛に一夜仮寝の夢覚めて 子 恋
朝のうちからわかる雷 城
先ず孫に月見団子をわけてやり 雨 月
白い紅いはおしろいの花 子
ナウ
秋の空丘の丸きに家建ちて 城
踏切越せば税関がある 雨
夜もすがら何処の鍛冶屋の鎚(ツチ)の音 子
幾日の果ての葬(ホフリ)悲しき 城
此度は花見にさとの母連れて 雨 花
小鮎の鰭(ヒレ)にいさゝかの色 子
※ この三吟歌仙で目立つのは、「二花三月」の「月・花の定座」を、脇句作者の「蓬里雨」が独占しているということである。
(オ「五句目」)
庭の木に梟来て啼く明けの月 蓬里 雨→月(「梟」=冬、冬の月、定石は秋の月。)
(ウ「十一句目」)
斵(キ)れて来て見付通れば花に月 蓬里雨→花・月・恋(「斵(キ)れる」=「女との縁を切る」、「見付」=「見付遊郭」、「花」=春で「春の月」、定石は夏の月。)
(ナオ「十一句目」)
先ず孫に月見団子をわけてやり 蓬里雨→月(「月見団子」=秋、「人情自」の秋の月。)
(ナウ「五句目」)
此度は花見にさとの母連れて 蓬里雨→花(「花見」=春。「人情自他半」の花。)
三吟の場合は、「A→B→C」の順を繰り返すと、「B」が「二花三月」を独占するので、宗匠・主宰(「捌き」)が、「A=発句と月、B=花と月、C=花と月」などと、「月花一句」(「月と花の句は、一人で独占しないで、他の連衆にも配分する)というルール」で、捌いていくのだが、その配慮は、ここでは完全に無視されている。
これらを肯定的に解するると、仙台(東北帝大)に赴任する「蓬里雨(連衆=芭蕉俳諧研究家・独逸文学者・漱石門」への最大限の餞として、「東洋城・寅日子・蓬里雨」座の、「東洋城(俳諧宗匠・『渋柿』主宰・漱石門)と寅日子(連衆=俳諧研究家・物理学者・漱石門)・との二人が、意図的に、送別する「脇=蓬里雨」に、この連句の「月の座・花の座」の、いわゆる、「花を持たせる」という進行をしたと解することもできよう。
(参考)「『3、月の句の心得』・『4.花の句の心得』・『5.恋の句の心得』・『6.特別扱いの句』・『7.句の続け方』・『8.季移り』・『9.付け順』・10.『「付け」と「転じ」』周辺(抜粋)
http://hakuhyodo.my.coocan.jp/kuzu/renku.html
[3.月の句の心得
(1) 月の句は春夏秋冬いずれの月を出してもよい。
(2) ただし、発句が秋季の場合には、第五句目の定座の月を「引き上げ」て、三句目までに月の句(これは秋の月とする)を詠むのが原則。
(3) 月の定座で、「月」や「有明」という語を出すのがまずい場合には、月の異名・(「桂男」とか「玉兎」など)を用いる。どういうのがまずいのかというと、表六句のうちに、「月」を含む言葉が使われており、定座で「月」を出すと「月」がだぶる場合、たとえば発句に如月とか霜月(これを月並の月という)などが出た場合。つまり、空の月は moon で、月並の月は month というわけ。
(4) 月の定座では落月や無月の句はできるだけ慎む。
(5) 秋の句が三句~五句続く場合、その中のどこかで必ず月の句を詠む。この月がないのを素秋(すあき)といって嫌う。
(6) 「星月夜(ほしづくよ)」は秋の季語であるが、星の光が月のように明るい夜をさし、直接月を詠んだ言葉ではない。そこで、この語が発句に出たら、それに続く秋の句には月を詠み込まず素秋にする。そのかわり、他の季の句中に「有明」など月のかわりになるものを詠み込む。
(7) どうしても月を詠まねばならぬのに、前句の具合で付けにくい場合は、実際空に浮かぶ月だけではなく、想像上の月を付ける方法もあり、これを「思いあわせの月」という。
(例)
堪忍ならぬ七夕の照り 利平
名月のまに合せ度(たき)芋畑 芭蕉
上の例では、名月は実際の月ではなく、名月の料理に間に合せたいということで、「照り」と「月」の不調和を避けております。
(8) 月の字を一種の助字(「かな」「や」の類)として用いることがあり、これを「投げこみの月」という。
(例)
革足袋(かはたび)に地雪踏(ぢせつた)重き秋の霜 洒堂
伏見あたりの古手屋の月 芭蕉
4.花の句の心得
花といえば、春の桜とだいたい相場が決っております。特定銘柄の老舗だけに、格式も高く、あだやおろそかには扱えません。定座に用いる花の句には、桜の花を詠んでも「桜」といってはならず、必ず「花」という言葉を用います。もちろん、「桜」という言葉を使うこともありますけれども、それは正式な「花」の句としては認められず、同様に、「豆の花」なども正式の花にはなりません。つまり、歌の世界では、桜はもはや単に植物としての存在を超えたものとしてあるわけです。
(1) 四句目には特に軽い句を出すべきだから、花の句のように大切なものは出さない。
(2) 月と花とを一句のうちに詠み込むのは、一座に一句と限る。こういう句の季は、花にひかれて春となる。
(例)
月と花比良の高ねを北にして 芭蕉
(3) 花に桜をつけることは、特別の場合には許される。
(例)
辛崎の松は花より朧(おぼろ)にて 芭蕉
山はさくらをしをる春雨 尚白
例の発句は松を詠んだものであり、花は実体のない「根なしの花」だから、脇に桜を出してもかまわないとする。
(4) 一句の中に花と吉野を同居させるのはかまわないが、「花」に「吉野」を、「吉野」に「花」を付けてはいけない。(同様に「宇治」に「茶」を付けてはいけ ない)
(5) 短句(七七)には、好んで「花」を持ち出さない。(五七五のほうに詠みなさいということ)
(6) 月花一句のこと、つまり俳諧ではひとりの作者が月や花の句を独占してはならない。みんなに「花」を持たせるよう、適当に按配するのである。
(7) 花前の句は、花の句が詠みやすいように配慮する。つまり、花の定座の前では、「秋」の字や、恋の句は控えて、軽い句を作る。
5.恋の句の心得
蕉門俳諧の恋の句の特徴は、ことばそのものよりも恋の情や気持を大事にするところにあります。蕉風以前には、式目書なる便利なものを参考にして、恋のことばを選べばそれでよしとする風があり、その中には、「そひふし」「人妻」「若後家」「男狂」「長枕」などという中年好みのことばも多かったようです。しかし、芭蕉がそんなことばをむき出しで使うはずはなく、
ものいへば扇子に顔をかくされて 芭蕉
きぬぎぬのあまりかぼそくあてやかに 芭蕉
と、さすがに品のよい中にも強烈な印象を与える色香が漂っております。面白いのは、芭蕉俳諧ではもともと恋の句を出す回数が少なかったのですけれども、晩年にむかってその傾向は顕著となり、まず一巻中一句が普通になったことです。
(1) 初折の裏の第一句目、つまり折立(おったて)に恋句を出すことを、昔は「待兼(まちかね)の、恋」といって嫌ったが、蕉門ではそれにこだわらない。
(2) 付句に恋の句をさそうような含みのある句を「恋の呼び出し」といい、恋の句に続いて付けると恋になるが、一句独立しては恋の意を持たぬものを「恋離れ」という。また、前句が恋とも恋ともつかぬような句である時には、必ず恋の句を付けて、前句ともども恋にすべきである。
(例)
(a) 砧(きぬた)うたるゝ尼達の家 曽良
(b) あの月も恋ゆゑにこそ悲しけれ 翠桃
(c) 露とも消ね胸のいたきに 芭蕉
(d) 錦繍(きんしう)に時めく花の憎かりし 曽良
上の例では、(a)が恋なのかどうかはっきりしない句、つまり「恋の呼び出し」にあたり、それを受けた翠桃は原則通り恋の句を付けている。また、(d)は(c)が恋句であるからはじめて恋になるという意味で「恋離れ」に相当する。
(3) 花の定座の前には恋句を出さぬこと。これは「花の句」の項で説明したとおり、花の句の前にはなるべく軽い句を出すことから。ただし、恋句自体の中に花や月を詠みこむのは自由である。
6.特別扱いの句
歌仙三十六句のうち、最初から三番目までと最終の句とは、特別の名称でよばれ、またその取り扱いにもきまりがあります。その他の句は全部平句(ヒラク)といいます。
(1) 第一句 …… 発句または立句(たてく)。これには、歌仙興行の季節にかなった季語をもち、完全に独立した形と内容をそなえていることが要求される。ふつう、「や」とか「かな」という切字(きれじ)を用いるが、それは絶対条件ではなく、あくまでも内容が問われる。歌仙全体の気分を左右しかねないので、あまりに重々 しいものや、縁起の悪いものは嫌われる。
(2) 第二句 …… 脇句(わきく)または脇。「客発句、亭主脇」ということばがあり、一座の賓客格が発句を出し、亭主格がそれに脇を付ける慣習があった。いわば、挨拶を交す心である。脇句はぴったりと発句の調子・用語に付け、発展させすぎてはいけない。季節、題材、発句にあわせるのが原則である。体言留めが多い。
(例)
市中(まちなか)は物のにほひや夏の月 凡兆
あつしあつしと門々の声 芭蕉
(3) 第三句 …… 第三。脇句が発句にぴったりと付くのに対して、第三は転句にあたり、変化をもたらす。発句・脇が初春の句ならば、第三では中春か晩春というふうに、季節にも気を配るのはもちろん、内容も思い切って離れるのである。
留め方にもきまりがあって、ふつうは「に」「て」「にて」「らん」「もなし」などで留める(例外あり)。ただし、発句・脇の腰(終りの五文字、または七文字)に「て」の字があれば、第三には「て」留めを用いず、発句が「かな」留めの場合には、第三では「にて」留めを用いない。また、発句の切字に推量・疑問の助詞・助動詞を用いた場合は、第三では「らん」留めは用いない。
(4) 第四句 …… 特別の名称はないが、四句目は軽く付けるのが昔からの習い。
(5) 第三十六句 …… 挙句(あげく)。挙句はあっさりとつけるのをよしとする。挙句は発句の作者や脇句の作者(亭主)が作らず、一座の最初の一巡に執筆の句が入っていない場合には、執筆が作る。また、ここでは季を変えない。
7.句の続け方
連句には句数(くかず)と去嫌(さりきらい)というルールがあります。句数というのは、春なら春の句を最低何句続けねばならず、また何句以上続けてはいけないというきまりです。また、去嫌とは、たとえば同季の句が三句続いた場合、つぎに同じ季の句を出すには最低五句は隔てなければならない(これを「同季五句去り」という)というふうに、類似したものの接近を嫌うというきまりです。
(1) 春・秋は句数は三句から五句まで。同季五句去りとする。
(2) 夏・冬は句数は一句から三句まで(ふつうは二句)。同季二句去り。
(3) 神祇・釈教(神社仏閣、神道・仏教に関係するもの)は、句数一句より三句、二句去りとする。
(4) 恋は句数二句から五句まで。三句去り。
(5) 述懐・無常(懐古・遁世・老い・うき世、死・葬儀・霊魂など)は、句数一句から三句。三句去り。
(6) 山類(さんるい)・水辺(すいへん)(山・峰・岡・谷・麓、海・浦・川・池・湖・水・氷の類)は、句数は一句から三句。三句去り。ただし、異山類・異水辺(山と谷、海と川など)は打越(うちこし)、つまり一句去りでもよい。
(7) 人倫(人間生活に関すること)は二句去り。ただし、実際は句数・去嫌ともかなり自由に付けている。
(8) 国名・名所は、句数一句から二句。二句去り。
(9) 生類(生き物)は、句数一句から二句。同種なら二句去り、異種なら打越を嫌わず。
(10) 木類・草類は、句数一句から二句。二句去りだが、木と草とは打越を嫌わず。
(11) 降物(ふりもの 雨・露・雪など)・聳物(そびきもの 雲・霞・虹など)は、句数一句から二句。二句去りだが、降物と聳物とは打越を嫌わず。
(12) 時分(朝・昼・夕など)は、句数一句から二句。同時分なら三句去りだが、異時分なら打越を嫌わず。(夜分二句去り、ただし打越を嫌わぬものあり、とあるが、どれが夜分の句かということになると煩雑に過ぎるので、省略する)
8.季移り
俳諧ではある季から他の季に移る場合、ふつうその間に雑(ゾウ)とよばれる、特定の季に属さない句を入れます。なるほど、これはうまい工夫です。中間に、どちらの季節にあってもおかしくない句を挿入しておけば、ごく自然に進行するはずですから。
(例)
(a) 雲雀なく小田に土持比(ツチモツコロ)なれや (春)
(b) しとぎ祝うて下されにけり (雑)
(C) 片隅に虫歯かゝへて暮の月 (秋)
すこし脇道にそれますが、「しとぎ」というのは、水につけて軟らかくなった生米を、ペースト状の粉にしてからまるめたもので、神仏へのお供えなどに用いられるものです。
ところが、中間に雑の句をはさまず、直接季を転じて付けることもあり、これを「季移り」といいます。これは、露のように春・夏・秋三季にわたるものや、月のように四季にわたるもの、その他特定の季の季語になってはいても一年中あっておかしくないものを巧みに利用するわけです。季移りは、秋から冬へ、冬から秋へというような二季移りが普通ですけれども、三季移り(ただし、歌仙では一箇所に限られる)もあります。
(例1)
(a) 放(ハナチ)やるうづらの跡は見えもせず (秋)
(b) 稲の葉延(ハノビ)の力なきかぜ (夏)
前句は「鶉(うづら)」で秋、付句は「稲の葉延」で夏(晩夏)。この例の場合、(a) の秋の鶉を、(a)(b)の両句でかもしだされる景色を味わう際には夏の鶉と見かえて解釈します。鶉は夏にもいるから、不自然はないとするのです。
(例2)
(a) 露とも消ね胸のいたきに (秋)
(b) 錦繍に時めく花の憎かりし (春)
「露」は秋の季語ですが、三季にわたるので春の情景としてもおかしくないというわけです。
なお、雑すなわち無季の句は、句数・句去りの制約を受けません。ただし、むやみに雑の句ばかりを出して、歌仙一巻の調和を破壊することがあってはいけません。
9.付け順
複数の人間が集まって歌仙を興行する際に、どういう順で句を続けていくのか、これには「出勝(でがち)」と「膝送り」というふたつのやり方があります。
出勝は「付勝(つけがち)」ともいって、まずは発句以下ひとりひとり句を付けて、一巡したら、その後は各句ごとに連衆全員が付句を考え、早くできた人が句を執筆に言うか短冊に書いて提出します。それを宗匠が、必要なら指導を加えたうえで、次の付句を促すのです。いわば、早いもの順ですから、腕のいい人にはかなわないわけです。芭蕉の俳席では、このやり方はあまり採用されなかったようです。
膝送りは、一定の順序によって付け進めていくやり方で、人数(芭蕉の俳席では、ふつう二人から六、七人)によって、次のように決っております。なお、カッコ内は、月花の定座を示し、「』」は初折・名残の折それぞれの表・裏の区切りを示します。なお、七吟以上では定まった順番を見いだし難く、六吟には基本的な順序はあるものの、付け順はいろいろだそうです。また、ぼくたちが真似事をするにしても、五吟くらいが関の山でしょうから、ここでは両吟から五吟までについて解説します。独吟の順序は、……わかりますね。
(1) 両吟(二人)
A,B,B,A,A(月),B』
B,A,A,B,B,A,A,B(月),B,A,A(花),B[折端]』
B[折立],A,A,B,B,A,A,B,B,A,A(月),B』
B,A,A,B,B(花),A』
これは一見でたらめのように思われるかも知れないが、実は月・花、長句・短句がきわめて公平に配分されている。
(2) 三吟
基本的には、A,B,C,A,B,Cを最後まで繰り返すのだが、それではBが月・花の句を独占してしまう。実際には、Aは発句、BとCは花を一句ずつ、月の句はひとり一句を理想とするが、一人二句のこともある。この辺は座のなりゆきと、宗匠の判断によるのだろう。
(3) 四吟
各人が四句おき、二句おきに出るように(「二飛び四飛び」という)、
A,B,C,D-B,A,D,C
を繰返す。これだと、Aには発句と花・月ひとつずつ、Bには月二つ、Cには花ひとつがあたるけれども、Dには定座があたらない。そこで、月の座を引き上げたり、後半で順序を変更している例もある。
(4) 五吟 三十六句を五人で割れば一句あまるので、最初の一巡の後で執筆がその一句を担当して数を合せる。執筆をFとすれば、
A,B,C,D,E(月),F』
B,A,D,C,A,E,C,B(月),E,D,B(花),A』
D,C,A,E,C,B,E,D,B,A,D(月),C』
A,E,C,B,E(花),D』
これではAとCには月・花の定座はあたらないので、やはり座を引き上げたりして調節しているようだ。
10.「付け」と「転じ」
すでに見たように、俳諧ではAにBを付け、BにCを付け、しかもAとBで構成される世界は、BとCとで新たに構成される世界によって「転じ」られることになります。こうして、付けることによって転じられるという「変化」が生ずるわけです。
「付け」については、蕉風よりはるか以前から様々の分類がなされておりますが、それを細かに検討することは即席入門の範囲を越えますので、ここでは触れません。『去来抄』にいう「物付」、「心付」、「匂い付」は、ふつうそれぞれ貞門、談林、蕉風にあてはめられております。しかし、貞門の付合(ツケアイ、寄合ともいい、付け方のこと)のすべてが物付で、蕉風ならば匂い付とするのは間違いで、貞門にも心付志向あれば、蕉風にも物付の例はあります。
(1) 物付 …… 宇治なら茶というふうに、前句のことばや物に縁のあることばを用いて付けていくやりかた。
(例)
歌いづれ小町をどりや伊勢踊 貞徳
どこの盆にかおりやるつらゆき 同
上の例では、「小町」「伊勢」から「貫之」、「踊」から「盆」が出ている。
(2) 心付 …… 前句のもつ意味や心持に応じて付ける(句意付)やりかた。
(例)
子をいだきつゝのり物のうち 宗因
度々の嫁入するは恥知らず 同
子供を抱きながら乗り物に乗っている女を、子持ちの再婚ととらえて、からかっている。
さて、肝心の匂い付ですが、広く言えば心付に含まれるとも考えられ、蕉門の場合は、前句の意味に即して付けるというよりも、前句の持つ気分・余情を把握した上で、それに響きあう内容の句を付けることが多い(当然句意付もあるわけです)と考えればよいでしょう。
「付合」が付けの種類をいうことばなら、付けの手法・態度を「付心」といい、その結果得られる効果を「付味」といいます。 ]
「東洋城・寅彦、そして、豊隆」(漱石没後~寅彦没まで)俳句・連句管見(その十) [東洋城・寅日子(寅彦)・蓬里雨(豊隆)]
その十「大正十五年・昭和元年(一九二六)」
[東洋城・四十九歳。月一回、寅彦と会合して連句を作る。大正天皇崩御され「大正天皇と私」連載。叡山に登る。]

「1927年(昭和2年)、大正天皇の大喪」(「ウィキペディア」)
(「大正天皇と私」より六句)
冬ごもり何に泣きたる涙かな
人の子におはす涙や時鳥
維武揚る微臣秋天をうたふべく
いくさ船並ぶや海の原の秋
草も木もこがらし防げ君が為め(前書「謹祷」)
神去りましゝ夜の凍る大地かな(前書「百姓相泣」)
[寅彦=寅日子・四十九歳
file:///C:/Users/user/Downloads/%E5%AF%BA%E7%94%B0%E5%AF%85%E5%BD%A6%E5%B9%B4%E8%A1%A8.pdf
1月20日、東京帝国大学地震研究所所員に補せられる。理学部教授はそのまま。2月8日、航空学談話会で「流体の運動に関する二三の実験(第一報)」を発表。3月13日、数学物理学会で“On theEffects of Winds on Sea-Level”(with S. Yamaguti)を発表。4月3日、数学物理学会で“Reports onSome Experiments on Motions of Fluid, Made by Students”を発表。5月20日、長女森貞子に男子博芳が誕生。6月6日、母亀が本郷区曙町の家で死去(84歳)。6月12日、帝国学士院で“A Preliminary Noteon the Form and Stucture of Long Spark”(with U. Nakaya)および“Propagation of Combustion inGaseous Mixture”(with K. Yumoto)を発表。6月22日、地震研究所談話会で「砂の崩れ方の話」および「不規則な衝撃に依る振動体の振動」を発表。11月1日、航空学談話会で「水の運動に関する実験」(服部邦男と共著)を発表。12月21日、地震研究所談話会で「弾性波の実験(第一報)
」(坪井忠二と共著)を発表。談話「火災論の論議に就て」、『日本消防新聞』、1月。
「TRSO」、『潮音』、1〜5月。
「新三つ物」、『渋柿』、2〜6月。
「俳諧六つ物」、『渋柿』、2月。
「俳諧 二枚折」、『渋柿』、7月。
「俳諧 二つ折」、『渋柿』、9月。
「書簡」、『アララギ』、10月。
「俳諧 二枚屏風」、『渋柿』、12月。 ]
※「TRSO『潮音』、1〜5月」の、連句新形式の「トルソー」関連については、次のアドレスで触れている。
https://yahan.blog.ss-blog.jp/2023-11-06
(再掲)
[▽トルソー 首および四肢を欠く胴体だけの彫像
▽「澁柿」俳誌。大正四年(一九一五)二月創刊。主宰・松根東洋城(明治十一~昭和三九)。誌名は、大正天皇が俳句につきご下問、東洋城が奉答した句「渋柿のごときものにては候へど」による。昭和二七年東洋城隠退し野村喜舟が主宰となる。平成十七年十二月号で一千百号(連句協会報一六一号)。「渋柿はその芭蕉に於いてなされし如く連句を大切にす。之により多くの俳諧を闡明(せんめい)拡充し高揚す」
TORSO(大正十四年八月『渋柿』)
シヤコンヌや国は亡びし歌の秋 寅日子
ラディオにたかる肌寒の群 ゝ
屋根裏は月さす窓の奢りにて 蓬里雨
古里遠し母病むといふ文 ゝ
新しきシャツのボタンのふと取れし 子
手函の底に枯るゝ白薔薇 ゝ
忘れにしあらねど恋はもの憂くて 雨
春雨の夜を忍び音のセロ 子
見下ろせば暗き彼方は海に似て 雨 ]
※「新三つ物(渋柿』2〜6月)」周辺
「新三つ物」(大正十五年六月「渋柿」)
吾が前を行く傀儡(クグツ)なりけり 東洋城
木枯の吼ゆる大路の黄昏に 寅日子
板橋通ひガタ馬車に乗る 蓬里雨
谷の深きに紅葉見るまで 寅日子
欄干に干す手拭の蝶々や 蓬里雨
湯治の日記(ニキ)の古い三月 東洋城
色々と娘の上のさたをして 東洋城
祭の寄附のいやもいはれず 寅日子
移り来て紅葉の色づく門構 蓬里雨
▽「新三つ物」=東洋城考案の「三つ物」(平句の三句形式)で、「三つ物/(三句)= 発句・脇・第三句の三句をいう。江戸時代から歳旦の祝詞として詠む習わしが生じ、明暦(一 六五五~五七)ごろから大流行となり、歳旦開きという行事までもが行われた。三句のう ち、月・花また神祇・釈経・恋など何を詠んでもよい。」の、それを柔軟にしたも。「発句・脇・第三」にとらわれず、平句(四句目以下の句)の「短句・長句・短句」など、「連句」の、謂わば、「トルソー」的な展開のもの(「俳諧 三つ物」=『東洋城全句集下巻』所収「大正十三年五月「渋柿」)。
※「俳諧六つ物(『渋柿』、2月)」周辺
臼の上には薪割(リ)の斧 東洋城
蕃椒(バンショウ)吊り干す軒さゝくれて 蓬里雨(※蕃椒=「トウガラシ」)
繭のあがつた噂している 寅日子
霧の中静に朝の江渡(ワタシ)して 城
朱盆の様な日を仰ぎけり 雨
画廊から画廊は遠き馬車の上に 子
(以下、五連(「折・面」を省略)
▽「俳諧六つ物=東洋城考案の「新三つ物」(平句の三句形式)の「三句形式」を「六句形式」にしたもの。上記のものは、その「六つ物」を「歌仙」の「三十六句」形式(折・面=六×六)の六連(折・面)と続けている。
※「俳諧 二つ折(『渋柿』、9月)」・「俳諧 二枚折(『渋柿』、7月)」)・「俳諧 二枚屏風(『渋柿』、12月」)周辺
▽「俳諧 二つ折(『渋柿』、9月)」は、「六つ物」(六句形式)を「二つ折」(「表と裏」の十二句)」を基本とするもの。「俳諧 二枚折(『渋柿』、7月)」は、「俳諧 二つ折」(十二句)を二枚続けて、「(六句・六句)+(六句・六句)=二十四句」を基本とするもの。「俳諧 二枚屏風(『渋柿』、12月」)は、「俳諧 二つ折」(十二句)を二枚続けて、「(六句・六句)+(六句・六句)=二十四句」を、「二曲一双」屏風のように、「一枚目屏風(六句+六句)=右隻」と「二枚目屏風(六句+六句)=左隻」と、「対(主題)」の仕立てにする形式のもの。これは、「六曲一隻(六句+六句+六句+六句+六句+六句)」ものなど、様々なバリエーションのものがあろう。
https://www.nippon.com/ja/japan-data/h01096/
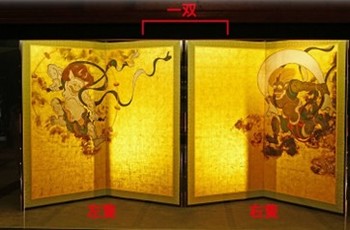
「二曲一双屏風」 (京都・建仁寺「風神雷神図」)
[豊隆(蓬里雨)・大正十三年(四十一歳)=東北大学教授となる。大正十五年(四十三歳)=芭蕉俳諧研究会を始める。五月合著『続々芭蕉俳句研究』出版。九月合訳ストリンドベリ全集『燕曲集』出版。]
https://yahan.blog.ss-blog.jp/2023-10-24
(再掲)
[[豊隆=蓬里雨・三十五歳。大正9年( 1920 )海軍大学校嘱託教授となる。大正10年 (1921 )芭蕉研究会に参加。]
※大正七年(1918)当時の豊隆は、『漱石全集』に取り組んでいて、「東洋城・寅日子・蓬里雨」の三吟歌仙とかは、大正十五年(1926)の頃が初出で、この頃は、「俳句・俳諧(連句)」には食指は伸ばしていなかったように思われる。大正十年(1921)の「芭蕉研究会」に参加は、東洋城の「渋柿」などとの「芭蕉研究会」ではなく、下記のアドレスのものなどによると、「太田水穂(歌誌「潮音」主宰)・幸田露伴・沼波瓊音・安倍能成・阿部次郎・小宮豊隆・和辻哲郎」らによる研究会のようである。
https://jyunku.hatenablog.com/entry/20100925/p1
「「芭蕉研究会」は田端の太田水穂(本名・貞一)宅で行われ、当初の会員は、阿部(次郎)、太田のほか、沼波瓊音、安倍能成、幸田露伴で、大正10年に小宮豊隆や和辻哲郎が加わった。」
この、阿部次郎・小宮豊隆らの「芭蕉研究会」の参加は、「大正15年( 1926) 芭蕉俳諧研究会を始める」と、「東北帝国大学」の「山田孝雄、村岡典嗣、岡崎義恵、太田正雄(木下杢太郎)」らの参加を得て、形を変えて継続されていくことになる。
https://www.library.tohoku.ac.jp/collection/collection/introduce.html ]
※「東洋城・寅日子(寅彦)・蓬里雨(豊隆)」の三者の中で、「芭蕉とその俳諧(連句・俳句)」周辺について最も造詣が深かったのは、大正十年(一九二一)の「芭蕉研究会」(太田水穂「歌誌『潮音』主宰)・幸田露伴・阿部次郎などの研究会)、そして、大正十五年(一九二六)の「芭蕉俳諧研究会」(東北帝大の同僚有志=阿部次郎・岡崎義恵・山田孝雄などによる研究会)で研鑽を積んでいた「蓬里雨(豊隆)」ということになろう。
その一端は、昭和十四年(一九三九)に刊行された『芭蕉俳諧論集』(小宮豊隆・横沢三郎編 岩波文庫)などで知ることができる。
https://dl.ndl.go.jp/pid/1684194/1/1
[『芭蕉俳諧論集』(小宮豊隆・横沢三郎編 岩波文庫)(「国立国会図書館デジタルコレクション」)
(「芭蕉俳諧論集・目次」)
序/3 (昭和十四年三月二十一日 小宮豊隆)
凡例/7
一、 心/21
二、 「風雅」/26
三、 「不易流行」/28
四、 「虛實」/38
五、 「さび、しをり、ほそみ」/41
六、 俳諧一般/45
(イ) 本質論/45
(ロ) 「修行敎」/57
(ハ) 個人評/73
七、 發句/89
(イ) 風體論/89
(ロ) 句作論/92
(ハ) 句評/111
八、 連句/215
(イ) 附合論/215
(ロ) 附句評/225
九、 作法/255
一〇、 雜/275
索引
索引に就いて/283
語句索引/287
句索引/297 ]
[東洋城・四十九歳。月一回、寅彦と会合して連句を作る。大正天皇崩御され「大正天皇と私」連載。叡山に登る。]

「1927年(昭和2年)、大正天皇の大喪」(「ウィキペディア」)
(「大正天皇と私」より六句)
冬ごもり何に泣きたる涙かな
人の子におはす涙や時鳥
維武揚る微臣秋天をうたふべく
いくさ船並ぶや海の原の秋
草も木もこがらし防げ君が為め(前書「謹祷」)
神去りましゝ夜の凍る大地かな(前書「百姓相泣」)
[寅彦=寅日子・四十九歳
file:///C:/Users/user/Downloads/%E5%AF%BA%E7%94%B0%E5%AF%85%E5%BD%A6%E5%B9%B4%E8%A1%A8.pdf
1月20日、東京帝国大学地震研究所所員に補せられる。理学部教授はそのまま。2月8日、航空学談話会で「流体の運動に関する二三の実験(第一報)」を発表。3月13日、数学物理学会で“On theEffects of Winds on Sea-Level”(with S. Yamaguti)を発表。4月3日、数学物理学会で“Reports onSome Experiments on Motions of Fluid, Made by Students”を発表。5月20日、長女森貞子に男子博芳が誕生。6月6日、母亀が本郷区曙町の家で死去(84歳)。6月12日、帝国学士院で“A Preliminary Noteon the Form and Stucture of Long Spark”(with U. Nakaya)および“Propagation of Combustion inGaseous Mixture”(with K. Yumoto)を発表。6月22日、地震研究所談話会で「砂の崩れ方の話」および「不規則な衝撃に依る振動体の振動」を発表。11月1日、航空学談話会で「水の運動に関する実験」(服部邦男と共著)を発表。12月21日、地震研究所談話会で「弾性波の実験(第一報)
」(坪井忠二と共著)を発表。談話「火災論の論議に就て」、『日本消防新聞』、1月。
「TRSO」、『潮音』、1〜5月。
「新三つ物」、『渋柿』、2〜6月。
「俳諧六つ物」、『渋柿』、2月。
「俳諧 二枚折」、『渋柿』、7月。
「俳諧 二つ折」、『渋柿』、9月。
「書簡」、『アララギ』、10月。
「俳諧 二枚屏風」、『渋柿』、12月。 ]
※「TRSO『潮音』、1〜5月」の、連句新形式の「トルソー」関連については、次のアドレスで触れている。
https://yahan.blog.ss-blog.jp/2023-11-06
(再掲)
[▽トルソー 首および四肢を欠く胴体だけの彫像
▽「澁柿」俳誌。大正四年(一九一五)二月創刊。主宰・松根東洋城(明治十一~昭和三九)。誌名は、大正天皇が俳句につきご下問、東洋城が奉答した句「渋柿のごときものにては候へど」による。昭和二七年東洋城隠退し野村喜舟が主宰となる。平成十七年十二月号で一千百号(連句協会報一六一号)。「渋柿はその芭蕉に於いてなされし如く連句を大切にす。之により多くの俳諧を闡明(せんめい)拡充し高揚す」
TORSO(大正十四年八月『渋柿』)
シヤコンヌや国は亡びし歌の秋 寅日子
ラディオにたかる肌寒の群 ゝ
屋根裏は月さす窓の奢りにて 蓬里雨
古里遠し母病むといふ文 ゝ
新しきシャツのボタンのふと取れし 子
手函の底に枯るゝ白薔薇 ゝ
忘れにしあらねど恋はもの憂くて 雨
春雨の夜を忍び音のセロ 子
見下ろせば暗き彼方は海に似て 雨 ]
※「新三つ物(渋柿』2〜6月)」周辺
「新三つ物」(大正十五年六月「渋柿」)
吾が前を行く傀儡(クグツ)なりけり 東洋城
木枯の吼ゆる大路の黄昏に 寅日子
板橋通ひガタ馬車に乗る 蓬里雨
谷の深きに紅葉見るまで 寅日子
欄干に干す手拭の蝶々や 蓬里雨
湯治の日記(ニキ)の古い三月 東洋城
色々と娘の上のさたをして 東洋城
祭の寄附のいやもいはれず 寅日子
移り来て紅葉の色づく門構 蓬里雨
▽「新三つ物」=東洋城考案の「三つ物」(平句の三句形式)で、「三つ物/(三句)= 発句・脇・第三句の三句をいう。江戸時代から歳旦の祝詞として詠む習わしが生じ、明暦(一 六五五~五七)ごろから大流行となり、歳旦開きという行事までもが行われた。三句のう ち、月・花また神祇・釈経・恋など何を詠んでもよい。」の、それを柔軟にしたも。「発句・脇・第三」にとらわれず、平句(四句目以下の句)の「短句・長句・短句」など、「連句」の、謂わば、「トルソー」的な展開のもの(「俳諧 三つ物」=『東洋城全句集下巻』所収「大正十三年五月「渋柿」)。
※「俳諧六つ物(『渋柿』、2月)」周辺
臼の上には薪割(リ)の斧 東洋城
蕃椒(バンショウ)吊り干す軒さゝくれて 蓬里雨(※蕃椒=「トウガラシ」)
繭のあがつた噂している 寅日子
霧の中静に朝の江渡(ワタシ)して 城
朱盆の様な日を仰ぎけり 雨
画廊から画廊は遠き馬車の上に 子
(以下、五連(「折・面」を省略)
▽「俳諧六つ物=東洋城考案の「新三つ物」(平句の三句形式)の「三句形式」を「六句形式」にしたもの。上記のものは、その「六つ物」を「歌仙」の「三十六句」形式(折・面=六×六)の六連(折・面)と続けている。
※「俳諧 二つ折(『渋柿』、9月)」・「俳諧 二枚折(『渋柿』、7月)」)・「俳諧 二枚屏風(『渋柿』、12月」)周辺
▽「俳諧 二つ折(『渋柿』、9月)」は、「六つ物」(六句形式)を「二つ折」(「表と裏」の十二句)」を基本とするもの。「俳諧 二枚折(『渋柿』、7月)」は、「俳諧 二つ折」(十二句)を二枚続けて、「(六句・六句)+(六句・六句)=二十四句」を基本とするもの。「俳諧 二枚屏風(『渋柿』、12月」)は、「俳諧 二つ折」(十二句)を二枚続けて、「(六句・六句)+(六句・六句)=二十四句」を、「二曲一双」屏風のように、「一枚目屏風(六句+六句)=右隻」と「二枚目屏風(六句+六句)=左隻」と、「対(主題)」の仕立てにする形式のもの。これは、「六曲一隻(六句+六句+六句+六句+六句+六句)」ものなど、様々なバリエーションのものがあろう。
https://www.nippon.com/ja/japan-data/h01096/
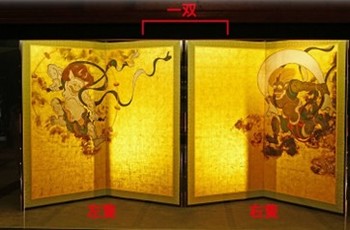
「二曲一双屏風」 (京都・建仁寺「風神雷神図」)
[豊隆(蓬里雨)・大正十三年(四十一歳)=東北大学教授となる。大正十五年(四十三歳)=芭蕉俳諧研究会を始める。五月合著『続々芭蕉俳句研究』出版。九月合訳ストリンドベリ全集『燕曲集』出版。]
https://yahan.blog.ss-blog.jp/2023-10-24
(再掲)
[[豊隆=蓬里雨・三十五歳。大正9年( 1920 )海軍大学校嘱託教授となる。大正10年 (1921 )芭蕉研究会に参加。]
※大正七年(1918)当時の豊隆は、『漱石全集』に取り組んでいて、「東洋城・寅日子・蓬里雨」の三吟歌仙とかは、大正十五年(1926)の頃が初出で、この頃は、「俳句・俳諧(連句)」には食指は伸ばしていなかったように思われる。大正十年(1921)の「芭蕉研究会」に参加は、東洋城の「渋柿」などとの「芭蕉研究会」ではなく、下記のアドレスのものなどによると、「太田水穂(歌誌「潮音」主宰)・幸田露伴・沼波瓊音・安倍能成・阿部次郎・小宮豊隆・和辻哲郎」らによる研究会のようである。
https://jyunku.hatenablog.com/entry/20100925/p1
「「芭蕉研究会」は田端の太田水穂(本名・貞一)宅で行われ、当初の会員は、阿部(次郎)、太田のほか、沼波瓊音、安倍能成、幸田露伴で、大正10年に小宮豊隆や和辻哲郎が加わった。」
この、阿部次郎・小宮豊隆らの「芭蕉研究会」の参加は、「大正15年( 1926) 芭蕉俳諧研究会を始める」と、「東北帝国大学」の「山田孝雄、村岡典嗣、岡崎義恵、太田正雄(木下杢太郎)」らの参加を得て、形を変えて継続されていくことになる。
https://www.library.tohoku.ac.jp/collection/collection/introduce.html ]
※「東洋城・寅日子(寅彦)・蓬里雨(豊隆)」の三者の中で、「芭蕉とその俳諧(連句・俳句)」周辺について最も造詣が深かったのは、大正十年(一九二一)の「芭蕉研究会」(太田水穂「歌誌『潮音』主宰)・幸田露伴・阿部次郎などの研究会)、そして、大正十五年(一九二六)の「芭蕉俳諧研究会」(東北帝大の同僚有志=阿部次郎・岡崎義恵・山田孝雄などによる研究会)で研鑽を積んでいた「蓬里雨(豊隆)」ということになろう。
その一端は、昭和十四年(一九三九)に刊行された『芭蕉俳諧論集』(小宮豊隆・横沢三郎編 岩波文庫)などで知ることができる。
https://dl.ndl.go.jp/pid/1684194/1/1
[『芭蕉俳諧論集』(小宮豊隆・横沢三郎編 岩波文庫)(「国立国会図書館デジタルコレクション」)
(「芭蕉俳諧論集・目次」)
序/3 (昭和十四年三月二十一日 小宮豊隆)
凡例/7
一、 心/21
二、 「風雅」/26
三、 「不易流行」/28
四、 「虛實」/38
五、 「さび、しをり、ほそみ」/41
六、 俳諧一般/45
(イ) 本質論/45
(ロ) 「修行敎」/57
(ハ) 個人評/73
七、 發句/89
(イ) 風體論/89
(ロ) 句作論/92
(ハ) 句評/111
八、 連句/215
(イ) 附合論/215
(ロ) 附句評/225
九、 作法/255
一〇、 雜/275
索引
索引に就いて/283
語句索引/287
句索引/297 ]
「東洋城・寅彦、そして、豊隆」(漱石没後~寅彦没まで)俳句・連句管見(その九) [東洋城・寅日子(寅彦)・蓬里雨(豊隆)]
その九「大正十四年(一九二五)」
[東洋城・四十八歳。東洋城・寅彦・豊隆共著の「漱石研究」岩波刊。足利にて俳諧道場。川中島、京洛、岩手、桐生、伊予に遊ぶ。古典文学の俳句諷詠を始める。就中、歌舞伎俳句を「渋柿」と雑誌「歌舞伎」に発表、歌舞伎十八番は殆ど俳句に諷詠した。連句新形式「新三つ物」「起承転結」「二枚折」創案制作を始めた。]
ふるさとへ老母を負ふや月の旅(前書「つひに母を伴ひ候」)
ふるさとのわが古家の芙蓉かな(前書「十幾年にして我家に起居して」)
「歌舞伎十八番の内 斬(新鹿島社頭の場)五十四句」のうちの五句

https://www2.ntj.jac.go.jp/unesco/kabuki/jp/play/play11.html
[権五郎が「花道」から「本舞台(ほんぶたい)」に来て両肌を脱いでいる間、舞台上では、「アーリャー、コーリャー」という声が繰り返され、権五郎の「見得(みえ)」に合わせて最後に「デッケエ」という声が上がります。この声を「化粧声(けしょうごえ)」といい、「荒事」の登場人物に対してかけられる褒めことばです。『寿曽我対面(ことぶきそがのたいめん)』の曽我五郎などでも掛けられます。]
一声や草の遥かの雉子が鳴く( 前書「斬(第一声)」
又の声の却て遠き長閑かな(前書「第二声」)
つゞけざまに雉子啼き立つるきほひかな(前書「第三声」)
松の花や本家本店荒事師(前書「今暫くと声をかけつん出た奴をよく見れば」)
こゝにこれの根源歌舞伎花盛(前書「歌舞伎十八番『斬』)
[寅彦(寅日子)・四十八歳。一月、柳田国男と地名について話する。五月、チェロを習い始める。六月、帝国学士院会員となる。八月、従四位に叙せられる。十月、最初の歌仙「水団扇の巻」(東洋城との両吟))が「渋柿」に掲載される。十一月、震災予防評議会評議委員となる。十二月、勲三等に叙せられる。]
※「歌仙 水団扇の巻」(東洋城・寅日子の両吟、大正十四年十月「渋柿」)
オ
水団扇鵜飼の絵なる篝(かがり)かな 東洋城 夏・景(外)
旅の話の更けて涼しき 寅日子 夏・人(自・他)
縁柱すがるところに瘤ありて 城 雑・景(内)
半分とけしあと解けぬ謎 子 雑・人(自)
吸物をあとから出した月の宴 城 月
庭のすゝきに風渡る頃 子 秋・景(外)
ウ
山里は洗足(ソソギ)の水も秋早く ゝ 秋・景(内)
只だ飼ふまゝに鯉の痩せやう 城 雑・景(外)
たまさかに内に居る日は不興にて 子 雑・人(自)
もの烹(ニタ)きながら結ひいそぐ髪 城 雑・人(「恋句」呼び出し)
君来べきしるしなればや宵の雨 子 恋
草紙の中の世さへ悲しく 城 恋
梅の実の色づく日々の医者通ひ 子 春・人(自)
医は医なれども謡のみ説く 城 雑・人(他)
提燈の箱も長押に年古(フ)りぬ 子 雑・景(内)
唯一軒の家囲む森 城 雑・景(外)
五加木(ウコギ)垣都の花に背を向けて 子 花
昔の春の御厨子黒棚 城 春・景(内)
ナオ
定めとて月の朔日目刺焼く ゝ 雑・人(自)※月=月日の月
不孝の悴九離勘当 子 雑・人(他)
持山の奥も見知らず代々に 城 雑・人(他)
狸を祭る大杉の蔭 子 雑・景(外)
降りすぐる一時雨に日のありて 城 冬・景(外)
土の匂ひの侘しなつかし 子 雑・人(自)
薪小屋の薪も尽きたる黄昏れに 城 雑・景(外)
うしろの藪の雪折の音 子 冬・景(外)
淋しさは水車の屋根の石叩 城 恋(?)
死んだ女房の襤褸(ボロ)干しゐる 子 恋
年回に当たらぬ年の盆の月 城 月
犬に物言ふ縁の白萩 子 秋・景(外)
ナウ
やうやうに野分の跡の片づきて ゝ 秋・景(外)
用はなけれどけふも出あるく 城 雑・人(自)
安本をあさり暮らすも癖のうち 子 雑・人(自)
めかけの数に殖える別荘 城 雑・人(他)
花見の場舞台廻ればものさびて 子 花
朧を刻む杉の四五本 城 春・景(外)
(参考その一) 「連句と寅日子(市川千年稿)」周辺
http://www.basho.jp/ronbun/ronbun_2018_11_01.html
[ 寺田寅彦(明治一一~昭和一〇)が巻いた歌仙は四七巻(未完成その他を入れると七〇巻)であるが、最初に満尾した歌仙は松根東洋城(明治一一~昭和三九)との両吟歌仙「水団扇の巻」である。
この歌仙は、寅彦四八歳(数え年)の大正一四年八月二七日、東洋城と新宿駅のプラットホームで落合い、昼食前から十二荘梅林の離亭を借りて「連句を開筵」、午後8時半まで、場所を変えつつ九時間余りで名残のウラ2句目まで付け、九月八日に追加満尾し、同年十月東洋城主宰の『渋柿』(大正四年二月創刊)に掲載された。(中略)
寅彦は初めて歌仙を巻いた感想を小宮豊隆に手紙で伝えている。「・・やつて見ると段々に六かしい事が分つて来るのを感じました。最初の二頁位は呑気に面白くても三頁辺からソロゝゝ単調と倦怠が目に立つて来る。それをグイゝゝ引立つて行くのは中々容易な事でないといふ事が朧気ながら分るやうな気がしました。此ういふ体験だけが一日の荒行の効果であつたかと思ひます。かういう事を考へて見ると、人の付け方が自分の気に入らぬ時でも、其れを其儘に受納して、そうして其れに附ける附け方によつて、その気に入らぬ句を自分の気に入るやうに活かす事を考へるのが、非常に張合のある事のやうに思はれて来ます。此れは勿論油臭い我の強いやり方でありますが、さういふ努力と闘争を続けることによつて、芭蕉の到達した処に近づく事が出来るのではないかという気もします。・・当日低気圧通過後の油照で恐ろしく蒸暑く、其れに一日頭を使つた為非常に疲労し、夜中非常な鼾で妻の安眠を妨害し抗議を申し込まれました・・・」 ]
[豊隆(蓬里雨)・大正十三年(四十一歳)=東北大学教授となる。大正十五年(四十三歳)=芭蕉俳諧研究会を始める。]
(参考その二)「連句とは」(「日本連句協会」)
https://renku-kyokai.net/renku/
[連句とは
連句(略)
歌仙・半歌仙(略)
歌仙式目(抜粋=「歌仙季題配置表」)
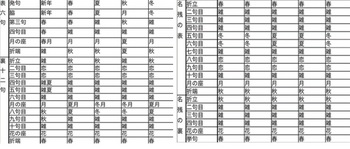
様々な形式(一部抜粋)
百韻=四折=百句/ 四花七月 /初の折/ 表八句/(七句目月)/ 裏十四句/(九句目月、十三句目花)/ 二の折 表十四句(月)/ 裏十四句 (月、十三句目花)/ 三の折/表十四句 (月) /裏十四句 (月、十三句目花)/ 名残の折/ 表十四句(十三句目月)/ 裏 八句 (七句目花)。 昔は百韻を五巻揃える五百韻や十巻の十百韻(とっぴゃくいん)も行われた。
八十八興(略)
七十二候(略)
易(えき)(略)
源氏(略)
五十韻=二折=五十句/二花四月 /百韻の初折と二の折を合わせたもの。
長歌行(略)
世吉(よよし)(略)
二十八宿(略)
短歌行(略)
箙(略)
半歌仙(略)
首尾吟(略)
歌仙首尾(略)
表白(略)
裏白(略)
表合(略)
三つ物/(三句)= 発句・脇・第三句の三句をいう。江戸時代から歳旦の祝詞として詠む習わしが生じ、明暦(一 六五五~五七)ごろから大流行となり、歳旦開きという行事までもが行われた。三句のう ち、月・花また神祇・釈経・恋など何を詠んでもよい。
新しい形式(一部抜粋)
胡蝶(略)
蜉蝣(かげろう)(略)
ソネット(略)
存風連句(略)
居待(略)。
十二調(略)
十八韻(略)
非懐紙形式(略) ]
(参考その三)「 芭蕉の時代が伝授する句の付け筋」(周辺)
http://www.local.co.jp/renku/5.html
[其の一(『去来抄』には、松尾芭蕉が語ったその時代の前句への付け方の「ひとつの傾向」として「うつり・ひびき・におい・くらいを以って付けるをよしとする」と述べられている。) (中略)
「移り」は、前句の余情や気分が、次の付句に柔らかく移る付け方。
「響き」は、前句に敏感に感応した付け方。
「匂い」は、前句の行間に漂う気持ちや情況、潜在するものに添う、あるいは応じる付け方。
「位」は、前句の人物・事物・言葉などを見定めて、その品格に添う、あるいは応じる付け方
其の二(各務支考は、付け方に関して「七名八体(しちみょうはったい)」と称する付け方の方法(七名)と狙い所(八体)を提示している。) (中略)
(七名=有心・向付・起情・会釈・拍子・色立・にげ句)
一)前句の情や景、状況などを見定めて、その言外のものを捉えて付ける(有心・うしん)。
二)前句の人物の性格や職業や境涯などを見定め、その人物と対応するように別の人物をもって付ける、いわば人間の存在的な一面を向かい合って付ける(向付・むかいづけ)。
三)人情味のない景色や事柄の前句の場合、その句の表現上のあやを頼りに、人情のある句を付ける(起情・きじょう)。
四)前句の人物、事柄、状態、品物などを受けて、軽くあしらって付ける(会釈・あしらい)。
五)前句の勢いに応じてテンポを合わせて付ける(拍子・ひょうし)。
六)前句の色に呼応して色彩のとり合わせで付ける(色立・いろだて)。
七)前句の意を軽く受け流してサラリと時節や気象などの句を付け、流れや気分を変える(にげ句)。
(八体=其人・其場・時節・時分・天象・事宜・観想・面影)
一)前句から感じ取れるその人物を見定めて、これを手がかりに人物描写として付ける(其人・そのひと)。
二)前句から感じ取れるその場所を見定め、これを手がかりに風景描写として付ける(其場・そのば)。
三)前句から感じ取れるその時節を見定め、これを手がかりに時節描写として付ける(時節・じせつ)。
四)前句から感じ取れるその時刻を見定め、これを手がかりに時刻描写として付ける(時分・じぶん)。
五)前句から感じ取れるその天象・気象を見定め、これを手がかり天象・気象描写として付ける(天象・てんしょう)。
六)前句から感じ取れるその人物やその時を見定め、これを手がかりにその人物のその時の状況描写として付ける(事宜・じぎ)。
七)前句から感じ取れるその心境を見定め、これを手がかり喜怒哀楽の描写として付ける(観想・かんそう)。
八)前句から感じ取れる物語の趣(おもむき)を見定め、これを手がかりに一般に知られている物語などがイメージできるように付ける(面影・おもかげ)。
其の三(立花北枝は、歌仙一巻の句を「人情無しの句」「人情自の句」「人情他の句」の三つに分類し、付句を工夫するように『付方自他伝』を著して提言した。) (中略)
「人情自の句」は自分のことを詠んだ句、「人情他の句」は自分以外の他者を詠んだ句、「自他半の句」は、自分および他者を同時に詠んだ句、「人情無しの句」は場の句で、自分および他者を入れずに景色や世相などを詠んだ句、のこと。(後略) ]
[東洋城・四十八歳。東洋城・寅彦・豊隆共著の「漱石研究」岩波刊。足利にて俳諧道場。川中島、京洛、岩手、桐生、伊予に遊ぶ。古典文学の俳句諷詠を始める。就中、歌舞伎俳句を「渋柿」と雑誌「歌舞伎」に発表、歌舞伎十八番は殆ど俳句に諷詠した。連句新形式「新三つ物」「起承転結」「二枚折」創案制作を始めた。]
ふるさとへ老母を負ふや月の旅(前書「つひに母を伴ひ候」)
ふるさとのわが古家の芙蓉かな(前書「十幾年にして我家に起居して」)
「歌舞伎十八番の内 斬(新鹿島社頭の場)五十四句」のうちの五句

https://www2.ntj.jac.go.jp/unesco/kabuki/jp/play/play11.html
[権五郎が「花道」から「本舞台(ほんぶたい)」に来て両肌を脱いでいる間、舞台上では、「アーリャー、コーリャー」という声が繰り返され、権五郎の「見得(みえ)」に合わせて最後に「デッケエ」という声が上がります。この声を「化粧声(けしょうごえ)」といい、「荒事」の登場人物に対してかけられる褒めことばです。『寿曽我対面(ことぶきそがのたいめん)』の曽我五郎などでも掛けられます。]
一声や草の遥かの雉子が鳴く( 前書「斬(第一声)」
又の声の却て遠き長閑かな(前書「第二声」)
つゞけざまに雉子啼き立つるきほひかな(前書「第三声」)
松の花や本家本店荒事師(前書「今暫くと声をかけつん出た奴をよく見れば」)
こゝにこれの根源歌舞伎花盛(前書「歌舞伎十八番『斬』)
[寅彦(寅日子)・四十八歳。一月、柳田国男と地名について話する。五月、チェロを習い始める。六月、帝国学士院会員となる。八月、従四位に叙せられる。十月、最初の歌仙「水団扇の巻」(東洋城との両吟))が「渋柿」に掲載される。十一月、震災予防評議会評議委員となる。十二月、勲三等に叙せられる。]
※「歌仙 水団扇の巻」(東洋城・寅日子の両吟、大正十四年十月「渋柿」)
オ
水団扇鵜飼の絵なる篝(かがり)かな 東洋城 夏・景(外)
旅の話の更けて涼しき 寅日子 夏・人(自・他)
縁柱すがるところに瘤ありて 城 雑・景(内)
半分とけしあと解けぬ謎 子 雑・人(自)
吸物をあとから出した月の宴 城 月
庭のすゝきに風渡る頃 子 秋・景(外)
ウ
山里は洗足(ソソギ)の水も秋早く ゝ 秋・景(内)
只だ飼ふまゝに鯉の痩せやう 城 雑・景(外)
たまさかに内に居る日は不興にて 子 雑・人(自)
もの烹(ニタ)きながら結ひいそぐ髪 城 雑・人(「恋句」呼び出し)
君来べきしるしなればや宵の雨 子 恋
草紙の中の世さへ悲しく 城 恋
梅の実の色づく日々の医者通ひ 子 春・人(自)
医は医なれども謡のみ説く 城 雑・人(他)
提燈の箱も長押に年古(フ)りぬ 子 雑・景(内)
唯一軒の家囲む森 城 雑・景(外)
五加木(ウコギ)垣都の花に背を向けて 子 花
昔の春の御厨子黒棚 城 春・景(内)
ナオ
定めとて月の朔日目刺焼く ゝ 雑・人(自)※月=月日の月
不孝の悴九離勘当 子 雑・人(他)
持山の奥も見知らず代々に 城 雑・人(他)
狸を祭る大杉の蔭 子 雑・景(外)
降りすぐる一時雨に日のありて 城 冬・景(外)
土の匂ひの侘しなつかし 子 雑・人(自)
薪小屋の薪も尽きたる黄昏れに 城 雑・景(外)
うしろの藪の雪折の音 子 冬・景(外)
淋しさは水車の屋根の石叩 城 恋(?)
死んだ女房の襤褸(ボロ)干しゐる 子 恋
年回に当たらぬ年の盆の月 城 月
犬に物言ふ縁の白萩 子 秋・景(外)
ナウ
やうやうに野分の跡の片づきて ゝ 秋・景(外)
用はなけれどけふも出あるく 城 雑・人(自)
安本をあさり暮らすも癖のうち 子 雑・人(自)
めかけの数に殖える別荘 城 雑・人(他)
花見の場舞台廻ればものさびて 子 花
朧を刻む杉の四五本 城 春・景(外)
(参考その一) 「連句と寅日子(市川千年稿)」周辺
http://www.basho.jp/ronbun/ronbun_2018_11_01.html
[ 寺田寅彦(明治一一~昭和一〇)が巻いた歌仙は四七巻(未完成その他を入れると七〇巻)であるが、最初に満尾した歌仙は松根東洋城(明治一一~昭和三九)との両吟歌仙「水団扇の巻」である。
この歌仙は、寅彦四八歳(数え年)の大正一四年八月二七日、東洋城と新宿駅のプラットホームで落合い、昼食前から十二荘梅林の離亭を借りて「連句を開筵」、午後8時半まで、場所を変えつつ九時間余りで名残のウラ2句目まで付け、九月八日に追加満尾し、同年十月東洋城主宰の『渋柿』(大正四年二月創刊)に掲載された。(中略)
寅彦は初めて歌仙を巻いた感想を小宮豊隆に手紙で伝えている。「・・やつて見ると段々に六かしい事が分つて来るのを感じました。最初の二頁位は呑気に面白くても三頁辺からソロゝゝ単調と倦怠が目に立つて来る。それをグイゝゝ引立つて行くのは中々容易な事でないといふ事が朧気ながら分るやうな気がしました。此ういふ体験だけが一日の荒行の効果であつたかと思ひます。かういう事を考へて見ると、人の付け方が自分の気に入らぬ時でも、其れを其儘に受納して、そうして其れに附ける附け方によつて、その気に入らぬ句を自分の気に入るやうに活かす事を考へるのが、非常に張合のある事のやうに思はれて来ます。此れは勿論油臭い我の強いやり方でありますが、さういふ努力と闘争を続けることによつて、芭蕉の到達した処に近づく事が出来るのではないかという気もします。・・当日低気圧通過後の油照で恐ろしく蒸暑く、其れに一日頭を使つた為非常に疲労し、夜中非常な鼾で妻の安眠を妨害し抗議を申し込まれました・・・」 ]
[豊隆(蓬里雨)・大正十三年(四十一歳)=東北大学教授となる。大正十五年(四十三歳)=芭蕉俳諧研究会を始める。]
(参考その二)「連句とは」(「日本連句協会」)
https://renku-kyokai.net/renku/
[連句とは
連句(略)
歌仙・半歌仙(略)
歌仙式目(抜粋=「歌仙季題配置表」)
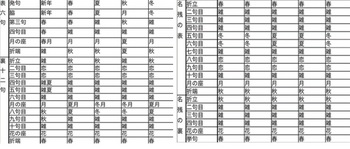
様々な形式(一部抜粋)
百韻=四折=百句/ 四花七月 /初の折/ 表八句/(七句目月)/ 裏十四句/(九句目月、十三句目花)/ 二の折 表十四句(月)/ 裏十四句 (月、十三句目花)/ 三の折/表十四句 (月) /裏十四句 (月、十三句目花)/ 名残の折/ 表十四句(十三句目月)/ 裏 八句 (七句目花)。 昔は百韻を五巻揃える五百韻や十巻の十百韻(とっぴゃくいん)も行われた。
八十八興(略)
七十二候(略)
易(えき)(略)
源氏(略)
五十韻=二折=五十句/二花四月 /百韻の初折と二の折を合わせたもの。
長歌行(略)
世吉(よよし)(略)
二十八宿(略)
短歌行(略)
箙(略)
半歌仙(略)
首尾吟(略)
歌仙首尾(略)
表白(略)
裏白(略)
表合(略)
三つ物/(三句)= 発句・脇・第三句の三句をいう。江戸時代から歳旦の祝詞として詠む習わしが生じ、明暦(一 六五五~五七)ごろから大流行となり、歳旦開きという行事までもが行われた。三句のう ち、月・花また神祇・釈経・恋など何を詠んでもよい。
新しい形式(一部抜粋)
胡蝶(略)
蜉蝣(かげろう)(略)
ソネット(略)
存風連句(略)
居待(略)。
十二調(略)
十八韻(略)
非懐紙形式(略) ]
(参考その三)「 芭蕉の時代が伝授する句の付け筋」(周辺)
http://www.local.co.jp/renku/5.html
[其の一(『去来抄』には、松尾芭蕉が語ったその時代の前句への付け方の「ひとつの傾向」として「うつり・ひびき・におい・くらいを以って付けるをよしとする」と述べられている。) (中略)
「移り」は、前句の余情や気分が、次の付句に柔らかく移る付け方。
「響き」は、前句に敏感に感応した付け方。
「匂い」は、前句の行間に漂う気持ちや情況、潜在するものに添う、あるいは応じる付け方。
「位」は、前句の人物・事物・言葉などを見定めて、その品格に添う、あるいは応じる付け方
其の二(各務支考は、付け方に関して「七名八体(しちみょうはったい)」と称する付け方の方法(七名)と狙い所(八体)を提示している。) (中略)
(七名=有心・向付・起情・会釈・拍子・色立・にげ句)
一)前句の情や景、状況などを見定めて、その言外のものを捉えて付ける(有心・うしん)。
二)前句の人物の性格や職業や境涯などを見定め、その人物と対応するように別の人物をもって付ける、いわば人間の存在的な一面を向かい合って付ける(向付・むかいづけ)。
三)人情味のない景色や事柄の前句の場合、その句の表現上のあやを頼りに、人情のある句を付ける(起情・きじょう)。
四)前句の人物、事柄、状態、品物などを受けて、軽くあしらって付ける(会釈・あしらい)。
五)前句の勢いに応じてテンポを合わせて付ける(拍子・ひょうし)。
六)前句の色に呼応して色彩のとり合わせで付ける(色立・いろだて)。
七)前句の意を軽く受け流してサラリと時節や気象などの句を付け、流れや気分を変える(にげ句)。
(八体=其人・其場・時節・時分・天象・事宜・観想・面影)
一)前句から感じ取れるその人物を見定めて、これを手がかりに人物描写として付ける(其人・そのひと)。
二)前句から感じ取れるその場所を見定め、これを手がかりに風景描写として付ける(其場・そのば)。
三)前句から感じ取れるその時節を見定め、これを手がかりに時節描写として付ける(時節・じせつ)。
四)前句から感じ取れるその時刻を見定め、これを手がかりに時刻描写として付ける(時分・じぶん)。
五)前句から感じ取れるその天象・気象を見定め、これを手がかり天象・気象描写として付ける(天象・てんしょう)。
六)前句から感じ取れるその人物やその時を見定め、これを手がかりにその人物のその時の状況描写として付ける(事宜・じぎ)。
七)前句から感じ取れるその心境を見定め、これを手がかり喜怒哀楽の描写として付ける(観想・かんそう)。
八)前句から感じ取れる物語の趣(おもむき)を見定め、これを手がかりに一般に知られている物語などがイメージできるように付ける(面影・おもかげ)。
其の三(立花北枝は、歌仙一巻の句を「人情無しの句」「人情自の句」「人情他の句」の三つに分類し、付句を工夫するように『付方自他伝』を著して提言した。) (中略)
「人情自の句」は自分のことを詠んだ句、「人情他の句」は自分以外の他者を詠んだ句、「自他半の句」は、自分および他者を同時に詠んだ句、「人情無しの句」は場の句で、自分および他者を入れずに景色や世相などを詠んだ句、のこと。(後略) ]
「東洋城・寅彦、そして、豊隆」(漱石没後~寅彦没まで)俳句・連句管見(その八) [東洋城・寅日子(寅彦)・蓬里雨(豊隆)]
その八「大正十三年(一九二四)」
[東洋城・四十七歳。那須、妙義山、金華山に遊ぶ。東洋城百詠短冊展覧会開催。漱石全集編纂。日本アルプス登山。歌仙を始む。]
仮の世の仮の棲家や年越ゆる(前書「三畳庵」)
寝るは死ぬるとばかり安き布団かな
蒲団敷くや今宵をなゐのともかくも
※故郷の故郷鄙に暑さかな(前書「前書「今の故郷は四国なれど十数代前の故郷は、最上、わが家の城趾やいづこと見渡さるゝ。昔の楽園上ノ山温泉もむさく暑くるしきのみ」)
夏海へ大河の口やあからさま(前書「北上川」)
荒潮に流れぬ島の茂かな(前書「金華山 二句」)
涼しさや頂にして海の中(同上)
静けさはひたと大地に蜻蛉かな(前書「あゝその九月一日」)
何よりも寒きに耐ふることを知れ(前書「甥 新生 誕生賀」)
白足袋や影あり行けるうしろつき(前書「断腸花追悼」)
石が吐く毒とはをかし枯るゝ山(「那須温泉 二十句」のうち「殺生石」)
(「東洋城」メモ)
※故郷の故郷鄙に暑さかな(前書「前書「今の故郷は四国なれど十数代前の故郷は、最上、わが家の城趾やいづこと見渡さるゝ。昔の楽園上ノ山温泉もむさく暑くるしきのみ」)
http://sp.mogamiyoshiaki.jp/?p=log&l=143960
[(松根備前守光広/まつねびぜんのかみあきひろ)~俳人・松根東洋城の先祖~
義光の弟である義保の子。義保は長瀞城主。兄の片腕となって出羽南部の平定に尽力したが、天正19年(1591)に戦死。ときに光広は3歳の幼児だった。義光がこれを哀れんで、息子同然にいつくしみ育てたと、宇和島市に残る古記録は伝えている。
光広は成人の後は山形市漆山に居住したこともあったが、西村山の名門白岩家の名跡を継いで「白岩備前守」を名乗る。
慶長5年(1600年)の関が原合戦、長谷堂合戦のときは12、3歳だったから、まず戦陣の経験はなかっただろうと思われる。元和2年(1616)、庄内櫛引郷に居城松根城を築いて松根姓を名乗る。一1万2千石、一書に1万3千石とある。
義光に育てられたことに対する報恩の気持ちからか、最上家を思う心が人一倍厚い人物だったようだ。
熊野夫須美神社に、那智権現別当あて、年次無記8月20日付、光広の書状が一通ある。
「最上出羽守義光が病につき、神馬一疋ならびに鳥目(銭)百疋を奉納いたします。御神前において御祈念くださるようお頼みします」という内容である。
「白岩備前守光広」の署名からみて、松根移転以前であることは明らか。義光の病が重くなった慶長18年(1613)のものと推定される。出羽からははるかに遠い紀州那智に使者を遣わして、病気平癒の祈りをささげたのである。あるいは、光広はそのころ上京中だったかもしれない。
義光が亡くなり、跡を継いだ駿河守家親も3年後の元和3年ににわかに亡くなり、その後を12歳の少年、源五郎家信が継ぐ。とかく問題行動を起こしがちな幼い主君に、家臣たちは動揺する。
家を守りたてるべき重臣たちのなかには、義光の四男山野辺光茂こそ山形の主にふさわしいとして、鮭延越前、楯岡甲斐らの一派が公然と動きはじめる。
かくてはならじ、お家のためになんとかせねばと、光広は「山野辺一派が策謀をめぐらし当主家親を亡きものにした」と幕府に直訴した。幕府でも一大事とばかり徹底的に究明したが、事実無根と判明。偽りの申し立てをした不届きの所業として、光広は九州柳川の立花家にあずけられてしまう。彼はここ柳川でおよそ五十年を過ごす。藩主立花宗茂との親交を保ちつつ、寛文12年(1672)84歳の生涯を終える。
その子孫が四国宇和島の伊達家につかえ、家老職の家柄を伝えて維新を迎えた。
高名な俳人松根東洋城(本名豊次郎1878~1964)は、この家の9代目にあたる。宮内省式部官などを勤めながら夏目漱石の門下として俳壇で活躍、のち芸術院会員となった。
昭和4年6月、父祖の地である庄内の松根から白岩をおとずれた東洋城は、昔をしのんで次のような句を残した。
故里の故里淋し閑古鳥
青嵐三百年の無沙汰かな
出羽の最上から九州柳川へ、そして更に四国の宇和島へ。先祖のたどった長い長い3百年の道程だった。宇和島市立伊達博物館の庭には、「我が祖先(おや)は奥の最上や天の川」の句碑がある。
最上家の改易で会津・蒲生氏により接収破却された松根城の跡には、最上院がある。光広の妻が晩年に住んだという松根庵には、彼女の墓碑が寂しくたっている。(片桐繁雄稿)]
(「最上義光歴史館」)

「松根洋城の句碑」(最上院の南側に光広の子孫で、伊予国宇和島藩家老職にあった松根家の子孫、松根洋城の句碑が建てられている。)
https://www.hb.pei.jp/shiro/dewa/matsune-jyo/
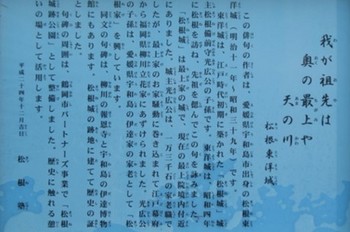
「松根洋城の句碑」(解説板) (「鶴岡市松根字中松根 松根東洋城句碑公園」)
https://www.hb.pei.jp/shiro/dewa/matsune-jyo/thumb/
※ 上記の「松根洋城の句碑」(解説板)によると、「柳川の報恩寺と宇和島の伊達博物館」に同文の句碑がある」。

報恩寺(福岡県柳川市)
http://urawa0328.babymilk.jp/fukuoka/22/houonji-3.jpg

伊達博物館(愛媛県宇和島市)
http://urawa0328.babymilk.jp/ehime/22/datehaku-5.jpg
[寅彦(寅日子)・四十七歳。松根東洋城と連句を実作する。五月、地質学会において「大正十二年九月一日の地震に就て」を講演する。理化学研究所研究員となる。]
※ 上記の年譜の、「松根東洋城と連句を実作する」は、「大正十四年十月『渋柿』」に掲載された「歌仙 水団扇の巻」(東洋城・寅日子の両吟)などを指しているのであろう。
「歌仙 水団扇の巻」(東洋城・寅日子の両吟)
オ
水団扇鵜飼の絵なる篝かな 東洋城
旅の話の更けて涼しき 寅日子
縁柱すがるところに瘤ありて 城
半分とけしあと解けぬ謎 子
(この歌仙は「大正十四年」の項で全句掲載する。)
[豊隆(蓬里雨)・四十一歳。帰国。東北大学教授となる。]
※ 大正十二年(一九二三)三月に渡欧していた豊隆は、その翌年(大正十五年)に帰国し、「東北大学教授」となり、仙台に居を移すことになる。その時と関係すると思われる「歌仙 みちのくの人の巻」(東洋城・寅日子・蓬里雨の三吟)が、昭和二年(一九二七)二月「渋柿」に掲載されている。
「歌仙 みちのく人の巻」(東洋城・寅日子・蓬里雨の三吟)
オ
送別
あすよりはみちのく人や春の雨 東洋城
まだ雪のこる西側の山 蓬里雨
沈丁花こぼるゝ里に移り来て 寅日子
(この歌仙は「昭和二年」の項で全句掲載する。)
[東洋城・四十七歳。那須、妙義山、金華山に遊ぶ。東洋城百詠短冊展覧会開催。漱石全集編纂。日本アルプス登山。歌仙を始む。]
仮の世の仮の棲家や年越ゆる(前書「三畳庵」)
寝るは死ぬるとばかり安き布団かな
蒲団敷くや今宵をなゐのともかくも
※故郷の故郷鄙に暑さかな(前書「前書「今の故郷は四国なれど十数代前の故郷は、最上、わが家の城趾やいづこと見渡さるゝ。昔の楽園上ノ山温泉もむさく暑くるしきのみ」)
夏海へ大河の口やあからさま(前書「北上川」)
荒潮に流れぬ島の茂かな(前書「金華山 二句」)
涼しさや頂にして海の中(同上)
静けさはひたと大地に蜻蛉かな(前書「あゝその九月一日」)
何よりも寒きに耐ふることを知れ(前書「甥 新生 誕生賀」)
白足袋や影あり行けるうしろつき(前書「断腸花追悼」)
石が吐く毒とはをかし枯るゝ山(「那須温泉 二十句」のうち「殺生石」)
(「東洋城」メモ)
※故郷の故郷鄙に暑さかな(前書「前書「今の故郷は四国なれど十数代前の故郷は、最上、わが家の城趾やいづこと見渡さるゝ。昔の楽園上ノ山温泉もむさく暑くるしきのみ」)
http://sp.mogamiyoshiaki.jp/?p=log&l=143960
[(松根備前守光広/まつねびぜんのかみあきひろ)~俳人・松根東洋城の先祖~
義光の弟である義保の子。義保は長瀞城主。兄の片腕となって出羽南部の平定に尽力したが、天正19年(1591)に戦死。ときに光広は3歳の幼児だった。義光がこれを哀れんで、息子同然にいつくしみ育てたと、宇和島市に残る古記録は伝えている。
光広は成人の後は山形市漆山に居住したこともあったが、西村山の名門白岩家の名跡を継いで「白岩備前守」を名乗る。
慶長5年(1600年)の関が原合戦、長谷堂合戦のときは12、3歳だったから、まず戦陣の経験はなかっただろうと思われる。元和2年(1616)、庄内櫛引郷に居城松根城を築いて松根姓を名乗る。一1万2千石、一書に1万3千石とある。
義光に育てられたことに対する報恩の気持ちからか、最上家を思う心が人一倍厚い人物だったようだ。
熊野夫須美神社に、那智権現別当あて、年次無記8月20日付、光広の書状が一通ある。
「最上出羽守義光が病につき、神馬一疋ならびに鳥目(銭)百疋を奉納いたします。御神前において御祈念くださるようお頼みします」という内容である。
「白岩備前守光広」の署名からみて、松根移転以前であることは明らか。義光の病が重くなった慶長18年(1613)のものと推定される。出羽からははるかに遠い紀州那智に使者を遣わして、病気平癒の祈りをささげたのである。あるいは、光広はそのころ上京中だったかもしれない。
義光が亡くなり、跡を継いだ駿河守家親も3年後の元和3年ににわかに亡くなり、その後を12歳の少年、源五郎家信が継ぐ。とかく問題行動を起こしがちな幼い主君に、家臣たちは動揺する。
家を守りたてるべき重臣たちのなかには、義光の四男山野辺光茂こそ山形の主にふさわしいとして、鮭延越前、楯岡甲斐らの一派が公然と動きはじめる。
かくてはならじ、お家のためになんとかせねばと、光広は「山野辺一派が策謀をめぐらし当主家親を亡きものにした」と幕府に直訴した。幕府でも一大事とばかり徹底的に究明したが、事実無根と判明。偽りの申し立てをした不届きの所業として、光広は九州柳川の立花家にあずけられてしまう。彼はここ柳川でおよそ五十年を過ごす。藩主立花宗茂との親交を保ちつつ、寛文12年(1672)84歳の生涯を終える。
その子孫が四国宇和島の伊達家につかえ、家老職の家柄を伝えて維新を迎えた。
高名な俳人松根東洋城(本名豊次郎1878~1964)は、この家の9代目にあたる。宮内省式部官などを勤めながら夏目漱石の門下として俳壇で活躍、のち芸術院会員となった。
昭和4年6月、父祖の地である庄内の松根から白岩をおとずれた東洋城は、昔をしのんで次のような句を残した。
故里の故里淋し閑古鳥
青嵐三百年の無沙汰かな
出羽の最上から九州柳川へ、そして更に四国の宇和島へ。先祖のたどった長い長い3百年の道程だった。宇和島市立伊達博物館の庭には、「我が祖先(おや)は奥の最上や天の川」の句碑がある。
最上家の改易で会津・蒲生氏により接収破却された松根城の跡には、最上院がある。光広の妻が晩年に住んだという松根庵には、彼女の墓碑が寂しくたっている。(片桐繁雄稿)]
(「最上義光歴史館」)

「松根洋城の句碑」(最上院の南側に光広の子孫で、伊予国宇和島藩家老職にあった松根家の子孫、松根洋城の句碑が建てられている。)
https://www.hb.pei.jp/shiro/dewa/matsune-jyo/
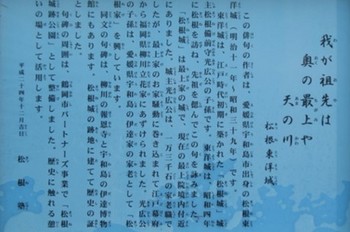
「松根洋城の句碑」(解説板) (「鶴岡市松根字中松根 松根東洋城句碑公園」)
https://www.hb.pei.jp/shiro/dewa/matsune-jyo/thumb/
※ 上記の「松根洋城の句碑」(解説板)によると、「柳川の報恩寺と宇和島の伊達博物館」に同文の句碑がある」。

報恩寺(福岡県柳川市)
http://urawa0328.babymilk.jp/fukuoka/22/houonji-3.jpg

伊達博物館(愛媛県宇和島市)
http://urawa0328.babymilk.jp/ehime/22/datehaku-5.jpg
[寅彦(寅日子)・四十七歳。松根東洋城と連句を実作する。五月、地質学会において「大正十二年九月一日の地震に就て」を講演する。理化学研究所研究員となる。]
※ 上記の年譜の、「松根東洋城と連句を実作する」は、「大正十四年十月『渋柿』」に掲載された「歌仙 水団扇の巻」(東洋城・寅日子の両吟)などを指しているのであろう。
「歌仙 水団扇の巻」(東洋城・寅日子の両吟)
オ
水団扇鵜飼の絵なる篝かな 東洋城
旅の話の更けて涼しき 寅日子
縁柱すがるところに瘤ありて 城
半分とけしあと解けぬ謎 子
(この歌仙は「大正十四年」の項で全句掲載する。)
[豊隆(蓬里雨)・四十一歳。帰国。東北大学教授となる。]
※ 大正十二年(一九二三)三月に渡欧していた豊隆は、その翌年(大正十五年)に帰国し、「東北大学教授」となり、仙台に居を移すことになる。その時と関係すると思われる「歌仙 みちのくの人の巻」(東洋城・寅日子・蓬里雨の三吟)が、昭和二年(一九二七)二月「渋柿」に掲載されている。
「歌仙 みちのく人の巻」(東洋城・寅日子・蓬里雨の三吟)
オ
送別
あすよりはみちのく人や春の雨 東洋城
まだ雪のこる西側の山 蓬里雨
沈丁花こぼるゝ里に移り来て 寅日子
(この歌仙は「昭和二年」の項で全句掲載する。)
「東洋城・寅彦、そして、豊隆」(漱石没後~寅彦没まで)俳句・連句管見(その七) [東洋城・寅日子(寅彦)・蓬里雨(豊隆)]
その七「大正十二年(一九二三)」
[東洋城・四十六歳。寅彦と連句の研究を始め、豊隆も帰朝後参加した。東北を行脚、京洛、伊予に遊ぶ。関東大震災により平河町の屋敷炎上。直ちに栃木に赴き、渋柿十月刊。(この縁により昭和二十六年まで栃木で印刷した。) 震災を機に「朝日俳壇」の選者を辞した。]
[寅彦(寅日子)・四十六歳。一月、漱石俳句研究会を開く。三月に小宮豊隆がドイツに留学したため、これが最後の研究会となる。四月、松根東洋城と古典連句の研究を始め、その内容は「渋柿」に掲載される。九月一日、関東大震災が起こり、各地の被害調査にあたる。十一月、土木学会帝都復興委員会において「旋風ら就て」を講演する。]
[豊隆(蓬里雨)・四十歳。三月、渡欧。五月にベルリンに到着し、以後欧州各国を歴訪。]
(東洋城)
春の夜のすみだ川あり君が為め(前書「小宮豊隆氏送別会「錦水」にて)
しかも其時秋静かなることにありき(前書「大地震ふ 十四句」)
驚きや垣朝顔も沓石も(同上)
冷かもしらで地踏む裸足かな(同上)
まざまざと抱ける母や老の秋(同上)
塀はたりたり倒る野分にもあらず(同上)
なゐふるや生色ゆるゝ秋の草(同上)
その時幾十万死にしを知らず蜻蛉かな(同上)
なゐふるやありなしの命人の秋(同上)
蛼(コオロギ)よ地軸折れしと人のいふに(同上)
洛陽に劫火(ゴオカ)つゞくや秋幾日(同上)
いねもせで備ふことあり夜半の秋(同上)
ももぐれば玄米悲し人の秋(同上)
鳥渡る下の現世なる地変かな(同上)
(寅彦(寅日子))
春の江は靄に暮れ行く別れ哉化(前書「三月小宮豊隆氏送別の句(錦水にて)」)

寺田寅彦から小宮豊隆へあてた手紙「大正12年10月関東大震災の被災状況を報告」
https://www.town.miyako.lg.jp/rekisiminnzoku/kankou/person/komiya_toyotaka.html
(参考) 寺田寅彦の随筆「震災日記より」(旧字・旧仮名) (抜粋)
http://sybrma.sakura.ne.jp/394torahiko.shinsainikki.html
[九月一日。(土曜)
朝はしけ模樣で時々暴雨が襲つて來た。非常な強度で降つて居ると思ふと、まるで斷ち切つたやうにぱたりと止む、さうかと思ふと又急に降り出す實に珍らしい斷續的な降り方であつた。雜誌「文化生活」への原稿「石油ラムプ」を書き上げた。雨が收まつたので上野二科會展招待日の見物に行く。會場に入つたのが十時半頃。蒸暑かつた。フランス展の影響が著しく眼についた。T君(※津田青楓)と喫茶店で紅茶を呑みながら同君の出品畫「I崎の女」(※津田の作品「出雲崎の女)に對する其モデルの良人からの撤囘要求問題の話を聞いて居るうちに急激な地震を感じた。椅子に腰かけて居る兩足の蹠を下から木槌で急速に亂打するやうに感じた。多分其前に來た筈の弱い初期微動を氣が付かずに直ちに主要動を感じたのだらうといふ氣がして、それにしても妙に短週期の振動だと思つて居るうちにいよいよ本當の主要動が急激に襲つて來た。同時に、此れは自分の全く經驗のない異常の大地震であると知つた。其瞬間に子供の時から何度となく母上に聞かされてゐた土佐の安政地震の話がありあり想出され、丁度船に乘つたやうに、ゆたりゆたり搖れると云ふ形容が適切である事を感じた。仰向いて會場の建築の搖れ工合を注意して見ると四五秒程と思はれる長い週期でみしみしみしみしと音を立てながら緩やかに搖れて居た。それを見たとき此れなら此建物は大丈夫だといふことが直感されたので恐ろしいといふ感じはすぐになくなつてしまつた。さうして、此珍らしい強震の振動の經過を出來るだけ精しく觀察しようと思つて骨を折つて居た。
主要動が始まつてびつくりしてから數秒後に一時振動が衰へ、此分では大した事もないと思ふ頃にもう一度急激な、最初にも増した烈しい波が來て、二度目にびつくりさせられたが、それからは次第に減衰して長週期の波ばかりになつた。
同じ食卓に居た人々は大抵最初の最大主要動で吾勝に立上つて出口の方へ驅出して行つたが、自分等の筋向ひに居た中年の夫婦は其時は未だ立たなかつた。しかも其夫人がビフテキを食つて居たのが、少くも見たところ平然と肉片を口に運んで居たのがハツキリ印象に殘つて居る。併し二度目の最大動が來たときは一人殘らず出てしまつて場内はがらんとしてしまつた。油畫の額はゆがんだり、落ちたりしたのもあつたが大抵はちやんとして懸かつて居るやうであつた。此れで見ても、さう此建物の震動は激烈なものでなかつたことがわかる。あとで考へて見ると、此れは建物の自己週期が著しく長いことが有利であつたのであらうと思はれる。震動が衰へてから外の樣子を見に出ようと思つたが喫茶店のボーイも一人殘らず出てしまつて誰れも居ないので勘定をすることが出來ない。それで勘定場近くの便所の口へ出て低い木柵越しに外を見ると、其處に一團、彼處に一團といふ風に人間が寄集つて茫然として空を眺めて居る。此便所口から柵を越えて逃出した人々らしい。空はもう半ば晴れて居たが千切れ千切れの綿雲が嵐の時のやうに飛んで居た。その内にボーイの一人が歸つて來たので勘定をすませた。ボーイがひどく丁寧に禮を云つたやうに記憶する。出口へ出ると其處では下足番の婆さんが唯一人落ち散らばつた履物の整理をして居るのを見付けて、預けた蝙蝠傘を出して貰つて館の裏手の集團の中からT畫伯を捜しあてた。同君の二人の子供も一緒に居た。其時氣のついたのは附近の大木の枯枝の大きなのが折れて墜ちて居る。地震の爲に折れ落ちたのかそれとも今朝の暴風雨で折れたのか分らない。T君に別れて東照宮前の方へ歩いて來ると異樣な黴臭い匂が鼻を突いた。空を仰ぐと下谷の方面からひどい土ほこりが飛んで來るのが見える。此れは非常に多數の家屋が倒潰したのだと思つた、同時に、此れでは東京中が火になるかも知れないと直感された。東照宮前から境内を覗くと石燈籠は一つ殘らず象棋倒しに北の方へ倒れて居る。大鳥居の柱は立つて居るが上の横桁が外れかゝり、しかも落ちないで危く止つて居るのであつた。精養軒のボーイ達が大きな櫻の根元に寄集つて居た。大佛の首の落ちた事は後で知つたがその時は少しも氣が付かなかつた。池の方へ下りる坂脇の稻荷の鳥居も、柱が立つて桁が落ち碎けて居た。坂を下りて見ると不忍辨天の社務所が池の方へのめるやうに倒れかゝつて居るのを見て、なる程此れは大地震だなといふことが漸くはつきり呑込めて來た。
無事な日の續いて居るうちに突然に起つた著しい變化を充分にリアライズするには存外手數が掛かる。此日は二科會を見てから日本橋邊へ出て晝飯を食ふつもりで出掛けたのであつたが、あの地震を體驗し下谷の方から吹上げて來る土埃りの臭を嗅いで大火を豫想し東照宮の石燈籠のあの象棋倒しを眼前に見ても、それでも未だ晝飯のプログラムは帳消しにならずそのまゝになつて居た。併し辨天社務所の倒潰を見たとき初めて此れはいけないと思つた、さうして始めて我家の事が少し氣懸りになつて來た。
辨天の前に電車が一臺停つたまゝ動きさうもない。車掌に聞いても何時動き出すか分らないといふ。後から考へると此んなことを聞くのが如何な非常識であつたかゞよく分るのであるが、其當時自分と同樣の質問を車掌に持出した市民の數は萬を以て數へられるであらう。
動物園裏迄來ると道路の眞中へ疊を持出して其上に病人をねかせて居るのがあつた。人通りのない町はひつそりして居た。根津を拔けて歸るつもりであつたが頻繁に襲つて來る餘震で煉瓦壁の頽れかゝつたのがあらたに倒れたりするのを見て低濕地の街路は危險だと思つたから谷中三崎町から團子坂へ向つた。谷中の狹い町の兩側に倒れかゝつた家もあつた。鹽煎餅屋の取散らされた店先に烈日の光がさして居たのが心を引いた。團子坂を上つて千駄木へ來るともう倒れかゝつた家などは一軒もなくて、所々唯瓦の一部分剝がれた家があるだけであつた。曙町へはいると、一寸見たところでは殆ど何事も起らなかつたかのやうに森閑として、春のやうに朗かな日光が門並を照して居る。宅の玄關へはいると妻は箒を持つて壁の隅々からこぼれ落ちた壁土を掃除して居るところであつた。隣の家の前の煉瓦塀はすつかり道路へ崩れ落ち、隣と宅の境の石垣も全部、此れは宅の方へ倒れて居る。若し裏庭へ出て居たら危險なわけであつた。聞いて見ると可なりひどいゆれ方で居間の唐紙がすつかり倒れ、猫が驚いて庭へ飛出したが、我家の人々は飛出さなかつた。此れは平生幾度となく家族に云ひ含めてあつたことの效果があつたのだといふやうな氣がした。ピアノが臺の下の小滑車で少しばかり歩き出して居り、花瓶臺の上の花瓶が板間にころがり落ちたのが不思議に碎けないでちやんとして居た。あとは瓦が數枚落ちたのと壁に龜裂が入つた位のものであつた。長男が中學校の始業日で本所の果迄行つて居たのだが地震のときはもう歸宅して居た。それで、時々の餘震はあつても、その餘は平日と何も變つたことがないやうな氣がして、ついさきに東京中が火になるだらうと考へたことなどは綺麗に忘れて居たのであつた。
その内に助手の西田君が來て大學の醫化學敎室が火事だが理學部は無事だといふ。N君が來る。隣のTM敎授が來て市中所々出火だといふ。縁側から見ると南の空に珍らしい積雲が盛り上つて居る。それは普通の積雲とは全くちがつて、先年櫻島大噴火の際の噴雲を寫眞で見るのと同じやうに典型的の所謂コーリフラワー狀のものであつた。餘程盛な火災の爲に生じたものと直感された。此雲の上には實に東京ではめつたに見られない紺靑の秋の空が澄み切つて、じりじり暑い殘暑の日光が無風の庭の葉鷄頭に輝いて居るのであつた。さうして電車の音も止り近所の大工の音も止み、世間がしんとして實に靜寂な感じがしたのであつた。
夕方藤田君が來て、圖書館と法文科も全燒、山上集會所も本部も燒け、理學部では木造の數學敎室が燒けたと云ふ。夕食後E君と白山へ行つて蠟燭を買つて來る。TM氏が來て大學の樣子を知らせてくれた。夜になつてから大學へ樣子を見に行く、圖書館の書庫の中の燃えて居るさまが窓外からよく見えた。一晩中位はかゝつて燃えさうに見えた。普通の火事ならば大勢の人が集つて居るであらうに、あたりには人影もなく唯野良犬が一匹そこいらにうろうろして居た。メートルとキログラムの副原器を收めた小屋の木造の屋根が燃えて居るのを三人掛りで消して居たが耐火構造の室内は大丈夫と思はれた。それにしても屋上に此んな燃草をわざわざ載せたのは愚な設計であつた。物理敎室の窓枠の一つに飛火が付いて燃えかけたのを秋山、小澤兩理學士が消して居た。バケツ一つだけで彌生町門外の井戸迄汲みに行つてはぶつかけて居るのであつた。此れも捨てゝ置けば建物全體が燒けてしまつたであらう。十一時頃歸る途中の電車通は露宿者で一杯であつた。火事で眞紅に染まつた雲の上には靑い月が照らして居た。
九月二日。曇
朝大學へ行つて破損の狀況を見廻つてから、本郷通を湯島五丁目邊迄行くと、綺麗に燒拂はれた湯島臺の起伏した地形が一目に見え上野の森が思ひもかけない近くに見えた。兵燹といふ文字が頭に浮んだ。又江戸以前の此邊の景色も想像されるのであつた。電線がかたまりこんがらがつて道を塞ぎ燒けた電車の骸骨が立往生して居た。土藏もみんな燒け、所々煉瓦塀の殘骸が交つて居る。焦げた樹木の梢が其儘眞白に灰をかぶつて居るのもある。明神前の交番と自働電話だけが奇蹟のやうに燒けずに殘つて居る。松住町迄行くと淺草下谷方面はまだ一面に燃えて居て黑煙と焰の海である。煙が暑く咽つぽく眼に滲みて進めない。其煙の奧の方から本郷の方へと陸續と避難して來る人々の中には顔も兩手も癩病患者のやうに火膨れのしたのを左右二人で肩に凭らせ引きずるやうにして連れて來るのがある。さうかと思ふと又反對に向ふへ行く人々の中には寫眞機を下げて遠足にでも行くやうな呑氣さうな樣子の人もあつた。淺草の親戚を見舞ふことは斷念して松住町から御茶の水の方へ上つて行くと、女子高等師範の庭は杏雲堂病院の避難所になつて居ると立札が讀まれる。御茶の水橋は中程の兩側が少し崩れただけで殘つて居たが駿河臺は全部焦土であつた。明治大學前に黑焦の死體がころがつて居て一枚の燒けたトタン板が被せてあつた。神保町から一ッ橋迄來て見ると氣象臺も大部分は燒けたらしいが官舎が不思議に殘つて居るのが石垣越しに見える。橋に火がついて燃えて居るので巡査が張番して居て人を通さない。自轉車が一臺飛んで來て制止にかまはず突切つて渡つて行つた。堀に沿うて牛が淵迄行つて道端で憩うて居ると前を避難者が引切なしに通る。實に色んな人が通る。五十恰好の女が一人大きな犬を一匹背中におぶつて行く、風呂敷包一つ持つて居ない。浴衣が泥水でも浴びたかのやうに黄色く染まつて居る。多勢の人が見て居るのも無關心のやうにわき見もしないで急いで行く。若い男で大きな蓮の葉を頭にかぶつて上から手拭でしばつて居るのがある。それから又氷袋に水を入れたのを頭にぶら下げて歩きながら、時々その水を煽つて居るのもある。と、土方風の男が一人繩か何かガラガラ引きずりながら引つぱつて來るのを見ると、一枚の燒けトタンの上に二尺角くらゐの氷塊をのつけたのを何となく得意げに引きずつて行くのであつた。さうした行列の中を一臺立派な高級自動車が人の流れに堰かれながら居るのを見ると、車の中には多分掛物でも入つて居るらしい桐の箱が一杯に積込まれて、その中にうづまるやうに一人の男が腰をかけてあたりを見廻して居た。
歸宅して見たら燒け出された淺草の親戚のものが十三人避難して來て居た。いづれも何一つ持出すひまもなく、昨夜上野公園で露宿して居たら巡査が來て○○人の放火者が徘徊するから注意しろと云つたさうだ。井戸に毒を入れるとか、爆彈を投げるとかさまざまな浮説が聞こえて來る。こんな場末の町へまでも荒して歩く爲には一體何千キロの毒藥、何萬キロの爆彈が入るであらうか、さういふ目の子勘定だけからでも自分にはその話は信ぜられなかつた。
夕方に駒込の通へ出て見ると、避難者の群が陸續と瀧野川の方へ流れて行く。表通の店屋などでも荷物を纏めて立退用意をして居る。歸つて見ると、近所でも家を引拂つたのがあるといふ。上野方面の火事がこの邊迄燒けて來ようとは思はれなかつたが萬一の場合の避難の心構だけはした。さて避難しようとして考へて見ると、どうしても持出さなければならないやうな物は殆ど無かつた。たゞ自分の描き集めた若干の油繪だけが一寸惜しいやうな氣がしたのと、人から預つて居たローマ字書きの書物の原稿に責任を感じたくらゐである。妻が三毛猫だけ連れてもう一匹の玉の方は置いて行かうと云つたら、子供等がどうしても連れて行くと云つてバスケットかなんかを用意して居た。
九月三日(月曜)曇後雨
朝九時頃から長男を板橋へやり、三代吉を賴んで白米、野菜、鹽などを送らせるやうにする。自分は大學へ出かけた。追分の通の片側を田舎へ避難する人が引切なしに通つた。反對の側は未だ避難して居た人が歸つて來るのや、田舎から入込んで來るのが反對の流れをなして居る。呑氣さうな顔をして居る人もあるが見ただけで隨分悲慘な感じのする人もある。負傷した片足を引きずり引きずり杖にすがつて行く若者の顔には何處へ行くといふあてもないらしい絶望の色があつた。夫婦して小さな躄車のやうなものに病人らしい老母を載せて引いて行く、病人が塵埃で眞黑になつた顔を仰向けて居る。
歸りに追分邊でミルクの罐やせんべいビスケットなど買つた。燒けた區域に接近した方面のあらゆる食料品店の店先はからつぽになつて居た。さうした食料品の缺乏が漸次に波及して行く樣が歴然とわかつた。歸つてから用心に鰹節、梅干、罐詰、片栗粉等を近所へ買ひにやる。何だか惡い事をするやうな氣がするが、二十餘人の口を託されて居るのだからやむを得ないと思つた。午後四時にはもう三代吉の父親の辰五郎が白米、薩摩芋、大根、茄子、醬油、砂糖など車に積んで持つて來たので少し安心する事が出來た。併し又この場合に、臺所から一車もの食料品を持込むのはかなり氣の引けることであつた。
E君に靑山の小宮君(※小宮豊隆)の留守宅の樣子を見に行つてもらつた。歸つての話によると、地震の時長男が二階に居たら書棚が倒れて出口をふさいだので心配した、それだけで別に異狀はなかつたさうである、その後は邸前の處に避難して居たさうである。
夜警で一緒になつた人で地震當時前橋に行つて居た人の話によると、一日の夜の東京の火事は丁度火柱のやうに見えたので大島の噴火でないかと云ふ噂があつたさうである。 (昭和十年十月) ]
(付記一)『寺田寅彦 妻たちの歳月(山田一郎著)』所収「関東大震災」に、関東大震災時の「寺田寅彦」一家の様子が記述されている。この翌年(大正十三)のことについて、次のように記述されている。
[ (※大正十三年)四月二十一日、「東一(※長男)始業式(※一高)、並に入寮式」、二十四日、「東一入寮」。この年はお目出が重なって、十月五日、長女の貞子が日本銀行勤務の森博道と芝公園の三縁亭で見合いをした。出席者「両方親子三人」と日記あるので志ん(再々婚の「紳」夫人)も出たのであろう。縁談は順調に進んで十五日、結納。十一月三十日、日比谷大神宮で結婚式、帝国ホテルで披露宴をした。
貞子は寅彦の最初の妻夏子の忘れがたみで、生まれるとすぐ祖母の亀(※寅彦の母・亀子)に引き取られて高知で育ち、女学校一年の夏、初めて東京で父と暮らした(※寅彦の母・亀子も同居することになる)。寅彦の二度目妻寛子には子どもが四人いたので、彼女は義理の弟妹四人と少女時代を送った。母親譲りの美貌だったので、結婚式の写真は京美人のように綺麗だったと、森博道の妹が書いている文章を読んだことがある(※「昭和五年一月に、森博道は男児を遺して亡くなっている」=『寺田寅彦覚書(山田一郎著)』)。
以下略 ](『寺田寅彦 妻たちの歳月(山田一郎著)』)
(再掲) 「寺田寅彦」の子どもたち
https://yahan.blog.ss-blog.jp/2023-10-04

「寺田寅彦の三人の妻」
https://ameblo.jp/koketsuyuzo/image-12373883266-14185283842.html
[右→再婚の妻「寛子」
左→寅彦の子供たち(左から「長男・東一、次女・弥生、三女・雪子、長女・貞子(先妻夏子との子)、次男・正二」)]
(付記二)『渋柿の木の下で(中村英利子著)』所収「東洋城、関東大震災で焼け出される」周辺(要約抜粋)
[大正十二年九月一日。
時刻は、正午のほんのすこし前だった。麹町区平河町の自宅兼「渋柿社」で、東洋城が昼飯を一口食べたとき、突然ガタガタと家が揺れた。東洋城は箸を捨てるやいなや立ち上がり、座卓の向こうに坐っていた母の敏子を抱えて裸足で庭へ飛び出した。
「※(上記の「東洋城」の句より)
驚きや垣朝顔も沓石
冷かもしらで地踏む裸足かな
まざまざと抱ける母や老の秋 」
避難先は紀尾井町の北白川邸と初めから心づもりをしており、万一の場合を考え、宵のうちから頼んでおいた。まず母を宮廷へ避難させ、少しばかりり荷物は何度か取りに帰ればいいと思っていた。
「※(上記の「東洋城」の句より)
塀はたりたり倒る野分にもあらず
なゐふるや生色ゆるゝ秋の草
その時幾十万死にしを知らず蜻蛉かな
なゐふるやありなしの命人の秋
蛼(コオロギ)よ地軸折れしと人のいふに 」
今の東洋城にとって大切なものは、老いた母の命であり、「渋柿」の原稿であった。東京の半分が猛火に包まれた際、東洋城はまず母を非難させ、選半ばの巻頭句稿や編集した原稿を救助し、それを詰めた大きな行折を一人で搬出し、細引きひもで引きずって避難先までもっていった。
「※(上記の「東洋城」の句より)
洛陽に劫火(ゴオカ)つゞくや秋幾日
いねもせで備ふことあり夜半の秋
ももぐれば玄米悲し人の秋
鳥渡る下の現世なる地変かな 」
東武鉄道が動き出すと東洋城はすぐ栃木へ行き、同人の小林晨悟(しんご)はじめ何人かの尽力で、両毛印刷という現地の印刷所で「渋柿」を発行する運びとなった。そして、帰郷すると、早速余丁町の三畳庵で次号の編集をはじめることになった。「渋柿」の刊行は一刻の渋滞も許さないと、物もなく生活も不自由ななか、筆一本、紙一帖で編集に挑んだのである、
三畳庵というのは、卓四郎家(※東洋城の三弟)の玄関脇にあった書生部屋のことで、障子は煤け、襖は色褪せ、電灯も古びて薄暗かったが、東洋城はこの三畳ひと間だけで寝起きし、当然編集もこの部屋で行った。]
(付記三) 「俳誌・渋柿(405号/昭和23・1)」周辺
.jpg)
「俳誌・渋柿(405号/昭和23・1)」(奥付/p17~17)
https://dl.ndl.go.jp/pid/6071536/1/10
(目次)
巻頭語 / 秋谷立石山人/p表1~
中野から / 小宮蓬里野人/p表2~
敗太郎(中) / みどり/p1~1
卷頭句 / 東洋城/p2~12
句作問答/p2~6
社告/p17~17
消息 / 諸氏/p17~17
勉強表の勉強表 / 山冬子調/p13~13
落木林森(十三)山中餅搗-雪山の薪 / 東洋城/p14~15
題詠/p16~16
雲の峯 / 喜舟/p16~16
暑さ / 括瓠/p16~16
東洋城近詠/p18~18
玉菜の外葉 / ひむがし/p18~18
奥付/p17~17
(※メモ)
一、「中野から / 小宮蓬里野人/p表2~」は、「小宮豊隆(俳号・蓬里雨)」の、当時の近況が知らされている。下記「年譜」の「※昭和21年 1946 東京音楽学校(現東京芸術大学)校長となる。教育刷新委員・国語審議会委員となる。」の頃である。
https://yahan.blog.ss-blog.jp/2023-10-14
二、「勉強表の勉強表 / 山冬子調/p13~13」は、昭和十四年から昭和二十二年までの「渋柿」の巻頭句(「ホトトギス」の「雑詠入選句」にあたるもの)を占めた句数の表(抜粋)である。

https://dl.ndl.go.jp/pid/6071536/1/8
上記のトップの「喜舟」は、昭和二十七年(1952)に東洋城の跡を引き継いで「渋柿・主宰」を務めた「野村喜舟」である。三番目の「晨悟」は、「小林晨悟(こばやししんご)/明治二十七年生れ、昭和四十三年没(1894~1968)」で、「晨悟」は、大正四年「渋柿」創刊より参加、昭和二十七年離脱。この離脱は、東洋城の誌事(主宰)より隠居(隠退)の節目の年となり、『渋柿』主宰は「野村喜舟」、その編集発行は、「勉強表の勉強表 / 山冬子調/p13~13」の、十番目の「(徳永)山冬子」と、八番目の「(徳永)夏川女」との「徳永御夫妻」に託されることになる。
この「(徳永)山冬子」は、昭和五十一年(1976)に、喜舟の跡を継いで「渋柿・主宰(三代)」となる。
https://kotobank.jp/word/%E5%BE%B3%E6%B0%B8%20%E5%B1%B1%E5%86%AC%E5%AD%90-1650332
四、冒頭の「奥付/p17~17」中、
〇「編集兼発行人」→「東京都品川区上大崎一丁目四百七十番地/松根卓四郎」の「松根卓四郎」は、東洋城(嫡男)の弟(三男)である。この「卓四郎」は、「編集兼発行人」となっているが、実質的には「編集兼発行人」は「主宰・東洋城」で、「卓四郎」宅の一間を「渋柿本社」としており、謂わば、「卓四郎」は「社主」ということになる。
〇「印刷者」→「栃木県栃木市室町二百四十五番地・松本寅吉」/「印刷所」→「同・両毛印刷株式会社」は、大正十二年(1926)の、関東大震災により、東洋城の平河町の屋敷、並びに、発行所が炎上して、直ちに、栃木市で、その年の「渋柿十月号」を刊行し、この縁により、昭和二十六・七年(1952)まで、ここが「印刷所・印刷者」となる。「発行所・渋柿者発行部」→「栃木県栃木市倭町二百九十五番地」は「「小林晨悟」の住所と思われる。
[東洋城・四十六歳。寅彦と連句の研究を始め、豊隆も帰朝後参加した。東北を行脚、京洛、伊予に遊ぶ。関東大震災により平河町の屋敷炎上。直ちに栃木に赴き、渋柿十月刊。(この縁により昭和二十六年まで栃木で印刷した。) 震災を機に「朝日俳壇」の選者を辞した。]
[寅彦(寅日子)・四十六歳。一月、漱石俳句研究会を開く。三月に小宮豊隆がドイツに留学したため、これが最後の研究会となる。四月、松根東洋城と古典連句の研究を始め、その内容は「渋柿」に掲載される。九月一日、関東大震災が起こり、各地の被害調査にあたる。十一月、土木学会帝都復興委員会において「旋風ら就て」を講演する。]
[豊隆(蓬里雨)・四十歳。三月、渡欧。五月にベルリンに到着し、以後欧州各国を歴訪。]
(東洋城)
春の夜のすみだ川あり君が為め(前書「小宮豊隆氏送別会「錦水」にて)
しかも其時秋静かなることにありき(前書「大地震ふ 十四句」)
驚きや垣朝顔も沓石も(同上)
冷かもしらで地踏む裸足かな(同上)
まざまざと抱ける母や老の秋(同上)
塀はたりたり倒る野分にもあらず(同上)
なゐふるや生色ゆるゝ秋の草(同上)
その時幾十万死にしを知らず蜻蛉かな(同上)
なゐふるやありなしの命人の秋(同上)
蛼(コオロギ)よ地軸折れしと人のいふに(同上)
洛陽に劫火(ゴオカ)つゞくや秋幾日(同上)
いねもせで備ふことあり夜半の秋(同上)
ももぐれば玄米悲し人の秋(同上)
鳥渡る下の現世なる地変かな(同上)
(寅彦(寅日子))
春の江は靄に暮れ行く別れ哉化(前書「三月小宮豊隆氏送別の句(錦水にて)」)

寺田寅彦から小宮豊隆へあてた手紙「大正12年10月関東大震災の被災状況を報告」
https://www.town.miyako.lg.jp/rekisiminnzoku/kankou/person/komiya_toyotaka.html
(参考) 寺田寅彦の随筆「震災日記より」(旧字・旧仮名) (抜粋)
http://sybrma.sakura.ne.jp/394torahiko.shinsainikki.html
[九月一日。(土曜)
朝はしけ模樣で時々暴雨が襲つて來た。非常な強度で降つて居ると思ふと、まるで斷ち切つたやうにぱたりと止む、さうかと思ふと又急に降り出す實に珍らしい斷續的な降り方であつた。雜誌「文化生活」への原稿「石油ラムプ」を書き上げた。雨が收まつたので上野二科會展招待日の見物に行く。會場に入つたのが十時半頃。蒸暑かつた。フランス展の影響が著しく眼についた。T君(※津田青楓)と喫茶店で紅茶を呑みながら同君の出品畫「I崎の女」(※津田の作品「出雲崎の女)に對する其モデルの良人からの撤囘要求問題の話を聞いて居るうちに急激な地震を感じた。椅子に腰かけて居る兩足の蹠を下から木槌で急速に亂打するやうに感じた。多分其前に來た筈の弱い初期微動を氣が付かずに直ちに主要動を感じたのだらうといふ氣がして、それにしても妙に短週期の振動だと思つて居るうちにいよいよ本當の主要動が急激に襲つて來た。同時に、此れは自分の全く經驗のない異常の大地震であると知つた。其瞬間に子供の時から何度となく母上に聞かされてゐた土佐の安政地震の話がありあり想出され、丁度船に乘つたやうに、ゆたりゆたり搖れると云ふ形容が適切である事を感じた。仰向いて會場の建築の搖れ工合を注意して見ると四五秒程と思はれる長い週期でみしみしみしみしと音を立てながら緩やかに搖れて居た。それを見たとき此れなら此建物は大丈夫だといふことが直感されたので恐ろしいといふ感じはすぐになくなつてしまつた。さうして、此珍らしい強震の振動の經過を出來るだけ精しく觀察しようと思つて骨を折つて居た。
主要動が始まつてびつくりしてから數秒後に一時振動が衰へ、此分では大した事もないと思ふ頃にもう一度急激な、最初にも増した烈しい波が來て、二度目にびつくりさせられたが、それからは次第に減衰して長週期の波ばかりになつた。
同じ食卓に居た人々は大抵最初の最大主要動で吾勝に立上つて出口の方へ驅出して行つたが、自分等の筋向ひに居た中年の夫婦は其時は未だ立たなかつた。しかも其夫人がビフテキを食つて居たのが、少くも見たところ平然と肉片を口に運んで居たのがハツキリ印象に殘つて居る。併し二度目の最大動が來たときは一人殘らず出てしまつて場内はがらんとしてしまつた。油畫の額はゆがんだり、落ちたりしたのもあつたが大抵はちやんとして懸かつて居るやうであつた。此れで見ても、さう此建物の震動は激烈なものでなかつたことがわかる。あとで考へて見ると、此れは建物の自己週期が著しく長いことが有利であつたのであらうと思はれる。震動が衰へてから外の樣子を見に出ようと思つたが喫茶店のボーイも一人殘らず出てしまつて誰れも居ないので勘定をすることが出來ない。それで勘定場近くの便所の口へ出て低い木柵越しに外を見ると、其處に一團、彼處に一團といふ風に人間が寄集つて茫然として空を眺めて居る。此便所口から柵を越えて逃出した人々らしい。空はもう半ば晴れて居たが千切れ千切れの綿雲が嵐の時のやうに飛んで居た。その内にボーイの一人が歸つて來たので勘定をすませた。ボーイがひどく丁寧に禮を云つたやうに記憶する。出口へ出ると其處では下足番の婆さんが唯一人落ち散らばつた履物の整理をして居るのを見付けて、預けた蝙蝠傘を出して貰つて館の裏手の集團の中からT畫伯を捜しあてた。同君の二人の子供も一緒に居た。其時氣のついたのは附近の大木の枯枝の大きなのが折れて墜ちて居る。地震の爲に折れ落ちたのかそれとも今朝の暴風雨で折れたのか分らない。T君に別れて東照宮前の方へ歩いて來ると異樣な黴臭い匂が鼻を突いた。空を仰ぐと下谷の方面からひどい土ほこりが飛んで來るのが見える。此れは非常に多數の家屋が倒潰したのだと思つた、同時に、此れでは東京中が火になるかも知れないと直感された。東照宮前から境内を覗くと石燈籠は一つ殘らず象棋倒しに北の方へ倒れて居る。大鳥居の柱は立つて居るが上の横桁が外れかゝり、しかも落ちないで危く止つて居るのであつた。精養軒のボーイ達が大きな櫻の根元に寄集つて居た。大佛の首の落ちた事は後で知つたがその時は少しも氣が付かなかつた。池の方へ下りる坂脇の稻荷の鳥居も、柱が立つて桁が落ち碎けて居た。坂を下りて見ると不忍辨天の社務所が池の方へのめるやうに倒れかゝつて居るのを見て、なる程此れは大地震だなといふことが漸くはつきり呑込めて來た。
無事な日の續いて居るうちに突然に起つた著しい變化を充分にリアライズするには存外手數が掛かる。此日は二科會を見てから日本橋邊へ出て晝飯を食ふつもりで出掛けたのであつたが、あの地震を體驗し下谷の方から吹上げて來る土埃りの臭を嗅いで大火を豫想し東照宮の石燈籠のあの象棋倒しを眼前に見ても、それでも未だ晝飯のプログラムは帳消しにならずそのまゝになつて居た。併し辨天社務所の倒潰を見たとき初めて此れはいけないと思つた、さうして始めて我家の事が少し氣懸りになつて來た。
辨天の前に電車が一臺停つたまゝ動きさうもない。車掌に聞いても何時動き出すか分らないといふ。後から考へると此んなことを聞くのが如何な非常識であつたかゞよく分るのであるが、其當時自分と同樣の質問を車掌に持出した市民の數は萬を以て數へられるであらう。
動物園裏迄來ると道路の眞中へ疊を持出して其上に病人をねかせて居るのがあつた。人通りのない町はひつそりして居た。根津を拔けて歸るつもりであつたが頻繁に襲つて來る餘震で煉瓦壁の頽れかゝつたのがあらたに倒れたりするのを見て低濕地の街路は危險だと思つたから谷中三崎町から團子坂へ向つた。谷中の狹い町の兩側に倒れかゝつた家もあつた。鹽煎餅屋の取散らされた店先に烈日の光がさして居たのが心を引いた。團子坂を上つて千駄木へ來るともう倒れかゝつた家などは一軒もなくて、所々唯瓦の一部分剝がれた家があるだけであつた。曙町へはいると、一寸見たところでは殆ど何事も起らなかつたかのやうに森閑として、春のやうに朗かな日光が門並を照して居る。宅の玄關へはいると妻は箒を持つて壁の隅々からこぼれ落ちた壁土を掃除して居るところであつた。隣の家の前の煉瓦塀はすつかり道路へ崩れ落ち、隣と宅の境の石垣も全部、此れは宅の方へ倒れて居る。若し裏庭へ出て居たら危險なわけであつた。聞いて見ると可なりひどいゆれ方で居間の唐紙がすつかり倒れ、猫が驚いて庭へ飛出したが、我家の人々は飛出さなかつた。此れは平生幾度となく家族に云ひ含めてあつたことの效果があつたのだといふやうな氣がした。ピアノが臺の下の小滑車で少しばかり歩き出して居り、花瓶臺の上の花瓶が板間にころがり落ちたのが不思議に碎けないでちやんとして居た。あとは瓦が數枚落ちたのと壁に龜裂が入つた位のものであつた。長男が中學校の始業日で本所の果迄行つて居たのだが地震のときはもう歸宅して居た。それで、時々の餘震はあつても、その餘は平日と何も變つたことがないやうな氣がして、ついさきに東京中が火になるだらうと考へたことなどは綺麗に忘れて居たのであつた。
その内に助手の西田君が來て大學の醫化學敎室が火事だが理學部は無事だといふ。N君が來る。隣のTM敎授が來て市中所々出火だといふ。縁側から見ると南の空に珍らしい積雲が盛り上つて居る。それは普通の積雲とは全くちがつて、先年櫻島大噴火の際の噴雲を寫眞で見るのと同じやうに典型的の所謂コーリフラワー狀のものであつた。餘程盛な火災の爲に生じたものと直感された。此雲の上には實に東京ではめつたに見られない紺靑の秋の空が澄み切つて、じりじり暑い殘暑の日光が無風の庭の葉鷄頭に輝いて居るのであつた。さうして電車の音も止り近所の大工の音も止み、世間がしんとして實に靜寂な感じがしたのであつた。
夕方藤田君が來て、圖書館と法文科も全燒、山上集會所も本部も燒け、理學部では木造の數學敎室が燒けたと云ふ。夕食後E君と白山へ行つて蠟燭を買つて來る。TM氏が來て大學の樣子を知らせてくれた。夜になつてから大學へ樣子を見に行く、圖書館の書庫の中の燃えて居るさまが窓外からよく見えた。一晩中位はかゝつて燃えさうに見えた。普通の火事ならば大勢の人が集つて居るであらうに、あたりには人影もなく唯野良犬が一匹そこいらにうろうろして居た。メートルとキログラムの副原器を收めた小屋の木造の屋根が燃えて居るのを三人掛りで消して居たが耐火構造の室内は大丈夫と思はれた。それにしても屋上に此んな燃草をわざわざ載せたのは愚な設計であつた。物理敎室の窓枠の一つに飛火が付いて燃えかけたのを秋山、小澤兩理學士が消して居た。バケツ一つだけで彌生町門外の井戸迄汲みに行つてはぶつかけて居るのであつた。此れも捨てゝ置けば建物全體が燒けてしまつたであらう。十一時頃歸る途中の電車通は露宿者で一杯であつた。火事で眞紅に染まつた雲の上には靑い月が照らして居た。
九月二日。曇
朝大學へ行つて破損の狀況を見廻つてから、本郷通を湯島五丁目邊迄行くと、綺麗に燒拂はれた湯島臺の起伏した地形が一目に見え上野の森が思ひもかけない近くに見えた。兵燹といふ文字が頭に浮んだ。又江戸以前の此邊の景色も想像されるのであつた。電線がかたまりこんがらがつて道を塞ぎ燒けた電車の骸骨が立往生して居た。土藏もみんな燒け、所々煉瓦塀の殘骸が交つて居る。焦げた樹木の梢が其儘眞白に灰をかぶつて居るのもある。明神前の交番と自働電話だけが奇蹟のやうに燒けずに殘つて居る。松住町迄行くと淺草下谷方面はまだ一面に燃えて居て黑煙と焰の海である。煙が暑く咽つぽく眼に滲みて進めない。其煙の奧の方から本郷の方へと陸續と避難して來る人々の中には顔も兩手も癩病患者のやうに火膨れのしたのを左右二人で肩に凭らせ引きずるやうにして連れて來るのがある。さうかと思ふと又反對に向ふへ行く人々の中には寫眞機を下げて遠足にでも行くやうな呑氣さうな樣子の人もあつた。淺草の親戚を見舞ふことは斷念して松住町から御茶の水の方へ上つて行くと、女子高等師範の庭は杏雲堂病院の避難所になつて居ると立札が讀まれる。御茶の水橋は中程の兩側が少し崩れただけで殘つて居たが駿河臺は全部焦土であつた。明治大學前に黑焦の死體がころがつて居て一枚の燒けたトタン板が被せてあつた。神保町から一ッ橋迄來て見ると氣象臺も大部分は燒けたらしいが官舎が不思議に殘つて居るのが石垣越しに見える。橋に火がついて燃えて居るので巡査が張番して居て人を通さない。自轉車が一臺飛んで來て制止にかまはず突切つて渡つて行つた。堀に沿うて牛が淵迄行つて道端で憩うて居ると前を避難者が引切なしに通る。實に色んな人が通る。五十恰好の女が一人大きな犬を一匹背中におぶつて行く、風呂敷包一つ持つて居ない。浴衣が泥水でも浴びたかのやうに黄色く染まつて居る。多勢の人が見て居るのも無關心のやうにわき見もしないで急いで行く。若い男で大きな蓮の葉を頭にかぶつて上から手拭でしばつて居るのがある。それから又氷袋に水を入れたのを頭にぶら下げて歩きながら、時々その水を煽つて居るのもある。と、土方風の男が一人繩か何かガラガラ引きずりながら引つぱつて來るのを見ると、一枚の燒けトタンの上に二尺角くらゐの氷塊をのつけたのを何となく得意げに引きずつて行くのであつた。さうした行列の中を一臺立派な高級自動車が人の流れに堰かれながら居るのを見ると、車の中には多分掛物でも入つて居るらしい桐の箱が一杯に積込まれて、その中にうづまるやうに一人の男が腰をかけてあたりを見廻して居た。
歸宅して見たら燒け出された淺草の親戚のものが十三人避難して來て居た。いづれも何一つ持出すひまもなく、昨夜上野公園で露宿して居たら巡査が來て○○人の放火者が徘徊するから注意しろと云つたさうだ。井戸に毒を入れるとか、爆彈を投げるとかさまざまな浮説が聞こえて來る。こんな場末の町へまでも荒して歩く爲には一體何千キロの毒藥、何萬キロの爆彈が入るであらうか、さういふ目の子勘定だけからでも自分にはその話は信ぜられなかつた。
夕方に駒込の通へ出て見ると、避難者の群が陸續と瀧野川の方へ流れて行く。表通の店屋などでも荷物を纏めて立退用意をして居る。歸つて見ると、近所でも家を引拂つたのがあるといふ。上野方面の火事がこの邊迄燒けて來ようとは思はれなかつたが萬一の場合の避難の心構だけはした。さて避難しようとして考へて見ると、どうしても持出さなければならないやうな物は殆ど無かつた。たゞ自分の描き集めた若干の油繪だけが一寸惜しいやうな氣がしたのと、人から預つて居たローマ字書きの書物の原稿に責任を感じたくらゐである。妻が三毛猫だけ連れてもう一匹の玉の方は置いて行かうと云つたら、子供等がどうしても連れて行くと云つてバスケットかなんかを用意して居た。
九月三日(月曜)曇後雨
朝九時頃から長男を板橋へやり、三代吉を賴んで白米、野菜、鹽などを送らせるやうにする。自分は大學へ出かけた。追分の通の片側を田舎へ避難する人が引切なしに通つた。反對の側は未だ避難して居た人が歸つて來るのや、田舎から入込んで來るのが反對の流れをなして居る。呑氣さうな顔をして居る人もあるが見ただけで隨分悲慘な感じのする人もある。負傷した片足を引きずり引きずり杖にすがつて行く若者の顔には何處へ行くといふあてもないらしい絶望の色があつた。夫婦して小さな躄車のやうなものに病人らしい老母を載せて引いて行く、病人が塵埃で眞黑になつた顔を仰向けて居る。
歸りに追分邊でミルクの罐やせんべいビスケットなど買つた。燒けた區域に接近した方面のあらゆる食料品店の店先はからつぽになつて居た。さうした食料品の缺乏が漸次に波及して行く樣が歴然とわかつた。歸つてから用心に鰹節、梅干、罐詰、片栗粉等を近所へ買ひにやる。何だか惡い事をするやうな氣がするが、二十餘人の口を託されて居るのだからやむを得ないと思つた。午後四時にはもう三代吉の父親の辰五郎が白米、薩摩芋、大根、茄子、醬油、砂糖など車に積んで持つて來たので少し安心する事が出來た。併し又この場合に、臺所から一車もの食料品を持込むのはかなり氣の引けることであつた。
E君に靑山の小宮君(※小宮豊隆)の留守宅の樣子を見に行つてもらつた。歸つての話によると、地震の時長男が二階に居たら書棚が倒れて出口をふさいだので心配した、それだけで別に異狀はなかつたさうである、その後は邸前の處に避難して居たさうである。
夜警で一緒になつた人で地震當時前橋に行つて居た人の話によると、一日の夜の東京の火事は丁度火柱のやうに見えたので大島の噴火でないかと云ふ噂があつたさうである。 (昭和十年十月) ]
(付記一)『寺田寅彦 妻たちの歳月(山田一郎著)』所収「関東大震災」に、関東大震災時の「寺田寅彦」一家の様子が記述されている。この翌年(大正十三)のことについて、次のように記述されている。
[ (※大正十三年)四月二十一日、「東一(※長男)始業式(※一高)、並に入寮式」、二十四日、「東一入寮」。この年はお目出が重なって、十月五日、長女の貞子が日本銀行勤務の森博道と芝公園の三縁亭で見合いをした。出席者「両方親子三人」と日記あるので志ん(再々婚の「紳」夫人)も出たのであろう。縁談は順調に進んで十五日、結納。十一月三十日、日比谷大神宮で結婚式、帝国ホテルで披露宴をした。
貞子は寅彦の最初の妻夏子の忘れがたみで、生まれるとすぐ祖母の亀(※寅彦の母・亀子)に引き取られて高知で育ち、女学校一年の夏、初めて東京で父と暮らした(※寅彦の母・亀子も同居することになる)。寅彦の二度目妻寛子には子どもが四人いたので、彼女は義理の弟妹四人と少女時代を送った。母親譲りの美貌だったので、結婚式の写真は京美人のように綺麗だったと、森博道の妹が書いている文章を読んだことがある(※「昭和五年一月に、森博道は男児を遺して亡くなっている」=『寺田寅彦覚書(山田一郎著)』)。
以下略 ](『寺田寅彦 妻たちの歳月(山田一郎著)』)
(再掲) 「寺田寅彦」の子どもたち
https://yahan.blog.ss-blog.jp/2023-10-04

「寺田寅彦の三人の妻」
https://ameblo.jp/koketsuyuzo/image-12373883266-14185283842.html
[右→再婚の妻「寛子」
左→寅彦の子供たち(左から「長男・東一、次女・弥生、三女・雪子、長女・貞子(先妻夏子との子)、次男・正二」)]
(付記二)『渋柿の木の下で(中村英利子著)』所収「東洋城、関東大震災で焼け出される」周辺(要約抜粋)
[大正十二年九月一日。
時刻は、正午のほんのすこし前だった。麹町区平河町の自宅兼「渋柿社」で、東洋城が昼飯を一口食べたとき、突然ガタガタと家が揺れた。東洋城は箸を捨てるやいなや立ち上がり、座卓の向こうに坐っていた母の敏子を抱えて裸足で庭へ飛び出した。
「※(上記の「東洋城」の句より)
驚きや垣朝顔も沓石
冷かもしらで地踏む裸足かな
まざまざと抱ける母や老の秋 」
避難先は紀尾井町の北白川邸と初めから心づもりをしており、万一の場合を考え、宵のうちから頼んでおいた。まず母を宮廷へ避難させ、少しばかりり荷物は何度か取りに帰ればいいと思っていた。
「※(上記の「東洋城」の句より)
塀はたりたり倒る野分にもあらず
なゐふるや生色ゆるゝ秋の草
その時幾十万死にしを知らず蜻蛉かな
なゐふるやありなしの命人の秋
蛼(コオロギ)よ地軸折れしと人のいふに 」
今の東洋城にとって大切なものは、老いた母の命であり、「渋柿」の原稿であった。東京の半分が猛火に包まれた際、東洋城はまず母を非難させ、選半ばの巻頭句稿や編集した原稿を救助し、それを詰めた大きな行折を一人で搬出し、細引きひもで引きずって避難先までもっていった。
「※(上記の「東洋城」の句より)
洛陽に劫火(ゴオカ)つゞくや秋幾日
いねもせで備ふことあり夜半の秋
ももぐれば玄米悲し人の秋
鳥渡る下の現世なる地変かな 」
東武鉄道が動き出すと東洋城はすぐ栃木へ行き、同人の小林晨悟(しんご)はじめ何人かの尽力で、両毛印刷という現地の印刷所で「渋柿」を発行する運びとなった。そして、帰郷すると、早速余丁町の三畳庵で次号の編集をはじめることになった。「渋柿」の刊行は一刻の渋滞も許さないと、物もなく生活も不自由ななか、筆一本、紙一帖で編集に挑んだのである、
三畳庵というのは、卓四郎家(※東洋城の三弟)の玄関脇にあった書生部屋のことで、障子は煤け、襖は色褪せ、電灯も古びて薄暗かったが、東洋城はこの三畳ひと間だけで寝起きし、当然編集もこの部屋で行った。]
(付記三) 「俳誌・渋柿(405号/昭和23・1)」周辺
.jpg)
「俳誌・渋柿(405号/昭和23・1)」(奥付/p17~17)
https://dl.ndl.go.jp/pid/6071536/1/10
(目次)
巻頭語 / 秋谷立石山人/p表1~
中野から / 小宮蓬里野人/p表2~
敗太郎(中) / みどり/p1~1
卷頭句 / 東洋城/p2~12
句作問答/p2~6
社告/p17~17
消息 / 諸氏/p17~17
勉強表の勉強表 / 山冬子調/p13~13
落木林森(十三)山中餅搗-雪山の薪 / 東洋城/p14~15
題詠/p16~16
雲の峯 / 喜舟/p16~16
暑さ / 括瓠/p16~16
東洋城近詠/p18~18
玉菜の外葉 / ひむがし/p18~18
奥付/p17~17
(※メモ)
一、「中野から / 小宮蓬里野人/p表2~」は、「小宮豊隆(俳号・蓬里雨)」の、当時の近況が知らされている。下記「年譜」の「※昭和21年 1946 東京音楽学校(現東京芸術大学)校長となる。教育刷新委員・国語審議会委員となる。」の頃である。
https://yahan.blog.ss-blog.jp/2023-10-14
二、「勉強表の勉強表 / 山冬子調/p13~13」は、昭和十四年から昭和二十二年までの「渋柿」の巻頭句(「ホトトギス」の「雑詠入選句」にあたるもの)を占めた句数の表(抜粋)である。

https://dl.ndl.go.jp/pid/6071536/1/8
上記のトップの「喜舟」は、昭和二十七年(1952)に東洋城の跡を引き継いで「渋柿・主宰」を務めた「野村喜舟」である。三番目の「晨悟」は、「小林晨悟(こばやししんご)/明治二十七年生れ、昭和四十三年没(1894~1968)」で、「晨悟」は、大正四年「渋柿」創刊より参加、昭和二十七年離脱。この離脱は、東洋城の誌事(主宰)より隠居(隠退)の節目の年となり、『渋柿』主宰は「野村喜舟」、その編集発行は、「勉強表の勉強表 / 山冬子調/p13~13」の、十番目の「(徳永)山冬子」と、八番目の「(徳永)夏川女」との「徳永御夫妻」に託されることになる。
この「(徳永)山冬子」は、昭和五十一年(1976)に、喜舟の跡を継いで「渋柿・主宰(三代)」となる。
https://kotobank.jp/word/%E5%BE%B3%E6%B0%B8%20%E5%B1%B1%E5%86%AC%E5%AD%90-1650332
四、冒頭の「奥付/p17~17」中、
〇「編集兼発行人」→「東京都品川区上大崎一丁目四百七十番地/松根卓四郎」の「松根卓四郎」は、東洋城(嫡男)の弟(三男)である。この「卓四郎」は、「編集兼発行人」となっているが、実質的には「編集兼発行人」は「主宰・東洋城」で、「卓四郎」宅の一間を「渋柿本社」としており、謂わば、「卓四郎」は「社主」ということになる。
〇「印刷者」→「栃木県栃木市室町二百四十五番地・松本寅吉」/「印刷所」→「同・両毛印刷株式会社」は、大正十二年(1926)の、関東大震災により、東洋城の平河町の屋敷、並びに、発行所が炎上して、直ちに、栃木市で、その年の「渋柿十月号」を刊行し、この縁により、昭和二十六・七年(1952)まで、ここが「印刷所・印刷者」となる。「発行所・渋柿者発行部」→「栃木県栃木市倭町二百九十五番地」は「「小林晨悟」の住所と思われる。
「東洋城・寅彦、そして、豊隆」(漱石没後~寅彦没まで)俳句・連句管見(その六) [東洋城・寅日子(寅彦)・蓬里雨(豊隆)]
その六「大正十一年(一九二二)」
[東洋城・四十五歳。鎌倉で俳諧道場。伊予を指導遍歴。「渋柿」『百号記念号』刊。奥州、伊予に遊ぶ。百号記念大会開催。]
秋山の一路なりけり天に通ず(前書「渋柿満一百号所感」)
梅に訪ひき牡丹に詩会なからめや(「鎌倉俳諧道場四十四句」の冒頭の句。前書「門内有花」)
よき声や春夜の堂のいづこより(「同上」の六句目。前書「夢窓国師)
蛙田も恋猫も遠し下の里(「同上」の十五句目。前書「燈下幾十房」)
花にして桜にして花盛りかな(「同上」の二十句目。前書「俳禅一昧」)
夜半春の石段の闇となりにけり(「同上」の末尾の句。前書「会後寂寥」)
ふるさとや土塀抽(ぬき)んず紅芙蓉(前書「家郷即事」)
初汐や浜からすぐに狭き町(前書「今治市」)
遠島に砂浜ありぬ秋晴るゝ(前書「北条より高浜へ」)
日を昏(くら)う眼持ちけり秋の蝶(前書「松山より中山へ」)
里淋しあまり垂り穂の稲の中
[寅彦=寅日子・四十五歳。連句の実作を始める。小宮豊隆の「客去って唯眺め居る炭火かな」に「麻布へ抜ける木枯の音」とつけたもの。十月、物理学第三講座担当となる。十一月、来日したアインシュタインの特別講義、歓迎レセプション等に出席する。研究のかたわらに油絵を描き、またバイオリンを習い始める。]
物云へど猫は答へぬ寒さ哉(「日記の中より二句/一月三十一日/小宮君への端書のはしに)
冰(こほ)る夜や顔に寄り来る猫の髭(同上)
[豊隆=蓬里雨・三十九歳。 四月、法政大学教授となる。東北帝国大学法文学部独文講座を引き受ける。]
(「寅彦=寅日子」と「豊隆=蓬里雨」との「付合(つけあい)」)
客去つて唯眺め居る炭火かな(「豊隆=蓬里雨」)
麻布へ抜ける木枯の音(「寅彦=寅日子」)
(墓地の空行く木枯の聲)(寅日子「日記・大正十一年一月三十一日」)
気になるは軍曹殿の鼻の疣(いぼ)( 「寅彦=寅日子」)
むざと折りしく秋の色草(同上)
※ この寅日子と蓬里雨の「付合(つけあい)」は、「片々」と題して、『寺田寅彦全集の「文学篇 第七巻』の「連句」の項に収載されている。
下記のアドレスの、「物理学者・寺田寅彦の連句」(水橋禎子稿)によると、「寅彦の連句制作の端緒は大正十一年頃の小宮との書簡の中に認められる」のとおり、これらは、寅彦と豊隆との「書簡(文音)を通して連句(「付け合い」)」の「文音連句」(参考「文音(連句)の作法)の一種のように思われる。
file:///C:/Users/user/Downloads/6%20(2).pdf
「物理学者・寺田寅彦の連句」(水橋禎子稿)
[寅彦の連句制作の端緒は大正十一年頃の小宮との書簡の中に認められる。本格的に作り始めたのは大正一四年頃からである。寅彦の詠んだ連句の数を表1に示す。
表 1 寅彦が諒んだ連句(歌仙)数
年 連句(歌仙)数
1925(T14) 1
1926 (T15/Sl) 4
1927(S2) 4
1928(S3) 5
1929 (S4) 1
1930(S5) 1
1931 (S6) 8
1932(S7) 8
1933 (S8) 6
1934 (S9) 4
1935(Slu) 5
※未完は除く ]
(参考) 「文音(連句)の作法)」(「猫蓑通信」第38号 平成12(2000)年1月15日刊より)
http://www.neko-mino.org/renkuQA/A38.html
[Q38・文音の作法
文音をやりたいと思っていますが、文音の作法などありましたらお教え下さい。
A38
文音とは連衆と一座して一巻を満尾するのではなく、手紙・ハガキ・電話・ファックスなどによって句を付け合う方法です。
Aが発句を三句作ってBに送ると、Bはその中から一句を選んで、その句に脇を三句付けてAに返します。するとAはまたその三句の中から一句を選んで、その脇に今度は第三を三句付けてBに返すという風にして、挙句まで進み、一巻を巻き上げるのです。特別な場合には一句だけで応酬することもないではありませんが、それはお互いの選句の楽しみを奪い、あるいは選句の資格を認めぬ事にもなりかねません。要するに対吟する人に失礼にならぬよう。これが文音の作法の基本です。尤も、昔は互いに五句ずつ遣り取りする作法が守られておりましたが、現代では簡便な三句付けの方がよろこばれ、段々定着して来ました。
それで文音を始めるには、熟知の間柄なら別ですが、そうでない場合は、お互いに、どのような形式の連句を、どの位のスピードで作る心算なのか、大体のところを決めておく方がよろしいと思います。その点の合意がないと、後でいろいろ悶着がおこる可能性があるからです。
文音の人数は、もちろん何人でも出来るわけですが、たとえば追善百韻の付け廻しなどを除いて、せいぜい三・四人ぐらいまでが最適ではないでしょうか。あまり多いと連衆心のない人が紛れこむ恐れがあり、一巻の気分も滅茶苦茶になってしまうものです。
文音の連句では、実際の一座の楽しい雰囲気が味わえないかわりに、前句を貰ってから付句を十分考え、それを練る時間がたっぷりあることが最大の特色であり長所であります。ただ、それに溺れてしまうと、前句を聞いて即座にそれに応ずる、いわゆる丁々発止のおもしろさがなくなり、また時間があるのにまかせて凝った句ばかりを付けると、一巻が重くなって生気を失う危険性も出て来ます。またあまり返句が遅いと、折角盛り上がっている連衆の気分に水を注す結果になりかねません。出来るだけ早く返句するよう心掛けるベきでありましょう。
ハガキの書き方も別にきまりはありません。
たとえば「文音歌仙 春愁の巻」と第一行に書き、「オ3 石尊掻き海猫ふり仰ぐこともなし 貴什」と次の行に書いたあとは、
「オ4 潮に濡れて光る袖口 拙次」・「乳ほしがりてぐずる背の児 拙次」等、自句を三句、余白は何を書いてもよいのです。
さらに文音が終ったら、必ず校合・清書して、一巻の反省をすることが望ましいです。]
これらを踏まえると、上記の「文音(書簡)連句「付合い」)は、次のとおりのものと解することも出来よう。
(発句=一句目) 客去つて唯眺め居る炭火かな(「豊隆=蓬里雨」、「炭火」=冬)
という「豊隆→寅彦」への「文音(手紙か端書)」という提示に対して、それに応えて「寅彦→豊隆」への「文音(手紙か端書)」で、次の三句(付け句)を返信した。
(脇句=二句目) 麻布へ抜ける木枯の音(「寅彦=寅日子」、「木枯」=冬)
(第三=三句目) 気になるは軍曹殿の鼻の疣(いぼ)( 「同上」、雑)
(四=四句目) むざと折りしく秋の色草(「同上」、「秋」=秋)
(脇句=二句目)の下に記載されている「(墓地の空行く木枯の聲)(寅日子「日記・大正十一年一月三十一日」)」は、寅彦の、この句の「初案」などのメモ書きの句なのであろう。
『渋柿の木の下で(中村英利子著)』では、この「付合い」を、「麻布三連隊」の駐屯地近くの小宮豊隆家での作として、脇句の「麻布へ抜ける木枯の音」も、第三の「気になるは軍曹殿の鼻の疣(いぼ)」も、その「麻布三連隊」からの連想のものとして解している。
その連想の解も捨て難いが、このメモ書きの「墓地の空行く木枯の聲」(初案?)から改案として、麻布へ抜ける木枯の音」の「麻布」は、「近衛師団監督部長」を歴任した「実父・利正」、そして、初婚(十九歳・寅彦と十五歳・夏子)の、その新妻「夏子」の父(「近衛歩兵第二旅団長」などを歴任し陸軍中将となり、後に、男爵を叙爵し華族となり、牛込区議、富士生命社長を務めた『坂井重季』(墓所は青山霊園) )」に連なるイメージとして捉えることも出来よう。
と同時に、下記アドレスの、『東洋城全句集(下巻)』の「連句篇」の冒頭の「歌仙(大正五年)」の、次の連句に準拠しているものと解したい。
(再掲)
[ https://yahan.blog.ss-blog.jp/
(発句)何時の間に月になり居りし花野かな(東洋城)
(「脇・第三・四句目」=「三つ物」)
(脇句) 鹿かあらぬか遠山の声(霽月)
(第三)温泉冷めすと障子〆切るうそ寒み(同上)
(四) 又くりかへす旅行案内(同上)
(以下、略) ]
そして、これらのことは、東洋城の「俳諧 新三つ物」(大正十三年五月「渋柿」所収)そして、「連句形式 起承転結―四折十二句の連句―」(大正十五年六月「渋柿」所収)の俳論などで、その実作が試みられていくものと解したい。
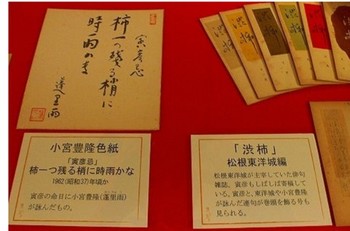
小宮豊隆色紙『寅彦忌 柿一つ残る梢に時雨かな 蓬里雨』と松根東洋城編『渋柿』(1932年~1933年出版)(「高知県立文学館」)
https://ameblo.jp/kochi-narukochan/entry-10789029253.html
(追記一) TORSO(大正十四年八月「渋柿」)周辺
http://www.basho.jp/ronbun/ronbun_2012_11_02.html
[「連句の魅力(連句入門Ⅰ)市川千年稿
「連句の基本は、一、前の句につける。二、鎖のようにつながる。三、同じことをしない(森羅万象を歌いあげよう)」「かつて寺田寅彦が「渋柿」に、トルソという革新的な連句を発表したことがありました。そのトルソは余分なものを切り捨て、連句の原点を求めるというものでした。」「今、ここに、私たちの連句の形式を「帰ってきたトルソ」と命名します。」
▽トルソー 首および四肢を欠く胴体だけの彫像
▽「澁柿」俳誌。大正四年(一九一五)二月創刊。主宰・松根東洋城(明治十一~昭和三九)。誌名は、大正天皇が俳句につきご下問、東洋城が奉答した句「渋柿のごときものにては候へど」による。昭和二七年東洋城隠退し野村喜舟が主宰となる。平成十七年十二月号で一千百号(連句協会報一六一号)。「渋柿はその芭蕉に於いてなされし如く連句を大切にす。之により多くの俳諧を闡明(せんめい)拡充し高揚す」
TORSO(大正十四年八月『渋柿』)
シヤコンヌや国は亡びし歌の秋 寅日子
ラディオにたかる肌寒の群 ゝ
屋根裏は月さす窓の奢りにて 蓬里雨
古里遠し母病むといふ文 ゝ
新しきシャツのボタンのふと取れし 子
手函の底に枯るゝ白薔薇 ゝ
忘れにしあらねど恋はもの憂くて 雨
春雨の夜を忍び音のセロ 子
見下ろせば暗き彼方は海に似て 雨
▽シャコンヌ バロック時代に始まったゆるやかな3拍子の舞曲で、一種の変奏曲。十六世紀に中南米からスペイン・イタリアに伝えられた舞曲に基づく。
▽蓬里雨(ほうりう) 小宮豊隆(明治十七~昭和四一)の俳号。
▽「「トルソ」という題は、それに費やす時間の関係上、歌仙形式の三十六でまとめるのが困難だったので、三句でまとめたり、六句でまとめたり、十句でまとめたり、その時々の気分次第で、いろいろになったが、結局それは、歌仙の断片にすぎないという意味を、しゃれて「トルソ」と名づけたまでであると小宮は云う。」(『寺田寅彦と連句』小林惟司 勉誠出版 平成一四)
「「トルソ」頂戴、いずれも結構でありますが、・・・それからこれは僕も気がつかなかったのだが、「シャコンヌ」の巻の長句が四つ続けて「て止め」になっています。これもいかがいたしましょうか。ご相談申し上げます。・・・」(小宮豊隆宛寺田書簡・大正十四年五月十六日) ]「芭蕉会議」所収「連句の魅力(連句入門Ⅰ)市川千年稿」
http://www.basho.jp/ronbun/ronbun_2013_10_01/06.html
[(連句を楽しむ その六 市川千年稿)
小宮豊隆宛寺田書簡(大正十四年五月十六日)には「・・・それからこれは僕も気がつかなかったのだが、「シャコンヌ」の巻の長句が四つ続けて「て止め」になっています。これもいかがいたしましょうか。ご相談申し上げます。」とあるので、「新しきシャツのボタンのふと取れし」は最初「・・・ふと取れて」であったことが分かる。
小宮豊隆は「「トルソ」という題は、それに費やす時間の関係上、歌仙形式の三十六でまとめるのが困難だったので、三句でまとめたり、六句でまとめたり、十句でまとめたり、その時々の気分次第で、いろいろになったが、結局それは、歌仙の断片にすぎないという意味を、しゃれて「トルソ」と名づけたまでである」と語っていたそうだ。(『寺田寅彦と連句』小林惟司 勉誠出版 平成一四)
寺田寅彦は「徒然草から受けた影響の一つと思はるゝものに自分の俳諧に対する興味と理解の起源があるやうに思ふ。」「心の自由を得てはじめて自己を認識することができる。・・・第百三十七段の前半を見れば、心の自由から風流俳諧の生れる所以を悟ることが出来よう。」(「徒然草の鑑賞」昭和九年)と述べている。「花は盛りに、月は隈なきをのみ見る物かは・・・」。「心に移りゆくよしなし事を、そこはかとなく書きつけ」られていった『徒然草』全二四四段の宇宙と連句の宇宙はどうやらつながっているようだ。(俳句雑誌『蝶』205号(2014年1・2月)]
(追記二)「TORSO―RONDO」(大正十五年十二月「潮音」)周辺
file:///C:/Users/user/Downloads/6%20(1).pdf
[「物理学者・寺田寅彦の連句」(水橋禎子稿)
RONDO №.7
塀のうちなる芝の枯色 蓬里雨
供侍の火鉢の灰も静まりて 寅日子
さざめきめきながら皿洗ふ音 雨
すれ違ふ廊下の簡の仇心 子
夢みる様に匂ふ木犀 雨
不図さめて開けば温泉を噴く谷の音 子
しんとしたのは雪が降るのか 雨
老の限に涙の光る強意見 子
詰ったまゝで煙管ころがる 雨
掃き寄せて縁の日南の塵寒く 子
塀のうちなる・・・
興味深いのは、大正一四~一五年頃、一風変わった連句論や実作が見られることである。
寅彦(寅日子)と小宮(蓬盟雨)・東洋城との日本文学の諸断片」(大正一四年)の中で、寅彦はこのような発言をしている。(中略)
(寅日子)しかしともかくも、連句が他の詩形に比べてよほど飛び放れて変っている事はたしかである。むしろある意味で音楽と似通った点が多いように思う。(略) 音楽の旋律は順序を逆にするとまるでちがったものになってしまう。連句の順序を逆転して読んで行ったらどんなものだろうという問題が起って来る。これは六かしい問題であろうが、私のちょっと試験してみた処では逆に読んでも相当に面白い場合が少なくないようである。
(中略)
『ロンド」といふのは、発句から始めて脇・第三と十句自まで続けて行くうちに、いくらかづつ加減して、その十句自が前句に附くとともに、亦うまく第一の発句に附くやうに工夫して附ける、従って全体が環をなしてぐるぐる廻るやうにと心がけたので、『ロンド」と名づけたのである。(『寺田寅彦全集 文学篇 第七巻・岩波書店)』月報「寅彦と俳諧(小宮豊隆稿・昭和二五年一一月)」) (補記一) 「トルソー(TORSO)」と「ロンド(RONDO)」(「寅日子と蓬里雨」の「新連句」)周辺について(メモ)
東洋城が、その主宰誌「渋柿」で、「東洋城・寅日子・蓬里雨」の三吟などで試みた「新連句」(新連句の試み)は、「俳諧六つ物」(大正十五年)」、「二枚折」(大正十五年)、「二枚屏風」(大正十五年)、「二つ折」(昭和三年・昭和七年)、「TORSO」(大正十五年)、「起承転結」(大正十五年~昭和五年)、『新三つ物』(大正十四年~昭和六年)」と、謂わば、東洋城の「俳諧(連句)・俳句(発句・巻頭句)」観(「俳論」)に基づくものは、『東洋城全句集(下巻)』に、その「俳論」を含めて、その実作が収載されている。
しかし、その「トルソー(TORSO)」のうちの、「ロンド(RONDO)」という形式ものは、
東洋城の「俳諧(連句)・俳句(発句・巻頭句)」観に基づく、その「起承転結」(大正十五年~昭和五年)の「連句新形式起承転結」(「四折十二句の連句」)とは、異質の世界のもので、より多く、「ヴァイオリン奏者」でもある、「寅彦(寅日子)」の世界のものであろう。
ここで、「師(芭蕉)の曰く『たとへば歌仙は三十六歩なり。一歩も後に帰る心なし。行くにしたがひ心の改まるは、ただ先へ行く心なればなり(『三冊子』土芳著)』」の、「俳諧・連句」の「歌仙(三十六句・二花三月)」の、その「一歩も後に帰る心なし」に相反することになる。
「トルソー(TORSO)」という形式は、東洋城らの「渋柿」で実践された、「俳諧新三つ物」・「俳諧六つ物」・「俳諧起承転結(四折十二句、月花一句)」の、一形式のものとして、「一歩も戻る心なし」の、「俳諧・連句」の基本中の基本の原則を踏まえている。
その「トルソー(TORSO)」の一形式の「ロンド(RONDO)」形式というのは、「発句のことは行きて帰る心の味はひなり。例えば、”山里は漫才遅し梅の花”といふ類なり。”山里は漫才遅し”と言ひはなして、梅は咲けりといふ心のごとくに、行きて帰るの心、発句なり(三冊子)」の、「発句のことは行きて帰る心の味はひなり」の、いわゆる、「発句はとり合物也(あわせものなり)。二つとり合わせて、よくとりはやすを上手と云うなり(森川許六著「篇突」)」の、「行きて帰る心」は、「発句」論だけではなく、一巻を成した「俳諧・連句(歌仙)」の諸形式にも、それが何らかの形で関与しているという、これまた、「物理学者(理論)・ヴァイオリン奏者(音楽)・連句・俳句・随筆作家(文芸)」の、一つの警鐘として理解したい。

「トルソ/彫刻 / 金属像 / 大正 / 日本/戸張孤雁 (1882-1927)/とばりこがん/1914年(大正3)年/ブロンズ/H20.0
https://bunka.nii.ac.jp/heritages/detail/43251
[ 高さ20cmの小品であるが、腰部から腹部、腹部から胸部へと、なだらかな起伏を示す量塊と、わずかにひねられた上半身の動勢など、豊かな表現を見せる、堂々とした作品である。東京。日本橋に生まれた孤雁は、もともと画家を志して渡米する。しかし、才気あふれる彫刻家、荻原守衛を通じてロダンに傾倒し、彫刻に転向した。
この「トルソ」の根底にあるのは、人間の生命に対するロマンチックな感動であり、その作風は、デリケートな形体把握と、みずみずしい肉づけの美しさを特徴とする。孤雁はモデルを表面的に写しとる当時の文展アカデミズムに疑問を抱き、生命感にあふれる新鮮な写実主義へと向かう。その意味で彼は、写真的な真実を排し、生きた真実をめざすロダンと荻原の系譜を引き継ぐ彫刻家といってよい。荻原の臨終に際して、孤雁が「折角開かれんとした我が彫刻界が、彼の早逝によって残念にも解し得ず、旧の杢阿弥に還った」と嘆いたのも無理はない。(中谷伸生)]
(補記二)「東洋城の連句」周辺
file:///C:/Users/user/Downloads/KB21%20(2).pdf
(補記三)「漱石と東洋城との連句」周辺
[ 病院
蝙蝠の宵々梅や薄き粥 (漱石)
団扇絵飽きし名所の月 (東洋城)
註文の鮎釣る男瀬に見えて (城)
庄屋の門にゴム輪一台 (石)
相伝の金創膏も練らぬよし (石)
遊女屋続き外楼
(こんな稿片が出てきた。表六句だけであとのないのも今は淋しい。大正八年 城記 )
http://www.basho.jp/ronbun/ronbun_2013_10_01/03.html
正岡子規が「発句は文学なり、連俳は文学に非ず。」(明治二六年「芭蕉雑談」)と評価した連句を、高浜虚子は「聯句はさまざまの宇宙の現象、それは連絡のない宇宙の現象を變化の鹽梅克く横様に配列したものである。」「聯句の面白味は半分その變化の點に在るのだ。」「蓋し聯句中の或る一句の趣味は其の句のすぐ前の句、及其の句のすぐ後の句の聯想によつて助けらるゝが為め(恰も俳句が季の者によつて助けらるゝが如く)季のものゝ助けを借らずとも充分に詩趣を運ぶことが出来る。」と「ホトトギス」第八号(明治三二年五月)で擁護している。
一方、子規は「自分は連句といふ者余り好まねば、古俳書を見ても連句を読みし事無く、又自ら作りし例も甚だ稀である。然るに此等の集にある連句を読めばいたく興に入り感に堪ふるので、終には、これほど面白い者ならば自分も連句をやつて見たいといふ念が起つて来る」と言っている事実がある。(「ホトトギス」第三巻第三号(明治三二年十二月)「発句を連句一巻から切り離し、これに「俳句」という名を付けて、新しい芸術とし」(『連句辞典』)「短詩形として自覚を明確にし」(『俳諧大辞典』)「地発句(ぢほっく・連句を伴わない発句)を新生させた」(『俳文学大辞典』)正岡子規は明治三五年九月十九日に死去。
その二年後の「ホトトギス」明治三七年九月号で虚子は、「俳諧といへば俳諧連歌の事である事はいふ迄も無いが、此明治の俳運復興以来文學者仲間には俳諧連歌は殆ど棄てゝ顧みられ無いで、同時に発句が俳句と呼ばるゝやうになつて、俳諧といふ二字が殆ど俳句といふ事と紛らわしくなつた。」と冒頭で述べ「連句論」を掲載。蕉門の『猿蓑』の「市中は」歌仙を「法則」「意味」「私見」と「三條」に分けて論じ、連句の文学的価値に迫った。
同年十月、虚子は、夏目漱石、坂本四方太(ホトトギス選者)と三吟歌仙を巻いている。その平句の一節は次のように展開。人事句を楽しんでいることがよく分る。
反吐を吐きたる乗合の僧 四方太
意地惡き肥後侍の酒臭く 漱 石
切つて落せし燭臺の足 虚 子
発句にて戀する術もなかりけり 虚 子
妹の婿に家を譲りて 四方太
和歌山で敵に遭ひぬ年の暮 漱 石
なお、この歌仙が巻かれた翌年の「ホトトギス」明治三八年一月号に漱石の「吾輩は猫である」が発表された。さて、「花鳥諷詠と申しますのは花鳥風月を諷詠するといふことで、一層細密に云へば、春夏秋冬四時の移り變りに依つて起る自然界の現象、並にそれに伴ふ人事界の現象を諷詠するの謂であります。」という虚子の自序(『虚子句集』春秋社 昭和三年)対して川崎展宏は高浜虚子全集(毎日新聞社)の月報⑥(昭和四九年四月)で次のように述べている。
「このよく知られた、棒のような定義に、昭和初年代、反ホトトギスの青年たちはいらだったことだろう。いらだったのは「近代」である。俳句を一個独立の近代詩たらしめようとする者たちにとって、今更何が花鳥風月か、ということになる。新興俳句から、いわゆる前衛俳句に至る烈しい俳句近代化の、ないしは現代化の運動は、子規の俳句革新の意図を、それぞれの年代の青年たちが、彼らの生きた時代に力点を置いて推し進めた運動であって、つねに、俳句が現代詩としての問題意識を進んで担おうとした結果であった。連句の座が崩壊し、そこから発句ではなく俳句として出発した近代俳句の、一つの必然の道なのである。
虚子の「花鳥諷詠」は、いまにして思えば、連句の座を失った近代にあって、なお人々の心に残っていた花鳥風月への思ひを拠りどころに、何とかして発句性を回復しようとしたものであった。」
「連句の座」(もちろん芭蕉の座は失われている)が脈々とつながっているから、こうして拙文を書かせてもらっているわけで、私などはこの虚子の花鳥諷詠論はまさに連句のことを的確に表現していると感じる者である。「連句の座を失った近代」に「連句雑俎」(昭和六年)、「俳諧の本質的概論」(昭和七年)を著し、松根東洋城、小宮豊隆らと盛んに連句の実作も試みた寺田寅彦の熱い思いを紹介しよう。
「この芸術はまたある意味で近代の活動映画の先駆者であり、ことにいわゆるモンタージュ映画や前衛映画、そうしておそらく未来に属するいろいろの映画芸術の予想のようなものでもある。それだのに、この「俳諧」という名が多くの人には現代の日本人とは何の交渉もない過去のゆう霊の名のように響くのは何ゆえか。その少なくも一つの理由は、これが従来ただいわゆる宗匠たちのかび臭いずだ袋の奥に秘められて、生きて歩いている人々の、うかがい見るのを許しても、手に取りはだに触れることを許されなかったせいであろう。俳諧自身はかび臭いものではない。いわゆる「さび」や「しおり」は枯骨のようなものではなくて、中には生々しい肉も血もあり、近ごろのいわゆるエロもグロもすべてのものを含有している。このユニークな永久に新鮮でありうべき芸術はすべての日本人に自由に解放され享有されなければならない。そうしてすべての人は自由に各自の解釈、各自の演奏を試みてもさしつかえないものである。俳諧も音楽同様に言葉や理屈では到底説明し難いものだからである。」(昭和六年一月三十日、東京朝日新聞『芭蕉連句の根本解説』(太田水穂著)の書評より抜粋)
通されて二階眩ゆき若葉かな 寅日子
まゐらす茶にも夏空の雲 行 人
これは、行人こと詩人の尾崎喜八が、生前の寅彦の句を発句として昭和二三年に連衆二人と巻いた脇起り歌仙の付合。座の成立、それは他者と共に楽しむ所から始まるのである。
(俳句雑誌『蝶』202号掲載(2013年7・8月)) ]
[東洋城・四十五歳。鎌倉で俳諧道場。伊予を指導遍歴。「渋柿」『百号記念号』刊。奥州、伊予に遊ぶ。百号記念大会開催。]
秋山の一路なりけり天に通ず(前書「渋柿満一百号所感」)
梅に訪ひき牡丹に詩会なからめや(「鎌倉俳諧道場四十四句」の冒頭の句。前書「門内有花」)
よき声や春夜の堂のいづこより(「同上」の六句目。前書「夢窓国師)
蛙田も恋猫も遠し下の里(「同上」の十五句目。前書「燈下幾十房」)
花にして桜にして花盛りかな(「同上」の二十句目。前書「俳禅一昧」)
夜半春の石段の闇となりにけり(「同上」の末尾の句。前書「会後寂寥」)
ふるさとや土塀抽(ぬき)んず紅芙蓉(前書「家郷即事」)
初汐や浜からすぐに狭き町(前書「今治市」)
遠島に砂浜ありぬ秋晴るゝ(前書「北条より高浜へ」)
日を昏(くら)う眼持ちけり秋の蝶(前書「松山より中山へ」)
里淋しあまり垂り穂の稲の中
[寅彦=寅日子・四十五歳。連句の実作を始める。小宮豊隆の「客去って唯眺め居る炭火かな」に「麻布へ抜ける木枯の音」とつけたもの。十月、物理学第三講座担当となる。十一月、来日したアインシュタインの特別講義、歓迎レセプション等に出席する。研究のかたわらに油絵を描き、またバイオリンを習い始める。]
物云へど猫は答へぬ寒さ哉(「日記の中より二句/一月三十一日/小宮君への端書のはしに)
冰(こほ)る夜や顔に寄り来る猫の髭(同上)
[豊隆=蓬里雨・三十九歳。 四月、法政大学教授となる。東北帝国大学法文学部独文講座を引き受ける。]
(「寅彦=寅日子」と「豊隆=蓬里雨」との「付合(つけあい)」)
客去つて唯眺め居る炭火かな(「豊隆=蓬里雨」)
麻布へ抜ける木枯の音(「寅彦=寅日子」)
(墓地の空行く木枯の聲)(寅日子「日記・大正十一年一月三十一日」)
気になるは軍曹殿の鼻の疣(いぼ)( 「寅彦=寅日子」)
むざと折りしく秋の色草(同上)
※ この寅日子と蓬里雨の「付合(つけあい)」は、「片々」と題して、『寺田寅彦全集の「文学篇 第七巻』の「連句」の項に収載されている。
下記のアドレスの、「物理学者・寺田寅彦の連句」(水橋禎子稿)によると、「寅彦の連句制作の端緒は大正十一年頃の小宮との書簡の中に認められる」のとおり、これらは、寅彦と豊隆との「書簡(文音)を通して連句(「付け合い」)」の「文音連句」(参考「文音(連句)の作法)の一種のように思われる。
file:///C:/Users/user/Downloads/6%20(2).pdf
「物理学者・寺田寅彦の連句」(水橋禎子稿)
[寅彦の連句制作の端緒は大正十一年頃の小宮との書簡の中に認められる。本格的に作り始めたのは大正一四年頃からである。寅彦の詠んだ連句の数を表1に示す。
表 1 寅彦が諒んだ連句(歌仙)数
年 連句(歌仙)数
1925(T14) 1
1926 (T15/Sl) 4
1927(S2) 4
1928(S3) 5
1929 (S4) 1
1930(S5) 1
1931 (S6) 8
1932(S7) 8
1933 (S8) 6
1934 (S9) 4
1935(Slu) 5
※未完は除く ]
(参考) 「文音(連句)の作法)」(「猫蓑通信」第38号 平成12(2000)年1月15日刊より)
http://www.neko-mino.org/renkuQA/A38.html
[Q38・文音の作法
文音をやりたいと思っていますが、文音の作法などありましたらお教え下さい。
A38
文音とは連衆と一座して一巻を満尾するのではなく、手紙・ハガキ・電話・ファックスなどによって句を付け合う方法です。
Aが発句を三句作ってBに送ると、Bはその中から一句を選んで、その句に脇を三句付けてAに返します。するとAはまたその三句の中から一句を選んで、その脇に今度は第三を三句付けてBに返すという風にして、挙句まで進み、一巻を巻き上げるのです。特別な場合には一句だけで応酬することもないではありませんが、それはお互いの選句の楽しみを奪い、あるいは選句の資格を認めぬ事にもなりかねません。要するに対吟する人に失礼にならぬよう。これが文音の作法の基本です。尤も、昔は互いに五句ずつ遣り取りする作法が守られておりましたが、現代では簡便な三句付けの方がよろこばれ、段々定着して来ました。
それで文音を始めるには、熟知の間柄なら別ですが、そうでない場合は、お互いに、どのような形式の連句を、どの位のスピードで作る心算なのか、大体のところを決めておく方がよろしいと思います。その点の合意がないと、後でいろいろ悶着がおこる可能性があるからです。
文音の人数は、もちろん何人でも出来るわけですが、たとえば追善百韻の付け廻しなどを除いて、せいぜい三・四人ぐらいまでが最適ではないでしょうか。あまり多いと連衆心のない人が紛れこむ恐れがあり、一巻の気分も滅茶苦茶になってしまうものです。
文音の連句では、実際の一座の楽しい雰囲気が味わえないかわりに、前句を貰ってから付句を十分考え、それを練る時間がたっぷりあることが最大の特色であり長所であります。ただ、それに溺れてしまうと、前句を聞いて即座にそれに応ずる、いわゆる丁々発止のおもしろさがなくなり、また時間があるのにまかせて凝った句ばかりを付けると、一巻が重くなって生気を失う危険性も出て来ます。またあまり返句が遅いと、折角盛り上がっている連衆の気分に水を注す結果になりかねません。出来るだけ早く返句するよう心掛けるベきでありましょう。
ハガキの書き方も別にきまりはありません。
たとえば「文音歌仙 春愁の巻」と第一行に書き、「オ3 石尊掻き海猫ふり仰ぐこともなし 貴什」と次の行に書いたあとは、
「オ4 潮に濡れて光る袖口 拙次」・「乳ほしがりてぐずる背の児 拙次」等、自句を三句、余白は何を書いてもよいのです。
さらに文音が終ったら、必ず校合・清書して、一巻の反省をすることが望ましいです。]
これらを踏まえると、上記の「文音(書簡)連句「付合い」)は、次のとおりのものと解することも出来よう。
(発句=一句目) 客去つて唯眺め居る炭火かな(「豊隆=蓬里雨」、「炭火」=冬)
という「豊隆→寅彦」への「文音(手紙か端書)」という提示に対して、それに応えて「寅彦→豊隆」への「文音(手紙か端書)」で、次の三句(付け句)を返信した。
(脇句=二句目) 麻布へ抜ける木枯の音(「寅彦=寅日子」、「木枯」=冬)
(第三=三句目) 気になるは軍曹殿の鼻の疣(いぼ)( 「同上」、雑)
(四=四句目) むざと折りしく秋の色草(「同上」、「秋」=秋)
(脇句=二句目)の下に記載されている「(墓地の空行く木枯の聲)(寅日子「日記・大正十一年一月三十一日」)」は、寅彦の、この句の「初案」などのメモ書きの句なのであろう。
『渋柿の木の下で(中村英利子著)』では、この「付合い」を、「麻布三連隊」の駐屯地近くの小宮豊隆家での作として、脇句の「麻布へ抜ける木枯の音」も、第三の「気になるは軍曹殿の鼻の疣(いぼ)」も、その「麻布三連隊」からの連想のものとして解している。
その連想の解も捨て難いが、このメモ書きの「墓地の空行く木枯の聲」(初案?)から改案として、麻布へ抜ける木枯の音」の「麻布」は、「近衛師団監督部長」を歴任した「実父・利正」、そして、初婚(十九歳・寅彦と十五歳・夏子)の、その新妻「夏子」の父(「近衛歩兵第二旅団長」などを歴任し陸軍中将となり、後に、男爵を叙爵し華族となり、牛込区議、富士生命社長を務めた『坂井重季』(墓所は青山霊園) )」に連なるイメージとして捉えることも出来よう。
と同時に、下記アドレスの、『東洋城全句集(下巻)』の「連句篇」の冒頭の「歌仙(大正五年)」の、次の連句に準拠しているものと解したい。
(再掲)
[ https://yahan.blog.ss-blog.jp/
(発句)何時の間に月になり居りし花野かな(東洋城)
(「脇・第三・四句目」=「三つ物」)
(脇句) 鹿かあらぬか遠山の声(霽月)
(第三)温泉冷めすと障子〆切るうそ寒み(同上)
(四) 又くりかへす旅行案内(同上)
(以下、略) ]
そして、これらのことは、東洋城の「俳諧 新三つ物」(大正十三年五月「渋柿」所収)そして、「連句形式 起承転結―四折十二句の連句―」(大正十五年六月「渋柿」所収)の俳論などで、その実作が試みられていくものと解したい。
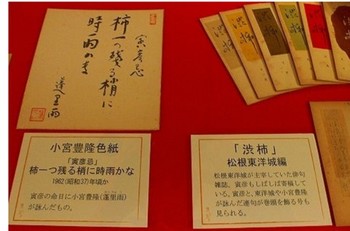
小宮豊隆色紙『寅彦忌 柿一つ残る梢に時雨かな 蓬里雨』と松根東洋城編『渋柿』(1932年~1933年出版)(「高知県立文学館」)
https://ameblo.jp/kochi-narukochan/entry-10789029253.html
(追記一) TORSO(大正十四年八月「渋柿」)周辺
http://www.basho.jp/ronbun/ronbun_2012_11_02.html
[「連句の魅力(連句入門Ⅰ)市川千年稿
「連句の基本は、一、前の句につける。二、鎖のようにつながる。三、同じことをしない(森羅万象を歌いあげよう)」「かつて寺田寅彦が「渋柿」に、トルソという革新的な連句を発表したことがありました。そのトルソは余分なものを切り捨て、連句の原点を求めるというものでした。」「今、ここに、私たちの連句の形式を「帰ってきたトルソ」と命名します。」
▽トルソー 首および四肢を欠く胴体だけの彫像
▽「澁柿」俳誌。大正四年(一九一五)二月創刊。主宰・松根東洋城(明治十一~昭和三九)。誌名は、大正天皇が俳句につきご下問、東洋城が奉答した句「渋柿のごときものにては候へど」による。昭和二七年東洋城隠退し野村喜舟が主宰となる。平成十七年十二月号で一千百号(連句協会報一六一号)。「渋柿はその芭蕉に於いてなされし如く連句を大切にす。之により多くの俳諧を闡明(せんめい)拡充し高揚す」
TORSO(大正十四年八月『渋柿』)
シヤコンヌや国は亡びし歌の秋 寅日子
ラディオにたかる肌寒の群 ゝ
屋根裏は月さす窓の奢りにて 蓬里雨
古里遠し母病むといふ文 ゝ
新しきシャツのボタンのふと取れし 子
手函の底に枯るゝ白薔薇 ゝ
忘れにしあらねど恋はもの憂くて 雨
春雨の夜を忍び音のセロ 子
見下ろせば暗き彼方は海に似て 雨
▽シャコンヌ バロック時代に始まったゆるやかな3拍子の舞曲で、一種の変奏曲。十六世紀に中南米からスペイン・イタリアに伝えられた舞曲に基づく。
▽蓬里雨(ほうりう) 小宮豊隆(明治十七~昭和四一)の俳号。
▽「「トルソ」という題は、それに費やす時間の関係上、歌仙形式の三十六でまとめるのが困難だったので、三句でまとめたり、六句でまとめたり、十句でまとめたり、その時々の気分次第で、いろいろになったが、結局それは、歌仙の断片にすぎないという意味を、しゃれて「トルソ」と名づけたまでであると小宮は云う。」(『寺田寅彦と連句』小林惟司 勉誠出版 平成一四)
「「トルソ」頂戴、いずれも結構でありますが、・・・それからこれは僕も気がつかなかったのだが、「シャコンヌ」の巻の長句が四つ続けて「て止め」になっています。これもいかがいたしましょうか。ご相談申し上げます。・・・」(小宮豊隆宛寺田書簡・大正十四年五月十六日) ]「芭蕉会議」所収「連句の魅力(連句入門Ⅰ)市川千年稿」
http://www.basho.jp/ronbun/ronbun_2013_10_01/06.html
[(連句を楽しむ その六 市川千年稿)
小宮豊隆宛寺田書簡(大正十四年五月十六日)には「・・・それからこれは僕も気がつかなかったのだが、「シャコンヌ」の巻の長句が四つ続けて「て止め」になっています。これもいかがいたしましょうか。ご相談申し上げます。」とあるので、「新しきシャツのボタンのふと取れし」は最初「・・・ふと取れて」であったことが分かる。
小宮豊隆は「「トルソ」という題は、それに費やす時間の関係上、歌仙形式の三十六でまとめるのが困難だったので、三句でまとめたり、六句でまとめたり、十句でまとめたり、その時々の気分次第で、いろいろになったが、結局それは、歌仙の断片にすぎないという意味を、しゃれて「トルソ」と名づけたまでである」と語っていたそうだ。(『寺田寅彦と連句』小林惟司 勉誠出版 平成一四)
寺田寅彦は「徒然草から受けた影響の一つと思はるゝものに自分の俳諧に対する興味と理解の起源があるやうに思ふ。」「心の自由を得てはじめて自己を認識することができる。・・・第百三十七段の前半を見れば、心の自由から風流俳諧の生れる所以を悟ることが出来よう。」(「徒然草の鑑賞」昭和九年)と述べている。「花は盛りに、月は隈なきをのみ見る物かは・・・」。「心に移りゆくよしなし事を、そこはかとなく書きつけ」られていった『徒然草』全二四四段の宇宙と連句の宇宙はどうやらつながっているようだ。(俳句雑誌『蝶』205号(2014年1・2月)]
(追記二)「TORSO―RONDO」(大正十五年十二月「潮音」)周辺
file:///C:/Users/user/Downloads/6%20(1).pdf
[「物理学者・寺田寅彦の連句」(水橋禎子稿)
RONDO №.7
塀のうちなる芝の枯色 蓬里雨
供侍の火鉢の灰も静まりて 寅日子
さざめきめきながら皿洗ふ音 雨
すれ違ふ廊下の簡の仇心 子
夢みる様に匂ふ木犀 雨
不図さめて開けば温泉を噴く谷の音 子
しんとしたのは雪が降るのか 雨
老の限に涙の光る強意見 子
詰ったまゝで煙管ころがる 雨
掃き寄せて縁の日南の塵寒く 子
塀のうちなる・・・
興味深いのは、大正一四~一五年頃、一風変わった連句論や実作が見られることである。
寅彦(寅日子)と小宮(蓬盟雨)・東洋城との日本文学の諸断片」(大正一四年)の中で、寅彦はこのような発言をしている。(中略)
(寅日子)しかしともかくも、連句が他の詩形に比べてよほど飛び放れて変っている事はたしかである。むしろある意味で音楽と似通った点が多いように思う。(略) 音楽の旋律は順序を逆にするとまるでちがったものになってしまう。連句の順序を逆転して読んで行ったらどんなものだろうという問題が起って来る。これは六かしい問題であろうが、私のちょっと試験してみた処では逆に読んでも相当に面白い場合が少なくないようである。
(中略)
『ロンド」といふのは、発句から始めて脇・第三と十句自まで続けて行くうちに、いくらかづつ加減して、その十句自が前句に附くとともに、亦うまく第一の発句に附くやうに工夫して附ける、従って全体が環をなしてぐるぐる廻るやうにと心がけたので、『ロンド」と名づけたのである。(『寺田寅彦全集 文学篇 第七巻・岩波書店)』月報「寅彦と俳諧(小宮豊隆稿・昭和二五年一一月)」) (補記一) 「トルソー(TORSO)」と「ロンド(RONDO)」(「寅日子と蓬里雨」の「新連句」)周辺について(メモ)
東洋城が、その主宰誌「渋柿」で、「東洋城・寅日子・蓬里雨」の三吟などで試みた「新連句」(新連句の試み)は、「俳諧六つ物」(大正十五年)」、「二枚折」(大正十五年)、「二枚屏風」(大正十五年)、「二つ折」(昭和三年・昭和七年)、「TORSO」(大正十五年)、「起承転結」(大正十五年~昭和五年)、『新三つ物』(大正十四年~昭和六年)」と、謂わば、東洋城の「俳諧(連句)・俳句(発句・巻頭句)」観(「俳論」)に基づくものは、『東洋城全句集(下巻)』に、その「俳論」を含めて、その実作が収載されている。
しかし、その「トルソー(TORSO)」のうちの、「ロンド(RONDO)」という形式ものは、
東洋城の「俳諧(連句)・俳句(発句・巻頭句)」観に基づく、その「起承転結」(大正十五年~昭和五年)の「連句新形式起承転結」(「四折十二句の連句」)とは、異質の世界のもので、より多く、「ヴァイオリン奏者」でもある、「寅彦(寅日子)」の世界のものであろう。
ここで、「師(芭蕉)の曰く『たとへば歌仙は三十六歩なり。一歩も後に帰る心なし。行くにしたがひ心の改まるは、ただ先へ行く心なればなり(『三冊子』土芳著)』」の、「俳諧・連句」の「歌仙(三十六句・二花三月)」の、その「一歩も後に帰る心なし」に相反することになる。
「トルソー(TORSO)」という形式は、東洋城らの「渋柿」で実践された、「俳諧新三つ物」・「俳諧六つ物」・「俳諧起承転結(四折十二句、月花一句)」の、一形式のものとして、「一歩も戻る心なし」の、「俳諧・連句」の基本中の基本の原則を踏まえている。
その「トルソー(TORSO)」の一形式の「ロンド(RONDO)」形式というのは、「発句のことは行きて帰る心の味はひなり。例えば、”山里は漫才遅し梅の花”といふ類なり。”山里は漫才遅し”と言ひはなして、梅は咲けりといふ心のごとくに、行きて帰るの心、発句なり(三冊子)」の、「発句のことは行きて帰る心の味はひなり」の、いわゆる、「発句はとり合物也(あわせものなり)。二つとり合わせて、よくとりはやすを上手と云うなり(森川許六著「篇突」)」の、「行きて帰る心」は、「発句」論だけではなく、一巻を成した「俳諧・連句(歌仙)」の諸形式にも、それが何らかの形で関与しているという、これまた、「物理学者(理論)・ヴァイオリン奏者(音楽)・連句・俳句・随筆作家(文芸)」の、一つの警鐘として理解したい。

「トルソ/彫刻 / 金属像 / 大正 / 日本/戸張孤雁 (1882-1927)/とばりこがん/1914年(大正3)年/ブロンズ/H20.0
https://bunka.nii.ac.jp/heritages/detail/43251
[ 高さ20cmの小品であるが、腰部から腹部、腹部から胸部へと、なだらかな起伏を示す量塊と、わずかにひねられた上半身の動勢など、豊かな表現を見せる、堂々とした作品である。東京。日本橋に生まれた孤雁は、もともと画家を志して渡米する。しかし、才気あふれる彫刻家、荻原守衛を通じてロダンに傾倒し、彫刻に転向した。
この「トルソ」の根底にあるのは、人間の生命に対するロマンチックな感動であり、その作風は、デリケートな形体把握と、みずみずしい肉づけの美しさを特徴とする。孤雁はモデルを表面的に写しとる当時の文展アカデミズムに疑問を抱き、生命感にあふれる新鮮な写実主義へと向かう。その意味で彼は、写真的な真実を排し、生きた真実をめざすロダンと荻原の系譜を引き継ぐ彫刻家といってよい。荻原の臨終に際して、孤雁が「折角開かれんとした我が彫刻界が、彼の早逝によって残念にも解し得ず、旧の杢阿弥に還った」と嘆いたのも無理はない。(中谷伸生)]
(補記二)「東洋城の連句」周辺
file:///C:/Users/user/Downloads/KB21%20(2).pdf
(補記三)「漱石と東洋城との連句」周辺
[ 病院
蝙蝠の宵々梅や薄き粥 (漱石)
団扇絵飽きし名所の月 (東洋城)
註文の鮎釣る男瀬に見えて (城)
庄屋の門にゴム輪一台 (石)
相伝の金創膏も練らぬよし (石)
遊女屋続き外楼
(こんな稿片が出てきた。表六句だけであとのないのも今は淋しい。大正八年 城記 )
http://www.basho.jp/ronbun/ronbun_2013_10_01/03.html
正岡子規が「発句は文学なり、連俳は文学に非ず。」(明治二六年「芭蕉雑談」)と評価した連句を、高浜虚子は「聯句はさまざまの宇宙の現象、それは連絡のない宇宙の現象を變化の鹽梅克く横様に配列したものである。」「聯句の面白味は半分その變化の點に在るのだ。」「蓋し聯句中の或る一句の趣味は其の句のすぐ前の句、及其の句のすぐ後の句の聯想によつて助けらるゝが為め(恰も俳句が季の者によつて助けらるゝが如く)季のものゝ助けを借らずとも充分に詩趣を運ぶことが出来る。」と「ホトトギス」第八号(明治三二年五月)で擁護している。
一方、子規は「自分は連句といふ者余り好まねば、古俳書を見ても連句を読みし事無く、又自ら作りし例も甚だ稀である。然るに此等の集にある連句を読めばいたく興に入り感に堪ふるので、終には、これほど面白い者ならば自分も連句をやつて見たいといふ念が起つて来る」と言っている事実がある。(「ホトトギス」第三巻第三号(明治三二年十二月)「発句を連句一巻から切り離し、これに「俳句」という名を付けて、新しい芸術とし」(『連句辞典』)「短詩形として自覚を明確にし」(『俳諧大辞典』)「地発句(ぢほっく・連句を伴わない発句)を新生させた」(『俳文学大辞典』)正岡子規は明治三五年九月十九日に死去。
その二年後の「ホトトギス」明治三七年九月号で虚子は、「俳諧といへば俳諧連歌の事である事はいふ迄も無いが、此明治の俳運復興以来文學者仲間には俳諧連歌は殆ど棄てゝ顧みられ無いで、同時に発句が俳句と呼ばるゝやうになつて、俳諧といふ二字が殆ど俳句といふ事と紛らわしくなつた。」と冒頭で述べ「連句論」を掲載。蕉門の『猿蓑』の「市中は」歌仙を「法則」「意味」「私見」と「三條」に分けて論じ、連句の文学的価値に迫った。
同年十月、虚子は、夏目漱石、坂本四方太(ホトトギス選者)と三吟歌仙を巻いている。その平句の一節は次のように展開。人事句を楽しんでいることがよく分る。
反吐を吐きたる乗合の僧 四方太
意地惡き肥後侍の酒臭く 漱 石
切つて落せし燭臺の足 虚 子
発句にて戀する術もなかりけり 虚 子
妹の婿に家を譲りて 四方太
和歌山で敵に遭ひぬ年の暮 漱 石
なお、この歌仙が巻かれた翌年の「ホトトギス」明治三八年一月号に漱石の「吾輩は猫である」が発表された。さて、「花鳥諷詠と申しますのは花鳥風月を諷詠するといふことで、一層細密に云へば、春夏秋冬四時の移り變りに依つて起る自然界の現象、並にそれに伴ふ人事界の現象を諷詠するの謂であります。」という虚子の自序(『虚子句集』春秋社 昭和三年)対して川崎展宏は高浜虚子全集(毎日新聞社)の月報⑥(昭和四九年四月)で次のように述べている。
「このよく知られた、棒のような定義に、昭和初年代、反ホトトギスの青年たちはいらだったことだろう。いらだったのは「近代」である。俳句を一個独立の近代詩たらしめようとする者たちにとって、今更何が花鳥風月か、ということになる。新興俳句から、いわゆる前衛俳句に至る烈しい俳句近代化の、ないしは現代化の運動は、子規の俳句革新の意図を、それぞれの年代の青年たちが、彼らの生きた時代に力点を置いて推し進めた運動であって、つねに、俳句が現代詩としての問題意識を進んで担おうとした結果であった。連句の座が崩壊し、そこから発句ではなく俳句として出発した近代俳句の、一つの必然の道なのである。
虚子の「花鳥諷詠」は、いまにして思えば、連句の座を失った近代にあって、なお人々の心に残っていた花鳥風月への思ひを拠りどころに、何とかして発句性を回復しようとしたものであった。」
「連句の座」(もちろん芭蕉の座は失われている)が脈々とつながっているから、こうして拙文を書かせてもらっているわけで、私などはこの虚子の花鳥諷詠論はまさに連句のことを的確に表現していると感じる者である。「連句の座を失った近代」に「連句雑俎」(昭和六年)、「俳諧の本質的概論」(昭和七年)を著し、松根東洋城、小宮豊隆らと盛んに連句の実作も試みた寺田寅彦の熱い思いを紹介しよう。
「この芸術はまたある意味で近代の活動映画の先駆者であり、ことにいわゆるモンタージュ映画や前衛映画、そうしておそらく未来に属するいろいろの映画芸術の予想のようなものでもある。それだのに、この「俳諧」という名が多くの人には現代の日本人とは何の交渉もない過去のゆう霊の名のように響くのは何ゆえか。その少なくも一つの理由は、これが従来ただいわゆる宗匠たちのかび臭いずだ袋の奥に秘められて、生きて歩いている人々の、うかがい見るのを許しても、手に取りはだに触れることを許されなかったせいであろう。俳諧自身はかび臭いものではない。いわゆる「さび」や「しおり」は枯骨のようなものではなくて、中には生々しい肉も血もあり、近ごろのいわゆるエロもグロもすべてのものを含有している。このユニークな永久に新鮮でありうべき芸術はすべての日本人に自由に解放され享有されなければならない。そうしてすべての人は自由に各自の解釈、各自の演奏を試みてもさしつかえないものである。俳諧も音楽同様に言葉や理屈では到底説明し難いものだからである。」(昭和六年一月三十日、東京朝日新聞『芭蕉連句の根本解説』(太田水穂著)の書評より抜粋)
通されて二階眩ゆき若葉かな 寅日子
まゐらす茶にも夏空の雲 行 人
これは、行人こと詩人の尾崎喜八が、生前の寅彦の句を発句として昭和二三年に連衆二人と巻いた脇起り歌仙の付合。座の成立、それは他者と共に楽しむ所から始まるのである。
(俳句雑誌『蝶』202号掲載(2013年7・8月)) ]
「東洋城・寅彦、そして、豊隆」(漱石没後~寅彦没まで)俳句・連句管見(その五) [東洋城・寅日子(寅彦)・蓬里雨(豊隆)]
その五「大正十年(一九二一)」
[東洋城・四十四歳。寅彦、豊隆と毎月一回づつ「俳句を通しての漱石研究」の会を始めて「渋柿」に連載した。京都に遊ぶ。米良にて「俳諧草庵」。]
歳旦やわが俳諧のあら尊と(前書に「渋柿新年号扉の一句より」)
※『東洋城全句集(上巻)』所収「大正十年(四十四歳)」の冒頭の一句である。この句の上五の「歳旦や」の「歳旦」は、「① (「旦」は朝の意) 一月一日の朝。元旦。元日。年頭。《季・新年》」の、「年頭」の句ということを意味しているであろう。
これが、これに続く「わが俳諧のあら尊と」の、「わが俳諧」の「俳諧」と結びつけると、この「俳諧=連句」は、「歳旦三つ物(「歳旦開き」の「歳旦三つ物)、「歳旦開きの席で作る発句(ほっく)・脇句(わきく)・第三の、三句。→ (三句形式の連句)」と解することも出来よう。
『東洋城全句集(下巻)』の「連句篇」の冒頭の「歌仙(大正五年)」は、次のとおりの、東洋城の句を発句として、その付け句が、霽月(村上)以下五吟(五人)の「三つ物(三句提示)」と、芭蕉俳諧(連句)などでは見られないものとなっている。
(発句)何時の間に月になり居りし花野かな(東洋城)
(「脇・第三・四句目」=「三つ物」)
(脇句) 鹿かあらぬか遠山の声(霽月)
(第三)温泉冷めすと障子〆切るうそ寒み(同上)
(四) 又くりかへす旅行案内(同上)
(「五・六・七句目」=「三つ物」)
(五) 一昔あはぬ子なれば心せき(枯山楼)
(六) 此世の中は皆めくらなり(同上)
(七)ウ一 物買うて消ゆ山人山人や雪の暮(同上
(「八・九・十句目」=「三つ物」)
(八) 熊が出でしと噂ありけり(喜舟)
(九) 田の中に石油の脈を掘りあてて(同上)
(十) 襖へかかす大観を呼ぶ(同上)
(「十一・十二・十三句目」=「三つ物」)
(十一) 法会済みて猶泊り居る僧二人(坪谷)
(十二) 風呂が涌いたと鳴子曳く見ゆ(同上)
(十三) 西すれば月遠ざかる俥にて(同上)
この、『東洋城全句集(下巻)』の「連句篇」の冒頭の「歌仙(大正五年)」の、五人の連衆(東洋城・霽月・故山楼・喜舟・坪谷)の、この「霽月」は、漱石の「松山時代の愚陀佛庵」に連なる、「子規・漱石」の忘れ得ざる俳人「村上霽月」(1869(明治2)年~1946(昭和21)年)その人であろう。

「村上霽月=むらかみせいげつ」(1869(明治2)年~1946(昭和21)年)
https://tamutamu2020.web.fc2.com/murakamiseigetu.htm
https://www.murakamisangyo.co.jp/about/media.html
https://yahan.blog.ss-blog.jp/2023-08-19
https://yahan.blog.ss-blog.jp/2023-08-27
https://yahan.blog.ss-blog.jp/2023-09-02
さらに、「喜舟」とは、昭和二十七年(一九五二)に、東洋城の隠退後の後継者となる「野村喜舟」(1886(明治19)年~1983(昭和58)年)、その人ということになる。

「野村喜舟(のむらきしゅう)」(1886(明治19)年~1983(昭和58)年)
https://www.kitakyushucity-bungakukan.jp/display/169.html
https://kotobank.jp/word/%E9%87%8E%E6%9D%91%20%E5%96%9C%E8%88%9F-1652233
https://yahan.blog.ss-blog.jp/2023-09-28
https://yahan.blog.ss-blog.jp/2023-10-06
https://yahan.blog.ss-blog.jp/2023-10-16
https://yahan.blog.ss-blog.jp/2023-10-24
https://yahan.blog.ss-blog.jp/2023-10-26
[寅彦=寅日子・四十四歳。七月、航空研究員となる。九月、勲四等に叙せられる。この頃、写生のため散策に出かけるようになる。十二月、小宮豊隆、松根東洋城との三人で第一回の漱石俳句研究会を開く。その内容は翌年の一月から七月まで俳誌「渋柿」に掲載される。連句に関心を寄せ始める。]
[豊隆=蓬里雨・三十八歳。 芭蕉研究会に参加。]
https://yahan.blog.ss-blog.jp/2023-10-24
https://jyunku.hatenablog.com/entry/20100925/p1
※大正十年(1921)の「芭蕉研究会」に参加は、東洋城の「渋柿」などとの「芭蕉研究会」ではなく、下記のアドレスのものなどによると、「太田水穂(歌誌「潮音」主宰)・幸田露伴・沼波瓊音・安倍能成・阿部次郎・小宮豊隆・和辻哲郎」らによる研究会のようである。
(追記その一)「東洋城・三允・虚子」の未完「歌仙」(表六句・明治三十七年九月「鵜川・二巻四号)周辺
発句 草の露馬も夜打の支度かな (子規)
脇 秋冷かに草摺の音 東洋城
第三 長き夜の評定の席罷り出て 三允
四 月にゐねむる奴よぶなり 虚子
五 門前にはたと躓(つまづ)く竹箒 子
六 家越車の荷は山の如 城
※ 子規の発句だが、子規は、前々年(明治三十五年)に亡くなっており、その亡き子規の俳句を発句としての、「脇(わき)起(おこ)り・(脇(わき)起(おこ)し)」歌仙である。
明治三十七年(一九〇四)、東洋城、二十七歳の時で、新設の京都帝大(仏法科)に東京帝大から転校した年で、その年末に、東洋城が帰京した折の、虚子の句会(日盛会)での歌仙のように思われる。
この虚子の句会(日盛会)の連衆は、「中野三允(さんいん)・岡本癖三酔(へきさんすい)」らで、この句会は、東洋城が、その翌年(七月)に京都帝大を卒業して、明治三十九年(一九〇六)に宮内省入りした当時は、碧悟桐の「俳三昧」に対抗しての「俳諧散心」(勉強会)へと様変わりをする。
当時の東洋城は、虚子の主宰する「日盛会」・「俳諧散心」などの有力連衆の一人だったのである。そして、東洋城は、そのスタートの時点で、夏目漱石によって開眼した俳句(「松山中・一高・東大」で漱石に師事)と共に、京都の三高に在籍して京都の俳人と親交のある、子規没後の「ホトトギス」の俳句を支えている高浜虚子の「句会」・「勉強会」で、「俳諧(連句)」にも深く足を踏み入れていたのである。
そして、それは、当時の「俳諧(連句)・俳句」で兄事していた「高浜虚子」(東洋城より四歳年長)の影響などが大であることを物語っている。事実、虚子は、子規との両吟など、「俳諧(連句)」に、東洋城以上に、精通していたのである。
http://yahantei.blogspot.com/search/label/%E5%AD%90%E8%A6%8F%E3%83%BB%E6%BC%B1%E7%9F%B3%E3%83%BB%E8%99%9A%E5%AD%90%E3%81%AA%E3%81%A9%E3%81%AE%E4%B8%96%E7%95%8C
子規と虚子の両吟(明治三十一年十一月号「ほととぎす」)
オ 発句 荻吹くや崩れ初(そ)めたる雲の峰 子規
脇句 かげたる月の出づる川上 虚子
第三 うそ寒み里は鎖(とざ)さぬ家もなし 子規
四 駕舁(かごかき)二人銭かりに来る 虚子
五 洗足の湯を流したる夜の雪 子規
折端 残りすくなに風呂吹の味噌 虚子
ウ 折立 開山忌三百年を取り越して 子規
二 鐘楼に鐘を引き揚ぐる声 虚子
三 うたゝ寝の馬上に覚めて駅近き 子規
四 公事の長びく畑荒れたり 虚子
五 水と火のたゝかふといふ占ひに 子規
六 妻子ある身のうき名呼ばるゝ 虚子
七 鸚鵡鳴く西の廂の月落ちて 子規
八 石に吹き散る萩の上露 虚子
九 捨てかねて秋の扇に日記書く 子規
十 座つて見れば細長き膝 虚子
十一 六十の祝ひにあたる花盛 子規
折端 暖き日を灸据ゑに来る 虚子
ナオ 折立 まじなひに目ぼの落ちたる春の暮 虚子
二 地虫の穴へ燈心をさす 子規
三 しろがねの猫うちくれて去りにけり 虚子
四 卯木も見えず小林淋しき 子規
五 此夏は遅き富山の薬売 虚子
六 いくさ急なり予備を集むる 子規
七 足早に提灯曲る蔵の角 虚子
八 使いの男路で行き逢ふ 子規
九 亡骸は玉のごとくに美しき 虚子
十 ひつそりとして御簾の透影 子規
十一 桐壺の月梨壺の月の秋 虚子
折端 葱の宿に物語読む 子規
ナウ 折立 ひゝと啼く遠音の鹿や老ならん 虚子
二 物買ひに出る禰宜のしはぶき 子規
三 此頃の天気定まる南風 虚子
四 もみの張絹乾く陽炎 子規
五 花踏んで十歩の庭を歩行きけり 虚子
挙句 柿の古根に柿の芽をふく 子規
(参考) 「日本派」特別展4 ―虚子派と碧梧桐派の鍛錬句会稿―
http://www.kyoshi.or.jp/j-huuten/nihonha/nihonha4/03.htm
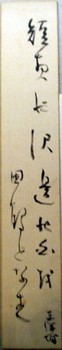
「短冊 松根東洋城(明治11~昭和39)」
「短夜や沢辺の白を田鶴となす 東洋城」
[ 東京生まれ。松山中学、一高、東大を経て京大卒。39年に宮内庁に入り、一高では漱石に師事。「俳諧散心」に参加。41年から国民俳壇を虚子から引継ぎ、この頃虚子が尤も気にとめていた門人であったが、大正期に国民新聞の俳句選者に虚子が復帰依頼を受けた問題でもめ、後「ホトトギス」を離反した。]
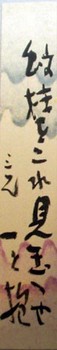
「短冊 中野三允(明治12~昭和30)」
「蚊柱をこれ見玉へや一と抱き 三允」
[ 埼玉生まれ。早稲田大学の学生であった頃子規に師事し、「早稲田俳句会」を設立。俳諧散心第一回句会には参加できず、「デンポーデ フサンヲワビル チヂツカナ」と電報で不参を詫びた。]

[短冊 高浜虚子 (明治7~昭和34)」
「黄金虫擲(なげう)つ闇の深さ哉 虚子」
[軸でも展示しているが、明治41年8月11日、鍛錬句会「日盛会」第11回の作。後に虚子自選句集『五百句』に所収された。 ]
(追記その二)「虚子の連句」(松井幸子稿)
file:///C:/Users/user/Downloads/AN101977030050010.pdf
[東洋城・四十四歳。寅彦、豊隆と毎月一回づつ「俳句を通しての漱石研究」の会を始めて「渋柿」に連載した。京都に遊ぶ。米良にて「俳諧草庵」。]
歳旦やわが俳諧のあら尊と(前書に「渋柿新年号扉の一句より」)
※『東洋城全句集(上巻)』所収「大正十年(四十四歳)」の冒頭の一句である。この句の上五の「歳旦や」の「歳旦」は、「① (「旦」は朝の意) 一月一日の朝。元旦。元日。年頭。《季・新年》」の、「年頭」の句ということを意味しているであろう。
これが、これに続く「わが俳諧のあら尊と」の、「わが俳諧」の「俳諧」と結びつけると、この「俳諧=連句」は、「歳旦三つ物(「歳旦開き」の「歳旦三つ物)、「歳旦開きの席で作る発句(ほっく)・脇句(わきく)・第三の、三句。→ (三句形式の連句)」と解することも出来よう。
『東洋城全句集(下巻)』の「連句篇」の冒頭の「歌仙(大正五年)」は、次のとおりの、東洋城の句を発句として、その付け句が、霽月(村上)以下五吟(五人)の「三つ物(三句提示)」と、芭蕉俳諧(連句)などでは見られないものとなっている。
(発句)何時の間に月になり居りし花野かな(東洋城)
(「脇・第三・四句目」=「三つ物」)
(脇句) 鹿かあらぬか遠山の声(霽月)
(第三)温泉冷めすと障子〆切るうそ寒み(同上)
(四) 又くりかへす旅行案内(同上)
(「五・六・七句目」=「三つ物」)
(五) 一昔あはぬ子なれば心せき(枯山楼)
(六) 此世の中は皆めくらなり(同上)
(七)ウ一 物買うて消ゆ山人山人や雪の暮(同上
(「八・九・十句目」=「三つ物」)
(八) 熊が出でしと噂ありけり(喜舟)
(九) 田の中に石油の脈を掘りあてて(同上)
(十) 襖へかかす大観を呼ぶ(同上)
(「十一・十二・十三句目」=「三つ物」)
(十一) 法会済みて猶泊り居る僧二人(坪谷)
(十二) 風呂が涌いたと鳴子曳く見ゆ(同上)
(十三) 西すれば月遠ざかる俥にて(同上)
この、『東洋城全句集(下巻)』の「連句篇」の冒頭の「歌仙(大正五年)」の、五人の連衆(東洋城・霽月・故山楼・喜舟・坪谷)の、この「霽月」は、漱石の「松山時代の愚陀佛庵」に連なる、「子規・漱石」の忘れ得ざる俳人「村上霽月」(1869(明治2)年~1946(昭和21)年)その人であろう。

「村上霽月=むらかみせいげつ」(1869(明治2)年~1946(昭和21)年)
https://tamutamu2020.web.fc2.com/murakamiseigetu.htm
https://www.murakamisangyo.co.jp/about/media.html
https://yahan.blog.ss-blog.jp/2023-08-19
https://yahan.blog.ss-blog.jp/2023-08-27
https://yahan.blog.ss-blog.jp/2023-09-02
さらに、「喜舟」とは、昭和二十七年(一九五二)に、東洋城の隠退後の後継者となる「野村喜舟」(1886(明治19)年~1983(昭和58)年)、その人ということになる。

「野村喜舟(のむらきしゅう)」(1886(明治19)年~1983(昭和58)年)
https://www.kitakyushucity-bungakukan.jp/display/169.html
https://kotobank.jp/word/%E9%87%8E%E6%9D%91%20%E5%96%9C%E8%88%9F-1652233
https://yahan.blog.ss-blog.jp/2023-09-28
https://yahan.blog.ss-blog.jp/2023-10-06
https://yahan.blog.ss-blog.jp/2023-10-16
https://yahan.blog.ss-blog.jp/2023-10-24
https://yahan.blog.ss-blog.jp/2023-10-26
[寅彦=寅日子・四十四歳。七月、航空研究員となる。九月、勲四等に叙せられる。この頃、写生のため散策に出かけるようになる。十二月、小宮豊隆、松根東洋城との三人で第一回の漱石俳句研究会を開く。その内容は翌年の一月から七月まで俳誌「渋柿」に掲載される。連句に関心を寄せ始める。]
[豊隆=蓬里雨・三十八歳。 芭蕉研究会に参加。]
https://yahan.blog.ss-blog.jp/2023-10-24
https://jyunku.hatenablog.com/entry/20100925/p1
※大正十年(1921)の「芭蕉研究会」に参加は、東洋城の「渋柿」などとの「芭蕉研究会」ではなく、下記のアドレスのものなどによると、「太田水穂(歌誌「潮音」主宰)・幸田露伴・沼波瓊音・安倍能成・阿部次郎・小宮豊隆・和辻哲郎」らによる研究会のようである。
(追記その一)「東洋城・三允・虚子」の未完「歌仙」(表六句・明治三十七年九月「鵜川・二巻四号)周辺
発句 草の露馬も夜打の支度かな (子規)
脇 秋冷かに草摺の音 東洋城
第三 長き夜の評定の席罷り出て 三允
四 月にゐねむる奴よぶなり 虚子
五 門前にはたと躓(つまづ)く竹箒 子
六 家越車の荷は山の如 城
※ 子規の発句だが、子規は、前々年(明治三十五年)に亡くなっており、その亡き子規の俳句を発句としての、「脇(わき)起(おこ)り・(脇(わき)起(おこ)し)」歌仙である。
明治三十七年(一九〇四)、東洋城、二十七歳の時で、新設の京都帝大(仏法科)に東京帝大から転校した年で、その年末に、東洋城が帰京した折の、虚子の句会(日盛会)での歌仙のように思われる。
この虚子の句会(日盛会)の連衆は、「中野三允(さんいん)・岡本癖三酔(へきさんすい)」らで、この句会は、東洋城が、その翌年(七月)に京都帝大を卒業して、明治三十九年(一九〇六)に宮内省入りした当時は、碧悟桐の「俳三昧」に対抗しての「俳諧散心」(勉強会)へと様変わりをする。
当時の東洋城は、虚子の主宰する「日盛会」・「俳諧散心」などの有力連衆の一人だったのである。そして、東洋城は、そのスタートの時点で、夏目漱石によって開眼した俳句(「松山中・一高・東大」で漱石に師事)と共に、京都の三高に在籍して京都の俳人と親交のある、子規没後の「ホトトギス」の俳句を支えている高浜虚子の「句会」・「勉強会」で、「俳諧(連句)」にも深く足を踏み入れていたのである。
そして、それは、当時の「俳諧(連句)・俳句」で兄事していた「高浜虚子」(東洋城より四歳年長)の影響などが大であることを物語っている。事実、虚子は、子規との両吟など、「俳諧(連句)」に、東洋城以上に、精通していたのである。
http://yahantei.blogspot.com/search/label/%E5%AD%90%E8%A6%8F%E3%83%BB%E6%BC%B1%E7%9F%B3%E3%83%BB%E8%99%9A%E5%AD%90%E3%81%AA%E3%81%A9%E3%81%AE%E4%B8%96%E7%95%8C
子規と虚子の両吟(明治三十一年十一月号「ほととぎす」)
オ 発句 荻吹くや崩れ初(そ)めたる雲の峰 子規
脇句 かげたる月の出づる川上 虚子
第三 うそ寒み里は鎖(とざ)さぬ家もなし 子規
四 駕舁(かごかき)二人銭かりに来る 虚子
五 洗足の湯を流したる夜の雪 子規
折端 残りすくなに風呂吹の味噌 虚子
ウ 折立 開山忌三百年を取り越して 子規
二 鐘楼に鐘を引き揚ぐる声 虚子
三 うたゝ寝の馬上に覚めて駅近き 子規
四 公事の長びく畑荒れたり 虚子
五 水と火のたゝかふといふ占ひに 子規
六 妻子ある身のうき名呼ばるゝ 虚子
七 鸚鵡鳴く西の廂の月落ちて 子規
八 石に吹き散る萩の上露 虚子
九 捨てかねて秋の扇に日記書く 子規
十 座つて見れば細長き膝 虚子
十一 六十の祝ひにあたる花盛 子規
折端 暖き日を灸据ゑに来る 虚子
ナオ 折立 まじなひに目ぼの落ちたる春の暮 虚子
二 地虫の穴へ燈心をさす 子規
三 しろがねの猫うちくれて去りにけり 虚子
四 卯木も見えず小林淋しき 子規
五 此夏は遅き富山の薬売 虚子
六 いくさ急なり予備を集むる 子規
七 足早に提灯曲る蔵の角 虚子
八 使いの男路で行き逢ふ 子規
九 亡骸は玉のごとくに美しき 虚子
十 ひつそりとして御簾の透影 子規
十一 桐壺の月梨壺の月の秋 虚子
折端 葱の宿に物語読む 子規
ナウ 折立 ひゝと啼く遠音の鹿や老ならん 虚子
二 物買ひに出る禰宜のしはぶき 子規
三 此頃の天気定まる南風 虚子
四 もみの張絹乾く陽炎 子規
五 花踏んで十歩の庭を歩行きけり 虚子
挙句 柿の古根に柿の芽をふく 子規
(参考) 「日本派」特別展4 ―虚子派と碧梧桐派の鍛錬句会稿―
http://www.kyoshi.or.jp/j-huuten/nihonha/nihonha4/03.htm
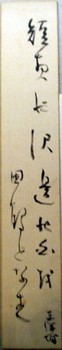
「短冊 松根東洋城(明治11~昭和39)」
「短夜や沢辺の白を田鶴となす 東洋城」
[ 東京生まれ。松山中学、一高、東大を経て京大卒。39年に宮内庁に入り、一高では漱石に師事。「俳諧散心」に参加。41年から国民俳壇を虚子から引継ぎ、この頃虚子が尤も気にとめていた門人であったが、大正期に国民新聞の俳句選者に虚子が復帰依頼を受けた問題でもめ、後「ホトトギス」を離反した。]
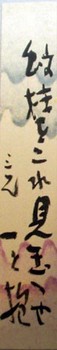
「短冊 中野三允(明治12~昭和30)」
「蚊柱をこれ見玉へや一と抱き 三允」
[ 埼玉生まれ。早稲田大学の学生であった頃子規に師事し、「早稲田俳句会」を設立。俳諧散心第一回句会には参加できず、「デンポーデ フサンヲワビル チヂツカナ」と電報で不参を詫びた。]

[短冊 高浜虚子 (明治7~昭和34)」
「黄金虫擲(なげう)つ闇の深さ哉 虚子」
[軸でも展示しているが、明治41年8月11日、鍛錬句会「日盛会」第11回の作。後に虚子自選句集『五百句』に所収された。 ]
(追記その二)「虚子の連句」(松井幸子稿)
file:///C:/Users/user/Downloads/AN101977030050010.pdf
「東洋城・寅彦、そして、豊隆」(漱石没後~寅彦没まで)俳句・連句管見(その四) [東洋城・寅日子(寅彦)・蓬里雨(豊隆)]
その四「大正九年(一九二〇)」
[東洋城・四十三歳。桐生及び岩手で俳諧道場を催す。赤城山に登る。(秋櫻子参加。)
寅彦、豊隆「渋柿」に毎号執筆するようになる。]
わが恋の久しきありぬ常陸帯(※「わが恋ひさしくありぬ」とは、「白蓮」関連の句とも。)
かくし妻清らに住みぬ福寿草(※「かくし妻」も東洋城の境涯性を感じさせられる。)
闇中に近江の湖や年惜しむ(※前書に「洛の初春 三十句」の冒頭の句。)
冬山や大河の海へ注ぐところ(※前書に「伊予長浜 二句」。)
河口に町と村ある時雨かな(※同上)
ふるさとへ入る海からや山眠る(※前書に「宇和島 二句」。)
山眠り海湛(たゝ)へけり故郷(ふるさと)は(※同上)
図書殿は寒紅梅に咲かれけり(※前書に「昨冬祖父故三楽松根図書功により正五位を贈らる。墓前報告記念」。「伊予長浜」・「宇和島」の句も、この時の句なのであろう。)
どこの田の蛙が化けし遊女かな(※前書に「三浦半島 二十八句」の冒頭の句。)
栃木野のこゝに始まる若葉かな(※「出流詣」より四十五句のうちの一句。)
障子しめて雪に籠るかと涼みけり(※「聴雪庵十景」の末尾の句。前書に「篭居」。川越の「聴雪庵」の句であろう。)
峰宿の秋の灯守(も)りや十四人(※「赤城山へ 四十二句」の一句。これは「渋柿」の「赤城山吟行」での一句であろう。この「赤城山吟行」に、「水原秋櫻子」も参加していた。)
(付記) 「秋櫻子の足あと」谷岡健彦稿(「銀漢」同人)
https://sectpoclit.com/ashiato-6/
[医学生時代の秋櫻子が、「ホトトギス」への投句を始める前に、しばらく松根東洋城が主宰する「渋柿」で俳句の手ほどきを受けていたことは、彼の句業を検討する際に留意しておいた方がよい事実だろう。虚子の目指すところとは異なる秋櫻子の詠みぶりは、すでに初学の時点で種を蒔かれていたものかもしれないのである。
1920年、秋櫻子は「渋柿」の赤城山吟行に参加している。『水原秋櫻子全集』(講談社)の作家論の巻に収められた文章によれば、秋櫻子は、このとき初めて大場白水郎という俳人の名を耳にしたそうである。ある吟行参加者が、「渋柿」の柏舟という若手と、三田俳句会出身の白水郎との比較を始めたところ、東洋城は即座に「それは白水郎の方がうまい」と断じたらしい。秋櫻子は、このように他結社の主宰からも一目置かれている白水郎に畏敬の念を覚えたという。
この吟行からほどなくして、秋櫻子は「渋柿」から「ホトトギス」に移るのだが、人の縁というものは面白い。20年ほどの歳月を経た後、秋櫻子は柏舟や白水郎と定期的に句座を囲むことになる。久保田万太郎を宗匠として渋谷のいとう旅館で開かれていた、いとう句会に3人は顔をそろえたのだった。ちなみに、柏舟とは映画監督の五所平之助が学生時代に用いていた俳号であり、秋櫻子は平之助の第一句集『五所亭句集』(1966年、牧羊社)の帯に文を寄せている。]
[寅彦=寅日子・四十三歳。大学を辞職しようとするが、理学部長の説得により保留する。三月、高等官二等に叙せられる。俳誌「渋柿」に「病院の夜明の物音」を発表し、やがて随筆を書く機会が増える。六月、正六位に叙せられる。胃痛、不眠、神経衰弱に悩まされる。十一月、随筆「小さな出来事」を吉村冬彦の筆名で「中央公論」に発表、以後、随筆にはこの筆名を使用するようになる。学術研究会議委員となる。十二月、物理学第三講座担当を免じられ、高層気象学の研究に従事するよう辞令を受ける。この年、油絵を始める。]
※寺田寅彦は、その随筆の筆名は「吉村冬彦」を用いている。この「吉村冬彦」の筆名は、「僕の家の先祖は吉村という姓だったので、それで僕が冬年生れた男だから、吉村冬彦としたわけさ。だから此の名はペンネームというより、むしろ僕は一つの本名と思っているのだ」(『寺田寅彦の追想(中谷宇吉郎稿)』)ということが、『寺田寅彦覚書(山田一郎著)』に記されているが、この「吉村」は、寅彦の高知出身の「父・利正」と深い関わりのもので、そして、この「冬彦」も、寅彦(二十歳)の時の、その高知で「父・利正」の友人の娘「夏子(十五歳)」との結婚、そして、その夏子の死(明治三十五年、寅彦=二十五歳、夏子=二十歳)と深く関わるものなのであろう。
この「吉村冬彦」という筆名は、大正九年(一九二〇)、寅彦(四十三歳)の時の、上記の「年譜」にあるとおり、「十一月、随筆「小さな出来事」を吉村冬彦の筆名で「中央公論」に発表、以後、随筆にはこの筆名を使用するようになる」の、それ以後の筆名ということになる。
その以前に、寅彦は、「藪柑子」という、筆名を用いている。これらのことに関して、『寺田寅彦覚書(山田一郎著)』では、「藪柑子の名が使われたのは、『寺田寅彦は小説を書いている』という非難が大学内部で起こったからである」と指摘している。
この「寅彦から藪柑子」への筆名の変遷は、『寺田寅彦覚書(山田一郎著)』のものに、次のアドレスのものですると、次のとおりとなる。
https://kyuurisha.com/torahiko-to-yabukohji/
[明治38年4月→「団栗」=筆名:寅彦(1月は本多光太郎博士と実験三昧)
明治38年6月→「龍舌蘭」=筆名:寅彦(8月に寛子と結婚、11月「熱海間欠泉の変動」)
明治39年10月→「嵐」=筆名:寅彦(4月「尺八に就て」)
明治40年1月→「森の絵」=筆名:寅彦(1月に長男の東一誕生)
明治40年2月→「枯菊の影」=筆名:寅彦(4月「潮汐の副振動」、7~8月に三原山調査)
明治40年10月→「やもり物語」=筆名:寅彦
明治41年1月→「障子の落書」=筆名:藪柑子
明治41年4月→「伊太利人」=筆名:藪柑子
明治41年10月→「花物語」= 筆名:藪柑子(同月に博士論文「尺八の音響学的研究」)
明治42年1月→「まじょりか皿」=筆名:藪柑子(3月から欧州留学) ]
[豊隆=蓬里雨・三十七歳。 海軍大学校嘱託教授となる。]
※『寺田寅彦覚書(山田一郎著)』では、これらの「藪柑子から冬彦へ」の筆名の変遷などに関連して、「漱石・寅彦・豊隆」の三者関係について、概略、次のとおり記述している。
[小宮豊隆は夏目漱石を敬慕することが極めて厚かったが、彼がまた寺田寅彦にも兄事して深く敬愛していた。寅彦に『藪柑子集』の佳品を書かせたのは漱石であるが、『冬彦集』には豊隆の『啓示と奨励(寅彦)があった。(中略)
小宮豊隆は「『藪柑子集』は『冬彦集』作家の昔の「顔」である」と書く。そして明治文学史における寺田寅彦の作品を次のように位置づける。すなわち「団栗」によって鈴木三重吉の「千鳥」が生まれ、「千鳥」によって夏目漱石の「草枕」が胚胎されたと見るのである。]
.jpg)
「花物語(藪柑子)」掲載「ホトトギス(明治四十一年十月号・表紙と目次)(「熊本県立大学図書館オンライン展示」)
https://soseki-kumamoto-anniversary.com/#mv
※ 上記の「ホトトギス(明治四十一年十月号・表紙と目次)の、その「目次」(下段)に、「文鳥(夏目漱石)」に続いて「花物語(藪柑子)」が掲載されている。その「目次」(上段)に、「地方俳句界(東洋城選)」・「消息(虚子記)」・「雑詠(虚子選)」・「表紙図案(中村不折)」の名が掲載されている。
この当時の「ホトトギス」は、「虚子と東洋城」とが、「ホトトギス」の「俳句の部」(「雑詠(虚子選)」と「地方俳句界(東洋城選)」など)を、そして、「漱石と藪柑子=寅彦」とが「小説の部」(「文鳥(夏目漱石)」と「花物語(藪柑子=寅彦)」など)を、タッグを組んでコンビになっていたことが覗える。
そして、この当時は、「漱石・寅彦(藪柑子)」とは、「俳句」とは疎遠になっていて「小説」の方に軸足を移していたということになる。そして、小宮豊隆は、当然のことながら、「漱石・寅彦(藪柑子)」の「小説」の『解説(評論)』に主力を投入していて、「俳句・俳諧(連句)」とは無縁であったといっても過言ではなかろう。
これが、大正九年(一九二〇)当時になると、虚子と東洋城とが、大正五年(一九一六)の漱石が亡くなった年(十二月)の四月に、「国民新聞」の「国民俳壇」の選者交替(虚子→東洋城→虚子)を契機としての「虚子と東洋城との絶縁」状態で、この年に、東洋城が全力を傾注していた「渋柿」の主要同人(水原秋櫻子など)が、カムバックした虚子の「ホトトギス」へ移行するなど、大きく様変わりをしていた。
これらのことと併せて、大正六年(一九一七)の、東洋城の「渋柿」の、「漱石先生追悼号」・「漱石忌記念号」、そして、『漱石俳句集(東洋城編・岩波刊)』の刊行などが、漱石最側近の「寅彦・東洋城・豊隆」とが、東洋城の「渋柿」上に、東洋城の年譜に、「寅彦、豊隆、『渋柿』に毎号執筆する」とあるとおり、その名を並べることになる。
この時には、寅彦は、「藪柑子」時代の「小説」の世界とは絶縁していて、「小説家・藪柑子」ではなく「随筆家・冬彦」の、その「年譜」にあるとおり、「北村冬彦」という筆名が用いられることになる。
この漱石の時代の「小説家・藪柑子」から、漱石没後の「随筆家・北村冬彦」への転換は、その寅彦の弟分にあたる「小宮豊隆」が大きく関与していたことが、次の『藪柑子集(小宮豊隆後記・岩波刊)』と『冬彦集(小宮豊隆後記・岩波刊)』との二著から覗える。
『藪柑子集(小宮豊隆後記・岩波刊)』(「国立国会図書館デジタルコレクション」)
https://dl.ndl.go.jp/pid/978015/1/1
[標題
目次
自序
團栗/1
龍舌蘭/16
嵐/31
森の繪/45
枯菊の影/52
やもり物語/73
障子の落書/88
伊太利人/99
まじよりか皿/112
花物語/126
旅日記/160
先生への通信/242
自畫挿畫二葉
『藪柑子集』の後に 小宮豐隆/281 ]
『冬彦集(小宮豊隆後記・岩波刊)』(「国立国会図書館デジタルコレクション」)
https://dl.ndl.go.jp/pid/969389/1/1
[標題
目次
自序
病院の夜明の物音/1
病室の花/7
電車と風呂/20
丸善と三越/30
自畫像/59
小さな出來事/93
鸚鵡のイズム/124
芝刈/130
球根/150
春寒/165
厄年とetc./173
淺草紙/193
春六題/201
蜂が團子を拵へる話/214
田園雜感/222
アインシュタイン/236
或日の經驗/262
鼠と猫/273
寫生紀行/305
笑/337
案内者/354
斷水の日/372
簔蟲と蜘蛛/385
夢/394
マルコポロから/400
蓄音機/407
亮の追憶/431
一つの思考實驗/453
文學中の科學的要素/479
漫畫と科學/490
『冬彦集』後話 小宮豐隆/499 ]
(補記その一) 『漱石俳句集(東洋城編・岩波刊)』周辺
.jpg)
『漱石俳句集(東洋城編・岩波刊)』(「熊本県立大学図書館オンライン展示」)
https://soseki-kumamoto-anniversary.com/#mv
(補記その二) 「俳句から小説へ ― 小説家漱石の弟子としての寅彦」周辺」(「熊本県立大学図書館オンライン展示」)
https://soseki-kumamoto-anniversary.com/#mv
[寅彦は、漱石に俳句の指導を受けていた明治31年から第五高等学校を卒業し東京帝国大学に入学することになって子規に会った明治32年までの2年間で、合計822句を作っていたが、留学のために7月に漱石が熊本を離れて9月に横浜からプロイセン号で出発した明治33年(1900年)になると、俳句の数は159句に減った。また妻夏子が病気療養のために高知に帰り、自分も肺尖カタル療養のために1年間休学した明治34年にはさらに減って、110句になり、子規が亡くなり、夏子も亡くなった明治35年(1902年)には、7句に激減している。また漱石が留学から帰って東京に住むようになった明治36年の作句も11句でしかなかった。
漱石から直接指導を受けていた熊本時代が、寅彦がもっとも俳句に打ち込んでいた時期だった。その後、留学中に子規が亡くなったこともあってか、帰朝後漱石は以前ほど熱心に俳句を作らなくなり、明治37年には、新体詩や俳体詩、連句を作るようになっていた。寅彦もまた師の漱石と歩調を合わせるかのように俳句から遠ざかって行った。
寅彦は、明治38年頃から『ホトヽギス』に小説を載せるようになった。きっかけは、寅彦が『藪柑子集』(大正12年2月/岩波書店)の自序で次のように書いているように、師の漱石が小説を発表しはじめたことであった。
明治三十八年の正月に、先生の「我輩は猫である」が現はれて、「ホトヽギス」が新しい活気を帯びて来ると同時に、先生の周囲も急に賑やかになつた。時々先生の家で写生文や短篇小説の持寄り会が催されたりした。さういふ空気に刺戟されて、自分も何かしら書いて見たくなつたのであつた。「団栗」の出たのは、先生の「猫」の第三回と、「幻影の盾」の現はれた、第百号の増刊であつた。「花物語」の出たのも、矢張何時かの増大号で、先生の「文鳥」を始めとして、碧梧桐、鼠骨、彌生子、左千夫の創作が並んで居た。
寅彦は、目次に「(小説)」とある「団栗」を明治38年4月号に「寺田寅彦」の本名で載せたのを初めとして、「竜舌蘭(小説)」(明治38年6月号)、「森の絵(小説)」(明治40年1月号/漱石「野分」掲載)、「枯菊の影(小説)」(明治40年2月号)や、「藪柑子」の筆名で載せた「伊太利人(小説)」(明治41年4月号巻頭/漱石「創作家の態度」(論文)掲載)などの小説を『ホトヽギス』に発表して行った。なお、明治41年10月号に「藪柑子」の筆名で漱石の「文鳥」の次に載った「花物語」は、「(小説)」という注記はないが、その少し前、同年7月~8月『東京朝日新聞』『大阪朝日新聞』に連載された漱石の「夢十夜」の影響を考える説もあるように幻想的な世界を持つ作品である。寅彦は小説でも漱石の弟子であった。
ただ、寅彦は一方的に漱石の影響を受けていただけではない。小宮豊隆が「『藪柑子集』の後に」(『藪柑子集』)で「『春秋』の筆法を用ふれば、集中に収められた『団栗』や『竜舌蘭』は、三重吉の『千鳥』の父であり、漱石先生の『草枕』の祖父である。」と書いているように、『ホトヽギス』掲載の寅彦の小説が『新小説』明治39年9月号掲載の漱石の『草枕』などにも影響をあたえた可能性が考えられないわけではない。小説の創作では寅彦と漱石は互いに影響をあたえあっていたのかもしれない。]
(補記その三) 「夏目漱石『吾輩は猫である』挿絵(中村不折画)」(「台東区ヴァーチャル美術館」)周辺

「吾輩ハ猫デアル」挿絵(中村不折(1866~1943)画/明治38年(1905))
https://archive.is/20151003155928/https://www.city.taito.lg.jp/bunkasinko/virtualmuseum/shodo_03/003/index.html#selection-111.0-111.28
[「吾輩ハ猫デアル」は、明治を代表する文豪の一人・夏目漱石(なつめそうせき)(1867~1916)の代表作。雑誌「ホトトギス」紙上に明治38年1月号から翌39年8月号まで、合計10回にわたって連載された。
これは、明治38年10月に出版された同作の単行本上巻冒頭の挿絵であり、中村不折の画である。著者の漱石からは、「発売の日からわずか20日で初版が売り切れ、それは不折の軽妙な挿絵のおかげであり、大いに売り上げの景気を助けてくれたことを感謝する」という内容の手紙が不折あてに送られている。 ]
[東洋城・四十三歳。桐生及び岩手で俳諧道場を催す。赤城山に登る。(秋櫻子参加。)
寅彦、豊隆「渋柿」に毎号執筆するようになる。]
わが恋の久しきありぬ常陸帯(※「わが恋ひさしくありぬ」とは、「白蓮」関連の句とも。)
かくし妻清らに住みぬ福寿草(※「かくし妻」も東洋城の境涯性を感じさせられる。)
闇中に近江の湖や年惜しむ(※前書に「洛の初春 三十句」の冒頭の句。)
冬山や大河の海へ注ぐところ(※前書に「伊予長浜 二句」。)
河口に町と村ある時雨かな(※同上)
ふるさとへ入る海からや山眠る(※前書に「宇和島 二句」。)
山眠り海湛(たゝ)へけり故郷(ふるさと)は(※同上)
図書殿は寒紅梅に咲かれけり(※前書に「昨冬祖父故三楽松根図書功により正五位を贈らる。墓前報告記念」。「伊予長浜」・「宇和島」の句も、この時の句なのであろう。)
どこの田の蛙が化けし遊女かな(※前書に「三浦半島 二十八句」の冒頭の句。)
栃木野のこゝに始まる若葉かな(※「出流詣」より四十五句のうちの一句。)
障子しめて雪に籠るかと涼みけり(※「聴雪庵十景」の末尾の句。前書に「篭居」。川越の「聴雪庵」の句であろう。)
峰宿の秋の灯守(も)りや十四人(※「赤城山へ 四十二句」の一句。これは「渋柿」の「赤城山吟行」での一句であろう。この「赤城山吟行」に、「水原秋櫻子」も参加していた。)
(付記) 「秋櫻子の足あと」谷岡健彦稿(「銀漢」同人)
https://sectpoclit.com/ashiato-6/
[医学生時代の秋櫻子が、「ホトトギス」への投句を始める前に、しばらく松根東洋城が主宰する「渋柿」で俳句の手ほどきを受けていたことは、彼の句業を検討する際に留意しておいた方がよい事実だろう。虚子の目指すところとは異なる秋櫻子の詠みぶりは、すでに初学の時点で種を蒔かれていたものかもしれないのである。
1920年、秋櫻子は「渋柿」の赤城山吟行に参加している。『水原秋櫻子全集』(講談社)の作家論の巻に収められた文章によれば、秋櫻子は、このとき初めて大場白水郎という俳人の名を耳にしたそうである。ある吟行参加者が、「渋柿」の柏舟という若手と、三田俳句会出身の白水郎との比較を始めたところ、東洋城は即座に「それは白水郎の方がうまい」と断じたらしい。秋櫻子は、このように他結社の主宰からも一目置かれている白水郎に畏敬の念を覚えたという。
この吟行からほどなくして、秋櫻子は「渋柿」から「ホトトギス」に移るのだが、人の縁というものは面白い。20年ほどの歳月を経た後、秋櫻子は柏舟や白水郎と定期的に句座を囲むことになる。久保田万太郎を宗匠として渋谷のいとう旅館で開かれていた、いとう句会に3人は顔をそろえたのだった。ちなみに、柏舟とは映画監督の五所平之助が学生時代に用いていた俳号であり、秋櫻子は平之助の第一句集『五所亭句集』(1966年、牧羊社)の帯に文を寄せている。]
[寅彦=寅日子・四十三歳。大学を辞職しようとするが、理学部長の説得により保留する。三月、高等官二等に叙せられる。俳誌「渋柿」に「病院の夜明の物音」を発表し、やがて随筆を書く機会が増える。六月、正六位に叙せられる。胃痛、不眠、神経衰弱に悩まされる。十一月、随筆「小さな出来事」を吉村冬彦の筆名で「中央公論」に発表、以後、随筆にはこの筆名を使用するようになる。学術研究会議委員となる。十二月、物理学第三講座担当を免じられ、高層気象学の研究に従事するよう辞令を受ける。この年、油絵を始める。]
※寺田寅彦は、その随筆の筆名は「吉村冬彦」を用いている。この「吉村冬彦」の筆名は、「僕の家の先祖は吉村という姓だったので、それで僕が冬年生れた男だから、吉村冬彦としたわけさ。だから此の名はペンネームというより、むしろ僕は一つの本名と思っているのだ」(『寺田寅彦の追想(中谷宇吉郎稿)』)ということが、『寺田寅彦覚書(山田一郎著)』に記されているが、この「吉村」は、寅彦の高知出身の「父・利正」と深い関わりのもので、そして、この「冬彦」も、寅彦(二十歳)の時の、その高知で「父・利正」の友人の娘「夏子(十五歳)」との結婚、そして、その夏子の死(明治三十五年、寅彦=二十五歳、夏子=二十歳)と深く関わるものなのであろう。
この「吉村冬彦」という筆名は、大正九年(一九二〇)、寅彦(四十三歳)の時の、上記の「年譜」にあるとおり、「十一月、随筆「小さな出来事」を吉村冬彦の筆名で「中央公論」に発表、以後、随筆にはこの筆名を使用するようになる」の、それ以後の筆名ということになる。
その以前に、寅彦は、「藪柑子」という、筆名を用いている。これらのことに関して、『寺田寅彦覚書(山田一郎著)』では、「藪柑子の名が使われたのは、『寺田寅彦は小説を書いている』という非難が大学内部で起こったからである」と指摘している。
この「寅彦から藪柑子」への筆名の変遷は、『寺田寅彦覚書(山田一郎著)』のものに、次のアドレスのものですると、次のとおりとなる。
https://kyuurisha.com/torahiko-to-yabukohji/
[明治38年4月→「団栗」=筆名:寅彦(1月は本多光太郎博士と実験三昧)
明治38年6月→「龍舌蘭」=筆名:寅彦(8月に寛子と結婚、11月「熱海間欠泉の変動」)
明治39年10月→「嵐」=筆名:寅彦(4月「尺八に就て」)
明治40年1月→「森の絵」=筆名:寅彦(1月に長男の東一誕生)
明治40年2月→「枯菊の影」=筆名:寅彦(4月「潮汐の副振動」、7~8月に三原山調査)
明治40年10月→「やもり物語」=筆名:寅彦
明治41年1月→「障子の落書」=筆名:藪柑子
明治41年4月→「伊太利人」=筆名:藪柑子
明治41年10月→「花物語」= 筆名:藪柑子(同月に博士論文「尺八の音響学的研究」)
明治42年1月→「まじょりか皿」=筆名:藪柑子(3月から欧州留学) ]
[豊隆=蓬里雨・三十七歳。 海軍大学校嘱託教授となる。]
※『寺田寅彦覚書(山田一郎著)』では、これらの「藪柑子から冬彦へ」の筆名の変遷などに関連して、「漱石・寅彦・豊隆」の三者関係について、概略、次のとおり記述している。
[小宮豊隆は夏目漱石を敬慕することが極めて厚かったが、彼がまた寺田寅彦にも兄事して深く敬愛していた。寅彦に『藪柑子集』の佳品を書かせたのは漱石であるが、『冬彦集』には豊隆の『啓示と奨励(寅彦)があった。(中略)
小宮豊隆は「『藪柑子集』は『冬彦集』作家の昔の「顔」である」と書く。そして明治文学史における寺田寅彦の作品を次のように位置づける。すなわち「団栗」によって鈴木三重吉の「千鳥」が生まれ、「千鳥」によって夏目漱石の「草枕」が胚胎されたと見るのである。]
.jpg)
「花物語(藪柑子)」掲載「ホトトギス(明治四十一年十月号・表紙と目次)(「熊本県立大学図書館オンライン展示」)
https://soseki-kumamoto-anniversary.com/#mv
※ 上記の「ホトトギス(明治四十一年十月号・表紙と目次)の、その「目次」(下段)に、「文鳥(夏目漱石)」に続いて「花物語(藪柑子)」が掲載されている。その「目次」(上段)に、「地方俳句界(東洋城選)」・「消息(虚子記)」・「雑詠(虚子選)」・「表紙図案(中村不折)」の名が掲載されている。
この当時の「ホトトギス」は、「虚子と東洋城」とが、「ホトトギス」の「俳句の部」(「雑詠(虚子選)」と「地方俳句界(東洋城選)」など)を、そして、「漱石と藪柑子=寅彦」とが「小説の部」(「文鳥(夏目漱石)」と「花物語(藪柑子=寅彦)」など)を、タッグを組んでコンビになっていたことが覗える。
そして、この当時は、「漱石・寅彦(藪柑子)」とは、「俳句」とは疎遠になっていて「小説」の方に軸足を移していたということになる。そして、小宮豊隆は、当然のことながら、「漱石・寅彦(藪柑子)」の「小説」の『解説(評論)』に主力を投入していて、「俳句・俳諧(連句)」とは無縁であったといっても過言ではなかろう。
これが、大正九年(一九二〇)当時になると、虚子と東洋城とが、大正五年(一九一六)の漱石が亡くなった年(十二月)の四月に、「国民新聞」の「国民俳壇」の選者交替(虚子→東洋城→虚子)を契機としての「虚子と東洋城との絶縁」状態で、この年に、東洋城が全力を傾注していた「渋柿」の主要同人(水原秋櫻子など)が、カムバックした虚子の「ホトトギス」へ移行するなど、大きく様変わりをしていた。
これらのことと併せて、大正六年(一九一七)の、東洋城の「渋柿」の、「漱石先生追悼号」・「漱石忌記念号」、そして、『漱石俳句集(東洋城編・岩波刊)』の刊行などが、漱石最側近の「寅彦・東洋城・豊隆」とが、東洋城の「渋柿」上に、東洋城の年譜に、「寅彦、豊隆、『渋柿』に毎号執筆する」とあるとおり、その名を並べることになる。
この時には、寅彦は、「藪柑子」時代の「小説」の世界とは絶縁していて、「小説家・藪柑子」ではなく「随筆家・冬彦」の、その「年譜」にあるとおり、「北村冬彦」という筆名が用いられることになる。
この漱石の時代の「小説家・藪柑子」から、漱石没後の「随筆家・北村冬彦」への転換は、その寅彦の弟分にあたる「小宮豊隆」が大きく関与していたことが、次の『藪柑子集(小宮豊隆後記・岩波刊)』と『冬彦集(小宮豊隆後記・岩波刊)』との二著から覗える。
『藪柑子集(小宮豊隆後記・岩波刊)』(「国立国会図書館デジタルコレクション」)
https://dl.ndl.go.jp/pid/978015/1/1
[標題
目次
自序
團栗/1
龍舌蘭/16
嵐/31
森の繪/45
枯菊の影/52
やもり物語/73
障子の落書/88
伊太利人/99
まじよりか皿/112
花物語/126
旅日記/160
先生への通信/242
自畫挿畫二葉
『藪柑子集』の後に 小宮豐隆/281 ]
『冬彦集(小宮豊隆後記・岩波刊)』(「国立国会図書館デジタルコレクション」)
https://dl.ndl.go.jp/pid/969389/1/1
[標題
目次
自序
病院の夜明の物音/1
病室の花/7
電車と風呂/20
丸善と三越/30
自畫像/59
小さな出來事/93
鸚鵡のイズム/124
芝刈/130
球根/150
春寒/165
厄年とetc./173
淺草紙/193
春六題/201
蜂が團子を拵へる話/214
田園雜感/222
アインシュタイン/236
或日の經驗/262
鼠と猫/273
寫生紀行/305
笑/337
案内者/354
斷水の日/372
簔蟲と蜘蛛/385
夢/394
マルコポロから/400
蓄音機/407
亮の追憶/431
一つの思考實驗/453
文學中の科學的要素/479
漫畫と科學/490
『冬彦集』後話 小宮豐隆/499 ]
(補記その一) 『漱石俳句集(東洋城編・岩波刊)』周辺
.jpg)
『漱石俳句集(東洋城編・岩波刊)』(「熊本県立大学図書館オンライン展示」)
https://soseki-kumamoto-anniversary.com/#mv
(補記その二) 「俳句から小説へ ― 小説家漱石の弟子としての寅彦」周辺」(「熊本県立大学図書館オンライン展示」)
https://soseki-kumamoto-anniversary.com/#mv
[寅彦は、漱石に俳句の指導を受けていた明治31年から第五高等学校を卒業し東京帝国大学に入学することになって子規に会った明治32年までの2年間で、合計822句を作っていたが、留学のために7月に漱石が熊本を離れて9月に横浜からプロイセン号で出発した明治33年(1900年)になると、俳句の数は159句に減った。また妻夏子が病気療養のために高知に帰り、自分も肺尖カタル療養のために1年間休学した明治34年にはさらに減って、110句になり、子規が亡くなり、夏子も亡くなった明治35年(1902年)には、7句に激減している。また漱石が留学から帰って東京に住むようになった明治36年の作句も11句でしかなかった。
漱石から直接指導を受けていた熊本時代が、寅彦がもっとも俳句に打ち込んでいた時期だった。その後、留学中に子規が亡くなったこともあってか、帰朝後漱石は以前ほど熱心に俳句を作らなくなり、明治37年には、新体詩や俳体詩、連句を作るようになっていた。寅彦もまた師の漱石と歩調を合わせるかのように俳句から遠ざかって行った。
寅彦は、明治38年頃から『ホトヽギス』に小説を載せるようになった。きっかけは、寅彦が『藪柑子集』(大正12年2月/岩波書店)の自序で次のように書いているように、師の漱石が小説を発表しはじめたことであった。
明治三十八年の正月に、先生の「我輩は猫である」が現はれて、「ホトヽギス」が新しい活気を帯びて来ると同時に、先生の周囲も急に賑やかになつた。時々先生の家で写生文や短篇小説の持寄り会が催されたりした。さういふ空気に刺戟されて、自分も何かしら書いて見たくなつたのであつた。「団栗」の出たのは、先生の「猫」の第三回と、「幻影の盾」の現はれた、第百号の増刊であつた。「花物語」の出たのも、矢張何時かの増大号で、先生の「文鳥」を始めとして、碧梧桐、鼠骨、彌生子、左千夫の創作が並んで居た。
寅彦は、目次に「(小説)」とある「団栗」を明治38年4月号に「寺田寅彦」の本名で載せたのを初めとして、「竜舌蘭(小説)」(明治38年6月号)、「森の絵(小説)」(明治40年1月号/漱石「野分」掲載)、「枯菊の影(小説)」(明治40年2月号)や、「藪柑子」の筆名で載せた「伊太利人(小説)」(明治41年4月号巻頭/漱石「創作家の態度」(論文)掲載)などの小説を『ホトヽギス』に発表して行った。なお、明治41年10月号に「藪柑子」の筆名で漱石の「文鳥」の次に載った「花物語」は、「(小説)」という注記はないが、その少し前、同年7月~8月『東京朝日新聞』『大阪朝日新聞』に連載された漱石の「夢十夜」の影響を考える説もあるように幻想的な世界を持つ作品である。寅彦は小説でも漱石の弟子であった。
ただ、寅彦は一方的に漱石の影響を受けていただけではない。小宮豊隆が「『藪柑子集』の後に」(『藪柑子集』)で「『春秋』の筆法を用ふれば、集中に収められた『団栗』や『竜舌蘭』は、三重吉の『千鳥』の父であり、漱石先生の『草枕』の祖父である。」と書いているように、『ホトヽギス』掲載の寅彦の小説が『新小説』明治39年9月号掲載の漱石の『草枕』などにも影響をあたえた可能性が考えられないわけではない。小説の創作では寅彦と漱石は互いに影響をあたえあっていたのかもしれない。]
(補記その三) 「夏目漱石『吾輩は猫である』挿絵(中村不折画)」(「台東区ヴァーチャル美術館」)周辺

「吾輩ハ猫デアル」挿絵(中村不折(1866~1943)画/明治38年(1905))
https://archive.is/20151003155928/https://www.city.taito.lg.jp/bunkasinko/virtualmuseum/shodo_03/003/index.html#selection-111.0-111.28
[「吾輩ハ猫デアル」は、明治を代表する文豪の一人・夏目漱石(なつめそうせき)(1867~1916)の代表作。雑誌「ホトトギス」紙上に明治38年1月号から翌39年8月号まで、合計10回にわたって連載された。
これは、明治38年10月に出版された同作の単行本上巻冒頭の挿絵であり、中村不折の画である。著者の漱石からは、「発売の日からわずか20日で初版が売り切れ、それは不折の軽妙な挿絵のおかげであり、大いに売り上げの景気を助けてくれたことを感謝する」という内容の手紙が不折あてに送られている。 ]
「東洋城・寅彦、そして、豊隆」(漱石没後~寅彦没まで)俳句・連句管見(その三) [東洋城・寅日子(寅彦)・蓬里雨(豊隆)]
その三「大正八年(一九一九)」
[東洋城・四十二歳。木曽、吉野及び伊予に遊ぶ。宇和島で俳諧道場を催す。十二月宮内省退官。野人となる。東京朝日新聞の「朝日俳壇」の選を担当す。]
弾初や絃の外なる恋の事
しぐるゝや艶書(ふみ)の中なる仮名遣ひ
化粧して来て侍す人の蒲団かな
つと遠く千鳥飛びけり戻りけり
落葉せよ我も隠れん隠れ里
逢はずなりし女と語る火桶かな
遠火事を芝居の中の噂かな
※ 東洋城は、こま年の暮れに、明治三十九年(一九〇六)から十三年間務めた宮内省を、四十二歳の若さで退官する。東洋城としては、明治四十五年(一九一二)の、明治天皇の「大喪の儀」、そして、大正四年(一九一五)の、京都御所で挙行された正天皇の「即位の大礼」を式部官として成し遂げたという、そういう感慨もあったことであろう。
それに加えて、この大正天皇の「即位の大礼」が挙行された年の二月に、東洋城は、主宰誌「渋柿」を刊行し、さらに、虚子より引き継いだ「国民俳壇」を軌道に乗せることなど多忙を極めていた。そして、その翌年の大正五年四月十五日に、「国民俳壇」の「国民新聞」(徳富蘇峰創刊・社長)に、突如として次のとおりの「社告」が掲載されたのである。
「本紙俳句欄は従来松根東洋城氏担当せられしが、今回都合に依り高浜虚子氏を担当する事と相成。来る十七日紙上より同氏の選句を掲載し、猶ほ同氏の文章をも時々掲載すべく、此段投句並に愛読各位に謹告す。」(『俳句講座八 現代作家論』所収「松根東洋城(野村喜舟)」)
この時の、東洋城の「大正五年・年譜」(『東洋城全句集(中巻))は、次のとおりのものであった。
[東洋城・三十九歳。虚子は大正二年、俳句に復活したが、四月、東洋城に無断で「国民俳壇」を手に入れた。爾後、虚子及び「ホトトギス」と絶縁し、「渋柿」によつて芭蕉を宗とし俳諧を道として立った。]
(再掲)
https://yahan.blog.ss-blog.jp/2023-10-18
※怒る事知つてあれども水温む(前書「有感(大正五年四月十七日国民俳壇選者更迭発表の日)」)
[※「大正五年、虚子が俳句に復活し、四月十七日、東洋城はついに国民俳壇の選者を下りた。それというのも、国民新聞の社長・徳富蘇峰が、選者を下りてほしい旨、手紙を送ってきたためであった。東洋城はかねてより、社長からなにか言ってくるまで辞めないつもりだったが、読むと、かなり困って書いてきたものだとわかった。「仕方がない、社長は大将だ。ここまで書いてくるのは、よほどのことなのであろう」と、ついに下りることを承諾した。そして、
有感(感有リ)
いかること知つてあれども水温(ぬる)む
という句をつくり、以後虚子とは義絶した。九月には母の上京を促すため、帰郷した。末弟の宗一(そういち)が東京高商に入学するため上京し、以後、宇和島で独り住まいになっていた母の面倒を見るのは長男(※嫡男)の務めだと思い、同居の説得に行ったのだった。この年、東洋城にとって肉親の死にも等しい哀しいできごとがあった。十二月九日、漱石が死亡したのである。」(『渋柿の木の下で(中村英利子著)』) ]
※ 東洋城の、大正八年(一九一九)の、宮内省退官には、この、それまで、「子規」門の俳人の中で、最も信頼を置いて、そして、相互に切磋琢磨し、年長者の俳人として兄事していた虚子の「国民俳壇」選者再帰ということと大きく関わっているように思われる。
これらのことは、この東洋城の退官時の、その年譜の「十二月宮内省退官。野人となる。東京朝日新聞の「朝日俳壇」の選を担当す」の、この「野人」と「『朝日俳壇』」の選を担当す」に、端的に表れているように思われる。
即ち、「虚子の『ホトトギス』対する東洋城の『渋柿』」・「虚子の『国民俳壇』対する東洋城の『朝日俳壇』」と、虚子へのライバル化しての挑戦が見え隠れしているように解したい。
上記の年譜の「野人となる」ことに関連しての句が、『東洋城全句集(上巻)・大正八年』に掲載されているが、これらの句は、退官の少し前の、「会計審査官として木曽の御料林
深くわけ入った時の紀行文『木曽』」での作のようであ(『俳句講座八 現代作家論』所収「松根東洋城(野村喜舟)」)る
野人となる
木の実落ちてしかと打ちたる大地かな(紀行文「木曽」)
有感
きのふとも昔とも思ふ夜長かな(同上)
※ しかし、この東洋城の退官は、「東洋城が、『妻持たぬ』の句を詠んだ五年後の明治四十四年(一九一一)、福岡の炭鉱王だった伊藤伝右衛門と結婚させられた、柳原燁子(白蓮)の、大正六年(一九一七)の歌集『几帳の陰』、同八年の『幻の花』に所収されている、『激しい恋の歌』」の、その相手方は、「東洋城」その人という流聞など(それに関連しての、同じ式部官の某男爵夫人とのスキャンダル=『俳人風狂列伝』)による、当時の東洋城の上司の勧告に由る」ものとされている(『渋柿の木の下で(中村英利子著)』)。
これらの、東洋城の「女性スキャンダル」を背景にしている思われる句などを、『東洋城全句集(上巻)・大正八年』の句から抜粋すると、冒頭に掲出した、俳諧(連句)上の「恋の座(恋の句)」ということになる。
因みに、『東洋城全句集(上巻)・大正八年』の末尾の三句は、次のものである。
木枯や巷の群に白昼鬼(※「巷の群に白昼鬼」が意味深長である。)
逢はずなりし女と語る火桶かな(※「逢はずなりし」の「し」は過去形の措辞である。)
遠火事を芝居の中の噂かな(※「遠火事」「芝居」「噂」も「境涯」性を感じさせる。)
[寅彦=寅日子・四十二歳。発熱、発疹および胃痛に悩まされる。四月、大学内で倒れ、診察を受ける。十二月、胃潰瘍のため大学研究室で吐血、帝大付属病院に入学する。]
※ 『寺田寅彦 文学篇 第七巻(岩波書店)』には「大正八年」(一九一九)の収載句は無い。
[豊隆=蓬里雨の「小宮豊隆氏(年譜)」(「みやこ町歴史民俗博物館/小宮豊隆資料」)には、「大正八年」(一九一九)の記載は無い。]
https://adeac.jp/miyako-hf-mus/top/
(再掲) 「東洋城と白蓮」
https://yahan.blog.ss-blog.jp/2023-10-04
https://yahan.blog.ss-blog.jp/2023-10-03


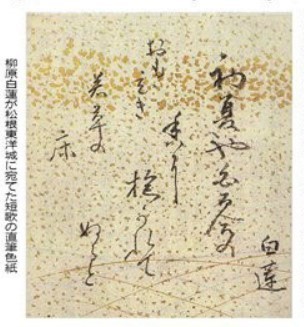
2014.9.24愛媛H新聞より
https://toonbusclub.jimdofree.com/%E6%83%A3%E6%B2%B3%E5%86%85%E7%A5%9E%E7%A4%BE-%E4%B8%80%E7%95%B3%E5%BA%B5/
※ 「初夏や白百合の/香に/抱かれて/ぬると/思ひき/若草の床」(柳原白蓮が松根東洋城に宛てた短歌の直筆色紙)
この「直筆色紙」を保管していた「川崎在住親族・松根敦子」さんは、「東洋城妹弟(妹・房子、弟・新八郎、弟・卓四郎、弟・宗一)」の、「三弟・卓四郎」家に嫁いだ方で、この「三弟・卓四郎」が、東洋城が「渋柿」を創刊したときの、名目上の「社主」のような、その事務所(「三畳庵」など)を提供していた方で、東洋城の遺品というのは、この「直筆色紙」の保管などからすると、「三弟・卓四郎」家が引き継いでいるように思われる。
(再掲) 「「東洋城兄弟(四人の男兄弟)」
https://yahan.blog.ss-blog.jp/2023-10-06
.jpg)
「兄東洋城と私(松根新八郎稿)」所収の「「東洋城兄弟(四人の男兄弟)」(「国立国会図書館デジタルコレクション」所収)
https://dl.ndl.go.jp/pid/6071686/1/50
[前列左から「宗一(六十四歳)・卓四郎(七十三歳)・東洋城(豊次郎)(八十六歳)・新八郎(八十一歳)」と思われる。後列の二人は東洋城の甥。中央に「松根家家宝の旗印(三畳敷の麻に朱墨の生首図=「「伊達の生首」)」が掲げられている。「伊達の生首」については、次のアドレスで紹介している。
https://yahan.blog.ss-blog.jp/2023-10-02 ]
[東洋城・四十二歳。木曽、吉野及び伊予に遊ぶ。宇和島で俳諧道場を催す。十二月宮内省退官。野人となる。東京朝日新聞の「朝日俳壇」の選を担当す。]
弾初や絃の外なる恋の事
しぐるゝや艶書(ふみ)の中なる仮名遣ひ
化粧して来て侍す人の蒲団かな
つと遠く千鳥飛びけり戻りけり
落葉せよ我も隠れん隠れ里
逢はずなりし女と語る火桶かな
遠火事を芝居の中の噂かな
※ 東洋城は、こま年の暮れに、明治三十九年(一九〇六)から十三年間務めた宮内省を、四十二歳の若さで退官する。東洋城としては、明治四十五年(一九一二)の、明治天皇の「大喪の儀」、そして、大正四年(一九一五)の、京都御所で挙行された正天皇の「即位の大礼」を式部官として成し遂げたという、そういう感慨もあったことであろう。
それに加えて、この大正天皇の「即位の大礼」が挙行された年の二月に、東洋城は、主宰誌「渋柿」を刊行し、さらに、虚子より引き継いだ「国民俳壇」を軌道に乗せることなど多忙を極めていた。そして、その翌年の大正五年四月十五日に、「国民俳壇」の「国民新聞」(徳富蘇峰創刊・社長)に、突如として次のとおりの「社告」が掲載されたのである。
「本紙俳句欄は従来松根東洋城氏担当せられしが、今回都合に依り高浜虚子氏を担当する事と相成。来る十七日紙上より同氏の選句を掲載し、猶ほ同氏の文章をも時々掲載すべく、此段投句並に愛読各位に謹告す。」(『俳句講座八 現代作家論』所収「松根東洋城(野村喜舟)」)
この時の、東洋城の「大正五年・年譜」(『東洋城全句集(中巻))は、次のとおりのものであった。
[東洋城・三十九歳。虚子は大正二年、俳句に復活したが、四月、東洋城に無断で「国民俳壇」を手に入れた。爾後、虚子及び「ホトトギス」と絶縁し、「渋柿」によつて芭蕉を宗とし俳諧を道として立った。]
(再掲)
https://yahan.blog.ss-blog.jp/2023-10-18
※怒る事知つてあれども水温む(前書「有感(大正五年四月十七日国民俳壇選者更迭発表の日)」)
[※「大正五年、虚子が俳句に復活し、四月十七日、東洋城はついに国民俳壇の選者を下りた。それというのも、国民新聞の社長・徳富蘇峰が、選者を下りてほしい旨、手紙を送ってきたためであった。東洋城はかねてより、社長からなにか言ってくるまで辞めないつもりだったが、読むと、かなり困って書いてきたものだとわかった。「仕方がない、社長は大将だ。ここまで書いてくるのは、よほどのことなのであろう」と、ついに下りることを承諾した。そして、
有感(感有リ)
いかること知つてあれども水温(ぬる)む
という句をつくり、以後虚子とは義絶した。九月には母の上京を促すため、帰郷した。末弟の宗一(そういち)が東京高商に入学するため上京し、以後、宇和島で独り住まいになっていた母の面倒を見るのは長男(※嫡男)の務めだと思い、同居の説得に行ったのだった。この年、東洋城にとって肉親の死にも等しい哀しいできごとがあった。十二月九日、漱石が死亡したのである。」(『渋柿の木の下で(中村英利子著)』) ]
※ 東洋城の、大正八年(一九一九)の、宮内省退官には、この、それまで、「子規」門の俳人の中で、最も信頼を置いて、そして、相互に切磋琢磨し、年長者の俳人として兄事していた虚子の「国民俳壇」選者再帰ということと大きく関わっているように思われる。
これらのことは、この東洋城の退官時の、その年譜の「十二月宮内省退官。野人となる。東京朝日新聞の「朝日俳壇」の選を担当す」の、この「野人」と「『朝日俳壇』」の選を担当す」に、端的に表れているように思われる。
即ち、「虚子の『ホトトギス』対する東洋城の『渋柿』」・「虚子の『国民俳壇』対する東洋城の『朝日俳壇』」と、虚子へのライバル化しての挑戦が見え隠れしているように解したい。
上記の年譜の「野人となる」ことに関連しての句が、『東洋城全句集(上巻)・大正八年』に掲載されているが、これらの句は、退官の少し前の、「会計審査官として木曽の御料林
深くわけ入った時の紀行文『木曽』」での作のようであ(『俳句講座八 現代作家論』所収「松根東洋城(野村喜舟)」)る
野人となる
木の実落ちてしかと打ちたる大地かな(紀行文「木曽」)
有感
きのふとも昔とも思ふ夜長かな(同上)
※ しかし、この東洋城の退官は、「東洋城が、『妻持たぬ』の句を詠んだ五年後の明治四十四年(一九一一)、福岡の炭鉱王だった伊藤伝右衛門と結婚させられた、柳原燁子(白蓮)の、大正六年(一九一七)の歌集『几帳の陰』、同八年の『幻の花』に所収されている、『激しい恋の歌』」の、その相手方は、「東洋城」その人という流聞など(それに関連しての、同じ式部官の某男爵夫人とのスキャンダル=『俳人風狂列伝』)による、当時の東洋城の上司の勧告に由る」ものとされている(『渋柿の木の下で(中村英利子著)』)。
これらの、東洋城の「女性スキャンダル」を背景にしている思われる句などを、『東洋城全句集(上巻)・大正八年』の句から抜粋すると、冒頭に掲出した、俳諧(連句)上の「恋の座(恋の句)」ということになる。
因みに、『東洋城全句集(上巻)・大正八年』の末尾の三句は、次のものである。
木枯や巷の群に白昼鬼(※「巷の群に白昼鬼」が意味深長である。)
逢はずなりし女と語る火桶かな(※「逢はずなりし」の「し」は過去形の措辞である。)
遠火事を芝居の中の噂かな(※「遠火事」「芝居」「噂」も「境涯」性を感じさせる。)
[寅彦=寅日子・四十二歳。発熱、発疹および胃痛に悩まされる。四月、大学内で倒れ、診察を受ける。十二月、胃潰瘍のため大学研究室で吐血、帝大付属病院に入学する。]
※ 『寺田寅彦 文学篇 第七巻(岩波書店)』には「大正八年」(一九一九)の収載句は無い。
[豊隆=蓬里雨の「小宮豊隆氏(年譜)」(「みやこ町歴史民俗博物館/小宮豊隆資料」)には、「大正八年」(一九一九)の記載は無い。]
https://adeac.jp/miyako-hf-mus/top/
(再掲) 「東洋城と白蓮」
https://yahan.blog.ss-blog.jp/2023-10-04
https://yahan.blog.ss-blog.jp/2023-10-03


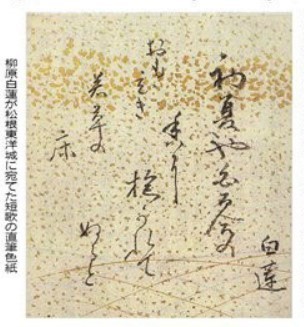
2014.9.24愛媛H新聞より
https://toonbusclub.jimdofree.com/%E6%83%A3%E6%B2%B3%E5%86%85%E7%A5%9E%E7%A4%BE-%E4%B8%80%E7%95%B3%E5%BA%B5/
※ 「初夏や白百合の/香に/抱かれて/ぬると/思ひき/若草の床」(柳原白蓮が松根東洋城に宛てた短歌の直筆色紙)
この「直筆色紙」を保管していた「川崎在住親族・松根敦子」さんは、「東洋城妹弟(妹・房子、弟・新八郎、弟・卓四郎、弟・宗一)」の、「三弟・卓四郎」家に嫁いだ方で、この「三弟・卓四郎」が、東洋城が「渋柿」を創刊したときの、名目上の「社主」のような、その事務所(「三畳庵」など)を提供していた方で、東洋城の遺品というのは、この「直筆色紙」の保管などからすると、「三弟・卓四郎」家が引き継いでいるように思われる。
(再掲) 「「東洋城兄弟(四人の男兄弟)」
https://yahan.blog.ss-blog.jp/2023-10-06
.jpg)
「兄東洋城と私(松根新八郎稿)」所収の「「東洋城兄弟(四人の男兄弟)」(「国立国会図書館デジタルコレクション」所収)
https://dl.ndl.go.jp/pid/6071686/1/50
[前列左から「宗一(六十四歳)・卓四郎(七十三歳)・東洋城(豊次郎)(八十六歳)・新八郎(八十一歳)」と思われる。後列の二人は東洋城の甥。中央に「松根家家宝の旗印(三畳敷の麻に朱墨の生首図=「「伊達の生首」)」が掲げられている。「伊達の生首」については、次のアドレスで紹介している。
https://yahan.blog.ss-blog.jp/2023-10-02 ]
「東洋城・寅彦、そして、豊隆」(漱石没後~寅彦没まで)俳句・連句管見(その五) [東洋城・寅日子(寅彦)・蓬里雨(豊隆)]
その二「大正七年(一九一八)」
[東洋城・四十一歳。奥州に遊び、『新奥の細道』連載。]
松島やそれより先の風薫れ(『新奥の細道』より四十五句の冒頭の句)
昔涼し芭蕉も子規も詣で居る(同上の三句目)
時鳥なくや雄島の明の明烏(同上・瑞巌寺)
杉を見て古く涼しき心かな(同上・中尊寺)
卯の花も兼房も見えぬ茂りかな(同上・高館)
風薫る星や義経勲功記(同上・平泉)
※ 東洋城が主宰した俳誌「渋柿」の「俳句の理念(モットー)」を、「松尾芭蕉の俳諧理念(わび・さび・しをり)を探究、『芭蕉直結・芭蕉に還れ』」を掲げて心境・境涯俳句の創作に努める」(「ウィキペディア」)とも、「芭蕉直結、写生を通して心境を詠む」(「俳人協会・「渋柿」の「俳誌のモットー」)とも、それらは、東洋城の「俳論」(「芭蕉の旅心」・「子規・芭蕉」・「俳諧根本義」・「俳諧至上」・「頭の無い恐竜」・「奥の細道夜話」・「芭蕉翁と」・「芭蕉の句について」等々)に基づいてのものなのであろう。
この前年の大正六年(一九一七)の、「渋柿」(二月号)は「漱石先生追悼号」として、その「終焉記」を書き、「漱石俳句輪講」が始められ、続いて、同年十二月号は、「漱石忌(十二月九日)記念号」と一年間に二回も追悼及び記念号を発刊すると、『漱石俳句集(東洋城編・岩波刊)』に没頭した。
明けて大正七年(一九一八)は、「『新奥の細道』より四十五句」・「『南部と津軽』より二十二句」・「『鹿島』十八句」・「『栗中山と大州』二十三句」・「『南北野分舟(松山・宇和島)』十七句」と、まさに、東洋城の「芭蕉の旅心」の、芭蕉俳諧追慕の吟行の連続であった。
(付記一)「漱石一周忌 三十七句」(大正六年「漱石一周忌」)
1 文の徳や冬嶺高く枯野広し(「漱石一周忌 三十七句」)
2 凩や天の一字の御心 (同上)
3 死悼めど御作読めば小春かな(同上)
4 凩や師の遺著犇(ひし)と書架の棚(同上)
5 小説とほ句との霜の一路かな(同上)
6 腹中に先生の書や冬籠(同上)
7 境涯に先生おはす冬籠(同上)
8 什麽(そも)先生死して生きざる寒夜かな(同上。「什麽(そも)」=「そもさん(作麽生)」の略。※正法眼蔵(1231‐53)仏性「この宗旨は作麽生なるべきぞ」。)
9 この忌修す初めての冬となりにけり(同上)
10 早稲田の夜急に時雨れぬ九日忌(同上)
11 凩の許樹さながらや漱石忌(同上)
12 師の御忌や二日隔てし白隠忌(同上)
13 九日のその夕暮や漱石忌(同上)
14 鶏頭の子規忌木枯の漱石忌(同上)
15 木枯の御墓も思ふ忌日かな(同上)
16 作中の誰れ彼れ参れ漱石忌(同上)
17 墓へまはる事も木枯や九日忌(同上)
18 吏となりて好める文や漱石忌(同上)
19 木枯やされども温泉の湧く力(同上。前書「漱石忌句会」。)
20 枯芭蕉も木賊(とくさ)も寒き庭となりぬ(同上。前書「早稲田南町」。)
21 ストーブに且火鉢ある書斎かな(同上)
22 枯蔦やベルも押さずに通りしか(同上)
23 或時は茶の間の炉にぞ挙(あが)りける(同上)
24 冬木して静かなるべき眠りかな(同上)
25 護国寺の屋根が見ゆるも寒さかな(同上)
26 菊活けて帰り去るあとの乞食かな(同上)
27 謡一番墓の下より秋静か(同上)
28 墓の時雨洛の春雨と通ふや否や(同上)
29 木立あれど紅葉あらざるお墓かな(同上)
30 こむる霧に独りぞあらん墓のそば(同上。前書「断腸」。)
31 芒枯れて何刈られたる根株かな(同上)
32 墓掃けば垣の外降る木の葉かな(同上)
33 御墓のうしろ風呂屋の小六月(同上)
34 その折の凩の音や耳に今(同上。前書「一年昨日」)
35 木枯や接心もゆる我が眼(同上。前書「逮夜句座三句」。)
36 木枯や浪のいづこに地の力((同上)
37 木枯や川の長さに足らぬ堤(同上) (『東洋城全句集(上巻)』)
(付記二) 「思ひ出るまゝ」寺田寅彦(大正六年二月「渋柿(夏目漱石追悼号)」・大正六年十二月「渋柿(漱石忌記念号)」)
「思ひ出るまゝ」寺田寅彦(大正六年二月「渋柿(夏目漱石追悼号)」)
講壇の隅にのせおくニッケルの袂(たまと)時計を貴しと見き
春寒き午前七時の課外講義オセロを読みしその頃の君
何もなき庭の垣根に朝顔の枯れたるままの坪井の邸(やしき)
帽を振り巾(きれ)振る人の中にたゞ黙して君は舷(ふなばた)に立ちし
家づとのカバン開けば一束の花ありぬ絹の白薔薇の花
行春の音楽会の帰るさに神田牛込そゞろあるきぬ
瀬戸物の瓶につめたる甘き酒青豆のスープ小鳥のロース
庭に咲く泰山木を指して此花君は如何に見ると云ひし
先生の湯浴果てるを待つひまに※スチユヂオの絵を幾度か見し(※Studio=仕事場)
或時は空間論に時間論生れぬ先の我を論じき
帽子着て前垂かけて小春日の縁の日向に初書きし君
美しき蔦の葉蔭の呼鈴の釦(ぼたん)を押すが嬉しかりしか
年毎に生ひ茂るまゝの木賊(とくさ)原茂りを愛(め)でし君は今亡し
此の憂(うれひ)誰に語らん語るべき一人の君を失ひし憂
(『寺田寅彦全集 文学篇 七巻・岩波書店』)
「思ひ出るまま」寺田寅彦(大正六年十二月「渋柿(漱石忌記念号)」)
金縁の老眼鏡をつくらせて初めてかけし其時の顔
マント着て黙りて歩く先生と肩をならべて江戸川端を
もみ上げの白髪抜けども拭きあへず老いぬと言ひし春の或夕
杉の香を籠めたる酒ぞ飲めと云ひて酔ひたる吾を笑ひし先生
先生と対(むか)ひてあれば腹立しき世とも思はず小春の日向
俳句とはかゝかるものぞと説かれしより天地開けて我が眼に新
(『寺田寅彦全集 文学篇 七巻・岩波書店』)
[寅彦=寅日子・四十一歳。数学物理学会において「原子構造概観」を特別講演する。四月、本郷区曙町に転居する。八月、酒井紳子と見合い結婚。]
骨を抱いて家を出づれば寒き朝(「渋柿」七年一月。六年十二月、東洋城宛書簡)
出迎ふる人亡くて門の冬の月(「日記」六年十二月二十五日)
今そこに居たかと思ふ火燵哉(同上)
亡き魂も出迎へよ門の冬の月(「渋柿」七年二月。前書「十二月二十五日帰京」)
※ これらの句は、大正六年(一九一七)十月十八日に亡くなった寛子夫人への追悼句であろう。行年三十一歳、十九歳の夏に結婚して円満な家庭を営み、二男一女を遺した。年内に、高知の寺田家の墓地に埋骨するため、十二月二十一日に東京を発ち、翌日の二十二日に高知港に着き、埋骨を済ませた。二十四日に高知を発ち、翌二十五日に帰京した。その時の一連の寅彦の句である。冒頭の句は、「東洋城宛書簡」の句で、「渋柿」(七年一月)に掲載された。
春風が吹いても石は石佛(「日記(一月二十三日)」。前書に「東洋城より端書きにて渋柿に前置付句の募集をする故選をせよとの事なり、柄になき故断る事とす」)
※ 大正五年(一九一六)十二月九日に、恩師・夏目漱石を失い、そして、それに続く、大正六(一九一七)十月十八日に、二男一女を遺して、寛子夫人を失うという、不運続きの寅彦への、東洋城の、気分転換の励ましの配慮を背後に託しているような、「渋柿」への「前置付句」(「連句」などの「前句付け=二句連句」)へのお誘いに対しての、寅彦の、その返答の句なのであろう。
この東洋城の「前置付句」のお誘いが、後の、大正十二年(一九二三)の、「東洋城・寅日子(寅彦)・蓬里雨(豊隆)」の「三吟連句」などに結実していいくのであろう。
[豊隆=蓬里雨・三十五歳。大正9年( 1920 )海軍大学校嘱託教授となる。大正10年 (1921 )芭蕉研究会に参加。]
※大正七年(1918)当時の豊隆は、『漱石全集』に取り組んでいて、「東洋城・寅日子・蓬里雨」の三吟歌仙とかは、大正十五年(1926)の頃が初出で、この頃は、「俳句・俳諧(連句)」には食指は伸ばしていなかったように思われる。大正十年(1921)の「芭蕉研究会」に参加は、東洋城の「渋柿」などとの「芭蕉研究会」ではなく、下記のアドレスのものなどによると、「太田水穂(歌誌「潮音」主宰)・幸田露伴・沼波瓊音・安倍能成・阿部次郎・小宮豊隆・和辻哲郎」らによる研究会のようである。
https://jyunku.hatenablog.com/entry/20100925/p1
「「芭蕉研究会」は田端の太田水穂(本名・貞一)宅で行われ、当初の会員は、阿部(次郎)、太田のほか、沼波瓊音、安倍能成、幸田露伴で、大正10年に小宮豊隆や和辻哲郎が加わった。」
この、阿部次郎・小宮豊隆らの「芭蕉研究会」の参加は、「大正15年( 1926) 芭蕉俳諧研究会を始める」と、「東北帝国大学」の「山田孝雄、村岡典嗣、岡崎義恵、太田正雄(木下杢太郎)」らの参加を得て、形を変えて継続されていくことになる。
https://www.library.tohoku.ac.jp/collection/collection/introduce.html
(追記一) 「青春時代を語る / 東洋城 ; 洋一/p54~73」)」(「俳誌『渋柿(昭和四十年(一九六五)の一月号) 』 (「松根東洋城追悼号」)」所収
(再掲)
https://yahan.blog.ss-blog.jp/2023-10-10

「青春時代を語る / 東洋城 ; 洋一/p54~73」時の「東洋城と吉田洋一」(左「東洋城」、右「吉田洋一」)
https://dl.ndl.go.jp/pid/6071686/1/41
「俳誌『渋柿(昭和四十年(一九六五)の一月号)』 (「松根東洋城追悼号」)」は、毀誉褒貶の風聞の中で、その全貌が未だに謎にみちたままの、明治・大正・昭和の三代にわたって、俳諧一筋の、東洋城の言葉でするならば、「芭蕉の誠の俳諧」一筋を貫いた生涯は、この「松根東洋城追悼号」は、その周辺の確かな道標を示すものであろう。
そして、それは、東洋城が没して十年後に刊行された、生前の東洋城の謦咳に接している俳句総合誌の「俳句研究」に携わった俳人の「石川桂郎」著の『俳人風狂列伝』(「読売文学賞」受賞)の、東洋城をめぐるスキャンダル(「白蓮事件」にも連動する「男爵夫人」あるいは「渋柿」からの「あら野」離脱に関連する「同人夫人」)とかの「東洋城の虚像(?)」に対する、その「東洋城の実像(?)」を語るものとして、この「青春時代を語る / 東洋城 ; 洋一/p54~73」や「兄東洋城と私 / 松根新八郎/p74~90」などは、いわば、「石川桂郎」著の『俳人風狂列伝』の「東洋城像(虚像?)」を覆すものの、すなわち、「東洋城(実像?)」を示しているものの、その一端を物語っているように思われる。
そして、これらことは、「虚子と東洋城」との、「ホトトギス(虚子)・国民俳壇(虚子・徳富蘇峰)・渋柿創刊(東洋城)・新傾向俳句の台頭(碧悟桐・井泉水・乙字・一碧楼など)との、混沌した中にあっての、「高浜虚子と松根東洋城」との、その「実像(?)と虚像(?)」との、これまた、その一端を物語る、一つの道標となり得るものであろう。
これらのことに関して、「虚子と東洋城」とが、「新傾向俳句(自由律俳句)」(碧悟桐・井泉水・乙字・一碧楼など)に対して、「伝統俳句(定型律俳句)」の牙城として、「ホトトギス」(虚子主宰)と「渋柿(東洋城主宰)」の二誌が、未曾有の、太平洋戦争前後の統制下にあって、その命脈を保ちつづけたということになる。
上記の写真(「東洋城と吉田洋一」)は、吉田洋一の軽井沢の山荘のもので、東洋城と洋一との接点は、寺田寅彦門下の北海道大学理学部教授の「中谷宇吉郎」を介してのもののようである(『渋柿の木の下で(中村英利子著)』)。
晩年の東洋城の避暑先は、この吉田洋一夫妻の山荘で過ごすのが常のようで、軽井沢は、寺田寅彦・小宮豊隆・中谷宇吉郎・吉田洋一らの忘れ得ざる邂逅の出会いの避暑地でもあったのである。
ここで、「明治四十二年(一九〇九)」の冒頭に戻って、その東洋城年譜の、[東洋城、三十二歳。東洋城の下宿「望遠館」(九段中坂)において、毎週一会の句会が催された。択ばれた者のみが出席できる会で、暮雨(万太郎)、蛇笏、零余子、松浜、喜舟などが、そのメンバーである。三月、東洋城選「新春夏秋冬」夏の部(「序」は夏目漱石)、十月「同・秋の部」を俳書堂より刊行した。]は、「東洋城・虚子、そして、漱石」との三者関係の、その最期の「華やぎ」のような、東洋城の「タンタヂイル(タンタジールの死)十八句」、そして、後の虚子の「大正初期に初めて書いた能『鐵門(てつもん)』(「タンタジールの死」に典拠する)との、当時の最晩年の漱石の膝下にあっての、「虚子と東洋城」との切磋琢磨の時代でもあった。
漱石は、この年に、東洋城選「新春夏秋冬」夏の部の、その刊行に当たって、その「序」を草している。
この東洋城選「新春夏秋冬」夏の部(「漱石・序」)も、下記のアドレスで閲覧することが出来る。
https://kindai.nijl.ac.jp/kindais/HKDT-01067
(追記二) 「新春夏秋冬 夏の部/俳諧叢書第二十二篇/松根東洋城 編」の「夏目漱石(序)」

「新春夏秋冬 夏の部/俳諧叢書第二十二篇/松根東洋城 編」/東洋城撰/明治42.3.5/ 1909.35/函館市中央図書館/
https://kindai.nijl.ac.jp/kindais/HKDT-01067
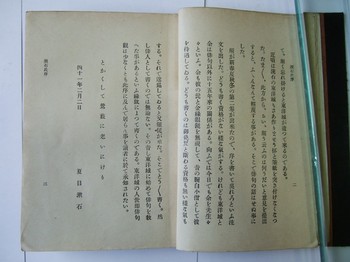
「新春夏秋冬 夏の部/俳諧叢書第二十二篇/松根東洋城 編」所収「夏目漱石『序』(明治四十二年二月二日)」
https://kindai.nijl.ac.jp/kindais/HKDT-01067
「夏目漱石『序』(明治四十二年二月二日)」全文
[ 東洋城は俳句本位の男である。あらゆる文字を十七字にしたがる許でない、人世則俳句観を抱いて道途に呻吟してゐる。時々来ては作りませうと催促する。題を貸して遣つて見ると遅吟である。君の句には嫌味がある杯と云ふと、中々承知しない。あなたのは十八世紀だと云つて、大変新しがつてゐる。
さう説明されて見ると、左様んな所もあるやうに思はる。実の所余は近来俳句には全く興味を失つて、其後の動静を頓と弁へない老骨である。運座は無論の事出ない。斯様にして追々十七字と縁が遠くなつて、漸く忘れ掛けると東洋城が遣つて来るのである。
近頃の流石の東洋城もさあ作りませう杯と筆紙を突き付けなくなつた。たまたま、此方から、おい、斯う云ふのは何うだいと意見を提出すると、ふゝんなんて軽蔑する事がある。そこで俳句の話はせぬ事にした。
所が新春夏秋冬の第二巻が出来たので、序を書いて呉れろといふ注文を出した。どうも書く資格がない様な気がする。けれども東洋城と余は俳句以外に十五年来の関係がある。向こふでは今日でも余を先生々々といふ。余も彼の髭と金縁眼鏡を無視して、昔の腕白小僧として彼を待遇してゐる。どうも書くのは御免だと断わる資格も無い様な気もする。それで逡巡してゐると又催促が来た。そこでとうとう書く。然し俳人として書くのでは無論ない。その昔し、東洋城に始めて俳句を教へた事があるといふ縁故によつて書くのである。東洋城の人生則俳句観は少なくとも此序に及んで居らん事を読者に於て承知されたい。
とかくして鶯藪に老いにけり
四十一年二月二日 夏目漱石 ]
(『俳句講座八 現代作家論』所収「松根東洋城(野村喜舟)」)
[東洋城・四十一歳。奥州に遊び、『新奥の細道』連載。]
松島やそれより先の風薫れ(『新奥の細道』より四十五句の冒頭の句)
昔涼し芭蕉も子規も詣で居る(同上の三句目)
時鳥なくや雄島の明の明烏(同上・瑞巌寺)
杉を見て古く涼しき心かな(同上・中尊寺)
卯の花も兼房も見えぬ茂りかな(同上・高館)
風薫る星や義経勲功記(同上・平泉)
※ 東洋城が主宰した俳誌「渋柿」の「俳句の理念(モットー)」を、「松尾芭蕉の俳諧理念(わび・さび・しをり)を探究、『芭蕉直結・芭蕉に還れ』」を掲げて心境・境涯俳句の創作に努める」(「ウィキペディア」)とも、「芭蕉直結、写生を通して心境を詠む」(「俳人協会・「渋柿」の「俳誌のモットー」)とも、それらは、東洋城の「俳論」(「芭蕉の旅心」・「子規・芭蕉」・「俳諧根本義」・「俳諧至上」・「頭の無い恐竜」・「奥の細道夜話」・「芭蕉翁と」・「芭蕉の句について」等々)に基づいてのものなのであろう。
この前年の大正六年(一九一七)の、「渋柿」(二月号)は「漱石先生追悼号」として、その「終焉記」を書き、「漱石俳句輪講」が始められ、続いて、同年十二月号は、「漱石忌(十二月九日)記念号」と一年間に二回も追悼及び記念号を発刊すると、『漱石俳句集(東洋城編・岩波刊)』に没頭した。
明けて大正七年(一九一八)は、「『新奥の細道』より四十五句」・「『南部と津軽』より二十二句」・「『鹿島』十八句」・「『栗中山と大州』二十三句」・「『南北野分舟(松山・宇和島)』十七句」と、まさに、東洋城の「芭蕉の旅心」の、芭蕉俳諧追慕の吟行の連続であった。
(付記一)「漱石一周忌 三十七句」(大正六年「漱石一周忌」)
1 文の徳や冬嶺高く枯野広し(「漱石一周忌 三十七句」)
2 凩や天の一字の御心 (同上)
3 死悼めど御作読めば小春かな(同上)
4 凩や師の遺著犇(ひし)と書架の棚(同上)
5 小説とほ句との霜の一路かな(同上)
6 腹中に先生の書や冬籠(同上)
7 境涯に先生おはす冬籠(同上)
8 什麽(そも)先生死して生きざる寒夜かな(同上。「什麽(そも)」=「そもさん(作麽生)」の略。※正法眼蔵(1231‐53)仏性「この宗旨は作麽生なるべきぞ」。)
9 この忌修す初めての冬となりにけり(同上)
10 早稲田の夜急に時雨れぬ九日忌(同上)
11 凩の許樹さながらや漱石忌(同上)
12 師の御忌や二日隔てし白隠忌(同上)
13 九日のその夕暮や漱石忌(同上)
14 鶏頭の子規忌木枯の漱石忌(同上)
15 木枯の御墓も思ふ忌日かな(同上)
16 作中の誰れ彼れ参れ漱石忌(同上)
17 墓へまはる事も木枯や九日忌(同上)
18 吏となりて好める文や漱石忌(同上)
19 木枯やされども温泉の湧く力(同上。前書「漱石忌句会」。)
20 枯芭蕉も木賊(とくさ)も寒き庭となりぬ(同上。前書「早稲田南町」。)
21 ストーブに且火鉢ある書斎かな(同上)
22 枯蔦やベルも押さずに通りしか(同上)
23 或時は茶の間の炉にぞ挙(あが)りける(同上)
24 冬木して静かなるべき眠りかな(同上)
25 護国寺の屋根が見ゆるも寒さかな(同上)
26 菊活けて帰り去るあとの乞食かな(同上)
27 謡一番墓の下より秋静か(同上)
28 墓の時雨洛の春雨と通ふや否や(同上)
29 木立あれど紅葉あらざるお墓かな(同上)
30 こむる霧に独りぞあらん墓のそば(同上。前書「断腸」。)
31 芒枯れて何刈られたる根株かな(同上)
32 墓掃けば垣の外降る木の葉かな(同上)
33 御墓のうしろ風呂屋の小六月(同上)
34 その折の凩の音や耳に今(同上。前書「一年昨日」)
35 木枯や接心もゆる我が眼(同上。前書「逮夜句座三句」。)
36 木枯や浪のいづこに地の力((同上)
37 木枯や川の長さに足らぬ堤(同上) (『東洋城全句集(上巻)』)
(付記二) 「思ひ出るまゝ」寺田寅彦(大正六年二月「渋柿(夏目漱石追悼号)」・大正六年十二月「渋柿(漱石忌記念号)」)
「思ひ出るまゝ」寺田寅彦(大正六年二月「渋柿(夏目漱石追悼号)」)
講壇の隅にのせおくニッケルの袂(たまと)時計を貴しと見き
春寒き午前七時の課外講義オセロを読みしその頃の君
何もなき庭の垣根に朝顔の枯れたるままの坪井の邸(やしき)
帽を振り巾(きれ)振る人の中にたゞ黙して君は舷(ふなばた)に立ちし
家づとのカバン開けば一束の花ありぬ絹の白薔薇の花
行春の音楽会の帰るさに神田牛込そゞろあるきぬ
瀬戸物の瓶につめたる甘き酒青豆のスープ小鳥のロース
庭に咲く泰山木を指して此花君は如何に見ると云ひし
先生の湯浴果てるを待つひまに※スチユヂオの絵を幾度か見し(※Studio=仕事場)
或時は空間論に時間論生れぬ先の我を論じき
帽子着て前垂かけて小春日の縁の日向に初書きし君
美しき蔦の葉蔭の呼鈴の釦(ぼたん)を押すが嬉しかりしか
年毎に生ひ茂るまゝの木賊(とくさ)原茂りを愛(め)でし君は今亡し
此の憂(うれひ)誰に語らん語るべき一人の君を失ひし憂
(『寺田寅彦全集 文学篇 七巻・岩波書店』)
「思ひ出るまま」寺田寅彦(大正六年十二月「渋柿(漱石忌記念号)」)
金縁の老眼鏡をつくらせて初めてかけし其時の顔
マント着て黙りて歩く先生と肩をならべて江戸川端を
もみ上げの白髪抜けども拭きあへず老いぬと言ひし春の或夕
杉の香を籠めたる酒ぞ飲めと云ひて酔ひたる吾を笑ひし先生
先生と対(むか)ひてあれば腹立しき世とも思はず小春の日向
俳句とはかゝかるものぞと説かれしより天地開けて我が眼に新
(『寺田寅彦全集 文学篇 七巻・岩波書店』)
[寅彦=寅日子・四十一歳。数学物理学会において「原子構造概観」を特別講演する。四月、本郷区曙町に転居する。八月、酒井紳子と見合い結婚。]
骨を抱いて家を出づれば寒き朝(「渋柿」七年一月。六年十二月、東洋城宛書簡)
出迎ふる人亡くて門の冬の月(「日記」六年十二月二十五日)
今そこに居たかと思ふ火燵哉(同上)
亡き魂も出迎へよ門の冬の月(「渋柿」七年二月。前書「十二月二十五日帰京」)
※ これらの句は、大正六年(一九一七)十月十八日に亡くなった寛子夫人への追悼句であろう。行年三十一歳、十九歳の夏に結婚して円満な家庭を営み、二男一女を遺した。年内に、高知の寺田家の墓地に埋骨するため、十二月二十一日に東京を発ち、翌日の二十二日に高知港に着き、埋骨を済ませた。二十四日に高知を発ち、翌二十五日に帰京した。その時の一連の寅彦の句である。冒頭の句は、「東洋城宛書簡」の句で、「渋柿」(七年一月)に掲載された。
春風が吹いても石は石佛(「日記(一月二十三日)」。前書に「東洋城より端書きにて渋柿に前置付句の募集をする故選をせよとの事なり、柄になき故断る事とす」)
※ 大正五年(一九一六)十二月九日に、恩師・夏目漱石を失い、そして、それに続く、大正六(一九一七)十月十八日に、二男一女を遺して、寛子夫人を失うという、不運続きの寅彦への、東洋城の、気分転換の励ましの配慮を背後に託しているような、「渋柿」への「前置付句」(「連句」などの「前句付け=二句連句」)へのお誘いに対しての、寅彦の、その返答の句なのであろう。
この東洋城の「前置付句」のお誘いが、後の、大正十二年(一九二三)の、「東洋城・寅日子(寅彦)・蓬里雨(豊隆)」の「三吟連句」などに結実していいくのであろう。
[豊隆=蓬里雨・三十五歳。大正9年( 1920 )海軍大学校嘱託教授となる。大正10年 (1921 )芭蕉研究会に参加。]
※大正七年(1918)当時の豊隆は、『漱石全集』に取り組んでいて、「東洋城・寅日子・蓬里雨」の三吟歌仙とかは、大正十五年(1926)の頃が初出で、この頃は、「俳句・俳諧(連句)」には食指は伸ばしていなかったように思われる。大正十年(1921)の「芭蕉研究会」に参加は、東洋城の「渋柿」などとの「芭蕉研究会」ではなく、下記のアドレスのものなどによると、「太田水穂(歌誌「潮音」主宰)・幸田露伴・沼波瓊音・安倍能成・阿部次郎・小宮豊隆・和辻哲郎」らによる研究会のようである。
https://jyunku.hatenablog.com/entry/20100925/p1
「「芭蕉研究会」は田端の太田水穂(本名・貞一)宅で行われ、当初の会員は、阿部(次郎)、太田のほか、沼波瓊音、安倍能成、幸田露伴で、大正10年に小宮豊隆や和辻哲郎が加わった。」
この、阿部次郎・小宮豊隆らの「芭蕉研究会」の参加は、「大正15年( 1926) 芭蕉俳諧研究会を始める」と、「東北帝国大学」の「山田孝雄、村岡典嗣、岡崎義恵、太田正雄(木下杢太郎)」らの参加を得て、形を変えて継続されていくことになる。
https://www.library.tohoku.ac.jp/collection/collection/introduce.html
(追記一) 「青春時代を語る / 東洋城 ; 洋一/p54~73」)」(「俳誌『渋柿(昭和四十年(一九六五)の一月号) 』 (「松根東洋城追悼号」)」所収
(再掲)
https://yahan.blog.ss-blog.jp/2023-10-10

「青春時代を語る / 東洋城 ; 洋一/p54~73」時の「東洋城と吉田洋一」(左「東洋城」、右「吉田洋一」)
https://dl.ndl.go.jp/pid/6071686/1/41
「俳誌『渋柿(昭和四十年(一九六五)の一月号)』 (「松根東洋城追悼号」)」は、毀誉褒貶の風聞の中で、その全貌が未だに謎にみちたままの、明治・大正・昭和の三代にわたって、俳諧一筋の、東洋城の言葉でするならば、「芭蕉の誠の俳諧」一筋を貫いた生涯は、この「松根東洋城追悼号」は、その周辺の確かな道標を示すものであろう。
そして、それは、東洋城が没して十年後に刊行された、生前の東洋城の謦咳に接している俳句総合誌の「俳句研究」に携わった俳人の「石川桂郎」著の『俳人風狂列伝』(「読売文学賞」受賞)の、東洋城をめぐるスキャンダル(「白蓮事件」にも連動する「男爵夫人」あるいは「渋柿」からの「あら野」離脱に関連する「同人夫人」)とかの「東洋城の虚像(?)」に対する、その「東洋城の実像(?)」を語るものとして、この「青春時代を語る / 東洋城 ; 洋一/p54~73」や「兄東洋城と私 / 松根新八郎/p74~90」などは、いわば、「石川桂郎」著の『俳人風狂列伝』の「東洋城像(虚像?)」を覆すものの、すなわち、「東洋城(実像?)」を示しているものの、その一端を物語っているように思われる。
そして、これらことは、「虚子と東洋城」との、「ホトトギス(虚子)・国民俳壇(虚子・徳富蘇峰)・渋柿創刊(東洋城)・新傾向俳句の台頭(碧悟桐・井泉水・乙字・一碧楼など)との、混沌した中にあっての、「高浜虚子と松根東洋城」との、その「実像(?)と虚像(?)」との、これまた、その一端を物語る、一つの道標となり得るものであろう。
これらのことに関して、「虚子と東洋城」とが、「新傾向俳句(自由律俳句)」(碧悟桐・井泉水・乙字・一碧楼など)に対して、「伝統俳句(定型律俳句)」の牙城として、「ホトトギス」(虚子主宰)と「渋柿(東洋城主宰)」の二誌が、未曾有の、太平洋戦争前後の統制下にあって、その命脈を保ちつづけたということになる。
上記の写真(「東洋城と吉田洋一」)は、吉田洋一の軽井沢の山荘のもので、東洋城と洋一との接点は、寺田寅彦門下の北海道大学理学部教授の「中谷宇吉郎」を介してのもののようである(『渋柿の木の下で(中村英利子著)』)。
晩年の東洋城の避暑先は、この吉田洋一夫妻の山荘で過ごすのが常のようで、軽井沢は、寺田寅彦・小宮豊隆・中谷宇吉郎・吉田洋一らの忘れ得ざる邂逅の出会いの避暑地でもあったのである。
ここで、「明治四十二年(一九〇九)」の冒頭に戻って、その東洋城年譜の、[東洋城、三十二歳。東洋城の下宿「望遠館」(九段中坂)において、毎週一会の句会が催された。択ばれた者のみが出席できる会で、暮雨(万太郎)、蛇笏、零余子、松浜、喜舟などが、そのメンバーである。三月、東洋城選「新春夏秋冬」夏の部(「序」は夏目漱石)、十月「同・秋の部」を俳書堂より刊行した。]は、「東洋城・虚子、そして、漱石」との三者関係の、その最期の「華やぎ」のような、東洋城の「タンタヂイル(タンタジールの死)十八句」、そして、後の虚子の「大正初期に初めて書いた能『鐵門(てつもん)』(「タンタジールの死」に典拠する)との、当時の最晩年の漱石の膝下にあっての、「虚子と東洋城」との切磋琢磨の時代でもあった。
漱石は、この年に、東洋城選「新春夏秋冬」夏の部の、その刊行に当たって、その「序」を草している。
この東洋城選「新春夏秋冬」夏の部(「漱石・序」)も、下記のアドレスで閲覧することが出来る。
https://kindai.nijl.ac.jp/kindais/HKDT-01067
(追記二) 「新春夏秋冬 夏の部/俳諧叢書第二十二篇/松根東洋城 編」の「夏目漱石(序)」

「新春夏秋冬 夏の部/俳諧叢書第二十二篇/松根東洋城 編」/東洋城撰/明治42.3.5/ 1909.35/函館市中央図書館/
https://kindai.nijl.ac.jp/kindais/HKDT-01067
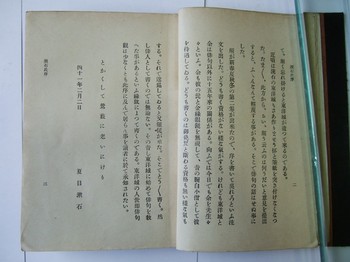
「新春夏秋冬 夏の部/俳諧叢書第二十二篇/松根東洋城 編」所収「夏目漱石『序』(明治四十二年二月二日)」
https://kindai.nijl.ac.jp/kindais/HKDT-01067
「夏目漱石『序』(明治四十二年二月二日)」全文
[ 東洋城は俳句本位の男である。あらゆる文字を十七字にしたがる許でない、人世則俳句観を抱いて道途に呻吟してゐる。時々来ては作りませうと催促する。題を貸して遣つて見ると遅吟である。君の句には嫌味がある杯と云ふと、中々承知しない。あなたのは十八世紀だと云つて、大変新しがつてゐる。
さう説明されて見ると、左様んな所もあるやうに思はる。実の所余は近来俳句には全く興味を失つて、其後の動静を頓と弁へない老骨である。運座は無論の事出ない。斯様にして追々十七字と縁が遠くなつて、漸く忘れ掛けると東洋城が遣つて来るのである。
近頃の流石の東洋城もさあ作りませう杯と筆紙を突き付けなくなつた。たまたま、此方から、おい、斯う云ふのは何うだいと意見を提出すると、ふゝんなんて軽蔑する事がある。そこで俳句の話はせぬ事にした。
所が新春夏秋冬の第二巻が出来たので、序を書いて呉れろといふ注文を出した。どうも書く資格がない様な気がする。けれども東洋城と余は俳句以外に十五年来の関係がある。向こふでは今日でも余を先生々々といふ。余も彼の髭と金縁眼鏡を無視して、昔の腕白小僧として彼を待遇してゐる。どうも書くのは御免だと断わる資格も無い様な気もする。それで逡巡してゐると又催促が来た。そこでとうとう書く。然し俳人として書くのでは無論ない。その昔し、東洋城に始めて俳句を教へた事があるといふ縁故によつて書くのである。東洋城の人生則俳句観は少なくとも此序に及んで居らん事を読者に於て承知されたい。
とかくして鶯藪に老いにけり
四十一年二月二日 夏目漱石 ]
(『俳句講座八 現代作家論』所収「松根東洋城(野村喜舟)」)
「東洋城・寅彦、そして、豊隆」(漱石没後~寅彦没まで)俳句・連句管見(その一) [東洋城・寅日子(寅彦)・蓬里雨(豊隆)]
その一「大正六年(一九一七)」
[東洋城・四十歳。「渋柿」=『漱石先生追悼号』・『漱石忌記念号』刊。駿遠地方に遊び、北白川宮と天龍川を下った。『漱石俳句集(東洋城編・岩波版)』刊。]
冴え返るよきお句などを偲び合ひぬ(前書「漱石先生追悼三句)
いまそかりし師の座かしこき火桶かな(前書「漱石庵」)
小説で比叡に登るや春の風(前書「虞美人草」)
[寅彦=寅日子・四十歳。『漱石全集(岩波版)』の編集委員となる。二月、俳句雑誌「渋柿」の夏目漱石追悼号に短歌を発表する。三月、航空学調査委員となる。七月、「ラウエ映画の実験方法及其説明に関する研究」により帝国学士院から恩賜賞を受ける。九月、高等官三等に叙せられる。十月、妻の寛子が死亡。寅彦、従五位に叙せられる。]
触れて見れど唯つめたさの小袖哉(十一月二十八日、「渋柿(七年二月)」)
[蓬里雨=豊隆・三十四歳。大正5年=1916、 東京医学専門学校講師となる。12月9日夏目漱石死去。大正6年= 1917、「漱石全集」の編集にとりかかる。]
(追記一)夏目漱石葬儀前後の「東洋城・寅彦・豊隆」周辺
大正五(一九一六)十二月九日、夏目漱石は、その五十年の生涯を閉じた。その翌日に、東大で解剖に付せられ、十一日に、通夜、十二日に、青山斎場で葬儀、落合火葬場で荼毘に付された。
葬儀委員長は「中村是公」(漱石と「一高」同期、大蔵官僚、満鉄総裁、東京市長を歴任)、弔辞は「村山龍平」(朝日新聞社社長・社主、貴族院議員を歴任)、友人総代は「狩野亨吉」(漱石と東京帝国時代に親炙、第五高校と共に教鞭、後に、一高校長、京都大学初代文科大学長を歴任)、導師は「釈宗演」(円覚寺派管長)、門下生有志総代は「小宮豊隆」、当日の進行・司会は「松根東洋城」が務めた。
門下生有志総代は、「寺田寅彦」が務めるべきであったが、漱石と同じ病の胃潰瘍で、絶対安静の病臥中で、「小宮豊隆」が門下生有志総代を務めることになった。豊隆は、その弔辞を寅彦に認めていただくことを寅彦に依頼したが、それも叶わなかった。
寅彦が、最期の漱石の病気見舞い行ったのは、十二月二日で、寅彦の、その時のことが、日記に記されている。
「午後、夏目先生を見舞いに行く。重態なり。午後四時半、再度の出血ありたるごとく容態悪くなり、真鍋、宮本、南三博士と井上、安倍両学士詰め切る。夜十一時、安静となりたれば一旦辞し帰る。」
続く、十二月三日に、
「胃潰瘍の疑いあれば安静を要する由なり。午後、夏目へ見舞に行く。経過良好なり。」
寅彦も、「いよいよ胃の出血らしいので絶対安静を要する」との状態で、寅彦の再婚の夫人「寛子」も、この時に、「慢性結核リンパ腺炎・頸部リンパ腺炎」との診断がなされている。
十二月九日の漱石の亡くなる前に、寛子夫人が寅彦にかわり夏目家に見舞いに行き、その翌日の弔問、そして、十二日の葬儀にも、寛子夫人が列席した。(『寺田寅彦 妻たちの歳月(山田一郎著)』)
これらの夏目漱石の一連の最期・通夜・葬儀関連の段取りは、「漱石門下生(木曜会・九日会)」のメンバーの中で、好むと好まざるとにかかわらず、結果的に、「漱石門下生」の最古参の、「夏目家」との信頼抜群の、そして、宮内省「式部官(「北白川家御用掛」兼職)」の「松根東洋城」が担うことになった。
.jpg)
「兄東洋城と私(松根新八郎稿)」所収の「松根東洋城」(「式部職の大礼服」着衣)(「国立国会図書館デジタルコレクション」所収)
https://dl.ndl.go.jp/pid/6071686/1/42
[ 葬式の当日、東洋城は金筋の入った宮内省の礼服姿でシルクハットを小脇に抱え、祭壇より一段低い土間の上に参列者の方を向いて立ち、それなりに威厳に満ちた姿であったのだが、弟子たちにはいかにも場内を見下すかのように傲然として見え、「あの俗臭芬々とした姿は、漱石先生の葬儀にはまったくふさわしからぬものに見えたね」と散々な評価であった。また、東洋城は、告別が終わった人の群れを、右手を平らにして、それで臼でも挽く時のように動かしていたのだが、それが弟子たちにはなんとも妙な手つきに見え、芥川龍之介が「あれは、礼をしたら順々に棺の後ろを回って、出ていってくれという合図だろう」と言った。すると、やきもち焼きでうるさい鈴木三重吉は、「松根のやつが、頼まれもしないのに余計なところへ出しゃべって」と、まずそれからしてはなはだ面白くないところへ、例の「臼でも挽く」ような手つきがますます気に入らないと言い、その後、酒に酔うと必ず、「なんだあいつ、こんな手つきをしやがって、どうぞこちらへ、どうぞこちらへと言っていやがる」と毎度同じ手真似を繰り返し、並居る人を笑わせた。
三重吉はほかにも、「自分たちは斎場へ電車で行ったのに、小宮だけは遺族と一緒に馬車で行った」と、その厚かましさに憤慨したが、それは小宮豊隆が勝手に遺族の馬車へ乗り込んだわけではなく、夫人の鏡子が小さい子どもたちの付き添いをしてくれとわざわざ頼んだためだった。三重吉は、漱石の死と数日来の疲労から日頃に増していらいらし、怒りぽっくなっていた。(中略)
「九日会」は毎回幹事が変わり、安倍能成や鈴木三重吉などがその役を果たして、弟子同士で旧交を温めていたのだが、東洋城はその会に一度も出なかった。理由は、漱石が危篤に陥った頃からの東洋城の独断と他の弟子たちとの軋轢だと思われたが、それだけというわけではなかった。東洋城は、俳誌「渋柿」の編集に追われ、特に漱石追悼の特集が続いて多忙だったのである。
また、東洋城は弟子たちのすべてと交際を絶っていたわけではなく、そのうちの何人かとは個別に会っており、特に仲の良い寺田寅彦や小宮豊隆らの数人とはかなり頻繁に会っていた。」(『渋柿の木の下で(中村英利子著)』)
(追記二)当時の「寺田寅彦」周辺
https://www.jstage.jst.go.jp/article/ningendock1986/7/2/7_7/_pdf
[ 夏子さん はその年(明治三十五年=1902) の11月15日 に亡 くな りま した。
寅彦は不幸な運命を背負うわけですが、日露戦争の終わった年ですから明治38年、28歳の時、再婚をします。種崎の隣の仁井田という所 の出身で、山内家の家扶をしていた漢詩人の浜口真徴の三女寛子さんを迎えます。菊池寛の寛と書 いてユタコと読むんですが、この人との間に男2人と女2人の子宝に恵まれましたが、夏目漱石が亡くなった大正5年の翌年、6月の10日に一 夜のうちに肺を侵され寛子さんは亡 くなります。 恩師漱石の葬儀にも寅彦自身も胃潰瘍 になって参列できなか ったのです。そういうふうにいろいろ不幸せに見舞われますが、明るい話題もあります。31歳で理学博士になり、翌年5月、欧米へ留学します。そして大正6年の7月、「ラウエ映画 の実験方法 とその説明に関する研究」で学士院恩賜賞をもらいます。
40歳の若さでした。そして寛子夫人が亡 くな ったのは3カ 月後の10月 のことでした。西川正治という後 に文化勲章をもらった大変偉 い物理学者がいますが、この先生が書いて るのを読みますと、ラウエ ・スポ ッ トの研究 は大 変画期的な発 見であ って、もし寺田先生が 日本でな くてイギ リスなりフラ ンスなりで生まれていたらばノーベ ル賞を寺田先生がもらったに違いないというんですね。この研究に寅彦はレントゲンを使 ったのですが、 それは大学の医学部で廃品 にな った レン トゲ ンをもらって来て改造 したもので した。
寛子夫人を亡 くし、4人 の子ど も抱えて苦 しむ心境 は寅彦 の「蓄音機 」と いう随筆に書いてあります。 こど もた ちを慰 め るため に蓄音機 を買う。童謡 をかけてやる。下 の女の子 は3歳 上 の女の子が5歳 です。]
(追記三) 当時の「小宮豊隆」周辺

「漱石忌(12/9)と九日会」(「漱石の肉筆を後世へ!漱石文庫デジタルアーカイブプロジェクト」東北大学附属図書館)
https://readyfor.jp/projects/soseki-library/announcements/118615
[写真は大正6年(1917)1月9日の第一回の九日会です(神奈川近代文学館蔵)。
左から安倍能成、野上豊一郎、鏡子夫人、内田百閒、津田青楓、久米正雄、赤木桁平、芥川龍之介、森田草平、和辻哲郎。右から滝田樗蔭、速水滉、阿部次郎、岩波茂雄、小宮豊隆という顔ぶれです。奥の部屋が漱石山房の書斎部分で、手前が客間部分でした。]
上記の写真は、漱石没後(大正5年12月9日)の、その翌年の「大正6年(1917)1月9日第一回の九日会」の写真である。この写真に出てくるメンバーは「左から安倍能成、野上豊一郎、鏡子夫人、内田百閒、津田青楓、久米正雄、赤木桁平、芥川龍之介、森田草平、和辻哲郎。右から滝田樗蔭、速水滉、阿部次郎、岩波茂雄、小宮豊隆」という顔ぶれである。
この時に、『漱石全集』の刊行の発議をしたのは、小宮豊隆のようである(『漱石山脈(長尾剛著)』)。この写真の「小宮豊隆・岩波茂雄・阿部次郎」が、火鉢に手をかざしているが、この三人は『岩波全集』の刊行の中心的な人物で、あたかも「漱石没後の最初の『岩波全集』刊行について何やら会話している」ような風情である。
「漱石が亡くなってすぐ、豊隆は『漱石山脈』の面々に向かって『漱石全集』の刊行を発議し、自らが『漱石伝』を執筆すると宣言した。漱石の危篤状態の時からずっと考えていたことだったに違いない。
この頃すでに岩波茂雄が古書店として立ち上げた岩波書店は出版社として確立していた。そこで、漱石作品を長く刊行していた春陽堂と大倉書店に岩波書店が加わって、三社で全集を刊行することになり、編集作業は岩波書店のプロジェクトとなった。
豊隆の『漱石全集』編集に対する執念は、すさまじいものだった。膨大な資料を搔き集め続け、全集を刊行し直すたびに少しずつ改訂増補を加えていった。
昭和十年、漱石没後二十年を記念として岩波書店から刊行された決定版『漱石全集』では、なんと全巻の解説文まで引き受けた。
それぞれの巻の解説を別々の弟子が受け持ってもよさそうなものである。が、安倍能成が「小宮にすべてを託したい」と提案し、豊隆が大乗り気で引き受けたのだ。豊隆には「漱石について語る第一人者は俺なのだ」といった自負があったし、周りもそれを認めていたらしい。取りも直さず「漱石と豊隆の深い親密さ」を、誰もが認めていたということだろう。」(『漱石山脈(長尾剛著)』)。
岩波茂雄については、『漱石山脈(長尾剛著)』では、「岩波茂雄『漱石全集』を作った男」(「曰く付きの岩波書店の看板/漱石から借金しまくった岩波茂雄/『こゝろ』は漱石の自費出版」)と、岩波茂雄の一端を披露しているが、[『思想』(1921年)『科学』(1931年)『文化』(1934年)などの雑誌や、1927年(昭和2年)には「岩波文庫」を創刊。日中戦争について「日本はしなくてもいい戦争をしている」と日本軍に対して批判的な立場から活動を展開していた。これによって軍部の圧力をかけられるようになる。](「ウィキペディア」)と、「1945年3月に貴族院多額納税者議員に互選、同年4月4日に任命されるが、それから6ヶ月後に脳出血で倒れる。翌年には雑誌『世界』が創刊され、文化勲章も受ける」(「ウィキペディア」)と、茂雄自身が、「漱石山脈」に連なる一人として、「高浜虚子」(漱石の木曜会に連なる「ホトトギス」派の総帥且つ「日本俳壇大御所」)の、「1954年(昭和29年)、文化勲章受章」と、「漱石山脈」の中での一巨峰というへき位置を占めるべき一人なのであろう。
阿部次郎については、次の「ウィキペディア」の紹介記事のとおり、「岩波茂雄と『一高』同期で、そして、後に、『東北帝国大学教授・小宮豊隆』を招聘する」、まさに、上記の「大正6年(1917)1月9日第一回の九日会」の写真の「小宮豊隆・岩波茂雄・阿部次郎」の、この三人が、同じ火鉢で手をかざしている画像は、誠に、漱石没後の『漱石全集』の誕生の、その切っ掛けを暗示しているような象徴的な一スナップとして評価されるぺきものであろう。
「1901年(明治34年)、第一高等学校入学。同級生に鳩山秀夫、岩波茂雄、荻原井泉水、一級下に斎藤茂吉がいた。1907年(明治40年)、東京帝国大学に入学し、ラファエル・フォン・ケーベル博士を師と仰ぐ。卒業論文「スピノーザの本体論」で哲学科を卒業。夏目漱石の門に出入りして、森田草平、小宮豊隆、安倍能成とともに「朝日文芸欄」の主要な執筆者となり、「自ら知らざる自然主義者」(明治43年)等の評論で、漱石門下の論客として注目された[3]。1911年(明治44年)、森田・小宮・安倍との合著による評論集『影と聲』を上梓する。
1914年(大正3年)に発表した『三太郎の日記』は大正昭和期の青春のバイブルとして有名で、学生必読の書であった[4](大正教養主義を主導)。1917年(大正6年)に一高の同級生であった岩波茂雄が雑誌『思潮』(現在の『思想』)を創刊。その主幹となる。
慶應義塾、日本女子大学校の講師を経て1922年(大正11年)、文部省在外研究員としてのヨーロッパ留学。
同年に『人格主義』を発表。真・善・美を豊かに自由に追究する人、自己の尊厳を自覚する自由の人、そうした人格の結合による社会こそ真の理想的社会であると説く(人格主義を主張)。
同年刊行された『地獄の征服』はゲーテ・ニーチェ・ダンテに関する論文をまとめたもので、従来の研究水準を大きく超えており、ダンテの愛読者だった正宗白鳥も「私はこれによってはじめて、ダンテに対する日本人の独創の見解に接した(中略)翻訳して欧米のダンテ学者に示すに足るもの」と称賛している。」(「ウィキペディア」)

「漱石山房の門下生(前列左から「松根東洋城・三重吉・森田草平・小宮豊隆」)
https://yahan.blog.ss-blog.jp/2023-10-05
この前列の「東洋城・三重吉・草平・豊隆」の、この背後の人物は、「阿部次郎」と解したい。

[阿部 次郎(あべ じろう、1883年〈明治16年〉8月27日 - 1959年〈昭和34年〉10月20日)は、日本の哲学者・美学者・作家。東北帝国大学法文学部教授、同学部長、帝国学士院会員。仙台市名誉市民。『三太郎の日記』著者。](「ウィキペディア」)
[東洋城・四十歳。「渋柿」=『漱石先生追悼号』・『漱石忌記念号』刊。駿遠地方に遊び、北白川宮と天龍川を下った。『漱石俳句集(東洋城編・岩波版)』刊。]
冴え返るよきお句などを偲び合ひぬ(前書「漱石先生追悼三句)
いまそかりし師の座かしこき火桶かな(前書「漱石庵」)
小説で比叡に登るや春の風(前書「虞美人草」)
[寅彦=寅日子・四十歳。『漱石全集(岩波版)』の編集委員となる。二月、俳句雑誌「渋柿」の夏目漱石追悼号に短歌を発表する。三月、航空学調査委員となる。七月、「ラウエ映画の実験方法及其説明に関する研究」により帝国学士院から恩賜賞を受ける。九月、高等官三等に叙せられる。十月、妻の寛子が死亡。寅彦、従五位に叙せられる。]
触れて見れど唯つめたさの小袖哉(十一月二十八日、「渋柿(七年二月)」)
[蓬里雨=豊隆・三十四歳。大正5年=1916、 東京医学専門学校講師となる。12月9日夏目漱石死去。大正6年= 1917、「漱石全集」の編集にとりかかる。]
(追記一)夏目漱石葬儀前後の「東洋城・寅彦・豊隆」周辺
大正五(一九一六)十二月九日、夏目漱石は、その五十年の生涯を閉じた。その翌日に、東大で解剖に付せられ、十一日に、通夜、十二日に、青山斎場で葬儀、落合火葬場で荼毘に付された。
葬儀委員長は「中村是公」(漱石と「一高」同期、大蔵官僚、満鉄総裁、東京市長を歴任)、弔辞は「村山龍平」(朝日新聞社社長・社主、貴族院議員を歴任)、友人総代は「狩野亨吉」(漱石と東京帝国時代に親炙、第五高校と共に教鞭、後に、一高校長、京都大学初代文科大学長を歴任)、導師は「釈宗演」(円覚寺派管長)、門下生有志総代は「小宮豊隆」、当日の進行・司会は「松根東洋城」が務めた。
門下生有志総代は、「寺田寅彦」が務めるべきであったが、漱石と同じ病の胃潰瘍で、絶対安静の病臥中で、「小宮豊隆」が門下生有志総代を務めることになった。豊隆は、その弔辞を寅彦に認めていただくことを寅彦に依頼したが、それも叶わなかった。
寅彦が、最期の漱石の病気見舞い行ったのは、十二月二日で、寅彦の、その時のことが、日記に記されている。
「午後、夏目先生を見舞いに行く。重態なり。午後四時半、再度の出血ありたるごとく容態悪くなり、真鍋、宮本、南三博士と井上、安倍両学士詰め切る。夜十一時、安静となりたれば一旦辞し帰る。」
続く、十二月三日に、
「胃潰瘍の疑いあれば安静を要する由なり。午後、夏目へ見舞に行く。経過良好なり。」
寅彦も、「いよいよ胃の出血らしいので絶対安静を要する」との状態で、寅彦の再婚の夫人「寛子」も、この時に、「慢性結核リンパ腺炎・頸部リンパ腺炎」との診断がなされている。
十二月九日の漱石の亡くなる前に、寛子夫人が寅彦にかわり夏目家に見舞いに行き、その翌日の弔問、そして、十二日の葬儀にも、寛子夫人が列席した。(『寺田寅彦 妻たちの歳月(山田一郎著)』)
これらの夏目漱石の一連の最期・通夜・葬儀関連の段取りは、「漱石門下生(木曜会・九日会)」のメンバーの中で、好むと好まざるとにかかわらず、結果的に、「漱石門下生」の最古参の、「夏目家」との信頼抜群の、そして、宮内省「式部官(「北白川家御用掛」兼職)」の「松根東洋城」が担うことになった。
.jpg)
「兄東洋城と私(松根新八郎稿)」所収の「松根東洋城」(「式部職の大礼服」着衣)(「国立国会図書館デジタルコレクション」所収)
https://dl.ndl.go.jp/pid/6071686/1/42
[ 葬式の当日、東洋城は金筋の入った宮内省の礼服姿でシルクハットを小脇に抱え、祭壇より一段低い土間の上に参列者の方を向いて立ち、それなりに威厳に満ちた姿であったのだが、弟子たちにはいかにも場内を見下すかのように傲然として見え、「あの俗臭芬々とした姿は、漱石先生の葬儀にはまったくふさわしからぬものに見えたね」と散々な評価であった。また、東洋城は、告別が終わった人の群れを、右手を平らにして、それで臼でも挽く時のように動かしていたのだが、それが弟子たちにはなんとも妙な手つきに見え、芥川龍之介が「あれは、礼をしたら順々に棺の後ろを回って、出ていってくれという合図だろう」と言った。すると、やきもち焼きでうるさい鈴木三重吉は、「松根のやつが、頼まれもしないのに余計なところへ出しゃべって」と、まずそれからしてはなはだ面白くないところへ、例の「臼でも挽く」ような手つきがますます気に入らないと言い、その後、酒に酔うと必ず、「なんだあいつ、こんな手つきをしやがって、どうぞこちらへ、どうぞこちらへと言っていやがる」と毎度同じ手真似を繰り返し、並居る人を笑わせた。
三重吉はほかにも、「自分たちは斎場へ電車で行ったのに、小宮だけは遺族と一緒に馬車で行った」と、その厚かましさに憤慨したが、それは小宮豊隆が勝手に遺族の馬車へ乗り込んだわけではなく、夫人の鏡子が小さい子どもたちの付き添いをしてくれとわざわざ頼んだためだった。三重吉は、漱石の死と数日来の疲労から日頃に増していらいらし、怒りぽっくなっていた。(中略)
「九日会」は毎回幹事が変わり、安倍能成や鈴木三重吉などがその役を果たして、弟子同士で旧交を温めていたのだが、東洋城はその会に一度も出なかった。理由は、漱石が危篤に陥った頃からの東洋城の独断と他の弟子たちとの軋轢だと思われたが、それだけというわけではなかった。東洋城は、俳誌「渋柿」の編集に追われ、特に漱石追悼の特集が続いて多忙だったのである。
また、東洋城は弟子たちのすべてと交際を絶っていたわけではなく、そのうちの何人かとは個別に会っており、特に仲の良い寺田寅彦や小宮豊隆らの数人とはかなり頻繁に会っていた。」(『渋柿の木の下で(中村英利子著)』)
(追記二)当時の「寺田寅彦」周辺
https://www.jstage.jst.go.jp/article/ningendock1986/7/2/7_7/_pdf
[ 夏子さん はその年(明治三十五年=1902) の11月15日 に亡 くな りま した。
寅彦は不幸な運命を背負うわけですが、日露戦争の終わった年ですから明治38年、28歳の時、再婚をします。種崎の隣の仁井田という所 の出身で、山内家の家扶をしていた漢詩人の浜口真徴の三女寛子さんを迎えます。菊池寛の寛と書 いてユタコと読むんですが、この人との間に男2人と女2人の子宝に恵まれましたが、夏目漱石が亡くなった大正5年の翌年、6月の10日に一 夜のうちに肺を侵され寛子さんは亡 くなります。 恩師漱石の葬儀にも寅彦自身も胃潰瘍 になって参列できなか ったのです。そういうふうにいろいろ不幸せに見舞われますが、明るい話題もあります。31歳で理学博士になり、翌年5月、欧米へ留学します。そして大正6年の7月、「ラウエ映画 の実験方法 とその説明に関する研究」で学士院恩賜賞をもらいます。
40歳の若さでした。そして寛子夫人が亡 くな ったのは3カ 月後の10月 のことでした。西川正治という後 に文化勲章をもらった大変偉 い物理学者がいますが、この先生が書いて るのを読みますと、ラウエ ・スポ ッ トの研究 は大 変画期的な発 見であ って、もし寺田先生が 日本でな くてイギ リスなりフラ ンスなりで生まれていたらばノーベ ル賞を寺田先生がもらったに違いないというんですね。この研究に寅彦はレントゲンを使 ったのですが、 それは大学の医学部で廃品 にな った レン トゲ ンをもらって来て改造 したもので した。
寛子夫人を亡 くし、4人 の子ど も抱えて苦 しむ心境 は寅彦 の「蓄音機 」と いう随筆に書いてあります。 こど もた ちを慰 め るため に蓄音機 を買う。童謡 をかけてやる。下 の女の子 は3歳 上 の女の子が5歳 です。]
(追記三) 当時の「小宮豊隆」周辺

「漱石忌(12/9)と九日会」(「漱石の肉筆を後世へ!漱石文庫デジタルアーカイブプロジェクト」東北大学附属図書館)
https://readyfor.jp/projects/soseki-library/announcements/118615
[写真は大正6年(1917)1月9日の第一回の九日会です(神奈川近代文学館蔵)。
左から安倍能成、野上豊一郎、鏡子夫人、内田百閒、津田青楓、久米正雄、赤木桁平、芥川龍之介、森田草平、和辻哲郎。右から滝田樗蔭、速水滉、阿部次郎、岩波茂雄、小宮豊隆という顔ぶれです。奥の部屋が漱石山房の書斎部分で、手前が客間部分でした。]
上記の写真は、漱石没後(大正5年12月9日)の、その翌年の「大正6年(1917)1月9日第一回の九日会」の写真である。この写真に出てくるメンバーは「左から安倍能成、野上豊一郎、鏡子夫人、内田百閒、津田青楓、久米正雄、赤木桁平、芥川龍之介、森田草平、和辻哲郎。右から滝田樗蔭、速水滉、阿部次郎、岩波茂雄、小宮豊隆」という顔ぶれである。
この時に、『漱石全集』の刊行の発議をしたのは、小宮豊隆のようである(『漱石山脈(長尾剛著)』)。この写真の「小宮豊隆・岩波茂雄・阿部次郎」が、火鉢に手をかざしているが、この三人は『岩波全集』の刊行の中心的な人物で、あたかも「漱石没後の最初の『岩波全集』刊行について何やら会話している」ような風情である。
「漱石が亡くなってすぐ、豊隆は『漱石山脈』の面々に向かって『漱石全集』の刊行を発議し、自らが『漱石伝』を執筆すると宣言した。漱石の危篤状態の時からずっと考えていたことだったに違いない。
この頃すでに岩波茂雄が古書店として立ち上げた岩波書店は出版社として確立していた。そこで、漱石作品を長く刊行していた春陽堂と大倉書店に岩波書店が加わって、三社で全集を刊行することになり、編集作業は岩波書店のプロジェクトとなった。
豊隆の『漱石全集』編集に対する執念は、すさまじいものだった。膨大な資料を搔き集め続け、全集を刊行し直すたびに少しずつ改訂増補を加えていった。
昭和十年、漱石没後二十年を記念として岩波書店から刊行された決定版『漱石全集』では、なんと全巻の解説文まで引き受けた。
それぞれの巻の解説を別々の弟子が受け持ってもよさそうなものである。が、安倍能成が「小宮にすべてを託したい」と提案し、豊隆が大乗り気で引き受けたのだ。豊隆には「漱石について語る第一人者は俺なのだ」といった自負があったし、周りもそれを認めていたらしい。取りも直さず「漱石と豊隆の深い親密さ」を、誰もが認めていたということだろう。」(『漱石山脈(長尾剛著)』)。
岩波茂雄については、『漱石山脈(長尾剛著)』では、「岩波茂雄『漱石全集』を作った男」(「曰く付きの岩波書店の看板/漱石から借金しまくった岩波茂雄/『こゝろ』は漱石の自費出版」)と、岩波茂雄の一端を披露しているが、[『思想』(1921年)『科学』(1931年)『文化』(1934年)などの雑誌や、1927年(昭和2年)には「岩波文庫」を創刊。日中戦争について「日本はしなくてもいい戦争をしている」と日本軍に対して批判的な立場から活動を展開していた。これによって軍部の圧力をかけられるようになる。](「ウィキペディア」)と、「1945年3月に貴族院多額納税者議員に互選、同年4月4日に任命されるが、それから6ヶ月後に脳出血で倒れる。翌年には雑誌『世界』が創刊され、文化勲章も受ける」(「ウィキペディア」)と、茂雄自身が、「漱石山脈」に連なる一人として、「高浜虚子」(漱石の木曜会に連なる「ホトトギス」派の総帥且つ「日本俳壇大御所」)の、「1954年(昭和29年)、文化勲章受章」と、「漱石山脈」の中での一巨峰というへき位置を占めるべき一人なのであろう。
阿部次郎については、次の「ウィキペディア」の紹介記事のとおり、「岩波茂雄と『一高』同期で、そして、後に、『東北帝国大学教授・小宮豊隆』を招聘する」、まさに、上記の「大正6年(1917)1月9日第一回の九日会」の写真の「小宮豊隆・岩波茂雄・阿部次郎」の、この三人が、同じ火鉢で手をかざしている画像は、誠に、漱石没後の『漱石全集』の誕生の、その切っ掛けを暗示しているような象徴的な一スナップとして評価されるぺきものであろう。
「1901年(明治34年)、第一高等学校入学。同級生に鳩山秀夫、岩波茂雄、荻原井泉水、一級下に斎藤茂吉がいた。1907年(明治40年)、東京帝国大学に入学し、ラファエル・フォン・ケーベル博士を師と仰ぐ。卒業論文「スピノーザの本体論」で哲学科を卒業。夏目漱石の門に出入りして、森田草平、小宮豊隆、安倍能成とともに「朝日文芸欄」の主要な執筆者となり、「自ら知らざる自然主義者」(明治43年)等の評論で、漱石門下の論客として注目された[3]。1911年(明治44年)、森田・小宮・安倍との合著による評論集『影と聲』を上梓する。
1914年(大正3年)に発表した『三太郎の日記』は大正昭和期の青春のバイブルとして有名で、学生必読の書であった[4](大正教養主義を主導)。1917年(大正6年)に一高の同級生であった岩波茂雄が雑誌『思潮』(現在の『思想』)を創刊。その主幹となる。
慶應義塾、日本女子大学校の講師を経て1922年(大正11年)、文部省在外研究員としてのヨーロッパ留学。
同年に『人格主義』を発表。真・善・美を豊かに自由に追究する人、自己の尊厳を自覚する自由の人、そうした人格の結合による社会こそ真の理想的社会であると説く(人格主義を主張)。
同年刊行された『地獄の征服』はゲーテ・ニーチェ・ダンテに関する論文をまとめたもので、従来の研究水準を大きく超えており、ダンテの愛読者だった正宗白鳥も「私はこれによってはじめて、ダンテに対する日本人の独創の見解に接した(中略)翻訳して欧米のダンテ学者に示すに足るもの」と称賛している。」(「ウィキペディア」)

「漱石山房の門下生(前列左から「松根東洋城・三重吉・森田草平・小宮豊隆」)
https://yahan.blog.ss-blog.jp/2023-10-05
この前列の「東洋城・三重吉・草平・豊隆」の、この背後の人物は、「阿部次郎」と解したい。

[阿部 次郎(あべ じろう、1883年〈明治16年〉8月27日 - 1959年〈昭和34年〉10月20日)は、日本の哲学者・美学者・作家。東北帝国大学法文学部教授、同学部長、帝国学士院会員。仙台市名誉市民。『三太郎の日記』著者。](「ウィキペディア」)
「漱石・寅彦・東洋城」(子規没後~漱石没まで)俳句管見(その十四) [漱石・東洋城・寅彦]
その十四「大正五(一九一六)」
[漱石・十二月九日、漱石没(五十歳)。5月~12月、「明暗」。]
2452 春風や故人に贈る九花蘭(「九花蘭」は五月頃に芳香のある黄緑色の花を開く。)
2453 白梅にしぶきかゝるや水車(2483までの三十一句は「手帳に記された句」。)
2454 孟宗の根を行く春の筧(かけひ)哉(同上)
2455 梅早く咲いて温泉(ゆ)の出る小村哉(同上)
2456 いち早き梅を見付けぬ竹の間(同上)
2457 梅咲くや日の旗立つる草の戸に(同上)
2458 裏山に蜜柑みのるや長者振(同上)
2459 温泉に信濃の客や春を待つ(同上)
2460 橙も黄色になりぬ温泉(ゆ)の流(同上)
2461 鶯に聞き入る茶屋の床几哉(同上)
2462 鶯や草鞋(わらじ)を易(か)ふる峠茶屋(同上)
2463 鶯や竹の根方に鍬の尻(同上)
2464 鶯や藪くゞり行く蓑一つ(同上)
2465 鶯を聴いてゐるなり縫箔屋(ぬいはくや)(同上。「縫箔屋」=衣服模様を業とする)
2466 鶯に餌をやる寮の妾かな(同上)
2467 温泉の里橙山の麓かな(同上)
2468 桃の花家に唐画を蔵しけり(同上)
2469 桃咲くやいまだに流行(はや)る漢方医(同上)
2470 輿(こし)に乗るは帰化の僧らし桃の花(同上)
2471 町儒者の玄関構や桃の花(同上)
2472 かりにする寺小屋なれど梅の花(同上)
2473 文も候(そろ)稚子(ちご)に持たせて桃の花(同上)
2474 琵琶法師召されて春の夜なりけり(同上)
2475 春雨や身をすり寄せて一つ傘(同上)
2476 鶯を飼ひて床屋の主人哉(同上)
2477 耳の穴掘つてもらひぬ春の風(同上)
2478 嫁の里向ふに見えて春の川(同上)
2479 岡持の傘にあまりて春の雨(同上)
2480 一燈の青幾更ぞ瓶の梅(同上)
2481 病める人枕に倚れば瓶の梅(同上)
2482 梅活けて聊(いささ)かなれど手習す(同上)
2483 桃に琴弾くは心越禅師哉(同上)
2484 秋立つや一巻の書の読み残し(「芥川龍之介宛書簡」九月二日)
2485 蝸牛や五月をわたるふきの茎(「画賛九月八日」)
2486 朝貌にまつはられてよ芒の穂(同上)
2487 萩と歯朶に賛書く月の団居哉(「夏目漱石遺墨集・第三巻」の画賛の句)
2488 棕櫚竹や月に背いて影二本(「自画賛九月八日」)
2489 秋立つ日猫の蚤取眼かな(「画賛九月」)
2490 秋となれば竹もかくなり俳諧師(同上)
2491 風呂吹きや頭の丸き影二つ(前書「禅僧二人宿して」、「十月」)
2492 煮て食ふかはた焼いてくふか春の魚(「画賛十月」)
2493 いたづらに書きたるものを梅とこそ(「自画賛十一月」)
2494 まきを割るかはた祖を割るか秋の空(「鬼村元成宛書簡」、「十一月十日」)
2495 饅頭に礼拝すれば晴れて秋(「富沢敬道宛書簡」、「十一月十五日」)
2496 饅頭は食つたと雁に言伝よ(同上)
2497 吾心点じ了りぬ正に秋(同上。前書「徳山の故事を思ひだして 一句」)
2498 僧のくれし此饅頭の丸きかな(同上。「無季」の句)
2499 瓢箪は鳴るか鳴らぬか秋の風(同上。前書「瓢箪はどうしました」)
(東洋城・三十九歳。虚子は大正二年、俳句に復活したが、四月、東洋城に無断で「国民俳壇」を手に入れた。爾後、虚子及び「ホトトギス」と絶縁し、「渋柿」によつて芭蕉を宗とし俳諧を道として立った。)
※怒る事知つてあれども水温む(前書「有感(大正五年四月十七日国民俳壇選者更迭発表の日)」)
[※「大正五年、虚子が俳句に復活し、四月十七日、東洋城はついに国民俳壇の選者を下りた。それというのも、国民新聞の社長・徳富蘇峰が、選者を下りてほしい旨、手紙を送ってきたためであった。東洋城はかねてより、社長からなにか言ってくるまで辞めないつもりだったが、読むと、かなり困って書いてきたものだとわかった。「仕方がない、社長は大将だ。ここまで書いてくるのは、よほどのことなのであろう」と、ついに下りることを承諾した。そして、
有感(感有リ)
いかること知つてあれども水温(ぬる)む
という句をつくり、以後虚子とは義絶した。九月には母の上京を促すため、帰郷した。末弟の宗一(そういち)が東京高商に入学するため上京し、以後、宇和島で独り住まいになっていた母の面倒を見るのは長男(※嫡男)の務めだと思い、同居の説得に行ったのだった。この年、東洋城にとって肉親の死にも等しい哀しいできごとがあった。十二月九日、漱石が死亡したのである。」(『渋柿の木の下で(中村英利子著)』) ]
用ふべき薬も絶えし火桶かな(前書「黒き枠の中より(「漱石先生の死))六句」)
木枯に深山木折るゝ音を聞け(同上)
埋火は灰の深きに消えにけり(同上)
祖父も父も繕ひし土塀冬日さす(同上)
ともし火に枯荷の月を観じけり(同上)
元日や人の心の一大事(同上)
[「東洋城はかって、父が亡くなるときにもこうして末期の水を捧げたが、師の漱石にも同じことをしていると思いながら、あと筆を進めず漱石の顔を見た。この時の東洋城の心には、師とか文豪などというものはなく、父を失ったときと同じ悲しみがあった。「先生、先生」、呼んだ後、漱石はふ―っと息を吐いたが、その後はもう続かない。真鍋が夫人に「お目を」と言い、夫人は手で静かに漱石の目をつむらせたが、初めから開いていないのをそうしたのは、永遠に安らかに瞑目させようとしたものだった。阿部学士検脈。真鍋学士検脈。退いて「すでに」と言う。部屋の中は、しのび泣きや声を上げて泣く声で満ちた。時に午後六時五十分。曇った日はすでに暮れ、闇の中に寒風がさみしく吹いた。
( 東洋城はこのあと、一連の葬儀に関して仕切り役ともいうべき重要な働きをした。しかし、それにもかかわらず、弟子たちのあいだに軋轢が生じた。」(『渋柿の木の下で(中村英利子著)』) ]

「夏目漱石の娘 愛子さん(「父漱石の霊に捧ぐ」より)」
http://enmi19.seesaa.net/article/463137651.html
(寅彦・三十九歳。十一月、東京帝国大学理科大学教授となる。十二月、胃潰瘍のため医者より絶対安静を命じられる。十二月九日、夏目漱石死亡。) →[『寺田寅彦全集/文学篇/七巻』には収載句は無い。]
(参考一) [葬儀記 芥川龍之介]
https://www.aozora.gr.jp/cards/000879/files/150_15210.html
[ 離れで電話をかけて、皺(しわ)くちゃになったフロックの袖(そで)を気にしながら、玄関へ来ると、誰(だれ)もいない。客間をのぞいたら、奥さんが誰だか黒の紋付(もんつき)を着た人と話していた。が、そこと書斎との堺(さかい)には、さっきまで柩(ひつぎ)の後ろに立ててあった、白い屏風(びょうぶ)が立っている。どうしたのかと思って、書斎の方へ行くと、入口の所に和辻(わつじ)さんや何かが二、三人かたまっていた。中にももちろん大ぜいいる。ちょうど皆が、先生の死顔(しにがお)に、最後の別れを惜んでいる時だったのである。
僕は、岡田(おかだ)君のあとについて、自分の番が来るのを待っていた。もう明るくなったガラス戸の外には、霜よけの藁(わら)を着た芭蕉(ばしょう)が、何本も軒近くならんでいる。書斎でお通夜(つや)をしていると、いつもこの芭蕉がいちばん早く、うす暗い中からうき上がってきた。――そんなことをぼんやり考えているうちに、やがて人が減って書斎の中へはいれた。
書斎の中には、電灯がついていたのか、それともろうそくがついていたのか、それは覚えていない。が、なんでも、外光だけではなかったようである。僕は、妙に改まった心もちで、中へはいった。そうして、岡田君が礼をしたあとで、柩の前へ行った。
柩のそばには、松根(まつねさん)が立っている。そうして右の手を平(たいら)にして、それを臼(うす)でも挽(ひく)時のように動かしている。礼をしたら、順々に柩の後ろをまわって、出て行ってくれという合図(あいず)だろう。
柩は寝棺(ねかん)である。のせてある台は三尺ばかりしかない。そばに立つと、眼と鼻の間に、中が見下された。中には、細くきざんだ紙に南無阿弥陀仏(なむあみだぶつ)と書いたのが、雪のようにふりまいてある。先生の顔は、半ば頬(ほお)をその紙の中にうずめながら、静かに眼をつぶっていた。ちょうど蝋(ろう)ででもつくった、面型(めんがた)のような感じである。輪廓(りんかく)は、生前と少しもちがわない。が、どこかようすがちがう。脣(くちびる)の色が黒(くろ)ずんでいたり、顔色が変わっていたりする以外に、どこかちがっているところがある。僕はその前で、ほとんど無感動に礼をした。「これは先生じゃない」そんな気が、強くした。(これは始めから、そうであった。現に今でも僕は誇張なしに先生が生きているような気がしてしかたがない)僕は、柩の前に一、二分立っていた。それから、松根さんの合図通り、あとの人に代わって、書斎の外へ出た。
ところが、外へ出ると、急にまた先生の顔が見たくなった。なんだかよく見て来るのを忘れたような心もちがする。そうして、それが取り返しのつかない、ばかな事だったような心もちがする。僕はよっぽど、もう一度行こうかと思った。が、なんだかそれが恥しかった。それに感情を誇張しているような気も、少しはした。「もうしかたがない」――そう、思ってとうとうやめにした。そうしたら、いやに悲しくなった。
外へ出ると、松岡が「よく見て来たか」と言う。僕は、「うん」と答えながら、うそをついたような気がして、不快だった。
青山の斎場(さいじょう)へ行ったら、靄(もや)がまったく晴れて、葉のない桜のこずえにもう朝日がさしていた。下から見ると、その桜の枝が、ちょうど鉄網のように細(こま)かく空をかがっている。僕たちはその下に敷いた新しいむしろの上を歩きながら、みんな、体をそらせて、「やっと眼がさめたような気がする」と言った。
斎場は、小学校の教室とお寺の本堂とを、一つにしたような建築である。丸い柱や、両方のガラス窓が、はなはだみすぼらしい。正面には一段高い所があって、その上に朱塗(しゅぬり)の曲禄(きょくろく)が三つすえてある。それが、その下に、一面に並べてある安直な椅子(いす)と、妙な対照をつくっていた。「この曲禄を、書斎の椅子(いす)にしたら、おもしろいぜ」――僕は久米(くめ)にこんなことを言った。久米は、曲禄の足をなでながら、うんとかなんとかいいかげんな返事をしていた。
斎場を出て、入口の休所やすみどころへかえって来ると、もう森田さん、鈴木さん、安倍さん、などが、かんかん火を起した炉(ろ)のまわりに集って、新聞を読んだり、駄弁(だべん)をふるったりしていた。新聞に出ている先生の逸話(いつわ)や、内外の人の追憶が時々問題になる。僕は、和辻さんにもらった「朝日」を吸いながら、炉のふちへ足をかけて、ぬれたくつから煙が出るのをぼんやり、遠い所のものを見るようにながめていた。なんだか、みんなの心もちに、どこか穴のあいている所でもあるような気がして、しかたがない。
そのうちに、葬儀の始まる時間が近くなってきた。「そろそろ受付へ行こうじゃないか」――気の早い赤木君が、新聞をほうり出しながら、「行(い)」の所へ独特のアクセントをつけて言う。そこでみんな、ぞろぞろ、休所を出て、入口の両側にある受付へ分れ分れに、行くことになった。松浦君、江口君、岡君が、こっちの受付をやってくれる。向こうは、和辻さん、赤木君、久米という顔ぶれである。そのほか、朝日新聞社の人が、一人ずつ両方へ手伝いに来てくれた。
やがて、霊柩車(れいきゅうしゃ)が来る。続いて、一般の会葬者が、ぽつぽつ来はじめた。休所の方を見ると、人影がだいぶんふえて、その中に小宮(こみや)さんや野上(のがみ)さんの顔が見える。中幅(ちゅうはば)の白木綿(しろもめん)を薬屋のように、フロックの上からかけた人がいると思ったら、それは宮崎虎之助(みやざきとらのすけ)氏だった。
始めは、時刻が時刻だから、それに前日の新聞に葬儀の時間がまちがって出たから、会葬者は存外少かろうと思ったが、実際はそれと全く反対だった。ぐずぐずしていると、会葬者の宿所を、帳面につけるのもまにあわない。僕はいろんな人の名刺をうけとるのに忙殺された。
すると、どこかで「死は厳粛である」と言う声がした。僕は驚いた。この場合、こんな芝居じみたことを言う人が、僕たちの中にいるわけはない。そこで、休所(やすみどころ)の方をのぞくと、宮崎虎之助氏が、椅子(いす)の上へのって、伝道演説をやっていた。僕はちょいと不快になった。が、あまり宮崎虎之助らしいので、それ以上には腹もたたなかった。接待係の人が止(とめ)たが、やめないらしい。やっぱり右手で盛なジェステュアをしながら、死は厳粛であるとかなんとか言っている。
が、それもほどなくやめになった。会葬者は皆、接待係の案内で、斎場の中へはいって行く。葬儀の始まる時刻がきたのであろう。もう受付へ来る人も、あまりない。そこで、帳面や香奠(こうでん)をしまつしていると、向こうの受付にいた連中が、そろってぞろぞろ出て来た。そうして、その先に立って、赤木君が、しきりに何か憤慨している。聞いてみると、誰かが、受付係は葬儀のすむまで、受付に残っていなければならんと言ったのだそうである。至極もっともな憤慨だから、僕もさっそくこれに雷同した。そうして皆で、受付を閉じて、斎場へはいった。
正面の高い所にあった曲ろくは、いつの間にか一つになって、それへ向こうをむいた宗演(そうえん)老師が腰をかけている。その両側にはいろいろな楽器を持った坊さんが、一列にずっと並んでいる。奥の方には、柩があるのであろう。夏目金之助之柩(なつめきんのすけのひつぎ)と書いた幡(はた)が、下のほうだけ見えている。うす暗いのと香の煙とで、そのほかは何があるのだかはっきりしない。ただ花輪の菊が、その中でうずたかく、白いものを重ねている。――式はもう誦経(ずきょう)がはじまっていた。
僕は、式に臨んでも、悲しくなる気づかいはないと思っていた。そういう心もちになるには、あまり形式が勝っていて、万事がおおぎょうにできすぎている。――そう思って、平気で、宗演老師の秉炬法語(へいきょほうご)を聞いていた。だから、松浦君の泣き声を聞いた時も、始めは誰かが笑っているのではないかと疑ったくらいである。
ところが、式がだんだん進んで、小宮さんが伸六(しんろく)さんといっしょに、弔辞(ちょうじ)を持って、柩の前へ行くのを見たら、急に瞼(まぶた)の裏が熱くなってきた。僕の左には、後藤末雄(ごとうすえお)君が立っている。僕の右には、高等学校の村田先生がすわっている。僕は、なんだか泣くのが外聞の悪いような気がした。けれども、涙はだんだん流れそうになってくる。僕の後ろに久米(くめ)がいるのを、僕は前から知っていた。だからその方を見たら、どうかなるかもしれない。――こんなあいまいな、救助を請うような心もちで、僕は後ろをふりむいた。すると、久米の眼が見えた。が、その眼にも、涙がいっぱいにたまっていた。僕はとうとうやりきれなくなって、泣いてしまった。隣にいた後藤君が、けげんな顔をして、僕の方を見たのは、いまだによく覚えている。
それから、何がどうしたか、それは少しも判然しない。ただ久米が僕の肘(ひじ)をつかまえて、「おい、あっちへ行こう」とかなんとか言ったことだけは、記憶している。そのあとで、涙をふいて、眼をあいたら、僕の前に掃きだめがあった。なんでも、斎場とどこかの家との間らしい。掃きだめには、卵のからが三つ四つすててあった。
少したって、久米と斎場へ行ってみると、もう会葬者がおおかた出て行ったあとで、広い建物の中はどこを見ても、がらんとしている。そうして、その中で、ほこりのにおいと香のにおいとが、むせっぽくいっしょになっている。僕たちは、安倍さんのあとで、お焼香(しょうこう)をした。すると、また、涙が出た。
外へ出ると、ふてくされた日が一面に霜(しも)どけの土を照らしている。その日の中を向こうへ突つっきって、休所へはいったら、誰かが蕎麦饅頭(そばまんじゅう)を食えと言ってくれた。僕は、腹がへっていたから、すぐに一つとって口へ入れた。そこへ大学の松浦先生が来て、骨上(こつあげ)のことか何か僕に話しかけられたように思う。僕は、天とうも蕎麦饅頭もしゃくにさわっていた時だから、はなはだ無礼な答をしたのに相違ない。先生は手がつけられないという顔をして、帰られたようだった。あの時のことを今思うと、少からず恐縮する。
涙のかわいたのちには、なんだか張合(はりあい)ない疲労ばかりが残った。会葬者の名刺を束にする。弔電や宿所書きを一つにする。それから、葬儀式場の外の往来で、柩車の火葬場へ行くのを見送った。
その後は、ただ、頭がぼんやりして、眠いということよりほかに、何も考えられなかった。
(大正五年十二月) ]
(参考二) 「木曜会・漱石没後=「九日会」メンバー」(周辺)
https://soseki-museum.jp/soseki-natsume/surround-soseki/
[ (「漱石・東洋城」親近者)
1 松根東洋城(まつねとうようじょう)=明治11(1878)~昭和39(1964)年。俳人。愛媛県尋常中学校で漱石に学ぶ。上京後、漱石の紹介で正岡子規と出会い、句作を始め、雑誌「渋柿」を創刊した。(「漱石門」の年長組、「木曜会」のメンバー、「漱石十大弟子の一人」。)
2 寺田寅彦(てらだとらひこ)=明治11(1878)~昭和10(1935)年。物理学者、随筆家。第五高等学校で漱石に学んだ。物理学の研究の一方で吉村冬彦の名前で多くの随筆を書いた。(「漱石門」の年長組、「木曜会」のメンバー、「漱石十大弟子の一人」。)
3 小宮豊隆(こみやとよたか)=明治17(1884)~昭和41(1966)年。独文学者、評論家。漱石の全集編集の中心的役割を担った。また、『夏目漱石』などの評伝を書いた。阿部次郎に招かれて東北帝国大学(東北大学)で定年まで勤め、その後は学習院大学で教えた。(「漱石門」の最側近、「木曜会・九日会」のメンバー、「漱石門」の四天王の一人、「漱石十大弟子の一人」。東洋城没後の「東洋城全句集」編者の一人。)
4 安倍能成(あべよししげ)=明治16(1883)~昭和41(1966)年。哲学者、評論家、教育者。第一高等学校で漱石に学んだ。母校の校長を務め、戦後は文部大臣、学習院大学の院長を務めた。(「漱石門」の出世頭(戦後の昭和二十一年に文部大臣)、「漱石門」の四天王の一人、「漱石十大弟子の一人」。「木曜会・九日会」のメンバー、東洋城没後の「東洋城全句集」編者の一人。)
(「漱石」親近の友人・門人)
5 高浜虚子(たかはまきょし)=明治7(1874)~昭和34(1959)年。俳人、小説家。漱石の友人正岡子規に俳句を教わった。漱石に小説執筆を薦め、「吾輩は猫である」を書かせた。
(「木曜会」のメンバーであるが、常連メンバーではない。)
6 岩波茂雄(いわなみしげお)=明治14(1881)~昭和21(1946)年。岩波書店創業者。岩波書店を開業し、『こころ』を初めとする漱石の作品を多く出版した。(「木曜会」のメンバーであるが、常連メンバーではない。)
7 阿部次郎(あべじろう)=明治16(1883)~昭和34(1959)年。哲学者、評論家。自伝的小説「三太郎の日記」は大正期のベストセラーになった。その後は人格主義という思想を提唱した。大正12(1923)年からは長く東北帝国大学(東北大学)の教員を務めた。(「漱石十大弟子の一人)」。)
8 和辻哲郎(わつじてつろう)=明治22(1889)~昭和35(1960)年。哲学者、文化史家、倫理学者。漱石に教わったことはなかったが、漱石を敬愛して付きあうようになった。『古寺巡礼』など文化史方面の著作も多い。昭和9(1934)年からは東京大学教授として定年まで勤めた。(「木曜会」のメンバーというよりも「九日会」のメンバー。)
9 津田青楓(つだせいふう)=明治13(1880)~昭和53(1978)年。画家。『道草』や『明暗』など漱石の本の装丁を手がけた。また、漱石に絵画の手ほどきをした。(「漱石十大弟子の一人」、実兄は「去風流七代・西川一草亭」、漱石側近の画家、後に「左翼」に転向。)
10 野村伝四(のむらでんし)=明治13(1880)~昭和23(1948)年。教育者。漱石の教え子で学校教諭などを務めた後、奈良県立図書館の館長になった。一方で郷里鹿児島の方言研究にも努めた。(「野村伝四は漱石が最も愛した弟子だといわれている。彼は朴訥で接すると春風飴蕩のおもむきがあった。ちょうど、複雑なハムレットが、激情の奴隷でないホレイショを愛したように、複雑な漱石も朴訥な伝四を愛したのであろう。」=「ウィキペディア」)
11 林原耕三(はやしばらこうぞう)=明治20(1887)~昭和50(1975)年。英文学者、俳人。漱石の教え子で久米正雄、芥川龍之介を漱石に紹介した。東京帝国大学卒業後は法政大学や明治大学で教えつつ、句作にも熱心だった。(俳句は、「東洋城」の「渋柿」ではなく、「石楠」の「臼田亜浪」に師事。)
(「漱石」門の作家たち=「木曜会・九日会」のメンバー)
12 森田草平(もりたそうへい)=明治14(1881)~昭和24(1949)年。小説家。漱石に薦められて平塚らいてうとの恋愛を「煤煙」という作品として発表し、漱石が朝日新聞の紙面に作った「朝日文芸欄」では編集を担った。(「漱石門」の四天王の一人、「漱石十大弟子の一人」、漱石の「野分」のモデルとされている。)
13 鈴木三重吉(すずきみえきち)=明治15(1882)~昭和11(1936)年。小説家、童話作家。漱石に小説を評価されるが、漱石没後は童話作家として活躍し、雑誌「赤い鳥」を編集した。(「漱石門」の四天王の一人、「漱石十大弟子の一人」、東洋城と三重吉は当初は昵懇の関係であったが、後に、東洋城との関係は疎遠となる。)
14 野上豊一郎(のがみとよいちろう)=明治16(1883)~昭和25(1950)年。能楽研究者、英文学者。第一高等学校で漱石に学んだ。英文学では特に演劇研究をよくし、後には能楽研究で名を成し、教員を務めた法政大学にはその名を冠した能楽研究所が置かれている。妻は小説家の野上弥生子。(「漱石十大弟子の一人」。)
15 中勘助(なかかんすけ)=明治18(1885)~昭和40(1965)年。小説家、詩人、随筆家。第一高等学校からの漱石の教え子で小説「銀の匙」が漱石に高く評価された。(詩人としても、三好達治は、中勘助の詩には人間の善意識を呼び覚ます力と涯底(そこい)のしれぬ哀感があると高く評価した。65年(昭和40)1月朝日賞受賞「日本大百科全書(ニッポニカ)」)
16 赤木桁平(あかぎこうへい)=明治24(1891)~昭和24(1949)年。評論家、政治家。友人の鈴木三重吉を介して漱石と出会い、漱石にとって初の伝記『夏目漱石』を書いた。(「漱石十大弟子の一人」。日米開戦の積極論者で、漱石門の最右翼の人物。)
17 内田百閒(うちだひゃっけん)=明治22(1889)~昭和46(1971)年。小説家、随筆家。漱石全集の校正を担った。作家としての代表作に「冥途」や「贋作吾輩は猫である」など。(「夏目漱石」と「芥川龍之介」との接点の中心的人物で、「俳句」の造詣も深い。)
18 江口渙(えぐちかん)=明治20(1887)~昭和50(1975)年。小説家、評論家。芥川龍之介の作品をいち早く評価した。その後は社会主義運動に関わるようになっていった。(「夏目漱石と芥川龍之介」との接点にあって、漱石門の、戦中・戦後の最左翼の文学を担った人物。)
(「漱石」門の作家たち=主として「木曜会(ニューフェイス達=第4次『新思潮』派の作家たち」など」)のメンバー)
19 菊池寛(きくちかん)=明治21(1888)~昭和23(1948)年。文藝春秋社創設者、小説家。小説や戯曲を書くかたわら、文藝春秋社を開業し、幅広い事業を展開した。(第三・四次「新思潮」同人。「文芸春秋」を創刊、文芸春秋社を設立。芥川賞、直木賞を設定し、作家の育成、文芸の普及に努めた。作家として通俗小説に一生面を開く。著作「父帰る」「無名作家の日記」「恩讐の彼方に」「真珠夫人」。)(「精選版 日本国語大辞典」)
20 芥川龍之介(あくたがわりゅうのすけ)=明治25(1892)~昭和2(1927)年。小説家。「鼻」が漱石小説家。東京生まれ。別号澄江堂主人、我鬼。第三次、第四次の「新思潮」同人。「鼻」が夏目漱石に認められ、文壇出世作となる。歴史に材を取った理知的・技巧的作品で、抜群の才能を開花させた。致死量の睡眠薬を飲み自殺。著作「羅生門」「地獄変」「歯車」「或阿呆の一生」「西方の人」など。明治二五~昭和二年(一八九二‐一九二七)に高く評価され、大正期を代表する作家になった。主な作品に「地獄変」や「歯車」など(「精選版 日本国語大辞典」)
21 松岡譲(まつおかゆずる)=明治24(1891)~昭和44(1969)年。小説家。漱石の長女筆子と結婚した。漱石の妻鏡子の談話を編集して『漱石の思ひ出』を刊行した。
22 久米正雄(くめまさお)=明治24(1891)~昭和27(1952)年。小説家、劇作家。芥川と共に作家として評価された。漱石没後は戯曲や大衆向けの小説を多く書いた
23 成瀬 正一(なるせ せいいち、1892年4月26日 - 1936年4月13日)は、日本のフランス文学者。ロマン・ロランの翻訳・紹介を行った。大学卒業後まもなく創作から研究の道に転じ、九州帝国大学法文学部教授として仏蘭西浪漫主義思想を専門とした。43歳で病死したが、この時代の良き知識人として、後世の文学や美術研究に大いに寄与した。パリ留学中の1921年、松方幸次郎のアドバイザーとして松方コレクション(国立西洋美術館)の絵画彫刻の蒐集購入に協力した。(「ウィキペディア」) ]

「東京帝国大学を卒業する1916年(大正5年)頃の第4次『新思潮』のメンバー。成瀬正一は一番右、その左は芥川龍之介、次いで松岡譲、一番左が久米正雄。」
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%88%90%E7%80%AC%E6%AD%A3%E4%B8%80_%28%E3%83%95%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%82%B9%E6%96%87%E5%AD%A6%E8%80%85%29
(参考三) 「文豪、夏目漱石の葬儀」と「陸軍大将大山巌の国葬」
http://web.sanin.jp/p/sousen/1/3/1/14/11/
[ 文豪、夏目漱石の葬儀(大正5年12月)
夏目漱石の遺体は故人の希望により、12月10日午後1時40分より、医科大学病理解剖室で解剖された。作業は3時30分に終り、遺体は再び邸宅に帰った。翌11日は通夜が行なわれた。白絹の被いが掛けられた棺の上にはケーベル博士の花輪が飾られ、「文献院古道漱石居士」と書かれた位牌を棺前に安置された。葬儀の当日は、午前7時半より読経が始められた。8時半に、第1の馬車に僧侶、次に棺馬車、次に遺族、親族など6輛の馬車に分乘して出発。柩車は9時半に青山斎場に到着。芥川竜之介がフロックコートを着て受付をした。柩は直ちに祭壇に安置され、その上に「夏目金之助之柩」と大書きした銘旗を掲げられた。10時半に読経が始まり、朝日新聞社社長の弔辞朗読が行なわれた。遺体は葬儀後、落合火葬場にて荼毘に附された。
陸軍大将大山巌の国葬(大正5年12月)
12月10日に逝去した大山巌の国葬は、同17日日比谷公園で行なわれた。早朝より、日比谷公園正門から葬儀場の内外は、白い砂をまき掃き清められた。幔門から左右は黒白の幕を張り、正面の祭場は白木造りに白の幕を絞り、白の布で祭壇を設置。左右に立ち並ぶ幄舎は黒白段々の布で天井を覆い、同じ色で柱を包んだ。9時10分、行列が到着し、11時には国葬が終了した。再び霊柩は霊柩馬に移され、上野駅にと向かった。上野駅についた霊柩は、馬車に載せたまま、兵士20名によって担がれ、特別列車の待つ1番線へと向かう。プラットホームには鯨幕を張り、その中で鉄道職員、葬儀係員立会の下で馬車より柩を引き下ろして、特別列車内に運び入れた。列車の内部はことごとく白い幕で飾り、床だけは黒布を敷き詰めた。告別式のあと、霊柩列車は那須野へ向かった。]
[漱石・十二月九日、漱石没(五十歳)。5月~12月、「明暗」。]
2452 春風や故人に贈る九花蘭(「九花蘭」は五月頃に芳香のある黄緑色の花を開く。)
2453 白梅にしぶきかゝるや水車(2483までの三十一句は「手帳に記された句」。)
2454 孟宗の根を行く春の筧(かけひ)哉(同上)
2455 梅早く咲いて温泉(ゆ)の出る小村哉(同上)
2456 いち早き梅を見付けぬ竹の間(同上)
2457 梅咲くや日の旗立つる草の戸に(同上)
2458 裏山に蜜柑みのるや長者振(同上)
2459 温泉に信濃の客や春を待つ(同上)
2460 橙も黄色になりぬ温泉(ゆ)の流(同上)
2461 鶯に聞き入る茶屋の床几哉(同上)
2462 鶯や草鞋(わらじ)を易(か)ふる峠茶屋(同上)
2463 鶯や竹の根方に鍬の尻(同上)
2464 鶯や藪くゞり行く蓑一つ(同上)
2465 鶯を聴いてゐるなり縫箔屋(ぬいはくや)(同上。「縫箔屋」=衣服模様を業とする)
2466 鶯に餌をやる寮の妾かな(同上)
2467 温泉の里橙山の麓かな(同上)
2468 桃の花家に唐画を蔵しけり(同上)
2469 桃咲くやいまだに流行(はや)る漢方医(同上)
2470 輿(こし)に乗るは帰化の僧らし桃の花(同上)
2471 町儒者の玄関構や桃の花(同上)
2472 かりにする寺小屋なれど梅の花(同上)
2473 文も候(そろ)稚子(ちご)に持たせて桃の花(同上)
2474 琵琶法師召されて春の夜なりけり(同上)
2475 春雨や身をすり寄せて一つ傘(同上)
2476 鶯を飼ひて床屋の主人哉(同上)
2477 耳の穴掘つてもらひぬ春の風(同上)
2478 嫁の里向ふに見えて春の川(同上)
2479 岡持の傘にあまりて春の雨(同上)
2480 一燈の青幾更ぞ瓶の梅(同上)
2481 病める人枕に倚れば瓶の梅(同上)
2482 梅活けて聊(いささ)かなれど手習す(同上)
2483 桃に琴弾くは心越禅師哉(同上)
2484 秋立つや一巻の書の読み残し(「芥川龍之介宛書簡」九月二日)
2485 蝸牛や五月をわたるふきの茎(「画賛九月八日」)
2486 朝貌にまつはられてよ芒の穂(同上)
2487 萩と歯朶に賛書く月の団居哉(「夏目漱石遺墨集・第三巻」の画賛の句)
2488 棕櫚竹や月に背いて影二本(「自画賛九月八日」)
2489 秋立つ日猫の蚤取眼かな(「画賛九月」)
2490 秋となれば竹もかくなり俳諧師(同上)
2491 風呂吹きや頭の丸き影二つ(前書「禅僧二人宿して」、「十月」)
2492 煮て食ふかはた焼いてくふか春の魚(「画賛十月」)
2493 いたづらに書きたるものを梅とこそ(「自画賛十一月」)
2494 まきを割るかはた祖を割るか秋の空(「鬼村元成宛書簡」、「十一月十日」)
2495 饅頭に礼拝すれば晴れて秋(「富沢敬道宛書簡」、「十一月十五日」)
2496 饅頭は食つたと雁に言伝よ(同上)
2497 吾心点じ了りぬ正に秋(同上。前書「徳山の故事を思ひだして 一句」)
2498 僧のくれし此饅頭の丸きかな(同上。「無季」の句)
2499 瓢箪は鳴るか鳴らぬか秋の風(同上。前書「瓢箪はどうしました」)
(東洋城・三十九歳。虚子は大正二年、俳句に復活したが、四月、東洋城に無断で「国民俳壇」を手に入れた。爾後、虚子及び「ホトトギス」と絶縁し、「渋柿」によつて芭蕉を宗とし俳諧を道として立った。)
※怒る事知つてあれども水温む(前書「有感(大正五年四月十七日国民俳壇選者更迭発表の日)」)
[※「大正五年、虚子が俳句に復活し、四月十七日、東洋城はついに国民俳壇の選者を下りた。それというのも、国民新聞の社長・徳富蘇峰が、選者を下りてほしい旨、手紙を送ってきたためであった。東洋城はかねてより、社長からなにか言ってくるまで辞めないつもりだったが、読むと、かなり困って書いてきたものだとわかった。「仕方がない、社長は大将だ。ここまで書いてくるのは、よほどのことなのであろう」と、ついに下りることを承諾した。そして、
有感(感有リ)
いかること知つてあれども水温(ぬる)む
という句をつくり、以後虚子とは義絶した。九月には母の上京を促すため、帰郷した。末弟の宗一(そういち)が東京高商に入学するため上京し、以後、宇和島で独り住まいになっていた母の面倒を見るのは長男(※嫡男)の務めだと思い、同居の説得に行ったのだった。この年、東洋城にとって肉親の死にも等しい哀しいできごとがあった。十二月九日、漱石が死亡したのである。」(『渋柿の木の下で(中村英利子著)』) ]
用ふべき薬も絶えし火桶かな(前書「黒き枠の中より(「漱石先生の死))六句」)
木枯に深山木折るゝ音を聞け(同上)
埋火は灰の深きに消えにけり(同上)
祖父も父も繕ひし土塀冬日さす(同上)
ともし火に枯荷の月を観じけり(同上)
元日や人の心の一大事(同上)
[「東洋城はかって、父が亡くなるときにもこうして末期の水を捧げたが、師の漱石にも同じことをしていると思いながら、あと筆を進めず漱石の顔を見た。この時の東洋城の心には、師とか文豪などというものはなく、父を失ったときと同じ悲しみがあった。「先生、先生」、呼んだ後、漱石はふ―っと息を吐いたが、その後はもう続かない。真鍋が夫人に「お目を」と言い、夫人は手で静かに漱石の目をつむらせたが、初めから開いていないのをそうしたのは、永遠に安らかに瞑目させようとしたものだった。阿部学士検脈。真鍋学士検脈。退いて「すでに」と言う。部屋の中は、しのび泣きや声を上げて泣く声で満ちた。時に午後六時五十分。曇った日はすでに暮れ、闇の中に寒風がさみしく吹いた。
( 東洋城はこのあと、一連の葬儀に関して仕切り役ともいうべき重要な働きをした。しかし、それにもかかわらず、弟子たちのあいだに軋轢が生じた。」(『渋柿の木の下で(中村英利子著)』) ]

「夏目漱石の娘 愛子さん(「父漱石の霊に捧ぐ」より)」
http://enmi19.seesaa.net/article/463137651.html
(寅彦・三十九歳。十一月、東京帝国大学理科大学教授となる。十二月、胃潰瘍のため医者より絶対安静を命じられる。十二月九日、夏目漱石死亡。) →[『寺田寅彦全集/文学篇/七巻』には収載句は無い。]
(参考一) [葬儀記 芥川龍之介]
https://www.aozora.gr.jp/cards/000879/files/150_15210.html
[ 離れで電話をかけて、皺(しわ)くちゃになったフロックの袖(そで)を気にしながら、玄関へ来ると、誰(だれ)もいない。客間をのぞいたら、奥さんが誰だか黒の紋付(もんつき)を着た人と話していた。が、そこと書斎との堺(さかい)には、さっきまで柩(ひつぎ)の後ろに立ててあった、白い屏風(びょうぶ)が立っている。どうしたのかと思って、書斎の方へ行くと、入口の所に和辻(わつじ)さんや何かが二、三人かたまっていた。中にももちろん大ぜいいる。ちょうど皆が、先生の死顔(しにがお)に、最後の別れを惜んでいる時だったのである。
僕は、岡田(おかだ)君のあとについて、自分の番が来るのを待っていた。もう明るくなったガラス戸の外には、霜よけの藁(わら)を着た芭蕉(ばしょう)が、何本も軒近くならんでいる。書斎でお通夜(つや)をしていると、いつもこの芭蕉がいちばん早く、うす暗い中からうき上がってきた。――そんなことをぼんやり考えているうちに、やがて人が減って書斎の中へはいれた。
書斎の中には、電灯がついていたのか、それともろうそくがついていたのか、それは覚えていない。が、なんでも、外光だけではなかったようである。僕は、妙に改まった心もちで、中へはいった。そうして、岡田君が礼をしたあとで、柩の前へ行った。
柩のそばには、松根(まつねさん)が立っている。そうして右の手を平(たいら)にして、それを臼(うす)でも挽(ひく)時のように動かしている。礼をしたら、順々に柩の後ろをまわって、出て行ってくれという合図(あいず)だろう。
柩は寝棺(ねかん)である。のせてある台は三尺ばかりしかない。そばに立つと、眼と鼻の間に、中が見下された。中には、細くきざんだ紙に南無阿弥陀仏(なむあみだぶつ)と書いたのが、雪のようにふりまいてある。先生の顔は、半ば頬(ほお)をその紙の中にうずめながら、静かに眼をつぶっていた。ちょうど蝋(ろう)ででもつくった、面型(めんがた)のような感じである。輪廓(りんかく)は、生前と少しもちがわない。が、どこかようすがちがう。脣(くちびる)の色が黒(くろ)ずんでいたり、顔色が変わっていたりする以外に、どこかちがっているところがある。僕はその前で、ほとんど無感動に礼をした。「これは先生じゃない」そんな気が、強くした。(これは始めから、そうであった。現に今でも僕は誇張なしに先生が生きているような気がしてしかたがない)僕は、柩の前に一、二分立っていた。それから、松根さんの合図通り、あとの人に代わって、書斎の外へ出た。
ところが、外へ出ると、急にまた先生の顔が見たくなった。なんだかよく見て来るのを忘れたような心もちがする。そうして、それが取り返しのつかない、ばかな事だったような心もちがする。僕はよっぽど、もう一度行こうかと思った。が、なんだかそれが恥しかった。それに感情を誇張しているような気も、少しはした。「もうしかたがない」――そう、思ってとうとうやめにした。そうしたら、いやに悲しくなった。
外へ出ると、松岡が「よく見て来たか」と言う。僕は、「うん」と答えながら、うそをついたような気がして、不快だった。
青山の斎場(さいじょう)へ行ったら、靄(もや)がまったく晴れて、葉のない桜のこずえにもう朝日がさしていた。下から見ると、その桜の枝が、ちょうど鉄網のように細(こま)かく空をかがっている。僕たちはその下に敷いた新しいむしろの上を歩きながら、みんな、体をそらせて、「やっと眼がさめたような気がする」と言った。
斎場は、小学校の教室とお寺の本堂とを、一つにしたような建築である。丸い柱や、両方のガラス窓が、はなはだみすぼらしい。正面には一段高い所があって、その上に朱塗(しゅぬり)の曲禄(きょくろく)が三つすえてある。それが、その下に、一面に並べてある安直な椅子(いす)と、妙な対照をつくっていた。「この曲禄を、書斎の椅子(いす)にしたら、おもしろいぜ」――僕は久米(くめ)にこんなことを言った。久米は、曲禄の足をなでながら、うんとかなんとかいいかげんな返事をしていた。
斎場を出て、入口の休所やすみどころへかえって来ると、もう森田さん、鈴木さん、安倍さん、などが、かんかん火を起した炉(ろ)のまわりに集って、新聞を読んだり、駄弁(だべん)をふるったりしていた。新聞に出ている先生の逸話(いつわ)や、内外の人の追憶が時々問題になる。僕は、和辻さんにもらった「朝日」を吸いながら、炉のふちへ足をかけて、ぬれたくつから煙が出るのをぼんやり、遠い所のものを見るようにながめていた。なんだか、みんなの心もちに、どこか穴のあいている所でもあるような気がして、しかたがない。
そのうちに、葬儀の始まる時間が近くなってきた。「そろそろ受付へ行こうじゃないか」――気の早い赤木君が、新聞をほうり出しながら、「行(い)」の所へ独特のアクセントをつけて言う。そこでみんな、ぞろぞろ、休所を出て、入口の両側にある受付へ分れ分れに、行くことになった。松浦君、江口君、岡君が、こっちの受付をやってくれる。向こうは、和辻さん、赤木君、久米という顔ぶれである。そのほか、朝日新聞社の人が、一人ずつ両方へ手伝いに来てくれた。
やがて、霊柩車(れいきゅうしゃ)が来る。続いて、一般の会葬者が、ぽつぽつ来はじめた。休所の方を見ると、人影がだいぶんふえて、その中に小宮(こみや)さんや野上(のがみ)さんの顔が見える。中幅(ちゅうはば)の白木綿(しろもめん)を薬屋のように、フロックの上からかけた人がいると思ったら、それは宮崎虎之助(みやざきとらのすけ)氏だった。
始めは、時刻が時刻だから、それに前日の新聞に葬儀の時間がまちがって出たから、会葬者は存外少かろうと思ったが、実際はそれと全く反対だった。ぐずぐずしていると、会葬者の宿所を、帳面につけるのもまにあわない。僕はいろんな人の名刺をうけとるのに忙殺された。
すると、どこかで「死は厳粛である」と言う声がした。僕は驚いた。この場合、こんな芝居じみたことを言う人が、僕たちの中にいるわけはない。そこで、休所(やすみどころ)の方をのぞくと、宮崎虎之助氏が、椅子(いす)の上へのって、伝道演説をやっていた。僕はちょいと不快になった。が、あまり宮崎虎之助らしいので、それ以上には腹もたたなかった。接待係の人が止(とめ)たが、やめないらしい。やっぱり右手で盛なジェステュアをしながら、死は厳粛であるとかなんとか言っている。
が、それもほどなくやめになった。会葬者は皆、接待係の案内で、斎場の中へはいって行く。葬儀の始まる時刻がきたのであろう。もう受付へ来る人も、あまりない。そこで、帳面や香奠(こうでん)をしまつしていると、向こうの受付にいた連中が、そろってぞろぞろ出て来た。そうして、その先に立って、赤木君が、しきりに何か憤慨している。聞いてみると、誰かが、受付係は葬儀のすむまで、受付に残っていなければならんと言ったのだそうである。至極もっともな憤慨だから、僕もさっそくこれに雷同した。そうして皆で、受付を閉じて、斎場へはいった。
正面の高い所にあった曲ろくは、いつの間にか一つになって、それへ向こうをむいた宗演(そうえん)老師が腰をかけている。その両側にはいろいろな楽器を持った坊さんが、一列にずっと並んでいる。奥の方には、柩があるのであろう。夏目金之助之柩(なつめきんのすけのひつぎ)と書いた幡(はた)が、下のほうだけ見えている。うす暗いのと香の煙とで、そのほかは何があるのだかはっきりしない。ただ花輪の菊が、その中でうずたかく、白いものを重ねている。――式はもう誦経(ずきょう)がはじまっていた。
僕は、式に臨んでも、悲しくなる気づかいはないと思っていた。そういう心もちになるには、あまり形式が勝っていて、万事がおおぎょうにできすぎている。――そう思って、平気で、宗演老師の秉炬法語(へいきょほうご)を聞いていた。だから、松浦君の泣き声を聞いた時も、始めは誰かが笑っているのではないかと疑ったくらいである。
ところが、式がだんだん進んで、小宮さんが伸六(しんろく)さんといっしょに、弔辞(ちょうじ)を持って、柩の前へ行くのを見たら、急に瞼(まぶた)の裏が熱くなってきた。僕の左には、後藤末雄(ごとうすえお)君が立っている。僕の右には、高等学校の村田先生がすわっている。僕は、なんだか泣くのが外聞の悪いような気がした。けれども、涙はだんだん流れそうになってくる。僕の後ろに久米(くめ)がいるのを、僕は前から知っていた。だからその方を見たら、どうかなるかもしれない。――こんなあいまいな、救助を請うような心もちで、僕は後ろをふりむいた。すると、久米の眼が見えた。が、その眼にも、涙がいっぱいにたまっていた。僕はとうとうやりきれなくなって、泣いてしまった。隣にいた後藤君が、けげんな顔をして、僕の方を見たのは、いまだによく覚えている。
それから、何がどうしたか、それは少しも判然しない。ただ久米が僕の肘(ひじ)をつかまえて、「おい、あっちへ行こう」とかなんとか言ったことだけは、記憶している。そのあとで、涙をふいて、眼をあいたら、僕の前に掃きだめがあった。なんでも、斎場とどこかの家との間らしい。掃きだめには、卵のからが三つ四つすててあった。
少したって、久米と斎場へ行ってみると、もう会葬者がおおかた出て行ったあとで、広い建物の中はどこを見ても、がらんとしている。そうして、その中で、ほこりのにおいと香のにおいとが、むせっぽくいっしょになっている。僕たちは、安倍さんのあとで、お焼香(しょうこう)をした。すると、また、涙が出た。
外へ出ると、ふてくされた日が一面に霜(しも)どけの土を照らしている。その日の中を向こうへ突つっきって、休所へはいったら、誰かが蕎麦饅頭(そばまんじゅう)を食えと言ってくれた。僕は、腹がへっていたから、すぐに一つとって口へ入れた。そこへ大学の松浦先生が来て、骨上(こつあげ)のことか何か僕に話しかけられたように思う。僕は、天とうも蕎麦饅頭もしゃくにさわっていた時だから、はなはだ無礼な答をしたのに相違ない。先生は手がつけられないという顔をして、帰られたようだった。あの時のことを今思うと、少からず恐縮する。
涙のかわいたのちには、なんだか張合(はりあい)ない疲労ばかりが残った。会葬者の名刺を束にする。弔電や宿所書きを一つにする。それから、葬儀式場の外の往来で、柩車の火葬場へ行くのを見送った。
その後は、ただ、頭がぼんやりして、眠いということよりほかに、何も考えられなかった。
(大正五年十二月) ]
(参考二) 「木曜会・漱石没後=「九日会」メンバー」(周辺)
https://soseki-museum.jp/soseki-natsume/surround-soseki/
[ (「漱石・東洋城」親近者)
1 松根東洋城(まつねとうようじょう)=明治11(1878)~昭和39(1964)年。俳人。愛媛県尋常中学校で漱石に学ぶ。上京後、漱石の紹介で正岡子規と出会い、句作を始め、雑誌「渋柿」を創刊した。(「漱石門」の年長組、「木曜会」のメンバー、「漱石十大弟子の一人」。)
2 寺田寅彦(てらだとらひこ)=明治11(1878)~昭和10(1935)年。物理学者、随筆家。第五高等学校で漱石に学んだ。物理学の研究の一方で吉村冬彦の名前で多くの随筆を書いた。(「漱石門」の年長組、「木曜会」のメンバー、「漱石十大弟子の一人」。)
3 小宮豊隆(こみやとよたか)=明治17(1884)~昭和41(1966)年。独文学者、評論家。漱石の全集編集の中心的役割を担った。また、『夏目漱石』などの評伝を書いた。阿部次郎に招かれて東北帝国大学(東北大学)で定年まで勤め、その後は学習院大学で教えた。(「漱石門」の最側近、「木曜会・九日会」のメンバー、「漱石門」の四天王の一人、「漱石十大弟子の一人」。東洋城没後の「東洋城全句集」編者の一人。)
4 安倍能成(あべよししげ)=明治16(1883)~昭和41(1966)年。哲学者、評論家、教育者。第一高等学校で漱石に学んだ。母校の校長を務め、戦後は文部大臣、学習院大学の院長を務めた。(「漱石門」の出世頭(戦後の昭和二十一年に文部大臣)、「漱石門」の四天王の一人、「漱石十大弟子の一人」。「木曜会・九日会」のメンバー、東洋城没後の「東洋城全句集」編者の一人。)
(「漱石」親近の友人・門人)
5 高浜虚子(たかはまきょし)=明治7(1874)~昭和34(1959)年。俳人、小説家。漱石の友人正岡子規に俳句を教わった。漱石に小説執筆を薦め、「吾輩は猫である」を書かせた。
(「木曜会」のメンバーであるが、常連メンバーではない。)
6 岩波茂雄(いわなみしげお)=明治14(1881)~昭和21(1946)年。岩波書店創業者。岩波書店を開業し、『こころ』を初めとする漱石の作品を多く出版した。(「木曜会」のメンバーであるが、常連メンバーではない。)
7 阿部次郎(あべじろう)=明治16(1883)~昭和34(1959)年。哲学者、評論家。自伝的小説「三太郎の日記」は大正期のベストセラーになった。その後は人格主義という思想を提唱した。大正12(1923)年からは長く東北帝国大学(東北大学)の教員を務めた。(「漱石十大弟子の一人)」。)
8 和辻哲郎(わつじてつろう)=明治22(1889)~昭和35(1960)年。哲学者、文化史家、倫理学者。漱石に教わったことはなかったが、漱石を敬愛して付きあうようになった。『古寺巡礼』など文化史方面の著作も多い。昭和9(1934)年からは東京大学教授として定年まで勤めた。(「木曜会」のメンバーというよりも「九日会」のメンバー。)
9 津田青楓(つだせいふう)=明治13(1880)~昭和53(1978)年。画家。『道草』や『明暗』など漱石の本の装丁を手がけた。また、漱石に絵画の手ほどきをした。(「漱石十大弟子の一人」、実兄は「去風流七代・西川一草亭」、漱石側近の画家、後に「左翼」に転向。)
10 野村伝四(のむらでんし)=明治13(1880)~昭和23(1948)年。教育者。漱石の教え子で学校教諭などを務めた後、奈良県立図書館の館長になった。一方で郷里鹿児島の方言研究にも努めた。(「野村伝四は漱石が最も愛した弟子だといわれている。彼は朴訥で接すると春風飴蕩のおもむきがあった。ちょうど、複雑なハムレットが、激情の奴隷でないホレイショを愛したように、複雑な漱石も朴訥な伝四を愛したのであろう。」=「ウィキペディア」)
11 林原耕三(はやしばらこうぞう)=明治20(1887)~昭和50(1975)年。英文学者、俳人。漱石の教え子で久米正雄、芥川龍之介を漱石に紹介した。東京帝国大学卒業後は法政大学や明治大学で教えつつ、句作にも熱心だった。(俳句は、「東洋城」の「渋柿」ではなく、「石楠」の「臼田亜浪」に師事。)
(「漱石」門の作家たち=「木曜会・九日会」のメンバー)
12 森田草平(もりたそうへい)=明治14(1881)~昭和24(1949)年。小説家。漱石に薦められて平塚らいてうとの恋愛を「煤煙」という作品として発表し、漱石が朝日新聞の紙面に作った「朝日文芸欄」では編集を担った。(「漱石門」の四天王の一人、「漱石十大弟子の一人」、漱石の「野分」のモデルとされている。)
13 鈴木三重吉(すずきみえきち)=明治15(1882)~昭和11(1936)年。小説家、童話作家。漱石に小説を評価されるが、漱石没後は童話作家として活躍し、雑誌「赤い鳥」を編集した。(「漱石門」の四天王の一人、「漱石十大弟子の一人」、東洋城と三重吉は当初は昵懇の関係であったが、後に、東洋城との関係は疎遠となる。)
14 野上豊一郎(のがみとよいちろう)=明治16(1883)~昭和25(1950)年。能楽研究者、英文学者。第一高等学校で漱石に学んだ。英文学では特に演劇研究をよくし、後には能楽研究で名を成し、教員を務めた法政大学にはその名を冠した能楽研究所が置かれている。妻は小説家の野上弥生子。(「漱石十大弟子の一人」。)
15 中勘助(なかかんすけ)=明治18(1885)~昭和40(1965)年。小説家、詩人、随筆家。第一高等学校からの漱石の教え子で小説「銀の匙」が漱石に高く評価された。(詩人としても、三好達治は、中勘助の詩には人間の善意識を呼び覚ます力と涯底(そこい)のしれぬ哀感があると高く評価した。65年(昭和40)1月朝日賞受賞「日本大百科全書(ニッポニカ)」)
16 赤木桁平(あかぎこうへい)=明治24(1891)~昭和24(1949)年。評論家、政治家。友人の鈴木三重吉を介して漱石と出会い、漱石にとって初の伝記『夏目漱石』を書いた。(「漱石十大弟子の一人」。日米開戦の積極論者で、漱石門の最右翼の人物。)
17 内田百閒(うちだひゃっけん)=明治22(1889)~昭和46(1971)年。小説家、随筆家。漱石全集の校正を担った。作家としての代表作に「冥途」や「贋作吾輩は猫である」など。(「夏目漱石」と「芥川龍之介」との接点の中心的人物で、「俳句」の造詣も深い。)
18 江口渙(えぐちかん)=明治20(1887)~昭和50(1975)年。小説家、評論家。芥川龍之介の作品をいち早く評価した。その後は社会主義運動に関わるようになっていった。(「夏目漱石と芥川龍之介」との接点にあって、漱石門の、戦中・戦後の最左翼の文学を担った人物。)
(「漱石」門の作家たち=主として「木曜会(ニューフェイス達=第4次『新思潮』派の作家たち」など」)のメンバー)
19 菊池寛(きくちかん)=明治21(1888)~昭和23(1948)年。文藝春秋社創設者、小説家。小説や戯曲を書くかたわら、文藝春秋社を開業し、幅広い事業を展開した。(第三・四次「新思潮」同人。「文芸春秋」を創刊、文芸春秋社を設立。芥川賞、直木賞を設定し、作家の育成、文芸の普及に努めた。作家として通俗小説に一生面を開く。著作「父帰る」「無名作家の日記」「恩讐の彼方に」「真珠夫人」。)(「精選版 日本国語大辞典」)
20 芥川龍之介(あくたがわりゅうのすけ)=明治25(1892)~昭和2(1927)年。小説家。「鼻」が漱石小説家。東京生まれ。別号澄江堂主人、我鬼。第三次、第四次の「新思潮」同人。「鼻」が夏目漱石に認められ、文壇出世作となる。歴史に材を取った理知的・技巧的作品で、抜群の才能を開花させた。致死量の睡眠薬を飲み自殺。著作「羅生門」「地獄変」「歯車」「或阿呆の一生」「西方の人」など。明治二五~昭和二年(一八九二‐一九二七)に高く評価され、大正期を代表する作家になった。主な作品に「地獄変」や「歯車」など(「精選版 日本国語大辞典」)
21 松岡譲(まつおかゆずる)=明治24(1891)~昭和44(1969)年。小説家。漱石の長女筆子と結婚した。漱石の妻鏡子の談話を編集して『漱石の思ひ出』を刊行した。
22 久米正雄(くめまさお)=明治24(1891)~昭和27(1952)年。小説家、劇作家。芥川と共に作家として評価された。漱石没後は戯曲や大衆向けの小説を多く書いた
23 成瀬 正一(なるせ せいいち、1892年4月26日 - 1936年4月13日)は、日本のフランス文学者。ロマン・ロランの翻訳・紹介を行った。大学卒業後まもなく創作から研究の道に転じ、九州帝国大学法文学部教授として仏蘭西浪漫主義思想を専門とした。43歳で病死したが、この時代の良き知識人として、後世の文学や美術研究に大いに寄与した。パリ留学中の1921年、松方幸次郎のアドバイザーとして松方コレクション(国立西洋美術館)の絵画彫刻の蒐集購入に協力した。(「ウィキペディア」) ]

「東京帝国大学を卒業する1916年(大正5年)頃の第4次『新思潮』のメンバー。成瀬正一は一番右、その左は芥川龍之介、次いで松岡譲、一番左が久米正雄。」
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%88%90%E7%80%AC%E6%AD%A3%E4%B8%80_%28%E3%83%95%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%82%B9%E6%96%87%E5%AD%A6%E8%80%85%29
(参考三) 「文豪、夏目漱石の葬儀」と「陸軍大将大山巌の国葬」
http://web.sanin.jp/p/sousen/1/3/1/14/11/
[ 文豪、夏目漱石の葬儀(大正5年12月)
夏目漱石の遺体は故人の希望により、12月10日午後1時40分より、医科大学病理解剖室で解剖された。作業は3時30分に終り、遺体は再び邸宅に帰った。翌11日は通夜が行なわれた。白絹の被いが掛けられた棺の上にはケーベル博士の花輪が飾られ、「文献院古道漱石居士」と書かれた位牌を棺前に安置された。葬儀の当日は、午前7時半より読経が始められた。8時半に、第1の馬車に僧侶、次に棺馬車、次に遺族、親族など6輛の馬車に分乘して出発。柩車は9時半に青山斎場に到着。芥川竜之介がフロックコートを着て受付をした。柩は直ちに祭壇に安置され、その上に「夏目金之助之柩」と大書きした銘旗を掲げられた。10時半に読経が始まり、朝日新聞社社長の弔辞朗読が行なわれた。遺体は葬儀後、落合火葬場にて荼毘に附された。
陸軍大将大山巌の国葬(大正5年12月)
12月10日に逝去した大山巌の国葬は、同17日日比谷公園で行なわれた。早朝より、日比谷公園正門から葬儀場の内外は、白い砂をまき掃き清められた。幔門から左右は黒白の幕を張り、正面の祭場は白木造りに白の幕を絞り、白の布で祭壇を設置。左右に立ち並ぶ幄舎は黒白段々の布で天井を覆い、同じ色で柱を包んだ。9時10分、行列が到着し、11時には国葬が終了した。再び霊柩は霊柩馬に移され、上野駅にと向かった。上野駅についた霊柩は、馬車に載せたまま、兵士20名によって担がれ、特別列車の待つ1番線へと向かう。プラットホームには鯨幕を張り、その中で鉄道職員、葬儀係員立会の下で馬車より柩を引き下ろして、特別列車内に運び入れた。列車の内部はことごとく白い幕で飾り、床だけは黒布を敷き詰めた。告別式のあと、霊柩列車は那須野へ向かった。]
タグ:子規・漱石・寅彦・東洋城
「漱石・東洋城・寅彦」(子規没後~漱石没まで)俳句管見(その十三) [漱石・東洋城・寅彦]
その十三「大正四年(一九一五)」
[漱石・四十八歳。大正4(1915)、 1月~2月、「硝子戸の中」、3月、京都旅行、 6月~9月、「道草」、12月、芥川龍之介・久米正雄らが木曜会に参加。]
2437 柳芽を吹いて四条のはたごかな
[漱石は三月十九日から四月十六日まで京都に滞在した。この句(2437)から(2443)の句は、その滞在中の句である。この句(2437)は、この滞京中に磯田多佳(2440の前書に記載されている)に贈った画帖『観自在帖』(付記その一・再掲)に記されている。]
2438 筋違(すじかい)に四条の橋や春の川
[京都滞在中の句。蕪村の「ほとゝぎす平安城の筋違に」に由来のある句。]
2439 紅梅や舞の地を弾く金之助
[京都滞在中の句。金之助は祇園 の芸妓の名。本名=梅垣きぬ。]
2440 春の川を隔てゝ男女かな(前書「木屋町に宿をとりて川向の御多佳さんに、一句」)
[京都の漱石の宿は木屋町三条上ルにあった北大嘉(きたのたいが)。多嘉は祇園大友(だいとも)の女将、磯田多佳。鴨川の東に大友、西に北大嘉があった。(付記その一・再掲)]
2441 萱草の一輪咲きぬ草の中
[京都滞在中の句。漱石門の側近の画家・津田青楓の実兄・西川一草亭(次句の「一草亭」)が描いた萱草の絵に賛をした自賛句も知られている。それらと連作している自画賛句と思われる。]
2442 牡丹剪つて一草亭を待つ日哉
[京都滞在中の句。「一草亭」は、華道去風流の「西川一草亭」。実弟が津田青楓であり、漱石は京都滞在中に親しく交わった。(付記その二・再掲)]
2443 椿とも見えぬ花かな夕曇
[京都滞在中の句。この句も自画賛の句。]
(付記その一・再掲)
https://yahan.blog.ss-blog.jp/2023-09-12
[ 漱石の「観自在帖」周辺
.jpg)
「観自在帖(全作品紹介)」
https://hzrhq.agaterlm.top/index.php?main_page=product_info&products_id=30145
≪右一列上段「観自在帖(1)」→「観自在(漱石題)/紙本墨書・淡彩・24.4×36.3㎝」
右一列中段「観自在帖(2)」→「藤花図」/同上」
右一列下段「観自在帖(3)」→「隔水東西住」/同上」
右二列上段「観自在帖(4)」→「竹図」/同上」
右二列中段「観自在帖(5)」→「渡尽東西水」/同上」
右二列下段「観自在帖(6)」→「鉢花図」/同上」
右三列上段「観自在帖7)」→「柳芽を」/同上」
右三列中段「観自在帖(8)」→「牡丹図」/同上」
右三列下段「観自在帖(9)」→「起臥乾抻」/同上」
右四列上段「観自在帖10)」→「松林図」/同上」
右四列中段「観自在帖(11)」→「二十年来愛碧林/同上」
右四列下段「観自在帖(12)」→「竹石図/同上」 以下「略」 ]
(付記その二・再掲)

「去風流七代・西川一草亭」
http://www.kyofuryu.com/about.html
https://yahan.blog.ss-blog.jp/2023-09-12
[☆去風洞主人・西川一草亭
漱石は、大正4年3月21日、京都滞在中に西川一草亭の招きで彼の住居である茶室を訪れています。まず、漱石自身の筆記を見ることにいたします。
漱石全集 大正4年 日記14 (日記・断片 下)
「二一日(日)
八時起る。下女に一体何時に起ると聞けば大抵八時半か九時だといふ。夜はと聞けば二時頃と答ふ。驚くべし。」
漱石は旅館の女中の生活を聞き、労働時間が長いのに驚いています。それから宿の窓からのぞむ加茂川とかなたの東山が霞でよく見えないのに河原で合羽を干すさまを書きとめています。
☆漱石 去風洞・小間の茶室に入る
「東山霞んで見えず、春気曖、河原に合羽を干す。西川氏より電話可成(なるべく)早くとの注文。二人で出掛ける。去風洞といふ門をくぐる。奥まりたる小路の行き当たり、左に玄関。くつ脱ぎ。水打ちて庭樹幽すい、寒きこと夥し。」
寒がりの漱石はここでも京の底冷えの寒さに震え上がっています。数奇屋の庭はこの時期殺風景な感じもあったでしょうし、待合の座敷から暖かい陽光の遮られた暗い茶室へ入り、心寒いばかりの想いがあったのではないでしょうか。それでも漱石の観察眼はするどく克明に記憶にとどめています。
「床に方祝の六歌仙の下絵らしきもの。花屏風。壁に去風洞の記をかく。黙雷の華厳世界。一草亭中人。御公卿様の手習い机。茶席へ案内、数奇屋草履。石を踏んでし尺(しせき)のうちに路を間違へる。再び本道に就けばすぐ茶亭の前に行きつまる。どこから這入るのかと聞く。戸をあけて入る。方三尺ばかり。ニジリ上り。」
ここは、露地を歩きながら茶室への方向を間違え、やっと茶室のにじり口を見つけたところです。武士も刀を外して身分の上下なく入る狭き入り口なのです。漱石はどうやら身をかがめて茶室内に入ったようです。
「更紗の布団の上にあぐらをかき壁による。つきあげ窓。それを明けると松見える。床に守信の梅、「梅の香の匂いや水屋のうち迄も」といふ月並みな俳句の賛あり。」
暗い茶室内には天井に突き上げ窓が開けられていました。ここから自然光が入る仕組みになっているのです。しかし、同時に冷気も入ったことでしょう。次に懐石料理が書かれています。この去風洞の近くに「松清」という料理屋があり、亭主は懐石をそこから取り寄せたもようです。]
(東洋城・三十八歳。二月「渋柿」創刊。東洋城の主力は「国民俳壇」に注がれてゐるので「渋柿」は本城に対する陣屋といふ形であった。漱石が「渋柿」の題籢を書いた。)
※渋柿の如きものに候へど(大正三年作。前書「※さて仰せかしこまり奉るとて」。)
※能もなき渋柿共が誠かな(大正四年作。前書「Le petit 小さき者汝の名は「渋柿」なり、情ある者汝の名は「渋柿」なり。唯誠なる者その名も亦「渋柿」なり。(中略))如斯「渋柿」は借る腹も拠る技もなくして只自らなる生地のままに自らふとまろぶが如く生れ出でたり。人の誌名を乞ふにまかせて蘭菊を選み桜桃を品するに薫酒(くんしゅう)半日決せず、談偶「渋柿の如きものにては」に及ぶ言未だ終らざるに人は膝を叩いて「此他はあらじ」と立上がり驚喜怱々汽車に乗じて去る。去るの後※「能もなき渋柿どもや門の内」の句を思ひ出して独りほほ笑みつつ漱石先生に和して自ら安んじて曰(く)。」)
※壺菫小さきなさけを咲きにけり(同上。前書「(中略) ひたぶるに剛き人明るき者は世に少くもあらじ、剛きが中にあはれあり、透明の中に漂砂とせん事こそや、その霑(うるお)ひよ・・・弥(いよいよ)ぎごちなく弥せち辛く弥あさましくなり行くらん現世の一隅に・・・『国民俳壇』と共に『渋柿』は斯あるなり。※あゝまこと、あゝなさけ、さて、Le petit『渋柿』」)
[寅彦・三十八歳。神経痛および神経症に悩まされる。二月、三女雪子誕生。四月、東京地学協会総会において「アイソスタシーに就て」を講演する。十月、正六位に叙せられる。]→[『寺田寅彦全集/文学篇/七巻』には収載句は無い。]
(参考その一) 俳誌「渋柿」周辺(「ウィキペディア」)
≪『渋柿』(しぶがき)は、渋柿社による俳誌。夏目漱石の弟子、松根東洋城が1915年に大正天皇侍従として式部官在任中に主宰創刊。松尾芭蕉の俳諧理念(わび・さび・しをり)を探究、「芭蕉直結・芭蕉に還れ」を掲げて心境・境涯俳句の創作に努める。夏目漱石門下の小宮豊隆、寺田寅彦、安倍能成、鈴木三重吉、戸川幸夫、吉田洋一も投稿している。現在は安原谿游が主宰。
(沿革)1914年(大正3年)松根東洋城が宮内省式部官のとき、大正天皇から俳句について聞かれ「渋柿のごときものにては候へど」と答えたことが有名となった。
1915年(大正4年)松根東洋城が俳誌『渋柿』を創刊主宰。
1916年(大正5年)正岡子規没後『ホトトギス』を継承した高浜虚子が、東洋城を『国民新聞』俳壇の選者から下ろし、代わって虚子自身が選者になったことを契機に東洋城は『ホトトギス』を離脱した。
1952年(昭和27年)東洋城は隠居を表明し、主宰を創刊時から選者として参加し、「国民新聞」の俳句欄で活躍していた門下の野村喜舟に譲る。24年間主宰を務める。句集『小石川』「紫川」などを発刊し、小倉北区の篠崎八幡神社には「鶯や紫川にひびく声」の句碑がある。(後略)
(名称の由来)1914年(大正3年)、東洋城が宮内省式部官のとき、大正天皇から俳句について聞かれ「渋柿のごときものにては候へど」と答えたことが有名となったことから。なお「渋柿」平成29年3月号の谷本清流氏の文章によれば、もう一説あり、かつての漱石の〈能もなき渋柿共や門の内〉という句に和して、東洋城が、〈能もなき渋柿共が誠かな〉という句を作っていたことから「渋柿」に決まったと言われている。≫(「ウィキペディア」)
(参考その二) 「俳誌 渋柿」の題籢(夏目漱石書)周辺

「公益社団法人 俳人協会・俳句文学館:賛助会員:渋柿」
https://www.haijinkyokai.jp/member/ini03/1299.html
(参考その三) 漱石の「渋柿」の句など(その周辺)
https://yahan.blog.ss-blog.jp/2023-10-02
[ 渋柿の下に稲こく夫婦かな 漱石(明28)
渋柿や寺の後の芋畠 漱石(明治28)
渋柿やあかの他人であるからは 漱石(明治30)
※能もなき渋柿共や門の内 漱石(明治31)
渋柿や長者と見えて岡の家 漱石(明治32)
渋柿やにくき庄屋の門構 漱石(明治34)
渋柿も熟れて王維の詩集哉 漱石(明治43)
「※能もなき渋柿共や門の内 漱石(明治31)」の句は、「能もなき教師とならんあら涼し 漱石(明治36)」の句と連動している。 ]
[漱石・四十八歳。大正4(1915)、 1月~2月、「硝子戸の中」、3月、京都旅行、 6月~9月、「道草」、12月、芥川龍之介・久米正雄らが木曜会に参加。]
2437 柳芽を吹いて四条のはたごかな
[漱石は三月十九日から四月十六日まで京都に滞在した。この句(2437)から(2443)の句は、その滞在中の句である。この句(2437)は、この滞京中に磯田多佳(2440の前書に記載されている)に贈った画帖『観自在帖』(付記その一・再掲)に記されている。]
2438 筋違(すじかい)に四条の橋や春の川
[京都滞在中の句。蕪村の「ほとゝぎす平安城の筋違に」に由来のある句。]
2439 紅梅や舞の地を弾く金之助
[京都滞在中の句。金之助は祇園 の芸妓の名。本名=梅垣きぬ。]
2440 春の川を隔てゝ男女かな(前書「木屋町に宿をとりて川向の御多佳さんに、一句」)
[京都の漱石の宿は木屋町三条上ルにあった北大嘉(きたのたいが)。多嘉は祇園大友(だいとも)の女将、磯田多佳。鴨川の東に大友、西に北大嘉があった。(付記その一・再掲)]
2441 萱草の一輪咲きぬ草の中
[京都滞在中の句。漱石門の側近の画家・津田青楓の実兄・西川一草亭(次句の「一草亭」)が描いた萱草の絵に賛をした自賛句も知られている。それらと連作している自画賛句と思われる。]
2442 牡丹剪つて一草亭を待つ日哉
[京都滞在中の句。「一草亭」は、華道去風流の「西川一草亭」。実弟が津田青楓であり、漱石は京都滞在中に親しく交わった。(付記その二・再掲)]
2443 椿とも見えぬ花かな夕曇
[京都滞在中の句。この句も自画賛の句。]
(付記その一・再掲)
https://yahan.blog.ss-blog.jp/2023-09-12
[ 漱石の「観自在帖」周辺
.jpg)
「観自在帖(全作品紹介)」
https://hzrhq.agaterlm.top/index.php?main_page=product_info&products_id=30145
≪右一列上段「観自在帖(1)」→「観自在(漱石題)/紙本墨書・淡彩・24.4×36.3㎝」
右一列中段「観自在帖(2)」→「藤花図」/同上」
右一列下段「観自在帖(3)」→「隔水東西住」/同上」
右二列上段「観自在帖(4)」→「竹図」/同上」
右二列中段「観自在帖(5)」→「渡尽東西水」/同上」
右二列下段「観自在帖(6)」→「鉢花図」/同上」
右三列上段「観自在帖7)」→「柳芽を」/同上」
右三列中段「観自在帖(8)」→「牡丹図」/同上」
右三列下段「観自在帖(9)」→「起臥乾抻」/同上」
右四列上段「観自在帖10)」→「松林図」/同上」
右四列中段「観自在帖(11)」→「二十年来愛碧林/同上」
右四列下段「観自在帖(12)」→「竹石図/同上」 以下「略」 ]
(付記その二・再掲)

「去風流七代・西川一草亭」
http://www.kyofuryu.com/about.html
https://yahan.blog.ss-blog.jp/2023-09-12
[☆去風洞主人・西川一草亭
漱石は、大正4年3月21日、京都滞在中に西川一草亭の招きで彼の住居である茶室を訪れています。まず、漱石自身の筆記を見ることにいたします。
漱石全集 大正4年 日記14 (日記・断片 下)
「二一日(日)
八時起る。下女に一体何時に起ると聞けば大抵八時半か九時だといふ。夜はと聞けば二時頃と答ふ。驚くべし。」
漱石は旅館の女中の生活を聞き、労働時間が長いのに驚いています。それから宿の窓からのぞむ加茂川とかなたの東山が霞でよく見えないのに河原で合羽を干すさまを書きとめています。
☆漱石 去風洞・小間の茶室に入る
「東山霞んで見えず、春気曖、河原に合羽を干す。西川氏より電話可成(なるべく)早くとの注文。二人で出掛ける。去風洞といふ門をくぐる。奥まりたる小路の行き当たり、左に玄関。くつ脱ぎ。水打ちて庭樹幽すい、寒きこと夥し。」
寒がりの漱石はここでも京の底冷えの寒さに震え上がっています。数奇屋の庭はこの時期殺風景な感じもあったでしょうし、待合の座敷から暖かい陽光の遮られた暗い茶室へ入り、心寒いばかりの想いがあったのではないでしょうか。それでも漱石の観察眼はするどく克明に記憶にとどめています。
「床に方祝の六歌仙の下絵らしきもの。花屏風。壁に去風洞の記をかく。黙雷の華厳世界。一草亭中人。御公卿様の手習い机。茶席へ案内、数奇屋草履。石を踏んでし尺(しせき)のうちに路を間違へる。再び本道に就けばすぐ茶亭の前に行きつまる。どこから這入るのかと聞く。戸をあけて入る。方三尺ばかり。ニジリ上り。」
ここは、露地を歩きながら茶室への方向を間違え、やっと茶室のにじり口を見つけたところです。武士も刀を外して身分の上下なく入る狭き入り口なのです。漱石はどうやら身をかがめて茶室内に入ったようです。
「更紗の布団の上にあぐらをかき壁による。つきあげ窓。それを明けると松見える。床に守信の梅、「梅の香の匂いや水屋のうち迄も」といふ月並みな俳句の賛あり。」
暗い茶室内には天井に突き上げ窓が開けられていました。ここから自然光が入る仕組みになっているのです。しかし、同時に冷気も入ったことでしょう。次に懐石料理が書かれています。この去風洞の近くに「松清」という料理屋があり、亭主は懐石をそこから取り寄せたもようです。]
(東洋城・三十八歳。二月「渋柿」創刊。東洋城の主力は「国民俳壇」に注がれてゐるので「渋柿」は本城に対する陣屋といふ形であった。漱石が「渋柿」の題籢を書いた。)
※渋柿の如きものに候へど(大正三年作。前書「※さて仰せかしこまり奉るとて」。)
※能もなき渋柿共が誠かな(大正四年作。前書「Le petit 小さき者汝の名は「渋柿」なり、情ある者汝の名は「渋柿」なり。唯誠なる者その名も亦「渋柿」なり。(中略))如斯「渋柿」は借る腹も拠る技もなくして只自らなる生地のままに自らふとまろぶが如く生れ出でたり。人の誌名を乞ふにまかせて蘭菊を選み桜桃を品するに薫酒(くんしゅう)半日決せず、談偶「渋柿の如きものにては」に及ぶ言未だ終らざるに人は膝を叩いて「此他はあらじ」と立上がり驚喜怱々汽車に乗じて去る。去るの後※「能もなき渋柿どもや門の内」の句を思ひ出して独りほほ笑みつつ漱石先生に和して自ら安んじて曰(く)。」)
※壺菫小さきなさけを咲きにけり(同上。前書「(中略) ひたぶるに剛き人明るき者は世に少くもあらじ、剛きが中にあはれあり、透明の中に漂砂とせん事こそや、その霑(うるお)ひよ・・・弥(いよいよ)ぎごちなく弥せち辛く弥あさましくなり行くらん現世の一隅に・・・『国民俳壇』と共に『渋柿』は斯あるなり。※あゝまこと、あゝなさけ、さて、Le petit『渋柿』」)
[寅彦・三十八歳。神経痛および神経症に悩まされる。二月、三女雪子誕生。四月、東京地学協会総会において「アイソスタシーに就て」を講演する。十月、正六位に叙せられる。]→[『寺田寅彦全集/文学篇/七巻』には収載句は無い。]
(参考その一) 俳誌「渋柿」周辺(「ウィキペディア」)
≪『渋柿』(しぶがき)は、渋柿社による俳誌。夏目漱石の弟子、松根東洋城が1915年に大正天皇侍従として式部官在任中に主宰創刊。松尾芭蕉の俳諧理念(わび・さび・しをり)を探究、「芭蕉直結・芭蕉に還れ」を掲げて心境・境涯俳句の創作に努める。夏目漱石門下の小宮豊隆、寺田寅彦、安倍能成、鈴木三重吉、戸川幸夫、吉田洋一も投稿している。現在は安原谿游が主宰。
(沿革)1914年(大正3年)松根東洋城が宮内省式部官のとき、大正天皇から俳句について聞かれ「渋柿のごときものにては候へど」と答えたことが有名となった。
1915年(大正4年)松根東洋城が俳誌『渋柿』を創刊主宰。
1916年(大正5年)正岡子規没後『ホトトギス』を継承した高浜虚子が、東洋城を『国民新聞』俳壇の選者から下ろし、代わって虚子自身が選者になったことを契機に東洋城は『ホトトギス』を離脱した。
1952年(昭和27年)東洋城は隠居を表明し、主宰を創刊時から選者として参加し、「国民新聞」の俳句欄で活躍していた門下の野村喜舟に譲る。24年間主宰を務める。句集『小石川』「紫川」などを発刊し、小倉北区の篠崎八幡神社には「鶯や紫川にひびく声」の句碑がある。(後略)
(名称の由来)1914年(大正3年)、東洋城が宮内省式部官のとき、大正天皇から俳句について聞かれ「渋柿のごときものにては候へど」と答えたことが有名となったことから。なお「渋柿」平成29年3月号の谷本清流氏の文章によれば、もう一説あり、かつての漱石の〈能もなき渋柿共や門の内〉という句に和して、東洋城が、〈能もなき渋柿共が誠かな〉という句を作っていたことから「渋柿」に決まったと言われている。≫(「ウィキペディア」)
(参考その二) 「俳誌 渋柿」の題籢(夏目漱石書)周辺

「公益社団法人 俳人協会・俳句文学館:賛助会員:渋柿」
https://www.haijinkyokai.jp/member/ini03/1299.html
(参考その三) 漱石の「渋柿」の句など(その周辺)
https://yahan.blog.ss-blog.jp/2023-10-02
[ 渋柿の下に稲こく夫婦かな 漱石(明28)
渋柿や寺の後の芋畠 漱石(明治28)
渋柿やあかの他人であるからは 漱石(明治30)
※能もなき渋柿共や門の内 漱石(明治31)
渋柿や長者と見えて岡の家 漱石(明治32)
渋柿やにくき庄屋の門構 漱石(明治34)
渋柿も熟れて王維の詩集哉 漱石(明治43)
「※能もなき渋柿共や門の内 漱石(明治31)」の句は、「能もなき教師とならんあら涼し 漱石(明治36)」の句と連動している。 ]
「漱石・東洋城・寅彦」(子規没後~漱石没まで)俳句管見(その十二) [漱石・東洋城・寅彦]
その十二「大正三年(一九一四)」
[漱石・四十七歳。大正3(1914)3月「私の個人主義」(『輔人会雑誌』)4月~8月 「こゝろ」]
2345 錦絵に此春雨や八代目
[八代目は、歌舞伎役者の八代目市川団十郎。美貌と愛敬で江戸の婦女子の絶大な人気を集めた。独身のまま三十二歳で自殺。その容姿は数多くの錦絵に描かれ後世にまで伝えられた。

「八代目市川團十郎涅槃図の見立絵、死絵」
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B8%82%E5%B7%9D%E5%9C%98%E5%8D%81%E9%83%8E_%288%E4%BB%A3%E7%9B%AE%29#/media/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:Journey_to_the_Nirvana,_ICHIKAWA_DanjuroVIII.jpg ]
2346 京楽の水注(みずさし)買ふや春の町
[京洛(きょうらく)は陶器の楽焼。千利休の指導で始まったといい、手でかたちを作り、低い火度で焼く。]
2348 春の夜や妻に教はる荻江節
[荻江節は三味線唄の節の一つ。江戸長唄に上方長唄の曲節を交え、長唄から一派をなした。十八世紀半ばに荻江霞友が興した。

恋川春町画・作『吉原大通会(よしわらだいつうえ)』(国立国会図書館デジタルコレクション)
http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/9892509
https://yahan.blog.ss-blog.jp/2019-05-03
(抜粋)
≪上記の図の花魁の右脇の立膝をしている方が、初代荻江露友のようで、その右脇の三味線を弾いているのは芸者衆であろう。そして、その芸者衆から左周りに花魁まで大通(お大尽)衆が並び、中央の荻江露友と正面向きになっている武士風の大通は、蝶四(朝四大尽=佐藤晩得)のように思われる。この場面は、荻江節の初代荻江露友より、自分の作詞した「九月がや」の節付けなどの指導を受けているように解して置きたい。≫
2362 小座敷の一中は誰梅に月
[一中(いっちゅう)は一中節を語る人。一中節は京浄瑠璃の一派。 ]
2366 売茶翁花に隠るゝ身なりけり
〔売茶翁=「売茶翁(ばいさおう、まいさおう、延宝3年5月16日(1675年7月8日) - 宝暦13年7月16日(1763年8月24日))は、江戸時代の黄檗宗の僧。煎茶の中興の祖。本名は柴山元昭、幼名は菊泉。法名は月海で、還俗後は高遊外(こうゆうがい)とも称した。」
(「ウィキペディア」)
https://yahan.blog.ss-blog.jp/2017-05-20
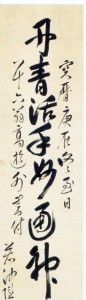
「一行書/丹青活手妙通神/売茶翁作」
「若冲は、この一行書の「丹青活手妙通神(丹青活手の妙神に通ず)」の七文字を二行にわかって印刻し、生涯にわたってそれを使用し続けた。」 ]
2373 経政の琵琶に御室の朧かな
[経政(つねまさ)は平経政。御室(おむろ)は仁和寺。謡曲「経政」を踏まえた句。『虞美人草(三)』に「御室の御所の春寒に、銘は給はる琵琶の風流は知る筈がない」とある。]
2380 ちらちらと陽炎立ちぬ猫の塚
[猫の塚は猫の墓である。
https://yahan.blog.ss-blog.jp/2023-08-18
「漱石『猫』句五句選
https://nekohon.jp/neko-wp/bunken-natsumesouseki/
里の子の猫加えけり涅槃像 (漱石・30歳「明治29年(1896)」)
行く年や猫うづくまる膝の上 (漱石・32歳「明治31年(1898)」)
朝がおの葉影に猫の目玉かな (漱石・39歳「明治38年(1905)」)
恋猫の眼(まなこ)ばかりに痩せにけり (漱石・41歳「明治40年(1907)」)
この下に稲妻起こる宵あらん(漱石・42歳「明治41年(1908)」)=『吾輩は猫である』のモデルとなった猫の墓に書いた句)

「あかざと黒猫図」(夏目漱石画/墨,軸/1311×323/箱書き:漱石書「あかざと黒猫」「大正三年七月漱石自題」)(「夏目漱石デジタルコレクション」)
https://www.kanabun.or.jp/souseki/list.html ]
2434 秋風の聞えぬ土に埋めてやりぬ(前書「わが犬のために」)

https://soseki-museum.jp/blog/blog_soseki/6614/
[「吾輩は犬派である-野村胡堂の証言-」
夏目漱石と言えば、何と言っても猫ですが、実は犬の方が好きだったというのは、
銭形平次で有名な作家・野村胡堂(1882-1963)の証言です。このことは、昭和34(1959)年に刊行された『胡堂百話』(角川書店)に載っているものです。
私が、はじめて夏目漱石氏の書斎を訪ねた時、漱石邸には猫はいなかった。(中略)
「どうも、すっかり有名になっちまいましてね。
(中略)私は、実は、好きじゃあないのです。
世間では、よっぽど猫好きのように思っているが、犬の方が、ずっと、好きです」(中略)
私は、はっきりと、この耳で聞いた。
野村胡堂、本名野村長一(おさかず)は、岩手県紫波郡彦部町出身で、東京帝国大学法科大学を退学後、報知新聞記者となり、昭和6(1931)年より銭形平次を主人公とする
数多くの長短篇を発表した時代小説家です。
『胡堂百話』は、胡堂77歳のときの書き下ろしのエッセイ集ですが、胡堂の記憶は本当なのでしょうか。
実は、胡堂が漱石邸を訪問したときの模様が、
『報知新聞(夕刊)』大正4(1915)年8月25・26日号の連載コラム「楯の半面」に、「夏目漱石氏 猫の話絵の話」として掲載されています。
当時、漱石は朝日新聞に「道草」を連載中。胡堂は33歳の報知新聞記者としての取材でした。
気爽(きさく)に、
「何でも問ふて下されば、お話しませう」と之には一寸困つた
「お好なものは、時々お書きになる物にも出て来るやうですが、例へば猫とか文鳥とか……」と云へば
「イヤ猫は飛んだ有名なものになりましたが、好きではありませんよ」と笑はれる。
尤も決してお嫌ではないが、何方(どちら)かと云へば先生は犬がお好き、
猫は夫人の方がお好なのだと云ふ、
「アノ猫から三代目のがツイ此間まで居りました」と語る、
遺憾ながら「吾輩の猫」の令孫にお目にかゝる事は出来なかつた。
この記事は、無署名原稿だったため、これまであまり注目されてきませんでしたが、
先の『胡堂百話』と内容がほとんど同じで、間違いなく胡堂が書いた記事であることがわかります。漱石の生存中に書かれた新聞記事として大変貴重なものです。
なお、荒正人氏の『漱石研究年表』では、記者名を特定していませんが、8月16日(月)から18日(水)までの取材と推定しています。この前年10月31日には、漱石自ら命名した犬のヘクトーが死んでいます。
「硝子戸の中」には、初めてもらわれてきた夜のこと、ジステンパーにかかって入院させたときのこと、犬の遊び仲間のことなどが、漱石のやさしい筆致で書かれています。
3代目の猫も「硝子戸の中」に登場し、皮膚病から回復した真っ黒な猫でしたが、
胡堂の取材までに亡くなったことがわかります。
普通、鏡子夫人は猫嫌いだったとされ、本人の証言もありますが、漱石の目からは、自分よりは猫好きに見えたのかもしれません。
胡堂による漱石への取材は、この後、絵画の話などに発展し、5分の取材予定が、1時間以上になり、胡堂は恐縮しながら辞去したと書いています。
50年後、胡堂はこのときのことを思い返したのでしょう。
「私は、ひょっとしたはずみで、猫の孫にも逢わず、漱石門下にも加わらなかったが、
あの風格は、忘れ難いものがある。」
胡堂が感じた強烈な印象と貴重な証言。夏目漱石は、犬派でした。(漱石山房記念館学芸員 今野慶信稿) ]
[東洋城・三十七歳。天皇よりのご沙汰により俳句三句を奉答した。その感慨を「渋柿のごときものにてはへど」と詠じた。]
元朝や二世に仕え式部官
[元旦詠である。「二世」は、明治天皇と大正天皇の二代に亘って仕えるの意。「式部官」は、「宮内省(現在は宮内庁)の式部職の職員で、祭典、儀礼、接待などを担当する官」で、東洋城は、式部官として、「明治天皇の崩御の大喪の儀」、そして、「大正天皇の即位式の大礼の儀」を奉仕した。]
長き夜や要塞穿つ鶴の嘴(前書「青島征戦」)
柿嚙むや青島の役に従はず(前書「壮丁田舎に肥ゆ」)
秋風世界に亡ぶ国一つ(怪魔独逸を呪ふ)
[『東洋城全句集(中巻)』所収の「年譜」に記載のある「天皇よりのご沙汰により俳句三句を奉答した」の三句は、この掲出の三句を指している。一句目の「青島(チンタオ)征戦」は、「中国山東省、山東半島の膠州(こうしゅう)湾に臨む港湾都市。1898年、ドイツが租借し、第一次大戦中は日本が占領した」時の戦いを指している。二句目は、戦地に従軍しないで、本土でのほんと過ごしたことの、東洋城の感慨の句なのであろう。三句目は、第一次世界大戦の相手国の「独逸」を指していて、前書の「怪魔」は東洋城の造語であろう。]
渋柿の如きものにては候へど(前書「さて仰せかしこまり奉るとて」)
[この句は、大正天皇の御下問に対して、上記の三句を奉答した際の、東洋城の感慨の句なのであろう。大正天皇は和歌に精通しており、その「和歌」(五七五七七)を「甘柿」とすると、「俳句」(五七五)は「渋柿」のようなもので、言外(七七)の余情を感じ取ることによって、「和歌」の「甘柿」になるというような意が思い浮かんでくる。]
[寅彦・三十七歳。一月、日本ろーま字社総会に出席。八月、高知の母と長女貞子を東京に連れ、同居する。]→[『寺田寅彦全集/文学篇/七巻』には収載句は無い。]
[漱石・四十七歳。大正3(1914)3月「私の個人主義」(『輔人会雑誌』)4月~8月 「こゝろ」]
2345 錦絵に此春雨や八代目
[八代目は、歌舞伎役者の八代目市川団十郎。美貌と愛敬で江戸の婦女子の絶大な人気を集めた。独身のまま三十二歳で自殺。その容姿は数多くの錦絵に描かれ後世にまで伝えられた。

「八代目市川團十郎涅槃図の見立絵、死絵」
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B8%82%E5%B7%9D%E5%9C%98%E5%8D%81%E9%83%8E_%288%E4%BB%A3%E7%9B%AE%29#/media/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:Journey_to_the_Nirvana,_ICHIKAWA_DanjuroVIII.jpg ]
2346 京楽の水注(みずさし)買ふや春の町
[京洛(きょうらく)は陶器の楽焼。千利休の指導で始まったといい、手でかたちを作り、低い火度で焼く。]
2348 春の夜や妻に教はる荻江節
[荻江節は三味線唄の節の一つ。江戸長唄に上方長唄の曲節を交え、長唄から一派をなした。十八世紀半ばに荻江霞友が興した。

恋川春町画・作『吉原大通会(よしわらだいつうえ)』(国立国会図書館デジタルコレクション)
http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/9892509
https://yahan.blog.ss-blog.jp/2019-05-03
(抜粋)
≪上記の図の花魁の右脇の立膝をしている方が、初代荻江露友のようで、その右脇の三味線を弾いているのは芸者衆であろう。そして、その芸者衆から左周りに花魁まで大通(お大尽)衆が並び、中央の荻江露友と正面向きになっている武士風の大通は、蝶四(朝四大尽=佐藤晩得)のように思われる。この場面は、荻江節の初代荻江露友より、自分の作詞した「九月がや」の節付けなどの指導を受けているように解して置きたい。≫
2362 小座敷の一中は誰梅に月
[一中(いっちゅう)は一中節を語る人。一中節は京浄瑠璃の一派。 ]
2366 売茶翁花に隠るゝ身なりけり
〔売茶翁=「売茶翁(ばいさおう、まいさおう、延宝3年5月16日(1675年7月8日) - 宝暦13年7月16日(1763年8月24日))は、江戸時代の黄檗宗の僧。煎茶の中興の祖。本名は柴山元昭、幼名は菊泉。法名は月海で、還俗後は高遊外(こうゆうがい)とも称した。」
(「ウィキペディア」)
https://yahan.blog.ss-blog.jp/2017-05-20
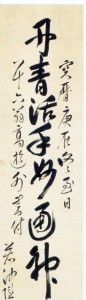
「一行書/丹青活手妙通神/売茶翁作」
「若冲は、この一行書の「丹青活手妙通神(丹青活手の妙神に通ず)」の七文字を二行にわかって印刻し、生涯にわたってそれを使用し続けた。」 ]
2373 経政の琵琶に御室の朧かな
[経政(つねまさ)は平経政。御室(おむろ)は仁和寺。謡曲「経政」を踏まえた句。『虞美人草(三)』に「御室の御所の春寒に、銘は給はる琵琶の風流は知る筈がない」とある。]
2380 ちらちらと陽炎立ちぬ猫の塚
[猫の塚は猫の墓である。
https://yahan.blog.ss-blog.jp/2023-08-18
「漱石『猫』句五句選
https://nekohon.jp/neko-wp/bunken-natsumesouseki/
里の子の猫加えけり涅槃像 (漱石・30歳「明治29年(1896)」)
行く年や猫うづくまる膝の上 (漱石・32歳「明治31年(1898)」)
朝がおの葉影に猫の目玉かな (漱石・39歳「明治38年(1905)」)
恋猫の眼(まなこ)ばかりに痩せにけり (漱石・41歳「明治40年(1907)」)
この下に稲妻起こる宵あらん(漱石・42歳「明治41年(1908)」)=『吾輩は猫である』のモデルとなった猫の墓に書いた句)

「あかざと黒猫図」(夏目漱石画/墨,軸/1311×323/箱書き:漱石書「あかざと黒猫」「大正三年七月漱石自題」)(「夏目漱石デジタルコレクション」)
https://www.kanabun.or.jp/souseki/list.html ]
2434 秋風の聞えぬ土に埋めてやりぬ(前書「わが犬のために」)

https://soseki-museum.jp/blog/blog_soseki/6614/
[「吾輩は犬派である-野村胡堂の証言-」
夏目漱石と言えば、何と言っても猫ですが、実は犬の方が好きだったというのは、
銭形平次で有名な作家・野村胡堂(1882-1963)の証言です。このことは、昭和34(1959)年に刊行された『胡堂百話』(角川書店)に載っているものです。
私が、はじめて夏目漱石氏の書斎を訪ねた時、漱石邸には猫はいなかった。(中略)
「どうも、すっかり有名になっちまいましてね。
(中略)私は、実は、好きじゃあないのです。
世間では、よっぽど猫好きのように思っているが、犬の方が、ずっと、好きです」(中略)
私は、はっきりと、この耳で聞いた。
野村胡堂、本名野村長一(おさかず)は、岩手県紫波郡彦部町出身で、東京帝国大学法科大学を退学後、報知新聞記者となり、昭和6(1931)年より銭形平次を主人公とする
数多くの長短篇を発表した時代小説家です。
『胡堂百話』は、胡堂77歳のときの書き下ろしのエッセイ集ですが、胡堂の記憶は本当なのでしょうか。
実は、胡堂が漱石邸を訪問したときの模様が、
『報知新聞(夕刊)』大正4(1915)年8月25・26日号の連載コラム「楯の半面」に、「夏目漱石氏 猫の話絵の話」として掲載されています。
当時、漱石は朝日新聞に「道草」を連載中。胡堂は33歳の報知新聞記者としての取材でした。
気爽(きさく)に、
「何でも問ふて下されば、お話しませう」と之には一寸困つた
「お好なものは、時々お書きになる物にも出て来るやうですが、例へば猫とか文鳥とか……」と云へば
「イヤ猫は飛んだ有名なものになりましたが、好きではありませんよ」と笑はれる。
尤も決してお嫌ではないが、何方(どちら)かと云へば先生は犬がお好き、
猫は夫人の方がお好なのだと云ふ、
「アノ猫から三代目のがツイ此間まで居りました」と語る、
遺憾ながら「吾輩の猫」の令孫にお目にかゝる事は出来なかつた。
この記事は、無署名原稿だったため、これまであまり注目されてきませんでしたが、
先の『胡堂百話』と内容がほとんど同じで、間違いなく胡堂が書いた記事であることがわかります。漱石の生存中に書かれた新聞記事として大変貴重なものです。
なお、荒正人氏の『漱石研究年表』では、記者名を特定していませんが、8月16日(月)から18日(水)までの取材と推定しています。この前年10月31日には、漱石自ら命名した犬のヘクトーが死んでいます。
「硝子戸の中」には、初めてもらわれてきた夜のこと、ジステンパーにかかって入院させたときのこと、犬の遊び仲間のことなどが、漱石のやさしい筆致で書かれています。
3代目の猫も「硝子戸の中」に登場し、皮膚病から回復した真っ黒な猫でしたが、
胡堂の取材までに亡くなったことがわかります。
普通、鏡子夫人は猫嫌いだったとされ、本人の証言もありますが、漱石の目からは、自分よりは猫好きに見えたのかもしれません。
胡堂による漱石への取材は、この後、絵画の話などに発展し、5分の取材予定が、1時間以上になり、胡堂は恐縮しながら辞去したと書いています。
50年後、胡堂はこのときのことを思い返したのでしょう。
「私は、ひょっとしたはずみで、猫の孫にも逢わず、漱石門下にも加わらなかったが、
あの風格は、忘れ難いものがある。」
胡堂が感じた強烈な印象と貴重な証言。夏目漱石は、犬派でした。(漱石山房記念館学芸員 今野慶信稿) ]
[東洋城・三十七歳。天皇よりのご沙汰により俳句三句を奉答した。その感慨を「渋柿のごときものにてはへど」と詠じた。]
元朝や二世に仕え式部官
[元旦詠である。「二世」は、明治天皇と大正天皇の二代に亘って仕えるの意。「式部官」は、「宮内省(現在は宮内庁)の式部職の職員で、祭典、儀礼、接待などを担当する官」で、東洋城は、式部官として、「明治天皇の崩御の大喪の儀」、そして、「大正天皇の即位式の大礼の儀」を奉仕した。]
長き夜や要塞穿つ鶴の嘴(前書「青島征戦」)
柿嚙むや青島の役に従はず(前書「壮丁田舎に肥ゆ」)
秋風世界に亡ぶ国一つ(怪魔独逸を呪ふ)
[『東洋城全句集(中巻)』所収の「年譜」に記載のある「天皇よりのご沙汰により俳句三句を奉答した」の三句は、この掲出の三句を指している。一句目の「青島(チンタオ)征戦」は、「中国山東省、山東半島の膠州(こうしゅう)湾に臨む港湾都市。1898年、ドイツが租借し、第一次大戦中は日本が占領した」時の戦いを指している。二句目は、戦地に従軍しないで、本土でのほんと過ごしたことの、東洋城の感慨の句なのであろう。三句目は、第一次世界大戦の相手国の「独逸」を指していて、前書の「怪魔」は東洋城の造語であろう。]
渋柿の如きものにては候へど(前書「さて仰せかしこまり奉るとて」)
[この句は、大正天皇の御下問に対して、上記の三句を奉答した際の、東洋城の感慨の句なのであろう。大正天皇は和歌に精通しており、その「和歌」(五七五七七)を「甘柿」とすると、「俳句」(五七五)は「渋柿」のようなもので、言外(七七)の余情を感じ取ることによって、「和歌」の「甘柿」になるというような意が思い浮かんでくる。]
[寅彦・三十七歳。一月、日本ろーま字社総会に出席。八月、高知の母と長女貞子を東京に連れ、同居する。]→[『寺田寅彦全集/文学篇/七巻』には収載句は無い。]
「漱石・東洋城・寅彦」(子規没後~漱石没まで)俳句管見(その十一) [漱石・東洋城・寅彦]
その十一「大正二年(一九一三)」
[漱石・四十六歳。大正2(1913)2月『社会と自分』。三月より五月まで、胃潰瘍の三度目の再発で病臥する。病中より、楽しみに絵筆を執る。 ]
2307 人形も馬もうごかぬ長閑さよ
2308 菊一本画いて君の佳節哉
2309 四五本の竹をあつめて月夜哉
2310 萩の粥月待つ庵となりにけり
2311 葉鶏頭高さ五尺に育てけり

夏目漱石画「菊図」(「みやこ町歴史民俗博物館/WEB博物館「みやこ町遺産」/小宮豊隆資料」)
http://miyako-museum.jp/list/detail.php?uniq_id=107
≪小宮豊隆(1884-1966)は、みやこ町犀川久富出身のドイツ文学者・文芸評論家です。夏目漱石の門下として詳細な漱石研究や、今なお刊行が続く漱石全集を監修したことでも知られています。平成25年(2013)以降、1000点近い資料が小宮氏遺族から故郷のみやこ町に寄贈されました。みやこ町ではこれを「小宮豊隆資料」と名付け、博物館内に記念展示室を設け、小宮の人生と業績の紹介・顕彰につとめています。≫
2308 菊一本画いて君の佳節哉
[この句の「君」は、上記の「菊図」(「みやこ町歴史民俗博物館/小宮豊隆資料」)と対応させると、「小宮豊隆」(「漱石の『三四郎』のモデルとしても知られる。俳号の逢里雨(ほうりう)は、豊隆の音読み(ほうりゅう)に別の字を宛てたもの」)の、その「佳節」「(明治44年/1911/1月郷里にて結婚」)祝いのものなのかも知れない。]
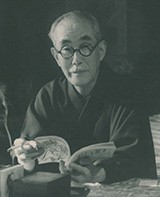
「小宮豊隆(俳号・逢里雨)」(「みやこ町歴史民俗博物館/小宮豊隆資料」)
https://adeac.jp/miyako-hf-mus/top/
[小宮豊隆氏(年譜)
明治17年 1884 3月7日福岡県仲津郡久富村(現犀川町久富)で生まれる。
明治20年 1887 父・弥三郎の転勤にともない大和郡山へ移る。
明治24年 1891 帰郷し、豊津尋常小学校に転校。
明治27年 1894 5月22日父・弥三郎死去。
明治30年 1897 豊津高等小学校卒業。福岡県立尋常中学校に入学。
明治35年 1902 豊津中学校卒業。7月に第一高等学校入学。
明治38年 1905 7月第一高等学校卒業。9月東京帝国大学文学部独文科に入学。従兄の犬塚武夫の紹介で夏目漱石の知遇を得、在学中の保証人を依頼する。大学ではドイツ語の講義とともに、漱石の「文学評論」やシェイクスピアの講義も聴講する。
明治41年 1908 7月東京帝国大学卒業。
明治42年 1909 4月慶応義塾大学に文学部が創設され、講師となる。このころから、ロシア文学への興味が深まる。朝日新聞に文芸欄が創設され、漱石の手伝いをする。
明治44年 1911 1月郷里にて結婚。
大正5年 1916 東京医学専門学校講師となる。12月9日夏目漱石死去。
大正6年 1917 「漱石全集」の編集にとりかかる。
大正9年 1920 海軍大学校嘱託教授となる。
大正10年 1921 芭蕉研究会に参加。
大正11年 1922 4月法政大学教授となる。東北帝国大学法文学部独文講座を引き受ける。
大正12年 1923 3月渡欧。5月にベルリンに到着し、以後欧州各国を歴訪。
大正13年 1924 帰国。東北帝国大学教授となる。
大正15年 1926 芭蕉俳諧研究会を始める。
昭和21年 1946 東京音楽学校(現東京芸術大学)校長となる。教育刷新委員・国語審議会委員となる。
昭和22年 1947 6月都民劇場運営委員長となる。
昭和23年 1948 11月東北帝国大学名誉教授の称号を贈られる。
昭和24年 1949 6月東京音楽学校々長辞職。東京女子大学講師・俳文学会々長となる。
昭和25年 1950 4月学習院大学教授となる。以降、学習院では文学部長・女子短期大学々長をつとめる。12月文化財専門審議会専門委員となる。
昭和26年 1951 10月学士院会員となる。
昭和29年 1954 5月著書「夏目漱石」で芸術院賞受賞。
昭和30年 1955 4月財団法人都民劇場会長。7月国立劇場設立準備協議会々長を委嘱される。
昭和32年 1957 3月学習院退職。4月東京都教育委員となる。
昭和33年 1958 「世阿弥の芸術」を御進講する。
昭和34年 1959 東京都教育委員辞任。
昭和35年 1960 東大病院に入院。手術を受ける。
昭和36年 1961 喜寿・金婚式。
昭和40年 1965 3月都民劇場会長辞任。同名誉会長となる。
昭和41年 1966 5月3日午前4時、肺炎のため東京都杉並区の自宅にて逝去。享年82歳。東京南多摩霊園と豊津町峯高寺に分骨埋葬。
(「篷里雨句集」巻末年譜及び小宮里子氏のご教示により作成) )
[東洋城・三十六歳。筑紫明石町六十一番地へ移転。]
旧作の松は雪より新にて(大正二年作)
[前書に「古(ふる)き新(あたらし)き弁
虚子曰く「・・・それでは陳腐を主張する者と誤解される恐があらう」、城曰く「だから古くといはず古臭くといい又或意味に於てと小書付にして置いた」。。虚曰く「俳句の関する範囲内で可成新しくというた方が穏当ぢゃないか」、城曰く「そんな事は言を俟たぬ事だ。元禄天明の句を見て明治の句をなし去年の句を措いて今年の句を作り昨日も作つてゐたのに今日も亦俳句を止めぬのが、皆後の前に異り今の作に同じからぬ新しきを欲求する故に続いて俳句に従事してゐるのである。俳句を続けてやるということが即ち句々の新境を所幾する事ではないか。取立てていふには余りに分りきつた事だ。星学者が望星鏡の下に寝て他所目には一生同じ事を繰返してゐるかの様に毎日毎日空を仰いでゐるのも畢竟毎日毎日香刻一刻の新しきを窺う為めである。俳句我等の俳句は研究的、創作的である。遊戯でも玩弄物でもない以上之を続けるといふ事其事が新しからむとするに外ならぬ事は明らかである。何の御苦労にも事々しく新し呼ばはりする必要があろう」。虚曰く、「それならよいが衆人の誤解き引起させぬ為めに新しくといふ事をいうてもいいぢやないか」。城曰く「イヤそれは時宜ではない、迷ふた者が新しくと誤用して迷ふ者の道標としてゐる当今に又新しくといふては迷ふ者にとつて差別がつかぬ、新しくといふ事が言ふまでもない当然の事である以上いつそ古めかしくいうて俳句の本体を教へてやるのもよかろ」。虚曰く「どうして?」]
[寅彦・三十六歳。八月、父が死亡する。十月、従六位に叙せられる。]→[『寺田寅彦全集/文学篇/七巻』には収載句は無い。]
(参考) 明治俳壇の喧囂(けんごう)な終局―│虚子の俳壇復帰とその時代」―(田辺知季稿)周辺
https://www.jstage.jst.go.jp/article/nihonkindaibungaku/103/0/103_1/_pdf/-char/ja
(抜粋)
[ 現下の俳壇には勗(つと)めて近代の思想趣味に接触せんとする者、極力古典趣味に生きんとする者との二個の潮流がある。前者は取りも直さず日本及日本人を中心とせる碧梧桐の一派で所謂新傾向の一団である、後者は即ち国民俳壇に依る所謂古き新派を代表せる東洋城の一派である。]
[ あるいは国民俳壇の東洋城はどうか。当時の彼は旧弊とみなされがちな自派の句風を擁護するなかで、 「いつまでも元禄でなく明治であり大正である事を忘れて居らぬが故に、或意味にて、我等は殊更古臭く作る事をほ句の使命と思ふ」と語っている(大一・一二・三『国民新聞』俳句欄)。
とはいえ、虚子との対話を録した「俳諧古き新き弁(上)」(大一・一二・八『国民新聞』 )
によると、東洋城はあくまでも「句々の新境を庶幾する」からこそ句作を続けるのであり、単純な「古さ」を是認するわけではないという。そもそも「俳句は出来上つた詩」、「方向の定まつた文学」である以上( 「俳諧古き新き弁(下) 」、大一・一二・一、同前、)その枠内で「新境」を模索すべきだというのだ。
さらに先述の俳誌『ツボミ』では、田中蛇湖が右の東洋城の一文を「有益の文字」と認め、 「只々新しひあたらしひと云つて、芸術の本領を没却し、彼の発明家者流などと齷齪日を終るべけんやである」と同調している( 「筆のまにまに㈦」、、大二・一・二〇、三巻一号。)
また木内螢覇郎も、 「古き形式を守り古き約束を固守し、大正式文明に後れまじと古き中より、新しき十七字を形成するこそ所謂新俳句と云ふべけれ」と謳っている( 「蒙御免」 、
大二・三・二〇、三巻三号。)
こうした論調は当然『ホトトギス』俳壇の再興と共鳴しており、「ホトヽギスの雑吟を読めば読む程そぞろに爽快を覚ゆ」(同前)や、「虚子氏の平明調を唱導してより句界の特に活気を引き興し候は喜はしき事に候」(秋元虚受「巻末録」、同前)といった文言も認められる。さらには、「新らしき思想を練り所謂穏健なる平明調の鼓吹に努め」ることこそが「本誌兼ての希望なの」だと表明し(無署名「告白」、大二・七・二〇、三巻六号)、「ツボミは真面目に健やかなる思想の下に、所謂平明調を鼓吹する事に決し候」と宣言している(虚受「巻
末録」、同前。) ]
[ 虚子はこうした状況の下、「『新』といふ言葉」に「心を躍らす」 「青年」(虚子「俳話」 、大一・一二・二『東京朝日新聞』朝刊)には迎合しない「守旧派」として俳句に復帰する。
ただし最後に付言しておくと、彼が提示する俳句像は必ずしも時流に真っ向から逆行しているわけではない。当時の虚子は「余が俳句の中には芸術品としてイプセンやハウプトマン位に比肩すべきものは沢山ある」と自負し、「これから何年俳句を作つたとて、俳句の文学的価値のレベルは高まりはし無い」と論じている(前掲「鎌倉日記」、、明四五・六・一)。
既存の俳句史では軽視されているが、明治四十年代の『ホトトギス』では脚本や劇評な
どを掲載し、文芸協会の改組などに沸く文壇の演劇熱に乗じていた。ここでは、当時劇界を中心に文壇で広く仰望された二人の名を挙げることで、俳句をそれに匹敵する文芸として演出しているのだ。]
[ 明治末頃から大正初頭の新傾向派、特に碧梧桐の下から自立していった乙字や井泉水は、最先端の世界的な文芸思潮に共鳴しながら各々が理想とする俳句像を確立していく。対する虚子は、それとは別の経路で俳句を「世界の文芸」と結びつけ、季題趣味によって「旧」に止まる守旧派を価値づけている。周知のように、後年の彼は俳句を「花鳥諷詠の文学」、 「我国にひとり存在するところの特異な文学」と位置づけつつ、「花鳥諷詠の文学(詩)が存在してゐるといふことは、我が国民の誇りとすべきもの」だと語っている(『俳句への道』 、一九五五・一、岩波新書、「俳句への道」 )。俳句の「正統」として信奉される「花鳥諷詠」は、「国民性」を意識した俳壇復帰の延長線上から立ち現われてくることとなる。]
[漱石・四十六歳。大正2(1913)2月『社会と自分』。三月より五月まで、胃潰瘍の三度目の再発で病臥する。病中より、楽しみに絵筆を執る。 ]
2307 人形も馬もうごかぬ長閑さよ
2308 菊一本画いて君の佳節哉
2309 四五本の竹をあつめて月夜哉
2310 萩の粥月待つ庵となりにけり
2311 葉鶏頭高さ五尺に育てけり

夏目漱石画「菊図」(「みやこ町歴史民俗博物館/WEB博物館「みやこ町遺産」/小宮豊隆資料」)
http://miyako-museum.jp/list/detail.php?uniq_id=107
≪小宮豊隆(1884-1966)は、みやこ町犀川久富出身のドイツ文学者・文芸評論家です。夏目漱石の門下として詳細な漱石研究や、今なお刊行が続く漱石全集を監修したことでも知られています。平成25年(2013)以降、1000点近い資料が小宮氏遺族から故郷のみやこ町に寄贈されました。みやこ町ではこれを「小宮豊隆資料」と名付け、博物館内に記念展示室を設け、小宮の人生と業績の紹介・顕彰につとめています。≫
2308 菊一本画いて君の佳節哉
[この句の「君」は、上記の「菊図」(「みやこ町歴史民俗博物館/小宮豊隆資料」)と対応させると、「小宮豊隆」(「漱石の『三四郎』のモデルとしても知られる。俳号の逢里雨(ほうりう)は、豊隆の音読み(ほうりゅう)に別の字を宛てたもの」)の、その「佳節」「(明治44年/1911/1月郷里にて結婚」)祝いのものなのかも知れない。]
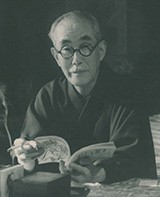
「小宮豊隆(俳号・逢里雨)」(「みやこ町歴史民俗博物館/小宮豊隆資料」)
https://adeac.jp/miyako-hf-mus/top/
[小宮豊隆氏(年譜)
明治17年 1884 3月7日福岡県仲津郡久富村(現犀川町久富)で生まれる。
明治20年 1887 父・弥三郎の転勤にともない大和郡山へ移る。
明治24年 1891 帰郷し、豊津尋常小学校に転校。
明治27年 1894 5月22日父・弥三郎死去。
明治30年 1897 豊津高等小学校卒業。福岡県立尋常中学校に入学。
明治35年 1902 豊津中学校卒業。7月に第一高等学校入学。
明治38年 1905 7月第一高等学校卒業。9月東京帝国大学文学部独文科に入学。従兄の犬塚武夫の紹介で夏目漱石の知遇を得、在学中の保証人を依頼する。大学ではドイツ語の講義とともに、漱石の「文学評論」やシェイクスピアの講義も聴講する。
明治41年 1908 7月東京帝国大学卒業。
明治42年 1909 4月慶応義塾大学に文学部が創設され、講師となる。このころから、ロシア文学への興味が深まる。朝日新聞に文芸欄が創設され、漱石の手伝いをする。
明治44年 1911 1月郷里にて結婚。
大正5年 1916 東京医学専門学校講師となる。12月9日夏目漱石死去。
大正6年 1917 「漱石全集」の編集にとりかかる。
大正9年 1920 海軍大学校嘱託教授となる。
大正10年 1921 芭蕉研究会に参加。
大正11年 1922 4月法政大学教授となる。東北帝国大学法文学部独文講座を引き受ける。
大正12年 1923 3月渡欧。5月にベルリンに到着し、以後欧州各国を歴訪。
大正13年 1924 帰国。東北帝国大学教授となる。
大正15年 1926 芭蕉俳諧研究会を始める。
昭和21年 1946 東京音楽学校(現東京芸術大学)校長となる。教育刷新委員・国語審議会委員となる。
昭和22年 1947 6月都民劇場運営委員長となる。
昭和23年 1948 11月東北帝国大学名誉教授の称号を贈られる。
昭和24年 1949 6月東京音楽学校々長辞職。東京女子大学講師・俳文学会々長となる。
昭和25年 1950 4月学習院大学教授となる。以降、学習院では文学部長・女子短期大学々長をつとめる。12月文化財専門審議会専門委員となる。
昭和26年 1951 10月学士院会員となる。
昭和29年 1954 5月著書「夏目漱石」で芸術院賞受賞。
昭和30年 1955 4月財団法人都民劇場会長。7月国立劇場設立準備協議会々長を委嘱される。
昭和32年 1957 3月学習院退職。4月東京都教育委員となる。
昭和33年 1958 「世阿弥の芸術」を御進講する。
昭和34年 1959 東京都教育委員辞任。
昭和35年 1960 東大病院に入院。手術を受ける。
昭和36年 1961 喜寿・金婚式。
昭和40年 1965 3月都民劇場会長辞任。同名誉会長となる。
昭和41年 1966 5月3日午前4時、肺炎のため東京都杉並区の自宅にて逝去。享年82歳。東京南多摩霊園と豊津町峯高寺に分骨埋葬。
(「篷里雨句集」巻末年譜及び小宮里子氏のご教示により作成) )
[東洋城・三十六歳。筑紫明石町六十一番地へ移転。]
旧作の松は雪より新にて(大正二年作)
[前書に「古(ふる)き新(あたらし)き弁
虚子曰く「・・・それでは陳腐を主張する者と誤解される恐があらう」、城曰く「だから古くといはず古臭くといい又或意味に於てと小書付にして置いた」。。虚曰く「俳句の関する範囲内で可成新しくというた方が穏当ぢゃないか」、城曰く「そんな事は言を俟たぬ事だ。元禄天明の句を見て明治の句をなし去年の句を措いて今年の句を作り昨日も作つてゐたのに今日も亦俳句を止めぬのが、皆後の前に異り今の作に同じからぬ新しきを欲求する故に続いて俳句に従事してゐるのである。俳句を続けてやるということが即ち句々の新境を所幾する事ではないか。取立てていふには余りに分りきつた事だ。星学者が望星鏡の下に寝て他所目には一生同じ事を繰返してゐるかの様に毎日毎日空を仰いでゐるのも畢竟毎日毎日香刻一刻の新しきを窺う為めである。俳句我等の俳句は研究的、創作的である。遊戯でも玩弄物でもない以上之を続けるといふ事其事が新しからむとするに外ならぬ事は明らかである。何の御苦労にも事々しく新し呼ばはりする必要があろう」。虚曰く、「それならよいが衆人の誤解き引起させぬ為めに新しくといふ事をいうてもいいぢやないか」。城曰く「イヤそれは時宜ではない、迷ふた者が新しくと誤用して迷ふ者の道標としてゐる当今に又新しくといふては迷ふ者にとつて差別がつかぬ、新しくといふ事が言ふまでもない当然の事である以上いつそ古めかしくいうて俳句の本体を教へてやるのもよかろ」。虚曰く「どうして?」]
[寅彦・三十六歳。八月、父が死亡する。十月、従六位に叙せられる。]→[『寺田寅彦全集/文学篇/七巻』には収載句は無い。]
(参考) 明治俳壇の喧囂(けんごう)な終局―│虚子の俳壇復帰とその時代」―(田辺知季稿)周辺
https://www.jstage.jst.go.jp/article/nihonkindaibungaku/103/0/103_1/_pdf/-char/ja
(抜粋)
[ 現下の俳壇には勗(つと)めて近代の思想趣味に接触せんとする者、極力古典趣味に生きんとする者との二個の潮流がある。前者は取りも直さず日本及日本人を中心とせる碧梧桐の一派で所謂新傾向の一団である、後者は即ち国民俳壇に依る所謂古き新派を代表せる東洋城の一派である。]
[ あるいは国民俳壇の東洋城はどうか。当時の彼は旧弊とみなされがちな自派の句風を擁護するなかで、 「いつまでも元禄でなく明治であり大正である事を忘れて居らぬが故に、或意味にて、我等は殊更古臭く作る事をほ句の使命と思ふ」と語っている(大一・一二・三『国民新聞』俳句欄)。
とはいえ、虚子との対話を録した「俳諧古き新き弁(上)」(大一・一二・八『国民新聞』 )
によると、東洋城はあくまでも「句々の新境を庶幾する」からこそ句作を続けるのであり、単純な「古さ」を是認するわけではないという。そもそも「俳句は出来上つた詩」、「方向の定まつた文学」である以上( 「俳諧古き新き弁(下) 」、大一・一二・一、同前、)その枠内で「新境」を模索すべきだというのだ。
さらに先述の俳誌『ツボミ』では、田中蛇湖が右の東洋城の一文を「有益の文字」と認め、 「只々新しひあたらしひと云つて、芸術の本領を没却し、彼の発明家者流などと齷齪日を終るべけんやである」と同調している( 「筆のまにまに㈦」、、大二・一・二〇、三巻一号。)
また木内螢覇郎も、 「古き形式を守り古き約束を固守し、大正式文明に後れまじと古き中より、新しき十七字を形成するこそ所謂新俳句と云ふべけれ」と謳っている( 「蒙御免」 、
大二・三・二〇、三巻三号。)
こうした論調は当然『ホトトギス』俳壇の再興と共鳴しており、「ホトヽギスの雑吟を読めば読む程そぞろに爽快を覚ゆ」(同前)や、「虚子氏の平明調を唱導してより句界の特に活気を引き興し候は喜はしき事に候」(秋元虚受「巻末録」、同前)といった文言も認められる。さらには、「新らしき思想を練り所謂穏健なる平明調の鼓吹に努め」ることこそが「本誌兼ての希望なの」だと表明し(無署名「告白」、大二・七・二〇、三巻六号)、「ツボミは真面目に健やかなる思想の下に、所謂平明調を鼓吹する事に決し候」と宣言している(虚受「巻
末録」、同前。) ]
[ 虚子はこうした状況の下、「『新』といふ言葉」に「心を躍らす」 「青年」(虚子「俳話」 、大一・一二・二『東京朝日新聞』朝刊)には迎合しない「守旧派」として俳句に復帰する。
ただし最後に付言しておくと、彼が提示する俳句像は必ずしも時流に真っ向から逆行しているわけではない。当時の虚子は「余が俳句の中には芸術品としてイプセンやハウプトマン位に比肩すべきものは沢山ある」と自負し、「これから何年俳句を作つたとて、俳句の文学的価値のレベルは高まりはし無い」と論じている(前掲「鎌倉日記」、、明四五・六・一)。
既存の俳句史では軽視されているが、明治四十年代の『ホトトギス』では脚本や劇評な
どを掲載し、文芸協会の改組などに沸く文壇の演劇熱に乗じていた。ここでは、当時劇界を中心に文壇で広く仰望された二人の名を挙げることで、俳句をそれに匹敵する文芸として演出しているのだ。]
[ 明治末頃から大正初頭の新傾向派、特に碧梧桐の下から自立していった乙字や井泉水は、最先端の世界的な文芸思潮に共鳴しながら各々が理想とする俳句像を確立していく。対する虚子は、それとは別の経路で俳句を「世界の文芸」と結びつけ、季題趣味によって「旧」に止まる守旧派を価値づけている。周知のように、後年の彼は俳句を「花鳥諷詠の文学」、 「我国にひとり存在するところの特異な文学」と位置づけつつ、「花鳥諷詠の文学(詩)が存在してゐるといふことは、我が国民の誇りとすべきもの」だと語っている(『俳句への道』 、一九五五・一、岩波新書、「俳句への道」 )。俳句の「正統」として信奉される「花鳥諷詠」は、「国民性」を意識した俳壇復帰の延長線上から立ち現われてくることとなる。]
漱石・東洋城・寅彦」(子規没後~漱石没まで)俳句管見(その十) [漱石・東洋城・寅彦]
その十「明治四十五年・大正元年(一九一二)」
[漱石・四十五歳。明治45・大正元(1912) 1月~4月「彼岸過迄」12月~翌11月「行人」]
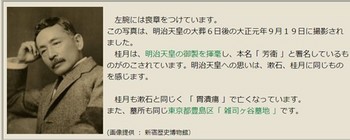
「夏目漱石」(監修・大町芳章/参考・高橋正著「 評伝 大町桂月 」)
http://keigetsu1869.la.coocan.jp/hito/souseki/souseki.html
2300 厳かに松明振り行くや星月夜(前書「奉送(一句)」、松根東洋城宛書簡)
[東洋城宛の書簡には「奉悼や葬送の句はどうも出来ないね。天子様の悼亡の句なんか作つた事がないから仕方がない」とある。明治天皇は七月三十日に逝去。]
2302 秋風や屠られに行く牛の尻(松根東洋城書簡)
[東洋城宛書簡には「一週間にて退院の筈、十句集も気が乗らずそれなりなり。発句を書いてくれと所望されると作らねばならぬと思ふが、左もなきときは作る了見も出ず済度致しがたき俗物と相成候」とある。九月二十六日佐藤診療所に入院、痔の手術を受けた。]
[東洋城・三十五歳。明治天皇崩御、式部官として大喪の儀奉仕。]

「松根東洋城」(「明治四十四年・『漱石夫妻 愛のかたち』より「森成麟造医師送別会(?)」の部分拡大図像)
https://blog.rnb.co.jp/sakanoue/?p=1062
明治天皇崩御矣嗟呼(ああ)暑退き栗実る(前書「明治天皇崩御 十二句」)
この秋や供奉(くぶ)に泣かるゝ太刀冠(同上)
菊咲くや仮の名ながら菊花節(同上)
和歌の君に俳諧の臣や菊花節(同上)
大輪の菊に御偉業や菊花節(同上)
(以下、七句「略」)
[寅彦・三十五歳。四月、中央気象台の全国気象協議会において海洋学の集中講義を開く。五月、次女の弥生誕生。十一月、日本天文学例会において「地球内部の構造に就て」を講演する。]→[『寺田寅彦全集/文学篇/七巻』には収載句は無い。]→[『寺田寅彦全集/文学篇/七巻』には収載句は無い。]
(参考) 「明治天皇大喪儀」周辺

「明治天皇大喪儀絵巻物1~4」(「宮内公文書館所蔵」)
https://www.archives.go.jp/exhibition/digital/modean_state/contents/imperial-mourning/photo/taimo/pn04.html
http://web.sanin.jp/p/sousen/1/3/1/14/11/
[明治天皇大喪(大正1年9月)
明治天皇の大喪は、9月13日から3日間にわたり行なわれた。大喪費用は当時の金で150万円であった。午後8時、1発の号砲を合図に明治天皇の霊柩を乗せた轜車(じしゃ)は、78対の松明(たいまつ)に導かれて宮殿を出発。轜車が青山の葬場殿に到着したのは夜の10時56分。葬場殿の儀が終わったのは午前零時45分である。夜間の葬列のため、その準備も大変だった。
皇居の正面の二重橋から西の丸の馬場先門までの間には、約20メートル間隔で高さ6メートルの根越榊10対を立て、その土台には約45センチの白木の台に白木の枠を設けた。榊の梢からは黒白、あるいは濃い鼠色の帛(絹布)を垂らし、榊と榊の間に約18メートルの間隔で、高さ3メートルのガスのかがり火を20対設置した。このかがり火は赤松の丸太3本を組み合わせて作ったもので、これにしめ縄を張り、さらに榊のかがり火の後方には10対のアーク灯を点じ、辺り一帯を真昼のように照らした。馬場先門からは36メートルおきに9メートルの柱を立て、その上にアーク灯をつけた。その間に18メートルおきに、黒白の布を巻いた間柱を立て、頂上から幡旗をつるし、途中で緑葉の環を付けた。さらに柱と柱の間には銀色、あるいは黒白の喪飾りを施した。麹町大通りは車道と人道との間に黒の幔幕を張り、各戸に白張りの提灯を掲げた。
青山大葬場入口左右には、擦りガラスをはめた高さ8メートルの白木作りの春日形大燈篭一対を立て、総門の左右には清涼殿形の吊り燈篭4個を立てて、夜間の葬列にふさわしい備えをした。
乃木大将夫妻の葬儀(大正1年9月)
明治天皇大葬の当夜、霊柩発引の号砲を合図に自刃を遂げた乃木大将夫妻の葬儀が9月18日に行なわれた。午後3時赤坂の自宅を出棺、青山斎場に於て神式の葬儀を執り行なった。午後2時半にラッパの合図第1声とともに、前駆並びに花旗の行列を整え、第2声で大将の棺を載せた砲車、及び夫人の棺を載せた馬車の出発準備に取り掛かり、葬儀係はいずれも行列位置についた。次ぎに会葬者一同出発準備をして、第3声「気を付け前へ」の合図とともに行進が始まった。午後4時、祭式が始まり、4時25分、道路に整列した1個連隊の儀杖兵は、「命を棄てて」のラッパの吹奏を終えて、一斉に銃口を天に向け3発の弔銃を発射した。
午後5時頃より一般会葬者の参拝が始まった。葬儀委員の3名は椅子に登って「礼拝が済みますれば、すぐにご退出を願います。後がたくさんでございますから、何とぞ早くご退出を願います」と声を嗄らしても、棺前で泣き伏して棺の前を去らない人もいた。5時45分には、一般の参拝を差し止めたがなかなか人は減らず、なかには白髪の老人が懐から祭文を取り出し、涙を流しながら朗読し始め、委員が「ご祭文はそこに置いていただきます」といっても聞き入れないというひと幕があった。 ](「大正葬祭史」)
[漱石・四十五歳。明治45・大正元(1912) 1月~4月「彼岸過迄」12月~翌11月「行人」]
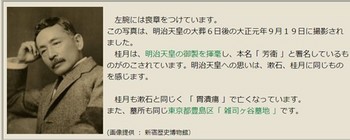
「夏目漱石」(監修・大町芳章/参考・高橋正著「 評伝 大町桂月 」)
http://keigetsu1869.la.coocan.jp/hito/souseki/souseki.html
2300 厳かに松明振り行くや星月夜(前書「奉送(一句)」、松根東洋城宛書簡)
[東洋城宛の書簡には「奉悼や葬送の句はどうも出来ないね。天子様の悼亡の句なんか作つた事がないから仕方がない」とある。明治天皇は七月三十日に逝去。]
2302 秋風や屠られに行く牛の尻(松根東洋城書簡)
[東洋城宛書簡には「一週間にて退院の筈、十句集も気が乗らずそれなりなり。発句を書いてくれと所望されると作らねばならぬと思ふが、左もなきときは作る了見も出ず済度致しがたき俗物と相成候」とある。九月二十六日佐藤診療所に入院、痔の手術を受けた。]
[東洋城・三十五歳。明治天皇崩御、式部官として大喪の儀奉仕。]

「松根東洋城」(「明治四十四年・『漱石夫妻 愛のかたち』より「森成麟造医師送別会(?)」の部分拡大図像)
https://blog.rnb.co.jp/sakanoue/?p=1062
明治天皇崩御矣嗟呼(ああ)暑退き栗実る(前書「明治天皇崩御 十二句」)
この秋や供奉(くぶ)に泣かるゝ太刀冠(同上)
菊咲くや仮の名ながら菊花節(同上)
和歌の君に俳諧の臣や菊花節(同上)
大輪の菊に御偉業や菊花節(同上)
(以下、七句「略」)
[寅彦・三十五歳。四月、中央気象台の全国気象協議会において海洋学の集中講義を開く。五月、次女の弥生誕生。十一月、日本天文学例会において「地球内部の構造に就て」を講演する。]→[『寺田寅彦全集/文学篇/七巻』には収載句は無い。]→[『寺田寅彦全集/文学篇/七巻』には収載句は無い。]
(参考) 「明治天皇大喪儀」周辺

「明治天皇大喪儀絵巻物1~4」(「宮内公文書館所蔵」)
https://www.archives.go.jp/exhibition/digital/modean_state/contents/imperial-mourning/photo/taimo/pn04.html
http://web.sanin.jp/p/sousen/1/3/1/14/11/
[明治天皇大喪(大正1年9月)
明治天皇の大喪は、9月13日から3日間にわたり行なわれた。大喪費用は当時の金で150万円であった。午後8時、1発の号砲を合図に明治天皇の霊柩を乗せた轜車(じしゃ)は、78対の松明(たいまつ)に導かれて宮殿を出発。轜車が青山の葬場殿に到着したのは夜の10時56分。葬場殿の儀が終わったのは午前零時45分である。夜間の葬列のため、その準備も大変だった。
皇居の正面の二重橋から西の丸の馬場先門までの間には、約20メートル間隔で高さ6メートルの根越榊10対を立て、その土台には約45センチの白木の台に白木の枠を設けた。榊の梢からは黒白、あるいは濃い鼠色の帛(絹布)を垂らし、榊と榊の間に約18メートルの間隔で、高さ3メートルのガスのかがり火を20対設置した。このかがり火は赤松の丸太3本を組み合わせて作ったもので、これにしめ縄を張り、さらに榊のかがり火の後方には10対のアーク灯を点じ、辺り一帯を真昼のように照らした。馬場先門からは36メートルおきに9メートルの柱を立て、その上にアーク灯をつけた。その間に18メートルおきに、黒白の布を巻いた間柱を立て、頂上から幡旗をつるし、途中で緑葉の環を付けた。さらに柱と柱の間には銀色、あるいは黒白の喪飾りを施した。麹町大通りは車道と人道との間に黒の幔幕を張り、各戸に白張りの提灯を掲げた。
青山大葬場入口左右には、擦りガラスをはめた高さ8メートルの白木作りの春日形大燈篭一対を立て、総門の左右には清涼殿形の吊り燈篭4個を立てて、夜間の葬列にふさわしい備えをした。
乃木大将夫妻の葬儀(大正1年9月)
明治天皇大葬の当夜、霊柩発引の号砲を合図に自刃を遂げた乃木大将夫妻の葬儀が9月18日に行なわれた。午後3時赤坂の自宅を出棺、青山斎場に於て神式の葬儀を執り行なった。午後2時半にラッパの合図第1声とともに、前駆並びに花旗の行列を整え、第2声で大将の棺を載せた砲車、及び夫人の棺を載せた馬車の出発準備に取り掛かり、葬儀係はいずれも行列位置についた。次ぎに会葬者一同出発準備をして、第3声「気を付け前へ」の合図とともに行進が始まった。午後4時、祭式が始まり、4時25分、道路に整列した1個連隊の儀杖兵は、「命を棄てて」のラッパの吹奏を終えて、一斉に銃口を天に向け3発の弔銃を発射した。
午後5時頃より一般会葬者の参拝が始まった。葬儀委員の3名は椅子に登って「礼拝が済みますれば、すぐにご退出を願います。後がたくさんでございますから、何とぞ早くご退出を願います」と声を嗄らしても、棺前で泣き伏して棺の前を去らない人もいた。5時45分には、一般の参拝を差し止めたがなかなか人は減らず、なかには白髪の老人が懐から祭文を取り出し、涙を流しながら朗読し始め、委員が「ご祭文はそこに置いていただきます」といっても聞き入れないというひと幕があった。 ](「大正葬祭史」)
「漱石・東洋城・寅彦」(子規没後~漱石没まで)俳句管見(その九) [漱石・東洋城・寅彦]
その九「明治四十四年(一九一一)」
[漱石・四十四歳。明治44(1911) 2月、文学博士号を辞退。7月、「ケーベル先生」、11月、ひな子急死。]

『漱石夫妻 愛のかたち』より
https://yamabato.exblog.jp/32354048/
夏目漱石の長女・筆子の次女(松岡陽子マックレイン)による著作『漱石夫妻 愛のかたち』。
『漱石の思い出』(漱石の妻・鏡子の語りを、筆子の夫で漱石の門人でもあった松岡譲が書き取ったもの)を軽く補足するような内容)。)
[漱石家族(前列左から「二女・恒子、妻・鏡子、長男・純一、四女・愛子、長女・筆子、三女・栄子」、後列、左から「松根東洋城・森成麟造医師」など) ]

「漱石家族(左から 純一・愛子・筆子・恒子・栄子・伸六・ (枠内)雛子)」
https://ameblo.jp/senna351103/entry-12244785229.html
2261 腸に春滴るや粥の味(『思ひ出す事など(二十六)』)
[やがて粥(かゆ)を許された。その旨(うま)さはただの記憶となって冷やかに残っているだけだから実感としては今思い出せないが、こんな旨いものが世にあるかと疑いつつ舌を鳴らしたのは確かである。それからオートミールが来た。ソーダビスケットが来た。余はすべてをありがたく食った。そうして、より多く食いたいと云う事を日課のように繰り返して森成さんに訴えた。森成さんはしまいに余の病床に近づくのを恐れた。東君(ひがしくん)はわざわざ妻(さい)の所へ行って、先生はあんなもっともな顔をしている癖に、子供のように始終(しじゅう)食物(くいもの)の話ばかりしていておかしいと告げた。]
2269 蝙蝠の宵々毎や薄き粥
[この句を記した寺田寅彦宛のはがきには、入院していた大阪の湯川胃腸病院の三階の病室から見える風景が書かれ、「毎日粥を食ふ」とある。]
2270 稲妻に近くて眠り安からず(前書「三階の隅の病室に臥して」)
[前書きは服部嘉に贈ったとされる短冊(「英語教育(大正6年1月15日)」の写真版による。)
2271 灯を消せば涼しき星や窓に入る(「松根東洋城宛書簡」)
2272 風折々萩先づ散つて芒哉(「寺田寅彦宛書簡」)
2273 耳の底の腫物を打つや秋の雨(「松根東洋城宛書簡」)
[耳痛の東洋城を思いやった句。]
2274 切口に冷やかな風の厠より(「松根東洋城宛書簡」)
[東洋城宛書簡に、「肛門の方は段々よけれど創口未だ肉を上げずガーゼの詰替頗る痛み候」とある。漱石は痔の手術を受けたばかりであった。]
2275 たのまれて戒名選む鶏頭哉(「松根東洋城宛書簡」)
[東洋城の母の戒名を選んだことが句の背景。]
2276 抱一の芒に月の円かなる
[抱一の芒は画家の抱一が描いたような芒。]
(付記)

「月下尾花図 酒井抱一筆」(「(MIHO MUSEUM)蔵」)
https://www.miho.jp/booth/html/artcon/00000654.htm
[旧暦8月15日は仲秋の名月。この時期、台風や霧雨で空気が湿ったり、小雨の降ったあと、移動性高気圧におおわれて晴れた夜間に冷え込みがあったりして、霧が発生しやすい。「十二カ月花鳥図」のようにとりどりの秋草や虫などの小動物も描かれていないが、たらし込みの技法で描かれたススキに、夜霧に浮かぶ名月を取り合わせ、俳諧にも親しんだ抱一らしい、しっとりとした詩情に充たされた作品である。
(酒井抱一)
1761~1829(宝暦11~文政11)。江戸時代後期の琳派の画家。姫路城主、酒井忠以の弟として江戸に生まれた。多種の才芸に富み、書、俳階狂歌にも長じ、涛花・杜陵・屠竜の別号がある。画は初め浮世絵や狩野派、円山派、土佐派など諸派の画風を広く学んだが、尾形光琳の作品に感動しその芸術の再興を志した。草花図を得意とし、深い観察力で豊かな抒情性をたたえた装飾画風を形成した。抱一は当時の文人的かつ粋人的生活を送った人で、光琳様式もその立場で解釈し、繊細、華麗な新しい画風によって光琳芸術を発展的に継承し江戸琳派を確立した画家である。宗達に始まる宗達派は光琳を経て抱一で三転したといえる。]
[東洋城・三十四歳。一月、父没す。望遠館を引払つて、築地に一戸を構へた。五月二十四日の日記に「松根の宅は妾宅の様な所である云々。漱石の博士問題起る。六月、四十二年より留学中の寅彦帰朝。九月、漱石大阪に病み、東洋城は伊予より帰京の途見舞つた。]
元日やわが俳諧も十五年
[※(補記)虚子から引き継いだ「国民俳壇」の選や、毎週一会の「望遠館句会」など、碧悟桐の新傾向(非定型)]に対する、定型の伝統を固守する自負が込められている。]
天下泰平の御講書始かな(前書「御講書始 十二句)
[1911年(明治44年)/洋書: 穂積八束「希臘及羅馬ノ古典ニ顕ハレル祖先崇拝ノ事蹟」/
漢書: 三島毅「周易、大有ノ卦」/国書: 猪熊夏樹「出雲風土記国引ノ條「所以号意宇者ヨリ蘭之長浜是也マテ」」(「ウィキペディア」)]
訪ね来よ朧の路地の行どまり(前書「新居」)
[「この家は、東洋城の城の字をとって「城庵(じょうあん)」と名づけ、東洋城もいつしか「城師(じょうし)」と呼ばれるようになった。」(『渋柿の木の下で(中村英利子著)』) ]
我が舳先(へさき)島ばかりなる霞かな(前書「今治を出でて」)
陽炎やお寺の塀で萌ゆる草
松の葉に春の雨降る深山かな
行列が過ぎて深山の松毟鳥(まつむしり)
[※(補記)『東洋城全句集(上巻)』には、その「年譜」(『同書(中巻)』所収)に記載されている「一月、父没す」に関する、直接的な(前書などによる)東洋城の句は収載されていない。そして、その「年譜」の「九月、漱石大阪に病み、東洋城は伊予より帰京の途見舞つた」に関連して、「今治を出でて」の前書を有する句が、掲出句の冒頭の句である。それに続く「寺・深山・行列」などの句は、父(松根権六)の葬儀関連の句のように思われる。]
これらのことに関して、次のアドレスの「東洋城と漱石、そして壷天子」(山本典男稿)は、その背景を明らかにしている。
https://www.i-manabi.jp/system/app/webroot/PARK/PK26980007/h12.htm
(抜粋)
[一〇、東洋城の父母の墓
東洋城の先祖は宇和島藩伊達家の城代家老であった。平成十五年の八月、私は宇和島の大隆寺の松根東洋城の墓碑を訪ねた。大隆寺は宇和島藩伊達藩主の菩提寺で、その家老を勤めた松根家代々の墓地もそこにあった。豊次郎、松月院殿東洋城雲居士、昭和三十九年十月二十八日没八十七歳、友人の安倍能成の筆である。松根東洋城は本名を豊次郎といい、明治十一年二月二十五日、東京の築地に生まれた。東洋城の号は豊次郎をもじったものである。父の権六は、宇和島藩首席家老松根図書の長男、母の敏子は伊達宗城公の次女。祖父の松根図書といえば、幕末四賢公の一人といわれた伊達宗城を裏から支え、宇和島に図書ありと他藩の藩主から羨まれた希代の切れ者。松根家といえば親戚に皇族や華族がいる名門である。
一一、漱石に依頼の東洋城の母の戒名
東洋城の墓碑の横に、右に松雲院殿閉道自覚居士、左に霊源院殿水月一如大姉とあるのが父権六と母敏子の墓である。東洋城の『句全集』の年譜には、父の権六は明治四十四年に死亡とある。ところが『漱石全集』の「書簡集」には、明治四十四年に東洋城の母の戒名を相談したことの漱石の返信の手紙が五通残っている。明治四十四年の漱石の「頼まれて戒名選む鶏頭かな」はこの時の句である。単純に考えれば明治四十四年に亡くなったのは父の権六の筈である。それを生存中の母の戒名を漱石に相談するのは変でないかと書簡を見直したが、手紙で漱石に託した東洋城の相談は母敏子の戒名の件で、亡くなった筈の父の権六の戒名の相談は皆無である。そこで、父の権六の戒名は、権六が亡くなった一月には戒名は大隆寺の住職より贈られ解決済みでなかったかと解釈した。その上で、東洋城の漱石への依頼の内容は次の三点にあると考えた。
① 権六の一回忌までに墓石を建立する必要があるが、この際母の戒名も敬愛する漱石に決めてもらって墓石に彫っておきたい。
② 漱石の玄関の表札の字が気に入ったので、両親の墓碑は、これを書いた菅虎雄に頼んでもらいたい。
③ 母の戒名には宇和島のイメージから海に因んだものを漱石に考えてもらいたい。
以上の三点が東洋城の漱石への依頼の内容ではなかったかと漱石の手紙から考えた。ところで、漱石の書簡では、東洋城の願いを聞き、滄?院殿水月(一夢)一如大姉ではどうかと東洋城に提案している。それに対し、漱石は「浩洋院殿では水月云々に即かず不賛成に候」と書き、海に関する五つの別の院殿号を提案、また翌日の手紙で、漱石は「昨日ある本を見たら海のことを霊源というように覚え候。霊源院殿は戒名らしく候、如何にや」とあれこれ詮索し、翌日、気の早い漱石は、友人の菅虎雄に戒名の揮毫を依頼している。文意は「縁起は悪いが戒名を是非書いて貰いたい。僕の教えた松根という男の父母である。書体は正楷、字配り封入の割の通り、右は父、左は母、ご承知ありたし。松根という男は引っ越しの時、僕の門札を書くところを見ていたから君に頼みたいといっている」とある。
一二、菅虎雄のこと
菅虎雄は漱石の大学時代の友人で、漱石を松山中学に紹介したり、熊本の五高の教師に紹介したのも彼で、漱石の親友であった。安倍能成が、漱石が生前、最も親しくしていた友人に菅虎雄を挙げている。彼はドイツ語教師であったが、書にも堪能で一高の時の教え子芥川龍之介の著作『羅生門』の題字や、漱石が亡くなった時、雑司ケ谷にある漱石の墓碑も彼が書いている。菅は漱石の頼みでもあり、数枚の候補作を書いている。ところが、東洋城は、直前になって中止したい、などと優柔不断なことを言っている。漱石は慌てて、「実は先刻、菅に手紙を出して頼んでしまった、いまさらよすと云うのも異なものではないか。それに私もこの戒名に愛着もある。」と東洋城に翻意を促しています。また別便では、菅虎雄の書いた戒名を複数見せて「小生のよしと思うに朱円を付し置き候」と結び、これで漱石達のやり取りは終わる。漱石は大正五年に亡くなり、東洋城の母親は昭和八年に亡くなっており、書簡だけでは分からないので漱石の戒名は実現したのか確かめる必要があると考えた。なお菅虎雄は漱石の墓碑も揮毫している。この顛末を宇和島の大隆寺の墓地で実際に確認するのが、旅の目的だった。だが、私の危惧に関わらず、漱石が考えた戒名は一字も修正されず、権六の戒名の横に母親の「霊源院殿水月一如大姉」はあった。漱石の「頼まれて戒名選む鶏頭かな」は確かに実行されていたのであった。(以下一三・一四は編集の都合上了解を得て省略) ]
(付記)「宇和島の松根家の邸宅と家族」(明治四十二年九月四日写)

(裏面に、「明治四十二年九月四日写之、秋風やこぼつときめてきめて撮す家」と認めてある宇和島の宏壮な郷邸で、私の推定では敷地三千坪もあつたろうか。大半を町へ売られ、跡は町立病院が建った。残った二百坪程度の敷地に七間位の邸を建てられ、私どもはそこへ通つた。それも戦火に罹つて炎上、今は唯「我が祖先(おや)は奥の最上や天の川」の句碑一基を残すのみである。徳永山冬子)
「青春時代を語る / 東洋城 ; 洋一/p54~73」)」(「俳誌『渋柿(昭和四十年(一九六五)の一月号) 』 (「松根東洋城追悼号」)」
https://dl.ndl.go.jp/pid/6071686/1/37
[寅彦・三十四歳。欧米各国の地球物理学を調査するため、二月にフランス、四月にイギリス、五月にアメリカ、六月、帰国。七月、正七位に叙せられる。十一月、物理学第三講座を担任、第二講座を分担する。十一月、本郷区弥生町に転居。]
霜柱猟人畑を荒しけり(一月十四日「東京朝日新聞」)
小笹原下る近道霜ばしら(同上)
[漱石・四十四歳。明治44(1911) 2月、文学博士号を辞退。7月、「ケーベル先生」、11月、ひな子急死。]

『漱石夫妻 愛のかたち』より
https://yamabato.exblog.jp/32354048/
夏目漱石の長女・筆子の次女(松岡陽子マックレイン)による著作『漱石夫妻 愛のかたち』。
『漱石の思い出』(漱石の妻・鏡子の語りを、筆子の夫で漱石の門人でもあった松岡譲が書き取ったもの)を軽く補足するような内容)。)
[漱石家族(前列左から「二女・恒子、妻・鏡子、長男・純一、四女・愛子、長女・筆子、三女・栄子」、後列、左から「松根東洋城・森成麟造医師」など) ]

「漱石家族(左から 純一・愛子・筆子・恒子・栄子・伸六・ (枠内)雛子)」
https://ameblo.jp/senna351103/entry-12244785229.html
2261 腸に春滴るや粥の味(『思ひ出す事など(二十六)』)
[やがて粥(かゆ)を許された。その旨(うま)さはただの記憶となって冷やかに残っているだけだから実感としては今思い出せないが、こんな旨いものが世にあるかと疑いつつ舌を鳴らしたのは確かである。それからオートミールが来た。ソーダビスケットが来た。余はすべてをありがたく食った。そうして、より多く食いたいと云う事を日課のように繰り返して森成さんに訴えた。森成さんはしまいに余の病床に近づくのを恐れた。東君(ひがしくん)はわざわざ妻(さい)の所へ行って、先生はあんなもっともな顔をしている癖に、子供のように始終(しじゅう)食物(くいもの)の話ばかりしていておかしいと告げた。]
2269 蝙蝠の宵々毎や薄き粥
[この句を記した寺田寅彦宛のはがきには、入院していた大阪の湯川胃腸病院の三階の病室から見える風景が書かれ、「毎日粥を食ふ」とある。]
2270 稲妻に近くて眠り安からず(前書「三階の隅の病室に臥して」)
[前書きは服部嘉に贈ったとされる短冊(「英語教育(大正6年1月15日)」の写真版による。)
2271 灯を消せば涼しき星や窓に入る(「松根東洋城宛書簡」)
2272 風折々萩先づ散つて芒哉(「寺田寅彦宛書簡」)
2273 耳の底の腫物を打つや秋の雨(「松根東洋城宛書簡」)
[耳痛の東洋城を思いやった句。]
2274 切口に冷やかな風の厠より(「松根東洋城宛書簡」)
[東洋城宛書簡に、「肛門の方は段々よけれど創口未だ肉を上げずガーゼの詰替頗る痛み候」とある。漱石は痔の手術を受けたばかりであった。]
2275 たのまれて戒名選む鶏頭哉(「松根東洋城宛書簡」)
[東洋城の母の戒名を選んだことが句の背景。]
2276 抱一の芒に月の円かなる
[抱一の芒は画家の抱一が描いたような芒。]
(付記)

「月下尾花図 酒井抱一筆」(「(MIHO MUSEUM)蔵」)
https://www.miho.jp/booth/html/artcon/00000654.htm
[旧暦8月15日は仲秋の名月。この時期、台風や霧雨で空気が湿ったり、小雨の降ったあと、移動性高気圧におおわれて晴れた夜間に冷え込みがあったりして、霧が発生しやすい。「十二カ月花鳥図」のようにとりどりの秋草や虫などの小動物も描かれていないが、たらし込みの技法で描かれたススキに、夜霧に浮かぶ名月を取り合わせ、俳諧にも親しんだ抱一らしい、しっとりとした詩情に充たされた作品である。
(酒井抱一)
1761~1829(宝暦11~文政11)。江戸時代後期の琳派の画家。姫路城主、酒井忠以の弟として江戸に生まれた。多種の才芸に富み、書、俳階狂歌にも長じ、涛花・杜陵・屠竜の別号がある。画は初め浮世絵や狩野派、円山派、土佐派など諸派の画風を広く学んだが、尾形光琳の作品に感動しその芸術の再興を志した。草花図を得意とし、深い観察力で豊かな抒情性をたたえた装飾画風を形成した。抱一は当時の文人的かつ粋人的生活を送った人で、光琳様式もその立場で解釈し、繊細、華麗な新しい画風によって光琳芸術を発展的に継承し江戸琳派を確立した画家である。宗達に始まる宗達派は光琳を経て抱一で三転したといえる。]
[東洋城・三十四歳。一月、父没す。望遠館を引払つて、築地に一戸を構へた。五月二十四日の日記に「松根の宅は妾宅の様な所である云々。漱石の博士問題起る。六月、四十二年より留学中の寅彦帰朝。九月、漱石大阪に病み、東洋城は伊予より帰京の途見舞つた。]
元日やわが俳諧も十五年
[※(補記)虚子から引き継いだ「国民俳壇」の選や、毎週一会の「望遠館句会」など、碧悟桐の新傾向(非定型)]に対する、定型の伝統を固守する自負が込められている。]
天下泰平の御講書始かな(前書「御講書始 十二句)
[1911年(明治44年)/洋書: 穂積八束「希臘及羅馬ノ古典ニ顕ハレル祖先崇拝ノ事蹟」/
漢書: 三島毅「周易、大有ノ卦」/国書: 猪熊夏樹「出雲風土記国引ノ條「所以号意宇者ヨリ蘭之長浜是也マテ」」(「ウィキペディア」)]
訪ね来よ朧の路地の行どまり(前書「新居」)
[「この家は、東洋城の城の字をとって「城庵(じょうあん)」と名づけ、東洋城もいつしか「城師(じょうし)」と呼ばれるようになった。」(『渋柿の木の下で(中村英利子著)』) ]
我が舳先(へさき)島ばかりなる霞かな(前書「今治を出でて」)
陽炎やお寺の塀で萌ゆる草
松の葉に春の雨降る深山かな
行列が過ぎて深山の松毟鳥(まつむしり)
[※(補記)『東洋城全句集(上巻)』には、その「年譜」(『同書(中巻)』所収)に記載されている「一月、父没す」に関する、直接的な(前書などによる)東洋城の句は収載されていない。そして、その「年譜」の「九月、漱石大阪に病み、東洋城は伊予より帰京の途見舞つた」に関連して、「今治を出でて」の前書を有する句が、掲出句の冒頭の句である。それに続く「寺・深山・行列」などの句は、父(松根権六)の葬儀関連の句のように思われる。]
これらのことに関して、次のアドレスの「東洋城と漱石、そして壷天子」(山本典男稿)は、その背景を明らかにしている。
https://www.i-manabi.jp/system/app/webroot/PARK/PK26980007/h12.htm
(抜粋)
[一〇、東洋城の父母の墓
東洋城の先祖は宇和島藩伊達家の城代家老であった。平成十五年の八月、私は宇和島の大隆寺の松根東洋城の墓碑を訪ねた。大隆寺は宇和島藩伊達藩主の菩提寺で、その家老を勤めた松根家代々の墓地もそこにあった。豊次郎、松月院殿東洋城雲居士、昭和三十九年十月二十八日没八十七歳、友人の安倍能成の筆である。松根東洋城は本名を豊次郎といい、明治十一年二月二十五日、東京の築地に生まれた。東洋城の号は豊次郎をもじったものである。父の権六は、宇和島藩首席家老松根図書の長男、母の敏子は伊達宗城公の次女。祖父の松根図書といえば、幕末四賢公の一人といわれた伊達宗城を裏から支え、宇和島に図書ありと他藩の藩主から羨まれた希代の切れ者。松根家といえば親戚に皇族や華族がいる名門である。
一一、漱石に依頼の東洋城の母の戒名
東洋城の墓碑の横に、右に松雲院殿閉道自覚居士、左に霊源院殿水月一如大姉とあるのが父権六と母敏子の墓である。東洋城の『句全集』の年譜には、父の権六は明治四十四年に死亡とある。ところが『漱石全集』の「書簡集」には、明治四十四年に東洋城の母の戒名を相談したことの漱石の返信の手紙が五通残っている。明治四十四年の漱石の「頼まれて戒名選む鶏頭かな」はこの時の句である。単純に考えれば明治四十四年に亡くなったのは父の権六の筈である。それを生存中の母の戒名を漱石に相談するのは変でないかと書簡を見直したが、手紙で漱石に託した東洋城の相談は母敏子の戒名の件で、亡くなった筈の父の権六の戒名の相談は皆無である。そこで、父の権六の戒名は、権六が亡くなった一月には戒名は大隆寺の住職より贈られ解決済みでなかったかと解釈した。その上で、東洋城の漱石への依頼の内容は次の三点にあると考えた。
① 権六の一回忌までに墓石を建立する必要があるが、この際母の戒名も敬愛する漱石に決めてもらって墓石に彫っておきたい。
② 漱石の玄関の表札の字が気に入ったので、両親の墓碑は、これを書いた菅虎雄に頼んでもらいたい。
③ 母の戒名には宇和島のイメージから海に因んだものを漱石に考えてもらいたい。
以上の三点が東洋城の漱石への依頼の内容ではなかったかと漱石の手紙から考えた。ところで、漱石の書簡では、東洋城の願いを聞き、滄?院殿水月(一夢)一如大姉ではどうかと東洋城に提案している。それに対し、漱石は「浩洋院殿では水月云々に即かず不賛成に候」と書き、海に関する五つの別の院殿号を提案、また翌日の手紙で、漱石は「昨日ある本を見たら海のことを霊源というように覚え候。霊源院殿は戒名らしく候、如何にや」とあれこれ詮索し、翌日、気の早い漱石は、友人の菅虎雄に戒名の揮毫を依頼している。文意は「縁起は悪いが戒名を是非書いて貰いたい。僕の教えた松根という男の父母である。書体は正楷、字配り封入の割の通り、右は父、左は母、ご承知ありたし。松根という男は引っ越しの時、僕の門札を書くところを見ていたから君に頼みたいといっている」とある。
一二、菅虎雄のこと
菅虎雄は漱石の大学時代の友人で、漱石を松山中学に紹介したり、熊本の五高の教師に紹介したのも彼で、漱石の親友であった。安倍能成が、漱石が生前、最も親しくしていた友人に菅虎雄を挙げている。彼はドイツ語教師であったが、書にも堪能で一高の時の教え子芥川龍之介の著作『羅生門』の題字や、漱石が亡くなった時、雑司ケ谷にある漱石の墓碑も彼が書いている。菅は漱石の頼みでもあり、数枚の候補作を書いている。ところが、東洋城は、直前になって中止したい、などと優柔不断なことを言っている。漱石は慌てて、「実は先刻、菅に手紙を出して頼んでしまった、いまさらよすと云うのも異なものではないか。それに私もこの戒名に愛着もある。」と東洋城に翻意を促しています。また別便では、菅虎雄の書いた戒名を複数見せて「小生のよしと思うに朱円を付し置き候」と結び、これで漱石達のやり取りは終わる。漱石は大正五年に亡くなり、東洋城の母親は昭和八年に亡くなっており、書簡だけでは分からないので漱石の戒名は実現したのか確かめる必要があると考えた。なお菅虎雄は漱石の墓碑も揮毫している。この顛末を宇和島の大隆寺の墓地で実際に確認するのが、旅の目的だった。だが、私の危惧に関わらず、漱石が考えた戒名は一字も修正されず、権六の戒名の横に母親の「霊源院殿水月一如大姉」はあった。漱石の「頼まれて戒名選む鶏頭かな」は確かに実行されていたのであった。(以下一三・一四は編集の都合上了解を得て省略) ]
(付記)「宇和島の松根家の邸宅と家族」(明治四十二年九月四日写)

(裏面に、「明治四十二年九月四日写之、秋風やこぼつときめてきめて撮す家」と認めてある宇和島の宏壮な郷邸で、私の推定では敷地三千坪もあつたろうか。大半を町へ売られ、跡は町立病院が建った。残った二百坪程度の敷地に七間位の邸を建てられ、私どもはそこへ通つた。それも戦火に罹つて炎上、今は唯「我が祖先(おや)は奥の最上や天の川」の句碑一基を残すのみである。徳永山冬子)
「青春時代を語る / 東洋城 ; 洋一/p54~73」)」(「俳誌『渋柿(昭和四十年(一九六五)の一月号) 』 (「松根東洋城追悼号」)」
https://dl.ndl.go.jp/pid/6071686/1/37
[寅彦・三十四歳。欧米各国の地球物理学を調査するため、二月にフランス、四月にイギリス、五月にアメリカ、六月、帰国。七月、正七位に叙せられる。十一月、物理学第三講座を担任、第二講座を分担する。十一月、本郷区弥生町に転居。]
霜柱猟人畑を荒しけり(一月十四日「東京朝日新聞」)
小笹原下る近道霜ばしら(同上)
「漱石・東洋城・寅彦」(子規没後~漱石没まで)俳句管見(その八) [漱石・東洋城・寅彦]
その八「明治四十三年(一九一〇)」
[漱石・四十三歳、3月~6月、「門」、6月、胃潰瘍のため長与胃腸病院に入院。8月、伊豆修善寺温泉に転地療養、大量の吐血のため危篤状態に陥る。10月~翌2月、「思ひ出す事など。]
2124 秋の江に打ち込む杭の響かな (同上。※「思ひ出す事など(五)」で触れている句。)
[これは生き返ってから約十日ばかりしてふとできた句である。澄み渡る秋の空、広き江、遠くよりする杭の響、この三つの事相(じそう)に相応したような情調が当時絶えずわが微かすかなる頭の中を徂徠(そらい)した事はいまだに覚えている。「思ひ出す事など(五)」]
2127 秋の空浅黄に澄めり杉に斧 (同上)
[これも同じ心の耽(ふけ)りを他(ほか)の言葉で云い現したものである。「思ひ出す事など(五)」]
2123 別るゝるや夢一筋の天の川 (同上)
[何という意味かその時も知らず、今でも分らないが、あるいは仄(ほのか)に東洋城(とうようじょう)と別れる折の連想が夢のような頭の中に這回(はいまわっ)て、恍惚(こうこつ)とでき上ったものではないかと思う。当時の余は西洋の語にほとんど見当らぬ風流と云う趣をのみ愛していた。その風流のうちでもここに挙(あげ)た句に現れるような一種の趣だけをとくに愛していた。「思ひ出す事など(五)」]
2125 秋風や唐紅(からくれない)の咽喉仏 (同上)
[という句はむしろ実況であるが、何だか殺気があって含蓄(がんちく)が足りなくて、口に浮かんだ時からすでに変な心持がした。「思ひ出す事など(五)」]
※2242 有る程の菊抛(な)げ入れよ棺の中(同上。「思ひ出す事など(七)」で触れている句。)
[人間の生死も人間を本位とする吾らから云えば大事件に相違ないが、しばらく立場を易(かえ)て、自己が自然になり済ました気分で観察したら、ただ至当(しとう)の成行で、そこに喜びそこに悲しむ理窟(りくつ)は毫(ごう)も存在していないだろう。
こう考えた時、余ははなはだ心細くなった。またはなはだつまらなくなった。そこでことさらに気分を易えて、この間大磯(おおいそ)で亡なくなった大塚夫人の事を思い出しながら、夫人のために手向(たむけ)の句を作った。※「思ひ出す事など(七)」}
※『思ひ出す事など(一)~(三十三)』
https://www.aozora.gr.jp/cards/000148/files/792_14937.html
「※2242 有る程の菊抛(な)げ入れよ棺の中」周辺

「大塚楠緒子」(「漱石と大塚楠緒子」)
https://plaza.rakuten.co.jp/akiradoinaka/diary/201807230000/
[門人の内田百閒は、『漱石俳句鑑賞』で、この句について「夫人の訃は、先生に取っては、その大学時代の学友である所の大塚博士の夫人の夙き死を悼まれる気持の外に、また夫人の文をおしむ念も一しお強かったことと思われるのである。前掲の句は、そういうわけでつくられた哀悼の句であって、故人に対する先生の愛情の感じが情味あふるる句調に盛られている。「有る程の」というのは、あるだけの、ありったけのという意味、いくらでも、いくらでも、ありったけの菊を手向けとしてお棺の中へ入れて上げてくれ、という迫った感じを、それに応じた句格を以て詠ってある。愛惜しても愛惜しても及ばないという気持を、「秋」の象徴の如き菊花に託し、更にその菊を棺の中に抛げ入れるということに尽きない哀悼の情を託せられたのである」と書きました。](「漱石と大塚楠緒子」)

「修善寺温泉」(「漱石と温泉14/修善寺温泉」)
https://plaza.rakuten.co.jp/akiradoinaka/diary/201909140000/
[ 宮様の御立のあとや温泉の秋(漱石「明治43」)
明治43年8月6日から10月11日にかけて、転地療養のために伊豆修善寺温泉の菊屋別館(現菊屋)を訪れています。
門下の松根東洋城が、当時、宮内省式部官であり、北白川宮のお付きのために修善寺に出かける予定がありました。伊豆半島最古の温泉地といわれる修善寺温泉は、弘法大師が見つけたという「独鈷の湯」や、源頼家が幽閉された古刹・修禅寺をはじめとする源氏の興亡の舞台にもなり、しかも自然豊かな桂川渓谷に位置するところから、漱石が療養の舞台に選んだのも、当然といえるほどの場所でした。(後略) ](「漱石と温泉14/修善寺温泉」)
[東洋城・三十三歳。北白川宮御用掛兼職。八月、漱石と修善寺に赴いた。修善寺で漱石は吐血、重態となった。『東洋城全句集(上)』では「修善寺大患 二十四句」が収載されている。]
秋立つや何の胃の腑の滞り(前書「先生病む」)
又しては残暑の布団脱ぐや干す(前書「一日の公務を了へてより夜々行く」)
師の病訪ふて帰るや滝の月(前書「本館の通ひ路は白糸の滝を過ぐ、ある夜」)
程ヶ谷で遅れし汽車や秋の雨(前書「漱石先生還る。十二句、十月十一日、横浜駅に先生を待つ)
多勢で担架かきけり秋の雨(前書「人々三島駅乗替の騒動など語る」)
久々の秋の夕日の晴れにけり(前書「病室より 六句。面会謝絶の立札に関所潜りするのは病用家用に余儀なき特許に依る。頼まれたバクを提げ其他の用向を抱えて通る。枕を埋める堆書裏に静臥の漱石先生の顔色が此間内とは異なつた縁に射す日と共に鮮かだ」)
病院や消灯十時夜半の秋(前書「謝客は医の厳命で又自分の僥倖、神身を安静にしつゝ此機会を利用して読書三昧に入る。と浮世の人々に告げて呉れ、其内「朝日」に何か書くよ。ナチュラル、モーラルス」に色鉛筆が挟まれたまゝ灯の下に))
[寅彦・三十三歳。十月、ゲッチンゲン大学に学ぶ。]→(『寺田寅彦全集/文学篇/七巻』には収載句は無い。)]
(再掲・抜粋)
https://yahan.blog.ss-blog.jp/archive/c2306351243-1
【(参考その一) 「夏目漱石の漢詩(石川忠久稿))所収「漱石漢詩文年表(斎藤希文監修)」(抜粋)
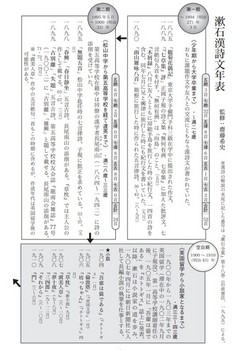
第一期〜 1894(明治27)年3 月 → 「修養期」
《少年期から大学卒業まで》・〜満二七歳
おもに課題作文や友人との交流にともなう漢詩文が書かれていた。
第二期1895 年 5 月〜 1900(明治33)年 → 「俳句の時代」
《松山中学から第五高等学校を経て渡英まで》・満二八歳〜三三歳
第五高等学校在籍中は同僚の漢学者長尾雨山(ながおうざん)(一八六四〜一九四二)に詩の添削を受けていた。
空白期1900 〜 1910(明治 43)年 → 「作家(小説)の時代」
《英国留学から小説家となるまで》・満三三〜四三歳
一九〇〇年から一九〇三年までの英国留学(滞在中の一九〇二年九月に子規没)、第一高等学校講師着任の後、一九〇五年一月に「吾輩は猫である」を「ホトトギス」誌上に発表。
以降、漱石は小説家の道を歩み、一九〇七年四月には朝日新聞社に入社して長編小説の執筆を仕事とする。

第三期1910(明治43)年 7 〜10 月 → 「病臥・転換期」
《修禅寺大患前後》・満四三歳
胃潰瘍による入院を機に再び詩を作り始める。とくに修禅寺大患後の作が多い。
第四期1912 年 5 月〜 1916(大正5)年春 →「漢詩(南画)の時代」
《詩と画の世界》・満四五〜四九歳
この時期の漱石は好んで南画を描くようになり、しばしば自ら詩を題した。また、人に求められて書いた作も少なくない。
第五期1916(大正 5)年 8 月〜 11 月20 日 「最晩年期」
《『明暗』執筆期》・満四九歳
七言律詩を作ることを日課とし、生涯で最も集中して詩が作られた時期。 】
[漱石・四十三歳、3月~6月、「門」、6月、胃潰瘍のため長与胃腸病院に入院。8月、伊豆修善寺温泉に転地療養、大量の吐血のため危篤状態に陥る。10月~翌2月、「思ひ出す事など。]
2124 秋の江に打ち込む杭の響かな (同上。※「思ひ出す事など(五)」で触れている句。)
[これは生き返ってから約十日ばかりしてふとできた句である。澄み渡る秋の空、広き江、遠くよりする杭の響、この三つの事相(じそう)に相応したような情調が当時絶えずわが微かすかなる頭の中を徂徠(そらい)した事はいまだに覚えている。「思ひ出す事など(五)」]
2127 秋の空浅黄に澄めり杉に斧 (同上)
[これも同じ心の耽(ふけ)りを他(ほか)の言葉で云い現したものである。「思ひ出す事など(五)」]
2123 別るゝるや夢一筋の天の川 (同上)
[何という意味かその時も知らず、今でも分らないが、あるいは仄(ほのか)に東洋城(とうようじょう)と別れる折の連想が夢のような頭の中に這回(はいまわっ)て、恍惚(こうこつ)とでき上ったものではないかと思う。当時の余は西洋の語にほとんど見当らぬ風流と云う趣をのみ愛していた。その風流のうちでもここに挙(あげ)た句に現れるような一種の趣だけをとくに愛していた。「思ひ出す事など(五)」]
2125 秋風や唐紅(からくれない)の咽喉仏 (同上)
[という句はむしろ実況であるが、何だか殺気があって含蓄(がんちく)が足りなくて、口に浮かんだ時からすでに変な心持がした。「思ひ出す事など(五)」]
※2242 有る程の菊抛(な)げ入れよ棺の中(同上。「思ひ出す事など(七)」で触れている句。)
[人間の生死も人間を本位とする吾らから云えば大事件に相違ないが、しばらく立場を易(かえ)て、自己が自然になり済ました気分で観察したら、ただ至当(しとう)の成行で、そこに喜びそこに悲しむ理窟(りくつ)は毫(ごう)も存在していないだろう。
こう考えた時、余ははなはだ心細くなった。またはなはだつまらなくなった。そこでことさらに気分を易えて、この間大磯(おおいそ)で亡なくなった大塚夫人の事を思い出しながら、夫人のために手向(たむけ)の句を作った。※「思ひ出す事など(七)」}
※『思ひ出す事など(一)~(三十三)』
https://www.aozora.gr.jp/cards/000148/files/792_14937.html
「※2242 有る程の菊抛(な)げ入れよ棺の中」周辺

「大塚楠緒子」(「漱石と大塚楠緒子」)
https://plaza.rakuten.co.jp/akiradoinaka/diary/201807230000/
[門人の内田百閒は、『漱石俳句鑑賞』で、この句について「夫人の訃は、先生に取っては、その大学時代の学友である所の大塚博士の夫人の夙き死を悼まれる気持の外に、また夫人の文をおしむ念も一しお強かったことと思われるのである。前掲の句は、そういうわけでつくられた哀悼の句であって、故人に対する先生の愛情の感じが情味あふるる句調に盛られている。「有る程の」というのは、あるだけの、ありったけのという意味、いくらでも、いくらでも、ありったけの菊を手向けとしてお棺の中へ入れて上げてくれ、という迫った感じを、それに応じた句格を以て詠ってある。愛惜しても愛惜しても及ばないという気持を、「秋」の象徴の如き菊花に託し、更にその菊を棺の中に抛げ入れるということに尽きない哀悼の情を託せられたのである」と書きました。](「漱石と大塚楠緒子」)

「修善寺温泉」(「漱石と温泉14/修善寺温泉」)
https://plaza.rakuten.co.jp/akiradoinaka/diary/201909140000/
[ 宮様の御立のあとや温泉の秋(漱石「明治43」)
明治43年8月6日から10月11日にかけて、転地療養のために伊豆修善寺温泉の菊屋別館(現菊屋)を訪れています。
門下の松根東洋城が、当時、宮内省式部官であり、北白川宮のお付きのために修善寺に出かける予定がありました。伊豆半島最古の温泉地といわれる修善寺温泉は、弘法大師が見つけたという「独鈷の湯」や、源頼家が幽閉された古刹・修禅寺をはじめとする源氏の興亡の舞台にもなり、しかも自然豊かな桂川渓谷に位置するところから、漱石が療養の舞台に選んだのも、当然といえるほどの場所でした。(後略) ](「漱石と温泉14/修善寺温泉」)
[東洋城・三十三歳。北白川宮御用掛兼職。八月、漱石と修善寺に赴いた。修善寺で漱石は吐血、重態となった。『東洋城全句集(上)』では「修善寺大患 二十四句」が収載されている。]
秋立つや何の胃の腑の滞り(前書「先生病む」)
又しては残暑の布団脱ぐや干す(前書「一日の公務を了へてより夜々行く」)
師の病訪ふて帰るや滝の月(前書「本館の通ひ路は白糸の滝を過ぐ、ある夜」)
程ヶ谷で遅れし汽車や秋の雨(前書「漱石先生還る。十二句、十月十一日、横浜駅に先生を待つ)
多勢で担架かきけり秋の雨(前書「人々三島駅乗替の騒動など語る」)
久々の秋の夕日の晴れにけり(前書「病室より 六句。面会謝絶の立札に関所潜りするのは病用家用に余儀なき特許に依る。頼まれたバクを提げ其他の用向を抱えて通る。枕を埋める堆書裏に静臥の漱石先生の顔色が此間内とは異なつた縁に射す日と共に鮮かだ」)
病院や消灯十時夜半の秋(前書「謝客は医の厳命で又自分の僥倖、神身を安静にしつゝ此機会を利用して読書三昧に入る。と浮世の人々に告げて呉れ、其内「朝日」に何か書くよ。ナチュラル、モーラルス」に色鉛筆が挟まれたまゝ灯の下に))
[寅彦・三十三歳。十月、ゲッチンゲン大学に学ぶ。]→(『寺田寅彦全集/文学篇/七巻』には収載句は無い。)]
(再掲・抜粋)
https://yahan.blog.ss-blog.jp/archive/c2306351243-1
【(参考その一) 「夏目漱石の漢詩(石川忠久稿))所収「漱石漢詩文年表(斎藤希文監修)」(抜粋)
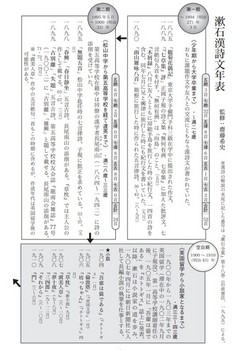
第一期〜 1894(明治27)年3 月 → 「修養期」
《少年期から大学卒業まで》・〜満二七歳
おもに課題作文や友人との交流にともなう漢詩文が書かれていた。
第二期1895 年 5 月〜 1900(明治33)年 → 「俳句の時代」
《松山中学から第五高等学校を経て渡英まで》・満二八歳〜三三歳
第五高等学校在籍中は同僚の漢学者長尾雨山(ながおうざん)(一八六四〜一九四二)に詩の添削を受けていた。
空白期1900 〜 1910(明治 43)年 → 「作家(小説)の時代」
《英国留学から小説家となるまで》・満三三〜四三歳
一九〇〇年から一九〇三年までの英国留学(滞在中の一九〇二年九月に子規没)、第一高等学校講師着任の後、一九〇五年一月に「吾輩は猫である」を「ホトトギス」誌上に発表。
以降、漱石は小説家の道を歩み、一九〇七年四月には朝日新聞社に入社して長編小説の執筆を仕事とする。

第三期1910(明治43)年 7 〜10 月 → 「病臥・転換期」
《修禅寺大患前後》・満四三歳
胃潰瘍による入院を機に再び詩を作り始める。とくに修禅寺大患後の作が多い。
第四期1912 年 5 月〜 1916(大正5)年春 →「漢詩(南画)の時代」
《詩と画の世界》・満四五〜四九歳
この時期の漱石は好んで南画を描くようになり、しばしば自ら詩を題した。また、人に求められて書いた作も少なくない。
第五期1916(大正 5)年 8 月〜 11 月20 日 「最晩年期」
《『明暗』執筆期》・満四九歳
七言律詩を作ることを日課とし、生涯で最も集中して詩が作られた時期。 】
「漱石・東洋城・寅彦」(子規没後~漱石没まで)俳句管見(その七) [漱石・東洋城・寅彦]
その七「明治四十二年(一九〇九)」
[漱石・四十二歳]
[明治42(1909) 1月~3月、「永日小品」、6月~10月、「それから」、9月~10月、中村是公と満州・朝鮮旅行、10月~12月、「満韓ところどころ」、11月、朝日文芸欄創設。 ]
2096 空に消ゆる鐸のひゞきや春の塔(前書「空間を研究せる天然居士の肖像に題す」。)
[天然居士は、漱石の学生時代の友人米山保三郎の号。この句はその兄である米山熊次郎へ送った句。]
(再掲) 「漱石の親友 天然居士・米山保三郎」周辺
https://rendezvou.exblog.jp/7067220/
[学生時代の夏目金之助に作家になることを勧め漱石が彼の言葉に強く動かされた人物・米山保三郎のことはよく知られています。ただ、これまで研究者の中で誤解があり、漱石の語句の解釈に問題があるまま流布されてきたのが現状です。
「天然居士は空間を研究し、論語を読み、焼芋を食い、鼻汁を垂らす人である」
焼き芋と鼻汁を垂らす、これは禅の歴史に実在した中国の禅僧・懶さん(王ヘンに賛)和尚の故事から来る引用なのでした。漱石は畏敬する親友の米山保三郎へ深い愛情と禅に生きる彼を讃える意味で書いたものでしょう。しかし、世間一般ではなかなか通用しない事も充分知っていました。そうであるからこそ、『猫』のなかで次のように書いているのです。
「天然居士は空間を研究し、論語を読み、焼芋を食い、鼻汁を垂らす人である」
苦沙弥先生、一気呵成にこう書き流し、声を出してこれを読み、「ハハハ面白い」と笑うが、「うん。鼻汁を垂らすはさすがに酷だ、焼き芋も蛇足だ」と線を引き。結局「天然居士は空間を研究し論語を読む人である」だけにしたころで、これではあまりに簡単すぎると全部ボツにして、原稿用紙の裏に「空間に生れ、空間を究め、空間に死す。空たり間たり天然居士、噫」
実際、漱石はこの米山の兄、熊次郎から実弟の写真へ揮毫を懇望されて、漱石は俳句を書いています。その俳句とは、
空に消ゆる鐸のひびきや春の塔 という追悼の一句です。親友の死を悼む漱石の心情があふるるばかり、見事な名句と思います。写真は400X300mm、単身像の右側にこの句があり、左にこう記されています。
空間を研究する天然居士の肖像に題す 己酉 四月 漱石
己酉,となれば、1909年、明治四十二年です。漱石が朝日新聞社に入社して2年目の四月に詠んだものと明確に判るのが嬉しいところです。また、米山が鼻水を垂らすの表現がとかく世俗的に解釈され、漱石がいかにしてこの語句を入れたかということは研究者の間でないがしろにされて来ました。しかし、漱石がただ、ユーモラスにこんな語句を入れるはずはないのです。洟を垂らそうが自分は三昧になっているのだという仏道の修行による逸話なのです。
出典もありますから、その引用もしておきましょう。『碧巖録』第三十四則より。
「懶瓚和尚。隱居衡山石室中。唐德宗聞其名。遣使召之。使者至其室宣言。天子有詔。尊者當起謝恩。瓚方撥牛糞火。尋煨芋而食。寒涕垂頤未甞答。使者笑曰。且勸尊者拭涕。瓚曰。我豈有工夫為俗人拭涕耶。竟不起。使回奏。德宗甚欽嘆之。」
(懶瓚和尚、衡山石室の中に隱居す。唐の德、宗其の名を聞いて、使を遣して之を召す。使者、其の室に至つて宣言す。天子詔有り、尊者まさに起つて恩を謝すべし。瓚、まさに牛糞の火を撥つて、煨芋を尋ねて食す。寒涕、頤に垂れて未だ甞て答えず。使者笑つて曰く、且らく勸む、尊者、涕を拭え。瓚曰く、我れ豈に工夫の俗人の為に涕を拭くこと有らん耶といつて、竟に起たず。使、回つて奏す。德宗、甚だ之を欽嘆す。) (以下略) ]
(追記)

漱石(左)と米山保三郎(明治25年)
https://www.asahi.com/articles/ASJ615FM7J61UCVL00W.html
https://yahan.blog.ss-blog.jp/2023-09-08
[東洋城、三十二歳。東洋城の下宿「望遠館」(九段中坂)において、毎週一会の句会が催された。択ばれた者のみが出席できる会で、暮雨(万太郎)、蛇笏、零余子、松浜、喜舟などが、そのメンバーである。三月、東洋城選「新春夏秋冬」夏の部(「序」は夏目漱石)、十月「同・秋の部」を俳書堂より刊行した。]
春月や暗き灯持つ峰の城(「タンタヂイル(タンタジールの死)十八句」第一幕)
雁帰る女王の心疑へば(同上)
暗き灯を貝に吊りけり春四人(「同上」第二幕)
すみれ草しほれ草とは見えにけり(同上)
春の夜の廓冷かに柱かな(「同上」第四幕)
烏賊共は墨に隠れて来りけり(同上)
春の燭鉄の扉に凍りけり(「同上」第五幕)
おそろしや椿の落つる音もなく(同上)

「タンタヂールの死 (泰西傑作叢書 ; 2)」書誌情報/著者モゥリス・メーテルリンク 作, 小島春潮 訳/出版者 集栄館/出版年月日 大正12)/(「国立国会図書館デジタルコレクション」)
https://dl.ndl.go.jp/pid/915275/1/2
[寅彦・三十二歳。一月、東京帝国大学理科大学助教授となる。二月、次男の正二誕生。三月、宇宙物理学研究のためヨーロッパへ留学。ベルリン大学に学ぶ。四月、従七位に叙せられる。]→(『寺田寅彦全集/文学篇/七巻』には収載句は無い。)
(参考その一) 「タンタジールの死」と《ギルちゃん》(「宮沢賢治の世界」)周辺
https://ihatov.cc/blog/archives/2016/01/post_841.htm
(参考その二) 「西洋文明と融合、新作の糧に 高浜虚子の能、戦後初の復曲上演」周辺

「鐵門」の復曲上演に向け、所作の検討をする観世流能楽師の青木道喜さん(中)ら(京都市左京区の京都観世会館)
https://www.nikkei.com/news/print-article/?ng=DGXLASIH04H07_V00C16A1AA2P00
[(抜粋)
俳人の高浜虚子(1874~1959年)が大正初期に初めて書いた能「鐵門(てつもん)」が6月、京都観世会館(京都市)で復曲上演される。初演から100年に合わせた試みで、戦後の上演は初。西洋戯曲を翻案した新作能の嚆矢(こうし)とされるが、長く上演機会がなかった。今後の能の制作や役作りに生かす狙いだ。(中略)
「鐵門」はベルギーの劇作家・詩人モーリス・メーテルリンク(1862~1949年)が人形劇向けに書いた戯曲「タンタジールの死」に典拠する。死への恐怖と運命を、人間には開けることのできない鉄の門に象徴させた。
虚子は舞台を西洋から日本に移し替え、城に住む姫と姫に仕える老僕らの物語にした。長野県の善光寺に詣でた僧が、門前の者に案内されて暗穴の道に赴くところから始まる。そこに、老僕の霊が姫の霊と共に現れる。老僕はかつて城に忍び入った死の使いの悪尼(あくに)に姫を連れ去られ、そびえ立つ鉄の門に阻(はば)まれて姫を救えなかった経緯などを語る。
(後略) ]
(参考その三) 「青春時代を語る / 東洋城 ; 洋一/p54~73」)」(「俳誌『渋柿(昭和四十年(一九六五)の一月号) 』 (「松根東洋城追悼号」)」所収

「青春時代を語る / 東洋城 ; 洋一/p54~73」時の「東洋城と吉田洋一」(左「東洋城」、右「吉田洋一」)
https://dl.ndl.go.jp/pid/6071686/1/41
「俳誌『渋柿(昭和四十年(一九六五)の一月号)』 (「松根東洋城追悼号」)」は、毀誉褒貶の風聞の中で、その全貌が未だに謎にみちたままの、明治・大正・昭和の三代にわたって、俳諧一筋の、東洋城の言葉でするならば、「芭蕉の誠の俳諧」一筋を貫いた生涯は、この「松根東洋城追悼号」は、その周辺の確かな道標を示すものであろう。
そして、それは、東洋城が没して十年後に刊行された、生前の東洋城の謦咳に接している俳句総合誌の「俳句研究」に携わった俳人の「石川桂郎」著の『俳人風狂列伝』(「読売文学賞」受賞)の、東洋城をめぐるスキャンダル(「白蓮事件」にも連動する「男爵夫人」あるいは「渋柿」からの「あら野」離脱に関連する「同人夫人」)とかの「東洋城の虚像(?)」に対する、その「東洋城の実像(?)」を語るものとして、この「青春時代を語る / 東洋城 ; 洋一/p54~73」や「兄東洋城と私 / 松根新八郎/p74~90」などは、いわば、「石川桂郎」著の『俳人風狂列伝』の「東洋城像(虚像?)」を覆すものの、すなわち、「東洋城(実像?)」を示しているものの、その一端を物語っているように思われる。
そして、これらことは、「虚子と東洋城」との、「ホトトギス(虚子)・国民俳壇(虚子・徳富蘇峰)・渋柿創刊(東洋城)・新傾向俳句の台頭(碧悟桐・井泉水・乙字・一碧楼など)との、混沌した中にあっての、「高浜虚子と松根東洋城」との、その「実像(?)と虚像(?)」との、これまた、その一端を物語る、一つの道標となり得るものであろう。
これらのことに関して、「虚子と東洋城」とが、「新傾向俳句(自由律俳句)」(碧悟桐・井泉水・乙字・一碧楼など)に対して、「伝統俳句(定型律俳句)」の牙城として、「ホトトギス」(虚子主宰)と「渋柿(東洋城主宰)」の二誌が、未曾有の、太平洋戦争前後の統制下にあって、その命脈を保ちつづけたということになる。
上記の写真(「東洋城と吉田洋一」)は、吉田洋一の軽井沢の山荘のもので、東洋城と洋一との接点は、寺田寅彦門下の北海道大学理学部教授の「中谷宇吉郎」を介してのもののようである(『渋柿の木の下で(中村英利子著)』)。
晩年の東洋城の避暑先は、この吉田洋一夫妻の山荘で過ごすのが常のようで、軽井沢は、寺田寅彦・小宮豊隆・中谷宇吉郎・吉田洋一らの忘れ得ざる邂逅の出会いの避暑地でもあったのである。
ここで、「明治四十二年(一九〇九)」の冒頭に戻って、その東洋城年譜の、[東洋城、三十二歳。東洋城の下宿「望遠館」(九段中坂)において、毎週一会の句会が催された。択ばれた者のみが出席できる会で、暮雨(万太郎)、蛇笏、零余子、松浜、喜舟などが、そのメンバーである。三月、東洋城選「新春夏秋冬」夏の部(「序」は夏目漱石)、十月「同・秋の部」を俳書堂より刊行した。]は、「東洋城・虚子、そして、漱石」との三者関係の、その最期の「華やぎ」のような、東洋城の「タンタヂイル(タンタジールの死)十八句」、そして、後の虚子の「大正初期に初めて書いた能『鐵門(てつもん)』(「タンタジールの死」に典拠する)との、当時の最晩年の漱石の膝下にあっての、「虚子と東洋城」との切磋琢磨の時代でもあった。
漱石は、この年に、東洋城選「新春夏秋冬」夏の部の、その刊行に当たって、その「序」を草している。
この東洋城選「新春夏秋冬」夏の部(「漱石・序」)も、下記のアドレスで閲覧することが出来る。
https://kindai.nijl.ac.jp/kindais/HKDT-01067

「新春夏秋冬 夏の部/俳諧叢書第二十二篇/松根東洋城 編」/東洋城撰/明治42.3.5/ 1909.35/函館市中央図書館/
https://kindai.nijl.ac.jp/kindais/HKDT-01067
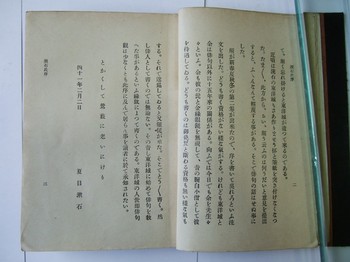
「新春夏秋冬 夏の部/俳諧叢書第二十二篇/松根東洋城 編」所収「夏目漱石『序』(明治四十二年二月二日)」
https://kindai.nijl.ac.jp/kindais/HKDT-01067
[漱石・四十二歳]
[明治42(1909) 1月~3月、「永日小品」、6月~10月、「それから」、9月~10月、中村是公と満州・朝鮮旅行、10月~12月、「満韓ところどころ」、11月、朝日文芸欄創設。 ]
2096 空に消ゆる鐸のひゞきや春の塔(前書「空間を研究せる天然居士の肖像に題す」。)
[天然居士は、漱石の学生時代の友人米山保三郎の号。この句はその兄である米山熊次郎へ送った句。]
(再掲) 「漱石の親友 天然居士・米山保三郎」周辺
https://rendezvou.exblog.jp/7067220/
[学生時代の夏目金之助に作家になることを勧め漱石が彼の言葉に強く動かされた人物・米山保三郎のことはよく知られています。ただ、これまで研究者の中で誤解があり、漱石の語句の解釈に問題があるまま流布されてきたのが現状です。
「天然居士は空間を研究し、論語を読み、焼芋を食い、鼻汁を垂らす人である」
焼き芋と鼻汁を垂らす、これは禅の歴史に実在した中国の禅僧・懶さん(王ヘンに賛)和尚の故事から来る引用なのでした。漱石は畏敬する親友の米山保三郎へ深い愛情と禅に生きる彼を讃える意味で書いたものでしょう。しかし、世間一般ではなかなか通用しない事も充分知っていました。そうであるからこそ、『猫』のなかで次のように書いているのです。
「天然居士は空間を研究し、論語を読み、焼芋を食い、鼻汁を垂らす人である」
苦沙弥先生、一気呵成にこう書き流し、声を出してこれを読み、「ハハハ面白い」と笑うが、「うん。鼻汁を垂らすはさすがに酷だ、焼き芋も蛇足だ」と線を引き。結局「天然居士は空間を研究し論語を読む人である」だけにしたころで、これではあまりに簡単すぎると全部ボツにして、原稿用紙の裏に「空間に生れ、空間を究め、空間に死す。空たり間たり天然居士、噫」
実際、漱石はこの米山の兄、熊次郎から実弟の写真へ揮毫を懇望されて、漱石は俳句を書いています。その俳句とは、
空に消ゆる鐸のひびきや春の塔 という追悼の一句です。親友の死を悼む漱石の心情があふるるばかり、見事な名句と思います。写真は400X300mm、単身像の右側にこの句があり、左にこう記されています。
空間を研究する天然居士の肖像に題す 己酉 四月 漱石
己酉,となれば、1909年、明治四十二年です。漱石が朝日新聞社に入社して2年目の四月に詠んだものと明確に判るのが嬉しいところです。また、米山が鼻水を垂らすの表現がとかく世俗的に解釈され、漱石がいかにしてこの語句を入れたかということは研究者の間でないがしろにされて来ました。しかし、漱石がただ、ユーモラスにこんな語句を入れるはずはないのです。洟を垂らそうが自分は三昧になっているのだという仏道の修行による逸話なのです。
出典もありますから、その引用もしておきましょう。『碧巖録』第三十四則より。
「懶瓚和尚。隱居衡山石室中。唐德宗聞其名。遣使召之。使者至其室宣言。天子有詔。尊者當起謝恩。瓚方撥牛糞火。尋煨芋而食。寒涕垂頤未甞答。使者笑曰。且勸尊者拭涕。瓚曰。我豈有工夫為俗人拭涕耶。竟不起。使回奏。德宗甚欽嘆之。」
(懶瓚和尚、衡山石室の中に隱居す。唐の德、宗其の名を聞いて、使を遣して之を召す。使者、其の室に至つて宣言す。天子詔有り、尊者まさに起つて恩を謝すべし。瓚、まさに牛糞の火を撥つて、煨芋を尋ねて食す。寒涕、頤に垂れて未だ甞て答えず。使者笑つて曰く、且らく勸む、尊者、涕を拭え。瓚曰く、我れ豈に工夫の俗人の為に涕を拭くこと有らん耶といつて、竟に起たず。使、回つて奏す。德宗、甚だ之を欽嘆す。) (以下略) ]
(追記)

漱石(左)と米山保三郎(明治25年)
https://www.asahi.com/articles/ASJ615FM7J61UCVL00W.html
https://yahan.blog.ss-blog.jp/2023-09-08
[東洋城、三十二歳。東洋城の下宿「望遠館」(九段中坂)において、毎週一会の句会が催された。択ばれた者のみが出席できる会で、暮雨(万太郎)、蛇笏、零余子、松浜、喜舟などが、そのメンバーである。三月、東洋城選「新春夏秋冬」夏の部(「序」は夏目漱石)、十月「同・秋の部」を俳書堂より刊行した。]
春月や暗き灯持つ峰の城(「タンタヂイル(タンタジールの死)十八句」第一幕)
雁帰る女王の心疑へば(同上)
暗き灯を貝に吊りけり春四人(「同上」第二幕)
すみれ草しほれ草とは見えにけり(同上)
春の夜の廓冷かに柱かな(「同上」第四幕)
烏賊共は墨に隠れて来りけり(同上)
春の燭鉄の扉に凍りけり(「同上」第五幕)
おそろしや椿の落つる音もなく(同上)

「タンタヂールの死 (泰西傑作叢書 ; 2)」書誌情報/著者モゥリス・メーテルリンク 作, 小島春潮 訳/出版者 集栄館/出版年月日 大正12)/(「国立国会図書館デジタルコレクション」)
https://dl.ndl.go.jp/pid/915275/1/2
[寅彦・三十二歳。一月、東京帝国大学理科大学助教授となる。二月、次男の正二誕生。三月、宇宙物理学研究のためヨーロッパへ留学。ベルリン大学に学ぶ。四月、従七位に叙せられる。]→(『寺田寅彦全集/文学篇/七巻』には収載句は無い。)
(参考その一) 「タンタジールの死」と《ギルちゃん》(「宮沢賢治の世界」)周辺
https://ihatov.cc/blog/archives/2016/01/post_841.htm
(参考その二) 「西洋文明と融合、新作の糧に 高浜虚子の能、戦後初の復曲上演」周辺

「鐵門」の復曲上演に向け、所作の検討をする観世流能楽師の青木道喜さん(中)ら(京都市左京区の京都観世会館)
https://www.nikkei.com/news/print-article/?ng=DGXLASIH04H07_V00C16A1AA2P00
[(抜粋)
俳人の高浜虚子(1874~1959年)が大正初期に初めて書いた能「鐵門(てつもん)」が6月、京都観世会館(京都市)で復曲上演される。初演から100年に合わせた試みで、戦後の上演は初。西洋戯曲を翻案した新作能の嚆矢(こうし)とされるが、長く上演機会がなかった。今後の能の制作や役作りに生かす狙いだ。(中略)
「鐵門」はベルギーの劇作家・詩人モーリス・メーテルリンク(1862~1949年)が人形劇向けに書いた戯曲「タンタジールの死」に典拠する。死への恐怖と運命を、人間には開けることのできない鉄の門に象徴させた。
虚子は舞台を西洋から日本に移し替え、城に住む姫と姫に仕える老僕らの物語にした。長野県の善光寺に詣でた僧が、門前の者に案内されて暗穴の道に赴くところから始まる。そこに、老僕の霊が姫の霊と共に現れる。老僕はかつて城に忍び入った死の使いの悪尼(あくに)に姫を連れ去られ、そびえ立つ鉄の門に阻(はば)まれて姫を救えなかった経緯などを語る。
(後略) ]
(参考その三) 「青春時代を語る / 東洋城 ; 洋一/p54~73」)」(「俳誌『渋柿(昭和四十年(一九六五)の一月号) 』 (「松根東洋城追悼号」)」所収

「青春時代を語る / 東洋城 ; 洋一/p54~73」時の「東洋城と吉田洋一」(左「東洋城」、右「吉田洋一」)
https://dl.ndl.go.jp/pid/6071686/1/41
「俳誌『渋柿(昭和四十年(一九六五)の一月号)』 (「松根東洋城追悼号」)」は、毀誉褒貶の風聞の中で、その全貌が未だに謎にみちたままの、明治・大正・昭和の三代にわたって、俳諧一筋の、東洋城の言葉でするならば、「芭蕉の誠の俳諧」一筋を貫いた生涯は、この「松根東洋城追悼号」は、その周辺の確かな道標を示すものであろう。
そして、それは、東洋城が没して十年後に刊行された、生前の東洋城の謦咳に接している俳句総合誌の「俳句研究」に携わった俳人の「石川桂郎」著の『俳人風狂列伝』(「読売文学賞」受賞)の、東洋城をめぐるスキャンダル(「白蓮事件」にも連動する「男爵夫人」あるいは「渋柿」からの「あら野」離脱に関連する「同人夫人」)とかの「東洋城の虚像(?)」に対する、その「東洋城の実像(?)」を語るものとして、この「青春時代を語る / 東洋城 ; 洋一/p54~73」や「兄東洋城と私 / 松根新八郎/p74~90」などは、いわば、「石川桂郎」著の『俳人風狂列伝』の「東洋城像(虚像?)」を覆すものの、すなわち、「東洋城(実像?)」を示しているものの、その一端を物語っているように思われる。
そして、これらことは、「虚子と東洋城」との、「ホトトギス(虚子)・国民俳壇(虚子・徳富蘇峰)・渋柿創刊(東洋城)・新傾向俳句の台頭(碧悟桐・井泉水・乙字・一碧楼など)との、混沌した中にあっての、「高浜虚子と松根東洋城」との、その「実像(?)と虚像(?)」との、これまた、その一端を物語る、一つの道標となり得るものであろう。
これらのことに関して、「虚子と東洋城」とが、「新傾向俳句(自由律俳句)」(碧悟桐・井泉水・乙字・一碧楼など)に対して、「伝統俳句(定型律俳句)」の牙城として、「ホトトギス」(虚子主宰)と「渋柿(東洋城主宰)」の二誌が、未曾有の、太平洋戦争前後の統制下にあって、その命脈を保ちつづけたということになる。
上記の写真(「東洋城と吉田洋一」)は、吉田洋一の軽井沢の山荘のもので、東洋城と洋一との接点は、寺田寅彦門下の北海道大学理学部教授の「中谷宇吉郎」を介してのもののようである(『渋柿の木の下で(中村英利子著)』)。
晩年の東洋城の避暑先は、この吉田洋一夫妻の山荘で過ごすのが常のようで、軽井沢は、寺田寅彦・小宮豊隆・中谷宇吉郎・吉田洋一らの忘れ得ざる邂逅の出会いの避暑地でもあったのである。
ここで、「明治四十二年(一九〇九)」の冒頭に戻って、その東洋城年譜の、[東洋城、三十二歳。東洋城の下宿「望遠館」(九段中坂)において、毎週一会の句会が催された。択ばれた者のみが出席できる会で、暮雨(万太郎)、蛇笏、零余子、松浜、喜舟などが、そのメンバーである。三月、東洋城選「新春夏秋冬」夏の部(「序」は夏目漱石)、十月「同・秋の部」を俳書堂より刊行した。]は、「東洋城・虚子、そして、漱石」との三者関係の、その最期の「華やぎ」のような、東洋城の「タンタヂイル(タンタジールの死)十八句」、そして、後の虚子の「大正初期に初めて書いた能『鐵門(てつもん)』(「タンタジールの死」に典拠する)との、当時の最晩年の漱石の膝下にあっての、「虚子と東洋城」との切磋琢磨の時代でもあった。
漱石は、この年に、東洋城選「新春夏秋冬」夏の部の、その刊行に当たって、その「序」を草している。
この東洋城選「新春夏秋冬」夏の部(「漱石・序」)も、下記のアドレスで閲覧することが出来る。
https://kindai.nijl.ac.jp/kindais/HKDT-01067

「新春夏秋冬 夏の部/俳諧叢書第二十二篇/松根東洋城 編」/東洋城撰/明治42.3.5/ 1909.35/函館市中央図書館/
https://kindai.nijl.ac.jp/kindais/HKDT-01067
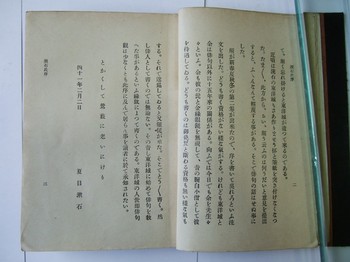
「新春夏秋冬 夏の部/俳諧叢書第二十二篇/松根東洋城 編」所収「夏目漱石『序』(明治四十二年二月二日)」
https://kindai.nijl.ac.jp/kindais/HKDT-01067



