「漱石・東洋城・寅彦」(子規没後~漱石没まで)俳句管見(その十一) [漱石・東洋城・寅彦]
その十一「大正二年(一九一三)」
[漱石・四十六歳。大正2(1913)2月『社会と自分』。三月より五月まで、胃潰瘍の三度目の再発で病臥する。病中より、楽しみに絵筆を執る。 ]
2307 人形も馬もうごかぬ長閑さよ
2308 菊一本画いて君の佳節哉
2309 四五本の竹をあつめて月夜哉
2310 萩の粥月待つ庵となりにけり
2311 葉鶏頭高さ五尺に育てけり

夏目漱石画「菊図」(「みやこ町歴史民俗博物館/WEB博物館「みやこ町遺産」/小宮豊隆資料」)
http://miyako-museum.jp/list/detail.php?uniq_id=107
≪小宮豊隆(1884-1966)は、みやこ町犀川久富出身のドイツ文学者・文芸評論家です。夏目漱石の門下として詳細な漱石研究や、今なお刊行が続く漱石全集を監修したことでも知られています。平成25年(2013)以降、1000点近い資料が小宮氏遺族から故郷のみやこ町に寄贈されました。みやこ町ではこれを「小宮豊隆資料」と名付け、博物館内に記念展示室を設け、小宮の人生と業績の紹介・顕彰につとめています。≫
2308 菊一本画いて君の佳節哉
[この句の「君」は、上記の「菊図」(「みやこ町歴史民俗博物館/小宮豊隆資料」)と対応させると、「小宮豊隆」(「漱石の『三四郎』のモデルとしても知られる。俳号の逢里雨(ほうりう)は、豊隆の音読み(ほうりゅう)に別の字を宛てたもの」)の、その「佳節」「(明治44年/1911/1月郷里にて結婚」)祝いのものなのかも知れない。]
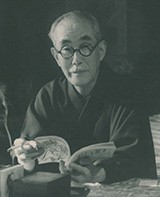
「小宮豊隆(俳号・逢里雨)」(「みやこ町歴史民俗博物館/小宮豊隆資料」)
https://adeac.jp/miyako-hf-mus/top/
[小宮豊隆氏(年譜)
明治17年 1884 3月7日福岡県仲津郡久富村(現犀川町久富)で生まれる。
明治20年 1887 父・弥三郎の転勤にともない大和郡山へ移る。
明治24年 1891 帰郷し、豊津尋常小学校に転校。
明治27年 1894 5月22日父・弥三郎死去。
明治30年 1897 豊津高等小学校卒業。福岡県立尋常中学校に入学。
明治35年 1902 豊津中学校卒業。7月に第一高等学校入学。
明治38年 1905 7月第一高等学校卒業。9月東京帝国大学文学部独文科に入学。従兄の犬塚武夫の紹介で夏目漱石の知遇を得、在学中の保証人を依頼する。大学ではドイツ語の講義とともに、漱石の「文学評論」やシェイクスピアの講義も聴講する。
明治41年 1908 7月東京帝国大学卒業。
明治42年 1909 4月慶応義塾大学に文学部が創設され、講師となる。このころから、ロシア文学への興味が深まる。朝日新聞に文芸欄が創設され、漱石の手伝いをする。
明治44年 1911 1月郷里にて結婚。
大正5年 1916 東京医学専門学校講師となる。12月9日夏目漱石死去。
大正6年 1917 「漱石全集」の編集にとりかかる。
大正9年 1920 海軍大学校嘱託教授となる。
大正10年 1921 芭蕉研究会に参加。
大正11年 1922 4月法政大学教授となる。東北帝国大学法文学部独文講座を引き受ける。
大正12年 1923 3月渡欧。5月にベルリンに到着し、以後欧州各国を歴訪。
大正13年 1924 帰国。東北帝国大学教授となる。
大正15年 1926 芭蕉俳諧研究会を始める。
昭和21年 1946 東京音楽学校(現東京芸術大学)校長となる。教育刷新委員・国語審議会委員となる。
昭和22年 1947 6月都民劇場運営委員長となる。
昭和23年 1948 11月東北帝国大学名誉教授の称号を贈られる。
昭和24年 1949 6月東京音楽学校々長辞職。東京女子大学講師・俳文学会々長となる。
昭和25年 1950 4月学習院大学教授となる。以降、学習院では文学部長・女子短期大学々長をつとめる。12月文化財専門審議会専門委員となる。
昭和26年 1951 10月学士院会員となる。
昭和29年 1954 5月著書「夏目漱石」で芸術院賞受賞。
昭和30年 1955 4月財団法人都民劇場会長。7月国立劇場設立準備協議会々長を委嘱される。
昭和32年 1957 3月学習院退職。4月東京都教育委員となる。
昭和33年 1958 「世阿弥の芸術」を御進講する。
昭和34年 1959 東京都教育委員辞任。
昭和35年 1960 東大病院に入院。手術を受ける。
昭和36年 1961 喜寿・金婚式。
昭和40年 1965 3月都民劇場会長辞任。同名誉会長となる。
昭和41年 1966 5月3日午前4時、肺炎のため東京都杉並区の自宅にて逝去。享年82歳。東京南多摩霊園と豊津町峯高寺に分骨埋葬。
(「篷里雨句集」巻末年譜及び小宮里子氏のご教示により作成) )
[東洋城・三十六歳。筑紫明石町六十一番地へ移転。]
旧作の松は雪より新にて(大正二年作)
[前書に「古(ふる)き新(あたらし)き弁
虚子曰く「・・・それでは陳腐を主張する者と誤解される恐があらう」、城曰く「だから古くといはず古臭くといい又或意味に於てと小書付にして置いた」。。虚曰く「俳句の関する範囲内で可成新しくというた方が穏当ぢゃないか」、城曰く「そんな事は言を俟たぬ事だ。元禄天明の句を見て明治の句をなし去年の句を措いて今年の句を作り昨日も作つてゐたのに今日も亦俳句を止めぬのが、皆後の前に異り今の作に同じからぬ新しきを欲求する故に続いて俳句に従事してゐるのである。俳句を続けてやるということが即ち句々の新境を所幾する事ではないか。取立てていふには余りに分りきつた事だ。星学者が望星鏡の下に寝て他所目には一生同じ事を繰返してゐるかの様に毎日毎日空を仰いでゐるのも畢竟毎日毎日香刻一刻の新しきを窺う為めである。俳句我等の俳句は研究的、創作的である。遊戯でも玩弄物でもない以上之を続けるといふ事其事が新しからむとするに外ならぬ事は明らかである。何の御苦労にも事々しく新し呼ばはりする必要があろう」。虚曰く、「それならよいが衆人の誤解き引起させぬ為めに新しくといふ事をいうてもいいぢやないか」。城曰く「イヤそれは時宜ではない、迷ふた者が新しくと誤用して迷ふ者の道標としてゐる当今に又新しくといふては迷ふ者にとつて差別がつかぬ、新しくといふ事が言ふまでもない当然の事である以上いつそ古めかしくいうて俳句の本体を教へてやるのもよかろ」。虚曰く「どうして?」]
[寅彦・三十六歳。八月、父が死亡する。十月、従六位に叙せられる。]→[『寺田寅彦全集/文学篇/七巻』には収載句は無い。]
(参考) 明治俳壇の喧囂(けんごう)な終局―│虚子の俳壇復帰とその時代」―(田辺知季稿)周辺
https://www.jstage.jst.go.jp/article/nihonkindaibungaku/103/0/103_1/_pdf/-char/ja
(抜粋)
[ 現下の俳壇には勗(つと)めて近代の思想趣味に接触せんとする者、極力古典趣味に生きんとする者との二個の潮流がある。前者は取りも直さず日本及日本人を中心とせる碧梧桐の一派で所謂新傾向の一団である、後者は即ち国民俳壇に依る所謂古き新派を代表せる東洋城の一派である。]
[ あるいは国民俳壇の東洋城はどうか。当時の彼は旧弊とみなされがちな自派の句風を擁護するなかで、 「いつまでも元禄でなく明治であり大正である事を忘れて居らぬが故に、或意味にて、我等は殊更古臭く作る事をほ句の使命と思ふ」と語っている(大一・一二・三『国民新聞』俳句欄)。
とはいえ、虚子との対話を録した「俳諧古き新き弁(上)」(大一・一二・八『国民新聞』 )
によると、東洋城はあくまでも「句々の新境を庶幾する」からこそ句作を続けるのであり、単純な「古さ」を是認するわけではないという。そもそも「俳句は出来上つた詩」、「方向の定まつた文学」である以上( 「俳諧古き新き弁(下) 」、大一・一二・一、同前、)その枠内で「新境」を模索すべきだというのだ。
さらに先述の俳誌『ツボミ』では、田中蛇湖が右の東洋城の一文を「有益の文字」と認め、 「只々新しひあたらしひと云つて、芸術の本領を没却し、彼の発明家者流などと齷齪日を終るべけんやである」と同調している( 「筆のまにまに㈦」、、大二・一・二〇、三巻一号。)
また木内螢覇郎も、 「古き形式を守り古き約束を固守し、大正式文明に後れまじと古き中より、新しき十七字を形成するこそ所謂新俳句と云ふべけれ」と謳っている( 「蒙御免」 、
大二・三・二〇、三巻三号。)
こうした論調は当然『ホトトギス』俳壇の再興と共鳴しており、「ホトヽギスの雑吟を読めば読む程そぞろに爽快を覚ゆ」(同前)や、「虚子氏の平明調を唱導してより句界の特に活気を引き興し候は喜はしき事に候」(秋元虚受「巻末録」、同前)といった文言も認められる。さらには、「新らしき思想を練り所謂穏健なる平明調の鼓吹に努め」ることこそが「本誌兼ての希望なの」だと表明し(無署名「告白」、大二・七・二〇、三巻六号)、「ツボミは真面目に健やかなる思想の下に、所謂平明調を鼓吹する事に決し候」と宣言している(虚受「巻
末録」、同前。) ]
[ 虚子はこうした状況の下、「『新』といふ言葉」に「心を躍らす」 「青年」(虚子「俳話」 、大一・一二・二『東京朝日新聞』朝刊)には迎合しない「守旧派」として俳句に復帰する。
ただし最後に付言しておくと、彼が提示する俳句像は必ずしも時流に真っ向から逆行しているわけではない。当時の虚子は「余が俳句の中には芸術品としてイプセンやハウプトマン位に比肩すべきものは沢山ある」と自負し、「これから何年俳句を作つたとて、俳句の文学的価値のレベルは高まりはし無い」と論じている(前掲「鎌倉日記」、、明四五・六・一)。
既存の俳句史では軽視されているが、明治四十年代の『ホトトギス』では脚本や劇評な
どを掲載し、文芸協会の改組などに沸く文壇の演劇熱に乗じていた。ここでは、当時劇界を中心に文壇で広く仰望された二人の名を挙げることで、俳句をそれに匹敵する文芸として演出しているのだ。]
[ 明治末頃から大正初頭の新傾向派、特に碧梧桐の下から自立していった乙字や井泉水は、最先端の世界的な文芸思潮に共鳴しながら各々が理想とする俳句像を確立していく。対する虚子は、それとは別の経路で俳句を「世界の文芸」と結びつけ、季題趣味によって「旧」に止まる守旧派を価値づけている。周知のように、後年の彼は俳句を「花鳥諷詠の文学」、 「我国にひとり存在するところの特異な文学」と位置づけつつ、「花鳥諷詠の文学(詩)が存在してゐるといふことは、我が国民の誇りとすべきもの」だと語っている(『俳句への道』 、一九五五・一、岩波新書、「俳句への道」 )。俳句の「正統」として信奉される「花鳥諷詠」は、「国民性」を意識した俳壇復帰の延長線上から立ち現われてくることとなる。]
[漱石・四十六歳。大正2(1913)2月『社会と自分』。三月より五月まで、胃潰瘍の三度目の再発で病臥する。病中より、楽しみに絵筆を執る。 ]
2307 人形も馬もうごかぬ長閑さよ
2308 菊一本画いて君の佳節哉
2309 四五本の竹をあつめて月夜哉
2310 萩の粥月待つ庵となりにけり
2311 葉鶏頭高さ五尺に育てけり

夏目漱石画「菊図」(「みやこ町歴史民俗博物館/WEB博物館「みやこ町遺産」/小宮豊隆資料」)
http://miyako-museum.jp/list/detail.php?uniq_id=107
≪小宮豊隆(1884-1966)は、みやこ町犀川久富出身のドイツ文学者・文芸評論家です。夏目漱石の門下として詳細な漱石研究や、今なお刊行が続く漱石全集を監修したことでも知られています。平成25年(2013)以降、1000点近い資料が小宮氏遺族から故郷のみやこ町に寄贈されました。みやこ町ではこれを「小宮豊隆資料」と名付け、博物館内に記念展示室を設け、小宮の人生と業績の紹介・顕彰につとめています。≫
2308 菊一本画いて君の佳節哉
[この句の「君」は、上記の「菊図」(「みやこ町歴史民俗博物館/小宮豊隆資料」)と対応させると、「小宮豊隆」(「漱石の『三四郎』のモデルとしても知られる。俳号の逢里雨(ほうりう)は、豊隆の音読み(ほうりゅう)に別の字を宛てたもの」)の、その「佳節」「(明治44年/1911/1月郷里にて結婚」)祝いのものなのかも知れない。]
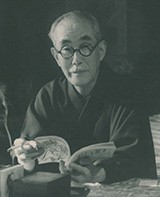
「小宮豊隆(俳号・逢里雨)」(「みやこ町歴史民俗博物館/小宮豊隆資料」)
https://adeac.jp/miyako-hf-mus/top/
[小宮豊隆氏(年譜)
明治17年 1884 3月7日福岡県仲津郡久富村(現犀川町久富)で生まれる。
明治20年 1887 父・弥三郎の転勤にともない大和郡山へ移る。
明治24年 1891 帰郷し、豊津尋常小学校に転校。
明治27年 1894 5月22日父・弥三郎死去。
明治30年 1897 豊津高等小学校卒業。福岡県立尋常中学校に入学。
明治35年 1902 豊津中学校卒業。7月に第一高等学校入学。
明治38年 1905 7月第一高等学校卒業。9月東京帝国大学文学部独文科に入学。従兄の犬塚武夫の紹介で夏目漱石の知遇を得、在学中の保証人を依頼する。大学ではドイツ語の講義とともに、漱石の「文学評論」やシェイクスピアの講義も聴講する。
明治41年 1908 7月東京帝国大学卒業。
明治42年 1909 4月慶応義塾大学に文学部が創設され、講師となる。このころから、ロシア文学への興味が深まる。朝日新聞に文芸欄が創設され、漱石の手伝いをする。
明治44年 1911 1月郷里にて結婚。
大正5年 1916 東京医学専門学校講師となる。12月9日夏目漱石死去。
大正6年 1917 「漱石全集」の編集にとりかかる。
大正9年 1920 海軍大学校嘱託教授となる。
大正10年 1921 芭蕉研究会に参加。
大正11年 1922 4月法政大学教授となる。東北帝国大学法文学部独文講座を引き受ける。
大正12年 1923 3月渡欧。5月にベルリンに到着し、以後欧州各国を歴訪。
大正13年 1924 帰国。東北帝国大学教授となる。
大正15年 1926 芭蕉俳諧研究会を始める。
昭和21年 1946 東京音楽学校(現東京芸術大学)校長となる。教育刷新委員・国語審議会委員となる。
昭和22年 1947 6月都民劇場運営委員長となる。
昭和23年 1948 11月東北帝国大学名誉教授の称号を贈られる。
昭和24年 1949 6月東京音楽学校々長辞職。東京女子大学講師・俳文学会々長となる。
昭和25年 1950 4月学習院大学教授となる。以降、学習院では文学部長・女子短期大学々長をつとめる。12月文化財専門審議会専門委員となる。
昭和26年 1951 10月学士院会員となる。
昭和29年 1954 5月著書「夏目漱石」で芸術院賞受賞。
昭和30年 1955 4月財団法人都民劇場会長。7月国立劇場設立準備協議会々長を委嘱される。
昭和32年 1957 3月学習院退職。4月東京都教育委員となる。
昭和33年 1958 「世阿弥の芸術」を御進講する。
昭和34年 1959 東京都教育委員辞任。
昭和35年 1960 東大病院に入院。手術を受ける。
昭和36年 1961 喜寿・金婚式。
昭和40年 1965 3月都民劇場会長辞任。同名誉会長となる。
昭和41年 1966 5月3日午前4時、肺炎のため東京都杉並区の自宅にて逝去。享年82歳。東京南多摩霊園と豊津町峯高寺に分骨埋葬。
(「篷里雨句集」巻末年譜及び小宮里子氏のご教示により作成) )
[東洋城・三十六歳。筑紫明石町六十一番地へ移転。]
旧作の松は雪より新にて(大正二年作)
[前書に「古(ふる)き新(あたらし)き弁
虚子曰く「・・・それでは陳腐を主張する者と誤解される恐があらう」、城曰く「だから古くといはず古臭くといい又或意味に於てと小書付にして置いた」。。虚曰く「俳句の関する範囲内で可成新しくというた方が穏当ぢゃないか」、城曰く「そんな事は言を俟たぬ事だ。元禄天明の句を見て明治の句をなし去年の句を措いて今年の句を作り昨日も作つてゐたのに今日も亦俳句を止めぬのが、皆後の前に異り今の作に同じからぬ新しきを欲求する故に続いて俳句に従事してゐるのである。俳句を続けてやるということが即ち句々の新境を所幾する事ではないか。取立てていふには余りに分りきつた事だ。星学者が望星鏡の下に寝て他所目には一生同じ事を繰返してゐるかの様に毎日毎日空を仰いでゐるのも畢竟毎日毎日香刻一刻の新しきを窺う為めである。俳句我等の俳句は研究的、創作的である。遊戯でも玩弄物でもない以上之を続けるといふ事其事が新しからむとするに外ならぬ事は明らかである。何の御苦労にも事々しく新し呼ばはりする必要があろう」。虚曰く、「それならよいが衆人の誤解き引起させぬ為めに新しくといふ事をいうてもいいぢやないか」。城曰く「イヤそれは時宜ではない、迷ふた者が新しくと誤用して迷ふ者の道標としてゐる当今に又新しくといふては迷ふ者にとつて差別がつかぬ、新しくといふ事が言ふまでもない当然の事である以上いつそ古めかしくいうて俳句の本体を教へてやるのもよかろ」。虚曰く「どうして?」]
[寅彦・三十六歳。八月、父が死亡する。十月、従六位に叙せられる。]→[『寺田寅彦全集/文学篇/七巻』には収載句は無い。]
(参考) 明治俳壇の喧囂(けんごう)な終局―│虚子の俳壇復帰とその時代」―(田辺知季稿)周辺
https://www.jstage.jst.go.jp/article/nihonkindaibungaku/103/0/103_1/_pdf/-char/ja
(抜粋)
[ 現下の俳壇には勗(つと)めて近代の思想趣味に接触せんとする者、極力古典趣味に生きんとする者との二個の潮流がある。前者は取りも直さず日本及日本人を中心とせる碧梧桐の一派で所謂新傾向の一団である、後者は即ち国民俳壇に依る所謂古き新派を代表せる東洋城の一派である。]
[ あるいは国民俳壇の東洋城はどうか。当時の彼は旧弊とみなされがちな自派の句風を擁護するなかで、 「いつまでも元禄でなく明治であり大正である事を忘れて居らぬが故に、或意味にて、我等は殊更古臭く作る事をほ句の使命と思ふ」と語っている(大一・一二・三『国民新聞』俳句欄)。
とはいえ、虚子との対話を録した「俳諧古き新き弁(上)」(大一・一二・八『国民新聞』 )
によると、東洋城はあくまでも「句々の新境を庶幾する」からこそ句作を続けるのであり、単純な「古さ」を是認するわけではないという。そもそも「俳句は出来上つた詩」、「方向の定まつた文学」である以上( 「俳諧古き新き弁(下) 」、大一・一二・一、同前、)その枠内で「新境」を模索すべきだというのだ。
さらに先述の俳誌『ツボミ』では、田中蛇湖が右の東洋城の一文を「有益の文字」と認め、 「只々新しひあたらしひと云つて、芸術の本領を没却し、彼の発明家者流などと齷齪日を終るべけんやである」と同調している( 「筆のまにまに㈦」、、大二・一・二〇、三巻一号。)
また木内螢覇郎も、 「古き形式を守り古き約束を固守し、大正式文明に後れまじと古き中より、新しき十七字を形成するこそ所謂新俳句と云ふべけれ」と謳っている( 「蒙御免」 、
大二・三・二〇、三巻三号。)
こうした論調は当然『ホトトギス』俳壇の再興と共鳴しており、「ホトヽギスの雑吟を読めば読む程そぞろに爽快を覚ゆ」(同前)や、「虚子氏の平明調を唱導してより句界の特に活気を引き興し候は喜はしき事に候」(秋元虚受「巻末録」、同前)といった文言も認められる。さらには、「新らしき思想を練り所謂穏健なる平明調の鼓吹に努め」ることこそが「本誌兼ての希望なの」だと表明し(無署名「告白」、大二・七・二〇、三巻六号)、「ツボミは真面目に健やかなる思想の下に、所謂平明調を鼓吹する事に決し候」と宣言している(虚受「巻
末録」、同前。) ]
[ 虚子はこうした状況の下、「『新』といふ言葉」に「心を躍らす」 「青年」(虚子「俳話」 、大一・一二・二『東京朝日新聞』朝刊)には迎合しない「守旧派」として俳句に復帰する。
ただし最後に付言しておくと、彼が提示する俳句像は必ずしも時流に真っ向から逆行しているわけではない。当時の虚子は「余が俳句の中には芸術品としてイプセンやハウプトマン位に比肩すべきものは沢山ある」と自負し、「これから何年俳句を作つたとて、俳句の文学的価値のレベルは高まりはし無い」と論じている(前掲「鎌倉日記」、、明四五・六・一)。
既存の俳句史では軽視されているが、明治四十年代の『ホトトギス』では脚本や劇評な
どを掲載し、文芸協会の改組などに沸く文壇の演劇熱に乗じていた。ここでは、当時劇界を中心に文壇で広く仰望された二人の名を挙げることで、俳句をそれに匹敵する文芸として演出しているのだ。]
[ 明治末頃から大正初頭の新傾向派、特に碧梧桐の下から自立していった乙字や井泉水は、最先端の世界的な文芸思潮に共鳴しながら各々が理想とする俳句像を確立していく。対する虚子は、それとは別の経路で俳句を「世界の文芸」と結びつけ、季題趣味によって「旧」に止まる守旧派を価値づけている。周知のように、後年の彼は俳句を「花鳥諷詠の文学」、 「我国にひとり存在するところの特異な文学」と位置づけつつ、「花鳥諷詠の文学(詩)が存在してゐるといふことは、我が国民の誇りとすべきもの」だと語っている(『俳句への道』 、一九五五・一、岩波新書、「俳句への道」 )。俳句の「正統」として信奉される「花鳥諷詠」は、「国民性」を意識した俳壇復帰の延長線上から立ち現われてくることとなる。]




コメント 0