「子規・漱石・寅彦・東洋城」俳句管見(その十四) [子規・漱石・寅彦・東洋城]
その十四「明治三十五年(一九〇二)・「糸瓜・絲瓜」など」
(子規、九月十八日、「絶筆三句」、十九日、午前一時永眠(三十六歳)
https://shiki-museum.com/masaokashiki/haiku?post_type=haiku&post_type=haiku&haiku_id=&p_age=&season=&classification=&kigo=%E7%B3%B8%E7%93%9C&s=&select=
秋に形あらば糸瓜に似たるべし ID1461 制作年24 季節秋 分類植物 季語糸瓜
しばらくは風のもつるゝ糸瓜かな ID1462 制作年24 季節秋 分類植物 季語糸瓜
露いくつ糸瓜の尻に出あひけり ID4026 制作年25 季節秋 分類植物 季語糸瓜
蔓かれてへちまぶらりと不二の山 ID4027 制作年25 季節秋 分類植物 季語糸瓜
茶屋淋し糸瓜の蔓の這ひかゝる ID8458 制作年26 季節秋 分類植物 季語糸瓜
家一つ門は糸瓜の月夜かな ID11585 制作年27 季節秋 分類植物 季語糸瓜
柴の戸に糸瓜の風の静かさよ ID11586 制作年27 季節秋 分類植物 季語糸瓜
投げ出したやうな糸瓜や垣の外 ID11587 制作年27 季節秋 分類植物 季語糸瓜
投げ出したやうに垣根の糸瓜哉 ID11588 制作年27 季節秋 分類植物 季語糸瓜
糸瓜肥え鶏頭痩せぬ背戸の雨 ID11589 制作年27 季節秋 分類植物 季語糸瓜
わぐなつて残る糸瓜や屋根の上 ID11590 制作年27 季節秋 分類植物 季語糸瓜
五六反叔父がつくりし糸瓜かな ID14851 制作年28 季節秋 分類植物 季語糸瓜
雪隠の窓にぶらりと糸瓜かな ID14852 制作年28 季節秋 分類植物 季語糸瓜
行く秋を糸瓜にさはる雲もなし ID14853 制作年28 季節秋 分類植物 季語糸瓜
垢すりになるべく糸瓜愚也けり ID18381 制作年29 季節秋 分類植物 季語糸瓜
秋のいろあかきへちまを畫にかゝむ ID20297 制作年30 季節秋 分類植物 季語糸瓜
へちまとは糸瓜のようなものならん ID20298 制作年30 季節秋 分類植物 季語糸瓜
夕顔の貧に處る糸瓜の愚を守る ID20299 制作年30 季節秋 分類植物 季語糸瓜
西行に糸瓜の歌はなかりけり ID21889 制作年31 季節秋 分類植物 季語糸瓜
内閣を糸瓜にたとへ論ずべく ID21890 制作年31 季節秋 分類植物 季語糸瓜
糸瓜とも瓢ともわかぬ目利哉 ID23012 制作年32 季節秋 分類植物 季語糸瓜
愚なる処すなはち雅なる糸瓜かな ID23888 制作年33 季節秋 分類植物 季語糸瓜
目鼻画く糸瓜の顔の長さ哉 ID23889 制作年33 季節秋 分類植物 季語糸瓜
秋ノ灯ノ糸瓜ノ尻ニ映リケリ ID24485 制作年34 季節秋 分類植物 季語糸瓜
棚ノ糸瓜思フ処ヘブラ下ル ID24486 制作年34 季節秋 分類植物 季語糸瓜
西ヘマハル秋ノ日影ヤ糸瓜棚 ID24487 制作年34 季節秋 分類植物 季語糸瓜
病間ニ糸瓜ノ句ナド作リケル ID24488 制作年34 季節秋 分類植物 季語糸瓜
病閑ニ糸瓜ノ花ノ落ツル昼 ID24489 制作年34 季節秋 分類植物 季語糸瓜
日掩棚糸瓜ノ蔓ノ這ヒ足ラズ ID24490 制作年34 季節秋 分類植物 季語糸瓜
糸瓜サヘ仏ニナルゾ後ルゝナ ID24491 制作年34 季節秋 分類植物 季語糸瓜
糸瓜ニハ可モ不可モナキ残暑カナ ID24492 制作年34 季節秋 分類植物 季語糸瓜
糸瓜ブラリ夕顔ダラリ秋ノ風 ID24493 制作年34 季節秋 分類植物 季語糸瓜
牡丹ニモ死ナズ瓜ニモ糸瓜ニモ ID24494 制作年34 季節秋 分類植物 季語糸瓜
黙然ト糸瓜ノサガル庭ノ秋 ID24495 制作年34 季節秋 分類植物 季語糸瓜
物思フ窓ニブラリト糸瓜哉 ID24496 制作年34 季節秋 分類植物 季語糸瓜
夕顔ト糸瓜残暑ト新涼と ID24497 制作年34 季節秋 分類植物 季語糸瓜
夕顔ノ棚に糸瓜モ下リケリ ID24498 制作年34 季節秋 分類植物 季語糸瓜
夕顔モ糸瓜モ同ジ棚子同士 ID24499 制作年34 季節秋 分類植物 季語糸瓜
「絶筆三句」
痰一斗糸瓜の水も間にあはず ID25012 制作年35 季節秋 分類植物 季語糸瓜
糸瓜咲て痰のつまりし仏かな ID25013 制作年35 季節秋 分類植物 季語糸瓜
をととひのへちまの水も取らざりき ID25014 制作年35 季節秋 分類植物 季語糸瓜
(漱石、三十六歳。十二月、帰国の途につく。その直前に子規没との虚子・碧悟桐の書翰が届く。)
66 風ふけば糸瓜をなぐるふくべ哉(明治二十八年)
904 長けれど何の糸瓜とさがりけり(明治二十九年。「子規へ送りたる句稿十七」)
1737 容赦なく瓢を叩く糸瓜かな(明治三十二年。「子規へ送りたる句稿三十五」)
1848 一大事も糸瓜も糞もあらばこそ(明治三十六年)
(寅彦、二十五歳。『俳句と地球物理』所収「略年譜」/『寺田寅彦全集/文学篇/七巻』」)
面白し瀬戸の絲瓜(へちま)の長短(明治三十一年作)
日一日ぶらりぶらりと絲瓜哉(同上)
世をすねて日影の絲瓜そりかへる(明治三十一~二年作)
長過て肥手桶たゝく絲瓜哉(同上)
干からびし絲瓜をつるす納屋の軒(同上)
(東洋城、二十五歳。『東洋城全句集上・中巻』)
糸瓜忌や只句を作るあな尊と(明治四十五年作)
道の家の糸瓜に起す話頭かな(大正九年作。前書「子規忌順礼 二十七句」)
(参考その一) 「絶筆三句 子規」周辺
https://yahan.blog.ss-blog.jp/2023-09-05
(再掲)
https://www.ndl.go.jp/exhibit70/23.html
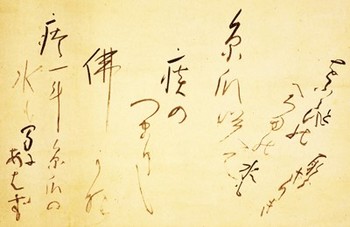
「絶筆三句 子規」(紙本墨書/31.0×44.3㎝/国立国会図書館蔵)
https://www.ndl.go.jp/exhibit70/23.html
≪〔正岡子規 著〕〔正岡子規 明治35(1902)年〕写【WB41-61】43 〔絶筆三句〕の画像(デジタルコレクション)
日本の近代文学に多大な影響を及ぼした俳人、歌人の正岡子規が臨終間際に書き残した三句。明治35(1902)年9月18日の午前11時頃、紙を貼りつけた画板を妹の律に持たせ、仰臥しながら記した。翌19日午前1時頃、子規の息は絶えた。満34歳の若さであった。病魔に苦しみながらも、死の直前まで俳人として生き抜いた壮絶な姿がうかがえる。
(書き起こし)
をととひのへちまの水も取らざりき/糸瓜咲て痰のつまりし佛かな/痰一斗糸瓜の水も間にあはず ≫
(追記)
倫敦にて子規の訃を聞て(五句)
1824 筒袖や秋の棺にしたがはず (漱石・36歳「明治35年(1902)」)
≪ 季=秋(雑)。※子規は九月十九日に他界した。虚子から要請のあった子規追悼文に代えてこれらの句を送った。その書簡では子規の死について、「かかる病苦になやみ候よりも早く往生致す方或は本人の幸福かと存候」と述べている。その後で、「子規追悼の句何かと案じ煩ひ候へども、かく筒袖にてピステキのみ食ひ居候者には容易に俳想なるもの出現仕らず、昨夜ストーブの傍にて左の駄句を得申候。得たると申すよりは寧ろ無理やりに得さしめたる次第に候へば、只申訳の為め御笑草として御覧に入候。近頃の如く半ば西洋人にて半日本人にては甚だ妙ちきりんなものに候」と言い、これらの句を記した。句のあとに「皆蕪雑句をなさず。叱正」とある。筒袖は洋服姿。◇書簡(高浜虚子宛、明治35.12.1)。雑誌「ホトトギス」(明治36.2)。 ≫(『漱石全集第十七巻・坪内稔典注解』)
1825 手向くべき線香もなくて暮の秋 (漱石・36歳「明治35年(1902)」)
≪ 季=暮の秋。◇1824。≫(「同上」)
1826 霜黄なる市に動くや影法師 (漱石・36歳「明治35年(1902)」)
≪ 季=霧(秋)。◇1824。(「同上」)≫
1827 きりぎりすの昔を忍び帰るべし (漱石・36歳「明治35年(1902)」)
≪ 季=きりぎりす(秋)。◇1824。≫(「同上」)
1626 招かざる薄に帰り来る人ぞ (漱石・36歳「明治35年(1902)」)
≪ 季=薄(秋)。◇1824。≫(「同上」)
(参考その二) 「碧梧桐の『子規の回想』」周辺
https://plaza.rakuten.co.jp/akiradoinaka/diary/202105250000/
≪ 子規の最期については、高浜虚子の『子規居士と余』が引き合いに出されます。かたや河東碧梧桐の文が引用されることはあまりありません。『子規居士と余』は岩波文庫の『回想 子規・漱石』に収録されていますが、碧梧桐の『子規の回想』は、子規が漱石の下宿・愚陀仏庵に行くところまでしか『子規を語る』に収録されていないのです。
『子規の回想』に記された「辞世の句」を、次の回は「死後」をみていただきます。
これが終わりましたら、虚子と碧梧桐の俳句観について書かせていただきます。
二十八 辞世
ことさらに辞世の句を作らないと言った芭蕉を、さすがに芭蕉らしい、と話したこともある。また太祇の辞世の句が、平生の伎価に似ない。あれ程の蕪村にしても辞世はどこか弱々しいと言ったこともある。
古人の辞世の句をおおむね否定していたから、自分の場合にも無論思い及んだ筈であるが、どういうものか、辞世を作ることにかなり執着を持っていた。芭蕉でもない者が、芭蕉を気取るのを避けた意味であったかも知れぬ。死ぬる三日前に「九月十四日の朝」と題して文章を口誦した程、死生の間に超然としていた人であるから、考え得るなら辞世を考えてもいい、と例の強烈な心的生活力が働いていたかも知れない。
明治三十三年十八日の「病牀六尺」と四月発行の「ほととぎす」の消息は、子規自らも「近頃不覚をとった」と言っているように、辞世について閑葛藤のあったことを明らかにしている。それによって、追憶の糸たぐって見ると、その五月十三日午後六時頃、子規直筆の急便によって、私はある宴会の席上から駆け付け、虚子も宮本国手も相次いで来着したのだが、子規の阿鼻叫喚の苦悶は、真に見るに堪えぬものがあった。その夜は虚子宿直して翌十四日となり、病苦はやや平静に帰したが、疲労その極に達して、何の食欲もなく、時には失神したのかを患える程全く元気がなかった。その夜私が宿直することになったが、夜九時頃、枕元に坐っておられた母堂に、低いかすれかすれな声で、またとぎれとぎれに、自分死後如何にすべきかの心得と言ったようなようなものを、さも最後の遺言のように語るのであった。側に他人の私の居るのに関らず、随分突っ込んだ辛辣な言葉も交じる。居るにも居られずというのは、その時の私の思いで、さし出口はならず、膝をただしたまま身動きも出来なかった。
その翌日の朝のことである。三日間の絶食にも煩いされたのであろう。もういよいよ最後だというような悲観的なことのみを口にし、その応接に狼狽困倒したのであった。私の書いた消息に、
…松山の親族へ電報を打とう、何と打とうか、サヨナラ、ネギシでわかるだろうか、ゴキゲンヨウ、ネギシとしょうかなどと言わるるに到っては小生の衷心矢も楯も堪らず…ご親族への電報ならば看護人より打つかた穏やかなるべし、とて異議申立てしに、さらば露月に、カツ〇ネギシと打つてくれとて、電報頼信紙を取出さるるなど・・・。
とある。今までも幾度か病体危険を報ぜられたが、私の知る限りにおいて、ここまで切羽詰まったことはなかった。あるいは子規も他日告白しているように、以前自分が何死ぬるものか、と思っている時には周囲が顛動し、今度自分が危険だと思う時には、周囲が冷静である。と言った多少の反抗気分も手伝っていたかも知れぬ。それから、秀真の作った子規の塑像を持って来いと言って、その裏に「白題 土一塊牡丹生けたる其下に 年月日」と墨をつぎつぎ書くのであった。「病林六尺」にも、
もしこのままに眠ったらこれが絶筆であるぞと言わぬ許りの振舞。
とあるように、明らかに辞世の一句であったのだ。
「お前はこれ(塑像)を持っといでるので手がダルイかな。
「石膏というものは墨付きの心持のいいものだ。
「いくらでも書いて見たいよ。
など、静かに言われる・・・°
と同じ消息にある。どの位の大きさのものか判然記憶はしないが、ともかく仰向けに寝ていたなら、病体に触れないように持っていなけねばならない。横向きであれば、字を書くに都合のいいように向けなければならない。手がだるいより、その工夫の方に苦しみつつ、私はアア辞世の句だ、と「土一塊」の初筆で、もうじーんとと電気をかけられたようになってしまった。
ところが時経るままに天気回復して、その日の根岸祭りを祝う料理注文など、打って変わった微笑、平和な光景になった。
この祭いつも卯の花下しにして (子規)
と、さきの辞世はどこへやらと言った即吟さえ浮かぶ、周囲の愁眉を開くシーンとなった。
これが歿年五月十五日のことであった。この夏の酷暑を乗り切れば、あるいはまた余命をつなぐことが出来るであろうとも、周囲の人々と話し合っていたのであるが、幸いにして危篤を患えることもなく過ぎた。同七月の『ほととぎす」消息に、
意外の事には例の腰の患部の痛み次第に薄らぎ行きて、昨今は殆んどその疼痛を忘れらるる程とも相成り……されば子規君はその虚に乗じて元気百倍日に十句二十句を作り、写生画一枚二枚を画き、病牀六尺の原稿も手づからみとめらるることあり……
と近来の快事とさえ報じている。患部の痛みの去ったというのは、その癒着のためでなくて、かえって病勢の進行した麻痺状態でなかったであろうか。
かくて九月に入って、三、四日頃より先ず下痢症に罹り、日に三、四回の便通を見、同八日に初めて脚の水腫を発見した。当時の消息に、
…丁度点灯後小生ー碧梧桐ーと外に数人、例の枕頭にて何くれと雑談中、子規君もいつになく快詞を挟み一時病苦など忘れられたる様子ありしに、突如同君の声にて「アラッ」とさも驚きたる調子に叫ばれ候、何れも何事の起りしぞと、病人の方を注視したる際「早く灯を見せておくれ」と甚だ性急に申され、母上と妹君ランプを提げてその足の方を照されしに、子規君つくづく己が足の甲を見て「コンナに水を持ってる…」と申され…聞けばその水腫れは数日前よりその兆候見えしも、さして著しき変化も見えざれば、それと病人にも明されざりしものの由…
とある。医師は運動不足の病体には普通に見る徴候だと言っている、子規は「甚だ不気味な物じゃな」と不安な言葉を漏らしている。七、八月小康を得ていた病勢は、この水腫を皮切りに、再び猛威を逞しくして、十日の朝には腰部以下の自由を失い、かつ左右両足の位置によって激烈な痛みを感じ、モヒ剤も功を奏しないので、十二日には皮下注射を行っている。子規の苦悶状態はその極度に達したらしく、自ら「拷問」と歎息している。十三日、再び注射、十四日水腫腰部に及び、という風に加速度に昂進を示して、十八日の朝となった。
午後十時頃、いつも画を書く紙を貼る板に、唐紙を張らせたのをお律さんに持たせて、仰向けのまま何かを書こうとする。もう余り物も言わない。痰が切れないということで、かなり苦しそうな咳をする。私が筆に墨を含ませて、子規の右手に渡すしぐさを幾度も繰り返して、
糸瓜咲て痰のつまり仏かな(子規)
以下三句の絶筆が出来た。私は五月の辞世の先例もあるので、またこの辞世が笑い話の種となるのではないかの空想を描いたりした。この三句の辞世のことは、「子規言行録」に私の見たままを詳細に報告している。一句書いては休み休みして、最後の「取らざりき」を書き終えた後、筆を捨てるのも、もの臭ささそうに、穂先がシーツの上に落ちて、すこしばかり墨を印した。その画板はそのまま病室の障子に先せかけられて、誰にも見えるようになっている。子規も一度はそれを注視したようであるが、何とも口をきかない。先程この辞世を書き始めてから、一切だんまりで、誰一人口をきかないのであるから、病人の咳が時々静寂を破る外、シーンとして闇の底へ落ちて行くような、重々しい空気がよどんでしまった。それに辞世がいつまでもそこにさらされているのが辛かった。どこかへ片付けようか、と言って見たい咽が強ワ張って詰まっていた。
どうも五月の時のような余裕も活気もない、もうぐったりした子規であった。いっさい万事これでおしまいだ、と言う風に見える顔色でもあった。私は何を聞こうにも、何を話しかけようにも、頭の中が洞になって、考えも工夫もなかった。どよんだ部屋の空気に金縛りになって、指一本動かすことも出来なかった。子規は最後の元気で、句を考える力もあったのであるから、次に辞世の歌をと思わないでも無かったであろう。また、そこらに居合わす誰にでも、さらに最後の言葉を与えよう思いに耽っていたのかも知れない。不幸にして、丁度その言葉を分かつ適当な人が居なかったせいで、余儀なく、沈黙していたのかも知れない。あるいは平凡なお別れの言葉なんかと、この二月頃時々試みていた仏偶39のような、奇抜な文言でも練っていたのか。それとも最後を取り乱さないように、心の平静を破るまいとしていたのか。
遺憾ながら、この三句の辞世は、終に真の辞世になってしまった。また好個の記念の絶筆ともなってしまった。私には、それを書き終わった当時の息詰まるような沈黙の方が、一層深く焼きつけられた辞世の印象となった。≫
(子規、九月十八日、「絶筆三句」、十九日、午前一時永眠(三十六歳)
https://shiki-museum.com/masaokashiki/haiku?post_type=haiku&post_type=haiku&haiku_id=&p_age=&season=&classification=&kigo=%E7%B3%B8%E7%93%9C&s=&select=
秋に形あらば糸瓜に似たるべし ID1461 制作年24 季節秋 分類植物 季語糸瓜
しばらくは風のもつるゝ糸瓜かな ID1462 制作年24 季節秋 分類植物 季語糸瓜
露いくつ糸瓜の尻に出あひけり ID4026 制作年25 季節秋 分類植物 季語糸瓜
蔓かれてへちまぶらりと不二の山 ID4027 制作年25 季節秋 分類植物 季語糸瓜
茶屋淋し糸瓜の蔓の這ひかゝる ID8458 制作年26 季節秋 分類植物 季語糸瓜
家一つ門は糸瓜の月夜かな ID11585 制作年27 季節秋 分類植物 季語糸瓜
柴の戸に糸瓜の風の静かさよ ID11586 制作年27 季節秋 分類植物 季語糸瓜
投げ出したやうな糸瓜や垣の外 ID11587 制作年27 季節秋 分類植物 季語糸瓜
投げ出したやうに垣根の糸瓜哉 ID11588 制作年27 季節秋 分類植物 季語糸瓜
糸瓜肥え鶏頭痩せぬ背戸の雨 ID11589 制作年27 季節秋 分類植物 季語糸瓜
わぐなつて残る糸瓜や屋根の上 ID11590 制作年27 季節秋 分類植物 季語糸瓜
五六反叔父がつくりし糸瓜かな ID14851 制作年28 季節秋 分類植物 季語糸瓜
雪隠の窓にぶらりと糸瓜かな ID14852 制作年28 季節秋 分類植物 季語糸瓜
行く秋を糸瓜にさはる雲もなし ID14853 制作年28 季節秋 分類植物 季語糸瓜
垢すりになるべく糸瓜愚也けり ID18381 制作年29 季節秋 分類植物 季語糸瓜
秋のいろあかきへちまを畫にかゝむ ID20297 制作年30 季節秋 分類植物 季語糸瓜
へちまとは糸瓜のようなものならん ID20298 制作年30 季節秋 分類植物 季語糸瓜
夕顔の貧に處る糸瓜の愚を守る ID20299 制作年30 季節秋 分類植物 季語糸瓜
西行に糸瓜の歌はなかりけり ID21889 制作年31 季節秋 分類植物 季語糸瓜
内閣を糸瓜にたとへ論ずべく ID21890 制作年31 季節秋 分類植物 季語糸瓜
糸瓜とも瓢ともわかぬ目利哉 ID23012 制作年32 季節秋 分類植物 季語糸瓜
愚なる処すなはち雅なる糸瓜かな ID23888 制作年33 季節秋 分類植物 季語糸瓜
目鼻画く糸瓜の顔の長さ哉 ID23889 制作年33 季節秋 分類植物 季語糸瓜
秋ノ灯ノ糸瓜ノ尻ニ映リケリ ID24485 制作年34 季節秋 分類植物 季語糸瓜
棚ノ糸瓜思フ処ヘブラ下ル ID24486 制作年34 季節秋 分類植物 季語糸瓜
西ヘマハル秋ノ日影ヤ糸瓜棚 ID24487 制作年34 季節秋 分類植物 季語糸瓜
病間ニ糸瓜ノ句ナド作リケル ID24488 制作年34 季節秋 分類植物 季語糸瓜
病閑ニ糸瓜ノ花ノ落ツル昼 ID24489 制作年34 季節秋 分類植物 季語糸瓜
日掩棚糸瓜ノ蔓ノ這ヒ足ラズ ID24490 制作年34 季節秋 分類植物 季語糸瓜
糸瓜サヘ仏ニナルゾ後ルゝナ ID24491 制作年34 季節秋 分類植物 季語糸瓜
糸瓜ニハ可モ不可モナキ残暑カナ ID24492 制作年34 季節秋 分類植物 季語糸瓜
糸瓜ブラリ夕顔ダラリ秋ノ風 ID24493 制作年34 季節秋 分類植物 季語糸瓜
牡丹ニモ死ナズ瓜ニモ糸瓜ニモ ID24494 制作年34 季節秋 分類植物 季語糸瓜
黙然ト糸瓜ノサガル庭ノ秋 ID24495 制作年34 季節秋 分類植物 季語糸瓜
物思フ窓ニブラリト糸瓜哉 ID24496 制作年34 季節秋 分類植物 季語糸瓜
夕顔ト糸瓜残暑ト新涼と ID24497 制作年34 季節秋 分類植物 季語糸瓜
夕顔ノ棚に糸瓜モ下リケリ ID24498 制作年34 季節秋 分類植物 季語糸瓜
夕顔モ糸瓜モ同ジ棚子同士 ID24499 制作年34 季節秋 分類植物 季語糸瓜
「絶筆三句」
痰一斗糸瓜の水も間にあはず ID25012 制作年35 季節秋 分類植物 季語糸瓜
糸瓜咲て痰のつまりし仏かな ID25013 制作年35 季節秋 分類植物 季語糸瓜
をととひのへちまの水も取らざりき ID25014 制作年35 季節秋 分類植物 季語糸瓜
(漱石、三十六歳。十二月、帰国の途につく。その直前に子規没との虚子・碧悟桐の書翰が届く。)
66 風ふけば糸瓜をなぐるふくべ哉(明治二十八年)
904 長けれど何の糸瓜とさがりけり(明治二十九年。「子規へ送りたる句稿十七」)
1737 容赦なく瓢を叩く糸瓜かな(明治三十二年。「子規へ送りたる句稿三十五」)
1848 一大事も糸瓜も糞もあらばこそ(明治三十六年)
(寅彦、二十五歳。『俳句と地球物理』所収「略年譜」/『寺田寅彦全集/文学篇/七巻』」)
面白し瀬戸の絲瓜(へちま)の長短(明治三十一年作)
日一日ぶらりぶらりと絲瓜哉(同上)
世をすねて日影の絲瓜そりかへる(明治三十一~二年作)
長過て肥手桶たゝく絲瓜哉(同上)
干からびし絲瓜をつるす納屋の軒(同上)
(東洋城、二十五歳。『東洋城全句集上・中巻』)
糸瓜忌や只句を作るあな尊と(明治四十五年作)
道の家の糸瓜に起す話頭かな(大正九年作。前書「子規忌順礼 二十七句」)
(参考その一) 「絶筆三句 子規」周辺
https://yahan.blog.ss-blog.jp/2023-09-05
(再掲)
https://www.ndl.go.jp/exhibit70/23.html
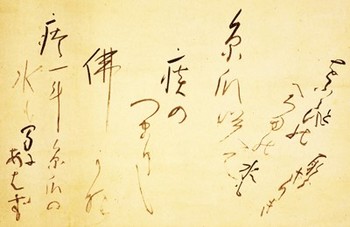
「絶筆三句 子規」(紙本墨書/31.0×44.3㎝/国立国会図書館蔵)
https://www.ndl.go.jp/exhibit70/23.html
≪〔正岡子規 著〕〔正岡子規 明治35(1902)年〕写【WB41-61】43 〔絶筆三句〕の画像(デジタルコレクション)
日本の近代文学に多大な影響を及ぼした俳人、歌人の正岡子規が臨終間際に書き残した三句。明治35(1902)年9月18日の午前11時頃、紙を貼りつけた画板を妹の律に持たせ、仰臥しながら記した。翌19日午前1時頃、子規の息は絶えた。満34歳の若さであった。病魔に苦しみながらも、死の直前まで俳人として生き抜いた壮絶な姿がうかがえる。
(書き起こし)
をととひのへちまの水も取らざりき/糸瓜咲て痰のつまりし佛かな/痰一斗糸瓜の水も間にあはず ≫
(追記)
倫敦にて子規の訃を聞て(五句)
1824 筒袖や秋の棺にしたがはず (漱石・36歳「明治35年(1902)」)
≪ 季=秋(雑)。※子規は九月十九日に他界した。虚子から要請のあった子規追悼文に代えてこれらの句を送った。その書簡では子規の死について、「かかる病苦になやみ候よりも早く往生致す方或は本人の幸福かと存候」と述べている。その後で、「子規追悼の句何かと案じ煩ひ候へども、かく筒袖にてピステキのみ食ひ居候者には容易に俳想なるもの出現仕らず、昨夜ストーブの傍にて左の駄句を得申候。得たると申すよりは寧ろ無理やりに得さしめたる次第に候へば、只申訳の為め御笑草として御覧に入候。近頃の如く半ば西洋人にて半日本人にては甚だ妙ちきりんなものに候」と言い、これらの句を記した。句のあとに「皆蕪雑句をなさず。叱正」とある。筒袖は洋服姿。◇書簡(高浜虚子宛、明治35.12.1)。雑誌「ホトトギス」(明治36.2)。 ≫(『漱石全集第十七巻・坪内稔典注解』)
1825 手向くべき線香もなくて暮の秋 (漱石・36歳「明治35年(1902)」)
≪ 季=暮の秋。◇1824。≫(「同上」)
1826 霜黄なる市に動くや影法師 (漱石・36歳「明治35年(1902)」)
≪ 季=霧(秋)。◇1824。(「同上」)≫
1827 きりぎりすの昔を忍び帰るべし (漱石・36歳「明治35年(1902)」)
≪ 季=きりぎりす(秋)。◇1824。≫(「同上」)
1626 招かざる薄に帰り来る人ぞ (漱石・36歳「明治35年(1902)」)
≪ 季=薄(秋)。◇1824。≫(「同上」)
(参考その二) 「碧梧桐の『子規の回想』」周辺
https://plaza.rakuten.co.jp/akiradoinaka/diary/202105250000/
≪ 子規の最期については、高浜虚子の『子規居士と余』が引き合いに出されます。かたや河東碧梧桐の文が引用されることはあまりありません。『子規居士と余』は岩波文庫の『回想 子規・漱石』に収録されていますが、碧梧桐の『子規の回想』は、子規が漱石の下宿・愚陀仏庵に行くところまでしか『子規を語る』に収録されていないのです。
『子規の回想』に記された「辞世の句」を、次の回は「死後」をみていただきます。
これが終わりましたら、虚子と碧梧桐の俳句観について書かせていただきます。
二十八 辞世
ことさらに辞世の句を作らないと言った芭蕉を、さすがに芭蕉らしい、と話したこともある。また太祇の辞世の句が、平生の伎価に似ない。あれ程の蕪村にしても辞世はどこか弱々しいと言ったこともある。
古人の辞世の句をおおむね否定していたから、自分の場合にも無論思い及んだ筈であるが、どういうものか、辞世を作ることにかなり執着を持っていた。芭蕉でもない者が、芭蕉を気取るのを避けた意味であったかも知れぬ。死ぬる三日前に「九月十四日の朝」と題して文章を口誦した程、死生の間に超然としていた人であるから、考え得るなら辞世を考えてもいい、と例の強烈な心的生活力が働いていたかも知れない。
明治三十三年十八日の「病牀六尺」と四月発行の「ほととぎす」の消息は、子規自らも「近頃不覚をとった」と言っているように、辞世について閑葛藤のあったことを明らかにしている。それによって、追憶の糸たぐって見ると、その五月十三日午後六時頃、子規直筆の急便によって、私はある宴会の席上から駆け付け、虚子も宮本国手も相次いで来着したのだが、子規の阿鼻叫喚の苦悶は、真に見るに堪えぬものがあった。その夜は虚子宿直して翌十四日となり、病苦はやや平静に帰したが、疲労その極に達して、何の食欲もなく、時には失神したのかを患える程全く元気がなかった。その夜私が宿直することになったが、夜九時頃、枕元に坐っておられた母堂に、低いかすれかすれな声で、またとぎれとぎれに、自分死後如何にすべきかの心得と言ったようなようなものを、さも最後の遺言のように語るのであった。側に他人の私の居るのに関らず、随分突っ込んだ辛辣な言葉も交じる。居るにも居られずというのは、その時の私の思いで、さし出口はならず、膝をただしたまま身動きも出来なかった。
その翌日の朝のことである。三日間の絶食にも煩いされたのであろう。もういよいよ最後だというような悲観的なことのみを口にし、その応接に狼狽困倒したのであった。私の書いた消息に、
…松山の親族へ電報を打とう、何と打とうか、サヨナラ、ネギシでわかるだろうか、ゴキゲンヨウ、ネギシとしょうかなどと言わるるに到っては小生の衷心矢も楯も堪らず…ご親族への電報ならば看護人より打つかた穏やかなるべし、とて異議申立てしに、さらば露月に、カツ〇ネギシと打つてくれとて、電報頼信紙を取出さるるなど・・・。
とある。今までも幾度か病体危険を報ぜられたが、私の知る限りにおいて、ここまで切羽詰まったことはなかった。あるいは子規も他日告白しているように、以前自分が何死ぬるものか、と思っている時には周囲が顛動し、今度自分が危険だと思う時には、周囲が冷静である。と言った多少の反抗気分も手伝っていたかも知れぬ。それから、秀真の作った子規の塑像を持って来いと言って、その裏に「白題 土一塊牡丹生けたる其下に 年月日」と墨をつぎつぎ書くのであった。「病林六尺」にも、
もしこのままに眠ったらこれが絶筆であるぞと言わぬ許りの振舞。
とあるように、明らかに辞世の一句であったのだ。
「お前はこれ(塑像)を持っといでるので手がダルイかな。
「石膏というものは墨付きの心持のいいものだ。
「いくらでも書いて見たいよ。
など、静かに言われる・・・°
と同じ消息にある。どの位の大きさのものか判然記憶はしないが、ともかく仰向けに寝ていたなら、病体に触れないように持っていなけねばならない。横向きであれば、字を書くに都合のいいように向けなければならない。手がだるいより、その工夫の方に苦しみつつ、私はアア辞世の句だ、と「土一塊」の初筆で、もうじーんとと電気をかけられたようになってしまった。
ところが時経るままに天気回復して、その日の根岸祭りを祝う料理注文など、打って変わった微笑、平和な光景になった。
この祭いつも卯の花下しにして (子規)
と、さきの辞世はどこへやらと言った即吟さえ浮かぶ、周囲の愁眉を開くシーンとなった。
これが歿年五月十五日のことであった。この夏の酷暑を乗り切れば、あるいはまた余命をつなぐことが出来るであろうとも、周囲の人々と話し合っていたのであるが、幸いにして危篤を患えることもなく過ぎた。同七月の『ほととぎす」消息に、
意外の事には例の腰の患部の痛み次第に薄らぎ行きて、昨今は殆んどその疼痛を忘れらるる程とも相成り……されば子規君はその虚に乗じて元気百倍日に十句二十句を作り、写生画一枚二枚を画き、病牀六尺の原稿も手づからみとめらるることあり……
と近来の快事とさえ報じている。患部の痛みの去ったというのは、その癒着のためでなくて、かえって病勢の進行した麻痺状態でなかったであろうか。
かくて九月に入って、三、四日頃より先ず下痢症に罹り、日に三、四回の便通を見、同八日に初めて脚の水腫を発見した。当時の消息に、
…丁度点灯後小生ー碧梧桐ーと外に数人、例の枕頭にて何くれと雑談中、子規君もいつになく快詞を挟み一時病苦など忘れられたる様子ありしに、突如同君の声にて「アラッ」とさも驚きたる調子に叫ばれ候、何れも何事の起りしぞと、病人の方を注視したる際「早く灯を見せておくれ」と甚だ性急に申され、母上と妹君ランプを提げてその足の方を照されしに、子規君つくづく己が足の甲を見て「コンナに水を持ってる…」と申され…聞けばその水腫れは数日前よりその兆候見えしも、さして著しき変化も見えざれば、それと病人にも明されざりしものの由…
とある。医師は運動不足の病体には普通に見る徴候だと言っている、子規は「甚だ不気味な物じゃな」と不安な言葉を漏らしている。七、八月小康を得ていた病勢は、この水腫を皮切りに、再び猛威を逞しくして、十日の朝には腰部以下の自由を失い、かつ左右両足の位置によって激烈な痛みを感じ、モヒ剤も功を奏しないので、十二日には皮下注射を行っている。子規の苦悶状態はその極度に達したらしく、自ら「拷問」と歎息している。十三日、再び注射、十四日水腫腰部に及び、という風に加速度に昂進を示して、十八日の朝となった。
午後十時頃、いつも画を書く紙を貼る板に、唐紙を張らせたのをお律さんに持たせて、仰向けのまま何かを書こうとする。もう余り物も言わない。痰が切れないということで、かなり苦しそうな咳をする。私が筆に墨を含ませて、子規の右手に渡すしぐさを幾度も繰り返して、
糸瓜咲て痰のつまり仏かな(子規)
以下三句の絶筆が出来た。私は五月の辞世の先例もあるので、またこの辞世が笑い話の種となるのではないかの空想を描いたりした。この三句の辞世のことは、「子規言行録」に私の見たままを詳細に報告している。一句書いては休み休みして、最後の「取らざりき」を書き終えた後、筆を捨てるのも、もの臭ささそうに、穂先がシーツの上に落ちて、すこしばかり墨を印した。その画板はそのまま病室の障子に先せかけられて、誰にも見えるようになっている。子規も一度はそれを注視したようであるが、何とも口をきかない。先程この辞世を書き始めてから、一切だんまりで、誰一人口をきかないのであるから、病人の咳が時々静寂を破る外、シーンとして闇の底へ落ちて行くような、重々しい空気がよどんでしまった。それに辞世がいつまでもそこにさらされているのが辛かった。どこかへ片付けようか、と言って見たい咽が強ワ張って詰まっていた。
どうも五月の時のような余裕も活気もない、もうぐったりした子規であった。いっさい万事これでおしまいだ、と言う風に見える顔色でもあった。私は何を聞こうにも、何を話しかけようにも、頭の中が洞になって、考えも工夫もなかった。どよんだ部屋の空気に金縛りになって、指一本動かすことも出来なかった。子規は最後の元気で、句を考える力もあったのであるから、次に辞世の歌をと思わないでも無かったであろう。また、そこらに居合わす誰にでも、さらに最後の言葉を与えよう思いに耽っていたのかも知れない。不幸にして、丁度その言葉を分かつ適当な人が居なかったせいで、余儀なく、沈黙していたのかも知れない。あるいは平凡なお別れの言葉なんかと、この二月頃時々試みていた仏偶39のような、奇抜な文言でも練っていたのか。それとも最後を取り乱さないように、心の平静を破るまいとしていたのか。
遺憾ながら、この三句の辞世は、終に真の辞世になってしまった。また好個の記念の絶筆ともなってしまった。私には、それを書き終わった当時の息詰まるような沈黙の方が、一層深く焼きつけられた辞世の印象となった。≫
「子規・漱石・寅彦・東洋城」俳句管見(その十三) [子規・漱石・寅彦・東洋城]
その十三「明治三十四年(一九〇一)・「野分」など」
(子規・三十五歳。)
https://shiki-museum.com/masaokashiki/haiku?post_type=haiku&post_type=haiku&haiku_id=&p_age=34&season=&classification=&kigo=%E9%87%8E%E5%88%86&s=&select=
鶏頭ノマダイトケナキ野分カナ ID24393 制作年34 季節秋 分類天文 季語野分
野分近ク夕顔ノ實ノ太リ哉 ID24394 制作年34 季節秋 分類天文 季語野分
夕顔ヤ野分恐ルヽ實ノ太リ ID24395 制作年34 季節秋 分類天文 季語野分
(漱石・三十五歳。)
112 この夕野分に向て分れけり(明治二十八年。「子規へ送りたる句稿一」)
206 鎌倉堂野分の中に傾けり(同上。「子規へ送りたる句稿四」)
219 四里あまり野分に吹かれ参りたり(同上)
240 荒滝や野分を斫て捲き落す(同上)
257 野分吹く瀑砕け散る脚下より(同上)
258 滝遠近谷も尾上も野分哉(同上。「子規へ送りたる句稿五」)
505 野分して朝鳥早く立ちけらし(同上。「承露盤」より)
954 野分して一人障子を張る男(明治二十九年。「子規へ送りたる句稿二十」)
1246 砂山に薄許りの野分哉(明治三十年。「七月四日~九月七日まで上京。子規句会」)
1296 野分して蟷螂を窓に吹き入るゝ(明治三十年。「子規へ送りたる句稿二十六」)
1425 病癒えず蹲る夜の野分かな(明治三十一年。「子規へ送りたる句稿三十一」)
1808 礎に砂吹きあつる野分かな(明治三十四年。「ロンドン在留邦人句会での作」)
1809 角巾を吹き落し行く野分かな(同上)
1899 釣鐘のうなる許りに野分かな(明治三十九年。「東洋城宛書簡」)
(寅彦、二十四歳。高知から夏子をよび本郷西片町に住む。夏子喀血。夏子療養のため帰郷、種崎に住む。長女貞子誕生。肺尖カタルのため一年休学須崎にて療養。)
弦月の下吹き通す野分かな(明治三十一年作)
一夜荒れて晴てしまひし野分哉(同上)
悉く稲倒れ伏す野分哉(同上)
牛小屋の屋根を野分にさらはれつ(明治三十一~二年作)
旅僧の袖もさけよと野分かな(同上)
ばらばらに芭蕉さけたる野分哉(同上)
引越して野分淋しや野分の夜(明治三十二年作)
散々に卒塔婆倒れし野分哉(同上)
本堂の瓦はがれし野分哉(同上)
汽笛高く野分の汽車の通りけり(同上)
野分止んで夕日の富士を望みけり(同上)
雪隠の窓や野分の森を見る(明治三十三年作)
野分やんで波を己に出る浜辺哉(同上)
(東洋城、二十四歳。「東洋城全句集上・中巻」)
一泊の旅の松戸の野分か (明治三十四年作)
この町の尽くる我が家に野分かな(同上)
(参考) 「子規・碧悟桐・虚子」(碧悟桐「子規の回想」)周辺
https://plaza.rakuten.co.jp/akiradoinaka/diary/202105190000/

http://www.s-kawano.net/s-kawano/%E6%AD%A3%E5%B2%A1%E5%AD%90%E8%A6%8F.pdf
≪ 二高を辞めた碧梧桐と虚子は、子規を頼って上京し、初めは小石川にあった新海非風の家に逗留しています。この頃、日清戦争の取材で、従軍記者として中国に渡った子規は、帰りの船で吐血し、生死の際を彷徨います。碧梧桐と虚子は、子規のいる神戸の病院へ向かい、力の限りの看病をしました。
このころの二人の生活は、学問を疎にして遊び歩く放蕩の時間を過ごしています。
子規は、二人を案じました。虚子の『子規居士と余』には「お前一人の時はその程でもないが、秉公(=碧梧桐)と一緒になると忽ち駄目になってしまうように思う。どちらが悪いということもあるまいが、要するに二人一緒になるということがいけないのである」と言われたことを記しています。
明治28年12月9日、子規は虚子を道灌山へ呼び出し、後継者として身を律し、ふさわしい学問を身につけるように迫ります。しかし、虚子は後継者への道を拒絶します。
子規が早くから俳句の才能を認めていたのは碧梧桐でした。
明治24年の句会で詠んだ碧梧桐の「面白うきけば蜩夕日かな」に、子規は「諸君取りたまわず。余独りこれを賞す。けだし蕉翁の余韻あればなり」と激賞しています。また、翌年1月21日の碧梧桐宛手の手紙では「我庵はの御句近頃斬新の御手並驚入申候。余は古白の胸中より出しものかと思候もおかし」と書き、6月7日の碧梧桐宛手紙にも「先便の炭売の句蚊柱の句を拝見してその妙なるに驚きしが今度の句はことごとく極上極上、吉のしろ物のみにて貴兄今までの御什中かくの如きのものは一句も見当り不申候。小生一両月前貴兄すでに理想の極点に達し給いし故、日ならずして上達し給わんとは予言せしかともかくまで早からんとは存し不申き」と、碧梧桐の進歩を認めています。
しかし、碧梧桐は放蕩を好みました。俳句への関心もそれほど深いものではない碧梧桐に対して、子規は幻滅するようになりました。子規は、道灌山での様子を俳友五百木瓢亭に知らせる手紙で「碧梧虚子の中にても碧梧才能ありと覚えしは真のはじめのことにて小生は以前よりすでに碧梧を捨て申し候」と記しています。子規は放埓な生活ぶりのために碧梧桐を後継者として認めることはできなかったのでした。
明治29年12月10日、雑誌「日本人」に連載した時評『文学』で、子規は碧梧桐の変化を記しています。
河東碧梧桐が俳句なるものを認めたるは明治二十三年の頃なるべし。二十四年より作り始めたるにその敏才ははやく奇想を捻出し、句法の奇なるものを作りてもって吾人を驚かしぬ。
……
二十七年春以後彼は毫も進歩をなさざりき。曩時の麒麟児も一個の豚犬と化し去りぬ。由来彼は秩序的の能力と推理的の常識とを欠く者、少事にありて敏才の人を驚かしたるは彼の不規則なる発達がたまたま文学の方面に向かいしがためなるべし。薄弱なる彼の脳漿は平和なる時沈静しおる時に当りて初めて用をなすべし。一たび外部の刺激に逢えば脳漿忽ちに混乱すべく、混乱して後は殆ど狂の如く愚の如し。彼は修学のため一たび東京に来り。二たび故郷に帰り、三たぴ京都に行き、四たび仙台に遷る。(これ学校制度変更の結果なり)さらでも規則的の修学に適せざる頭脳はこの大混乱に逢うていかでか堪え得ん、この年の暮退学して東京に来れり。明治二十八年は最早学課無く束縛無く詩人として如何様にも発逹すべき機会に遭遇せり。しかれどもその混乱せられたる頭脳は未だ沈静せざるがため彼は平平凡凡なる一年を送りたり。あるいは人をして邪路に陥るにはあらずやと疑はしむるに至りぬ。
……
明治二十九年とはなりぬ。吾は咋年末昏昏として睡眠に余念なき俳友を起さんとしてしきりに務めたり。しかして第一に起き来りしは碧梧桐なり。最早脳漿沈静したりとおぼし。彼はたしかに一点の霊光を拝したるに相違あらじ。その俳句は一種の趣味を具えてしかも古人の言わざる処をのみ言えり。しかしてその句法一として勁抜ならざるはなし。
……
これらの句は実に碧梧桐の特色にして去年の碧梧桐は未だこれを知らざりしなり。吾人も始めてこの種の句を見たるなり。俳句自身もまた始めてこの種の句を見たるならん。しかしてこの句を読む者皆その印象の明瞭なるを認むなるべし。印象の明瞭ということは多く余韻ということと相反す。鳴雪の余韻を好むに反して碧梧桐は明瞭なる印象を好む。印象をして明瞭ならしめんとせば空間を狭くせざるべからず。空間狭ければ些事徽物または大事物の断片を容るるに過ぎず。故に碧梧桐の句には小事小物を詠ずる者自ら多し。
……
碧梧桐既に印象の明瞭なる者を好む、従って客観の事物といえども壮大に過ぎて茫漠たる者を排す。況して主観的の句に至りてはほとんど全くこれを排し去りて毫も取る所なし。これその性質の然らしむるもの。碧梧桐は始終このままにて押し行くべし。故にその作句また主観的なる極めて稀なり。(文学 明治29年12月10日)
11月20日の「「日本人」」『文学』には碧梧桐と虚子を比べ、「詩人の頭脳に両面の活動あり。一面は冷淡に社会を観察し、他の一面は熱情をもってある事物に同感を表す。両面斉しく発達するものもなきにあらねど、多くは両者執れかに僻す。前者に僻するを写実派といい、後者に僻するを理想派という。碧梧桐は冷かなること水の如く、虚子は熱きこと火の如し。碧梧桐の人間を見るはなお無心の草木を見るがごとく、虚子の草木を見るはなお有情の人間を見るがごとし。随ってその作る所の俳句も一は写実に傾き、一は理想に傾く。一は空間を現し、一は時間を現す」と書いています。
碧梧桐は『子規の回想』で、当時を振り返っていますが、こうした放蕩生活で、明治28年から勤めていた「日本」を辞めなければならなくなります。ただ、こうした放蕩な生活は、次第に影を潜めていきます。碧梧桐は『子規の回想』で、当時を振り返っていますが、こうした放蕩生活で、明治28年から勤めていた「日本」を辞めなければならなくなります。ただ、こうした放蕩な生活は、次第に影を潜めていきます。
子規との道潅山のいきさつなど全然知らなかった私は、虚子に会う毎に別れている不便と寂寞を訴えていたのみならず、子規との喧嘩別れに、少々ヤケも手伝ってか、もう大ぴらに私と同宿する気にもなったのだろう。
実は初めて白状するが、と言って、須磨保養院以来の話をして、それをお前に打ち明けて言えなかったアシの心の苦痛を察しておくれ、実際お前の顔を見る度にすまんすまんと思っていたのだ、もうアシもな、升さんに捨てられたのだから、今後はお互いに思う存分勝手なことをやろうじゃないか、などとその頃よく行った連雀町の「ぼたん」という安鳥屋で、酔った虚子が管を巻いたものだった。
この高田屋へは、子規も一、二度来たこともあるが、瓢亭、肋骨など主人夫婦と仲良しになって、オイ阿爺と門口から大きな声で呼びかけたりしていた。ことに牛伴君は八々のいい相手というので、我々のいるいないにに関らず、遊びに来たものだった。
われわれの中学同窓の青木森々も、二十九年中には同宿の仲間になっていた。三人してかなり放埒な日々をおくったものだ。それに私は何月であったか表面は、従軍していた先輩達が皆帰って来たし、社の人物過剰という意味で、「日本」新聞社をやめさせられた。が、実は無学無能、新聞人にはなれないという折紙をつけられたのだ。ここに再び、前年のように、先輩誰もが匙を投げるような、碧虚二人の荒んだ遊蕩生活が繰返されるいいコンディションを醸成していた。何かしら不平であり、不安であり、身は自由不拘束なんだ。もし軍資金でも十分であったとしたら、それこそ本当に、子規から見放されていたかも知れなかった。
が、二年前の本郷下宿時代、二高をやめて東上した自分とは、もう環境がすっかり違っていた。俳句の世が、我々内輪のものでなくて、世間に公認された公のものになっていた。我々のようなデカダンなあばずれ書生でもが、いわゆる日本派中堅どころの声誉を嬴得ていた。ポッポツ文学雑誌などの選などを頼まれて、小遣い位出来るようになっていた。(河東碧梧桐 子規の回想 当事の新調)
また、明治30年1月の「ホトトギス」掲載の『明治二十九年の俳諧』でも、碧梧桐の句を「極めて印象の明瞭なる句」とし、虚子と碧梧桐が日本派のエースとして俳壇の前面に強く押し出していきます。
碧梧桐と虚子は、明治29年4月から旧前橋藩士族・大畠豊水経営する神田淡路町の高田屋という下宿屋で、碧梧桐と再び同居を始めました。そこで22歳の虚子は、大畠家の次女いとを見初め、翌年6月に結婚することになります。たまたま、その年の1月に碧梧桐は天然痘に罹り、一か月ほど入院しなくてはならなくなりました。碧梧桐の方がいとと親しかったのですが、空白の時間のために虚子といとの親密度が増した結果でした。
5月になると傷心の碧梧桐は、北陸の旅を思いつきます。まず京都へ行き、三高で学んでいた寒川鼠骨や新聞記者の中川四明に会い、米原から敦賀に出て金沢に着きました。金沢では同郷の竹村秋竹の家に身を寄せました。虚子の結婚式のある6月には能登へ向かっていると子規の容態が重くなったという知らせが届きます。しかし、虚子から焼香を得たとの連絡があり、碧梧桐は旅を続けました。この紀行は「日本」に連載され、碧梧桐が東京に戻ったのは7月でした。
子規は、帰ってきた碧梧桐に句を贈っています。
団扇出して先づ問ふ加賀は能登は如何 ≫
(子規・三十五歳。)
https://shiki-museum.com/masaokashiki/haiku?post_type=haiku&post_type=haiku&haiku_id=&p_age=34&season=&classification=&kigo=%E9%87%8E%E5%88%86&s=&select=
鶏頭ノマダイトケナキ野分カナ ID24393 制作年34 季節秋 分類天文 季語野分
野分近ク夕顔ノ實ノ太リ哉 ID24394 制作年34 季節秋 分類天文 季語野分
夕顔ヤ野分恐ルヽ實ノ太リ ID24395 制作年34 季節秋 分類天文 季語野分
(漱石・三十五歳。)
112 この夕野分に向て分れけり(明治二十八年。「子規へ送りたる句稿一」)
206 鎌倉堂野分の中に傾けり(同上。「子規へ送りたる句稿四」)
219 四里あまり野分に吹かれ参りたり(同上)
240 荒滝や野分を斫て捲き落す(同上)
257 野分吹く瀑砕け散る脚下より(同上)
258 滝遠近谷も尾上も野分哉(同上。「子規へ送りたる句稿五」)
505 野分して朝鳥早く立ちけらし(同上。「承露盤」より)
954 野分して一人障子を張る男(明治二十九年。「子規へ送りたる句稿二十」)
1246 砂山に薄許りの野分哉(明治三十年。「七月四日~九月七日まで上京。子規句会」)
1296 野分して蟷螂を窓に吹き入るゝ(明治三十年。「子規へ送りたる句稿二十六」)
1425 病癒えず蹲る夜の野分かな(明治三十一年。「子規へ送りたる句稿三十一」)
1808 礎に砂吹きあつる野分かな(明治三十四年。「ロンドン在留邦人句会での作」)
1809 角巾を吹き落し行く野分かな(同上)
1899 釣鐘のうなる許りに野分かな(明治三十九年。「東洋城宛書簡」)
(寅彦、二十四歳。高知から夏子をよび本郷西片町に住む。夏子喀血。夏子療養のため帰郷、種崎に住む。長女貞子誕生。肺尖カタルのため一年休学須崎にて療養。)
弦月の下吹き通す野分かな(明治三十一年作)
一夜荒れて晴てしまひし野分哉(同上)
悉く稲倒れ伏す野分哉(同上)
牛小屋の屋根を野分にさらはれつ(明治三十一~二年作)
旅僧の袖もさけよと野分かな(同上)
ばらばらに芭蕉さけたる野分哉(同上)
引越して野分淋しや野分の夜(明治三十二年作)
散々に卒塔婆倒れし野分哉(同上)
本堂の瓦はがれし野分哉(同上)
汽笛高く野分の汽車の通りけり(同上)
野分止んで夕日の富士を望みけり(同上)
雪隠の窓や野分の森を見る(明治三十三年作)
野分やんで波を己に出る浜辺哉(同上)
(東洋城、二十四歳。「東洋城全句集上・中巻」)
一泊の旅の松戸の野分か (明治三十四年作)
この町の尽くる我が家に野分かな(同上)
(参考) 「子規・碧悟桐・虚子」(碧悟桐「子規の回想」)周辺
https://plaza.rakuten.co.jp/akiradoinaka/diary/202105190000/

http://www.s-kawano.net/s-kawano/%E6%AD%A3%E5%B2%A1%E5%AD%90%E8%A6%8F.pdf
≪ 二高を辞めた碧梧桐と虚子は、子規を頼って上京し、初めは小石川にあった新海非風の家に逗留しています。この頃、日清戦争の取材で、従軍記者として中国に渡った子規は、帰りの船で吐血し、生死の際を彷徨います。碧梧桐と虚子は、子規のいる神戸の病院へ向かい、力の限りの看病をしました。
このころの二人の生活は、学問を疎にして遊び歩く放蕩の時間を過ごしています。
子規は、二人を案じました。虚子の『子規居士と余』には「お前一人の時はその程でもないが、秉公(=碧梧桐)と一緒になると忽ち駄目になってしまうように思う。どちらが悪いということもあるまいが、要するに二人一緒になるということがいけないのである」と言われたことを記しています。
明治28年12月9日、子規は虚子を道灌山へ呼び出し、後継者として身を律し、ふさわしい学問を身につけるように迫ります。しかし、虚子は後継者への道を拒絶します。
子規が早くから俳句の才能を認めていたのは碧梧桐でした。
明治24年の句会で詠んだ碧梧桐の「面白うきけば蜩夕日かな」に、子規は「諸君取りたまわず。余独りこれを賞す。けだし蕉翁の余韻あればなり」と激賞しています。また、翌年1月21日の碧梧桐宛手の手紙では「我庵はの御句近頃斬新の御手並驚入申候。余は古白の胸中より出しものかと思候もおかし」と書き、6月7日の碧梧桐宛手紙にも「先便の炭売の句蚊柱の句を拝見してその妙なるに驚きしが今度の句はことごとく極上極上、吉のしろ物のみにて貴兄今までの御什中かくの如きのものは一句も見当り不申候。小生一両月前貴兄すでに理想の極点に達し給いし故、日ならずして上達し給わんとは予言せしかともかくまで早からんとは存し不申き」と、碧梧桐の進歩を認めています。
しかし、碧梧桐は放蕩を好みました。俳句への関心もそれほど深いものではない碧梧桐に対して、子規は幻滅するようになりました。子規は、道灌山での様子を俳友五百木瓢亭に知らせる手紙で「碧梧虚子の中にても碧梧才能ありと覚えしは真のはじめのことにて小生は以前よりすでに碧梧を捨て申し候」と記しています。子規は放埓な生活ぶりのために碧梧桐を後継者として認めることはできなかったのでした。
明治29年12月10日、雑誌「日本人」に連載した時評『文学』で、子規は碧梧桐の変化を記しています。
河東碧梧桐が俳句なるものを認めたるは明治二十三年の頃なるべし。二十四年より作り始めたるにその敏才ははやく奇想を捻出し、句法の奇なるものを作りてもって吾人を驚かしぬ。
……
二十七年春以後彼は毫も進歩をなさざりき。曩時の麒麟児も一個の豚犬と化し去りぬ。由来彼は秩序的の能力と推理的の常識とを欠く者、少事にありて敏才の人を驚かしたるは彼の不規則なる発達がたまたま文学の方面に向かいしがためなるべし。薄弱なる彼の脳漿は平和なる時沈静しおる時に当りて初めて用をなすべし。一たび外部の刺激に逢えば脳漿忽ちに混乱すべく、混乱して後は殆ど狂の如く愚の如し。彼は修学のため一たび東京に来り。二たび故郷に帰り、三たぴ京都に行き、四たび仙台に遷る。(これ学校制度変更の結果なり)さらでも規則的の修学に適せざる頭脳はこの大混乱に逢うていかでか堪え得ん、この年の暮退学して東京に来れり。明治二十八年は最早学課無く束縛無く詩人として如何様にも発逹すべき機会に遭遇せり。しかれどもその混乱せられたる頭脳は未だ沈静せざるがため彼は平平凡凡なる一年を送りたり。あるいは人をして邪路に陥るにはあらずやと疑はしむるに至りぬ。
……
明治二十九年とはなりぬ。吾は咋年末昏昏として睡眠に余念なき俳友を起さんとしてしきりに務めたり。しかして第一に起き来りしは碧梧桐なり。最早脳漿沈静したりとおぼし。彼はたしかに一点の霊光を拝したるに相違あらじ。その俳句は一種の趣味を具えてしかも古人の言わざる処をのみ言えり。しかしてその句法一として勁抜ならざるはなし。
……
これらの句は実に碧梧桐の特色にして去年の碧梧桐は未だこれを知らざりしなり。吾人も始めてこの種の句を見たるなり。俳句自身もまた始めてこの種の句を見たるならん。しかしてこの句を読む者皆その印象の明瞭なるを認むなるべし。印象の明瞭ということは多く余韻ということと相反す。鳴雪の余韻を好むに反して碧梧桐は明瞭なる印象を好む。印象をして明瞭ならしめんとせば空間を狭くせざるべからず。空間狭ければ些事徽物または大事物の断片を容るるに過ぎず。故に碧梧桐の句には小事小物を詠ずる者自ら多し。
……
碧梧桐既に印象の明瞭なる者を好む、従って客観の事物といえども壮大に過ぎて茫漠たる者を排す。況して主観的の句に至りてはほとんど全くこれを排し去りて毫も取る所なし。これその性質の然らしむるもの。碧梧桐は始終このままにて押し行くべし。故にその作句また主観的なる極めて稀なり。(文学 明治29年12月10日)
11月20日の「「日本人」」『文学』には碧梧桐と虚子を比べ、「詩人の頭脳に両面の活動あり。一面は冷淡に社会を観察し、他の一面は熱情をもってある事物に同感を表す。両面斉しく発達するものもなきにあらねど、多くは両者執れかに僻す。前者に僻するを写実派といい、後者に僻するを理想派という。碧梧桐は冷かなること水の如く、虚子は熱きこと火の如し。碧梧桐の人間を見るはなお無心の草木を見るがごとく、虚子の草木を見るはなお有情の人間を見るがごとし。随ってその作る所の俳句も一は写実に傾き、一は理想に傾く。一は空間を現し、一は時間を現す」と書いています。
碧梧桐は『子規の回想』で、当時を振り返っていますが、こうした放蕩生活で、明治28年から勤めていた「日本」を辞めなければならなくなります。ただ、こうした放蕩な生活は、次第に影を潜めていきます。碧梧桐は『子規の回想』で、当時を振り返っていますが、こうした放蕩生活で、明治28年から勤めていた「日本」を辞めなければならなくなります。ただ、こうした放蕩な生活は、次第に影を潜めていきます。
子規との道潅山のいきさつなど全然知らなかった私は、虚子に会う毎に別れている不便と寂寞を訴えていたのみならず、子規との喧嘩別れに、少々ヤケも手伝ってか、もう大ぴらに私と同宿する気にもなったのだろう。
実は初めて白状するが、と言って、須磨保養院以来の話をして、それをお前に打ち明けて言えなかったアシの心の苦痛を察しておくれ、実際お前の顔を見る度にすまんすまんと思っていたのだ、もうアシもな、升さんに捨てられたのだから、今後はお互いに思う存分勝手なことをやろうじゃないか、などとその頃よく行った連雀町の「ぼたん」という安鳥屋で、酔った虚子が管を巻いたものだった。
この高田屋へは、子規も一、二度来たこともあるが、瓢亭、肋骨など主人夫婦と仲良しになって、オイ阿爺と門口から大きな声で呼びかけたりしていた。ことに牛伴君は八々のいい相手というので、我々のいるいないにに関らず、遊びに来たものだった。
われわれの中学同窓の青木森々も、二十九年中には同宿の仲間になっていた。三人してかなり放埒な日々をおくったものだ。それに私は何月であったか表面は、従軍していた先輩達が皆帰って来たし、社の人物過剰という意味で、「日本」新聞社をやめさせられた。が、実は無学無能、新聞人にはなれないという折紙をつけられたのだ。ここに再び、前年のように、先輩誰もが匙を投げるような、碧虚二人の荒んだ遊蕩生活が繰返されるいいコンディションを醸成していた。何かしら不平であり、不安であり、身は自由不拘束なんだ。もし軍資金でも十分であったとしたら、それこそ本当に、子規から見放されていたかも知れなかった。
が、二年前の本郷下宿時代、二高をやめて東上した自分とは、もう環境がすっかり違っていた。俳句の世が、我々内輪のものでなくて、世間に公認された公のものになっていた。我々のようなデカダンなあばずれ書生でもが、いわゆる日本派中堅どころの声誉を嬴得ていた。ポッポツ文学雑誌などの選などを頼まれて、小遣い位出来るようになっていた。(河東碧梧桐 子規の回想 当事の新調)
また、明治30年1月の「ホトトギス」掲載の『明治二十九年の俳諧』でも、碧梧桐の句を「極めて印象の明瞭なる句」とし、虚子と碧梧桐が日本派のエースとして俳壇の前面に強く押し出していきます。
碧梧桐と虚子は、明治29年4月から旧前橋藩士族・大畠豊水経営する神田淡路町の高田屋という下宿屋で、碧梧桐と再び同居を始めました。そこで22歳の虚子は、大畠家の次女いとを見初め、翌年6月に結婚することになります。たまたま、その年の1月に碧梧桐は天然痘に罹り、一か月ほど入院しなくてはならなくなりました。碧梧桐の方がいとと親しかったのですが、空白の時間のために虚子といとの親密度が増した結果でした。
5月になると傷心の碧梧桐は、北陸の旅を思いつきます。まず京都へ行き、三高で学んでいた寒川鼠骨や新聞記者の中川四明に会い、米原から敦賀に出て金沢に着きました。金沢では同郷の竹村秋竹の家に身を寄せました。虚子の結婚式のある6月には能登へ向かっていると子規の容態が重くなったという知らせが届きます。しかし、虚子から焼香を得たとの連絡があり、碧梧桐は旅を続けました。この紀行は「日本」に連載され、碧梧桐が東京に戻ったのは7月でした。
子規は、帰ってきた碧梧桐に句を贈っています。
団扇出して先づ問ふ加賀は能登は如何 ≫
「子規・漱石・寅彦・東洋城」俳句管見(その十二) [子規・漱石・寅彦・東洋城]
その十二「明治三十三年(一九〇〇)・「五月雨」など」
(子規・三十四歳。八月、喀血。同、二十六日渡欧前の離別に漱石が訪問。)
https://shiki-museum.com/masaokashiki/haiku?post_type=haiku&post_type=haiku&haiku_id=&p_age=34&season=&classification=&kigo=%E4%BA%94%E6%9C%88%E9%9B%A8&s=&select=
五月雨や上野の山も見あきたり ID24271 制作年34 季節夏 分類天文 季語五月雨
五月雨や背戸に落ちあふ傘と傘 ID24272 制作年34 季節夏 分類天文 季語五月雨
五月雨や畳に上る青蛙 ID24273 制作年34 季節夏 分類天文 季語五月雨
五月雨や棚へとりつくものゝ蔓 ID24274 制作年34 季節夏 分類天文 季語五月雨
根だ搖く川辺の宿や五月雨 ID24275 制作年34 季節夏 分類天文 季語五月雨
病人に鯛の見舞や五月雨 ID24276 制作年34 季節夏 分類天文 季語五月雨
病人の枕ならべて五月雨 ID24277 制作年34 季節夏 分類天文 季語五月雨
(漱石・三十四歳。英国留学。)
11 さみだれに持ちあつかふや蛇目傘(明治二十四年)
185 五月雨ぞ何処まで行ても時鳥(明治二十八年。「子規へ送りたる句稿三」)
499 馬子歌や小夜の中山さみだるゝ(同上。「子規へ送りたる句稿九」)
798 海嘯去つて後すさまじや五月雨(明治二十九年。「子規へ送りたる句稿十五」)
935 橋落ちて恋中絶えぬ五月雨(同上。「子規へ送りたる句稿十九」)
938 五月雨や鏡曇りて恨めしき(同上)
1196 五月雨や小袖をほどく酒のしみ(同上。「子規へ送りたる句稿(二十五))
1197 五月雨の壁落しけり枕元(同上)
1198 五月雨や四つ手繕ふ旧士族(同上)
1199 目を病んで灯ともさぬ夜や五月雨(同上)
1213 五月雨の弓張らんとすればくるひたる(明治三十年。「子規へ送りたる句稿二十五」)
1215 水攻の城落ちんとす五月雨(同上)
2082 五月雨や主と云はれし御月並(明治四十一年)
2091 一つ家を中に夜すがら五月雨るゝ(同上)
2098 五月雨やももだち高く来る人(明治四十二年)
(寅彦、二十三歳。「夏子(初妻))を高知から呼び寄せ、本郷区西片町(現、文京区に住む。田丸卓郎が東京帝国大学助教授となり、再び教えを受けるようになる。九月、イギリスに留学する漱石を横浜埠頭(ふとう)を見送る。十二月、夏子が喀血する。)
五月雨や窓を背にして物思ふ(明治三十一年作)
五月雨や堂朽ち盡し屋根の草(明治三十四年作)
五月雨の町掘りかへす工事かな(同上)
五月雨や土佐は石原小石原(同上)
五月雨や根を洗はるゝ屋根の草(同上)
(東洋城、二十三歳。「東洋城全句集上・中巻」)
「七月第一高等学校卒業。東京帝国大学へ入学す。東洋城と号す。その後、緑山、松琴書屋主人、秋谷立石山人の別号をもった。九月、漱石がイギリスへ留学の途に上った。」
五月雨(さみだれ)や茶を挽くにねむうなり(明治三十三年作。二十三歳。)
五月雨(さつきあめ)試験の心くだちけり(同上)
(参考) 「子規・碧悟桐・虚子」(碧悟桐「子規を語る」)周辺
https://plaza.rakuten.co.jp/akiradoinaka/diary/202105170000/

正岡子規(自画像)
https://www.mcvb.jp/photo/detail.php?i=203
≪ 碧梧桐は、帰郷した子規に野球を教わったことがきっかけとして、同級生の高浜虚子を誘って子規より俳句を学びます。
明治26(1893)年には、第三高等学校(現京都大学)入学しますが、第三高等学校解散のあおりを受けて、第二高等学校(現東北大学)に編入します。ただ、碧梧桐は勉強に興味がなくなり、中退しようと認め、子規に注意を受けています。一方、虚子も碧梧桐とともに中退していたのですが、子規にそのことを隠しており、虚子の人生にかいま見える狡さがこのころからも現れています。
『子規を語る』の「二高退学」をご覧ください。
明治二十七年は私一個人にとって、いろんな事件の起伏した、落着かない騒がしい年だった。二月には子規からほとんど突然に「小日本」の見本を数百部も郵送されて、それをどう処分しようかに戸惑いしたりした。やむなく学校の生徒控席の掲示版に貼り出して、誰でも取るに任せたりした。子規が「小日本」を創刊するについて、どれほど日夜気苦労していたか、それをさえ想見する予備知識を私は持たなかった。ただ多年の宿題になっていた「月の都」がその第一号から発表されたことが、私の胸を躍らせた位だった。「小日本」は気の利いた、挿画の多い、調子の高い賑やかな新聞だった、と古い記憶を持っている人は、今でも口をそろえてそういう。アアいう調子の新聞がこの頃創刊されたのであったら、必ず成功したであろうともいう。私はそういう批判を明らかに下すほど、新聞に対する感興も持っていなかった。私は新聞「日本」を購読しながら政治論などには一度も目を通さなかった。予規の随筆と俳句欄を見るのみで満足していたのだ。
四月の末には急病で父を失なった。そのため帰郷して、やっと学期試験に入洛した。学期試験中の試験勉強に草臥れて、ぐっすり寝込んでいた蚊帳の中に、意外にもこの一月から上京中であった虚子を迎える唐突な出来事があった。
「お前、どうしたんぞな」
「もうやめて来たのよ」
「やめて?」
「思うような学問するところは東京にもないな」
「ヘエー」
私は彼の突然な転身を、ただ驚きの眼で迎えたきりだった。虚子は上京中殆んど何もしなかった。少々遊蕩気分を味った位だった。それで復校して、また窮窟な重詰学課をやると言った。
学期試験が終るのと同時に、第三高等中学は解散されて、生徒は各地に四散せねばならぬ運命になった。復校を許された虚子は、私と同期生で、文科の本科一年生になったのであるが、私達は仙台の二高移転を志願して許可された。熊本に行くか、金沢に行くか、もしくは鹿児島に行くかが順当なのであったが、私達はただ東京を通過するという点だけで仙台を志願したのだった。
仙台の二高は、選りに選って私達の意思に反する校風のギゴチなさで一杯だった。三高時代の生徒の自由が極度に束縛されていた。
文科の本科生も、小学校生徒同様に取扱われていた。裏切られた私達は、毎日気まずい、重苦しい日を送った。毎晩蒸栗を買って来ては、それを二人で剥ぎながら、文学論、人間論、小説家論、現代の小説家評論などで僅かに鬱を散じていた。広瀬川を下に臨む公園を夜半に散歩しては、虚子の燈火観などをしみじみ聞き味うのだった。かくて二年もこの校風に縛られねばならない月日を無限に永いもののように思いなして、今度は私の方が退校論を高調した。復校して問もない虚子は、理性では幾分鈍っていたが、感情ではすっかり私に共鳴した。それで二高在学僅かに二ヶ月で、断然学校と縁を絶った。
十一月末日のうら寒い日に、私は一人で松島見物などをして上京した。
それまで子規は新聞事業で多忙であったし、私はいろんな身辺の事実に追われて、手紙の往復もほとんど絶えていた。ただ二高入学当時、東京で親しく子規の謦咳に接したのみだったが、この退学事件については子規も黙止し難かったと見え、左の一書を久しぶりにくれた。子規が仙台の下宿ーー大町通五丁目新町七、鈴木芳吉方ーー宛によこした手紙で、遺っている唯一のものである。
碧梧桐詞兄 几下 子規拝
御手紙拝見仕候、益々御清勝奉賀候、御申越之趣にていよいよ学校御退学と御決定被成候由誠にめでたく存候、それ位之御決心なくては小説家にはとてもなれ申まじく天ッ張れ見上げたる御事かなと祝い申候、虚子君の復校せられてよりまだ半年も立たぬ内に、またまた貴兄の退校とはよくよく入組んだ仕掛にて天公の戯謔もまたおもしろく候(以上世界観)
然れども小生一個より見ればやはり退校之事は御とめ申候、殷鑑遠からず虚子兄にありと存候、学校をやめることがなぜ小説家になれるか一向分らぬ様に思われ候、学校をやめて何となさる御積りか定めて独学とか何とかいわるるならん、なれども独学の難きは虚子兄之熟知せらるる所に候えば同兄より御聞取り成さるべく候、況んや家郷と縁を断ちても遣りとげんとの御決定の由、万一貴兄独立して渡世せねばならぬようになりし暁には何となされ候ぞ「ただ一人の糊口なればそれにてよろしき事と思い居候」との御詞は已に世の中を御存知なき証拠なり、ただ一人の糊口を何とし遂げ給うぞ、よし糊口の道あるにせよそれは非常の困難と労力とを要する仕事にて、つまり小説書くひまなんどは無く、矢ッ張り中学にぶらぶらしておって、相間相間にむだ書していた方が余程ましだったというようなことにはならぬかと存候、つまり貴兄の退校は先日の虚子兄と同じく学校がいやという一点より湧き出した考にて、学校を出て後始めて学校の極楽場たるを知るの愚を学び給わぬかと推察致候。
それよりもここにもっともおかしきは御書中「これ実に小子の身において最大激変なり」などと書き立て給いしことなり、貴兄自身において最大激変と思い給う程ならば、先ず学校はやめぬ方がよきかと存候、人間世界で最大激変ということは総て善からぬことに候、自分之事いうでなけれど小生の退学せし時などは、小生自身に取りては毫も変動なかりしことにて、一週間に一度くらい登校せしものがその義務を免れし位之者にて候いき、鷺は立てども後を濁さずとか、退学するにしても先ずこの学期だけは試験をすまし、冬期休業には一旦御上京なさるべく御面会致候上縷々可申上候(以上個人観)
十月二十九日夜獺祭書屋燈下に認む
この手紙では退学を相談してやった返事のようであるが、この時は既に万事を決行していた後だった。虚子も同時に退学したのだったが、子規の手前を気がねして、ただ私一人の問題のように繕っていたのだった。
虚子は退学攻撃の鉾先きを避けるためであったであろう、なおしばらく仙台に留まっていた。「のぽさん、おこっといでるな」と二人で話し合った心の中は息のつまるような暗さだった。
「よく退学おしたな」と誉められようとも予期してはいなかったのであるが、こう冷静に真向うからドヤしつけられようとも考えていなかったのだった。
それでも同じクラスの人達が二人の送別会を開いてくれた時には、今日から社会の自由大学で奮闘して、必ず素志を達して見せる、と言ったような気烙を吐いて、私は何か留別の句を席上で読み上げたりした。 ≫
(子規・三十四歳。八月、喀血。同、二十六日渡欧前の離別に漱石が訪問。)
https://shiki-museum.com/masaokashiki/haiku?post_type=haiku&post_type=haiku&haiku_id=&p_age=34&season=&classification=&kigo=%E4%BA%94%E6%9C%88%E9%9B%A8&s=&select=
五月雨や上野の山も見あきたり ID24271 制作年34 季節夏 分類天文 季語五月雨
五月雨や背戸に落ちあふ傘と傘 ID24272 制作年34 季節夏 分類天文 季語五月雨
五月雨や畳に上る青蛙 ID24273 制作年34 季節夏 分類天文 季語五月雨
五月雨や棚へとりつくものゝ蔓 ID24274 制作年34 季節夏 分類天文 季語五月雨
根だ搖く川辺の宿や五月雨 ID24275 制作年34 季節夏 分類天文 季語五月雨
病人に鯛の見舞や五月雨 ID24276 制作年34 季節夏 分類天文 季語五月雨
病人の枕ならべて五月雨 ID24277 制作年34 季節夏 分類天文 季語五月雨
(漱石・三十四歳。英国留学。)
11 さみだれに持ちあつかふや蛇目傘(明治二十四年)
185 五月雨ぞ何処まで行ても時鳥(明治二十八年。「子規へ送りたる句稿三」)
499 馬子歌や小夜の中山さみだるゝ(同上。「子規へ送りたる句稿九」)
798 海嘯去つて後すさまじや五月雨(明治二十九年。「子規へ送りたる句稿十五」)
935 橋落ちて恋中絶えぬ五月雨(同上。「子規へ送りたる句稿十九」)
938 五月雨や鏡曇りて恨めしき(同上)
1196 五月雨や小袖をほどく酒のしみ(同上。「子規へ送りたる句稿(二十五))
1197 五月雨の壁落しけり枕元(同上)
1198 五月雨や四つ手繕ふ旧士族(同上)
1199 目を病んで灯ともさぬ夜や五月雨(同上)
1213 五月雨の弓張らんとすればくるひたる(明治三十年。「子規へ送りたる句稿二十五」)
1215 水攻の城落ちんとす五月雨(同上)
2082 五月雨や主と云はれし御月並(明治四十一年)
2091 一つ家を中に夜すがら五月雨るゝ(同上)
2098 五月雨やももだち高く来る人(明治四十二年)
(寅彦、二十三歳。「夏子(初妻))を高知から呼び寄せ、本郷区西片町(現、文京区に住む。田丸卓郎が東京帝国大学助教授となり、再び教えを受けるようになる。九月、イギリスに留学する漱石を横浜埠頭(ふとう)を見送る。十二月、夏子が喀血する。)
五月雨や窓を背にして物思ふ(明治三十一年作)
五月雨や堂朽ち盡し屋根の草(明治三十四年作)
五月雨の町掘りかへす工事かな(同上)
五月雨や土佐は石原小石原(同上)
五月雨や根を洗はるゝ屋根の草(同上)
(東洋城、二十三歳。「東洋城全句集上・中巻」)
「七月第一高等学校卒業。東京帝国大学へ入学す。東洋城と号す。その後、緑山、松琴書屋主人、秋谷立石山人の別号をもった。九月、漱石がイギリスへ留学の途に上った。」
五月雨(さみだれ)や茶を挽くにねむうなり(明治三十三年作。二十三歳。)
五月雨(さつきあめ)試験の心くだちけり(同上)
(参考) 「子規・碧悟桐・虚子」(碧悟桐「子規を語る」)周辺
https://plaza.rakuten.co.jp/akiradoinaka/diary/202105170000/

正岡子規(自画像)
https://www.mcvb.jp/photo/detail.php?i=203
≪ 碧梧桐は、帰郷した子規に野球を教わったことがきっかけとして、同級生の高浜虚子を誘って子規より俳句を学びます。
明治26(1893)年には、第三高等学校(現京都大学)入学しますが、第三高等学校解散のあおりを受けて、第二高等学校(現東北大学)に編入します。ただ、碧梧桐は勉強に興味がなくなり、中退しようと認め、子規に注意を受けています。一方、虚子も碧梧桐とともに中退していたのですが、子規にそのことを隠しており、虚子の人生にかいま見える狡さがこのころからも現れています。
『子規を語る』の「二高退学」をご覧ください。
明治二十七年は私一個人にとって、いろんな事件の起伏した、落着かない騒がしい年だった。二月には子規からほとんど突然に「小日本」の見本を数百部も郵送されて、それをどう処分しようかに戸惑いしたりした。やむなく学校の生徒控席の掲示版に貼り出して、誰でも取るに任せたりした。子規が「小日本」を創刊するについて、どれほど日夜気苦労していたか、それをさえ想見する予備知識を私は持たなかった。ただ多年の宿題になっていた「月の都」がその第一号から発表されたことが、私の胸を躍らせた位だった。「小日本」は気の利いた、挿画の多い、調子の高い賑やかな新聞だった、と古い記憶を持っている人は、今でも口をそろえてそういう。アアいう調子の新聞がこの頃創刊されたのであったら、必ず成功したであろうともいう。私はそういう批判を明らかに下すほど、新聞に対する感興も持っていなかった。私は新聞「日本」を購読しながら政治論などには一度も目を通さなかった。予規の随筆と俳句欄を見るのみで満足していたのだ。
四月の末には急病で父を失なった。そのため帰郷して、やっと学期試験に入洛した。学期試験中の試験勉強に草臥れて、ぐっすり寝込んでいた蚊帳の中に、意外にもこの一月から上京中であった虚子を迎える唐突な出来事があった。
「お前、どうしたんぞな」
「もうやめて来たのよ」
「やめて?」
「思うような学問するところは東京にもないな」
「ヘエー」
私は彼の突然な転身を、ただ驚きの眼で迎えたきりだった。虚子は上京中殆んど何もしなかった。少々遊蕩気分を味った位だった。それで復校して、また窮窟な重詰学課をやると言った。
学期試験が終るのと同時に、第三高等中学は解散されて、生徒は各地に四散せねばならぬ運命になった。復校を許された虚子は、私と同期生で、文科の本科一年生になったのであるが、私達は仙台の二高移転を志願して許可された。熊本に行くか、金沢に行くか、もしくは鹿児島に行くかが順当なのであったが、私達はただ東京を通過するという点だけで仙台を志願したのだった。
仙台の二高は、選りに選って私達の意思に反する校風のギゴチなさで一杯だった。三高時代の生徒の自由が極度に束縛されていた。
文科の本科生も、小学校生徒同様に取扱われていた。裏切られた私達は、毎日気まずい、重苦しい日を送った。毎晩蒸栗を買って来ては、それを二人で剥ぎながら、文学論、人間論、小説家論、現代の小説家評論などで僅かに鬱を散じていた。広瀬川を下に臨む公園を夜半に散歩しては、虚子の燈火観などをしみじみ聞き味うのだった。かくて二年もこの校風に縛られねばならない月日を無限に永いもののように思いなして、今度は私の方が退校論を高調した。復校して問もない虚子は、理性では幾分鈍っていたが、感情ではすっかり私に共鳴した。それで二高在学僅かに二ヶ月で、断然学校と縁を絶った。
十一月末日のうら寒い日に、私は一人で松島見物などをして上京した。
それまで子規は新聞事業で多忙であったし、私はいろんな身辺の事実に追われて、手紙の往復もほとんど絶えていた。ただ二高入学当時、東京で親しく子規の謦咳に接したのみだったが、この退学事件については子規も黙止し難かったと見え、左の一書を久しぶりにくれた。子規が仙台の下宿ーー大町通五丁目新町七、鈴木芳吉方ーー宛によこした手紙で、遺っている唯一のものである。
碧梧桐詞兄 几下 子規拝
御手紙拝見仕候、益々御清勝奉賀候、御申越之趣にていよいよ学校御退学と御決定被成候由誠にめでたく存候、それ位之御決心なくては小説家にはとてもなれ申まじく天ッ張れ見上げたる御事かなと祝い申候、虚子君の復校せられてよりまだ半年も立たぬ内に、またまた貴兄の退校とはよくよく入組んだ仕掛にて天公の戯謔もまたおもしろく候(以上世界観)
然れども小生一個より見ればやはり退校之事は御とめ申候、殷鑑遠からず虚子兄にありと存候、学校をやめることがなぜ小説家になれるか一向分らぬ様に思われ候、学校をやめて何となさる御積りか定めて独学とか何とかいわるるならん、なれども独学の難きは虚子兄之熟知せらるる所に候えば同兄より御聞取り成さるべく候、況んや家郷と縁を断ちても遣りとげんとの御決定の由、万一貴兄独立して渡世せねばならぬようになりし暁には何となされ候ぞ「ただ一人の糊口なればそれにてよろしき事と思い居候」との御詞は已に世の中を御存知なき証拠なり、ただ一人の糊口を何とし遂げ給うぞ、よし糊口の道あるにせよそれは非常の困難と労力とを要する仕事にて、つまり小説書くひまなんどは無く、矢ッ張り中学にぶらぶらしておって、相間相間にむだ書していた方が余程ましだったというようなことにはならぬかと存候、つまり貴兄の退校は先日の虚子兄と同じく学校がいやという一点より湧き出した考にて、学校を出て後始めて学校の極楽場たるを知るの愚を学び給わぬかと推察致候。
それよりもここにもっともおかしきは御書中「これ実に小子の身において最大激変なり」などと書き立て給いしことなり、貴兄自身において最大激変と思い給う程ならば、先ず学校はやめぬ方がよきかと存候、人間世界で最大激変ということは総て善からぬことに候、自分之事いうでなけれど小生の退学せし時などは、小生自身に取りては毫も変動なかりしことにて、一週間に一度くらい登校せしものがその義務を免れし位之者にて候いき、鷺は立てども後を濁さずとか、退学するにしても先ずこの学期だけは試験をすまし、冬期休業には一旦御上京なさるべく御面会致候上縷々可申上候(以上個人観)
十月二十九日夜獺祭書屋燈下に認む
この手紙では退学を相談してやった返事のようであるが、この時は既に万事を決行していた後だった。虚子も同時に退学したのだったが、子規の手前を気がねして、ただ私一人の問題のように繕っていたのだった。
虚子は退学攻撃の鉾先きを避けるためであったであろう、なおしばらく仙台に留まっていた。「のぽさん、おこっといでるな」と二人で話し合った心の中は息のつまるような暗さだった。
「よく退学おしたな」と誉められようとも予期してはいなかったのであるが、こう冷静に真向うからドヤしつけられようとも考えていなかったのだった。
それでも同じクラスの人達が二人の送別会を開いてくれた時には、今日から社会の自由大学で奮闘して、必ず素志を達して見せる、と言ったような気烙を吐いて、私は何か留別の句を席上で読み上げたりした。 ≫
「子規・漱石・寅彦・東洋城」俳句管見(その十一) [子規・漱石・寅彦・東洋城]
その十一「明治三十二年(一八九九)・「萩」など」
(子規・三十三歳。『俳諧諧大要』)『俳人蕪村』刊。中村不折の指導を受けて水彩画を試みる。)
https://shiki-museum.com/masaokashiki/haiku?post_type=haiku&post_type=haiku&haiku_id=&p_age=32&season=&classification=&kigo=%E8%90%A9&s=&select=
草庵に千句の會や萩の花 ID22929 制作年32 季節秋 分類植物 季語萩
妻を呼ぶ籠の鶉や庭の萩 ID22930 制作年32 季節秋 分類植物 季語萩
杖によりて立ち上りけり萩の花 ID22931 制作年32 季節秋 分類植物 季語萩
庭荒れて萩の亂れをつくろはず ID22932 制作年32 季節秋 分類植物 季語萩
萩咲いて俗に墮つ松の小庭哉 ID22933 制作年32 季節秋 分類植物 季語萩
萩咲て抱一の画を掛にけり ID22934 制作年32 季節秋 分類植物 季語萩
萩を題に歌つくらしむ萩の宿 ID22935 制作年32 季節秋 分類植物 季語萩
箔燒けて萩の模樣や古色紙 ID22936 制作年32 季節秋 分類植物 季語萩
彫物の鹿を置きけり萩の庭 ID22937 制作年32 季節秋 分類植物 季語萩
(漱石・三十三歳。五月、長女(筆子)誕生。子規宛句稿(三十二~三十五)。)
161 はらはらとせう事なしに萩の露(明治二十八年。「子規へ送りたる句稿一」)
896 垂れかゝる萩静かなり背戸の川(明治二十九年。「子規へ送りたる句稿十七」)
897 落ち延びて只一騎なり萩の原(同上)
1264 萩に伏し薄にみだれ故里は(明治三十年。「子規へ送りたる句稿二十六」)
1395 早稲晩稲花なら見せう萩紫苑(明治三十一年。「子規へ送りたる句稿三十」)
1678 白萩の露をこぼすや温泉の流(明治三十二年。「子規へ送りたる句稿三十四」)
1688 灰に濡れて立つや薄と萩の中(同上)
1689 行けど萩行けど薄の原広し(同上)
1860 伏す萩の風情にそれと覚りてよ(明治三十七年)
(寅彦・二十二歳。東京帝国大学物理学科入学。正岡子規と初対面。)
漁歌止んで只汐風の萩を吹く(明治三十一~二年作)
(東洋城・二十二歳。)
枯萩や汀の屑の鶴一羽(明治四十年作)
萩枯るゝ小御門とそれも連句かな(同上)
(参考)「 正岡子規の俳句革新(三)」
https://blog.goo.ne.jp/seisei14/e/b335fca44e92fab339326c17a14a1b79

http://www.s-kawano.net/s-kawano/%E6%AD%A3%E5%B2%A1%E5%AD%90%E8%A6%8F.pdf
明治三十年一月、子規は、編集発行人を柳原極堂(やなぎはらきょくどう)をして、伊予松山で、俳誌「ホトトギス」を発刊させる。そして、これは、二十号まで続くが、その後、東京の高浜虚子が引き継ぎ、昭和三十五年の子規没後、この虚子が子規の継承者となる。その後、文芸雑誌の時代を経て、大正元年から「花鳥諷詠」という俳句理念の下に、客観写生俳句を提唱・推進し、所謂、「ホトトギス」王国を築き上げる。
この「ホトトギス」の雑詠欄から、渡辺水巴(わたなべすいは)・村上鬼城(むらかみきじょう)・原石鼎(はらせきてい)・飯田蛇忽(いいだだこつ)らの俊秀が巣立っていた。さらに、その大正時代に入ると、所謂、四Sといわれる、水原秋桜子(みずはらしゅうおうし)・山口誓子(やまぐちせいし)・阿波野青畝(あわのせいほ)・高野素十(たかのすじゅう)を始め、富安風生(とみやすふうせい)・山口青邨(やまぐちせいそん)という一大「ホトトギス」山脈が築かれていったのである。
昭和三十四年虚子没後は、長男の高浜年尾(たかはまとしお)が引き継ぎ、その後、年尾の次女の稲畑汀子(いなはたていこ)が継承し、平成六年四月で一一六八号に至っている。
もう一つ、子規の活動の拠点は、「日本」新聞であったが、この新聞紙上により、子規は数々の「俳句革新」運動に係わる俳論を発表すると共に。明治二十六に、「子規選句欄」を設け、子規の新派の俳句の興隆に繋げるのであるが、子規の没後は、これを、河東碧梧桐に引き継がれた。
碧梧桐は、当初、虚子と歩を同じくしていたが、後に、進歩的、写実的色彩を強め、虚子と袂を断つこととなる。
この碧梧桐門にも、大須賀乙字(おおすがおつじ)・荻原井泉水(おぎわらせいせんすい)・小沢碧童(おざわへきどう)・中塚一碧楼(なかつかいっぺきろう)などの新進気鋭の俳人を輩出し、これまた、碧門隆盛の一時代を築いた。
これらの碧門俳句は、「新傾向に非ずんば俳句に非ず」と称され、この「新傾向俳句」は一世を風靡するが、後に、この「新傾向俳句」は内部分裂を始め、乙字は伝統尊重と古典復帰を目指し「石楠(しやくなげ)」に拠り、井泉水は無季の自由律俳句の「層雲(そううん)」に走り、四分五裂の状態となり、ここに碧門俳句は、虚子の「ホトトギス」の隆盛に比して衰退転落の運命に堕するのである。
とまれ、子規の「俳句革新」運動は、子規の没後、その二大俊秀の、虚子の俳誌「ホトトギス」と碧梧桐の新聞「日本」の影響下で、強力に推進され、子規の時代の「新派と旧派」との闘いは、圧倒的な差で子規らの新派の新俳句が、旧派の宗匠俳句を駆逐していくのである。
しかし、子規の「俳句革新」運動が、さほどまでに成果を上げ得たのは、子規と子規門の力だけによるのであろうか。これは、決してそうではないのである。
ここで、芭蕉没後(一六九四)三百年にも当たる平成四年(一九九三)に没した、芭蕉俳諧の正統な継承を目指した、加藤楸邨(かとうしゅうそん)の「明治俳句史(上)」(『俳句講座』・明治書院)から、興味ある指摘の要約を見ることにいたしたい。
○江戸は西方の力に圧せられて敗北した舞台である。新しい政治・社会の勢力は西方から来た人々によって形成さられ、江戸の人は社会の中枢にあって勢いを占めることが不可能な状態に置かれた。
○従って、文化の中心であった江戸の旧俳人(注・旧派)たちが、おのずと逸楽遊閑の方向に追いこまれたるのは、避けがたい傾向だったわけである。
○この結果、俳人の生活はおのずと遊閑的・寄生的となって、時代の生動する力からは全く遊離せざるを得なかった。従って、そこに辛うじて認められるのは、過ぎ去った過去の郷愁をよりどころとする江戸趣味の世界であった。生きて動きゆく新しい社会の流れに目を閉じて、すでに昨日のものとなった花の残香をなつかしむに過ぎない無気力が氾濫したのであった。
○また、芭蕉の没後は、その門下たちも点印(注・選句料の点料)を用いるようになり、時代が下るにつれて点も甘くなって、大衆に媚びる輩も増加して、(注・そのような状況が)幕末から明治に至ったのである。
○月並というのは月次とも書いて、毎月いとなむ例会という意味である。(注・この例会での寄せ句を集めたものが、月並集で)、その月並集は遠隔の人の寄せ句まで集めて出されるようになる。それらの句はいずれも入花料が必要とされ、入花料というのは出句の料金で、これが点者の点料や月並集の開板費用に当てられたわけである。こうなると、出句者の側からいえば、芸の問題が中心になるのではなく、次第に高点を競う勢いが馴致され、その結果、高点を取る手引の参考書まで出るようになった。点者がそういう大衆の嗜好を察知して堕落することも、逆に、出句者が点者の好みに迎合してねらいをつけることも、自然の勢いであった。
○子規は当然動かねばならなかった時代の機運に、最もふさわしい人間の在り方で際会したとみるべきで、その革新運動は、子規の功績に帰すべきところ極めて多大であるが、根本的には、時代の要求が子規を促したということも、見のがしてはならぬところである。
○子規のそれ(注・「俳句革新」)は、封建的な時代の庶民の文学から、近代資本主義時代の新しい市民の声の解放という、歴史的役割を負うものと考えられてよいと思うのだが、その第二の波頭(注・「俳句革新」)は、複雑な時代の後進性を負わされていたために、子規において完全な成立を見ることができなかったのである。
○加えるに、子規の在り方と後年の病臥生活という特殊な事情の下に、解放された個は、広い社会とかかわる社会的人間として個となる代りに、狭い「病牀六尺」の中に心境的な定着を示して、多くの課題は子規以後に遺されてきているということができる
○(注・最後に)正岡子規の「日本派」の新しい俳句の運動が進められていた頃、一方では、尾崎紅葉・大野酒竹・角田竹冷らの各々の一団(注・「秋声会」・「筑波会」など)が、旧派とは一線を画して「日本派」と近い動きを示していたことは忘れてはならない。
これらの楸邨の、子規の「俳句革新」運動に関連した背景の分析や周辺の動向の分析は、極めて適切なものがあるが、さらに、これらに、付け加える事項としては、次のようなことが上げられるかと思う。それらは、今までに、色々の角度から側面的に触れられてきたところではあるが、ここで一括まとめをしておきたいと思う。
○即ち、子規らの「俳句革新」運動というのは、西洋的な文学思想を持った学生上がりの、まだ、若干二十五歳という少壮ジヤーナリストともいうべき、職業俳人ではない(アマ)子規をリーダとする、いわば、素人(アマ)集団によって成し遂げられたということである。
○また、当時の旧派の俳句は、江戸末期の俗調の延長線上にあり、それは、まさしく、子規が指摘するように、「俳句は已に盡きたりと思ふなり。よし未だ盡きずとするも明治年間に盡きんこと期して待つべきなり」との、崩壊寸前にあり、その崩壊は修復する程度では持ち堪えることができず、それは、新しい近代の西洋的な文学思想をもっての全面改築をする必要があったということである。
○更には、これらの「俳句革新」運動は、主として、子規をリーダとする、伊予松山出身の地方の面々から成る「日本派」が活躍するのであるが、その他にも、「秋声会」や「筑波会」という、これまた、職業俳人ではなく、趣味で俳句をしている余技的俳句人(アマ)の活躍も大きな役割を果たした。
○因みに、「秋声会」の、角田竹冷は東京株式取引所理事長などの要職を歴任し、伊藤松宇は王子製紙の幹部職員、巌谷小波は児童文学では多大の貢献をした作家でもあり学者でもある。尾崎紅葉は『金色夜叉』などの大作をものにしている明治文壇の大立者である。
○一方、「筑波会」の面々は、これは、主として東大関係者の会であり、大野酒竹は東大の皮膚科の教授、佐々醒星は国文学の権威の文学博士、笹川臨風は美術評論家としても一流のこれまた文学博士、沼波瓊音は東大の俳諧史の教授と、いずれも、日本の近代化を背負っていた超一流人である。
○こういう当時の、最高級の教育を受け、その西洋の思想をもろに受け止め、そして、明治維新以降の日本の近代化に、それぞれが、それぞれに貢献し、それを推進している超知識人達が、こぞって、新派の近代俳句の「俳句革新」運動に、直接と間接とを問わず、携わったのであるから、これは、其角堂とか雪中庵とかの嗣号の下の家元制度のような旧派の宗匠俳句が駆逐せられていったのは、けだし、止むを得なかったということなのであろう。
以上が、楸邨の、子規の「俳句革新」運動に関連した背景の分析や周辺の動向の分析に追加して付記しておきたい事項なのであるが、更に、今となっては、子規の「俳句革新」運動の影に隠れて余り指摘することも少ない幾つかの重要な事項について付記しておくこととする。
その一は、子規が、明治二十八年に「発句(注・俳句)は文学なり、連俳(連句)は文学に非ず」と抹殺したところ連俳(連句)について、子規自身、その四年後の、明治三十八年に、その『俳諧三佳書序』で、「連句に興味を持っている」旨の、それまでの「連俳(連句)非文学論」を撤回するような記載を残しているのである。
○自分は連句という者余り好まねば古俳書を見て連句を読みし事無く又自ら作りし例も甚だ稀である。然るに此等の集(注・『猿蓑』・『続明烏』・『五車反古』)にある連句を読めばいたく興に入り感に堪ふるので、終には、これ程面白い者ならば自分も連 句をやつて見たいという念が起つてくる。
そして、それだけではなく、子規と虚子との両吟すら「ホトトギス」誌上(第二巻第二号)に登場しているのである。その表の六句を掲げておくこととする。
○発句 萩咲くや崩れ初めたる雲の峰 (子規)
脇 かげたる月の出づる川上 (月が引き上げられている 虚子)
第三 うそ寒み里は鎖さぬ家もなし (子規)
四句目 駕籠二人銭かりに来る (虚子)
五句目 洗石の場を流したる夜の雪 (子規)
折端 残りすくなに風呂吹の味噌(虚子)
その二は、子規、虚子とも連なり、夏目漱石門の松根東洋城(まつねとうようじょう)とその俳誌「渋柿」が、芭蕉以来の伝統ある連句の世界を、今に伝えているということである。
○渋柿はその芭蕉に於てなされし如く「連句」を大切にす。之に依り多く俳諧を闡明(注・びんめい)し拡充し高揚す
これは、大正四年に、東洋城がその俳誌「渋柿」を創刊した時の、その目指すべきもの一つとして東洋城が掲げたものである。
そして、東洋城は、その生涯において、歌仙(三十六句形式の連句)百六巻の他、数々の連句作品を残しているとか。
また、東洋城門には、寺田寅日子(寅彦)・野村喜舟(のむらきしゅう)・阿片瓢郎(あがたひょうろう)などがおり、現在に、その連句の伝統を守っている。
次に、東洋城と寅日子との両吟の、その表の六句を掲げておくこととする。
○発句 水団扇鵜飼の絵なる篝かな (東洋城)
脇 旅の話の更けて涼しき (寅日子)
第三 縁柱すがるところに瘤ありて (東洋城)
四句目 半分とけしあと解けぬ謎 (寅日子)
五句目 吸物をあとから出した月の宴 ( 月の定座 東洋城)
折端 庭のすゝきに風渡る頃 (寅日子)
その三は、子規の「俳句革新」運動というのは、虚子と碧梧桐という二人の傑出した弟子により受け継がれ、そして、虚子によって、その近代俳句(新派の俳句)が確立するのであった。そして、碧梧桐の「新傾向俳句」によって、極端なまでに、無季自由律の分野など、現代俳句に見られる多種多様な分野のリーデイングケースのような役割を演じるのであった。
そして、この俳句の前衛的な碧梧桐はともかくとして、新しい伝統俳句を樹立した虚子は、既に、子規の生存中の頃から、「連句の趣味」(「ホトトギス」・明治三二・五)なる一文を発表し、子規の「連俳(注・連句)非文学論」とは一味違った見解を発表しているのである。
また、虚子は、昭和十三年四月に、その後継者の年尾に「誹諧」という雑誌を刊行させ、この「誹諧」には、「俳句・俳文・俳論・連句・俳諧詩」まで多彩な内容となっているとのことである。
ここにいう「俳諧詩」とは、それは、自由詩なのであるが、俳人も、俳句だけではなくもっと自由に創作を試みるべきとする虚子の心情を物語るものであろう。
○ 俳諧詩 麦踏(虚子作)
夕ぐれの 畑中に 麦踏んで ゐる女
もうすぐに 足もとも わからなく なるだろう
夕靄が だんだんと 濃くなりて やはらかく
おしつゝみ かいいだく
その四は、子規の「日本派」(伊予派)と同じく、新派の俳句として「秋声会」・「筑波会」なども、旧派の俳句を一掃するために一つの役割を演じるのであるが、これらの「秋声会」・「筑波会」などの面々においては、子規の「連俳(注・連句)非文学論」にかかわらず、「連句」の復興に力を尽くした人が少なくない。
その筆頭は、「秋声会」の大物、伊藤松宇である。松宇は、明治四十四年六月に俳誌「にひはり」を創刊主宰して、俳諧の史的研究・連句の再認識に尽力する。松宇は実作者というよりは、俳諧の研究・考証・連句の鼓吹などに大きく寄与した。
次に、松宇と根津芦丈(ねずろじょう)との両吟の、その表の六句を掲げておくこととする。この芦丈は、連句完成数三千巻ともいわれ、その芦丈門に、清水瓢左(しみずひょうざ)・野村牛耳(のむらぎゅうじ)・東明雅(ひがしあきまさ)などの多くの連句人が輩出している。
○発句 夜半の冬狸が付けし継句かな (松宇)
脇 衾すっぽり冠る凩 (芦丈)
第三 振って見る徳利の酒を命じて (松宇)
四句目 素彫りの像に会心の笑み (芦丈)
五句目 啄木鳥の月になるまで啄くらむ (月の定座 松宇)
折端 連れし小者の水落し去る (芦丈)
その五は、子規の「日本派」(伊予派)そして、「秋声会」・「筑波会」などの新派の俳句が、芭蕉以来延々と続いていた旧派の宗匠俳諧(連句・俳句)を簡単に駆逐し、その生命を完全に絶ったかというと、それは、そうではなく、今になお、その伝統は受け継がれているものを目にすることができるのである。
しかし、それは、子規そして虚子につながる近代俳句が巨大化し、その巨大化に比して矮小化されるという運命にはあった。
いや、言葉を変えれば、子規そして虚子につながる近代俳句の巨大化は、新しい主宰者という一種の権威ある者を誕生させ、かっての宗匠に代わるべき地位を得させたのである。とすれば、「其角堂」とか「雪中庵」とかの嗣号のもとに、かっての宗匠を中心とした伝統俳句が、かっての栄光を取り戻すことは、もはやあり得ないと思われる。
しかし、こと連句に限っていえば、実は、その近代俳句が避けて通った分野であり、これは、間違いなく、その近代俳句の成果を摂取しながら、再び、脚光を浴びることは、現代の連句界の動向を見て、そう間違っている結論にはならないと予測されるのである。
かかる連句の再興に鑑み、実は、かって、宗匠と呼ばれた方々は、名うての連句人であり、それらに連なる伝統俳諧(連句・発句)に携わっている方々との発掘と、その連携ということは、今後の連句に携わっていく者の課題ともいえるであろう。
かっての、宗匠と呼ばれた、著名な嗣号などを持つ俳諧師の連句を、前句と付句の二句仕立てで、その幾つかを次に掲げることとする。
○発句 水海に昼の月ありほとゝぎす (嗣号「花の本」・聴秋)
脇 子供も載せて早苗つむ舟 (湖月)
○ナウ五 囀にましらぬ鳩の巣について (素朗)
挙句 とけて残らぬ頃の雪垣 (東都三大家・橘田春湖)
○ウ折立 網とりの寒の兎をかきいだき (東都三大家・ 関為山)
二 ぬからす酒の用意してある (壺公)
○ウ十一 幾万の心をそゝる花日和 (嗣号「其角堂」・機一)
折端 素足のなじむ若草の上 (一滴)
○ウ 五 凩のたゆたふ隙を鐘の声 (予雲)
六 船を世帯に夫婦わりなき (東都三大家・鳥越等栽)
さて、この「俳句革新」の原点ということに思いをいたす時、やはり、子規の最晩年の『病牀六尺』の冒頭の書き出しを想起せざるを得ないのである。
○病牀六尺、これが我世界である。しかも此六尺の病牀が余には広過ぎるのである。
正岡子規、その三十五年の生涯は、まさに、それは「病牀六尺」の世界であったろう。そして、その「病牀六尺」は、当時の誰よりも広大無限の世界だったのである。
当時の誰が、子規に匹敵するだけの広大無限の世界を熟知したであろうか。つくづく、人間というのは、自分がその生を保っている、その所を、その世界を、何も目に焼き付けることもなく、何の感慨もなく、ただ、他人ごとのように眺めて、それで、その一生を終わってしまうことであろうか。
子規は、「病牀六尺」の世界にあって、その目に入る一木一草を、そして、生きとして生けるものを、凝縮して、凝縮して、その全ての在りようを克明に自分の「頭・心・五感」の焼き付けていったのである。
まさしく、神というのは、人間に等しく、その恩寵というものを分け与えるものなのだろう。普通人が、八十年、そして、その生涯で見聞きする全てのことを、子規は、その三十五年の生涯で、その「病牀六尺」の世界で全てを見通したのである。
こと、「俳句革新」ということに限っていえば、伊予松山出身の、一書生の子規が、その「病牀六尺」の世界で出会った、非常に限られた書生仲間と、その「病牀六尺」の世界で切磋琢磨し、その切磋琢磨の成果をもって、日本全土に「正岡子規の近代俳句」を押し進め、その「正岡子規の近代俳句」で一時代の全てを覆うてしまったのである。
まさに、それは革命であった。それは、まさしく、江戸から東京への変化と機を一にするものであった。時は、子規を必要とし、しかも、時は、「病牀六尺」の世界での、子規を必要としたのである。その針のような小ささで、そのダイヤモンドのような固さで、そのレザーのような鋭さで、当時の江戸俳諧(古典俳句・旧派)を東京俳句(近代俳句・新派)に変却せしめたのである。
かって、子規は、明治二十九年に、「俳人ヲ戒メルノ書」を、同郷の伊予の、一舟という俳人に書きおくっている。その冒頭の書き出しは次のとおりである。
○俳句ハ人ニ向ツテ威張ルガタメニ作ルモノニ非ズ
これこそ、子規の「俳句革新」の、その原点に位置するものではなかろうか。即ち、「俳句革新」の、その視点は、この「俳句ハ人ニ向ツテ威張ルガタメニ作ルモノニ非ズ」の、このアマチュアリズムこそ、その視点であったのではなかろうか。
そして、子規の、そのアマチュアリズムの視点には、当時の、旧態然とした職業俳人(プロ)は鼻もちならぬものに映じたのであろう。そして、その職業俳人(プロ)の手から、芭蕉以来の燦然と輝く本当の俳句(連句・発句)を取り戻し、そして、それを、純粋に俳句を愛好する、いわば、純粋俳人(アマ)の手に委ねようとしたのであろう。
その「俳人ヲ戒メルノ書」は、次の子規の句で結んでいる。
○ 柿くふて文学論を草しけり
その江戸俳諧(古典俳句・旧派)を東京俳句(近代俳句・新派)に変却せしめた原点とは何か。それは、それこそが、職業俳人(俳諧師・プロ)に対する素人俳人(俳句人・アマ)の挑戦以外の何ものでもない。
即ち、子規の「俳句革新」というのは、「書生(アマ)の、書生(アマ)のための、書生(アマチュア)による」俳句革新運動であったのである。
(子規・三十三歳。『俳諧諧大要』)『俳人蕪村』刊。中村不折の指導を受けて水彩画を試みる。)
https://shiki-museum.com/masaokashiki/haiku?post_type=haiku&post_type=haiku&haiku_id=&p_age=32&season=&classification=&kigo=%E8%90%A9&s=&select=
草庵に千句の會や萩の花 ID22929 制作年32 季節秋 分類植物 季語萩
妻を呼ぶ籠の鶉や庭の萩 ID22930 制作年32 季節秋 分類植物 季語萩
杖によりて立ち上りけり萩の花 ID22931 制作年32 季節秋 分類植物 季語萩
庭荒れて萩の亂れをつくろはず ID22932 制作年32 季節秋 分類植物 季語萩
萩咲いて俗に墮つ松の小庭哉 ID22933 制作年32 季節秋 分類植物 季語萩
萩咲て抱一の画を掛にけり ID22934 制作年32 季節秋 分類植物 季語萩
萩を題に歌つくらしむ萩の宿 ID22935 制作年32 季節秋 分類植物 季語萩
箔燒けて萩の模樣や古色紙 ID22936 制作年32 季節秋 分類植物 季語萩
彫物の鹿を置きけり萩の庭 ID22937 制作年32 季節秋 分類植物 季語萩
(漱石・三十三歳。五月、長女(筆子)誕生。子規宛句稿(三十二~三十五)。)
161 はらはらとせう事なしに萩の露(明治二十八年。「子規へ送りたる句稿一」)
896 垂れかゝる萩静かなり背戸の川(明治二十九年。「子規へ送りたる句稿十七」)
897 落ち延びて只一騎なり萩の原(同上)
1264 萩に伏し薄にみだれ故里は(明治三十年。「子規へ送りたる句稿二十六」)
1395 早稲晩稲花なら見せう萩紫苑(明治三十一年。「子規へ送りたる句稿三十」)
1678 白萩の露をこぼすや温泉の流(明治三十二年。「子規へ送りたる句稿三十四」)
1688 灰に濡れて立つや薄と萩の中(同上)
1689 行けど萩行けど薄の原広し(同上)
1860 伏す萩の風情にそれと覚りてよ(明治三十七年)
(寅彦・二十二歳。東京帝国大学物理学科入学。正岡子規と初対面。)
漁歌止んで只汐風の萩を吹く(明治三十一~二年作)
(東洋城・二十二歳。)
枯萩や汀の屑の鶴一羽(明治四十年作)
萩枯るゝ小御門とそれも連句かな(同上)
(参考)「 正岡子規の俳句革新(三)」
https://blog.goo.ne.jp/seisei14/e/b335fca44e92fab339326c17a14a1b79

http://www.s-kawano.net/s-kawano/%E6%AD%A3%E5%B2%A1%E5%AD%90%E8%A6%8F.pdf
明治三十年一月、子規は、編集発行人を柳原極堂(やなぎはらきょくどう)をして、伊予松山で、俳誌「ホトトギス」を発刊させる。そして、これは、二十号まで続くが、その後、東京の高浜虚子が引き継ぎ、昭和三十五年の子規没後、この虚子が子規の継承者となる。その後、文芸雑誌の時代を経て、大正元年から「花鳥諷詠」という俳句理念の下に、客観写生俳句を提唱・推進し、所謂、「ホトトギス」王国を築き上げる。
この「ホトトギス」の雑詠欄から、渡辺水巴(わたなべすいは)・村上鬼城(むらかみきじょう)・原石鼎(はらせきてい)・飯田蛇忽(いいだだこつ)らの俊秀が巣立っていた。さらに、その大正時代に入ると、所謂、四Sといわれる、水原秋桜子(みずはらしゅうおうし)・山口誓子(やまぐちせいし)・阿波野青畝(あわのせいほ)・高野素十(たかのすじゅう)を始め、富安風生(とみやすふうせい)・山口青邨(やまぐちせいそん)という一大「ホトトギス」山脈が築かれていったのである。
昭和三十四年虚子没後は、長男の高浜年尾(たかはまとしお)が引き継ぎ、その後、年尾の次女の稲畑汀子(いなはたていこ)が継承し、平成六年四月で一一六八号に至っている。
もう一つ、子規の活動の拠点は、「日本」新聞であったが、この新聞紙上により、子規は数々の「俳句革新」運動に係わる俳論を発表すると共に。明治二十六に、「子規選句欄」を設け、子規の新派の俳句の興隆に繋げるのであるが、子規の没後は、これを、河東碧梧桐に引き継がれた。
碧梧桐は、当初、虚子と歩を同じくしていたが、後に、進歩的、写実的色彩を強め、虚子と袂を断つこととなる。
この碧梧桐門にも、大須賀乙字(おおすがおつじ)・荻原井泉水(おぎわらせいせんすい)・小沢碧童(おざわへきどう)・中塚一碧楼(なかつかいっぺきろう)などの新進気鋭の俳人を輩出し、これまた、碧門隆盛の一時代を築いた。
これらの碧門俳句は、「新傾向に非ずんば俳句に非ず」と称され、この「新傾向俳句」は一世を風靡するが、後に、この「新傾向俳句」は内部分裂を始め、乙字は伝統尊重と古典復帰を目指し「石楠(しやくなげ)」に拠り、井泉水は無季の自由律俳句の「層雲(そううん)」に走り、四分五裂の状態となり、ここに碧門俳句は、虚子の「ホトトギス」の隆盛に比して衰退転落の運命に堕するのである。
とまれ、子規の「俳句革新」運動は、子規の没後、その二大俊秀の、虚子の俳誌「ホトトギス」と碧梧桐の新聞「日本」の影響下で、強力に推進され、子規の時代の「新派と旧派」との闘いは、圧倒的な差で子規らの新派の新俳句が、旧派の宗匠俳句を駆逐していくのである。
しかし、子規の「俳句革新」運動が、さほどまでに成果を上げ得たのは、子規と子規門の力だけによるのであろうか。これは、決してそうではないのである。
ここで、芭蕉没後(一六九四)三百年にも当たる平成四年(一九九三)に没した、芭蕉俳諧の正統な継承を目指した、加藤楸邨(かとうしゅうそん)の「明治俳句史(上)」(『俳句講座』・明治書院)から、興味ある指摘の要約を見ることにいたしたい。
○江戸は西方の力に圧せられて敗北した舞台である。新しい政治・社会の勢力は西方から来た人々によって形成さられ、江戸の人は社会の中枢にあって勢いを占めることが不可能な状態に置かれた。
○従って、文化の中心であった江戸の旧俳人(注・旧派)たちが、おのずと逸楽遊閑の方向に追いこまれたるのは、避けがたい傾向だったわけである。
○この結果、俳人の生活はおのずと遊閑的・寄生的となって、時代の生動する力からは全く遊離せざるを得なかった。従って、そこに辛うじて認められるのは、過ぎ去った過去の郷愁をよりどころとする江戸趣味の世界であった。生きて動きゆく新しい社会の流れに目を閉じて、すでに昨日のものとなった花の残香をなつかしむに過ぎない無気力が氾濫したのであった。
○また、芭蕉の没後は、その門下たちも点印(注・選句料の点料)を用いるようになり、時代が下るにつれて点も甘くなって、大衆に媚びる輩も増加して、(注・そのような状況が)幕末から明治に至ったのである。
○月並というのは月次とも書いて、毎月いとなむ例会という意味である。(注・この例会での寄せ句を集めたものが、月並集で)、その月並集は遠隔の人の寄せ句まで集めて出されるようになる。それらの句はいずれも入花料が必要とされ、入花料というのは出句の料金で、これが点者の点料や月並集の開板費用に当てられたわけである。こうなると、出句者の側からいえば、芸の問題が中心になるのではなく、次第に高点を競う勢いが馴致され、その結果、高点を取る手引の参考書まで出るようになった。点者がそういう大衆の嗜好を察知して堕落することも、逆に、出句者が点者の好みに迎合してねらいをつけることも、自然の勢いであった。
○子規は当然動かねばならなかった時代の機運に、最もふさわしい人間の在り方で際会したとみるべきで、その革新運動は、子規の功績に帰すべきところ極めて多大であるが、根本的には、時代の要求が子規を促したということも、見のがしてはならぬところである。
○子規のそれ(注・「俳句革新」)は、封建的な時代の庶民の文学から、近代資本主義時代の新しい市民の声の解放という、歴史的役割を負うものと考えられてよいと思うのだが、その第二の波頭(注・「俳句革新」)は、複雑な時代の後進性を負わされていたために、子規において完全な成立を見ることができなかったのである。
○加えるに、子規の在り方と後年の病臥生活という特殊な事情の下に、解放された個は、広い社会とかかわる社会的人間として個となる代りに、狭い「病牀六尺」の中に心境的な定着を示して、多くの課題は子規以後に遺されてきているということができる
○(注・最後に)正岡子規の「日本派」の新しい俳句の運動が進められていた頃、一方では、尾崎紅葉・大野酒竹・角田竹冷らの各々の一団(注・「秋声会」・「筑波会」など)が、旧派とは一線を画して「日本派」と近い動きを示していたことは忘れてはならない。
これらの楸邨の、子規の「俳句革新」運動に関連した背景の分析や周辺の動向の分析は、極めて適切なものがあるが、さらに、これらに、付け加える事項としては、次のようなことが上げられるかと思う。それらは、今までに、色々の角度から側面的に触れられてきたところではあるが、ここで一括まとめをしておきたいと思う。
○即ち、子規らの「俳句革新」運動というのは、西洋的な文学思想を持った学生上がりの、まだ、若干二十五歳という少壮ジヤーナリストともいうべき、職業俳人ではない(アマ)子規をリーダとする、いわば、素人(アマ)集団によって成し遂げられたということである。
○また、当時の旧派の俳句は、江戸末期の俗調の延長線上にあり、それは、まさしく、子規が指摘するように、「俳句は已に盡きたりと思ふなり。よし未だ盡きずとするも明治年間に盡きんこと期して待つべきなり」との、崩壊寸前にあり、その崩壊は修復する程度では持ち堪えることができず、それは、新しい近代の西洋的な文学思想をもっての全面改築をする必要があったということである。
○更には、これらの「俳句革新」運動は、主として、子規をリーダとする、伊予松山出身の地方の面々から成る「日本派」が活躍するのであるが、その他にも、「秋声会」や「筑波会」という、これまた、職業俳人ではなく、趣味で俳句をしている余技的俳句人(アマ)の活躍も大きな役割を果たした。
○因みに、「秋声会」の、角田竹冷は東京株式取引所理事長などの要職を歴任し、伊藤松宇は王子製紙の幹部職員、巌谷小波は児童文学では多大の貢献をした作家でもあり学者でもある。尾崎紅葉は『金色夜叉』などの大作をものにしている明治文壇の大立者である。
○一方、「筑波会」の面々は、これは、主として東大関係者の会であり、大野酒竹は東大の皮膚科の教授、佐々醒星は国文学の権威の文学博士、笹川臨風は美術評論家としても一流のこれまた文学博士、沼波瓊音は東大の俳諧史の教授と、いずれも、日本の近代化を背負っていた超一流人である。
○こういう当時の、最高級の教育を受け、その西洋の思想をもろに受け止め、そして、明治維新以降の日本の近代化に、それぞれが、それぞれに貢献し、それを推進している超知識人達が、こぞって、新派の近代俳句の「俳句革新」運動に、直接と間接とを問わず、携わったのであるから、これは、其角堂とか雪中庵とかの嗣号の下の家元制度のような旧派の宗匠俳句が駆逐せられていったのは、けだし、止むを得なかったということなのであろう。
以上が、楸邨の、子規の「俳句革新」運動に関連した背景の分析や周辺の動向の分析に追加して付記しておきたい事項なのであるが、更に、今となっては、子規の「俳句革新」運動の影に隠れて余り指摘することも少ない幾つかの重要な事項について付記しておくこととする。
その一は、子規が、明治二十八年に「発句(注・俳句)は文学なり、連俳(連句)は文学に非ず」と抹殺したところ連俳(連句)について、子規自身、その四年後の、明治三十八年に、その『俳諧三佳書序』で、「連句に興味を持っている」旨の、それまでの「連俳(連句)非文学論」を撤回するような記載を残しているのである。
○自分は連句という者余り好まねば古俳書を見て連句を読みし事無く又自ら作りし例も甚だ稀である。然るに此等の集(注・『猿蓑』・『続明烏』・『五車反古』)にある連句を読めばいたく興に入り感に堪ふるので、終には、これ程面白い者ならば自分も連 句をやつて見たいという念が起つてくる。
そして、それだけではなく、子規と虚子との両吟すら「ホトトギス」誌上(第二巻第二号)に登場しているのである。その表の六句を掲げておくこととする。
○発句 萩咲くや崩れ初めたる雲の峰 (子規)
脇 かげたる月の出づる川上 (月が引き上げられている 虚子)
第三 うそ寒み里は鎖さぬ家もなし (子規)
四句目 駕籠二人銭かりに来る (虚子)
五句目 洗石の場を流したる夜の雪 (子規)
折端 残りすくなに風呂吹の味噌(虚子)
その二は、子規、虚子とも連なり、夏目漱石門の松根東洋城(まつねとうようじょう)とその俳誌「渋柿」が、芭蕉以来の伝統ある連句の世界を、今に伝えているということである。
○渋柿はその芭蕉に於てなされし如く「連句」を大切にす。之に依り多く俳諧を闡明(注・びんめい)し拡充し高揚す
これは、大正四年に、東洋城がその俳誌「渋柿」を創刊した時の、その目指すべきもの一つとして東洋城が掲げたものである。
そして、東洋城は、その生涯において、歌仙(三十六句形式の連句)百六巻の他、数々の連句作品を残しているとか。
また、東洋城門には、寺田寅日子(寅彦)・野村喜舟(のむらきしゅう)・阿片瓢郎(あがたひょうろう)などがおり、現在に、その連句の伝統を守っている。
次に、東洋城と寅日子との両吟の、その表の六句を掲げておくこととする。
○発句 水団扇鵜飼の絵なる篝かな (東洋城)
脇 旅の話の更けて涼しき (寅日子)
第三 縁柱すがるところに瘤ありて (東洋城)
四句目 半分とけしあと解けぬ謎 (寅日子)
五句目 吸物をあとから出した月の宴 ( 月の定座 東洋城)
折端 庭のすゝきに風渡る頃 (寅日子)
その三は、子規の「俳句革新」運動というのは、虚子と碧梧桐という二人の傑出した弟子により受け継がれ、そして、虚子によって、その近代俳句(新派の俳句)が確立するのであった。そして、碧梧桐の「新傾向俳句」によって、極端なまでに、無季自由律の分野など、現代俳句に見られる多種多様な分野のリーデイングケースのような役割を演じるのであった。
そして、この俳句の前衛的な碧梧桐はともかくとして、新しい伝統俳句を樹立した虚子は、既に、子規の生存中の頃から、「連句の趣味」(「ホトトギス」・明治三二・五)なる一文を発表し、子規の「連俳(注・連句)非文学論」とは一味違った見解を発表しているのである。
また、虚子は、昭和十三年四月に、その後継者の年尾に「誹諧」という雑誌を刊行させ、この「誹諧」には、「俳句・俳文・俳論・連句・俳諧詩」まで多彩な内容となっているとのことである。
ここにいう「俳諧詩」とは、それは、自由詩なのであるが、俳人も、俳句だけではなくもっと自由に創作を試みるべきとする虚子の心情を物語るものであろう。
○ 俳諧詩 麦踏(虚子作)
夕ぐれの 畑中に 麦踏んで ゐる女
もうすぐに 足もとも わからなく なるだろう
夕靄が だんだんと 濃くなりて やはらかく
おしつゝみ かいいだく
その四は、子規の「日本派」(伊予派)と同じく、新派の俳句として「秋声会」・「筑波会」なども、旧派の俳句を一掃するために一つの役割を演じるのであるが、これらの「秋声会」・「筑波会」などの面々においては、子規の「連俳(注・連句)非文学論」にかかわらず、「連句」の復興に力を尽くした人が少なくない。
その筆頭は、「秋声会」の大物、伊藤松宇である。松宇は、明治四十四年六月に俳誌「にひはり」を創刊主宰して、俳諧の史的研究・連句の再認識に尽力する。松宇は実作者というよりは、俳諧の研究・考証・連句の鼓吹などに大きく寄与した。
次に、松宇と根津芦丈(ねずろじょう)との両吟の、その表の六句を掲げておくこととする。この芦丈は、連句完成数三千巻ともいわれ、その芦丈門に、清水瓢左(しみずひょうざ)・野村牛耳(のむらぎゅうじ)・東明雅(ひがしあきまさ)などの多くの連句人が輩出している。
○発句 夜半の冬狸が付けし継句かな (松宇)
脇 衾すっぽり冠る凩 (芦丈)
第三 振って見る徳利の酒を命じて (松宇)
四句目 素彫りの像に会心の笑み (芦丈)
五句目 啄木鳥の月になるまで啄くらむ (月の定座 松宇)
折端 連れし小者の水落し去る (芦丈)
その五は、子規の「日本派」(伊予派)そして、「秋声会」・「筑波会」などの新派の俳句が、芭蕉以来延々と続いていた旧派の宗匠俳諧(連句・俳句)を簡単に駆逐し、その生命を完全に絶ったかというと、それは、そうではなく、今になお、その伝統は受け継がれているものを目にすることができるのである。
しかし、それは、子規そして虚子につながる近代俳句が巨大化し、その巨大化に比して矮小化されるという運命にはあった。
いや、言葉を変えれば、子規そして虚子につながる近代俳句の巨大化は、新しい主宰者という一種の権威ある者を誕生させ、かっての宗匠に代わるべき地位を得させたのである。とすれば、「其角堂」とか「雪中庵」とかの嗣号のもとに、かっての宗匠を中心とした伝統俳句が、かっての栄光を取り戻すことは、もはやあり得ないと思われる。
しかし、こと連句に限っていえば、実は、その近代俳句が避けて通った分野であり、これは、間違いなく、その近代俳句の成果を摂取しながら、再び、脚光を浴びることは、現代の連句界の動向を見て、そう間違っている結論にはならないと予測されるのである。
かかる連句の再興に鑑み、実は、かって、宗匠と呼ばれた方々は、名うての連句人であり、それらに連なる伝統俳諧(連句・発句)に携わっている方々との発掘と、その連携ということは、今後の連句に携わっていく者の課題ともいえるであろう。
かっての、宗匠と呼ばれた、著名な嗣号などを持つ俳諧師の連句を、前句と付句の二句仕立てで、その幾つかを次に掲げることとする。
○発句 水海に昼の月ありほとゝぎす (嗣号「花の本」・聴秋)
脇 子供も載せて早苗つむ舟 (湖月)
○ナウ五 囀にましらぬ鳩の巣について (素朗)
挙句 とけて残らぬ頃の雪垣 (東都三大家・橘田春湖)
○ウ折立 網とりの寒の兎をかきいだき (東都三大家・ 関為山)
二 ぬからす酒の用意してある (壺公)
○ウ十一 幾万の心をそゝる花日和 (嗣号「其角堂」・機一)
折端 素足のなじむ若草の上 (一滴)
○ウ 五 凩のたゆたふ隙を鐘の声 (予雲)
六 船を世帯に夫婦わりなき (東都三大家・鳥越等栽)
さて、この「俳句革新」の原点ということに思いをいたす時、やはり、子規の最晩年の『病牀六尺』の冒頭の書き出しを想起せざるを得ないのである。
○病牀六尺、これが我世界である。しかも此六尺の病牀が余には広過ぎるのである。
正岡子規、その三十五年の生涯は、まさに、それは「病牀六尺」の世界であったろう。そして、その「病牀六尺」は、当時の誰よりも広大無限の世界だったのである。
当時の誰が、子規に匹敵するだけの広大無限の世界を熟知したであろうか。つくづく、人間というのは、自分がその生を保っている、その所を、その世界を、何も目に焼き付けることもなく、何の感慨もなく、ただ、他人ごとのように眺めて、それで、その一生を終わってしまうことであろうか。
子規は、「病牀六尺」の世界にあって、その目に入る一木一草を、そして、生きとして生けるものを、凝縮して、凝縮して、その全ての在りようを克明に自分の「頭・心・五感」の焼き付けていったのである。
まさしく、神というのは、人間に等しく、その恩寵というものを分け与えるものなのだろう。普通人が、八十年、そして、その生涯で見聞きする全てのことを、子規は、その三十五年の生涯で、その「病牀六尺」の世界で全てを見通したのである。
こと、「俳句革新」ということに限っていえば、伊予松山出身の、一書生の子規が、その「病牀六尺」の世界で出会った、非常に限られた書生仲間と、その「病牀六尺」の世界で切磋琢磨し、その切磋琢磨の成果をもって、日本全土に「正岡子規の近代俳句」を押し進め、その「正岡子規の近代俳句」で一時代の全てを覆うてしまったのである。
まさに、それは革命であった。それは、まさしく、江戸から東京への変化と機を一にするものであった。時は、子規を必要とし、しかも、時は、「病牀六尺」の世界での、子規を必要としたのである。その針のような小ささで、そのダイヤモンドのような固さで、そのレザーのような鋭さで、当時の江戸俳諧(古典俳句・旧派)を東京俳句(近代俳句・新派)に変却せしめたのである。
かって、子規は、明治二十九年に、「俳人ヲ戒メルノ書」を、同郷の伊予の、一舟という俳人に書きおくっている。その冒頭の書き出しは次のとおりである。
○俳句ハ人ニ向ツテ威張ルガタメニ作ルモノニ非ズ
これこそ、子規の「俳句革新」の、その原点に位置するものではなかろうか。即ち、「俳句革新」の、その視点は、この「俳句ハ人ニ向ツテ威張ルガタメニ作ルモノニ非ズ」の、このアマチュアリズムこそ、その視点であったのではなかろうか。
そして、子規の、そのアマチュアリズムの視点には、当時の、旧態然とした職業俳人(プロ)は鼻もちならぬものに映じたのであろう。そして、その職業俳人(プロ)の手から、芭蕉以来の燦然と輝く本当の俳句(連句・発句)を取り戻し、そして、それを、純粋に俳句を愛好する、いわば、純粋俳人(アマ)の手に委ねようとしたのであろう。
その「俳人ヲ戒メルノ書」は、次の子規の句で結んでいる。
○ 柿くふて文学論を草しけり
その江戸俳諧(古典俳句・旧派)を東京俳句(近代俳句・新派)に変却せしめた原点とは何か。それは、それこそが、職業俳人(俳諧師・プロ)に対する素人俳人(俳句人・アマ)の挑戦以外の何ものでもない。
即ち、子規の「俳句革新」というのは、「書生(アマ)の、書生(アマ)のための、書生(アマチュア)による」俳句革新運動であったのである。
「子規・漱石・寅彦・東洋城」俳句管見(その十) [子規・漱石・寅彦・東洋城]
その十「明治三十一年(一八九八)・「凩・木枯し」など」
(子規・三十二歳。二月、「歌よみに与ふる書」により「短歌革新運動」始まる。十月、東京で「ホトトギス」発刊(松山の極堂から東京の虚子へと継受される)。)
※凩や芭蕉の緑吹き盡す ID22019 ※制作年31 季節冬 分類天文 季語凩
凩や松葉吹き散る能舞臺 ID22020 制作年31 季節冬 分類天文 季語凩
※から尻に凩あるゝ廣野哉 ID15129※ 制作年28 季節冬 分類天文 季語凩
から尻に凩つよき廣野哉 ID15130 制作年28 季節冬 分類天文 季語凩
凩に尖らぬ頭ぞなかりける ID15131 制作年28 季節冬 分類天文 季語凩
凩に向ふて登る峠かな ID15132 制作年28 季節冬 分類天文 季語凩
凩の馬吹き飛ばす廣野哉 ID15133 制作年28 季節冬 分類天文 季語凩
凩の外は落葉の月夜哉 ID15134 制作年28 季節冬 分類天文 季語凩
凩や犬吠え立つる外が濱 ID15135 制作年28 季節冬 分類天文 季語凩
凩や海へ吹かるゝ人の聲 ID15136 制作年28 季節冬 分類天文 季語凩
凩やがうがうとして瀧落つる ID15137 制作年28 季節冬 分類天文 季語凩
木枯やかちりついたる馬の鞍 ID15138 制作年28 季節冬 分類天文 季語凩
凩や鐘引きすてし道の端 ID15139 制作年28 季節冬 分類天文 季語凩
凩や君がまぼろし吹きちらす ID15140 制作年28 季節冬 分類天文 季語凩
凩や雲吹き落す海のはて ID15141 制作年28 季節冬 分類天文 季語凩
凩や鹿の餌賣れぬ豆腐殼 ID15142 制作年28 季節冬 分類天文 季語凩
凩や十年賣れぬ古佛 ID15143 制作年28 季節冬 分類天文 季語凩
凩や月の光りを吹き散らす ID15144 制作年28 季節冬 分類天文 季語凩
凩や胴の破れし太鼓橋 ID15145 制作年28 季節冬 分類天文 季語凩
凩や鼠の腐る狐罠 ID15146 制作年28 季節冬 分類天文 季語凩
凩や髯いかめしき騎馬の人 ID15147 制作年28 季節冬 分類天文 季語凩
凩や船沈みたるあたりより ID15148 制作年28 季節冬 分類天文 季語凩
凩やものもうつらぬ窓の月 ID15149 制作年28 季節冬 分類天文 季語凩
凩やよろよろ薄よろよろと ID15150 制作年28 季節冬 分類天文 季語凩
凩を空へ吹かせて谷の家 ID15151 制作年28 季節冬 分類天文 季語凩
ひうひうと凩鳴るや庵の空 ID15152 制作年28 季節冬 分類天文 季語凩
古御所や凩更けて笑ひ聲 ID15153 制作年28 季節冬 分類天文 季語凩
(漱石・三十二歳。寅彦に「俳句とはレトリックを煎じ詰めたものだ」を教授する。東洋城、子規庵の句会に出席。「子規宛句稿(二十八~三十一)。)
106 驀地に凩ふくや鳰の湖 (明治二十八年。「子規へ送りたる句稿一」)
114 凩に裸で御はす仁王哉 (同上。「子規へ送りたる句稿二」)
127 凩に鯨潮吹く平戸かな (同上)
133 凩や弦のきれたる弓のそり(同上)
259 凩や滝に当つて引き返す(同上。「子規へ送りたる句稿五」)
304 木枯の今や吹くとも散る葉なし(同上。「子規へ送りたる句稿六」)
309 凩の上に物なき月夜哉(同上)
311 凩や真赤になつて仁王尊(同上)
474 凩に牛怒りたる縄手哉(同上。「子規へ送りたる句稿九」)
479 凩や冠者の墓撲つ落松葉(同上)
533 凩に早鐘つくや増上寺 (明治二十九年。「子規へ送りたる句稿十」)
969 凩や海に夕日を吹き落す(同上。子規へ送りたる句稿二十一」)
980 凩の松はねぢれつ岡の上(同上)
982 策つて凩の中に馬のり入るゝ(同上)
1308 凩や鐘をつくなら踏む張つて(明治三十年。「子規へ送りたる句稿二十七」)
1341 凩の沖へとあるゝ筑紫潟(明治三十一年)
(寅彦・二十一歳。田丸卓郎のすすめで物理学専攻と決意。漱石を中心に俳句結社。)
木枯や故郷の火事を見る夜かな(明治三十一年作)
凩や枯葉するすると馳り出す(同上)
凩や怪しき雲のたゝずまひ(同上)
凩の雨戸をたゝくや夜もすがら(同上)
凩や鉋屑舞ふ普請小屋(同上)
凩の煙突に鳴る夜半哉(同上)
凩や枯葉の走る塔の屋根(同上)
凩や練兵場の砂けむり(同上)
凩の裏の山から鳴て来る(同上)
明け方や凩とぎれとぎれ吹く(同上)
凩の庭の折戸をあほる音(明治三十一~二年作)
木枯の上野の山を鳴て来る(明治三十二年作)
(東洋城・二十一歳。)
木枯に此枝が飛ぶかと思ひけり(明治三十八年作)
木枯や兼平塚を吹き余し(同上。前書「粟津ケ原」)
木枯や二つ越え来し又峠(明治三十九年作)
(参考) 「正岡子規の俳句革新(二)」周辺
https://blog.goo.ne.jp/seisei14/e/ffca6e092d833589740f5b1e0a2bb393

「旅装での子規(二)」(明治二十六年「はてしらずの記(東北旅行)」の頃?)
https://plaza.rakuten.co.jp/orimasa2001/diary/200808060003/
誠に、子規は「俳句は已に盡きたり」というのである。また、「よし未だ盡きずとするも明治年間に盡きんこと期して待つべきなり」と断言するのである。
正に、子規の「俳句革新」の第一声は、この「俳句滅亡論」という、その実感からスタートをきるのである。
そして、その「俳句革新」の第一声は、古色蒼然とした宗匠俳諧への痛罵となって、その矛先を、旧派の宗匠俳諧へと向けるのである。この『獺祭書屋俳話(だつさいしょおくはいわ)』の結びは、「発句作法指南の評」という、その著者、其角堂機一という宗匠に向けられたものであった。
○近頃其角堂機一なる宗匠あり。発句作法指南と云ふ一書を著して世に刊行す。(中略)之を読んで猶不満足を感ずるの箇處多きは勿論の事にて之を詳述するに勝(た)へずといへども一読の際思ひあたりしことのみを挙げて著者の教を乞わはんと欲するなり。
このような書き出しの「発句作法指南の評」は、これは、正に、明治以前のもの(宗匠俳諧・俳諧・発句・月並俳句)に対する、明治維新後の、新しい近代という息吹をもたらさんとする、西洋思想(西洋思想的な新文学観)に基づく近代俳句(俳諧・発句・月並俳句からの脱却)の挑戦でもあった。
そして、この子規の西洋思想的な新文学観とは、概括すると、以下、次のように展開されるのであった。
明治二十七年 「文学は直接に吾人が感覚に訴へて快楽を生ぜしむべき美術の一種」(「日本」・明治二七・七)
明治二十八年 「感情的文学即ち純粋なる文学」(「日本」・明治二七・十二)
明治二十九年 「絵画も美術なり、文学も美術なり、美術は感情に訴ふべくして道理に訴ふべからず」(「日本」・明治二九・八) 明治三十一年 「詩歌に限らず総ての文学が感情を本とする事は古今東西相異あるべく無之」(「日本」・明治三一・二)
当時の子規の周辺には、子規の郷里の伊予松山藩の面々が顔を揃えていた。子規は、明治二十五年に、東京下谷根岸に居を構えるのだが、その大学予備門入学の頃は、伊予松山藩の本郷真砂町の常磐会寄宿舎にいた。その舎監が、内藤鳴雪(ないとうめいせつ)、そして、その寄宿生は、新海非風(にいのみひふう)・五百木飄亭(いおぎひようてい)・竹村黄塔・勝田明庵、そして、従弟の藤野古白等であった。
そして、後に、子規門の二大俊秀の、河東碧梧桐(かわひがしへきごどう)・高浜虚子(たかはまきょし)が加わってくる。これらの面々が、後に、伊予派と呼ばれる面々で、郷党的色彩が強く、固い師弟朋友の絆で結ばれていた。
この伊予派は、別名、「日本派」とも呼ばれるが、これは、子規選俳句欄を擁し、そして、その「俳句革新」のための数々の俳論を発表する、その媒体となった「日本」新聞の名をとって、そう呼ばれるのであった。
この「日本派」の面々には、先程の伊予派の面々の他に、石井露月(いしいろげつ)・佐藤紅緑(さとうこうろく)・寒川鼠骨(さけかわそこつ)・松瀬青々(まつせせいせい)・夏目漱石(なつめそうせき)・坂本四方太(さかもとしほうだ)など錚々たるメンバーが顔を揃えた。
さらに、子規らと同じく旧派の月並俳句の刷新には、新派として、伊藤松宇(いとうしょうう)、そして、この松宇に繋がる「秋声会」の、角田竹冷(つのだちくれい)・巌谷小波(いわやさざなみ)・尾崎紅葉(おざきこうよう)・星野麦人(ほしのばくじん)らの面々も活躍していた。
また、「秋声会」にも関係のあった、大野洒竹(おおのしゃちく)の「筑波会」の面々の、佐々醒星(さつさせいせつ)・笹川臨風(ささがわりんぷう)・沼波瓊音(ぬなみけいおん)などの面々も、新派として旧派の宗匠俳句を排斥するのであった。
このように、子規の「俳句革新」運動というものは、子規と子規の「日本派」(伊予派)の面々が主力であったが、その「俳句革新」運動の周辺には、当時の錚々たるメンバーの「秋声会」や「筑波会」に連なる新派の面々が、旧派の月並俳句・宗匠俳句と鋭く対立していたということは特記しておく必要があるのであろう。
それらの面々の、当時の俳句の幾つかについて記して見よう。
○ 子に鳴いて見せるか雉の高調子 (子規・明治二五年作)
○ 菊は古し人形作る躑躅(つつじ)かな(鳴雪・俳調の変易に感じて)
○ 梅が香に届かぬくまもなき小庭 (碧梧桐・子規改作)
○ 子規逝くや十七日の月明に (虚子・子規追悼句)
○ 葉葡萄に酒成る秋わ契りけり (露月・「碧梧桐来」の前書きあり)
○ 甘酒屋打出の浜に卸しけり (青々・子規激賞の句)
○ 帰ろふと泣かずに笑へ時鳥 (漱石・子規宛の手紙の漱石俳句の初見)
○ 絶壁の一本芒乱れけり (紅緑・処女作)
○ 汽車で行く東海道の月夜かな (鼠骨・子規選)
○ 鶏頭に芋堀り尽す畑かな (四方太・鶏頭の句)
○ 深草や秋に似た夜の麦鶉 (松宇・新派俳句雑誌「俳諧」収録)
○ 帰るさに宵の雨知る十夜哉 (竹冷・代表作)
○ 雨蛙梢に雨を称へけり (小波・代表作)
○ 死なば秋露の干ぬ間ぞおもしろき (紅葉・辞世の句)
○ 妹が門遊行の柳しだれけり (洒竹・「帝国文学」所収)
○ 駿河屋の暖簾古りたり乙鳥 (醒星・代表作)
○ 先ず春の曙染や濃紫 (臨風・代表作)
○ 障子しめて秋の夜となる一間かな (瓊音・代表作)
さて、新派の新俳句を標榜する面々について、その主たるメンバーは以上であるが、これらの新派の面々と、それに対立する旧派の月並俳句の主たる面々との、当時の俳句愛好者の間での人気の度合いは、どうであったのであろうか。
これにらについて、尾形仂氏の興味ある解題(『子規全集第五巻』)の記載がある。
○明治三十一年三月五日、「都新聞」紙上に発表された読者による「俳諧十傑」の投票結果によれば、三万四千四百六十一票を獲得した老鼠堂永機を筆頭に、蕉露庵蕉露・善哉庵孝節・春秋庵幹雄以下、一万八千八百九十二票の桃支庵指直に至るまで、十傑に入選したのはいずれも旧派の宗匠ばかりであった。新派の俳人では角田竹冷が十六位、大野洒竹が二十八位、子規は千十六票で三十七位に止まっている。
○翌三十二年六月に雑誌ら「太陽」が催した「俳諧十二傑」の投票では、老鼠堂永機・正岡子規・三森幹雄・尾崎紅葉・花の本聴秋・角田竹冷・巌谷小波・雪中庵雀志・幸堂得知・内藤鳴雪・桂花園桂花が選ばれ、新派俳人が十二傑の半数を占めるに至っているが、これは両誌の読者層の相違にもとづくものであろう。
この当時、人気投票ナンバーワンであった老鼠堂永機が、晋子(其角)の発句に、脇を付けて巻いた「脇越(わきおこし)」の連句(歌仙)が残されているが、その表(おもて)の六句を次に引用して見よう。
○ 発句 いそのかみしみづ也けり手前橋 晋子(其角)
脇 真菰(まこも)に交る一株の苗 永機
第三 よき人のはなしの答静にて 為山
四句目 筆とるさまの滞なき 壺公
五句目 初月のながめにはづす玉すだれ (月の定座) 春湖
折端 渡るにしては早きあぢむら きく雄
これらの連句を、子規は、明治二十八年の『芭蕉雑談』の「或問」の中で、「発句(注・俳句)は文学なり、連俳(連句)は文学に非ず」と、これを抹殺してしまうのである。 そして、この態度を、子規は終始変えようとはせず、そして、その連句抹殺の思想は、今日まで、延々と、百年余も続いているのである。
子規という革新的な人物は、理論の人とも呼ばれるが、同時に、直観力に優れた情の人でもあった。繰り返すこととなるが、子規の真の狙いは、連句そのものというよりは、宗匠という人種への挑戦にあった。
即ち、言葉を変えていえば、それは、当時の権威の象徴でもある宗匠(プロ・職業俳人)を排斥し、「「書生(アマ・素人)の、書生(アマ・素人)のための、書生(アマ・素人)による」俳句を標榜したのであった。
これらのことは、ずばり、明治二十九年の『俳句問答』の中で、当時の人気投票ナンバーワンであった老鼠堂永機に係わる子規の痛罵となって現れる。
○問 老鼠堂永機翁は俳諧師中の大家と称せられる。左の翁の句は名句なりや否や。且つ翁の俳句の位置は如何。
時鳥恋に寝ぬ夜の若かりし
夕立の戻りの雲や夜の雨
霜月やはじめて松の嵐山
名月やさすがに雲も捨てられず
若楓ぬれ釜かけてうつらせん
○答 老鼠と云ひ、永機と言う人、幾人もありと許り覚えて能く其人を区別せず。故に此句の作者は価値のある人かはた如何なる俳句を詠みしか知らず。若し、こゝに列挙したる五句に就きて見れば盡く句法のしまりたるは多少の熟練を証せりといへども意匠は皆軽くして句に重み無し。若し此種の句のみならには到底二流以下の俳家たるを過ぎず。右五句の中にては夕立、霜月、若楓の句など面白し。名月は俗気多く最も嫌ふべし。
時に、子規、二十九歳で、その前年に、日清戦争に従軍し、その帰途、喀血し、以後、子規は病床の日々の中にあったのだ。その子規が、敢然と、当時の俳壇の大御所に対して攻撃をしかけているのである。
子規が、俳句を作り始めたのは、十七歳の頃、そして、本格的に、その終生の仕事となった「俳句分類」に着手したのが、その二十四歳の頃、そして、新聞社「日本」」に入社し、旧派の月並俳句を攻撃を開始したのが、その二十五歳の頃であった。
そして、その四年後に、まだ、一介の、書生(アマ)の、ジャーナリストの、短歌も俳句も俳論もやるマルチストの(それだけ、俳句の実作では名は売れていない)、その子規が、時の俳壇の人気投票ナンバーワンの老鼠堂永機に対して、「此句の作者は価値のある人かはた如何なる俳句を詠みしか知らず」というのであるから、子規という人物は、丁度、戦国時代の織田信長のような、そんな印象すら与えるのである。
子規が、最も忌み嫌ったものは何か。それは、戦国時代の織田信長と同じように、その時の実体の無いまやかしの「権威」と、その権威に群がる「亡者」のような人種とであったろう。
そして、それこそが、子規にとっては、宗匠俳諧(連句・俳句)の、その「庵号」への挑戦であったのであろう。そして、その根源もまた、松尾芭蕉その人に由来しているのであった。
その芭蕉は、その「権威」の頂点に祭り上げられ、そして、その芭蕉十哲の高弟達の「嗣号」が、延々と、子規の時代まで続いていたのである。
中でも、芭蕉十哲の双璧である宝井其角と服部嵐雪の「嗣号」は、甚だ名誉のあるものであったのだろう。其角のそれは「其角堂」であり、嵐雪のそれは「雪中庵」である。
この「其角堂」が、当時の人気投票ナンバーワンであった(老鼠堂)永機から機一に継がれた時の嗣号代が、何と、当時のお金で三百円であったとかいう。
子規が、明治二十五年の『獺祭書屋俳話(だつさいしょおくはいわ)』の結びの「発句作法指南の評」で、攻撃したその相手こそ、この其角堂機一についてであつた。
そして、明治二十九年に、其角堂機一の親玉の老鼠堂永機を槍玉にあげるのである。
この老鼠堂永機は、本名は穂積永機(ほづみえいき)といい、その父が、其角堂六世鼠肝で、その父を継ぎ其角堂七世となり、明治二十年に、門人・田辺機一(たなべきいち)に其角堂を譲ったという。その後、老鼠堂または阿心庵との号を用い、全国各地を行脚し、門弟一千人を数えたという。とにもかくにも、学識・人望とも抜群で、当時の大御所的な存在であったのだ。
この大御所に対して、「こゝに列挙したる五句に就きて見れば盡く句法のしまりたるは多少の熟練を証せりといへども意匠は皆軽くして句に重み無し」と、その作品の酷評までするのだから、これは、正に、織田信長的な行動というのが一番似つかわしいのかも知れない。
(子規・三十二歳。二月、「歌よみに与ふる書」により「短歌革新運動」始まる。十月、東京で「ホトトギス」発刊(松山の極堂から東京の虚子へと継受される)。)
※凩や芭蕉の緑吹き盡す ID22019 ※制作年31 季節冬 分類天文 季語凩
凩や松葉吹き散る能舞臺 ID22020 制作年31 季節冬 分類天文 季語凩
※から尻に凩あるゝ廣野哉 ID15129※ 制作年28 季節冬 分類天文 季語凩
から尻に凩つよき廣野哉 ID15130 制作年28 季節冬 分類天文 季語凩
凩に尖らぬ頭ぞなかりける ID15131 制作年28 季節冬 分類天文 季語凩
凩に向ふて登る峠かな ID15132 制作年28 季節冬 分類天文 季語凩
凩の馬吹き飛ばす廣野哉 ID15133 制作年28 季節冬 分類天文 季語凩
凩の外は落葉の月夜哉 ID15134 制作年28 季節冬 分類天文 季語凩
凩や犬吠え立つる外が濱 ID15135 制作年28 季節冬 分類天文 季語凩
凩や海へ吹かるゝ人の聲 ID15136 制作年28 季節冬 分類天文 季語凩
凩やがうがうとして瀧落つる ID15137 制作年28 季節冬 分類天文 季語凩
木枯やかちりついたる馬の鞍 ID15138 制作年28 季節冬 分類天文 季語凩
凩や鐘引きすてし道の端 ID15139 制作年28 季節冬 分類天文 季語凩
凩や君がまぼろし吹きちらす ID15140 制作年28 季節冬 分類天文 季語凩
凩や雲吹き落す海のはて ID15141 制作年28 季節冬 分類天文 季語凩
凩や鹿の餌賣れぬ豆腐殼 ID15142 制作年28 季節冬 分類天文 季語凩
凩や十年賣れぬ古佛 ID15143 制作年28 季節冬 分類天文 季語凩
凩や月の光りを吹き散らす ID15144 制作年28 季節冬 分類天文 季語凩
凩や胴の破れし太鼓橋 ID15145 制作年28 季節冬 分類天文 季語凩
凩や鼠の腐る狐罠 ID15146 制作年28 季節冬 分類天文 季語凩
凩や髯いかめしき騎馬の人 ID15147 制作年28 季節冬 分類天文 季語凩
凩や船沈みたるあたりより ID15148 制作年28 季節冬 分類天文 季語凩
凩やものもうつらぬ窓の月 ID15149 制作年28 季節冬 分類天文 季語凩
凩やよろよろ薄よろよろと ID15150 制作年28 季節冬 分類天文 季語凩
凩を空へ吹かせて谷の家 ID15151 制作年28 季節冬 分類天文 季語凩
ひうひうと凩鳴るや庵の空 ID15152 制作年28 季節冬 分類天文 季語凩
古御所や凩更けて笑ひ聲 ID15153 制作年28 季節冬 分類天文 季語凩
(漱石・三十二歳。寅彦に「俳句とはレトリックを煎じ詰めたものだ」を教授する。東洋城、子規庵の句会に出席。「子規宛句稿(二十八~三十一)。)
106 驀地に凩ふくや鳰の湖 (明治二十八年。「子規へ送りたる句稿一」)
114 凩に裸で御はす仁王哉 (同上。「子規へ送りたる句稿二」)
127 凩に鯨潮吹く平戸かな (同上)
133 凩や弦のきれたる弓のそり(同上)
259 凩や滝に当つて引き返す(同上。「子規へ送りたる句稿五」)
304 木枯の今や吹くとも散る葉なし(同上。「子規へ送りたる句稿六」)
309 凩の上に物なき月夜哉(同上)
311 凩や真赤になつて仁王尊(同上)
474 凩に牛怒りたる縄手哉(同上。「子規へ送りたる句稿九」)
479 凩や冠者の墓撲つ落松葉(同上)
533 凩に早鐘つくや増上寺 (明治二十九年。「子規へ送りたる句稿十」)
969 凩や海に夕日を吹き落す(同上。子規へ送りたる句稿二十一」)
980 凩の松はねぢれつ岡の上(同上)
982 策つて凩の中に馬のり入るゝ(同上)
1308 凩や鐘をつくなら踏む張つて(明治三十年。「子規へ送りたる句稿二十七」)
1341 凩の沖へとあるゝ筑紫潟(明治三十一年)
(寅彦・二十一歳。田丸卓郎のすすめで物理学専攻と決意。漱石を中心に俳句結社。)
木枯や故郷の火事を見る夜かな(明治三十一年作)
凩や枯葉するすると馳り出す(同上)
凩や怪しき雲のたゝずまひ(同上)
凩の雨戸をたゝくや夜もすがら(同上)
凩や鉋屑舞ふ普請小屋(同上)
凩の煙突に鳴る夜半哉(同上)
凩や枯葉の走る塔の屋根(同上)
凩や練兵場の砂けむり(同上)
凩の裏の山から鳴て来る(同上)
明け方や凩とぎれとぎれ吹く(同上)
凩の庭の折戸をあほる音(明治三十一~二年作)
木枯の上野の山を鳴て来る(明治三十二年作)
(東洋城・二十一歳。)
木枯に此枝が飛ぶかと思ひけり(明治三十八年作)
木枯や兼平塚を吹き余し(同上。前書「粟津ケ原」)
木枯や二つ越え来し又峠(明治三十九年作)
(参考) 「正岡子規の俳句革新(二)」周辺
https://blog.goo.ne.jp/seisei14/e/ffca6e092d833589740f5b1e0a2bb393

「旅装での子規(二)」(明治二十六年「はてしらずの記(東北旅行)」の頃?)
https://plaza.rakuten.co.jp/orimasa2001/diary/200808060003/
誠に、子規は「俳句は已に盡きたり」というのである。また、「よし未だ盡きずとするも明治年間に盡きんこと期して待つべきなり」と断言するのである。
正に、子規の「俳句革新」の第一声は、この「俳句滅亡論」という、その実感からスタートをきるのである。
そして、その「俳句革新」の第一声は、古色蒼然とした宗匠俳諧への痛罵となって、その矛先を、旧派の宗匠俳諧へと向けるのである。この『獺祭書屋俳話(だつさいしょおくはいわ)』の結びは、「発句作法指南の評」という、その著者、其角堂機一という宗匠に向けられたものであった。
○近頃其角堂機一なる宗匠あり。発句作法指南と云ふ一書を著して世に刊行す。(中略)之を読んで猶不満足を感ずるの箇處多きは勿論の事にて之を詳述するに勝(た)へずといへども一読の際思ひあたりしことのみを挙げて著者の教を乞わはんと欲するなり。
このような書き出しの「発句作法指南の評」は、これは、正に、明治以前のもの(宗匠俳諧・俳諧・発句・月並俳句)に対する、明治維新後の、新しい近代という息吹をもたらさんとする、西洋思想(西洋思想的な新文学観)に基づく近代俳句(俳諧・発句・月並俳句からの脱却)の挑戦でもあった。
そして、この子規の西洋思想的な新文学観とは、概括すると、以下、次のように展開されるのであった。
明治二十七年 「文学は直接に吾人が感覚に訴へて快楽を生ぜしむべき美術の一種」(「日本」・明治二七・七)
明治二十八年 「感情的文学即ち純粋なる文学」(「日本」・明治二七・十二)
明治二十九年 「絵画も美術なり、文学も美術なり、美術は感情に訴ふべくして道理に訴ふべからず」(「日本」・明治二九・八) 明治三十一年 「詩歌に限らず総ての文学が感情を本とする事は古今東西相異あるべく無之」(「日本」・明治三一・二)
当時の子規の周辺には、子規の郷里の伊予松山藩の面々が顔を揃えていた。子規は、明治二十五年に、東京下谷根岸に居を構えるのだが、その大学予備門入学の頃は、伊予松山藩の本郷真砂町の常磐会寄宿舎にいた。その舎監が、内藤鳴雪(ないとうめいせつ)、そして、その寄宿生は、新海非風(にいのみひふう)・五百木飄亭(いおぎひようてい)・竹村黄塔・勝田明庵、そして、従弟の藤野古白等であった。
そして、後に、子規門の二大俊秀の、河東碧梧桐(かわひがしへきごどう)・高浜虚子(たかはまきょし)が加わってくる。これらの面々が、後に、伊予派と呼ばれる面々で、郷党的色彩が強く、固い師弟朋友の絆で結ばれていた。
この伊予派は、別名、「日本派」とも呼ばれるが、これは、子規選俳句欄を擁し、そして、その「俳句革新」のための数々の俳論を発表する、その媒体となった「日本」新聞の名をとって、そう呼ばれるのであった。
この「日本派」の面々には、先程の伊予派の面々の他に、石井露月(いしいろげつ)・佐藤紅緑(さとうこうろく)・寒川鼠骨(さけかわそこつ)・松瀬青々(まつせせいせい)・夏目漱石(なつめそうせき)・坂本四方太(さかもとしほうだ)など錚々たるメンバーが顔を揃えた。
さらに、子規らと同じく旧派の月並俳句の刷新には、新派として、伊藤松宇(いとうしょうう)、そして、この松宇に繋がる「秋声会」の、角田竹冷(つのだちくれい)・巌谷小波(いわやさざなみ)・尾崎紅葉(おざきこうよう)・星野麦人(ほしのばくじん)らの面々も活躍していた。
また、「秋声会」にも関係のあった、大野洒竹(おおのしゃちく)の「筑波会」の面々の、佐々醒星(さつさせいせつ)・笹川臨風(ささがわりんぷう)・沼波瓊音(ぬなみけいおん)などの面々も、新派として旧派の宗匠俳句を排斥するのであった。
このように、子規の「俳句革新」運動というものは、子規と子規の「日本派」(伊予派)の面々が主力であったが、その「俳句革新」運動の周辺には、当時の錚々たるメンバーの「秋声会」や「筑波会」に連なる新派の面々が、旧派の月並俳句・宗匠俳句と鋭く対立していたということは特記しておく必要があるのであろう。
それらの面々の、当時の俳句の幾つかについて記して見よう。
○ 子に鳴いて見せるか雉の高調子 (子規・明治二五年作)
○ 菊は古し人形作る躑躅(つつじ)かな(鳴雪・俳調の変易に感じて)
○ 梅が香に届かぬくまもなき小庭 (碧梧桐・子規改作)
○ 子規逝くや十七日の月明に (虚子・子規追悼句)
○ 葉葡萄に酒成る秋わ契りけり (露月・「碧梧桐来」の前書きあり)
○ 甘酒屋打出の浜に卸しけり (青々・子規激賞の句)
○ 帰ろふと泣かずに笑へ時鳥 (漱石・子規宛の手紙の漱石俳句の初見)
○ 絶壁の一本芒乱れけり (紅緑・処女作)
○ 汽車で行く東海道の月夜かな (鼠骨・子規選)
○ 鶏頭に芋堀り尽す畑かな (四方太・鶏頭の句)
○ 深草や秋に似た夜の麦鶉 (松宇・新派俳句雑誌「俳諧」収録)
○ 帰るさに宵の雨知る十夜哉 (竹冷・代表作)
○ 雨蛙梢に雨を称へけり (小波・代表作)
○ 死なば秋露の干ぬ間ぞおもしろき (紅葉・辞世の句)
○ 妹が門遊行の柳しだれけり (洒竹・「帝国文学」所収)
○ 駿河屋の暖簾古りたり乙鳥 (醒星・代表作)
○ 先ず春の曙染や濃紫 (臨風・代表作)
○ 障子しめて秋の夜となる一間かな (瓊音・代表作)
さて、新派の新俳句を標榜する面々について、その主たるメンバーは以上であるが、これらの新派の面々と、それに対立する旧派の月並俳句の主たる面々との、当時の俳句愛好者の間での人気の度合いは、どうであったのであろうか。
これにらについて、尾形仂氏の興味ある解題(『子規全集第五巻』)の記載がある。
○明治三十一年三月五日、「都新聞」紙上に発表された読者による「俳諧十傑」の投票結果によれば、三万四千四百六十一票を獲得した老鼠堂永機を筆頭に、蕉露庵蕉露・善哉庵孝節・春秋庵幹雄以下、一万八千八百九十二票の桃支庵指直に至るまで、十傑に入選したのはいずれも旧派の宗匠ばかりであった。新派の俳人では角田竹冷が十六位、大野洒竹が二十八位、子規は千十六票で三十七位に止まっている。
○翌三十二年六月に雑誌ら「太陽」が催した「俳諧十二傑」の投票では、老鼠堂永機・正岡子規・三森幹雄・尾崎紅葉・花の本聴秋・角田竹冷・巌谷小波・雪中庵雀志・幸堂得知・内藤鳴雪・桂花園桂花が選ばれ、新派俳人が十二傑の半数を占めるに至っているが、これは両誌の読者層の相違にもとづくものであろう。
この当時、人気投票ナンバーワンであった老鼠堂永機が、晋子(其角)の発句に、脇を付けて巻いた「脇越(わきおこし)」の連句(歌仙)が残されているが、その表(おもて)の六句を次に引用して見よう。
○ 発句 いそのかみしみづ也けり手前橋 晋子(其角)
脇 真菰(まこも)に交る一株の苗 永機
第三 よき人のはなしの答静にて 為山
四句目 筆とるさまの滞なき 壺公
五句目 初月のながめにはづす玉すだれ (月の定座) 春湖
折端 渡るにしては早きあぢむら きく雄
これらの連句を、子規は、明治二十八年の『芭蕉雑談』の「或問」の中で、「発句(注・俳句)は文学なり、連俳(連句)は文学に非ず」と、これを抹殺してしまうのである。 そして、この態度を、子規は終始変えようとはせず、そして、その連句抹殺の思想は、今日まで、延々と、百年余も続いているのである。
子規という革新的な人物は、理論の人とも呼ばれるが、同時に、直観力に優れた情の人でもあった。繰り返すこととなるが、子規の真の狙いは、連句そのものというよりは、宗匠という人種への挑戦にあった。
即ち、言葉を変えていえば、それは、当時の権威の象徴でもある宗匠(プロ・職業俳人)を排斥し、「「書生(アマ・素人)の、書生(アマ・素人)のための、書生(アマ・素人)による」俳句を標榜したのであった。
これらのことは、ずばり、明治二十九年の『俳句問答』の中で、当時の人気投票ナンバーワンであった老鼠堂永機に係わる子規の痛罵となって現れる。
○問 老鼠堂永機翁は俳諧師中の大家と称せられる。左の翁の句は名句なりや否や。且つ翁の俳句の位置は如何。
時鳥恋に寝ぬ夜の若かりし
夕立の戻りの雲や夜の雨
霜月やはじめて松の嵐山
名月やさすがに雲も捨てられず
若楓ぬれ釜かけてうつらせん
○答 老鼠と云ひ、永機と言う人、幾人もありと許り覚えて能く其人を区別せず。故に此句の作者は価値のある人かはた如何なる俳句を詠みしか知らず。若し、こゝに列挙したる五句に就きて見れば盡く句法のしまりたるは多少の熟練を証せりといへども意匠は皆軽くして句に重み無し。若し此種の句のみならには到底二流以下の俳家たるを過ぎず。右五句の中にては夕立、霜月、若楓の句など面白し。名月は俗気多く最も嫌ふべし。
時に、子規、二十九歳で、その前年に、日清戦争に従軍し、その帰途、喀血し、以後、子規は病床の日々の中にあったのだ。その子規が、敢然と、当時の俳壇の大御所に対して攻撃をしかけているのである。
子規が、俳句を作り始めたのは、十七歳の頃、そして、本格的に、その終生の仕事となった「俳句分類」に着手したのが、その二十四歳の頃、そして、新聞社「日本」」に入社し、旧派の月並俳句を攻撃を開始したのが、その二十五歳の頃であった。
そして、その四年後に、まだ、一介の、書生(アマ)の、ジャーナリストの、短歌も俳句も俳論もやるマルチストの(それだけ、俳句の実作では名は売れていない)、その子規が、時の俳壇の人気投票ナンバーワンの老鼠堂永機に対して、「此句の作者は価値のある人かはた如何なる俳句を詠みしか知らず」というのであるから、子規という人物は、丁度、戦国時代の織田信長のような、そんな印象すら与えるのである。
子規が、最も忌み嫌ったものは何か。それは、戦国時代の織田信長と同じように、その時の実体の無いまやかしの「権威」と、その権威に群がる「亡者」のような人種とであったろう。
そして、それこそが、子規にとっては、宗匠俳諧(連句・俳句)の、その「庵号」への挑戦であったのであろう。そして、その根源もまた、松尾芭蕉その人に由来しているのであった。
その芭蕉は、その「権威」の頂点に祭り上げられ、そして、その芭蕉十哲の高弟達の「嗣号」が、延々と、子規の時代まで続いていたのである。
中でも、芭蕉十哲の双璧である宝井其角と服部嵐雪の「嗣号」は、甚だ名誉のあるものであったのだろう。其角のそれは「其角堂」であり、嵐雪のそれは「雪中庵」である。
この「其角堂」が、当時の人気投票ナンバーワンであった(老鼠堂)永機から機一に継がれた時の嗣号代が、何と、当時のお金で三百円であったとかいう。
子規が、明治二十五年の『獺祭書屋俳話(だつさいしょおくはいわ)』の結びの「発句作法指南の評」で、攻撃したその相手こそ、この其角堂機一についてであつた。
そして、明治二十九年に、其角堂機一の親玉の老鼠堂永機を槍玉にあげるのである。
この老鼠堂永機は、本名は穂積永機(ほづみえいき)といい、その父が、其角堂六世鼠肝で、その父を継ぎ其角堂七世となり、明治二十年に、門人・田辺機一(たなべきいち)に其角堂を譲ったという。その後、老鼠堂または阿心庵との号を用い、全国各地を行脚し、門弟一千人を数えたという。とにもかくにも、学識・人望とも抜群で、当時の大御所的な存在であったのだ。
この大御所に対して、「こゝに列挙したる五句に就きて見れば盡く句法のしまりたるは多少の熟練を証せりといへども意匠は皆軽くして句に重み無し」と、その作品の酷評までするのだから、これは、正に、織田信長的な行動というのが一番似つかわしいのかも知れない。
「子規・漱石・寅彦・東洋城」俳句管見(その九) [子規・漱石・寅彦・東洋城]
その九「明治三十年(一八九七)・「旅・枯野」など」
(子規・三十一歳。正月、松山で「ホトトギス」創刊(柳原極堂主宰)。十二月、子規庵で「第一回蕪村忌」を開く。 )
馬士につれ車夫につれ旅の日ぞ長き ID19176 制作年30 季節春 分類時候 季語日永
街道の旅人多き霞かな ID19219 制作年30 季節春 分類天文 季語霞
旅人の焼野に迷ひとげを踏む ID19245 制作年30 季節春 分類地理 季語焼野
旅人のついでに参る彼岸哉 ID19257 制作年30 季節春 分類人事 季語彼岸
人の子の凧あげて居る我は旅 ID19307 制作年30 季節春 分類人事 季語凧
旅人の知らで過ぎ行く清水哉 ID19606 制作年30 季節夏 分類地理 季語清水
京近く旅費の尽きたる袷哉 ID19637 制作年30 季節夏 分類人事 季語袷
閑古鳥かなどゝ思へば旅淋し ID19753 制作年30 季節夏 分類動物 季語閑古鳥
朝寒や木曾に脚絆の旅心 ID19896 制作年30 季節秋 分類時候 季語朝寒
朝寒や脚絆に木曾の旅心 ID19897 制作年30 季節秋 分類時候 季語朝寒
旅籠屋の淨手場遠き夜寒哉 ID19919 制作年30 季節秋 分類時候 季語夜寒
更科や旅人見ゆる十日月 ID19980 制作年30 季節秋 分類天文 季語月
雨晴れて旅僧おこす月見哉 ID20120 制作年30 季節秋 分類人事 季語月見
こほろぎに宿かる蝶の旅寐哉 ID20156 制作年30 季節秋 分類動物 季語蟋蟀
こほろぎに宿かる旅の胡蝶哉 ID20158 制作年30 季節秋 分類動物 季語蟋蟀
朝飯に木犀匂ふ旅籠哉 ID20191 制作年30 季節秋 分類植物 季語木犀
山葛の風に動きて旅淋し ID20205 制作年30 季節秋 分類植物 季語葛
柿くふて腹痛み出す旅籠哉 ID20210 制作年30 季節秋 分類植物 季語柿
旅人の荷にかけし粟の一穗哉 ID20282 制作年30 季節秋 分類植物 季語粟
初旅をなぐさめ顔の野菊哉 ID20332 制作年30 季節秋 分類植物 季語野菊
旅二人話盡きたる枯野哉 ID20502 制作年30 季節冬 分類天文 季語枯野
旅二人話盡きぬる枯野哉 ID20503 制作年30 季節冬 分類天文 季語枯野
旅二人話なくて越す枯野哉 ID20504 制作年30 季節冬 分類天文 季語枯野
我は京へ神は出雲へ道二つ ID20511 制作年30 季節冬 分類人事 季語神の旅
鯨突に通り合せし旅路哉 ID20633 制作年30 季節冬 分類動物 季語鯨
旅にして水鳥多き池を見つ ID20647 制作年30 季節冬 分類動物 季語水鳥
獻上や五十三次鷹の旅 ID20660 制作年30 季節冬 分類動物 季語鷹
吹きおろす木葉の中を旅の人 ID20703 制作年30 季節冬 分類植物 季語落葉
(漱石・三十一歳。「子規宛句稿(二十二~二十七)。)
1003 汽車を遂(とひ)て煙這行(はひゆく)枯野哉(明治三十年「子規へ送りたる句稿二十一」)
1007 かたまつて野武士落行(おちゆく) 枯野哉(明治三十年「子規へ送りたる句稿二十一」)
1008 星飛ぶや枯野に動く椎の影(同上。前書「魏叔子(ぎしゅくし)大鉄推伝一句」)
1009 島一つ吹き返さるゝ枯野かな(同上)
(寅彦・二十歳。七月、阪井夏子(十五歳)と結婚。夏目漱石を訪ね俳句の話を聞く。)
枯野行けば道連(づれ)は影法師かな(明治三十一年作)
山あれて灰の降りたる枯野かな(明治三十一年~二年作)
美しき女に逢ひし枯野かな(大正六年作)
(東洋城・二十歳。松山中学在学中に、熊本五高教授に句を送って添削して貰ふようになり、上京後根岸の子規庵へ通ひ初めた。一高では、潮音、三子、狐雁が仲間であり、教師には五城がゐた。子規庵のほか、ホトトギス例会や碧悟桐庵会への出席も欠かさなかった。俳号は、一声、造酒、造酒充、二葉、みどりとも号した。)
藁しべに蒟蒻さげて枯野かな(明治三十七年作)
鷲の居る石に日当る枯野かな(明治四十一年作)
電線に魂入りし枯野かな(同上)
かゝる里に生れて死ぬる枯野人(同上)
虎の子に鶯飼へり枯野茶屋(同上)
つひそこの火山十里や枯野原(同上)
世の終を入日に見せし枯野かな(同上)
(参考) 「正岡子規の俳句革新(一)」周辺
https://blog.goo.ne.jp/seisei14/e/e0b36fc7362cdd8f080c01a196827075

「旅装での子規(一)」(明治二十六年「はてしらずの記(東北旅行)」の頃?)
https://tenki.jp/suppl/emi_iwaki/2017/06/12/23271.html
正岡子規の「俳句革新」 (抜粋)
目次
⑴ 「俳句革新」の原点 (アマチュアリズムの視点)
⑵ 芭蕉の実像と虚像 (『芭蕉雑談』の意味するもの)
⑶ 子規の俳句観(『俳諧大要』その一)
⑷ 子規の写生論 (『俳諧大要』その二)
⑸ 子規の俳句修学論(『俳諧大要』その三)
⑹ 子規の連句非文学論 (『俳諧大要』その四)
⑺ 蕪村再発見 (『俳人蕪村』の意味するもの)
⑻ 子規の実像と虚像 (「子規俳論」の総括的考察)
(参考文献)
① 『子規全集第四巻(俳論俳話)』(浅原勝解題)・講談社(昭和 五〇)
② 『子規全集第五巻(俳論俳話)』(尾形仂解題)・講談社(昭和五〇)
③ 『正岡子規集(日本近代文学体系)(松井利彦校注)・角川書店(昭和四七)
④ 『正岡子規』(松井利彦著)・桜楓社(昭和五四)
⑤ 『俳句・短歌(近代文学鑑賞講座)』(山本健吉編)・角川書店(昭和三五)
⑥ 『俳句講座七(現代俳句史)』(加藤楸邨他著)・明治書院(昭和三四)
⑦ 『俳句講座八(現代作家論)』(山口誓子他著)・明治書院(昭和三三)
⑧ 『子規と漱石と私』(高浜虚子著)・永田書房(昭和五八)
⑨ 『俳句で読む正岡子規』(山下一海著)・永田書房(平成四)
⑩ 『正岡子規』(粟津則雄著)・講談社(平成七)
☆ その他「本文」中に記載
⑴ 「俳句革新」の原点 (アマチュアリズムの視点)
慶応四年(一八六八)七月、江戸は東京に改称され、その年の九月、年号が明治に改元された。明治維新は、日本のあらゆる面において一大変革をもたらした。
その一大変革とは、日本文学史上、古典文学から近代文学への衣替えでもあった。それは、いわば、それまでの和服という衣を脱ぎ棄てて、新しい洋服という衣で身を包むという革新的なことを意味した。
即ち、これを芭蕉の樹立した俳諧(連句・発句)という世界でいえば、それは、芭蕉以来、営々と続いていたその俳諧(連句・発句)という和服は、明治二十年代に入り、正岡子規(一八六七~一九〇二)によって、近代の「俳句」という新しい洋服に生まれ変わってしまうのである。
これが、子規の「俳句革新」であり、これが「月並俳句(つきなみはいく)から近代俳句」への移行でもあった。
この子規の「俳句革新」とは何だったのであろうか。
子規の「俳句革新」というのは、「書生(アマ)の、書生(アマ)のための、書生(アマチュア)による」俳句革新運動であった。 子規が批判の対象とした、月並(月次)俳句とは、当時の俳諧の宗匠達が開く毎月の例会を意味したが、子規は、それらの月並俳句を「平凡・陳腐・卑俗」として攻撃したのである。
そして、子規の月並俳句(旧派)の批判と子規らが目指す近代俳句(新派)との違いは、子規は、その『俳句問答』(明治二十九年五月から九月まで「日本」新聞に連載され、後に刊行本となる)において、要約すれば以下のとおりに主張するのである。
○問 新俳句と月並俳句とは句作に差異あるものと考へられる。果して差異あらば新俳句は如何なる点を主眼とし月並句は如何なる点を主眼として句作するものなりや
○答 第一は、我(注・新俳句)は直接に感情に訴へんと欲し、彼(注・月並俳句)は往々智識(注・知識)に訴へんと欲す。
○第二は、我(注・新俳句)は意匠の陳腐なるを嫌へども、彼(注・月並俳句)は意匠の陳腐を嫌ふこと我より少なし、寧ろ彼は陳腐を好み新奇を嫌ふ傾向あり。
○第三は、我(注・新俳句)は言語の懈弛(注・たるみ)を嫌ひ彼(注・月並俳句)は言語の懈弛(注・たるみ)を嫌ふこと我より少なし、寧ろ彼は懈弛(注・たるみ)を好み緊密を嫌ふ傾向あり。
○第四は、我(注・新俳句)は音調の調和する限りに於て雅語俗語漢語洋語を問はず、彼(注・月並俳句)は洋語を排斥し漢語は自己が用ゐなれたる狭き範囲を出づべからずとし雅語も多くは用ゐず。
○第五は、我(注・」新俳句)に俳諧の系統無く又流派無し、彼(注・月並俳句)は俳諧の系統と流派とを有し且つ之があるが為に特殊の光栄ありと自信せるが如し、従って其派の開祖及び其伝統を受けたる人には特別の尊敬を表し且つ其人等の著作を無比の価値あるものとす。我(注・新俳句)はある俳人を尊敬することあれどもそは其著作の佳なるが為なり。されども尊敬を表する俳人の著作といへども佳なる者と佳ならざる者とあり。正当に言へば我(注・新俳句)は其人を尊敬せずして其著作を尊敬するなり。故に我(注・新俳句)は多くの反対せる流派に於て俳句を認め又悪句を認む。
この第一から第五までの子規の主張の中で、子規が最も強調したのは、この第五であった。即ち、子規が排斥して止まなかったものは、それは、日本という土地に平然と土俗化し風化した垢まみれの宗匠達が牛耳っいる、その古色蒼然とした宗匠俳諧への痛罵であった。
それは、作品そのものというよりは、宗匠という人種への挑戦であった。即ち、言葉を変えていえば、それは、当時の権威の象徴でもある宗匠(プロ・職業俳人)を排斥し、「「書生(アマ・素人)の、書生(アマ・素人)のための、書生(アマ・素人)による」俳句を標榜したのであった。
正岡子規の生涯というのは、実に三十五年という短いものであった。そして、喀血して子規(「卯の花をめがけてきたか時鳥」・「卯の花の散るまで鳴くか子規」より子規の由来があるとか)と号したのが、明治二十二年、子規十七歳の時、そして、病床の人となり、文字とおり『病牀六尺』の境遇に置かれたのが、明治二十八年、その二十八歳の時であった。
その永く病床にあったその短い生涯にあって、子規は、「俳句革新」と「短歌革新」において、超人的な足跡を残したのである。 その「俳句革新」は、明治二十五年(二十五歳の時)の『獺祭書屋俳話(だつさいしょおくはいわ)』において口火が切られ、その「短歌革新」は、明治三十一年(三十一歳の時)の『歌よみに与ふる書』においてであった。
この「俳句革新」の第一声の『獺祭書屋俳話(だつさいしょおくはいわ)』は、明治二十五年六月から十月にかけて「日本」新聞に連載されたものであった。
そして、この『獺祭書屋俳話(だつさいしょおくはいわ)』は、その「俳句分類」の子規の作業を通しながら会得された古俳諧の膨大な情報集積を縦横に駆使しながら、随筆的に表したもので、当初から系統だった俳論という体裁ではなかった。
後に、単行本として出版されるに及び、それは、「俳諧史」・「俳諧論」・「俳人俳句」・「俳書批評」という分野で再編集されるのであった。
子規は、この俳話において、「俳諧」・「発句」という言葉のほかに、さりげなく「俳句」という言葉も用い、現在の「俳句」という分野を、「俳諧」・「発句」という分野から、全く、単独のものとして独立させるに至るのである。
即ち、その俳話は、「俳諧という名称」・「連歌と俳諧」・「延宝天和貞享の俳風」・「足利時代より元禄に至る発句」・「俳書」として、次に、「字余りの俳句」という項目が来て、この後に、この俳話において、最も注目すべき「俳句の前途」という俳論が続くのである。
そして、その前提には、「連歌と俳諧」という項目で、次のような、「俳諧」・「発句」という分野から「俳句」という分野に切り替えようとする、子規の主張の兆しが見られるのである。
○芭蕉は発句のみならず俳諧連歌(注・連句)にも一様に力を尽し其門弟の如きも猶其遺訓を守りしが後世に至りては単に十七字の発句を重んじ俳諧連歌(注・連句)は僅に其付属物として存ず(注・す)るの傾向あるが如し。
そして、この『獺祭書屋俳話(だつさいしょおくはいわ)』において、最も注目すべき「俳句滅亡論」が、その「俳句の前途」において展開されるのである。それを要約すると以下のとおりとなる。
○日本の和歌俳句の如きは一首の字音僅に二三十に過ぎざれば之を錯列法(バーミュテーシヨン)に由て算するも其数に限りあるを知るべきなり。語を換へて之をいはゞ和歌(重に短歌をいふ)俳句は早晩其限りに達して最早此上に一首の新しきものだに作り得べからさ(注・ざ)るに至るべしと。
○試みに見よ古往今来吟詠せし所の幾万の和歌俳句は一見其面目を異にするが如しといへども細かに之を観(注・み)広く之を比ぶれば其類似せる者真に幾何(注・いくばく)ぞや。弟子は師より脱化し来り後輩は先哲より剽窃(注・窃は旧字体)し去りて作為せる者比々皆是れなり。
○終に一箇の新観念を提起するものなし。而して世の下るに従い平凡宗匠平凡歌人のみ多く現はるゝは罪其人に在りとはいへ一は和歌又俳句其物の狭隘なるによらずんばあらざるなり。
○さらば和歌俳句の運命は何れの時に窮まると。対へて云ふ。其窮り盡すの時は固より之を知るべからずといへども概言すれば俳句は已に盡きたりと思ふなり。よし未だ盡きずとするも明治年間に盡きんこと期して待つべきなり。
(子規・三十一歳。正月、松山で「ホトトギス」創刊(柳原極堂主宰)。十二月、子規庵で「第一回蕪村忌」を開く。 )
馬士につれ車夫につれ旅の日ぞ長き ID19176 制作年30 季節春 分類時候 季語日永
街道の旅人多き霞かな ID19219 制作年30 季節春 分類天文 季語霞
旅人の焼野に迷ひとげを踏む ID19245 制作年30 季節春 分類地理 季語焼野
旅人のついでに参る彼岸哉 ID19257 制作年30 季節春 分類人事 季語彼岸
人の子の凧あげて居る我は旅 ID19307 制作年30 季節春 分類人事 季語凧
旅人の知らで過ぎ行く清水哉 ID19606 制作年30 季節夏 分類地理 季語清水
京近く旅費の尽きたる袷哉 ID19637 制作年30 季節夏 分類人事 季語袷
閑古鳥かなどゝ思へば旅淋し ID19753 制作年30 季節夏 分類動物 季語閑古鳥
朝寒や木曾に脚絆の旅心 ID19896 制作年30 季節秋 分類時候 季語朝寒
朝寒や脚絆に木曾の旅心 ID19897 制作年30 季節秋 分類時候 季語朝寒
旅籠屋の淨手場遠き夜寒哉 ID19919 制作年30 季節秋 分類時候 季語夜寒
更科や旅人見ゆる十日月 ID19980 制作年30 季節秋 分類天文 季語月
雨晴れて旅僧おこす月見哉 ID20120 制作年30 季節秋 分類人事 季語月見
こほろぎに宿かる蝶の旅寐哉 ID20156 制作年30 季節秋 分類動物 季語蟋蟀
こほろぎに宿かる旅の胡蝶哉 ID20158 制作年30 季節秋 分類動物 季語蟋蟀
朝飯に木犀匂ふ旅籠哉 ID20191 制作年30 季節秋 分類植物 季語木犀
山葛の風に動きて旅淋し ID20205 制作年30 季節秋 分類植物 季語葛
柿くふて腹痛み出す旅籠哉 ID20210 制作年30 季節秋 分類植物 季語柿
旅人の荷にかけし粟の一穗哉 ID20282 制作年30 季節秋 分類植物 季語粟
初旅をなぐさめ顔の野菊哉 ID20332 制作年30 季節秋 分類植物 季語野菊
旅二人話盡きたる枯野哉 ID20502 制作年30 季節冬 分類天文 季語枯野
旅二人話盡きぬる枯野哉 ID20503 制作年30 季節冬 分類天文 季語枯野
旅二人話なくて越す枯野哉 ID20504 制作年30 季節冬 分類天文 季語枯野
我は京へ神は出雲へ道二つ ID20511 制作年30 季節冬 分類人事 季語神の旅
鯨突に通り合せし旅路哉 ID20633 制作年30 季節冬 分類動物 季語鯨
旅にして水鳥多き池を見つ ID20647 制作年30 季節冬 分類動物 季語水鳥
獻上や五十三次鷹の旅 ID20660 制作年30 季節冬 分類動物 季語鷹
吹きおろす木葉の中を旅の人 ID20703 制作年30 季節冬 分類植物 季語落葉
(漱石・三十一歳。「子規宛句稿(二十二~二十七)。)
1003 汽車を遂(とひ)て煙這行(はひゆく)枯野哉(明治三十年「子規へ送りたる句稿二十一」)
1007 かたまつて野武士落行(おちゆく) 枯野哉(明治三十年「子規へ送りたる句稿二十一」)
1008 星飛ぶや枯野に動く椎の影(同上。前書「魏叔子(ぎしゅくし)大鉄推伝一句」)
1009 島一つ吹き返さるゝ枯野かな(同上)
(寅彦・二十歳。七月、阪井夏子(十五歳)と結婚。夏目漱石を訪ね俳句の話を聞く。)
枯野行けば道連(づれ)は影法師かな(明治三十一年作)
山あれて灰の降りたる枯野かな(明治三十一年~二年作)
美しき女に逢ひし枯野かな(大正六年作)
(東洋城・二十歳。松山中学在学中に、熊本五高教授に句を送って添削して貰ふようになり、上京後根岸の子規庵へ通ひ初めた。一高では、潮音、三子、狐雁が仲間であり、教師には五城がゐた。子規庵のほか、ホトトギス例会や碧悟桐庵会への出席も欠かさなかった。俳号は、一声、造酒、造酒充、二葉、みどりとも号した。)
藁しべに蒟蒻さげて枯野かな(明治三十七年作)
鷲の居る石に日当る枯野かな(明治四十一年作)
電線に魂入りし枯野かな(同上)
かゝる里に生れて死ぬる枯野人(同上)
虎の子に鶯飼へり枯野茶屋(同上)
つひそこの火山十里や枯野原(同上)
世の終を入日に見せし枯野かな(同上)
(参考) 「正岡子規の俳句革新(一)」周辺
https://blog.goo.ne.jp/seisei14/e/e0b36fc7362cdd8f080c01a196827075

「旅装での子規(一)」(明治二十六年「はてしらずの記(東北旅行)」の頃?)
https://tenki.jp/suppl/emi_iwaki/2017/06/12/23271.html
正岡子規の「俳句革新」 (抜粋)
目次
⑴ 「俳句革新」の原点 (アマチュアリズムの視点)
⑵ 芭蕉の実像と虚像 (『芭蕉雑談』の意味するもの)
⑶ 子規の俳句観(『俳諧大要』その一)
⑷ 子規の写生論 (『俳諧大要』その二)
⑸ 子規の俳句修学論(『俳諧大要』その三)
⑹ 子規の連句非文学論 (『俳諧大要』その四)
⑺ 蕪村再発見 (『俳人蕪村』の意味するもの)
⑻ 子規の実像と虚像 (「子規俳論」の総括的考察)
(参考文献)
① 『子規全集第四巻(俳論俳話)』(浅原勝解題)・講談社(昭和 五〇)
② 『子規全集第五巻(俳論俳話)』(尾形仂解題)・講談社(昭和五〇)
③ 『正岡子規集(日本近代文学体系)(松井利彦校注)・角川書店(昭和四七)
④ 『正岡子規』(松井利彦著)・桜楓社(昭和五四)
⑤ 『俳句・短歌(近代文学鑑賞講座)』(山本健吉編)・角川書店(昭和三五)
⑥ 『俳句講座七(現代俳句史)』(加藤楸邨他著)・明治書院(昭和三四)
⑦ 『俳句講座八(現代作家論)』(山口誓子他著)・明治書院(昭和三三)
⑧ 『子規と漱石と私』(高浜虚子著)・永田書房(昭和五八)
⑨ 『俳句で読む正岡子規』(山下一海著)・永田書房(平成四)
⑩ 『正岡子規』(粟津則雄著)・講談社(平成七)
☆ その他「本文」中に記載
⑴ 「俳句革新」の原点 (アマチュアリズムの視点)
慶応四年(一八六八)七月、江戸は東京に改称され、その年の九月、年号が明治に改元された。明治維新は、日本のあらゆる面において一大変革をもたらした。
その一大変革とは、日本文学史上、古典文学から近代文学への衣替えでもあった。それは、いわば、それまでの和服という衣を脱ぎ棄てて、新しい洋服という衣で身を包むという革新的なことを意味した。
即ち、これを芭蕉の樹立した俳諧(連句・発句)という世界でいえば、それは、芭蕉以来、営々と続いていたその俳諧(連句・発句)という和服は、明治二十年代に入り、正岡子規(一八六七~一九〇二)によって、近代の「俳句」という新しい洋服に生まれ変わってしまうのである。
これが、子規の「俳句革新」であり、これが「月並俳句(つきなみはいく)から近代俳句」への移行でもあった。
この子規の「俳句革新」とは何だったのであろうか。
子規の「俳句革新」というのは、「書生(アマ)の、書生(アマ)のための、書生(アマチュア)による」俳句革新運動であった。 子規が批判の対象とした、月並(月次)俳句とは、当時の俳諧の宗匠達が開く毎月の例会を意味したが、子規は、それらの月並俳句を「平凡・陳腐・卑俗」として攻撃したのである。
そして、子規の月並俳句(旧派)の批判と子規らが目指す近代俳句(新派)との違いは、子規は、その『俳句問答』(明治二十九年五月から九月まで「日本」新聞に連載され、後に刊行本となる)において、要約すれば以下のとおりに主張するのである。
○問 新俳句と月並俳句とは句作に差異あるものと考へられる。果して差異あらば新俳句は如何なる点を主眼とし月並句は如何なる点を主眼として句作するものなりや
○答 第一は、我(注・新俳句)は直接に感情に訴へんと欲し、彼(注・月並俳句)は往々智識(注・知識)に訴へんと欲す。
○第二は、我(注・新俳句)は意匠の陳腐なるを嫌へども、彼(注・月並俳句)は意匠の陳腐を嫌ふこと我より少なし、寧ろ彼は陳腐を好み新奇を嫌ふ傾向あり。
○第三は、我(注・新俳句)は言語の懈弛(注・たるみ)を嫌ひ彼(注・月並俳句)は言語の懈弛(注・たるみ)を嫌ふこと我より少なし、寧ろ彼は懈弛(注・たるみ)を好み緊密を嫌ふ傾向あり。
○第四は、我(注・新俳句)は音調の調和する限りに於て雅語俗語漢語洋語を問はず、彼(注・月並俳句)は洋語を排斥し漢語は自己が用ゐなれたる狭き範囲を出づべからずとし雅語も多くは用ゐず。
○第五は、我(注・」新俳句)に俳諧の系統無く又流派無し、彼(注・月並俳句)は俳諧の系統と流派とを有し且つ之があるが為に特殊の光栄ありと自信せるが如し、従って其派の開祖及び其伝統を受けたる人には特別の尊敬を表し且つ其人等の著作を無比の価値あるものとす。我(注・新俳句)はある俳人を尊敬することあれどもそは其著作の佳なるが為なり。されども尊敬を表する俳人の著作といへども佳なる者と佳ならざる者とあり。正当に言へば我(注・新俳句)は其人を尊敬せずして其著作を尊敬するなり。故に我(注・新俳句)は多くの反対せる流派に於て俳句を認め又悪句を認む。
この第一から第五までの子規の主張の中で、子規が最も強調したのは、この第五であった。即ち、子規が排斥して止まなかったものは、それは、日本という土地に平然と土俗化し風化した垢まみれの宗匠達が牛耳っいる、その古色蒼然とした宗匠俳諧への痛罵であった。
それは、作品そのものというよりは、宗匠という人種への挑戦であった。即ち、言葉を変えていえば、それは、当時の権威の象徴でもある宗匠(プロ・職業俳人)を排斥し、「「書生(アマ・素人)の、書生(アマ・素人)のための、書生(アマ・素人)による」俳句を標榜したのであった。
正岡子規の生涯というのは、実に三十五年という短いものであった。そして、喀血して子規(「卯の花をめがけてきたか時鳥」・「卯の花の散るまで鳴くか子規」より子規の由来があるとか)と号したのが、明治二十二年、子規十七歳の時、そして、病床の人となり、文字とおり『病牀六尺』の境遇に置かれたのが、明治二十八年、その二十八歳の時であった。
その永く病床にあったその短い生涯にあって、子規は、「俳句革新」と「短歌革新」において、超人的な足跡を残したのである。 その「俳句革新」は、明治二十五年(二十五歳の時)の『獺祭書屋俳話(だつさいしょおくはいわ)』において口火が切られ、その「短歌革新」は、明治三十一年(三十一歳の時)の『歌よみに与ふる書』においてであった。
この「俳句革新」の第一声の『獺祭書屋俳話(だつさいしょおくはいわ)』は、明治二十五年六月から十月にかけて「日本」新聞に連載されたものであった。
そして、この『獺祭書屋俳話(だつさいしょおくはいわ)』は、その「俳句分類」の子規の作業を通しながら会得された古俳諧の膨大な情報集積を縦横に駆使しながら、随筆的に表したもので、当初から系統だった俳論という体裁ではなかった。
後に、単行本として出版されるに及び、それは、「俳諧史」・「俳諧論」・「俳人俳句」・「俳書批評」という分野で再編集されるのであった。
子規は、この俳話において、「俳諧」・「発句」という言葉のほかに、さりげなく「俳句」という言葉も用い、現在の「俳句」という分野を、「俳諧」・「発句」という分野から、全く、単独のものとして独立させるに至るのである。
即ち、その俳話は、「俳諧という名称」・「連歌と俳諧」・「延宝天和貞享の俳風」・「足利時代より元禄に至る発句」・「俳書」として、次に、「字余りの俳句」という項目が来て、この後に、この俳話において、最も注目すべき「俳句の前途」という俳論が続くのである。
そして、その前提には、「連歌と俳諧」という項目で、次のような、「俳諧」・「発句」という分野から「俳句」という分野に切り替えようとする、子規の主張の兆しが見られるのである。
○芭蕉は発句のみならず俳諧連歌(注・連句)にも一様に力を尽し其門弟の如きも猶其遺訓を守りしが後世に至りては単に十七字の発句を重んじ俳諧連歌(注・連句)は僅に其付属物として存ず(注・す)るの傾向あるが如し。
そして、この『獺祭書屋俳話(だつさいしょおくはいわ)』において、最も注目すべき「俳句滅亡論」が、その「俳句の前途」において展開されるのである。それを要約すると以下のとおりとなる。
○日本の和歌俳句の如きは一首の字音僅に二三十に過ぎざれば之を錯列法(バーミュテーシヨン)に由て算するも其数に限りあるを知るべきなり。語を換へて之をいはゞ和歌(重に短歌をいふ)俳句は早晩其限りに達して最早此上に一首の新しきものだに作り得べからさ(注・ざ)るに至るべしと。
○試みに見よ古往今来吟詠せし所の幾万の和歌俳句は一見其面目を異にするが如しといへども細かに之を観(注・み)広く之を比ぶれば其類似せる者真に幾何(注・いくばく)ぞや。弟子は師より脱化し来り後輩は先哲より剽窃(注・窃は旧字体)し去りて作為せる者比々皆是れなり。
○終に一箇の新観念を提起するものなし。而して世の下るに従い平凡宗匠平凡歌人のみ多く現はるゝは罪其人に在りとはいへ一は和歌又俳句其物の狭隘なるによらずんばあらざるなり。
○さらば和歌俳句の運命は何れの時に窮まると。対へて云ふ。其窮り盡すの時は固より之を知るべからずといへども概言すれば俳句は已に盡きたりと思ふなり。よし未だ盡きずとするも明治年間に盡きんこと期して待つべきなり。
「子規・漱石・寅彦・東洋城」俳句管見(その八) [子規・漱石・寅彦・東洋城]
その八「明治二十九年(一八九六)・「梨の花・柳」など」
(子規・三十歳。正月三日鴎外・漱石らと子規庵で句会。)
https://shiki-museum.com/masaokashiki/haiku?post_type=haiku&post_type=haiku&haiku_id=&p_age=28&season=&classification=&kigo=&s=%E9%87%91%E5%B7%9E&select=
此春は金州城に暮れてけり ID12528 制作年28 季節春 分類時候 季語春の暮
金州や矢の根をひろふ春の風 ID12609 制作年28 季節春 分類天文 季語春風
金州の城門高き柳かな ID12930 制作年28 季節春 分類植物 季語柳
金州にいくさせし人よ畠打つ ID16063 制作年29 季節春 分類人事 季語畑打
金州や東門の外に梨の花 ID16343 制作年29 季節春 分類植物 季語梨の花
(漱石・三十歳。四月、熊本第五高校講師として赴任。六月、中根鏡子と結婚。「子規宛句稿が始まる(十~二十一)。東洋城、漱石に句を送り、添削を乞う。)
766 待つ宵の夢ともならず梨の花(明治二十九年「子規へ送りたる句稿十四」)
(寅彦・十九歳。高知県尋常中学校首席で卒業。熊本第五高等学校に入学する。)
ごみをかぶる柳の下のポストかな(明治三十一~二年作)
県庁の柳芽をふく広小路(同上)
門前に泥舟つなぐ柳哉(同上)
招集の掲示を撫る柳哉(同上)
雨の家鴨柳の下につどひけり(同上)
二階から女郎が手招く柳かな(明治三十二年作)
煙草屋の娘うつくしき柳かな(明治三十三年作)
(東洋城・十九歳。)
県道や柳を植ゑずペンキ橋(明治三十三年作)
飛々に村飛々に柳哉(明治三十三年作)
(参考) 「子規と鷗外と饅頭茶漬」(周辺)
.jpg)
「子規・日清戦争。従軍記者の頃の森鷗外(近衛師団の軍医部長)」
https://plaza.rakuten.co.jp/akiradoinaka/diary/201803220000/
≪ 此春は金州城に暮れてけり(明治28)
金州の城門高き柳かな (明治28)
金州にいくさせし人よ畠打つ(明治29)
金州や東門の外に梨の花(明治29)
金州の南門見ゆる枯野哉(明治31)
子規が日清戦争の従軍記者として遼東半島に向かいましたが、金州に上陸した時、すでに日本と清の交戦は終わっていました。子規の金州滞在は、明治28年4月15日から5月10日までで、金州を離れた日に日清講和条約が批准されました。
この時、近衛師団の軍医部長だった森鷗外も金州に駐屯していました。暇を持て余していた子規と鷗外は、俳句についての意見を戦わせています。鷗外はこのことを「但征日記」に「正岡常規来り訪う俳譜の事を談ず」(5月4日)、「子規来り別る。几董等の歌仙一巻を手写して我に贈る」(5月10日)と記しています。『子規全集』月報7の宮地伸一著「子規と鴎外との出会い」には、「今度の戦争に行って、非常に仕合わせなのは正岡君と懇意になったことだ」と鷗外が柳田國男に語っていたとあります。≫
子規も、門人たちに書きとらせた「病床日誌」明治28年6月5日に「いちごを食い、頗る壮快なるおももちなり。曰く、いちごとりとは中々おもしろき名なり。小説にすれば森鷗外の好む所か……森に金州にて会いし話をせしや。……中略……金州の兵站部長は森なりと聞き訪問せしに、兵站部長には非ず、軍医部長なりし。これより毎日訪問せり」と書かれています。
帰国後、鷗外は子規との交遊を深め、明治29年の正月3日。子規庵の発句始に、鷗外が初めて顔を出しました。鳴雪、瓢亭、虚子、可全、碧梧桐、漱石らが参加した会の季題は「あられ」で、鷗外は「おもひきつて出で立つ門の霞哉」と詠み、最高点を獲得しました。この年、鷗外は「めさまし草」を創刊したため、子規一門も俳句や評論を寄稿しました。子規と鷗外の親交は、明治32年6月に、鷗外が小倉師団に転勤するまで続いています。
学生時代、子規は鷗外の作品に対して、いい感情を持っていませんでした。明治24年8月23日の漱石から子規に宛てた手紙には「鷗外の作ほめ候とて図らずも大兄の怒りを惹き申訳もこれなく、これも小子嗜好の下等なる故とひたすら慚愧(ざんき)致居候。元来、同人の作は僅かに二短篇を見たるまでにて、全体を窺うことかたく候得ども、当世の文人中にては先ず一角あるものと存居候いし、試みに彼が作を評し候わんに、結構を泰西に得、思想をその学問に得、行文は漢文に胚胎して和俗を混淆したるものと存候。右等の諸分子あいまって、小子の目には一種沈鬱奇雅の特色ある様に思われ候。もっとも人の嗜好は行き掛かりの教育にて(たとい文学中にても)種々なるもの故、己れは公平の批評と存候ても他人には極めて偏屈な議論に見ゆるものに候ば、小生自身は要所に心酔致候。心持ちはなくとも大兄より見れば作用に見ゆるもごもっとものことに御座候」とあり、鷗外の著作に対して、子規は否定的だったことがわかります。 ≫
(子規・三十歳。正月三日鴎外・漱石らと子規庵で句会。)
https://shiki-museum.com/masaokashiki/haiku?post_type=haiku&post_type=haiku&haiku_id=&p_age=28&season=&classification=&kigo=&s=%E9%87%91%E5%B7%9E&select=
此春は金州城に暮れてけり ID12528 制作年28 季節春 分類時候 季語春の暮
金州や矢の根をひろふ春の風 ID12609 制作年28 季節春 分類天文 季語春風
金州の城門高き柳かな ID12930 制作年28 季節春 分類植物 季語柳
金州にいくさせし人よ畠打つ ID16063 制作年29 季節春 分類人事 季語畑打
金州や東門の外に梨の花 ID16343 制作年29 季節春 分類植物 季語梨の花
(漱石・三十歳。四月、熊本第五高校講師として赴任。六月、中根鏡子と結婚。「子規宛句稿が始まる(十~二十一)。東洋城、漱石に句を送り、添削を乞う。)
766 待つ宵の夢ともならず梨の花(明治二十九年「子規へ送りたる句稿十四」)
(寅彦・十九歳。高知県尋常中学校首席で卒業。熊本第五高等学校に入学する。)
ごみをかぶる柳の下のポストかな(明治三十一~二年作)
県庁の柳芽をふく広小路(同上)
門前に泥舟つなぐ柳哉(同上)
招集の掲示を撫る柳哉(同上)
雨の家鴨柳の下につどひけり(同上)
二階から女郎が手招く柳かな(明治三十二年作)
煙草屋の娘うつくしき柳かな(明治三十三年作)
(東洋城・十九歳。)
県道や柳を植ゑずペンキ橋(明治三十三年作)
飛々に村飛々に柳哉(明治三十三年作)
(参考) 「子規と鷗外と饅頭茶漬」(周辺)
.jpg)
「子規・日清戦争。従軍記者の頃の森鷗外(近衛師団の軍医部長)」
https://plaza.rakuten.co.jp/akiradoinaka/diary/201803220000/
≪ 此春は金州城に暮れてけり(明治28)
金州の城門高き柳かな (明治28)
金州にいくさせし人よ畠打つ(明治29)
金州や東門の外に梨の花(明治29)
金州の南門見ゆる枯野哉(明治31)
子規が日清戦争の従軍記者として遼東半島に向かいましたが、金州に上陸した時、すでに日本と清の交戦は終わっていました。子規の金州滞在は、明治28年4月15日から5月10日までで、金州を離れた日に日清講和条約が批准されました。
この時、近衛師団の軍医部長だった森鷗外も金州に駐屯していました。暇を持て余していた子規と鷗外は、俳句についての意見を戦わせています。鷗外はこのことを「但征日記」に「正岡常規来り訪う俳譜の事を談ず」(5月4日)、「子規来り別る。几董等の歌仙一巻を手写して我に贈る」(5月10日)と記しています。『子規全集』月報7の宮地伸一著「子規と鴎外との出会い」には、「今度の戦争に行って、非常に仕合わせなのは正岡君と懇意になったことだ」と鷗外が柳田國男に語っていたとあります。≫
子規も、門人たちに書きとらせた「病床日誌」明治28年6月5日に「いちごを食い、頗る壮快なるおももちなり。曰く、いちごとりとは中々おもしろき名なり。小説にすれば森鷗外の好む所か……森に金州にて会いし話をせしや。……中略……金州の兵站部長は森なりと聞き訪問せしに、兵站部長には非ず、軍医部長なりし。これより毎日訪問せり」と書かれています。
帰国後、鷗外は子規との交遊を深め、明治29年の正月3日。子規庵の発句始に、鷗外が初めて顔を出しました。鳴雪、瓢亭、虚子、可全、碧梧桐、漱石らが参加した会の季題は「あられ」で、鷗外は「おもひきつて出で立つ門の霞哉」と詠み、最高点を獲得しました。この年、鷗外は「めさまし草」を創刊したため、子規一門も俳句や評論を寄稿しました。子規と鷗外の親交は、明治32年6月に、鷗外が小倉師団に転勤するまで続いています。
学生時代、子規は鷗外の作品に対して、いい感情を持っていませんでした。明治24年8月23日の漱石から子規に宛てた手紙には「鷗外の作ほめ候とて図らずも大兄の怒りを惹き申訳もこれなく、これも小子嗜好の下等なる故とひたすら慚愧(ざんき)致居候。元来、同人の作は僅かに二短篇を見たるまでにて、全体を窺うことかたく候得ども、当世の文人中にては先ず一角あるものと存居候いし、試みに彼が作を評し候わんに、結構を泰西に得、思想をその学問に得、行文は漢文に胚胎して和俗を混淆したるものと存候。右等の諸分子あいまって、小子の目には一種沈鬱奇雅の特色ある様に思われ候。もっとも人の嗜好は行き掛かりの教育にて(たとい文学中にても)種々なるもの故、己れは公平の批評と存候ても他人には極めて偏屈な議論に見ゆるものに候ば、小生自身は要所に心酔致候。心持ちはなくとも大兄より見れば作用に見ゆるもごもっとものことに御座候」とあり、鷗外の著作に対して、子規は否定的だったことがわかります。 ≫
「子規・漱石・寅彦・東洋城」俳句管見(その七) [子規・漱石・寅彦・東洋城]
その七「明治二十八年(一八九四)・「朧・朧夜」など」
(子規・二十九歳。日清戦争従軍記者となり、帰途中に喀血。五月、神戸の病院に入院。室月、須磨保養院に移り、八月帰省。松山中学校教師として赴任した、漱石の「愚垜仏庵」に奇遇、地元の「松風会」の句作を指導。十月、奈良・京都を経て帰京。十二月、道灌山で虚子に後継を委託するも断られる。)
朧とは桜の中の柳かな ID639 制作年23 季節春 分類天文 季語朧
烏帽子きた殿居姿の朧なり ID1712 制作年25 季節春 分類天文 季語朧
面顔の声朧也春の陣 ID1713 制作年25 季節春 分類天文 季語朧
白き山青き山皆おぼろなり D1714 制作年25 季節春 分類天文 季語朧
朧より朧に人の咄かな ID4977 制作年26 季節春 分類天文 季語朧
小夜更て上戸の声の朧なり ID4978 制作年26 季節春 分類天文 季語朧
昼の月さらに朧と見えぬなり ID4979 制作年26 季節春 分類天文 季語朧
行燈を消せば小窓の朧かな ID12700 制作年28 季節春 分類天文 季語朧
男やら女やら更に朧かな ID15975 制作年29 季節春 分類天文 季語朧
ある夜更けて貴人来ます朧哉 ID19236 制作年30 季節春 分類天文 季語朧
茶屋を出る箱提灯や朧人 ID19237 制作年30 季節春 分類天文 季語朧
京の灯や朧の上る東山 ID20862 制作年31 季節春 分類天文 季語朧
吾折々死なんと思ふ朧かな ID23383 制作年33 季節春 分類天文 季語朧
朧野ヤ朧ヲ破ル藁砧 ID24683 制作年35 季節春 分類天文 季語朧
末遂ゲヌ恋ノ始ヤオボロナル ID24684 制作年35 季節春 分類天文 季語朧
背ノ高キ人佇メリ朧陰 ID24685 制作年35 季節春 分類天文 季語朧
背ノ高キ人ニ逢ヒケル朧哉 ID24686 制作年35 季節春 分類天文 季語朧
大仏ノ目ニハ吾等モ朧カナ ID24687 制作年35 季節春 分類天文 季語朧
遠クトモ近クトモ見エテ灯朧 ID24688 制作年35 季節春 分類天文 季語朧
篷アゲテ見ル両岸ノ朧カナ ID24689 制作年35 季節春 分類天文 季語朧
話シナガラ土手ノ上行ク人朧 ID24690 制作年35 季節春 分類天文 季語朧
見返レバ住吉ノ灯ノ朧ナル ID24691 制作年35 季節春 分類天文 季語朧
闇ヲ出テ朧ニ人ノ陰二ツ ID24692 制作年35 季節春 分類天文 季語朧
両岸ノ人家朧ニ下リ舟 ID24693 制作年35 季節春 分類天文 季語朧
路次口ヲ出デヽ朧ノ大路カナ ID24694 制作年35 季節春 分類天文 季語朧
(漱石・二十九歳。四月、松山中学校教師として赴任。六月、松山市二番町の「愚陀仏庵」。八月、子規が寄寓して、十月に帰省するまで作句に励む。「子規宛句稿が始まる(一~九)。東洋城、松山在学中に漱石に英語を教わる。)
511 いそがしや霰ふる夜の鉢叩
512 十月の月ややうやう凄くなる
513 山茶花の垣一重なり法華寺
514 行く年や膝と膝とをつき合せ
515 雪深し出家を宿し参らする
516 詩神とは朧夜に出る化ものか
≪ 季=朧夜(春)。※漱石は虚子の「松山的ならぬ淡泊なる処、のんきなる処、気の利かぬ処」などを愛した(子規宛書簡)。(後略) ≫(『漱石全集第十七巻・坪内稔典注解』)
(寅彦・十八歳)
朧夜や湯殿の窓の磨硝子(すりがらす)(明治三十四年作。二十四歳)
湯煙りの白粉臭き朧かな (同上)
(東洋城・十八歳)
わたつみへ浪を巻きさる朧かな (明治三十四年作。二十四歳)
三軒家橋の人呼ぶ朧かな (同上、前書「嵐山」)
(参考)「道灌山事件(その一)~(その六)」周辺

「道灌山事件(明治二十八年)」当時の「高浜虚子」
https://plaza.rakuten.co.jp/akiradoinaka/diary/201803220000/
http://yahantei.blogspot.com/2008/06/blog-post_01.html
(再掲)「道灌山事件(その一)~(その六)」
虚子の亡霊(四十九~五十四)
虚子の亡霊(四十九) 道灌山事件(その一)
ホトトギス「百年史」の年譜は「明治三十年一月 柳原極堂、松山で『ほとゝぎす』創刊」より始まり、明治二十八年の子規と虚子との「道灌山事件」の記載はない。ここで、「子規年譜」の当該年については、下記のとおりの記述がある。
http://www2a.biglobe.ne.jp/~kimura/siki01.htm
(子規略年譜)
明治28年(1895) 28歳
4月、日清戦争従軍記者として遼東半島に渡り、金州、旅順に赴く。金州で藤野古曰の死を知る。「陣中日記」を『日本』に連載する。5月4日、従軍中の森鴎外を訪ねる。17日、帰国の船中で喀血。23日、神戸に上陸し、直ちに県立神戸病院に入院。一時重体に陥る。7月、須磨保養院に転院。8月20日退院。28日、松山の漱石の下宿に移り50日余を過ごす。極堂ら地元の松風会会員と連日句会を開き、漱石も加わる。10月、松山を離れ、広島、大阪、奈良を経て帰京。12月、虚子を誘って道灌山へ行き、自らの文学上の後継者となることを依頼するが断られる。
http://www.shikian.or.jp/sikian2.htm
この十二月の、「虚子を誘って道灌山へ行き、自らの文学上の後継者となることを依頼するが断られる」というのが、いわゆる「道灌山事件」と呼ばれるもので、次のアドレスのもので、その全容を知ることができる。
http://www5e.biglobe.ne.jp/~haijiten/haiku9-1.htm
☆俳句史などには「道灌山事件」などと呼ばれているが、事件というほどの物ではない。道灌山事件とは明治二十八年十二月九日(推定)道灌山の茶店で子規が虚子に俳句上の仕事の後継者になる事を頼み、虚子がこれを拒絶したという出来事である。ことはそれ以前の、子規が日清戦争の従軍記者としての帰途、船中にて喀血した子規は須磨保養院において療養をしていた。その時、短命を悟った子規は虚子に後事を託したいと思ったという。その当時、虚子は子規の看護のため須磨に滞在していたのだ。明治二十八年七月二十五日(推定)、須磨保養院での夕食の時の事、明朝ここを発って帰京するという虚子に対して「今度の病気の介抱の恩は長く忘れん。幸いに自分は一命を取りとめたが、併し今後幾年生きる命かそれは自分にも判らん。要するに長い前途を頼むことは出来んと思ふ。其につけて自分は後継者といふ事を常に考へて居る。(中略)其処でお前は迷惑か知らぬけれど、自分はお前を後継者と心に極めて居る。」(子規居士と余)と子規は打ち明ける。この子規の頼みに対して、虚子は荷が重く、多少迷惑に感じながらも、「やれる事ならやってみよう。」と返答したという。併し子規は虚子の言葉と態度から「虚子もやや決心せしが如く」と感じたらしく、五百木瓢亭宛の書簡に書いている。そして明治二十八年十二月九日、東京に戻っていた子規から虚子宛に手紙が届く。虚子は根岸の子規庵へ行ってみたところ、子規は少し話したい事がある。家よりは外のほうが良かろう、という事で二人は日暮里駅に近い道灌山にあった婆(ばば)の茶店に行くことになった。その時子規は「死はますます近づきぬ文学はようやく佳境に入りぬ」とたたみ掛け、我が文学の相続者は子以外にないのだ。その上は学問せよ、野心、名誉心を持てと膝詰め談判したという。しかし虚子は「人が野心名誉心を目的にして学問修行等をするもそれを悪しとは思わず。然れども自分は野心名誉心を起こすことを好まず」と子規の申し出を断ったという。数日後に虚子は子規宛に手紙を書き、きっちりと虚子の態度を表明している。「愚考するところによれば、よし多少小生に功名の念ありとも、生の我儘は終に大兄の鋳形にはまること能はず、我乍ら残念に存じ候へど、この点に在っては終に見棄てられざるを得ざるものとせん方なくも明め申候。」これに対して子規は瓢亭あての書簡に「最早小生の事業は小生一代の者に相成候」「非風去り、碧梧去り、虚子亦去る」と嘆いたという。道灌山事件の事は直ぐには世間に知らされず、かなり後に虚子が碧梧桐に打ち明けて話し、子規の死後、瓢亭の子規書簡が公表されてから一般に知られるようになったそうである。
(参考) 清崎敏郎・川崎展宏「虚子物語」有斐閣ブックス 宮坂静生著「正岡子規・死生観を見据えて」明治書院
上記が、いわゆる「道灌山事件」の全容なのであるが、その後、子規自身も、「獺祭書屋俳句帖上巻を出版するに就きて思ひつきたる所をいふ」などで、虚子も、「子規居士と余」などで、この「道灌山事件」については記述しているのであるが、「何故に、子規と虚子とで決定的に意見が相違して、何故に、虚子は頑なに子規の依頼を拒絶したのか」という、その真相になると、これがどうにもウヤムヤなのである。
このウヤムヤの所に、前回までの、虚子は「芸能・文芸としての俳句」という「第二芸術的」な俳句観を有していたのに、子規は「芸術・文学としての俳句」、すなわち、「第一芸術的」な俳句観を、虚子に無理強いをしたので、虚子はこれを拒絶する他は術がなかったと理解すると、何となく、この子規と虚子との「道灌山事件」の背景が見えてくるような思いがするのである。
虚子の亡霊(五十) 道灌山事件(その二)
子規と虚子との「道灌山事件」というのは、明治二十八年と、もはや遠い歴史の中に埋没したかに思えたのだが、この平成十六年に、『夕顔の花——虚子の連句論——』(村松友次著)が刊行され、全く新しい視点での「道灌山事件」の背景を論述されたのであった。この「全く新しい視点」ということは、その「あとがき」の言葉でするならば、
「子規の連句否定論」と「虚子の連句肯定論」との対立が、「道灌山事件」の背景とするところの、とにもかくにも大胆な推理と仮説とに基づくものを指していることに他ならない。
この「子規の連句否定論」と「虚子の連句肯定論」との対立の推理と仮説は、さらに、例えば、子規の『俳諧大要』の最終尾の「連句」の項の、「ある部分は、子規の依頼の下でゴーストライターとして虚子が書いているのではなかろうか」(同書所収「『俳諧大要』(子規)最終尾の不審」)と、さらに大胆な推理と仮説を提示することとなる。
この著者は、古典(芭蕉・蕪村・一茶など)もの、現代(素十など)もの、連句(芭蕉連句鑑賞など)ものと、こと、「古典・連句・俳句・ホトトギス」全般にわたって論述することに、その最右翼に位置することは、まずは多くの人が肯定するところであろう。そして、通説的な見解よりも、独創的な異説などもしばしば見られ、例えば、その著の『蕪村の手紙』所収の、「『北寿老仙をいたむ』の製作時期」・「『北寿老仙をいたむ』の解釈の流れ」などの論稿は、今や、通説的にもなりつつ状況にあるといっても過言ではなかろう。
虚子・素十に師事し、俳誌 「雪」を主宰し、「ホトトギス」同人でもあり、東洋大学の学長も歴任した、この著者が、最新刊のものとして、この『夕顔の花——虚子の連句論——』を世に問うたということは、今後、この著を巡って、どのように、例えば、子規と虚子との「道灌山事件」などの真相があばかれていくのか、大変に興味のそそられるところである。
ここで、ネット記事で、東大総長・文部大臣も歴任した現代俳人の一躍を担う有馬朗人の上記の村松友次のものと交差する「読売新聞」での記事のものを、次のアドレスのものにより紹介をしておきたい。
http://art-random.main.jp/samescale/085-1.html
☆正岡子規は俳諧連句の発句を独立させて俳句とした。と同時に多数の人で作る連句は、西欧の個人主義的芸術論に合わないと考え切り捨てたのである。一方子規の第一の後継者である虚子は連句を大切にしていた。---子規が虚子に後継者になってくれと懇願するが、虚子が断ったという有名な道灌山事件のことである。その結果、子規は虚子を破門したと思われるにもかかわらず、一生両者の親密な関係は代わらなかった。
「読売新聞」2004.08.08朝刊 有馬朗人「本よみうり堂」より抜粋。
虚子の亡霊(五十一) 道灌山事件(その三)
この「道灌山事件」とは別項で、「虚子・年尾の連句論」に触れる予定なので、ここでは、『夕顔の花——虚子の連句論——』(村松友次著)の詳細については後述といたしたい。そして、ここでは、明治二十八年の「道灌山事件」の頃の子規の句について、
次のアドレス(『春星』連載中の中川みえ氏の稿)のものを紹介しておきたい。
http://www.geocities.co.jp/Hollywood-Kouen/9280/shikiku/shikiku5.htm#shikiku52
☆ 語りけり大つごもりの来ぬところ 子規
漱石虚子来る
漱石が来て虚子が来て大三十日 同上
漱石来るべき約あり
梅活けて君待つ庵の大三十日 同上
足柄はさぞ寒かったでこざんしよう 同上
明治二十八年作。
漱石はこの年五月、神戸病院に入院中の子規に、病気見舞かたがた「小子近頃俳文に入らんと存候。御閑暇の節は御高示を仰ぎたく候」と手紙で言って来た。第一回の句稿を九月二十三日に送って来たのを嚆矢として、三十二年十月十七日まて三十五回に渡って膨大な数の句を子規のもとに送って、批評と添削を乞うた。
粟津則雄氏は「漱石・子規往復書簡集」(和田茂樹編)の解説でこのことに触れて、
ロンドン留学の前年、明治三十二年の十月まで、これほどの数の句稿を送り続けるのは、ただ作句熱と言うだけでは片付くまい。もちろん、ひとつには、俳句が、手紙とちがって、自分の経験や印象や感慨を端的直載に示しうるからだろうが、同時にそこには、病床の子規を楽しませたいという心配りが働いていたと見るべきだろう。
と述べておられる。
漱石は句稿に添えた手紙の中で、この年十二月に上京する旨伝えて来た。この時期漱石には縁談があって、そのことなども子規に手紙で相談していたようである。
漱石は十二月二十七日に上京して、翌日、貴族院書記官長中根重一の長女鏡子と見合をし、婚約した。
大みそかに訪ねて来るという漱石を、子規は梅を活けて、こたつをあたためて、楽しみに持っていたのである。
大みそかには虚子も訪ねてきた。
この月の幾日かに、子規は道潅山の茶店に虚子を誘い、先に須磨で言い出した後継委嘱問題を改めて切り出して、虚子の意向を問い正した。
文学者になるためには、何よりも学問をすることだ、と説く子規に、厭でたまらない学問をしてまで文学者になろうとは思わない、と虚子は答えた。会談は決裂した。
子規と虚子の間は少々ぎくしゃくしたが、それでも大みそかに虚子はやって来た。子規は最も信頼する友漱石と、一番好きてあった虚子の来訪を心待ちにしていたのである。
漱石は一月七日まで東京に滞在して、子規庵初句会(一月三日)にも出席した。
この年を振り返って、子規は次のように記している。
明治二十八年といふ歳は日本の国が世界に紹介せられた大切な年であると同時に而かも反対に自分の一身は取っては殆ど生命を奪はれた程の不吉な大切な年である。しかし乍らそれ程一身に大切な年であるにかかはらず俳句の上には殆ど著しい影響は受けなかった様に思ふ。(略)幾多の智識と感情とは永久に余の心に印記せられたことであらうがそれは俳句の上に何等の影響をも及ぼさなかった。七月頃神戸の病院にあって病の少しく快くなった時傍に居た碧梧桐が課題の俳句百首許りを作らうと言ふのを聞て自分も一日に四十題許りを作った。其時に何だか少し進歩したかの様に思ふて自分で嬉しかつたのは嘘であらう。二ヶ月程も全く死んで居た俳句が僅かに蘇ったと云ふ迄の事て此年は病余の勢力甚だ振はなかった。尤も秋の末に二三日奈良めぐりをして矢鱈に駄句を吐いたのは自分に取っては非常に嬉しかった。(獺祭書屋俳句帖上巻を出版するに就きて思ひつきたる所をいふ)
時に、子規、二十九歳、漱石、二十九歳、虚子は若干二十二歳であった。当時の虚子は、虚子の言葉でするならば、「放浪の一書生」(『子規居士と余』)で、今の言葉でするならば、「ニート族」(若年無業者)の代表格のようなものであろう。子規とて、書生上がりの「日本新聞」などの「フリーター」(請負文筆業)という趣で、漱石はというと、丁度、その小説の「坊っちゃん」の主人公のように、松山中学校の英語の教師という身分であった。しかし、この三人が、いや、この三人を取り巻く、いわば、「子規塾」の面々が、日本の文化・芸術・文学の一翼を担うものに成長していくとは、
誠に、何とも痛快極まるものと思えてならない。そして、これも、虚子の言葉なのであるが、子規をして、「余はいつも其事を思ひ出す度に人の師となり親分となる上に是非欠くことの出来ぬ一要素は弟子なり子分なりに対する執着であることを考へずにはゐられぬのである」(前掲書)という、この子規の存在は極めて大きいという感慨を抱くのである。
ここらへんのことについて、先に紹介した次のアドレスで、これまた、「読売新聞」のコラムの記事を是非紹介をしておきたい。
http://art-random.main.jp/samescale/085-1.html
☆高浜虚子には、独特なユーモアをたたえた句がある。5枚の葉をつけた、ひと枝だの笹がある。「初雪や綺麗に笹の五六枚」等々、葉の1枚ずつに俳句が書かれている。東京にいた24歳の正岡子規が郷里・松山の友、17歳の高浜虚子に贈った。「飯が食えぬから」と虚子が文学の志を捨てようとしているらしい。人づてに聞いた子規がこの笹を添えて手紙を送ったのは、1982年1月のことである。「食ヘヌニ困ルト仰セアラバ 小生衰ヘタリト雖 貴兄ニ半碗ノ飯ヲ分タン」。「目的物ヲ手ニ入レル為ニ費スベキ最後ノ租税ハ 生命ナリ」。3年前に血を吐き、四年後には病床につく人が友に寄せた言葉は、悲しいまでに温かい。この笹の枝を子規は、「心竹」と呼んでいる。ささ(笹)いな贈り物だという。心の丈でもあったのだろう。虚子の胸深くに心竹は根を張り、近代詩歌の美しい実りとなった詩業を支えたに違いない。
「読売新聞」2004.01.01朝刊「編集手帳」より抜粋。
虚子の亡霊(五十二) 道灌山事件(その四)
ネットの記事は雲隠れをするときがある。一度、雲隠れをしてしまうとなかなか出てこない。かつて、「俳句第二芸術論」について触れていたときに、桑原武夫が高浜虚子の、俳句ではなく、その小説について褒めたことがあり、その桑原の初評論ともいえるようなものが、虚子の「ホトトギス」に掲載されたことがあり、その桑原のものを、ネットの記事で見た覚えがあるのだが、どうにも、それが雲隠れして、それを探すことができなかったのである。
それが、しばらく、この虚子のものを休んでいたら、まるでその休みを止めて、また続けるようにとの催促をするように、そのネット記事が偶然に眼前に現れてきたのである。その記事は、次のアドレスのもので、「小さな耳鼻科診療所での話です」というタイトルのブログ記事のものであったのだ。今度は、雲隠れしないように、その前後の関連するところを、ここに再掲をしておくこととしたい。
http://www.geocities.jp/kayo_clinic/geodiary.311-320.html
317.俳談(その一)
センセは、俳句をすなる。パソコンを使い始めて5年。俳句を始めて4年。ちょうど、「俳句とは」を考えたくなる時期にきたようだ。
乱雑に突っ込まれた本棚を見てみると、それなりに俳句入門の本が並んでいる。鷹羽狩行、稲畑汀子、阿部肖人、藤田湘子、我が師匠の大串章。先生方の言わんとされることが理解できれば俳句ももう少し上手くなれたのであろうか。句集もそれなりに積んである....
悪あがきついでに「俳句への道」高浜虚子(岩波文庫)を読むことにした。本の後半の研究座談会が面白そうだったので、そこから読み始めた。ところが、いきなりこんな文に出会った。
「近頃の人は、四五年俳句を作って見て、すぐ、『俳句とは』という議論をしたがる。そういう人が多い。こういう人は長続きしない。やがてその議論はかげをひそめるばかりかその人もかげをひそめる。」と、ある。ガーン!!!虚子先生は厳しい。
とはいえ、「私はしばらく俳論、俳話のやうなものは書かないでをりました。..」と、いいながら「玉藻」(主宰、星野立子)に、俳話を載せた。(昭和27年)ここでの俳論、俳話がまとめられたのが、この文庫である。「私の信じる俳句というのもは斯様なのもであるということを書き残して置くのもである。」と序にある。
なんたってセンセはミーハーである。いくら大虚子先生のお話でも、まず、愉快そうなところかに目をつける。まず、研究座談会の章から。
虚子は、子規のところに手紙を出したのも「文学の志しがあるから宜しくたのむ」と、いうことで、俳句をしたいというわけではなかったらしい。本心は小説を書きたかったらしい。虚子は俳句を軽蔑していたのに、子規が俳句を作るので自然と俳句を作るようになった。「我が輩は猫である」がホトトギスに載る。漱石が小説家としてどんどん有名になっていく。
「漱石のその後の小説を先生はどういう風に感じられますか」と、弟子の深見けん二。虚子のこの質問に対する答えは、愉快である。「漱石の作品は高いのもがあります。だが、写生文という見地からは同調しかねるものもあります。」さーすが、客観写生の虚子先生である。そして、虚子は小説を書いたのである。けん二は、虚子の小説を「写生文」と、言い切っていろいろ質問しているが、虚子は「小説というより写生文という方がいいかもしれません」と答えているが小説の中ではという意味で言っているのである。「写生文は事実を曲げてはいけない。事実に重きをおかなければならない。その上に、心の深みがあらわれるように来るようにならなければならない。私は写生文からはいって行く小説というものを考えています」と、フィクションを否定している。花鳥諷詠の説明を聞いてるようだ。
「ただ、今のところ文壇からみれば傍流であって、この流れは、現在では、まだ大きな流れではありませんが、しかし、将来は本流と合体するかも知れないし...」ごにょごにょ....。あは。虚子先生、負けん気が強いですね。そして、小説への憧れがいじらしい。
「お父さん、最近『虹』とか、『椿物語』とか、いろいろの範囲の女性を書かれるようですが、お父さんの女性観といったのもをひとつ」と、秦に聞かれた。
「さあ、私は女の人と深くつきあっていませんからね。..小説家といっても、そんなに、女の人と深くつきあうことは出来んでしょう。大抵は、小説家が、自分で作ってしまうのでしょう。」
「里見さんなんかは、そうでもないらしいんですが」と、今井千鶴子。
「少しはつき合わないと書けないのでしょうか」と、なんとカワユイきょしせんせい。
虚子先生は、やはり小説より俳句ですよね。きっぱり。
(余白に)
☆ここのところでは、「虚子は、子規のところに手紙を出したのも『文学の志しがあるから宜しくたのむ』と、いうことで、俳句をしたいというわけではなかったらしい。本心は小説を書きたかったらしい。虚子は俳句を軽蔑していたのに、子規が俳句を作るので自然と俳句を作るようになった」というところは、いわゆる、子規と虚子との「道灌山事件」の背景を知る上で、非常に重要なものと思われる。すなわち、子規の在世中には、虚子は、「俳句を軽蔑していて、文学=小説」という考えを持っていて、「小説家」になろうとする道を選んでいた。そして、子規も当初は小説家を夢見ていたのであるが、幸田露伴に草稿などを見て頂いて、余り色よい返事が貰えず、当初の小説家の夢を断念して、俳句分類などの「古俳諧」探求への俳句の道へと方向転換をしたのであった。そういうことが背景にあって、虚子は、「文学者になるためには、何よりも学問をすることだ」と説く子規に、「厭でたまらない学問をしてまで文学者になろうとは思わない」と、いわゆる、子規の「後継委嘱」を断るという、これが、「道灌山事件」の真相だということなのであろう。そして、子規没後、子規の「俳句革新」の承継は、碧梧桐がして、虚子は小説家の道を歩むこととなる。しかし、虚子の小説家の道は、なかなか思うようにはことが進まなかった。そんなこともあって、たまたま、当時の碧梧桐の第一芸術的「新傾向俳句」を良しとはせず、ここは、第二芸術的な「伝統俳句」に立ち戻るべしとして、再び、俳句の方に軸足を移して、何時の間にやら、「虚子の俳句」、イコール、「俳句」というようになっていったということが、大雑把な見方であるが、その後の虚子の生き様と日本俳壇の流れだったといえるのではなかろうか。そして、上記のネット記事の紹介にもあるとおり、虚子は、その当初の、第一芸術の、「文学」=「小説」、その小説家の道は断念せず、その創作活動を終始続けていたというのが、俳壇の大御所・虚子の、もう一つの素顔であったということは特記しておく必要があろう。
虚子の亡霊(五十三) 道灌山事件(その五)
前回に続いて、下記のアドレスの、「小さな耳鼻科診療所での話です」の、その続きである。ここに、桑原武夫の「俳句第二芸術論」ではなく、「虚子の散文」と題する一文が紹介されていたのである。
「小さな耳鼻科診療所での話です」(続き)
http://www.geocities.jp/kayo_clinic/geodiary.311-320.html
初心者が考える俳句とは、について書いてみようと思ったのだが、虚子先生の小説に話が流れたので、続けてみよう。(昨日、早速ありがたい読者から、「虚子は食えない男だと思う。まさに自分でも詠んでいるように『悪人』だね。」という忠告あり。いいえ、恋人にするつもりないから.......御安心を!)
「ただ、今のところ文壇からみれば傍流であって、..」と、自分の小説を虚子先生らしからぬ弱きでつぶやいているのだが、なんと、虚子の小説に大賛辞を送っている人がいたんですね。(百鳥2001 10月号『虚子と戦争』渡辺伸一郎著参考)
誰だと思いますか?桑原武夫。わかりますね、あの俳句第二芸術論を発表した(「世界」昭和22年)桑原武夫です。曰く、現代俳句は、その感覚や用語がせまい俳壇の中でしか通用しないきわめて特殊なものである。普遍的な享受を前提とする「第一芸術」でなく、「第二芸術」とされるものであると、主張しました。これに対して当時、俳壇は憤然としたそうです。
読者の指摘どうり「食えない男」の虚子先生は「いいんじゃあないの。自分達が俳句を始めたころは、せいぜい第二十芸術ぐらいだったから、それを十八級特進させてくれたんだから結構なことじゃあないか」と、涼しい顔をしていたとか。でも、これって大人の余裕というより本音かもしれませんね。俳句を軽蔑していたと、御本人が言っているくらいですから。第一、ウイットで返すという御性格でもなさそうだしィ。
その、俳壇にとって憎き相手の桑原博士が、虚子の小説を誉めたのです。(「虚子の散文」と題して東京帝国大学新聞に掲載された。1934年1月)
「私はいまフランスものを訳しているが、その分析的な文章に慣れた眼でみると、日本文は解体するか、いきづまるものが多いのだが、この文章(ホトトギスに掲載された『釧路港』1933年)ばかりは強靱で、それを支える思想がよほどしっかりしている。その点はモーパッサンに匹敵し、フランス写実派の正統はわが国ではそれを受け継いだはずの自然主義作家よりも、むしろ当時その反対の立場にあった人によって示されたくらいだ。....著者は句と文とによって、はっきり態度を違えて立ち向かっている。.....これは、珍しい例ではないかと思う。詩人の文章はどうしても詠嘆的になりがちで、文章をささえる思想が感情になりやすい。......観察写実から出発した作家は完成に近づくと、無私の眼をもって見た澄明な景色のうちに何か不気味なものを感じさせるものである。そして、人間の感情にしてもむしろ冷淡な意地悪なものがよけいに沁み出る傾向がある。....」と、エールを送っている。もちろん、この文章は、ホトトギスに転載された。虚子先生の「最後には勝つ」という人生観に、更に自信をもたれたでしょうね。そうだ、桑原武夫も同じく、虚子先生はイジワルと決めつけている。
ここで、不思議なのは、桑原武夫が書いている「著者は句と文とによって、はっきり態度を違えて立ち向かっている。.....これは、珍しい例ではないかと思う。」という下りである。
虚子は「写生文は事実を偽って書くのは卑怯ですよ。写生文がそういう根底に立ってそれが積み重なって、自然に小説としての構成を成してくるのは差し支えないでしょう。....面白くするために容易に事実を曲げるということはしない。」と言っている小説観と、口すっぱく主張している「客観写生」は、意味するところが共通しており「態度を違えて」ないのではなかろうか。
「客観写生ということに努めていると、その客観描写を透して主観が浸透して出てくる。作者の主観は隠すことが出来ないのであって客観写生の技量が進むにつれて主観が擡げてくる。」この虚子の主張と矛盾しないように思うし、あまりにも虚子らしい文章観であり散文であると思ったのであるが、いかがであろう。そして、あっぱれな頑固者だなとも思ったのだが.....。
(余白に)
☆これまでに数多くの「虚子論」というものを目にすることができるが、それらの多くは、どう足掻いても、田辺聖子の言葉でするならば、「虚子韜晦」と、その全貌を垣間見ることすらも困難のような、その「実像と虚像」との狭間に翻弄されている思いを深くさせられるものが多いのである。それらに比すると、上記の「小さな耳鼻科診療所での話です」と題するものの、この随想風のネット記事のものは、「高浜虚子」の一番中核に位置するものを見事に見据えているという思いを深くするのである。それと同時に、このネット記事で紹介されている、いわゆる「俳句第二芸術論」の著者の桑原武夫という評論家も、正しく、虚子その人を見据えていたという思いを深くする。桑原が、上記の「虚子の散文」という一文は、戦前も戦前の昭和九年に書かれたもので、桑原が「俳句第二芸術論」を草したのは、戦後のどさくさの、昭和二十一年のことであり、桑原は、終始一貫して、「俳人・小説家」としての「高浜虚子」という人を見据え続けてきたといっても差し支えなかろう。
その「小説家」(散文)の「虚子」の特徴として、「この文章(ホトトギスに掲載された『釧路港』1933年)ばかりは強靱で、それを支える思想がよほどしっかりしている。その点はモーパッサンに匹敵」するというのである。この虚子の文章(そしてその思想)の「強靱さ」(ネット記事の耳鼻咽喉科医の言葉でするならば「頑固者」)というのは、例えば、子規の「後継委嘱」を断り、子規をして絶望の局地に追いやったところの、いわゆる「道灌山事件」の背後にある最も根っ子の部分にあたるところのものであろう。この虚子の「強靱さ」(「頑固者」)というものをキィーワードとすると、虚子に係わる様々な「謎」が解明されてくるような思いがする。すなわち、子規と虚子との「道灌山事件」の謎は勿論、碧梧桐との「新傾向俳句」を巡る対立の謎も、秋桜子の「ホトトギス脱会」の背景の謎も、さらにまた、杉田久女らの「ホトトギス除名」の真相を巡る謎も、全ては、虚子の頑なまでの、その「強靱さ」(「頑固者」)に起因があると言って決して過言ではなかろう。
さらに、桑原の、「詩人の文章はどうしても詠嘆的になりがちで、文章をささえる思想が感情になりやすい。… 観察写実から出発した作家は完成に近づくと、無私の眼をもって見た澄明な景色のうちに何か不気味なものを感じさせるものである。そして、人間の感情にしてもむしろ冷淡な意地悪なものがよけいに沁み出る傾向がある」という指摘は、これは、実に、「虚子」その人と、その「創作活動」(小説と俳句)の中心を、見事に射抜いている、けだし、達眼という思いを深くするのである。このことは、上記のネット記事の基になっている、虚子の『俳句への道』の「研究座談会」のものですると、すなわち、虚子の句に対しての平畑静塔の言葉ですると、「痴呆的」という言葉と一致するものであろう。この、桑原の言葉でするならば、「無私の眼をもって見た澄明な景色のうちに何か不気味なものを感じさせるものである。そして、人間の感情にしてもむしろ冷淡な意地悪なものがよけいに沁み出る傾向がある」という指摘は、これこそ、「虚子の実像」という思いを深くするのである。これこそ、虚子と秋桜子とを巡る虚子の小説の「厭な顔」、そして、虚子と久女を巡る「久女伝説」を誕生させたところの虚子の小説の「国子の手紙」の根底に流れているものであろう。
虚子の亡霊(五十四) 道灌山事件(その六)
今回も、「小さな耳鼻科診療所での話です」の、その続きである。
http://www.geocities.jp/kayo_clinic/geodiary.311-320.html
「小さな耳鼻科診療所での話です」(続き)
虚子先生の「俳句への道」を頭をたれながら正座して読んでいたのである(ほんまかな)が、虚子大先生をぼろくそに無視(?)する評論家もいるようです。
「俳句の世界」(講談社学術文庫)の、小西甚一氏。「実は、虚子の写生は看板であって、中味はかなり主観的なものを含み、しかもその把握は伝統的な季題趣味を多く出なかった。木の実植うといへば直ちに人里離れた場所、白い髭をのばした隠者ふうの人物などを連想する行き方で、碧梧桐とは正反対の立場である。子規が第一芸術にしようと努めたのもを第二芸術にひきもどしたのである。」言いますね、コニシさん。
小西氏は、どうも楸邨と友人関係、その師と縁戚関係にあり、私情がたぶんに入った評論のようにも思うが、たぶんに半官びいきにも聞える。虚子のライバルとされた、結果的に俳句界に大きな足跡を残さなかった碧梧桐からの流れをくむ自由律の俳句への応援は温かい。ただ、「定型俳句があっての自由律俳句でなんでしてね。父親の脛を齧ることによって父親無用論を主張できる道楽息子と別ものではありません。」と、その限界を述べている。
ところが、虚子は「俳句への道」のなかで、「自らいい俳句を作らないで。俳句論をするものがある。そういうのは絶対に資格がない。俳句では。作る人が論ずる人であり得ない場合は多いが、論ずる人は、作家であるべきである。」と、痛快に反論しているので、これも愉快である。(小西氏も激辛評論の阿部氏も俳句作者としては、凡作の域をでなかったようだ。)
また、俳句を作る者に対しても理論を先立てることを戒めている。「私は理論はあとから来るほうがいいと考えている。少なくとも創作家というのもはそうあるべきものだと考えている。理論に導かれて創作をしようと試むるのもは迫力のあるものは出来ない。それよりも何物かに導かれるような感じの上に何ものも忘れて創作をする。出来て後にその創作の中から理論を見出す。創作家の理論というのはそんなものであるべきだと思う。」だそうな。
ということで、資格のないセンセの俳談は終わり。...
(余白に)
☆ここで、小西甚一著『俳句の世界』(講談社学術文庫)について触れられている。この著は、後世に永く伝えられる名著の部類に入るものであろう。その裏表紙に、編集子のものと思われる、次のような一文が付せられている。
○名著『日本文藝史』に先行して執筆された本書において、著者は「雅」と「俗」の交錯によって各時代の芸術が形成されたとする独創的な表現意識史観を提唱した。俳諧連歌の第一句である発句と、子規による革新以後の俳句を同列に論じることの誤りをただし、俳諧と俳句の本質的な差を、文学史の流れを見すえた鋭い史眼で明らかにする。俳句鑑賞に新機軸を拓き、俳句史はこの一冊で十分と絶讃された不朽の書。
確かに、こういうものは、「不朽の書」といえるものなのであろうが(また、この著者の業績は、この著書の解説者の平井照敏氏が記しているとおり、「大碩学」の名が最も相応しいのかも知れないが)、それでもなおかつ、この著者以後の者は、この著を乗り越えていかなければならないのであろう。
そういう観点に立って、この著の「高浜虚子」関連(「碧梧桐の新傾向と虚子の保守化」)のみに焦点を絞って、それをつぶさに見ていくと、この著者一流の、連句でいうところの、ここは「飛躍し過ぎではないか」というところが、散見されるように思われるのである。これらのことについて、稿を改めて、その幾つかについて見ていくことにする。
(子規・二十九歳。日清戦争従軍記者となり、帰途中に喀血。五月、神戸の病院に入院。室月、須磨保養院に移り、八月帰省。松山中学校教師として赴任した、漱石の「愚垜仏庵」に奇遇、地元の「松風会」の句作を指導。十月、奈良・京都を経て帰京。十二月、道灌山で虚子に後継を委託するも断られる。)
朧とは桜の中の柳かな ID639 制作年23 季節春 分類天文 季語朧
烏帽子きた殿居姿の朧なり ID1712 制作年25 季節春 分類天文 季語朧
面顔の声朧也春の陣 ID1713 制作年25 季節春 分類天文 季語朧
白き山青き山皆おぼろなり D1714 制作年25 季節春 分類天文 季語朧
朧より朧に人の咄かな ID4977 制作年26 季節春 分類天文 季語朧
小夜更て上戸の声の朧なり ID4978 制作年26 季節春 分類天文 季語朧
昼の月さらに朧と見えぬなり ID4979 制作年26 季節春 分類天文 季語朧
行燈を消せば小窓の朧かな ID12700 制作年28 季節春 分類天文 季語朧
男やら女やら更に朧かな ID15975 制作年29 季節春 分類天文 季語朧
ある夜更けて貴人来ます朧哉 ID19236 制作年30 季節春 分類天文 季語朧
茶屋を出る箱提灯や朧人 ID19237 制作年30 季節春 分類天文 季語朧
京の灯や朧の上る東山 ID20862 制作年31 季節春 分類天文 季語朧
吾折々死なんと思ふ朧かな ID23383 制作年33 季節春 分類天文 季語朧
朧野ヤ朧ヲ破ル藁砧 ID24683 制作年35 季節春 分類天文 季語朧
末遂ゲヌ恋ノ始ヤオボロナル ID24684 制作年35 季節春 分類天文 季語朧
背ノ高キ人佇メリ朧陰 ID24685 制作年35 季節春 分類天文 季語朧
背ノ高キ人ニ逢ヒケル朧哉 ID24686 制作年35 季節春 分類天文 季語朧
大仏ノ目ニハ吾等モ朧カナ ID24687 制作年35 季節春 分類天文 季語朧
遠クトモ近クトモ見エテ灯朧 ID24688 制作年35 季節春 分類天文 季語朧
篷アゲテ見ル両岸ノ朧カナ ID24689 制作年35 季節春 分類天文 季語朧
話シナガラ土手ノ上行ク人朧 ID24690 制作年35 季節春 分類天文 季語朧
見返レバ住吉ノ灯ノ朧ナル ID24691 制作年35 季節春 分類天文 季語朧
闇ヲ出テ朧ニ人ノ陰二ツ ID24692 制作年35 季節春 分類天文 季語朧
両岸ノ人家朧ニ下リ舟 ID24693 制作年35 季節春 分類天文 季語朧
路次口ヲ出デヽ朧ノ大路カナ ID24694 制作年35 季節春 分類天文 季語朧
(漱石・二十九歳。四月、松山中学校教師として赴任。六月、松山市二番町の「愚陀仏庵」。八月、子規が寄寓して、十月に帰省するまで作句に励む。「子規宛句稿が始まる(一~九)。東洋城、松山在学中に漱石に英語を教わる。)
511 いそがしや霰ふる夜の鉢叩
512 十月の月ややうやう凄くなる
513 山茶花の垣一重なり法華寺
514 行く年や膝と膝とをつき合せ
515 雪深し出家を宿し参らする
516 詩神とは朧夜に出る化ものか
≪ 季=朧夜(春)。※漱石は虚子の「松山的ならぬ淡泊なる処、のんきなる処、気の利かぬ処」などを愛した(子規宛書簡)。(後略) ≫(『漱石全集第十七巻・坪内稔典注解』)
(寅彦・十八歳)
朧夜や湯殿の窓の磨硝子(すりがらす)(明治三十四年作。二十四歳)
湯煙りの白粉臭き朧かな (同上)
(東洋城・十八歳)
わたつみへ浪を巻きさる朧かな (明治三十四年作。二十四歳)
三軒家橋の人呼ぶ朧かな (同上、前書「嵐山」)
(参考)「道灌山事件(その一)~(その六)」周辺

「道灌山事件(明治二十八年)」当時の「高浜虚子」
https://plaza.rakuten.co.jp/akiradoinaka/diary/201803220000/
http://yahantei.blogspot.com/2008/06/blog-post_01.html
(再掲)「道灌山事件(その一)~(その六)」
虚子の亡霊(四十九~五十四)
虚子の亡霊(四十九) 道灌山事件(その一)
ホトトギス「百年史」の年譜は「明治三十年一月 柳原極堂、松山で『ほとゝぎす』創刊」より始まり、明治二十八年の子規と虚子との「道灌山事件」の記載はない。ここで、「子規年譜」の当該年については、下記のとおりの記述がある。
http://www2a.biglobe.ne.jp/~kimura/siki01.htm
(子規略年譜)
明治28年(1895) 28歳
4月、日清戦争従軍記者として遼東半島に渡り、金州、旅順に赴く。金州で藤野古曰の死を知る。「陣中日記」を『日本』に連載する。5月4日、従軍中の森鴎外を訪ねる。17日、帰国の船中で喀血。23日、神戸に上陸し、直ちに県立神戸病院に入院。一時重体に陥る。7月、須磨保養院に転院。8月20日退院。28日、松山の漱石の下宿に移り50日余を過ごす。極堂ら地元の松風会会員と連日句会を開き、漱石も加わる。10月、松山を離れ、広島、大阪、奈良を経て帰京。12月、虚子を誘って道灌山へ行き、自らの文学上の後継者となることを依頼するが断られる。
http://www.shikian.or.jp/sikian2.htm
この十二月の、「虚子を誘って道灌山へ行き、自らの文学上の後継者となることを依頼するが断られる」というのが、いわゆる「道灌山事件」と呼ばれるもので、次のアドレスのもので、その全容を知ることができる。
http://www5e.biglobe.ne.jp/~haijiten/haiku9-1.htm
☆俳句史などには「道灌山事件」などと呼ばれているが、事件というほどの物ではない。道灌山事件とは明治二十八年十二月九日(推定)道灌山の茶店で子規が虚子に俳句上の仕事の後継者になる事を頼み、虚子がこれを拒絶したという出来事である。ことはそれ以前の、子規が日清戦争の従軍記者としての帰途、船中にて喀血した子規は須磨保養院において療養をしていた。その時、短命を悟った子規は虚子に後事を託したいと思ったという。その当時、虚子は子規の看護のため須磨に滞在していたのだ。明治二十八年七月二十五日(推定)、須磨保養院での夕食の時の事、明朝ここを発って帰京するという虚子に対して「今度の病気の介抱の恩は長く忘れん。幸いに自分は一命を取りとめたが、併し今後幾年生きる命かそれは自分にも判らん。要するに長い前途を頼むことは出来んと思ふ。其につけて自分は後継者といふ事を常に考へて居る。(中略)其処でお前は迷惑か知らぬけれど、自分はお前を後継者と心に極めて居る。」(子規居士と余)と子規は打ち明ける。この子規の頼みに対して、虚子は荷が重く、多少迷惑に感じながらも、「やれる事ならやってみよう。」と返答したという。併し子規は虚子の言葉と態度から「虚子もやや決心せしが如く」と感じたらしく、五百木瓢亭宛の書簡に書いている。そして明治二十八年十二月九日、東京に戻っていた子規から虚子宛に手紙が届く。虚子は根岸の子規庵へ行ってみたところ、子規は少し話したい事がある。家よりは外のほうが良かろう、という事で二人は日暮里駅に近い道灌山にあった婆(ばば)の茶店に行くことになった。その時子規は「死はますます近づきぬ文学はようやく佳境に入りぬ」とたたみ掛け、我が文学の相続者は子以外にないのだ。その上は学問せよ、野心、名誉心を持てと膝詰め談判したという。しかし虚子は「人が野心名誉心を目的にして学問修行等をするもそれを悪しとは思わず。然れども自分は野心名誉心を起こすことを好まず」と子規の申し出を断ったという。数日後に虚子は子規宛に手紙を書き、きっちりと虚子の態度を表明している。「愚考するところによれば、よし多少小生に功名の念ありとも、生の我儘は終に大兄の鋳形にはまること能はず、我乍ら残念に存じ候へど、この点に在っては終に見棄てられざるを得ざるものとせん方なくも明め申候。」これに対して子規は瓢亭あての書簡に「最早小生の事業は小生一代の者に相成候」「非風去り、碧梧去り、虚子亦去る」と嘆いたという。道灌山事件の事は直ぐには世間に知らされず、かなり後に虚子が碧梧桐に打ち明けて話し、子規の死後、瓢亭の子規書簡が公表されてから一般に知られるようになったそうである。
(参考) 清崎敏郎・川崎展宏「虚子物語」有斐閣ブックス 宮坂静生著「正岡子規・死生観を見据えて」明治書院
上記が、いわゆる「道灌山事件」の全容なのであるが、その後、子規自身も、「獺祭書屋俳句帖上巻を出版するに就きて思ひつきたる所をいふ」などで、虚子も、「子規居士と余」などで、この「道灌山事件」については記述しているのであるが、「何故に、子規と虚子とで決定的に意見が相違して、何故に、虚子は頑なに子規の依頼を拒絶したのか」という、その真相になると、これがどうにもウヤムヤなのである。
このウヤムヤの所に、前回までの、虚子は「芸能・文芸としての俳句」という「第二芸術的」な俳句観を有していたのに、子規は「芸術・文学としての俳句」、すなわち、「第一芸術的」な俳句観を、虚子に無理強いをしたので、虚子はこれを拒絶する他は術がなかったと理解すると、何となく、この子規と虚子との「道灌山事件」の背景が見えてくるような思いがするのである。
虚子の亡霊(五十) 道灌山事件(その二)
子規と虚子との「道灌山事件」というのは、明治二十八年と、もはや遠い歴史の中に埋没したかに思えたのだが、この平成十六年に、『夕顔の花——虚子の連句論——』(村松友次著)が刊行され、全く新しい視点での「道灌山事件」の背景を論述されたのであった。この「全く新しい視点」ということは、その「あとがき」の言葉でするならば、
「子規の連句否定論」と「虚子の連句肯定論」との対立が、「道灌山事件」の背景とするところの、とにもかくにも大胆な推理と仮説とに基づくものを指していることに他ならない。
この「子規の連句否定論」と「虚子の連句肯定論」との対立の推理と仮説は、さらに、例えば、子規の『俳諧大要』の最終尾の「連句」の項の、「ある部分は、子規の依頼の下でゴーストライターとして虚子が書いているのではなかろうか」(同書所収「『俳諧大要』(子規)最終尾の不審」)と、さらに大胆な推理と仮説を提示することとなる。
この著者は、古典(芭蕉・蕪村・一茶など)もの、現代(素十など)もの、連句(芭蕉連句鑑賞など)ものと、こと、「古典・連句・俳句・ホトトギス」全般にわたって論述することに、その最右翼に位置することは、まずは多くの人が肯定するところであろう。そして、通説的な見解よりも、独創的な異説などもしばしば見られ、例えば、その著の『蕪村の手紙』所収の、「『北寿老仙をいたむ』の製作時期」・「『北寿老仙をいたむ』の解釈の流れ」などの論稿は、今や、通説的にもなりつつ状況にあるといっても過言ではなかろう。
虚子・素十に師事し、俳誌 「雪」を主宰し、「ホトトギス」同人でもあり、東洋大学の学長も歴任した、この著者が、最新刊のものとして、この『夕顔の花——虚子の連句論——』を世に問うたということは、今後、この著を巡って、どのように、例えば、子規と虚子との「道灌山事件」などの真相があばかれていくのか、大変に興味のそそられるところである。
ここで、ネット記事で、東大総長・文部大臣も歴任した現代俳人の一躍を担う有馬朗人の上記の村松友次のものと交差する「読売新聞」での記事のものを、次のアドレスのものにより紹介をしておきたい。
http://art-random.main.jp/samescale/085-1.html
☆正岡子規は俳諧連句の発句を独立させて俳句とした。と同時に多数の人で作る連句は、西欧の個人主義的芸術論に合わないと考え切り捨てたのである。一方子規の第一の後継者である虚子は連句を大切にしていた。---子規が虚子に後継者になってくれと懇願するが、虚子が断ったという有名な道灌山事件のことである。その結果、子規は虚子を破門したと思われるにもかかわらず、一生両者の親密な関係は代わらなかった。
「読売新聞」2004.08.08朝刊 有馬朗人「本よみうり堂」より抜粋。
虚子の亡霊(五十一) 道灌山事件(その三)
この「道灌山事件」とは別項で、「虚子・年尾の連句論」に触れる予定なので、ここでは、『夕顔の花——虚子の連句論——』(村松友次著)の詳細については後述といたしたい。そして、ここでは、明治二十八年の「道灌山事件」の頃の子規の句について、
次のアドレス(『春星』連載中の中川みえ氏の稿)のものを紹介しておきたい。
http://www.geocities.co.jp/Hollywood-Kouen/9280/shikiku/shikiku5.htm#shikiku52
☆ 語りけり大つごもりの来ぬところ 子規
漱石虚子来る
漱石が来て虚子が来て大三十日 同上
漱石来るべき約あり
梅活けて君待つ庵の大三十日 同上
足柄はさぞ寒かったでこざんしよう 同上
明治二十八年作。
漱石はこの年五月、神戸病院に入院中の子規に、病気見舞かたがた「小子近頃俳文に入らんと存候。御閑暇の節は御高示を仰ぎたく候」と手紙で言って来た。第一回の句稿を九月二十三日に送って来たのを嚆矢として、三十二年十月十七日まて三十五回に渡って膨大な数の句を子規のもとに送って、批評と添削を乞うた。
粟津則雄氏は「漱石・子規往復書簡集」(和田茂樹編)の解説でこのことに触れて、
ロンドン留学の前年、明治三十二年の十月まで、これほどの数の句稿を送り続けるのは、ただ作句熱と言うだけでは片付くまい。もちろん、ひとつには、俳句が、手紙とちがって、自分の経験や印象や感慨を端的直載に示しうるからだろうが、同時にそこには、病床の子規を楽しませたいという心配りが働いていたと見るべきだろう。
と述べておられる。
漱石は句稿に添えた手紙の中で、この年十二月に上京する旨伝えて来た。この時期漱石には縁談があって、そのことなども子規に手紙で相談していたようである。
漱石は十二月二十七日に上京して、翌日、貴族院書記官長中根重一の長女鏡子と見合をし、婚約した。
大みそかに訪ねて来るという漱石を、子規は梅を活けて、こたつをあたためて、楽しみに持っていたのである。
大みそかには虚子も訪ねてきた。
この月の幾日かに、子規は道潅山の茶店に虚子を誘い、先に須磨で言い出した後継委嘱問題を改めて切り出して、虚子の意向を問い正した。
文学者になるためには、何よりも学問をすることだ、と説く子規に、厭でたまらない学問をしてまで文学者になろうとは思わない、と虚子は答えた。会談は決裂した。
子規と虚子の間は少々ぎくしゃくしたが、それでも大みそかに虚子はやって来た。子規は最も信頼する友漱石と、一番好きてあった虚子の来訪を心待ちにしていたのである。
漱石は一月七日まで東京に滞在して、子規庵初句会(一月三日)にも出席した。
この年を振り返って、子規は次のように記している。
明治二十八年といふ歳は日本の国が世界に紹介せられた大切な年であると同時に而かも反対に自分の一身は取っては殆ど生命を奪はれた程の不吉な大切な年である。しかし乍らそれ程一身に大切な年であるにかかはらず俳句の上には殆ど著しい影響は受けなかった様に思ふ。(略)幾多の智識と感情とは永久に余の心に印記せられたことであらうがそれは俳句の上に何等の影響をも及ぼさなかった。七月頃神戸の病院にあって病の少しく快くなった時傍に居た碧梧桐が課題の俳句百首許りを作らうと言ふのを聞て自分も一日に四十題許りを作った。其時に何だか少し進歩したかの様に思ふて自分で嬉しかつたのは嘘であらう。二ヶ月程も全く死んで居た俳句が僅かに蘇ったと云ふ迄の事て此年は病余の勢力甚だ振はなかった。尤も秋の末に二三日奈良めぐりをして矢鱈に駄句を吐いたのは自分に取っては非常に嬉しかった。(獺祭書屋俳句帖上巻を出版するに就きて思ひつきたる所をいふ)
時に、子規、二十九歳、漱石、二十九歳、虚子は若干二十二歳であった。当時の虚子は、虚子の言葉でするならば、「放浪の一書生」(『子規居士と余』)で、今の言葉でするならば、「ニート族」(若年無業者)の代表格のようなものであろう。子規とて、書生上がりの「日本新聞」などの「フリーター」(請負文筆業)という趣で、漱石はというと、丁度、その小説の「坊っちゃん」の主人公のように、松山中学校の英語の教師という身分であった。しかし、この三人が、いや、この三人を取り巻く、いわば、「子規塾」の面々が、日本の文化・芸術・文学の一翼を担うものに成長していくとは、
誠に、何とも痛快極まるものと思えてならない。そして、これも、虚子の言葉なのであるが、子規をして、「余はいつも其事を思ひ出す度に人の師となり親分となる上に是非欠くことの出来ぬ一要素は弟子なり子分なりに対する執着であることを考へずにはゐられぬのである」(前掲書)という、この子規の存在は極めて大きいという感慨を抱くのである。
ここらへんのことについて、先に紹介した次のアドレスで、これまた、「読売新聞」のコラムの記事を是非紹介をしておきたい。
http://art-random.main.jp/samescale/085-1.html
☆高浜虚子には、独特なユーモアをたたえた句がある。5枚の葉をつけた、ひと枝だの笹がある。「初雪や綺麗に笹の五六枚」等々、葉の1枚ずつに俳句が書かれている。東京にいた24歳の正岡子規が郷里・松山の友、17歳の高浜虚子に贈った。「飯が食えぬから」と虚子が文学の志を捨てようとしているらしい。人づてに聞いた子規がこの笹を添えて手紙を送ったのは、1982年1月のことである。「食ヘヌニ困ルト仰セアラバ 小生衰ヘタリト雖 貴兄ニ半碗ノ飯ヲ分タン」。「目的物ヲ手ニ入レル為ニ費スベキ最後ノ租税ハ 生命ナリ」。3年前に血を吐き、四年後には病床につく人が友に寄せた言葉は、悲しいまでに温かい。この笹の枝を子規は、「心竹」と呼んでいる。ささ(笹)いな贈り物だという。心の丈でもあったのだろう。虚子の胸深くに心竹は根を張り、近代詩歌の美しい実りとなった詩業を支えたに違いない。
「読売新聞」2004.01.01朝刊「編集手帳」より抜粋。
虚子の亡霊(五十二) 道灌山事件(その四)
ネットの記事は雲隠れをするときがある。一度、雲隠れをしてしまうとなかなか出てこない。かつて、「俳句第二芸術論」について触れていたときに、桑原武夫が高浜虚子の、俳句ではなく、その小説について褒めたことがあり、その桑原の初評論ともいえるようなものが、虚子の「ホトトギス」に掲載されたことがあり、その桑原のものを、ネットの記事で見た覚えがあるのだが、どうにも、それが雲隠れして、それを探すことができなかったのである。
それが、しばらく、この虚子のものを休んでいたら、まるでその休みを止めて、また続けるようにとの催促をするように、そのネット記事が偶然に眼前に現れてきたのである。その記事は、次のアドレスのもので、「小さな耳鼻科診療所での話です」というタイトルのブログ記事のものであったのだ。今度は、雲隠れしないように、その前後の関連するところを、ここに再掲をしておくこととしたい。
http://www.geocities.jp/kayo_clinic/geodiary.311-320.html
317.俳談(その一)
センセは、俳句をすなる。パソコンを使い始めて5年。俳句を始めて4年。ちょうど、「俳句とは」を考えたくなる時期にきたようだ。
乱雑に突っ込まれた本棚を見てみると、それなりに俳句入門の本が並んでいる。鷹羽狩行、稲畑汀子、阿部肖人、藤田湘子、我が師匠の大串章。先生方の言わんとされることが理解できれば俳句ももう少し上手くなれたのであろうか。句集もそれなりに積んである....
悪あがきついでに「俳句への道」高浜虚子(岩波文庫)を読むことにした。本の後半の研究座談会が面白そうだったので、そこから読み始めた。ところが、いきなりこんな文に出会った。
「近頃の人は、四五年俳句を作って見て、すぐ、『俳句とは』という議論をしたがる。そういう人が多い。こういう人は長続きしない。やがてその議論はかげをひそめるばかりかその人もかげをひそめる。」と、ある。ガーン!!!虚子先生は厳しい。
とはいえ、「私はしばらく俳論、俳話のやうなものは書かないでをりました。..」と、いいながら「玉藻」(主宰、星野立子)に、俳話を載せた。(昭和27年)ここでの俳論、俳話がまとめられたのが、この文庫である。「私の信じる俳句というのもは斯様なのもであるということを書き残して置くのもである。」と序にある。
なんたってセンセはミーハーである。いくら大虚子先生のお話でも、まず、愉快そうなところかに目をつける。まず、研究座談会の章から。
虚子は、子規のところに手紙を出したのも「文学の志しがあるから宜しくたのむ」と、いうことで、俳句をしたいというわけではなかったらしい。本心は小説を書きたかったらしい。虚子は俳句を軽蔑していたのに、子規が俳句を作るので自然と俳句を作るようになった。「我が輩は猫である」がホトトギスに載る。漱石が小説家としてどんどん有名になっていく。
「漱石のその後の小説を先生はどういう風に感じられますか」と、弟子の深見けん二。虚子のこの質問に対する答えは、愉快である。「漱石の作品は高いのもがあります。だが、写生文という見地からは同調しかねるものもあります。」さーすが、客観写生の虚子先生である。そして、虚子は小説を書いたのである。けん二は、虚子の小説を「写生文」と、言い切っていろいろ質問しているが、虚子は「小説というより写生文という方がいいかもしれません」と答えているが小説の中ではという意味で言っているのである。「写生文は事実を曲げてはいけない。事実に重きをおかなければならない。その上に、心の深みがあらわれるように来るようにならなければならない。私は写生文からはいって行く小説というものを考えています」と、フィクションを否定している。花鳥諷詠の説明を聞いてるようだ。
「ただ、今のところ文壇からみれば傍流であって、この流れは、現在では、まだ大きな流れではありませんが、しかし、将来は本流と合体するかも知れないし...」ごにょごにょ....。あは。虚子先生、負けん気が強いですね。そして、小説への憧れがいじらしい。
「お父さん、最近『虹』とか、『椿物語』とか、いろいろの範囲の女性を書かれるようですが、お父さんの女性観といったのもをひとつ」と、秦に聞かれた。
「さあ、私は女の人と深くつきあっていませんからね。..小説家といっても、そんなに、女の人と深くつきあうことは出来んでしょう。大抵は、小説家が、自分で作ってしまうのでしょう。」
「里見さんなんかは、そうでもないらしいんですが」と、今井千鶴子。
「少しはつき合わないと書けないのでしょうか」と、なんとカワユイきょしせんせい。
虚子先生は、やはり小説より俳句ですよね。きっぱり。
(余白に)
☆ここのところでは、「虚子は、子規のところに手紙を出したのも『文学の志しがあるから宜しくたのむ』と、いうことで、俳句をしたいというわけではなかったらしい。本心は小説を書きたかったらしい。虚子は俳句を軽蔑していたのに、子規が俳句を作るので自然と俳句を作るようになった」というところは、いわゆる、子規と虚子との「道灌山事件」の背景を知る上で、非常に重要なものと思われる。すなわち、子規の在世中には、虚子は、「俳句を軽蔑していて、文学=小説」という考えを持っていて、「小説家」になろうとする道を選んでいた。そして、子規も当初は小説家を夢見ていたのであるが、幸田露伴に草稿などを見て頂いて、余り色よい返事が貰えず、当初の小説家の夢を断念して、俳句分類などの「古俳諧」探求への俳句の道へと方向転換をしたのであった。そういうことが背景にあって、虚子は、「文学者になるためには、何よりも学問をすることだ」と説く子規に、「厭でたまらない学問をしてまで文学者になろうとは思わない」と、いわゆる、子規の「後継委嘱」を断るという、これが、「道灌山事件」の真相だということなのであろう。そして、子規没後、子規の「俳句革新」の承継は、碧梧桐がして、虚子は小説家の道を歩むこととなる。しかし、虚子の小説家の道は、なかなか思うようにはことが進まなかった。そんなこともあって、たまたま、当時の碧梧桐の第一芸術的「新傾向俳句」を良しとはせず、ここは、第二芸術的な「伝統俳句」に立ち戻るべしとして、再び、俳句の方に軸足を移して、何時の間にやら、「虚子の俳句」、イコール、「俳句」というようになっていったということが、大雑把な見方であるが、その後の虚子の生き様と日本俳壇の流れだったといえるのではなかろうか。そして、上記のネット記事の紹介にもあるとおり、虚子は、その当初の、第一芸術の、「文学」=「小説」、その小説家の道は断念せず、その創作活動を終始続けていたというのが、俳壇の大御所・虚子の、もう一つの素顔であったということは特記しておく必要があろう。
虚子の亡霊(五十三) 道灌山事件(その五)
前回に続いて、下記のアドレスの、「小さな耳鼻科診療所での話です」の、その続きである。ここに、桑原武夫の「俳句第二芸術論」ではなく、「虚子の散文」と題する一文が紹介されていたのである。
「小さな耳鼻科診療所での話です」(続き)
http://www.geocities.jp/kayo_clinic/geodiary.311-320.html
初心者が考える俳句とは、について書いてみようと思ったのだが、虚子先生の小説に話が流れたので、続けてみよう。(昨日、早速ありがたい読者から、「虚子は食えない男だと思う。まさに自分でも詠んでいるように『悪人』だね。」という忠告あり。いいえ、恋人にするつもりないから.......御安心を!)
「ただ、今のところ文壇からみれば傍流であって、..」と、自分の小説を虚子先生らしからぬ弱きでつぶやいているのだが、なんと、虚子の小説に大賛辞を送っている人がいたんですね。(百鳥2001 10月号『虚子と戦争』渡辺伸一郎著参考)
誰だと思いますか?桑原武夫。わかりますね、あの俳句第二芸術論を発表した(「世界」昭和22年)桑原武夫です。曰く、現代俳句は、その感覚や用語がせまい俳壇の中でしか通用しないきわめて特殊なものである。普遍的な享受を前提とする「第一芸術」でなく、「第二芸術」とされるものであると、主張しました。これに対して当時、俳壇は憤然としたそうです。
読者の指摘どうり「食えない男」の虚子先生は「いいんじゃあないの。自分達が俳句を始めたころは、せいぜい第二十芸術ぐらいだったから、それを十八級特進させてくれたんだから結構なことじゃあないか」と、涼しい顔をしていたとか。でも、これって大人の余裕というより本音かもしれませんね。俳句を軽蔑していたと、御本人が言っているくらいですから。第一、ウイットで返すという御性格でもなさそうだしィ。
その、俳壇にとって憎き相手の桑原博士が、虚子の小説を誉めたのです。(「虚子の散文」と題して東京帝国大学新聞に掲載された。1934年1月)
「私はいまフランスものを訳しているが、その分析的な文章に慣れた眼でみると、日本文は解体するか、いきづまるものが多いのだが、この文章(ホトトギスに掲載された『釧路港』1933年)ばかりは強靱で、それを支える思想がよほどしっかりしている。その点はモーパッサンに匹敵し、フランス写実派の正統はわが国ではそれを受け継いだはずの自然主義作家よりも、むしろ当時その反対の立場にあった人によって示されたくらいだ。....著者は句と文とによって、はっきり態度を違えて立ち向かっている。.....これは、珍しい例ではないかと思う。詩人の文章はどうしても詠嘆的になりがちで、文章をささえる思想が感情になりやすい。......観察写実から出発した作家は完成に近づくと、無私の眼をもって見た澄明な景色のうちに何か不気味なものを感じさせるものである。そして、人間の感情にしてもむしろ冷淡な意地悪なものがよけいに沁み出る傾向がある。....」と、エールを送っている。もちろん、この文章は、ホトトギスに転載された。虚子先生の「最後には勝つ」という人生観に、更に自信をもたれたでしょうね。そうだ、桑原武夫も同じく、虚子先生はイジワルと決めつけている。
ここで、不思議なのは、桑原武夫が書いている「著者は句と文とによって、はっきり態度を違えて立ち向かっている。.....これは、珍しい例ではないかと思う。」という下りである。
虚子は「写生文は事実を偽って書くのは卑怯ですよ。写生文がそういう根底に立ってそれが積み重なって、自然に小説としての構成を成してくるのは差し支えないでしょう。....面白くするために容易に事実を曲げるということはしない。」と言っている小説観と、口すっぱく主張している「客観写生」は、意味するところが共通しており「態度を違えて」ないのではなかろうか。
「客観写生ということに努めていると、その客観描写を透して主観が浸透して出てくる。作者の主観は隠すことが出来ないのであって客観写生の技量が進むにつれて主観が擡げてくる。」この虚子の主張と矛盾しないように思うし、あまりにも虚子らしい文章観であり散文であると思ったのであるが、いかがであろう。そして、あっぱれな頑固者だなとも思ったのだが.....。
(余白に)
☆これまでに数多くの「虚子論」というものを目にすることができるが、それらの多くは、どう足掻いても、田辺聖子の言葉でするならば、「虚子韜晦」と、その全貌を垣間見ることすらも困難のような、その「実像と虚像」との狭間に翻弄されている思いを深くさせられるものが多いのである。それらに比すると、上記の「小さな耳鼻科診療所での話です」と題するものの、この随想風のネット記事のものは、「高浜虚子」の一番中核に位置するものを見事に見据えているという思いを深くするのである。それと同時に、このネット記事で紹介されている、いわゆる「俳句第二芸術論」の著者の桑原武夫という評論家も、正しく、虚子その人を見据えていたという思いを深くする。桑原が、上記の「虚子の散文」という一文は、戦前も戦前の昭和九年に書かれたもので、桑原が「俳句第二芸術論」を草したのは、戦後のどさくさの、昭和二十一年のことであり、桑原は、終始一貫して、「俳人・小説家」としての「高浜虚子」という人を見据え続けてきたといっても差し支えなかろう。
その「小説家」(散文)の「虚子」の特徴として、「この文章(ホトトギスに掲載された『釧路港』1933年)ばかりは強靱で、それを支える思想がよほどしっかりしている。その点はモーパッサンに匹敵」するというのである。この虚子の文章(そしてその思想)の「強靱さ」(ネット記事の耳鼻咽喉科医の言葉でするならば「頑固者」)というのは、例えば、子規の「後継委嘱」を断り、子規をして絶望の局地に追いやったところの、いわゆる「道灌山事件」の背後にある最も根っ子の部分にあたるところのものであろう。この虚子の「強靱さ」(「頑固者」)というものをキィーワードとすると、虚子に係わる様々な「謎」が解明されてくるような思いがする。すなわち、子規と虚子との「道灌山事件」の謎は勿論、碧梧桐との「新傾向俳句」を巡る対立の謎も、秋桜子の「ホトトギス脱会」の背景の謎も、さらにまた、杉田久女らの「ホトトギス除名」の真相を巡る謎も、全ては、虚子の頑なまでの、その「強靱さ」(「頑固者」)に起因があると言って決して過言ではなかろう。
さらに、桑原の、「詩人の文章はどうしても詠嘆的になりがちで、文章をささえる思想が感情になりやすい。… 観察写実から出発した作家は完成に近づくと、無私の眼をもって見た澄明な景色のうちに何か不気味なものを感じさせるものである。そして、人間の感情にしてもむしろ冷淡な意地悪なものがよけいに沁み出る傾向がある」という指摘は、これは、実に、「虚子」その人と、その「創作活動」(小説と俳句)の中心を、見事に射抜いている、けだし、達眼という思いを深くするのである。このことは、上記のネット記事の基になっている、虚子の『俳句への道』の「研究座談会」のものですると、すなわち、虚子の句に対しての平畑静塔の言葉ですると、「痴呆的」という言葉と一致するものであろう。この、桑原の言葉でするならば、「無私の眼をもって見た澄明な景色のうちに何か不気味なものを感じさせるものである。そして、人間の感情にしてもむしろ冷淡な意地悪なものがよけいに沁み出る傾向がある」という指摘は、これこそ、「虚子の実像」という思いを深くするのである。これこそ、虚子と秋桜子とを巡る虚子の小説の「厭な顔」、そして、虚子と久女を巡る「久女伝説」を誕生させたところの虚子の小説の「国子の手紙」の根底に流れているものであろう。
虚子の亡霊(五十四) 道灌山事件(その六)
今回も、「小さな耳鼻科診療所での話です」の、その続きである。
http://www.geocities.jp/kayo_clinic/geodiary.311-320.html
「小さな耳鼻科診療所での話です」(続き)
虚子先生の「俳句への道」を頭をたれながら正座して読んでいたのである(ほんまかな)が、虚子大先生をぼろくそに無視(?)する評論家もいるようです。
「俳句の世界」(講談社学術文庫)の、小西甚一氏。「実は、虚子の写生は看板であって、中味はかなり主観的なものを含み、しかもその把握は伝統的な季題趣味を多く出なかった。木の実植うといへば直ちに人里離れた場所、白い髭をのばした隠者ふうの人物などを連想する行き方で、碧梧桐とは正反対の立場である。子規が第一芸術にしようと努めたのもを第二芸術にひきもどしたのである。」言いますね、コニシさん。
小西氏は、どうも楸邨と友人関係、その師と縁戚関係にあり、私情がたぶんに入った評論のようにも思うが、たぶんに半官びいきにも聞える。虚子のライバルとされた、結果的に俳句界に大きな足跡を残さなかった碧梧桐からの流れをくむ自由律の俳句への応援は温かい。ただ、「定型俳句があっての自由律俳句でなんでしてね。父親の脛を齧ることによって父親無用論を主張できる道楽息子と別ものではありません。」と、その限界を述べている。
ところが、虚子は「俳句への道」のなかで、「自らいい俳句を作らないで。俳句論をするものがある。そういうのは絶対に資格がない。俳句では。作る人が論ずる人であり得ない場合は多いが、論ずる人は、作家であるべきである。」と、痛快に反論しているので、これも愉快である。(小西氏も激辛評論の阿部氏も俳句作者としては、凡作の域をでなかったようだ。)
また、俳句を作る者に対しても理論を先立てることを戒めている。「私は理論はあとから来るほうがいいと考えている。少なくとも創作家というのもはそうあるべきものだと考えている。理論に導かれて創作をしようと試むるのもは迫力のあるものは出来ない。それよりも何物かに導かれるような感じの上に何ものも忘れて創作をする。出来て後にその創作の中から理論を見出す。創作家の理論というのはそんなものであるべきだと思う。」だそうな。
ということで、資格のないセンセの俳談は終わり。...
(余白に)
☆ここで、小西甚一著『俳句の世界』(講談社学術文庫)について触れられている。この著は、後世に永く伝えられる名著の部類に入るものであろう。その裏表紙に、編集子のものと思われる、次のような一文が付せられている。
○名著『日本文藝史』に先行して執筆された本書において、著者は「雅」と「俗」の交錯によって各時代の芸術が形成されたとする独創的な表現意識史観を提唱した。俳諧連歌の第一句である発句と、子規による革新以後の俳句を同列に論じることの誤りをただし、俳諧と俳句の本質的な差を、文学史の流れを見すえた鋭い史眼で明らかにする。俳句鑑賞に新機軸を拓き、俳句史はこの一冊で十分と絶讃された不朽の書。
確かに、こういうものは、「不朽の書」といえるものなのであろうが(また、この著者の業績は、この著書の解説者の平井照敏氏が記しているとおり、「大碩学」の名が最も相応しいのかも知れないが)、それでもなおかつ、この著者以後の者は、この著を乗り越えていかなければならないのであろう。
そういう観点に立って、この著の「高浜虚子」関連(「碧梧桐の新傾向と虚子の保守化」)のみに焦点を絞って、それをつぶさに見ていくと、この著者一流の、連句でいうところの、ここは「飛躍し過ぎではないか」というところが、散見されるように思われるのである。これらのことについて、稿を改めて、その幾つかについて見ていくことにする。
「子規・漱石・寅彦・東洋城」俳句管見(その六) [子規・漱石・寅彦・東洋城]
その六「明治二十七年(一八九三)・「花・花曇り」など」
(子規・二十八歳。根岸に転居。浅井忠の紹介で中村不折を知り、写生俳句を作る。)
此花がいやぢやいやぢやと死なれけん ID10315 制作年27 季節春 分類植物 季語花
咲く咲かぬ花にも嘘の世なりけり ID10316 制作年27 季節春 分類植物 季語花
其まゝに花を見た目を瞑がれぬ ID10317 制作年27 季節春 分類植物 季語花
花咲て今人の親の病かな ID10319 制作年27 季節春 分類植物 季語花
花咲て知らぬ男の出入かな ID10320 制作年27 季節春 分類植物 季語花
花咲て笋飯のさかりかな ID10321 制作年27 季節春 分類植物 季語花
花咲て老莱の親の病かな ID10322 制作年27 季節春 分類植物 季語花
花の寺濁酒売の這入けり ID10323 制作年27 季節春 分類植物 季語花
花の山浮世画の美人来る哉 ID10324 制作年27 季節春 分類植物 季語花
花を見た其目を直に瞑がれぬ ID10325 制作年27 季節春 分類植物 季語花
晴れつ降りつ花にもならで狐雨 ID10326 制作年27 季節春 分類植物 季語花
山ぞひや花の根岸の一くるわ ID10327 制作年27 季節春 分類植物 季語花
(漱石・二十八歳。小石川の尼寺法蔵院に下宿。)
https://yahan.blog.ss-blog.jp/2023-08-21
40 何となう死に来た世の惜まるゝ
41 春雨や柳の中を濡れて行く
42 大弓やひらりひらりと梅の花
43 矢響の只聞ゆなり梅の中
44 弦音にほたりと落る椿かな
45 弦音になれて来て鳴く小鳥かな
46 春雨や寐ながら横に梅を見る
47 烏帽子着て渡る禰宜あり春の川
48 小柄杓や蝶を追ひ追ひ子順礼
49 菜の花の中に小川のうねりかな
50 風に乗って軽くのし行く燕かな
51 尼寺に有髪の僧を尋ね来よ
52 花に酔ふ事を許さぬ物思ひ

「夏目漱石短冊『君を苦しむるは詩魔か病魔かはた情魔か/花に酔ふ事を許さぬ物思ひ』」
(注記・寒川鼠骨函書:「明治廿四年子規居士病む漱石慰問の尺牘に此短冊を添へて贈れり」) (「夏目漱石デジタルコレクション」)
https://www.kanabun.or.jp/souseki/list.html
≪ 君を苦しむるは詩魔か病魔かはた情魔か/寄子規
52 花に酔ふ事を許さぬ物思ひ (漱石・28歳「明治27年(1894)」)
≪ 季=花(春)。 ◇全集(大6)に明治二十七年頃として収める。(上記の「夏目漱石デジタルコレクション」では、寒川鼠骨函書により[1891(明治24).3-4]としている。)≫(『漱石全集第十七巻・坪内稔典注解』) ≫
(寅彦・十七歳。)
亡妻の四十九日や花曇り(明治三十二年作。二十二歳。)
(東洋城・十七歳。)
花の山学校を忘れ遊びけり(明治三十四年作。二十四歳。)
(参考)
https://shikihaku-digital-archive.jp/meijinijukunen_haikuko
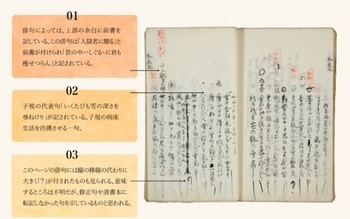
子規筆「明治廿九年俳句稿」明治29(1896)年頃/縦245㎜×横170㎜(綴じた状態)
(「松山市立子規記念博物館/デジタルアーカイブ」)
https://shikihaku-digital-archive.jp/meijinijukunen_haikuko
≪※子規の自作句稿としては最大規模の一冊
本資料「明治廿九年俳句稿」は、子規が明治29年に詠んだ俳句をまとめた自筆の俳句稿です。国立国会図書館に所蔵されている子規自選句集「寒山落木(かんざんらくぼく)五」の草稿にあたるもので、季語を四季別・分類(時候・地理・人事・動物・植物など)別に配列し、句集としての体裁を整えています。収録句数は実に3,000句を超え、子規の自作句稿としては最大規模の一冊です。
明治29年は、子規の俳句革新運動が軌道に乗り、日本派(子規派)の俳句結社が全国に現れはじめた時期にあたります。また子規自身の俳句数の面でも、「寒山落木」清書本に記された俳句数は、明治27年で2,366句(抹消句含む、以下同じ)、同28年で2,843句、そして同29年は3,001句に及んでいます(講談社版『子規全集』第2巻解題)。子規にとって明治29年は、自分自身の俳句の上達にとっても、門人たちの活動の面でも、一つのピークを迎えた年でした。
本資料は、もともと明治32年までの4年分の俳句稿と一綴りにされていましたが、昭和20年の終戦後に一年ごとに分けて綴じ直されました。その後、明治31年と同32年の俳句稿は国立国会図書館に収蔵されましたが、明治29年と同30年の俳句稿は長らく行方不明のままでした。現在は、明治29年・30年ともに当館に収蔵され、子規の俳句革新を物語る貴重な資料として保存・活用されています。≫
(子規・二十八歳。根岸に転居。浅井忠の紹介で中村不折を知り、写生俳句を作る。)
此花がいやぢやいやぢやと死なれけん ID10315 制作年27 季節春 分類植物 季語花
咲く咲かぬ花にも嘘の世なりけり ID10316 制作年27 季節春 分類植物 季語花
其まゝに花を見た目を瞑がれぬ ID10317 制作年27 季節春 分類植物 季語花
花咲て今人の親の病かな ID10319 制作年27 季節春 分類植物 季語花
花咲て知らぬ男の出入かな ID10320 制作年27 季節春 分類植物 季語花
花咲て笋飯のさかりかな ID10321 制作年27 季節春 分類植物 季語花
花咲て老莱の親の病かな ID10322 制作年27 季節春 分類植物 季語花
花の寺濁酒売の這入けり ID10323 制作年27 季節春 分類植物 季語花
花の山浮世画の美人来る哉 ID10324 制作年27 季節春 分類植物 季語花
花を見た其目を直に瞑がれぬ ID10325 制作年27 季節春 分類植物 季語花
晴れつ降りつ花にもならで狐雨 ID10326 制作年27 季節春 分類植物 季語花
山ぞひや花の根岸の一くるわ ID10327 制作年27 季節春 分類植物 季語花
(漱石・二十八歳。小石川の尼寺法蔵院に下宿。)
https://yahan.blog.ss-blog.jp/2023-08-21
40 何となう死に来た世の惜まるゝ
41 春雨や柳の中を濡れて行く
42 大弓やひらりひらりと梅の花
43 矢響の只聞ゆなり梅の中
44 弦音にほたりと落る椿かな
45 弦音になれて来て鳴く小鳥かな
46 春雨や寐ながら横に梅を見る
47 烏帽子着て渡る禰宜あり春の川
48 小柄杓や蝶を追ひ追ひ子順礼
49 菜の花の中に小川のうねりかな
50 風に乗って軽くのし行く燕かな
51 尼寺に有髪の僧を尋ね来よ
52 花に酔ふ事を許さぬ物思ひ

「夏目漱石短冊『君を苦しむるは詩魔か病魔かはた情魔か/花に酔ふ事を許さぬ物思ひ』」
(注記・寒川鼠骨函書:「明治廿四年子規居士病む漱石慰問の尺牘に此短冊を添へて贈れり」) (「夏目漱石デジタルコレクション」)
https://www.kanabun.or.jp/souseki/list.html
≪ 君を苦しむるは詩魔か病魔かはた情魔か/寄子規
52 花に酔ふ事を許さぬ物思ひ (漱石・28歳「明治27年(1894)」)
≪ 季=花(春)。 ◇全集(大6)に明治二十七年頃として収める。(上記の「夏目漱石デジタルコレクション」では、寒川鼠骨函書により[1891(明治24).3-4]としている。)≫(『漱石全集第十七巻・坪内稔典注解』) ≫
(寅彦・十七歳。)
亡妻の四十九日や花曇り(明治三十二年作。二十二歳。)
(東洋城・十七歳。)
花の山学校を忘れ遊びけり(明治三十四年作。二十四歳。)
(参考)
https://shikihaku-digital-archive.jp/meijinijukunen_haikuko
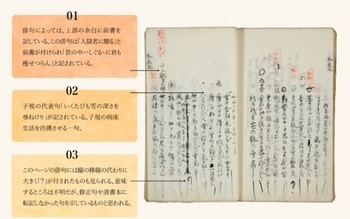
子規筆「明治廿九年俳句稿」明治29(1896)年頃/縦245㎜×横170㎜(綴じた状態)
(「松山市立子規記念博物館/デジタルアーカイブ」)
https://shikihaku-digital-archive.jp/meijinijukunen_haikuko
≪※子規の自作句稿としては最大規模の一冊
本資料「明治廿九年俳句稿」は、子規が明治29年に詠んだ俳句をまとめた自筆の俳句稿です。国立国会図書館に所蔵されている子規自選句集「寒山落木(かんざんらくぼく)五」の草稿にあたるもので、季語を四季別・分類(時候・地理・人事・動物・植物など)別に配列し、句集としての体裁を整えています。収録句数は実に3,000句を超え、子規の自作句稿としては最大規模の一冊です。
明治29年は、子規の俳句革新運動が軌道に乗り、日本派(子規派)の俳句結社が全国に現れはじめた時期にあたります。また子規自身の俳句数の面でも、「寒山落木」清書本に記された俳句数は、明治27年で2,366句(抹消句含む、以下同じ)、同28年で2,843句、そして同29年は3,001句に及んでいます(講談社版『子規全集』第2巻解題)。子規にとって明治29年は、自分自身の俳句の上達にとっても、門人たちの活動の面でも、一つのピークを迎えた年でした。
本資料は、もともと明治32年までの4年分の俳句稿と一綴りにされていましたが、昭和20年の終戦後に一年ごとに分けて綴じ直されました。その後、明治31年と同32年の俳句稿は国立国会図書館に収蔵されましたが、明治29年と同30年の俳句稿は長らく行方不明のままでした。現在は、明治29年・30年ともに当館に収蔵され、子規の俳句革新を物語る貴重な資料として保存・活用されています。≫
「子規・漱石・寅彦・東洋城」俳句管見(その五) [子規・漱石・寅彦・東洋城]
その五「明治二十六年(一八九三)・「蒟蒻・心太」など」
(子規・二十七歳。帝国大学文化大学中退。『獺祭書屋俳話』刊。)
菎蒻につゝじの名あれ太山寺 ID2069 制作年25 季節春 分類植物 季語つつじ
菎蒻の水さえ返る濁りかな ID4744 制作年26 季節春 分類時候 季語冴返る
立ちながら心太くふ飛脚哉 ID6983 制作年26 季節夏 分類人事 季語心太
心太水にもならず明けにけり ID6984 制作年26 季節夏 分類人事 季語心太
心太龍宮城のはしら立て ID6985 制作年26 季節夏 分類人事 季語心太
庭先の清水に白し心太 ID6986 制作年26 季節夏 分類人事 季語心太
婆々の留守海月にやならん心太 ID6987 制作年26 季節夏 分類人事 季語心太
みちのくの水の味しれ心太 ID6988 制作年26 季節夏 分類人事 季語心太
(参考その一) 高浜虚子『子規句解』(「菎蒻」の句)
菎蒻につゝじの名あれ太山寺(明治廿五年)
松山から一里ばかり離れた處に三津といふ港があつて、それが其時分松山から他に旅行する時の唯一の港であつた。現在は高濱といふ港が其近傍に出來て、其方に汽船が主として發著するやうになつたのであるが其頃は未だ其處は一漁村に過ぎなかつたのである。其の三津の近傍に太山寺といふ山があつて、そこには太山寺といふ寺がある。菎蒻が其處の名物であつてそれを太山寺菎蒻といつて、松山あたりの人々は特に賞翫して居た。そのまた太山寺には躑躅の花が見事であつた。そこで蒟蒻には太山寺菎蒻といふ名前があるが、又つゝじ蒟蒻といふ名前があつてもいゝではないか、と戯れて言つたものであらう。私の子供の時分には太山寺菎蒻といふのは名物であつたが、今は果してどうであらうか。躑躅の花も尚盛りであるかどうか。
(漱石・二十七歳。帝国大学文化大学卒業。高等師範学校英語教師。)
1218 槽底に魚あり沈む心太(明治三十年作。「子規へ送りたる句稿二十五」)
1557 蒟蒻に梅を踏み込む男かな(明治三十二年作。「子規へ送りたる句稿三十三」)
1951 ところてんの叩かれてゐる清水かな(明治四十年作。「手帳より」)
(寅彦・十六歳。高知県尋常中学校(現・高知追手前高等学校)。)
心太とラムネの瓶を浸しけり(明治三十二年作。二十二歳。)
心太水晶簾と賛すべく(明治三十四年作。二十四歳。)
涼しさの心太とや凝りけらし(三十四年作。二十四歳。)
(東洋城・十六歳。愛媛県尋常中学校(現・松山東高等学校))
甘酒や一樹の下の心太(明治三十三年作。二十三歳。)
(参考その二) 「寒山落木抄」周辺
https://shikihaku-digital-archive.jp/kanzanrakubok_sho
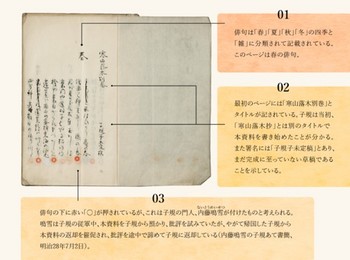
「子規自選句稿「寒山落木抄」明治27(1894)年秋/縦245㎜×横167㎜(綴じた状態)
(「松山市立子規記念博物館/デジタルアーカイブ」)
≪※子規の選句眼の成長を物語る、まぼろしの自選句集
本資料「寒山落木抄」(かんざんらくぼくしょう)は、子規が明治23年頃から同27年冬までの間に自分が作った俳句の中から、計945句を書き抜いて作成した自選句稿です。本文は全50丁、各頁は10行ずつ記されており、収録された俳句は春223句(うち抹消16句)、夏293句(うち抹消32句)、秋236句(うち抹消20句)、冬193句(うち抹消11句)を数えます。
子規は明治18年頃に俳句を作り始めて以降、明治27年までに1万句を超える俳句を作っていました。子規が自分自身で詠んだ膨大な俳句の中から、様々な観点で良いと思う句を選抜して書き写し、一冊にまとめたのが本資料です。しかしながら本資料は、正式な子規の句集として出版されることはなく、子規の死後も自筆句稿のまま長く保管されていました。
子規は晩年、唯一の自選句集として『獺祭書屋俳句帖抄上巻(だっさいしょおくはいくちょうしょうじょうかん)』(明治35年4月刊)を出版しています。この『獺祭書屋俳句帖抄』と「寒山落木抄」を比較してみると、共通して選抜されている俳句は全体の半数にも満たず、子規の選句眼(何をもって「良い俳句」とするか)が明治27年と同35年の間で大きく変化したことがうかがえます。本資料「寒山落木抄」は、子規の俳句の成長過程を知る上で、たいへん貴重な資料です。 ≫
(子規・二十七歳。帝国大学文化大学中退。『獺祭書屋俳話』刊。)
菎蒻につゝじの名あれ太山寺 ID2069 制作年25 季節春 分類植物 季語つつじ
菎蒻の水さえ返る濁りかな ID4744 制作年26 季節春 分類時候 季語冴返る
立ちながら心太くふ飛脚哉 ID6983 制作年26 季節夏 分類人事 季語心太
心太水にもならず明けにけり ID6984 制作年26 季節夏 分類人事 季語心太
心太龍宮城のはしら立て ID6985 制作年26 季節夏 分類人事 季語心太
庭先の清水に白し心太 ID6986 制作年26 季節夏 分類人事 季語心太
婆々の留守海月にやならん心太 ID6987 制作年26 季節夏 分類人事 季語心太
みちのくの水の味しれ心太 ID6988 制作年26 季節夏 分類人事 季語心太
(参考その一) 高浜虚子『子規句解』(「菎蒻」の句)
菎蒻につゝじの名あれ太山寺(明治廿五年)
松山から一里ばかり離れた處に三津といふ港があつて、それが其時分松山から他に旅行する時の唯一の港であつた。現在は高濱といふ港が其近傍に出來て、其方に汽船が主として發著するやうになつたのであるが其頃は未だ其處は一漁村に過ぎなかつたのである。其の三津の近傍に太山寺といふ山があつて、そこには太山寺といふ寺がある。菎蒻が其處の名物であつてそれを太山寺菎蒻といつて、松山あたりの人々は特に賞翫して居た。そのまた太山寺には躑躅の花が見事であつた。そこで蒟蒻には太山寺菎蒻といふ名前があるが、又つゝじ蒟蒻といふ名前があつてもいゝではないか、と戯れて言つたものであらう。私の子供の時分には太山寺菎蒻といふのは名物であつたが、今は果してどうであらうか。躑躅の花も尚盛りであるかどうか。
(漱石・二十七歳。帝国大学文化大学卒業。高等師範学校英語教師。)
1218 槽底に魚あり沈む心太(明治三十年作。「子規へ送りたる句稿二十五」)
1557 蒟蒻に梅を踏み込む男かな(明治三十二年作。「子規へ送りたる句稿三十三」)
1951 ところてんの叩かれてゐる清水かな(明治四十年作。「手帳より」)
(寅彦・十六歳。高知県尋常中学校(現・高知追手前高等学校)。)
心太とラムネの瓶を浸しけり(明治三十二年作。二十二歳。)
心太水晶簾と賛すべく(明治三十四年作。二十四歳。)
涼しさの心太とや凝りけらし(三十四年作。二十四歳。)
(東洋城・十六歳。愛媛県尋常中学校(現・松山東高等学校))
甘酒や一樹の下の心太(明治三十三年作。二十三歳。)
(参考その二) 「寒山落木抄」周辺
https://shikihaku-digital-archive.jp/kanzanrakubok_sho
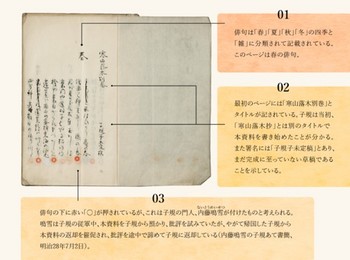
「子規自選句稿「寒山落木抄」明治27(1894)年秋/縦245㎜×横167㎜(綴じた状態)
(「松山市立子規記念博物館/デジタルアーカイブ」)
≪※子規の選句眼の成長を物語る、まぼろしの自選句集
本資料「寒山落木抄」(かんざんらくぼくしょう)は、子規が明治23年頃から同27年冬までの間に自分が作った俳句の中から、計945句を書き抜いて作成した自選句稿です。本文は全50丁、各頁は10行ずつ記されており、収録された俳句は春223句(うち抹消16句)、夏293句(うち抹消32句)、秋236句(うち抹消20句)、冬193句(うち抹消11句)を数えます。
子規は明治18年頃に俳句を作り始めて以降、明治27年までに1万句を超える俳句を作っていました。子規が自分自身で詠んだ膨大な俳句の中から、様々な観点で良いと思う句を選抜して書き写し、一冊にまとめたのが本資料です。しかしながら本資料は、正式な子規の句集として出版されることはなく、子規の死後も自筆句稿のまま長く保管されていました。
子規は晩年、唯一の自選句集として『獺祭書屋俳句帖抄上巻(だっさいしょおくはいくちょうしょうじょうかん)』(明治35年4月刊)を出版しています。この『獺祭書屋俳句帖抄』と「寒山落木抄」を比較してみると、共通して選抜されている俳句は全体の半数にも満たず、子規の選句眼(何をもって「良い俳句」とするか)が明治27年と同35年の間で大きく変化したことがうかがえます。本資料「寒山落木抄」は、子規の俳句の成長過程を知る上で、たいへん貴重な資料です。 ≫
「子規・漱石・寅彦・東洋城」俳句管見(その四) [子規・漱石・寅彦・東洋城]
その四「明治二十五年(一八九二)・「満月・炬燵」など」
(子規・二十六歳。十二月、陸羯南の紹介で新聞「日本」入社。)
https://shiki-museum.com/masaokashiki/haiku?post_type=haiku&post_type=haiku&haiku_id=&p_age=24&season=&classification=&kigo=%E9%9B%AA%E8%A6%8B&s=&select=
春風や巨燵櫓のよそよそし ID1688 制作年25 季節春 分類天文 季語春風
猫のこひ巨燵をふんで忍ひけり ID1816 制作年25 季節春 分類動物 季語猫の恋
第一ハ雪なり第二巨燵なり ID4321 制作年25 季節冬 分類天文 季語雪
撰集の沙汰にくれたる巨燵哉 ID4443 制作年25 季節冬 分類人事 季語炬燵
冬こもり命うちこむ巨燵哉 ID4479 制作年25 季節冬 分類人事 季語冬籠
冬籠り倉にもちこむ巨燵哉 ID4480 制作年25 季節冬 分類人事 季語冬籠
(漱石・二十六歳。五月、東京専門学校講師となる。)
https://yahan.blog.ss-blog.jp/2023-08-21
(再掲)
38 鳴くならば満月になけほとゝぎす(落第した子規に「退学するな」の意を込めての句。)
39 病む人の巨燵離れて雪見かな(子規書翰「東京専門学校講師」の評判=「悪」との返句。)

「病床図画賛/鳴雪・四方太書/子規画/紙本墨書/29.7×45.7㎝」
≪明治三十二年頃の作か。ほぼ同種の画と賛のものが遺っている。病床に筆をとる子規の写生画に、
湯たんぽに足のとどかぬふとん哉 方(四方太)
画箋紙に鼻水にじむ寒かな 鳴雪
の賛がある。同冬十二月初旬に病室の南手にガラス戸が入り、暖炉が設けられ暖かい冬を過ごすことが出来た年のことである。(後略)
※内藤鳴雪=俳人。江戸に生まれる。本名素行。松山藩校明教館・昌平黌で漢学を学ぶ。明治に入り文部省に勤務。藩の常盤会寄宿舎の舎監となり正岡子規を知り句作、日本派の長老と仰がれた。句集に「鳴雪句集」「鳴雪俳句鈔」など。弘化四~大正一五年(一八四七‐一九二六) (「精選版 日本国語大辞典)」
※阪本四方太=俳人。本名四方太(よもた)。鳥取県出身。東大国文科卒。正岡子規の指導をうけ、俳誌「ホトトギス」に俳句と共に多くの写生文を発表した。著に「夢の如し」など。明治六~大正六年(一八七三‐一九一七) (「精選版 日本国語大辞典)」 ≫
(追記)
(寅彦=「漱石」との出会い「明治二十九年・十八歳時=第五高校入学時。出典=『牛頓先生俳句集・季題別』、『寺田寅彦全集/文学篇/七巻』」)
姑の顔むつかしき炬燵かな(明治三十一~二年作。二十一歳~二十二歳)
掻餅に新聞を読む火燵かな(同上。)
火燵してアルバムを見る女哉(同上。)
ねころんで新聞を見る炬燵哉(同上。)
炬燵して絵草紙見て居る女の子(同上。)
炬燵して鏡に対す夫婦哉(明治三十九年作。満二十八歳)
睦じき頸をならべて炬燵かな(同上。)
母なき子の父に親しむ火燵哉(大正六年作。満三十六歳)
今そこに居たかと思ふ火燵(同上。)
(東洋城=「明治二十八年、十八歳時、松山中学校五年生の四月、漱石が教師として来任し、英語の教授を受ける。明治三十八年、京大卒業、翌年、二十九歳時に、宮内省に入り、式部官などを歴任。出典=『東洋城全句集(上・中・下)』の中巻の「年譜」)
筆を硯に届かせんとする炬燵かな (明治三十三年作、二十三歳)
腸焦げて黒き詩を吐く炬燵かな (明治四十二年作、三十二歳)
沓掛も枯野の宿の炬燵かな (明治四十二年作、三十二歳)
(参考その一) 「松山市立子規記念博物館/デジタルアーカイブ」周辺
https://shikihaku-digital-archive.jp/
子規自選句稿「寒山落木抄」
↓
https://shikihaku-digital-archive.jp/kanzanrakubok_sho#gallery1-1
子規筆「明治廿九年俳句稿」
↓
https://shikihaku-digital-archive.jp/meijinijukunen_haikuko
子規編「郷党人物月旦評論」
↓
https://shikihaku-digital-archive.jp/kyotojinbutsu_gettanhyoron
子規選句稿「なじみ集」
↓
https://shikihaku-digital-archive.jp/najimishu
子規歌稿「竹乃里歌」
↓
https://shikihaku-digital-archive.jp/takenosato_uta
(俳句検索)
↓
https://shiki-museum.com/masaokashiki/haiku/page/18?post_type=haiku&haiku_id&p_age=26&season&classification&kigo&s&select&doing_wp_cron=1694506083.4227440357208251953125
(参考その二)『寒山落木』と『俳句稿』周辺
『寒山落木・巻一(明治二十四年~二十五年)』・「寒山落木・巻二(明治二十六年)』→『子規全集』(第一巻)
↓
http://geo.d51498.com/urawa0328/siki/siki-ku.html
『寒山落木・巻三(明治二十七年)』・『寒山落木・巻四(明治二十八年)』・『寒山落木・巻五(明治二十九年)』→『子規全集』(第二巻)
↓
http://geo.d51498.com/urawa0328/siki/siki-ku.html
『俳句稿(明治三十年~三十三年)』→『子規全集』(第三巻)
↓
http://geo.d51498.com/urawa0328/siki/siki-ku2.html
高浜虚子『子規句解』
↓
http://geo.d51498.com/urawa0328/siki/sikikukai.html
(子規・二十六歳。十二月、陸羯南の紹介で新聞「日本」入社。)
https://shiki-museum.com/masaokashiki/haiku?post_type=haiku&post_type=haiku&haiku_id=&p_age=24&season=&classification=&kigo=%E9%9B%AA%E8%A6%8B&s=&select=
春風や巨燵櫓のよそよそし ID1688 制作年25 季節春 分類天文 季語春風
猫のこひ巨燵をふんで忍ひけり ID1816 制作年25 季節春 分類動物 季語猫の恋
第一ハ雪なり第二巨燵なり ID4321 制作年25 季節冬 分類天文 季語雪
撰集の沙汰にくれたる巨燵哉 ID4443 制作年25 季節冬 分類人事 季語炬燵
冬こもり命うちこむ巨燵哉 ID4479 制作年25 季節冬 分類人事 季語冬籠
冬籠り倉にもちこむ巨燵哉 ID4480 制作年25 季節冬 分類人事 季語冬籠
(漱石・二十六歳。五月、東京専門学校講師となる。)
https://yahan.blog.ss-blog.jp/2023-08-21
(再掲)
38 鳴くならば満月になけほとゝぎす(落第した子規に「退学するな」の意を込めての句。)
39 病む人の巨燵離れて雪見かな(子規書翰「東京専門学校講師」の評判=「悪」との返句。)

「病床図画賛/鳴雪・四方太書/子規画/紙本墨書/29.7×45.7㎝」
≪明治三十二年頃の作か。ほぼ同種の画と賛のものが遺っている。病床に筆をとる子規の写生画に、
湯たんぽに足のとどかぬふとん哉 方(四方太)
画箋紙に鼻水にじむ寒かな 鳴雪
の賛がある。同冬十二月初旬に病室の南手にガラス戸が入り、暖炉が設けられ暖かい冬を過ごすことが出来た年のことである。(後略)
※内藤鳴雪=俳人。江戸に生まれる。本名素行。松山藩校明教館・昌平黌で漢学を学ぶ。明治に入り文部省に勤務。藩の常盤会寄宿舎の舎監となり正岡子規を知り句作、日本派の長老と仰がれた。句集に「鳴雪句集」「鳴雪俳句鈔」など。弘化四~大正一五年(一八四七‐一九二六) (「精選版 日本国語大辞典)」
※阪本四方太=俳人。本名四方太(よもた)。鳥取県出身。東大国文科卒。正岡子規の指導をうけ、俳誌「ホトトギス」に俳句と共に多くの写生文を発表した。著に「夢の如し」など。明治六~大正六年(一八七三‐一九一七) (「精選版 日本国語大辞典)」 ≫
(追記)
(寅彦=「漱石」との出会い「明治二十九年・十八歳時=第五高校入学時。出典=『牛頓先生俳句集・季題別』、『寺田寅彦全集/文学篇/七巻』」)
姑の顔むつかしき炬燵かな(明治三十一~二年作。二十一歳~二十二歳)
掻餅に新聞を読む火燵かな(同上。)
火燵してアルバムを見る女哉(同上。)
ねころんで新聞を見る炬燵哉(同上。)
炬燵して絵草紙見て居る女の子(同上。)
炬燵して鏡に対す夫婦哉(明治三十九年作。満二十八歳)
睦じき頸をならべて炬燵かな(同上。)
母なき子の父に親しむ火燵哉(大正六年作。満三十六歳)
今そこに居たかと思ふ火燵(同上。)
(東洋城=「明治二十八年、十八歳時、松山中学校五年生の四月、漱石が教師として来任し、英語の教授を受ける。明治三十八年、京大卒業、翌年、二十九歳時に、宮内省に入り、式部官などを歴任。出典=『東洋城全句集(上・中・下)』の中巻の「年譜」)
筆を硯に届かせんとする炬燵かな (明治三十三年作、二十三歳)
腸焦げて黒き詩を吐く炬燵かな (明治四十二年作、三十二歳)
沓掛も枯野の宿の炬燵かな (明治四十二年作、三十二歳)
(参考その一) 「松山市立子規記念博物館/デジタルアーカイブ」周辺
https://shikihaku-digital-archive.jp/
子規自選句稿「寒山落木抄」
↓
https://shikihaku-digital-archive.jp/kanzanrakubok_sho#gallery1-1
子規筆「明治廿九年俳句稿」
↓
https://shikihaku-digital-archive.jp/meijinijukunen_haikuko
子規編「郷党人物月旦評論」
↓
https://shikihaku-digital-archive.jp/kyotojinbutsu_gettanhyoron
子規選句稿「なじみ集」
↓
https://shikihaku-digital-archive.jp/najimishu
子規歌稿「竹乃里歌」
↓
https://shikihaku-digital-archive.jp/takenosato_uta
(俳句検索)
↓
https://shiki-museum.com/masaokashiki/haiku/page/18?post_type=haiku&haiku_id&p_age=26&season&classification&kigo&s&select&doing_wp_cron=1694506083.4227440357208251953125
(参考その二)『寒山落木』と『俳句稿』周辺
『寒山落木・巻一(明治二十四年~二十五年)』・「寒山落木・巻二(明治二十六年)』→『子規全集』(第一巻)
↓
http://geo.d51498.com/urawa0328/siki/siki-ku.html
『寒山落木・巻三(明治二十七年)』・『寒山落木・巻四(明治二十八年)』・『寒山落木・巻五(明治二十九年)』→『子規全集』(第二巻)
↓
http://geo.d51498.com/urawa0328/siki/siki-ku.html
『俳句稿(明治三十年~三十三年)』→『子規全集』(第三巻)
↓
http://geo.d51498.com/urawa0328/siki/siki-ku2.html
高浜虚子『子規句解』
↓
http://geo.d51498.com/urawa0328/siki/sikikukai.html
「子規・漱石・寅彦・東洋城」俳句管見(その三) [子規・漱石・寅彦・東洋城]
その三「明治二十四年(一八九一)・朝顔(朝貌)など」
(子規・二十五歳。二月、国文科に転科。虚子を指導。駒込に転居)
https://shiki-museum.com/masaokashiki/haiku?post_type=haiku&post_type=haiku&haiku_id=&p_age=24&season=&classification=&kigo=%E6%9C%9D%E9%A1%94&s=&select=
朝かほや斜にさきしつる一ツ ID1471 制作年24 季節秋 分類植物 季語朝顔
朝な朝な朝がほながき契り哉 ID1472 制作年24 季節秋 分類植物 季語朝顔
朝な朝な朝がほながきさかり哉 ID1473 制作年24 季節秋 分類植物 季語朝顔
(漱石・二十五歳。七月、親しかった兄嫁・登世没)
(再掲)
https://yahan.blog.ss-blog.jp/2023-08-21
23 朝貌に好かれそうなる竹垣根 (季=「朝貌」=「朝顔」=秋。)
25 朝貌や咲た許りの命哉(「悼亡十三句」(嫂登世の追悼句)、冒頭の句。「朝顔=秋」。)
(付記)
26 細眉を落す間もなく此世をば (「同上」、無季の句。)
27 人生を廿五年に縮めけり (「同上」、無季。)
28 君逝きて浮世に花はなかりけり (「同上」、花(春)の句とうより無季の句。)
29 仮位牌焚く線香に黒む迄 (「同上」、無季の句。「通夜」の句。)
30 こうろげの飛ぶや木魚の声の下 (「同上」、「こうろげ=こおろぎ=秋」。「通夜」の句)
31 通夜僧の経の絶間やきりぎりす (「同上」、「きりぎりす=秋」、「通夜」の句)
32 骸骨や是も美人のなれの果 (「同上」、無季、「骨揚(こつあげ)のとき」の句)
33 何事ぞ手向し花に狂ふ蝶 (「同上」、「花・蝶=春)」、「無季(花=亡嫂、蝶=漱石)」)
34 鏡台の主の行衛や塵埃 (「同上」、無季。「初七日」の句)
35 ますら男に染模様あるかたみかな (「同上」)
36 聖人の生れ代りか桐の花 (「同上」、「桐の花」=夏、「朝顔の花」=秋。)
37 今日よりは誰に見立ん秋の月(「同上」、「秋の月」=秋。「月」=亡嫂の見立て。)
(追記)
(寅彦=「漱石」との出会い「明治二十九年・十八歳時=第五高校入学時。出典=『牛頓先生俳句集・季題別』、『寺田寅彦全集/文学篇/七巻』」)
枳殻(キコク=からたち)垣を朝顔二三のぞきけり(明治三十一年作。二十一歳、漱石初出会)
所狭きまで朝顔並べ屋根の上(「同上」。漱石との初出会いは試験失敗の友人の「点貰い」)
かれがれの朝顔からむれんじ窓(「同上」。五高(田丸卓郎)で「物理学」専攻を固める。)
朝顔の唯一色に淋しさよ(漱石に「俳句」の話を聞き、漱石に師事。「落穂集」など。)
(東洋城=「明治二十八年、十八歳時、松山中学校五年生の四月、漱石が教師として来任し、英語の教授を受ける。明治三十八年、京大卒業、翌年、二十九歳時に、宮内省に入り、式部官などを歴任。出典=『東洋城全句集(上・中・下)』の中巻の「年譜」)
朝顔の夕顔の種蒔きにけり(明治三十五年作、二十五歳。九月、子規没。)
朝顔や置屋もすなる鄙の宿(明治三十七年作、二十七歳。新設の京都大学へ転校。)
朝顔や縁を畳へ日二尺(明治四十四年作、三十四歳。寅彦帰朝。漱石、大阪で病む。)
朝顔や天過つて紺青を(大正八年作、四十二歳。宮内省を退官。「朝日俳壇」の選を担当。)
朝顔やどの色とめし妹が帯(大正九年作、四十三歳。寅彦・豊隆「渋柿」に毎号執筆。)

「仰臥漫録・朝顔」(子規画賛)
https://plaza.rakuten.co.jp/akiradoinaka/diary/202010050000/
(参考その一) 「仰臥漫録5:朝顔」周辺
≪ 子規は明治34年9月9日の『仰臥漫録』には、川崎(のちに原)安民が鋳造した蛙の置物の絵を描きました。高さ7cmの実物大の絵には正面と背面が描かれ、「無花果に手足生えたると御覧ぜよ」と句を詠んでふざけています。(中略)
9月13日には、中央に朝顔を置き、句を添えています。
朝皃や絵の具にじんで絵を成さず
朝顔や絵にかくうちに萎れけり
朝顔のしぼまぬ秋となりにけり
蕣のー輪ざしに萎れけり
明治32年8月10日の「ホトトギス」に掲載された『庭』という文に子規庵の庭の変遷が書かれています。子規が家族と移った明治27年2月の頃の庭には、「余が六年前にこの家に移って来た時は、始めて空地を開いて建てた家で、その新しい家へ始めて住んだのだから、庭の隅に一本の椎があり、垣の外に大きな椎と槻がある外は、木も草も何もなかった」とあり、ほとんど何も植えていませんでした。この年の秋の「朝顔の引き捨てられし莟かな」という句には、「草庵の囲いあるとある限り、蕣はいつかせて朝な朝な楽しみしに、ある日家主なる人の使して杉垣枯れなんとてことごとくそを引かせたる。誠に悲しく浮世のさまなりける」の詞書があり、引かれてしまった庭の朝顔を寂しく思う子規が感じられます。
ただ、翌年もまた、庭の朝顔は花を咲かせました。当時の子規は、日清戦争取材の帰りの船中で吐血したため、須磨保養院で療養していました。看病していた高浜虚子が、子規の母に子規の病状を報告するために一時東京に帰りました。その時の庭の様子を子規に告げたのでしょう。子規は「須磨にある頃、虚子おとずれして、君が庵の朝顔は今さかりというに」の詞書で「帰るかと朝顔咲きし留守の垣」と詠んでいます。(後略) ≫
(参考その二) 高浜虚子『子規句解』(「蕣」二句抜粋)
http://geo.d51498.com/urawa0328/siki/sikikukai.html
≪蕣や君いかめしき文學士(明治廿六年)
朝顔は立派な花をつけている。漱石は新たに文學士になつてやつて來た、といふだけの句であるあるが、子規も大學につゞけて居さへすれば共に文學士となつたのである。自分から好んでゞはあつたが、併し病氣のためもあつて、大學を中途退學した。「前にも「孑孑の蚊になる頃や何學士」といふ句があるやうに、もとの同窓生が何學士といふ肩書を背負つて世の中に出て來るのを見ると、多少の感慨が無いでもない。殊に親しい交りを呈した漱石が、文學士といふ肩書を持つてけふ改まつて子規のところへ來た、といふやうな感じである。
蕣に今朝は朝寢の亭主あり(明治廿六年)
この句はおそらく東北の旅を終へて歸つた時の句であらうと思ふ。子規は元來朝寢坊であつた。それといふのも、夜更かしをして仕事をする癖があつたので自然朝寢をする傾きになつたものであらう。子規の留守中はお母さんも妹さんも、朝早く起きて拭掃除も早く出來る日がつづいたのであるが、子規が歸つて來ると、旅疲れもまじつて忽ち朝寢坊の主人がある家になつた、と云ふことをいつたものである。 ≫
(子規・二十五歳。二月、国文科に転科。虚子を指導。駒込に転居)
https://shiki-museum.com/masaokashiki/haiku?post_type=haiku&post_type=haiku&haiku_id=&p_age=24&season=&classification=&kigo=%E6%9C%9D%E9%A1%94&s=&select=
朝かほや斜にさきしつる一ツ ID1471 制作年24 季節秋 分類植物 季語朝顔
朝な朝な朝がほながき契り哉 ID1472 制作年24 季節秋 分類植物 季語朝顔
朝な朝な朝がほながきさかり哉 ID1473 制作年24 季節秋 分類植物 季語朝顔
(漱石・二十五歳。七月、親しかった兄嫁・登世没)
(再掲)
https://yahan.blog.ss-blog.jp/2023-08-21
23 朝貌に好かれそうなる竹垣根 (季=「朝貌」=「朝顔」=秋。)
25 朝貌や咲た許りの命哉(「悼亡十三句」(嫂登世の追悼句)、冒頭の句。「朝顔=秋」。)
(付記)
26 細眉を落す間もなく此世をば (「同上」、無季の句。)
27 人生を廿五年に縮めけり (「同上」、無季。)
28 君逝きて浮世に花はなかりけり (「同上」、花(春)の句とうより無季の句。)
29 仮位牌焚く線香に黒む迄 (「同上」、無季の句。「通夜」の句。)
30 こうろげの飛ぶや木魚の声の下 (「同上」、「こうろげ=こおろぎ=秋」。「通夜」の句)
31 通夜僧の経の絶間やきりぎりす (「同上」、「きりぎりす=秋」、「通夜」の句)
32 骸骨や是も美人のなれの果 (「同上」、無季、「骨揚(こつあげ)のとき」の句)
33 何事ぞ手向し花に狂ふ蝶 (「同上」、「花・蝶=春)」、「無季(花=亡嫂、蝶=漱石)」)
34 鏡台の主の行衛や塵埃 (「同上」、無季。「初七日」の句)
35 ますら男に染模様あるかたみかな (「同上」)
36 聖人の生れ代りか桐の花 (「同上」、「桐の花」=夏、「朝顔の花」=秋。)
37 今日よりは誰に見立ん秋の月(「同上」、「秋の月」=秋。「月」=亡嫂の見立て。)
(追記)
(寅彦=「漱石」との出会い「明治二十九年・十八歳時=第五高校入学時。出典=『牛頓先生俳句集・季題別』、『寺田寅彦全集/文学篇/七巻』」)
枳殻(キコク=からたち)垣を朝顔二三のぞきけり(明治三十一年作。二十一歳、漱石初出会)
所狭きまで朝顔並べ屋根の上(「同上」。漱石との初出会いは試験失敗の友人の「点貰い」)
かれがれの朝顔からむれんじ窓(「同上」。五高(田丸卓郎)で「物理学」専攻を固める。)
朝顔の唯一色に淋しさよ(漱石に「俳句」の話を聞き、漱石に師事。「落穂集」など。)
(東洋城=「明治二十八年、十八歳時、松山中学校五年生の四月、漱石が教師として来任し、英語の教授を受ける。明治三十八年、京大卒業、翌年、二十九歳時に、宮内省に入り、式部官などを歴任。出典=『東洋城全句集(上・中・下)』の中巻の「年譜」)
朝顔の夕顔の種蒔きにけり(明治三十五年作、二十五歳。九月、子規没。)
朝顔や置屋もすなる鄙の宿(明治三十七年作、二十七歳。新設の京都大学へ転校。)
朝顔や縁を畳へ日二尺(明治四十四年作、三十四歳。寅彦帰朝。漱石、大阪で病む。)
朝顔や天過つて紺青を(大正八年作、四十二歳。宮内省を退官。「朝日俳壇」の選を担当。)
朝顔やどの色とめし妹が帯(大正九年作、四十三歳。寅彦・豊隆「渋柿」に毎号執筆。)

「仰臥漫録・朝顔」(子規画賛)
https://plaza.rakuten.co.jp/akiradoinaka/diary/202010050000/
(参考その一) 「仰臥漫録5:朝顔」周辺
≪ 子規は明治34年9月9日の『仰臥漫録』には、川崎(のちに原)安民が鋳造した蛙の置物の絵を描きました。高さ7cmの実物大の絵には正面と背面が描かれ、「無花果に手足生えたると御覧ぜよ」と句を詠んでふざけています。(中略)
9月13日には、中央に朝顔を置き、句を添えています。
朝皃や絵の具にじんで絵を成さず
朝顔や絵にかくうちに萎れけり
朝顔のしぼまぬ秋となりにけり
蕣のー輪ざしに萎れけり
明治32年8月10日の「ホトトギス」に掲載された『庭』という文に子規庵の庭の変遷が書かれています。子規が家族と移った明治27年2月の頃の庭には、「余が六年前にこの家に移って来た時は、始めて空地を開いて建てた家で、その新しい家へ始めて住んだのだから、庭の隅に一本の椎があり、垣の外に大きな椎と槻がある外は、木も草も何もなかった」とあり、ほとんど何も植えていませんでした。この年の秋の「朝顔の引き捨てられし莟かな」という句には、「草庵の囲いあるとある限り、蕣はいつかせて朝な朝な楽しみしに、ある日家主なる人の使して杉垣枯れなんとてことごとくそを引かせたる。誠に悲しく浮世のさまなりける」の詞書があり、引かれてしまった庭の朝顔を寂しく思う子規が感じられます。
ただ、翌年もまた、庭の朝顔は花を咲かせました。当時の子規は、日清戦争取材の帰りの船中で吐血したため、須磨保養院で療養していました。看病していた高浜虚子が、子規の母に子規の病状を報告するために一時東京に帰りました。その時の庭の様子を子規に告げたのでしょう。子規は「須磨にある頃、虚子おとずれして、君が庵の朝顔は今さかりというに」の詞書で「帰るかと朝顔咲きし留守の垣」と詠んでいます。(後略) ≫
(参考その二) 高浜虚子『子規句解』(「蕣」二句抜粋)
http://geo.d51498.com/urawa0328/siki/sikikukai.html
≪蕣や君いかめしき文學士(明治廿六年)
朝顔は立派な花をつけている。漱石は新たに文學士になつてやつて來た、といふだけの句であるあるが、子規も大學につゞけて居さへすれば共に文學士となつたのである。自分から好んでゞはあつたが、併し病氣のためもあつて、大學を中途退學した。「前にも「孑孑の蚊になる頃や何學士」といふ句があるやうに、もとの同窓生が何學士といふ肩書を背負つて世の中に出て來るのを見ると、多少の感慨が無いでもない。殊に親しい交りを呈した漱石が、文學士といふ肩書を持つてけふ改まつて子規のところへ來た、といふやうな感じである。
蕣に今朝は朝寢の亭主あり(明治廿六年)
この句はおそらく東北の旅を終へて歸つた時の句であらうと思ふ。子規は元來朝寢坊であつた。それといふのも、夜更かしをして仕事をする癖があつたので自然朝寢をする傾きになつたものであらう。子規の留守中はお母さんも妹さんも、朝早く起きて拭掃除も早く出來る日がつづいたのであるが、子規が歸つて來ると、旅疲れもまじつて忽ち朝寢坊の主人がある家になつた、と云ふことをいつたものである。 ≫
「子規・漱石・寅彦・東洋城」俳句管見(その二) [子規・漱石・寅彦・東洋城]
その二「明治二十三年(一八九〇)・東風(春風)など」
(子規・二十四歳。第一高等中学校卒、帝国大学文化大学哲学科入学。碧悟桐を指導。)
https://shiki-museum.com/masaokashiki/haiku?post_type=haiku&haiku_id&p_age=23&season&classification&kigo=%E6%98%A5%E9%A2%A8&s&select&doing_wp_cron=1694306169.9556319713592529296875
春風の吹き残したり富士の雪 ID623 制作年23 季節春 分類天文 季語春風
春風も眠る日和や子守うた ID625 制作年23 季節春 分類天文 季語春風
(漱石・二十四歳。帝国大学文化大学英文科入学。)
https://yahan.blog.ss-blog.jp/2023-08-21
4 寐てくらす人もありけり夢の世に(「眼病で退屈している」旨の子規宛書簡、無季)
6 東風吹くや山一ぱいの雲の影(「東風(こち)」=東から吹く風。春風)
(※=付記)
※2337 春風に吹かれ心地や温泉(ゆ)の戻り(大正三年作。四十八歳)
(追記)
(寅彦=「漱石」との出会い「明治二十九年・十八歳時=第五高校入学時。出典=『牛頓先生俳句集・季題別』、『寺田寅彦全集/文学篇/七巻』」)
電線に凧のかかりて春の風(明治三十一~二年作。「漱石へ送りたる句稿その十一」)
春風や遊女屋並ぶ向ふ岸(明治三十二年作。「ホトトギス(五月)」)
(東洋城=「明治二十八年、十八歳時、松山中学校五年生の四月、漱石が教師として来任し、英語の教授を受ける。明治三十六年、二十六歳時、漱石帰朝、一高・東大講師となり、漱石を師とする。腸チフスで東大休学、翌年、新設の京大に入学、明治三十八年、京大卒業、翌年、二十九歳時に、宮内省に入り、式部官などを歴任。出典=『東洋城全句集(上・中・下)』の中巻の「年譜」)
東風の汐膨ると思ひ地球かな(明治四十四年作。三十四歳)
東風吹くや伊豆眞鶴へただむきに(大正四年作。三十八歳)
東風の汐昔江の島といふを遺しぬ(同上)
東風吹くや鶏犬声を忘れ里(昭和八年作、五十六歳)
(参考)「 ※2337 春風に吹かれ心地や温泉(ゆ)の戻り(漱石、大正三年作。四十八歳)
https://plaza.rakuten.co.jp/akiradoinaka/diary/201901290000/

「春風に吹かれ心地や温泉(ゆ)の戻り(大正三年作。四十八歳)」当時の「漱石・千駄木時代」の「銭湯風景」(?)
https://plaza.rakuten.co.jp/akiradoinaka/diary/201901290000/
≪ 垢つきし赤き手絡や春惜しむ(明治41)
黍遠し河原の風呂へ渡る人(明治43)
春風に吹かれ心地や温泉の戻り(大正3)
漱石の長女・筆子の回想録『夏目漱石の「猫」の娘』によると、初めて自宅に風呂がとりつけられたのは、家中で大騒ぎだったといいます。
筆子の娘婿である半藤一利は『漱石先生ぞな、もし』で「漱石邸に内風呂が入ったのは? となると、残念ながらさだかではないが、明治末年、少なくとも大正元年に『彼岸過迄』が書かれる直前ぐらいのことではないかと二ランでいる。おそらく明治四十三年の修善寺大患後であろう。千駄木町の家に湯殿のあったことを示す図解があるが、風呂桶は据えられていなかったのである」とあります。長女の筆子が生まれたのは明治32年ですから、20歳前後の頃だったのでしょう。
初めて、私の家にお風呂がとりつけられた時にも、家中で大騒ぎをした記憶がございます。家中はしゃぎ回って、私達は勿論のこと、父まで、何度も何度も書斎から出て来ては、お風呂に手を突込んで熱さ加減をみながら、右往左往して居りました。
ところが、誰一人として、お湯を下の方から掻きまわさなければならないことを知らないのです。お手伝いさんの一人が、手を入れてもう良さそうだと、「旦那様、お湯がわきました」と書斎の父に報らせに参りますと、
「うん、よし、よし」
と待ちに待って板父が、張り切って出て参りました。
ジャブンと飛び込んだ途端に、
「ひやっ、冷たい」 ≫

道後温泉本館「泳ぐべからず」
https://kinarino.jp/cat8/33008
≪ おれはここへ来てから、毎日住田の温泉へ行くことに極(き)めている。ほかの所は何を見ても東京の足元にも及ばないが温泉丈(だけ)は立派なものだ。」
そう坊っちゃんも褒める「住田の温泉」とは、道後温泉のこと。道後温泉本館が完成した翌年の明治28(1895)年に松山に赴任した漱石は、知人にあてた手紙の中でも絶賛するほど道後温泉がお気に入りで、「坊っちゃん」さながら足繁く通っていたそうです。≫
(子規・二十四歳。第一高等中学校卒、帝国大学文化大学哲学科入学。碧悟桐を指導。)
https://shiki-museum.com/masaokashiki/haiku?post_type=haiku&haiku_id&p_age=23&season&classification&kigo=%E6%98%A5%E9%A2%A8&s&select&doing_wp_cron=1694306169.9556319713592529296875
春風の吹き残したり富士の雪 ID623 制作年23 季節春 分類天文 季語春風
春風も眠る日和や子守うた ID625 制作年23 季節春 分類天文 季語春風
(漱石・二十四歳。帝国大学文化大学英文科入学。)
https://yahan.blog.ss-blog.jp/2023-08-21
4 寐てくらす人もありけり夢の世に(「眼病で退屈している」旨の子規宛書簡、無季)
6 東風吹くや山一ぱいの雲の影(「東風(こち)」=東から吹く風。春風)
(※=付記)
※2337 春風に吹かれ心地や温泉(ゆ)の戻り(大正三年作。四十八歳)
(追記)
(寅彦=「漱石」との出会い「明治二十九年・十八歳時=第五高校入学時。出典=『牛頓先生俳句集・季題別』、『寺田寅彦全集/文学篇/七巻』」)
電線に凧のかかりて春の風(明治三十一~二年作。「漱石へ送りたる句稿その十一」)
春風や遊女屋並ぶ向ふ岸(明治三十二年作。「ホトトギス(五月)」)
(東洋城=「明治二十八年、十八歳時、松山中学校五年生の四月、漱石が教師として来任し、英語の教授を受ける。明治三十六年、二十六歳時、漱石帰朝、一高・東大講師となり、漱石を師とする。腸チフスで東大休学、翌年、新設の京大に入学、明治三十八年、京大卒業、翌年、二十九歳時に、宮内省に入り、式部官などを歴任。出典=『東洋城全句集(上・中・下)』の中巻の「年譜」)
東風の汐膨ると思ひ地球かな(明治四十四年作。三十四歳)
東風吹くや伊豆眞鶴へただむきに(大正四年作。三十八歳)
東風の汐昔江の島といふを遺しぬ(同上)
東風吹くや鶏犬声を忘れ里(昭和八年作、五十六歳)
(参考)「 ※2337 春風に吹かれ心地や温泉(ゆ)の戻り(漱石、大正三年作。四十八歳)
https://plaza.rakuten.co.jp/akiradoinaka/diary/201901290000/

「春風に吹かれ心地や温泉(ゆ)の戻り(大正三年作。四十八歳)」当時の「漱石・千駄木時代」の「銭湯風景」(?)
https://plaza.rakuten.co.jp/akiradoinaka/diary/201901290000/
≪ 垢つきし赤き手絡や春惜しむ(明治41)
黍遠し河原の風呂へ渡る人(明治43)
春風に吹かれ心地や温泉の戻り(大正3)
漱石の長女・筆子の回想録『夏目漱石の「猫」の娘』によると、初めて自宅に風呂がとりつけられたのは、家中で大騒ぎだったといいます。
筆子の娘婿である半藤一利は『漱石先生ぞな、もし』で「漱石邸に内風呂が入ったのは? となると、残念ながらさだかではないが、明治末年、少なくとも大正元年に『彼岸過迄』が書かれる直前ぐらいのことではないかと二ランでいる。おそらく明治四十三年の修善寺大患後であろう。千駄木町の家に湯殿のあったことを示す図解があるが、風呂桶は据えられていなかったのである」とあります。長女の筆子が生まれたのは明治32年ですから、20歳前後の頃だったのでしょう。
初めて、私の家にお風呂がとりつけられた時にも、家中で大騒ぎをした記憶がございます。家中はしゃぎ回って、私達は勿論のこと、父まで、何度も何度も書斎から出て来ては、お風呂に手を突込んで熱さ加減をみながら、右往左往して居りました。
ところが、誰一人として、お湯を下の方から掻きまわさなければならないことを知らないのです。お手伝いさんの一人が、手を入れてもう良さそうだと、「旦那様、お湯がわきました」と書斎の父に報らせに参りますと、
「うん、よし、よし」
と待ちに待って板父が、張り切って出て参りました。
ジャブンと飛び込んだ途端に、
「ひやっ、冷たい」 ≫

道後温泉本館「泳ぐべからず」
https://kinarino.jp/cat8/33008
≪ おれはここへ来てから、毎日住田の温泉へ行くことに極(き)めている。ほかの所は何を見ても東京の足元にも及ばないが温泉丈(だけ)は立派なものだ。」
そう坊っちゃんも褒める「住田の温泉」とは、道後温泉のこと。道後温泉本館が完成した翌年の明治28(1895)年に松山に赴任した漱石は、知人にあてた手紙の中でも絶賛するほど道後温泉がお気に入りで、「坊っちゃん」さながら足繁く通っていたそうです。≫
タグ:子規・漱石・寅彦・東洋城
「子規・漱石・寅彦・東洋城」(~子規没まで)俳句管見(その一) [子規・漱石・寅彦・東洋城]
その一「明治二十二年(一八八九)・時鳥(子規・ほととぎす)など」
(子規・二十三歳。正月、漱石を知る。五月九日喀血。)
https://shiki-museum.com/masaokashiki/haiku?post_type=haiku&haiku_id&p_age=22&season&classification&kigo=%E6%99%82%E9%B3%A5&s&select&doing_wp_cron=1694245298.6711421012878417968750
川向ひどこのやしきへ時鳥 ID501 制作年22 季節夏 分類動物 季語時鳥
五月雨を思ふてなくか子規 ID502 制作年22 季節夏 分類動物 季語時鳥
往て還るほどは夜もなし子規 ID508 制作年22 季節夏 分類動物 季語時鳥
卯の花をめかけてきたかほとゝきす ID509 制作年22 季節夏 分類植物 季語卯の花
(漱石・二十三歳。子規見舞い二句)
https://yahan.blog.ss-blog.jp/2023-08-19
(再掲)
漱石の俳句は、明治二十二年(一八八九)に、東京大学(予備門)での、正岡子規との出会いによる、次の二句から始まる。
1 帰ろふと鳴かずに笑へ時鳥 (漱石・23歳「明治22年(1889)」)
2 聞かふとて誰も待たぬに時鳥 (漱石・23歳「明治22年(1889)」)
≪季語=時鳥(夏)。「時鳥」の異名「不如帰」(帰るに如かず)に託して喀血した正岡子規を激励した句。子規と時鳥とは同義。正岡子規は明治二十二年五月九日に喀血した。翌日、医者に肺病と診断され、「卯の花をめがけてきたか時鳥」「卯の花の散るまで鳴くか子規」などの句を作った。卯の花を自分になぞらえ(子規は卯年生れ)、肺病(結核)を時鳥と表現俳句。(中略) 子規はこれらの俳句を作ったことから、自ら子規と号するようになった。この年の一月頃に急速に親しくなった漱石は、五月十三日に子規を見舞い、その帰途に子規のかかっていた医師を訪ねて病状や療養の仕方を聞いている。(後略 )≫(『漱石全集第十七巻・坪内稔典注解』)
(追記)
(寅彦=「漱石」との出会い「明治二十九年・十八歳時=第五高校入学時。出典=『牛頓先生俳句集・季題別』、『寺田寅彦全集/文学篇/七巻』」)
時鳥京に客たる三年目 (明治三十四年作。満二十三歳)
時鳥一寸先の闇の声 (同上)
時鳥くらがり坂を君帰る (同上)
時鳥剣(けん)を按(あん)じて失せ玉ひぬ(同上、「失せ玉ひぬ」の原句は「君逝けり」)
(東洋城=「明治二十八年、十八歳時、松山中学校五年生の四月、漱石が教師として来任し、英語の教授を受ける。明治三十三年、二十三歳時、一高・東大へ入学、東洋城と号す。明治三十六年、二十六歳時、漱石帰朝、一高・東大講師となり、漱石を師とする。腸チフスで東大休学、翌年、新設の京大に入学、明治三十八年、京大卒業、翌年、二十九歳時に、宮内省に入り、式部官などを歴任。出典=『東洋城全句集(上・中・下)』の中巻の「年譜」)
時鳥牡丹に月の雫せよ(明治三十五年作。二十五歳)
時鳥硯に墨を立てる時(明治四十三年作。三十三歳)
二階から朝顔棚や時鳥(同上)
時鳥雨の鳥居は松の中(同上)
時鳥も鳴かで明けたる一夜かな(大正十五年、昭和元年、四十九歳)
時鳥あららぎに奈良の夜あるかな(昭和四年作、五十二歳)
.jpg)
「紫陽花郭公図(あじさいほととぎすず)」日本画 / 絵画 / 江戸 / 日本/与謝蕪村 (1716-1784年)/江戸時代/明和7-安永6/紙本,墨画淡彩/38.7 x 64.3cm(「文化遺産オンライン」)
https://bunka.nii.ac.jp/heritages/detail/90300
≪(解説) 俳人、文人、画家であった蕪村は、享保年間末に江戸に下り、俳諧を学び、江戸俳壇に出る一方、絵画にも親しみ、寛保初年に江戸を後にして放浪生活に入り、各地を旅して10年余を過ごした。宝暦初年に京に上り、画業に心を寄せ、国内のさまざまな流派はもとより、中国諸家の作品や版本類を研究して自己の画風を形成した。初期文人画の足跡を受け継ぎ、日本の文人画を大成したのは池大雅と与謝蕪村であった。中国への憧れをもちつつもその影響を離れ、日本的な文人画を創り出すことに大きく貢献した。「岩くらの狂女戀せよほととぎす」この句は天明三年刊維駒編『五車反古』に出ている。おそらく蕪村最晩年の句であろう。空に鋭く啼き渡る郭公と、たっぷりとした墨色の葉にすがすがしい藍色の施された紫陽花が大きく描かれている。句のもつ激しい情調を象徴的に表した珠玉の作品である。≫
(参考) 「一寸先は闇ではなく光」(周辺)
時鳥一寸先の闇の声(寅彦、明治三十四年作。二十三歳)
https://www.engakuji.or.jp/blog/35010/
(抜粋)
≪ 「二度とない人生(坂村真民)」
(1989年 「二度とない人生だから」は藤掛廣幸に依り曲が付けられ8月6日に「89 海と島の博覧会・ひろしま」のメイン会場で初演された。)
二度とない人生だから
二度とない人生だから
一輪の花にも
無限の愛を
そそいでゆこう
一羽の鳥の声にも
無心の耳を
かたむけてゆこう
二度とない人生だから
一匹のこおろぎでも
ふみころさないように
こころしてゆこう
どんなにか
よろこぶことだろう
二度とない人生だから
一ぺんでも多く
便りをしよう
返事は必ず
書くことにしよう
二度とない人生だから
まず一番身近な者たちに
できるだけのことをしよう
貧しいけれど
こころ豊かに接してゆこう
二度とない人生だから
つゆくさのつゆにも
めぐりあいのふしぎを思い
足をとどめてみつめてゆこう
二度とない人生だから
のぼる日 しずむ日
まるい月 かけてゆく月
四季それぞれの
星々の光にふれて
わがこころを
あらいきよめてゆこう
二度とない人生だから
戦争のない世の
実現に努力し
そういう詩を
一遍でも多く
作ってゆこう
わたしが死んだら
あとをついでくれる
若い人たちのために
この大願を
書きつづけてゆこう ≫
(子規・二十三歳。正月、漱石を知る。五月九日喀血。)
https://shiki-museum.com/masaokashiki/haiku?post_type=haiku&haiku_id&p_age=22&season&classification&kigo=%E6%99%82%E9%B3%A5&s&select&doing_wp_cron=1694245298.6711421012878417968750
川向ひどこのやしきへ時鳥 ID501 制作年22 季節夏 分類動物 季語時鳥
五月雨を思ふてなくか子規 ID502 制作年22 季節夏 分類動物 季語時鳥
往て還るほどは夜もなし子規 ID508 制作年22 季節夏 分類動物 季語時鳥
卯の花をめかけてきたかほとゝきす ID509 制作年22 季節夏 分類植物 季語卯の花
(漱石・二十三歳。子規見舞い二句)
https://yahan.blog.ss-blog.jp/2023-08-19
(再掲)
漱石の俳句は、明治二十二年(一八八九)に、東京大学(予備門)での、正岡子規との出会いによる、次の二句から始まる。
1 帰ろふと鳴かずに笑へ時鳥 (漱石・23歳「明治22年(1889)」)
2 聞かふとて誰も待たぬに時鳥 (漱石・23歳「明治22年(1889)」)
≪季語=時鳥(夏)。「時鳥」の異名「不如帰」(帰るに如かず)に託して喀血した正岡子規を激励した句。子規と時鳥とは同義。正岡子規は明治二十二年五月九日に喀血した。翌日、医者に肺病と診断され、「卯の花をめがけてきたか時鳥」「卯の花の散るまで鳴くか子規」などの句を作った。卯の花を自分になぞらえ(子規は卯年生れ)、肺病(結核)を時鳥と表現俳句。(中略) 子規はこれらの俳句を作ったことから、自ら子規と号するようになった。この年の一月頃に急速に親しくなった漱石は、五月十三日に子規を見舞い、その帰途に子規のかかっていた医師を訪ねて病状や療養の仕方を聞いている。(後略 )≫(『漱石全集第十七巻・坪内稔典注解』)
(追記)
(寅彦=「漱石」との出会い「明治二十九年・十八歳時=第五高校入学時。出典=『牛頓先生俳句集・季題別』、『寺田寅彦全集/文学篇/七巻』」)
時鳥京に客たる三年目 (明治三十四年作。満二十三歳)
時鳥一寸先の闇の声 (同上)
時鳥くらがり坂を君帰る (同上)
時鳥剣(けん)を按(あん)じて失せ玉ひぬ(同上、「失せ玉ひぬ」の原句は「君逝けり」)
(東洋城=「明治二十八年、十八歳時、松山中学校五年生の四月、漱石が教師として来任し、英語の教授を受ける。明治三十三年、二十三歳時、一高・東大へ入学、東洋城と号す。明治三十六年、二十六歳時、漱石帰朝、一高・東大講師となり、漱石を師とする。腸チフスで東大休学、翌年、新設の京大に入学、明治三十八年、京大卒業、翌年、二十九歳時に、宮内省に入り、式部官などを歴任。出典=『東洋城全句集(上・中・下)』の中巻の「年譜」)
時鳥牡丹に月の雫せよ(明治三十五年作。二十五歳)
時鳥硯に墨を立てる時(明治四十三年作。三十三歳)
二階から朝顔棚や時鳥(同上)
時鳥雨の鳥居は松の中(同上)
時鳥も鳴かで明けたる一夜かな(大正十五年、昭和元年、四十九歳)
時鳥あららぎに奈良の夜あるかな(昭和四年作、五十二歳)
.jpg)
「紫陽花郭公図(あじさいほととぎすず)」日本画 / 絵画 / 江戸 / 日本/与謝蕪村 (1716-1784年)/江戸時代/明和7-安永6/紙本,墨画淡彩/38.7 x 64.3cm(「文化遺産オンライン」)
https://bunka.nii.ac.jp/heritages/detail/90300
≪(解説) 俳人、文人、画家であった蕪村は、享保年間末に江戸に下り、俳諧を学び、江戸俳壇に出る一方、絵画にも親しみ、寛保初年に江戸を後にして放浪生活に入り、各地を旅して10年余を過ごした。宝暦初年に京に上り、画業に心を寄せ、国内のさまざまな流派はもとより、中国諸家の作品や版本類を研究して自己の画風を形成した。初期文人画の足跡を受け継ぎ、日本の文人画を大成したのは池大雅と与謝蕪村であった。中国への憧れをもちつつもその影響を離れ、日本的な文人画を創り出すことに大きく貢献した。「岩くらの狂女戀せよほととぎす」この句は天明三年刊維駒編『五車反古』に出ている。おそらく蕪村最晩年の句であろう。空に鋭く啼き渡る郭公と、たっぷりとした墨色の葉にすがすがしい藍色の施された紫陽花が大きく描かれている。句のもつ激しい情調を象徴的に表した珠玉の作品である。≫
(参考) 「一寸先は闇ではなく光」(周辺)
時鳥一寸先の闇の声(寅彦、明治三十四年作。二十三歳)
https://www.engakuji.or.jp/blog/35010/
(抜粋)
≪ 「二度とない人生(坂村真民)」
(1989年 「二度とない人生だから」は藤掛廣幸に依り曲が付けられ8月6日に「89 海と島の博覧会・ひろしま」のメイン会場で初演された。)
二度とない人生だから
二度とない人生だから
一輪の花にも
無限の愛を
そそいでゆこう
一羽の鳥の声にも
無心の耳を
かたむけてゆこう
二度とない人生だから
一匹のこおろぎでも
ふみころさないように
こころしてゆこう
どんなにか
よろこぶことだろう
二度とない人生だから
一ぺんでも多く
便りをしよう
返事は必ず
書くことにしよう
二度とない人生だから
まず一番身近な者たちに
できるだけのことをしよう
貧しいけれど
こころ豊かに接してゆこう
二度とない人生だから
つゆくさのつゆにも
めぐりあいのふしぎを思い
足をとどめてみつめてゆこう
二度とない人生だから
のぼる日 しずむ日
まるい月 かけてゆく月
四季それぞれの
星々の光にふれて
わがこころを
あらいきよめてゆこう
二度とない人生だから
戦争のない世の
実現に努力し
そういう詩を
一遍でも多く
作ってゆこう
わたしが死んだら
あとをついでくれる
若い人たちのために
この大願を
書きつづけてゆこう ≫



