四季花卉下絵古今集和歌巻(その十二) [光悦・宗達・素庵]
その十二 妙顕寺の「尾形光琳の墓」など

B図:寛永後萬治前洛中絵図(部分図・京都大学附属図書館蔵)
https://rmda.kulib.kyoto-u.ac.jp/libraries/uv-wrapper/uv.php?archive=metadata_manifest&id=RB00000143#?c=0&m=0&s=0&cv=0&xywh=30213%2C8303%2C3087%2C6111&r=270
上図(B図)の中央上部が、本阿弥家(そして光悦)の菩提寺の「本法寺」、その左側(西側)には、光悦筆の「立正安国論」を所蔵している「妙蓮寺」、そして、右側(東側)は、「妙顕寺」である。
この「妙顕寺」は、「本能寺」が織田信長の京都の宿泊寺とすると、「妙顕寺」は豊臣秀吉の京都の宿泊寺と、秀吉と関係の深い「日蓮宗大本山」の、京都法華宗の根本をなす寺である。そして、この「妙顕寺」の塔頭(本寺=妙顕寺の境内にある小寺)の「泉妙院」(妙顕寺の興善院の旧跡)が、尾形光琳・乾山の「尾形家」の菩提所なのである。
この「泉妙院」については、下記のアドレスで紹介されている。
https://kyotofukoh.jp/report350.html
そのアドレスの「泉妙院」のマップ図は、次のとおりである。

C図「妙顕寺と泉妙院」マップ図(中央上部の赤の位置マークの地点=泉妙院)
ここには(C図)、光悦と等伯と関係の深い「本法寺」(日蓮宗本山)も、「妙蓮寺」(本門法華宗大本山)も図示されていないが、「本法寺」は、この地図の「茶道総合資料館」の右(東)寄り、そして、「妙蓮寺」は左(西)寄りに位置する。
https://blog.goo.ne.jp/korede193/e/788d6d021e1305253c20b39434684815
↓
尾形光琳とその一族の墓は、日蓮宗大本山妙顕寺の表門の東に接する塔頭・泉妙院にあって境内の北隅に南面する4つの墓石がそれである。この内中央の大小2基の墓石が古く、光琳の没後につくられたもので、大碑の方には尾形家の初代伊春以下、2代道柏(光琳の曾祖父)、3代宗伯(光琳の祖父)、4代宗甫(光琳の叔父)、5代宗謙(光琳の父)及び光琳の「長江軒寂明青々光琳」の法名がきざまれ、小碑の方には、光琳の弟乾山の法名「雲海深省居士」をはじめ10数名の名がみえ、尾形家の有為転変さを如実に示しているようである。
↓
尾形(緒方)家はもと武家であったが、のちに町人になり、雁金屋と号し、京呉服商を営み、巨万の財を成した江戸初期の豪商である。2代目道柏までは貧乏であったが、本阿弥光悦の姉(日秀)を妻に迎えてから家運は次第に栄え、後には上層町人の筆頭の一人となった。
↓
このような家柄であったから、当然墓も立派なものを建てるべきであるが、5代目宗謙の子 藤三郎、子 市之丞(光琳)兄弟の徹底的な遊蕩によって、家庭を蕩尽し、のちには個々の墓をたてることができず、このような合葬墓としたものだろう。墓石の側面に「小形」とあるのは、晩年の光琳が家運の挽回を図って「尾形」と姓を改めたのだが、ついに復興することができず、光琳の没後しばらくして同家は断絶した。元来、尾形家の宿坊は興善院といい、今の泉妙院のあたりにあったと伝える。しかし尾形家断絶後は墓のみ残して取り払い、本行院(妙顕寺塔頭)の管理下に入った。その本行院も天明の大火によって焼亡したので、墓は妙顕寺の総墓地に移すことに至った。
↓
光琳が没して100年後に画家酒井抱一は光琳を追慕するあまり上洛し(メモ:抱一の名代・佐原鞠塢を派遣し、調査させる)、尾形家の墓に詣で、本行院跡に光琳だけの墓を建てたのが、現在善行院(妙顕寺塔頭)の南にあるのがそれである。これには表面に「長江軒青々光琳墓」、側面に「文政2年(1819)画家酒井抱一再建」の旨をしるしている。一方、泉妙院は天保2年(1831)尾形家の宿坊興善院跡に建立され、旧本行院が預かっていた尾形家先祖の墓を管理し、またその菩提寺となったが、一般には酒井抱一の建てた墓が光琳の本墓とみられ、妙顕寺総墓地のある肝心の古い墓は忘れられたかたちになっていた。近年、光琳・乾山兄弟の名が有名になるにつれ、寺もほっておけなくなり、昭和37年、総墓地から古い墓を移し、さらに昭和57年有志の人によって、光琳・乾山両人の供養塔(宝塔)が建立され、併せて光琳の位牌が保管されるに至った。

D図「尾形光琳邸宅跡」(上御霊前通東入る北側=上記赤の位置マーク)
https://blog.goo.ne.jp/korede193/e/788d6d021e1305253c20b39434684815
↓
上御霊神社より西、烏丸通に及ぶ上御霊中町の西北部は、尾形光琳が生涯の半ばをすごし、ここで没したところである。光琳は呉服商 雁金屋宗謙の次男として、万治元年(1658)に生まれた金持ちのぼんぼんで、若い頃から兄藤三郎とともにぜいたく三昧な生活を送ったため、兄は廃嫡となり、父が亡くなって家督をついだ頃家業は左前になっていた。そこで上京区智恵光院中立売下ル西側、山里町にあった広大な屋敷を売り払い、上京薮内町とよばれていたこの地に転居するに至った。
https://ja.kyoto.travel/journey/winter2018/special/public01.php?special_exhibition_id=8

E図 長谷川等伯筆「波龍図屏風」(六曲一隻のうち「第二扇から第四扇) 本法寺蔵
上記は、等伯の本法寺所蔵の「波龍図屏風」(六曲一隻)の部分図である。等伯には、この種の「龍虎図」を何点か手掛けているが、その代表的なものが、下記のアドレスで紹介されているボストン美術館所蔵の「龍虎図屏風」(六曲一双)である。この作品には、「自雪舟五代長谷川法眼等伯」の署名があり、等伯、六十八歳の時のものである。
https://j-art.hix05.com/16.2.hasegawa-tohaku/tohaku16.ryuko.html

F図 長谷川等伯筆「龍虎図屏風」(六曲一双のうち「左隻の第四扇から第六扇) ボストン美術館蔵(綴プロジェクト画像)
https://www.kyohaku.go.jp/jp/syuzou/meihin/kinsei/item09.html

J図 尾形光琳筆「竹虎図」(紙本墨画 28.3×39.0cm) 京都国立博物館蔵
【著色の花鳥図や草花図などを描く時の光琳には、どこかしら肩肘張ったように見受けられる場合があるが、墨画に関してはまことに軽妙で、親しみ易い作品が多い。その代表作品が「維摩図」と本図である。竹林を背景にちんまりと腰をおろした虎は、いたずらっ子のようなやんちゃな眼をして横を睨む。中国画の影響を受けた狩野山楽などの「龍虎図」が、強烈な力と力の対決の場面に仕上げているのに比すれば、これはもはや戯画とでも称すべき画風であって、本図が対幅であったとすれば、龍もまた愛くるしい龍であるに違いない。それにしても戯画を描くということは、画家の自由性を物語って余りある。】
この光琳の「虎」(J図)は、等伯の「虎」(F図)に通じていて、それを一層戯画化し、「まことに軽妙で、親しみ易い作品」に仕上がっている。
https://global.canon/ja/tsuzuri/works/17.html

H図 俵屋宗達筆「雲龍図屏風」(六曲一双のうち「右隻の第一扇から第三扇) フリーア美術館蔵(綴プロジェクト画像)
https://j-art.hix05.com/17sotatsu/sotatsu13.unryu.html
【「雲龍図屏風」は、「松島図屏風」とともに海外に流出した宗達の傑作。ワシントンのフリーア美術館が所蔵している。水墨画の名品だ。六曲一双の屏風絵で、左右の龍が互いに睨みあっている図柄だ。どちらも背景を黒く塗りつぶすことで、龍の輪郭を浮かび上がらせる工夫をしている。また、波の描き方に、宗達らしい特徴がある。(中略)
こちらは右隻の図柄(メモ:上図H図)。左の龍とは対照的な姿勢で、左隻の龍を睨んでいる。その表情にはどこかしらユーモアが感じられる。波の描き方は、細い線を組み合わせる手法をとっているが、この手法は光琳や抱一にそのまま受け継がれていった。全体として、墨の濃淡を生かした、ダイナミックさを感じさせる絵である。(紙本墨画 各150.6×353.6㎝ フリーア美術館) 】
この宗達の「龍」(H図)も、等伯の「龍」(E図)の「厳しい目つき」ではなく、同じ等伯の「虎」(F図)の「優しげな眼つき」をも加味している雰囲気を有している。
これらは、等伯が、織田信長、そして、豊臣秀吉の激動の時代を潜り抜けてきた冷厳な絵師の眼とすると、宗達は、慶長五年(一六〇〇)の「関ヶ原の戦い」以後の「パクス・トクガワーナ」(戦乱なき徳川時代)の夜明け前後の、闊達自在な絵師の眼ということになろう。
そして、光琳は、その「パクス・トクガワーナ」(戦乱なき徳川時代)の頂点の「元禄文化」(「憂き世から浮世へ」の時代)の、華麗優美な絵師の眼ということになろう。
ここに一つ付け加えることは、これらの「等伯から宗達・光琳」への橋渡しをした中心人物こそ、等伯より、二十歳前後若い、そして、宗達・光琳と続く「琳派の創始者」(書家・陶芸家・蒔絵師・芸術家・茶人)たる本阿弥光悦その人ということになろう。

B図:寛永後萬治前洛中絵図(部分図・京都大学附属図書館蔵)
https://rmda.kulib.kyoto-u.ac.jp/libraries/uv-wrapper/uv.php?archive=metadata_manifest&id=RB00000143#?c=0&m=0&s=0&cv=0&xywh=30213%2C8303%2C3087%2C6111&r=270
上図(B図)の中央上部が、本阿弥家(そして光悦)の菩提寺の「本法寺」、その左側(西側)には、光悦筆の「立正安国論」を所蔵している「妙蓮寺」、そして、右側(東側)は、「妙顕寺」である。
この「妙顕寺」は、「本能寺」が織田信長の京都の宿泊寺とすると、「妙顕寺」は豊臣秀吉の京都の宿泊寺と、秀吉と関係の深い「日蓮宗大本山」の、京都法華宗の根本をなす寺である。そして、この「妙顕寺」の塔頭(本寺=妙顕寺の境内にある小寺)の「泉妙院」(妙顕寺の興善院の旧跡)が、尾形光琳・乾山の「尾形家」の菩提所なのである。
この「泉妙院」については、下記のアドレスで紹介されている。
https://kyotofukoh.jp/report350.html
そのアドレスの「泉妙院」のマップ図は、次のとおりである。

C図「妙顕寺と泉妙院」マップ図(中央上部の赤の位置マークの地点=泉妙院)
ここには(C図)、光悦と等伯と関係の深い「本法寺」(日蓮宗本山)も、「妙蓮寺」(本門法華宗大本山)も図示されていないが、「本法寺」は、この地図の「茶道総合資料館」の右(東)寄り、そして、「妙蓮寺」は左(西)寄りに位置する。
https://blog.goo.ne.jp/korede193/e/788d6d021e1305253c20b39434684815
↓
尾形光琳とその一族の墓は、日蓮宗大本山妙顕寺の表門の東に接する塔頭・泉妙院にあって境内の北隅に南面する4つの墓石がそれである。この内中央の大小2基の墓石が古く、光琳の没後につくられたもので、大碑の方には尾形家の初代伊春以下、2代道柏(光琳の曾祖父)、3代宗伯(光琳の祖父)、4代宗甫(光琳の叔父)、5代宗謙(光琳の父)及び光琳の「長江軒寂明青々光琳」の法名がきざまれ、小碑の方には、光琳の弟乾山の法名「雲海深省居士」をはじめ10数名の名がみえ、尾形家の有為転変さを如実に示しているようである。
↓
尾形(緒方)家はもと武家であったが、のちに町人になり、雁金屋と号し、京呉服商を営み、巨万の財を成した江戸初期の豪商である。2代目道柏までは貧乏であったが、本阿弥光悦の姉(日秀)を妻に迎えてから家運は次第に栄え、後には上層町人の筆頭の一人となった。
↓
このような家柄であったから、当然墓も立派なものを建てるべきであるが、5代目宗謙の子 藤三郎、子 市之丞(光琳)兄弟の徹底的な遊蕩によって、家庭を蕩尽し、のちには個々の墓をたてることができず、このような合葬墓としたものだろう。墓石の側面に「小形」とあるのは、晩年の光琳が家運の挽回を図って「尾形」と姓を改めたのだが、ついに復興することができず、光琳の没後しばらくして同家は断絶した。元来、尾形家の宿坊は興善院といい、今の泉妙院のあたりにあったと伝える。しかし尾形家断絶後は墓のみ残して取り払い、本行院(妙顕寺塔頭)の管理下に入った。その本行院も天明の大火によって焼亡したので、墓は妙顕寺の総墓地に移すことに至った。
↓
光琳が没して100年後に画家酒井抱一は光琳を追慕するあまり上洛し(メモ:抱一の名代・佐原鞠塢を派遣し、調査させる)、尾形家の墓に詣で、本行院跡に光琳だけの墓を建てたのが、現在善行院(妙顕寺塔頭)の南にあるのがそれである。これには表面に「長江軒青々光琳墓」、側面に「文政2年(1819)画家酒井抱一再建」の旨をしるしている。一方、泉妙院は天保2年(1831)尾形家の宿坊興善院跡に建立され、旧本行院が預かっていた尾形家先祖の墓を管理し、またその菩提寺となったが、一般には酒井抱一の建てた墓が光琳の本墓とみられ、妙顕寺総墓地のある肝心の古い墓は忘れられたかたちになっていた。近年、光琳・乾山兄弟の名が有名になるにつれ、寺もほっておけなくなり、昭和37年、総墓地から古い墓を移し、さらに昭和57年有志の人によって、光琳・乾山両人の供養塔(宝塔)が建立され、併せて光琳の位牌が保管されるに至った。

D図「尾形光琳邸宅跡」(上御霊前通東入る北側=上記赤の位置マーク)
https://blog.goo.ne.jp/korede193/e/788d6d021e1305253c20b39434684815
↓
上御霊神社より西、烏丸通に及ぶ上御霊中町の西北部は、尾形光琳が生涯の半ばをすごし、ここで没したところである。光琳は呉服商 雁金屋宗謙の次男として、万治元年(1658)に生まれた金持ちのぼんぼんで、若い頃から兄藤三郎とともにぜいたく三昧な生活を送ったため、兄は廃嫡となり、父が亡くなって家督をついだ頃家業は左前になっていた。そこで上京区智恵光院中立売下ル西側、山里町にあった広大な屋敷を売り払い、上京薮内町とよばれていたこの地に転居するに至った。
https://ja.kyoto.travel/journey/winter2018/special/public01.php?special_exhibition_id=8

E図 長谷川等伯筆「波龍図屏風」(六曲一隻のうち「第二扇から第四扇) 本法寺蔵
上記は、等伯の本法寺所蔵の「波龍図屏風」(六曲一隻)の部分図である。等伯には、この種の「龍虎図」を何点か手掛けているが、その代表的なものが、下記のアドレスで紹介されているボストン美術館所蔵の「龍虎図屏風」(六曲一双)である。この作品には、「自雪舟五代長谷川法眼等伯」の署名があり、等伯、六十八歳の時のものである。
https://j-art.hix05.com/16.2.hasegawa-tohaku/tohaku16.ryuko.html

F図 長谷川等伯筆「龍虎図屏風」(六曲一双のうち「左隻の第四扇から第六扇) ボストン美術館蔵(綴プロジェクト画像)
https://www.kyohaku.go.jp/jp/syuzou/meihin/kinsei/item09.html

J図 尾形光琳筆「竹虎図」(紙本墨画 28.3×39.0cm) 京都国立博物館蔵
【著色の花鳥図や草花図などを描く時の光琳には、どこかしら肩肘張ったように見受けられる場合があるが、墨画に関してはまことに軽妙で、親しみ易い作品が多い。その代表作品が「維摩図」と本図である。竹林を背景にちんまりと腰をおろした虎は、いたずらっ子のようなやんちゃな眼をして横を睨む。中国画の影響を受けた狩野山楽などの「龍虎図」が、強烈な力と力の対決の場面に仕上げているのに比すれば、これはもはや戯画とでも称すべき画風であって、本図が対幅であったとすれば、龍もまた愛くるしい龍であるに違いない。それにしても戯画を描くということは、画家の自由性を物語って余りある。】
この光琳の「虎」(J図)は、等伯の「虎」(F図)に通じていて、それを一層戯画化し、「まことに軽妙で、親しみ易い作品」に仕上がっている。
https://global.canon/ja/tsuzuri/works/17.html

H図 俵屋宗達筆「雲龍図屏風」(六曲一双のうち「右隻の第一扇から第三扇) フリーア美術館蔵(綴プロジェクト画像)
https://j-art.hix05.com/17sotatsu/sotatsu13.unryu.html
【「雲龍図屏風」は、「松島図屏風」とともに海外に流出した宗達の傑作。ワシントンのフリーア美術館が所蔵している。水墨画の名品だ。六曲一双の屏風絵で、左右の龍が互いに睨みあっている図柄だ。どちらも背景を黒く塗りつぶすことで、龍の輪郭を浮かび上がらせる工夫をしている。また、波の描き方に、宗達らしい特徴がある。(中略)
こちらは右隻の図柄(メモ:上図H図)。左の龍とは対照的な姿勢で、左隻の龍を睨んでいる。その表情にはどこかしらユーモアが感じられる。波の描き方は、細い線を組み合わせる手法をとっているが、この手法は光琳や抱一にそのまま受け継がれていった。全体として、墨の濃淡を生かした、ダイナミックさを感じさせる絵である。(紙本墨画 各150.6×353.6㎝ フリーア美術館) 】
この宗達の「龍」(H図)も、等伯の「龍」(E図)の「厳しい目つき」ではなく、同じ等伯の「虎」(F図)の「優しげな眼つき」をも加味している雰囲気を有している。
これらは、等伯が、織田信長、そして、豊臣秀吉の激動の時代を潜り抜けてきた冷厳な絵師の眼とすると、宗達は、慶長五年(一六〇〇)の「関ヶ原の戦い」以後の「パクス・トクガワーナ」(戦乱なき徳川時代)の夜明け前後の、闊達自在な絵師の眼ということになろう。
そして、光琳は、その「パクス・トクガワーナ」(戦乱なき徳川時代)の頂点の「元禄文化」(「憂き世から浮世へ」の時代)の、華麗優美な絵師の眼ということになろう。
ここに一つ付け加えることは、これらの「等伯から宗達・光琳」への橋渡しをした中心人物こそ、等伯より、二十歳前後若い、そして、宗達・光琳と続く「琳派の創始者」(書家・陶芸家・蒔絵師・芸術家・茶人)たる本阿弥光悦その人ということになろう。
四季花卉下絵古今集和歌巻(その十一) [光悦・宗達・素庵]
その十一 妙蓮寺の「立正安国論」(光悦筆)

B図:寛永後萬治前洛中絵図(部分図・京都大学附属図書館蔵)
https://rmda.kulib.kyoto-u.ac.jp/libraries/uv-wrapper/uv.php?archive=metadata_manifest&id=RB00000143#?c=0&m=0&s=0&cv=0&xywh=30213%2C8303%2C3087%2C6111&r=270
上図(B図)の中央上部に「本法寺」、その左側(西)に「妙蓮寺」がある。ここに、光悦筆の「立正安国論 と「始聞仏乗義」とが所蔵されている。「本阿弥光悦略年表」(『光悦―琳派の創始者―(河野元昭編)所収)の元和五年(一六一九)の項に、次のような記述がある
【元和五年(一六一九) 六十二歳 本阿弥宗家九代光徳没する(一五五六~)。母の忌日にあたって『立正安国論』を、父の忌日にあたって『始聞仏乗義(儀)』を、それぞれ京都妙蓮寺の日源上人のために書く。加賀藩の長九郎左衛門連龍没する(一五四六~)。角倉素庵嵯峨に退隠して学究生活に入る。 】
本阿弥宗家(本阿弥一類=一族)の菩提寺は「本法寺」で、本阿弥家と本法寺との関係については、下記のアドレスが参考となる。
https://eishouzan.honpouji.nichiren-shu.jp/info/info.htm
「本法寺」は日蓮宗の本山(由緒寺院、開祖=日親、開基=本阿弥清信)、この「妙蓮寺」は本門法華宗の大本山(開祖=日像、開基=柳屋仲興)で、共に、天正十五年(一五八七)の、豊臣秀吉の命(聚楽第の整備に伴う都市改造)により、現在地に移転したことに伴う、強制的な隣接関係ということになる。
この「聚楽第の整備に伴う都市改造」については、次のアドレスが参考となる。
https://www.city.kyoto.lg.jp/kamigyo/page/0000012443.html
この「妙蓮寺」には、「立正安国論(三九・一㎝×三五一・四㎝)」と「始聞仏乗義(三九・一㎝×八七六㎝)」とが、当時の、「妙蓮寺法印権大僧都日源上人依御所望書之」とし、前者には「元和五年七月五日」(光悦の父の忌日)、後者には「元和五年十二月二十七日」(母の忌日)とを記し、「大虚庵光悦(花押)」の署名したものを、今に遺している。
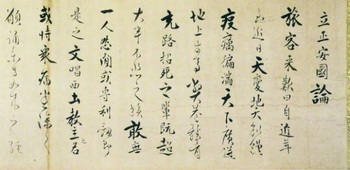
※立正安国論 本阿弥光悦筆→『書道芸術第十八巻 本阿弥光悦』作品解説136
(巻頭の部分)
【立正安国論
「旅客来たりて嘆いて曰く、
近年より近日に至るまで、
天変地夭飢饉疫癘遍く天下に満ち、
広く地上にはびこる。
牛馬巷に斃れ、骸骨路に充てり。
死を招くの輩既に大半に超え、
之を悲しまざるの族敢えて一人も無し。
然る間或いは利剣即是の文を専らとして、
西土教主の名を唱え、
或いは衆病悉除の願を恃んで、
東方如来の経を誦し、」 】
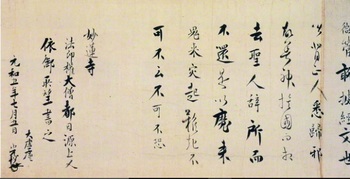
※立正安国論 本阿弥光悦筆→『書道芸術第十八巻 本阿弥光悦』作品解説136
(巻末の部分)
【いささか経文を披きたるに、世皆正に背き、
人悉く悪に帰す。故に善神国を捨てて相去り、
聖人所を辞して還らず、
是を以て魔来たり鬼来たり、
災起こり難起こる、言わずんばあるべからず、
恐れずんばあるべからずと。
妙蓮寺
法印権大僧都日源上人
依御所望書之(御所望に依って之を書す。)
元和五年七五日
大虚庵 光悦(花押) 】
(「巻頭」と巻末との間に次の文章が続く=この図録は省略されている)
http://www.daianzi.com/ronbun/ronb0138.htm
【然りと雖も、唯肝胆をくだくのみにしていよいよ
飢疫にせまる。
乞客目に溢れ、死人眼に満てり。
屍を臥せて観となし、尸を並べて橋と作す。
観ればそれ二離璧を合わせ、
五緯珠を連ね、三宝世に在し、
百王未だ窮らざるに、この世早く衰え、
その法何ぞ廃れたる。
是何なる禍に依り、是何なる誤りに由るや。
主人の曰く、独り此の事を愁えて胸臆に憤す。
客来たりて共に嘆く、しばしば談話を致さん。
それ出家して道に入る者は、
法に依って仏を期する也。
しかるに今神術もかなわず、仏威も験無し。
つぶさに当世の体をみて、
愚にして後生の疑いを発す。
然れば則ち円覆を仰いで恨みを呑み。
方載に俯して慮りを深くす。つらつら微管を傾け、
いささか経文を披きたるに、世皆正に背き、
人悉く悪に帰す。故に善神国を捨てて相去り、 】
https://ci.nii.ac.jp/naid/110008915196
↓
本阿弥光悦筆《立正安国論》《始聞仏乗義》について
Rissho Ankoku-ron and Shimonbutsujo-gi by Hon'ami Koetsu
高橋 伸城(TAKAHASHI Nobushiro 立命館大学文学研究科)
↓
【 (要点抜粋)
この寺院の再興が前政権者であった豊臣秀吉の都市計画によるものであることを考えると、日源の任期は政治的過渡期である慶長から元和に重なっていたと思われる。では日源と光悦の接点はどこにあったのか。この問題についても、寺院などに残る文書は多くを語らない。唯一手がかりとなるのが、光悦から妙蓮寺宛てに送られた手紙である。これは妙蓮寺の本光院に宛てられたものであり、光悦が昵懇にしていた神尾之直への伝言を託している。文中に膳所藩主の菅沼定芳に頼まれたという揮毫の話が出てくるが、定芳と光悦との交流を考えるとこの手紙が書かれたのは元和中期以降と推測できる。つまり、《立正安国論》等が書かれた時期にはすでに、妙蓮寺を通じて光悦と彼の友人間でメッセージの受け渡しを行うような関係が築かれていたのである。
また、妙蓮寺と光悦とのつながりを考える上で、地理的な要素も考慮しなければなるまい。秀吉の聚楽第建設によって、天正十五年(一五八七)頃から洛中の多くの寺院が移転を余儀なくされた。京都の法華宗において中心的役割を果たしてきた本法寺も例外ではなく、秀吉の命が下ってから間もなく、一条堀川から現在の堀川寺之内へと移動している。同じように妙蓮寺も都市の再編成から逃れることはできず、天文年間以降そこにあった大宮西北小路を去ることになるのだが、その移転地は本法寺のちょうど真向いであった。堀川通りを挟んで、本法寺と妙蓮寺は対峙する形になったのである
(中略)
日源もしくは光悦がなぜ「立正安国論」と「始聞仏乗義」をテキストに選んだかについては、やはり法華宗内での両書の扱われ方と無関係ではない。「立正安国論」はもともと、日蓮が文応元年(一二六〇)に国家諫暁を目的として北条時頼に提出したものである。当時、鎌倉を中心に多発していた天変地異を法華経への違背によるものとし、日蓮は時頼に改宗を迫ったのだ。臨済宗に帰依していた時頼は当然のことながらこれを退け、日蓮の迫害に満ちた人生が始まるのである。時頼に提出された「立正安国論」の原本は行方が知れないが、日蓮当人による写しが中山法華経寺に残っている。法華宗の間では重書中の重書とされ、繰り返しその教義について講義されたのみならず、後に述べるように写本も数多くつくられた。光悦の書の題材に選ばれたのも不思議ではない。
「始聞仏乗義」についても中山法華経寺に真蹟が残っており、元和頃に 最初に出版されたと考えられている『録内御書』にも、「立正安国(論」ともども収録されている((())。これは建治四年(一二七八)、日蓮から弟子の一人である富木常忍に宛てられた消息であり、内容は日蓮仏法の教義を巡る問答となっている。そして最後に、末法の凡夫がこの法華経の法門を聞けば、自身のみならず父母までをも成仏させることができると結んで終わっている。日蓮の直弟子の一人であった日興が「始聞仏乗義」を写していることなどからも、日蓮の生前からいかにこの書が大切に受け止められてきたかがわかるであろう。
(中略)
日蓮提唱の文字曼荼羅を本尊としてきた法華宗においては、書の内容だけではなく、日蓮が残した文字の形そのものも写し取るべき神聖なものであった。現在、鎌倉の妙本寺に保管されている「立正安国論」の写本は寂静房日進の筆になるものと言われているが、日蓮の原典と比べてみると、祖師の筆跡まで忠実になぞられた臨書であることがわかる(図7・図8)。
これら前例と照らし合わせると、光悦筆《立正安国論》《始聞仏乗義》の特異性がよりはっきりと浮かび上がってくる。それはつまり、光悦にそもそも日蓮の書を「写し取る」という意識はあったのかどうかという問題に言い換えられよう。
(中略)
光悦の書と日蓮のそれとを比較してみると、形と内容その両面において光悦は原典から逸脱していると言えよう。多数に上る脱字や教義に関わる誤字などは、本来の写経では許されることではない。これは、光悦の書写態度の不遜や教義の無理解からくるというよりも、そもそも彼の目指すべきものが写経者のそれとは違ったと考える方が自然であろう。《立正安国論》や《始聞仏乗義》に見られる光悦の筆は、それが写経の枠にはまるものではなく、書の「作品」として鑑賞されるべきものであることをより強調してはいないだろうか。
(後略) 】
(本法寺の重要文化財) 『ウィキペディア(Wikipedia)』
重要文化財(国指定)
松尾社一切経3545巻(附 経箱38合)
奥書院及び玄関の間障壁画 38面 長谷川派
紙本金地著色松桜図 一之間 襖貼付8、天袋貼付4
紙本金地著色松桜図 二之間 襖貼付8
紙本金地著色松杉桜図 脇一之間 襖貼付6
紙本金地著色松桜図 玄関之間 襖貼付12
附指定:紙本著色柳図 脇二之間 襖貼付4
伏見天皇宸翰法華経(沈金箱入り)8巻
※立正安国論 本阿弥光悦筆
※始聞仏乗義 本阿弥光悦筆
(メモ)
※立正安国論 本阿弥光悦筆→『書道芸術第十八巻 本阿弥光悦』作品解説136
紙本 一巻 三九・一㎝×三五一・四㎝ 元和五年(一六一九)
※始聞仏乗義 本阿弥光悦筆→『書道芸術第十八巻 本阿弥光悦』作品解説137
紙本 一巻 三九・一㎝×八七六㎝ 元和五年(一六一九)

B図:寛永後萬治前洛中絵図(部分図・京都大学附属図書館蔵)
https://rmda.kulib.kyoto-u.ac.jp/libraries/uv-wrapper/uv.php?archive=metadata_manifest&id=RB00000143#?c=0&m=0&s=0&cv=0&xywh=30213%2C8303%2C3087%2C6111&r=270
上図(B図)の中央上部に「本法寺」、その左側(西)に「妙蓮寺」がある。ここに、光悦筆の「立正安国論 と「始聞仏乗義」とが所蔵されている。「本阿弥光悦略年表」(『光悦―琳派の創始者―(河野元昭編)所収)の元和五年(一六一九)の項に、次のような記述がある
【元和五年(一六一九) 六十二歳 本阿弥宗家九代光徳没する(一五五六~)。母の忌日にあたって『立正安国論』を、父の忌日にあたって『始聞仏乗義(儀)』を、それぞれ京都妙蓮寺の日源上人のために書く。加賀藩の長九郎左衛門連龍没する(一五四六~)。角倉素庵嵯峨に退隠して学究生活に入る。 】
本阿弥宗家(本阿弥一類=一族)の菩提寺は「本法寺」で、本阿弥家と本法寺との関係については、下記のアドレスが参考となる。
https://eishouzan.honpouji.nichiren-shu.jp/info/info.htm
「本法寺」は日蓮宗の本山(由緒寺院、開祖=日親、開基=本阿弥清信)、この「妙蓮寺」は本門法華宗の大本山(開祖=日像、開基=柳屋仲興)で、共に、天正十五年(一五八七)の、豊臣秀吉の命(聚楽第の整備に伴う都市改造)により、現在地に移転したことに伴う、強制的な隣接関係ということになる。
この「聚楽第の整備に伴う都市改造」については、次のアドレスが参考となる。
https://www.city.kyoto.lg.jp/kamigyo/page/0000012443.html
この「妙蓮寺」には、「立正安国論(三九・一㎝×三五一・四㎝)」と「始聞仏乗義(三九・一㎝×八七六㎝)」とが、当時の、「妙蓮寺法印権大僧都日源上人依御所望書之」とし、前者には「元和五年七月五日」(光悦の父の忌日)、後者には「元和五年十二月二十七日」(母の忌日)とを記し、「大虚庵光悦(花押)」の署名したものを、今に遺している。
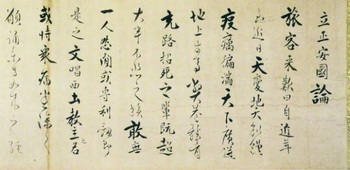
※立正安国論 本阿弥光悦筆→『書道芸術第十八巻 本阿弥光悦』作品解説136
(巻頭の部分)
【立正安国論
「旅客来たりて嘆いて曰く、
近年より近日に至るまで、
天変地夭飢饉疫癘遍く天下に満ち、
広く地上にはびこる。
牛馬巷に斃れ、骸骨路に充てり。
死を招くの輩既に大半に超え、
之を悲しまざるの族敢えて一人も無し。
然る間或いは利剣即是の文を専らとして、
西土教主の名を唱え、
或いは衆病悉除の願を恃んで、
東方如来の経を誦し、」 】
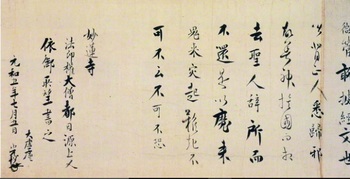
※立正安国論 本阿弥光悦筆→『書道芸術第十八巻 本阿弥光悦』作品解説136
(巻末の部分)
【いささか経文を披きたるに、世皆正に背き、
人悉く悪に帰す。故に善神国を捨てて相去り、
聖人所を辞して還らず、
是を以て魔来たり鬼来たり、
災起こり難起こる、言わずんばあるべからず、
恐れずんばあるべからずと。
妙蓮寺
法印権大僧都日源上人
依御所望書之(御所望に依って之を書す。)
元和五年七五日
大虚庵 光悦(花押) 】
(「巻頭」と巻末との間に次の文章が続く=この図録は省略されている)
http://www.daianzi.com/ronbun/ronb0138.htm
【然りと雖も、唯肝胆をくだくのみにしていよいよ
飢疫にせまる。
乞客目に溢れ、死人眼に満てり。
屍を臥せて観となし、尸を並べて橋と作す。
観ればそれ二離璧を合わせ、
五緯珠を連ね、三宝世に在し、
百王未だ窮らざるに、この世早く衰え、
その法何ぞ廃れたる。
是何なる禍に依り、是何なる誤りに由るや。
主人の曰く、独り此の事を愁えて胸臆に憤す。
客来たりて共に嘆く、しばしば談話を致さん。
それ出家して道に入る者は、
法に依って仏を期する也。
しかるに今神術もかなわず、仏威も験無し。
つぶさに当世の体をみて、
愚にして後生の疑いを発す。
然れば則ち円覆を仰いで恨みを呑み。
方載に俯して慮りを深くす。つらつら微管を傾け、
いささか経文を披きたるに、世皆正に背き、
人悉く悪に帰す。故に善神国を捨てて相去り、 】
https://ci.nii.ac.jp/naid/110008915196
↓
本阿弥光悦筆《立正安国論》《始聞仏乗義》について
Rissho Ankoku-ron and Shimonbutsujo-gi by Hon'ami Koetsu
高橋 伸城(TAKAHASHI Nobushiro 立命館大学文学研究科)
↓
【 (要点抜粋)
この寺院の再興が前政権者であった豊臣秀吉の都市計画によるものであることを考えると、日源の任期は政治的過渡期である慶長から元和に重なっていたと思われる。では日源と光悦の接点はどこにあったのか。この問題についても、寺院などに残る文書は多くを語らない。唯一手がかりとなるのが、光悦から妙蓮寺宛てに送られた手紙である。これは妙蓮寺の本光院に宛てられたものであり、光悦が昵懇にしていた神尾之直への伝言を託している。文中に膳所藩主の菅沼定芳に頼まれたという揮毫の話が出てくるが、定芳と光悦との交流を考えるとこの手紙が書かれたのは元和中期以降と推測できる。つまり、《立正安国論》等が書かれた時期にはすでに、妙蓮寺を通じて光悦と彼の友人間でメッセージの受け渡しを行うような関係が築かれていたのである。
また、妙蓮寺と光悦とのつながりを考える上で、地理的な要素も考慮しなければなるまい。秀吉の聚楽第建設によって、天正十五年(一五八七)頃から洛中の多くの寺院が移転を余儀なくされた。京都の法華宗において中心的役割を果たしてきた本法寺も例外ではなく、秀吉の命が下ってから間もなく、一条堀川から現在の堀川寺之内へと移動している。同じように妙蓮寺も都市の再編成から逃れることはできず、天文年間以降そこにあった大宮西北小路を去ることになるのだが、その移転地は本法寺のちょうど真向いであった。堀川通りを挟んで、本法寺と妙蓮寺は対峙する形になったのである
(中略)
日源もしくは光悦がなぜ「立正安国論」と「始聞仏乗義」をテキストに選んだかについては、やはり法華宗内での両書の扱われ方と無関係ではない。「立正安国論」はもともと、日蓮が文応元年(一二六〇)に国家諫暁を目的として北条時頼に提出したものである。当時、鎌倉を中心に多発していた天変地異を法華経への違背によるものとし、日蓮は時頼に改宗を迫ったのだ。臨済宗に帰依していた時頼は当然のことながらこれを退け、日蓮の迫害に満ちた人生が始まるのである。時頼に提出された「立正安国論」の原本は行方が知れないが、日蓮当人による写しが中山法華経寺に残っている。法華宗の間では重書中の重書とされ、繰り返しその教義について講義されたのみならず、後に述べるように写本も数多くつくられた。光悦の書の題材に選ばれたのも不思議ではない。
「始聞仏乗義」についても中山法華経寺に真蹟が残っており、元和頃に 最初に出版されたと考えられている『録内御書』にも、「立正安国(論」ともども収録されている((())。これは建治四年(一二七八)、日蓮から弟子の一人である富木常忍に宛てられた消息であり、内容は日蓮仏法の教義を巡る問答となっている。そして最後に、末法の凡夫がこの法華経の法門を聞けば、自身のみならず父母までをも成仏させることができると結んで終わっている。日蓮の直弟子の一人であった日興が「始聞仏乗義」を写していることなどからも、日蓮の生前からいかにこの書が大切に受け止められてきたかがわかるであろう。
(中略)
日蓮提唱の文字曼荼羅を本尊としてきた法華宗においては、書の内容だけではなく、日蓮が残した文字の形そのものも写し取るべき神聖なものであった。現在、鎌倉の妙本寺に保管されている「立正安国論」の写本は寂静房日進の筆になるものと言われているが、日蓮の原典と比べてみると、祖師の筆跡まで忠実になぞられた臨書であることがわかる(図7・図8)。
これら前例と照らし合わせると、光悦筆《立正安国論》《始聞仏乗義》の特異性がよりはっきりと浮かび上がってくる。それはつまり、光悦にそもそも日蓮の書を「写し取る」という意識はあったのかどうかという問題に言い換えられよう。
(中略)
光悦の書と日蓮のそれとを比較してみると、形と内容その両面において光悦は原典から逸脱していると言えよう。多数に上る脱字や教義に関わる誤字などは、本来の写経では許されることではない。これは、光悦の書写態度の不遜や教義の無理解からくるというよりも、そもそも彼の目指すべきものが写経者のそれとは違ったと考える方が自然であろう。《立正安国論》や《始聞仏乗義》に見られる光悦の筆は、それが写経の枠にはまるものではなく、書の「作品」として鑑賞されるべきものであることをより強調してはいないだろうか。
(後略) 】
(本法寺の重要文化財) 『ウィキペディア(Wikipedia)』
重要文化財(国指定)
松尾社一切経3545巻(附 経箱38合)
奥書院及び玄関の間障壁画 38面 長谷川派
紙本金地著色松桜図 一之間 襖貼付8、天袋貼付4
紙本金地著色松桜図 二之間 襖貼付8
紙本金地著色松杉桜図 脇一之間 襖貼付6
紙本金地著色松桜図 玄関之間 襖貼付12
附指定:紙本著色柳図 脇二之間 襖貼付4
伏見天皇宸翰法華経(沈金箱入り)8巻
※立正安国論 本阿弥光悦筆
※始聞仏乗義 本阿弥光悦筆
(メモ)
※立正安国論 本阿弥光悦筆→『書道芸術第十八巻 本阿弥光悦』作品解説136
紙本 一巻 三九・一㎝×三五一・四㎝ 元和五年(一六一九)
※始聞仏乗義 本阿弥光悦筆→『書道芸術第十八巻 本阿弥光悦』作品解説137
紙本 一巻 三九・一㎝×八七六㎝ 元和五年(一六一九)
四季花卉下絵古今集和歌巻(その十) [光悦・宗達・素庵]
その十 「本阿弥辻子」から「本法寺」へ ―光悦(書・作庭)そして等伯(像・画)―

(A図:「本阿弥辻子」(白峯神社)から「本法寺」(本阿弥家菩提寺)へ
https://www.meguru-kyoto.com/event/detail.html?id=32
この図面(A図)の「中小川町」近辺が「本阿弥家」が居住していた「本阿弥辻子(横丁)」で、その小川通りを行くと、「妙顕寺」そして、本阿弥家の菩提寺の「本法寺」に至る。

B図:寛永後萬治前洛中絵図(部分図・京都大学附属図書館蔵)
https://rmda.kulib.kyoto-u.ac.jp/libraries/uv-wrapper/uv.php?archive=metadata_manifest&id=RB00000143#?c=0&m=0&s=0&cv=0&xywh=30213%2C8303%2C3087%2C6111&r=270
これ(B図)は、寛永(一六二四~一六四五)後、萬治(一六五八~一六六一)前の、京都(上京区)の部分図である。この下辺の「本阿弥」と表示されている(何軒か表示されている)ところが、「本阿弥辻子」で、その上方に、「本法寺」(右に「妙顕寺」、左に「妙蓮寺」)がある。
この「本法寺」の、本堂の扁額は「本阿弥光悦筆」である。
https://kyotofukoh.jp/report287.html

【本堂扁額「本法寺」は、本阿弥光悦筆による。】
ここには、光悦の「作庭」の「三巴の庭」も下記のアドレスで紹介されている。
https://otogoze.exblog.jp/6550753/

【三巴の庭】手前の半円形の石を二つ合わせた円石は「妙」を表わし蓮池と合わせて「妙法蓮華経」となる(メモ:手前の二つ合わせた円石は「日」、そして、「蓮池」は「蓮」の、「日蓮」とも読める。また、この「蓮池」を「八つ橋の池」で紹介しているものもある=(『光悦―琳派の創始者―(河野元昭編)所収))。
↓
この庭は全体が法華経の宇宙観を表わし、その中ほどには十本の切石を円形に組んで縁石にした池が造られ、その池の中には白蓮が植えられています。
↓
蓮池を縁取る十本の切石で、法華経(妙法蓮華経)を最上の経典とする天台宗の宗祖である天台智顗(ちぎ)大師の著書「法華玄義十巻」を表現して組み「法華経」を意味し、
また「十界勧請(仏界・菩薩界・縁覚界・声聞界・天人界・人間界・修羅界・畜生界・餓鬼界・地獄界)」「三世十方(過去・現在・未来の三世と東・西・南・北・北東・北西・南東・南西・上・下の十方)」という法華経の宇宙観が表わされています。
↓
つまり法華経においては「十」という数が重要な意味を持つのです。
↓
そして経題(妙法蓮華経)に含まれている蓮華(白蓮)は法華経の核となる存在であり、釈迦さらには日輪をも象徴しています。
法華経のサンスクリット(梵語)の原典名「サッダルマ・ブンダリカ・スートラ」を直訳すると「何よりも正しい白蓮のような教え」という意味になります。
↓
白蓮は池底の泥濘から花茎を伸ばし、やがて水面に清浄無垢な白い花を咲かせる。妙法蓮華経(法華経)の教えは最上のすぐれたものであり、美の極致ともいうべき蓮華、中でも最も秀でた白蓮に託してその至上性を標榜しているのです。
↓

【蓮下絵百人一首和歌巻断簡】 個人蔵 俵屋宗達の蓮の下絵に光悦が和歌を書き散らした。
https://blog.goo.ne.jp/38_gosiki/e/e898fa686f05612b4dc583c5a6d3eb65

境内に建つ等伯の銅像(メモ:後方の松は「本阿弥光悦手植えの松」か?)
↓
長谷川等伯は1571(元亀2)年頃、故郷の七尾の菩提寺の本山だった本法寺を頼り、京都に出てきました。七尾ですでに画業で名を挙げていましたが、京都で絵の腕にさらに磨きをかけようとしたのでしょうか。現在も本法寺に隣接する塔頭の教行院(きょうぎょういん)に生活の拠点を得て、当時の最先端都市だった京や堺で絵を学びます。並行して千利休ら有力者とのパイプを築いていったと考えられています。
https://media.thisisgallery.com/works/hasegawatohaku_06

仏涅槃図(長谷川等伯筆)・本法寺蔵(メモ:光悦の寄進した「法華題目抄: 三九・七㎝×一四八八㎝」と「如説修行抄: 三九・七㎝×一四七二㎝」とも、長大な一巻である。)
【作品解説
東福寺、大徳寺所蔵のものと並び、京都の三大涅槃図に数えられる作品です。縦約10メートル、横約6メートルという巨大な作品で、首を上下左右に動かさなければ全体を見ることができません。この作品は完成後に宮中に披露された後、等伯が深く信頼を寄せていた本法寺に寄進されました。釈迦の入滅と、その死を嘆く弟子や動物たちが集まっている様子が、鮮やかな色合いで表情豊かに描かれています。裏面には、等伯が信仰していた日蓮宗の祖師たちの名、本法寺の歴代住職、等伯の親族、そして長谷川一門を担う存在として期待を寄せていた長男・久蔵たちの供養名が記されています。等伯の信仰の深さと、一族への祈りが込められた作品といえるでしょう。】
(本法寺の重要文化財) 『ウィキペディア(Wikipedia)』
重要文化財(国指定)
長谷川等伯関係資料
絹本著色日堯像(長谷川信春(等伯)筆)
絹本著色日通像(長谷川等伯筆)
紙本墨画妙法尼像(長谷川等伯筆)
紙本著色仏涅槃図(長谷川等伯筆)
等伯画説(日通筆)
附:日通書状
附:法華論要文(日蓮筆)
附:本尊曼荼羅(日親筆)
絹本著色日親像 伝狩野正信筆 - 2017年度指定[4][5]。
紙本金地著色唐獅子図 四曲屏風一隻[6][7]
金銅宝塔 応安三年(1370年)銘
紙本墨画文殊寒山拾得像[8] 3幅(文殊:啓牧筆、寒山拾得:啓孫筆)
絹本著色蓮花図(伝・銭舜挙筆)
絹本著色群介図
紫紙金字法華経(開結共)10巻
附:花唐草文螺鈿経箱
附:正月十三日本阿弥光悦寄進状
※法華題目抄(本阿弥光悦筆)
※如説修行抄(本阿弥光悦筆)
(周辺メモ)
※法華題目抄(本阿弥光悦筆)→『書道芸術第十八巻 本阿弥光悦』作品解説138
紙本 一巻 三九・七㎝×一四八八㎝
※如説修行抄(本阿弥光悦筆)→『書道芸術第十八巻 本阿弥光悦』作品解説139
紙本 一巻 三九・七㎝×一四七二㎝

(A図:「本阿弥辻子」(白峯神社)から「本法寺」(本阿弥家菩提寺)へ
https://www.meguru-kyoto.com/event/detail.html?id=32
この図面(A図)の「中小川町」近辺が「本阿弥家」が居住していた「本阿弥辻子(横丁)」で、その小川通りを行くと、「妙顕寺」そして、本阿弥家の菩提寺の「本法寺」に至る。

B図:寛永後萬治前洛中絵図(部分図・京都大学附属図書館蔵)
https://rmda.kulib.kyoto-u.ac.jp/libraries/uv-wrapper/uv.php?archive=metadata_manifest&id=RB00000143#?c=0&m=0&s=0&cv=0&xywh=30213%2C8303%2C3087%2C6111&r=270
これ(B図)は、寛永(一六二四~一六四五)後、萬治(一六五八~一六六一)前の、京都(上京区)の部分図である。この下辺の「本阿弥」と表示されている(何軒か表示されている)ところが、「本阿弥辻子」で、その上方に、「本法寺」(右に「妙顕寺」、左に「妙蓮寺」)がある。
この「本法寺」の、本堂の扁額は「本阿弥光悦筆」である。
https://kyotofukoh.jp/report287.html

【本堂扁額「本法寺」は、本阿弥光悦筆による。】
ここには、光悦の「作庭」の「三巴の庭」も下記のアドレスで紹介されている。
https://otogoze.exblog.jp/6550753/

【三巴の庭】手前の半円形の石を二つ合わせた円石は「妙」を表わし蓮池と合わせて「妙法蓮華経」となる(メモ:手前の二つ合わせた円石は「日」、そして、「蓮池」は「蓮」の、「日蓮」とも読める。また、この「蓮池」を「八つ橋の池」で紹介しているものもある=(『光悦―琳派の創始者―(河野元昭編)所収))。
↓
この庭は全体が法華経の宇宙観を表わし、その中ほどには十本の切石を円形に組んで縁石にした池が造られ、その池の中には白蓮が植えられています。
↓
蓮池を縁取る十本の切石で、法華経(妙法蓮華経)を最上の経典とする天台宗の宗祖である天台智顗(ちぎ)大師の著書「法華玄義十巻」を表現して組み「法華経」を意味し、
また「十界勧請(仏界・菩薩界・縁覚界・声聞界・天人界・人間界・修羅界・畜生界・餓鬼界・地獄界)」「三世十方(過去・現在・未来の三世と東・西・南・北・北東・北西・南東・南西・上・下の十方)」という法華経の宇宙観が表わされています。
↓
つまり法華経においては「十」という数が重要な意味を持つのです。
↓
そして経題(妙法蓮華経)に含まれている蓮華(白蓮)は法華経の核となる存在であり、釈迦さらには日輪をも象徴しています。
法華経のサンスクリット(梵語)の原典名「サッダルマ・ブンダリカ・スートラ」を直訳すると「何よりも正しい白蓮のような教え」という意味になります。
↓
白蓮は池底の泥濘から花茎を伸ばし、やがて水面に清浄無垢な白い花を咲かせる。妙法蓮華経(法華経)の教えは最上のすぐれたものであり、美の極致ともいうべき蓮華、中でも最も秀でた白蓮に託してその至上性を標榜しているのです。
↓

【蓮下絵百人一首和歌巻断簡】 個人蔵 俵屋宗達の蓮の下絵に光悦が和歌を書き散らした。
https://blog.goo.ne.jp/38_gosiki/e/e898fa686f05612b4dc583c5a6d3eb65

境内に建つ等伯の銅像(メモ:後方の松は「本阿弥光悦手植えの松」か?)
↓
長谷川等伯は1571(元亀2)年頃、故郷の七尾の菩提寺の本山だった本法寺を頼り、京都に出てきました。七尾ですでに画業で名を挙げていましたが、京都で絵の腕にさらに磨きをかけようとしたのでしょうか。現在も本法寺に隣接する塔頭の教行院(きょうぎょういん)に生活の拠点を得て、当時の最先端都市だった京や堺で絵を学びます。並行して千利休ら有力者とのパイプを築いていったと考えられています。
https://media.thisisgallery.com/works/hasegawatohaku_06

仏涅槃図(長谷川等伯筆)・本法寺蔵(メモ:光悦の寄進した「法華題目抄: 三九・七㎝×一四八八㎝」と「如説修行抄: 三九・七㎝×一四七二㎝」とも、長大な一巻である。)
【作品解説
東福寺、大徳寺所蔵のものと並び、京都の三大涅槃図に数えられる作品です。縦約10メートル、横約6メートルという巨大な作品で、首を上下左右に動かさなければ全体を見ることができません。この作品は完成後に宮中に披露された後、等伯が深く信頼を寄せていた本法寺に寄進されました。釈迦の入滅と、その死を嘆く弟子や動物たちが集まっている様子が、鮮やかな色合いで表情豊かに描かれています。裏面には、等伯が信仰していた日蓮宗の祖師たちの名、本法寺の歴代住職、等伯の親族、そして長谷川一門を担う存在として期待を寄せていた長男・久蔵たちの供養名が記されています。等伯の信仰の深さと、一族への祈りが込められた作品といえるでしょう。】
(本法寺の重要文化財) 『ウィキペディア(Wikipedia)』
重要文化財(国指定)
長谷川等伯関係資料
絹本著色日堯像(長谷川信春(等伯)筆)
絹本著色日通像(長谷川等伯筆)
紙本墨画妙法尼像(長谷川等伯筆)
紙本著色仏涅槃図(長谷川等伯筆)
等伯画説(日通筆)
附:日通書状
附:法華論要文(日蓮筆)
附:本尊曼荼羅(日親筆)
絹本著色日親像 伝狩野正信筆 - 2017年度指定[4][5]。
紙本金地著色唐獅子図 四曲屏風一隻[6][7]
金銅宝塔 応安三年(1370年)銘
紙本墨画文殊寒山拾得像[8] 3幅(文殊:啓牧筆、寒山拾得:啓孫筆)
絹本著色蓮花図(伝・銭舜挙筆)
絹本著色群介図
紫紙金字法華経(開結共)10巻
附:花唐草文螺鈿経箱
附:正月十三日本阿弥光悦寄進状
※法華題目抄(本阿弥光悦筆)
※如説修行抄(本阿弥光悦筆)
(周辺メモ)
※法華題目抄(本阿弥光悦筆)→『書道芸術第十八巻 本阿弥光悦』作品解説138
紙本 一巻 三九・七㎝×一四八八㎝
※如説修行抄(本阿弥光悦筆)→『書道芸術第十八巻 本阿弥光悦』作品解説139
紙本 一巻 三九・七㎝×一四七二㎝
四季花卉下絵古今集和歌巻(その九) [光悦・宗達・素庵]
その九 蔦

「尾形光琳生誕三五〇周年記念 大琳派展―継承と変奏(東京国立博物館・読売新聞社編)」
所収「1-01 俵屋宗達下絵・本阿弥光悦筆 四季草花下絵古今和歌巻・重要文化財・畠山記念館蔵」(「四季花卉下絵古今集和歌巻」=『光悦……琳派の創始者(河野元昭編)』所収「書画の二重奏への道……光悦書・宗達画和歌巻の展開(玉蟲敏子稿)」) 三三・七×九一八・七
題しらず
882 天の河雲のみをにてはやければ光とどめず月ぞ流るる(読人知らず)
(天の川は雲の「水脈(みを)=水路」で流れが早いので、月も光を留めず流れて行く。)
釈文(揮毫上の書体)=(『書道芸術第十八巻 本阿弥光悦』)
882 天河(あまのかは)雲濃(の)三於(みを)尓(に)天(て)ハ(は)や介(け)連(れ)者(ば)光と々(ど)め須(ず)月曾(ぞ)な可(が)る々
※雲濃(の)三於(みを=雲の水脈。雲の水路。天の川を雲の川と見立てる。
※月曾(ぞ)な可(が)る々=月ぞ流るる。天の川の流れの早い水脈の中を月が流されてゆくという見立ての一首。この月にも、月日の「月」を掛けているの意に解したい。
この「和歌巻」の最終章の、この「月」の歌の一首は、それまでの、「877(読人知らずの「月」の歌)、 878(読人知らずの「月」の歌)、 879(在原業平の「月」の歌)、 880(紀貫之の「月」の歌)、 881(紀貫之の「月」の歌)」を締め括るとともに、巻頭の次の「天の川」の歌に対応している。ここで、その巻頭の一首と、この巻末の一首を並列して掲げて置きたい。
(巻頭の一首)
863 わが上に露ぞ置くなる天の川とわたる舟のかいのしずくか(読人知らず)
(私の体が濡れているのは露が降りているのだそうだ。それならその露は天の川の渡し場を彦星が渡る舟の櫂から落ちた雫なのであろうか。)
(巻末の一首)
882 天の河雲のみをにてはやければ光とどめず月ぞ流るる(読人知らず)
(天の川は雲の「水脈(みを)=水路」で流れが早いので、月もまさに「※『光陰矢の如し』さながらに」光を留めず流れて行く。)
この「和歌巻」の末尾を飾る一首の「歌意」に、「※『光陰矢の如し』さながらに」の、この修飾語を加えて置きたい。
(参考) 「四季花卉下絵古今集和歌巻」(「その一~その三」「その四~その六」「その七~その九)

「四季草花下絵古今和歌巻」(その一・その二・その三)

「四季草花下絵古今和歌巻」(その四・その五・その六)

「四季草花下絵古今和歌巻」(その七・その八・その九)
この「四季草花下絵古今和歌巻」については、下記アドレスの、「宗達の金銀泥絵と明代の花卉図について―畠山記念館蔵《重文 金銀泥四季草花下絵古今集和歌巻》の分析を中心として―(仲町啓子稿)」の全文に接することが出来る。
https://ci.nii.ac.jp/naid/120006250417
「宗達の金銀泥絵と明代の花卉図について―畠山記念館蔵《重文 金銀泥四季草花下絵古今集和歌巻》の分析を中心として―(仲町啓子稿)」
この論稿の、巻末(蔦)と巻頭(竹)との部分を抜粋して置きたい。
巻末(蔦)―抜粋―
【『蔦』
最後の大団円に位置するのが蔦(挿図29)である。竹(新春)、梅(早春)、躑躅(夏)に続いて秋の季節を表すものと思われる。ただ秋を示すだけなら、ことさら蔦を選択する必要もなかったように思われる。むしろ薄や萩などの秋草あるいはそれに月などを取り合わせるほうが、よほどふさわしいように思われる。蔦は『伊勢物語』第九段宇津山の場面に因んだモチーフとして、少なくとも室町時代より表されているが、そこでは「紅葉の蔦」ではない。それなのに何故ここで「秋」のモチーフとして蔦が選択されたのであろうか。ちなみに《ベルリン本》では、蔦は夏に割り当てられている。実はこの蔦の構図こそ、宗達が最も挑戦したかった部分であった。そこには全体の構図的バランスを考えた、宗達ならではの意図があったのではないかと推測する。
(略)
《畠山本》は画面が広いせいか、最も複雑に多くの要素が盛り込まれる。躑躅の上方に垂れ下がる小さめの葉に始まり、続いて急にクローズアップされた葉が濃淡をつけられつつ描かれる。そこでは蔓や葉柄がまるでスウィングしているかのような独特なリズムを奏でている。こうした濃淡をつけられた「面的な葉が画巻の上端から下がる構図」の採用を宗達に促したものこそ、徐渭に代表される何らかの中国の花卉雑画巻(挿図14、挿図36)を実見した体験であったと思われる。横長の画面に蔓植物を描くということでは、滋賀・都久夫須麻神社の長押上の小壁に描かれた狩野派の《藤図》などの例は見られるが、巻物という画面形式、没骨法、画面上端から下へ向けての動感を強調した構図、濃淡を付けられた面を交錯させる構成、などいくつかの重要な造形的な要素が、右記の《藤図》には欠落している。しかもそれらの諸要素こそ、宗達が最も見せたかったものであり、巻物の最後のクライマックスで蔦が選ばれた理由でもあった。 】(「宗達の金銀泥絵と明代の花卉図について―畠山記念館蔵《重文 金銀泥四季草花下絵古今集和歌巻》の分析を中心として―(仲町啓子稿)」)
巻頭(竹)―抜粋―

【『竹』
《畠山本》の巻頭に描かれるのは竹(挿図1)である。大小十一本の竹幹のみを金泥に濃淡をつけながら描き出している。竹のモチーフは、《小謡本》(挿図2)、《百番本》には二図(挿図3、挿図4)、《花卉風景図扇面》(挿図5)、《秋草本》(挿図6)、《ベルリン本》(挿図7)、《隆達節巻》(挿図8)に登場する。《桜山吹本》以外はすべてに取り上げられていることになる。
(略)
宗達はすでに自然物の一部をトリミングした構図を採用しているが、それを巻物形式に応用するにはかなりの飛躍が必要であるように思われる。徐渭ないしはそれに類した作品を見知っていて、それをヒントにして奇抜な構図を生み出したと考えたい。ただ、宗達はそれを文様風な構成へと変えて、巧妙にも原画とは異なった印象の画面にしているため、原図様がわかりにくくなっていることも事実である。】(「宗達の金銀泥絵と明代の花卉図について―畠山記念館蔵《重文 金銀泥四季草花下絵古今集和歌巻》の分析を中心として―(仲町啓子稿)」)

「尾形光琳生誕三五〇周年記念 大琳派展―継承と変奏(東京国立博物館・読売新聞社編)」
所収「1-01 俵屋宗達下絵・本阿弥光悦筆 四季草花下絵古今和歌巻・重要文化財・畠山記念館蔵」(「四季花卉下絵古今集和歌巻」=『光悦……琳派の創始者(河野元昭編)』所収「書画の二重奏への道……光悦書・宗達画和歌巻の展開(玉蟲敏子稿)」) 三三・七×九一八・七
題しらず
882 天の河雲のみをにてはやければ光とどめず月ぞ流るる(読人知らず)
(天の川は雲の「水脈(みを)=水路」で流れが早いので、月も光を留めず流れて行く。)
釈文(揮毫上の書体)=(『書道芸術第十八巻 本阿弥光悦』)
882 天河(あまのかは)雲濃(の)三於(みを)尓(に)天(て)ハ(は)や介(け)連(れ)者(ば)光と々(ど)め須(ず)月曾(ぞ)な可(が)る々
※雲濃(の)三於(みを=雲の水脈。雲の水路。天の川を雲の川と見立てる。
※月曾(ぞ)な可(が)る々=月ぞ流るる。天の川の流れの早い水脈の中を月が流されてゆくという見立ての一首。この月にも、月日の「月」を掛けているの意に解したい。
この「和歌巻」の最終章の、この「月」の歌の一首は、それまでの、「877(読人知らずの「月」の歌)、 878(読人知らずの「月」の歌)、 879(在原業平の「月」の歌)、 880(紀貫之の「月」の歌)、 881(紀貫之の「月」の歌)」を締め括るとともに、巻頭の次の「天の川」の歌に対応している。ここで、その巻頭の一首と、この巻末の一首を並列して掲げて置きたい。
(巻頭の一首)
863 わが上に露ぞ置くなる天の川とわたる舟のかいのしずくか(読人知らず)
(私の体が濡れているのは露が降りているのだそうだ。それならその露は天の川の渡し場を彦星が渡る舟の櫂から落ちた雫なのであろうか。)
(巻末の一首)
882 天の河雲のみをにてはやければ光とどめず月ぞ流るる(読人知らず)
(天の川は雲の「水脈(みを)=水路」で流れが早いので、月もまさに「※『光陰矢の如し』さながらに」光を留めず流れて行く。)
この「和歌巻」の末尾を飾る一首の「歌意」に、「※『光陰矢の如し』さながらに」の、この修飾語を加えて置きたい。
(参考) 「四季花卉下絵古今集和歌巻」(「その一~その三」「その四~その六」「その七~その九)
「四季草花下絵古今和歌巻」(その一・その二・その三)
「四季草花下絵古今和歌巻」(その四・その五・その六)
「四季草花下絵古今和歌巻」(その七・その八・その九)
この「四季草花下絵古今和歌巻」については、下記アドレスの、「宗達の金銀泥絵と明代の花卉図について―畠山記念館蔵《重文 金銀泥四季草花下絵古今集和歌巻》の分析を中心として―(仲町啓子稿)」の全文に接することが出来る。
https://ci.nii.ac.jp/naid/120006250417
「宗達の金銀泥絵と明代の花卉図について―畠山記念館蔵《重文 金銀泥四季草花下絵古今集和歌巻》の分析を中心として―(仲町啓子稿)」
この論稿の、巻末(蔦)と巻頭(竹)との部分を抜粋して置きたい。
巻末(蔦)―抜粋―
【『蔦』
最後の大団円に位置するのが蔦(挿図29)である。竹(新春)、梅(早春)、躑躅(夏)に続いて秋の季節を表すものと思われる。ただ秋を示すだけなら、ことさら蔦を選択する必要もなかったように思われる。むしろ薄や萩などの秋草あるいはそれに月などを取り合わせるほうが、よほどふさわしいように思われる。蔦は『伊勢物語』第九段宇津山の場面に因んだモチーフとして、少なくとも室町時代より表されているが、そこでは「紅葉の蔦」ではない。それなのに何故ここで「秋」のモチーフとして蔦が選択されたのであろうか。ちなみに《ベルリン本》では、蔦は夏に割り当てられている。実はこの蔦の構図こそ、宗達が最も挑戦したかった部分であった。そこには全体の構図的バランスを考えた、宗達ならではの意図があったのではないかと推測する。
(略)
《畠山本》は画面が広いせいか、最も複雑に多くの要素が盛り込まれる。躑躅の上方に垂れ下がる小さめの葉に始まり、続いて急にクローズアップされた葉が濃淡をつけられつつ描かれる。そこでは蔓や葉柄がまるでスウィングしているかのような独特なリズムを奏でている。こうした濃淡をつけられた「面的な葉が画巻の上端から下がる構図」の採用を宗達に促したものこそ、徐渭に代表される何らかの中国の花卉雑画巻(挿図14、挿図36)を実見した体験であったと思われる。横長の画面に蔓植物を描くということでは、滋賀・都久夫須麻神社の長押上の小壁に描かれた狩野派の《藤図》などの例は見られるが、巻物という画面形式、没骨法、画面上端から下へ向けての動感を強調した構図、濃淡を付けられた面を交錯させる構成、などいくつかの重要な造形的な要素が、右記の《藤図》には欠落している。しかもそれらの諸要素こそ、宗達が最も見せたかったものであり、巻物の最後のクライマックスで蔦が選ばれた理由でもあった。 】(「宗達の金銀泥絵と明代の花卉図について―畠山記念館蔵《重文 金銀泥四季草花下絵古今集和歌巻》の分析を中心として―(仲町啓子稿)」)
巻頭(竹)―抜粋―

【『竹』
《畠山本》の巻頭に描かれるのは竹(挿図1)である。大小十一本の竹幹のみを金泥に濃淡をつけながら描き出している。竹のモチーフは、《小謡本》(挿図2)、《百番本》には二図(挿図3、挿図4)、《花卉風景図扇面》(挿図5)、《秋草本》(挿図6)、《ベルリン本》(挿図7)、《隆達節巻》(挿図8)に登場する。《桜山吹本》以外はすべてに取り上げられていることになる。
(略)
宗達はすでに自然物の一部をトリミングした構図を採用しているが、それを巻物形式に応用するにはかなりの飛躍が必要であるように思われる。徐渭ないしはそれに類した作品を見知っていて、それをヒントにして奇抜な構図を生み出したと考えたい。ただ、宗達はそれを文様風な構成へと変えて、巧妙にも原画とは異なった印象の画面にしているため、原図様がわかりにくくなっていることも事実である。】(「宗達の金銀泥絵と明代の花卉図について―畠山記念館蔵《重文 金銀泥四季草花下絵古今集和歌巻》の分析を中心として―(仲町啓子稿)」)
四季花卉下絵古今集和歌巻(その八) [光悦・宗達・素庵]
その八「蔦と躑躅・糸薄」

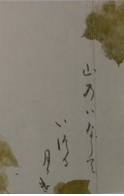
「尾形光琳生誕三五〇周年記念 大琳派展―継承と変奏(東京国立博物館・読売新聞社編)」
所収「1-01 俵屋宗達下絵・本阿弥光悦筆 四季草花下絵古今和歌巻・重要文化財・畠山記念館蔵」(「四季花卉下絵古今集和歌巻」=『光悦……琳派の創始者(河野元昭編)』所収「書画の二重奏への道……光悦書・宗達画和歌巻の展開(玉蟲敏子稿)」) 三三・七×九一八・七
題しらず
879 おほかたは月をもめでじこれぞこのつもれば人の老いとなるもの(在原業平)
(今の気持ちをおおまかに言えば、月をも愛でる気がしない。この月こそが、月日を重ねると、積もり積もって、老いたということを感じさせるが故に。)
月おもしろしとて凡河内の躬恒がまうできたりけるによめる
880 かつ見れどうとくもあるかな月影のいたらぬ里もあらじと思へば(紀貫之)
(月を見て「素晴らしい」と思う一方で、「そうでもない」という感じがするのは、この月の光がささない里がないように、私にだけ特別でないと思うが故に。)
池に月の見えけるをよめる
881 ふたつなきものと思ひしを水底に山の端ならでいづる月影(紀貫之)
(またとない美しい月だから二つはないものと思っていたのに、山上ではなく、水底にも、美しい月の姿が映し出されたよ。)
釈文(揮毫上の書体)=(『書道芸術第十八巻 本阿弥光悦』)
879 大方盤(は)月をもめ天(で)じ是曾(ぞ)此(この)徒(つ)も禮(れ)盤(ば)人濃(の)老(おい)登(と)なるも乃(の)
※大方盤(は)=大方は。普通のことならば。たいていは。
※月をも=人が賞美する月をも。この月は、空の月と年月の月を掛けている。
880 可(か)徒(つ)見連(れ)どう登(と)久(く)も安(あ)類(る)可(か)那(な)月影能(の)以(い)多(た)らぬ里も安(あ)らじ登(と)於(お)も遍(へ)半(ば)
※可(か)徒(つ)見連(れ)ど=かつ見れど。すばらしいと見る一方で
う登(と)久(く)も安(あ)類(る)=うとくもある。疎くもある。そうでもない。
※※月おもしろしとて凡河内の躬恒がまうできたりける=この月が自分(たち)だけのためにこうして美しく輝いているならいいのに、という気分を詠ったものだろうが、躬恒が女の所に行くついでに、ちょっと貫之の所に顔を出したという状況も考えられなくもなく、それをからかっているようにも見える。
881 婦(ふ)多(た)徒(つ)那(な)幾(き)物(もの)とおも日(ひ)しを水底尓(に)山乃(の)ハ(は)なら天(で)い徒(づ)る月可(か)遣(げ)
※婦(ふ)多(た)徒(つ)那(な)幾(き=二つ無き。月が一つしかない意と、またとなく美しいの意とを掛けている。
※山乃(の)ハ(は)なら天(で)=山の端(は)ならで。山の端でない所に。
https://www.asahi-net.or.jp/~sg2h-ymst/yamatouta/sennin/turayuki.html
【紀貫之(きのつらゆき) 貞観十四?~天慶八?(872-945)
生年については貞観十年・同十三年・同十六年など諸説ある。下野守本道の孫。望行(もちゆき)の子。母は内教坊の伎女か(目崎徳衛説)。童名は阿古久曽(あこくそ)と伝わる(紀氏系図)。子に後撰集の撰者時文がいる。紀有朋はおじ。友則は従兄。
幼くして父を失う。若くして歌才をあらわし、寛平四年(892)以前の「寛平后宮歌合」、「是貞親王家歌合」に歌を採られる(いずれも机上の撰歌合であろうとするのが有力説)。昌泰元年(898)、「亭子院女郎花合」に出詠。ほかにも「宇多院歌合」(延喜五年以前か)など、宮廷歌壇で活躍し、また請われて多くの屏風歌を作った。延喜五年(905)、古今和歌集撰進の勅を奉ず。友則の没後は編者の中心として歌集編纂を主導したと思われる。延喜十三年(913)、宇多法皇の「亭子院歌合」、醍醐天皇の「内裏菊合」に出詠。
官職は御書所預を経たのち、延喜六年(906)、越前権少掾。内膳典膳・少内記・大内記を経て、延喜十七年(917)、従五位下。同年、加賀介となり、翌年美濃介に移る。延長元年(923)、大監物となり、右京亮を経て、同八年(930)には土佐守に任ぜられる。この年、醍醐天皇の勅命により『新撰和歌』を編むが、同年九月、醍醐天皇は譲位直後に崩御。承平五年(935)、土佐より帰京。その後も藤原実頼・忠平など貴顕から機会ある毎に歌を請われるが、官職には恵まれず、不遇をかこった。やがて周防の国司に任ぜられたものか、天慶元年(938)には周防国にあり、自邸で歌合を催す。天慶三年(940)、玄蕃頭に任ぜられる。同六年、従五位上。同八年三月、木工権頭。同年十月以前に死去。七十四歳か。
原本は自撰と推測される家集『貫之集』がある。三代集(古今・後撰・拾遺)すべて最多入集歌人。勅撰入集計四百七十五首。古今仮名序の作者。またその著『土佐日記』は、わが国最初の仮名文日記作品とされる。三十六歌仙の一人。 】
https://www.asahi-net.or.jp/~sg2h-ymst/yamatouta/sennin/mitune.html
【凡河内躬恒(おうしこうちのみつね) 生没年未詳
父祖等は不詳。凡河内(大河内)氏は河内地方の国造。
寛平六年(894)二月、甲斐少目(または権少目)。その後、御厨子所に仕える。延喜七年(907)正月、丹波権大目。延喜十一年正月、和泉権掾。延喜二十一年正月、淡路掾(または権掾)。延長三年(925)、任国の和泉より帰京し、まもなく没したと推定される。
歌人としては、昌泰元年(898)秋の亭子院女郎花合に出詠したのを始め、宇多法皇主催の歌合に多く詠進するなど活躍し、古今集の撰者にも任ぜられた。延喜七年九月、大井川行幸に参加。延喜十三年三月、亭子院歌合に参加。以後も多くの歌合に出詠し、また屏風歌などを請われて詠んでいる。古今集には紀貫之(九十九首)に次ぐ六十首を入集し、後世、貫之と併称された。貫之とは深い友情で結ばれていたことが知られる。三十六歌仙の一人。家集『躬恒集』がある。勅撰入集二百十四首。 】
上記三首の、一番目の「879 おほかたは月をもめでじこれぞこのつもれば人の老いとなるもの(在原業平)」は、そのものずばりで、『伊勢物語第八十八段・月をもめでじ』に出て来る。
【むかし、いと若きにはあらぬ、これかれ友だちども集りて、月を見て、それがなかにひとり、
おほかたは月をもめでじこれぞこの
つもれば人の老いとなるもの 】(『伊勢物語第八十八段・月をもめでじ』)
そして、どことなく、この『伊勢物語第八十八段・月をもめでじ』の詞書の、「いと若きにはあらぬ、これかれ友だちども集りて」のような場面が連想され、それは、「在原業平(八二五年生れ)・紀貫之(八七二年の生れか?)・凡河内躬恒(紀貫之と同時代の歌人)」らの、架空の「歌会」の一場面のような、そんな雰囲気が、この『古今和歌集』の三首から感じ取れるのである。
『古今和歌集』の撰者は、「紀友則・紀貫之・凡河内躬恒・壬生忠岑」の四人であるが、その編纂の中心的な歌人は、紀貫之(紀友則は、その編纂過程で没しているか?)ということになろう(在原業平は、その前の時期の「六歌仙(僧正遍昭・在原業平・文屋康秀・喜撰法師・小野小町・、大友黒主の六人)」の一人)。
そして、『伊勢物語』も、在原業平の作ではなく、この紀貫之ではないかという説(「折口信夫説」など)も、『古今和歌集』と『伊勢物語』との一体性という雰囲気から肯定的に解することは、否定的に解するよりも、より受け入れ易い感じなのである。
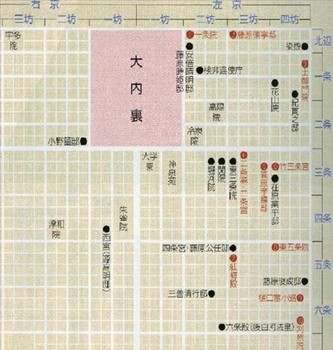
A図 平安京条坊図(大内裏周辺)
↑
http://gekkoushinjyu.kt.fc2.com/heian/kyou.html
この「平安京条坊図(大内裏周辺)」関連については、下記のアドレスで触れている。
https://yahan.blog.ss-blog.jp/2020-11-06
https://yahan.blog.ss-blog.jp/2020-10-23

B図 平安京内裏跡と現在の京都御所周辺
↑
https://mapandnews-japan.com/26kyotogosho_autumn/demo.html?csv=poi.csv
A図の「紀貫之邸」(「四坊・一条と二条間」)は、B図の「仙洞御所」の敷地内にある。
https://hellokcb.or.jp/bunka/pdf/geihinkan-map_20170301_no4_1_a.pdf
https://kyotofukoh.jp/report20-1.html
同様に、A図の「在原業平邸」(「四坊・三条と四条間」)、「藤原公任邸(「三坊・四条と五条の間)そして「藤原俊成邸」(四坊・五条と六条の間)を、上記のアドレスのマップを頼りして探索していくと、「光悦書・宗達画和歌巻」(『古今和歌集』から『新古今和歌集』までの八代勅撰和歌集)の、その全貌の一端が見えてくる。
そして、「業平・貫之・公任・俊成・定家」の「平安時代」を下って、「光悦・宗達」の「関ヶ原合戦」後の、「江戸初期・慶長時代」の、その「光悦書・宗達画和歌巻」の陣頭指揮をとった「本阿弥光悦」の仕事場(「大虚庵)」)は、このB図の、中央に位置する「楽美術館」の上方の「小川通り」上方の「白峯神社」の、その東側の横丁の「本阿弥辻子(ずし・つし)」にある。
http://youryuboku.blog39.fc2.com/blog-entry-211.html?sp
参考) 「四季花卉下絵古今集和歌巻」(「その一~その三」「その四~その六」「その七~その九)

「四季草花下絵古今和歌巻」(その一・その二・その三)

「四季草花下絵古今和歌巻」(その四・その五・その六)

「四季草花下絵古今和歌巻」(その七・その八・その九)

C図「楽美術館」(アクセス)
https://www.raku-yaki.or.jp/museum/access.html
上記アドレスの「楽美術館」の「アクセス」マップに、「本阿弥家旧跡」が図示されている。この「本阿弥家旧跡」関連については、下記のアドレスの「コミュニケーション行為論(六)─文化社会学へのいざない─(田中義久稿)」が参考となる。
https://hosei.repo.nii.ac.jp/?action=pages_view_main&active_action=repository_view_main_item_detail&item_id=21250&item_no=1&page_id=13&block_id=83
「コミュニケーション行為論(六)─文化社会学へのいざない─(田中義久稿)」(抜粋)
【 京都市上京区油小路通り五辻下る東側―1558年(永禄元年),本阿弥光悦(六郎左衛門,六左衛門,法名日豫,太虚庵,徳友斎)は,この地に生まれた。その地は,また,上京区小川今出川上る西側とも呼ばれ,上京の地域を東西に走る今出川通りを,それぞれ南北に横切る小川通りから油小路通りまでをつなぐ「本阿弥辻子」という地域であった。
「辻子」は,「ずし」もしくは「つし」と訓(よまれ),「細道」・「小路」・「横町」を意味し,十世紀の平安京に既に存在していたが,それは,平安京の本来の「条坊制」に基づく道路ではなくて,とくに,平安京の北郊の発達にともない,新たに開発された東西の道路なのであった。ちなみに,『広辞苑』(第六版)の下巻(「た―ん」)に,「辻子」という項目は見当らず,「辻」の関連においても説明されていない。かえって,上巻(「あ―そ」)の方に,「ずし」(辻)⇨つじ(字類抄)という簡略な説明があり,その5項目後ろのところに,「ずし」(途子・図子)の項が存在し,「よこちょう。路地。伊京集『図子,小路也,或いは通次に作る』」という説明が付されている。
実際には,前述の油小路通りを,今出川通りとの交差点から北に100m余り歩いた場所に,「上京区文化振興会」の手に成る「本阿弥光悦屋敷跡」の立札がたてられており,そこには「この地は,足利時代初期より,刀剣の研(とぎ)・拭(ぬぐひ)・目利(き)のいわゆる三事を以て,世に重きをなした本阿弥家代々の屋敷跡として,『本阿弥辻子』の名を今に遺している」と,説明されているのであった。
私が2016年秋に実踏した限りでは,この立札―その脚下には,白い玉砂利が敷きつめられ,石碑と井戸がしつらえられていた―の南側に,たしかに東の小川通りに向かって道幅一間ばかりの細い道が存在していたけれども,小川通りにまで突き抜けているようには思われず,今日では,京都の市街地によく見られる「路地」(ろうじ)になっているようであった。
「本阿弥辻子」は,今日の町名で言えば,上京区実相院町に所在する。そこは,室町幕府の将軍御所である「室町第」(別名,花の御所)の真西400mばかりの近さ,である。この町名は,天台宗寺門派(比叡山延暦寺を本山とする山門派に対立する,円珍を派祖として園城寺を総本山とする一派)の門跡寺院,実相院(1229年,近衛基通の孫,静基僧正の開山)に由来するけれども,1411年に,足利三代将軍義満の弟,義運僧正が住持の際に,この寺は現在地の左京区岩倉に移っている。「室町第」は,今日の上京区役所の東側,築山北半町から南半町にかけての地域に所在したが,その周囲には,近衛殿表町,同北口町,一条殿町,徳大寺殿町などが存在し,また,これらの周辺に,中御霊図子町,今図子町,常盤井図子町や一条横町など,「辻子」に類縁する町名・地名が残っている。
(中略)
私は,本阿弥光悦の「京屋敷」の旧跡から本阿弥家の菩提寺である本法寺まで歩きながら,多くの「金襴」,「金糸・銀糸」,「金箔」の工房の家々を,見出した。それらの家々の戸口の軒先きには,一様に,祇園祭の山鉾巡行の先頭に立つ「長刀鉾」の御札が,貼られているのであった。 さて,とりあえず,光悦をめぐる本阿弥家の系譜―「家系図」―を辿るならば,第1図のようになる。周知のように,資・史料としての「家系図」は,時系列のそれぞれの段階で「混同」や「粉飾」がまぎれ込む場合があり,この系譜4 4も,当然のこととして,今後の研究の深化に応じて,さらに正確なものとされるべき性格のものである。
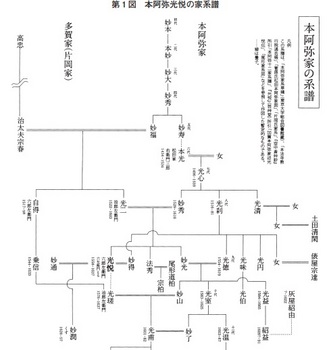
(以下略) 】「コミュニケーション行為論(六)─文化社会学へのいざない─(田中義久稿)」

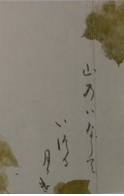
「尾形光琳生誕三五〇周年記念 大琳派展―継承と変奏(東京国立博物館・読売新聞社編)」
所収「1-01 俵屋宗達下絵・本阿弥光悦筆 四季草花下絵古今和歌巻・重要文化財・畠山記念館蔵」(「四季花卉下絵古今集和歌巻」=『光悦……琳派の創始者(河野元昭編)』所収「書画の二重奏への道……光悦書・宗達画和歌巻の展開(玉蟲敏子稿)」) 三三・七×九一八・七
題しらず
879 おほかたは月をもめでじこれぞこのつもれば人の老いとなるもの(在原業平)
(今の気持ちをおおまかに言えば、月をも愛でる気がしない。この月こそが、月日を重ねると、積もり積もって、老いたということを感じさせるが故に。)
月おもしろしとて凡河内の躬恒がまうできたりけるによめる
880 かつ見れどうとくもあるかな月影のいたらぬ里もあらじと思へば(紀貫之)
(月を見て「素晴らしい」と思う一方で、「そうでもない」という感じがするのは、この月の光がささない里がないように、私にだけ特別でないと思うが故に。)
池に月の見えけるをよめる
881 ふたつなきものと思ひしを水底に山の端ならでいづる月影(紀貫之)
(またとない美しい月だから二つはないものと思っていたのに、山上ではなく、水底にも、美しい月の姿が映し出されたよ。)
釈文(揮毫上の書体)=(『書道芸術第十八巻 本阿弥光悦』)
879 大方盤(は)月をもめ天(で)じ是曾(ぞ)此(この)徒(つ)も禮(れ)盤(ば)人濃(の)老(おい)登(と)なるも乃(の)
※大方盤(は)=大方は。普通のことならば。たいていは。
※月をも=人が賞美する月をも。この月は、空の月と年月の月を掛けている。
880 可(か)徒(つ)見連(れ)どう登(と)久(く)も安(あ)類(る)可(か)那(な)月影能(の)以(い)多(た)らぬ里も安(あ)らじ登(と)於(お)も遍(へ)半(ば)
※可(か)徒(つ)見連(れ)ど=かつ見れど。すばらしいと見る一方で
う登(と)久(く)も安(あ)類(る)=うとくもある。疎くもある。そうでもない。
※※月おもしろしとて凡河内の躬恒がまうできたりける=この月が自分(たち)だけのためにこうして美しく輝いているならいいのに、という気分を詠ったものだろうが、躬恒が女の所に行くついでに、ちょっと貫之の所に顔を出したという状況も考えられなくもなく、それをからかっているようにも見える。
881 婦(ふ)多(た)徒(つ)那(な)幾(き)物(もの)とおも日(ひ)しを水底尓(に)山乃(の)ハ(は)なら天(で)い徒(づ)る月可(か)遣(げ)
※婦(ふ)多(た)徒(つ)那(な)幾(き=二つ無き。月が一つしかない意と、またとなく美しいの意とを掛けている。
※山乃(の)ハ(は)なら天(で)=山の端(は)ならで。山の端でない所に。
https://www.asahi-net.or.jp/~sg2h-ymst/yamatouta/sennin/turayuki.html
【紀貫之(きのつらゆき) 貞観十四?~天慶八?(872-945)
生年については貞観十年・同十三年・同十六年など諸説ある。下野守本道の孫。望行(もちゆき)の子。母は内教坊の伎女か(目崎徳衛説)。童名は阿古久曽(あこくそ)と伝わる(紀氏系図)。子に後撰集の撰者時文がいる。紀有朋はおじ。友則は従兄。
幼くして父を失う。若くして歌才をあらわし、寛平四年(892)以前の「寛平后宮歌合」、「是貞親王家歌合」に歌を採られる(いずれも机上の撰歌合であろうとするのが有力説)。昌泰元年(898)、「亭子院女郎花合」に出詠。ほかにも「宇多院歌合」(延喜五年以前か)など、宮廷歌壇で活躍し、また請われて多くの屏風歌を作った。延喜五年(905)、古今和歌集撰進の勅を奉ず。友則の没後は編者の中心として歌集編纂を主導したと思われる。延喜十三年(913)、宇多法皇の「亭子院歌合」、醍醐天皇の「内裏菊合」に出詠。
官職は御書所預を経たのち、延喜六年(906)、越前権少掾。内膳典膳・少内記・大内記を経て、延喜十七年(917)、従五位下。同年、加賀介となり、翌年美濃介に移る。延長元年(923)、大監物となり、右京亮を経て、同八年(930)には土佐守に任ぜられる。この年、醍醐天皇の勅命により『新撰和歌』を編むが、同年九月、醍醐天皇は譲位直後に崩御。承平五年(935)、土佐より帰京。その後も藤原実頼・忠平など貴顕から機会ある毎に歌を請われるが、官職には恵まれず、不遇をかこった。やがて周防の国司に任ぜられたものか、天慶元年(938)には周防国にあり、自邸で歌合を催す。天慶三年(940)、玄蕃頭に任ぜられる。同六年、従五位上。同八年三月、木工権頭。同年十月以前に死去。七十四歳か。
原本は自撰と推測される家集『貫之集』がある。三代集(古今・後撰・拾遺)すべて最多入集歌人。勅撰入集計四百七十五首。古今仮名序の作者。またその著『土佐日記』は、わが国最初の仮名文日記作品とされる。三十六歌仙の一人。 】
https://www.asahi-net.or.jp/~sg2h-ymst/yamatouta/sennin/mitune.html
【凡河内躬恒(おうしこうちのみつね) 生没年未詳
父祖等は不詳。凡河内(大河内)氏は河内地方の国造。
寛平六年(894)二月、甲斐少目(または権少目)。その後、御厨子所に仕える。延喜七年(907)正月、丹波権大目。延喜十一年正月、和泉権掾。延喜二十一年正月、淡路掾(または権掾)。延長三年(925)、任国の和泉より帰京し、まもなく没したと推定される。
歌人としては、昌泰元年(898)秋の亭子院女郎花合に出詠したのを始め、宇多法皇主催の歌合に多く詠進するなど活躍し、古今集の撰者にも任ぜられた。延喜七年九月、大井川行幸に参加。延喜十三年三月、亭子院歌合に参加。以後も多くの歌合に出詠し、また屏風歌などを請われて詠んでいる。古今集には紀貫之(九十九首)に次ぐ六十首を入集し、後世、貫之と併称された。貫之とは深い友情で結ばれていたことが知られる。三十六歌仙の一人。家集『躬恒集』がある。勅撰入集二百十四首。 】
上記三首の、一番目の「879 おほかたは月をもめでじこれぞこのつもれば人の老いとなるもの(在原業平)」は、そのものずばりで、『伊勢物語第八十八段・月をもめでじ』に出て来る。
【むかし、いと若きにはあらぬ、これかれ友だちども集りて、月を見て、それがなかにひとり、
おほかたは月をもめでじこれぞこの
つもれば人の老いとなるもの 】(『伊勢物語第八十八段・月をもめでじ』)
そして、どことなく、この『伊勢物語第八十八段・月をもめでじ』の詞書の、「いと若きにはあらぬ、これかれ友だちども集りて」のような場面が連想され、それは、「在原業平(八二五年生れ)・紀貫之(八七二年の生れか?)・凡河内躬恒(紀貫之と同時代の歌人)」らの、架空の「歌会」の一場面のような、そんな雰囲気が、この『古今和歌集』の三首から感じ取れるのである。
『古今和歌集』の撰者は、「紀友則・紀貫之・凡河内躬恒・壬生忠岑」の四人であるが、その編纂の中心的な歌人は、紀貫之(紀友則は、その編纂過程で没しているか?)ということになろう(在原業平は、その前の時期の「六歌仙(僧正遍昭・在原業平・文屋康秀・喜撰法師・小野小町・、大友黒主の六人)」の一人)。
そして、『伊勢物語』も、在原業平の作ではなく、この紀貫之ではないかという説(「折口信夫説」など)も、『古今和歌集』と『伊勢物語』との一体性という雰囲気から肯定的に解することは、否定的に解するよりも、より受け入れ易い感じなのである。
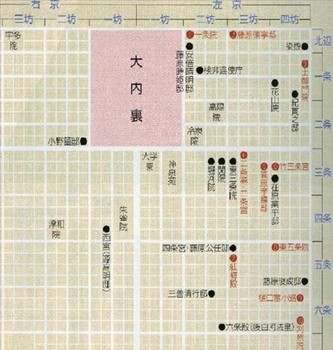
A図 平安京条坊図(大内裏周辺)
↑
http://gekkoushinjyu.kt.fc2.com/heian/kyou.html
この「平安京条坊図(大内裏周辺)」関連については、下記のアドレスで触れている。
https://yahan.blog.ss-blog.jp/2020-11-06
https://yahan.blog.ss-blog.jp/2020-10-23

B図 平安京内裏跡と現在の京都御所周辺
↑
https://mapandnews-japan.com/26kyotogosho_autumn/demo.html?csv=poi.csv
A図の「紀貫之邸」(「四坊・一条と二条間」)は、B図の「仙洞御所」の敷地内にある。
https://hellokcb.or.jp/bunka/pdf/geihinkan-map_20170301_no4_1_a.pdf
https://kyotofukoh.jp/report20-1.html
同様に、A図の「在原業平邸」(「四坊・三条と四条間」)、「藤原公任邸(「三坊・四条と五条の間)そして「藤原俊成邸」(四坊・五条と六条の間)を、上記のアドレスのマップを頼りして探索していくと、「光悦書・宗達画和歌巻」(『古今和歌集』から『新古今和歌集』までの八代勅撰和歌集)の、その全貌の一端が見えてくる。
そして、「業平・貫之・公任・俊成・定家」の「平安時代」を下って、「光悦・宗達」の「関ヶ原合戦」後の、「江戸初期・慶長時代」の、その「光悦書・宗達画和歌巻」の陣頭指揮をとった「本阿弥光悦」の仕事場(「大虚庵)」)は、このB図の、中央に位置する「楽美術館」の上方の「小川通り」上方の「白峯神社」の、その東側の横丁の「本阿弥辻子(ずし・つし)」にある。
http://youryuboku.blog39.fc2.com/blog-entry-211.html?sp
参考) 「四季花卉下絵古今集和歌巻」(「その一~その三」「その四~その六」「その七~その九)
「四季草花下絵古今和歌巻」(その一・その二・その三)
「四季草花下絵古今和歌巻」(その四・その五・その六)
「四季草花下絵古今和歌巻」(その七・その八・その九)

C図「楽美術館」(アクセス)
https://www.raku-yaki.or.jp/museum/access.html
上記アドレスの「楽美術館」の「アクセス」マップに、「本阿弥家旧跡」が図示されている。この「本阿弥家旧跡」関連については、下記のアドレスの「コミュニケーション行為論(六)─文化社会学へのいざない─(田中義久稿)」が参考となる。
https://hosei.repo.nii.ac.jp/?action=pages_view_main&active_action=repository_view_main_item_detail&item_id=21250&item_no=1&page_id=13&block_id=83
「コミュニケーション行為論(六)─文化社会学へのいざない─(田中義久稿)」(抜粋)
【 京都市上京区油小路通り五辻下る東側―1558年(永禄元年),本阿弥光悦(六郎左衛門,六左衛門,法名日豫,太虚庵,徳友斎)は,この地に生まれた。その地は,また,上京区小川今出川上る西側とも呼ばれ,上京の地域を東西に走る今出川通りを,それぞれ南北に横切る小川通りから油小路通りまでをつなぐ「本阿弥辻子」という地域であった。
「辻子」は,「ずし」もしくは「つし」と訓(よまれ),「細道」・「小路」・「横町」を意味し,十世紀の平安京に既に存在していたが,それは,平安京の本来の「条坊制」に基づく道路ではなくて,とくに,平安京の北郊の発達にともない,新たに開発された東西の道路なのであった。ちなみに,『広辞苑』(第六版)の下巻(「た―ん」)に,「辻子」という項目は見当らず,「辻」の関連においても説明されていない。かえって,上巻(「あ―そ」)の方に,「ずし」(辻)⇨つじ(字類抄)という簡略な説明があり,その5項目後ろのところに,「ずし」(途子・図子)の項が存在し,「よこちょう。路地。伊京集『図子,小路也,或いは通次に作る』」という説明が付されている。
実際には,前述の油小路通りを,今出川通りとの交差点から北に100m余り歩いた場所に,「上京区文化振興会」の手に成る「本阿弥光悦屋敷跡」の立札がたてられており,そこには「この地は,足利時代初期より,刀剣の研(とぎ)・拭(ぬぐひ)・目利(き)のいわゆる三事を以て,世に重きをなした本阿弥家代々の屋敷跡として,『本阿弥辻子』の名を今に遺している」と,説明されているのであった。
私が2016年秋に実踏した限りでは,この立札―その脚下には,白い玉砂利が敷きつめられ,石碑と井戸がしつらえられていた―の南側に,たしかに東の小川通りに向かって道幅一間ばかりの細い道が存在していたけれども,小川通りにまで突き抜けているようには思われず,今日では,京都の市街地によく見られる「路地」(ろうじ)になっているようであった。
「本阿弥辻子」は,今日の町名で言えば,上京区実相院町に所在する。そこは,室町幕府の将軍御所である「室町第」(別名,花の御所)の真西400mばかりの近さ,である。この町名は,天台宗寺門派(比叡山延暦寺を本山とする山門派に対立する,円珍を派祖として園城寺を総本山とする一派)の門跡寺院,実相院(1229年,近衛基通の孫,静基僧正の開山)に由来するけれども,1411年に,足利三代将軍義満の弟,義運僧正が住持の際に,この寺は現在地の左京区岩倉に移っている。「室町第」は,今日の上京区役所の東側,築山北半町から南半町にかけての地域に所在したが,その周囲には,近衛殿表町,同北口町,一条殿町,徳大寺殿町などが存在し,また,これらの周辺に,中御霊図子町,今図子町,常盤井図子町や一条横町など,「辻子」に類縁する町名・地名が残っている。
(中略)
私は,本阿弥光悦の「京屋敷」の旧跡から本阿弥家の菩提寺である本法寺まで歩きながら,多くの「金襴」,「金糸・銀糸」,「金箔」の工房の家々を,見出した。それらの家々の戸口の軒先きには,一様に,祇園祭の山鉾巡行の先頭に立つ「長刀鉾」の御札が,貼られているのであった。 さて,とりあえず,光悦をめぐる本阿弥家の系譜―「家系図」―を辿るならば,第1図のようになる。周知のように,資・史料としての「家系図」は,時系列のそれぞれの段階で「混同」や「粉飾」がまぎれ込む場合があり,この系譜4 4も,当然のこととして,今後の研究の深化に応じて,さらに正確なものとされるべき性格のものである。
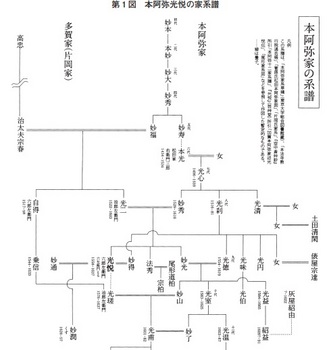
(以下略) 】「コミュニケーション行為論(六)─文化社会学へのいざない─(田中義久稿)」
四季花卉下絵古今集和歌巻(その七) [光悦・宗達・素庵]
その七「躑躅・糸薄(その七のAとB))」

(その七のA「躑躅と糸薄」)

(その七のB「躑躅・糸薄(続き)」)
「尾形光琳生誕三五〇周年記念 大琳派展―継承と変奏(東京国立博物館・読売新聞社編)」
所収「1-01 俵屋宗達下絵・本阿弥光悦筆 四季草花下絵古今和歌巻・重要文化財・畠山記念館蔵」(「四季花卉下絵古今集和歌巻」=『光悦……琳派の創始者(河野元昭編)』所収「書画の二重奏への道……光悦書・宗達画和歌巻の展開(玉蟲敏子稿)」) 三三・七×九一八・七
方たがへに人の家にまかれりける時に、
あるじのきぬをきせたりけるを、
あしたに返すとてよみける
876 蝉の羽の夜の衣は薄けれど移り香濃くも匂ひぬるかな(紀友則)
(蝉の羽のような夜着は薄いけれど、移り香は濃く匂っていました。)
題しらず
877 遅くいづる月にもあるかなあしひきの山のあなたも惜しむべらなり(読人知らず)
(遅く出てくる月であることだ。きっと山の向こう側も月を惜しんでいるに違いない。)
題しらず
878 我が心なぐさめかねつ更級やをばすて山に 照る月を見て(読人知らず)
(この心を静めることができない。姥捨山に照る月を見ていると。)
釈文(揮毫上の書体)=(『書道芸術第十八巻 本阿弥光悦』)
876 世三(せみ)乃(の)羽(は)濃(の)よる能(の)衣(ころも)ハ(は)う須(す)介(け)連(れ)ど移(うつり)香(か)こ久(く)も尓(に)保(ほ)日(ひ)ぬる哉
※※方たがへ(「詞書」の意など)=外出の際、「方違へ」と言って、方角の吉凶を占い、悪い方角を避けて一晩別の方向の家に泊めてもらう風習があった。その家の主人に借りた夜着を翌朝返す時、心遣いに感謝をこめた歌。
877 遅(おそく)出類(いづる)月尓(に)も有(ある)可(か)那(な)安(あ)し日(び)支(き)能(の)山濃(の)安(あ)な多(た)も於(お)し無(む)べら也
※月尓(に)も有(ある)可(か)那(な)=月にもあるかな。月であるなあ。
※安(あ)し日(び)支(き)能(の)=あしびきの。山の枕詞。
※於(お)し無(む)べら也=惜しむべらなり。惜しんでいるようだ。
878 我(わが)心な久(ぐ)左(さ)め可(か)年(ね)徒(つ)更級や祖母(をぼ)捨(すて)山に照(てる)月を見天(て)
※更級(さらしな)=更科とも。長野県千曲市 (ちくまし) 南部の地名。姨捨山 (おばすてやま) 伝説や田毎 (たごと) の月などで有名。
※祖母(をぼ)捨(すて)山=姨捨山(をぼすてやま・うばすてやま)。「姥捨山」とも書く。長野県千曲 (ちくま) 市にある冠着 (かむりき) 山の別名。標高1252メートル。古くから「田毎 (たごと) の月」とよばれる月見の名所。更級 (さらしな) に住む男が、山に捨てた親代わりの伯母を、明月の輝きに恥じて翌朝には連れ戻しに行ったという、姨捨山伝説で知られる。
http://www.asahi-net.or.jp/~sg2h-ymst/yamatouta/sennin/tomonori.html
【 紀友則(きのとものり) 生没年未詳
宮内少輔紀有朋の子。貫之の従兄。子に淡路守清正・房則がいる(尊卑分脈)。
四十代半ばまで無官のまま過ごし(後撰集)、寛平九年(897)、ようやく土佐掾の官職を得る。翌年、少内記となり、延喜四年(904)には大内記に任官した。歌人としては、宇多天皇が親王であった頃、すなわち元慶八年(884)以前に近侍して歌を奉っている(『亭子院御集』)ので、この頃すでに歌才を認められていたらしい。寛平三年(891)秋以前の内裏菊合、同四年頃の是貞親王家歌合・寛平御時后宮歌合などに出詠。壬生忠岑と並ぶ寛平期の代表的歌人であった。延喜五年(905)二月二十一日、藤原定国の四十賀の屏風歌を詠んだのが、年月日の明らかな最終事蹟。おそらくこの年、古今集撰者に任命されたが、まもなく病を得て死去したらしい。享年は五十余歳か。紀貫之・壬生忠岑がその死を悼んだ哀傷歌が古今集に見える。
古今集に四十七首収録(作者名不明記の一首を含む)。その数は貫之・躬恒に次ぐ第三位にあたる。勅撰入集は総計七十首。家集『友則集』がある。三十六歌仙の一人。小倉百人一首に歌を採られている。 】
ここは『伊勢物語』の「東下り」(第7段から第9段)、殊に、その第8段(信濃)などを背景にあるもののように解したい。
https://yahan.blog.ss-blog.jp/2020-11-27
第7段 東下り(伊勢・尾張)(いとゞしく過ぎ行く方の恋しきにらやましくもかへる浪かな)
第8段 東下り(信濃)(信濃なる浅間の嶽にたつ煙をちこち人の見やはとがめぬ)
第9段 東下り(八橋)(唐衣きつゝ馴にしつましあればはるばる来ぬる旅をしぞ思ふ)
同(宇津)(駿河なる宇津の山辺のうゝにも夢にも人に逢はぬなりけり)
同(富士)(時しらぬ山は富士の嶺いつとてか鹿の子まだらに雪の降るらむ)
同(隅田川)(名にしおはゞいざこと問は都鳥むわが思ふ人はありやなしやと)
https://ise-monogatari.hix05.com/1/ise008.asama.html

『伊勢物語(第8段 東下り・信濃)』(住吉如慶筆)
【むかし、をとこありけり。京や住みうかりけむ、あづまのかたにゆきて、住み所もとむとて、友とする人ひとりふたりして行きけり。信濃の国浅間の嶽にけぶりの立つを見て、
信濃なる浅間の嶽にたつ煙をちこち人の見やはとがめぬ 】(『伊勢物語(第8段 東下り・信濃)』)
『新古今和歌集(巻第十・羇旅歌)』に、この在原業平の「浅間山」の歌が収載されている。
東(あづま)の方(かた)にまかりけるに、浅間の嶽(たけ)
に煙(けぶり)の立つを見てよめる
903 信濃なる淺間の嶽に立つけぶりをちこち人(びと)の見やはとがめぬ(在原業平朝臣『新古今集』)
(信濃の国にある浅間山に立ちのぼる噴煙は、遠くの人も近くの人も、どうして目を見張ら
ないことであろうか、誰しも目を見張ることであろう。)
(参考) 「四季花卉下絵古今集和歌巻」(「その一~その三」「その四~その六」「その七A・B)

「四季草花下絵古今和歌巻」(その一・その二・その三)

「四季草花下絵古今和歌巻」(その四・その五・その六)

「四季草花下絵古今和歌巻」(その七・その八・その九)
https://yahan.blog.ss-blog.jp/2020-11-27
↑
上記のアドレスの「コメント」の欄で、次のように記した。
【 https://www.jisyameguri.com/event/cyomyoj
↑
このサイトで「牛図」(宗達筆、・光広賛)が見られる。ここに、何と「伝俵屋宗達墓」の写真もアップされていた。この種のものは、数ある「活字情報・ネット情報」でも、管見の限り、このサイトで初めての感じ。
関連して、『ウィキペディア(Wikipedia)』を見ると、そもそもは、禁裏(御所)の近くにあったのを、「1673年(寛文13年)禁裏に隣接しているという理由で、現在の地に移転した」とある。】
この頂妙寺(現: 京都府京都市左京区大菊町)の「伝俵屋宗達墓」について、終戦直後の、昭和二十三年(一九四八)に刊行された『宗達の水墨画(徳川義恭著・座右宝刊行会刊)で紹介されているようである。
https://www.kosho.or.jp/products/detail.php?product_id=114985763

文庫版『宗達の水墨画(徳川義恭著・座右宝刊行会刊)
【徳川 義恭(とくがわ よしやす、1921年(大正10年)1月18日 - 1949年(昭和24年)12月12日)は、日本の美術研究者、装幀家。尾張徳川家の分家の当主である男爵・徳川義恕の四男。母方の祖父・津軽承昭は弘前藩主。長兄・徳川義寛は昭和天皇の侍従・侍従長。姉・祥子の夫は北白川宮永久王。次兄・義孝(津軽英麿の養子となる)の娘は、常陸宮正仁親王妃華子で、義恭の姪にあたる。夫人・雅子(のりこ)は田安徳川家の徳川達成の長女。
1942年(昭和17年)、学習院高等科を卒業し、東京帝国大学文学部美学美術史学科に入学。同年7月1日、三島由紀夫や東文彦と共に同人誌『赤絵』を創刊した。同誌および、1944年(昭和19年)10月発行の三島の処女作品集『花ざかりの森』(七丈書院)の装幀を担当した。
著書は1941年(昭和16年)に私家版の編著『暢美』を、1948年(昭和23年)に『宗達の水墨画』(座右宝刊行会(座右寳叢書))がある。
亜急性細菌性心内膜炎で夭折した。享年28。三島は人となりを偲んで、短篇小説『貴顕』]を書いている。
三島との往復書簡が、数通だが『三島由紀夫十代書簡集』(新潮社、のち新潮文庫)に収められている。2010年(平成22年)に遺族宅で、新たに三島からの手紙9通(1942年 - 1944年)が発見された。 】(『ウィキペディア(Wikipedia)』)
https://www.chugainippoh.co.jp/article/ron-kikou/ron/20200612-001.html
【1946(昭和21)年、美術研究者の徳川義恭氏は当時、俵屋蓮池・喜多川第17代当主である喜多川平朗氏の協力を得て喜多川家伝来の歴代譜、頂妙寺墓所にある俵屋喜多川一門の供養塔の碑銘を調査し、蓮池平右衛門尉秀明に始まる俵屋喜多川宗家の系譜を明らかにされた。自著『宗達の水墨画』においてその調査結果を公表された中で「蓮池俵屋についてはそれを系統的に知り得ず、之が引いては宗達との関係を不明瞭にしているものと思われる」と述べられている。ちなみに現当主、第18代喜多川俵二氏は師父と同様に人間国宝として俵屋の家職を継承し頂妙寺大乗院と結縁されている。】(「謎多い絵師・俵屋宗達の実像」日蓮宗大法寺住職 栗原啓允稿)
https://userweb.pep.ne.jp/c6v00030/r122.html
【宗達・光悦 試論 ― 宗達研究の一節 ― 徳川 義恭
宗達と光悦との関係は 歌巻、色紙、短冊、謡曲本の合作が現存する事により 証明されるが、更に 片岡家本、菅原氏松田本阿弥家系が信じられるとすれば、宗達の妻は光悦の妻の姉と云ふ事になり、極めて近い間柄となる。 又、光悦の書簡の一に 「俵屋方、光悦」と記したものがある。 少庵書状 (1) に依つて 宗達が俵屋を号した事が確認されて居る現在、之も亦 宗達の家に光悦が居たと云ふ事実を知る 興味ある資料である。
処で 私が此の小論で述べようとする所は、此の二人の芸術的立場に於ける先後問題なのである。 つまり 光悦の芸術から宗達の芸術が生れたものであるか、或は宗達から光悦か、の問題である。 之は 近世美術史上、極めて重大な問題であるにも拘らず、批判的立場から余り論じられて居ない。 そして先づ一般には 光悦から宗達が出たのであるとする説が大部分の様である。 中には 光悦派と云ふ名称を掲げ その中に宗達光琳を含ませる考へもある。 尤も 私が之から述べようとする処は 光悦―宗達説を全然否定し去らうと云ふのではない。 此の問題は 現在の資料を以てしては 確言することは勿論出来ないのである。 それ故、試論として 私が宗達―光悦説を述べてみるのである。
注 (1) 少庵書状 ― 美術研究第百十一号
私は先づ、光悦の芸術が 世に余りに高く評価され過ぎてゐはしないか、と思ふ。 彼をレオナルド・ダヴインチと並べて評した一説の如きは 問題外としても、万能の天才 光悦と云ふ文字は 余りにも多く見かける。 勿論私は 彼の茶碗のよさは認めて居る。 陶器に於て あれだけの大きさと深み、渋さを表現した事は 確かに一つの大きな仕事である。 処が 之を賞讃するの余り、彼の他の作品分野に迄 無批判的にそのよさを及ぼし評価することが 行はれて居はしないだらうか。 書道に於て光悦は 松花堂(松花堂 昭堂、1582~1639。真言宗の僧侶にして書家。松花堂流を創始した。)、三藐院(近衛 信尹、1565~1614。五摂家の筆頭たる近衛家の嫡流にして、書家。三藐院と号した。)と共に三筆とうたはれた。 確かに彼の書は暢達であり、独創的で自由な処がある。 殊に 金銀泥の飾絵の上に 太く細く配置して行く技巧と感覚には 勝れたものがある。 当時、賞讃された事もよく肯ける。 併し 一たび視界を広く書の美と云ふ点に置いた場合に、彼の書は 達者ではあるが 真の深みあるよさを感じられない様な気がする。 因みに 宗達の下絵ある歌巻なり、短冊なりの、其の下絵無しで見た場合に さう云ふ事は感じられると思ふ。 処で 今私が問題とするのは 茶碗や書ではなく(勿論 之等も宗達を考へる上に必要なのであるが)彼の蒔絵と絵画なのである。
元来、光悦が如何なる程度に絵画をよくしたかは 明瞭でない。 屢々記録に現はれるものに 自讃三十六歌仙絵があるが、之に就て古画備考は 「画は皺法正敷歌仙絵也」と記して居る。 尾形流百図を見ると、抱一文庫の光悦自画讃三十六歌仙の絵が載せられて居る。 此の様式が所謂 光悦画の本体であるとすれば、それは又 著しく宗達様式とは離れたものと言はねばならぬ。 又 同書に本田家蔵として、萩之坊乗円讃光悦画定家卿なる図が掲げられて居るが、様式は先の三十六歌仙図と全く同じであり、之には光悦の方印が捺してある。 之等の図に見られる描線は 宗達風のものではない。 而して 従来の説の如く 光悦の蒔絵等に於ける図様を光悦画の本体とするならば、此の三十六歌仙絵の系統(前述の如く その同類のものに光悦の印さへある)は 光悦の画様式の如何なる位置に置かれるものであらうか。 ―― 私は案外、光悦画の様式の本体は所謂宗達風のものではなく、右(上)の例の様な描線を有する 比較的常識的な画様であつたのではないかと思ふ。 そして 若し光悦が、一般に宗達光琳の祖と言はれて居る作風のものを描いたとすれば、それは実は 光悦が宗達の作風に影響されて以後のものではないかと思ふ。 而も 光悦筆と確証し得る絵画作品のないと云ふ事実は、半面に 下絵を宗達に仰いでゐる作品が確実に存する(宗達の伊年円印あるもの三点、その他色紙、短冊等確実に様式上宗達と見做されるもの数十点)と云ふ事実と相俟つて、彼の絵画に対する疑問を一層増大せしめるのである。
光悦伝に依ると、光悦は書に於ては相当自信を持つて居たかの如く思はれる。 有名な話ではあるが、続近世畸人伝(江戸中期の文人・伴蒿蹊が著した人物伝。1898年刊。)に 「或時 近衛三藐院 光悦にたづねたまふ 今天下に能書といふは誰とかするぞと 光悦 先づ さて次は君 次は八幡の坊也 その先づとは誰ぞと仰たまふに 恐ながら私なりと申す 此時此三筆 天下に名あり」 とある。 即ち 自分が最上で 次が三藐院 次が松花堂 と云ふのである。 此の話は勿論 一概に信じ難いとは言ひ條、光悦が書に於て相当自信があつたと云ふ事実を 察する事が出来る様に思はれる。 又、社会的にも彼の色紙が高く評価されて居た事は 次の話でも分る。 即ち、光悦の甥 光室が江戸城中に於て急病に斃れた際、彼は急ぎ東下した。 こゝで 思ひ掛けなくも 将軍家光に拝謁する事になつたが、献上物を持参してゐないので それを土井大炊頭に告げると、色紙を差し上げるがよからうと言ふ。 光悦は「差上候程の色紙有合不レ申」と述べると、大炊頭は「先年御貰ひ候色紙有レ之候間、先是御貸可レ申候間、献上致可レ然」と言ひ、之を以て事が運んだと云ふ。 現存の光悦色紙が皆彼の書のあるもので 絵画のみのものを右の場合に想像する事は当らない様に思はれるから、此の話を以て 書に於ては文字通り自他共に許したと云ふ事が分るのである。
所が 今問題とする絵画に就ては 寧ろ自信に乏しかつたかの如き記録がある。 本阿弥行状記の一節で、同じく無条件に信ずべき性質のものではないが、次の様な話がある。 「或時 猩々翁(松花堂ノコト)、予(光悦)が新に建てたる小室を見て、さても あら壁に山水鳥獣あらゆるものあり、絵心なき処にては、かやうのことも時々写し度思ふ時も遠慮せり、幸と別懇のその宅中 ねがふてもなきことゝ、一宿をして終日色々の絵をしたゝめ 予にも恵まれし、我も絵は少しはかく事を得たりといへども中々其妙に至らざれば、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、あら壁の模様をよき絵の手本とも知らず、勿論古来よりあら壁に絵の姿あると申すことは聞伝ふるといへども、まのあたり猩々翁のかきとられしにて疑もはれ何事も上達せざれば其奥義をとられぬものと今更の様に思ひぬ」 ―― 而して光悦は 一方同じ書に於て、「陶器を作ることは 予は猩々翁にまされり」と述べたと記してある。 即ち 絵画に対する彼の態度が、陶器、書に対するものと異つてゐた事が窺ひ得るのである。 自信あるものは飽く迄も明瞭にしてゐたのであるから、画事に就て松花堂に示した態度は 単なる表面の謙譲ではなかつたと見るべきである。 又、特に文中 猩々翁○とある点に留意すれば、松花堂は光悦より略々廿五年程若いのであるから、此の話は光悦の若い時の事とは思はれない、(ここは 読点(。)の誤りであろう。) (例へ翁と云ふ言葉が敬称として用ひられ、松花堂の所謂 晩年に用ひられたのではないとしても、余り若くしては此の称は用ひられぬであらう(。)) 要するに光悦は 晩年に至つて画事に自信ある境地に達し得たのではなからうか、と云ふ推論の余地は無い訳である。 而も宗達は 慶長十一年には光悦の和歌下絵を既に描いて居るのであるから、此の点に於ても 宗達画の先駆を光悦とすることは困難なのである。 (慶長十一年に 光悦は四十九歳、松花堂は略々廿三歳)
慶長十一年十一月十一日銘ある 宗達下絵光悦和歌色紙に就ては、嘗て矢代幸雄先生が 美術研究第九十三号に発表されたが、此の特殊なる年紀に関しては疑問のまゝ 問題を残された。 私は 黒板博士の国史研究年表に依り、此の日に近衛三藐院が関白を辞して居る事実を知つた。 三藐院と光悦との交際は既に証せられて居る。 而して 矢代先生も指摘されて居る様に、此等十一枚の色紙には 新古今集秋上の部に互に相近く載せられた月に関する歌が書かれて居る。 而して それらは淋しい歌が多いのである。 例へば 「ことはりの秋にはあへぬ涙哉つきのかつらもかはるひかりに」 「ふかからぬ外山の庵のねさめたにさそなこの間の月はさひしき」 「詠れは千々にものおもふ月にまた我身ひとつのみねのまつかせ」 等。 故に私は 親友信尹の辞職を淋しく思ひ、光悦が宗達の下絵の色紙に筆をふるひ、さびしくも又華やかな作をなして、心をなぐさめたのではないか、と想像して居る。 又、宗達と三藐院の合作らしきものゝあるを 私は聞いて居るが、それが事実とすれば 此の問題は一層趣を増すことゝならう、―― 聊か 本論には蛇足の感もあるが、この紙面を一応の報告として置く。
処で、所謂宗達派の祖が光悦であるとすれば、光悦は新様式の創始者である。 而して 絵画に於ける優れた新様式は、絵画的天分の豊かなる者に依つてのみ 始めて創造し得るものである。 光悦に それ程の絵画的天分が認められるであらうか。 光悦がさう云ふ天分を十分に備へた作家であつたならば、私は恐らく彼の独立した絵画作品がもう少し現存して居てもいゝのではないかと思ふ。 色紙、歌巻等の筆蹟にも 大虚庵光悦などと筆太に思ひ切つた署名をして居る位の人であるから、独立した絵を描けば 必ず明瞭に落款、捺印をなしたであらう。 つまり さう云ふ彼の独立作品が少いと云ふ事は、彼の絵画的方面への消極性を物語り、彼の絵画的天分の乏しさをも肯定する事になる。 そして同時に考へられるのは、同じ時代の絵画の天才 宗達が、斯くの如き作家の様式に影響されたと見るよりも、寧ろ其の逆を考へる方がより自然であり、素直なのではなからうかと云ふ事である。 而も、前掲の菅原氏松田本阿弥家系の書入れを容認した場合は 宗達は光悦より年長とさへ考へられるし、又 俵屋方に光悦が居た事など思ふと、一層 此の説が有利になるのである。 併し、必ずしも宗達が光悦より年長でなければならぬ事はない。 現に光悦は 年下の松花堂の絵に感心した態度を示して居る。 しかも此の松花堂の絵なるものは 私の見た所、殆ど感朊出来ぬものばかりである。 それに感朊した光悦の美的感覚を 私は余り認めたくない。
斯くして私は 光悦の絵画が宗達様式の淵源であるとの説に 同意し兼ねるのである。 世に言ふ程 彼は万能の一大天才ではないと思ふ。 而して又、さう云ふ見方の方が寧ろ 光悦の芸術に対して親切であらう。 彼の陶器や蒔絵など いゝ仕事である。 鷹峯(たかがみね。京都の北部の丘陵地帯で、丹波・若狭への街道入口。光悦は、徳川家康よりこの原野を拝領、一族と共に移住し、ここで制作活動に当ったという。)に於ける活動も 当時の美術界に清新な気風を与えたに違ひない。 光琳の蒔絵や乾山の仕事にも 彼の影響はある。 併し、要するに彼の仕事は趣味人的な性格に止つてゐて、大作家宗達には及ぶべくもなかつたのである。 光悦の芸術の特質は 素人的気分である。 いゝ点も悪い点も皆 此の中にある。 具体的に云へば、素直に他人の長所を取り入れて合作などをし、又 自分の感情をも自由に表現する事も行つて居る点、それから其の反面に 彼の芸術の表面華やかに見えながらも、弘く東洋西洋の芸術を含めての観点に立つ時、覆ひ難い事実として消極性を認めねばならぬ点である。
A 舟橋蒔絵硯筥
B 伊勢物語図帖 「むかしをとこふして思ひ…」図部分、土坡
C 源氏物語関屋図屏風部分、土坡
D 御物 扇面屏風保元物語巻二左府負傷図部分、土坡
E 醍醐三宝院扇面屏風牛車図部分、土坡
蒔絵に就て 私は今迄故意に語らなかつた。 それは 光悦の絵画に対して 如上の見解を先づ示して置く必要があつたからである。 さて、光悦の傑作とされて居る舟橋硯筥(帝室博物館蔵)は 宗達派の感覚と同種のものであり、広くは我工芸史上の一異彩でもある。 「あづまじの佐野の舟橋かけてのみ思ひわたるをしる人ぞなき」(後撰集)の歌意に因み、作られて居る。 高さ 三寸九分、竪 八寸、横 七寸五分。 波と舟 ━━ 金溜地、金蒔絵。 橋 ━━ 鉛。 文字 ━━ 銀金具、金蒔絵。 (歌中の舟橋の二字は 鉛に依る図様を以て暗示され、文字としては記してない。)
処で 此の硯筥(すずりばこ)に就て私考を述べるに先だち、私は先づ 広く光悦、光琳の漆工芸に就て 次のことを述べて置く。 「漆工芸に於て 銀、鉛、青貝等を嵌入せる意匠が、宗達派の技法的特色たるたらし込み、、、、、の感覚と殆ど同じ感覚を有すること」 である。 具体的に言ふと、鉛の地は墨の肌と同種の重厚な渋味を示し、貝の肌にある一種の濃淡を想はせる自然の調子は 胡粉その他の顔料を以てするたらし込みの濃淡の調子と合し、又更に 其の貝が素地との境目に接する所に出来る輪廓の味は、やはり たらし込みの絵具によつて出来た一種の輪廓の味と共通する。 而して 蒔絵に於ける金銀の感じは、そのまゝ絵画の金銀泥に通ずるのである。 即ち 材料こそ異れ、全く同じ感じを 私は受けるのである。 絵画と工芸が之程迄、密接に関係して居る例は 他に殆ど見られない様に思ふ。 併し、宗達派絵画と光悦光琳派蒔絵との此の不思議な迄の様式の合致は 決して偶然ではない。 要するに 装飾的絵画への十分な理解と感覚が 之を為さしめたのである。
所で 此の舟橋硯筥に就て 私は次の三点に留意する。 (一) 形態に関する解釈、(二) 宗達下絵光悦色紙との様式類似、(三) 光悦の書体。
(一) 此の形態に関する解釈は色々あり、或人は田家の形と云ひ、又 或人は鷹峯の山の形に暗示を得たのであらうと言ふ。 確かに鷹峯の形は之に似て居る。 併し 私は之を 宗達の暗示に依つて作られたものであらうと解釈する。 つまり 此の奇抜な形は 何を意味すると云ふのでなく、宗達がヒントを直接与へたか、或ひは光悦が宗達様式から学んだかして出来たのではなからうかと思ふ。 更に具体的に言へば、宗達様式の例へば源氏関屋図屏風に於ける築山風の山塊、三宝院蔵扇面画中に見られる雲形の土坡(つつみ、土手)、慶長十一年十一月十一日銘ある色紙の中「ことはりの……」の和歌ある図の土坡、平家紊経化城喩品見返し画中の土坡、帝室御物扇面屏風画中、梅の図 及び保元物語巻二左府負傷図中に見られる土坡、更に 伊勢物語図帖の中「むかしおとこ、うゐかうぶりして……」の図、「われならて、したひほとくな…」の図、「むかしをとこ、ふして思ひ……」の各図に見られる土坡。 或は源氏澪標関屋図屏風、フリーア画廊蔵松島図屏風を始めとして宗達画の多くに見られる単純化された松葉の表現。 何れも皆、此の硯筥の盛上げの形とよく似て居る。 要するに私は 此の硯筥の形も或特定の意味あるものではなく、宗達的な一種の感覚から生じた装飾形態と解したいのである。 只、之が真に美的効果の上から言つて成功してゐるか何うかと云ふ問題になると、私は 此の形はやゝ奇に走り過ぎて、静けさを欠いて居る点がないでもない様な気がする。
(二) (一)の場合が側面観を基調としたのに対し、之は真上から見た場合である。 今、中央の盛上げを無くして考へると、其の図は宗達画に近い様式を示し、その上に和歌の散らしてある点、宗達光悦合作の色紙と極めて類似して居る事が分る。 要するに私は 此の図様も宗達画に暗示を得て光悦が描いたか、或は宗達が直接下絵として描いたかの何れではないかとするのである。 尚、忍草蒔絵硯箱は 三藐院風の字が嵌入されて居る所から 光悦三藐院合作と伝へられ、(此の忍草の中に兎のゐる図柄は光悦以前の時代に存するから 光悦の独創ではない) 又、竹の図柄ある硯箱があるが、此の図は松花堂の絵に似て居るから 松花堂との合作ではないかと思つて居るが、要するに かう云ふ事から考へても 宗達光悦の合作も十分あり得ると思ふのである。
(三) 此の硯筥に嵌入せる光悦の文字に依り、彼の書体の様式を検討すれば 此の蒔絵の製作年代が分る筈である。 大体、慶長末か元和始め頃ではないかと推定されるが、私は未だ光悦の書体に関し 自信ある発言をなし得ない。 只 工芸として金属を以て示された書なるが故に 年代推定が全く不可能と思はれないので 大方の御教示を得たい。
斯くして私は 此の硯箱が形態及び装飾図様に於て、宗達の様式に近似せる点、更に光悦画に対する先の見解との立場から、之を光悦の独創の作品として提唱する事の危険なるを思ふに至つたのである。
次に 伝光悦作なる蒔絵作品に就て調べる必要がある。 (光悦以前から 漆工作品には作者の名を記す事は殆ど行はれなかつた。 光悦も 其の例に習つたものと思はれる。)
(一) 宗達の絵画様式に極めて近い様式を示すもの。 例へば 山月蒔絵経筥、蓮蒔絵経筥、等。 之等は 一見宗達様式に似て居りながら、よく見ると宗達画に比して著しく生気に乏しく、間の抜けた感じを持つて居る。 (経筥蓋裏の鹿と宗達筆謡本飾絵の鹿を比べれば明瞭。 又、蓮を示した蒔絵にも宗達の如き写実性は全くない。) 此の事実からも 光悦様式から宗達様式が生ずると云ふ事は 私には考へ難くなる。 之等の蒔絵の下図は 光悦か或は彼の弟子が 宗達画を基にして作つたのであらう。
(二) 宗達様式と傾向を異にする作品。 岩崎家の秋草蒔絵謡本箱がそれである。 此の園(ママ)は 光悦以前の蒔絵の延長と見られる点が多い。
要するに私は 光悦蒔絵に於ける新機軸と云はれて居るたつぷりした図様は宗達から出たものであつて、従つて 其の材料に於ける新しい試みも宗達画に接近せんとして用ひられたとさへも考へ得ると思ふ。 光悦の弟子の作も 結局此の作風のものは宗達の流れを汲むものであらう。
光悦以前に 蒔絵師が一流の画人に其の下絵を描いてもらつて居る例はある。 幸阿弥道長(文明十年、七十一歳にて歿)は 将軍義政の近くにあつて蒔絵を作り、形状その他の好みは相阿弥に習ひ、下絵は光信に受けたと言はれて居る。 又、帝室博物館蔵、葦穂高蒔絵鞍及び鐙は 秀吉が狩野永徳に命じて下絵を描かせ、古作の鞍と鐙に高蒔絵させたものである。 蒔絵の図様とて、絵画の天分無き者に依つて出来るものではない。
斯くして私は 従来一方的に光悦 ― 宗達説が称へられて来た事に対して 其の逆説を提唱する十分なる可能性ありとするのである。 それに就て付け加へて置くが、私は 蒔絵の図様から絵画の様式が生ずると云ふ事実を否定して居るのではない。 (宗達の様式は 光悦以前の蒔絵の様式に暗示を得て居ることは種々の点に於て指摘し得る。) 私は 飽く迄も光悦と宗達の関係に於て 之を論じて居るのである。 最後に、何故光悦が今迄高く評価され過ぎてゐたのかと云ふに、その一は 鷹峯光悦村の経営や彼の広い交際 (青蓮院宮尊朝法親王、三藐院、応山信尋、烏丸光広、徳川家康、家光、老中松平信綱、土井利勝、所司代板倉勝重、同重宗、前田利家、同利常、小堀政一、林羅山、等)に依つて知られる政治家的性格の為であり、その二は 彼が茶道の関係者から持て囃された為と思はれる。 茶道に於ける美術品の価値評価には 時々不健全なものがあるからである。】(「『座右宝』創刊号(第一巻第一号)所収 )

(その七のA「躑躅と糸薄」)

(その七のB「躑躅・糸薄(続き)」)
「尾形光琳生誕三五〇周年記念 大琳派展―継承と変奏(東京国立博物館・読売新聞社編)」
所収「1-01 俵屋宗達下絵・本阿弥光悦筆 四季草花下絵古今和歌巻・重要文化財・畠山記念館蔵」(「四季花卉下絵古今集和歌巻」=『光悦……琳派の創始者(河野元昭編)』所収「書画の二重奏への道……光悦書・宗達画和歌巻の展開(玉蟲敏子稿)」) 三三・七×九一八・七
方たがへに人の家にまかれりける時に、
あるじのきぬをきせたりけるを、
あしたに返すとてよみける
876 蝉の羽の夜の衣は薄けれど移り香濃くも匂ひぬるかな(紀友則)
(蝉の羽のような夜着は薄いけれど、移り香は濃く匂っていました。)
題しらず
877 遅くいづる月にもあるかなあしひきの山のあなたも惜しむべらなり(読人知らず)
(遅く出てくる月であることだ。きっと山の向こう側も月を惜しんでいるに違いない。)
題しらず
878 我が心なぐさめかねつ更級やをばすて山に 照る月を見て(読人知らず)
(この心を静めることができない。姥捨山に照る月を見ていると。)
釈文(揮毫上の書体)=(『書道芸術第十八巻 本阿弥光悦』)
876 世三(せみ)乃(の)羽(は)濃(の)よる能(の)衣(ころも)ハ(は)う須(す)介(け)連(れ)ど移(うつり)香(か)こ久(く)も尓(に)保(ほ)日(ひ)ぬる哉
※※方たがへ(「詞書」の意など)=外出の際、「方違へ」と言って、方角の吉凶を占い、悪い方角を避けて一晩別の方向の家に泊めてもらう風習があった。その家の主人に借りた夜着を翌朝返す時、心遣いに感謝をこめた歌。
877 遅(おそく)出類(いづる)月尓(に)も有(ある)可(か)那(な)安(あ)し日(び)支(き)能(の)山濃(の)安(あ)な多(た)も於(お)し無(む)べら也
※月尓(に)も有(ある)可(か)那(な)=月にもあるかな。月であるなあ。
※安(あ)し日(び)支(き)能(の)=あしびきの。山の枕詞。
※於(お)し無(む)べら也=惜しむべらなり。惜しんでいるようだ。
878 我(わが)心な久(ぐ)左(さ)め可(か)年(ね)徒(つ)更級や祖母(をぼ)捨(すて)山に照(てる)月を見天(て)
※更級(さらしな)=更科とも。長野県千曲市 (ちくまし) 南部の地名。姨捨山 (おばすてやま) 伝説や田毎 (たごと) の月などで有名。
※祖母(をぼ)捨(すて)山=姨捨山(をぼすてやま・うばすてやま)。「姥捨山」とも書く。長野県千曲 (ちくま) 市にある冠着 (かむりき) 山の別名。標高1252メートル。古くから「田毎 (たごと) の月」とよばれる月見の名所。更級 (さらしな) に住む男が、山に捨てた親代わりの伯母を、明月の輝きに恥じて翌朝には連れ戻しに行ったという、姨捨山伝説で知られる。
http://www.asahi-net.or.jp/~sg2h-ymst/yamatouta/sennin/tomonori.html
【 紀友則(きのとものり) 生没年未詳
宮内少輔紀有朋の子。貫之の従兄。子に淡路守清正・房則がいる(尊卑分脈)。
四十代半ばまで無官のまま過ごし(後撰集)、寛平九年(897)、ようやく土佐掾の官職を得る。翌年、少内記となり、延喜四年(904)には大内記に任官した。歌人としては、宇多天皇が親王であった頃、すなわち元慶八年(884)以前に近侍して歌を奉っている(『亭子院御集』)ので、この頃すでに歌才を認められていたらしい。寛平三年(891)秋以前の内裏菊合、同四年頃の是貞親王家歌合・寛平御時后宮歌合などに出詠。壬生忠岑と並ぶ寛平期の代表的歌人であった。延喜五年(905)二月二十一日、藤原定国の四十賀の屏風歌を詠んだのが、年月日の明らかな最終事蹟。おそらくこの年、古今集撰者に任命されたが、まもなく病を得て死去したらしい。享年は五十余歳か。紀貫之・壬生忠岑がその死を悼んだ哀傷歌が古今集に見える。
古今集に四十七首収録(作者名不明記の一首を含む)。その数は貫之・躬恒に次ぐ第三位にあたる。勅撰入集は総計七十首。家集『友則集』がある。三十六歌仙の一人。小倉百人一首に歌を採られている。 】
ここは『伊勢物語』の「東下り」(第7段から第9段)、殊に、その第8段(信濃)などを背景にあるもののように解したい。
https://yahan.blog.ss-blog.jp/2020-11-27
第7段 東下り(伊勢・尾張)(いとゞしく過ぎ行く方の恋しきにらやましくもかへる浪かな)
第8段 東下り(信濃)(信濃なる浅間の嶽にたつ煙をちこち人の見やはとがめぬ)
第9段 東下り(八橋)(唐衣きつゝ馴にしつましあればはるばる来ぬる旅をしぞ思ふ)
同(宇津)(駿河なる宇津の山辺のうゝにも夢にも人に逢はぬなりけり)
同(富士)(時しらぬ山は富士の嶺いつとてか鹿の子まだらに雪の降るらむ)
同(隅田川)(名にしおはゞいざこと問は都鳥むわが思ふ人はありやなしやと)
https://ise-monogatari.hix05.com/1/ise008.asama.html

『伊勢物語(第8段 東下り・信濃)』(住吉如慶筆)
【むかし、をとこありけり。京や住みうかりけむ、あづまのかたにゆきて、住み所もとむとて、友とする人ひとりふたりして行きけり。信濃の国浅間の嶽にけぶりの立つを見て、
信濃なる浅間の嶽にたつ煙をちこち人の見やはとがめぬ 】(『伊勢物語(第8段 東下り・信濃)』)
『新古今和歌集(巻第十・羇旅歌)』に、この在原業平の「浅間山」の歌が収載されている。
東(あづま)の方(かた)にまかりけるに、浅間の嶽(たけ)
に煙(けぶり)の立つを見てよめる
903 信濃なる淺間の嶽に立つけぶりをちこち人(びと)の見やはとがめぬ(在原業平朝臣『新古今集』)
(信濃の国にある浅間山に立ちのぼる噴煙は、遠くの人も近くの人も、どうして目を見張ら
ないことであろうか、誰しも目を見張ることであろう。)
(参考) 「四季花卉下絵古今集和歌巻」(「その一~その三」「その四~その六」「その七A・B)
「四季草花下絵古今和歌巻」(その一・その二・その三)
「四季草花下絵古今和歌巻」(その四・その五・その六)
「四季草花下絵古今和歌巻」(その七・その八・その九)
https://yahan.blog.ss-blog.jp/2020-11-27
↑
上記のアドレスの「コメント」の欄で、次のように記した。
【 https://www.jisyameguri.com/event/cyomyoj
↑
このサイトで「牛図」(宗達筆、・光広賛)が見られる。ここに、何と「伝俵屋宗達墓」の写真もアップされていた。この種のものは、数ある「活字情報・ネット情報」でも、管見の限り、このサイトで初めての感じ。
関連して、『ウィキペディア(Wikipedia)』を見ると、そもそもは、禁裏(御所)の近くにあったのを、「1673年(寛文13年)禁裏に隣接しているという理由で、現在の地に移転した」とある。】
この頂妙寺(現: 京都府京都市左京区大菊町)の「伝俵屋宗達墓」について、終戦直後の、昭和二十三年(一九四八)に刊行された『宗達の水墨画(徳川義恭著・座右宝刊行会刊)で紹介されているようである。
https://www.kosho.or.jp/products/detail.php?product_id=114985763

文庫版『宗達の水墨画(徳川義恭著・座右宝刊行会刊)
【徳川 義恭(とくがわ よしやす、1921年(大正10年)1月18日 - 1949年(昭和24年)12月12日)は、日本の美術研究者、装幀家。尾張徳川家の分家の当主である男爵・徳川義恕の四男。母方の祖父・津軽承昭は弘前藩主。長兄・徳川義寛は昭和天皇の侍従・侍従長。姉・祥子の夫は北白川宮永久王。次兄・義孝(津軽英麿の養子となる)の娘は、常陸宮正仁親王妃華子で、義恭の姪にあたる。夫人・雅子(のりこ)は田安徳川家の徳川達成の長女。
1942年(昭和17年)、学習院高等科を卒業し、東京帝国大学文学部美学美術史学科に入学。同年7月1日、三島由紀夫や東文彦と共に同人誌『赤絵』を創刊した。同誌および、1944年(昭和19年)10月発行の三島の処女作品集『花ざかりの森』(七丈書院)の装幀を担当した。
著書は1941年(昭和16年)に私家版の編著『暢美』を、1948年(昭和23年)に『宗達の水墨画』(座右宝刊行会(座右寳叢書))がある。
亜急性細菌性心内膜炎で夭折した。享年28。三島は人となりを偲んで、短篇小説『貴顕』]を書いている。
三島との往復書簡が、数通だが『三島由紀夫十代書簡集』(新潮社、のち新潮文庫)に収められている。2010年(平成22年)に遺族宅で、新たに三島からの手紙9通(1942年 - 1944年)が発見された。 】(『ウィキペディア(Wikipedia)』)
https://www.chugainippoh.co.jp/article/ron-kikou/ron/20200612-001.html
【1946(昭和21)年、美術研究者の徳川義恭氏は当時、俵屋蓮池・喜多川第17代当主である喜多川平朗氏の協力を得て喜多川家伝来の歴代譜、頂妙寺墓所にある俵屋喜多川一門の供養塔の碑銘を調査し、蓮池平右衛門尉秀明に始まる俵屋喜多川宗家の系譜を明らかにされた。自著『宗達の水墨画』においてその調査結果を公表された中で「蓮池俵屋についてはそれを系統的に知り得ず、之が引いては宗達との関係を不明瞭にしているものと思われる」と述べられている。ちなみに現当主、第18代喜多川俵二氏は師父と同様に人間国宝として俵屋の家職を継承し頂妙寺大乗院と結縁されている。】(「謎多い絵師・俵屋宗達の実像」日蓮宗大法寺住職 栗原啓允稿)
https://userweb.pep.ne.jp/c6v00030/r122.html
【宗達・光悦 試論 ― 宗達研究の一節 ― 徳川 義恭
宗達と光悦との関係は 歌巻、色紙、短冊、謡曲本の合作が現存する事により 証明されるが、更に 片岡家本、菅原氏松田本阿弥家系が信じられるとすれば、宗達の妻は光悦の妻の姉と云ふ事になり、極めて近い間柄となる。 又、光悦の書簡の一に 「俵屋方、光悦」と記したものがある。 少庵書状 (1) に依つて 宗達が俵屋を号した事が確認されて居る現在、之も亦 宗達の家に光悦が居たと云ふ事実を知る 興味ある資料である。
処で 私が此の小論で述べようとする所は、此の二人の芸術的立場に於ける先後問題なのである。 つまり 光悦の芸術から宗達の芸術が生れたものであるか、或は宗達から光悦か、の問題である。 之は 近世美術史上、極めて重大な問題であるにも拘らず、批判的立場から余り論じられて居ない。 そして先づ一般には 光悦から宗達が出たのであるとする説が大部分の様である。 中には 光悦派と云ふ名称を掲げ その中に宗達光琳を含ませる考へもある。 尤も 私が之から述べようとする処は 光悦―宗達説を全然否定し去らうと云ふのではない。 此の問題は 現在の資料を以てしては 確言することは勿論出来ないのである。 それ故、試論として 私が宗達―光悦説を述べてみるのである。
注 (1) 少庵書状 ― 美術研究第百十一号
私は先づ、光悦の芸術が 世に余りに高く評価され過ぎてゐはしないか、と思ふ。 彼をレオナルド・ダヴインチと並べて評した一説の如きは 問題外としても、万能の天才 光悦と云ふ文字は 余りにも多く見かける。 勿論私は 彼の茶碗のよさは認めて居る。 陶器に於て あれだけの大きさと深み、渋さを表現した事は 確かに一つの大きな仕事である。 処が 之を賞讃するの余り、彼の他の作品分野に迄 無批判的にそのよさを及ぼし評価することが 行はれて居はしないだらうか。 書道に於て光悦は 松花堂(松花堂 昭堂、1582~1639。真言宗の僧侶にして書家。松花堂流を創始した。)、三藐院(近衛 信尹、1565~1614。五摂家の筆頭たる近衛家の嫡流にして、書家。三藐院と号した。)と共に三筆とうたはれた。 確かに彼の書は暢達であり、独創的で自由な処がある。 殊に 金銀泥の飾絵の上に 太く細く配置して行く技巧と感覚には 勝れたものがある。 当時、賞讃された事もよく肯ける。 併し 一たび視界を広く書の美と云ふ点に置いた場合に、彼の書は 達者ではあるが 真の深みあるよさを感じられない様な気がする。 因みに 宗達の下絵ある歌巻なり、短冊なりの、其の下絵無しで見た場合に さう云ふ事は感じられると思ふ。 処で 今私が問題とするのは 茶碗や書ではなく(勿論 之等も宗達を考へる上に必要なのであるが)彼の蒔絵と絵画なのである。
元来、光悦が如何なる程度に絵画をよくしたかは 明瞭でない。 屢々記録に現はれるものに 自讃三十六歌仙絵があるが、之に就て古画備考は 「画は皺法正敷歌仙絵也」と記して居る。 尾形流百図を見ると、抱一文庫の光悦自画讃三十六歌仙の絵が載せられて居る。 此の様式が所謂 光悦画の本体であるとすれば、それは又 著しく宗達様式とは離れたものと言はねばならぬ。 又 同書に本田家蔵として、萩之坊乗円讃光悦画定家卿なる図が掲げられて居るが、様式は先の三十六歌仙図と全く同じであり、之には光悦の方印が捺してある。 之等の図に見られる描線は 宗達風のものではない。 而して 従来の説の如く 光悦の蒔絵等に於ける図様を光悦画の本体とするならば、此の三十六歌仙絵の系統(前述の如く その同類のものに光悦の印さへある)は 光悦の画様式の如何なる位置に置かれるものであらうか。 ―― 私は案外、光悦画の様式の本体は所謂宗達風のものではなく、右(上)の例の様な描線を有する 比較的常識的な画様であつたのではないかと思ふ。 そして 若し光悦が、一般に宗達光琳の祖と言はれて居る作風のものを描いたとすれば、それは実は 光悦が宗達の作風に影響されて以後のものではないかと思ふ。 而も 光悦筆と確証し得る絵画作品のないと云ふ事実は、半面に 下絵を宗達に仰いでゐる作品が確実に存する(宗達の伊年円印あるもの三点、その他色紙、短冊等確実に様式上宗達と見做されるもの数十点)と云ふ事実と相俟つて、彼の絵画に対する疑問を一層増大せしめるのである。
光悦伝に依ると、光悦は書に於ては相当自信を持つて居たかの如く思はれる。 有名な話ではあるが、続近世畸人伝(江戸中期の文人・伴蒿蹊が著した人物伝。1898年刊。)に 「或時 近衛三藐院 光悦にたづねたまふ 今天下に能書といふは誰とかするぞと 光悦 先づ さて次は君 次は八幡の坊也 その先づとは誰ぞと仰たまふに 恐ながら私なりと申す 此時此三筆 天下に名あり」 とある。 即ち 自分が最上で 次が三藐院 次が松花堂 と云ふのである。 此の話は勿論 一概に信じ難いとは言ひ條、光悦が書に於て相当自信があつたと云ふ事実を 察する事が出来る様に思はれる。 又、社会的にも彼の色紙が高く評価されて居た事は 次の話でも分る。 即ち、光悦の甥 光室が江戸城中に於て急病に斃れた際、彼は急ぎ東下した。 こゝで 思ひ掛けなくも 将軍家光に拝謁する事になつたが、献上物を持参してゐないので それを土井大炊頭に告げると、色紙を差し上げるがよからうと言ふ。 光悦は「差上候程の色紙有合不レ申」と述べると、大炊頭は「先年御貰ひ候色紙有レ之候間、先是御貸可レ申候間、献上致可レ然」と言ひ、之を以て事が運んだと云ふ。 現存の光悦色紙が皆彼の書のあるもので 絵画のみのものを右の場合に想像する事は当らない様に思はれるから、此の話を以て 書に於ては文字通り自他共に許したと云ふ事が分るのである。
所が 今問題とする絵画に就ては 寧ろ自信に乏しかつたかの如き記録がある。 本阿弥行状記の一節で、同じく無条件に信ずべき性質のものではないが、次の様な話がある。 「或時 猩々翁(松花堂ノコト)、予(光悦)が新に建てたる小室を見て、さても あら壁に山水鳥獣あらゆるものあり、絵心なき処にては、かやうのことも時々写し度思ふ時も遠慮せり、幸と別懇のその宅中 ねがふてもなきことゝ、一宿をして終日色々の絵をしたゝめ 予にも恵まれし、我も絵は少しはかく事を得たりといへども中々其妙に至らざれば、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、あら壁の模様をよき絵の手本とも知らず、勿論古来よりあら壁に絵の姿あると申すことは聞伝ふるといへども、まのあたり猩々翁のかきとられしにて疑もはれ何事も上達せざれば其奥義をとられぬものと今更の様に思ひぬ」 ―― 而して光悦は 一方同じ書に於て、「陶器を作ることは 予は猩々翁にまされり」と述べたと記してある。 即ち 絵画に対する彼の態度が、陶器、書に対するものと異つてゐた事が窺ひ得るのである。 自信あるものは飽く迄も明瞭にしてゐたのであるから、画事に就て松花堂に示した態度は 単なる表面の謙譲ではなかつたと見るべきである。 又、特に文中 猩々翁○とある点に留意すれば、松花堂は光悦より略々廿五年程若いのであるから、此の話は光悦の若い時の事とは思はれない、(ここは 読点(。)の誤りであろう。) (例へ翁と云ふ言葉が敬称として用ひられ、松花堂の所謂 晩年に用ひられたのではないとしても、余り若くしては此の称は用ひられぬであらう(。)) 要するに光悦は 晩年に至つて画事に自信ある境地に達し得たのではなからうか、と云ふ推論の余地は無い訳である。 而も宗達は 慶長十一年には光悦の和歌下絵を既に描いて居るのであるから、此の点に於ても 宗達画の先駆を光悦とすることは困難なのである。 (慶長十一年に 光悦は四十九歳、松花堂は略々廿三歳)
慶長十一年十一月十一日銘ある 宗達下絵光悦和歌色紙に就ては、嘗て矢代幸雄先生が 美術研究第九十三号に発表されたが、此の特殊なる年紀に関しては疑問のまゝ 問題を残された。 私は 黒板博士の国史研究年表に依り、此の日に近衛三藐院が関白を辞して居る事実を知つた。 三藐院と光悦との交際は既に証せられて居る。 而して 矢代先生も指摘されて居る様に、此等十一枚の色紙には 新古今集秋上の部に互に相近く載せられた月に関する歌が書かれて居る。 而して それらは淋しい歌が多いのである。 例へば 「ことはりの秋にはあへぬ涙哉つきのかつらもかはるひかりに」 「ふかからぬ外山の庵のねさめたにさそなこの間の月はさひしき」 「詠れは千々にものおもふ月にまた我身ひとつのみねのまつかせ」 等。 故に私は 親友信尹の辞職を淋しく思ひ、光悦が宗達の下絵の色紙に筆をふるひ、さびしくも又華やかな作をなして、心をなぐさめたのではないか、と想像して居る。 又、宗達と三藐院の合作らしきものゝあるを 私は聞いて居るが、それが事実とすれば 此の問題は一層趣を増すことゝならう、―― 聊か 本論には蛇足の感もあるが、この紙面を一応の報告として置く。
処で、所謂宗達派の祖が光悦であるとすれば、光悦は新様式の創始者である。 而して 絵画に於ける優れた新様式は、絵画的天分の豊かなる者に依つてのみ 始めて創造し得るものである。 光悦に それ程の絵画的天分が認められるであらうか。 光悦がさう云ふ天分を十分に備へた作家であつたならば、私は恐らく彼の独立した絵画作品がもう少し現存して居てもいゝのではないかと思ふ。 色紙、歌巻等の筆蹟にも 大虚庵光悦などと筆太に思ひ切つた署名をして居る位の人であるから、独立した絵を描けば 必ず明瞭に落款、捺印をなしたであらう。 つまり さう云ふ彼の独立作品が少いと云ふ事は、彼の絵画的方面への消極性を物語り、彼の絵画的天分の乏しさをも肯定する事になる。 そして同時に考へられるのは、同じ時代の絵画の天才 宗達が、斯くの如き作家の様式に影響されたと見るよりも、寧ろ其の逆を考へる方がより自然であり、素直なのではなからうかと云ふ事である。 而も、前掲の菅原氏松田本阿弥家系の書入れを容認した場合は 宗達は光悦より年長とさへ考へられるし、又 俵屋方に光悦が居た事など思ふと、一層 此の説が有利になるのである。 併し、必ずしも宗達が光悦より年長でなければならぬ事はない。 現に光悦は 年下の松花堂の絵に感心した態度を示して居る。 しかも此の松花堂の絵なるものは 私の見た所、殆ど感朊出来ぬものばかりである。 それに感朊した光悦の美的感覚を 私は余り認めたくない。
斯くして私は 光悦の絵画が宗達様式の淵源であるとの説に 同意し兼ねるのである。 世に言ふ程 彼は万能の一大天才ではないと思ふ。 而して又、さう云ふ見方の方が寧ろ 光悦の芸術に対して親切であらう。 彼の陶器や蒔絵など いゝ仕事である。 鷹峯(たかがみね。京都の北部の丘陵地帯で、丹波・若狭への街道入口。光悦は、徳川家康よりこの原野を拝領、一族と共に移住し、ここで制作活動に当ったという。)に於ける活動も 当時の美術界に清新な気風を与えたに違ひない。 光琳の蒔絵や乾山の仕事にも 彼の影響はある。 併し、要するに彼の仕事は趣味人的な性格に止つてゐて、大作家宗達には及ぶべくもなかつたのである。 光悦の芸術の特質は 素人的気分である。 いゝ点も悪い点も皆 此の中にある。 具体的に云へば、素直に他人の長所を取り入れて合作などをし、又 自分の感情をも自由に表現する事も行つて居る点、それから其の反面に 彼の芸術の表面華やかに見えながらも、弘く東洋西洋の芸術を含めての観点に立つ時、覆ひ難い事実として消極性を認めねばならぬ点である。
A 舟橋蒔絵硯筥
B 伊勢物語図帖 「むかしをとこふして思ひ…」図部分、土坡
C 源氏物語関屋図屏風部分、土坡
D 御物 扇面屏風保元物語巻二左府負傷図部分、土坡
E 醍醐三宝院扇面屏風牛車図部分、土坡
蒔絵に就て 私は今迄故意に語らなかつた。 それは 光悦の絵画に対して 如上の見解を先づ示して置く必要があつたからである。 さて、光悦の傑作とされて居る舟橋硯筥(帝室博物館蔵)は 宗達派の感覚と同種のものであり、広くは我工芸史上の一異彩でもある。 「あづまじの佐野の舟橋かけてのみ思ひわたるをしる人ぞなき」(後撰集)の歌意に因み、作られて居る。 高さ 三寸九分、竪 八寸、横 七寸五分。 波と舟 ━━ 金溜地、金蒔絵。 橋 ━━ 鉛。 文字 ━━ 銀金具、金蒔絵。 (歌中の舟橋の二字は 鉛に依る図様を以て暗示され、文字としては記してない。)
処で 此の硯筥(すずりばこ)に就て私考を述べるに先だち、私は先づ 広く光悦、光琳の漆工芸に就て 次のことを述べて置く。 「漆工芸に於て 銀、鉛、青貝等を嵌入せる意匠が、宗達派の技法的特色たるたらし込み、、、、、の感覚と殆ど同じ感覚を有すること」 である。 具体的に言ふと、鉛の地は墨の肌と同種の重厚な渋味を示し、貝の肌にある一種の濃淡を想はせる自然の調子は 胡粉その他の顔料を以てするたらし込みの濃淡の調子と合し、又更に 其の貝が素地との境目に接する所に出来る輪廓の味は、やはり たらし込みの絵具によつて出来た一種の輪廓の味と共通する。 而して 蒔絵に於ける金銀の感じは、そのまゝ絵画の金銀泥に通ずるのである。 即ち 材料こそ異れ、全く同じ感じを 私は受けるのである。 絵画と工芸が之程迄、密接に関係して居る例は 他に殆ど見られない様に思ふ。 併し、宗達派絵画と光悦光琳派蒔絵との此の不思議な迄の様式の合致は 決して偶然ではない。 要するに 装飾的絵画への十分な理解と感覚が 之を為さしめたのである。
所で 此の舟橋硯筥に就て 私は次の三点に留意する。 (一) 形態に関する解釈、(二) 宗達下絵光悦色紙との様式類似、(三) 光悦の書体。
(一) 此の形態に関する解釈は色々あり、或人は田家の形と云ひ、又 或人は鷹峯の山の形に暗示を得たのであらうと言ふ。 確かに鷹峯の形は之に似て居る。 併し 私は之を 宗達の暗示に依つて作られたものであらうと解釈する。 つまり 此の奇抜な形は 何を意味すると云ふのでなく、宗達がヒントを直接与へたか、或ひは光悦が宗達様式から学んだかして出来たのではなからうかと思ふ。 更に具体的に言へば、宗達様式の例へば源氏関屋図屏風に於ける築山風の山塊、三宝院蔵扇面画中に見られる雲形の土坡(つつみ、土手)、慶長十一年十一月十一日銘ある色紙の中「ことはりの……」の和歌ある図の土坡、平家紊経化城喩品見返し画中の土坡、帝室御物扇面屏風画中、梅の図 及び保元物語巻二左府負傷図中に見られる土坡、更に 伊勢物語図帖の中「むかしおとこ、うゐかうぶりして……」の図、「われならて、したひほとくな…」の図、「むかしをとこ、ふして思ひ……」の各図に見られる土坡。 或は源氏澪標関屋図屏風、フリーア画廊蔵松島図屏風を始めとして宗達画の多くに見られる単純化された松葉の表現。 何れも皆、此の硯筥の盛上げの形とよく似て居る。 要するに私は 此の硯筥の形も或特定の意味あるものではなく、宗達的な一種の感覚から生じた装飾形態と解したいのである。 只、之が真に美的効果の上から言つて成功してゐるか何うかと云ふ問題になると、私は 此の形はやゝ奇に走り過ぎて、静けさを欠いて居る点がないでもない様な気がする。
(二) (一)の場合が側面観を基調としたのに対し、之は真上から見た場合である。 今、中央の盛上げを無くして考へると、其の図は宗達画に近い様式を示し、その上に和歌の散らしてある点、宗達光悦合作の色紙と極めて類似して居る事が分る。 要するに私は 此の図様も宗達画に暗示を得て光悦が描いたか、或は宗達が直接下絵として描いたかの何れではないかとするのである。 尚、忍草蒔絵硯箱は 三藐院風の字が嵌入されて居る所から 光悦三藐院合作と伝へられ、(此の忍草の中に兎のゐる図柄は光悦以前の時代に存するから 光悦の独創ではない) 又、竹の図柄ある硯箱があるが、此の図は松花堂の絵に似て居るから 松花堂との合作ではないかと思つて居るが、要するに かう云ふ事から考へても 宗達光悦の合作も十分あり得ると思ふのである。
(三) 此の硯筥に嵌入せる光悦の文字に依り、彼の書体の様式を検討すれば 此の蒔絵の製作年代が分る筈である。 大体、慶長末か元和始め頃ではないかと推定されるが、私は未だ光悦の書体に関し 自信ある発言をなし得ない。 只 工芸として金属を以て示された書なるが故に 年代推定が全く不可能と思はれないので 大方の御教示を得たい。
斯くして私は 此の硯箱が形態及び装飾図様に於て、宗達の様式に近似せる点、更に光悦画に対する先の見解との立場から、之を光悦の独創の作品として提唱する事の危険なるを思ふに至つたのである。
次に 伝光悦作なる蒔絵作品に就て調べる必要がある。 (光悦以前から 漆工作品には作者の名を記す事は殆ど行はれなかつた。 光悦も 其の例に習つたものと思はれる。)
(一) 宗達の絵画様式に極めて近い様式を示すもの。 例へば 山月蒔絵経筥、蓮蒔絵経筥、等。 之等は 一見宗達様式に似て居りながら、よく見ると宗達画に比して著しく生気に乏しく、間の抜けた感じを持つて居る。 (経筥蓋裏の鹿と宗達筆謡本飾絵の鹿を比べれば明瞭。 又、蓮を示した蒔絵にも宗達の如き写実性は全くない。) 此の事実からも 光悦様式から宗達様式が生ずると云ふ事は 私には考へ難くなる。 之等の蒔絵の下図は 光悦か或は彼の弟子が 宗達画を基にして作つたのであらう。
(二) 宗達様式と傾向を異にする作品。 岩崎家の秋草蒔絵謡本箱がそれである。 此の園(ママ)は 光悦以前の蒔絵の延長と見られる点が多い。
要するに私は 光悦蒔絵に於ける新機軸と云はれて居るたつぷりした図様は宗達から出たものであつて、従つて 其の材料に於ける新しい試みも宗達画に接近せんとして用ひられたとさへも考へ得ると思ふ。 光悦の弟子の作も 結局此の作風のものは宗達の流れを汲むものであらう。
光悦以前に 蒔絵師が一流の画人に其の下絵を描いてもらつて居る例はある。 幸阿弥道長(文明十年、七十一歳にて歿)は 将軍義政の近くにあつて蒔絵を作り、形状その他の好みは相阿弥に習ひ、下絵は光信に受けたと言はれて居る。 又、帝室博物館蔵、葦穂高蒔絵鞍及び鐙は 秀吉が狩野永徳に命じて下絵を描かせ、古作の鞍と鐙に高蒔絵させたものである。 蒔絵の図様とて、絵画の天分無き者に依つて出来るものではない。
斯くして私は 従来一方的に光悦 ― 宗達説が称へられて来た事に対して 其の逆説を提唱する十分なる可能性ありとするのである。 それに就て付け加へて置くが、私は 蒔絵の図様から絵画の様式が生ずると云ふ事実を否定して居るのではない。 (宗達の様式は 光悦以前の蒔絵の様式に暗示を得て居ることは種々の点に於て指摘し得る。) 私は 飽く迄も光悦と宗達の関係に於て 之を論じて居るのである。 最後に、何故光悦が今迄高く評価され過ぎてゐたのかと云ふに、その一は 鷹峯光悦村の経営や彼の広い交際 (青蓮院宮尊朝法親王、三藐院、応山信尋、烏丸光広、徳川家康、家光、老中松平信綱、土井利勝、所司代板倉勝重、同重宗、前田利家、同利常、小堀政一、林羅山、等)に依つて知られる政治家的性格の為であり、その二は 彼が茶道の関係者から持て囃された為と思はれる。 茶道に於ける美術品の価値評価には 時々不健全なものがあるからである。】(「『座右宝』創刊号(第一巻第一号)所収 )
四季花卉下絵古今集和歌巻(その六) [光悦・宗達・素庵]
その六 躑躅と糸薄

「尾形光琳生誕三五〇周年記念 大琳派展―継承と変奏(東京国立博物館・読売新聞社編)」
所収「1-01 俵屋宗達下絵・本阿弥光悦筆 四季草花下絵古今和歌巻・重要文化財・畠山記念館蔵」(「四季花卉下絵古今集和歌巻」=『光悦……琳派の創始者(河野元昭編)』所収「書画の二重奏への道……光悦書・宗達画和歌巻の展開(玉蟲敏子稿)」) 三三・七×九一八・七
寛平の御時に、うへのさぶらひに侍りけるをのこども、
かめをもたせてきさいの宮の御方に大御酒のおろしと
きこえにたてまつりたりけるを、蔵人ども笑ひて、
かめをおまへにもていでてともかくもいはずなりにければ、
つかひのかへりきて、さなむありつるといひければ、
蔵人のなかにおくりける
874 玉だれのこがめやいづらこよろぎの磯の浪わけ沖にいでにけり(藤原敏行 )
(あの小亀はどこへいったやら、こよろぎの磯の浪を分けて沖に出ていってしまったよ。)
女どもの見て笑ひければよめる
875 かたちこそみ山隠れの朽ち木なれ心は花になさばなりなむ(兼芸法師)
(見た目こそ山奥の朽木のようではあるが、心は花にしようと思えばいつでも花を咲かせられますよ。)
釈文(揮毫上の書体)=(『書道芸術第十八巻 本阿弥光悦』)
874玉だ連(れ)能(の)こ可(が)めやい徒(づ)らこよろ支(ぎ)能(の)い曾(そ)濃(の)波王(わ)遺(け)於(お)き尓(に)出(いで)尓(に)介(け)利(り)
※玉だ連(れ)能(の)=玉だれの。「子」の枕詞として用いる。
※こよろ支(ぎ)能(の)=こよろぎ。いまの神奈川県大磯市あたりの海岸。
※於(お)き尓(に)出(いで)尓(に)介(け)利(り)=おきにいでけり。「沖」に「奥=皇后宮の御前」の意を掛ける。
※※寛平の御時に=宇多天皇の御時。
※※うへのさぶらひに侍りけるをのこども=清涼殿の殿上の間に侍っていた侍臣たち。
※※きさいの宮=后宮。皇后藤原温子。
※※蔵人=女蔵人(下臈の女房)。
875形(かたち)こ曾(そ)深山(みやま)隠(がくれ)濃(の)朽木(くちき)那(な)禮(れ)心盤(は)華(はな)尓(に)な左(さ)ハ(ば)成(なり)南(なむ)
※形(かたち)こ曾(そ)=かたちこそ。顔かたち。容貌。
※深山(みやま)隠(がくれ)濃(の)朽木(くちき)那(な)禮(れ)=深山隠れの朽ち木なれ。奥山に隠れている朽ち木のようなものですが。
http://www.asahi-net.or.jp/~SG2H-YMST/yamatouta/sennin/tosiyuki.html
【 藤原敏行(ふじわらのとしゆき) 生年未詳~延喜元(?-901)
陸奥出羽按察使であった南家富士麿の長男。母は紀名虎の娘。紀有常の娘(在原業平室の姉妹)を妻とする。子には歌人で参議に到った伊衡などがいる。
貞観八年(866)、少内記。地方官や右近少将を経て、寛平七年(895)、蔵人頭。同九年、従四位上右兵衛督。『古今集和歌目録』に「延喜七年卒。家伝云、昌泰四年卒」とある(昌泰四年は昌泰三年=延喜元年の誤りか)。
三十六歌仙の一人。能書家としても名高い。古今集に十九首、後撰集に四首採られ、勅撰集入集は計二十九首。三十六人集の一巻として家集『敏行集』が伝存する。一世代前の六歌仙歌人たちにくらべ、技巧性を増しながら繊細流麗、かつ清新な感覚がある。和歌史的には、まさに業平から貫之への橋渡しをしたような歌人である。 】
https://www.asahi-net.or.jp/~SG2H-ymst/yamatouta/sennin/kengei.html
【 兼芸法師=兼藝(けんげい(けむげい)) 生没年未詳
『古今和歌集目録』によれば伊勢少掾古之の二男で、大和国城上郡の人かという。左大臣源融の孫占の子とも。即位以前の光孝天皇と親しかったことを窺わせる歌を古今集に残している(巻八離別歌)。勅撰入集は古今集のみ四首。 】
これらの歌(藤原敏行と兼芸法師の二首)は、『古今集(巻第十四・恋歌四)の、次の在原業平の歌と関係があるようである。
藤原の敏行の朝臣の、業平の朝臣の家なりける女を
あひ知りてふみつかはせりけることばに、いままうでく、
あめの降りけるをなむ見わづらひ侍る、といへりけるを聞きて、
かの女にかはりてよめりける
705 かずかずに思ひ思はずとひがたみ身を知る雨は降りぞまされる(在原業平)
(いろいろと、貴方と私の間は、相思相愛の間柄なのかと思い悩んだりしていますが、貴方に直接聞くわけにもいかず、この雨に聞けば、この雨の降り様は、「そうではない」と告げているようです。)
そして、これまた、『伊勢物語(第一〇七段)』に由来があるような雰囲気である。
http://teppou13.fc2web.com/hana/narihira/ise/old/ise_o107.html
【むかし、あてなる男ありけり。その男のもとなりける人を、内記にありける藤原の敏行といふ人よばひけり。されど若ければ、文もをさをさしからず、言葉もいひ知らず、いはんや歌はよまざりければ、かのあれじなる人、案を書きてかゝせてやりけり。めでまどひにけり。さて男のよめる、
つれづれのながめにまさる涙川
袖のみひぢて逢ふよしもなし
かへし、れいの男、女にかはりて、
浅みこそ袖はひづらめ涙川
身さへながると聞かばたのまむ
といへりければ、男いといたうめでて、いままでまきて文箱に入れてありとなむいふなる。 男文おこせたり。えてのちの事なりけり。「雨の降りぬべきになむ見わづらひ侍る。身さいはひあらば、この雨は降らじ」といへりければ、例の男、女に代りてよみてやらす。
かずかずに思ひ思はず問ひがたみ
身をしる雨は降りぞまされる
とよみてやれりければ、蓑も笠もとりあへで、しとゞに濡れてまどひきにけり。】(『伊勢物語(第一〇七段)』)
(参考) 「四季花卉下絵古今集和歌巻」(「その一~その三」「その四~その六」)

「四季草花下絵古今和歌巻」(その一・その二・その三)

「四季草花下絵古今和歌巻」(その四・その五・その六)
上記の「その一」は「竹」図(冬)、「その二・その三・その三・その四」は「梅(春)」図、そして、「その四」は「土坡(梅から椿)」(春から夏)への「季移り」(「季節の替わり」・「連歌・連句で、雑(ぞう)の句をはさまず、ある季の句に直ちに他の季の句を付けること」の「雑」の場面、「その一」と「その「二」は「季移り」)の図柄の雰囲気である。
今回の「その六」(躑躅と糸薄)は、全体に「躑躅」(夏)の景物で、中ほどに、直接の「季移り」を避ける「雑」(間を取る)のような「土坡」を上部に描いて(「その五」の土坡は下部)、その次に「躑躅」の根本に「糸薄」(秋)を添えている図柄のようである。
この「その六」の関連については、次のアドレスで触れている。画像は省略して、その紹介記事や、そのアドレスでの「光悦と宗達」周辺のことを再掲して置きたい。
https://yahan.blog.ss-blog.jp/2018-07-11
(再掲)
(画像省略=上掲の「その六」冒頭の図と「その一」の「竹」部分図)
俵屋宗達画・本阿弥光悦書「四季草花下絵和歌巻」(部分図=躑躅) 紙本金銀泥
三三・五×九一八・七㎝ 重要文化財 畠山記念館蔵
【 太い竹の幹のクローズアップから始まり、巻物を操るに従って、梅・躑躅(つつじ)・蔦(つた)が現れる。それぞれ、正月・春・夏・秋の四季の移り変わりを表わす。竹の表面は「たらし込み」の技法で質感が表現されている。宗達は以前、版画による料紙装飾で同様の竹をモティーフとしたが、版木を離すときに生じる金泥のムラの効果を、筆で描くときにも応用した。巻末に光悦の印章と、宗達の「伊年」の印章がある。 】(『日本の美をめぐる 奇跡の出会い 宗達と光悦(小学館)』)
「本阿弥光悦」の「本阿弥」家は、刀剣の「磨ぎ・浄拭(ぬぐい)・鑑定(めきき)」を専門とする家柄である。そもそも、「本阿弥」の「阿弥」というのは、将軍家に仕えて芸能や美術などの特殊技能をつかさどった「同朋衆」が名のることが多かった。室町時代に活躍した「能阿弥・芸阿弥・相阿弥」など三阿弥と呼ばれる同朋たちは、足利将軍家で儀式の飾りつけのコーディネートや美術品の鑑定・管理などをこなし、新たな美術品を注文する際に意見を求められた家柄である。
その「同朋衆」の出の「本阿弥光悦」は、元和元年(一六一五)に徳川家康より鷹ケ峰(洛北)に広大な土地を与えられ、ここに様々な工芸に携わる職人たちと移り住んで芸術村を形成し、日本で最初の「アートディレクター」(総合芸術の演出家)兼「書家」(「寛永三筆」の一人)兼「蒔絵師」兼「陶工師」などの、当時の超一流の文化人ということになる。
もう一人の「俵屋宗達」は、光悦と縁戚関係にあるとも、本阿弥家と同じ小川町(上京区)の「蓮池家・喜多川家」出の「絵屋」(「俵屋」という屋号で「絵屋」=「屛風・掛幅のほか料紙装飾・扇絵・貝絵など、主に仕込み絵的な一種の既製品を制作・販売する」)を主宰していたともいわれているが、絵師としても法橋を授与されており、これまた、当時の超一流の文化人の一人であったのであろう。
ここで、この「四季草花下絵和歌巻」の宗達の印章の「伊年」は、宗達が主宰する「俵屋工房」(宗達を中心とする絵師・工匠等のグルーブ)の「ブランド」(他と区別できる特徴を持ち価値の高い製品)に押される印章と解せられているが、それと同じように、「法橋宗達」「宗達法橋」の署名も、「ブランド」(「俵屋工房・宗達工房」の「商標」)化されており、杓子定規に、「伊年」=「俵屋(宗達)工房」、「法橋宗達・宗達法橋」=「宗達」と、それらの物差しをもって、それらの区別をすることは甚だ危険なことなのであろう。
それよりも、当時の超一流のアートディレクター兼書家の「本阿弥宗達」の「書」と、超一流の「絵屋」主宰者兼絵師の「俵屋宗達」(下絵)との、その「コラボレーション」(合作・共同作業)の作品は、両者の、丁々発止とする個人作業の多い、いわゆる、「俵屋宗達画・本阿弥光悦書」とする方が、より分かり易い目安になるのかも知れない。(以下略)
(追記メモ)
この「四季草花下絵古今集和歌巻(四季花卉下絵古今集和歌巻)」(光悦書・宗達画)の「躑躅」など、両者の「コラボレーション」(合作・共同作業)の作品には、例えば、宗達の傑作画の「風神雷神図」の「風神」の衣装(下紐)などに施された「朱色」系統のものは目にしない。これは、両者の「コラボレーション」の作品として、「画」は下絵に徹して、「書」がメインであることの配慮のように思われる。
「朱夏」に相応しい鮮やかな「朱」の躑躅が、宗達・光悦に私淑した光琳が見事に実写している。こちらは、朱の椿(メイン)と白の椿(サブ)との対比で、流水を挟んで、土坡は褐色で「大きな土坡」(メイン)と「小さな土坡」(サブ)が対比している。
https://www.ebara.co.jp/csr/hatakeyama/colle008.html

重要文化財 躑躅図 尾形光琳筆 (畠山記念館蔵)
【年代:江戸時代
材質・技法:絹本著色
サイズ(cm):縦39.3 横60.7
「たらし込み」で描かれた土坡と流水のほとりに、鮮やかな紅色の躑躅が空に向かって枝を伸ばす。その手前に、白い躑躅がひっそりと咲く姿が、また対照的で美しい。流水を挟んで左右に大小の土坡も配しており、本図は小品ながらも、このような形や色彩の対比が見事に計算されている。まるで箱庭でもみるかのようにすべてが縮小された作品には、洗練された意匠感覚が反映されている。作者の尾形光琳(1658~1716)は江戸時代中期に絵師として活躍した。 】

「尾形光琳生誕三五〇周年記念 大琳派展―継承と変奏(東京国立博物館・読売新聞社編)」
所収「1-01 俵屋宗達下絵・本阿弥光悦筆 四季草花下絵古今和歌巻・重要文化財・畠山記念館蔵」(「四季花卉下絵古今集和歌巻」=『光悦……琳派の創始者(河野元昭編)』所収「書画の二重奏への道……光悦書・宗達画和歌巻の展開(玉蟲敏子稿)」) 三三・七×九一八・七
寛平の御時に、うへのさぶらひに侍りけるをのこども、
かめをもたせてきさいの宮の御方に大御酒のおろしと
きこえにたてまつりたりけるを、蔵人ども笑ひて、
かめをおまへにもていでてともかくもいはずなりにければ、
つかひのかへりきて、さなむありつるといひければ、
蔵人のなかにおくりける
874 玉だれのこがめやいづらこよろぎの磯の浪わけ沖にいでにけり(藤原敏行 )
(あの小亀はどこへいったやら、こよろぎの磯の浪を分けて沖に出ていってしまったよ。)
女どもの見て笑ひければよめる
875 かたちこそみ山隠れの朽ち木なれ心は花になさばなりなむ(兼芸法師)
(見た目こそ山奥の朽木のようではあるが、心は花にしようと思えばいつでも花を咲かせられますよ。)
釈文(揮毫上の書体)=(『書道芸術第十八巻 本阿弥光悦』)
874玉だ連(れ)能(の)こ可(が)めやい徒(づ)らこよろ支(ぎ)能(の)い曾(そ)濃(の)波王(わ)遺(け)於(お)き尓(に)出(いで)尓(に)介(け)利(り)
※玉だ連(れ)能(の)=玉だれの。「子」の枕詞として用いる。
※こよろ支(ぎ)能(の)=こよろぎ。いまの神奈川県大磯市あたりの海岸。
※於(お)き尓(に)出(いで)尓(に)介(け)利(り)=おきにいでけり。「沖」に「奥=皇后宮の御前」の意を掛ける。
※※寛平の御時に=宇多天皇の御時。
※※うへのさぶらひに侍りけるをのこども=清涼殿の殿上の間に侍っていた侍臣たち。
※※きさいの宮=后宮。皇后藤原温子。
※※蔵人=女蔵人(下臈の女房)。
875形(かたち)こ曾(そ)深山(みやま)隠(がくれ)濃(の)朽木(くちき)那(な)禮(れ)心盤(は)華(はな)尓(に)な左(さ)ハ(ば)成(なり)南(なむ)
※形(かたち)こ曾(そ)=かたちこそ。顔かたち。容貌。
※深山(みやま)隠(がくれ)濃(の)朽木(くちき)那(な)禮(れ)=深山隠れの朽ち木なれ。奥山に隠れている朽ち木のようなものですが。
http://www.asahi-net.or.jp/~SG2H-YMST/yamatouta/sennin/tosiyuki.html
【 藤原敏行(ふじわらのとしゆき) 生年未詳~延喜元(?-901)
陸奥出羽按察使であった南家富士麿の長男。母は紀名虎の娘。紀有常の娘(在原業平室の姉妹)を妻とする。子には歌人で参議に到った伊衡などがいる。
貞観八年(866)、少内記。地方官や右近少将を経て、寛平七年(895)、蔵人頭。同九年、従四位上右兵衛督。『古今集和歌目録』に「延喜七年卒。家伝云、昌泰四年卒」とある(昌泰四年は昌泰三年=延喜元年の誤りか)。
三十六歌仙の一人。能書家としても名高い。古今集に十九首、後撰集に四首採られ、勅撰集入集は計二十九首。三十六人集の一巻として家集『敏行集』が伝存する。一世代前の六歌仙歌人たちにくらべ、技巧性を増しながら繊細流麗、かつ清新な感覚がある。和歌史的には、まさに業平から貫之への橋渡しをしたような歌人である。 】
https://www.asahi-net.or.jp/~SG2H-ymst/yamatouta/sennin/kengei.html
【 兼芸法師=兼藝(けんげい(けむげい)) 生没年未詳
『古今和歌集目録』によれば伊勢少掾古之の二男で、大和国城上郡の人かという。左大臣源融の孫占の子とも。即位以前の光孝天皇と親しかったことを窺わせる歌を古今集に残している(巻八離別歌)。勅撰入集は古今集のみ四首。 】
これらの歌(藤原敏行と兼芸法師の二首)は、『古今集(巻第十四・恋歌四)の、次の在原業平の歌と関係があるようである。
藤原の敏行の朝臣の、業平の朝臣の家なりける女を
あひ知りてふみつかはせりけることばに、いままうでく、
あめの降りけるをなむ見わづらひ侍る、といへりけるを聞きて、
かの女にかはりてよめりける
705 かずかずに思ひ思はずとひがたみ身を知る雨は降りぞまされる(在原業平)
(いろいろと、貴方と私の間は、相思相愛の間柄なのかと思い悩んだりしていますが、貴方に直接聞くわけにもいかず、この雨に聞けば、この雨の降り様は、「そうではない」と告げているようです。)
そして、これまた、『伊勢物語(第一〇七段)』に由来があるような雰囲気である。
http://teppou13.fc2web.com/hana/narihira/ise/old/ise_o107.html
【むかし、あてなる男ありけり。その男のもとなりける人を、内記にありける藤原の敏行といふ人よばひけり。されど若ければ、文もをさをさしからず、言葉もいひ知らず、いはんや歌はよまざりければ、かのあれじなる人、案を書きてかゝせてやりけり。めでまどひにけり。さて男のよめる、
つれづれのながめにまさる涙川
袖のみひぢて逢ふよしもなし
かへし、れいの男、女にかはりて、
浅みこそ袖はひづらめ涙川
身さへながると聞かばたのまむ
といへりければ、男いといたうめでて、いままでまきて文箱に入れてありとなむいふなる。 男文おこせたり。えてのちの事なりけり。「雨の降りぬべきになむ見わづらひ侍る。身さいはひあらば、この雨は降らじ」といへりければ、例の男、女に代りてよみてやらす。
かずかずに思ひ思はず問ひがたみ
身をしる雨は降りぞまされる
とよみてやれりければ、蓑も笠もとりあへで、しとゞに濡れてまどひきにけり。】(『伊勢物語(第一〇七段)』)
(参考) 「四季花卉下絵古今集和歌巻」(「その一~その三」「その四~その六」)
「四季草花下絵古今和歌巻」(その一・その二・その三)
「四季草花下絵古今和歌巻」(その四・その五・その六)
上記の「その一」は「竹」図(冬)、「その二・その三・その三・その四」は「梅(春)」図、そして、「その四」は「土坡(梅から椿)」(春から夏)への「季移り」(「季節の替わり」・「連歌・連句で、雑(ぞう)の句をはさまず、ある季の句に直ちに他の季の句を付けること」の「雑」の場面、「その一」と「その「二」は「季移り」)の図柄の雰囲気である。
今回の「その六」(躑躅と糸薄)は、全体に「躑躅」(夏)の景物で、中ほどに、直接の「季移り」を避ける「雑」(間を取る)のような「土坡」を上部に描いて(「その五」の土坡は下部)、その次に「躑躅」の根本に「糸薄」(秋)を添えている図柄のようである。
この「その六」の関連については、次のアドレスで触れている。画像は省略して、その紹介記事や、そのアドレスでの「光悦と宗達」周辺のことを再掲して置きたい。
https://yahan.blog.ss-blog.jp/2018-07-11
(再掲)
(画像省略=上掲の「その六」冒頭の図と「その一」の「竹」部分図)
俵屋宗達画・本阿弥光悦書「四季草花下絵和歌巻」(部分図=躑躅) 紙本金銀泥
三三・五×九一八・七㎝ 重要文化財 畠山記念館蔵
【 太い竹の幹のクローズアップから始まり、巻物を操るに従って、梅・躑躅(つつじ)・蔦(つた)が現れる。それぞれ、正月・春・夏・秋の四季の移り変わりを表わす。竹の表面は「たらし込み」の技法で質感が表現されている。宗達は以前、版画による料紙装飾で同様の竹をモティーフとしたが、版木を離すときに生じる金泥のムラの効果を、筆で描くときにも応用した。巻末に光悦の印章と、宗達の「伊年」の印章がある。 】(『日本の美をめぐる 奇跡の出会い 宗達と光悦(小学館)』)
「本阿弥光悦」の「本阿弥」家は、刀剣の「磨ぎ・浄拭(ぬぐい)・鑑定(めきき)」を専門とする家柄である。そもそも、「本阿弥」の「阿弥」というのは、将軍家に仕えて芸能や美術などの特殊技能をつかさどった「同朋衆」が名のることが多かった。室町時代に活躍した「能阿弥・芸阿弥・相阿弥」など三阿弥と呼ばれる同朋たちは、足利将軍家で儀式の飾りつけのコーディネートや美術品の鑑定・管理などをこなし、新たな美術品を注文する際に意見を求められた家柄である。
その「同朋衆」の出の「本阿弥光悦」は、元和元年(一六一五)に徳川家康より鷹ケ峰(洛北)に広大な土地を与えられ、ここに様々な工芸に携わる職人たちと移り住んで芸術村を形成し、日本で最初の「アートディレクター」(総合芸術の演出家)兼「書家」(「寛永三筆」の一人)兼「蒔絵師」兼「陶工師」などの、当時の超一流の文化人ということになる。
もう一人の「俵屋宗達」は、光悦と縁戚関係にあるとも、本阿弥家と同じ小川町(上京区)の「蓮池家・喜多川家」出の「絵屋」(「俵屋」という屋号で「絵屋」=「屛風・掛幅のほか料紙装飾・扇絵・貝絵など、主に仕込み絵的な一種の既製品を制作・販売する」)を主宰していたともいわれているが、絵師としても法橋を授与されており、これまた、当時の超一流の文化人の一人であったのであろう。
ここで、この「四季草花下絵和歌巻」の宗達の印章の「伊年」は、宗達が主宰する「俵屋工房」(宗達を中心とする絵師・工匠等のグルーブ)の「ブランド」(他と区別できる特徴を持ち価値の高い製品)に押される印章と解せられているが、それと同じように、「法橋宗達」「宗達法橋」の署名も、「ブランド」(「俵屋工房・宗達工房」の「商標」)化されており、杓子定規に、「伊年」=「俵屋(宗達)工房」、「法橋宗達・宗達法橋」=「宗達」と、それらの物差しをもって、それらの区別をすることは甚だ危険なことなのであろう。
それよりも、当時の超一流のアートディレクター兼書家の「本阿弥宗達」の「書」と、超一流の「絵屋」主宰者兼絵師の「俵屋宗達」(下絵)との、その「コラボレーション」(合作・共同作業)の作品は、両者の、丁々発止とする個人作業の多い、いわゆる、「俵屋宗達画・本阿弥光悦書」とする方が、より分かり易い目安になるのかも知れない。(以下略)
(追記メモ)
この「四季草花下絵古今集和歌巻(四季花卉下絵古今集和歌巻)」(光悦書・宗達画)の「躑躅」など、両者の「コラボレーション」(合作・共同作業)の作品には、例えば、宗達の傑作画の「風神雷神図」の「風神」の衣装(下紐)などに施された「朱色」系統のものは目にしない。これは、両者の「コラボレーション」の作品として、「画」は下絵に徹して、「書」がメインであることの配慮のように思われる。
「朱夏」に相応しい鮮やかな「朱」の躑躅が、宗達・光悦に私淑した光琳が見事に実写している。こちらは、朱の椿(メイン)と白の椿(サブ)との対比で、流水を挟んで、土坡は褐色で「大きな土坡」(メイン)と「小さな土坡」(サブ)が対比している。
https://www.ebara.co.jp/csr/hatakeyama/colle008.html

重要文化財 躑躅図 尾形光琳筆 (畠山記念館蔵)
【年代:江戸時代
材質・技法:絹本著色
サイズ(cm):縦39.3 横60.7
「たらし込み」で描かれた土坡と流水のほとりに、鮮やかな紅色の躑躅が空に向かって枝を伸ばす。その手前に、白い躑躅がひっそりと咲く姿が、また対照的で美しい。流水を挟んで左右に大小の土坡も配しており、本図は小品ながらも、このような形や色彩の対比が見事に計算されている。まるで箱庭でもみるかのようにすべてが縮小された作品には、洗練された意匠感覚が反映されている。作者の尾形光琳(1658~1716)は江戸時代中期に絵師として活躍した。 】
四季花卉下絵古今集和歌巻(その五) [光悦・宗達・素庵]
その五 梅(その四)

「尾形光琳生誕三五〇周年記念 大琳派展―継承と変奏(東京国立博物館・読売新聞社編)」
所収「1-01 俵屋宗達下絵・本阿弥光悦筆 四季草花下絵古今和歌巻・重要文化財・畠山記念館蔵」(「四季花卉下絵古今集和歌巻」=『光悦……琳派の創始者(河野元昭編)』所収「書画の二重奏への道……光悦書・宗達画和歌巻の展開(玉蟲敏子稿)」) 三三・七×九一八・七
五節の舞姫を見てよめる
872 天つ風雲のかよひぢ吹きとぢよ乙女の姿しばしとどめむ(良岑宗貞 )
(空を吹く風よ、雲の通い路を吹き閉じてくれ。そして、空に帰る乙女たちの姿を今しばらく留めておきたいのだ。)
五節のあしたに簪の玉の落ちたりけるを見て、
誰がならむととぶらひてよめる
873 主や誰問へど白玉言はなくにさらばなべてやあはれと思はむ(河原左大臣)
(誰のものかと聞いても簪の白玉は何も言わない。それ故に、誰とかは特定せずに、五節の舞女全員が愛らしく思えるのだ。)
釈文(揮毫上の書体)=(『書道芸術第十八巻 本阿弥光悦』)
872 安(あ)ま徒(つ)可(か)世(ぜ)雲濃(の)通路(かよひぢ)吹(ふき)きと知(ぢ)よをとめ能(の)姿しハ(ば)しと々(ど)免無(めむ)
※安(あ)ま徒(つ)可(か)世(ぜ)=天つ風。天空を吹き渡る風。乙女が舞う宮廷の庭を天上になぞらえているために、そこを吹く風を「天つ風」と言っている。
※雲濃(の)通路(かよひぢ)=雲の通ひ路。天空の通り路。「殿上をば雲の上と云へば、そのおりのぼる道を雲のかよひぢとは云也」(『顕註密勘抄』)。
※吹(ふき)きと知(ぢ)よ=「天つ風」に対し、「雲をたくさん吹き寄せて、天の通り道を塞いでしまえ」と願っている。
※をとめ=乙女。五節の舞姫のこと。
※※五節(ごせち)=新嘗祭の翌日(十一月の中の辰の日)、豊明(とよのあかり)の節会に際して舞われた少女楽。公卿・国司の娘より美しい少女を四、五名選んで舞姫に召した。
873 ぬしやた連(れ)問(とへ)ど白玉以(い)者(は)那(な)久(く)尓(に)左(さ)ら半(ば)なべ天(て)や阿(あ)ハ(は)連(れ)と於(お)もハ(は)無(む)
※ぬしやた連(れ)=主(持ち主)や誰。白玉に対して問いかけている。
※以(い)者(は)那(な)久(く)尓(に)=言わないのに。「でも、それなら私はこう思おう」と続く文脈。
※左(さ)ら半(ば)なべ天(て)=さらば(それなら)なべて(すべて)。
※※とぶらひて=訪ねて。
https://www.asahi-net.or.jp/~sg2h-ymst/yamatouta/sennin/henjou.html
良岑宗貞(よしみねのむねさだ)→遍昭(へんじょう)
【遍昭(へんじょう) 弘仁七~寛平二(816-890) 俗名:良岑宗貞 号:花山僧正
桓武天皇の孫。大納言良岑朝臣安世の八男。素性法師は在俗時にもうけた息子。名は遍照とも書かれる。
承和十二年(845)、従五位下に叙せられ、左兵衛佐となる。蔵人・左近少将等を経て、嘉祥二年(849)、蔵人頭の要職に就く。翌三年正月、従五位上に叙されたが、同年三月二十一日、寵遇を受けた仁明天皇が崩御すると、装束司の任を果たさず出家した。この時三十五歳。比叡山に入り、慈覚大師円仁より菩薩戒を受け、台密の修行に励む。貞観十年(868)に創建された花山寺(元慶寺)の座主となる。また、貞観十一年(869)に仁明天皇の皇子常康親王より譲り受けた雲林院をその別院とした。元慶三年(879)、権僧正。仁和元年(885)十月、僧正。同年十二月、七十の賀を光孝天皇より受ける。寛平二年正月十九日、七十五歳で死去。花山(かざん)僧正の称がある。
六歌仙・三十六歌仙。後世の他撰家集『遍昭集』がある。惟喬親王や小野小町と歌を贈答している。古今集に十七首、勅撰集入集歌は計三十六首(連歌一首含む)。】
https://www.asahi-net.or.jp/~sg2h-ymst/yamatouta/sennin/tohoru.html
河原左大臣(河原の左のおほいまうちの君=かわらのさだいじん)→源融(みなもとのとおる)
【源融(みなもとのとおる) 弘仁一三~寛平七(822-895) 号:河原左大臣
嵯峨天皇の皇子。母は大原全子。子に大納言昇ほか。子孫に安法法師がいる。系図
臣籍に下って侍従・右衛門督などを歴任、貞観十四年(872)、五十一歳で左大臣にのぼった。元慶八年(884)、陽成天皇譲位の際には、新帝擁立をめぐって藤原基経と争い、自らを皇位継承候補に擬した(『大鏡』)。仁和三年(887)、従一位。寛平七年(895)八月二十五日、薨去。七十四歳。贈正一位。河原院と呼ばれた邸宅は庭園に海水を運び入れて陸奥の名所塩釜を模すなど、その暮らしぶりは豪奢を極めたという。また宇治に有した別荘は、その後変遷を経て現在の平等院となる。古今集・後撰集に各二首の歌を残す。】
(参考) 「四季花卉下絵古今集和歌巻」(「その一~その三」「その四~その六」)
「四季草花下絵古今和歌巻」(その一・その二・その三)

「「四季草花下絵古今和歌巻」(その四・その五・その六)

これまでの、「その一、その二、その三/その四」と今回(「その五」)の歌(863~873、865は欠番)と関連する『伊勢物語』の歌(と※※※)一首は、次のとおりである。
(その一)
863 わが上に露ぞ置くなる天の川とわたる舟のかいのしずくか(読人知らず)
864 思ふどちまどゐせる夜は唐錦たたまく惜しきものにぞありける(読人知らず)
865 (省略されている。)
(その二)
866 限りなき君がためにと折る花は時しもわかぬ物にぞありける(読人知らず)
867 紫のひともとゆゑに武蔵野の草はみながらあはれとぞ見る(読人知らず)
(その三)
※868 紫の色こき時は目もはるに野なる草木ぞわかれざりける(※業平朝臣)
869 色なしと人や見るらむ昔より深き心に染めてしものを(近院右大臣)
(その四)
870 日の光の藪しわかねば石上(いそのかみ) ふりにし里に花も咲きけり(布留今道)
※二条のきさきのまだ東宮の御息所と申しける時に、
大原野にまうでたまひける日よめる
※871 大原や小塩(をしほ)の山も今日こそは神世のことも思ひいづらめ(※在原業平)
※※※白玉かなにぞと人の問ひし時露とこたへて消えなましものを(『伊勢物語』第6段)
(その五)
872 天つ風雲のかよひぢ吹きとぢよ※乙女の姿しばしとどめむ(良岑宗貞 )
873 主や誰問へど※※白玉言はなくにさらばなべてやあはれと思はむ(河原左大臣)
ここで、今回の「873 主や誰問へど※※白玉言はなくにさらばなべてやあはれと思はむ(河原左大臣)」の、この「※※白玉」は、「『伊勢物語』第6段(芥川)」の「※※※ 白玉かなにぞと人の問ひし時露とこたへて消えなましものを」の「※※※白玉」と、同じ意図を持ったもので、その主題は、「五節の舞姫」の「簪の白玉」ということになろう。
そして、それは同時に、『伊勢物語』の主人公(※在原業平、この『古今集』の「868・871」の作者)と「五節の舞姫」の一人であった「※二条の后(后となる以前の乙女の頃)」との、その「恋物語(ラブストーリー・ロマンス)」を背景にしているものと理解をしたい。
『伊勢物語』での、この「恋物語(ラブストーリー・ロマンス)」は、主として次の段(第3段~第9段、第76段)などにその背景が書かれているが、第1段(初冠)、第65段(御手洗川)、第69段(伊勢の斎宮)そして第125段(終章)も付記して置きたい。
http://teppou13.fc2web.com/hana/narihira/ise_story.html
※第1段 初冠(春日野の若紫の摺衣(しのぶずり)しのぶの乱れかぎり知られず)
第3段 ひじき藻(思ひあらば葎の宿にねもしなむひじきのものには袖をしつゝも)
第4段 西の対(月やあらぬ春や昔の春ならぬわが身は一つもとの身にして)
第5段 関守(人知れぬわが通ひ路の関守は宵々ごとにうちも寝ななむ)
※※※第6段 芥川(白玉かなにぞと人の問ひし時露とこたへて消えなましものを)
第7段 東下り(伊勢・尾張)(いとゞしく過ぎ行く方の恋しきにらやましくもかへる浪かな)
第8段 東下り(信濃)(信濃なる浅間の嶽にたつ煙をちこち人の見やはとがめぬ)
第9段 東下り(八橋)(唐衣きつゝ馴にしつましあればはるばる来ぬる旅をしぞ思ふ)
同(宇津)(駿河なる宇津の山辺のうゝにも夢にも人に逢はぬなりけり)
同(富士)(時しらぬ山は富士の嶺いつとてか鹿の子まだらに雪の降るらむ)
同(隅田川)(名にしおはゞいざこと問は都鳥むわが思ふ人はありやなしやと)
※第65段 御手洗川(恋せじと御手洗川にせしみそぎ神はうけずもなりにけるかな)
※第69段 伊勢の斎宮(かち人の渡れどぬれぬ江にしあれば/またあふさかの関は越えなむ
第76段 小塩の山(大原やをしほの山も今日こそは神代のことも思ひいづらめ)
(※※871 大原や小塩(をしほ)の山も今日こそは神世のことも思ひいづらめ(※※在原業平『古今集』))
※第125段 終章(つひにゆく道とはかねて聞きしかどきのふけふとは思はざりしを)
ここまで来ると、前回の『伊勢物語・第七段(芥川)』=「伊勢物語図色紙・芥川:伝俵屋宗達筆」に続くものとしては、次の「蔦の細道図屏風」(書=烏丸光広、画=伝俵屋宗達、萬野美術館旧蔵→相国寺承天閣美術館蔵)ということになろう。

俵屋宗達派「蔦の細道図屏風」(「伊年」印) 右隻 十七世紀後半 六曲一双
各一五八・〇×三五八・四㎝ 萬野美術館旧蔵 紙本金地着色 重要文化財

俵屋宗達派「蔦の細道図屏風」(「伊年」印) 左隻 十七世紀後半 六曲一双
各一五八・〇×三五八・四㎝ 萬野美術館旧蔵 紙本金地着色 重要文化財
これらについては、下記のアドレスで触れている。その「作品解説(山根有三稿)」を全文掲載して置きたい。
(再掲)
https://yahan.blog.ss-blog.jp/2018-07-22
【 六曲一双の金地屏風に、緑青一色の濃淡だけで蔦の葉と土坡を描いたもの。上部に書かれた烏丸光広の賛から『伊勢物語』第八段に出てくる蔦かずらの生い茂った宇津の山の細道であることがわかる。話の筋は、東に行けばなにかよいことがあるだろうと、都をあとにした男が途中三河の八ツ橋を渡り、駿河の宇津の山の細道を抜け、富士の山を眺めつつ、やっとの思いで東についたが、隅田川に遊ぶ鳥が都(みやこ)鳥であると聞き、有名な「名にし負はば……」を歌を詠み、都に思いをはせる、という一種の旅日記である。この蔦の細道は、原文では、「いと暗う細きに、つたかえでは茂り、物心ぼそく……」とあって、暗く心細いことが都への郷愁をいっそうかきたてる心理的に重要なくだりであるが、この屏風ではそんなことは頓着なく、すっきりと明るく仕上げている。『伊勢物語』のくだりは、発想のための一起点にすぎず、画家の心は金と緑青のあやなす夢幻の世界を快げに飛びかっている。
それにつけても大胆、かつ斬新な構図である。屏風の大画面を左から右へゆるやかに流れる三本の線、おそらく中央の蔦を描いた細い帯は、山あいを走る蔦の細道の象徴的な表現であろう。この蔦を除いて、あとは三本の線で区切られた抽象的な面の響き合いによる構成である。
では、この屏風は宗達の作であろうか。結論からいえば宗達ではないと私は考えている。理由の第一は、空間処理の感覚が宗達とは異質のものである。宗達の画面に描かれたものは、必ず二次元の平面的な位置だけではなく、三次元の前後関係における位置もしっかりと定められている。つまり広がりと奥行が綿密な計算のうえに、きわめて整然と画面のなかに組み立てられているのである。しかるにこの屏風では、三次元的な前後関係はいっさい無視して、平面におけるパターンの効果とおもしろ味をねらっている。もちろん蔦の葉の重なりには、おのずから前後ん゛描かれているが、この蔦全体の属する空間の位どりが゜は、はっきりしておらず、そのため土坡らしき緑青(補彩が多い)の面と、賛の書かれた金地の空間との関係も明確にされていない。しかし、それは技及ばずして描きえなかったのではなく、初めその意図がなかったとみるべきであろう。
古くより、宗達でなければこれほどのものは描けまいとする説があるが、もし宗達に共通点を求めるならば、金銀泥絵巻物の世界であろう。たしかに、上下よりも左右への広がりを見せるこの屏風は、巻物的な構図をしており、技法も金銀泥絵的といえる。また名士烏丸光広の賛があることからみて、宗達が金銀泥絵巻物を媒体にして、直接または間接に影響を与えた可能性は考えられる。
宗達の作でないとする第二の理由は、その金銀泥絵巻物に関連する蔦の葉の描法である。宗達の「四季草花図」和歌巻(注・(その四)俵屋宗達画・本阿弥光悦書「四季草花下絵和歌巻」=https://yahan.blog.so-net.ne.jp/2018-07-11)の巻末に、一面蔦の葉ばかりを描いた場面があるが、濃淡による葉の重なり、葉の配置による奥行の深さなどにおいて、この屏風より一段まさっている。同一画家の出来・不出来であることに異論はない。なお光広とされる賛は次のとおり。
行さきもつたのした道しけるより
花は昨日のあとのやまふみ
夏山のしつくを見えは青葉もや
今一入(ひとしお)のつたのしたみち
宇津の山蔦の青葉のしけりつゝ
ゆめにもうとき花の面影
書もあへすみやこに送る玉章(たまずさ)よ
いてことつてむひとはいつらは
あとつけていくらの人のかよふらん
ちよもかはらぬ蔦の細道
茂りてそむむかしの跡も残りける
たとらはたとれ蔦のほそ道
ゆかて見る宇津の山辺はうつしゑの
まことわすれて夢かとそおもふ 】
(『原色日本の美術14宗達と光琳(小学館)』所収「作品57「『蔦の細道図(山根有三稿)』」)
(追記メモ) 「蔦の細道図屏風」(書=烏丸光広、画=伝俵屋宗達、萬野美術館旧蔵→相国寺承天閣美術館蔵)周辺
↓
(『ウィキペディア(Wikipedia)』)
承天閣美術館(じょうてんかくびじゅつかん)は、京都府京都市上京区の相国寺境内にある美術館。
相国寺創建600年記念事業の一環として1984年に開館した。相国寺および臨済宗相国寺派に属する鹿苑寺(金閣寺)や慈照寺(銀閣寺)などが所有する墨蹟・絵画・工芸品等の文化財(国宝 2件(5点)[1]と国の重要文化財多数を含む)を収蔵・展示している。2004年には同年閉館した萬野美術館(大阪市)から国宝・重要文化財を含む約200点の美術品が寄贈された。
『形成される教養 十七世紀日本の<知>(鈴木健一編・勉誠出版)』所収「烏丸光広の画賛(田代一葉稿)」
↓
蔦の細道図屏風(絵師・画者:俵屋宗達)
(左隻)
行さきもつたのした道しげるより花は昨日のあとのやまふみ
夏山のしづくをみえは青葉もや今一入(ひとしお)のつたのしたみち
宇津の山蔦の青葉のしげりつゝゆめにもうとき花の面影
書もあへずみやこに送る玉章(たまずさ)よいでことづてむひとはいづらば
あとつけていくらの人のかよふらんち世もかはらぬ蔦の細道
(右隻)
茂りてぞむかしの跡も残りけるたどらばたどれ蔦のほそ道
ゆかで見る宇津の山辺はうつしゑのまことわすれて夢かとぞおもふ

「尾形光琳生誕三五〇周年記念 大琳派展―継承と変奏(東京国立博物館・読売新聞社編)」
所収「1-01 俵屋宗達下絵・本阿弥光悦筆 四季草花下絵古今和歌巻・重要文化財・畠山記念館蔵」(「四季花卉下絵古今集和歌巻」=『光悦……琳派の創始者(河野元昭編)』所収「書画の二重奏への道……光悦書・宗達画和歌巻の展開(玉蟲敏子稿)」) 三三・七×九一八・七
五節の舞姫を見てよめる
872 天つ風雲のかよひぢ吹きとぢよ乙女の姿しばしとどめむ(良岑宗貞 )
(空を吹く風よ、雲の通い路を吹き閉じてくれ。そして、空に帰る乙女たちの姿を今しばらく留めておきたいのだ。)
五節のあしたに簪の玉の落ちたりけるを見て、
誰がならむととぶらひてよめる
873 主や誰問へど白玉言はなくにさらばなべてやあはれと思はむ(河原左大臣)
(誰のものかと聞いても簪の白玉は何も言わない。それ故に、誰とかは特定せずに、五節の舞女全員が愛らしく思えるのだ。)
釈文(揮毫上の書体)=(『書道芸術第十八巻 本阿弥光悦』)
872 安(あ)ま徒(つ)可(か)世(ぜ)雲濃(の)通路(かよひぢ)吹(ふき)きと知(ぢ)よをとめ能(の)姿しハ(ば)しと々(ど)免無(めむ)
※安(あ)ま徒(つ)可(か)世(ぜ)=天つ風。天空を吹き渡る風。乙女が舞う宮廷の庭を天上になぞらえているために、そこを吹く風を「天つ風」と言っている。
※雲濃(の)通路(かよひぢ)=雲の通ひ路。天空の通り路。「殿上をば雲の上と云へば、そのおりのぼる道を雲のかよひぢとは云也」(『顕註密勘抄』)。
※吹(ふき)きと知(ぢ)よ=「天つ風」に対し、「雲をたくさん吹き寄せて、天の通り道を塞いでしまえ」と願っている。
※をとめ=乙女。五節の舞姫のこと。
※※五節(ごせち)=新嘗祭の翌日(十一月の中の辰の日)、豊明(とよのあかり)の節会に際して舞われた少女楽。公卿・国司の娘より美しい少女を四、五名選んで舞姫に召した。
873 ぬしやた連(れ)問(とへ)ど白玉以(い)者(は)那(な)久(く)尓(に)左(さ)ら半(ば)なべ天(て)や阿(あ)ハ(は)連(れ)と於(お)もハ(は)無(む)
※ぬしやた連(れ)=主(持ち主)や誰。白玉に対して問いかけている。
※以(い)者(は)那(な)久(く)尓(に)=言わないのに。「でも、それなら私はこう思おう」と続く文脈。
※左(さ)ら半(ば)なべ天(て)=さらば(それなら)なべて(すべて)。
※※とぶらひて=訪ねて。
https://www.asahi-net.or.jp/~sg2h-ymst/yamatouta/sennin/henjou.html
良岑宗貞(よしみねのむねさだ)→遍昭(へんじょう)
【遍昭(へんじょう) 弘仁七~寛平二(816-890) 俗名:良岑宗貞 号:花山僧正
桓武天皇の孫。大納言良岑朝臣安世の八男。素性法師は在俗時にもうけた息子。名は遍照とも書かれる。
承和十二年(845)、従五位下に叙せられ、左兵衛佐となる。蔵人・左近少将等を経て、嘉祥二年(849)、蔵人頭の要職に就く。翌三年正月、従五位上に叙されたが、同年三月二十一日、寵遇を受けた仁明天皇が崩御すると、装束司の任を果たさず出家した。この時三十五歳。比叡山に入り、慈覚大師円仁より菩薩戒を受け、台密の修行に励む。貞観十年(868)に創建された花山寺(元慶寺)の座主となる。また、貞観十一年(869)に仁明天皇の皇子常康親王より譲り受けた雲林院をその別院とした。元慶三年(879)、権僧正。仁和元年(885)十月、僧正。同年十二月、七十の賀を光孝天皇より受ける。寛平二年正月十九日、七十五歳で死去。花山(かざん)僧正の称がある。
六歌仙・三十六歌仙。後世の他撰家集『遍昭集』がある。惟喬親王や小野小町と歌を贈答している。古今集に十七首、勅撰集入集歌は計三十六首(連歌一首含む)。】
https://www.asahi-net.or.jp/~sg2h-ymst/yamatouta/sennin/tohoru.html
河原左大臣(河原の左のおほいまうちの君=かわらのさだいじん)→源融(みなもとのとおる)
【源融(みなもとのとおる) 弘仁一三~寛平七(822-895) 号:河原左大臣
嵯峨天皇の皇子。母は大原全子。子に大納言昇ほか。子孫に安法法師がいる。系図
臣籍に下って侍従・右衛門督などを歴任、貞観十四年(872)、五十一歳で左大臣にのぼった。元慶八年(884)、陽成天皇譲位の際には、新帝擁立をめぐって藤原基経と争い、自らを皇位継承候補に擬した(『大鏡』)。仁和三年(887)、従一位。寛平七年(895)八月二十五日、薨去。七十四歳。贈正一位。河原院と呼ばれた邸宅は庭園に海水を運び入れて陸奥の名所塩釜を模すなど、その暮らしぶりは豪奢を極めたという。また宇治に有した別荘は、その後変遷を経て現在の平等院となる。古今集・後撰集に各二首の歌を残す。】
(参考) 「四季花卉下絵古今集和歌巻」(「その一~その三」「その四~その六」)
「四季草花下絵古今和歌巻」(その一・その二・その三)
「「四季草花下絵古今和歌巻」(その四・その五・その六)
これまでの、「その一、その二、その三/その四」と今回(「その五」)の歌(863~873、865は欠番)と関連する『伊勢物語』の歌(と※※※)一首は、次のとおりである。
(その一)
863 わが上に露ぞ置くなる天の川とわたる舟のかいのしずくか(読人知らず)
864 思ふどちまどゐせる夜は唐錦たたまく惜しきものにぞありける(読人知らず)
865 (省略されている。)
(その二)
866 限りなき君がためにと折る花は時しもわかぬ物にぞありける(読人知らず)
867 紫のひともとゆゑに武蔵野の草はみながらあはれとぞ見る(読人知らず)
(その三)
※868 紫の色こき時は目もはるに野なる草木ぞわかれざりける(※業平朝臣)
869 色なしと人や見るらむ昔より深き心に染めてしものを(近院右大臣)
(その四)
870 日の光の藪しわかねば石上(いそのかみ) ふりにし里に花も咲きけり(布留今道)
※二条のきさきのまだ東宮の御息所と申しける時に、
大原野にまうでたまひける日よめる
※871 大原や小塩(をしほ)の山も今日こそは神世のことも思ひいづらめ(※在原業平)
※※※白玉かなにぞと人の問ひし時露とこたへて消えなましものを(『伊勢物語』第6段)
(その五)
872 天つ風雲のかよひぢ吹きとぢよ※乙女の姿しばしとどめむ(良岑宗貞 )
873 主や誰問へど※※白玉言はなくにさらばなべてやあはれと思はむ(河原左大臣)
ここで、今回の「873 主や誰問へど※※白玉言はなくにさらばなべてやあはれと思はむ(河原左大臣)」の、この「※※白玉」は、「『伊勢物語』第6段(芥川)」の「※※※ 白玉かなにぞと人の問ひし時露とこたへて消えなましものを」の「※※※白玉」と、同じ意図を持ったもので、その主題は、「五節の舞姫」の「簪の白玉」ということになろう。
そして、それは同時に、『伊勢物語』の主人公(※在原業平、この『古今集』の「868・871」の作者)と「五節の舞姫」の一人であった「※二条の后(后となる以前の乙女の頃)」との、その「恋物語(ラブストーリー・ロマンス)」を背景にしているものと理解をしたい。
『伊勢物語』での、この「恋物語(ラブストーリー・ロマンス)」は、主として次の段(第3段~第9段、第76段)などにその背景が書かれているが、第1段(初冠)、第65段(御手洗川)、第69段(伊勢の斎宮)そして第125段(終章)も付記して置きたい。
http://teppou13.fc2web.com/hana/narihira/ise_story.html
※第1段 初冠(春日野の若紫の摺衣(しのぶずり)しのぶの乱れかぎり知られず)
第3段 ひじき藻(思ひあらば葎の宿にねもしなむひじきのものには袖をしつゝも)
第4段 西の対(月やあらぬ春や昔の春ならぬわが身は一つもとの身にして)
第5段 関守(人知れぬわが通ひ路の関守は宵々ごとにうちも寝ななむ)
※※※第6段 芥川(白玉かなにぞと人の問ひし時露とこたへて消えなましものを)
第7段 東下り(伊勢・尾張)(いとゞしく過ぎ行く方の恋しきにらやましくもかへる浪かな)
第8段 東下り(信濃)(信濃なる浅間の嶽にたつ煙をちこち人の見やはとがめぬ)
第9段 東下り(八橋)(唐衣きつゝ馴にしつましあればはるばる来ぬる旅をしぞ思ふ)
同(宇津)(駿河なる宇津の山辺のうゝにも夢にも人に逢はぬなりけり)
同(富士)(時しらぬ山は富士の嶺いつとてか鹿の子まだらに雪の降るらむ)
同(隅田川)(名にしおはゞいざこと問は都鳥むわが思ふ人はありやなしやと)
※第65段 御手洗川(恋せじと御手洗川にせしみそぎ神はうけずもなりにけるかな)
※第69段 伊勢の斎宮(かち人の渡れどぬれぬ江にしあれば/またあふさかの関は越えなむ
第76段 小塩の山(大原やをしほの山も今日こそは神代のことも思ひいづらめ)
(※※871 大原や小塩(をしほ)の山も今日こそは神世のことも思ひいづらめ(※※在原業平『古今集』))
※第125段 終章(つひにゆく道とはかねて聞きしかどきのふけふとは思はざりしを)
ここまで来ると、前回の『伊勢物語・第七段(芥川)』=「伊勢物語図色紙・芥川:伝俵屋宗達筆」に続くものとしては、次の「蔦の細道図屏風」(書=烏丸光広、画=伝俵屋宗達、萬野美術館旧蔵→相国寺承天閣美術館蔵)ということになろう。

俵屋宗達派「蔦の細道図屏風」(「伊年」印) 右隻 十七世紀後半 六曲一双
各一五八・〇×三五八・四㎝ 萬野美術館旧蔵 紙本金地着色 重要文化財

俵屋宗達派「蔦の細道図屏風」(「伊年」印) 左隻 十七世紀後半 六曲一双
各一五八・〇×三五八・四㎝ 萬野美術館旧蔵 紙本金地着色 重要文化財
これらについては、下記のアドレスで触れている。その「作品解説(山根有三稿)」を全文掲載して置きたい。
(再掲)
https://yahan.blog.ss-blog.jp/2018-07-22
【 六曲一双の金地屏風に、緑青一色の濃淡だけで蔦の葉と土坡を描いたもの。上部に書かれた烏丸光広の賛から『伊勢物語』第八段に出てくる蔦かずらの生い茂った宇津の山の細道であることがわかる。話の筋は、東に行けばなにかよいことがあるだろうと、都をあとにした男が途中三河の八ツ橋を渡り、駿河の宇津の山の細道を抜け、富士の山を眺めつつ、やっとの思いで東についたが、隅田川に遊ぶ鳥が都(みやこ)鳥であると聞き、有名な「名にし負はば……」を歌を詠み、都に思いをはせる、という一種の旅日記である。この蔦の細道は、原文では、「いと暗う細きに、つたかえでは茂り、物心ぼそく……」とあって、暗く心細いことが都への郷愁をいっそうかきたてる心理的に重要なくだりであるが、この屏風ではそんなことは頓着なく、すっきりと明るく仕上げている。『伊勢物語』のくだりは、発想のための一起点にすぎず、画家の心は金と緑青のあやなす夢幻の世界を快げに飛びかっている。
それにつけても大胆、かつ斬新な構図である。屏風の大画面を左から右へゆるやかに流れる三本の線、おそらく中央の蔦を描いた細い帯は、山あいを走る蔦の細道の象徴的な表現であろう。この蔦を除いて、あとは三本の線で区切られた抽象的な面の響き合いによる構成である。
では、この屏風は宗達の作であろうか。結論からいえば宗達ではないと私は考えている。理由の第一は、空間処理の感覚が宗達とは異質のものである。宗達の画面に描かれたものは、必ず二次元の平面的な位置だけではなく、三次元の前後関係における位置もしっかりと定められている。つまり広がりと奥行が綿密な計算のうえに、きわめて整然と画面のなかに組み立てられているのである。しかるにこの屏風では、三次元的な前後関係はいっさい無視して、平面におけるパターンの効果とおもしろ味をねらっている。もちろん蔦の葉の重なりには、おのずから前後ん゛描かれているが、この蔦全体の属する空間の位どりが゜は、はっきりしておらず、そのため土坡らしき緑青(補彩が多い)の面と、賛の書かれた金地の空間との関係も明確にされていない。しかし、それは技及ばずして描きえなかったのではなく、初めその意図がなかったとみるべきであろう。
古くより、宗達でなければこれほどのものは描けまいとする説があるが、もし宗達に共通点を求めるならば、金銀泥絵巻物の世界であろう。たしかに、上下よりも左右への広がりを見せるこの屏風は、巻物的な構図をしており、技法も金銀泥絵的といえる。また名士烏丸光広の賛があることからみて、宗達が金銀泥絵巻物を媒体にして、直接または間接に影響を与えた可能性は考えられる。
宗達の作でないとする第二の理由は、その金銀泥絵巻物に関連する蔦の葉の描法である。宗達の「四季草花図」和歌巻(注・(その四)俵屋宗達画・本阿弥光悦書「四季草花下絵和歌巻」=https://yahan.blog.so-net.ne.jp/2018-07-11)の巻末に、一面蔦の葉ばかりを描いた場面があるが、濃淡による葉の重なり、葉の配置による奥行の深さなどにおいて、この屏風より一段まさっている。同一画家の出来・不出来であることに異論はない。なお光広とされる賛は次のとおり。
行さきもつたのした道しけるより
花は昨日のあとのやまふみ
夏山のしつくを見えは青葉もや
今一入(ひとしお)のつたのしたみち
宇津の山蔦の青葉のしけりつゝ
ゆめにもうとき花の面影
書もあへすみやこに送る玉章(たまずさ)よ
いてことつてむひとはいつらは
あとつけていくらの人のかよふらん
ちよもかはらぬ蔦の細道
茂りてそむむかしの跡も残りける
たとらはたとれ蔦のほそ道
ゆかて見る宇津の山辺はうつしゑの
まことわすれて夢かとそおもふ 】
(『原色日本の美術14宗達と光琳(小学館)』所収「作品57「『蔦の細道図(山根有三稿)』」)
(追記メモ) 「蔦の細道図屏風」(書=烏丸光広、画=伝俵屋宗達、萬野美術館旧蔵→相国寺承天閣美術館蔵)周辺
↓
(『ウィキペディア(Wikipedia)』)
承天閣美術館(じょうてんかくびじゅつかん)は、京都府京都市上京区の相国寺境内にある美術館。
相国寺創建600年記念事業の一環として1984年に開館した。相国寺および臨済宗相国寺派に属する鹿苑寺(金閣寺)や慈照寺(銀閣寺)などが所有する墨蹟・絵画・工芸品等の文化財(国宝 2件(5点)[1]と国の重要文化財多数を含む)を収蔵・展示している。2004年には同年閉館した萬野美術館(大阪市)から国宝・重要文化財を含む約200点の美術品が寄贈された。
『形成される教養 十七世紀日本の<知>(鈴木健一編・勉誠出版)』所収「烏丸光広の画賛(田代一葉稿)」
↓
蔦の細道図屏風(絵師・画者:俵屋宗達)
(左隻)
行さきもつたのした道しげるより花は昨日のあとのやまふみ
夏山のしづくをみえは青葉もや今一入(ひとしお)のつたのしたみち
宇津の山蔦の青葉のしげりつゝゆめにもうとき花の面影
書もあへずみやこに送る玉章(たまずさ)よいでことづてむひとはいづらば
あとつけていくらの人のかよふらんち世もかはらぬ蔦の細道
(右隻)
茂りてぞむかしの跡も残りけるたどらばたどれ蔦のほそ道
ゆかで見る宇津の山辺はうつしゑのまことわすれて夢かとぞおもふ
四季花卉下絵古今集和歌巻(その四) [光悦・宗達・素庵]
その四 梅(その三)
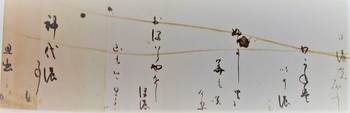
「尾形光琳生誕三五〇周年記念 大琳派展―継承と変奏(東京国立博物館・読売新聞社編)」
所収「1-01 俵屋宗達下絵・本阿弥光悦筆 四季草花下絵古今和歌巻・重要文化財・畠山記念館蔵」(「四季花卉下絵古今集和歌巻」=『光悦……琳派の創始者(河野元昭編)』所収「書画の二重奏への道……光悦書・宗達画和歌巻の展開(玉蟲敏子稿)」) 三三・七×九一八・七
いそのかみのなむまつが宮づかへもせで、
石上といふ所にこもり侍りけるを、
にはかにかうぶりたまはりければ、よろこび
いひつかはすとてよみてつかはしける
870 日の光の藪しわかねば石上(いそのかみ) ふりにし里に花も咲きけり(布留今道)
(日の光が籔も区別することなく照らすように、あまねく照らすお恵みにより、石上の古い里にも花が咲いた。)
二条のきさきのまだ東宮の御息所と申しける時に、
大原野にまうでたまひける日よめる
871 大原や小塩(をしほ)の山も今日こそは神世のことも思ひいづらめ(在原業平)
(大原の小塩山も今日こそは、神世のことも思い出すであろう。)
釈文(揮毫上の書体)=(『書道芸術第十八巻 本阿弥光悦』)
870 日濃(の)光屋(や)ぶしわ可(か)年(ね)盤(ば)以曾濃可三(いそのかみ)婦利(ふり)尓(に)し里尓(に)華も咲(さき)介梨(けり)
※わ可(か)年(ね)盤(ば)=分かねば。区別することなく。
※以曾濃可三(いそのかみ)=石上(いそのかみ)。天理市の石上神宮付近から西一帯。
※婦利(ふり)尓(に)し里=「古い里」と「布留の里」とを掛けている。古い都のあった「石上の布留の里」の意。)
※※いそのかみのなむまつ=石上並松(人名)。仁和二年(八八六)に従七位から従五位下に昇叙された。石上神宮に関わりのある人物か。
※※かうぶりたまはり=冠(かうぶり)賜り。位階を賜った。
871 お保(ほ)ハ(は)らやをしほ濃(の)山も今日こ曾(そ)ハ神代(かみよ)濃(の)事を思出(おもひいづ)らめ
※お保(ほ)ハ(は)らや=大原や。大原野神社。大和の春日神社を勧請したもので、京都市右京区にある。
※をしほ濃(の)山=小塩の山。大原野神社の背後の山。
※神代(かみよ)濃(の)事=藤原氏の祖神・天児屋命(あめのこやねのみこと)が皇祖・瓊瓊杵尊(ににぎのみこと)に従って天降りしたことを指しているか。
※※二条のきさき=二条の后。清和天皇の女御、藤原高子(たかいこ)。
http://www.asahi-net.or.jp/~sg2h-ymst/yamatouta/sennin/imamiti.html
【 布留今道(ふるのいまみち) 生没年未詳
布留氏は代々石上神宮の神主をつとめた家系。貞観三年(861)、内蔵少属。元慶六年(882)、従五位下。下野介などを経て、寛平十年(898)、三河介。古今集に三首を載せる。 】
http://www.asahi-net.or.jp/~SG2H-YMST/yamatouta/sennin/narihira.html
【 在原業平(ありわらのなりひら)=前掲=下記アドレス
https://yahan.blog.ss-blog.jp/2020-11-23 】

A図(『伊勢物語・第七段(芥川)』=「伊勢物語図色紙・芥川:伝俵屋宗達筆」)
(「尾形光琳生誕三五〇周年記念 大琳派展―継承と変奏(東京国立博物館・読売新聞社編)」出品目録1-53: 伝俵屋宗達筆 紙本着色 縦二四・六 横二〇 大和文華館蔵)
【むかし、男ありけり。女のえ得まじかりけるを、年を経てよばひわたりけるを、からうじて盗み出でて、いと暗きにきけり。芥河といふ河を率ていきければ、草のうへにおきたりける露を、「かれは何ぞ」となむ男に問ひける。ゆくさきおほく、夜もふけにければ、鬼ある所とも知らで、神さへいといみじう鳴り、雨もいたう降りければ、あばらなる蔵に、女をば奥におし入れて、男、弓、やなぐひを負ひて、戸口にをり。はや夜も明けなむと思ひつゝゐたりけるに、鬼一口に食ひてけり。 「あなや」といひけれど、神鳴る騒ぎにえ聞かざりけり。やうやう夜も明けゆくに、見れば、率て来し女もなし。足ずりをして泣けどもかひなし。
白玉かなにぞと人の問ひし時
露とこたへて消えなましものを
これは、二条の后の、いとこの女御の御もとに、仕うまつるやうにてゐ給へりけるを、かたちのいとめでたくおはしければ、盗みて負ひて出でたりけるを、御せうと堀河の大臣、太郎国経の大納言、まだ下臈にて内裏へまゐり給ふに、いみじう泣く人あるを聞きつけて、とゞめてとり返し給うてけり。それをかく鬼とはいふなりけり。まだいと若うて后のたゞにおはしける時とや。 】『伊勢物語・第七段(芥河)』
871 大原や小塩(をしほ)の山も今日こそは神世のことも思ひいづらめ(在原業平)
(大原の小塩山も今日こそは、神世のことも思い出すであろう。)
この業平の歌の「詞書」(「二条のきさきのまだ東宮の御息所と申しける時に、大原野にまうでたまひける日よめる」)の「二条のきさき(后)」は、上記の「伊勢物語図色紙・芥川: 伝俵屋宗達筆」の「男性(在原業平か)に背負われて女性(のちの二条の后か)」の女性である。
この絵図について、次のように絵解きをしたものもある。
【 「男=業平」は手に入れがたい「女=のちの二条の后」に何年ものあいだ求婚しつづけ、やっとのことで盗みだし、暗いなか、「芥川」(大阪府高槻市を流れる川)のほとりまで逃げてきた場面。男と女の駆け落ちの場面だ。画面のほぼ中央に大きく、女を背負った男を描く。二人の体はもはや離れがたく一体化している。夢のなかにふわりと浮かんでいるように見え、リアリズム絵画にない幻想的な表現だ。「恋の逃走行」なのだが、切迫した悲壮感はない。
絵の詞書は、「女のえうまじかりけるを、としをへてよばひわたりけるを、からうじてぬすみて、いとくらきに、来けり」とある。この段の初めの一節だ。詞書は絵の一部かのように染筆されている。色紙の肌表紙の裏書に「昌程」とあり、その染筆は連歌師の里村昌程が担当したことがわかる。
なお、素庵の叔父吉田宗恂の女は、連歌師の里村玄仲に嫁しており、里村家と角倉・吉田家とは親戚関係にあった。素庵は、近衛信尹・近衛信尋・昌俔らの連歌会で詠まれた和歌・発句・連歌の清書を行なっている。素庵は公家たちと親交をもった。 】(『宗達絵画の解釈学―「風神雷神図屏風」の雷神はなぜ白いのか(林進著)』(敬文舎・2016年)
(参考)「四季花卉下絵古今集和歌巻」(梅その三・梅その四・躑躅・躑躅と糸薄)

「尾形光琳生誕三五〇周年記念 大琳派展―継承と変奏(東京国立博物館・読売新聞社編)」
所収「1-01 俵屋宗達下絵・本阿弥光悦筆 四季草花下絵古今和歌巻・重要文化財・畠山記念館蔵」彩箋墨書、三三・七×九一八・七

B図(『伊勢物語・第七段(芥川・雷神)』=「伊勢物語図色紙・芥川:伝俵屋宗達筆」)
(「尾形光琳生誕三五〇周年記念 大琳派展―継承と変奏(東京国立博物館・読売新聞社編)」出品目録1-54: 伝俵屋宗達筆 紙本着色 縦二四・六 横二〇 個人蔵)
上記で紹介したA図(大和文華館蔵)とこのB図(個人蔵)については、嘗て、次のアドレスで次のように記した。それを関連するところを全文再掲して置きたい。
https://yahan.blog.ss-blog.jp/2020-04-03
(再掲)
【『伊勢物語』(第六段)は「芥川」と題される段で、「伊勢物語図色紙(伝俵屋宗達画)」の三十六図(益田家本)の中では、この第六段中の「芥川」の図は夙に知られている。
これを第六段の全文に照らすと(上記の※)、「をとこ(若い男=業平)と女(愛する尊い女性=後の二条の后)」とが「駆け落ち」する場面で、これは、宗達自身の肉筆画というよりも、宗達工房(宗達が主宰する工房)の一般受けする、いわゆる「宗達工房ブランド」の絵図と解したい。
そして、次の「雷神」図なのであるが、この「雷神」図は、宗達画の代表的な作品の「風神雷神図屏風」(建仁寺蔵・国宝)の、その「雷神」図の原型のようで、これこそ、「伊勢物語図色紙」の三十六図(益田家本)中の、宗達自身の肉筆画のように解したい。
それにしても、この「雷神」図の詞書の「か見(神)さへ/いと/伊(い)ミし(じ)う/奈(な)り」は、どうにも謎めいているような感じで、『伊勢物語』の原文と照らすと、「神→雷神→鬼→(駆け落ちした女の「兄」)」という図式となり、その結末は、「鬼はや一口に食ひけり」、即ち、「女を連れ戻したり」ということで、何とも、他愛いない、これこそ、滑稽(俳諧)の極みという感じでなくもない。
しかし、『宗達絵画の解釈学(林進著・敬文社)』の口絵(『伊勢物語図色紙』第六段「雷神図」)の紹介は次のとおりで、何と角倉素庵の追善画というものである。
[宗達は、癩(ハンセン病)で亡くなった角倉素庵を追善するために『伊勢物語図色紙』三六図を描き、素庵の知友、親王・門跡・公家・大名・連歌師らも、詞書をその上に書き入れ、表立ってはおこなえぬ法要に替えて供養した。素庵も雷神となって色紙のなかに登場し、生前の知己たちの間をとび回り、出来映えをたのしんでいるようだ。] (『宗達絵画の解釈学(林進著・敬文社)』)
その「友人素庵を追善する『伊勢物語図色紙』」(第六章)では、その制作年代を寛永十一年(一六三四)十一月二十八日、二十二歳の若さで亡くなった、後陽成天皇の第十二皇子の「道周法親王」(「益田家本」第八八段の詞書染筆者、同染筆者の「近衛信尋・高松宮好仁親王・聖衛院道晃法親王の弟宮)の染筆以前の頃としている。
ちなみに、その「益田家本『伊勢物語図色紙』詞書揮毫者一覧」の主だった段とその揮毫者などは次のとおりである。
第六段 芥川 里村昌程(二二歳) 連歌師・里村昌琢庄の継嗣(子)
同上 雷神 同上
第九段 宇津の山 曼殊院良尚法親王(一二歳) 親王(後水尾天皇の猶子)
同上 富士の山 烏丸資慶(一二歳) 公家・大納言光広の継嗣(孫)
同上 隅田川 板倉重郷(一八歳) 京都所司代重宗の継嗣(子)
第三九段 女車の蛍 高松宮好仁親王(三一歳) 親王(後陽成天皇の第七皇子)
第四九段 若草の妹 近衛信尋(三五歳) 親王(後陽成天皇の第四皇子)
第五六段 臥して思ひ 聖衛院道晃法親王(二二歳)親王後陽成天皇の第一一皇子?)
第五八段 田刈らむ 烏丸光広(五五歳) 公家(大納言)
これらの「詞書揮毫者一覧」を見ていくと、『伊勢物語図色紙』」は角倉素庵追善というよりも、第九段(東下り)の詞書揮毫者の「曼殊院良尚法親王(一二歳)・烏丸資慶(一二歳)」などの「※初冠(ういこうぶり)」(元服=十一歳から十七歳の間におこなわれる成人儀礼)関連のお祝いものという見方も成り立つであろう。
ちなみに、烏丸光広(五五歳)の後継子(光広嫡子・光賢の長子)、烏丸資慶(一二歳)は、寛永八年(一六三一)、十歳の時に、後水尾上皇の御所で催された若年のための稽古歌会に出席を許され、その時の探題(「連夜照射」)の歌、「つらしとも知らでや鹿の照射さす端山によらぬ一夜だになき」が記録に遺されている(『松永貞徳と烏丸光広(高梨素子著)』)。 】
(追記メモ)
いそのかみのなむまつが宮づかへもせで、
石上といふ所にこもり侍りけるを、
にはかに※かうぶりたまはりければ、よろこび
いひつかはすとてよみてつかはしける
870 日の光の藪しわかねば石上(いそのかみ) ふりにし里に花も咲きけり(布留今道)
(日の光が籔も区別することなく照らすように、あまねく照らすお恵みにより、石上の古い里にも花が咲いた。)
この歌の詞書の「※かうぶり」と、上記の「※初冠(ういこうぶり)」は関連性がある。
※二条のきさきのまだ東宮の御息所と申しける時に、
大原野にまうでたまひける日よめる
871 大原や小塩(をしほ)の山も今日こそは神世のことも思ひいづらめ(在原業平)
(大原の小塩山も今日こそは、神世のことも思い出すであろう。)
この歌の詞書の「※二条のきさき」は、紛れもなく、「『伊勢物語』(第六段・芥川)」の「二条の后」そのものであろう。
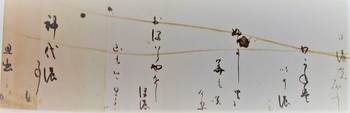
「尾形光琳生誕三五〇周年記念 大琳派展―継承と変奏(東京国立博物館・読売新聞社編)」
所収「1-01 俵屋宗達下絵・本阿弥光悦筆 四季草花下絵古今和歌巻・重要文化財・畠山記念館蔵」(「四季花卉下絵古今集和歌巻」=『光悦……琳派の創始者(河野元昭編)』所収「書画の二重奏への道……光悦書・宗達画和歌巻の展開(玉蟲敏子稿)」) 三三・七×九一八・七
いそのかみのなむまつが宮づかへもせで、
石上といふ所にこもり侍りけるを、
にはかにかうぶりたまはりければ、よろこび
いひつかはすとてよみてつかはしける
870 日の光の藪しわかねば石上(いそのかみ) ふりにし里に花も咲きけり(布留今道)
(日の光が籔も区別することなく照らすように、あまねく照らすお恵みにより、石上の古い里にも花が咲いた。)
二条のきさきのまだ東宮の御息所と申しける時に、
大原野にまうでたまひける日よめる
871 大原や小塩(をしほ)の山も今日こそは神世のことも思ひいづらめ(在原業平)
(大原の小塩山も今日こそは、神世のことも思い出すであろう。)
釈文(揮毫上の書体)=(『書道芸術第十八巻 本阿弥光悦』)
870 日濃(の)光屋(や)ぶしわ可(か)年(ね)盤(ば)以曾濃可三(いそのかみ)婦利(ふり)尓(に)し里尓(に)華も咲(さき)介梨(けり)
※わ可(か)年(ね)盤(ば)=分かねば。区別することなく。
※以曾濃可三(いそのかみ)=石上(いそのかみ)。天理市の石上神宮付近から西一帯。
※婦利(ふり)尓(に)し里=「古い里」と「布留の里」とを掛けている。古い都のあった「石上の布留の里」の意。)
※※いそのかみのなむまつ=石上並松(人名)。仁和二年(八八六)に従七位から従五位下に昇叙された。石上神宮に関わりのある人物か。
※※かうぶりたまはり=冠(かうぶり)賜り。位階を賜った。
871 お保(ほ)ハ(は)らやをしほ濃(の)山も今日こ曾(そ)ハ神代(かみよ)濃(の)事を思出(おもひいづ)らめ
※お保(ほ)ハ(は)らや=大原や。大原野神社。大和の春日神社を勧請したもので、京都市右京区にある。
※をしほ濃(の)山=小塩の山。大原野神社の背後の山。
※神代(かみよ)濃(の)事=藤原氏の祖神・天児屋命(あめのこやねのみこと)が皇祖・瓊瓊杵尊(ににぎのみこと)に従って天降りしたことを指しているか。
※※二条のきさき=二条の后。清和天皇の女御、藤原高子(たかいこ)。
http://www.asahi-net.or.jp/~sg2h-ymst/yamatouta/sennin/imamiti.html
【 布留今道(ふるのいまみち) 生没年未詳
布留氏は代々石上神宮の神主をつとめた家系。貞観三年(861)、内蔵少属。元慶六年(882)、従五位下。下野介などを経て、寛平十年(898)、三河介。古今集に三首を載せる。 】
http://www.asahi-net.or.jp/~SG2H-YMST/yamatouta/sennin/narihira.html
【 在原業平(ありわらのなりひら)=前掲=下記アドレス
https://yahan.blog.ss-blog.jp/2020-11-23 】

A図(『伊勢物語・第七段(芥川)』=「伊勢物語図色紙・芥川:伝俵屋宗達筆」)
(「尾形光琳生誕三五〇周年記念 大琳派展―継承と変奏(東京国立博物館・読売新聞社編)」出品目録1-53: 伝俵屋宗達筆 紙本着色 縦二四・六 横二〇 大和文華館蔵)
【むかし、男ありけり。女のえ得まじかりけるを、年を経てよばひわたりけるを、からうじて盗み出でて、いと暗きにきけり。芥河といふ河を率ていきければ、草のうへにおきたりける露を、「かれは何ぞ」となむ男に問ひける。ゆくさきおほく、夜もふけにければ、鬼ある所とも知らで、神さへいといみじう鳴り、雨もいたう降りければ、あばらなる蔵に、女をば奥におし入れて、男、弓、やなぐひを負ひて、戸口にをり。はや夜も明けなむと思ひつゝゐたりけるに、鬼一口に食ひてけり。 「あなや」といひけれど、神鳴る騒ぎにえ聞かざりけり。やうやう夜も明けゆくに、見れば、率て来し女もなし。足ずりをして泣けどもかひなし。
白玉かなにぞと人の問ひし時
露とこたへて消えなましものを
これは、二条の后の、いとこの女御の御もとに、仕うまつるやうにてゐ給へりけるを、かたちのいとめでたくおはしければ、盗みて負ひて出でたりけるを、御せうと堀河の大臣、太郎国経の大納言、まだ下臈にて内裏へまゐり給ふに、いみじう泣く人あるを聞きつけて、とゞめてとり返し給うてけり。それをかく鬼とはいふなりけり。まだいと若うて后のたゞにおはしける時とや。 】『伊勢物語・第七段(芥河)』
871 大原や小塩(をしほ)の山も今日こそは神世のことも思ひいづらめ(在原業平)
(大原の小塩山も今日こそは、神世のことも思い出すであろう。)
この業平の歌の「詞書」(「二条のきさきのまだ東宮の御息所と申しける時に、大原野にまうでたまひける日よめる」)の「二条のきさき(后)」は、上記の「伊勢物語図色紙・芥川: 伝俵屋宗達筆」の「男性(在原業平か)に背負われて女性(のちの二条の后か)」の女性である。
この絵図について、次のように絵解きをしたものもある。
【 「男=業平」は手に入れがたい「女=のちの二条の后」に何年ものあいだ求婚しつづけ、やっとのことで盗みだし、暗いなか、「芥川」(大阪府高槻市を流れる川)のほとりまで逃げてきた場面。男と女の駆け落ちの場面だ。画面のほぼ中央に大きく、女を背負った男を描く。二人の体はもはや離れがたく一体化している。夢のなかにふわりと浮かんでいるように見え、リアリズム絵画にない幻想的な表現だ。「恋の逃走行」なのだが、切迫した悲壮感はない。
絵の詞書は、「女のえうまじかりけるを、としをへてよばひわたりけるを、からうじてぬすみて、いとくらきに、来けり」とある。この段の初めの一節だ。詞書は絵の一部かのように染筆されている。色紙の肌表紙の裏書に「昌程」とあり、その染筆は連歌師の里村昌程が担当したことがわかる。
なお、素庵の叔父吉田宗恂の女は、連歌師の里村玄仲に嫁しており、里村家と角倉・吉田家とは親戚関係にあった。素庵は、近衛信尹・近衛信尋・昌俔らの連歌会で詠まれた和歌・発句・連歌の清書を行なっている。素庵は公家たちと親交をもった。 】(『宗達絵画の解釈学―「風神雷神図屏風」の雷神はなぜ白いのか(林進著)』(敬文舎・2016年)
(参考)「四季花卉下絵古今集和歌巻」(梅その三・梅その四・躑躅・躑躅と糸薄)
「尾形光琳生誕三五〇周年記念 大琳派展―継承と変奏(東京国立博物館・読売新聞社編)」
所収「1-01 俵屋宗達下絵・本阿弥光悦筆 四季草花下絵古今和歌巻・重要文化財・畠山記念館蔵」彩箋墨書、三三・七×九一八・七

B図(『伊勢物語・第七段(芥川・雷神)』=「伊勢物語図色紙・芥川:伝俵屋宗達筆」)
(「尾形光琳生誕三五〇周年記念 大琳派展―継承と変奏(東京国立博物館・読売新聞社編)」出品目録1-54: 伝俵屋宗達筆 紙本着色 縦二四・六 横二〇 個人蔵)
上記で紹介したA図(大和文華館蔵)とこのB図(個人蔵)については、嘗て、次のアドレスで次のように記した。それを関連するところを全文再掲して置きたい。
https://yahan.blog.ss-blog.jp/2020-04-03
(再掲)
【『伊勢物語』(第六段)は「芥川」と題される段で、「伊勢物語図色紙(伝俵屋宗達画)」の三十六図(益田家本)の中では、この第六段中の「芥川」の図は夙に知られている。
これを第六段の全文に照らすと(上記の※)、「をとこ(若い男=業平)と女(愛する尊い女性=後の二条の后)」とが「駆け落ち」する場面で、これは、宗達自身の肉筆画というよりも、宗達工房(宗達が主宰する工房)の一般受けする、いわゆる「宗達工房ブランド」の絵図と解したい。
そして、次の「雷神」図なのであるが、この「雷神」図は、宗達画の代表的な作品の「風神雷神図屏風」(建仁寺蔵・国宝)の、その「雷神」図の原型のようで、これこそ、「伊勢物語図色紙」の三十六図(益田家本)中の、宗達自身の肉筆画のように解したい。
それにしても、この「雷神」図の詞書の「か見(神)さへ/いと/伊(い)ミし(じ)う/奈(な)り」は、どうにも謎めいているような感じで、『伊勢物語』の原文と照らすと、「神→雷神→鬼→(駆け落ちした女の「兄」)」という図式となり、その結末は、「鬼はや一口に食ひけり」、即ち、「女を連れ戻したり」ということで、何とも、他愛いない、これこそ、滑稽(俳諧)の極みという感じでなくもない。
しかし、『宗達絵画の解釈学(林進著・敬文社)』の口絵(『伊勢物語図色紙』第六段「雷神図」)の紹介は次のとおりで、何と角倉素庵の追善画というものである。
[宗達は、癩(ハンセン病)で亡くなった角倉素庵を追善するために『伊勢物語図色紙』三六図を描き、素庵の知友、親王・門跡・公家・大名・連歌師らも、詞書をその上に書き入れ、表立ってはおこなえぬ法要に替えて供養した。素庵も雷神となって色紙のなかに登場し、生前の知己たちの間をとび回り、出来映えをたのしんでいるようだ。] (『宗達絵画の解釈学(林進著・敬文社)』)
その「友人素庵を追善する『伊勢物語図色紙』」(第六章)では、その制作年代を寛永十一年(一六三四)十一月二十八日、二十二歳の若さで亡くなった、後陽成天皇の第十二皇子の「道周法親王」(「益田家本」第八八段の詞書染筆者、同染筆者の「近衛信尋・高松宮好仁親王・聖衛院道晃法親王の弟宮)の染筆以前の頃としている。
ちなみに、その「益田家本『伊勢物語図色紙』詞書揮毫者一覧」の主だった段とその揮毫者などは次のとおりである。
第六段 芥川 里村昌程(二二歳) 連歌師・里村昌琢庄の継嗣(子)
同上 雷神 同上
第九段 宇津の山 曼殊院良尚法親王(一二歳) 親王(後水尾天皇の猶子)
同上 富士の山 烏丸資慶(一二歳) 公家・大納言光広の継嗣(孫)
同上 隅田川 板倉重郷(一八歳) 京都所司代重宗の継嗣(子)
第三九段 女車の蛍 高松宮好仁親王(三一歳) 親王(後陽成天皇の第七皇子)
第四九段 若草の妹 近衛信尋(三五歳) 親王(後陽成天皇の第四皇子)
第五六段 臥して思ひ 聖衛院道晃法親王(二二歳)親王後陽成天皇の第一一皇子?)
第五八段 田刈らむ 烏丸光広(五五歳) 公家(大納言)
これらの「詞書揮毫者一覧」を見ていくと、『伊勢物語図色紙』」は角倉素庵追善というよりも、第九段(東下り)の詞書揮毫者の「曼殊院良尚法親王(一二歳)・烏丸資慶(一二歳)」などの「※初冠(ういこうぶり)」(元服=十一歳から十七歳の間におこなわれる成人儀礼)関連のお祝いものという見方も成り立つであろう。
ちなみに、烏丸光広(五五歳)の後継子(光広嫡子・光賢の長子)、烏丸資慶(一二歳)は、寛永八年(一六三一)、十歳の時に、後水尾上皇の御所で催された若年のための稽古歌会に出席を許され、その時の探題(「連夜照射」)の歌、「つらしとも知らでや鹿の照射さす端山によらぬ一夜だになき」が記録に遺されている(『松永貞徳と烏丸光広(高梨素子著)』)。 】
(追記メモ)
いそのかみのなむまつが宮づかへもせで、
石上といふ所にこもり侍りけるを、
にはかに※かうぶりたまはりければ、よろこび
いひつかはすとてよみてつかはしける
870 日の光の藪しわかねば石上(いそのかみ) ふりにし里に花も咲きけり(布留今道)
(日の光が籔も区別することなく照らすように、あまねく照らすお恵みにより、石上の古い里にも花が咲いた。)
この歌の詞書の「※かうぶり」と、上記の「※初冠(ういこうぶり)」は関連性がある。
※二条のきさきのまだ東宮の御息所と申しける時に、
大原野にまうでたまひける日よめる
871 大原や小塩(をしほ)の山も今日こそは神世のことも思ひいづらめ(在原業平)
(大原の小塩山も今日こそは、神世のことも思い出すであろう。)
この歌の詞書の「※二条のきさき」は、紛れもなく、「『伊勢物語』(第六段・芥川)」の「二条の后」そのものであろう。
四季花卉下絵古今集和歌巻(その三) [光悦・宗達・素庵]
その三 梅(その二)

「尾形光琳生誕三五〇周年記念 大琳派展―継承と変奏(東京国立博物館・読売新聞社編)」
所収「1-01 俵屋宗達下絵・本阿弥光悦筆 四季草花下絵古今和歌巻・重要文化財・畠山記念館蔵」(「四季花卉下絵古今集和歌巻」=『光悦……琳派の創始者(河野元昭編)』所収「書画の二重奏への道……光悦書・宗達画和歌巻の展開(玉蟲敏子稿)」) 三三・七×九一八・七
妻(め)のおとうとを持て侍りける人に、
袍(うへのきぬ)をおくるとてよみてや
りける
868 紫の色こき時は目もはるに野なる草木ぞわかれざりける(業平朝臣)
(紫草の色濃き時は目も見張るように、野にある草木も、(紫草の色濃き時は)、その区別がつきませんね。「親しい姉妹をそれぞれ妻にしている私たち二人がお互いに好感情を抱くのは当然のことですね」の意か。)
大納言藤原の国経の朝臣の、宰相より中納言
になりける時、染めぬ袍(うへのきぬ)のあや
をおくるとてよめる
869 色なしと人や見るらむ昔より深き心に染めてしものを(近院右大臣)
(これには色がない(無風流)とあなたは見るでしょうが、実際には、(この無色の、無風流な色合いの中に)、昔から、(貴方に対して)、深く思う気持ちの色合いを込めて染め上げているですよ。)
釈文(揮毫上の書体)=(『書道芸術第十八巻 本阿弥光悦』)
868 無(む)ら左支(さき)濃(の)色こ幾(き)時盤(は)めもハ(は)る尓(に)野那(な)類(る)草木曾(ぞ)可(か)禮(れ)左(ざ)里(り)介(け)流(る)
※無(む)ら左支(さき)濃(の)色こ幾(き)=紫の色こき。紫草の根の色が濃いことで、裏に自分たちの二人の妻が血を分けた姉妹である意が込められているか。
※野那(な)類(る)草木=野なる草木。歌を贈った相手を野にある草木にたとえた。自分の妻の妹を紫草にたとえ、「あなたもその妹と同様に懐かしい」という意を込めているか。
869 以(い)露(ろ)なし登(と)人や見るら無(む)无(む)可(か)しよ利(り)ふ可(か)支(き)心尓(に)曾(そ)め天(て)し物を
※以(い)露(ろ)なし=色無し。色彩の無い意と無風流の意とを掛ける。
※人や見るら無(む)=人や見るらむ。この「人」は歌を贈る相手。
※ふ可(か)支(き)心=深き心。貴方を思う深い心で染め上げているの意。
※※ 業平朝臣(なりひらのあそん)=在平業平
http://www.asahi-net.or.jp/~SG2H-YMST/yamatouta/sennin/narihira.html
【 在原業平(ありわらのなりひら) 天長二~元慶四(825-880) 通称:在五中将
平城天皇の孫。阿保親王の第五子。母は桓武天皇の皇女伊都内親王。兄に仲平・行平・守平などがいる。紀有常女(惟喬親王の従妹)を妻とする。子の棟梁・滋春、孫の元方も勅撰集に歌を収める歌人である。妻の妹を娶った藤原敏行と親交があった。(以下、略) 】
※※ 近院右大臣(こんゐんのみぎのおほいまうちぎみ)=源能有(みなもとのよしあり)
https://www.asahi-net.or.jp/~sg2h-ymst/yamatouta/sennin/yosiari.html
【 源能有(みなもとのよしあり) 承和十二~寛平九(845-897) 号:近院右大臣
文徳天皇の皇子。母は伴氏。藤原基経の娘を妻とする。子に当純がいる。仁寿三年(853)、源朝臣を賜わって臣籍降下。貞観四年(862)、従四位上に初叙され、貞観十一年、大蔵卿。同十四年、参議。元慶元年(877)、従三位。元慶六年(882)、中納言。寛平元年(889)、右近衛大将に東宮傳を兼任。翌年正三位に昇り、寛平三年、大納言。同八年、右大臣に就任したが、翌年五十三歳で薨じた。贈正二位。藤原因香・国経との贈答歌がある。古今初出。勅撰入集は四首。】
※※※ 「868 紫の色こき時は目もはるに野なる草木ぞわかれざりける(業平朝臣)」
↓
http://www.milord-club.com/Kokin/uta0868.htm
↓
【昔、女はらから二人ありけり。一人はいやしきをとこの貧しき、一人はあてなるをとこ持(も)たりけり。いやしきをとこ持たる、十二月のつごもりに、うへのきぬを洗ひて、手づから張りけり。心ざしはいたしけれど、さるいやしき業(わざ)もならはざりければ、うへのきぬの肩を張り破(や)りてけり。せむ方もなくて、たゞ泣きに泣きけり。これを、かのあてなるをとこ聞きて、いと心苦しかりければ、いと清らなる緑衫(ろうさう)のうへのきぬを見出でてやるとて、
紫の色濃き時はめもはるに野なる草木ぞ別れざりける
武蔵野の心なるべし。 】(『伊勢物語・第四十一段』)
http://teppou13.fc2web.com/hana/narihira/ise/now/ise_ns41.html

(『伊勢物語・第四十一段』)
(参考)「四季花卉下絵古今集和歌巻」(竹・梅その一・梅その二)

「尾形光琳生誕三五〇周年記念 大琳派展―継承と変奏(東京国立博物館・読売新聞社編)」
所収「1-01 俵屋宗達下絵・本阿弥光悦筆 四季草花下絵古今和歌巻・重要文化財・畠山記念館蔵」彩箋墨書、三三・七×九一八・七
(画像再掲)

B図「四季草花木版下絵隆達節小歌巻断簡」 画像番号:C0036766 32.9×81.0 東京国立博物館蔵
【 花卉摺絵隆達節断簡 伝角倉素庵 一幅 紙本金銀泥摺絵墨書 33.0×81.3 東京国立博物館蔵 】(『琳派―版と型の展開(町田市立国際版画美術館編)』出品目録二)
【 隆達節断簡 俵屋宗達下絵 一幅 彩箋墨書 32.9×81.0 東京国立博物館蔵 】(「尾形光琳生誕三五〇周年記念 大琳派展―継承と変奏(東京国立博物館・読売新聞社編)」出品目録1-08)
【(前略) 胡粉地の料紙に、梅・蔦・藤・細竹・太竹の図様を金銀泥で摺ったもので、一つの版木を幾度も重ね摺りし、金銀泥の変化をつけて大胆に画面を構成するなどの工夫があり、無造作に捺された版画に生じた捺しムラが「たらし込み」に通じる効果を見せている。草花を大きくクローズアップするのは、宗達金銀泥絵と共通した特色であるが、なかでも最も複雑な版木の活用法を見せる作品で、新たな巻子本装飾の手法がうかがえる。
隆達の自筆によると、慶長十年(一六〇五)九月、親交のあった茶屋又四郎の求めによって行間に譜付けを加えたことが明らかになる。茶屋又四郎とは、京都の豪商で、朱印船貿易に活躍、家康の信任を得た上層町衆の一人であった。本文は、光悦流随一の書き手角倉素庵(一五七一~一六三二)の筆と伝えられているが諸説があり断定できない。(高橋裕次) 】
(「尾形光琳生誕三五〇周年記念 大琳派展―継承と変奏(東京国立博物館・読売新聞社編)」出品目録1-08)
(画像再掲)

C図「花卉摺絵隆達節断簡」・京都民芸館蔵 (『琳派―版と型の展開(町田市立国際版画美術館編)』出品目録六)
【 (前略) 隆達小歌、隆達節の小歌などとも呼ばれる隆達節は、安土桃山時代、泉州堺の高三隆達が節付けして流行した歌謡である。それらは『日本古典文学大系』の「中世近世歌謡集」に収められている。高三隆達は、小歌の名人として織田信長の前で歌ったことがあり、また堺流書道の名手として豊臣秀吉に召されたともいう。款記にある「自庵」とは『大日本人名辞書』によれば隆達の別号であり、隆達の署名と花押まであるのだから、当然この巻は隆達自筆ということになるのだが、一般にこの小歌巻は角倉素庵の書であるといわれている。
そこで、隆達の自筆である「遊里図屏風」(ボストン美術館蔵)の片隻二扇に貼られている「隆達節」や巻子の「隆達節」(不二文庫蔵)などと比較して見ると、まるで書風が異なる一方、素庵の「百人一首」(根本家蔵)などとはかなり似ている。しかし、よく比べてみると、同一筆者に帰着させることは、難しいように思われる。光悦流ではあるものの、素庵の書風はより典型化されていて、ややくねくねとしている。そこで、試みに光悦と比較してみると、むしろこれとの共通性のほうが強いのである。これも断定は差し控えなければならないが、少なくとも、素庵よりは光悦のほうにより多くの可能性を認めるべきであろう。したがって、ここでは一応光悦として扱っておきたい。
そもそも、隆達は飛鳥井雅親(栄雅)の流れを引く栄雅流であるのに対し、光悦は光悦流の創始者である。なぜ、先のようなことが起こったのかよくわからない。しかし、改めて注意してみると、歌の部分と款記とは書風が異なっており、前者は光悦、後者は隆達と擬定することができそうである。おそらく、隆達が庇護者であった茶屋又四郎に贈物とするため、光悦に依頼し、特に美しい料紙に自分の隆達節を浄写してもらったのであろう。そして、巻末に署名、年紀、宛名をみずから書いたのである。墨譜を加えたのも、隆達自身であったにちがいない。
隆達と光悦とは親しい間柄であったはずであるが、ここでは隆達と又四郎との関係が第一義であって、書家や、まして料紙装飾を行なった職人の名などは、本紙上に明示する必要はなかったのである。ちなみに、贈られた茶屋又四郎は、豪商茶屋家の三代目四郎次郎清次のことである。慶長二十年本家名四郎次郎を襲名するまで、又四郎を名乗っていたのである。
(以下略) 】(『琳派―版と型の展開(町田市立国際版画美術館編)』所収「宗達金銀泥絵序説(河野元昭稿)」)
この『琳派―版と型の展開(町田市立国際版画美術館編)』所収「宗達金銀泥絵序説(河野元昭稿)」(1992年)は、『琳派―響きあう美(河野元昭著)』所収「※第6章 宗達金銀泥絵序説」(2015年)においても、そのまま踏襲されている。
『琳派―響きあう美(河野元昭著)』(思文閣出版・2015年)
(目次)
序 章 琳派と写意 (1989)
第1章 光悦試論 (2011/10-2012/7)
第2章 宗達関係資料と研究史 (1977)
第3章 養源院宗達画考 (1987)
第4章 宗達における町衆的性格と室町文化(1990)
第5章 宗達から光琳への変質 (1991)
※第6章 宗達金銀泥絵序説 (1992)
第7章 琳派の主題―宗達の場合 (1994)
第8章 宗達と能 (2003)
(第9章 光琳水墨画の展開と源泉~第16章 渡辺始興筆「真写鳥類図巻」について)
(第17章 乾山の伝記と絵画~第19章 乾山と光琳―兄弟逆転試論)
(第20章 抱一の伝記~第26章 鈴木其一の画業)

「尾形光琳生誕三五〇周年記念 大琳派展―継承と変奏(東京国立博物館・読売新聞社編)」
所収「1-01 俵屋宗達下絵・本阿弥光悦筆 四季草花下絵古今和歌巻・重要文化財・畠山記念館蔵」(「四季花卉下絵古今集和歌巻」=『光悦……琳派の創始者(河野元昭編)』所収「書画の二重奏への道……光悦書・宗達画和歌巻の展開(玉蟲敏子稿)」) 三三・七×九一八・七
妻(め)のおとうとを持て侍りける人に、
袍(うへのきぬ)をおくるとてよみてや
りける
868 紫の色こき時は目もはるに野なる草木ぞわかれざりける(業平朝臣)
(紫草の色濃き時は目も見張るように、野にある草木も、(紫草の色濃き時は)、その区別がつきませんね。「親しい姉妹をそれぞれ妻にしている私たち二人がお互いに好感情を抱くのは当然のことですね」の意か。)
大納言藤原の国経の朝臣の、宰相より中納言
になりける時、染めぬ袍(うへのきぬ)のあや
をおくるとてよめる
869 色なしと人や見るらむ昔より深き心に染めてしものを(近院右大臣)
(これには色がない(無風流)とあなたは見るでしょうが、実際には、(この無色の、無風流な色合いの中に)、昔から、(貴方に対して)、深く思う気持ちの色合いを込めて染め上げているですよ。)
釈文(揮毫上の書体)=(『書道芸術第十八巻 本阿弥光悦』)
868 無(む)ら左支(さき)濃(の)色こ幾(き)時盤(は)めもハ(は)る尓(に)野那(な)類(る)草木曾(ぞ)可(か)禮(れ)左(ざ)里(り)介(け)流(る)
※無(む)ら左支(さき)濃(の)色こ幾(き)=紫の色こき。紫草の根の色が濃いことで、裏に自分たちの二人の妻が血を分けた姉妹である意が込められているか。
※野那(な)類(る)草木=野なる草木。歌を贈った相手を野にある草木にたとえた。自分の妻の妹を紫草にたとえ、「あなたもその妹と同様に懐かしい」という意を込めているか。
869 以(い)露(ろ)なし登(と)人や見るら無(む)无(む)可(か)しよ利(り)ふ可(か)支(き)心尓(に)曾(そ)め天(て)し物を
※以(い)露(ろ)なし=色無し。色彩の無い意と無風流の意とを掛ける。
※人や見るら無(む)=人や見るらむ。この「人」は歌を贈る相手。
※ふ可(か)支(き)心=深き心。貴方を思う深い心で染め上げているの意。
※※ 業平朝臣(なりひらのあそん)=在平業平
http://www.asahi-net.or.jp/~SG2H-YMST/yamatouta/sennin/narihira.html
【 在原業平(ありわらのなりひら) 天長二~元慶四(825-880) 通称:在五中将
平城天皇の孫。阿保親王の第五子。母は桓武天皇の皇女伊都内親王。兄に仲平・行平・守平などがいる。紀有常女(惟喬親王の従妹)を妻とする。子の棟梁・滋春、孫の元方も勅撰集に歌を収める歌人である。妻の妹を娶った藤原敏行と親交があった。(以下、略) 】
※※ 近院右大臣(こんゐんのみぎのおほいまうちぎみ)=源能有(みなもとのよしあり)
https://www.asahi-net.or.jp/~sg2h-ymst/yamatouta/sennin/yosiari.html
【 源能有(みなもとのよしあり) 承和十二~寛平九(845-897) 号:近院右大臣
文徳天皇の皇子。母は伴氏。藤原基経の娘を妻とする。子に当純がいる。仁寿三年(853)、源朝臣を賜わって臣籍降下。貞観四年(862)、従四位上に初叙され、貞観十一年、大蔵卿。同十四年、参議。元慶元年(877)、従三位。元慶六年(882)、中納言。寛平元年(889)、右近衛大将に東宮傳を兼任。翌年正三位に昇り、寛平三年、大納言。同八年、右大臣に就任したが、翌年五十三歳で薨じた。贈正二位。藤原因香・国経との贈答歌がある。古今初出。勅撰入集は四首。】
※※※ 「868 紫の色こき時は目もはるに野なる草木ぞわかれざりける(業平朝臣)」
↓
http://www.milord-club.com/Kokin/uta0868.htm
↓
【昔、女はらから二人ありけり。一人はいやしきをとこの貧しき、一人はあてなるをとこ持(も)たりけり。いやしきをとこ持たる、十二月のつごもりに、うへのきぬを洗ひて、手づから張りけり。心ざしはいたしけれど、さるいやしき業(わざ)もならはざりければ、うへのきぬの肩を張り破(や)りてけり。せむ方もなくて、たゞ泣きに泣きけり。これを、かのあてなるをとこ聞きて、いと心苦しかりければ、いと清らなる緑衫(ろうさう)のうへのきぬを見出でてやるとて、
紫の色濃き時はめもはるに野なる草木ぞ別れざりける
武蔵野の心なるべし。 】(『伊勢物語・第四十一段』)
http://teppou13.fc2web.com/hana/narihira/ise/now/ise_ns41.html

(『伊勢物語・第四十一段』)
(参考)「四季花卉下絵古今集和歌巻」(竹・梅その一・梅その二)
「尾形光琳生誕三五〇周年記念 大琳派展―継承と変奏(東京国立博物館・読売新聞社編)」
所収「1-01 俵屋宗達下絵・本阿弥光悦筆 四季草花下絵古今和歌巻・重要文化財・畠山記念館蔵」彩箋墨書、三三・七×九一八・七
(画像再掲)

B図「四季草花木版下絵隆達節小歌巻断簡」 画像番号:C0036766 32.9×81.0 東京国立博物館蔵
【 花卉摺絵隆達節断簡 伝角倉素庵 一幅 紙本金銀泥摺絵墨書 33.0×81.3 東京国立博物館蔵 】(『琳派―版と型の展開(町田市立国際版画美術館編)』出品目録二)
【 隆達節断簡 俵屋宗達下絵 一幅 彩箋墨書 32.9×81.0 東京国立博物館蔵 】(「尾形光琳生誕三五〇周年記念 大琳派展―継承と変奏(東京国立博物館・読売新聞社編)」出品目録1-08)
【(前略) 胡粉地の料紙に、梅・蔦・藤・細竹・太竹の図様を金銀泥で摺ったもので、一つの版木を幾度も重ね摺りし、金銀泥の変化をつけて大胆に画面を構成するなどの工夫があり、無造作に捺された版画に生じた捺しムラが「たらし込み」に通じる効果を見せている。草花を大きくクローズアップするのは、宗達金銀泥絵と共通した特色であるが、なかでも最も複雑な版木の活用法を見せる作品で、新たな巻子本装飾の手法がうかがえる。
隆達の自筆によると、慶長十年(一六〇五)九月、親交のあった茶屋又四郎の求めによって行間に譜付けを加えたことが明らかになる。茶屋又四郎とは、京都の豪商で、朱印船貿易に活躍、家康の信任を得た上層町衆の一人であった。本文は、光悦流随一の書き手角倉素庵(一五七一~一六三二)の筆と伝えられているが諸説があり断定できない。(高橋裕次) 】
(「尾形光琳生誕三五〇周年記念 大琳派展―継承と変奏(東京国立博物館・読売新聞社編)」出品目録1-08)
(画像再掲)

C図「花卉摺絵隆達節断簡」・京都民芸館蔵 (『琳派―版と型の展開(町田市立国際版画美術館編)』出品目録六)
【 (前略) 隆達小歌、隆達節の小歌などとも呼ばれる隆達節は、安土桃山時代、泉州堺の高三隆達が節付けして流行した歌謡である。それらは『日本古典文学大系』の「中世近世歌謡集」に収められている。高三隆達は、小歌の名人として織田信長の前で歌ったことがあり、また堺流書道の名手として豊臣秀吉に召されたともいう。款記にある「自庵」とは『大日本人名辞書』によれば隆達の別号であり、隆達の署名と花押まであるのだから、当然この巻は隆達自筆ということになるのだが、一般にこの小歌巻は角倉素庵の書であるといわれている。
そこで、隆達の自筆である「遊里図屏風」(ボストン美術館蔵)の片隻二扇に貼られている「隆達節」や巻子の「隆達節」(不二文庫蔵)などと比較して見ると、まるで書風が異なる一方、素庵の「百人一首」(根本家蔵)などとはかなり似ている。しかし、よく比べてみると、同一筆者に帰着させることは、難しいように思われる。光悦流ではあるものの、素庵の書風はより典型化されていて、ややくねくねとしている。そこで、試みに光悦と比較してみると、むしろこれとの共通性のほうが強いのである。これも断定は差し控えなければならないが、少なくとも、素庵よりは光悦のほうにより多くの可能性を認めるべきであろう。したがって、ここでは一応光悦として扱っておきたい。
そもそも、隆達は飛鳥井雅親(栄雅)の流れを引く栄雅流であるのに対し、光悦は光悦流の創始者である。なぜ、先のようなことが起こったのかよくわからない。しかし、改めて注意してみると、歌の部分と款記とは書風が異なっており、前者は光悦、後者は隆達と擬定することができそうである。おそらく、隆達が庇護者であった茶屋又四郎に贈物とするため、光悦に依頼し、特に美しい料紙に自分の隆達節を浄写してもらったのであろう。そして、巻末に署名、年紀、宛名をみずから書いたのである。墨譜を加えたのも、隆達自身であったにちがいない。
隆達と光悦とは親しい間柄であったはずであるが、ここでは隆達と又四郎との関係が第一義であって、書家や、まして料紙装飾を行なった職人の名などは、本紙上に明示する必要はなかったのである。ちなみに、贈られた茶屋又四郎は、豪商茶屋家の三代目四郎次郎清次のことである。慶長二十年本家名四郎次郎を襲名するまで、又四郎を名乗っていたのである。
(以下略) 】(『琳派―版と型の展開(町田市立国際版画美術館編)』所収「宗達金銀泥絵序説(河野元昭稿)」)
この『琳派―版と型の展開(町田市立国際版画美術館編)』所収「宗達金銀泥絵序説(河野元昭稿)」(1992年)は、『琳派―響きあう美(河野元昭著)』所収「※第6章 宗達金銀泥絵序説」(2015年)においても、そのまま踏襲されている。
『琳派―響きあう美(河野元昭著)』(思文閣出版・2015年)
(目次)
序 章 琳派と写意 (1989)
第1章 光悦試論 (2011/10-2012/7)
第2章 宗達関係資料と研究史 (1977)
第3章 養源院宗達画考 (1987)
第4章 宗達における町衆的性格と室町文化(1990)
第5章 宗達から光琳への変質 (1991)
※第6章 宗達金銀泥絵序説 (1992)
第7章 琳派の主題―宗達の場合 (1994)
第8章 宗達と能 (2003)
(第9章 光琳水墨画の展開と源泉~第16章 渡辺始興筆「真写鳥類図巻」について)
(第17章 乾山の伝記と絵画~第19章 乾山と光琳―兄弟逆転試論)
(第20章 抱一の伝記~第26章 鈴木其一の画業)
四季花卉下絵古今集和歌巻(その二) [光悦・宗達・素庵]
その二 梅(その一)

「尾形光琳生誕三五〇周年記念 大琳派展―継承と変奏(東京国立博物館・読売新聞社編)」
所収「1-01 俵屋宗達下絵・本阿弥光悦筆 四季草花下絵古今和歌巻・重要文化財・畠山記念館蔵」(「四季花卉下絵古今集和歌巻」=『光悦……琳派の創始者(河野元昭編)』所収「書画の二重奏への道……光悦書・宗達画和歌巻の展開(玉蟲敏子稿)」)三三・七×九一八・七
題しらず
866 限りなき君がためにと折る花は時しもわかぬ物にぞありける(読人知らず)
(限りなき長寿のあなたのお祝いのために折り取った花は、季節に関係なく何時までも咲いている花でしたよ。)
867 紫のひともとゆゑに武蔵野の草はみながらあはれとぞ見る(読人知らず)
(紫草が一本あるために、武蔵野の草は、すべていとおしく見えることだなあ。)
釈文(揮毫上の書体)=(『書道芸術第十八巻 本阿弥光悦』)
866 限(かぎり)な幾(き)君可(が)為(ため)尓(に)と於(お)る華盤(は)時しも王可(わか)ぬも乃(の)尓(に)曾(ぞ)有(あり)介(け)る
※限(かぎり)な幾(き) 君可(が)為(ため)尓(に)=限りなき君がために。寿命の無限な貴方の為に。
※於(お)る華盤(は)=折る花は。
※時しも王可(わか)ぬ=時しもわかぬ。必ずしも時節を区別していない。
867 紫濃(の)日とも登(と)遊(ゆ)へ尓(に)武蔵野濃(の)草盤(は)三(み)な可(が)ら哀(あはれ)と曾(ぞ)見る
※紫濃(の)=紫草(むらさきそう)の。
※日とも登(と)遊(ゆ)へ尓(に)=一本(ひともと)故に。一本であるが故に。
※三(み)な可(が)ら=ことごとく。
※あはれ=しみじみとかわいい。いとしい。
下絵は、「竹」の図から「梅」の図(その一)と変わる。『古今和歌集』の部立(構成)は、「春(二巻)・夏(一巻)・秋(二巻)・冬(一巻)・賀(一巻)・離別(一巻)・羇旅(一巻)・物名(一巻)・恋(五巻)・哀傷(一巻)・雑(二巻)・雑体(一巻)・大歌所御歌(一巻)」の二十巻構成で、その後の勅撰集の模範とされている。
この「四季花卉下絵古今集和歌巻」の下絵で描かれている「竹・梅・躑躅・蔦・下草(糸薄)」などについては、この『古今和歌集』の「四季(春・夏・秋・冬)」の区分のものではなく、冒頭に、「四君子に属する竹・梅を選び、年初の歳寒のイメージを託す。弐種の素材であるので歳寒二友」ともいうべき、「竹(冬)・梅(春)」、そして、それに続く、「躑躅(夏)・蔦(秋)」という展開のイメージのような雰囲気である。
いずれにしろ、ここで「竹(冬)」から「梅(春)」へとの場面転換(「季移り」)の図柄である。それに相応してのものなのかどうかは判然としないが、(下絵=竹図=863と864の二首 )と(下絵=梅図その一=866と867)との間に、次の一首(865)が省かれている。
その一首(865)を、その前(下絵=竹図=863と864の二首)と、その後(下絵=梅図その一=866と867)との間に挿入すると、次のとおりとなる。
(下絵=竹図)
863 わが上に露ぞ置くなる天の川とわたる舟のかいのしずくか(読人知らず)
(私の体が濡れているのは露が降りているのだそうだ。それならその露は天の川の渡し場を彦星が渡る舟の櫂から落ちた雫なのであろうか。)
864 思ふどちまどゐせる夜は唐錦たたまく惜しきものにぞありける(読人知らず)
(仲のいい者たちが車座に座って楽しいひとときを送っている夜は、立ち上がるのが本当に惜しいものだ。)
865 うれしきを何に包まむ唐衣袂ゆたかにたてと言はしも(読人知らず)
(こんなにたくさんある嬉しいことを何に包んで持って帰ろうか。着物の袖にしまえるように、大きく作ってくれと言っておくのだったなぁ。)
(下絵=梅図その一)
866 限りなき君がためにと折る花は時しもわかぬ物にぞありける(読人知らず)
(限りなき長寿のあなたのお祝いのために折り取った花は、季節に関係なく何時までも咲いている花でしたよ。)
867 紫のひともとゆゑに武蔵野の草はみながらあはれとぞ見る(読人知らず)
(紫草が一本あるために、武蔵野の草は、すべていとおしく見えることだなあ。)
(参考) 「四季花卉下絵古今集和歌巻」(竹・梅その一・梅その二)

「尾形光琳生誕三五〇周年記念 大琳派展―継承と変奏(東京国立博物館・読売新聞社編)」
所収「1-01 俵屋宗達下絵・本阿弥光悦筆 四季草花下絵古今和歌巻・重要文化財・畠山記念館蔵」彩箋墨書、三三・七×九一八・七
http://www.miho.or.jp/booth/html/artcon/00000074.htm

A図「梅下絵隆達節断簡」紙本墨書金銀泥 縦:33.8cm 横:89.9cm MIHO MUSEUM蔵
【 堺の高三隆達によって始められた「隆達節」は,慶長年間(1596~1615)に流行した歌謡で,この隆達節をおよそ百種をおさめた巻物が作られたのだが,今は諸所に分蔵されている。
この巻物の特徴は,料紙に肉筆による装飾を施すのではなく,木版の金銀泥刷によって梅蔦細竹太竹を表現している点である。本図はそのうちの梅の部分の断簡で,梅の他の部分はたとえば東京国立博物館に所蔵される。
巻末にあたる部分は京都民芸館の所蔵で,そこには,慶長10年(1605)9月,高三隆達自身が京の豪商として名高い茶屋又四郎にこの巻物一巻を贈った旨が記されている。
なお,俵屋宗達による金銀泥下絵巻物とこの木版金銀泥刷下絵巻物とは,深い関係があることは確かではあるが,宗達との直接的関係を断定するのは時期尚早とすべきであろう。 】
この紹介文の「東京国立博物館蔵」のものは、次のものである。
https://webarchives.tnm.jp/imgsearch/show/C0036766

B図「四季草花木版下絵隆達節小歌巻断簡」 画像番号:C0036766 32.9×81.0 東京国立博物館蔵
【 花卉摺絵隆達節断簡 伝角倉素庵 一幅 紙本金銀泥摺絵墨書 33.0×81.3 東京国立博物館蔵 】(『琳派―版と型の展開(町田市立国際版画美術館編)』)
https://www.jstage.jst.go.jp/article/tja1948/17/2/17_2_155/_pdf/-char/ja
【(14)慶長十年九月茶屋又一郎宛本
角倉素庵筆というが、現所蔵者・内容共に未詳。その断簡と思われるもの(十章)、現在、東京国立博物館保管。左の如くである。
8 たねとりてうへし。うへなはむさし野も。せはくやあらん。わかおもひ草
9 みるめ。はかりになみたちて。なるとふねかや。あハてこかるエ
10 枕の海ハ、なみたつはかり。さらはみるめの。ありもせて
11 あハぬうらみハつもれとも。見れハことの葉もなし
12 うらみあるこそたのみなれ。おもハぬ中は。ふらすふられす
36 物のしゆむなハ春のあめ。なをもしゆむなは。たひのひとりね
37 華に。あらしのふかはふけ。君の心の。よそへちらすは
38 ひとりねてふたり。ぬるよのありさまを。かたるな人に。なふまくら
39 見製ゆるとなさけ。あれかし夢にさへ。つれなのふりや。なふきみは
40 月はにこりの水にもやとる。かすならぬ身に。なさけあれきみ
(頭の数字は文緑二年百五十章本の歌詞番号) 】(「隆達小歌集の伝本について(浅野健二稿)」)
http://www.ccf.or.jp/jp/04collection/item_view.cfm?P_no=2245
【高三隆達〈たかさぶりゅうたつ・1527-1611〉は、堺の薬種商の家の生まれ。日蓮宗顕本寺(けんぽんじ・大阪府堺市)の僧となり、日長(にっちょう)と改める。庵室を自在院(じざいいん)といい、高三坊(たかさぶぼう)と称したが、やがて還俗。小歌の名手としての盛名を高め、隆達節(りゅうたつぶし)と呼ばれる新しい歌謡を民衆に広めた。伏見城の能舞台において、細川幽斎〈ほそかわゆうさい・1534-1610〉の鼓に合わせて歌い、豊臣秀吉〈とよとみひでよし・1537-98〉らの喝采を浴びたことは有名。書にも巧みで、自ら書写した「隆達節」(一巻・個人蔵)などが伝存する。さらに、本阿弥光悦〈ほんあみこうえつ・1558-1637〉周辺の紙師宗二(そうじ)調製の料紙(金銀雲母下絵)に角倉素庵〈すみのくらそあん・1571-1632〉が揮毫した「隆達節」(もとは一巻。断簡が東京国立博物館に収蔵)などもあり、その交友も広範囲に及んでいたことを推察する。書流系譜においては、牡丹花肖柏〈ぼたんかしょうはく・1443-1527〉を祖とする堺流に挙げられる。これは、隆達自作の小歌(=隆達節)を短冊形に書写したもの。かなりの能書で、手馴れた筆致である。文句の右横には、墨譜(曲節を明らかにするための点)がしるされる。隆達の遺墨は稀少で、この譜付けの一幅などは、尊貴な遺品といえよう。】
https://hosei.repo.nii.ac.jp/?action=pages_view_main&active_action=repository_view_main_item_detail&item_id=21363&item_no=1&page_id=13&block_id=83
↓
「角倉素庵と『方丈記』(小秋元段 稿)」
なお、「梅下絵隆達節断簡」(MIHO MUSEUM蔵)の紹介文で、「巻末にあたる部分は京都民芸館の所蔵で,そこには,慶長10年(1605)9月,高三隆達自身が京の豪商として名高い茶屋又四郎にこの巻物一巻を贈った旨が記されている」の「京都民芸館」ものは、次のものである。
http://drei-punkte.cocolog-nifty.com/blog/2018/10/2-fbf6.html

C図「花卉摺絵隆達節断簡」・京都民芸館蔵 (『琳派―版と型の展開(町田市立国際版画美術館編)』)
ここで、「本阿弥光悦略年譜」(『光悦……琳派の創始者(河野元昭編)』所収)の「慶長十年(一六〇五)」の項を見ると、次のような記載がある。
「慶長十年(一六〇五) 四八(歳) この年の紀年のある角倉素庵筆と伝える隆達節の巻物がある。四十八歳になったという手紙がある。この年の紀年をもつ八十嶋道除筆木版下絵『琵琶幷序』がある。この頃『蓮下絵和歌巻』(前半)を書くか。」
この「本阿弥光悦略年譜」に記載されている「この年の紀年のある角倉素庵筆と伝える隆達節の巻物がある」というのが、上記の【C図「花卉摺絵隆達節断簡」・京都民芸館蔵】を指しているように解せられる。
しかし、この【C図「花卉摺絵隆達節断簡」・京都民芸館蔵】が紹介されている『琳派―版と型の展開(町田市立国際版画美術館編)』(出品目録五)には、「伝角倉素庵筆」の記載はなく、同時に出品されていた【B図「四季草花木版下絵隆達節小歌巻断簡」・東京国立博物館蔵】(出品目録二)の「作者」欄に、「伝角倉素庵筆」の記載があり、この【B図「四季草花木版下絵隆達節小歌巻断簡」・東京国立博物館蔵】(出品目録二)と【C図「花卉摺絵隆達節断簡」・京都民芸館蔵】(出品目録五)と、さらに、【A図「梅下絵隆達節断簡」(MIHO MUSEUM蔵=「神慈秀明会」旧蔵)】とは、元々は一巻のものと解しての、「伝角倉素庵筆」としているのかも知れない。
http://kotenseki.nijl.ac.jp/biblio/200008233/viewer/11
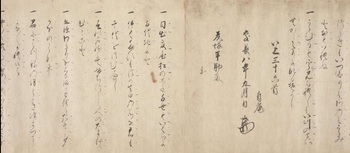
D図「初歌集」・著者:隆達・国文学研究資料館 貴重書・ 書誌ID:200008233
この【D図「初歌集」・著者:隆達・国文学研究資料館蔵】は、「高三隆達」の自筆筆とされており、この「自庵(隆達の号「自在院」の「自庵」)の署名・花押・紀年と宛名書き」は、
【C図「花卉摺絵隆達節断簡」・京都民芸館蔵】と同一であり、これらは、全て、「伝角倉素庵筆」ではなく、「高三隆達筆」と解するのが最も素直な理解のようにも思われる。

「尾形光琳生誕三五〇周年記念 大琳派展―継承と変奏(東京国立博物館・読売新聞社編)」
所収「1-01 俵屋宗達下絵・本阿弥光悦筆 四季草花下絵古今和歌巻・重要文化財・畠山記念館蔵」(「四季花卉下絵古今集和歌巻」=『光悦……琳派の創始者(河野元昭編)』所収「書画の二重奏への道……光悦書・宗達画和歌巻の展開(玉蟲敏子稿)」)三三・七×九一八・七
題しらず
866 限りなき君がためにと折る花は時しもわかぬ物にぞありける(読人知らず)
(限りなき長寿のあなたのお祝いのために折り取った花は、季節に関係なく何時までも咲いている花でしたよ。)
867 紫のひともとゆゑに武蔵野の草はみながらあはれとぞ見る(読人知らず)
(紫草が一本あるために、武蔵野の草は、すべていとおしく見えることだなあ。)
釈文(揮毫上の書体)=(『書道芸術第十八巻 本阿弥光悦』)
866 限(かぎり)な幾(き)君可(が)為(ため)尓(に)と於(お)る華盤(は)時しも王可(わか)ぬも乃(の)尓(に)曾(ぞ)有(あり)介(け)る
※限(かぎり)な幾(き) 君可(が)為(ため)尓(に)=限りなき君がために。寿命の無限な貴方の為に。
※於(お)る華盤(は)=折る花は。
※時しも王可(わか)ぬ=時しもわかぬ。必ずしも時節を区別していない。
867 紫濃(の)日とも登(と)遊(ゆ)へ尓(に)武蔵野濃(の)草盤(は)三(み)な可(が)ら哀(あはれ)と曾(ぞ)見る
※紫濃(の)=紫草(むらさきそう)の。
※日とも登(と)遊(ゆ)へ尓(に)=一本(ひともと)故に。一本であるが故に。
※三(み)な可(が)ら=ことごとく。
※あはれ=しみじみとかわいい。いとしい。
下絵は、「竹」の図から「梅」の図(その一)と変わる。『古今和歌集』の部立(構成)は、「春(二巻)・夏(一巻)・秋(二巻)・冬(一巻)・賀(一巻)・離別(一巻)・羇旅(一巻)・物名(一巻)・恋(五巻)・哀傷(一巻)・雑(二巻)・雑体(一巻)・大歌所御歌(一巻)」の二十巻構成で、その後の勅撰集の模範とされている。
この「四季花卉下絵古今集和歌巻」の下絵で描かれている「竹・梅・躑躅・蔦・下草(糸薄)」などについては、この『古今和歌集』の「四季(春・夏・秋・冬)」の区分のものではなく、冒頭に、「四君子に属する竹・梅を選び、年初の歳寒のイメージを託す。弐種の素材であるので歳寒二友」ともいうべき、「竹(冬)・梅(春)」、そして、それに続く、「躑躅(夏)・蔦(秋)」という展開のイメージのような雰囲気である。
いずれにしろ、ここで「竹(冬)」から「梅(春)」へとの場面転換(「季移り」)の図柄である。それに相応してのものなのかどうかは判然としないが、(下絵=竹図=863と864の二首 )と(下絵=梅図その一=866と867)との間に、次の一首(865)が省かれている。
その一首(865)を、その前(下絵=竹図=863と864の二首)と、その後(下絵=梅図その一=866と867)との間に挿入すると、次のとおりとなる。
(下絵=竹図)
863 わが上に露ぞ置くなる天の川とわたる舟のかいのしずくか(読人知らず)
(私の体が濡れているのは露が降りているのだそうだ。それならその露は天の川の渡し場を彦星が渡る舟の櫂から落ちた雫なのであろうか。)
864 思ふどちまどゐせる夜は唐錦たたまく惜しきものにぞありける(読人知らず)
(仲のいい者たちが車座に座って楽しいひとときを送っている夜は、立ち上がるのが本当に惜しいものだ。)
865 うれしきを何に包まむ唐衣袂ゆたかにたてと言はしも(読人知らず)
(こんなにたくさんある嬉しいことを何に包んで持って帰ろうか。着物の袖にしまえるように、大きく作ってくれと言っておくのだったなぁ。)
(下絵=梅図その一)
866 限りなき君がためにと折る花は時しもわかぬ物にぞありける(読人知らず)
(限りなき長寿のあなたのお祝いのために折り取った花は、季節に関係なく何時までも咲いている花でしたよ。)
867 紫のひともとゆゑに武蔵野の草はみながらあはれとぞ見る(読人知らず)
(紫草が一本あるために、武蔵野の草は、すべていとおしく見えることだなあ。)
(参考) 「四季花卉下絵古今集和歌巻」(竹・梅その一・梅その二)
「尾形光琳生誕三五〇周年記念 大琳派展―継承と変奏(東京国立博物館・読売新聞社編)」
所収「1-01 俵屋宗達下絵・本阿弥光悦筆 四季草花下絵古今和歌巻・重要文化財・畠山記念館蔵」彩箋墨書、三三・七×九一八・七
http://www.miho.or.jp/booth/html/artcon/00000074.htm

A図「梅下絵隆達節断簡」紙本墨書金銀泥 縦:33.8cm 横:89.9cm MIHO MUSEUM蔵
【 堺の高三隆達によって始められた「隆達節」は,慶長年間(1596~1615)に流行した歌謡で,この隆達節をおよそ百種をおさめた巻物が作られたのだが,今は諸所に分蔵されている。
この巻物の特徴は,料紙に肉筆による装飾を施すのではなく,木版の金銀泥刷によって梅蔦細竹太竹を表現している点である。本図はそのうちの梅の部分の断簡で,梅の他の部分はたとえば東京国立博物館に所蔵される。
巻末にあたる部分は京都民芸館の所蔵で,そこには,慶長10年(1605)9月,高三隆達自身が京の豪商として名高い茶屋又四郎にこの巻物一巻を贈った旨が記されている。
なお,俵屋宗達による金銀泥下絵巻物とこの木版金銀泥刷下絵巻物とは,深い関係があることは確かではあるが,宗達との直接的関係を断定するのは時期尚早とすべきであろう。 】
この紹介文の「東京国立博物館蔵」のものは、次のものである。
https://webarchives.tnm.jp/imgsearch/show/C0036766

B図「四季草花木版下絵隆達節小歌巻断簡」 画像番号:C0036766 32.9×81.0 東京国立博物館蔵
【 花卉摺絵隆達節断簡 伝角倉素庵 一幅 紙本金銀泥摺絵墨書 33.0×81.3 東京国立博物館蔵 】(『琳派―版と型の展開(町田市立国際版画美術館編)』)
https://www.jstage.jst.go.jp/article/tja1948/17/2/17_2_155/_pdf/-char/ja
【(14)慶長十年九月茶屋又一郎宛本
角倉素庵筆というが、現所蔵者・内容共に未詳。その断簡と思われるもの(十章)、現在、東京国立博物館保管。左の如くである。
8 たねとりてうへし。うへなはむさし野も。せはくやあらん。わかおもひ草
9 みるめ。はかりになみたちて。なるとふねかや。あハてこかるエ
10 枕の海ハ、なみたつはかり。さらはみるめの。ありもせて
11 あハぬうらみハつもれとも。見れハことの葉もなし
12 うらみあるこそたのみなれ。おもハぬ中は。ふらすふられす
36 物のしゆむなハ春のあめ。なをもしゆむなは。たひのひとりね
37 華に。あらしのふかはふけ。君の心の。よそへちらすは
38 ひとりねてふたり。ぬるよのありさまを。かたるな人に。なふまくら
39 見製ゆるとなさけ。あれかし夢にさへ。つれなのふりや。なふきみは
40 月はにこりの水にもやとる。かすならぬ身に。なさけあれきみ
(頭の数字は文緑二年百五十章本の歌詞番号) 】(「隆達小歌集の伝本について(浅野健二稿)」)
http://www.ccf.or.jp/jp/04collection/item_view.cfm?P_no=2245
【高三隆達〈たかさぶりゅうたつ・1527-1611〉は、堺の薬種商の家の生まれ。日蓮宗顕本寺(けんぽんじ・大阪府堺市)の僧となり、日長(にっちょう)と改める。庵室を自在院(じざいいん)といい、高三坊(たかさぶぼう)と称したが、やがて還俗。小歌の名手としての盛名を高め、隆達節(りゅうたつぶし)と呼ばれる新しい歌謡を民衆に広めた。伏見城の能舞台において、細川幽斎〈ほそかわゆうさい・1534-1610〉の鼓に合わせて歌い、豊臣秀吉〈とよとみひでよし・1537-98〉らの喝采を浴びたことは有名。書にも巧みで、自ら書写した「隆達節」(一巻・個人蔵)などが伝存する。さらに、本阿弥光悦〈ほんあみこうえつ・1558-1637〉周辺の紙師宗二(そうじ)調製の料紙(金銀雲母下絵)に角倉素庵〈すみのくらそあん・1571-1632〉が揮毫した「隆達節」(もとは一巻。断簡が東京国立博物館に収蔵)などもあり、その交友も広範囲に及んでいたことを推察する。書流系譜においては、牡丹花肖柏〈ぼたんかしょうはく・1443-1527〉を祖とする堺流に挙げられる。これは、隆達自作の小歌(=隆達節)を短冊形に書写したもの。かなりの能書で、手馴れた筆致である。文句の右横には、墨譜(曲節を明らかにするための点)がしるされる。隆達の遺墨は稀少で、この譜付けの一幅などは、尊貴な遺品といえよう。】
https://hosei.repo.nii.ac.jp/?action=pages_view_main&active_action=repository_view_main_item_detail&item_id=21363&item_no=1&page_id=13&block_id=83
↓
「角倉素庵と『方丈記』(小秋元段 稿)」
なお、「梅下絵隆達節断簡」(MIHO MUSEUM蔵)の紹介文で、「巻末にあたる部分は京都民芸館の所蔵で,そこには,慶長10年(1605)9月,高三隆達自身が京の豪商として名高い茶屋又四郎にこの巻物一巻を贈った旨が記されている」の「京都民芸館」ものは、次のものである。
http://drei-punkte.cocolog-nifty.com/blog/2018/10/2-fbf6.html

C図「花卉摺絵隆達節断簡」・京都民芸館蔵 (『琳派―版と型の展開(町田市立国際版画美術館編)』)
ここで、「本阿弥光悦略年譜」(『光悦……琳派の創始者(河野元昭編)』所収)の「慶長十年(一六〇五)」の項を見ると、次のような記載がある。
「慶長十年(一六〇五) 四八(歳) この年の紀年のある角倉素庵筆と伝える隆達節の巻物がある。四十八歳になったという手紙がある。この年の紀年をもつ八十嶋道除筆木版下絵『琵琶幷序』がある。この頃『蓮下絵和歌巻』(前半)を書くか。」
この「本阿弥光悦略年譜」に記載されている「この年の紀年のある角倉素庵筆と伝える隆達節の巻物がある」というのが、上記の【C図「花卉摺絵隆達節断簡」・京都民芸館蔵】を指しているように解せられる。
しかし、この【C図「花卉摺絵隆達節断簡」・京都民芸館蔵】が紹介されている『琳派―版と型の展開(町田市立国際版画美術館編)』(出品目録五)には、「伝角倉素庵筆」の記載はなく、同時に出品されていた【B図「四季草花木版下絵隆達節小歌巻断簡」・東京国立博物館蔵】(出品目録二)の「作者」欄に、「伝角倉素庵筆」の記載があり、この【B図「四季草花木版下絵隆達節小歌巻断簡」・東京国立博物館蔵】(出品目録二)と【C図「花卉摺絵隆達節断簡」・京都民芸館蔵】(出品目録五)と、さらに、【A図「梅下絵隆達節断簡」(MIHO MUSEUM蔵=「神慈秀明会」旧蔵)】とは、元々は一巻のものと解しての、「伝角倉素庵筆」としているのかも知れない。
http://kotenseki.nijl.ac.jp/biblio/200008233/viewer/11
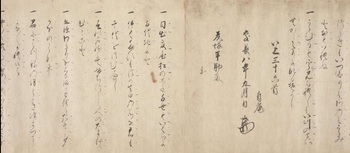
D図「初歌集」・著者:隆達・国文学研究資料館 貴重書・ 書誌ID:200008233
この【D図「初歌集」・著者:隆達・国文学研究資料館蔵】は、「高三隆達」の自筆筆とされており、この「自庵(隆達の号「自在院」の「自庵」)の署名・花押・紀年と宛名書き」は、
【C図「花卉摺絵隆達節断簡」・京都民芸館蔵】と同一であり、これらは、全て、「伝角倉素庵筆」ではなく、「高三隆達筆」と解するのが最も素直な理解のようにも思われる。
四季花卉下絵古今集和歌巻(その一) [光悦・宗達・素庵]
その一 竹

「尾形光琳生誕三五〇周年記念 大琳派展―継承と変奏(東京国立博物館・読売新聞社編)」
所収「1-01 俵屋宗達下絵・本阿弥光悦筆 四季草花下絵古今和歌巻・重要文化財・畠山記念館蔵」(「四季花卉下絵古今集和歌巻」=『光悦……琳派の創始者(河野元昭編)』所収「書画の二重奏への道……光悦書・宗達画和歌巻の展開(玉蟲敏子稿)」) 三三・七×九一八・七
題しらず
863 わが上に露ぞ置くなる天の川とわたる舟のかいのしずくか(読人知らず)
(私の体が濡れているのは露が降りているのだそうだ。それならその露は天の川の渡し場を彦星が渡る舟の櫂から落ちた雫なのであろうか。)
864 思ふどちまどゐせる夜は唐錦たたまく惜しきものにぞありける(読人知らず)
(仲のいい者たちが車座に座って楽しいひとときを送っている夜は、立ち上がるのが本当に惜しいものだ。)
釈文(揮毫上の書体)=(『書道芸術第十八巻 本阿弥光悦』)
863 我(わが)上尓(に)露曾(ぞ)を久(く)那類(なる)天河(あまのがわ)とわ多(た)る舟濃(の)可(か)い乃(の)し徒(づ)久(く)可(か)
※我(わが)上尓(に)=我が上に。私の体の上に。
※露曾(ぞ)を久(く)那類(なる)=露ぞ置くなる。露がおいているのだそうだ。
※天河(あまのがわ)とわ多(た)る=天の川とわたる。天の川の川門を渡る。
※舟濃(の) 可(か)い乃(の)し徒(づ)久(く)=舟(七夕の夜に彦星が乗る舟)の櫂の雫。
864 おもふど知(ち)園居(まどゐ)世流(せる)夜(よ)ハ(は)唐錦多々(たた)ま久(く)於(お)し支(き)物尓(に)曾(ぞ)有(あり)介流(ける)
※おもふど知(ち)=思い合っている者たち。
※園居(まどゐ)世流(せる)=丸く座っている。集会している。
※唐錦(からにしき)=布に関する意から「た(裁)つ」「お(織)る」などにかかる枕詞。
※多々(たた)ま久(く)於(お)し支(き)=立ち上がることが惜しい。
(周辺ノート)
『光悦……琳派の創始者(河野元昭編)』所収「書画の二重奏への道……光悦書・宗達画和歌巻の展開(玉蟲敏子稿)」では、「光悦書・宗達画和歌巻」の代表的なものとして、次の五巻を挙げている。
① 「四季花卉下絵古今集和歌巻」一巻、畠山記念館蔵、重要文化財
② 「鶴下絵三十六歌仙和歌巻」一巻、京都国立博物館蔵、重要文化財
③ 「鹿下絵新古今集和歌巻」一巻、MOA美術館、シアトル美術館ほか諸家分蔵
④ 「蓮下絵百人一首和歌巻」一巻、焼失を免れた断簡が東京国立博物館ほか諸家分蔵
➄ 「四季草花下絵千載集和歌巻」一巻、個人蔵
これらの五巻のうち、下記の三巻については、これまでに取り上げてきた。
② 「鶴下絵三十六歌仙和歌巻」一巻、京都国立博物館蔵、重要文化財
(『書道芸術第十八巻 本阿弥光悦』78-87=「鶴下絵三十六歌仙和歌巻」)
その一
https://yahan.blog.ss-blog.jp/2020-02-19
その三十九
https://yahan.blog.ss-blog.jp/2020-04-28
③ 「鹿下絵新古今集和歌巻」一巻、MOA美術館、シアトル美術館ほか諸家分蔵
(『書道芸術第十八巻 本阿弥光悦』88-103=「鹿下絵新古今和歌巻」)
その一
https://yahan.blog.ss-blog.jp/2020-05-05
その二十九
https://yahan.blog.ss-blog.jp/2020-07-10
➄ 「四季草花下絵千載集和歌巻」一巻、個人蔵
(『書道芸術第十八巻 本阿弥光悦』30-42=「四季花卉下絵千載和歌巻」)
その一
https://yahan.blog.ss-blog.jp/2020-10-06
その二十五
https://yahan.blog.ss-blog.jp/2020-11-17
今回取り上げるのは、【①「四季花卉下絵古今集和歌巻」一巻、畠山記念館蔵、重要文化財】(『書道芸術第十八巻 本阿弥光悦』70-77「四季草花下絵古今集和歌巻」)である。
【 この和歌巻は、書のほうからもっとものびのびと筆が運ばれていると評価され、確かに絵との関わりを見ると、書き手は下絵としての理解に徹し、『古今和歌集』巻十七歌上の巻頭から詞書・詠者名を省いて歌のみ十九首をほぼ七行程度の散らし書きで自在に連ねて行く。一首の単位はイメージのまとまりに対応しており、その特色は躑躅と糸薄を描いた箇所によく現れている。このようにほぼ一種類のイメージに和歌一首を割り当てる方法は色紙などの揮毫と同じであり、光悦は小品画で培った方法にならっているということができる。
「四季花卉下絵」と通称されるが、実際は樹木を含む竹・梅・躑躅・下草(糸薄)・蔦の五種の植物で構成され、このうち、竹と梅は中国の文人画の典型的な主題である四君子(しくんし)のうちに属している。下草を除く四種の素材が、共通してベルリン国立アジア美術館蔵「四季草花図和歌色紙帖」の上帖十八図に見出され、「新古今集」から選んだ和歌の部立によれば、春から夏のモティーフとして扱われている。この色紙帖の構成に基づいて①を見ると、竹梅は早春、躑躅は仲春に相応し、その次の蔦は、青葉茂れる夏から、実のなる秋にかけての題材として扱われているのがわかる。絵は冒頭に文人的な四君子に属する竹・梅を選び、年初の歳寒のイメージを託す。弐種の素材であるので歳寒二友というべきであろう。
】『光悦……琳派の創始者(河野元昭編)』所収「書画の二重奏への道……光悦書・宗達画和歌巻の展開(玉蟲敏子稿)」
(参考) 「四季花卉下絵古今集和歌巻」(竹・梅その一・梅その二)

「尾形光琳生誕三五〇周年記念 大琳派展―継承と変奏(東京国立博物館・読売新聞社編)」
所収「1-01 俵屋宗達下絵・本阿弥光悦筆 四季草花下絵古今和歌巻・重要文化財・畠山記念館蔵」彩箋墨書、三三・七×九一八・七
【 胡粉下地に金銀泥で、竹(冬)、梅(春)、躑躅(夏)、蔦(秋)を描いて下絵とし、その上に『古今和歌集』の十九首を散らし書きにした和歌巻である。右から左へ移動する巻物のもつ横長の連続的な画面の流れにのせて悠々と描かれたモティーフが、画面の中でドラマティックに展開する。竹の表面や梅・躑躅の幹など、滲みの効果をいかす「たらし込み」によって、量感や質感を見事に表現し、金銀の濃淡は、画面に情趣的な空間をつくりだしている。これに寛永の三筆の一人とされる光悦の豊麗秀潤な書が見事に調和し、絢爛豪華な美しさを生み出している。
巻末に「光悦」の黒文方印があり、光悦の書であることを示している。また「伊年」の朱文円印は「四季草花千載集和歌巻」、「蓮池水禽図」に捺されるものと同印で、宗達が法橋叙任以前、自作に用いた印であったと考えられている。同印を捺す作品には、やや作風を異なにするものもあり、これを工房印の一種とみる説もあるが、本作品については作風の優秀性からも宗達筆とするのに異論はなく、光悦の書体から、慶長末期頃の作と考えられている。(高橋祐次) 】「尾形光琳生誕三五〇周年記念 大琳派展―継承と変奏(東京国立博物館・読売新聞社編)」
所収「1-01 俵屋宗達下絵・本阿弥光悦筆 四季草花下絵古今和歌巻・重要文化財・畠山記念館蔵」
(再掲)
https://yahan.blog.ss-blog.jp/2018-07-13
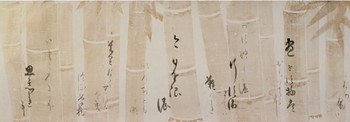
本阿弥光悦書「花卉摺絵新古今集和歌巻」(「竹図」・部分図)
時代 桃山~江戸時代(17世紀) 素材・技法 紙本木版金銀泥摺・墨書 一巻
サイズ 34.1×全長 907.0㎝ (MOA美術館蔵)
↑
http://www.moaart.or.jp/?collections=048
↓
【金銀泥(きんぎんでい)を用いて梅・藤・竹・勺薬(しゃくやく)・蔦の下絵を反復して摺り上げた版画下絵の料紙に、『新古今和歌集』の恋歌二十一首を選んで散らし書きした一巻である。全長九メートルにおよぶもので、巻末に篆書(てんしょ)体で「光悦」の黒印が捺されている。きわめて良質の料紙で、紙背には、伝統的な図様の松葉文様が見られ、紙継ぎ部分には、「紙師宗二」の縫合印が捺されている。大胆な構成による下絵に光悦の巧みな運筆が見事にマッチし、その書画一体の構成は独自の趣きのあるものとなっている。雲母(きら)などで文様を摺った料紙は、中国からの舶来品として平安時代すでに愛好されていたが、その美意識を当世風に再興させた光悦の斬新で洗練された感覚が、下絵の金銀泥絵に見られる。書風は、筆線の濃淡や太細の変化が著しく、装飾的である。】

下絵・俵屋宗達、書・本阿弥光悦 「花卉に蝶摺絵新古今集和歌巻」(一部)
桃山時代末期~江戸時代初期・17世紀初頭 岡田美術館蔵 「一巻 紙本金銀泥摺絵墨書 三三・三×九㈣一・七㎝」
↓
http://www.okada-museum.com/collection/japanese_painting/japanese_painting04.html
↑
http://salonofvertigo.blogspot.com/2015/02/rimpa.html
↓
【光悦と宗達の作品もいくつか展示されていて、中でも白眉は完本の「花卉に蝶摺絵新古今集和歌巻」。今に残る光悦の書の巻物はほとんどが断簡で、巻物として完全な形で残っているのは4本しかないそうです。宗達がデザインした色変わりの綺麗な料紙の上に流麗で美しい光悦の書。うっとりするほどの逸品です。】
この「花卉に蝶摺絵新古今集和歌巻」(岡田美術館蔵)も摺絵(金銀泥摺)なのである。しかし、冒頭の「花卉摺絵新古今集和歌巻」(MOA美術館蔵)に比して、こちらは、「下絵・俵屋宗達、書・本阿弥光悦」と、俵屋宗達の名が表示されている。表示の仕方としては、「書家」と「絵師」との「コラボレーション」(「響き合い」)という視点から、こちらの方をとりたい。

「尾形光琳生誕三五〇周年記念 大琳派展―継承と変奏(東京国立博物館・読売新聞社編)」
所収「1-01 俵屋宗達下絵・本阿弥光悦筆 四季草花下絵古今和歌巻・重要文化財・畠山記念館蔵」(「四季花卉下絵古今集和歌巻」=『光悦……琳派の創始者(河野元昭編)』所収「書画の二重奏への道……光悦書・宗達画和歌巻の展開(玉蟲敏子稿)」) 三三・七×九一八・七
題しらず
863 わが上に露ぞ置くなる天の川とわたる舟のかいのしずくか(読人知らず)
(私の体が濡れているのは露が降りているのだそうだ。それならその露は天の川の渡し場を彦星が渡る舟の櫂から落ちた雫なのであろうか。)
864 思ふどちまどゐせる夜は唐錦たたまく惜しきものにぞありける(読人知らず)
(仲のいい者たちが車座に座って楽しいひとときを送っている夜は、立ち上がるのが本当に惜しいものだ。)
釈文(揮毫上の書体)=(『書道芸術第十八巻 本阿弥光悦』)
863 我(わが)上尓(に)露曾(ぞ)を久(く)那類(なる)天河(あまのがわ)とわ多(た)る舟濃(の)可(か)い乃(の)し徒(づ)久(く)可(か)
※我(わが)上尓(に)=我が上に。私の体の上に。
※露曾(ぞ)を久(く)那類(なる)=露ぞ置くなる。露がおいているのだそうだ。
※天河(あまのがわ)とわ多(た)る=天の川とわたる。天の川の川門を渡る。
※舟濃(の) 可(か)い乃(の)し徒(づ)久(く)=舟(七夕の夜に彦星が乗る舟)の櫂の雫。
864 おもふど知(ち)園居(まどゐ)世流(せる)夜(よ)ハ(は)唐錦多々(たた)ま久(く)於(お)し支(き)物尓(に)曾(ぞ)有(あり)介流(ける)
※おもふど知(ち)=思い合っている者たち。
※園居(まどゐ)世流(せる)=丸く座っている。集会している。
※唐錦(からにしき)=布に関する意から「た(裁)つ」「お(織)る」などにかかる枕詞。
※多々(たた)ま久(く)於(お)し支(き)=立ち上がることが惜しい。
(周辺ノート)
『光悦……琳派の創始者(河野元昭編)』所収「書画の二重奏への道……光悦書・宗達画和歌巻の展開(玉蟲敏子稿)」では、「光悦書・宗達画和歌巻」の代表的なものとして、次の五巻を挙げている。
① 「四季花卉下絵古今集和歌巻」一巻、畠山記念館蔵、重要文化財
② 「鶴下絵三十六歌仙和歌巻」一巻、京都国立博物館蔵、重要文化財
③ 「鹿下絵新古今集和歌巻」一巻、MOA美術館、シアトル美術館ほか諸家分蔵
④ 「蓮下絵百人一首和歌巻」一巻、焼失を免れた断簡が東京国立博物館ほか諸家分蔵
➄ 「四季草花下絵千載集和歌巻」一巻、個人蔵
これらの五巻のうち、下記の三巻については、これまでに取り上げてきた。
② 「鶴下絵三十六歌仙和歌巻」一巻、京都国立博物館蔵、重要文化財
(『書道芸術第十八巻 本阿弥光悦』78-87=「鶴下絵三十六歌仙和歌巻」)
その一
https://yahan.blog.ss-blog.jp/2020-02-19
その三十九
https://yahan.blog.ss-blog.jp/2020-04-28
③ 「鹿下絵新古今集和歌巻」一巻、MOA美術館、シアトル美術館ほか諸家分蔵
(『書道芸術第十八巻 本阿弥光悦』88-103=「鹿下絵新古今和歌巻」)
その一
https://yahan.blog.ss-blog.jp/2020-05-05
その二十九
https://yahan.blog.ss-blog.jp/2020-07-10
➄ 「四季草花下絵千載集和歌巻」一巻、個人蔵
(『書道芸術第十八巻 本阿弥光悦』30-42=「四季花卉下絵千載和歌巻」)
その一
https://yahan.blog.ss-blog.jp/2020-10-06
その二十五
https://yahan.blog.ss-blog.jp/2020-11-17
今回取り上げるのは、【①「四季花卉下絵古今集和歌巻」一巻、畠山記念館蔵、重要文化財】(『書道芸術第十八巻 本阿弥光悦』70-77「四季草花下絵古今集和歌巻」)である。
【 この和歌巻は、書のほうからもっとものびのびと筆が運ばれていると評価され、確かに絵との関わりを見ると、書き手は下絵としての理解に徹し、『古今和歌集』巻十七歌上の巻頭から詞書・詠者名を省いて歌のみ十九首をほぼ七行程度の散らし書きで自在に連ねて行く。一首の単位はイメージのまとまりに対応しており、その特色は躑躅と糸薄を描いた箇所によく現れている。このようにほぼ一種類のイメージに和歌一首を割り当てる方法は色紙などの揮毫と同じであり、光悦は小品画で培った方法にならっているということができる。
「四季花卉下絵」と通称されるが、実際は樹木を含む竹・梅・躑躅・下草(糸薄)・蔦の五種の植物で構成され、このうち、竹と梅は中国の文人画の典型的な主題である四君子(しくんし)のうちに属している。下草を除く四種の素材が、共通してベルリン国立アジア美術館蔵「四季草花図和歌色紙帖」の上帖十八図に見出され、「新古今集」から選んだ和歌の部立によれば、春から夏のモティーフとして扱われている。この色紙帖の構成に基づいて①を見ると、竹梅は早春、躑躅は仲春に相応し、その次の蔦は、青葉茂れる夏から、実のなる秋にかけての題材として扱われているのがわかる。絵は冒頭に文人的な四君子に属する竹・梅を選び、年初の歳寒のイメージを託す。弐種の素材であるので歳寒二友というべきであろう。
】『光悦……琳派の創始者(河野元昭編)』所収「書画の二重奏への道……光悦書・宗達画和歌巻の展開(玉蟲敏子稿)」
(参考) 「四季花卉下絵古今集和歌巻」(竹・梅その一・梅その二)
「尾形光琳生誕三五〇周年記念 大琳派展―継承と変奏(東京国立博物館・読売新聞社編)」
所収「1-01 俵屋宗達下絵・本阿弥光悦筆 四季草花下絵古今和歌巻・重要文化財・畠山記念館蔵」彩箋墨書、三三・七×九一八・七
【 胡粉下地に金銀泥で、竹(冬)、梅(春)、躑躅(夏)、蔦(秋)を描いて下絵とし、その上に『古今和歌集』の十九首を散らし書きにした和歌巻である。右から左へ移動する巻物のもつ横長の連続的な画面の流れにのせて悠々と描かれたモティーフが、画面の中でドラマティックに展開する。竹の表面や梅・躑躅の幹など、滲みの効果をいかす「たらし込み」によって、量感や質感を見事に表現し、金銀の濃淡は、画面に情趣的な空間をつくりだしている。これに寛永の三筆の一人とされる光悦の豊麗秀潤な書が見事に調和し、絢爛豪華な美しさを生み出している。
巻末に「光悦」の黒文方印があり、光悦の書であることを示している。また「伊年」の朱文円印は「四季草花千載集和歌巻」、「蓮池水禽図」に捺されるものと同印で、宗達が法橋叙任以前、自作に用いた印であったと考えられている。同印を捺す作品には、やや作風を異なにするものもあり、これを工房印の一種とみる説もあるが、本作品については作風の優秀性からも宗達筆とするのに異論はなく、光悦の書体から、慶長末期頃の作と考えられている。(高橋祐次) 】「尾形光琳生誕三五〇周年記念 大琳派展―継承と変奏(東京国立博物館・読売新聞社編)」
所収「1-01 俵屋宗達下絵・本阿弥光悦筆 四季草花下絵古今和歌巻・重要文化財・畠山記念館蔵」
(再掲)
https://yahan.blog.ss-blog.jp/2018-07-13
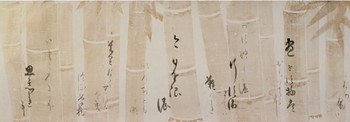
本阿弥光悦書「花卉摺絵新古今集和歌巻」(「竹図」・部分図)
時代 桃山~江戸時代(17世紀) 素材・技法 紙本木版金銀泥摺・墨書 一巻
サイズ 34.1×全長 907.0㎝ (MOA美術館蔵)
↑
http://www.moaart.or.jp/?collections=048
↓
【金銀泥(きんぎんでい)を用いて梅・藤・竹・勺薬(しゃくやく)・蔦の下絵を反復して摺り上げた版画下絵の料紙に、『新古今和歌集』の恋歌二十一首を選んで散らし書きした一巻である。全長九メートルにおよぶもので、巻末に篆書(てんしょ)体で「光悦」の黒印が捺されている。きわめて良質の料紙で、紙背には、伝統的な図様の松葉文様が見られ、紙継ぎ部分には、「紙師宗二」の縫合印が捺されている。大胆な構成による下絵に光悦の巧みな運筆が見事にマッチし、その書画一体の構成は独自の趣きのあるものとなっている。雲母(きら)などで文様を摺った料紙は、中国からの舶来品として平安時代すでに愛好されていたが、その美意識を当世風に再興させた光悦の斬新で洗練された感覚が、下絵の金銀泥絵に見られる。書風は、筆線の濃淡や太細の変化が著しく、装飾的である。】

下絵・俵屋宗達、書・本阿弥光悦 「花卉に蝶摺絵新古今集和歌巻」(一部)
桃山時代末期~江戸時代初期・17世紀初頭 岡田美術館蔵 「一巻 紙本金銀泥摺絵墨書 三三・三×九㈣一・七㎝」
↓
http://www.okada-museum.com/collection/japanese_painting/japanese_painting04.html
↑
http://salonofvertigo.blogspot.com/2015/02/rimpa.html
↓
【光悦と宗達の作品もいくつか展示されていて、中でも白眉は完本の「花卉に蝶摺絵新古今集和歌巻」。今に残る光悦の書の巻物はほとんどが断簡で、巻物として完全な形で残っているのは4本しかないそうです。宗達がデザインした色変わりの綺麗な料紙の上に流麗で美しい光悦の書。うっとりするほどの逸品です。】
この「花卉に蝶摺絵新古今集和歌巻」(岡田美術館蔵)も摺絵(金銀泥摺)なのである。しかし、冒頭の「花卉摺絵新古今集和歌巻」(MOA美術館蔵)に比して、こちらは、「下絵・俵屋宗達、書・本阿弥光悦」と、俵屋宗達の名が表示されている。表示の仕方としては、「書家」と「絵師」との「コラボレーション」(「響き合い」)という視点から、こちらの方をとりたい。
四季草花下絵千載集和歌巻(その二十五) [光悦・宗達・素庵]
(その二十五) 和歌巻(その二十五)

「光悦筆 四季草花宗達下絵和歌巻」(日本古典文学会・貴重本刊行会・日野原家蔵一巻)
96 あかなくにちりぬる花のおもかげや風に知られぬさくらなるらむ(覚盛法師)
(花に飽きることがない心から、すでに散ってしまった桜を面影に抱き続けて来たが、それは風に知られぬ桜なのだろう。)
釈文(揮毫上の書体)=(『書道芸術第十八巻 本阿弥光悦』)
阿可(あか)な久(く)尓(に)知里(ちり)ぬるハ(は)な乃(の)於(お)も影や可勢(かぜ)尓(に)しら連(れ)ぬ桜なるら無(む)
※阿可(あか)な久(く)尓(に)=飽かなくに。飽きることながないのに。
※可勢(かぜ)尓(に)しら連(れ)ぬ=風に知られぬ。風を擬人化した。
【 覚盛(かくじょう) 生没年未詳 比叡山阿闍梨
建久二年(一一九二)『若宮社歌合』に参加。『三十六人十八番』(散佚) の撰者。千載初出。】
(『新日本古典文学大系10 千載和歌集』)
(参考) 『無名抄』(鴨長明著)の「覚盛法師」周辺
【 (歌をつくろへば悪事)
覚盛法師のいはく、「歌は、荒々しく、止めもあはぬやうなる、一つの姿なり。それをあまり細工(さいく)みて、とかくすれば、果てにはまれまれ物めかしかりつる所さへ失せて、何にてもなき小物(こもの)になるなり」と申し、「さも」と聞こゆ。
季経卿歌に
年を経て返しもやらぬ小山田は種貸す人もあらじとぞ思ふ
この歌、艶なるかたこそ無けれど、一節(ひとふし)いひて、さる体の歌とみ給へしを、年経て後、彼の集の中に侍るを見れば、
賤(しづ)の男(を)が返しもやらぬ小山田にさのみはいかが種を貸すべき
これは直されたりけるにや。いみじうけ劣りて思え侍るなり。よくよく心すべきことにこそ。
(校注)=『日本古典文学大系65 歌論集・能楽論集(久松潜一・西尾実校注)』
※荒々しく、止めもあはぬやうなる=「荒削りで止めることができないような」の意か。「拉鬼体(らきてい)」(藤原定家がたてた和歌の十体の一つ。強いしらべの歌。のち、能楽の風体にも用いられた語。拉鬼様。)
※細工(さいく)みて=技巧を凝らして。
※まれまれ物めかし=たまたま物々しかった箇所。
※小物(こもの)=「つまらない物」の意か。
※さも=「尤も」。
※一節(ひとふし)いひて、さる体の歌=「趣向面白く表現してあって、そういう風体の歌と見ておりましたが」の意。「さる体の歌」は「誹諧歌」をさすか。 】
(参考メモ)「四季草花下絵千載集和歌巻」と「蓮下絵百人一首和歌巻」の「大虚庵光悦」(花押)周辺
この「四季草花下絵千載集和歌巻」(個人蔵)の巻末の署名は「大虚庵光悦」(花押)で、二行に分けて書かれている。この最終場面の署名(花押)が同じ和歌巻に、「蓮下絵百人一首和歌巻」(焼失を免れた断簡が東京国立博物館ほか諸家分蔵)がある。
この「➄四季草花下絵千載集和歌巻」と「④蓮下絵百人一首和歌巻」とを比較して、『光悦……琳派の創始者(河野元昭編)』所収「書画の二重奏への道……光悦書・宗達画和歌巻の展開(玉蟲敏子稿)」で、「➄は④とともに色替わり料紙を用い、しかも『大虚庵』の署名である点で製品としての体裁が共通しており、製作年や製作背景がかなり近接していることを類推させる」としている。
そして、この「書画の二重奏への道……光悦書・宗達画和歌巻の展開(玉蟲敏子稿)」の末尾で、次のように記している。
【 本阿弥光悦が、徳川家康から拝領した鷹峯の地所に「大虚庵」という庵居を営むのは、元和元年(一六一五)以降である。その頃の制作が確実な「蓮下絵和歌巻」のしばらく後に製作されたとおぼしい寛永年紀の書画巻は、絹本に金銀摺絵をほどこす別な表現に変わっていく。したがって金銀泥絵の色紙や和歌巻の制作された慶長七年前後からの十五年余りこそが、本阿弥光悦と、いずれ俵屋宗達と呼ばれていく個性ある下絵作者が繰り広げた至福の時であったといえるのである。それは、関ヶ原から元和偃武にいたる時期である。元和元年を指標として琳派四百年といわれるものの、本当の意味で琳派の揺籃といえるこの時期が、それから程なくして終了したとするならば、芸術の歴史にとって何と皮肉なことであろうか。 】『光悦……琳派の創始者(河野元昭編)』所収「書画の二重奏への道……光悦書・宗達画和歌巻の展開(玉蟲敏子稿)」

(「④蓮下絵百人一首和歌巻」末尾「順徳院(一首)」と「光悦署名(花押)」)
これは、「④蓮下絵百人一首和歌巻」末尾の「順徳院」の一首に続く「大虚庵/光悦(花押)」であるが、ここには、「➄四季草花下絵千載集和歌巻」に押印されている、次の「伊年」印は押印されていない。

(「➄四季草花下絵千載集和歌巻」末尾の「光悦署名(花押)」に続く「伊年」印)
ここで、この「伊年」印を取り上げた最初のものは、次のアドレスのものなのかも知れない。
https://yahan.blog.ss-blog.jp/2018-01-27
それから、この「➄四季草花下絵千載集和歌巻」の冒頭の「伊年」印に触れての、その期間は、二年余というタイムスパンがある。
https://yahan.blog.ss-blog.jp/2020-10-06
この二年有余のタイムスパンは、それこそが、「本阿弥光悦と、いずれ俵屋宗達と呼ばれていく個性ある下絵作者が繰り広げた至福の時」の、それを執拗に求め続けた一つのプロセス的な記録でもある。
(追記メモ)
この「伊年」印については、下記のアドレスなどが詳しい。そして、この「伊年」印=「俵屋」(「俵屋宗達工房」)のブランドマークとして、「俵屋宗達」個人の創作というよりは、「俵屋宗達工房」の協同(共同))創作の成果品として意味合いを強くしている。
https://www.kyohaku.go.jp/jp/dictio/pdf/dic_163.pdf
このアドレスで「伊年」印の最高傑作作品が紹介されているのだが、この作品は、「宗達のすぐれた弟子のひとりが描いた」ものとして紹介されている。
https://www.kintetsu-g-hd.co.jp/culture/yamato/shuppan/binotayori/pdf/91/1990_91_3_2p.pdf
このアドレスの「伊年」印については、「俵屋宗雪、伊年、宗達弟、仕賀州太守世白宗達画多雪之筆也」などが紹介されている。
これらのアドレスで紹介されている「伊年」印の周辺については、次のことと大きく関連しているように思われる。
【 従来の光悦書・宗達画和歌巻類の研究は、リストアップしたこれらの作品群を画の側から宗達・非宗達に分けて後者をはずし、次に前者の時系列上の位置を確定していく編年作業を主に行ってきた。ここではその成果を踏まえつつも、制作現場における書と画の協同性に考慮し、かつ巻物という形式をより重視する立場をとる。というのも、巻物は書写形式が規制される枠をもつ色紙・短冊・扇面とは異なり、左右に連続する開放的な空間を有し、書と画とがそれぞれストーリーをもち、相互に干渉し合いながら、一定の方向に連続する時空間を作り上げていくところに特色があるからだ。 】『光悦……琳派の創始者(河野元昭編)』所収「書画の二重奏への道……光悦書・宗達画和歌巻の展開(玉蟲敏子稿)」
この「宗達・非宗達」の区分けの一つとして、極論をすると、「『伊年』印=非宗達、『無印』=宗達」という見方も、一つの目安となってくる。ここで、光悦書・宗達画和歌巻類の鑑賞というのは、「光悦(光悦とその一門)と宗達(宗達とその一門)との『協同創作作品』という、「コラボレーション」(美術の世界では、作品の競作とか協力関係を意味し、複数の作家が一つの表現に関わることで、そこに起きる微妙なずれや摩擦が生み出す特有な空間を、従来のひとりの作家に限定された創作行為とは違った開かれた方法として、評価されている)
的視野が必須となってくる。
そして、このことは「『個』としてのアーティストの『肉筆画』と「『全(集団)としてのアーティストの『摺絵・木版画など』」との「個と全(集団)との相互浸透」などと係わってくる。
【 巻物という長大な画面を受け持つ仕事であるゆえに描き手の感覚が現れやすく、それが「個」の発露につながったのだと。そうした「個」のあり方を過度に強調して集団制作にまで敷衍し、個単位に分解することはかなり危険である。見え隠れする個性と俵屋という集団の構造を緩やかにとらえる視点とスタンスを保つことが、結局のところ、この近世初頭に生まれた稀有な造形活動の全体を視野に収めていく上で適切な構え方なのではないかと思われる。 】『光悦……琳派の創始者(河野元昭編)』所収「書画の二重奏への道……光悦書・宗達画和歌巻の展開(玉蟲敏子稿)」
この「個と全(集団)との相互浸透」という視点とスタンスから、今回の「四季草花下絵千載集和歌巻」(個人蔵)を、「書画二重奏への道」の「画」の面からのみ見て行くと、「四季の花や木に月・千鳥などの季節の景物を取り合わせ、平安時代以来の金銀泥下絵巻物や大和絵系景物画と重なる素材を選択している。」(玉蟲・前掲書)
そして、全体として「平明」で、「集団的な生産組織によるもの作りゆえに、俵屋内部のさまざまな個性をもった作り手も画房としての一定の様式を一様に担い」、この和歌巻に用いられた松林や薄のモティーフは、『平家納経』の補修部分に認められ」、全体として、「俵屋の標準的な共通様式の発展上において捉えられる。」(玉蟲・前掲書)
さらに続ければ、光悦と宗達(そして「宗達工房」)の「書画二重奏の道」、それは、同時に、「詩(和歌)・書・画三重奏の道」、それはまた、「光悦・宗達・素庵(角倉素庵)の三重奏の道」でもあったのだが、慶長七年(一六〇二・光悦=四十五歳)前後にスタートとして、素庵が宿痾によって「嵯峨に退隠」した元和五年(一六一九、光悦=六十二歳)前後にゴールとなった、十五年余りの「走馬灯」でもあった。
その後も、寛永年紀を有する「光悦書画和歌巻」は制作が続けられるが、それは、かっての「光悦と宗達(そして「宗達工房」)」、あるいは、「光悦・宗達・素庵」とが火花を散らした「書画二重奏の道」、あるいは、「詩(和歌)・書・画三重奏の道」とは、違った世界のものに変わり果ててしまったということなのであろう。
そして、このことを、「元和元年(一六一五=光悦の「鷹峯移住」)を指標とした琳派四百年といわれるものの、本当の意味での琳派の揺籃といえるこの時期が、それから程なくして終了した(元和五年=一六一九)とするならば、芸術の歴史にとって何と皮肉なことであろうか」(玉蟲・前掲書)という指摘が重みを有してくる。

「光悦筆 四季草花宗達下絵和歌巻」(日本古典文学会・貴重本刊行会・日野原家蔵一巻)
96 あかなくにちりぬる花のおもかげや風に知られぬさくらなるらむ(覚盛法師)
(花に飽きることがない心から、すでに散ってしまった桜を面影に抱き続けて来たが、それは風に知られぬ桜なのだろう。)
釈文(揮毫上の書体)=(『書道芸術第十八巻 本阿弥光悦』)
阿可(あか)な久(く)尓(に)知里(ちり)ぬるハ(は)な乃(の)於(お)も影や可勢(かぜ)尓(に)しら連(れ)ぬ桜なるら無(む)
※阿可(あか)な久(く)尓(に)=飽かなくに。飽きることながないのに。
※可勢(かぜ)尓(に)しら連(れ)ぬ=風に知られぬ。風を擬人化した。
【 覚盛(かくじょう) 生没年未詳 比叡山阿闍梨
建久二年(一一九二)『若宮社歌合』に参加。『三十六人十八番』(散佚) の撰者。千載初出。】
(『新日本古典文学大系10 千載和歌集』)
(参考) 『無名抄』(鴨長明著)の「覚盛法師」周辺
【 (歌をつくろへば悪事)
覚盛法師のいはく、「歌は、荒々しく、止めもあはぬやうなる、一つの姿なり。それをあまり細工(さいく)みて、とかくすれば、果てにはまれまれ物めかしかりつる所さへ失せて、何にてもなき小物(こもの)になるなり」と申し、「さも」と聞こゆ。
季経卿歌に
年を経て返しもやらぬ小山田は種貸す人もあらじとぞ思ふ
この歌、艶なるかたこそ無けれど、一節(ひとふし)いひて、さる体の歌とみ給へしを、年経て後、彼の集の中に侍るを見れば、
賤(しづ)の男(を)が返しもやらぬ小山田にさのみはいかが種を貸すべき
これは直されたりけるにや。いみじうけ劣りて思え侍るなり。よくよく心すべきことにこそ。
(校注)=『日本古典文学大系65 歌論集・能楽論集(久松潜一・西尾実校注)』
※荒々しく、止めもあはぬやうなる=「荒削りで止めることができないような」の意か。「拉鬼体(らきてい)」(藤原定家がたてた和歌の十体の一つ。強いしらべの歌。のち、能楽の風体にも用いられた語。拉鬼様。)
※細工(さいく)みて=技巧を凝らして。
※まれまれ物めかし=たまたま物々しかった箇所。
※小物(こもの)=「つまらない物」の意か。
※さも=「尤も」。
※一節(ひとふし)いひて、さる体の歌=「趣向面白く表現してあって、そういう風体の歌と見ておりましたが」の意。「さる体の歌」は「誹諧歌」をさすか。 】
(参考メモ)「四季草花下絵千載集和歌巻」と「蓮下絵百人一首和歌巻」の「大虚庵光悦」(花押)周辺
この「四季草花下絵千載集和歌巻」(個人蔵)の巻末の署名は「大虚庵光悦」(花押)で、二行に分けて書かれている。この最終場面の署名(花押)が同じ和歌巻に、「蓮下絵百人一首和歌巻」(焼失を免れた断簡が東京国立博物館ほか諸家分蔵)がある。
この「➄四季草花下絵千載集和歌巻」と「④蓮下絵百人一首和歌巻」とを比較して、『光悦……琳派の創始者(河野元昭編)』所収「書画の二重奏への道……光悦書・宗達画和歌巻の展開(玉蟲敏子稿)」で、「➄は④とともに色替わり料紙を用い、しかも『大虚庵』の署名である点で製品としての体裁が共通しており、製作年や製作背景がかなり近接していることを類推させる」としている。
そして、この「書画の二重奏への道……光悦書・宗達画和歌巻の展開(玉蟲敏子稿)」の末尾で、次のように記している。
【 本阿弥光悦が、徳川家康から拝領した鷹峯の地所に「大虚庵」という庵居を営むのは、元和元年(一六一五)以降である。その頃の制作が確実な「蓮下絵和歌巻」のしばらく後に製作されたとおぼしい寛永年紀の書画巻は、絹本に金銀摺絵をほどこす別な表現に変わっていく。したがって金銀泥絵の色紙や和歌巻の制作された慶長七年前後からの十五年余りこそが、本阿弥光悦と、いずれ俵屋宗達と呼ばれていく個性ある下絵作者が繰り広げた至福の時であったといえるのである。それは、関ヶ原から元和偃武にいたる時期である。元和元年を指標として琳派四百年といわれるものの、本当の意味で琳派の揺籃といえるこの時期が、それから程なくして終了したとするならば、芸術の歴史にとって何と皮肉なことであろうか。 】『光悦……琳派の創始者(河野元昭編)』所収「書画の二重奏への道……光悦書・宗達画和歌巻の展開(玉蟲敏子稿)」

(「④蓮下絵百人一首和歌巻」末尾「順徳院(一首)」と「光悦署名(花押)」)
これは、「④蓮下絵百人一首和歌巻」末尾の「順徳院」の一首に続く「大虚庵/光悦(花押)」であるが、ここには、「➄四季草花下絵千載集和歌巻」に押印されている、次の「伊年」印は押印されていない。

(「➄四季草花下絵千載集和歌巻」末尾の「光悦署名(花押)」に続く「伊年」印)
ここで、この「伊年」印を取り上げた最初のものは、次のアドレスのものなのかも知れない。
https://yahan.blog.ss-blog.jp/2018-01-27
それから、この「➄四季草花下絵千載集和歌巻」の冒頭の「伊年」印に触れての、その期間は、二年余というタイムスパンがある。
https://yahan.blog.ss-blog.jp/2020-10-06
この二年有余のタイムスパンは、それこそが、「本阿弥光悦と、いずれ俵屋宗達と呼ばれていく個性ある下絵作者が繰り広げた至福の時」の、それを執拗に求め続けた一つのプロセス的な記録でもある。
(追記メモ)
この「伊年」印については、下記のアドレスなどが詳しい。そして、この「伊年」印=「俵屋」(「俵屋宗達工房」)のブランドマークとして、「俵屋宗達」個人の創作というよりは、「俵屋宗達工房」の協同(共同))創作の成果品として意味合いを強くしている。
https://www.kyohaku.go.jp/jp/dictio/pdf/dic_163.pdf
このアドレスで「伊年」印の最高傑作作品が紹介されているのだが、この作品は、「宗達のすぐれた弟子のひとりが描いた」ものとして紹介されている。
https://www.kintetsu-g-hd.co.jp/culture/yamato/shuppan/binotayori/pdf/91/1990_91_3_2p.pdf
このアドレスの「伊年」印については、「俵屋宗雪、伊年、宗達弟、仕賀州太守世白宗達画多雪之筆也」などが紹介されている。
これらのアドレスで紹介されている「伊年」印の周辺については、次のことと大きく関連しているように思われる。
【 従来の光悦書・宗達画和歌巻類の研究は、リストアップしたこれらの作品群を画の側から宗達・非宗達に分けて後者をはずし、次に前者の時系列上の位置を確定していく編年作業を主に行ってきた。ここではその成果を踏まえつつも、制作現場における書と画の協同性に考慮し、かつ巻物という形式をより重視する立場をとる。というのも、巻物は書写形式が規制される枠をもつ色紙・短冊・扇面とは異なり、左右に連続する開放的な空間を有し、書と画とがそれぞれストーリーをもち、相互に干渉し合いながら、一定の方向に連続する時空間を作り上げていくところに特色があるからだ。 】『光悦……琳派の創始者(河野元昭編)』所収「書画の二重奏への道……光悦書・宗達画和歌巻の展開(玉蟲敏子稿)」
この「宗達・非宗達」の区分けの一つとして、極論をすると、「『伊年』印=非宗達、『無印』=宗達」という見方も、一つの目安となってくる。ここで、光悦書・宗達画和歌巻類の鑑賞というのは、「光悦(光悦とその一門)と宗達(宗達とその一門)との『協同創作作品』という、「コラボレーション」(美術の世界では、作品の競作とか協力関係を意味し、複数の作家が一つの表現に関わることで、そこに起きる微妙なずれや摩擦が生み出す特有な空間を、従来のひとりの作家に限定された創作行為とは違った開かれた方法として、評価されている)
的視野が必須となってくる。
そして、このことは「『個』としてのアーティストの『肉筆画』と「『全(集団)としてのアーティストの『摺絵・木版画など』」との「個と全(集団)との相互浸透」などと係わってくる。
【 巻物という長大な画面を受け持つ仕事であるゆえに描き手の感覚が現れやすく、それが「個」の発露につながったのだと。そうした「個」のあり方を過度に強調して集団制作にまで敷衍し、個単位に分解することはかなり危険である。見え隠れする個性と俵屋という集団の構造を緩やかにとらえる視点とスタンスを保つことが、結局のところ、この近世初頭に生まれた稀有な造形活動の全体を視野に収めていく上で適切な構え方なのではないかと思われる。 】『光悦……琳派の創始者(河野元昭編)』所収「書画の二重奏への道……光悦書・宗達画和歌巻の展開(玉蟲敏子稿)」
この「個と全(集団)との相互浸透」という視点とスタンスから、今回の「四季草花下絵千載集和歌巻」(個人蔵)を、「書画二重奏への道」の「画」の面からのみ見て行くと、「四季の花や木に月・千鳥などの季節の景物を取り合わせ、平安時代以来の金銀泥下絵巻物や大和絵系景物画と重なる素材を選択している。」(玉蟲・前掲書)
そして、全体として「平明」で、「集団的な生産組織によるもの作りゆえに、俵屋内部のさまざまな個性をもった作り手も画房としての一定の様式を一様に担い」、この和歌巻に用いられた松林や薄のモティーフは、『平家納経』の補修部分に認められ」、全体として、「俵屋の標準的な共通様式の発展上において捉えられる。」(玉蟲・前掲書)
さらに続ければ、光悦と宗達(そして「宗達工房」)の「書画二重奏の道」、それは、同時に、「詩(和歌)・書・画三重奏の道」、それはまた、「光悦・宗達・素庵(角倉素庵)の三重奏の道」でもあったのだが、慶長七年(一六〇二・光悦=四十五歳)前後にスタートとして、素庵が宿痾によって「嵯峨に退隠」した元和五年(一六一九、光悦=六十二歳)前後にゴールとなった、十五年余りの「走馬灯」でもあった。
その後も、寛永年紀を有する「光悦書画和歌巻」は制作が続けられるが、それは、かっての「光悦と宗達(そして「宗達工房」)」、あるいは、「光悦・宗達・素庵」とが火花を散らした「書画二重奏の道」、あるいは、「詩(和歌)・書・画三重奏の道」とは、違った世界のものに変わり果ててしまったということなのであろう。
そして、このことを、「元和元年(一六一五=光悦の「鷹峯移住」)を指標とした琳派四百年といわれるものの、本当の意味での琳派の揺籃といえるこの時期が、それから程なくして終了した(元和五年=一六一九)とするならば、芸術の歴史にとって何と皮肉なことであろうか」(玉蟲・前掲書)という指摘が重みを有してくる。
四季草花下絵千載集和歌巻(その二十四) [光悦・宗達・素庵]
(その二十四) 和歌巻(その二十四)

「光悦筆 四季草花宗達下絵和歌巻」(日本古典文学会・貴重本刊行会・日野原家蔵一巻)
95 ちる花を身にかふばかり思へどもかなはで年の老ひにけるかな(道因法師)
(散る花を惜しむあまり、わが身にかえてもとひたすら思い続けて来たが、それにもかなわず、年ごとに花は散り、わが齢も老いてしまったことだよ。)
釈文(揮毫上の書体)=(『書道芸術第十八巻 本阿弥光悦』)
地(ち)るハ(は)なを見尓(に)可(か)ふハ(ば)可利(かり)思へども可那ハ天(かなはで)年濃(の)老(おい)尓(に)介(け)る可(か)な
※地(ち)るハ(は)な=散る花。
※見尓(に)可(か)ふハ(ば)可利(かり=身にかふばかり。身にかえても。
※可那ハ天(かなはで)=(散る花と命を引き換えにすることも)できずに。
http://www.asahi-net.or.jp/~sg2h-ymst/yamatouta/sennin/douin.html
【 道因(どういん) 寛治四(1090)~没年未詳 俗名:藤原敦頼(あつより)
藤原北家高藤の末裔。治部丞清孝の息子。母は長門守藤原孝範女。子に敦中ほかがいる。
従五位上右馬助に至る。承安二年(1172)三月、藤原清輔が催した暮春白河尚歯会和歌に参加、この時「散位敦頼八十三歳」と記録されている(古今著聞集では八十四)。その後まもなく出家したか。歌壇での活動は主に晩年から見られ、俊恵の歌林苑の会衆の一人であった。永暦元年(1160)、太皇太后宮大進清輔歌合、嘉応二年(1170)の左衛門督実国歌合、安元元年(1175)及び治承三年(1179)の右大臣兼実歌合、治承二年(1178)の別雷社歌合などに出詠。また承安二年(1172)には広田社歌合を勧進した。
鴨長明『無名抄』には、歌への執心深く、秀歌を得ることを祈って住吉神社に月参したとある。没後、千載集に二十首もの歌を採られたが、これは最初十八首だったのを、編者藤原俊成の夢に現れ涙を流して喜んだのを俊成が憐れがり、さらに二首加えたものという(『無名抄』)。『歌仙落書』には歌仙として六首の歌を採られている。同書評に「風体義理を先としたるやうなれども、すがたすてたるにあらず。すべて上手なるべし」とある。小倉百人一首にも歌を採られている。私撰集『現存集』を撰したが、散佚した。千載集初出。勅撰入集四十首。 】
(参考) 『無名抄』(鴨長明著)の「道因法師」周辺
https://polygondrill.com/firstkaruta/list/hi082
(道因歌に志深事)
この道に心ざし深かりしことは、道因入道並びなき者なり。
七八十になるまで「秀歌詠ませ給へ」と祈らんため、徒歩(かち)より住吉へ月詣でしたる、いとありがたきことなり。
ある歌合に、清輔判者にて、道因が歌を負かしたりければ、わざと判者のもとにまうでて、まめやかに涙を流しつつ、泣き恨みければ
亭主、言はん方なく、「かばかりの大事にこそ逢はざりつれ」とぞ、語られける。
九十ばかりになりては、耳などもおぼろなりけるにや
会のときはことさらに講師の座の際(きわ)に分け寄りて、脇許(わきもと)につぶと添ひ居て、みづはさせる姿に耳を傾(かたぶ)けつつ
他事なく聞きける気色など なほざりのこととは見えざりき。
千載集撰ばれ侍りし事は、かの入道失せて後のことなり。
されど、亡き後にも、「さしも道に心ざし深かりし者なり」とて、優して十八首を入れられたりけるに
夢のうちに来たりて、涙を落しつつ、喜び言ふと見給ひたりければ
ことにあはれがりて、今二首を加へて二十首になされたりけるとぞ。
しかるべかりけることにこそ。
(大意)
この(歌の)道に志が深いことにかけては、道因入道の並ぶものはいない。
七、八十になるまで「素晴らしい歌を詠ませてくださいませ」と祈るために
徒歩で、住吉大社(大阪)まで、毎月、月詣でした。
まことに、めったにいない人である。
ある歌合に、藤原清輔が判者で道因の歌を負けとしたとき、わざわざ清輔のもとにやってきて、本当に涙を流して泣き恨んだので
清輔は何とも言いようがなく、「これほど大変な目にあったことはない」と言ったといわれている。
九十歳になって、耳などもはっきりと聞こえなくなると
歌会のときなど、とりわけ講師の席の側に分け行って、その脇に寄り添いひどく年老いた姿で耳を傾けつつ
よそ事などに気をとられることなく聞いている様子などは、いい加減なことのようには見えなかった。
藤原俊成さまが『千載集』に選ばれたときには、すでに道因入道の亡くなくなってからのことであった。
しかし、亡き後でも、「本当に歌の道に志深かった者であった」と評価されて十八首を入れられた。
すると俊成さまの夢の中に道因が来て、涙を流し、うれしく思う気持ちを言えば、
俊成さまはもっとあわれに思われて、もう二首加えて、二十首になされたとのことだ。
まことにそうあるべき事である。

「光悦筆 四季草花宗達下絵和歌巻」(日本古典文学会・貴重本刊行会・日野原家蔵一巻)
95 ちる花を身にかふばかり思へどもかなはで年の老ひにけるかな(道因法師)
(散る花を惜しむあまり、わが身にかえてもとひたすら思い続けて来たが、それにもかなわず、年ごとに花は散り、わが齢も老いてしまったことだよ。)
釈文(揮毫上の書体)=(『書道芸術第十八巻 本阿弥光悦』)
地(ち)るハ(は)なを見尓(に)可(か)ふハ(ば)可利(かり)思へども可那ハ天(かなはで)年濃(の)老(おい)尓(に)介(け)る可(か)な
※地(ち)るハ(は)な=散る花。
※見尓(に)可(か)ふハ(ば)可利(かり=身にかふばかり。身にかえても。
※可那ハ天(かなはで)=(散る花と命を引き換えにすることも)できずに。
http://www.asahi-net.or.jp/~sg2h-ymst/yamatouta/sennin/douin.html
【 道因(どういん) 寛治四(1090)~没年未詳 俗名:藤原敦頼(あつより)
藤原北家高藤の末裔。治部丞清孝の息子。母は長門守藤原孝範女。子に敦中ほかがいる。
従五位上右馬助に至る。承安二年(1172)三月、藤原清輔が催した暮春白河尚歯会和歌に参加、この時「散位敦頼八十三歳」と記録されている(古今著聞集では八十四)。その後まもなく出家したか。歌壇での活動は主に晩年から見られ、俊恵の歌林苑の会衆の一人であった。永暦元年(1160)、太皇太后宮大進清輔歌合、嘉応二年(1170)の左衛門督実国歌合、安元元年(1175)及び治承三年(1179)の右大臣兼実歌合、治承二年(1178)の別雷社歌合などに出詠。また承安二年(1172)には広田社歌合を勧進した。
鴨長明『無名抄』には、歌への執心深く、秀歌を得ることを祈って住吉神社に月参したとある。没後、千載集に二十首もの歌を採られたが、これは最初十八首だったのを、編者藤原俊成の夢に現れ涙を流して喜んだのを俊成が憐れがり、さらに二首加えたものという(『無名抄』)。『歌仙落書』には歌仙として六首の歌を採られている。同書評に「風体義理を先としたるやうなれども、すがたすてたるにあらず。すべて上手なるべし」とある。小倉百人一首にも歌を採られている。私撰集『現存集』を撰したが、散佚した。千載集初出。勅撰入集四十首。 】
(参考) 『無名抄』(鴨長明著)の「道因法師」周辺
https://polygondrill.com/firstkaruta/list/hi082
(道因歌に志深事)
この道に心ざし深かりしことは、道因入道並びなき者なり。
七八十になるまで「秀歌詠ませ給へ」と祈らんため、徒歩(かち)より住吉へ月詣でしたる、いとありがたきことなり。
ある歌合に、清輔判者にて、道因が歌を負かしたりければ、わざと判者のもとにまうでて、まめやかに涙を流しつつ、泣き恨みければ
亭主、言はん方なく、「かばかりの大事にこそ逢はざりつれ」とぞ、語られける。
九十ばかりになりては、耳などもおぼろなりけるにや
会のときはことさらに講師の座の際(きわ)に分け寄りて、脇許(わきもと)につぶと添ひ居て、みづはさせる姿に耳を傾(かたぶ)けつつ
他事なく聞きける気色など なほざりのこととは見えざりき。
千載集撰ばれ侍りし事は、かの入道失せて後のことなり。
されど、亡き後にも、「さしも道に心ざし深かりし者なり」とて、優して十八首を入れられたりけるに
夢のうちに来たりて、涙を落しつつ、喜び言ふと見給ひたりければ
ことにあはれがりて、今二首を加へて二十首になされたりけるとぞ。
しかるべかりけることにこそ。
(大意)
この(歌の)道に志が深いことにかけては、道因入道の並ぶものはいない。
七、八十になるまで「素晴らしい歌を詠ませてくださいませ」と祈るために
徒歩で、住吉大社(大阪)まで、毎月、月詣でした。
まことに、めったにいない人である。
ある歌合に、藤原清輔が判者で道因の歌を負けとしたとき、わざわざ清輔のもとにやってきて、本当に涙を流して泣き恨んだので
清輔は何とも言いようがなく、「これほど大変な目にあったことはない」と言ったといわれている。
九十歳になって、耳などもはっきりと聞こえなくなると
歌会のときなど、とりわけ講師の席の側に分け行って、その脇に寄り添いひどく年老いた姿で耳を傾けつつ
よそ事などに気をとられることなく聞いている様子などは、いい加減なことのようには見えなかった。
藤原俊成さまが『千載集』に選ばれたときには、すでに道因入道の亡くなくなってからのことであった。
しかし、亡き後でも、「本当に歌の道に志深かった者であった」と評価されて十八首を入れられた。
すると俊成さまの夢の中に道因が来て、涙を流し、うれしく思う気持ちを言えば、
俊成さまはもっとあわれに思われて、もう二首加えて、二十首になされたとのことだ。
まことにそうあるべき事である。
四季草花下絵千載集和歌巻(その二十二・二十三) [光悦・宗達・素庵]
(その二十二・二十三) 和歌巻(その二十二・二十三)

「光悦筆 四季草花宗達下絵和歌巻」(日本古典文学会・貴重本刊行会・日野原家蔵一巻)
花の歌とてよめる
93 み吉野の山した風やはらふらむこずゑにかへる花のしら雪(俊恵法師)
(み吉野の山の麓を吹く風が落花を吹き上げるからだろうか、雪のような花が梢に咲き返るよ。)
釈文(揮毫上の書体)=(『書道芸術第十八巻 本阿弥光悦』)
見よし野乃(みよし野の)山し多可勢(山したかぜ)やハ(は)らふら無(む)こ須衛尓(こずゑ)尓(に)可(か)へる花乃(の)しら雪
※山した風=山の麓を吹く風。
※はらふ=風が落花をまきあげる。
https://www.asahi-net.or.jp/~sg2h-ymst/yamatouta/sennin/syune.html
【俊恵(しゅんえ) 永久一(1113)~没年未詳 称:大夫公
源俊頼の息子。母は木工助橘敦隆の娘。兄の伊勢守俊重、弟の叡山阿闍梨祐盛も千載集ほかに歌を載せる歌人。子には叡山僧頼円がいる(千載集に歌が入集している)。大治四年(1129)、十七歳の時、父と死別。その後、東大寺に入り僧となる。
永暦元年(1160)の清輔朝臣家歌合をはじめ、仁安二年(1167)の経盛朝臣家歌合、嘉応二年(1170)の住吉社歌合、承安二年(1172)の広田社歌合、治承三年(1179)の右大臣家歌合など多くの歌合・歌会に参加。白川にあった自らの僧坊を歌林苑と名付け、保元から治承に至る二十年ほどの間、藤原清輔・源頼政・登蓮・道因・二条院讃岐ら多くの歌人が集まって月次歌会や歌合が行なわれた。ほかにも源師光・藤原俊成ら、幅広い歌人との交流が知られる。私撰集『歌苑抄』ほかがあったらしいが、伝存しない。弟子の一人鴨長明の歌論書『無名抄』の随所に俊恵の歌論を窺うことができる。家集『林葉和歌集』がある(以下「林葉集」と略)。中古六歌仙。詞花集初出。勅撰入集八十四首。千載集では二十二首を採られ、歌数第五位。 】
94 一枝(ひとえだ)を折りてかへらむ山ざくら風にのみやはちらしはつべき(源有房)
(山桜を一枝は折って帰ろう。どうせ散る桜ゆえ、風にばかりまかせきってよいものか。)
釈文(揮毫上の書体)=(『書道芸術第十八巻 本阿弥光悦』)
一枝ハ(は)折天(折りて)可(か)へら無(む)やま左具羅(さくら)可勢(かぜ)尓(に)乃三(のみ)やハ(は)知(ち)らしハ(は)徒(つ)べ幾(き)
※ちらしはつ=すっかり散らしきる。
【有房(ありふさ) 源氏、伯大夫と号す。生没年未詳。
神祇伯顕仲男、あるいは仲房男か。任安二年(一一六七)斎院長官、正五位下、久安五年(一一四九)『山路歌合』に出詠。千載初出、三首。】(『新日本古典文学大系10 千載和歌集』)
※『新勅撰和歌集』(第九勅撰集)の「源有房」(号:周防中将)とは、同名異人。
(参考) 俊恵法師と「歌林苑」周辺
https://wakadokoro.com/wonderful-songs/dailysongs/%E3%81%BF%E5%90%89%E9%87%8E%E3%81%AE%E5%B1%B1%E3%81%97%E3%81%9F%E9%A2%A8%E3%82%84%E6%89%95%E3%81%B5%E3%82%89%E3%82%80%E6%A2%A2%E3%81%AB%E3%81%8B%E3%81%B8%E3%82%8B%E8%8A%B1%E3%81%AE%E3%81%97%E3%82%89/
【 み吉野の山した風や払ふらむ梢にかへる花のしら雪(俊恵法師)
今日の歌人は俊恵法師。父は金葉集の選者「源俊頼」、方丈記などの執筆でも有名な「鴨長明」は歌の弟子であった。父とは17歳で死別しそのまま仏門に入ったというが、もし彼が堂上歌壇に留まっていたら御子左家が勃興する機会はなかったかもしれない。長明の「無名抄」に俊成と自賛歌について論じている段があるが、このやり取り見る限り、俊恵の方がはるかに的確※であるのだ。「幽玄」は俊成の専売特許のように思われているが、その本質にいち早く気付いていたのは俊恵だったのかもしれない。今日の歌にもそれが表れている。花を白雪に見立てるのは常套的だが、それを風が払って「梢に帰る」とした。とたんに物語性を帯びて、情趣に響く歌となった。
※「景気を言ひ流して、ただそらに身にしみけんかしと思はせたるこそ、心にくくも優に侍れ」(無名抄) 】
http://mie-ict.sakura.ne.jp/100n1s/kajin/k085.html
【俊恵法師(しゅんえほうし。1113年~1191年頃)
71番・源経信(つねのぶ)の孫、74番・源俊頼(としより)の息子で、3代続けて百人一首に歌が選ばれています。「金葉集」の撰者である父・俊頼に歌を学びましたが、17歳で死別し、出家して奈良・東大寺の僧となりました。40代になると、京都白川の自分の別邸を「歌林苑(かりんえん)」と名付け、歌人たちを集めて月例会を持つなど、保元(1156)以降治承(1177)の頃までサロンとしました。40人を越す参加者の中には、源頼政、82番・道因法師、84番・藤原清輔、87番・寂蓮法師、90番・殷富門院大輔、92番・二条院讃岐、など、有名な歌人もいましたが、身分・性別の区別なく幅広い階層の人々が集まりました。流派にこだわらない自由な雰囲気で、度々歌合や歌会を催しています。ここに集まった歌人たちは、生活での困りごとなども相談し合う仲だったらしく、俊恵法師が面倒見のよい人物だったことがうかがえます。俊恵法師の和歌の弟子である鴨長明は、その著書「無名抄(むみょうしょう)」に、俊恵法師の歌論を伝えています。現在、俊恵作と伝えられている歌は千百首あまりですが、その多くは40歳以降に詠まれたものです。自然詠や恋の歌を得意としていました。「詞花集」以下の勅撰集に84首入集しています。俊恵の父・源俊頼と親しかった83番・藤原俊成は「千載和歌集」に俊恵の歌を一番多い22首撰入しています。自撰家集に「俊恵法師集(林葉和歌集)」があります。 】
https://www.jstage.jst.go.jp/article/jeb1947/1980/129/1980_129_41/_pdf/-char/ja
【 「歌林苑歌壇の形成とその歌風 (上)」(大取一馬稿)……抜粋……
歌林苑の主宰者俊恵の初出は、父俊頼が催した歌合であった。当時一七歳であった俊恵は、恐らく作歌の練習のために詠んだもので、しかも代作の歌かも知れない。俊恵は、その後.久安二年三月左京大夫顕輔歌合」(当時俊恵三三歳) まで消息を断っている。俊恵自身、崇徳院との関係は全く不明であるが、『詞花集』に俊恵法師の名で載っている点からみると、『詞花集』撰集時の仁安元年にはすでに僧侶となっていたものと考えられる。俊恵の家集『林葉和歌集』によると、次の二条院との関係はその詞書に見られるが、父俊頼の関係か、あるいは清輔・頼政、その他の院の廷臣を通じてかかわっていたものと思える。又、清輔は為忠の歌合を初出としている。この歌合には清輔の父顕輔も出席しており、父に同行したものであろう。その後、清輔は崇徳院の催した『久安百首』の歌人に加えられているので、崇徳院近臣の教長、あるいは頼政とはこの時期に関係を持ったかと思われる。
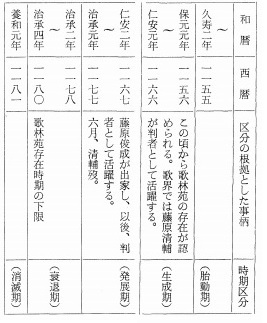
(歌林苑の胎動期・生成期・発展期・衰退期・消滅期)

(歌林苑の主な歌人たち) 】
https://plaza.rakuten.co.jp/sekkourou/diary/200604020000/
【 『後鳥羽院御口伝』の「釋阿(俊成)・西行・清輔・俊惠」評など】
俊頼の後には釋阿・西行・俊惠なり。すがたことにあらぬ體なり。釋阿はやさしくゑんに、心もふかくあはれなる所もありき。殊に愚意に庶幾するすがたなり。西行はおもしろくてしかもこゝろに殊にふかくあはれなる、ありがたく、出來しがたきかたもともに相兼てみゆ。生得の歌人とおぼゆ。これによりて、おぼろげの人のまねびなどすべき歌にあらず。不可説の上手なり。清輔はさせる事なけれども、さすがにふるめかしき事まゝみゆ。
としへたる宇治のはしもりこととはむいくよになりぬ水のみなかみ
これ體なり。俊惠法師おだしき樣に侍り。五尺のあやめ草に水をかけたるやうに歌はよむべしと申けり。
たつた山こずゑまばらになるまゝにふかくも簾のそよぐなるかな
釋阿、優なる歌に侍ると申き。
〔口訳〕源俊頼の次の世代では、藤原俊成、西行、俊恵である。歌の詞つづきがことにすぐれているという歌風ではない。ただし俊成は優艶で、艶っぽく、しみじみとした情趣に満ち、趣ぶかいところがあった。ことに私の好み理想とする歌風である。西行は機知や趣向に富み、しかも歌の心がまことに深く哀婉であって、なかなか世にめずらしい歌風であり、余人の真似がたい風を持っているようにも見える。生れつきの歌人というべきであろう。ただしそれゆえに初心の人の真似たり参考にしたりするような歌ではない。言葉にいいあらわしがたい名手である。藤原清輔はそれほどのこともないが、さすがに(歌学の大家であったらしく)古風なところが歌にところどころあらわれている。
としへたる宇治のはしもりこととはむいくよになりぬ水のみなかみ
こういう歌風である。俊恵はおとなしい歌風である。彼は「五尺のあやあ草に水をかけたように(清爽たるさまの)歌を詠むべきである」と言っていた。
たつた山こずゑまばらになるまゝにふかくも簾のそよぐなるかな
という歌があって、俊成はこれを優艶な歌であると言っていた。 】
(「俊恵と歌林苑のメモ」)
『後鳥羽院御口伝』の「俊頼の後には釋阿・西行・俊惠なり」のとおり、俊恵の父の「俊頼の時代」(第五勅撰集『金葉和歌集』の撰者)の次の時代は、「釋阿(俊成)・西行・俊惠」(第七勅撰集『千載和歌集(俊成撰)』)の時代ということになろう。
この「釋阿(俊成)・西行・俊惠」の時代は、「釋阿(俊成)」が主たる歌壇とする「殿上歌壇」(公的な宮廷歌壇)」の他に、「西行・俊恵」が主たる歌壇とする「在野歌壇」(個人的あるいは同好者的な私的な歌壇)が生成・発展した時代であった。
この「在野歌壇」の代表的な歌壇が、俊恵が中心となった「歌林苑」ということになろう。
この「歌林苑」の時代は、「歌林苑歌壇の形成とその歌風 (上)」(大取一馬稿)によると、その生成期は、保元元年(一一五六)から仁安元年(一一六六)の「藤原清輔が判者として活躍した時代」(「六条藤家」の時代)」で、次の発展期(仁安二年=一一六七~治承元年=一一七七)は、「藤原清輔が没して、俊成が判者として活躍した『御子左家』の時代」としている。
ここで、「殿上人歌壇」と「在野歌壇」とを、この「四季草花下絵千載集和歌巻」(光悦筆の『千載和歌集』)ですると、その『千載和歌集』の配列は、「官職名」が有るものが「殿上人歌壇」、「官職名」が無いものが「在野歌壇」と、一応の目安とすることも可能であろう。
(「殿上人歌壇」の作例)
87 あらしふく志賀の山辺のさくら花ちれば雲井にさゞ浪ぞたつ(右兵衛公行)
(志賀の山辺の桜花が、はげしい山風に吹き散らされると、空にはさざ波が立つよ。)
88 春風に志賀の山こゑ花ちれば峰にぞ浦のなみはたちける(前参議親隆)
(春風の中、花吹雪の志賀の山越えをして来ると、山の頂に浦の波が立つことだよ。)
89 さくら咲く比良の山風ふくまゝに花になりゆく志賀のうら浪(左近中将良経)
(桜咲く比良の峰々を山風が吹きおろすと、やがて志賀の浦波も花の白波となっていくよ。)
90 ちりかゝる花のにしきは着たれどもかへらむ事ぞわすられにける(右近大将実房)
(落花の下、花の錦は身につけたが、花に心を奪われて故郷へ帰ることを忘れてしまったよ。)
91 あかなくに袖につゝめばちる花をうれしと思ふになりぬべきかな(権大納言実国)
(散る花への飽きることのない愛惜の心から、それを袖に包みとると、花が散るのは悲しいのに、かえって喜んでいるようになってしまいそうだよ。)
92 桜花うき身にかふるためしあらば生きてちるをば惜しまざらまし(権中納言通親)
(桜の花が散るのを、この憂き身に代えて止めるというためしがあるのなら、私は(身代わりになるから)生き永らえて散る花を惜しむことはないであろう。)
そして、これに続く、この「四季草花下絵千載集和歌巻」(光悦筆の『千載和歌集』)の、次の歌は、「在野歌壇」の歌ということになる。
(「在野歌壇」の作例)
93 み吉野の山した風やはらふらむこずゑにかへる花のしら雪(俊恵法師)
(み吉野の山の麓を吹く風が落花を吹き上げるからだろうか、雪のような花が梢に咲き返るよ。)
94 一枝(ひとえだ)を折りてかへらむ山ざくら風にのみやはちらしはつべき(源有房)
(山桜を一枝は折って帰ろう。どうせ散る桜ゆえ、風にばかりまかせきってよいものか。)
95 ちる花を身にかふばかり思へどもかなはで年の老ひにけるかな(道因法師)
(散る花を惜しむあまり、わが身にかえてもとひたすら思い続けて来たが、それにもかなわず、年ごとに花は散り、わが齢も老いてしまったことだよ。)
96 あかなくにちりぬる花のおもかげや風に知られぬさくらなるらむ(覚盛法師)
(花に飽きることがない心から、すでに散ってしまった桜を面影に抱き続けて来たが、それは風に知られぬ桜なのだろう。)

「光悦筆 四季草花宗達下絵和歌巻」(日本古典文学会・貴重本刊行会・日野原家蔵一巻)
花の歌とてよめる
93 み吉野の山した風やはらふらむこずゑにかへる花のしら雪(俊恵法師)
(み吉野の山の麓を吹く風が落花を吹き上げるからだろうか、雪のような花が梢に咲き返るよ。)
釈文(揮毫上の書体)=(『書道芸術第十八巻 本阿弥光悦』)
見よし野乃(みよし野の)山し多可勢(山したかぜ)やハ(は)らふら無(む)こ須衛尓(こずゑ)尓(に)可(か)へる花乃(の)しら雪
※山した風=山の麓を吹く風。
※はらふ=風が落花をまきあげる。
https://www.asahi-net.or.jp/~sg2h-ymst/yamatouta/sennin/syune.html
【俊恵(しゅんえ) 永久一(1113)~没年未詳 称:大夫公
源俊頼の息子。母は木工助橘敦隆の娘。兄の伊勢守俊重、弟の叡山阿闍梨祐盛も千載集ほかに歌を載せる歌人。子には叡山僧頼円がいる(千載集に歌が入集している)。大治四年(1129)、十七歳の時、父と死別。その後、東大寺に入り僧となる。
永暦元年(1160)の清輔朝臣家歌合をはじめ、仁安二年(1167)の経盛朝臣家歌合、嘉応二年(1170)の住吉社歌合、承安二年(1172)の広田社歌合、治承三年(1179)の右大臣家歌合など多くの歌合・歌会に参加。白川にあった自らの僧坊を歌林苑と名付け、保元から治承に至る二十年ほどの間、藤原清輔・源頼政・登蓮・道因・二条院讃岐ら多くの歌人が集まって月次歌会や歌合が行なわれた。ほかにも源師光・藤原俊成ら、幅広い歌人との交流が知られる。私撰集『歌苑抄』ほかがあったらしいが、伝存しない。弟子の一人鴨長明の歌論書『無名抄』の随所に俊恵の歌論を窺うことができる。家集『林葉和歌集』がある(以下「林葉集」と略)。中古六歌仙。詞花集初出。勅撰入集八十四首。千載集では二十二首を採られ、歌数第五位。 】
94 一枝(ひとえだ)を折りてかへらむ山ざくら風にのみやはちらしはつべき(源有房)
(山桜を一枝は折って帰ろう。どうせ散る桜ゆえ、風にばかりまかせきってよいものか。)
釈文(揮毫上の書体)=(『書道芸術第十八巻 本阿弥光悦』)
一枝ハ(は)折天(折りて)可(か)へら無(む)やま左具羅(さくら)可勢(かぜ)尓(に)乃三(のみ)やハ(は)知(ち)らしハ(は)徒(つ)べ幾(き)
※ちらしはつ=すっかり散らしきる。
【有房(ありふさ) 源氏、伯大夫と号す。生没年未詳。
神祇伯顕仲男、あるいは仲房男か。任安二年(一一六七)斎院長官、正五位下、久安五年(一一四九)『山路歌合』に出詠。千載初出、三首。】(『新日本古典文学大系10 千載和歌集』)
※『新勅撰和歌集』(第九勅撰集)の「源有房」(号:周防中将)とは、同名異人。
(参考) 俊恵法師と「歌林苑」周辺
https://wakadokoro.com/wonderful-songs/dailysongs/%E3%81%BF%E5%90%89%E9%87%8E%E3%81%AE%E5%B1%B1%E3%81%97%E3%81%9F%E9%A2%A8%E3%82%84%E6%89%95%E3%81%B5%E3%82%89%E3%82%80%E6%A2%A2%E3%81%AB%E3%81%8B%E3%81%B8%E3%82%8B%E8%8A%B1%E3%81%AE%E3%81%97%E3%82%89/
【 み吉野の山した風や払ふらむ梢にかへる花のしら雪(俊恵法師)
今日の歌人は俊恵法師。父は金葉集の選者「源俊頼」、方丈記などの執筆でも有名な「鴨長明」は歌の弟子であった。父とは17歳で死別しそのまま仏門に入ったというが、もし彼が堂上歌壇に留まっていたら御子左家が勃興する機会はなかったかもしれない。長明の「無名抄」に俊成と自賛歌について論じている段があるが、このやり取り見る限り、俊恵の方がはるかに的確※であるのだ。「幽玄」は俊成の専売特許のように思われているが、その本質にいち早く気付いていたのは俊恵だったのかもしれない。今日の歌にもそれが表れている。花を白雪に見立てるのは常套的だが、それを風が払って「梢に帰る」とした。とたんに物語性を帯びて、情趣に響く歌となった。
※「景気を言ひ流して、ただそらに身にしみけんかしと思はせたるこそ、心にくくも優に侍れ」(無名抄) 】
http://mie-ict.sakura.ne.jp/100n1s/kajin/k085.html
【俊恵法師(しゅんえほうし。1113年~1191年頃)
71番・源経信(つねのぶ)の孫、74番・源俊頼(としより)の息子で、3代続けて百人一首に歌が選ばれています。「金葉集」の撰者である父・俊頼に歌を学びましたが、17歳で死別し、出家して奈良・東大寺の僧となりました。40代になると、京都白川の自分の別邸を「歌林苑(かりんえん)」と名付け、歌人たちを集めて月例会を持つなど、保元(1156)以降治承(1177)の頃までサロンとしました。40人を越す参加者の中には、源頼政、82番・道因法師、84番・藤原清輔、87番・寂蓮法師、90番・殷富門院大輔、92番・二条院讃岐、など、有名な歌人もいましたが、身分・性別の区別なく幅広い階層の人々が集まりました。流派にこだわらない自由な雰囲気で、度々歌合や歌会を催しています。ここに集まった歌人たちは、生活での困りごとなども相談し合う仲だったらしく、俊恵法師が面倒見のよい人物だったことがうかがえます。俊恵法師の和歌の弟子である鴨長明は、その著書「無名抄(むみょうしょう)」に、俊恵法師の歌論を伝えています。現在、俊恵作と伝えられている歌は千百首あまりですが、その多くは40歳以降に詠まれたものです。自然詠や恋の歌を得意としていました。「詞花集」以下の勅撰集に84首入集しています。俊恵の父・源俊頼と親しかった83番・藤原俊成は「千載和歌集」に俊恵の歌を一番多い22首撰入しています。自撰家集に「俊恵法師集(林葉和歌集)」があります。 】
https://www.jstage.jst.go.jp/article/jeb1947/1980/129/1980_129_41/_pdf/-char/ja
【 「歌林苑歌壇の形成とその歌風 (上)」(大取一馬稿)……抜粋……
歌林苑の主宰者俊恵の初出は、父俊頼が催した歌合であった。当時一七歳であった俊恵は、恐らく作歌の練習のために詠んだもので、しかも代作の歌かも知れない。俊恵は、その後.久安二年三月左京大夫顕輔歌合」(当時俊恵三三歳) まで消息を断っている。俊恵自身、崇徳院との関係は全く不明であるが、『詞花集』に俊恵法師の名で載っている点からみると、『詞花集』撰集時の仁安元年にはすでに僧侶となっていたものと考えられる。俊恵の家集『林葉和歌集』によると、次の二条院との関係はその詞書に見られるが、父俊頼の関係か、あるいは清輔・頼政、その他の院の廷臣を通じてかかわっていたものと思える。又、清輔は為忠の歌合を初出としている。この歌合には清輔の父顕輔も出席しており、父に同行したものであろう。その後、清輔は崇徳院の催した『久安百首』の歌人に加えられているので、崇徳院近臣の教長、あるいは頼政とはこの時期に関係を持ったかと思われる。
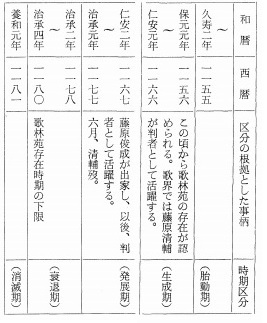
(歌林苑の胎動期・生成期・発展期・衰退期・消滅期)

(歌林苑の主な歌人たち) 】
https://plaza.rakuten.co.jp/sekkourou/diary/200604020000/
【 『後鳥羽院御口伝』の「釋阿(俊成)・西行・清輔・俊惠」評など】
俊頼の後には釋阿・西行・俊惠なり。すがたことにあらぬ體なり。釋阿はやさしくゑんに、心もふかくあはれなる所もありき。殊に愚意に庶幾するすがたなり。西行はおもしろくてしかもこゝろに殊にふかくあはれなる、ありがたく、出來しがたきかたもともに相兼てみゆ。生得の歌人とおぼゆ。これによりて、おぼろげの人のまねびなどすべき歌にあらず。不可説の上手なり。清輔はさせる事なけれども、さすがにふるめかしき事まゝみゆ。
としへたる宇治のはしもりこととはむいくよになりぬ水のみなかみ
これ體なり。俊惠法師おだしき樣に侍り。五尺のあやめ草に水をかけたるやうに歌はよむべしと申けり。
たつた山こずゑまばらになるまゝにふかくも簾のそよぐなるかな
釋阿、優なる歌に侍ると申き。
〔口訳〕源俊頼の次の世代では、藤原俊成、西行、俊恵である。歌の詞つづきがことにすぐれているという歌風ではない。ただし俊成は優艶で、艶っぽく、しみじみとした情趣に満ち、趣ぶかいところがあった。ことに私の好み理想とする歌風である。西行は機知や趣向に富み、しかも歌の心がまことに深く哀婉であって、なかなか世にめずらしい歌風であり、余人の真似がたい風を持っているようにも見える。生れつきの歌人というべきであろう。ただしそれゆえに初心の人の真似たり参考にしたりするような歌ではない。言葉にいいあらわしがたい名手である。藤原清輔はそれほどのこともないが、さすがに(歌学の大家であったらしく)古風なところが歌にところどころあらわれている。
としへたる宇治のはしもりこととはむいくよになりぬ水のみなかみ
こういう歌風である。俊恵はおとなしい歌風である。彼は「五尺のあやあ草に水をかけたように(清爽たるさまの)歌を詠むべきである」と言っていた。
たつた山こずゑまばらになるまゝにふかくも簾のそよぐなるかな
という歌があって、俊成はこれを優艶な歌であると言っていた。 】
(「俊恵と歌林苑のメモ」)
『後鳥羽院御口伝』の「俊頼の後には釋阿・西行・俊惠なり」のとおり、俊恵の父の「俊頼の時代」(第五勅撰集『金葉和歌集』の撰者)の次の時代は、「釋阿(俊成)・西行・俊惠」(第七勅撰集『千載和歌集(俊成撰)』)の時代ということになろう。
この「釋阿(俊成)・西行・俊惠」の時代は、「釋阿(俊成)」が主たる歌壇とする「殿上歌壇」(公的な宮廷歌壇)」の他に、「西行・俊恵」が主たる歌壇とする「在野歌壇」(個人的あるいは同好者的な私的な歌壇)が生成・発展した時代であった。
この「在野歌壇」の代表的な歌壇が、俊恵が中心となった「歌林苑」ということになろう。
この「歌林苑」の時代は、「歌林苑歌壇の形成とその歌風 (上)」(大取一馬稿)によると、その生成期は、保元元年(一一五六)から仁安元年(一一六六)の「藤原清輔が判者として活躍した時代」(「六条藤家」の時代)」で、次の発展期(仁安二年=一一六七~治承元年=一一七七)は、「藤原清輔が没して、俊成が判者として活躍した『御子左家』の時代」としている。
ここで、「殿上人歌壇」と「在野歌壇」とを、この「四季草花下絵千載集和歌巻」(光悦筆の『千載和歌集』)ですると、その『千載和歌集』の配列は、「官職名」が有るものが「殿上人歌壇」、「官職名」が無いものが「在野歌壇」と、一応の目安とすることも可能であろう。
(「殿上人歌壇」の作例)
87 あらしふく志賀の山辺のさくら花ちれば雲井にさゞ浪ぞたつ(右兵衛公行)
(志賀の山辺の桜花が、はげしい山風に吹き散らされると、空にはさざ波が立つよ。)
88 春風に志賀の山こゑ花ちれば峰にぞ浦のなみはたちける(前参議親隆)
(春風の中、花吹雪の志賀の山越えをして来ると、山の頂に浦の波が立つことだよ。)
89 さくら咲く比良の山風ふくまゝに花になりゆく志賀のうら浪(左近中将良経)
(桜咲く比良の峰々を山風が吹きおろすと、やがて志賀の浦波も花の白波となっていくよ。)
90 ちりかゝる花のにしきは着たれどもかへらむ事ぞわすられにける(右近大将実房)
(落花の下、花の錦は身につけたが、花に心を奪われて故郷へ帰ることを忘れてしまったよ。)
91 あかなくに袖につゝめばちる花をうれしと思ふになりぬべきかな(権大納言実国)
(散る花への飽きることのない愛惜の心から、それを袖に包みとると、花が散るのは悲しいのに、かえって喜んでいるようになってしまいそうだよ。)
92 桜花うき身にかふるためしあらば生きてちるをば惜しまざらまし(権中納言通親)
(桜の花が散るのを、この憂き身に代えて止めるというためしがあるのなら、私は(身代わりになるから)生き永らえて散る花を惜しむことはないであろう。)
そして、これに続く、この「四季草花下絵千載集和歌巻」(光悦筆の『千載和歌集』)の、次の歌は、「在野歌壇」の歌ということになる。
(「在野歌壇」の作例)
93 み吉野の山した風やはらふらむこずゑにかへる花のしら雪(俊恵法師)
(み吉野の山の麓を吹く風が落花を吹き上げるからだろうか、雪のような花が梢に咲き返るよ。)
94 一枝(ひとえだ)を折りてかへらむ山ざくら風にのみやはちらしはつべき(源有房)
(山桜を一枝は折って帰ろう。どうせ散る桜ゆえ、風にばかりまかせきってよいものか。)
95 ちる花を身にかふばかり思へどもかなはで年の老ひにけるかな(道因法師)
(散る花を惜しむあまり、わが身にかえてもとひたすら思い続けて来たが、それにもかなわず、年ごとに花は散り、わが齢も老いてしまったことだよ。)
96 あかなくにちりぬる花のおもかげや風に知られぬさくらなるらむ(覚盛法師)
(花に飽きることがない心から、すでに散ってしまった桜を面影に抱き続けて来たが、それは風に知られぬ桜なのだろう。)
四季草花下絵千載集和歌巻(その二十一) [光悦・宗達・素庵]
(その二十一) 和歌巻(その二十一)

「光悦筆 四季草花宗達下絵和歌巻」(日本古典文学会・貴重本刊行会・日野原家蔵一巻)
久我内大臣の家にて、「身ニ代エテ花ヲ惜シム」
といへる心をよめる
92 桜花うき身にかふるためしあらば生きてちるをば惜しまざらまし(権中納言通親)
(桜の花が散るのを、この憂き身に代えて止めるというためしがあるのなら、私は(身代わりになるから)生き永らえて散る花を惜しむことはないであろう。)
釈文(揮毫上の書体)=(『書道芸術第十八巻 本阿弥光悦』)
左久らハ那(さくらばな)う来身尓(うき身に)可ふる(かふる)多免し安ら半(ためしあらば)以来天(いきて)散るをハ(ば)おしま左(ざ)らまし
※左久らハ那(さくらばな)=桜花。
※う来身尓(うき身に)=憂き身。辛い現世を生きている身。
※多免し安ら半(ためしあらば)=ためしあらば。前例があるならば。
※以来天(いきて)散るをハ(ば)=いきて散るをば。生き永らえて散る(花)をば。
※おしま左(ざ)らまし=惜しまざらまし。惜しむことはないであろう。
※※久我内大臣=作者(通親)の父、源雅通。
http://www.asahi-net.or.jp/~sg2h-ymst/yamatouta/sennin/mititika.html
【源通親(みなもとのみちちか)久安五~建仁二(1149-1202) 号:土御門内大臣・源博陸(げんはくろく)
村上源氏。内大臣久我(こが)雅通の長男。母は藤原行兼の息女で美福門院の女房だった女性。権大納言通資の兄。子には、通宗(藤原忠雅女所生)、通具(平道盛女所生)、通光・定通(藤原範子所生)がいる。道元(松殿基房女所生)も通親の子とする説がある。後鳥羽院后在子は養女。
保元三年(1158)八月、従五位下に叙される。仁安二年(1167)、右近衛権少将。同三年正月、従四位下に昇叙され、加賀介を兼任する。同年二月、高倉天皇が践祚すると昇殿を許され、以後近臣として崩時まで仕えることになる。同年三月、従四位上、八月にはさらに正四位下に叙せられ、禁色宣下を受ける。嘉応元年(1169)四月、建春門院(平滋子)昇殿をゆるされる。承安元年(1171)正月、右近衛権中将。十二月、平清盛の息女徳子の入内に際し、女御家の侍所別当となる。治承二年(1178)、中宮平徳子所生の言仁(ときひと)親王(安徳天皇)の立太子に際し、東宮昇殿をゆるされる。同三年(1179)正月、蔵人頭に補される。十二月、中宮権亮を兼ねる。同四年正月、参議に任ぜられる。同年三月、高倉上皇の厳島行幸に供奉。六月には福原遷幸にも供奉し、宮都の地を点定した。
平安京還都後の治承五年(1181)正月、従三位に叙されたが、その直後、高倉上皇が崩御(二十一歳)。上皇危篤の時から一周忌までを通親が歌日記風に綴ったのが『高倉院升遐記』である。同年閏二月には平清盛が薨じ、政治の実権は後白河法皇へ移る。以後、通親も法皇のもとで公事に精励することになる。改元して養和元年の十一月、中宮権亮を罷め、建礼門院別当に補される。同二年正月、正三位。
寿永二年(1183)七月、平氏が安徳天皇を奉じて西下すると、通親はそれ以前に比叡山に逃れていた後白河天皇のもとに参入。ついで院御所での議定に列した。同年八月、後鳥羽天皇践祚。この後、通親は新帝の御乳母藤原範子(範兼の娘)を娶り、先夫との間の子在子を引き取って養女とした。
元暦二年(1185)正月、権中納言に昇進。文治二年(1186)三月、源頼朝の支持のもと、九条兼実が摂政に就任。この時通親は議奏公卿の一人に指名された。同三年正月、従二位。同五年正月、正二位(最終官位)。同年十二月、法皇寵愛の皇女覲子内親王(母は丹後局高階栄子)の勅別当に補される。以後、丹後局との結びつきを強固にし、内廷支配を確立してゆく。
建久元年(1190)七月、中納言に進む。同三年三月、後白河院が崩じ、摂政兼実が実権を握るに至るが、通親は故院の旧臣グループを中心に反兼実勢力を形成した。同六年十一月、養女の在子が皇子を出産(のちの土御門天皇)。同月、権大納言に昇る。建久七年(1196)十一月、任子の内裏追放と兼実の排斥に成功。同九年(1198)には外孫土御門天皇を即位させ、後鳥羽院の執事別当として朝政の実権を掌握。「天下独歩するの体なり」と言われ、権大納言の地位ながら「源博陸」(博陸は関白の異称)と呼ばれた(兼実『玉葉』)。
正治元年(1199)正月、右近衛大将に任ぜられる。その直後源頼朝が死去すると、通親排斥の動きがあり、院御所に隠れ籠る。結局幕府の支持を得て事なきを得、同年六月には内大臣に就任し、同二年四月、守成親王(のちの順徳天皇)立太子に際し、東宮傅を兼ねる。
和歌は若い頃から熱心で、嘉応二年(1170)秋頃、自邸で歌合を催している。同年の住吉社歌合・建春門院滋子北面歌合、治承二年(1178)の別雷社歌合などに参加。
殊に内大臣となって政局の安定を果したのちは、活発な和歌活動を展開し、後鳥羽院歌壇と新古今集の形成に向けて大きな役割を果すことになる。正治二年(1200)十月、初めて影供歌合を催し、以後もたびたび開催する。同年十一月には後鳥羽院百首歌会に参加(正治初度百首)。建仁元年(1201)三月、院御所の新宮撰歌合、同年六月の千五百番歌合に参加。同年七月には、二男通具と共に後鳥羽院の和歌所寄人に選ばれた。
しかし新古今集の完成は見ることなく、建仁二年(1202)冬、病に臥し、同年十月二十日夜(または二十一日朝)、薨去。五十四歳。民百姓に至るまで死を悲しみ泣き惑ったという(源家長日記)。贈従一位を宣下される。
著書には上記のほか『高倉院厳島御幸記』などがある。千載集初出。勅撰入集三十二首。】
(参考) 「九条兼実」と「源通親」周辺
「九条兼実」は、「藤原北家、関白・藤原忠通の六男。官位は従一位・摂政・関白・太政大臣。月輪殿、後法性寺殿とも呼ばれる」。一方の「源通親」は、「村上源氏久我流、内大臣・源雅通の子。官位は正二位・内大臣、右大将、贈従一位。土御門通親と呼ばれている」。
この二人は、共に、久安五年(一一四九)の同年の生まれで、没年は、兼実が、承元元年(一二〇七)、通親は、建仁二年(一二〇二)と、通親の方が、早く亡くなっている。
ここで、この通親が、「関白・兼実」を失脚させる「建久七年(一一九六)の政変」以降の、両者の「官職名」の推移を明記すると次のとおりとなる(『ウィキペディア(Wikipedia)』)。
「建久七年(一一九六)の政変」後の「兼実」
建久7年(1196年)11月25日:関白停任。無上表事。
建仁2年(1202年)1月28日:出家。法名「圓證」
承元元年(1207年)4月5日:薨去。享年59
「建久七年(一一九六)の政変」後の「通親」
建久9年(1198年)1月5日:後院別当を兼帯。
正治元年(1199年)
1月20日:右近衛大将を兼任。
6月22日:内大臣に転任。
6月23日:右近衛大将如元。
正治2年(1200年)4月15日:東宮傅を兼任。
建仁2年(1202年)10月21日、薨去。享年54。時に、内大臣正二位兼行右近衛大将東宮傅。
すなわち、兼実が出家した建仁二年(一二〇二)に、通親は、その生涯を閉じている。この通親の死について、兼実の異母弟の慈円の『愚管抄』は次のように記している。
http://www.st.rim.or.jp/~success/gukansyo06_yositune.html
【建仁二年十月廿一日ニ。通親公等ウセニケリ。頓死ノ躰ナリ。不可思議ノ事ト人モ思ヘリケリ。承明門院〔在子〕ヲゾ母ウセテ後ハアイシ参ラセケル。カカリケル程ニ。院ハ範季ガムスメヲ思召テ三位セサセテ。美福門院ノ例ニモニテ有ケルニ。王子モアマタ出キタル。御アニ〔守成〕ヲ東宮ニスエマイラセントヲボシメシタル御ケシキナレバ。通親ノ公申沙汰シテ立坊有テ。正治二年四月十四日ニ東宮ニ立テ。カヤウニテ過ル程ニ。九條〔良経〕殿ハ又北政所ニヲクレテ出家セラレニケリ。サル程ニ院ノ御心ニフカク世ノカハリシ我ガ御心ヨリヲコラズト云コトヲ人ニモシラレントヤ思召ケン。建仁二年十一月廿七日ニ。左大臣〔良経〕ニ内覧氏長者ノ宣旨ヲクダシテ。ヤガテ廿八日ニ熊野御進発ナリニケリ。母北政所重服コノ十二月バカリニテアリケリ。サテ熊野ヨリ御帰洛ノ後。十二月廿七日ニ摂政ノ詔クダサレニケリ。サテ正月一日ノ拝禮ノサキニヨロコビ申サセラレニケレバ。世ノ人ハコハユユシク目出キコトカナト思ケリ。宗頼大納言ハ成頼入道ガ高野ニ年比ヲコナイテアリケル入滅シタル服ヲキルベキヲ。真ノ親ノ光頼ノ大納言ガヲバ成頼ガヲキムズレバトテキザリケリ。是ハ又アマリニ世ニアイテイトマヲオシガリテキズ。サテ親モナカリケル者ニナリヌル事ヲ。人モカタブキケルニヤ。カク熊野ノ御幸ノ御トモニマイリテ。松明ノ火ニテ足ヲヤキタリケルガ。サシモ大事ニナリテ正月卅日ウセニケル。其後卿二位ハ夫ヲウシナイテ又トカクアンジツツ。コノ太相國頼実ノ七條院辺〔後鳥羽院御母〕ニ申ヨリテ候ケルニ申ナドシテ。又夫ニシテヤガテ院ノ御ウシロミセサセテ候ケル。】(『愚管抄第六』=上記アドレス)
この「建仁二年十月廿一日ニ。通親公等ウセニケリ。頓死ノ躰ナリ。不可思議ノ事ト人モ思ヘリケリ」の「頓死」とは「急死」のことであり、「不可思議ノ事ト人モ思ヘリケリ」については、例えば『藤原定家『明月記』の世界(村井康彦著・岩波新書)』では、「これまでの権謀術数の数々を思えば、敵はゴマンといたはずで、密かに殺害されたのではないかという疑念を抱かれてもおかしくない」と紹介されている。
これに続く、「建仁二年十一月廿七日ニ。左大臣〔良経〕ニ内覧氏長者ノ宣旨ヲクダシテ。」、そして、「十二月廿七日ニ摂政ノ詔クダサレニケリ。」と、失脚した兼実(この時には出家している)の継子の「九条良経」は、後鳥羽院の宣旨をもって「藤氏長者」(藤原氏一族全体の氏長者)となり、さらに、良経は、「左大臣」(「関白」にならず)のまま土御門天皇の「摂政」(君主に代わって政務をとること,またはその者)と朝廷のトップに立つこととなる。
この時、良経、三十五歳、この宣旨・詔を発した後鳥羽院は、二十三歳で、兼実は出家、
通親は頓死、既に後白河法皇・源頼朝も没しており、名実ともに治天の君となった。しかし、この良経は、元久三年(一二〇六)三月七日深夜に頓死。享年三十八歳であった。この良経の頓死(急死)についても、下記のアドレスで触れてきた。
https://yahan.blog.ss-blog.jp/2020-11-03
そして、承久三年(一二二一)の「承久の乱」(後鳥羽院と時の執権・北条義時との戦乱)により、後鳥羽院は隠岐島(隠岐国海士郡の中ノ島、現海士町)に配流され、そこで、延応元年(一二三九)に、その六十年の生涯を閉じた。
ここで、上記の『愚管抄第六』の事項を理解するには、下記のアドレスの図解が恰好のものである。
http://dabohazj.web.fc2.com/kibo/note/motomichi/motomichi.htm
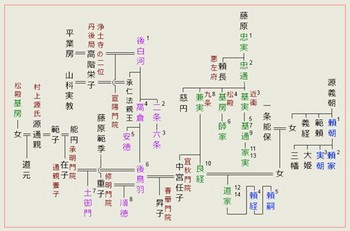
(「後白河~順徳天皇」・「藤原忠実~道家」・「源頼朝~頼嗣)」と「兼実と通親」関連図)
一 天皇家は、「1後白河→2二条→3六条→4高倉→5安徳→6後鳥羽→7土御門→8順徳」の流れである。
二 藤原家は、「1忠実→2忠通→3基実(近衛家)→4基房(松殿家)→5・7・9基通(近衛家)→6師家(松殿家)→8兼実(九条家)→10良経(九条家)→11・13家実(近衛家)→12・14道家」の流れである。
三 源頼朝家→1頼朝→2頼家→3実朝→4頼経→5頼嗣の流れである。
四 後鳥羽院=任子(兼実の娘、良経の妹)、後鳥羽院=在子(通親の養女、通親正室範子の娘)、後鳥羽院と任子(宜秋門院)の内親王=昇子(春華門院)、後鳥羽院と在子(承明門院)の親王=土御門天皇、後鳥羽院と重子(修明門院)の親王=順徳天皇
五 源通親の側室(兼実の兄・基房の娘)
六 兼実の娘任子は後鳥羽天皇の中宮宜秋門院となっているが、建久六年(1195)八月に女子を産む(昇子・春華門院)。源通親の養女・在子は宮仕していたが同十一月に皇子(為仁・土御門天皇)を生む。これで通親と兼実の形勢が逆転し、通親による「建久七年の政変」が起こり、かねて憎まれていた兼実は失脚する。そして、村上源氏の全盛時代となり、古い後白河派とみなされた近衛基通が10年ぶりに関白として返り咲く(上掲および前掲 系図 の基通の数字「9」)。
七 建久九年(1198年)正月に後鳥羽天皇(十九歳)は土御門天皇へ践祚した。これで通親は天皇の外祖父の地位を得たのであり、後鳥羽は若い院としての自由な立場を得て京都内外を活発に「御幸」したという。祖父・後白河の血が確かに伝わっていたのであろう。基通は土御門天皇(四歳)の摂政にもなる。政治の実権を握っていた通親は正治元年(1199)に内大臣となり、「源博陸」(げんはくりく、博陸は関白の意)と呼ばれた。
八 通親は建仁二年(1202)十月に急死(享年五十四歳)する。それを契機に九条家にバランスをとる人事がなされ、摂政が九条良経に移る。良経は溢れるほどの才能に恵まれた人物だったようで慈円が『愚管抄』に「コノ人は三ツノ舟ニノリヌベキ人」(詩・和歌・管弦の三つの舟)と言葉を極めて賞讃している。その良経は元久三年(1206)二月廿日に急死(享年三十八歳)する(『愚管抄』は「ネ死ニ頓死」、『玉葉』は夕刻まで良経が普段通りであったことを記したあと、良経の「女房」が走ってきて急を知らせ、兼実が「劇速して行く」が「身冷気絶」であったと)。このため良経の死には他殺説もある。
九 良経の急死を受け、近衛家実が摂政となった。基通の息子である。こののちは、松殿は摂関家としては基房-師家で絶え、近衛家と九条家のバランスを考えた人事となって、文永十年(1273)この両家から「五摂家」が成立する(近衛家・鷹司家・九条家・一条家・二条家)。「五摂家」体制のもとで江戸時代終末まで形式的な摂関は続く。
十 三代将軍実朝の暗殺で頼朝の系譜は断たれる。上掲系図のように、良経は義朝の娘と婚姻し、九条家が将軍となるきっかけを作っている。藤原将軍時代である。しかしそれも2代しか続かず、そのあとは親王将軍の時代となる。

「光悦筆 四季草花宗達下絵和歌巻」(日本古典文学会・貴重本刊行会・日野原家蔵一巻)
久我内大臣の家にて、「身ニ代エテ花ヲ惜シム」
といへる心をよめる
92 桜花うき身にかふるためしあらば生きてちるをば惜しまざらまし(権中納言通親)
(桜の花が散るのを、この憂き身に代えて止めるというためしがあるのなら、私は(身代わりになるから)生き永らえて散る花を惜しむことはないであろう。)
釈文(揮毫上の書体)=(『書道芸術第十八巻 本阿弥光悦』)
左久らハ那(さくらばな)う来身尓(うき身に)可ふる(かふる)多免し安ら半(ためしあらば)以来天(いきて)散るをハ(ば)おしま左(ざ)らまし
※左久らハ那(さくらばな)=桜花。
※う来身尓(うき身に)=憂き身。辛い現世を生きている身。
※多免し安ら半(ためしあらば)=ためしあらば。前例があるならば。
※以来天(いきて)散るをハ(ば)=いきて散るをば。生き永らえて散る(花)をば。
※おしま左(ざ)らまし=惜しまざらまし。惜しむことはないであろう。
※※久我内大臣=作者(通親)の父、源雅通。
http://www.asahi-net.or.jp/~sg2h-ymst/yamatouta/sennin/mititika.html
【源通親(みなもとのみちちか)久安五~建仁二(1149-1202) 号:土御門内大臣・源博陸(げんはくろく)
村上源氏。内大臣久我(こが)雅通の長男。母は藤原行兼の息女で美福門院の女房だった女性。権大納言通資の兄。子には、通宗(藤原忠雅女所生)、通具(平道盛女所生)、通光・定通(藤原範子所生)がいる。道元(松殿基房女所生)も通親の子とする説がある。後鳥羽院后在子は養女。
保元三年(1158)八月、従五位下に叙される。仁安二年(1167)、右近衛権少将。同三年正月、従四位下に昇叙され、加賀介を兼任する。同年二月、高倉天皇が践祚すると昇殿を許され、以後近臣として崩時まで仕えることになる。同年三月、従四位上、八月にはさらに正四位下に叙せられ、禁色宣下を受ける。嘉応元年(1169)四月、建春門院(平滋子)昇殿をゆるされる。承安元年(1171)正月、右近衛権中将。十二月、平清盛の息女徳子の入内に際し、女御家の侍所別当となる。治承二年(1178)、中宮平徳子所生の言仁(ときひと)親王(安徳天皇)の立太子に際し、東宮昇殿をゆるされる。同三年(1179)正月、蔵人頭に補される。十二月、中宮権亮を兼ねる。同四年正月、参議に任ぜられる。同年三月、高倉上皇の厳島行幸に供奉。六月には福原遷幸にも供奉し、宮都の地を点定した。
平安京還都後の治承五年(1181)正月、従三位に叙されたが、その直後、高倉上皇が崩御(二十一歳)。上皇危篤の時から一周忌までを通親が歌日記風に綴ったのが『高倉院升遐記』である。同年閏二月には平清盛が薨じ、政治の実権は後白河法皇へ移る。以後、通親も法皇のもとで公事に精励することになる。改元して養和元年の十一月、中宮権亮を罷め、建礼門院別当に補される。同二年正月、正三位。
寿永二年(1183)七月、平氏が安徳天皇を奉じて西下すると、通親はそれ以前に比叡山に逃れていた後白河天皇のもとに参入。ついで院御所での議定に列した。同年八月、後鳥羽天皇践祚。この後、通親は新帝の御乳母藤原範子(範兼の娘)を娶り、先夫との間の子在子を引き取って養女とした。
元暦二年(1185)正月、権中納言に昇進。文治二年(1186)三月、源頼朝の支持のもと、九条兼実が摂政に就任。この時通親は議奏公卿の一人に指名された。同三年正月、従二位。同五年正月、正二位(最終官位)。同年十二月、法皇寵愛の皇女覲子内親王(母は丹後局高階栄子)の勅別当に補される。以後、丹後局との結びつきを強固にし、内廷支配を確立してゆく。
建久元年(1190)七月、中納言に進む。同三年三月、後白河院が崩じ、摂政兼実が実権を握るに至るが、通親は故院の旧臣グループを中心に反兼実勢力を形成した。同六年十一月、養女の在子が皇子を出産(のちの土御門天皇)。同月、権大納言に昇る。建久七年(1196)十一月、任子の内裏追放と兼実の排斥に成功。同九年(1198)には外孫土御門天皇を即位させ、後鳥羽院の執事別当として朝政の実権を掌握。「天下独歩するの体なり」と言われ、権大納言の地位ながら「源博陸」(博陸は関白の異称)と呼ばれた(兼実『玉葉』)。
正治元年(1199)正月、右近衛大将に任ぜられる。その直後源頼朝が死去すると、通親排斥の動きがあり、院御所に隠れ籠る。結局幕府の支持を得て事なきを得、同年六月には内大臣に就任し、同二年四月、守成親王(のちの順徳天皇)立太子に際し、東宮傅を兼ねる。
和歌は若い頃から熱心で、嘉応二年(1170)秋頃、自邸で歌合を催している。同年の住吉社歌合・建春門院滋子北面歌合、治承二年(1178)の別雷社歌合などに参加。
殊に内大臣となって政局の安定を果したのちは、活発な和歌活動を展開し、後鳥羽院歌壇と新古今集の形成に向けて大きな役割を果すことになる。正治二年(1200)十月、初めて影供歌合を催し、以後もたびたび開催する。同年十一月には後鳥羽院百首歌会に参加(正治初度百首)。建仁元年(1201)三月、院御所の新宮撰歌合、同年六月の千五百番歌合に参加。同年七月には、二男通具と共に後鳥羽院の和歌所寄人に選ばれた。
しかし新古今集の完成は見ることなく、建仁二年(1202)冬、病に臥し、同年十月二十日夜(または二十一日朝)、薨去。五十四歳。民百姓に至るまで死を悲しみ泣き惑ったという(源家長日記)。贈従一位を宣下される。
著書には上記のほか『高倉院厳島御幸記』などがある。千載集初出。勅撰入集三十二首。】
(参考) 「九条兼実」と「源通親」周辺
「九条兼実」は、「藤原北家、関白・藤原忠通の六男。官位は従一位・摂政・関白・太政大臣。月輪殿、後法性寺殿とも呼ばれる」。一方の「源通親」は、「村上源氏久我流、内大臣・源雅通の子。官位は正二位・内大臣、右大将、贈従一位。土御門通親と呼ばれている」。
この二人は、共に、久安五年(一一四九)の同年の生まれで、没年は、兼実が、承元元年(一二〇七)、通親は、建仁二年(一二〇二)と、通親の方が、早く亡くなっている。
ここで、この通親が、「関白・兼実」を失脚させる「建久七年(一一九六)の政変」以降の、両者の「官職名」の推移を明記すると次のとおりとなる(『ウィキペディア(Wikipedia)』)。
「建久七年(一一九六)の政変」後の「兼実」
建久7年(1196年)11月25日:関白停任。無上表事。
建仁2年(1202年)1月28日:出家。法名「圓證」
承元元年(1207年)4月5日:薨去。享年59
「建久七年(一一九六)の政変」後の「通親」
建久9年(1198年)1月5日:後院別当を兼帯。
正治元年(1199年)
1月20日:右近衛大将を兼任。
6月22日:内大臣に転任。
6月23日:右近衛大将如元。
正治2年(1200年)4月15日:東宮傅を兼任。
建仁2年(1202年)10月21日、薨去。享年54。時に、内大臣正二位兼行右近衛大将東宮傅。
すなわち、兼実が出家した建仁二年(一二〇二)に、通親は、その生涯を閉じている。この通親の死について、兼実の異母弟の慈円の『愚管抄』は次のように記している。
http://www.st.rim.or.jp/~success/gukansyo06_yositune.html
【建仁二年十月廿一日ニ。通親公等ウセニケリ。頓死ノ躰ナリ。不可思議ノ事ト人モ思ヘリケリ。承明門院〔在子〕ヲゾ母ウセテ後ハアイシ参ラセケル。カカリケル程ニ。院ハ範季ガムスメヲ思召テ三位セサセテ。美福門院ノ例ニモニテ有ケルニ。王子モアマタ出キタル。御アニ〔守成〕ヲ東宮ニスエマイラセントヲボシメシタル御ケシキナレバ。通親ノ公申沙汰シテ立坊有テ。正治二年四月十四日ニ東宮ニ立テ。カヤウニテ過ル程ニ。九條〔良経〕殿ハ又北政所ニヲクレテ出家セラレニケリ。サル程ニ院ノ御心ニフカク世ノカハリシ我ガ御心ヨリヲコラズト云コトヲ人ニモシラレントヤ思召ケン。建仁二年十一月廿七日ニ。左大臣〔良経〕ニ内覧氏長者ノ宣旨ヲクダシテ。ヤガテ廿八日ニ熊野御進発ナリニケリ。母北政所重服コノ十二月バカリニテアリケリ。サテ熊野ヨリ御帰洛ノ後。十二月廿七日ニ摂政ノ詔クダサレニケリ。サテ正月一日ノ拝禮ノサキニヨロコビ申サセラレニケレバ。世ノ人ハコハユユシク目出キコトカナト思ケリ。宗頼大納言ハ成頼入道ガ高野ニ年比ヲコナイテアリケル入滅シタル服ヲキルベキヲ。真ノ親ノ光頼ノ大納言ガヲバ成頼ガヲキムズレバトテキザリケリ。是ハ又アマリニ世ニアイテイトマヲオシガリテキズ。サテ親モナカリケル者ニナリヌル事ヲ。人モカタブキケルニヤ。カク熊野ノ御幸ノ御トモニマイリテ。松明ノ火ニテ足ヲヤキタリケルガ。サシモ大事ニナリテ正月卅日ウセニケル。其後卿二位ハ夫ヲウシナイテ又トカクアンジツツ。コノ太相國頼実ノ七條院辺〔後鳥羽院御母〕ニ申ヨリテ候ケルニ申ナドシテ。又夫ニシテヤガテ院ノ御ウシロミセサセテ候ケル。】(『愚管抄第六』=上記アドレス)
この「建仁二年十月廿一日ニ。通親公等ウセニケリ。頓死ノ躰ナリ。不可思議ノ事ト人モ思ヘリケリ」の「頓死」とは「急死」のことであり、「不可思議ノ事ト人モ思ヘリケリ」については、例えば『藤原定家『明月記』の世界(村井康彦著・岩波新書)』では、「これまでの権謀術数の数々を思えば、敵はゴマンといたはずで、密かに殺害されたのではないかという疑念を抱かれてもおかしくない」と紹介されている。
これに続く、「建仁二年十一月廿七日ニ。左大臣〔良経〕ニ内覧氏長者ノ宣旨ヲクダシテ。」、そして、「十二月廿七日ニ摂政ノ詔クダサレニケリ。」と、失脚した兼実(この時には出家している)の継子の「九条良経」は、後鳥羽院の宣旨をもって「藤氏長者」(藤原氏一族全体の氏長者)となり、さらに、良経は、「左大臣」(「関白」にならず)のまま土御門天皇の「摂政」(君主に代わって政務をとること,またはその者)と朝廷のトップに立つこととなる。
この時、良経、三十五歳、この宣旨・詔を発した後鳥羽院は、二十三歳で、兼実は出家、
通親は頓死、既に後白河法皇・源頼朝も没しており、名実ともに治天の君となった。しかし、この良経は、元久三年(一二〇六)三月七日深夜に頓死。享年三十八歳であった。この良経の頓死(急死)についても、下記のアドレスで触れてきた。
https://yahan.blog.ss-blog.jp/2020-11-03
そして、承久三年(一二二一)の「承久の乱」(後鳥羽院と時の執権・北条義時との戦乱)により、後鳥羽院は隠岐島(隠岐国海士郡の中ノ島、現海士町)に配流され、そこで、延応元年(一二三九)に、その六十年の生涯を閉じた。
ここで、上記の『愚管抄第六』の事項を理解するには、下記のアドレスの図解が恰好のものである。
http://dabohazj.web.fc2.com/kibo/note/motomichi/motomichi.htm
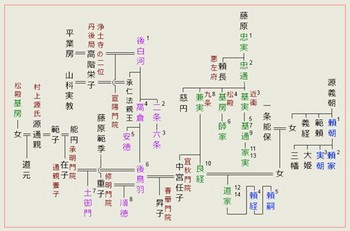
(「後白河~順徳天皇」・「藤原忠実~道家」・「源頼朝~頼嗣)」と「兼実と通親」関連図)
一 天皇家は、「1後白河→2二条→3六条→4高倉→5安徳→6後鳥羽→7土御門→8順徳」の流れである。
二 藤原家は、「1忠実→2忠通→3基実(近衛家)→4基房(松殿家)→5・7・9基通(近衛家)→6師家(松殿家)→8兼実(九条家)→10良経(九条家)→11・13家実(近衛家)→12・14道家」の流れである。
三 源頼朝家→1頼朝→2頼家→3実朝→4頼経→5頼嗣の流れである。
四 後鳥羽院=任子(兼実の娘、良経の妹)、後鳥羽院=在子(通親の養女、通親正室範子の娘)、後鳥羽院と任子(宜秋門院)の内親王=昇子(春華門院)、後鳥羽院と在子(承明門院)の親王=土御門天皇、後鳥羽院と重子(修明門院)の親王=順徳天皇
五 源通親の側室(兼実の兄・基房の娘)
六 兼実の娘任子は後鳥羽天皇の中宮宜秋門院となっているが、建久六年(1195)八月に女子を産む(昇子・春華門院)。源通親の養女・在子は宮仕していたが同十一月に皇子(為仁・土御門天皇)を生む。これで通親と兼実の形勢が逆転し、通親による「建久七年の政変」が起こり、かねて憎まれていた兼実は失脚する。そして、村上源氏の全盛時代となり、古い後白河派とみなされた近衛基通が10年ぶりに関白として返り咲く(上掲および前掲 系図 の基通の数字「9」)。
七 建久九年(1198年)正月に後鳥羽天皇(十九歳)は土御門天皇へ践祚した。これで通親は天皇の外祖父の地位を得たのであり、後鳥羽は若い院としての自由な立場を得て京都内外を活発に「御幸」したという。祖父・後白河の血が確かに伝わっていたのであろう。基通は土御門天皇(四歳)の摂政にもなる。政治の実権を握っていた通親は正治元年(1199)に内大臣となり、「源博陸」(げんはくりく、博陸は関白の意)と呼ばれた。
八 通親は建仁二年(1202)十月に急死(享年五十四歳)する。それを契機に九条家にバランスをとる人事がなされ、摂政が九条良経に移る。良経は溢れるほどの才能に恵まれた人物だったようで慈円が『愚管抄』に「コノ人は三ツノ舟ニノリヌベキ人」(詩・和歌・管弦の三つの舟)と言葉を極めて賞讃している。その良経は元久三年(1206)二月廿日に急死(享年三十八歳)する(『愚管抄』は「ネ死ニ頓死」、『玉葉』は夕刻まで良経が普段通りであったことを記したあと、良経の「女房」が走ってきて急を知らせ、兼実が「劇速して行く」が「身冷気絶」であったと)。このため良経の死には他殺説もある。
九 良経の急死を受け、近衛家実が摂政となった。基通の息子である。こののちは、松殿は摂関家としては基房-師家で絶え、近衛家と九条家のバランスを考えた人事となって、文永十年(1273)この両家から「五摂家」が成立する(近衛家・鷹司家・九条家・一条家・二条家)。「五摂家」体制のもとで江戸時代終末まで形式的な摂関は続く。
十 三代将軍実朝の暗殺で頼朝の系譜は断たれる。上掲系図のように、良経は義朝の娘と婚姻し、九条家が将軍となるきっかけを作っている。藤原将軍時代である。しかしそれも2代しか続かず、そのあとは親王将軍の時代となる。
四季草花下絵千載集和歌巻(その二十) [光悦・宗達・素庵]
(その二十) 和歌巻(その二十)
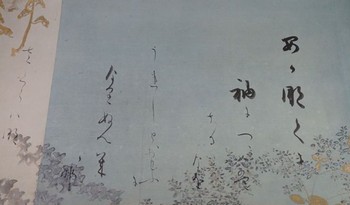
「光悦筆 四季草花宗達下絵和歌巻」(日本古典文学会・貴重本刊行会・日野原家蔵一巻)
落花の心をよめる
91 あかなくに袖につゝめばちる花をうれしと思ふになりぬべきかな(権大納言実国)
(散る花への飽きることのない愛惜の心から、それを袖に包みとると、花が散るのは悲しいのに、かえって喜んでいるようになってしまいそうだよ。)
釈文(揮毫上の書体)=(『書道芸術第十八巻 本阿弥光悦』)
安可那久尓(あかなくに)袖尓(袖に)つ々め盤(ば)知る(ちる)ハな(花)をう連(れ)しとおもふ尓(に)な里(り)ぬべ幾(き)可那(かな)
※安可那久尓(あかなくに)=飽きることがないのに。
http://www.asahi-net.or.jp/~SG2H-YMST/yamatouta/sennin//sanekuni.html
【藤原実国(ふじわらのさねくに) 保延六~寿永二(1140-1183)
太政大臣実行の孫。内大臣公教の子。左大臣実房の兄。母は家の女房。子には公時・公清ほかがいる。妻の藤原家成女は、藤原重家室と姉妹。
久安三年(1147)叙爵し、保元四年(1159)、蔵人頭。左衛門督などを歴任し、権大納言正二位に至る。寿永二年(1183)一月二日、四十四歳で薨ず。
縁戚関係のあった六条藤家と歌壇的にも深いつながりを持った。永万二年(1166)の中宮亮重家朝臣家歌合、嘉応二年(1170)十月の住吉社歌合・建春門院北面歌合、承安二年(1172)十二月の広田社歌合、治承二年(1178)の別雷社歌合などに出詠。また嘉応二年(1170)五月、自邸で歌合を主催し(実国家歌合)、判者に六条藤家の清輔を招いた。
家集『実国集』がある。千載集初出。高倉天皇の笛の師。『古今著聞集』に歌人としての逸話を残している。滋野井実国とも。滋野井家の祖。 】
(参考) 「右近大将実房」と「権大納言実国」周辺
『千載和歌集』が成った文治三年(一一八七)には、「権大納言実国」は亡くなっている(寿永二年=一一八三没)。この「権大納言」は実国の最後の官職名である。その弟の「右近大将実房」は、実国が亡くなった時には「大納言」で、「右近大将」を兼任したのは、『千載和歌集』が成る一年前の文治二年(一一八六)のことである。
この実国は、高倉天皇の笛の師で、この高倉天皇の母(国母)の「建春門院(平慈子)」(後白河天皇の女御・皇太后・女院)である。この建春門院の院号を宣下された翌年の、嘉応二年(一一七〇)十月の「住吉社歌合・建春門院北面歌合」には、「公通(左)対※※※俊成(右)、実定(左)対※※重家(右)、隆季※※(左)対※※清輔(右)、※実房(左)対実家、※実国(左)対頼政(右)、実守(左)対※※※隆信(右)、脩範(左)対通親(右)」の名が見られる。
https://archive.wul.waseda.ac.jp/kosho/he04/he04_03121/he04_03121_p0003.jpg
https://archive.wul.waseda.ac.jp/kosho/he04/he04_03121/he04_03121_p0004.jpg
この「建春門院北面歌合」には、「※実房(左)対実家、※実国(左)対頼政(右)」と、「※実国・※実房」兄弟は、「高倉天皇・建春門院」(後白河院政下)を支える、その一翼を担っていたのであろう。
同時に、この当時は、「実定(左)対※※重家(右)、隆季※※(左)対※※清輔(右)」の「※※重家」(「六条藤家」の顕輔の四男、子に「顕家・有家」)、「※※隆季」(「六条藤家」の顕季→家保→隆季)、「※※清輔」(「六条藤家」の顕輔の二男)と、いわゆる「歌の家」の筆頭の「六条藤家」時代であったということであろう。
同様に、この当時の、「御子左家」は、「公通(左)対※※※俊成(右)」「実守(左)対※※※隆信(右)」の「※※※俊成」と「実守(左)対※※※隆信(右)」の「※※※隆信」の二人であるが、この「※※※隆信」は、「母=美福門院加賀(藤原親忠女)、実父=藤原為経(寂超)、養父=俊成(美福門院加賀の再婚相手、定家は「異父弟」)で、「御子左家」に連なる歌人であるが、同時に「美福門院」(六条藤家の藤原清輔は従兄弟にあたる)と、「美福門院-八条院-二条天皇」の近臣でもあり、「六条藤家」と「御子左家」とを結びつける歌人というのが、より、その立つ位置を明瞭にしているのかも知れない。
さらに、この「建春門院北面歌合」には、「脩範(左)対通親」の「通親」の名も見られ、その官職名は「少将」と詠める。
この当時は、「俊成」(皇后宮太夫)、「実国」(左衛門督)、「実国」(権大納言)、「顕輔」(権大納言)と同等というよりも下級職で、後に、「建久七年(一一九六)の政変」で、「関白・九条兼実」を失脚させて、「源博陸(はくりく・はくろく)」(博陸=関白の唐名)と権勢を極めた「土御門通親」の面影はない。
ちなみに、この通親(右近衛少将)に対する「脩範(左近衛少将)」は、保元の乱(保元元年=一一五六)で勝者になった後白河院側の立役者の「信西=藤原通憲」の五男で、この乱後は
左近衛少将まで昇り上がるが、続く、平治の乱(保元四年=一一五九)で、信西は自害、信西の子息(俊憲・貞憲・成憲・脩憲)は全員流罪となり、脩憲(ながのり)は隠岐に流刑される。
この平治の乱は、「後白河院政派(信西派と反信西派=信頼派)」と「二条天皇親政派(美福門院派)」との対立、「源氏一門(源義朝派=信頼派と源頼政派=美福門院派)」と「平氏一門」(信西派で信西派が放逐された後、信頼派と源義朝派を放逐)との対立、これらが、平治元年(一一五九)から同二年(一一六〇)にかけて合戦が続くのだが、結果的には、続く、治承三年(一一七九)の政変(平清盛が軍勢を率いて京都を制圧、後白河院政を停止した事件)により、平清盛による「平氏政権の確立」と連なっている。
しかし、この平氏政権も、次のような政変・合戦を経ながら、源氏政権(鎌倉幕府)へと移行して行くことになる。
治承四年(一一八〇) 以仁王の挙兵 → 「以仁王・源頼政」対「平氏」
治承五年(一一八一) 高倉上皇崩御後白河法皇院政復活、平清盛死去
墨俣川の戦い → 「源行家・尾張源氏」対「平氏」
寿永二年(一一八三) 倶利伽羅峠の戦い → 「源(木曽)義仲」対「平氏」
平氏都落ち、後鳥羽天皇践祚
法住寺合戦 → 「後白河法皇」対「源(木曽)義仲」
寿永三年(一一八四) 宇治川の戦い → 「源範頼・源義経」対「源(木曽)義仲」
一ノ谷の戦い → 「源範頼・源義経」対「平氏」
元暦二年(一一八五) 屋島の戦い → 「源義経」対「平氏」
壇ノ浦の戦い → 「源範頼・源義経」対「平氏」
建久元年(一一九〇) 頼朝上洛により鎌倉幕府と朝廷の協調体制樹立
建久三年(一一九二) 後白河法皇が崩御、源頼朝の征夷大将軍の任命、鎌倉幕府確立
承久三年(一二二一) 承久の乱(院政終了)→「後鳥羽院」対「鎌倉幕府(北条義時・正子)」
上記の「「住吉社歌合・建春門院北面歌合」は、嘉応二年(一一七〇)、関白・兼実の失脚する「建久七年の政変」は、建久七年(一一九六)のことである。すなわち、この「嘉応二年(一一七〇)~建久七年(一一九六)」の時代は、「平家政権から平家の滅亡、そして、源氏政権の樹立」という、大乱世の時代で、そこには、さまざまなドラマが渦巻いている。
この『千載和歌集』が成った「文治三年(一一八七)」は、「壇ノ浦の戦い」の安徳天皇が入水崩御した二年後のことなのである。これらのさまざまなドラマが、この『千載和歌集の底流に流れている。
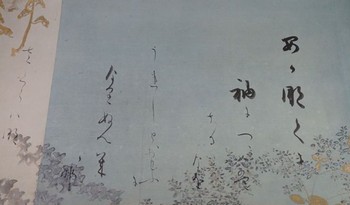
「光悦筆 四季草花宗達下絵和歌巻」(日本古典文学会・貴重本刊行会・日野原家蔵一巻)
落花の心をよめる
91 あかなくに袖につゝめばちる花をうれしと思ふになりぬべきかな(権大納言実国)
(散る花への飽きることのない愛惜の心から、それを袖に包みとると、花が散るのは悲しいのに、かえって喜んでいるようになってしまいそうだよ。)
釈文(揮毫上の書体)=(『書道芸術第十八巻 本阿弥光悦』)
安可那久尓(あかなくに)袖尓(袖に)つ々め盤(ば)知る(ちる)ハな(花)をう連(れ)しとおもふ尓(に)な里(り)ぬべ幾(き)可那(かな)
※安可那久尓(あかなくに)=飽きることがないのに。
http://www.asahi-net.or.jp/~SG2H-YMST/yamatouta/sennin//sanekuni.html
【藤原実国(ふじわらのさねくに) 保延六~寿永二(1140-1183)
太政大臣実行の孫。内大臣公教の子。左大臣実房の兄。母は家の女房。子には公時・公清ほかがいる。妻の藤原家成女は、藤原重家室と姉妹。
久安三年(1147)叙爵し、保元四年(1159)、蔵人頭。左衛門督などを歴任し、権大納言正二位に至る。寿永二年(1183)一月二日、四十四歳で薨ず。
縁戚関係のあった六条藤家と歌壇的にも深いつながりを持った。永万二年(1166)の中宮亮重家朝臣家歌合、嘉応二年(1170)十月の住吉社歌合・建春門院北面歌合、承安二年(1172)十二月の広田社歌合、治承二年(1178)の別雷社歌合などに出詠。また嘉応二年(1170)五月、自邸で歌合を主催し(実国家歌合)、判者に六条藤家の清輔を招いた。
家集『実国集』がある。千載集初出。高倉天皇の笛の師。『古今著聞集』に歌人としての逸話を残している。滋野井実国とも。滋野井家の祖。 】
(参考) 「右近大将実房」と「権大納言実国」周辺
『千載和歌集』が成った文治三年(一一八七)には、「権大納言実国」は亡くなっている(寿永二年=一一八三没)。この「権大納言」は実国の最後の官職名である。その弟の「右近大将実房」は、実国が亡くなった時には「大納言」で、「右近大将」を兼任したのは、『千載和歌集』が成る一年前の文治二年(一一八六)のことである。
この実国は、高倉天皇の笛の師で、この高倉天皇の母(国母)の「建春門院(平慈子)」(後白河天皇の女御・皇太后・女院)である。この建春門院の院号を宣下された翌年の、嘉応二年(一一七〇)十月の「住吉社歌合・建春門院北面歌合」には、「公通(左)対※※※俊成(右)、実定(左)対※※重家(右)、隆季※※(左)対※※清輔(右)、※実房(左)対実家、※実国(左)対頼政(右)、実守(左)対※※※隆信(右)、脩範(左)対通親(右)」の名が見られる。
https://archive.wul.waseda.ac.jp/kosho/he04/he04_03121/he04_03121_p0003.jpg
https://archive.wul.waseda.ac.jp/kosho/he04/he04_03121/he04_03121_p0004.jpg
この「建春門院北面歌合」には、「※実房(左)対実家、※実国(左)対頼政(右)」と、「※実国・※実房」兄弟は、「高倉天皇・建春門院」(後白河院政下)を支える、その一翼を担っていたのであろう。
同時に、この当時は、「実定(左)対※※重家(右)、隆季※※(左)対※※清輔(右)」の「※※重家」(「六条藤家」の顕輔の四男、子に「顕家・有家」)、「※※隆季」(「六条藤家」の顕季→家保→隆季)、「※※清輔」(「六条藤家」の顕輔の二男)と、いわゆる「歌の家」の筆頭の「六条藤家」時代であったということであろう。
同様に、この当時の、「御子左家」は、「公通(左)対※※※俊成(右)」「実守(左)対※※※隆信(右)」の「※※※俊成」と「実守(左)対※※※隆信(右)」の「※※※隆信」の二人であるが、この「※※※隆信」は、「母=美福門院加賀(藤原親忠女)、実父=藤原為経(寂超)、養父=俊成(美福門院加賀の再婚相手、定家は「異父弟」)で、「御子左家」に連なる歌人であるが、同時に「美福門院」(六条藤家の藤原清輔は従兄弟にあたる)と、「美福門院-八条院-二条天皇」の近臣でもあり、「六条藤家」と「御子左家」とを結びつける歌人というのが、より、その立つ位置を明瞭にしているのかも知れない。
さらに、この「建春門院北面歌合」には、「脩範(左)対通親」の「通親」の名も見られ、その官職名は「少将」と詠める。
この当時は、「俊成」(皇后宮太夫)、「実国」(左衛門督)、「実国」(権大納言)、「顕輔」(権大納言)と同等というよりも下級職で、後に、「建久七年(一一九六)の政変」で、「関白・九条兼実」を失脚させて、「源博陸(はくりく・はくろく)」(博陸=関白の唐名)と権勢を極めた「土御門通親」の面影はない。
ちなみに、この通親(右近衛少将)に対する「脩範(左近衛少将)」は、保元の乱(保元元年=一一五六)で勝者になった後白河院側の立役者の「信西=藤原通憲」の五男で、この乱後は
左近衛少将まで昇り上がるが、続く、平治の乱(保元四年=一一五九)で、信西は自害、信西の子息(俊憲・貞憲・成憲・脩憲)は全員流罪となり、脩憲(ながのり)は隠岐に流刑される。
この平治の乱は、「後白河院政派(信西派と反信西派=信頼派)」と「二条天皇親政派(美福門院派)」との対立、「源氏一門(源義朝派=信頼派と源頼政派=美福門院派)」と「平氏一門」(信西派で信西派が放逐された後、信頼派と源義朝派を放逐)との対立、これらが、平治元年(一一五九)から同二年(一一六〇)にかけて合戦が続くのだが、結果的には、続く、治承三年(一一七九)の政変(平清盛が軍勢を率いて京都を制圧、後白河院政を停止した事件)により、平清盛による「平氏政権の確立」と連なっている。
しかし、この平氏政権も、次のような政変・合戦を経ながら、源氏政権(鎌倉幕府)へと移行して行くことになる。
治承四年(一一八〇) 以仁王の挙兵 → 「以仁王・源頼政」対「平氏」
治承五年(一一八一) 高倉上皇崩御後白河法皇院政復活、平清盛死去
墨俣川の戦い → 「源行家・尾張源氏」対「平氏」
寿永二年(一一八三) 倶利伽羅峠の戦い → 「源(木曽)義仲」対「平氏」
平氏都落ち、後鳥羽天皇践祚
法住寺合戦 → 「後白河法皇」対「源(木曽)義仲」
寿永三年(一一八四) 宇治川の戦い → 「源範頼・源義経」対「源(木曽)義仲」
一ノ谷の戦い → 「源範頼・源義経」対「平氏」
元暦二年(一一八五) 屋島の戦い → 「源義経」対「平氏」
壇ノ浦の戦い → 「源範頼・源義経」対「平氏」
建久元年(一一九〇) 頼朝上洛により鎌倉幕府と朝廷の協調体制樹立
建久三年(一一九二) 後白河法皇が崩御、源頼朝の征夷大将軍の任命、鎌倉幕府確立
承久三年(一二二一) 承久の乱(院政終了)→「後鳥羽院」対「鎌倉幕府(北条義時・正子)」
上記の「「住吉社歌合・建春門院北面歌合」は、嘉応二年(一一七〇)、関白・兼実の失脚する「建久七年の政変」は、建久七年(一一九六)のことである。すなわち、この「嘉応二年(一一七〇)~建久七年(一一九六)」の時代は、「平家政権から平家の滅亡、そして、源氏政権の樹立」という、大乱世の時代で、そこには、さまざまなドラマが渦巻いている。
この『千載和歌集』が成った「文治三年(一一八七)」は、「壇ノ浦の戦い」の安徳天皇が入水崩御した二年後のことなのである。これらのさまざまなドラマが、この『千載和歌集の底流に流れている。
四季草花下絵千載集和歌巻(その十九) [光悦・宗達・素庵]
(その十九) 和歌巻(その十九)

「光悦筆 四季草花宗達下絵和歌巻」(日本古典文学会・貴重本刊行会・日野原家蔵一巻)
花留客(花客ヲ留ム)といへる心をよみ侍ける
90 ちりかゝる花のにしきは着たれどもかへらむ事ぞわすられにける(右近大将実房)
(落花の下、花の錦は身につけたが、花に心を奪われて故郷へ帰ることを忘れてしまったよ。)
釈文(揮毫上の書体)=(『書道芸術第十八巻 本阿弥光悦』)
知利懸(ちりかかる)ハな(はな)能(の)錦盤(は)きた連(れ)ども帰無事(かへらむこと)曾(ぞ)わ須(す)ら禮(れ)尓(に)介流(ける)
※知利懸(ちりかかる)=散りかかる。
※ハな(はな)能(の)錦=花の錦。衣の上に花の散ったさまを錦に見立てた。
※きた連(れ)ども=着たれども。身にまとったが。
※帰無事(かへらむこと)=(花に心を奪われて)故郷へ帰らんことを。
※わ須(す)ら禮(れ)尓(に)介流(ける)=忘れにける。忘れてしまったよ。
http://www.asahi-net.or.jp/~sg2h-ymst/yamatouta/sennin/sanehusa.html
【藤原実房(ふじわらのさねふさ) 久安三~嘉禄元(1147-1225) 号:三条入道左大臣
三条内大臣公教の三男。母は権中納言藤原清隆女。権大納言実国の弟。太政大臣公房・権大納言公宣・同公氏の父。
仁平二年(1152)叙爵。左少将・右中将などを経て、永暦元年(1160)、蔵人頭。同年従三位。永万二年(1166)、権中納言。仁安二年(1167)、従二位に叙され中納言に転じる。同三年、権大納言。承安元年(1171)、正二位。寿永二年(1183)、大納言。文治五年(1189)、右大臣。建久元年(1190)、左大臣に至る。同七年、病により引退。法名は静空。
住吉社歌合・広田社歌合・御室五十首・文治六年(1190)女御入内御屏風歌・正治二年初度百首などの作者。日記『愚昧記』がある。千載集初出。勅撰入集三十首。『歌仙落書』に「義理を存候、言葉妙也。末床しきさまなり」の評がある。 】
(参考) 「建久七年(一一九六)の政変」(九条兼実・良経の失脚と源通親の台頭)周辺
藤原俊成の編んだ『千載和歌集』の、「89左近中将良経→90右近大将実房→91権大納言実国→92権中納言通親」の収載配列(上記の和歌巻は、右側の部分図が前回の「89左近中将良経」の一首、左側が今回の「90右近大将実房」、「91権大納言実国」と「92権中納言通親」は、この後に続く)は、この十年後に勃発する「建久七年(一一九六)の政変」(九条兼実・良経の失脚と源通親の台頭)の予兆を感じさせるような趣で無くもない。
今回の「90右近大将実房」は、本姓は「藤原」だが、三条内大臣公教の三男で「三条実房」、二男の「91権大納言実国」は「滋野井実国」と、その姓は「三条家」(実房)、そして「滋野井家」(実国)が通姓のようである。
そして、この実房が、「大納言」と「右近衛大将」(右近衛に置かれた近衛大将)とを兼任したのは、文治二年(一一八六)のことで、この時に、「89左近中将良経」は、「正三位に昇叙、左近衛中将・播磨権守は元の如し」(若干十七歳)と、まさに、「九条兼実・良経」親子の絶頂期を迎える頃で、この「九条兼実・良経」親子のサポートの基に、「御子左家」(「藤原俊成・定家」親子等々の「歌道の家」)は、それまでの「六条藤家」(「藤原顕輔・清輔」親子等々の歌道の家)に代わり、それが俊成(「御子左家」)による、この第七勅撰集『千載和歌集』の撰集へと繋がっている。
そして、この実房は、九条兼実を支える両翼の一人(もう一人は「徳大寺実定」)で、これらの、当時(文治二年=一一八六)の官職名等は次のとおりである。
九条兼実 → 摂政宣下。藤原氏長者宣下。右大臣如元(十月、辞任)。建久二年(一一九一)=関白宣下。准摂政宣下。
徳大寺実定→ 右大臣(十月)。文治五年(一一八九年)七月左大臣となり、兼実の片腕として朝幕間の取り次ぎに奔走する。
三条実房 → 右近衛大将を兼ねる(寿永二年=大納言)。文治四年(一一八八)=左近衛大将、翌年=右大臣(左大将兼務)、その翌年(建久元年)=左大臣。
九条良経 → 正三位に昇叙、左近衛中将・播磨権守は元の如し。建久六年(一一九五)=内大臣に転任。11月12日、左近衛大将は元の如し。
これらの、当時の朝廷のトップ層の「九条兼実」派と当時の歌壇の主流となってきた「御子左家」派等が一同に名を連ねている「屏風歌」(長寿を祝う算賀、裳着(もぎ)、入内(じゅだい)、大嘗会等の行事のための屏風調進に伴って詠作される和歌)がある。
それは、「文治六年(一一九〇) 女御入内御屏風歌」で、その作者(詠進歌人)は「兼実(関白)・実定(左大臣)・実房(右大臣)・良経(近衛大将)・季経(「御子左家」寄りの「六条藤家」)・隆信(「六条藤家」寄りの「御子左家」)・定家(「御子左家」の嫡子)・俊成(「御子左家」再興の祖)の八名である。
この「文治六年(一一九〇) 女御入内御屏風歌」については、次のアドレスの「勅撰集の中の入内屏風和歌 : 作者・詞書を手がかりに(細川佐知子稿)」の論攷の中で、次のように紹介されている。
https://ir.library.osaka-u.ac.jp/repo/ouka/all/67625/shirin49_001.pdf
「文治六年(四月一一日より建久)正月に後鳥羽天皇に入内した、九条兼実の女任子の入内屏風和歌である。(中略) 月次一二帖(各月三面)三六面の屏風と夏・冬二面の泥絵記すために詠出されたものである。作者は、兼実・実定・実房・良経・季経・隆信・定家・俊成の八名で、各人が三八首詠じ、各面一首ずつ選定された。選定は俊成・実定が下選びをし、兼実が最終決定した。屏風歌に選定された歌だけでなく、全歌が作品として残る。」(「勅撰集の中の入内屏風和歌 : 作者・詞書を手がかりに(細川佐知子稿)」)
ここで、『藤原定家『明月記』の世界(村井康彦著・岩波新書)』で、この「文治六年(一一九〇) 女御入内御屏風歌」の二年後の『明月記』(定家の五十五カ年にわたる漢文体の「日記」)の「建久三年(一一九二)三月六日の条を紹介したい。
【六日、天晴、巳時(午前十時頃)「院」に入る。人々多く参る。未刻(午後二時頃)退出し、「七条」(院)・「八条院」へ参り、「家」に帰る。昏(夕方)に「内」(内裏)に参る。人なきにより、独り「宮御方」(任子・宜秋門院)に参り、格子を下ぐる後、「大将殿」(九条良経)に参り見参の後、「宮御方」(任子)に帰り参る。深更、又「大将殿」(良経)に参り、暁鐘の程「蓬」(自宅)に戻る。 】(『藤原定家『明月記』の世界(村井康彦著・岩波新書)』所収「序章『明月記』とは」)
ここに出てくる、定家の「出仕先」(公務として出向いた先)の「院」・「七条院」・「八条院」・「内」・「宮御方」・「大将殿」と、その「殿舎」(その出仕先の殿舎)は、次のとおりである。
※「大将殿」=九条良経(近衛大将)、「九条家」の「家司(けし)=貴人に供奉する秘書役など」として仕えた定家の「九条家の御曹司」)→「一条殿」(当時の「良経」の殿舎)
※「内」(「内裏」=「里内裏」)「宮御方」(後鳥羽中宮、任子、宜秋門院、兼実の息女、良経の妹)→「閑院(中宮御所)」(当時の「任子」の殿舎)
※「院」(後白河院、後白河院の崩御=建久三年三月十三日、上記の『明月記』=建久三年三月六日で、この一週間後「院」は亡くなる。)→「六条殿」→「建久3年(1192年)2月18日、雨の降る中を後鳥羽天皇が見舞いのため六条殿に行幸する(『玉葉』同日条)。後白河院は「事の外辛苦し給ふ」という病状だったが(『玉葉』2月17日条)大いに喜んで、後鳥羽の笛に合わせて今様を歌っている。後鳥羽帝が還御すると、後白河院は丹後局を使者として遺詔を伝えた。その内容は、法住寺殿・蓮華王院・六勝寺・鳥羽殿など主要な部分を天皇領に、他の院領は皇女の亮子・式子・好子・覲子にそれぞれ分与するというもので(『明月記』3月14日条)、後白河院に批判的な九条兼実も「御処分の体、誠に穏便なり」としている。」(『ウィキペディア(Wikipedia)』)
※「七条院(後鳥羽母)」=高倉天皇の後宮。後高倉院(守貞親王)と後鳥羽天皇の母=藤原 殖子 → 「三条殿」(七条院の殿舎)
※「八条院(鳥羽皇女、美福門院女)」=暲子内親王。「近衛天皇は同母弟、崇徳・後白河両天皇は異母兄にあたる。ほかに母を同じくする姉妹に、早世した叡子内親王と二条天皇中宮となった姝子内親王(高松院)がいる。終生、未婚であったが、甥の二条天皇の准母となったほか、以仁王とその子女、九条良輔(兼実の子)、昇子内親王(春華門院、後鳥羽上皇の皇女)らを養育した。」(『ウィキペディア(Wikipedia)』)
※「家」「蓬」(自宅)=当時の「定家」宅(九条宅)→「九条殿」(九条兼実の「殿舎」)に隣接している。定家の父の俊成宅は「五条京極邸」邸でそことは異なる。
これらの解説(解読)は、『藤原定家『明月記』の世界(村井康彦著・岩波新書)』の、下記の「目次」の随所にわたって、図表入りで、その一端が論述されている。
「序章」 →『明月記』とは
「第一章」→五条京極邸 1 五条三位 2 百首歌の時代
「第二章」→政変の前後 1 兼実の失脚 2 女院たちの命運 3 後鳥羽院政の創始 4 定家の「官途絶望」
「第三章」→新古今への道 1 正治初度百首 2 和歌所と寄人 3 終わりなき切継ぎ 4 水無瀬の遊興
ここでは、「文治六年(一一九〇) 女御入内御屏風歌」とその二年後の『明月記』(「建久三年=一一九二・三月六日の条」)の記載と「建久七年(一一九六)の政変」(九条兼実・良経の失脚と源通親の台頭)との関連などについて記して置きたい。
一 「建久七年(一一九六)の政変」(九条兼実・良経の失脚と源通親の台頭)とは、すべからく、『明月記』(「建久三年=一一九二・三月六日の条」)の、その一週間後の、建久三年(一一九二)三月十三日の「後白河院」の崩御を起因として勃発する。
二 この「後白河院政」から「後鳥羽院院政」への移行期を支えた体制は、「文治六年(一一九〇) 女御入内御屏風歌」の、「九条兼実体制(関白・兼実、左大臣・実定、右大臣・実房、近衛大将・良経)であったが、この時に、既に、「関白・兼実」の両翼の、「左大臣・実定」は「建久二年、病のため官を辞して出家、同年閏十二月に崩御」、「右大臣・実房」は、建久七年(一一九六)三月、病により左大臣を辞し、出家」している。
すなわち、「建久七年(一一九六)の政変」(九条兼実・良経の失脚と源通親の台頭)とは、それまでの「後白河(後鳥羽)・兼実」体制から、新しく「後鳥羽・通親」体制への移行ということを意味する。
三 そして、この「建久七年(一一九六)の政変」の背後には、親幕(親鎌倉)派の「兼実」に対する反幕(反鎌倉)感情を強めていた後白河院の寵妃「丹後局(高階栄子)」と「兼実」の娘の中宮「任子(宜秋門院)」を退けて「通親」の養女「在子(承明門院)」を後宮入りさせる画策とが、後白河院の没後に結実したということが挙げられよう。
建久六年(一一九五)八月十二日 任子、第一皇女昇子内親王(後に「春華門院」)を出産。
同 十一月一日 在子、第一皇子為仁親王(後に「土御門天皇)を出産。
四 この時(建久六年=一一九五)、任子、二十二歳、在子、二十四歳、後鳥羽天皇、十五歳、この後鳥羽天皇の外戚として、関白・兼実が強権を揮っていたが、この時を境に、権大納言・通親が実権を握り、その翌年(建久七年=一一九六)の十一月二十四日に、「八条院」(鳥羽皇女・美福門院女、兼実・四男=良輔と昇子内親王の養母)に居を移し、その翌日に、兼実は失脚している。これが、「建久七年(一一九六)の政変」の実態なのである。
五、しかし、この時点では、任子の再入内の余地は十分に残されていたのだが、正治元年(一一九六)、任子の兄の九条良経が左大臣となり政権に復帰した、その翌年の正治二年(一二〇〇)六月二十八日に、任子への「宜秋門院」の院号宣下があり、ここで、名実ともに、「後白河(後鳥羽)・兼実」体制から「後鳥羽・通親」体制へと移行することとなる。
六 ここで、「建久七年(一一九六)の政変」は、「クーデターでなく、兼実が目指していた外戚摂関再興の途が閉ざされたことによる『関白辞職』である」とする、下記のアドレスの論攷などは、やはり、上記の「建久七年(一一九六)の政変」の実態と併せ、その真実の一端を語っているものであろう。
https://hosei.repo.nii.ac.jp/?action=pages_view_main&active_action=repository_view_main_item_detail&item_id=11199&item_no=1&page_id=13&block_id=83
↓
「建久七年の九条兼実『関白辞職』」(遠城悦子稿)」
七 さらに、ここで、下記のアドレスで触れた「平安京条坊図(大内裏周辺)」と、上記で紹介した『藤原定家『明月記』の世界(村井康彦著・岩波新書)』の冒頭の『明月記』の「建久三年(一一九二)三月六日の条」とを重ね合わせると、様々なことかイメージ化されてくる。
https://yahan.blog.ss-blog.jp/2020-10-23
↓
平安京条坊図(大内裏周辺)
↓
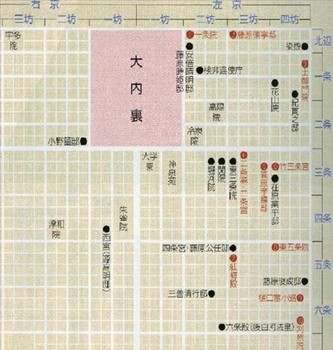

「光悦筆 四季草花宗達下絵和歌巻」(日本古典文学会・貴重本刊行会・日野原家蔵一巻)
花留客(花客ヲ留ム)といへる心をよみ侍ける
90 ちりかゝる花のにしきは着たれどもかへらむ事ぞわすられにける(右近大将実房)
(落花の下、花の錦は身につけたが、花に心を奪われて故郷へ帰ることを忘れてしまったよ。)
釈文(揮毫上の書体)=(『書道芸術第十八巻 本阿弥光悦』)
知利懸(ちりかかる)ハな(はな)能(の)錦盤(は)きた連(れ)ども帰無事(かへらむこと)曾(ぞ)わ須(す)ら禮(れ)尓(に)介流(ける)
※知利懸(ちりかかる)=散りかかる。
※ハな(はな)能(の)錦=花の錦。衣の上に花の散ったさまを錦に見立てた。
※きた連(れ)ども=着たれども。身にまとったが。
※帰無事(かへらむこと)=(花に心を奪われて)故郷へ帰らんことを。
※わ須(す)ら禮(れ)尓(に)介流(ける)=忘れにける。忘れてしまったよ。
http://www.asahi-net.or.jp/~sg2h-ymst/yamatouta/sennin/sanehusa.html
【藤原実房(ふじわらのさねふさ) 久安三~嘉禄元(1147-1225) 号:三条入道左大臣
三条内大臣公教の三男。母は権中納言藤原清隆女。権大納言実国の弟。太政大臣公房・権大納言公宣・同公氏の父。
仁平二年(1152)叙爵。左少将・右中将などを経て、永暦元年(1160)、蔵人頭。同年従三位。永万二年(1166)、権中納言。仁安二年(1167)、従二位に叙され中納言に転じる。同三年、権大納言。承安元年(1171)、正二位。寿永二年(1183)、大納言。文治五年(1189)、右大臣。建久元年(1190)、左大臣に至る。同七年、病により引退。法名は静空。
住吉社歌合・広田社歌合・御室五十首・文治六年(1190)女御入内御屏風歌・正治二年初度百首などの作者。日記『愚昧記』がある。千載集初出。勅撰入集三十首。『歌仙落書』に「義理を存候、言葉妙也。末床しきさまなり」の評がある。 】
(参考) 「建久七年(一一九六)の政変」(九条兼実・良経の失脚と源通親の台頭)周辺
藤原俊成の編んだ『千載和歌集』の、「89左近中将良経→90右近大将実房→91権大納言実国→92権中納言通親」の収載配列(上記の和歌巻は、右側の部分図が前回の「89左近中将良経」の一首、左側が今回の「90右近大将実房」、「91権大納言実国」と「92権中納言通親」は、この後に続く)は、この十年後に勃発する「建久七年(一一九六)の政変」(九条兼実・良経の失脚と源通親の台頭)の予兆を感じさせるような趣で無くもない。
今回の「90右近大将実房」は、本姓は「藤原」だが、三条内大臣公教の三男で「三条実房」、二男の「91権大納言実国」は「滋野井実国」と、その姓は「三条家」(実房)、そして「滋野井家」(実国)が通姓のようである。
そして、この実房が、「大納言」と「右近衛大将」(右近衛に置かれた近衛大将)とを兼任したのは、文治二年(一一八六)のことで、この時に、「89左近中将良経」は、「正三位に昇叙、左近衛中将・播磨権守は元の如し」(若干十七歳)と、まさに、「九条兼実・良経」親子の絶頂期を迎える頃で、この「九条兼実・良経」親子のサポートの基に、「御子左家」(「藤原俊成・定家」親子等々の「歌道の家」)は、それまでの「六条藤家」(「藤原顕輔・清輔」親子等々の歌道の家)に代わり、それが俊成(「御子左家」)による、この第七勅撰集『千載和歌集』の撰集へと繋がっている。
そして、この実房は、九条兼実を支える両翼の一人(もう一人は「徳大寺実定」)で、これらの、当時(文治二年=一一八六)の官職名等は次のとおりである。
九条兼実 → 摂政宣下。藤原氏長者宣下。右大臣如元(十月、辞任)。建久二年(一一九一)=関白宣下。准摂政宣下。
徳大寺実定→ 右大臣(十月)。文治五年(一一八九年)七月左大臣となり、兼実の片腕として朝幕間の取り次ぎに奔走する。
三条実房 → 右近衛大将を兼ねる(寿永二年=大納言)。文治四年(一一八八)=左近衛大将、翌年=右大臣(左大将兼務)、その翌年(建久元年)=左大臣。
九条良経 → 正三位に昇叙、左近衛中将・播磨権守は元の如し。建久六年(一一九五)=内大臣に転任。11月12日、左近衛大将は元の如し。
これらの、当時の朝廷のトップ層の「九条兼実」派と当時の歌壇の主流となってきた「御子左家」派等が一同に名を連ねている「屏風歌」(長寿を祝う算賀、裳着(もぎ)、入内(じゅだい)、大嘗会等の行事のための屏風調進に伴って詠作される和歌)がある。
それは、「文治六年(一一九〇) 女御入内御屏風歌」で、その作者(詠進歌人)は「兼実(関白)・実定(左大臣)・実房(右大臣)・良経(近衛大将)・季経(「御子左家」寄りの「六条藤家」)・隆信(「六条藤家」寄りの「御子左家」)・定家(「御子左家」の嫡子)・俊成(「御子左家」再興の祖)の八名である。
この「文治六年(一一九〇) 女御入内御屏風歌」については、次のアドレスの「勅撰集の中の入内屏風和歌 : 作者・詞書を手がかりに(細川佐知子稿)」の論攷の中で、次のように紹介されている。
https://ir.library.osaka-u.ac.jp/repo/ouka/all/67625/shirin49_001.pdf
「文治六年(四月一一日より建久)正月に後鳥羽天皇に入内した、九条兼実の女任子の入内屏風和歌である。(中略) 月次一二帖(各月三面)三六面の屏風と夏・冬二面の泥絵記すために詠出されたものである。作者は、兼実・実定・実房・良経・季経・隆信・定家・俊成の八名で、各人が三八首詠じ、各面一首ずつ選定された。選定は俊成・実定が下選びをし、兼実が最終決定した。屏風歌に選定された歌だけでなく、全歌が作品として残る。」(「勅撰集の中の入内屏風和歌 : 作者・詞書を手がかりに(細川佐知子稿)」)
ここで、『藤原定家『明月記』の世界(村井康彦著・岩波新書)』で、この「文治六年(一一九〇) 女御入内御屏風歌」の二年後の『明月記』(定家の五十五カ年にわたる漢文体の「日記」)の「建久三年(一一九二)三月六日の条を紹介したい。
【六日、天晴、巳時(午前十時頃)「院」に入る。人々多く参る。未刻(午後二時頃)退出し、「七条」(院)・「八条院」へ参り、「家」に帰る。昏(夕方)に「内」(内裏)に参る。人なきにより、独り「宮御方」(任子・宜秋門院)に参り、格子を下ぐる後、「大将殿」(九条良経)に参り見参の後、「宮御方」(任子)に帰り参る。深更、又「大将殿」(良経)に参り、暁鐘の程「蓬」(自宅)に戻る。 】(『藤原定家『明月記』の世界(村井康彦著・岩波新書)』所収「序章『明月記』とは」)
ここに出てくる、定家の「出仕先」(公務として出向いた先)の「院」・「七条院」・「八条院」・「内」・「宮御方」・「大将殿」と、その「殿舎」(その出仕先の殿舎)は、次のとおりである。
※「大将殿」=九条良経(近衛大将)、「九条家」の「家司(けし)=貴人に供奉する秘書役など」として仕えた定家の「九条家の御曹司」)→「一条殿」(当時の「良経」の殿舎)
※「内」(「内裏」=「里内裏」)「宮御方」(後鳥羽中宮、任子、宜秋門院、兼実の息女、良経の妹)→「閑院(中宮御所)」(当時の「任子」の殿舎)
※「院」(後白河院、後白河院の崩御=建久三年三月十三日、上記の『明月記』=建久三年三月六日で、この一週間後「院」は亡くなる。)→「六条殿」→「建久3年(1192年)2月18日、雨の降る中を後鳥羽天皇が見舞いのため六条殿に行幸する(『玉葉』同日条)。後白河院は「事の外辛苦し給ふ」という病状だったが(『玉葉』2月17日条)大いに喜んで、後鳥羽の笛に合わせて今様を歌っている。後鳥羽帝が還御すると、後白河院は丹後局を使者として遺詔を伝えた。その内容は、法住寺殿・蓮華王院・六勝寺・鳥羽殿など主要な部分を天皇領に、他の院領は皇女の亮子・式子・好子・覲子にそれぞれ分与するというもので(『明月記』3月14日条)、後白河院に批判的な九条兼実も「御処分の体、誠に穏便なり」としている。」(『ウィキペディア(Wikipedia)』)
※「七条院(後鳥羽母)」=高倉天皇の後宮。後高倉院(守貞親王)と後鳥羽天皇の母=藤原 殖子 → 「三条殿」(七条院の殿舎)
※「八条院(鳥羽皇女、美福門院女)」=暲子内親王。「近衛天皇は同母弟、崇徳・後白河両天皇は異母兄にあたる。ほかに母を同じくする姉妹に、早世した叡子内親王と二条天皇中宮となった姝子内親王(高松院)がいる。終生、未婚であったが、甥の二条天皇の准母となったほか、以仁王とその子女、九条良輔(兼実の子)、昇子内親王(春華門院、後鳥羽上皇の皇女)らを養育した。」(『ウィキペディア(Wikipedia)』)
※「家」「蓬」(自宅)=当時の「定家」宅(九条宅)→「九条殿」(九条兼実の「殿舎」)に隣接している。定家の父の俊成宅は「五条京極邸」邸でそことは異なる。
これらの解説(解読)は、『藤原定家『明月記』の世界(村井康彦著・岩波新書)』の、下記の「目次」の随所にわたって、図表入りで、その一端が論述されている。
「序章」 →『明月記』とは
「第一章」→五条京極邸 1 五条三位 2 百首歌の時代
「第二章」→政変の前後 1 兼実の失脚 2 女院たちの命運 3 後鳥羽院政の創始 4 定家の「官途絶望」
「第三章」→新古今への道 1 正治初度百首 2 和歌所と寄人 3 終わりなき切継ぎ 4 水無瀬の遊興
ここでは、「文治六年(一一九〇) 女御入内御屏風歌」とその二年後の『明月記』(「建久三年=一一九二・三月六日の条」)の記載と「建久七年(一一九六)の政変」(九条兼実・良経の失脚と源通親の台頭)との関連などについて記して置きたい。
一 「建久七年(一一九六)の政変」(九条兼実・良経の失脚と源通親の台頭)とは、すべからく、『明月記』(「建久三年=一一九二・三月六日の条」)の、その一週間後の、建久三年(一一九二)三月十三日の「後白河院」の崩御を起因として勃発する。
二 この「後白河院政」から「後鳥羽院院政」への移行期を支えた体制は、「文治六年(一一九〇) 女御入内御屏風歌」の、「九条兼実体制(関白・兼実、左大臣・実定、右大臣・実房、近衛大将・良経)であったが、この時に、既に、「関白・兼実」の両翼の、「左大臣・実定」は「建久二年、病のため官を辞して出家、同年閏十二月に崩御」、「右大臣・実房」は、建久七年(一一九六)三月、病により左大臣を辞し、出家」している。
すなわち、「建久七年(一一九六)の政変」(九条兼実・良経の失脚と源通親の台頭)とは、それまでの「後白河(後鳥羽)・兼実」体制から、新しく「後鳥羽・通親」体制への移行ということを意味する。
三 そして、この「建久七年(一一九六)の政変」の背後には、親幕(親鎌倉)派の「兼実」に対する反幕(反鎌倉)感情を強めていた後白河院の寵妃「丹後局(高階栄子)」と「兼実」の娘の中宮「任子(宜秋門院)」を退けて「通親」の養女「在子(承明門院)」を後宮入りさせる画策とが、後白河院の没後に結実したということが挙げられよう。
建久六年(一一九五)八月十二日 任子、第一皇女昇子内親王(後に「春華門院」)を出産。
同 十一月一日 在子、第一皇子為仁親王(後に「土御門天皇)を出産。
四 この時(建久六年=一一九五)、任子、二十二歳、在子、二十四歳、後鳥羽天皇、十五歳、この後鳥羽天皇の外戚として、関白・兼実が強権を揮っていたが、この時を境に、権大納言・通親が実権を握り、その翌年(建久七年=一一九六)の十一月二十四日に、「八条院」(鳥羽皇女・美福門院女、兼実・四男=良輔と昇子内親王の養母)に居を移し、その翌日に、兼実は失脚している。これが、「建久七年(一一九六)の政変」の実態なのである。
五、しかし、この時点では、任子の再入内の余地は十分に残されていたのだが、正治元年(一一九六)、任子の兄の九条良経が左大臣となり政権に復帰した、その翌年の正治二年(一二〇〇)六月二十八日に、任子への「宜秋門院」の院号宣下があり、ここで、名実ともに、「後白河(後鳥羽)・兼実」体制から「後鳥羽・通親」体制へと移行することとなる。
六 ここで、「建久七年(一一九六)の政変」は、「クーデターでなく、兼実が目指していた外戚摂関再興の途が閉ざされたことによる『関白辞職』である」とする、下記のアドレスの論攷などは、やはり、上記の「建久七年(一一九六)の政変」の実態と併せ、その真実の一端を語っているものであろう。
https://hosei.repo.nii.ac.jp/?action=pages_view_main&active_action=repository_view_main_item_detail&item_id=11199&item_no=1&page_id=13&block_id=83
↓
「建久七年の九条兼実『関白辞職』」(遠城悦子稿)」
七 さらに、ここで、下記のアドレスで触れた「平安京条坊図(大内裏周辺)」と、上記で紹介した『藤原定家『明月記』の世界(村井康彦著・岩波新書)』の冒頭の『明月記』の「建久三年(一一九二)三月六日の条」とを重ね合わせると、様々なことかイメージ化されてくる。
https://yahan.blog.ss-blog.jp/2020-10-23
↓
平安京条坊図(大内裏周辺)
↓
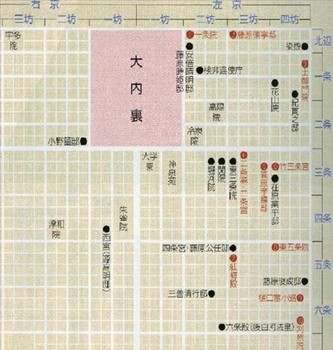
四季草花下絵千載集和歌巻(その十七・十八) [光悦・宗達・素庵]
(その十七・八) 和歌巻(その十七・八)

「光悦筆 四季草花宗達下絵和歌巻」(日本古典文学会・貴重本刊行会・日野原家蔵一巻)
百首歌たてまつりける時よめる
88 春風に志賀の山こゑ花ちれば峰にぞ浦のなみはたちける(前参議親隆)
(春風の中、花吹雪の志賀の山越えをして来ると、山の頂に浦の波が立つことだよ。)
釈文(揮毫上の書体)=(『書道芸術第十八巻 本阿弥光悦』)
ハ(は)る可世(かぜ)尓(に)し可(志賀)乃(の)やまこえ(山越え)ハ(は)な知連ハ(散れば)見年(峰)尓(に)曾(ぞ)浦乃(の)波ハ(は)多知(たち)介(け)る
※ハ(は)る可世(かぜ)尓(に)=春風に。
※し可(志賀)乃(の)やまこえ(山越え)=志賀の山越え。京都の北白川から山中峠を越え、滋賀の里へ抜ける道。近江の志賀寺(崇福寺)詣でに利用された。
※ハ(は)な知連ハ(散れば)=花散れば。
※見年(峰)尓(に)曾(ぞ)=峰にぞ。
※浦乃(の)波ハ(は)多知(たち)介(け)る=浦の波はたちける。「浦の波」は、志賀の浦の波で、志賀の縁語の「花吹雪」を見立てている。
https://www.asahi-net.or.jp/~sg2h-ymst/yamatouta/sennin/tikataka.html
【藤原親隆(ふじわらのちかたか) 康和元~永万元(1099-1165)
右大臣定方の裔。大蔵卿為房の息子。母は法橋隆尊の娘(忠通の乳母)。
保安四年(1123)、叙爵。伊予守・春宮亮などを経て、保元三年(1158)五月、従三位。同年の二条天皇即位後、正三位に昇叙される。永暦二年(1161)、参議。長寛元年(1163)、出家。法名は大覚。
関白内大臣忠通歌合・中宮亮顕輔歌合・木工権頭為忠家百首・久安百首などに出詠。家集『親隆集』は久安百首詠を一冊にしたもの。金葉集初出。勅撰入集十六首。 】
花の歌とてよみ侍ける
89 さくら咲く比良の山風ふくまゝに花になりゆく志賀のうら浪(左近中将良経)
(桜咲く比良の峰々を山風が吹きおろすと、やがて志賀の浦波も花の白波となっていくよ。)
釈文(揮毫上の書体)=(『書道芸術第十八巻 本阿弥光悦』)
左久良(さくら)咲(さく)日ら濃(の)山可勢(かぜ)吹(ふく)まゝ尓(に)ハ那(はな)尓(に)成行(なりゆく)志可(しが)濃(の)うらな見(み)
※左久良(さくら)咲(さく)=桜咲く。
※日ら濃(の)山可勢(かぜ)=比良の山風。比良の山は近江の歌枕。
※吹(ふく)まゝ尓(に)=吹くままに。
※ハ那(はな)尓(に)成行(なりゆく)=花になりゆく。湖面に花吹雪が散り敷くさま。
※志可(しが)濃(の)うらな見(み)=志賀の浦波。志賀の浦も近江の歌枕。
http://www.asahi-net.or.jp/~sg2h-ymst/yamatouta/sennin/yositune.html
【 藤原(九条)良経(ふじわらよしつね・くじょうよしつね) 嘉応元~建永元(1169-1206)
法性寺摂政太政大臣忠通の孫。後法性寺関白兼実の二男。母は従三位中宮亮藤原季行の娘。慈円は叔父。妹任子は後鳥羽院后宜秋門院。兄に良通(内大臣)、弟に良輔(左大臣)・良平(太政大臣)がいる。一条能保(源頼朝の妹婿)の息女、松殿基房(兼実の兄)の息女などを妻とした。子には藤原道家(摂政)・教家(大納言)・基家(内大臣)・東一条院立子(順徳院后)ほかがいる。
治承三年(1179)四月、十一歳で元服し、従五位上に叙される。八月、禁色昇殿。十月、侍従。同四年、正五位下。養和元年(1181)十二月、右少将。寿永元年(1182)十一月、左中将。同二年、従四位下。同年八月、従四位上。元暦元年(1184)十二月、正四位下。同二年、十七歳の時、従三位に叙され公卿に列す。兼播磨権守。文治二年(1186)、正三位。同三年、従二位。同四年、正二位。この年、兄良通が死去し、九条家の跡取りとなる。同五年七月、権大納言。十二月、兼左大将。同六年七月、兼中宮大夫。建久六年(1195)十一月、二十七歳にして内大臣(兼左大将)。同七年、父兼実は土御門通親の策謀により関白を辞し、良経も籠居。同九年正月、左大将罷免。しかし同十年六月には左大臣に昇進し、建仁二年(1202)以後は後鳥羽院の信任を得て、同年十二月、摂政に任ぜられる。同四年、従一位摂政太政大臣。元久二年(1205)四月、大臣を辞す。同三年三月、中御門京極の自邸で久しく絶えていた曲水の宴を再興する計画を立て、準備を進めていた最中の同月七日、急死した。三十八歳。
幼少期から学才をあらわし、漢詩文にすぐれたが、和歌の創作も早熟で、千載集には十代の作が七首収められた。藤原俊成を師とし、従者の定家からも大きな影響を受ける。叔父慈円の後援のもと、建久初年頃から歌壇を統率、建久元年(1190)の『花月百首』、同二年の『十題百首』、同四年の『六百番歌合』などを主催した。やがて歌壇の中心は後鳥羽院に移るが、良経はそこでも御子左家の歌人らと共に中核的な位置を占めた。建仁元年(1201)七月、和歌所設置に際しては寄人筆頭となり、『新古今和歌集』撰進に深く関与、仮名序を執筆するなどした。建仁元年の『老若五十首』、同二年の『水無瀬殿恋十五首歌合』、元久元年の『春日社歌合』『北野宮歌合』など院主催の和歌行事に参加し、『千五百番歌合』では判者もつとめた。
後京極摂政・中御門殿と称され、式部史生・秋篠月清・南海漁夫・西洞隠士などと号した。自撰の家集『式部史生秋篠月清集』『後京極摂政御自歌合』がある。千載集初出。新古今集では西行・慈円に次ぎ第三位の収録歌数七十九首。漢文の日記『殿記』は若干の遺文が存する。書も能くし、後世後京極様の名で伝わる。 】
(参考)「院政」(白河院・後白河院・後鳥羽院)時代周辺と「藤原(九条)良経(1169-1206)」
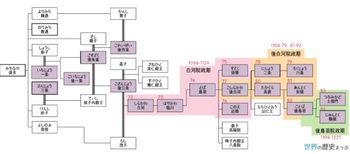
https://sekainorekisi.com/japanese_history/
「院政」時代というのは、「白河、鳥羽、後白河上皇三代の院政が行なわれた時代の応徳三年(一〇八六)から建久三年(一一九二)までの約一〇〇年間が中心となるが、藤原氏が摂関として政権を取った時代と、鎌倉幕府が朝廷に優越する政権となった時代との中間の時代と考えれば、後三条天皇即位の治暦四年(一〇六八)から後鳥羽上皇の退位した承久の乱の承久三年(一二二一)までの約一五〇年間がこれに当たる」(精選版 日本国語大辞典)。
それらを図示したものとして、上記のものは恰好のものである。これによると、「院政」時代というのは、次の三期に分かれる。
「白河院院政期」(1086-1129)=「白河→堀河→鳥羽→崇徳→近衛」時代
「後白河院政期」(1158~1179. 1181~1192)=「後白河→二条→六条→高倉→安徳」時代
「後鳥羽院制期」(1198~1221)=「後鳥羽→土御門→順徳」時代
「藤原親隆(1099-1165)」は、上記の「白河院院政期」の、特に、「崇徳天皇」時代に活躍した歌人である。
それに比して、次の「藤原(九条)良経(1169-1206)」は、「後鳥羽院院政期」時代の代表的な歌人で、『新古今和歌集』の「序(仮名序)」を起草した、時の「摂政太政大臣」(『新古今和歌集』搭載の官職名)である。
その『新古今和歌集』が成った元久二年(一二〇五)の翌年、元久三年(一二〇六)三月七日深夜に、享年三十八歳の若さで夭逝した。『千載和歌集』には七首、『新古今和歌集』には七十九首(西行=九十四首、慈円=九十二首に次いで第三位、俊成=七十二首、式子内親王=四十九首、定家=四十六首、家隆=四十三首、寂蓮=三十五首、後鳥羽院=三十四首と続く)入集している。
良経の『千載和歌集』に入集したのは、二十歳前(十七・八歳時)の頃で、御子左家の総帥、藤原俊成(『千載和歌集』の撰者)に見出された歌人ということになろう。良経の叔父にあたる慈円は、その著書『愚管抄』で「能芸群ニヌケタリキ、詩歌能書昔ニハヂズ、政理公事父祖ヲツゲリ」と記している。
書家としても著名で、その書風は後に「京極流」と呼ばれた。一方、有職故実の研究にも力を入れ,、『大間成文抄(除目大成抄)』『春除目抄』『秋除目抄』などの著書を残している。ほかに日記『殿記』も残している。
http://www.asahi-net.or.jp/~SG2H-ymst/yamatouta/sennin/0yositune_t.html
「故摂政は、たけをむねとして、諸方を兼ねたりき。いかにぞや見ゆる詞のなさ、哥ごとに由あるさま、不可思議なりき。百首などのあまりに地哥もなく見えしこそ、かへりては難ともいひつべかりしか。秀歌のあまり多くて、両三首などは書きのせがたし」(『後鳥羽院御口伝』)。
「後京極摂政の歌、毎首みな錦繍、句々悉々く金玉、意情を陳ぶれば、ただちに感慨を生じ、景色をいへば、まのあたりに見るが如し。風姿優艷にして、飽くまで力あり、語路(ごろ)逶迱(いだ)として、いささかも閑あらず、実に詞花言葉の精粋なるものなり」(荷田在満『国歌八論』)。
若き日の「藤原(九条)良経」の歌(『千載和歌集』の七首)
帰る雁の心をよみ侍りける
ながむればかすめる空のうき雲とひとつになりぬかへる雁がね(千載37)
【通釈】眺めると、北へ帰る雁は、霞んだ空の浮雲と見分けがつかなくなってしまった。
花の歌とてよみ侍りける
桜咲く比良の山風吹くままに花になりゆく志賀の浦波(千載89)
【通釈】桜咲く比良の峰々を山風が吹きおろすと、やがて志賀の浦波も花の白波となっていくよ。
虫ノ声非ズ一ニといへる心をよみ侍りける
さまざまなの浅茅が原の虫の音をあはれひとつに聞きぞなしつる(千載330)
【通釈】荒れ果てた野のさまざまな虫の音は、その「虫ノ音ハ一ツニ非ズ」と耳をすましている。
閑居聞ク霰ヲといへる心をよみ侍りける
さゆる夜の槙の板屋のひとり寝に心くだけと霰ふるなり(千載444)
【通釈】冷え冷えとした夜の板葺きの家で独り寝をしていると「霰ガ砕ケル」ように孤独感が増大してくる。
契ル暮ノ秋ヲ恋といへる心をよみ侍りける
秋はをし契りは待たるとにかくに心にかゝる暮の空かな(千載746)
【通釈】秋の暮れも、恋の契りも、とにかくに、心を悩ませる、この暮色の空であることか。
知られてもいとはれぬべき身ならずは名をさへ人に包まましやは(千載826)
【通釈】知られては厭われる身なので、ここは名を隠すほかはあるまいに。
法華経の弟子品、内秘菩薩行の心をよみ侍りける
ひとりのみ苦しき海を渡るとや底を悟らぬ人は見るらん(千載1227)
【通釈】悟らぬ人は一人で苦海(苦界)を渡ると思っているが、この法華経の声明は菩薩に導かれて苦海渡るとことを導いてくれる。
https://sidu.exblog.jp/1724542/
『新古今和歌集』「仮名序」(摂政太政大臣良経)
やまとうたは、昔あめつち開けはじめて、人のしわざいまだ定まらざりし時、葦原中国の言の葉として、稲田姫素鵞の里よりぞつたはれりける。しかありしよりこのかた、その道さかりに興り、その流れいまに絶ゆることなくして、色にふけり、心をのぶるなかだちとし、世をおさめ、民をやはらぐる道とせり。
かゝりければ、代々のみかどもこれを捨てたまはず、えらびをかれたる集ども、家々のもてあそびものとして、詞の花のこれる木のもとかたく、思ひの露もれたる草がくれもあるべからず。しかはあれども、伊勢の海きよき渚の玉は、ひろふとも尽くることなく、泉の杣しげき宮木は、ひくとも絶ゆべからず。ものみなかくのごとし。うたの道またおなじかるべし。
これによりて、右衛門督源朝臣通具、大蔵卿藤原朝臣有家、左近中将藤原朝臣定家、前上総介藤原朝臣家隆、左近少将藤原朝臣雅経らにおほせて、むかしいま時をわかたず、たかきいやしき人をきらはず、目に見えぬ神仏の言の葉も、うばたまの夢につたへたる事まで、ひろくもとめ、あまねく集めしむ。
をのをのえらびたてまつれるところ、夏引の糸のひとすぢならず、夕の雲のおもひ定めがたきゆへに、緑の洞、花かうばしきあした、玉の砌、風すゞしきゆふべ、難波津の流れをくみて、すみ濁れるをさだめ、安積山の跡をたづねて、ふかき浅きをわかてり。
万葉集にいれる歌は、これをのぞかず、古今よりこのかた七代の集にいれる歌をば、これを載する事なし。たゞし、詞の苑にあそび、筆の海をくみても、空とぶ鳥のあみをもれ、水にすむ魚のつりをのがれたるたぐひは、昔もなきにあらざれば、今も又しらざるところなり。すべてあつめたる歌二千ぢ二十巻、なづけて新古今和歌集といふ。
春霞立田の山に初花をしのぶより、夏は妻恋ひする神なびの郭公、秋は風にちる葛城の紅葉、冬は白たへの富士の高嶺に雪つもる年の暮まで、みなおりにふれたる情なるべし。しかのみならず、高き屋にとをきをのぞみて、民の時をしり、末の露もとの雫によそへて、人の世をさとり、たまぼこの道のべに別れをしたひ、あまざかる鄙の長路に都をおもひ、高間の山の雲居のよそなる人をこひ、長柄の橋の浪にくちぬる名をおしみても、心中にうごき、言外にあらはれずといふことなし。いはむや、住吉の神は片そぎの言の葉をのこし、伝教大師はわがたつ杣の思ひをのべたまへり。かくのごとき、しらぬ昔の人の心をもあらはし、ゆきて見ぬ境の外のことをもしるは、たゞこの道ならし。
そもそも、むかしは五たび譲りし跡をたづねて、天つ日嗣の位にそなはり、いまは八隅知る名をのがれて、藐姑射の山に住処をしめたりといへども、天皇は子たる道をまもり、星の位はまつりごとをたすけし契りをわすれずして、天の下しげき事わざ、雲の上のいにしへにもかはらざりければ、よろづの民、春日野の草のなびかぬかたなく、よもの海、秋津島の月しづかにすみて、和歌の浦の跡をたづね、敷島の道をもてあそびつゝ、この集をえらびて、永き世につたへんとなり。
かの万葉集はうたの源なり。時うつり事へだたりて、今の人しることかたし。延喜のひじりの御代には、四人に勅して古今集をえらばしめ、天暦のかしこきみかどは、五人におほせて後撰集をあつめしめたまへり。そののち、拾遺、後拾遺、金葉、詞華、千載等の集は、みな一人これをうけたまはれるゆへに、聞きもらし見をよばざるところもあるべし。よりて、古今、後撰のあとを改めず、五人のともがらを定めて、しるしたてまつらしむるなり。
そのうへ、みづから定め、てづから磨けることは、とをくもろこしの文の道をたづぬれば、浜千鳥あとありといへども、わが国やまと言の葉始まりてのち、呉竹のよゝに、かゝるためしなんなかりける。
このうち、みづからの歌を載せたること、古きたぐひはあれど、十首にはすぎざるべし。しかるを、今かれこれえらべるところ、三十首にあまれり。これみな、人の目たつべき色もなく、心とゞむべきふしもありがたきゆへに、かへりて、いづれとわきがたければ、森のくち葉かず積り、汀の藻くづかき捨てずなりぬることは、道にふける思ひふかくして、後の嘲りをかへりみざるなるべし。
時に元久二年三月廿六日なんしるしをはりぬる。
目をいやしみ、耳をたふとぶるあまり、石上ふるき跡を恥づといへども、流れをくみて、源をたづぬるゆへに、富緒河のたえせぬ道を興しつれば、露霜はあらたまるとも、松ふく風の散りうせず、春秋はめぐるとも、空ゆく月の曇なくして、この時にあへらんものは、これをよろこび、この道をあふがんものは、今をしのばざらめかも。
『藤原良経略年譜』(下記のアドレスなどによる。)
https://sidu.exblog.jp/1724542/
(0歳~16歳)
1169年 九条兼実の次男として生まれる。
1179年 元服し良経と名乗る。
1181年 このころから連句・詩会に出席。
1185年 従三位に叙され公卿の仲間入り。
(17歳~20歳)
1186年 父兼実が摂政となる。藤原定家が九条家に出仕する。
1188年 兄良通の死。『千載集』に入撰。
1189年 権大納言・左近衛大将となる。
(21歳~30歳)
1190年 『花月百首』『二夜百首』を詠む。
1191年 一条能保の娘と結婚。『十題百首』。
1193年 良経主催で『六百番歌合』が行われる。
1195年 内大臣となる。勅使として伊勢に下向。
1196年 建久の政変。九条家が失脚する。
1198年 『後京極殿御自歌合』を編む。
1199年 左大臣となる。
(31歳~38歳)
1200年 良経の妻、死去する。『院初度百首』。
1201年 『老若五十首歌合』、『千五百番歌合』。和歌所寄人となり、『新古今集』編纂を指揮。
1202年 内覧の宣旨を賜り、摂政・氏長者となる。
1204年 太政大臣となる。
1205年 『新古今集』が一応完成、お披露目。
1206年 曲水宴を目前に謎の頓死。享年38歳。
https://blog.goo.ne.jp/usaken_2/e/04432d5f6de5fc99653292ebd36ca6a7
【 良経は序(新古今集の)完成の翌日相国(摂政太政大臣)を辞していた。そうして中御門京極に壮美を極めた邸宅を造り営む。絶えて久しい曲水の宴を廷内で催すのも新築の目的の一つであった。実現を見たなら百年振りの絢爛たる晴儀となっていたことだろう。元久三年二月上旬彼はこの宴のための評定を開く。寛治の代、大江匡房の行った方式に則り、鸚鵡盃を用いること、南庭にさらに水溝を穿つことを定めた。数度評定の後当日の歌題が「羽觴随波」に決まったのは二月尽であった。
弥生三日の予定は熊野本宮二月二十八日炎上のため十二日に延期となった。良経が死者として発見されたのは七日未明のことである。禍事を告げる家臣女房の声が廷内に飛び交い、急変言上の使いの馬車が走ったのは午の刻であったと伝える。
尊卑分脈良経公伝の終りには「建仁二年二月二十七日内覧氏長者 同年十二月二十五日摂政元久元年正月五日従一位 同年十一月十六日辞左大臣 同年十二月十四日太政大臣 同二年四月二十七日辞太政大臣 建永元年三月七日薨 頓死但於寝所自天井被刺殺云云」と記されている。
天井から矛で突き刺したのは誰か。その疑問に応えるものはついにいない。下手人の名は菅原為長、頼実と卿二位兼子、定家、後鳥羽院と囁き交される。否夭折の家系、頓死怪しからずとの声もある。
良経を殺したのは誰か。神以外に知るものはいない。あるいは神であったかも知れぬ。良経は天井の孔から、春夜桃の花を挿頭に眠る今一人の良経の胸を刺した。生ける死者は死せる生者をこの暁に弑した。その時王朝は名実共に崩れ去ったのだ。 】(『塚本邦雄全集第14集』所収「藤原良経」(昭和50年6月20日初出))

「光悦筆 四季草花宗達下絵和歌巻」(日本古典文学会・貴重本刊行会・日野原家蔵一巻)
百首歌たてまつりける時よめる
88 春風に志賀の山こゑ花ちれば峰にぞ浦のなみはたちける(前参議親隆)
(春風の中、花吹雪の志賀の山越えをして来ると、山の頂に浦の波が立つことだよ。)
釈文(揮毫上の書体)=(『書道芸術第十八巻 本阿弥光悦』)
ハ(は)る可世(かぜ)尓(に)し可(志賀)乃(の)やまこえ(山越え)ハ(は)な知連ハ(散れば)見年(峰)尓(に)曾(ぞ)浦乃(の)波ハ(は)多知(たち)介(け)る
※ハ(は)る可世(かぜ)尓(に)=春風に。
※し可(志賀)乃(の)やまこえ(山越え)=志賀の山越え。京都の北白川から山中峠を越え、滋賀の里へ抜ける道。近江の志賀寺(崇福寺)詣でに利用された。
※ハ(は)な知連ハ(散れば)=花散れば。
※見年(峰)尓(に)曾(ぞ)=峰にぞ。
※浦乃(の)波ハ(は)多知(たち)介(け)る=浦の波はたちける。「浦の波」は、志賀の浦の波で、志賀の縁語の「花吹雪」を見立てている。
https://www.asahi-net.or.jp/~sg2h-ymst/yamatouta/sennin/tikataka.html
【藤原親隆(ふじわらのちかたか) 康和元~永万元(1099-1165)
右大臣定方の裔。大蔵卿為房の息子。母は法橋隆尊の娘(忠通の乳母)。
保安四年(1123)、叙爵。伊予守・春宮亮などを経て、保元三年(1158)五月、従三位。同年の二条天皇即位後、正三位に昇叙される。永暦二年(1161)、参議。長寛元年(1163)、出家。法名は大覚。
関白内大臣忠通歌合・中宮亮顕輔歌合・木工権頭為忠家百首・久安百首などに出詠。家集『親隆集』は久安百首詠を一冊にしたもの。金葉集初出。勅撰入集十六首。 】
花の歌とてよみ侍ける
89 さくら咲く比良の山風ふくまゝに花になりゆく志賀のうら浪(左近中将良経)
(桜咲く比良の峰々を山風が吹きおろすと、やがて志賀の浦波も花の白波となっていくよ。)
釈文(揮毫上の書体)=(『書道芸術第十八巻 本阿弥光悦』)
左久良(さくら)咲(さく)日ら濃(の)山可勢(かぜ)吹(ふく)まゝ尓(に)ハ那(はな)尓(に)成行(なりゆく)志可(しが)濃(の)うらな見(み)
※左久良(さくら)咲(さく)=桜咲く。
※日ら濃(の)山可勢(かぜ)=比良の山風。比良の山は近江の歌枕。
※吹(ふく)まゝ尓(に)=吹くままに。
※ハ那(はな)尓(に)成行(なりゆく)=花になりゆく。湖面に花吹雪が散り敷くさま。
※志可(しが)濃(の)うらな見(み)=志賀の浦波。志賀の浦も近江の歌枕。
http://www.asahi-net.or.jp/~sg2h-ymst/yamatouta/sennin/yositune.html
【 藤原(九条)良経(ふじわらよしつね・くじょうよしつね) 嘉応元~建永元(1169-1206)
法性寺摂政太政大臣忠通の孫。後法性寺関白兼実の二男。母は従三位中宮亮藤原季行の娘。慈円は叔父。妹任子は後鳥羽院后宜秋門院。兄に良通(内大臣)、弟に良輔(左大臣)・良平(太政大臣)がいる。一条能保(源頼朝の妹婿)の息女、松殿基房(兼実の兄)の息女などを妻とした。子には藤原道家(摂政)・教家(大納言)・基家(内大臣)・東一条院立子(順徳院后)ほかがいる。
治承三年(1179)四月、十一歳で元服し、従五位上に叙される。八月、禁色昇殿。十月、侍従。同四年、正五位下。養和元年(1181)十二月、右少将。寿永元年(1182)十一月、左中将。同二年、従四位下。同年八月、従四位上。元暦元年(1184)十二月、正四位下。同二年、十七歳の時、従三位に叙され公卿に列す。兼播磨権守。文治二年(1186)、正三位。同三年、従二位。同四年、正二位。この年、兄良通が死去し、九条家の跡取りとなる。同五年七月、権大納言。十二月、兼左大将。同六年七月、兼中宮大夫。建久六年(1195)十一月、二十七歳にして内大臣(兼左大将)。同七年、父兼実は土御門通親の策謀により関白を辞し、良経も籠居。同九年正月、左大将罷免。しかし同十年六月には左大臣に昇進し、建仁二年(1202)以後は後鳥羽院の信任を得て、同年十二月、摂政に任ぜられる。同四年、従一位摂政太政大臣。元久二年(1205)四月、大臣を辞す。同三年三月、中御門京極の自邸で久しく絶えていた曲水の宴を再興する計画を立て、準備を進めていた最中の同月七日、急死した。三十八歳。
幼少期から学才をあらわし、漢詩文にすぐれたが、和歌の創作も早熟で、千載集には十代の作が七首収められた。藤原俊成を師とし、従者の定家からも大きな影響を受ける。叔父慈円の後援のもと、建久初年頃から歌壇を統率、建久元年(1190)の『花月百首』、同二年の『十題百首』、同四年の『六百番歌合』などを主催した。やがて歌壇の中心は後鳥羽院に移るが、良経はそこでも御子左家の歌人らと共に中核的な位置を占めた。建仁元年(1201)七月、和歌所設置に際しては寄人筆頭となり、『新古今和歌集』撰進に深く関与、仮名序を執筆するなどした。建仁元年の『老若五十首』、同二年の『水無瀬殿恋十五首歌合』、元久元年の『春日社歌合』『北野宮歌合』など院主催の和歌行事に参加し、『千五百番歌合』では判者もつとめた。
後京極摂政・中御門殿と称され、式部史生・秋篠月清・南海漁夫・西洞隠士などと号した。自撰の家集『式部史生秋篠月清集』『後京極摂政御自歌合』がある。千載集初出。新古今集では西行・慈円に次ぎ第三位の収録歌数七十九首。漢文の日記『殿記』は若干の遺文が存する。書も能くし、後世後京極様の名で伝わる。 】
(参考)「院政」(白河院・後白河院・後鳥羽院)時代周辺と「藤原(九条)良経(1169-1206)」
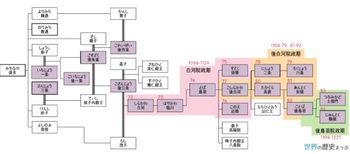
https://sekainorekisi.com/japanese_history/
「院政」時代というのは、「白河、鳥羽、後白河上皇三代の院政が行なわれた時代の応徳三年(一〇八六)から建久三年(一一九二)までの約一〇〇年間が中心となるが、藤原氏が摂関として政権を取った時代と、鎌倉幕府が朝廷に優越する政権となった時代との中間の時代と考えれば、後三条天皇即位の治暦四年(一〇六八)から後鳥羽上皇の退位した承久の乱の承久三年(一二二一)までの約一五〇年間がこれに当たる」(精選版 日本国語大辞典)。
それらを図示したものとして、上記のものは恰好のものである。これによると、「院政」時代というのは、次の三期に分かれる。
「白河院院政期」(1086-1129)=「白河→堀河→鳥羽→崇徳→近衛」時代
「後白河院政期」(1158~1179. 1181~1192)=「後白河→二条→六条→高倉→安徳」時代
「後鳥羽院制期」(1198~1221)=「後鳥羽→土御門→順徳」時代
「藤原親隆(1099-1165)」は、上記の「白河院院政期」の、特に、「崇徳天皇」時代に活躍した歌人である。
それに比して、次の「藤原(九条)良経(1169-1206)」は、「後鳥羽院院政期」時代の代表的な歌人で、『新古今和歌集』の「序(仮名序)」を起草した、時の「摂政太政大臣」(『新古今和歌集』搭載の官職名)である。
その『新古今和歌集』が成った元久二年(一二〇五)の翌年、元久三年(一二〇六)三月七日深夜に、享年三十八歳の若さで夭逝した。『千載和歌集』には七首、『新古今和歌集』には七十九首(西行=九十四首、慈円=九十二首に次いで第三位、俊成=七十二首、式子内親王=四十九首、定家=四十六首、家隆=四十三首、寂蓮=三十五首、後鳥羽院=三十四首と続く)入集している。
良経の『千載和歌集』に入集したのは、二十歳前(十七・八歳時)の頃で、御子左家の総帥、藤原俊成(『千載和歌集』の撰者)に見出された歌人ということになろう。良経の叔父にあたる慈円は、その著書『愚管抄』で「能芸群ニヌケタリキ、詩歌能書昔ニハヂズ、政理公事父祖ヲツゲリ」と記している。
書家としても著名で、その書風は後に「京極流」と呼ばれた。一方、有職故実の研究にも力を入れ,、『大間成文抄(除目大成抄)』『春除目抄』『秋除目抄』などの著書を残している。ほかに日記『殿記』も残している。
http://www.asahi-net.or.jp/~SG2H-ymst/yamatouta/sennin/0yositune_t.html
「故摂政は、たけをむねとして、諸方を兼ねたりき。いかにぞや見ゆる詞のなさ、哥ごとに由あるさま、不可思議なりき。百首などのあまりに地哥もなく見えしこそ、かへりては難ともいひつべかりしか。秀歌のあまり多くて、両三首などは書きのせがたし」(『後鳥羽院御口伝』)。
「後京極摂政の歌、毎首みな錦繍、句々悉々く金玉、意情を陳ぶれば、ただちに感慨を生じ、景色をいへば、まのあたりに見るが如し。風姿優艷にして、飽くまで力あり、語路(ごろ)逶迱(いだ)として、いささかも閑あらず、実に詞花言葉の精粋なるものなり」(荷田在満『国歌八論』)。
若き日の「藤原(九条)良経」の歌(『千載和歌集』の七首)
帰る雁の心をよみ侍りける
ながむればかすめる空のうき雲とひとつになりぬかへる雁がね(千載37)
【通釈】眺めると、北へ帰る雁は、霞んだ空の浮雲と見分けがつかなくなってしまった。
花の歌とてよみ侍りける
桜咲く比良の山風吹くままに花になりゆく志賀の浦波(千載89)
【通釈】桜咲く比良の峰々を山風が吹きおろすと、やがて志賀の浦波も花の白波となっていくよ。
虫ノ声非ズ一ニといへる心をよみ侍りける
さまざまなの浅茅が原の虫の音をあはれひとつに聞きぞなしつる(千載330)
【通釈】荒れ果てた野のさまざまな虫の音は、その「虫ノ音ハ一ツニ非ズ」と耳をすましている。
閑居聞ク霰ヲといへる心をよみ侍りける
さゆる夜の槙の板屋のひとり寝に心くだけと霰ふるなり(千載444)
【通釈】冷え冷えとした夜の板葺きの家で独り寝をしていると「霰ガ砕ケル」ように孤独感が増大してくる。
契ル暮ノ秋ヲ恋といへる心をよみ侍りける
秋はをし契りは待たるとにかくに心にかゝる暮の空かな(千載746)
【通釈】秋の暮れも、恋の契りも、とにかくに、心を悩ませる、この暮色の空であることか。
知られてもいとはれぬべき身ならずは名をさへ人に包まましやは(千載826)
【通釈】知られては厭われる身なので、ここは名を隠すほかはあるまいに。
法華経の弟子品、内秘菩薩行の心をよみ侍りける
ひとりのみ苦しき海を渡るとや底を悟らぬ人は見るらん(千載1227)
【通釈】悟らぬ人は一人で苦海(苦界)を渡ると思っているが、この法華経の声明は菩薩に導かれて苦海渡るとことを導いてくれる。
https://sidu.exblog.jp/1724542/
『新古今和歌集』「仮名序」(摂政太政大臣良経)
やまとうたは、昔あめつち開けはじめて、人のしわざいまだ定まらざりし時、葦原中国の言の葉として、稲田姫素鵞の里よりぞつたはれりける。しかありしよりこのかた、その道さかりに興り、その流れいまに絶ゆることなくして、色にふけり、心をのぶるなかだちとし、世をおさめ、民をやはらぐる道とせり。
かゝりければ、代々のみかどもこれを捨てたまはず、えらびをかれたる集ども、家々のもてあそびものとして、詞の花のこれる木のもとかたく、思ひの露もれたる草がくれもあるべからず。しかはあれども、伊勢の海きよき渚の玉は、ひろふとも尽くることなく、泉の杣しげき宮木は、ひくとも絶ゆべからず。ものみなかくのごとし。うたの道またおなじかるべし。
これによりて、右衛門督源朝臣通具、大蔵卿藤原朝臣有家、左近中将藤原朝臣定家、前上総介藤原朝臣家隆、左近少将藤原朝臣雅経らにおほせて、むかしいま時をわかたず、たかきいやしき人をきらはず、目に見えぬ神仏の言の葉も、うばたまの夢につたへたる事まで、ひろくもとめ、あまねく集めしむ。
をのをのえらびたてまつれるところ、夏引の糸のひとすぢならず、夕の雲のおもひ定めがたきゆへに、緑の洞、花かうばしきあした、玉の砌、風すゞしきゆふべ、難波津の流れをくみて、すみ濁れるをさだめ、安積山の跡をたづねて、ふかき浅きをわかてり。
万葉集にいれる歌は、これをのぞかず、古今よりこのかた七代の集にいれる歌をば、これを載する事なし。たゞし、詞の苑にあそび、筆の海をくみても、空とぶ鳥のあみをもれ、水にすむ魚のつりをのがれたるたぐひは、昔もなきにあらざれば、今も又しらざるところなり。すべてあつめたる歌二千ぢ二十巻、なづけて新古今和歌集といふ。
春霞立田の山に初花をしのぶより、夏は妻恋ひする神なびの郭公、秋は風にちる葛城の紅葉、冬は白たへの富士の高嶺に雪つもる年の暮まで、みなおりにふれたる情なるべし。しかのみならず、高き屋にとをきをのぞみて、民の時をしり、末の露もとの雫によそへて、人の世をさとり、たまぼこの道のべに別れをしたひ、あまざかる鄙の長路に都をおもひ、高間の山の雲居のよそなる人をこひ、長柄の橋の浪にくちぬる名をおしみても、心中にうごき、言外にあらはれずといふことなし。いはむや、住吉の神は片そぎの言の葉をのこし、伝教大師はわがたつ杣の思ひをのべたまへり。かくのごとき、しらぬ昔の人の心をもあらはし、ゆきて見ぬ境の外のことをもしるは、たゞこの道ならし。
そもそも、むかしは五たび譲りし跡をたづねて、天つ日嗣の位にそなはり、いまは八隅知る名をのがれて、藐姑射の山に住処をしめたりといへども、天皇は子たる道をまもり、星の位はまつりごとをたすけし契りをわすれずして、天の下しげき事わざ、雲の上のいにしへにもかはらざりければ、よろづの民、春日野の草のなびかぬかたなく、よもの海、秋津島の月しづかにすみて、和歌の浦の跡をたづね、敷島の道をもてあそびつゝ、この集をえらびて、永き世につたへんとなり。
かの万葉集はうたの源なり。時うつり事へだたりて、今の人しることかたし。延喜のひじりの御代には、四人に勅して古今集をえらばしめ、天暦のかしこきみかどは、五人におほせて後撰集をあつめしめたまへり。そののち、拾遺、後拾遺、金葉、詞華、千載等の集は、みな一人これをうけたまはれるゆへに、聞きもらし見をよばざるところもあるべし。よりて、古今、後撰のあとを改めず、五人のともがらを定めて、しるしたてまつらしむるなり。
そのうへ、みづから定め、てづから磨けることは、とをくもろこしの文の道をたづぬれば、浜千鳥あとありといへども、わが国やまと言の葉始まりてのち、呉竹のよゝに、かゝるためしなんなかりける。
このうち、みづからの歌を載せたること、古きたぐひはあれど、十首にはすぎざるべし。しかるを、今かれこれえらべるところ、三十首にあまれり。これみな、人の目たつべき色もなく、心とゞむべきふしもありがたきゆへに、かへりて、いづれとわきがたければ、森のくち葉かず積り、汀の藻くづかき捨てずなりぬることは、道にふける思ひふかくして、後の嘲りをかへりみざるなるべし。
時に元久二年三月廿六日なんしるしをはりぬる。
目をいやしみ、耳をたふとぶるあまり、石上ふるき跡を恥づといへども、流れをくみて、源をたづぬるゆへに、富緒河のたえせぬ道を興しつれば、露霜はあらたまるとも、松ふく風の散りうせず、春秋はめぐるとも、空ゆく月の曇なくして、この時にあへらんものは、これをよろこび、この道をあふがんものは、今をしのばざらめかも。
『藤原良経略年譜』(下記のアドレスなどによる。)
https://sidu.exblog.jp/1724542/
(0歳~16歳)
1169年 九条兼実の次男として生まれる。
1179年 元服し良経と名乗る。
1181年 このころから連句・詩会に出席。
1185年 従三位に叙され公卿の仲間入り。
(17歳~20歳)
1186年 父兼実が摂政となる。藤原定家が九条家に出仕する。
1188年 兄良通の死。『千載集』に入撰。
1189年 権大納言・左近衛大将となる。
(21歳~30歳)
1190年 『花月百首』『二夜百首』を詠む。
1191年 一条能保の娘と結婚。『十題百首』。
1193年 良経主催で『六百番歌合』が行われる。
1195年 内大臣となる。勅使として伊勢に下向。
1196年 建久の政変。九条家が失脚する。
1198年 『後京極殿御自歌合』を編む。
1199年 左大臣となる。
(31歳~38歳)
1200年 良経の妻、死去する。『院初度百首』。
1201年 『老若五十首歌合』、『千五百番歌合』。和歌所寄人となり、『新古今集』編纂を指揮。
1202年 内覧の宣旨を賜り、摂政・氏長者となる。
1204年 太政大臣となる。
1205年 『新古今集』が一応完成、お披露目。
1206年 曲水宴を目前に謎の頓死。享年38歳。
https://blog.goo.ne.jp/usaken_2/e/04432d5f6de5fc99653292ebd36ca6a7
【 良経は序(新古今集の)完成の翌日相国(摂政太政大臣)を辞していた。そうして中御門京極に壮美を極めた邸宅を造り営む。絶えて久しい曲水の宴を廷内で催すのも新築の目的の一つであった。実現を見たなら百年振りの絢爛たる晴儀となっていたことだろう。元久三年二月上旬彼はこの宴のための評定を開く。寛治の代、大江匡房の行った方式に則り、鸚鵡盃を用いること、南庭にさらに水溝を穿つことを定めた。数度評定の後当日の歌題が「羽觴随波」に決まったのは二月尽であった。
弥生三日の予定は熊野本宮二月二十八日炎上のため十二日に延期となった。良経が死者として発見されたのは七日未明のことである。禍事を告げる家臣女房の声が廷内に飛び交い、急変言上の使いの馬車が走ったのは午の刻であったと伝える。
尊卑分脈良経公伝の終りには「建仁二年二月二十七日内覧氏長者 同年十二月二十五日摂政元久元年正月五日従一位 同年十一月十六日辞左大臣 同年十二月十四日太政大臣 同二年四月二十七日辞太政大臣 建永元年三月七日薨 頓死但於寝所自天井被刺殺云云」と記されている。
天井から矛で突き刺したのは誰か。その疑問に応えるものはついにいない。下手人の名は菅原為長、頼実と卿二位兼子、定家、後鳥羽院と囁き交される。否夭折の家系、頓死怪しからずとの声もある。
良経を殺したのは誰か。神以外に知るものはいない。あるいは神であったかも知れぬ。良経は天井の孔から、春夜桃の花を挿頭に眠る今一人の良経の胸を刺した。生ける死者は死せる生者をこの暁に弑した。その時王朝は名実共に崩れ去ったのだ。 】(『塚本邦雄全集第14集』所収「藤原良経」(昭和50年6月20日初出))
四季草花下絵千載集和歌巻(その十六) [光悦・宗達・素庵]
(その十六) 和歌巻(その十六)

「光悦筆 四季草花宗達下絵和歌巻」(日本古典文学会・貴重本刊行会・日野原家蔵一巻)
崇徳院御時、十五首たてまつりける時、花
のうたをよめる
87 あらしふく志賀の山辺のさくら花ちれば雲井にさゞ浪ぞたつ(右兵衛公行)
(志賀の山辺の桜花が、はげしい山風に吹き散らされると、空にはさざ波が立つよ。)
釈文(揮毫上の書体)=(『書道芸術第十八巻 本阿弥光悦』)
安(あ)らしふ久(く)志賀濃(の)山邊乃(の)佐久ら華(ばな)知連(ちれ)(ば)雲井尓(に)左々波(さざなみ)曾(ぞ)多徒(たつ)
※安(あ)らしふ久(く)=嵐吹く。
※志賀濃(の)山=志賀の山。近江国の歌枕。
※佐久ら華(ばな)=桜花。
※知連(ちれ)(ば)=散れば。
※左々波(さざなみ)=さざ波。志賀の縁語。花吹雪の見立て。
※右兵衛公行(藤原公行=きんゆき)
藤原氏、長治二年(一一〇)生。久安4年(一一四八)六月二十二日没。四十四歳。八条太政大臣実行男。母は藤原顕季女。初名公輔。従三位右兵衛督。崇徳天皇内裏歌壇で活躍。詞華初出。
(参考) 『千載集』の詞書に出てくる「定数歌」周辺
https://www.jstage.jst.go.jp/article/nihonbungaku/62/7/62_2/_pdf
「単に「百首」 と言えば、 定数歌の百首歌のことを指す。定数歌には、他に、五十首、三十首、十五首、十首と百首より少ない例、逆に二百首、三百首、五百首、七百首、千首と多い例が存在する。また、歌仙やいろは歌にちなんだ三十六首や四十七首などで詠まれる場合もある。」
上記の「87 あらしふく志賀の山辺のさくら花ちれば雲井にさゞ浪ぞたつ(右兵衛公行)」の一首は、その詞書の「崇徳院御時、十五首たてまつりける時、花のうたをよめる」からすると、「定数歌」(一定の数を定めて和歌を詠む創作手法、及びその催し、作品)の「十五首歌」の一首ということになる。
先に見てきた、俊成の次の一首は、「十首歌」の例しなる。
https://yahan.blog.ss-blog.jp/2020-10-10
十首歌人によませ侍ける時、花のうたとてよめる
76 み吉野の花のさかりけふ見れば越(こし)の白根に春風ぞ吹く(皇太后大夫俊成)
これらの「十首歌」とか「十五首歌」とは、「百首歌」の「部立・歌題」などに準じたもののように思われる。これらのことは、先の「堀河百首(堀河院百首和歌)」の例ですると、「三 (部立・題等) 春 20題 夏 15題 秋 20題 冬 15題 恋 10題 雑 20題」の、例えば、「春・十五首」または「花・十首」なとの、「百首歌」の前提となるような歌作のようにも思われる。
https://yahan.blog.ss-blog.jp/2020-10-27
(参考) [『今鏡』に登場する和歌を詠む人々(陳文瑶) ]周辺
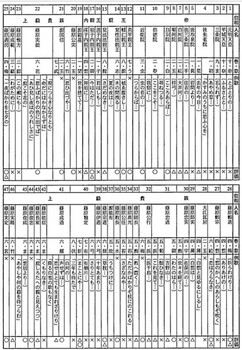
https://ir.lib.hiroshima-u.ac.jp/files/public/1/17608/2014101613121641411/KodaiChuseiKokubungaku_22_20.pdf
この[『今鏡』に登場する和歌を詠む人々(陳文瑶) ]の論攷は、『今鏡』に登場する和歌を詠む人々(133人)について、「和歌作者への評価の目」「評価される人々の位相」「階級という視点から」などの視点から、そこに収載されている全首について考察した労作である。
上記の図の「32」が「藤原公行」で、「45」が「藤原俊成」である。この「大鏡の作者による評価」は、「藤原公行(〇と△)」、「藤原俊成(〇)」で、同様に、「7白河院(△)」「8堀河院(△)」「9鳥羽院(〇)」「10崇徳院(〇)」「11近衛院(〇)」と、次の「後白河院」以降の「帝(天皇)」の記載はない。
これらからすると、「大鏡の作者」は、「鳥羽・崇徳・近衛」天皇の在世中、特に、崇徳天皇に仕えた「大原三寂(又は常盤三寂)」の三兄弟(寂念=藤原為業・寂超=藤原為経・寂然=藤原頼業)の中の「寂超=藤原為経」が有力説(他に「中山忠親、源通親」説)になっていることを裏付けている感じでなくもない。
ちなみに、「歴史物語」の「四鏡」(「大鏡」「今鏡」「水鏡」「増鏡」)の、この「今鏡」の前の時代を扱った「大鏡」の作者が、「寂超=藤原為経」の兄の「寂念=藤原為業」(摂関家やその縁戚の村上源氏に近い男性官人説の一人)であるとすると、なおさら、その感を大にする。
そして、「大原三寂(又は常盤三寂)」の、その「三兄弟(寂念=藤原為業・寂超=藤原為経・寂然=藤原頼業)」の、もう一人の「寂然=藤原頼業)」が、西行の無二の同胞であることについては、下記のアドレスで触れてきた。
https://yahan.blog.ss-blog.jp/2020-08-11
(再掲)
「大原三寂・御子左家系図」(『岩波新書西行(高橋貞夫著)』)
『古今著聞集(巻十五、宿執第二十三)』に、「西行法師、出家よりさきは、徳大寺左大臣の家人にて侍る」と記されている。西行の出家は、保延六年(一一四一)、二十三歳のときであるが、それ以前は「徳大寺家の家人」で、鳥羽院の北面武士として奉仕していたことも記録に遺されている。
この徳大寺家と俊成の「御子左家は、上記の系図のように近い姻族関係にあり、そして、この御子左家と「常盤三寂(大原三寂)」(「寂念・寂然・寂超」の三兄弟)で知られている「常盤家」と、寂超(藤原為経)の出家で離縁した妻の「美福門院加賀」が俊成の後妻に入り、「藤原定家」の生母となっているという、これまた、両家は因縁浅からぬ関係にある。
さらに、この美福門院加賀と寂超の子が「藤原隆信」(歌人で「肖像画=「似せ絵」の名手)なのである。この美福門院加賀は、天才歌人・藤原定家と天才画人・藤原隆信の生母で、御子左家の継嗣・定家は、隆信の異父弟ということになる。
上記の「大原三寂・御子左家系図」の左端の「徳大寺家」の「実能(さねよし)」に、西行は、佐藤義清時代は仕え、この実能の同母妹が「待賢門院璋子(しょうし)」(鳥羽天皇の皇后(中宮)、崇徳・後白河両天皇の母)なのである。

「光悦筆 四季草花宗達下絵和歌巻」(日本古典文学会・貴重本刊行会・日野原家蔵一巻)
崇徳院御時、十五首たてまつりける時、花
のうたをよめる
87 あらしふく志賀の山辺のさくら花ちれば雲井にさゞ浪ぞたつ(右兵衛公行)
(志賀の山辺の桜花が、はげしい山風に吹き散らされると、空にはさざ波が立つよ。)
釈文(揮毫上の書体)=(『書道芸術第十八巻 本阿弥光悦』)
安(あ)らしふ久(く)志賀濃(の)山邊乃(の)佐久ら華(ばな)知連(ちれ)(ば)雲井尓(に)左々波(さざなみ)曾(ぞ)多徒(たつ)
※安(あ)らしふ久(く)=嵐吹く。
※志賀濃(の)山=志賀の山。近江国の歌枕。
※佐久ら華(ばな)=桜花。
※知連(ちれ)(ば)=散れば。
※左々波(さざなみ)=さざ波。志賀の縁語。花吹雪の見立て。
※右兵衛公行(藤原公行=きんゆき)
藤原氏、長治二年(一一〇)生。久安4年(一一四八)六月二十二日没。四十四歳。八条太政大臣実行男。母は藤原顕季女。初名公輔。従三位右兵衛督。崇徳天皇内裏歌壇で活躍。詞華初出。
(参考) 『千載集』の詞書に出てくる「定数歌」周辺
https://www.jstage.jst.go.jp/article/nihonbungaku/62/7/62_2/_pdf
「単に「百首」 と言えば、 定数歌の百首歌のことを指す。定数歌には、他に、五十首、三十首、十五首、十首と百首より少ない例、逆に二百首、三百首、五百首、七百首、千首と多い例が存在する。また、歌仙やいろは歌にちなんだ三十六首や四十七首などで詠まれる場合もある。」
上記の「87 あらしふく志賀の山辺のさくら花ちれば雲井にさゞ浪ぞたつ(右兵衛公行)」の一首は、その詞書の「崇徳院御時、十五首たてまつりける時、花のうたをよめる」からすると、「定数歌」(一定の数を定めて和歌を詠む創作手法、及びその催し、作品)の「十五首歌」の一首ということになる。
先に見てきた、俊成の次の一首は、「十首歌」の例しなる。
https://yahan.blog.ss-blog.jp/2020-10-10
十首歌人によませ侍ける時、花のうたとてよめる
76 み吉野の花のさかりけふ見れば越(こし)の白根に春風ぞ吹く(皇太后大夫俊成)
これらの「十首歌」とか「十五首歌」とは、「百首歌」の「部立・歌題」などに準じたもののように思われる。これらのことは、先の「堀河百首(堀河院百首和歌)」の例ですると、「三 (部立・題等) 春 20題 夏 15題 秋 20題 冬 15題 恋 10題 雑 20題」の、例えば、「春・十五首」または「花・十首」なとの、「百首歌」の前提となるような歌作のようにも思われる。
https://yahan.blog.ss-blog.jp/2020-10-27
(参考) [『今鏡』に登場する和歌を詠む人々(陳文瑶) ]周辺
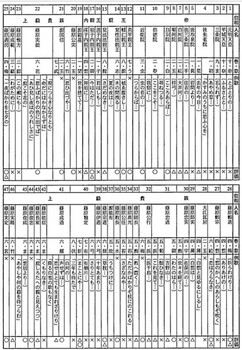
https://ir.lib.hiroshima-u.ac.jp/files/public/1/17608/2014101613121641411/KodaiChuseiKokubungaku_22_20.pdf
この[『今鏡』に登場する和歌を詠む人々(陳文瑶) ]の論攷は、『今鏡』に登場する和歌を詠む人々(133人)について、「和歌作者への評価の目」「評価される人々の位相」「階級という視点から」などの視点から、そこに収載されている全首について考察した労作である。
上記の図の「32」が「藤原公行」で、「45」が「藤原俊成」である。この「大鏡の作者による評価」は、「藤原公行(〇と△)」、「藤原俊成(〇)」で、同様に、「7白河院(△)」「8堀河院(△)」「9鳥羽院(〇)」「10崇徳院(〇)」「11近衛院(〇)」と、次の「後白河院」以降の「帝(天皇)」の記載はない。
これらからすると、「大鏡の作者」は、「鳥羽・崇徳・近衛」天皇の在世中、特に、崇徳天皇に仕えた「大原三寂(又は常盤三寂)」の三兄弟(寂念=藤原為業・寂超=藤原為経・寂然=藤原頼業)の中の「寂超=藤原為経」が有力説(他に「中山忠親、源通親」説)になっていることを裏付けている感じでなくもない。
ちなみに、「歴史物語」の「四鏡」(「大鏡」「今鏡」「水鏡」「増鏡」)の、この「今鏡」の前の時代を扱った「大鏡」の作者が、「寂超=藤原為経」の兄の「寂念=藤原為業」(摂関家やその縁戚の村上源氏に近い男性官人説の一人)であるとすると、なおさら、その感を大にする。
そして、「大原三寂(又は常盤三寂)」の、その「三兄弟(寂念=藤原為業・寂超=藤原為経・寂然=藤原頼業)」の、もう一人の「寂然=藤原頼業)」が、西行の無二の同胞であることについては、下記のアドレスで触れてきた。
https://yahan.blog.ss-blog.jp/2020-08-11
(再掲)
「大原三寂・御子左家系図」(『岩波新書西行(高橋貞夫著)』)
『古今著聞集(巻十五、宿執第二十三)』に、「西行法師、出家よりさきは、徳大寺左大臣の家人にて侍る」と記されている。西行の出家は、保延六年(一一四一)、二十三歳のときであるが、それ以前は「徳大寺家の家人」で、鳥羽院の北面武士として奉仕していたことも記録に遺されている。
この徳大寺家と俊成の「御子左家は、上記の系図のように近い姻族関係にあり、そして、この御子左家と「常盤三寂(大原三寂)」(「寂念・寂然・寂超」の三兄弟)で知られている「常盤家」と、寂超(藤原為経)の出家で離縁した妻の「美福門院加賀」が俊成の後妻に入り、「藤原定家」の生母となっているという、これまた、両家は因縁浅からぬ関係にある。
さらに、この美福門院加賀と寂超の子が「藤原隆信」(歌人で「肖像画=「似せ絵」の名手)なのである。この美福門院加賀は、天才歌人・藤原定家と天才画人・藤原隆信の生母で、御子左家の継嗣・定家は、隆信の異父弟ということになる。
上記の「大原三寂・御子左家系図」の左端の「徳大寺家」の「実能(さねよし)」に、西行は、佐藤義清時代は仕え、この実能の同母妹が「待賢門院璋子(しょうし)」(鳥羽天皇の皇后(中宮)、崇徳・後白河両天皇の母)なのである。



