「東洋城・寅彦、そして、豊隆」(漱石没後~寅彦没まで)俳句・連句管見(その十一) [東洋城・寅日子(寅彦)・蓬里雨(豊隆)]
その十一「昭和二年(一九二七)」
[東洋城・五十歳。塩原に句碑建立。伊予に遊ぶ。芥川龍之介自殺。「添削実相」掲載始まる。]

〇松根東洋城両面碑 塩湧橋先
【碑文】
「さまみえて土になりゐる落葉哉」表
「すずしさやこの山水に出湯とは」裏 (塩原四季郷より)
http://hotyu.starfree.jp/historicalspots/bungakuhi/bungakuhi.html
『東洋城全句集(上巻)』の「昭和二年」には、「塩原・四季郷」と題して、三十二句が収載されている。また、『東洋城全句集(中巻)』には、「昭和二年七月、塩原四季郷両面碑(西面)前にて」と題しての、当時の東洋城の肖像写真が掲載されている。この時の句に、上記の「両面句碑」の句に似た、次のような句がある。
涼しさや橋の下なる碧き山
涼しさや街道一つみえゐる灯(前書「瞰(かん) 流亭」)
径(ミチ)岐(キ)していづれか深き落葉かな
[寅彦=寅日子・五十歳
file:///C:/Users/user/Downloads/%E5%AF%BA%E7%94%B0%E5%AF%85%E5%BD%A6%E5%B9%B4%E8%A1%A8.pdf
3月10日、前年12月に辞職希望を申し出ていたが、理学部勤務を免ぜられ、地震研究所所員専任となる。3月12日、帝国学士院で“On Thermoelectric and Electrothermal Properties of Bismuth Single Crystal”(with T. Tsutsui)を発表。3月15日、地震研究所談話会で「砂の崩れ方の話」(宮部直巳と共著)を発表。
4月2日、数学物理学会で“Some Experiments on Periodic From of Convection Currents”(with Second Year Students)を発表。4月12日、帝国学士院で“On Thermoelectric Phenomena of Thin Metallic Films”(with S. Tanaka and S. Kusaba)を発表。4月19日、地震研究所談話会で「地球の激震帯と其長周期移動」(宮部と共著)を発表。
5月11日、帝国学士院“On a Long Period Fluctuation in Latitude of the the Macroseismic Zone of the Earth”(with N. Miyabe)を発表。5月17日、地震研究所談話会で「弾性波の実験(第二報)」(坪井と共著)および「日本海沿岸の島列に就て」を発表。5月30日、航空学談話会で「風の短周期変化に就て」(玉井光男と共著)。
6月21日、地震研究談話会で「沿岸島列に就て」および「島弧の生成に関する実験」(宮部と共著)を発表。7月12日、帝国学士院で“On the Vortical Motion of Fluid Produced by Rotating Body”(with K. Hattori)を発表。
9月20日、地震研究所談話会で「土佐南海岸の汀線変化に就て」(岸上冬彦・小平孝雄と共著)および「統計地震学に於けるSchwankung の理論の応用」(岸上・河角広と共著)を発表。
10月12日、帝国学士院で“Formation of Periodic Columnar Vortices by Convection”および“Residual Thermoelectric Phenomena of Apparently Homogeneous Wire”(with T. Tsutsui and M.Tamano)を発表。10月14日、水産講習所の海洋調査担当官会議で「大気の運動に就て」を講演。
10月18日、地震研究所談話会で「弾性波の実験(第三報)」(坪井と共著)、「微動遮断に関する堀の効果」(坪井と共著)および「砂の崩壊に就て」(宮部と共著)を発表。11月15日、地震研究所談話会で「本邦に於ける近年の山崩の分布」を発表。
12月12日、帝国学士院で“On the Mechanism of Formation of Step-Faults in Sand Layers—A Possible Analogy with Slip Bands in Deformed Metallic Crystals”(with N. Miyabe)を発表。この年の秋頃よりアイヌ語、マレイ語などの辞典から土佐の地名の語源を捜すことを試みる。
「断片」、『明星』、1月。
「備忘録」、『思想』、9月。
「Odisin no Okorikata ni kwansuru hitotuno Syukisei」、『RS』、9月。
「松島より」、『渋柿』、9月。
「怪異考」、『思想』、11月。
「昭和二年の二科会と美術院」、『霊山美術』、11月。
「人の言葉—自分の言葉」、『東京帝国大学理学部会誌』、12月。 ]
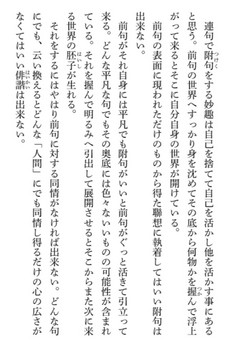
「断片」、『明星』、1月。(抜粋)
https://aozora-dev.binb.jp/reader/main.html?cid=42221
[豊隆(蓬里雨)・昭和二年(一九二七)、四十四歳。七月翻訳ストリンドベリ『父』出版。十二月翻訳ストリンドベリ『幽霊曲』(岩波文庫)出版。]
「歌仙『みちのく人の巻』(昭和二年二月「渋柿」)」
オ
送別
あすよりはみちのく人や春の雨 東洋城
まだ雪のこる西側の山 蓬里雨
沈丁花こぼるゝ里に移り来て 寅日子
筧は口をつけぬならはし 城
庭の木に梟来て啼く明けの月 雨 月
納豆うれしき肌寒の朝 子
ウ
年々を脚気の癒ゆる露深み 城
あすからかゝる約束の本 雨
切貼の馴れぬ手振もうら若く 子
母子(オヤコ)小町と唄はれにけり 城
一々に値上げ煙草の詫をいひ 雨
蠅取紙に光る秋の日 子
鰡(ボラ)鰯秋刀魚のきほふ魚の棚 城
蹇(アシナエ)の子のギス飼うてゐる 雨
針程のことを兎角に言ひつのり 子
白いうなじをふるはせて泣く 城 恋
斵(キ)れて来て見付通れば花に月 雨 花・月・恋
誰が捨てたか土手の猫の子 子
ナオ
蠶(コ)の頃の苗代の頃の忙しさ 城
家出の兄のよこす長文 雨
繰り言も浮世長屋の隣同士 子
箍(タガ)のはじけた桶提げて行く 城
大木の榎実こぼるゝ塀の前 雨
流れにまかせ葦を刈る船 子
悲しきは謡の中の秋の風 城
義理立たねばとあかで別るゝ 雨 恋
腰掛に一夜仮寝の夢覚めて 子 恋
朝のうちからわかる雷 城
先ず孫に月見団子をわけてやり 雨 月
白い紅いはおしろいの花 子
ナウ
秋の空丘の丸きに家建ちて 城
踏切越せば税関がある 雨
夜もすがら何処の鍛冶屋の鎚(ツチ)の音 子
幾日の果ての葬(ホフリ)悲しき 城
此度は花見にさとの母連れて 雨 花
小鮎の鰭(ヒレ)にいさゝかの色 子
※ この三吟歌仙で目立つのは、「二花三月」の「月・花の定座」を、脇句作者の「蓬里雨」が独占しているということである。
(オ「五句目」)
庭の木に梟来て啼く明けの月 蓬里 雨→月(「梟」=冬、冬の月、定石は秋の月。)
(ウ「十一句目」)
斵(キ)れて来て見付通れば花に月 蓬里雨→花・月・恋(「斵(キ)れる」=「女との縁を切る」、「見付」=「見付遊郭」、「花」=春で「春の月」、定石は夏の月。)
(ナオ「十一句目」)
先ず孫に月見団子をわけてやり 蓬里雨→月(「月見団子」=秋、「人情自」の秋の月。)
(ナウ「五句目」)
此度は花見にさとの母連れて 蓬里雨→花(「花見」=春。「人情自他半」の花。)
三吟の場合は、「A→B→C」の順を繰り返すと、「B」が「二花三月」を独占するので、宗匠・主宰(「捌き」)が、「A=発句と月、B=花と月、C=花と月」などと、「月花一句」(「月と花の句は、一人で独占しないで、他の連衆にも配分する)というルール」で、捌いていくのだが、その配慮は、ここでは完全に無視されている。
これらを肯定的に解するると、仙台(東北帝大)に赴任する「蓬里雨(連衆=芭蕉俳諧研究家・独逸文学者・漱石門」への最大限の餞として、「東洋城・寅日子・蓬里雨」座の、「東洋城(俳諧宗匠・『渋柿』主宰・漱石門)と寅日子(連衆=俳諧研究家・物理学者・漱石門)・との二人が、意図的に、送別する「脇=蓬里雨」に、この連句の「月の座・花の座」の、いわゆる、「花を持たせる」という進行をしたと解することもできよう。
(参考)「『3、月の句の心得』・『4.花の句の心得』・『5.恋の句の心得』・『6.特別扱いの句』・『7.句の続け方』・『8.季移り』・『9.付け順』・10.『「付け」と「転じ」』周辺(抜粋)
http://hakuhyodo.my.coocan.jp/kuzu/renku.html
[3.月の句の心得
(1) 月の句は春夏秋冬いずれの月を出してもよい。
(2) ただし、発句が秋季の場合には、第五句目の定座の月を「引き上げ」て、三句目までに月の句(これは秋の月とする)を詠むのが原則。
(3) 月の定座で、「月」や「有明」という語を出すのがまずい場合には、月の異名・(「桂男」とか「玉兎」など)を用いる。どういうのがまずいのかというと、表六句のうちに、「月」を含む言葉が使われており、定座で「月」を出すと「月」がだぶる場合、たとえば発句に如月とか霜月(これを月並の月という)などが出た場合。つまり、空の月は moon で、月並の月は month というわけ。
(4) 月の定座では落月や無月の句はできるだけ慎む。
(5) 秋の句が三句~五句続く場合、その中のどこかで必ず月の句を詠む。この月がないのを素秋(すあき)といって嫌う。
(6) 「星月夜(ほしづくよ)」は秋の季語であるが、星の光が月のように明るい夜をさし、直接月を詠んだ言葉ではない。そこで、この語が発句に出たら、それに続く秋の句には月を詠み込まず素秋にする。そのかわり、他の季の句中に「有明」など月のかわりになるものを詠み込む。
(7) どうしても月を詠まねばならぬのに、前句の具合で付けにくい場合は、実際空に浮かぶ月だけではなく、想像上の月を付ける方法もあり、これを「思いあわせの月」という。
(例)
堪忍ならぬ七夕の照り 利平
名月のまに合せ度(たき)芋畑 芭蕉
上の例では、名月は実際の月ではなく、名月の料理に間に合せたいということで、「照り」と「月」の不調和を避けております。
(8) 月の字を一種の助字(「かな」「や」の類)として用いることがあり、これを「投げこみの月」という。
(例)
革足袋(かはたび)に地雪踏(ぢせつた)重き秋の霜 洒堂
伏見あたりの古手屋の月 芭蕉
4.花の句の心得
花といえば、春の桜とだいたい相場が決っております。特定銘柄の老舗だけに、格式も高く、あだやおろそかには扱えません。定座に用いる花の句には、桜の花を詠んでも「桜」といってはならず、必ず「花」という言葉を用います。もちろん、「桜」という言葉を使うこともありますけれども、それは正式な「花」の句としては認められず、同様に、「豆の花」なども正式の花にはなりません。つまり、歌の世界では、桜はもはや単に植物としての存在を超えたものとしてあるわけです。
(1) 四句目には特に軽い句を出すべきだから、花の句のように大切なものは出さない。
(2) 月と花とを一句のうちに詠み込むのは、一座に一句と限る。こういう句の季は、花にひかれて春となる。
(例)
月と花比良の高ねを北にして 芭蕉
(3) 花に桜をつけることは、特別の場合には許される。
(例)
辛崎の松は花より朧(おぼろ)にて 芭蕉
山はさくらをしをる春雨 尚白
例の発句は松を詠んだものであり、花は実体のない「根なしの花」だから、脇に桜を出してもかまわないとする。
(4) 一句の中に花と吉野を同居させるのはかまわないが、「花」に「吉野」を、「吉野」に「花」を付けてはいけない。(同様に「宇治」に「茶」を付けてはいけ ない)
(5) 短句(七七)には、好んで「花」を持ち出さない。(五七五のほうに詠みなさいということ)
(6) 月花一句のこと、つまり俳諧ではひとりの作者が月や花の句を独占してはならない。みんなに「花」を持たせるよう、適当に按配するのである。
(7) 花前の句は、花の句が詠みやすいように配慮する。つまり、花の定座の前では、「秋」の字や、恋の句は控えて、軽い句を作る。
5.恋の句の心得
蕉門俳諧の恋の句の特徴は、ことばそのものよりも恋の情や気持を大事にするところにあります。蕉風以前には、式目書なる便利なものを参考にして、恋のことばを選べばそれでよしとする風があり、その中には、「そひふし」「人妻」「若後家」「男狂」「長枕」などという中年好みのことばも多かったようです。しかし、芭蕉がそんなことばをむき出しで使うはずはなく、
ものいへば扇子に顔をかくされて 芭蕉
きぬぎぬのあまりかぼそくあてやかに 芭蕉
と、さすがに品のよい中にも強烈な印象を与える色香が漂っております。面白いのは、芭蕉俳諧ではもともと恋の句を出す回数が少なかったのですけれども、晩年にむかってその傾向は顕著となり、まず一巻中一句が普通になったことです。
(1) 初折の裏の第一句目、つまり折立(おったて)に恋句を出すことを、昔は「待兼(まちかね)の、恋」といって嫌ったが、蕉門ではそれにこだわらない。
(2) 付句に恋の句をさそうような含みのある句を「恋の呼び出し」といい、恋の句に続いて付けると恋になるが、一句独立しては恋の意を持たぬものを「恋離れ」という。また、前句が恋とも恋ともつかぬような句である時には、必ず恋の句を付けて、前句ともども恋にすべきである。
(例)
(a) 砧(きぬた)うたるゝ尼達の家 曽良
(b) あの月も恋ゆゑにこそ悲しけれ 翠桃
(c) 露とも消ね胸のいたきに 芭蕉
(d) 錦繍(きんしう)に時めく花の憎かりし 曽良
上の例では、(a)が恋なのかどうかはっきりしない句、つまり「恋の呼び出し」にあたり、それを受けた翠桃は原則通り恋の句を付けている。また、(d)は(c)が恋句であるからはじめて恋になるという意味で「恋離れ」に相当する。
(3) 花の定座の前には恋句を出さぬこと。これは「花の句」の項で説明したとおり、花の句の前にはなるべく軽い句を出すことから。ただし、恋句自体の中に花や月を詠みこむのは自由である。
6.特別扱いの句
歌仙三十六句のうち、最初から三番目までと最終の句とは、特別の名称でよばれ、またその取り扱いにもきまりがあります。その他の句は全部平句(ヒラク)といいます。
(1) 第一句 …… 発句または立句(たてく)。これには、歌仙興行の季節にかなった季語をもち、完全に独立した形と内容をそなえていることが要求される。ふつう、「や」とか「かな」という切字(きれじ)を用いるが、それは絶対条件ではなく、あくまでも内容が問われる。歌仙全体の気分を左右しかねないので、あまりに重々 しいものや、縁起の悪いものは嫌われる。
(2) 第二句 …… 脇句(わきく)または脇。「客発句、亭主脇」ということばがあり、一座の賓客格が発句を出し、亭主格がそれに脇を付ける慣習があった。いわば、挨拶を交す心である。脇句はぴったりと発句の調子・用語に付け、発展させすぎてはいけない。季節、題材、発句にあわせるのが原則である。体言留めが多い。
(例)
市中(まちなか)は物のにほひや夏の月 凡兆
あつしあつしと門々の声 芭蕉
(3) 第三句 …… 第三。脇句が発句にぴったりと付くのに対して、第三は転句にあたり、変化をもたらす。発句・脇が初春の句ならば、第三では中春か晩春というふうに、季節にも気を配るのはもちろん、内容も思い切って離れるのである。
留め方にもきまりがあって、ふつうは「に」「て」「にて」「らん」「もなし」などで留める(例外あり)。ただし、発句・脇の腰(終りの五文字、または七文字)に「て」の字があれば、第三には「て」留めを用いず、発句が「かな」留めの場合には、第三では「にて」留めを用いない。また、発句の切字に推量・疑問の助詞・助動詞を用いた場合は、第三では「らん」留めは用いない。
(4) 第四句 …… 特別の名称はないが、四句目は軽く付けるのが昔からの習い。
(5) 第三十六句 …… 挙句(あげく)。挙句はあっさりとつけるのをよしとする。挙句は発句の作者や脇句の作者(亭主)が作らず、一座の最初の一巡に執筆の句が入っていない場合には、執筆が作る。また、ここでは季を変えない。
7.句の続け方
連句には句数(くかず)と去嫌(さりきらい)というルールがあります。句数というのは、春なら春の句を最低何句続けねばならず、また何句以上続けてはいけないというきまりです。また、去嫌とは、たとえば同季の句が三句続いた場合、つぎに同じ季の句を出すには最低五句は隔てなければならない(これを「同季五句去り」という)というふうに、類似したものの接近を嫌うというきまりです。
(1) 春・秋は句数は三句から五句まで。同季五句去りとする。
(2) 夏・冬は句数は一句から三句まで(ふつうは二句)。同季二句去り。
(3) 神祇・釈教(神社仏閣、神道・仏教に関係するもの)は、句数一句より三句、二句去りとする。
(4) 恋は句数二句から五句まで。三句去り。
(5) 述懐・無常(懐古・遁世・老い・うき世、死・葬儀・霊魂など)は、句数一句から三句。三句去り。
(6) 山類(さんるい)・水辺(すいへん)(山・峰・岡・谷・麓、海・浦・川・池・湖・水・氷の類)は、句数は一句から三句。三句去り。ただし、異山類・異水辺(山と谷、海と川など)は打越(うちこし)、つまり一句去りでもよい。
(7) 人倫(人間生活に関すること)は二句去り。ただし、実際は句数・去嫌ともかなり自由に付けている。
(8) 国名・名所は、句数一句から二句。二句去り。
(9) 生類(生き物)は、句数一句から二句。同種なら二句去り、異種なら打越を嫌わず。
(10) 木類・草類は、句数一句から二句。二句去りだが、木と草とは打越を嫌わず。
(11) 降物(ふりもの 雨・露・雪など)・聳物(そびきもの 雲・霞・虹など)は、句数一句から二句。二句去りだが、降物と聳物とは打越を嫌わず。
(12) 時分(朝・昼・夕など)は、句数一句から二句。同時分なら三句去りだが、異時分なら打越を嫌わず。(夜分二句去り、ただし打越を嫌わぬものあり、とあるが、どれが夜分の句かということになると煩雑に過ぎるので、省略する)
8.季移り
俳諧ではある季から他の季に移る場合、ふつうその間に雑(ゾウ)とよばれる、特定の季に属さない句を入れます。なるほど、これはうまい工夫です。中間に、どちらの季節にあってもおかしくない句を挿入しておけば、ごく自然に進行するはずですから。
(例)
(a) 雲雀なく小田に土持比(ツチモツコロ)なれや (春)
(b) しとぎ祝うて下されにけり (雑)
(C) 片隅に虫歯かゝへて暮の月 (秋)
すこし脇道にそれますが、「しとぎ」というのは、水につけて軟らかくなった生米を、ペースト状の粉にしてからまるめたもので、神仏へのお供えなどに用いられるものです。
ところが、中間に雑の句をはさまず、直接季を転じて付けることもあり、これを「季移り」といいます。これは、露のように春・夏・秋三季にわたるものや、月のように四季にわたるもの、その他特定の季の季語になってはいても一年中あっておかしくないものを巧みに利用するわけです。季移りは、秋から冬へ、冬から秋へというような二季移りが普通ですけれども、三季移り(ただし、歌仙では一箇所に限られる)もあります。
(例1)
(a) 放(ハナチ)やるうづらの跡は見えもせず (秋)
(b) 稲の葉延(ハノビ)の力なきかぜ (夏)
前句は「鶉(うづら)」で秋、付句は「稲の葉延」で夏(晩夏)。この例の場合、(a) の秋の鶉を、(a)(b)の両句でかもしだされる景色を味わう際には夏の鶉と見かえて解釈します。鶉は夏にもいるから、不自然はないとするのです。
(例2)
(a) 露とも消ね胸のいたきに (秋)
(b) 錦繍に時めく花の憎かりし (春)
「露」は秋の季語ですが、三季にわたるので春の情景としてもおかしくないというわけです。
なお、雑すなわち無季の句は、句数・句去りの制約を受けません。ただし、むやみに雑の句ばかりを出して、歌仙一巻の調和を破壊することがあってはいけません。
9.付け順
複数の人間が集まって歌仙を興行する際に、どういう順で句を続けていくのか、これには「出勝(でがち)」と「膝送り」というふたつのやり方があります。
出勝は「付勝(つけがち)」ともいって、まずは発句以下ひとりひとり句を付けて、一巡したら、その後は各句ごとに連衆全員が付句を考え、早くできた人が句を執筆に言うか短冊に書いて提出します。それを宗匠が、必要なら指導を加えたうえで、次の付句を促すのです。いわば、早いもの順ですから、腕のいい人にはかなわないわけです。芭蕉の俳席では、このやり方はあまり採用されなかったようです。
膝送りは、一定の順序によって付け進めていくやり方で、人数(芭蕉の俳席では、ふつう二人から六、七人)によって、次のように決っております。なお、カッコ内は、月花の定座を示し、「』」は初折・名残の折それぞれの表・裏の区切りを示します。なお、七吟以上では定まった順番を見いだし難く、六吟には基本的な順序はあるものの、付け順はいろいろだそうです。また、ぼくたちが真似事をするにしても、五吟くらいが関の山でしょうから、ここでは両吟から五吟までについて解説します。独吟の順序は、……わかりますね。
(1) 両吟(二人)
A,B,B,A,A(月),B』
B,A,A,B,B,A,A,B(月),B,A,A(花),B[折端]』
B[折立],A,A,B,B,A,A,B,B,A,A(月),B』
B,A,A,B,B(花),A』
これは一見でたらめのように思われるかも知れないが、実は月・花、長句・短句がきわめて公平に配分されている。
(2) 三吟
基本的には、A,B,C,A,B,Cを最後まで繰り返すのだが、それではBが月・花の句を独占してしまう。実際には、Aは発句、BとCは花を一句ずつ、月の句はひとり一句を理想とするが、一人二句のこともある。この辺は座のなりゆきと、宗匠の判断によるのだろう。
(3) 四吟
各人が四句おき、二句おきに出るように(「二飛び四飛び」という)、
A,B,C,D-B,A,D,C
を繰返す。これだと、Aには発句と花・月ひとつずつ、Bには月二つ、Cには花ひとつがあたるけれども、Dには定座があたらない。そこで、月の座を引き上げたり、後半で順序を変更している例もある。
(4) 五吟 三十六句を五人で割れば一句あまるので、最初の一巡の後で執筆がその一句を担当して数を合せる。執筆をFとすれば、
A,B,C,D,E(月),F』
B,A,D,C,A,E,C,B(月),E,D,B(花),A』
D,C,A,E,C,B,E,D,B,A,D(月),C』
A,E,C,B,E(花),D』
これではAとCには月・花の定座はあたらないので、やはり座を引き上げたりして調節しているようだ。
10.「付け」と「転じ」
すでに見たように、俳諧ではAにBを付け、BにCを付け、しかもAとBで構成される世界は、BとCとで新たに構成される世界によって「転じ」られることになります。こうして、付けることによって転じられるという「変化」が生ずるわけです。
「付け」については、蕉風よりはるか以前から様々の分類がなされておりますが、それを細かに検討することは即席入門の範囲を越えますので、ここでは触れません。『去来抄』にいう「物付」、「心付」、「匂い付」は、ふつうそれぞれ貞門、談林、蕉風にあてはめられております。しかし、貞門の付合(ツケアイ、寄合ともいい、付け方のこと)のすべてが物付で、蕉風ならば匂い付とするのは間違いで、貞門にも心付志向あれば、蕉風にも物付の例はあります。
(1) 物付 …… 宇治なら茶というふうに、前句のことばや物に縁のあることばを用いて付けていくやりかた。
(例)
歌いづれ小町をどりや伊勢踊 貞徳
どこの盆にかおりやるつらゆき 同
上の例では、「小町」「伊勢」から「貫之」、「踊」から「盆」が出ている。
(2) 心付 …… 前句のもつ意味や心持に応じて付ける(句意付)やりかた。
(例)
子をいだきつゝのり物のうち 宗因
度々の嫁入するは恥知らず 同
子供を抱きながら乗り物に乗っている女を、子持ちの再婚ととらえて、からかっている。
さて、肝心の匂い付ですが、広く言えば心付に含まれるとも考えられ、蕉門の場合は、前句の意味に即して付けるというよりも、前句の持つ気分・余情を把握した上で、それに響きあう内容の句を付けることが多い(当然句意付もあるわけです)と考えればよいでしょう。
「付合」が付けの種類をいうことばなら、付けの手法・態度を「付心」といい、その結果得られる効果を「付味」といいます。 ]
[東洋城・五十歳。塩原に句碑建立。伊予に遊ぶ。芥川龍之介自殺。「添削実相」掲載始まる。]

〇松根東洋城両面碑 塩湧橋先
【碑文】
「さまみえて土になりゐる落葉哉」表
「すずしさやこの山水に出湯とは」裏 (塩原四季郷より)
http://hotyu.starfree.jp/historicalspots/bungakuhi/bungakuhi.html
『東洋城全句集(上巻)』の「昭和二年」には、「塩原・四季郷」と題して、三十二句が収載されている。また、『東洋城全句集(中巻)』には、「昭和二年七月、塩原四季郷両面碑(西面)前にて」と題しての、当時の東洋城の肖像写真が掲載されている。この時の句に、上記の「両面句碑」の句に似た、次のような句がある。
涼しさや橋の下なる碧き山
涼しさや街道一つみえゐる灯(前書「瞰(かん) 流亭」)
径(ミチ)岐(キ)していづれか深き落葉かな
[寅彦=寅日子・五十歳
file:///C:/Users/user/Downloads/%E5%AF%BA%E7%94%B0%E5%AF%85%E5%BD%A6%E5%B9%B4%E8%A1%A8.pdf
3月10日、前年12月に辞職希望を申し出ていたが、理学部勤務を免ぜられ、地震研究所所員専任となる。3月12日、帝国学士院で“On Thermoelectric and Electrothermal Properties of Bismuth Single Crystal”(with T. Tsutsui)を発表。3月15日、地震研究所談話会で「砂の崩れ方の話」(宮部直巳と共著)を発表。
4月2日、数学物理学会で“Some Experiments on Periodic From of Convection Currents”(with Second Year Students)を発表。4月12日、帝国学士院で“On Thermoelectric Phenomena of Thin Metallic Films”(with S. Tanaka and S. Kusaba)を発表。4月19日、地震研究所談話会で「地球の激震帯と其長周期移動」(宮部と共著)を発表。
5月11日、帝国学士院“On a Long Period Fluctuation in Latitude of the the Macroseismic Zone of the Earth”(with N. Miyabe)を発表。5月17日、地震研究所談話会で「弾性波の実験(第二報)」(坪井と共著)および「日本海沿岸の島列に就て」を発表。5月30日、航空学談話会で「風の短周期変化に就て」(玉井光男と共著)。
6月21日、地震研究談話会で「沿岸島列に就て」および「島弧の生成に関する実験」(宮部と共著)を発表。7月12日、帝国学士院で“On the Vortical Motion of Fluid Produced by Rotating Body”(with K. Hattori)を発表。
9月20日、地震研究所談話会で「土佐南海岸の汀線変化に就て」(岸上冬彦・小平孝雄と共著)および「統計地震学に於けるSchwankung の理論の応用」(岸上・河角広と共著)を発表。
10月12日、帝国学士院で“Formation of Periodic Columnar Vortices by Convection”および“Residual Thermoelectric Phenomena of Apparently Homogeneous Wire”(with T. Tsutsui and M.Tamano)を発表。10月14日、水産講習所の海洋調査担当官会議で「大気の運動に就て」を講演。
10月18日、地震研究所談話会で「弾性波の実験(第三報)」(坪井と共著)、「微動遮断に関する堀の効果」(坪井と共著)および「砂の崩壊に就て」(宮部と共著)を発表。11月15日、地震研究所談話会で「本邦に於ける近年の山崩の分布」を発表。
12月12日、帝国学士院で“On the Mechanism of Formation of Step-Faults in Sand Layers—A Possible Analogy with Slip Bands in Deformed Metallic Crystals”(with N. Miyabe)を発表。この年の秋頃よりアイヌ語、マレイ語などの辞典から土佐の地名の語源を捜すことを試みる。
「断片」、『明星』、1月。
「備忘録」、『思想』、9月。
「Odisin no Okorikata ni kwansuru hitotuno Syukisei」、『RS』、9月。
「松島より」、『渋柿』、9月。
「怪異考」、『思想』、11月。
「昭和二年の二科会と美術院」、『霊山美術』、11月。
「人の言葉—自分の言葉」、『東京帝国大学理学部会誌』、12月。 ]
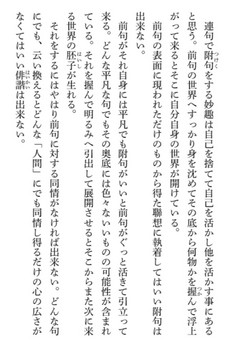
「断片」、『明星』、1月。(抜粋)
https://aozora-dev.binb.jp/reader/main.html?cid=42221
[豊隆(蓬里雨)・昭和二年(一九二七)、四十四歳。七月翻訳ストリンドベリ『父』出版。十二月翻訳ストリンドベリ『幽霊曲』(岩波文庫)出版。]
「歌仙『みちのく人の巻』(昭和二年二月「渋柿」)」
オ
送別
あすよりはみちのく人や春の雨 東洋城
まだ雪のこる西側の山 蓬里雨
沈丁花こぼるゝ里に移り来て 寅日子
筧は口をつけぬならはし 城
庭の木に梟来て啼く明けの月 雨 月
納豆うれしき肌寒の朝 子
ウ
年々を脚気の癒ゆる露深み 城
あすからかゝる約束の本 雨
切貼の馴れぬ手振もうら若く 子
母子(オヤコ)小町と唄はれにけり 城
一々に値上げ煙草の詫をいひ 雨
蠅取紙に光る秋の日 子
鰡(ボラ)鰯秋刀魚のきほふ魚の棚 城
蹇(アシナエ)の子のギス飼うてゐる 雨
針程のことを兎角に言ひつのり 子
白いうなじをふるはせて泣く 城 恋
斵(キ)れて来て見付通れば花に月 雨 花・月・恋
誰が捨てたか土手の猫の子 子
ナオ
蠶(コ)の頃の苗代の頃の忙しさ 城
家出の兄のよこす長文 雨
繰り言も浮世長屋の隣同士 子
箍(タガ)のはじけた桶提げて行く 城
大木の榎実こぼるゝ塀の前 雨
流れにまかせ葦を刈る船 子
悲しきは謡の中の秋の風 城
義理立たねばとあかで別るゝ 雨 恋
腰掛に一夜仮寝の夢覚めて 子 恋
朝のうちからわかる雷 城
先ず孫に月見団子をわけてやり 雨 月
白い紅いはおしろいの花 子
ナウ
秋の空丘の丸きに家建ちて 城
踏切越せば税関がある 雨
夜もすがら何処の鍛冶屋の鎚(ツチ)の音 子
幾日の果ての葬(ホフリ)悲しき 城
此度は花見にさとの母連れて 雨 花
小鮎の鰭(ヒレ)にいさゝかの色 子
※ この三吟歌仙で目立つのは、「二花三月」の「月・花の定座」を、脇句作者の「蓬里雨」が独占しているということである。
(オ「五句目」)
庭の木に梟来て啼く明けの月 蓬里 雨→月(「梟」=冬、冬の月、定石は秋の月。)
(ウ「十一句目」)
斵(キ)れて来て見付通れば花に月 蓬里雨→花・月・恋(「斵(キ)れる」=「女との縁を切る」、「見付」=「見付遊郭」、「花」=春で「春の月」、定石は夏の月。)
(ナオ「十一句目」)
先ず孫に月見団子をわけてやり 蓬里雨→月(「月見団子」=秋、「人情自」の秋の月。)
(ナウ「五句目」)
此度は花見にさとの母連れて 蓬里雨→花(「花見」=春。「人情自他半」の花。)
三吟の場合は、「A→B→C」の順を繰り返すと、「B」が「二花三月」を独占するので、宗匠・主宰(「捌き」)が、「A=発句と月、B=花と月、C=花と月」などと、「月花一句」(「月と花の句は、一人で独占しないで、他の連衆にも配分する)というルール」で、捌いていくのだが、その配慮は、ここでは完全に無視されている。
これらを肯定的に解するると、仙台(東北帝大)に赴任する「蓬里雨(連衆=芭蕉俳諧研究家・独逸文学者・漱石門」への最大限の餞として、「東洋城・寅日子・蓬里雨」座の、「東洋城(俳諧宗匠・『渋柿』主宰・漱石門)と寅日子(連衆=俳諧研究家・物理学者・漱石門)・との二人が、意図的に、送別する「脇=蓬里雨」に、この連句の「月の座・花の座」の、いわゆる、「花を持たせる」という進行をしたと解することもできよう。
(参考)「『3、月の句の心得』・『4.花の句の心得』・『5.恋の句の心得』・『6.特別扱いの句』・『7.句の続け方』・『8.季移り』・『9.付け順』・10.『「付け」と「転じ」』周辺(抜粋)
http://hakuhyodo.my.coocan.jp/kuzu/renku.html
[3.月の句の心得
(1) 月の句は春夏秋冬いずれの月を出してもよい。
(2) ただし、発句が秋季の場合には、第五句目の定座の月を「引き上げ」て、三句目までに月の句(これは秋の月とする)を詠むのが原則。
(3) 月の定座で、「月」や「有明」という語を出すのがまずい場合には、月の異名・(「桂男」とか「玉兎」など)を用いる。どういうのがまずいのかというと、表六句のうちに、「月」を含む言葉が使われており、定座で「月」を出すと「月」がだぶる場合、たとえば発句に如月とか霜月(これを月並の月という)などが出た場合。つまり、空の月は moon で、月並の月は month というわけ。
(4) 月の定座では落月や無月の句はできるだけ慎む。
(5) 秋の句が三句~五句続く場合、その中のどこかで必ず月の句を詠む。この月がないのを素秋(すあき)といって嫌う。
(6) 「星月夜(ほしづくよ)」は秋の季語であるが、星の光が月のように明るい夜をさし、直接月を詠んだ言葉ではない。そこで、この語が発句に出たら、それに続く秋の句には月を詠み込まず素秋にする。そのかわり、他の季の句中に「有明」など月のかわりになるものを詠み込む。
(7) どうしても月を詠まねばならぬのに、前句の具合で付けにくい場合は、実際空に浮かぶ月だけではなく、想像上の月を付ける方法もあり、これを「思いあわせの月」という。
(例)
堪忍ならぬ七夕の照り 利平
名月のまに合せ度(たき)芋畑 芭蕉
上の例では、名月は実際の月ではなく、名月の料理に間に合せたいということで、「照り」と「月」の不調和を避けております。
(8) 月の字を一種の助字(「かな」「や」の類)として用いることがあり、これを「投げこみの月」という。
(例)
革足袋(かはたび)に地雪踏(ぢせつた)重き秋の霜 洒堂
伏見あたりの古手屋の月 芭蕉
4.花の句の心得
花といえば、春の桜とだいたい相場が決っております。特定銘柄の老舗だけに、格式も高く、あだやおろそかには扱えません。定座に用いる花の句には、桜の花を詠んでも「桜」といってはならず、必ず「花」という言葉を用います。もちろん、「桜」という言葉を使うこともありますけれども、それは正式な「花」の句としては認められず、同様に、「豆の花」なども正式の花にはなりません。つまり、歌の世界では、桜はもはや単に植物としての存在を超えたものとしてあるわけです。
(1) 四句目には特に軽い句を出すべきだから、花の句のように大切なものは出さない。
(2) 月と花とを一句のうちに詠み込むのは、一座に一句と限る。こういう句の季は、花にひかれて春となる。
(例)
月と花比良の高ねを北にして 芭蕉
(3) 花に桜をつけることは、特別の場合には許される。
(例)
辛崎の松は花より朧(おぼろ)にて 芭蕉
山はさくらをしをる春雨 尚白
例の発句は松を詠んだものであり、花は実体のない「根なしの花」だから、脇に桜を出してもかまわないとする。
(4) 一句の中に花と吉野を同居させるのはかまわないが、「花」に「吉野」を、「吉野」に「花」を付けてはいけない。(同様に「宇治」に「茶」を付けてはいけ ない)
(5) 短句(七七)には、好んで「花」を持ち出さない。(五七五のほうに詠みなさいということ)
(6) 月花一句のこと、つまり俳諧ではひとりの作者が月や花の句を独占してはならない。みんなに「花」を持たせるよう、適当に按配するのである。
(7) 花前の句は、花の句が詠みやすいように配慮する。つまり、花の定座の前では、「秋」の字や、恋の句は控えて、軽い句を作る。
5.恋の句の心得
蕉門俳諧の恋の句の特徴は、ことばそのものよりも恋の情や気持を大事にするところにあります。蕉風以前には、式目書なる便利なものを参考にして、恋のことばを選べばそれでよしとする風があり、その中には、「そひふし」「人妻」「若後家」「男狂」「長枕」などという中年好みのことばも多かったようです。しかし、芭蕉がそんなことばをむき出しで使うはずはなく、
ものいへば扇子に顔をかくされて 芭蕉
きぬぎぬのあまりかぼそくあてやかに 芭蕉
と、さすがに品のよい中にも強烈な印象を与える色香が漂っております。面白いのは、芭蕉俳諧ではもともと恋の句を出す回数が少なかったのですけれども、晩年にむかってその傾向は顕著となり、まず一巻中一句が普通になったことです。
(1) 初折の裏の第一句目、つまり折立(おったて)に恋句を出すことを、昔は「待兼(まちかね)の、恋」といって嫌ったが、蕉門ではそれにこだわらない。
(2) 付句に恋の句をさそうような含みのある句を「恋の呼び出し」といい、恋の句に続いて付けると恋になるが、一句独立しては恋の意を持たぬものを「恋離れ」という。また、前句が恋とも恋ともつかぬような句である時には、必ず恋の句を付けて、前句ともども恋にすべきである。
(例)
(a) 砧(きぬた)うたるゝ尼達の家 曽良
(b) あの月も恋ゆゑにこそ悲しけれ 翠桃
(c) 露とも消ね胸のいたきに 芭蕉
(d) 錦繍(きんしう)に時めく花の憎かりし 曽良
上の例では、(a)が恋なのかどうかはっきりしない句、つまり「恋の呼び出し」にあたり、それを受けた翠桃は原則通り恋の句を付けている。また、(d)は(c)が恋句であるからはじめて恋になるという意味で「恋離れ」に相当する。
(3) 花の定座の前には恋句を出さぬこと。これは「花の句」の項で説明したとおり、花の句の前にはなるべく軽い句を出すことから。ただし、恋句自体の中に花や月を詠みこむのは自由である。
6.特別扱いの句
歌仙三十六句のうち、最初から三番目までと最終の句とは、特別の名称でよばれ、またその取り扱いにもきまりがあります。その他の句は全部平句(ヒラク)といいます。
(1) 第一句 …… 発句または立句(たてく)。これには、歌仙興行の季節にかなった季語をもち、完全に独立した形と内容をそなえていることが要求される。ふつう、「や」とか「かな」という切字(きれじ)を用いるが、それは絶対条件ではなく、あくまでも内容が問われる。歌仙全体の気分を左右しかねないので、あまりに重々 しいものや、縁起の悪いものは嫌われる。
(2) 第二句 …… 脇句(わきく)または脇。「客発句、亭主脇」ということばがあり、一座の賓客格が発句を出し、亭主格がそれに脇を付ける慣習があった。いわば、挨拶を交す心である。脇句はぴったりと発句の調子・用語に付け、発展させすぎてはいけない。季節、題材、発句にあわせるのが原則である。体言留めが多い。
(例)
市中(まちなか)は物のにほひや夏の月 凡兆
あつしあつしと門々の声 芭蕉
(3) 第三句 …… 第三。脇句が発句にぴったりと付くのに対して、第三は転句にあたり、変化をもたらす。発句・脇が初春の句ならば、第三では中春か晩春というふうに、季節にも気を配るのはもちろん、内容も思い切って離れるのである。
留め方にもきまりがあって、ふつうは「に」「て」「にて」「らん」「もなし」などで留める(例外あり)。ただし、発句・脇の腰(終りの五文字、または七文字)に「て」の字があれば、第三には「て」留めを用いず、発句が「かな」留めの場合には、第三では「にて」留めを用いない。また、発句の切字に推量・疑問の助詞・助動詞を用いた場合は、第三では「らん」留めは用いない。
(4) 第四句 …… 特別の名称はないが、四句目は軽く付けるのが昔からの習い。
(5) 第三十六句 …… 挙句(あげく)。挙句はあっさりとつけるのをよしとする。挙句は発句の作者や脇句の作者(亭主)が作らず、一座の最初の一巡に執筆の句が入っていない場合には、執筆が作る。また、ここでは季を変えない。
7.句の続け方
連句には句数(くかず)と去嫌(さりきらい)というルールがあります。句数というのは、春なら春の句を最低何句続けねばならず、また何句以上続けてはいけないというきまりです。また、去嫌とは、たとえば同季の句が三句続いた場合、つぎに同じ季の句を出すには最低五句は隔てなければならない(これを「同季五句去り」という)というふうに、類似したものの接近を嫌うというきまりです。
(1) 春・秋は句数は三句から五句まで。同季五句去りとする。
(2) 夏・冬は句数は一句から三句まで(ふつうは二句)。同季二句去り。
(3) 神祇・釈教(神社仏閣、神道・仏教に関係するもの)は、句数一句より三句、二句去りとする。
(4) 恋は句数二句から五句まで。三句去り。
(5) 述懐・無常(懐古・遁世・老い・うき世、死・葬儀・霊魂など)は、句数一句から三句。三句去り。
(6) 山類(さんるい)・水辺(すいへん)(山・峰・岡・谷・麓、海・浦・川・池・湖・水・氷の類)は、句数は一句から三句。三句去り。ただし、異山類・異水辺(山と谷、海と川など)は打越(うちこし)、つまり一句去りでもよい。
(7) 人倫(人間生活に関すること)は二句去り。ただし、実際は句数・去嫌ともかなり自由に付けている。
(8) 国名・名所は、句数一句から二句。二句去り。
(9) 生類(生き物)は、句数一句から二句。同種なら二句去り、異種なら打越を嫌わず。
(10) 木類・草類は、句数一句から二句。二句去りだが、木と草とは打越を嫌わず。
(11) 降物(ふりもの 雨・露・雪など)・聳物(そびきもの 雲・霞・虹など)は、句数一句から二句。二句去りだが、降物と聳物とは打越を嫌わず。
(12) 時分(朝・昼・夕など)は、句数一句から二句。同時分なら三句去りだが、異時分なら打越を嫌わず。(夜分二句去り、ただし打越を嫌わぬものあり、とあるが、どれが夜分の句かということになると煩雑に過ぎるので、省略する)
8.季移り
俳諧ではある季から他の季に移る場合、ふつうその間に雑(ゾウ)とよばれる、特定の季に属さない句を入れます。なるほど、これはうまい工夫です。中間に、どちらの季節にあってもおかしくない句を挿入しておけば、ごく自然に進行するはずですから。
(例)
(a) 雲雀なく小田に土持比(ツチモツコロ)なれや (春)
(b) しとぎ祝うて下されにけり (雑)
(C) 片隅に虫歯かゝへて暮の月 (秋)
すこし脇道にそれますが、「しとぎ」というのは、水につけて軟らかくなった生米を、ペースト状の粉にしてからまるめたもので、神仏へのお供えなどに用いられるものです。
ところが、中間に雑の句をはさまず、直接季を転じて付けることもあり、これを「季移り」といいます。これは、露のように春・夏・秋三季にわたるものや、月のように四季にわたるもの、その他特定の季の季語になってはいても一年中あっておかしくないものを巧みに利用するわけです。季移りは、秋から冬へ、冬から秋へというような二季移りが普通ですけれども、三季移り(ただし、歌仙では一箇所に限られる)もあります。
(例1)
(a) 放(ハナチ)やるうづらの跡は見えもせず (秋)
(b) 稲の葉延(ハノビ)の力なきかぜ (夏)
前句は「鶉(うづら)」で秋、付句は「稲の葉延」で夏(晩夏)。この例の場合、(a) の秋の鶉を、(a)(b)の両句でかもしだされる景色を味わう際には夏の鶉と見かえて解釈します。鶉は夏にもいるから、不自然はないとするのです。
(例2)
(a) 露とも消ね胸のいたきに (秋)
(b) 錦繍に時めく花の憎かりし (春)
「露」は秋の季語ですが、三季にわたるので春の情景としてもおかしくないというわけです。
なお、雑すなわち無季の句は、句数・句去りの制約を受けません。ただし、むやみに雑の句ばかりを出して、歌仙一巻の調和を破壊することがあってはいけません。
9.付け順
複数の人間が集まって歌仙を興行する際に、どういう順で句を続けていくのか、これには「出勝(でがち)」と「膝送り」というふたつのやり方があります。
出勝は「付勝(つけがち)」ともいって、まずは発句以下ひとりひとり句を付けて、一巡したら、その後は各句ごとに連衆全員が付句を考え、早くできた人が句を執筆に言うか短冊に書いて提出します。それを宗匠が、必要なら指導を加えたうえで、次の付句を促すのです。いわば、早いもの順ですから、腕のいい人にはかなわないわけです。芭蕉の俳席では、このやり方はあまり採用されなかったようです。
膝送りは、一定の順序によって付け進めていくやり方で、人数(芭蕉の俳席では、ふつう二人から六、七人)によって、次のように決っております。なお、カッコ内は、月花の定座を示し、「』」は初折・名残の折それぞれの表・裏の区切りを示します。なお、七吟以上では定まった順番を見いだし難く、六吟には基本的な順序はあるものの、付け順はいろいろだそうです。また、ぼくたちが真似事をするにしても、五吟くらいが関の山でしょうから、ここでは両吟から五吟までについて解説します。独吟の順序は、……わかりますね。
(1) 両吟(二人)
A,B,B,A,A(月),B』
B,A,A,B,B,A,A,B(月),B,A,A(花),B[折端]』
B[折立],A,A,B,B,A,A,B,B,A,A(月),B』
B,A,A,B,B(花),A』
これは一見でたらめのように思われるかも知れないが、実は月・花、長句・短句がきわめて公平に配分されている。
(2) 三吟
基本的には、A,B,C,A,B,Cを最後まで繰り返すのだが、それではBが月・花の句を独占してしまう。実際には、Aは発句、BとCは花を一句ずつ、月の句はひとり一句を理想とするが、一人二句のこともある。この辺は座のなりゆきと、宗匠の判断によるのだろう。
(3) 四吟
各人が四句おき、二句おきに出るように(「二飛び四飛び」という)、
A,B,C,D-B,A,D,C
を繰返す。これだと、Aには発句と花・月ひとつずつ、Bには月二つ、Cには花ひとつがあたるけれども、Dには定座があたらない。そこで、月の座を引き上げたり、後半で順序を変更している例もある。
(4) 五吟 三十六句を五人で割れば一句あまるので、最初の一巡の後で執筆がその一句を担当して数を合せる。執筆をFとすれば、
A,B,C,D,E(月),F』
B,A,D,C,A,E,C,B(月),E,D,B(花),A』
D,C,A,E,C,B,E,D,B,A,D(月),C』
A,E,C,B,E(花),D』
これではAとCには月・花の定座はあたらないので、やはり座を引き上げたりして調節しているようだ。
10.「付け」と「転じ」
すでに見たように、俳諧ではAにBを付け、BにCを付け、しかもAとBで構成される世界は、BとCとで新たに構成される世界によって「転じ」られることになります。こうして、付けることによって転じられるという「変化」が生ずるわけです。
「付け」については、蕉風よりはるか以前から様々の分類がなされておりますが、それを細かに検討することは即席入門の範囲を越えますので、ここでは触れません。『去来抄』にいう「物付」、「心付」、「匂い付」は、ふつうそれぞれ貞門、談林、蕉風にあてはめられております。しかし、貞門の付合(ツケアイ、寄合ともいい、付け方のこと)のすべてが物付で、蕉風ならば匂い付とするのは間違いで、貞門にも心付志向あれば、蕉風にも物付の例はあります。
(1) 物付 …… 宇治なら茶というふうに、前句のことばや物に縁のあることばを用いて付けていくやりかた。
(例)
歌いづれ小町をどりや伊勢踊 貞徳
どこの盆にかおりやるつらゆき 同
上の例では、「小町」「伊勢」から「貫之」、「踊」から「盆」が出ている。
(2) 心付 …… 前句のもつ意味や心持に応じて付ける(句意付)やりかた。
(例)
子をいだきつゝのり物のうち 宗因
度々の嫁入するは恥知らず 同
子供を抱きながら乗り物に乗っている女を、子持ちの再婚ととらえて、からかっている。
さて、肝心の匂い付ですが、広く言えば心付に含まれるとも考えられ、蕉門の場合は、前句の意味に即して付けるというよりも、前句の持つ気分・余情を把握した上で、それに響きあう内容の句を付けることが多い(当然句意付もあるわけです)と考えればよいでしょう。
「付合」が付けの種類をいうことばなら、付けの手法・態度を「付心」といい、その結果得られる効果を「付味」といいます。 ]




コメント 0