「東洋城・寅彦、そして、豊隆」(漱石没後~寅彦没まで)俳句・連句管見(その五) [東洋城・寅日子(寅彦)・蓬里雨(豊隆)]
その二「大正七年(一九一八)」
[東洋城・四十一歳。奥州に遊び、『新奥の細道』連載。]
松島やそれより先の風薫れ(『新奥の細道』より四十五句の冒頭の句)
昔涼し芭蕉も子規も詣で居る(同上の三句目)
時鳥なくや雄島の明の明烏(同上・瑞巌寺)
杉を見て古く涼しき心かな(同上・中尊寺)
卯の花も兼房も見えぬ茂りかな(同上・高館)
風薫る星や義経勲功記(同上・平泉)
※ 東洋城が主宰した俳誌「渋柿」の「俳句の理念(モットー)」を、「松尾芭蕉の俳諧理念(わび・さび・しをり)を探究、『芭蕉直結・芭蕉に還れ』」を掲げて心境・境涯俳句の創作に努める」(「ウィキペディア」)とも、「芭蕉直結、写生を通して心境を詠む」(「俳人協会・「渋柿」の「俳誌のモットー」)とも、それらは、東洋城の「俳論」(「芭蕉の旅心」・「子規・芭蕉」・「俳諧根本義」・「俳諧至上」・「頭の無い恐竜」・「奥の細道夜話」・「芭蕉翁と」・「芭蕉の句について」等々)に基づいてのものなのであろう。
この前年の大正六年(一九一七)の、「渋柿」(二月号)は「漱石先生追悼号」として、その「終焉記」を書き、「漱石俳句輪講」が始められ、続いて、同年十二月号は、「漱石忌(十二月九日)記念号」と一年間に二回も追悼及び記念号を発刊すると、『漱石俳句集(東洋城編・岩波刊)』に没頭した。
明けて大正七年(一九一八)は、「『新奥の細道』より四十五句」・「『南部と津軽』より二十二句」・「『鹿島』十八句」・「『栗中山と大州』二十三句」・「『南北野分舟(松山・宇和島)』十七句」と、まさに、東洋城の「芭蕉の旅心」の、芭蕉俳諧追慕の吟行の連続であった。
(付記一)「漱石一周忌 三十七句」(大正六年「漱石一周忌」)
1 文の徳や冬嶺高く枯野広し(「漱石一周忌 三十七句」)
2 凩や天の一字の御心 (同上)
3 死悼めど御作読めば小春かな(同上)
4 凩や師の遺著犇(ひし)と書架の棚(同上)
5 小説とほ句との霜の一路かな(同上)
6 腹中に先生の書や冬籠(同上)
7 境涯に先生おはす冬籠(同上)
8 什麽(そも)先生死して生きざる寒夜かな(同上。「什麽(そも)」=「そもさん(作麽生)」の略。※正法眼蔵(1231‐53)仏性「この宗旨は作麽生なるべきぞ」。)
9 この忌修す初めての冬となりにけり(同上)
10 早稲田の夜急に時雨れぬ九日忌(同上)
11 凩の許樹さながらや漱石忌(同上)
12 師の御忌や二日隔てし白隠忌(同上)
13 九日のその夕暮や漱石忌(同上)
14 鶏頭の子規忌木枯の漱石忌(同上)
15 木枯の御墓も思ふ忌日かな(同上)
16 作中の誰れ彼れ参れ漱石忌(同上)
17 墓へまはる事も木枯や九日忌(同上)
18 吏となりて好める文や漱石忌(同上)
19 木枯やされども温泉の湧く力(同上。前書「漱石忌句会」。)
20 枯芭蕉も木賊(とくさ)も寒き庭となりぬ(同上。前書「早稲田南町」。)
21 ストーブに且火鉢ある書斎かな(同上)
22 枯蔦やベルも押さずに通りしか(同上)
23 或時は茶の間の炉にぞ挙(あが)りける(同上)
24 冬木して静かなるべき眠りかな(同上)
25 護国寺の屋根が見ゆるも寒さかな(同上)
26 菊活けて帰り去るあとの乞食かな(同上)
27 謡一番墓の下より秋静か(同上)
28 墓の時雨洛の春雨と通ふや否や(同上)
29 木立あれど紅葉あらざるお墓かな(同上)
30 こむる霧に独りぞあらん墓のそば(同上。前書「断腸」。)
31 芒枯れて何刈られたる根株かな(同上)
32 墓掃けば垣の外降る木の葉かな(同上)
33 御墓のうしろ風呂屋の小六月(同上)
34 その折の凩の音や耳に今(同上。前書「一年昨日」)
35 木枯や接心もゆる我が眼(同上。前書「逮夜句座三句」。)
36 木枯や浪のいづこに地の力((同上)
37 木枯や川の長さに足らぬ堤(同上) (『東洋城全句集(上巻)』)
(付記二) 「思ひ出るまゝ」寺田寅彦(大正六年二月「渋柿(夏目漱石追悼号)」・大正六年十二月「渋柿(漱石忌記念号)」)
「思ひ出るまゝ」寺田寅彦(大正六年二月「渋柿(夏目漱石追悼号)」)
講壇の隅にのせおくニッケルの袂(たまと)時計を貴しと見き
春寒き午前七時の課外講義オセロを読みしその頃の君
何もなき庭の垣根に朝顔の枯れたるままの坪井の邸(やしき)
帽を振り巾(きれ)振る人の中にたゞ黙して君は舷(ふなばた)に立ちし
家づとのカバン開けば一束の花ありぬ絹の白薔薇の花
行春の音楽会の帰るさに神田牛込そゞろあるきぬ
瀬戸物の瓶につめたる甘き酒青豆のスープ小鳥のロース
庭に咲く泰山木を指して此花君は如何に見ると云ひし
先生の湯浴果てるを待つひまに※スチユヂオの絵を幾度か見し(※Studio=仕事場)
或時は空間論に時間論生れぬ先の我を論じき
帽子着て前垂かけて小春日の縁の日向に初書きし君
美しき蔦の葉蔭の呼鈴の釦(ぼたん)を押すが嬉しかりしか
年毎に生ひ茂るまゝの木賊(とくさ)原茂りを愛(め)でし君は今亡し
此の憂(うれひ)誰に語らん語るべき一人の君を失ひし憂
(『寺田寅彦全集 文学篇 七巻・岩波書店』)
「思ひ出るまま」寺田寅彦(大正六年十二月「渋柿(漱石忌記念号)」)
金縁の老眼鏡をつくらせて初めてかけし其時の顔
マント着て黙りて歩く先生と肩をならべて江戸川端を
もみ上げの白髪抜けども拭きあへず老いぬと言ひし春の或夕
杉の香を籠めたる酒ぞ飲めと云ひて酔ひたる吾を笑ひし先生
先生と対(むか)ひてあれば腹立しき世とも思はず小春の日向
俳句とはかゝかるものぞと説かれしより天地開けて我が眼に新
(『寺田寅彦全集 文学篇 七巻・岩波書店』)
[寅彦=寅日子・四十一歳。数学物理学会において「原子構造概観」を特別講演する。四月、本郷区曙町に転居する。八月、酒井紳子と見合い結婚。]
骨を抱いて家を出づれば寒き朝(「渋柿」七年一月。六年十二月、東洋城宛書簡)
出迎ふる人亡くて門の冬の月(「日記」六年十二月二十五日)
今そこに居たかと思ふ火燵哉(同上)
亡き魂も出迎へよ門の冬の月(「渋柿」七年二月。前書「十二月二十五日帰京」)
※ これらの句は、大正六年(一九一七)十月十八日に亡くなった寛子夫人への追悼句であろう。行年三十一歳、十九歳の夏に結婚して円満な家庭を営み、二男一女を遺した。年内に、高知の寺田家の墓地に埋骨するため、十二月二十一日に東京を発ち、翌日の二十二日に高知港に着き、埋骨を済ませた。二十四日に高知を発ち、翌二十五日に帰京した。その時の一連の寅彦の句である。冒頭の句は、「東洋城宛書簡」の句で、「渋柿」(七年一月)に掲載された。
春風が吹いても石は石佛(「日記(一月二十三日)」。前書に「東洋城より端書きにて渋柿に前置付句の募集をする故選をせよとの事なり、柄になき故断る事とす」)
※ 大正五年(一九一六)十二月九日に、恩師・夏目漱石を失い、そして、それに続く、大正六(一九一七)十月十八日に、二男一女を遺して、寛子夫人を失うという、不運続きの寅彦への、東洋城の、気分転換の励ましの配慮を背後に託しているような、「渋柿」への「前置付句」(「連句」などの「前句付け=二句連句」)へのお誘いに対しての、寅彦の、その返答の句なのであろう。
この東洋城の「前置付句」のお誘いが、後の、大正十二年(一九二三)の、「東洋城・寅日子(寅彦)・蓬里雨(豊隆)」の「三吟連句」などに結実していいくのであろう。
[豊隆=蓬里雨・三十五歳。大正9年( 1920 )海軍大学校嘱託教授となる。大正10年 (1921 )芭蕉研究会に参加。]
※大正七年(1918)当時の豊隆は、『漱石全集』に取り組んでいて、「東洋城・寅日子・蓬里雨」の三吟歌仙とかは、大正十五年(1926)の頃が初出で、この頃は、「俳句・俳諧(連句)」には食指は伸ばしていなかったように思われる。大正十年(1921)の「芭蕉研究会」に参加は、東洋城の「渋柿」などとの「芭蕉研究会」ではなく、下記のアドレスのものなどによると、「太田水穂(歌誌「潮音」主宰)・幸田露伴・沼波瓊音・安倍能成・阿部次郎・小宮豊隆・和辻哲郎」らによる研究会のようである。
https://jyunku.hatenablog.com/entry/20100925/p1
「「芭蕉研究会」は田端の太田水穂(本名・貞一)宅で行われ、当初の会員は、阿部(次郎)、太田のほか、沼波瓊音、安倍能成、幸田露伴で、大正10年に小宮豊隆や和辻哲郎が加わった。」
この、阿部次郎・小宮豊隆らの「芭蕉研究会」の参加は、「大正15年( 1926) 芭蕉俳諧研究会を始める」と、「東北帝国大学」の「山田孝雄、村岡典嗣、岡崎義恵、太田正雄(木下杢太郎)」らの参加を得て、形を変えて継続されていくことになる。
https://www.library.tohoku.ac.jp/collection/collection/introduce.html
(追記一) 「青春時代を語る / 東洋城 ; 洋一/p54~73」)」(「俳誌『渋柿(昭和四十年(一九六五)の一月号) 』 (「松根東洋城追悼号」)」所収
(再掲)
https://yahan.blog.ss-blog.jp/2023-10-10

「青春時代を語る / 東洋城 ; 洋一/p54~73」時の「東洋城と吉田洋一」(左「東洋城」、右「吉田洋一」)
https://dl.ndl.go.jp/pid/6071686/1/41
「俳誌『渋柿(昭和四十年(一九六五)の一月号)』 (「松根東洋城追悼号」)」は、毀誉褒貶の風聞の中で、その全貌が未だに謎にみちたままの、明治・大正・昭和の三代にわたって、俳諧一筋の、東洋城の言葉でするならば、「芭蕉の誠の俳諧」一筋を貫いた生涯は、この「松根東洋城追悼号」は、その周辺の確かな道標を示すものであろう。
そして、それは、東洋城が没して十年後に刊行された、生前の東洋城の謦咳に接している俳句総合誌の「俳句研究」に携わった俳人の「石川桂郎」著の『俳人風狂列伝』(「読売文学賞」受賞)の、東洋城をめぐるスキャンダル(「白蓮事件」にも連動する「男爵夫人」あるいは「渋柿」からの「あら野」離脱に関連する「同人夫人」)とかの「東洋城の虚像(?)」に対する、その「東洋城の実像(?)」を語るものとして、この「青春時代を語る / 東洋城 ; 洋一/p54~73」や「兄東洋城と私 / 松根新八郎/p74~90」などは、いわば、「石川桂郎」著の『俳人風狂列伝』の「東洋城像(虚像?)」を覆すものの、すなわち、「東洋城(実像?)」を示しているものの、その一端を物語っているように思われる。
そして、これらことは、「虚子と東洋城」との、「ホトトギス(虚子)・国民俳壇(虚子・徳富蘇峰)・渋柿創刊(東洋城)・新傾向俳句の台頭(碧悟桐・井泉水・乙字・一碧楼など)との、混沌した中にあっての、「高浜虚子と松根東洋城」との、その「実像(?)と虚像(?)」との、これまた、その一端を物語る、一つの道標となり得るものであろう。
これらのことに関して、「虚子と東洋城」とが、「新傾向俳句(自由律俳句)」(碧悟桐・井泉水・乙字・一碧楼など)に対して、「伝統俳句(定型律俳句)」の牙城として、「ホトトギス」(虚子主宰)と「渋柿(東洋城主宰)」の二誌が、未曾有の、太平洋戦争前後の統制下にあって、その命脈を保ちつづけたということになる。
上記の写真(「東洋城と吉田洋一」)は、吉田洋一の軽井沢の山荘のもので、東洋城と洋一との接点は、寺田寅彦門下の北海道大学理学部教授の「中谷宇吉郎」を介してのもののようである(『渋柿の木の下で(中村英利子著)』)。
晩年の東洋城の避暑先は、この吉田洋一夫妻の山荘で過ごすのが常のようで、軽井沢は、寺田寅彦・小宮豊隆・中谷宇吉郎・吉田洋一らの忘れ得ざる邂逅の出会いの避暑地でもあったのである。
ここで、「明治四十二年(一九〇九)」の冒頭に戻って、その東洋城年譜の、[東洋城、三十二歳。東洋城の下宿「望遠館」(九段中坂)において、毎週一会の句会が催された。択ばれた者のみが出席できる会で、暮雨(万太郎)、蛇笏、零余子、松浜、喜舟などが、そのメンバーである。三月、東洋城選「新春夏秋冬」夏の部(「序」は夏目漱石)、十月「同・秋の部」を俳書堂より刊行した。]は、「東洋城・虚子、そして、漱石」との三者関係の、その最期の「華やぎ」のような、東洋城の「タンタヂイル(タンタジールの死)十八句」、そして、後の虚子の「大正初期に初めて書いた能『鐵門(てつもん)』(「タンタジールの死」に典拠する)との、当時の最晩年の漱石の膝下にあっての、「虚子と東洋城」との切磋琢磨の時代でもあった。
漱石は、この年に、東洋城選「新春夏秋冬」夏の部の、その刊行に当たって、その「序」を草している。
この東洋城選「新春夏秋冬」夏の部(「漱石・序」)も、下記のアドレスで閲覧することが出来る。
https://kindai.nijl.ac.jp/kindais/HKDT-01067
(追記二) 「新春夏秋冬 夏の部/俳諧叢書第二十二篇/松根東洋城 編」の「夏目漱石(序)」

「新春夏秋冬 夏の部/俳諧叢書第二十二篇/松根東洋城 編」/東洋城撰/明治42.3.5/ 1909.35/函館市中央図書館/
https://kindai.nijl.ac.jp/kindais/HKDT-01067
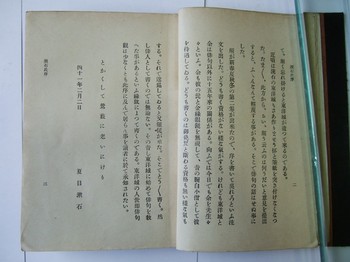
「新春夏秋冬 夏の部/俳諧叢書第二十二篇/松根東洋城 編」所収「夏目漱石『序』(明治四十二年二月二日)」
https://kindai.nijl.ac.jp/kindais/HKDT-01067
「夏目漱石『序』(明治四十二年二月二日)」全文
[ 東洋城は俳句本位の男である。あらゆる文字を十七字にしたがる許でない、人世則俳句観を抱いて道途に呻吟してゐる。時々来ては作りませうと催促する。題を貸して遣つて見ると遅吟である。君の句には嫌味がある杯と云ふと、中々承知しない。あなたのは十八世紀だと云つて、大変新しがつてゐる。
さう説明されて見ると、左様んな所もあるやうに思はる。実の所余は近来俳句には全く興味を失つて、其後の動静を頓と弁へない老骨である。運座は無論の事出ない。斯様にして追々十七字と縁が遠くなつて、漸く忘れ掛けると東洋城が遣つて来るのである。
近頃の流石の東洋城もさあ作りませう杯と筆紙を突き付けなくなつた。たまたま、此方から、おい、斯う云ふのは何うだいと意見を提出すると、ふゝんなんて軽蔑する事がある。そこで俳句の話はせぬ事にした。
所が新春夏秋冬の第二巻が出来たので、序を書いて呉れろといふ注文を出した。どうも書く資格がない様な気がする。けれども東洋城と余は俳句以外に十五年来の関係がある。向こふでは今日でも余を先生々々といふ。余も彼の髭と金縁眼鏡を無視して、昔の腕白小僧として彼を待遇してゐる。どうも書くのは御免だと断わる資格も無い様な気もする。それで逡巡してゐると又催促が来た。そこでとうとう書く。然し俳人として書くのでは無論ない。その昔し、東洋城に始めて俳句を教へた事があるといふ縁故によつて書くのである。東洋城の人生則俳句観は少なくとも此序に及んで居らん事を読者に於て承知されたい。
とかくして鶯藪に老いにけり
四十一年二月二日 夏目漱石 ]
(『俳句講座八 現代作家論』所収「松根東洋城(野村喜舟)」)
[東洋城・四十一歳。奥州に遊び、『新奥の細道』連載。]
松島やそれより先の風薫れ(『新奥の細道』より四十五句の冒頭の句)
昔涼し芭蕉も子規も詣で居る(同上の三句目)
時鳥なくや雄島の明の明烏(同上・瑞巌寺)
杉を見て古く涼しき心かな(同上・中尊寺)
卯の花も兼房も見えぬ茂りかな(同上・高館)
風薫る星や義経勲功記(同上・平泉)
※ 東洋城が主宰した俳誌「渋柿」の「俳句の理念(モットー)」を、「松尾芭蕉の俳諧理念(わび・さび・しをり)を探究、『芭蕉直結・芭蕉に還れ』」を掲げて心境・境涯俳句の創作に努める」(「ウィキペディア」)とも、「芭蕉直結、写生を通して心境を詠む」(「俳人協会・「渋柿」の「俳誌のモットー」)とも、それらは、東洋城の「俳論」(「芭蕉の旅心」・「子規・芭蕉」・「俳諧根本義」・「俳諧至上」・「頭の無い恐竜」・「奥の細道夜話」・「芭蕉翁と」・「芭蕉の句について」等々)に基づいてのものなのであろう。
この前年の大正六年(一九一七)の、「渋柿」(二月号)は「漱石先生追悼号」として、その「終焉記」を書き、「漱石俳句輪講」が始められ、続いて、同年十二月号は、「漱石忌(十二月九日)記念号」と一年間に二回も追悼及び記念号を発刊すると、『漱石俳句集(東洋城編・岩波刊)』に没頭した。
明けて大正七年(一九一八)は、「『新奥の細道』より四十五句」・「『南部と津軽』より二十二句」・「『鹿島』十八句」・「『栗中山と大州』二十三句」・「『南北野分舟(松山・宇和島)』十七句」と、まさに、東洋城の「芭蕉の旅心」の、芭蕉俳諧追慕の吟行の連続であった。
(付記一)「漱石一周忌 三十七句」(大正六年「漱石一周忌」)
1 文の徳や冬嶺高く枯野広し(「漱石一周忌 三十七句」)
2 凩や天の一字の御心 (同上)
3 死悼めど御作読めば小春かな(同上)
4 凩や師の遺著犇(ひし)と書架の棚(同上)
5 小説とほ句との霜の一路かな(同上)
6 腹中に先生の書や冬籠(同上)
7 境涯に先生おはす冬籠(同上)
8 什麽(そも)先生死して生きざる寒夜かな(同上。「什麽(そも)」=「そもさん(作麽生)」の略。※正法眼蔵(1231‐53)仏性「この宗旨は作麽生なるべきぞ」。)
9 この忌修す初めての冬となりにけり(同上)
10 早稲田の夜急に時雨れぬ九日忌(同上)
11 凩の許樹さながらや漱石忌(同上)
12 師の御忌や二日隔てし白隠忌(同上)
13 九日のその夕暮や漱石忌(同上)
14 鶏頭の子規忌木枯の漱石忌(同上)
15 木枯の御墓も思ふ忌日かな(同上)
16 作中の誰れ彼れ参れ漱石忌(同上)
17 墓へまはる事も木枯や九日忌(同上)
18 吏となりて好める文や漱石忌(同上)
19 木枯やされども温泉の湧く力(同上。前書「漱石忌句会」。)
20 枯芭蕉も木賊(とくさ)も寒き庭となりぬ(同上。前書「早稲田南町」。)
21 ストーブに且火鉢ある書斎かな(同上)
22 枯蔦やベルも押さずに通りしか(同上)
23 或時は茶の間の炉にぞ挙(あが)りける(同上)
24 冬木して静かなるべき眠りかな(同上)
25 護国寺の屋根が見ゆるも寒さかな(同上)
26 菊活けて帰り去るあとの乞食かな(同上)
27 謡一番墓の下より秋静か(同上)
28 墓の時雨洛の春雨と通ふや否や(同上)
29 木立あれど紅葉あらざるお墓かな(同上)
30 こむる霧に独りぞあらん墓のそば(同上。前書「断腸」。)
31 芒枯れて何刈られたる根株かな(同上)
32 墓掃けば垣の外降る木の葉かな(同上)
33 御墓のうしろ風呂屋の小六月(同上)
34 その折の凩の音や耳に今(同上。前書「一年昨日」)
35 木枯や接心もゆる我が眼(同上。前書「逮夜句座三句」。)
36 木枯や浪のいづこに地の力((同上)
37 木枯や川の長さに足らぬ堤(同上) (『東洋城全句集(上巻)』)
(付記二) 「思ひ出るまゝ」寺田寅彦(大正六年二月「渋柿(夏目漱石追悼号)」・大正六年十二月「渋柿(漱石忌記念号)」)
「思ひ出るまゝ」寺田寅彦(大正六年二月「渋柿(夏目漱石追悼号)」)
講壇の隅にのせおくニッケルの袂(たまと)時計を貴しと見き
春寒き午前七時の課外講義オセロを読みしその頃の君
何もなき庭の垣根に朝顔の枯れたるままの坪井の邸(やしき)
帽を振り巾(きれ)振る人の中にたゞ黙して君は舷(ふなばた)に立ちし
家づとのカバン開けば一束の花ありぬ絹の白薔薇の花
行春の音楽会の帰るさに神田牛込そゞろあるきぬ
瀬戸物の瓶につめたる甘き酒青豆のスープ小鳥のロース
庭に咲く泰山木を指して此花君は如何に見ると云ひし
先生の湯浴果てるを待つひまに※スチユヂオの絵を幾度か見し(※Studio=仕事場)
或時は空間論に時間論生れぬ先の我を論じき
帽子着て前垂かけて小春日の縁の日向に初書きし君
美しき蔦の葉蔭の呼鈴の釦(ぼたん)を押すが嬉しかりしか
年毎に生ひ茂るまゝの木賊(とくさ)原茂りを愛(め)でし君は今亡し
此の憂(うれひ)誰に語らん語るべき一人の君を失ひし憂
(『寺田寅彦全集 文学篇 七巻・岩波書店』)
「思ひ出るまま」寺田寅彦(大正六年十二月「渋柿(漱石忌記念号)」)
金縁の老眼鏡をつくらせて初めてかけし其時の顔
マント着て黙りて歩く先生と肩をならべて江戸川端を
もみ上げの白髪抜けども拭きあへず老いぬと言ひし春の或夕
杉の香を籠めたる酒ぞ飲めと云ひて酔ひたる吾を笑ひし先生
先生と対(むか)ひてあれば腹立しき世とも思はず小春の日向
俳句とはかゝかるものぞと説かれしより天地開けて我が眼に新
(『寺田寅彦全集 文学篇 七巻・岩波書店』)
[寅彦=寅日子・四十一歳。数学物理学会において「原子構造概観」を特別講演する。四月、本郷区曙町に転居する。八月、酒井紳子と見合い結婚。]
骨を抱いて家を出づれば寒き朝(「渋柿」七年一月。六年十二月、東洋城宛書簡)
出迎ふる人亡くて門の冬の月(「日記」六年十二月二十五日)
今そこに居たかと思ふ火燵哉(同上)
亡き魂も出迎へよ門の冬の月(「渋柿」七年二月。前書「十二月二十五日帰京」)
※ これらの句は、大正六年(一九一七)十月十八日に亡くなった寛子夫人への追悼句であろう。行年三十一歳、十九歳の夏に結婚して円満な家庭を営み、二男一女を遺した。年内に、高知の寺田家の墓地に埋骨するため、十二月二十一日に東京を発ち、翌日の二十二日に高知港に着き、埋骨を済ませた。二十四日に高知を発ち、翌二十五日に帰京した。その時の一連の寅彦の句である。冒頭の句は、「東洋城宛書簡」の句で、「渋柿」(七年一月)に掲載された。
春風が吹いても石は石佛(「日記(一月二十三日)」。前書に「東洋城より端書きにて渋柿に前置付句の募集をする故選をせよとの事なり、柄になき故断る事とす」)
※ 大正五年(一九一六)十二月九日に、恩師・夏目漱石を失い、そして、それに続く、大正六(一九一七)十月十八日に、二男一女を遺して、寛子夫人を失うという、不運続きの寅彦への、東洋城の、気分転換の励ましの配慮を背後に託しているような、「渋柿」への「前置付句」(「連句」などの「前句付け=二句連句」)へのお誘いに対しての、寅彦の、その返答の句なのであろう。
この東洋城の「前置付句」のお誘いが、後の、大正十二年(一九二三)の、「東洋城・寅日子(寅彦)・蓬里雨(豊隆)」の「三吟連句」などに結実していいくのであろう。
[豊隆=蓬里雨・三十五歳。大正9年( 1920 )海軍大学校嘱託教授となる。大正10年 (1921 )芭蕉研究会に参加。]
※大正七年(1918)当時の豊隆は、『漱石全集』に取り組んでいて、「東洋城・寅日子・蓬里雨」の三吟歌仙とかは、大正十五年(1926)の頃が初出で、この頃は、「俳句・俳諧(連句)」には食指は伸ばしていなかったように思われる。大正十年(1921)の「芭蕉研究会」に参加は、東洋城の「渋柿」などとの「芭蕉研究会」ではなく、下記のアドレスのものなどによると、「太田水穂(歌誌「潮音」主宰)・幸田露伴・沼波瓊音・安倍能成・阿部次郎・小宮豊隆・和辻哲郎」らによる研究会のようである。
https://jyunku.hatenablog.com/entry/20100925/p1
「「芭蕉研究会」は田端の太田水穂(本名・貞一)宅で行われ、当初の会員は、阿部(次郎)、太田のほか、沼波瓊音、安倍能成、幸田露伴で、大正10年に小宮豊隆や和辻哲郎が加わった。」
この、阿部次郎・小宮豊隆らの「芭蕉研究会」の参加は、「大正15年( 1926) 芭蕉俳諧研究会を始める」と、「東北帝国大学」の「山田孝雄、村岡典嗣、岡崎義恵、太田正雄(木下杢太郎)」らの参加を得て、形を変えて継続されていくことになる。
https://www.library.tohoku.ac.jp/collection/collection/introduce.html
(追記一) 「青春時代を語る / 東洋城 ; 洋一/p54~73」)」(「俳誌『渋柿(昭和四十年(一九六五)の一月号) 』 (「松根東洋城追悼号」)」所収
(再掲)
https://yahan.blog.ss-blog.jp/2023-10-10

「青春時代を語る / 東洋城 ; 洋一/p54~73」時の「東洋城と吉田洋一」(左「東洋城」、右「吉田洋一」)
https://dl.ndl.go.jp/pid/6071686/1/41
「俳誌『渋柿(昭和四十年(一九六五)の一月号)』 (「松根東洋城追悼号」)」は、毀誉褒貶の風聞の中で、その全貌が未だに謎にみちたままの、明治・大正・昭和の三代にわたって、俳諧一筋の、東洋城の言葉でするならば、「芭蕉の誠の俳諧」一筋を貫いた生涯は、この「松根東洋城追悼号」は、その周辺の確かな道標を示すものであろう。
そして、それは、東洋城が没して十年後に刊行された、生前の東洋城の謦咳に接している俳句総合誌の「俳句研究」に携わった俳人の「石川桂郎」著の『俳人風狂列伝』(「読売文学賞」受賞)の、東洋城をめぐるスキャンダル(「白蓮事件」にも連動する「男爵夫人」あるいは「渋柿」からの「あら野」離脱に関連する「同人夫人」)とかの「東洋城の虚像(?)」に対する、その「東洋城の実像(?)」を語るものとして、この「青春時代を語る / 東洋城 ; 洋一/p54~73」や「兄東洋城と私 / 松根新八郎/p74~90」などは、いわば、「石川桂郎」著の『俳人風狂列伝』の「東洋城像(虚像?)」を覆すものの、すなわち、「東洋城(実像?)」を示しているものの、その一端を物語っているように思われる。
そして、これらことは、「虚子と東洋城」との、「ホトトギス(虚子)・国民俳壇(虚子・徳富蘇峰)・渋柿創刊(東洋城)・新傾向俳句の台頭(碧悟桐・井泉水・乙字・一碧楼など)との、混沌した中にあっての、「高浜虚子と松根東洋城」との、その「実像(?)と虚像(?)」との、これまた、その一端を物語る、一つの道標となり得るものであろう。
これらのことに関して、「虚子と東洋城」とが、「新傾向俳句(自由律俳句)」(碧悟桐・井泉水・乙字・一碧楼など)に対して、「伝統俳句(定型律俳句)」の牙城として、「ホトトギス」(虚子主宰)と「渋柿(東洋城主宰)」の二誌が、未曾有の、太平洋戦争前後の統制下にあって、その命脈を保ちつづけたということになる。
上記の写真(「東洋城と吉田洋一」)は、吉田洋一の軽井沢の山荘のもので、東洋城と洋一との接点は、寺田寅彦門下の北海道大学理学部教授の「中谷宇吉郎」を介してのもののようである(『渋柿の木の下で(中村英利子著)』)。
晩年の東洋城の避暑先は、この吉田洋一夫妻の山荘で過ごすのが常のようで、軽井沢は、寺田寅彦・小宮豊隆・中谷宇吉郎・吉田洋一らの忘れ得ざる邂逅の出会いの避暑地でもあったのである。
ここで、「明治四十二年(一九〇九)」の冒頭に戻って、その東洋城年譜の、[東洋城、三十二歳。東洋城の下宿「望遠館」(九段中坂)において、毎週一会の句会が催された。択ばれた者のみが出席できる会で、暮雨(万太郎)、蛇笏、零余子、松浜、喜舟などが、そのメンバーである。三月、東洋城選「新春夏秋冬」夏の部(「序」は夏目漱石)、十月「同・秋の部」を俳書堂より刊行した。]は、「東洋城・虚子、そして、漱石」との三者関係の、その最期の「華やぎ」のような、東洋城の「タンタヂイル(タンタジールの死)十八句」、そして、後の虚子の「大正初期に初めて書いた能『鐵門(てつもん)』(「タンタジールの死」に典拠する)との、当時の最晩年の漱石の膝下にあっての、「虚子と東洋城」との切磋琢磨の時代でもあった。
漱石は、この年に、東洋城選「新春夏秋冬」夏の部の、その刊行に当たって、その「序」を草している。
この東洋城選「新春夏秋冬」夏の部(「漱石・序」)も、下記のアドレスで閲覧することが出来る。
https://kindai.nijl.ac.jp/kindais/HKDT-01067
(追記二) 「新春夏秋冬 夏の部/俳諧叢書第二十二篇/松根東洋城 編」の「夏目漱石(序)」

「新春夏秋冬 夏の部/俳諧叢書第二十二篇/松根東洋城 編」/東洋城撰/明治42.3.5/ 1909.35/函館市中央図書館/
https://kindai.nijl.ac.jp/kindais/HKDT-01067
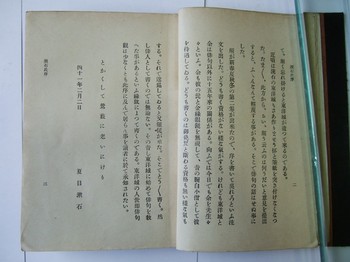
「新春夏秋冬 夏の部/俳諧叢書第二十二篇/松根東洋城 編」所収「夏目漱石『序』(明治四十二年二月二日)」
https://kindai.nijl.ac.jp/kindais/HKDT-01067
「夏目漱石『序』(明治四十二年二月二日)」全文
[ 東洋城は俳句本位の男である。あらゆる文字を十七字にしたがる許でない、人世則俳句観を抱いて道途に呻吟してゐる。時々来ては作りませうと催促する。題を貸して遣つて見ると遅吟である。君の句には嫌味がある杯と云ふと、中々承知しない。あなたのは十八世紀だと云つて、大変新しがつてゐる。
さう説明されて見ると、左様んな所もあるやうに思はる。実の所余は近来俳句には全く興味を失つて、其後の動静を頓と弁へない老骨である。運座は無論の事出ない。斯様にして追々十七字と縁が遠くなつて、漸く忘れ掛けると東洋城が遣つて来るのである。
近頃の流石の東洋城もさあ作りませう杯と筆紙を突き付けなくなつた。たまたま、此方から、おい、斯う云ふのは何うだいと意見を提出すると、ふゝんなんて軽蔑する事がある。そこで俳句の話はせぬ事にした。
所が新春夏秋冬の第二巻が出来たので、序を書いて呉れろといふ注文を出した。どうも書く資格がない様な気がする。けれども東洋城と余は俳句以外に十五年来の関係がある。向こふでは今日でも余を先生々々といふ。余も彼の髭と金縁眼鏡を無視して、昔の腕白小僧として彼を待遇してゐる。どうも書くのは御免だと断わる資格も無い様な気もする。それで逡巡してゐると又催促が来た。そこでとうとう書く。然し俳人として書くのでは無論ない。その昔し、東洋城に始めて俳句を教へた事があるといふ縁故によつて書くのである。東洋城の人生則俳句観は少なくとも此序に及んで居らん事を読者に於て承知されたい。
とかくして鶯藪に老いにけり
四十一年二月二日 夏目漱石 ]
(『俳句講座八 現代作家論』所収「松根東洋城(野村喜舟)」)



