「漱石・東洋城・寅彦」(子規没後~漱石没まで)俳句管見(その七) [漱石・東洋城・寅彦]
その七「明治四十二年(一九〇九)」
[漱石・四十二歳]
[明治42(1909) 1月~3月、「永日小品」、6月~10月、「それから」、9月~10月、中村是公と満州・朝鮮旅行、10月~12月、「満韓ところどころ」、11月、朝日文芸欄創設。 ]
2096 空に消ゆる鐸のひゞきや春の塔(前書「空間を研究せる天然居士の肖像に題す」。)
[天然居士は、漱石の学生時代の友人米山保三郎の号。この句はその兄である米山熊次郎へ送った句。]
(再掲) 「漱石の親友 天然居士・米山保三郎」周辺
https://rendezvou.exblog.jp/7067220/
[学生時代の夏目金之助に作家になることを勧め漱石が彼の言葉に強く動かされた人物・米山保三郎のことはよく知られています。ただ、これまで研究者の中で誤解があり、漱石の語句の解釈に問題があるまま流布されてきたのが現状です。
「天然居士は空間を研究し、論語を読み、焼芋を食い、鼻汁を垂らす人である」
焼き芋と鼻汁を垂らす、これは禅の歴史に実在した中国の禅僧・懶さん(王ヘンに賛)和尚の故事から来る引用なのでした。漱石は畏敬する親友の米山保三郎へ深い愛情と禅に生きる彼を讃える意味で書いたものでしょう。しかし、世間一般ではなかなか通用しない事も充分知っていました。そうであるからこそ、『猫』のなかで次のように書いているのです。
「天然居士は空間を研究し、論語を読み、焼芋を食い、鼻汁を垂らす人である」
苦沙弥先生、一気呵成にこう書き流し、声を出してこれを読み、「ハハハ面白い」と笑うが、「うん。鼻汁を垂らすはさすがに酷だ、焼き芋も蛇足だ」と線を引き。結局「天然居士は空間を研究し論語を読む人である」だけにしたころで、これではあまりに簡単すぎると全部ボツにして、原稿用紙の裏に「空間に生れ、空間を究め、空間に死す。空たり間たり天然居士、噫」
実際、漱石はこの米山の兄、熊次郎から実弟の写真へ揮毫を懇望されて、漱石は俳句を書いています。その俳句とは、
空に消ゆる鐸のひびきや春の塔 という追悼の一句です。親友の死を悼む漱石の心情があふるるばかり、見事な名句と思います。写真は400X300mm、単身像の右側にこの句があり、左にこう記されています。
空間を研究する天然居士の肖像に題す 己酉 四月 漱石
己酉,となれば、1909年、明治四十二年です。漱石が朝日新聞社に入社して2年目の四月に詠んだものと明確に判るのが嬉しいところです。また、米山が鼻水を垂らすの表現がとかく世俗的に解釈され、漱石がいかにしてこの語句を入れたかということは研究者の間でないがしろにされて来ました。しかし、漱石がただ、ユーモラスにこんな語句を入れるはずはないのです。洟を垂らそうが自分は三昧になっているのだという仏道の修行による逸話なのです。
出典もありますから、その引用もしておきましょう。『碧巖録』第三十四則より。
「懶瓚和尚。隱居衡山石室中。唐德宗聞其名。遣使召之。使者至其室宣言。天子有詔。尊者當起謝恩。瓚方撥牛糞火。尋煨芋而食。寒涕垂頤未甞答。使者笑曰。且勸尊者拭涕。瓚曰。我豈有工夫為俗人拭涕耶。竟不起。使回奏。德宗甚欽嘆之。」
(懶瓚和尚、衡山石室の中に隱居す。唐の德、宗其の名を聞いて、使を遣して之を召す。使者、其の室に至つて宣言す。天子詔有り、尊者まさに起つて恩を謝すべし。瓚、まさに牛糞の火を撥つて、煨芋を尋ねて食す。寒涕、頤に垂れて未だ甞て答えず。使者笑つて曰く、且らく勸む、尊者、涕を拭え。瓚曰く、我れ豈に工夫の俗人の為に涕を拭くこと有らん耶といつて、竟に起たず。使、回つて奏す。德宗、甚だ之を欽嘆す。) (以下略) ]
(追記)

漱石(左)と米山保三郎(明治25年)
https://www.asahi.com/articles/ASJ615FM7J61UCVL00W.html
https://yahan.blog.ss-blog.jp/2023-09-08
[東洋城、三十二歳。東洋城の下宿「望遠館」(九段中坂)において、毎週一会の句会が催された。択ばれた者のみが出席できる会で、暮雨(万太郎)、蛇笏、零余子、松浜、喜舟などが、そのメンバーである。三月、東洋城選「新春夏秋冬」夏の部(「序」は夏目漱石)、十月「同・秋の部」を俳書堂より刊行した。]
春月や暗き灯持つ峰の城(「タンタヂイル(タンタジールの死)十八句」第一幕)
雁帰る女王の心疑へば(同上)
暗き灯を貝に吊りけり春四人(「同上」第二幕)
すみれ草しほれ草とは見えにけり(同上)
春の夜の廓冷かに柱かな(「同上」第四幕)
烏賊共は墨に隠れて来りけり(同上)
春の燭鉄の扉に凍りけり(「同上」第五幕)
おそろしや椿の落つる音もなく(同上)

「タンタヂールの死 (泰西傑作叢書 ; 2)」書誌情報/著者モゥリス・メーテルリンク 作, 小島春潮 訳/出版者 集栄館/出版年月日 大正12)/(「国立国会図書館デジタルコレクション」)
https://dl.ndl.go.jp/pid/915275/1/2
[寅彦・三十二歳。一月、東京帝国大学理科大学助教授となる。二月、次男の正二誕生。三月、宇宙物理学研究のためヨーロッパへ留学。ベルリン大学に学ぶ。四月、従七位に叙せられる。]→(『寺田寅彦全集/文学篇/七巻』には収載句は無い。)
(参考その一) 「タンタジールの死」と《ギルちゃん》(「宮沢賢治の世界」)周辺
https://ihatov.cc/blog/archives/2016/01/post_841.htm
(参考その二) 「西洋文明と融合、新作の糧に 高浜虚子の能、戦後初の復曲上演」周辺

「鐵門」の復曲上演に向け、所作の検討をする観世流能楽師の青木道喜さん(中)ら(京都市左京区の京都観世会館)
https://www.nikkei.com/news/print-article/?ng=DGXLASIH04H07_V00C16A1AA2P00
[(抜粋)
俳人の高浜虚子(1874~1959年)が大正初期に初めて書いた能「鐵門(てつもん)」が6月、京都観世会館(京都市)で復曲上演される。初演から100年に合わせた試みで、戦後の上演は初。西洋戯曲を翻案した新作能の嚆矢(こうし)とされるが、長く上演機会がなかった。今後の能の制作や役作りに生かす狙いだ。(中略)
「鐵門」はベルギーの劇作家・詩人モーリス・メーテルリンク(1862~1949年)が人形劇向けに書いた戯曲「タンタジールの死」に典拠する。死への恐怖と運命を、人間には開けることのできない鉄の門に象徴させた。
虚子は舞台を西洋から日本に移し替え、城に住む姫と姫に仕える老僕らの物語にした。長野県の善光寺に詣でた僧が、門前の者に案内されて暗穴の道に赴くところから始まる。そこに、老僕の霊が姫の霊と共に現れる。老僕はかつて城に忍び入った死の使いの悪尼(あくに)に姫を連れ去られ、そびえ立つ鉄の門に阻(はば)まれて姫を救えなかった経緯などを語る。
(後略) ]
(参考その三) 「青春時代を語る / 東洋城 ; 洋一/p54~73」)」(「俳誌『渋柿(昭和四十年(一九六五)の一月号) 』 (「松根東洋城追悼号」)」所収

「青春時代を語る / 東洋城 ; 洋一/p54~73」時の「東洋城と吉田洋一」(左「東洋城」、右「吉田洋一」)
https://dl.ndl.go.jp/pid/6071686/1/41
「俳誌『渋柿(昭和四十年(一九六五)の一月号)』 (「松根東洋城追悼号」)」は、毀誉褒貶の風聞の中で、その全貌が未だに謎にみちたままの、明治・大正・昭和の三代にわたって、俳諧一筋の、東洋城の言葉でするならば、「芭蕉の誠の俳諧」一筋を貫いた生涯は、この「松根東洋城追悼号」は、その周辺の確かな道標を示すものであろう。
そして、それは、東洋城が没して十年後に刊行された、生前の東洋城の謦咳に接している俳句総合誌の「俳句研究」に携わった俳人の「石川桂郎」著の『俳人風狂列伝』(「読売文学賞」受賞)の、東洋城をめぐるスキャンダル(「白蓮事件」にも連動する「男爵夫人」あるいは「渋柿」からの「あら野」離脱に関連する「同人夫人」)とかの「東洋城の虚像(?)」に対する、その「東洋城の実像(?)」を語るものとして、この「青春時代を語る / 東洋城 ; 洋一/p54~73」や「兄東洋城と私 / 松根新八郎/p74~90」などは、いわば、「石川桂郎」著の『俳人風狂列伝』の「東洋城像(虚像?)」を覆すものの、すなわち、「東洋城(実像?)」を示しているものの、その一端を物語っているように思われる。
そして、これらことは、「虚子と東洋城」との、「ホトトギス(虚子)・国民俳壇(虚子・徳富蘇峰)・渋柿創刊(東洋城)・新傾向俳句の台頭(碧悟桐・井泉水・乙字・一碧楼など)との、混沌した中にあっての、「高浜虚子と松根東洋城」との、その「実像(?)と虚像(?)」との、これまた、その一端を物語る、一つの道標となり得るものであろう。
これらのことに関して、「虚子と東洋城」とが、「新傾向俳句(自由律俳句)」(碧悟桐・井泉水・乙字・一碧楼など)に対して、「伝統俳句(定型律俳句)」の牙城として、「ホトトギス」(虚子主宰)と「渋柿(東洋城主宰)」の二誌が、未曾有の、太平洋戦争前後の統制下にあって、その命脈を保ちつづけたということになる。
上記の写真(「東洋城と吉田洋一」)は、吉田洋一の軽井沢の山荘のもので、東洋城と洋一との接点は、寺田寅彦門下の北海道大学理学部教授の「中谷宇吉郎」を介してのもののようである(『渋柿の木の下で(中村英利子著)』)。
晩年の東洋城の避暑先は、この吉田洋一夫妻の山荘で過ごすのが常のようで、軽井沢は、寺田寅彦・小宮豊隆・中谷宇吉郎・吉田洋一らの忘れ得ざる邂逅の出会いの避暑地でもあったのである。
ここで、「明治四十二年(一九〇九)」の冒頭に戻って、その東洋城年譜の、[東洋城、三十二歳。東洋城の下宿「望遠館」(九段中坂)において、毎週一会の句会が催された。択ばれた者のみが出席できる会で、暮雨(万太郎)、蛇笏、零余子、松浜、喜舟などが、そのメンバーである。三月、東洋城選「新春夏秋冬」夏の部(「序」は夏目漱石)、十月「同・秋の部」を俳書堂より刊行した。]は、「東洋城・虚子、そして、漱石」との三者関係の、その最期の「華やぎ」のような、東洋城の「タンタヂイル(タンタジールの死)十八句」、そして、後の虚子の「大正初期に初めて書いた能『鐵門(てつもん)』(「タンタジールの死」に典拠する)との、当時の最晩年の漱石の膝下にあっての、「虚子と東洋城」との切磋琢磨の時代でもあった。
漱石は、この年に、東洋城選「新春夏秋冬」夏の部の、その刊行に当たって、その「序」を草している。
この東洋城選「新春夏秋冬」夏の部(「漱石・序」)も、下記のアドレスで閲覧することが出来る。
https://kindai.nijl.ac.jp/kindais/HKDT-01067

「新春夏秋冬 夏の部/俳諧叢書第二十二篇/松根東洋城 編」/東洋城撰/明治42.3.5/ 1909.35/函館市中央図書館/
https://kindai.nijl.ac.jp/kindais/HKDT-01067
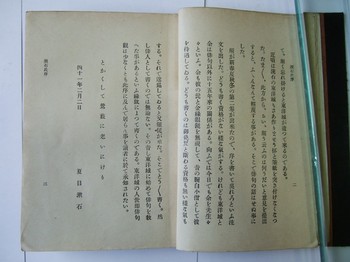
「新春夏秋冬 夏の部/俳諧叢書第二十二篇/松根東洋城 編」所収「夏目漱石『序』(明治四十二年二月二日)」
https://kindai.nijl.ac.jp/kindais/HKDT-01067
[漱石・四十二歳]
[明治42(1909) 1月~3月、「永日小品」、6月~10月、「それから」、9月~10月、中村是公と満州・朝鮮旅行、10月~12月、「満韓ところどころ」、11月、朝日文芸欄創設。 ]
2096 空に消ゆる鐸のひゞきや春の塔(前書「空間を研究せる天然居士の肖像に題す」。)
[天然居士は、漱石の学生時代の友人米山保三郎の号。この句はその兄である米山熊次郎へ送った句。]
(再掲) 「漱石の親友 天然居士・米山保三郎」周辺
https://rendezvou.exblog.jp/7067220/
[学生時代の夏目金之助に作家になることを勧め漱石が彼の言葉に強く動かされた人物・米山保三郎のことはよく知られています。ただ、これまで研究者の中で誤解があり、漱石の語句の解釈に問題があるまま流布されてきたのが現状です。
「天然居士は空間を研究し、論語を読み、焼芋を食い、鼻汁を垂らす人である」
焼き芋と鼻汁を垂らす、これは禅の歴史に実在した中国の禅僧・懶さん(王ヘンに賛)和尚の故事から来る引用なのでした。漱石は畏敬する親友の米山保三郎へ深い愛情と禅に生きる彼を讃える意味で書いたものでしょう。しかし、世間一般ではなかなか通用しない事も充分知っていました。そうであるからこそ、『猫』のなかで次のように書いているのです。
「天然居士は空間を研究し、論語を読み、焼芋を食い、鼻汁を垂らす人である」
苦沙弥先生、一気呵成にこう書き流し、声を出してこれを読み、「ハハハ面白い」と笑うが、「うん。鼻汁を垂らすはさすがに酷だ、焼き芋も蛇足だ」と線を引き。結局「天然居士は空間を研究し論語を読む人である」だけにしたころで、これではあまりに簡単すぎると全部ボツにして、原稿用紙の裏に「空間に生れ、空間を究め、空間に死す。空たり間たり天然居士、噫」
実際、漱石はこの米山の兄、熊次郎から実弟の写真へ揮毫を懇望されて、漱石は俳句を書いています。その俳句とは、
空に消ゆる鐸のひびきや春の塔 という追悼の一句です。親友の死を悼む漱石の心情があふるるばかり、見事な名句と思います。写真は400X300mm、単身像の右側にこの句があり、左にこう記されています。
空間を研究する天然居士の肖像に題す 己酉 四月 漱石
己酉,となれば、1909年、明治四十二年です。漱石が朝日新聞社に入社して2年目の四月に詠んだものと明確に判るのが嬉しいところです。また、米山が鼻水を垂らすの表現がとかく世俗的に解釈され、漱石がいかにしてこの語句を入れたかということは研究者の間でないがしろにされて来ました。しかし、漱石がただ、ユーモラスにこんな語句を入れるはずはないのです。洟を垂らそうが自分は三昧になっているのだという仏道の修行による逸話なのです。
出典もありますから、その引用もしておきましょう。『碧巖録』第三十四則より。
「懶瓚和尚。隱居衡山石室中。唐德宗聞其名。遣使召之。使者至其室宣言。天子有詔。尊者當起謝恩。瓚方撥牛糞火。尋煨芋而食。寒涕垂頤未甞答。使者笑曰。且勸尊者拭涕。瓚曰。我豈有工夫為俗人拭涕耶。竟不起。使回奏。德宗甚欽嘆之。」
(懶瓚和尚、衡山石室の中に隱居す。唐の德、宗其の名を聞いて、使を遣して之を召す。使者、其の室に至つて宣言す。天子詔有り、尊者まさに起つて恩を謝すべし。瓚、まさに牛糞の火を撥つて、煨芋を尋ねて食す。寒涕、頤に垂れて未だ甞て答えず。使者笑つて曰く、且らく勸む、尊者、涕を拭え。瓚曰く、我れ豈に工夫の俗人の為に涕を拭くこと有らん耶といつて、竟に起たず。使、回つて奏す。德宗、甚だ之を欽嘆す。) (以下略) ]
(追記)

漱石(左)と米山保三郎(明治25年)
https://www.asahi.com/articles/ASJ615FM7J61UCVL00W.html
https://yahan.blog.ss-blog.jp/2023-09-08
[東洋城、三十二歳。東洋城の下宿「望遠館」(九段中坂)において、毎週一会の句会が催された。択ばれた者のみが出席できる会で、暮雨(万太郎)、蛇笏、零余子、松浜、喜舟などが、そのメンバーである。三月、東洋城選「新春夏秋冬」夏の部(「序」は夏目漱石)、十月「同・秋の部」を俳書堂より刊行した。]
春月や暗き灯持つ峰の城(「タンタヂイル(タンタジールの死)十八句」第一幕)
雁帰る女王の心疑へば(同上)
暗き灯を貝に吊りけり春四人(「同上」第二幕)
すみれ草しほれ草とは見えにけり(同上)
春の夜の廓冷かに柱かな(「同上」第四幕)
烏賊共は墨に隠れて来りけり(同上)
春の燭鉄の扉に凍りけり(「同上」第五幕)
おそろしや椿の落つる音もなく(同上)

「タンタヂールの死 (泰西傑作叢書 ; 2)」書誌情報/著者モゥリス・メーテルリンク 作, 小島春潮 訳/出版者 集栄館/出版年月日 大正12)/(「国立国会図書館デジタルコレクション」)
https://dl.ndl.go.jp/pid/915275/1/2
[寅彦・三十二歳。一月、東京帝国大学理科大学助教授となる。二月、次男の正二誕生。三月、宇宙物理学研究のためヨーロッパへ留学。ベルリン大学に学ぶ。四月、従七位に叙せられる。]→(『寺田寅彦全集/文学篇/七巻』には収載句は無い。)
(参考その一) 「タンタジールの死」と《ギルちゃん》(「宮沢賢治の世界」)周辺
https://ihatov.cc/blog/archives/2016/01/post_841.htm
(参考その二) 「西洋文明と融合、新作の糧に 高浜虚子の能、戦後初の復曲上演」周辺

「鐵門」の復曲上演に向け、所作の検討をする観世流能楽師の青木道喜さん(中)ら(京都市左京区の京都観世会館)
https://www.nikkei.com/news/print-article/?ng=DGXLASIH04H07_V00C16A1AA2P00
[(抜粋)
俳人の高浜虚子(1874~1959年)が大正初期に初めて書いた能「鐵門(てつもん)」が6月、京都観世会館(京都市)で復曲上演される。初演から100年に合わせた試みで、戦後の上演は初。西洋戯曲を翻案した新作能の嚆矢(こうし)とされるが、長く上演機会がなかった。今後の能の制作や役作りに生かす狙いだ。(中略)
「鐵門」はベルギーの劇作家・詩人モーリス・メーテルリンク(1862~1949年)が人形劇向けに書いた戯曲「タンタジールの死」に典拠する。死への恐怖と運命を、人間には開けることのできない鉄の門に象徴させた。
虚子は舞台を西洋から日本に移し替え、城に住む姫と姫に仕える老僕らの物語にした。長野県の善光寺に詣でた僧が、門前の者に案内されて暗穴の道に赴くところから始まる。そこに、老僕の霊が姫の霊と共に現れる。老僕はかつて城に忍び入った死の使いの悪尼(あくに)に姫を連れ去られ、そびえ立つ鉄の門に阻(はば)まれて姫を救えなかった経緯などを語る。
(後略) ]
(参考その三) 「青春時代を語る / 東洋城 ; 洋一/p54~73」)」(「俳誌『渋柿(昭和四十年(一九六五)の一月号) 』 (「松根東洋城追悼号」)」所収

「青春時代を語る / 東洋城 ; 洋一/p54~73」時の「東洋城と吉田洋一」(左「東洋城」、右「吉田洋一」)
https://dl.ndl.go.jp/pid/6071686/1/41
「俳誌『渋柿(昭和四十年(一九六五)の一月号)』 (「松根東洋城追悼号」)」は、毀誉褒貶の風聞の中で、その全貌が未だに謎にみちたままの、明治・大正・昭和の三代にわたって、俳諧一筋の、東洋城の言葉でするならば、「芭蕉の誠の俳諧」一筋を貫いた生涯は、この「松根東洋城追悼号」は、その周辺の確かな道標を示すものであろう。
そして、それは、東洋城が没して十年後に刊行された、生前の東洋城の謦咳に接している俳句総合誌の「俳句研究」に携わった俳人の「石川桂郎」著の『俳人風狂列伝』(「読売文学賞」受賞)の、東洋城をめぐるスキャンダル(「白蓮事件」にも連動する「男爵夫人」あるいは「渋柿」からの「あら野」離脱に関連する「同人夫人」)とかの「東洋城の虚像(?)」に対する、その「東洋城の実像(?)」を語るものとして、この「青春時代を語る / 東洋城 ; 洋一/p54~73」や「兄東洋城と私 / 松根新八郎/p74~90」などは、いわば、「石川桂郎」著の『俳人風狂列伝』の「東洋城像(虚像?)」を覆すものの、すなわち、「東洋城(実像?)」を示しているものの、その一端を物語っているように思われる。
そして、これらことは、「虚子と東洋城」との、「ホトトギス(虚子)・国民俳壇(虚子・徳富蘇峰)・渋柿創刊(東洋城)・新傾向俳句の台頭(碧悟桐・井泉水・乙字・一碧楼など)との、混沌した中にあっての、「高浜虚子と松根東洋城」との、その「実像(?)と虚像(?)」との、これまた、その一端を物語る、一つの道標となり得るものであろう。
これらのことに関して、「虚子と東洋城」とが、「新傾向俳句(自由律俳句)」(碧悟桐・井泉水・乙字・一碧楼など)に対して、「伝統俳句(定型律俳句)」の牙城として、「ホトトギス」(虚子主宰)と「渋柿(東洋城主宰)」の二誌が、未曾有の、太平洋戦争前後の統制下にあって、その命脈を保ちつづけたということになる。
上記の写真(「東洋城と吉田洋一」)は、吉田洋一の軽井沢の山荘のもので、東洋城と洋一との接点は、寺田寅彦門下の北海道大学理学部教授の「中谷宇吉郎」を介してのもののようである(『渋柿の木の下で(中村英利子著)』)。
晩年の東洋城の避暑先は、この吉田洋一夫妻の山荘で過ごすのが常のようで、軽井沢は、寺田寅彦・小宮豊隆・中谷宇吉郎・吉田洋一らの忘れ得ざる邂逅の出会いの避暑地でもあったのである。
ここで、「明治四十二年(一九〇九)」の冒頭に戻って、その東洋城年譜の、[東洋城、三十二歳。東洋城の下宿「望遠館」(九段中坂)において、毎週一会の句会が催された。択ばれた者のみが出席できる会で、暮雨(万太郎)、蛇笏、零余子、松浜、喜舟などが、そのメンバーである。三月、東洋城選「新春夏秋冬」夏の部(「序」は夏目漱石)、十月「同・秋の部」を俳書堂より刊行した。]は、「東洋城・虚子、そして、漱石」との三者関係の、その最期の「華やぎ」のような、東洋城の「タンタヂイル(タンタジールの死)十八句」、そして、後の虚子の「大正初期に初めて書いた能『鐵門(てつもん)』(「タンタジールの死」に典拠する)との、当時の最晩年の漱石の膝下にあっての、「虚子と東洋城」との切磋琢磨の時代でもあった。
漱石は、この年に、東洋城選「新春夏秋冬」夏の部の、その刊行に当たって、その「序」を草している。
この東洋城選「新春夏秋冬」夏の部(「漱石・序」)も、下記のアドレスで閲覧することが出来る。
https://kindai.nijl.ac.jp/kindais/HKDT-01067

「新春夏秋冬 夏の部/俳諧叢書第二十二篇/松根東洋城 編」/東洋城撰/明治42.3.5/ 1909.35/函館市中央図書館/
https://kindai.nijl.ac.jp/kindais/HKDT-01067
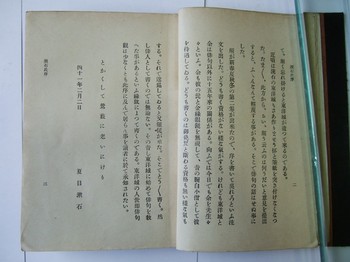
「新春夏秋冬 夏の部/俳諧叢書第二十二篇/松根東洋城 編」所収「夏目漱石『序』(明治四十二年二月二日)」
https://kindai.nijl.ac.jp/kindais/HKDT-01067



