「子規・漱石・寅彦・東洋城」(~子規没まで)俳句管見(その一) [子規・漱石・寅彦・東洋城]
その一「明治二十二年(一八八九)・時鳥(子規・ほととぎす)など」
(子規・二十三歳。正月、漱石を知る。五月九日喀血。)
https://shiki-museum.com/masaokashiki/haiku?post_type=haiku&haiku_id&p_age=22&season&classification&kigo=%E6%99%82%E9%B3%A5&s&select&doing_wp_cron=1694245298.6711421012878417968750
川向ひどこのやしきへ時鳥 ID501 制作年22 季節夏 分類動物 季語時鳥
五月雨を思ふてなくか子規 ID502 制作年22 季節夏 分類動物 季語時鳥
往て還るほどは夜もなし子規 ID508 制作年22 季節夏 分類動物 季語時鳥
卯の花をめかけてきたかほとゝきす ID509 制作年22 季節夏 分類植物 季語卯の花
(漱石・二十三歳。子規見舞い二句)
https://yahan.blog.ss-blog.jp/2023-08-19
(再掲)
漱石の俳句は、明治二十二年(一八八九)に、東京大学(予備門)での、正岡子規との出会いによる、次の二句から始まる。
1 帰ろふと鳴かずに笑へ時鳥 (漱石・23歳「明治22年(1889)」)
2 聞かふとて誰も待たぬに時鳥 (漱石・23歳「明治22年(1889)」)
≪季語=時鳥(夏)。「時鳥」の異名「不如帰」(帰るに如かず)に託して喀血した正岡子規を激励した句。子規と時鳥とは同義。正岡子規は明治二十二年五月九日に喀血した。翌日、医者に肺病と診断され、「卯の花をめがけてきたか時鳥」「卯の花の散るまで鳴くか子規」などの句を作った。卯の花を自分になぞらえ(子規は卯年生れ)、肺病(結核)を時鳥と表現俳句。(中略) 子規はこれらの俳句を作ったことから、自ら子規と号するようになった。この年の一月頃に急速に親しくなった漱石は、五月十三日に子規を見舞い、その帰途に子規のかかっていた医師を訪ねて病状や療養の仕方を聞いている。(後略 )≫(『漱石全集第十七巻・坪内稔典注解』)
(追記)
(寅彦=「漱石」との出会い「明治二十九年・十八歳時=第五高校入学時。出典=『牛頓先生俳句集・季題別』、『寺田寅彦全集/文学篇/七巻』」)
時鳥京に客たる三年目 (明治三十四年作。満二十三歳)
時鳥一寸先の闇の声 (同上)
時鳥くらがり坂を君帰る (同上)
時鳥剣(けん)を按(あん)じて失せ玉ひぬ(同上、「失せ玉ひぬ」の原句は「君逝けり」)
(東洋城=「明治二十八年、十八歳時、松山中学校五年生の四月、漱石が教師として来任し、英語の教授を受ける。明治三十三年、二十三歳時、一高・東大へ入学、東洋城と号す。明治三十六年、二十六歳時、漱石帰朝、一高・東大講師となり、漱石を師とする。腸チフスで東大休学、翌年、新設の京大に入学、明治三十八年、京大卒業、翌年、二十九歳時に、宮内省に入り、式部官などを歴任。出典=『東洋城全句集(上・中・下)』の中巻の「年譜」)
時鳥牡丹に月の雫せよ(明治三十五年作。二十五歳)
時鳥硯に墨を立てる時(明治四十三年作。三十三歳)
二階から朝顔棚や時鳥(同上)
時鳥雨の鳥居は松の中(同上)
時鳥も鳴かで明けたる一夜かな(大正十五年、昭和元年、四十九歳)
時鳥あららぎに奈良の夜あるかな(昭和四年作、五十二歳)
.jpg)
「紫陽花郭公図(あじさいほととぎすず)」日本画 / 絵画 / 江戸 / 日本/与謝蕪村 (1716-1784年)/江戸時代/明和7-安永6/紙本,墨画淡彩/38.7 x 64.3cm(「文化遺産オンライン」)
https://bunka.nii.ac.jp/heritages/detail/90300
≪(解説) 俳人、文人、画家であった蕪村は、享保年間末に江戸に下り、俳諧を学び、江戸俳壇に出る一方、絵画にも親しみ、寛保初年に江戸を後にして放浪生活に入り、各地を旅して10年余を過ごした。宝暦初年に京に上り、画業に心を寄せ、国内のさまざまな流派はもとより、中国諸家の作品や版本類を研究して自己の画風を形成した。初期文人画の足跡を受け継ぎ、日本の文人画を大成したのは池大雅と与謝蕪村であった。中国への憧れをもちつつもその影響を離れ、日本的な文人画を創り出すことに大きく貢献した。「岩くらの狂女戀せよほととぎす」この句は天明三年刊維駒編『五車反古』に出ている。おそらく蕪村最晩年の句であろう。空に鋭く啼き渡る郭公と、たっぷりとした墨色の葉にすがすがしい藍色の施された紫陽花が大きく描かれている。句のもつ激しい情調を象徴的に表した珠玉の作品である。≫
(参考) 「一寸先は闇ではなく光」(周辺)
時鳥一寸先の闇の声(寅彦、明治三十四年作。二十三歳)
https://www.engakuji.or.jp/blog/35010/
(抜粋)
≪ 「二度とない人生(坂村真民)」
(1989年 「二度とない人生だから」は藤掛廣幸に依り曲が付けられ8月6日に「89 海と島の博覧会・ひろしま」のメイン会場で初演された。)
二度とない人生だから
二度とない人生だから
一輪の花にも
無限の愛を
そそいでゆこう
一羽の鳥の声にも
無心の耳を
かたむけてゆこう
二度とない人生だから
一匹のこおろぎでも
ふみころさないように
こころしてゆこう
どんなにか
よろこぶことだろう
二度とない人生だから
一ぺんでも多く
便りをしよう
返事は必ず
書くことにしよう
二度とない人生だから
まず一番身近な者たちに
できるだけのことをしよう
貧しいけれど
こころ豊かに接してゆこう
二度とない人生だから
つゆくさのつゆにも
めぐりあいのふしぎを思い
足をとどめてみつめてゆこう
二度とない人生だから
のぼる日 しずむ日
まるい月 かけてゆく月
四季それぞれの
星々の光にふれて
わがこころを
あらいきよめてゆこう
二度とない人生だから
戦争のない世の
実現に努力し
そういう詩を
一遍でも多く
作ってゆこう
わたしが死んだら
あとをついでくれる
若い人たちのために
この大願を
書きつづけてゆこう ≫
(子規・二十三歳。正月、漱石を知る。五月九日喀血。)
https://shiki-museum.com/masaokashiki/haiku?post_type=haiku&haiku_id&p_age=22&season&classification&kigo=%E6%99%82%E9%B3%A5&s&select&doing_wp_cron=1694245298.6711421012878417968750
川向ひどこのやしきへ時鳥 ID501 制作年22 季節夏 分類動物 季語時鳥
五月雨を思ふてなくか子規 ID502 制作年22 季節夏 分類動物 季語時鳥
往て還るほどは夜もなし子規 ID508 制作年22 季節夏 分類動物 季語時鳥
卯の花をめかけてきたかほとゝきす ID509 制作年22 季節夏 分類植物 季語卯の花
(漱石・二十三歳。子規見舞い二句)
https://yahan.blog.ss-blog.jp/2023-08-19
(再掲)
漱石の俳句は、明治二十二年(一八八九)に、東京大学(予備門)での、正岡子規との出会いによる、次の二句から始まる。
1 帰ろふと鳴かずに笑へ時鳥 (漱石・23歳「明治22年(1889)」)
2 聞かふとて誰も待たぬに時鳥 (漱石・23歳「明治22年(1889)」)
≪季語=時鳥(夏)。「時鳥」の異名「不如帰」(帰るに如かず)に託して喀血した正岡子規を激励した句。子規と時鳥とは同義。正岡子規は明治二十二年五月九日に喀血した。翌日、医者に肺病と診断され、「卯の花をめがけてきたか時鳥」「卯の花の散るまで鳴くか子規」などの句を作った。卯の花を自分になぞらえ(子規は卯年生れ)、肺病(結核)を時鳥と表現俳句。(中略) 子規はこれらの俳句を作ったことから、自ら子規と号するようになった。この年の一月頃に急速に親しくなった漱石は、五月十三日に子規を見舞い、その帰途に子規のかかっていた医師を訪ねて病状や療養の仕方を聞いている。(後略 )≫(『漱石全集第十七巻・坪内稔典注解』)
(追記)
(寅彦=「漱石」との出会い「明治二十九年・十八歳時=第五高校入学時。出典=『牛頓先生俳句集・季題別』、『寺田寅彦全集/文学篇/七巻』」)
時鳥京に客たる三年目 (明治三十四年作。満二十三歳)
時鳥一寸先の闇の声 (同上)
時鳥くらがり坂を君帰る (同上)
時鳥剣(けん)を按(あん)じて失せ玉ひぬ(同上、「失せ玉ひぬ」の原句は「君逝けり」)
(東洋城=「明治二十八年、十八歳時、松山中学校五年生の四月、漱石が教師として来任し、英語の教授を受ける。明治三十三年、二十三歳時、一高・東大へ入学、東洋城と号す。明治三十六年、二十六歳時、漱石帰朝、一高・東大講師となり、漱石を師とする。腸チフスで東大休学、翌年、新設の京大に入学、明治三十八年、京大卒業、翌年、二十九歳時に、宮内省に入り、式部官などを歴任。出典=『東洋城全句集(上・中・下)』の中巻の「年譜」)
時鳥牡丹に月の雫せよ(明治三十五年作。二十五歳)
時鳥硯に墨を立てる時(明治四十三年作。三十三歳)
二階から朝顔棚や時鳥(同上)
時鳥雨の鳥居は松の中(同上)
時鳥も鳴かで明けたる一夜かな(大正十五年、昭和元年、四十九歳)
時鳥あららぎに奈良の夜あるかな(昭和四年作、五十二歳)
.jpg)
「紫陽花郭公図(あじさいほととぎすず)」日本画 / 絵画 / 江戸 / 日本/与謝蕪村 (1716-1784年)/江戸時代/明和7-安永6/紙本,墨画淡彩/38.7 x 64.3cm(「文化遺産オンライン」)
https://bunka.nii.ac.jp/heritages/detail/90300
≪(解説) 俳人、文人、画家であった蕪村は、享保年間末に江戸に下り、俳諧を学び、江戸俳壇に出る一方、絵画にも親しみ、寛保初年に江戸を後にして放浪生活に入り、各地を旅して10年余を過ごした。宝暦初年に京に上り、画業に心を寄せ、国内のさまざまな流派はもとより、中国諸家の作品や版本類を研究して自己の画風を形成した。初期文人画の足跡を受け継ぎ、日本の文人画を大成したのは池大雅と与謝蕪村であった。中国への憧れをもちつつもその影響を離れ、日本的な文人画を創り出すことに大きく貢献した。「岩くらの狂女戀せよほととぎす」この句は天明三年刊維駒編『五車反古』に出ている。おそらく蕪村最晩年の句であろう。空に鋭く啼き渡る郭公と、たっぷりとした墨色の葉にすがすがしい藍色の施された紫陽花が大きく描かれている。句のもつ激しい情調を象徴的に表した珠玉の作品である。≫
(参考) 「一寸先は闇ではなく光」(周辺)
時鳥一寸先の闇の声(寅彦、明治三十四年作。二十三歳)
https://www.engakuji.or.jp/blog/35010/
(抜粋)
≪ 「二度とない人生(坂村真民)」
(1989年 「二度とない人生だから」は藤掛廣幸に依り曲が付けられ8月6日に「89 海と島の博覧会・ひろしま」のメイン会場で初演された。)
二度とない人生だから
二度とない人生だから
一輪の花にも
無限の愛を
そそいでゆこう
一羽の鳥の声にも
無心の耳を
かたむけてゆこう
二度とない人生だから
一匹のこおろぎでも
ふみころさないように
こころしてゆこう
どんなにか
よろこぶことだろう
二度とない人生だから
一ぺんでも多く
便りをしよう
返事は必ず
書くことにしよう
二度とない人生だから
まず一番身近な者たちに
できるだけのことをしよう
貧しいけれど
こころ豊かに接してゆこう
二度とない人生だから
つゆくさのつゆにも
めぐりあいのふしぎを思い
足をとどめてみつめてゆこう
二度とない人生だから
のぼる日 しずむ日
まるい月 かけてゆく月
四季それぞれの
星々の光にふれて
わがこころを
あらいきよめてゆこう
二度とない人生だから
戦争のない世の
実現に努力し
そういう詩を
一遍でも多く
作ってゆこう
わたしが死んだら
あとをついでくれる
若い人たちのために
この大願を
書きつづけてゆこう ≫
夏目漱石の「俳句と書画」(その十五) [「子規と漱石」の世界]
その十五 漱石の「観自在帖」周辺
.jpg)
「観自在帖(全作品紹介)」
https://hzrhq.agaterlm.top/index.php?main_page=product_info&products_id=30145
≪右一列上段「観自在帖(1)」→「観自在(漱石題)/紙本墨書・淡彩・24.4×36.3㎝」
右一列中段「観自在帖(2)」→「藤花図」/同上」
右一列下段「観自在帖(3)」→「隔水東西住」/同上」
右二列上段「観自在帖(4)」→「竹図」/同上」
右二列中段「観自在帖(5)」→「渡尽東西水」/同上」
右二列下段「観自在帖(6)」→「鉢花図」/同上」
右三列上段「観自在帖7)」→「柳芽を」/同上」
右三列中段「観自在帖(8)」→「牡丹図」/同上」
右三列下段「観自在帖(9)」→「起臥乾抻」/同上」
右四列上段「観自在帖10)」→「松林図」/同上」
右四列中段「観自在帖(11)」→「二十年来愛碧林/同上」
右四列下段「観自在帖(12)」→「竹石図/同上」
≪ 観自在とは、迷いの執念から解放された境界にあって、事物のすがたが自由自在に正しくみきわめられることを意味する仏教語。
.jpg)
「観自在帖(1)」→「観自在(漱石題)」
https://jp.mercari.com/item/m87413254274
大正四年の春、漱石は京都に旅したが、病臥した。その後、小康を得て、乞わるるままに、小品の書画を楽しみながら書いた。贈られた磯田家では、この書画帖の巻頭の書「観自在」(上記図)をとって「観自在帖」と名付けている。
画帖は「観自在」に続いて「藤花図」(「観自在帖(2)」)「隔水東西住」(「観自在帖(3)」)の五言絶句に展開される。
隔水東西住 (水を隔てて東西に住み)
白雲往又還 (白雲往(ゆ)きて又(また)還(かえ)る)
東家松籟起 (東家(とうか)に松籟起(お))これば)
西屋竹珊々 (西屋(せいおく)竹) 珊々(さんさん))
この詩は、大正五年初夏頃の「断片」にも載っているが、そこでは「白雲」は「閑雲」、「又」は「復」と改められている。『漱石全集』では「又」は「也(また)」となっている。
松籟は松風、珊々は、もとは玉のふれあう音から竹の葉のそよぎを形容している。最後の句に呼応して水墨の「竹図」(「観自在帖(4)」)がある。
次の「渡尽東西水」(「観自在帖(5)」)には、
渡尽東西水 (渡り尽くす東西の水)
三過翠柳橋 (三(み)たび過(す)ぐ翠柳(すいりゅう)の橋)
春風吹不断 (春風(しゅんぷう)吹いて断(た)たず)
春恨幾條々 (春恨(しゅんこん)幾條々(いくじょうじょう))
春日偶成 漱石
の五言絶句があって、これは明治四十五年(一九一二)五月二十四日の「春日偶成 十首」中の最後の詩。
修善寺大患の『思ひ出す事など』以後、約一年半ばかり、全く作詩から遠ざかっていた漱石は、この「春日偶成 十首」以後、盛んに作詩した。しかし、それまでと趣を異にして、南画の賛、題詩の類か、少なくとも南画的光景を詠じたものばかりといっていいのが特色だと『漱石の漢詩』の中に松岡譲は述べている。
この詩は旧作だが「観自在帖」に入れるにふさわしいと思ったのであろう。吉川幸次郎氏は『漱石詩注』で、「渡尽東西水」は明の高青邱(こうせいきゅう)の「胡隠君(こいんくん)を尋ぬ」に「水を渡り復(また)水を渡る。花を看(み)て還(また)花を看る。春風江上の路、覚えず君が家に到る」があり、これはこの句を導いたのであろうと述べている。それはそれとして、前掲(8図=「木屋町の宿をとりて川向の御多佳さんに」の前書がある「春の川を隔てて男女哉」)の「春の川を隔てて男女哉」の情緒につながるものを、かつての作に感じて、記したように思えてならない。
なお、大正三年の作「同じ橋三たび渡りぬ春の宵」は、この漢詩と通ずるものがある。
「観自在帖(6)」は、可憐な花をつけた木を描いた「鉢花図」。
「観自在帖7)」は、
柳芽(やなぎめ)を吹いて四条のはたごかな 漱石
の俳句で、大正四年四月、京都にて作った八句中の第一句。
漱石の約一か月の京都滞在中の句で、続いて次の句がある。
見あぐれば坂の上なる柳かな
筋違に四条の橋や春の川
鴨川に面した宿の二階の部屋に通されたというが、久しぶりに京都の春景色に、旅情を感じている漱石の感慨が示されている。また「はたご」という古風な語が、いかにも京都の土地がらにふさわしい。
次の「観自在帖8)」は、満開の牡丹、蕾の牡丹を描いた「牡丹図」(下記の図)。
.jpg)
「観自在帖(8)」→「牡丹図」
https://jp.mercari.com/item/m87413254274
「観自在帖(9)」の「起臥乾抻」は、
起臥乾抻一草亭 (起臥す乾抻一草亭(けんこんいっそうてい))
眼中只有四山青 (眼中只有り四山の青(せい))
閑来放鶴長松下 (閑来(かんらい)鶴を放(はな)つ長松(ちょうしょう)の下)
又上虚堂読易経 (又(ま)た虚堂(きょどう)に上(のぼ)って易経を読む)
の七言絶句で、「閑来放鶴図」(下記の図)の題賛のみを書いたもの。『漱石全集』では「只」が「唯」となっている。
(付記) 「閑来放鶴図」
≪大正三年の題賛。漱石の理想境と思われるところを実に丹念に描き、この画は代表作の一つと目せられている。印は白文方印「漱石」。≫(『俳人の書画美術8 漱石』所収「作品解説39・40(福田清人稿)」)

「閑来放鶴図自画賛」紙本着色/146.0×39.0㎝
https://aucview.aucfan.com/yahoo/d205942908/

「(観自在帖10)」→「松林図」
https://hzrhq.agaterlm.top/index.php?main_page=product_info&products_id=30145
「(観自在帖10)」は、松林の中に庵があり、対話する二人の人物を配した「松林図」(上記の図)。
そして、「観自在帖(11)」は、次の七言絶句(「二十年来愛碧林」)。
二十年来愛碧林 (二十年来碧林(へきりん)を愛す)
山人須解友虚心 (山人(さんじん)須(す)べからく解す虚心を友とするを)
長毫漬墨時如雨 (長毫(ちょうもう)漬墨(しぼく)時に雨の如し)
欲写鏗鏘戞玉音 (写さんと欲(ほっ))す鏗鏘(こうしょう) 戞玉(かつぎょく)の音(ね))
碧林は青い竹林、山人は山の隠士、長毫は毛の長い筆、漬墨はにじんだ墨、鏗鏘は金属や玉がふれあって鳴る音、戞玉はふれあう玉。この詩は大正三年の画賛であるが「題竹」として、「観自在帖」のために重ねて書いた。
最後の「観自在帖(12)」岩に竹を配し、淡彩で描いた「竹石図」。詩句六点、画六点で「観自在帖」は構成されている。 ≫(『俳人の書画美術8 漱石』所収「作品解説14~25(福田清人稿)」)
この「観自在帖」は、「漢詩」(「観自在帖(3)」・「観自在帖(5)」・「観自在帖(9)」・「観自在帖(11)」)、「俳句」(「観自在帖7)」→「柳芽を」)、「書」(「観自在帖(1)」→「観自在(漱石題)」)、「南画」(「観自在帖10)」→「松林図」)、そして、「俳画」(「観自在帖(2)」・「観自在帖(4)」・「観自在帖(6)」・「観自在帖(8)」・「観自在帖(12)」」)と、漱石の世界の全貌を探索する上で、その総決算的な意味合いがあるものと解したい。
因みに、「俳句」(「観自在帖7)」→「柳芽を」)関連は、次の八句ということになる。
大正4年(1915年)
2437 柳芽を吹いて四条のはたごかな
≪季=柳の芽(春) ※2443までの七句は京都での作。漱石は三月十九日から四月十六日まで京都に滞在した。この句はこの滞在中に磯田多佳(2440参照)に贈った画帖『観自在帖』に記されている。◇全集(大6)が「四月京都にて 八句」として収める(ただし、八句のうち一句は、(2372))に同じ)。 ≫
2438 筋違に四条の橋や春の川
≪季=春の川。※筋違(すじかい)は斜め、はすかい。蕪村の句に「ほととぎす平安城を筋違に」があり、漱石は『創作家の態度』でこの句について言及している。 ≫(『漱石全集第十七巻・坪内稔典注解』)
2439 紅梅や舞の地を弾く金之助
≪季=紅梅(春)。※金之助は祇園 の芸妓の名。本名梅垣きぬ。≫(「同上」)
木屋町に宿とりて川向
の御多佳さんに(一句)
2440 春の川を隔てゝ男女かな
≪季=春の川。京都の漱石の宿は木屋町三条上ルにあった北大嘉(きたのたいが)。多佳は祇園 大友(だいとも)の女将、磯田多佳。鴨川の東に大友が、西に北大嘉があった。後略≫(「同上」)
2441 萱草の一輪咲きぬ草の中
≪季=萱草(かんぞう)=夏。※画賛の句。萱草はユリ科の多年草。夏に百合に似た橙赤色の花を一日だけ開く。忘れ草。西川一草亭が画いた萱草の絵に賛をしたものが知られている(『夏目漱石遺墨集』第三巻)。 ≫(「同上」)
2442 牡丹剪つて一草亭を待つ日哉
≪季=牡丹(夏)。※自画賛の句。一草亭は華道去風流の西川一草亭。実弟が津田青楓であり、漱石は京都滞在中に親しく交わった。≫(「同上」)
(付記) 「牡丹剪つて一草亭を待つ日哉(漱石)」自画賛(周辺)
https://rendezvou.exblog.jp/5253202/

「牡丹剪つて一草亭を待つ日哉(漱石)」自画賛図
牡丹剪って一草亭を待つ日かな 漱石
2443 椿とも見えぬ花かな夕曇
≪季=椿(春)。※自画賛の句。≫(「同上」)
大正3年(1914年)
2372 見上ぐれば坂の上なる柳哉
≪季=柳(春)。≫(「同上」)
(参考その一)「津田青楓・西川一草亭 と 漱石の交友」周辺
https://rendezvou.exblog.jp/6290544/
≪ 漱石と京都、学問の繋がりでは松本文三郎、狩野亨吉がいずれも京都帝国大学(旧文科大学)の長であり、漱石へ教師として講座を依頼していました。明治40年4月、漱石は京都の銀閣寺北にあった松本文三郎の山房に招かれその礼状を送っています。
「拝啓 京都滞在中は尊来を辱ふせるのみならず銀閣の仙境に俗塵を振るひ落し候」
市街と離れたこの地を漱石はたいへん気に入り、東京付近ではこんな住居は求められないと賞賛しています。しかし、41年6月、書状で教師就任と講義の件は断っているのです。狩野亨吉とも同じやりとりがあったは史実に遺されている処です。
ただ、これら碩学の友人は当時京都在住ではありましたが、故郷は別にあり後に京都を去った人でした。京都に生まれ育ったきっすいの京都人で、親密な知人といえば、津田青楓と西川一草亭きょうだいを措いてはないと思われます。今回はこのふたりにスポットを当ててみることにいたしましょう。
☆フランス帰りの青年画家・津田青楓
漱石門下の小宮豊隆の仲介で津田青楓が漱石に逢ったのは明治44年。京都に育ち、日露戦争が終わると官費でフランスに3年間留学した貧しい青年画家で、帰国してまもなく京都から東京に出た頃でした。本名津田亀次郎、雅号青楓。
彼は、フランスで日本人の仲間が落ち合うレストランでの思い出を述懐しています。留学生の彼らは、漱石の『坊っちゃん』や『我輩は猫である』『草枕』の掲載されている雑誌を持ち込み朗読していたそうです。
津田と共にいた安井(安井曽太郎)は新参者であり、朗読するのは古参の留学生ら。
「茶と聞いて少し辟易した。世間に茶人程勿体ぶった風流人はない。広い視界をわざとらしく窮屈に縄張りをして、極めて自尊的に、極めてことさらに、極めてせせこましく、必要もないのに、鞠躬如(きっきゅうじょ)として、あぶくを飲んで結構がるものは所謂茶人である…」
『草枕』の一節を聞いては「愉快だね」と、うれしがる古参者ら。津田はそれを横目で見ながらこの時、漱石に親愛の情を感じはじめたと書いています。
けれども、彼の父親は去風洞挿花家元西川源兵衛(一葉)であり、また表千家の茶人でもあったのですから、皮肉なものです。明治44年、縁あって漱石門下に入ることになります。漱石にとっては趣味にしている描画のよき相談相手になり、心許せる門下生でありました。津田が漱石山房に出入りするようになった後、実兄の西川一草亭をまた漱石に引き合わせるのでした。
津田清楓は述べています。
「京都はいやだった。親兄弟のお付き合いばかりして、やれお花見だ、やれお茶会だ、やれなんだかんだで引っ張り出されることばかしで、仕事なんかするひまはない。京都の人間は画家は風流人で、風流人は閑人だと思っているんだ。やりきれない…」
漱石と散歩しながらの話を彼はこんな風に書いています。
「君の親の商売は何だと云われるので、一寸嫌だったが思い切って、花屋です、店では花屋で奥では生花の先生です」といい、父は風雅な風采をして茶ばかり啜っていると云った後で、
「だから僕を学校にもやってくれないで、小学校を出ると丁稚にやらされて、それ家を飛び出して孤児のように自分でやっとここまでこぎつけたのです」
長男は特別で次男以下は同等ではなかった明治の家族制度を思いますと、こうした話も理解できるのではないでしょうか。いっぽう、兄の西川一草亭は長男として教育も受け家業を継ぎました。去風洞挿花をさらに盛り立て、『瓶史』を刊行する著名な文化人となっていました。
☆去風洞主人・西川一草亭
漱石は、大正4年3月21日、京都滞在中に西川一草亭の招きで彼の住居である茶室を訪れています。まず、漱石自身の筆記を見ることにいたします。
漱石全集 大正4年 日記14 (日記・断片 下)
「二一日(日)
八時起る。下女に一体何時に起ると聞けば大抵八時半か九時だといふ。夜はと聞けば二時頃と答ふ。驚くべし。」
漱石は旅館の女中の生活を聞き、労働時間が長いのに驚いています。それから宿の窓からのぞむ加茂川とかなたの東山が霞でよく見えないのに河原で合羽を干すさまを書きとめています。
☆漱石 去風洞・小間の茶室に入る
「東山霞んで見えず、春気曖、河原に合羽を干す。西川氏より電話可成(なるべく)早くとの注文。二人で出掛ける。去風洞といふ門をくぐる。奥まりたる小路の行き当たり、左に玄関。くつ脱ぎ。水打ちて庭樹幽すい、寒きこと夥し。」
寒がりの漱石はここでも京の底冷えの寒さに震え上がっています。数奇屋の庭はこの時期殺風景な感じもあったでしょうし、待合の座敷から暖かい陽光の遮られた暗い茶室へ入り、心寒いばかりの想いがあったのではないでしょうか。それでも漱石の観察眼はするどく克明に記憶にとどめています。
「床に方祝の六歌仙の下絵らしきもの。花屏風。壁に去風洞の記をかく。黙雷の華厳世界。一草亭中人。御公卿様の手習い机。茶席へ案内、数奇屋草履。石を踏んでし尺(しせき)のうちに路を間違へる。再び本道に就けばすぐ茶亭の前に行きつまる。どこから這入るのかと聞く。戸をあけて入る。方三尺ばかり。ニジリ上り。」
ここは、露地を歩きながら茶室への方向を間違え、やっと茶室のにじり口を見つけたところです。武士も刀を外して身分の上下なく入る狭き入り口なのです。漱石はどうやら身をかがめて茶室内に入ったようです。
「更紗の布団の上にあぐらをかき壁による。つきあげ窓。それを明けると松見える。床に守信の梅、「梅の香の匂いや水屋のうち迄も」といふ月並みな俳句の賛あり。」
暗い茶室内には天井に突き上げ窓が開けられていました。ここから自然光が入る仕組みになっているのです。しかし、同時に冷気も入ったことでしょう。次に懐石料理が書かれています。この去風洞の近くに「松清」という料理屋があり、亭主は懐石をそこから取り寄せたもようです。
☆懐石料理の献立はどういうものだったか
「料理 鯉の名物松清。鯉こく。鯉のあめ煮。鯛の刺身、鯛のうま煮。海老の汁。茶事をならはず勝手に食ふ。箸の置き方、それを膳の中に落とす音を聞いて主人が膳を引きにくるのだといふ話を聞く。最初に飯一膳、それから酒といふ順序。」
(後略)
箸の置き方、それを膳の中に落とす音を聞いて主人が膳を引きにくるのだ、のくだりは、茶道で懐石の作法になっているものです。客は食事が終わった合図として、静かに箸を膳の上に落とし亭主に知らせ、主はその音を水屋で聞くとすぐに膳を引きに来るわけです。
ところで、この献立を見るかぎりでは、西川一草亭は茶事を余りしていなかったのではないかと私は思います。理論はできても茶道の基本的な稽古をしていたかどうか…。父親から手前を習ったことはあるとだけ書かれています。
茶懐石では、海の幸、山の幸を少しづつとりまぜて消化の好い調理をし、無理なく食べられる分量で客に呈すのが本筋です。料理屋にまかせず亭主自ら客のことを考え吟味しなければいけません。しかし、この献立では胃腸の重篤な病をもつ漱石に如何なものかと思われてならないのです。
☆漱石「腹具合あしし」
案の定、漱石は23日の日記に「腹具合あしく且つ天気あしゝ。天気晴るれど腹具合なほらず。」とあるのです。翌24日には更に、腹具合は悪化します。
多佳女が云い出して北野天神の梅見の約束をしていたにも拘わらず、断りなく多佳が遠出していたことで漱石は深く傷つくのです。
「二十四日(水)
寒、暖なれば北野の梅を見に行こうと御多佳さんがいふから電話をかける。御多佳さんは遠方に行って今晩でなければ帰らないから夕方懸けてくれといふ。夕方懸けたって仕方がない。(中略)腹具合あしし。」
この時漱石は東京に帰るべく、「晩に気分あしき故明日出立と決心す」といったんは京都を離れる決意をしたのでした。この危機的状況を救ったのがまた津田青楓その人でした。
付きっ切りで看病する津田は多佳女に懸命にとりなすように依頼し、祇園の芸妓で漱石信奉者のお君さん、金之助にも来て貰い、最悪の状態を切り抜けました。京都滞在はこの後更に続くことになります。
「二十五日
御多佳さんが来る。出立ちをのばせと云ふ。医者を呼んで見てもらえと云ふ。(中略)多佳さんと青楓君と四人で話しているうちに腹具合よくなる。」
結局、漱石は翌月の4月16日まで、都合二十九日間京都に滞在したのです。東京へ帰ってから胃腸の病は深刻になり、翌月大正5年の12月9日までその病苦は続きました。
☆西川一草亭に漱石は感想をのべる
「漱石と庭」と題した一草亭のエッセイに、漱石が来庵した折の事柄が興味深く書かれています。その一部分を抜粋します。
「夏目さんの来られたのは三月の末で、さう云ふ時分にこう云ふ家を見ると只陰気で不愉快なばかりだった。夏目さんはその暗い陰気な座敷の床の前に坐って、欄間に懸かっている「一草亭中之人」と云ふ夏目さん自身の字を眺めたり、床の間に生けておいた室咲きの牡丹の花を見たりして、最後に此処の家賃はいくらするかねと尋ね、「こんな家は只でも嫌だね」と云って心から嫌な顔をされた。」
まあ、客としては失礼な物言いですが、体調の悪い人への亭主の心配りも「も一つ」だったようです。
江戸っ子漱石と京都、かならずしも相性は悪くなかったのです。相性が悪かったのは、京都の寒さだけだったのかもしれません
☆正直で飾り気のない交友
表裏のある狡猾な人間を嫌悪した漱石。それゆえに江戸っ子と自他ともに認めた気性でした。では、その対極にあるのが京都人だという世間の見方があるとすれば…。それは概には云えないのではないでしょうか。
西川・津田兄弟を見ましても自分の家はもとより時代へ厳しい批判精神をもち、それを公言して憚らなかった京都人なのでした。1千年有余の歴史を有し伝統を保ちつつ、京都が革新の都といわれる所以はここにも見られると思います。
漱石は祇園の一力で舞妓の運ぶ薄茶を喜んで喫しています。展覧会では茶道具の名品を手帳に書き付けています。そして漱石は乾山の向付けの一揃いを見つけそれを津田青楓に贈ってもいます。茶道そのものを嫌っていたのではありません。
漱石は、東京に帰ってからは「京都の閑雅をひとり懐かしんでいます、また行くつもりです」と書簡に書きながら、大正5年12月9日に、49歳の生涯を終えたのでした。
(後略) ≫
(参考その二) 「漱石遺墨について」周辺
file:///C:/Users/user/Downloads/8011_0005_05.pdf
(抜粋)
1.漢詩( 『不成帖』 )
2.椿図( 『不成帖』 )
3.春蘭図( 『画帖』 )
4.竹林図( 『不成帖』 )
5.藤花図( 『観自在帖』 )
6.牡丹図( 『観自在帖』 )
7.松林図( 『観自在帖』 )
8.春蘭図ヵ( 『不成帖』 )
9.竹石図( 『観自在帖』 )
10.芭蕉図( 『咄哉帖』 )
11.椿図
12.東家西屋図( 『画帖』 )
.jpg)
「観自在帖(全作品紹介)」
https://hzrhq.agaterlm.top/index.php?main_page=product_info&products_id=30145
≪右一列上段「観自在帖(1)」→「観自在(漱石題)/紙本墨書・淡彩・24.4×36.3㎝」
右一列中段「観自在帖(2)」→「藤花図」/同上」
右一列下段「観自在帖(3)」→「隔水東西住」/同上」
右二列上段「観自在帖(4)」→「竹図」/同上」
右二列中段「観自在帖(5)」→「渡尽東西水」/同上」
右二列下段「観自在帖(6)」→「鉢花図」/同上」
右三列上段「観自在帖7)」→「柳芽を」/同上」
右三列中段「観自在帖(8)」→「牡丹図」/同上」
右三列下段「観自在帖(9)」→「起臥乾抻」/同上」
右四列上段「観自在帖10)」→「松林図」/同上」
右四列中段「観自在帖(11)」→「二十年来愛碧林/同上」
右四列下段「観自在帖(12)」→「竹石図/同上」
≪ 観自在とは、迷いの執念から解放された境界にあって、事物のすがたが自由自在に正しくみきわめられることを意味する仏教語。
.jpg)
「観自在帖(1)」→「観自在(漱石題)」
https://jp.mercari.com/item/m87413254274
大正四年の春、漱石は京都に旅したが、病臥した。その後、小康を得て、乞わるるままに、小品の書画を楽しみながら書いた。贈られた磯田家では、この書画帖の巻頭の書「観自在」(上記図)をとって「観自在帖」と名付けている。
画帖は「観自在」に続いて「藤花図」(「観自在帖(2)」)「隔水東西住」(「観自在帖(3)」)の五言絶句に展開される。
隔水東西住 (水を隔てて東西に住み)
白雲往又還 (白雲往(ゆ)きて又(また)還(かえ)る)
東家松籟起 (東家(とうか)に松籟起(お))これば)
西屋竹珊々 (西屋(せいおく)竹) 珊々(さんさん))
この詩は、大正五年初夏頃の「断片」にも載っているが、そこでは「白雲」は「閑雲」、「又」は「復」と改められている。『漱石全集』では「又」は「也(また)」となっている。
松籟は松風、珊々は、もとは玉のふれあう音から竹の葉のそよぎを形容している。最後の句に呼応して水墨の「竹図」(「観自在帖(4)」)がある。
次の「渡尽東西水」(「観自在帖(5)」)には、
渡尽東西水 (渡り尽くす東西の水)
三過翠柳橋 (三(み)たび過(す)ぐ翠柳(すいりゅう)の橋)
春風吹不断 (春風(しゅんぷう)吹いて断(た)たず)
春恨幾條々 (春恨(しゅんこん)幾條々(いくじょうじょう))
春日偶成 漱石
の五言絶句があって、これは明治四十五年(一九一二)五月二十四日の「春日偶成 十首」中の最後の詩。
修善寺大患の『思ひ出す事など』以後、約一年半ばかり、全く作詩から遠ざかっていた漱石は、この「春日偶成 十首」以後、盛んに作詩した。しかし、それまでと趣を異にして、南画の賛、題詩の類か、少なくとも南画的光景を詠じたものばかりといっていいのが特色だと『漱石の漢詩』の中に松岡譲は述べている。
この詩は旧作だが「観自在帖」に入れるにふさわしいと思ったのであろう。吉川幸次郎氏は『漱石詩注』で、「渡尽東西水」は明の高青邱(こうせいきゅう)の「胡隠君(こいんくん)を尋ぬ」に「水を渡り復(また)水を渡る。花を看(み)て還(また)花を看る。春風江上の路、覚えず君が家に到る」があり、これはこの句を導いたのであろうと述べている。それはそれとして、前掲(8図=「木屋町の宿をとりて川向の御多佳さんに」の前書がある「春の川を隔てて男女哉」)の「春の川を隔てて男女哉」の情緒につながるものを、かつての作に感じて、記したように思えてならない。
なお、大正三年の作「同じ橋三たび渡りぬ春の宵」は、この漢詩と通ずるものがある。
「観自在帖(6)」は、可憐な花をつけた木を描いた「鉢花図」。
「観自在帖7)」は、
柳芽(やなぎめ)を吹いて四条のはたごかな 漱石
の俳句で、大正四年四月、京都にて作った八句中の第一句。
漱石の約一か月の京都滞在中の句で、続いて次の句がある。
見あぐれば坂の上なる柳かな
筋違に四条の橋や春の川
鴨川に面した宿の二階の部屋に通されたというが、久しぶりに京都の春景色に、旅情を感じている漱石の感慨が示されている。また「はたご」という古風な語が、いかにも京都の土地がらにふさわしい。
次の「観自在帖8)」は、満開の牡丹、蕾の牡丹を描いた「牡丹図」(下記の図)。
.jpg)
「観自在帖(8)」→「牡丹図」
https://jp.mercari.com/item/m87413254274
「観自在帖(9)」の「起臥乾抻」は、
起臥乾抻一草亭 (起臥す乾抻一草亭(けんこんいっそうてい))
眼中只有四山青 (眼中只有り四山の青(せい))
閑来放鶴長松下 (閑来(かんらい)鶴を放(はな)つ長松(ちょうしょう)の下)
又上虚堂読易経 (又(ま)た虚堂(きょどう)に上(のぼ)って易経を読む)
の七言絶句で、「閑来放鶴図」(下記の図)の題賛のみを書いたもの。『漱石全集』では「只」が「唯」となっている。
(付記) 「閑来放鶴図」
≪大正三年の題賛。漱石の理想境と思われるところを実に丹念に描き、この画は代表作の一つと目せられている。印は白文方印「漱石」。≫(『俳人の書画美術8 漱石』所収「作品解説39・40(福田清人稿)」)

「閑来放鶴図自画賛」紙本着色/146.0×39.0㎝
https://aucview.aucfan.com/yahoo/d205942908/

「(観自在帖10)」→「松林図」
https://hzrhq.agaterlm.top/index.php?main_page=product_info&products_id=30145
「(観自在帖10)」は、松林の中に庵があり、対話する二人の人物を配した「松林図」(上記の図)。
そして、「観自在帖(11)」は、次の七言絶句(「二十年来愛碧林」)。
二十年来愛碧林 (二十年来碧林(へきりん)を愛す)
山人須解友虚心 (山人(さんじん)須(す)べからく解す虚心を友とするを)
長毫漬墨時如雨 (長毫(ちょうもう)漬墨(しぼく)時に雨の如し)
欲写鏗鏘戞玉音 (写さんと欲(ほっ))す鏗鏘(こうしょう) 戞玉(かつぎょく)の音(ね))
碧林は青い竹林、山人は山の隠士、長毫は毛の長い筆、漬墨はにじんだ墨、鏗鏘は金属や玉がふれあって鳴る音、戞玉はふれあう玉。この詩は大正三年の画賛であるが「題竹」として、「観自在帖」のために重ねて書いた。
最後の「観自在帖(12)」岩に竹を配し、淡彩で描いた「竹石図」。詩句六点、画六点で「観自在帖」は構成されている。 ≫(『俳人の書画美術8 漱石』所収「作品解説14~25(福田清人稿)」)
この「観自在帖」は、「漢詩」(「観自在帖(3)」・「観自在帖(5)」・「観自在帖(9)」・「観自在帖(11)」)、「俳句」(「観自在帖7)」→「柳芽を」)、「書」(「観自在帖(1)」→「観自在(漱石題)」)、「南画」(「観自在帖10)」→「松林図」)、そして、「俳画」(「観自在帖(2)」・「観自在帖(4)」・「観自在帖(6)」・「観自在帖(8)」・「観自在帖(12)」」)と、漱石の世界の全貌を探索する上で、その総決算的な意味合いがあるものと解したい。
因みに、「俳句」(「観自在帖7)」→「柳芽を」)関連は、次の八句ということになる。
大正4年(1915年)
2437 柳芽を吹いて四条のはたごかな
≪季=柳の芽(春) ※2443までの七句は京都での作。漱石は三月十九日から四月十六日まで京都に滞在した。この句はこの滞在中に磯田多佳(2440参照)に贈った画帖『観自在帖』に記されている。◇全集(大6)が「四月京都にて 八句」として収める(ただし、八句のうち一句は、(2372))に同じ)。 ≫
2438 筋違に四条の橋や春の川
≪季=春の川。※筋違(すじかい)は斜め、はすかい。蕪村の句に「ほととぎす平安城を筋違に」があり、漱石は『創作家の態度』でこの句について言及している。 ≫(『漱石全集第十七巻・坪内稔典注解』)
2439 紅梅や舞の地を弾く金之助
≪季=紅梅(春)。※金之助は祇園 の芸妓の名。本名梅垣きぬ。≫(「同上」)
木屋町に宿とりて川向
の御多佳さんに(一句)
2440 春の川を隔てゝ男女かな
≪季=春の川。京都の漱石の宿は木屋町三条上ルにあった北大嘉(きたのたいが)。多佳は祇園 大友(だいとも)の女将、磯田多佳。鴨川の東に大友が、西に北大嘉があった。後略≫(「同上」)
2441 萱草の一輪咲きぬ草の中
≪季=萱草(かんぞう)=夏。※画賛の句。萱草はユリ科の多年草。夏に百合に似た橙赤色の花を一日だけ開く。忘れ草。西川一草亭が画いた萱草の絵に賛をしたものが知られている(『夏目漱石遺墨集』第三巻)。 ≫(「同上」)
2442 牡丹剪つて一草亭を待つ日哉
≪季=牡丹(夏)。※自画賛の句。一草亭は華道去風流の西川一草亭。実弟が津田青楓であり、漱石は京都滞在中に親しく交わった。≫(「同上」)
(付記) 「牡丹剪つて一草亭を待つ日哉(漱石)」自画賛(周辺)
https://rendezvou.exblog.jp/5253202/

「牡丹剪つて一草亭を待つ日哉(漱石)」自画賛図
牡丹剪って一草亭を待つ日かな 漱石
2443 椿とも見えぬ花かな夕曇
≪季=椿(春)。※自画賛の句。≫(「同上」)
大正3年(1914年)
2372 見上ぐれば坂の上なる柳哉
≪季=柳(春)。≫(「同上」)
(参考その一)「津田青楓・西川一草亭 と 漱石の交友」周辺
https://rendezvou.exblog.jp/6290544/
≪ 漱石と京都、学問の繋がりでは松本文三郎、狩野亨吉がいずれも京都帝国大学(旧文科大学)の長であり、漱石へ教師として講座を依頼していました。明治40年4月、漱石は京都の銀閣寺北にあった松本文三郎の山房に招かれその礼状を送っています。
「拝啓 京都滞在中は尊来を辱ふせるのみならず銀閣の仙境に俗塵を振るひ落し候」
市街と離れたこの地を漱石はたいへん気に入り、東京付近ではこんな住居は求められないと賞賛しています。しかし、41年6月、書状で教師就任と講義の件は断っているのです。狩野亨吉とも同じやりとりがあったは史実に遺されている処です。
ただ、これら碩学の友人は当時京都在住ではありましたが、故郷は別にあり後に京都を去った人でした。京都に生まれ育ったきっすいの京都人で、親密な知人といえば、津田青楓と西川一草亭きょうだいを措いてはないと思われます。今回はこのふたりにスポットを当ててみることにいたしましょう。
☆フランス帰りの青年画家・津田青楓
漱石門下の小宮豊隆の仲介で津田青楓が漱石に逢ったのは明治44年。京都に育ち、日露戦争が終わると官費でフランスに3年間留学した貧しい青年画家で、帰国してまもなく京都から東京に出た頃でした。本名津田亀次郎、雅号青楓。
彼は、フランスで日本人の仲間が落ち合うレストランでの思い出を述懐しています。留学生の彼らは、漱石の『坊っちゃん』や『我輩は猫である』『草枕』の掲載されている雑誌を持ち込み朗読していたそうです。
津田と共にいた安井(安井曽太郎)は新参者であり、朗読するのは古参の留学生ら。
「茶と聞いて少し辟易した。世間に茶人程勿体ぶった風流人はない。広い視界をわざとらしく窮屈に縄張りをして、極めて自尊的に、極めてことさらに、極めてせせこましく、必要もないのに、鞠躬如(きっきゅうじょ)として、あぶくを飲んで結構がるものは所謂茶人である…」
『草枕』の一節を聞いては「愉快だね」と、うれしがる古参者ら。津田はそれを横目で見ながらこの時、漱石に親愛の情を感じはじめたと書いています。
けれども、彼の父親は去風洞挿花家元西川源兵衛(一葉)であり、また表千家の茶人でもあったのですから、皮肉なものです。明治44年、縁あって漱石門下に入ることになります。漱石にとっては趣味にしている描画のよき相談相手になり、心許せる門下生でありました。津田が漱石山房に出入りするようになった後、実兄の西川一草亭をまた漱石に引き合わせるのでした。
津田清楓は述べています。
「京都はいやだった。親兄弟のお付き合いばかりして、やれお花見だ、やれお茶会だ、やれなんだかんだで引っ張り出されることばかしで、仕事なんかするひまはない。京都の人間は画家は風流人で、風流人は閑人だと思っているんだ。やりきれない…」
漱石と散歩しながらの話を彼はこんな風に書いています。
「君の親の商売は何だと云われるので、一寸嫌だったが思い切って、花屋です、店では花屋で奥では生花の先生です」といい、父は風雅な風采をして茶ばかり啜っていると云った後で、
「だから僕を学校にもやってくれないで、小学校を出ると丁稚にやらされて、それ家を飛び出して孤児のように自分でやっとここまでこぎつけたのです」
長男は特別で次男以下は同等ではなかった明治の家族制度を思いますと、こうした話も理解できるのではないでしょうか。いっぽう、兄の西川一草亭は長男として教育も受け家業を継ぎました。去風洞挿花をさらに盛り立て、『瓶史』を刊行する著名な文化人となっていました。
☆去風洞主人・西川一草亭
漱石は、大正4年3月21日、京都滞在中に西川一草亭の招きで彼の住居である茶室を訪れています。まず、漱石自身の筆記を見ることにいたします。
漱石全集 大正4年 日記14 (日記・断片 下)
「二一日(日)
八時起る。下女に一体何時に起ると聞けば大抵八時半か九時だといふ。夜はと聞けば二時頃と答ふ。驚くべし。」
漱石は旅館の女中の生活を聞き、労働時間が長いのに驚いています。それから宿の窓からのぞむ加茂川とかなたの東山が霞でよく見えないのに河原で合羽を干すさまを書きとめています。
☆漱石 去風洞・小間の茶室に入る
「東山霞んで見えず、春気曖、河原に合羽を干す。西川氏より電話可成(なるべく)早くとの注文。二人で出掛ける。去風洞といふ門をくぐる。奥まりたる小路の行き当たり、左に玄関。くつ脱ぎ。水打ちて庭樹幽すい、寒きこと夥し。」
寒がりの漱石はここでも京の底冷えの寒さに震え上がっています。数奇屋の庭はこの時期殺風景な感じもあったでしょうし、待合の座敷から暖かい陽光の遮られた暗い茶室へ入り、心寒いばかりの想いがあったのではないでしょうか。それでも漱石の観察眼はするどく克明に記憶にとどめています。
「床に方祝の六歌仙の下絵らしきもの。花屏風。壁に去風洞の記をかく。黙雷の華厳世界。一草亭中人。御公卿様の手習い机。茶席へ案内、数奇屋草履。石を踏んでし尺(しせき)のうちに路を間違へる。再び本道に就けばすぐ茶亭の前に行きつまる。どこから這入るのかと聞く。戸をあけて入る。方三尺ばかり。ニジリ上り。」
ここは、露地を歩きながら茶室への方向を間違え、やっと茶室のにじり口を見つけたところです。武士も刀を外して身分の上下なく入る狭き入り口なのです。漱石はどうやら身をかがめて茶室内に入ったようです。
「更紗の布団の上にあぐらをかき壁による。つきあげ窓。それを明けると松見える。床に守信の梅、「梅の香の匂いや水屋のうち迄も」といふ月並みな俳句の賛あり。」
暗い茶室内には天井に突き上げ窓が開けられていました。ここから自然光が入る仕組みになっているのです。しかし、同時に冷気も入ったことでしょう。次に懐石料理が書かれています。この去風洞の近くに「松清」という料理屋があり、亭主は懐石をそこから取り寄せたもようです。
☆懐石料理の献立はどういうものだったか
「料理 鯉の名物松清。鯉こく。鯉のあめ煮。鯛の刺身、鯛のうま煮。海老の汁。茶事をならはず勝手に食ふ。箸の置き方、それを膳の中に落とす音を聞いて主人が膳を引きにくるのだといふ話を聞く。最初に飯一膳、それから酒といふ順序。」
(後略)
箸の置き方、それを膳の中に落とす音を聞いて主人が膳を引きにくるのだ、のくだりは、茶道で懐石の作法になっているものです。客は食事が終わった合図として、静かに箸を膳の上に落とし亭主に知らせ、主はその音を水屋で聞くとすぐに膳を引きに来るわけです。
ところで、この献立を見るかぎりでは、西川一草亭は茶事を余りしていなかったのではないかと私は思います。理論はできても茶道の基本的な稽古をしていたかどうか…。父親から手前を習ったことはあるとだけ書かれています。
茶懐石では、海の幸、山の幸を少しづつとりまぜて消化の好い調理をし、無理なく食べられる分量で客に呈すのが本筋です。料理屋にまかせず亭主自ら客のことを考え吟味しなければいけません。しかし、この献立では胃腸の重篤な病をもつ漱石に如何なものかと思われてならないのです。
☆漱石「腹具合あしし」
案の定、漱石は23日の日記に「腹具合あしく且つ天気あしゝ。天気晴るれど腹具合なほらず。」とあるのです。翌24日には更に、腹具合は悪化します。
多佳女が云い出して北野天神の梅見の約束をしていたにも拘わらず、断りなく多佳が遠出していたことで漱石は深く傷つくのです。
「二十四日(水)
寒、暖なれば北野の梅を見に行こうと御多佳さんがいふから電話をかける。御多佳さんは遠方に行って今晩でなければ帰らないから夕方懸けてくれといふ。夕方懸けたって仕方がない。(中略)腹具合あしし。」
この時漱石は東京に帰るべく、「晩に気分あしき故明日出立と決心す」といったんは京都を離れる決意をしたのでした。この危機的状況を救ったのがまた津田青楓その人でした。
付きっ切りで看病する津田は多佳女に懸命にとりなすように依頼し、祇園の芸妓で漱石信奉者のお君さん、金之助にも来て貰い、最悪の状態を切り抜けました。京都滞在はこの後更に続くことになります。
「二十五日
御多佳さんが来る。出立ちをのばせと云ふ。医者を呼んで見てもらえと云ふ。(中略)多佳さんと青楓君と四人で話しているうちに腹具合よくなる。」
結局、漱石は翌月の4月16日まで、都合二十九日間京都に滞在したのです。東京へ帰ってから胃腸の病は深刻になり、翌月大正5年の12月9日までその病苦は続きました。
☆西川一草亭に漱石は感想をのべる
「漱石と庭」と題した一草亭のエッセイに、漱石が来庵した折の事柄が興味深く書かれています。その一部分を抜粋します。
「夏目さんの来られたのは三月の末で、さう云ふ時分にこう云ふ家を見ると只陰気で不愉快なばかりだった。夏目さんはその暗い陰気な座敷の床の前に坐って、欄間に懸かっている「一草亭中之人」と云ふ夏目さん自身の字を眺めたり、床の間に生けておいた室咲きの牡丹の花を見たりして、最後に此処の家賃はいくらするかねと尋ね、「こんな家は只でも嫌だね」と云って心から嫌な顔をされた。」
まあ、客としては失礼な物言いですが、体調の悪い人への亭主の心配りも「も一つ」だったようです。
江戸っ子漱石と京都、かならずしも相性は悪くなかったのです。相性が悪かったのは、京都の寒さだけだったのかもしれません
☆正直で飾り気のない交友
表裏のある狡猾な人間を嫌悪した漱石。それゆえに江戸っ子と自他ともに認めた気性でした。では、その対極にあるのが京都人だという世間の見方があるとすれば…。それは概には云えないのではないでしょうか。
西川・津田兄弟を見ましても自分の家はもとより時代へ厳しい批判精神をもち、それを公言して憚らなかった京都人なのでした。1千年有余の歴史を有し伝統を保ちつつ、京都が革新の都といわれる所以はここにも見られると思います。
漱石は祇園の一力で舞妓の運ぶ薄茶を喜んで喫しています。展覧会では茶道具の名品を手帳に書き付けています。そして漱石は乾山の向付けの一揃いを見つけそれを津田青楓に贈ってもいます。茶道そのものを嫌っていたのではありません。
漱石は、東京に帰ってからは「京都の閑雅をひとり懐かしんでいます、また行くつもりです」と書簡に書きながら、大正5年12月9日に、49歳の生涯を終えたのでした。
(後略) ≫
(参考その二) 「漱石遺墨について」周辺
file:///C:/Users/user/Downloads/8011_0005_05.pdf
(抜粋)
1.漢詩( 『不成帖』 )
2.椿図( 『不成帖』 )
3.春蘭図( 『画帖』 )
4.竹林図( 『不成帖』 )
5.藤花図( 『観自在帖』 )
6.牡丹図( 『観自在帖』 )
7.松林図( 『観自在帖』 )
8.春蘭図ヵ( 『不成帖』 )
9.竹石図( 『観自在帖』 )
10.芭蕉図( 『咄哉帖』 )
11.椿図
12.東家西屋図( 『画帖』 )
夏目漱石の「俳句と書画」(その十四) [「子規と漱石」の世界]
その十四 漱石の「漢詩と書画」周辺
E383BBE983A8E58886E59BB3.jpg)
「崖臨碧水図自画賛(漱石)」(部分図)
E383BBE585A8E4BD93E59BB3.jpg)
「崖臨碧水図自画賛(漱石)」紙本着色/134.0×33.0㎝
https://nipponkanshi.hankeidou.jp/2016/08/2016080702-242dd1bf16a.html
≪厓臨碧水老松愚 (厓は碧水に臨んで 老松 愚なり)
路過危橋仄徑迂 (路は危橋を過ぎて 仄径 迂なり)
佇立筇頭雲起處 (佇立す 筇頭に雲起こる処)
半空遙見古浮圖 (半空 遥かに見る 古浮図) ≫
≪ 七言絶句は大正三年作。仄徑(そくけい)はかすかな小道。筇頭(きょうとう)は杖の頭。
古浮圖(こふと)は古い寺塔。印は白文方印で「漱石」とある。 ≫(『俳人の書画美術8 漱石』所収「作品解説38(福田清人稿)」)
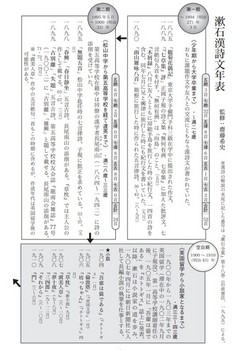
「夏目漱石の漢詩(石川忠久稿))所収「漱石漢詩文年表(斎藤希文監修)」)その一
https://www.taishukan.co.jp/files_upload/upload/owned_media_magazine/journalkanbun203.pdf

「夏目漱石の漢詩(石川忠久稿)」所収「漱石漢詩文年表(斎藤希文監修)」その二
https://www.taishukan.co.jp/files_upload/upload/owned_media_magazine/journalkanbun203.pdf
夏目漱石の「詩(漢詩)と画(南画)の世界」というのは、上記の「夏目漱石の漢詩(石川忠久稿)」所収「漱石漢詩文年表(斎藤希文監修)」の、その「第四期(1912年5月~1916(大正5年)春)・満四五~四九歳」の時代ということになる。
その中で、≪〔題自画〕「山上有山路不通」七言絶句。自らの画に題した最初の詩≫の、
その「山上有山路不通」(七言絶句)は次のものである。
.jpg)
「山上有山路自画賛(漱石)」紙本着色/66.5×45.0㎝
https://nipponkanshi.hankeidou.jp/2016/08/2016080701-6b734ac079c4.html
≪山上有山路不通 (山上に山有りて 路 通ぜず)
柳陰多柳水西東 (柳陰に柳多くして 水 西東)
扁舟盡日孤村岸 (扁舟 尽日 孤村の岸)
幾度鵞群訪釣翁 (幾度か鵞群 釣翁を訪ふ) ≫
≪大正元年十一月作。扁舟は小舟。盡日は終日。釣翁は年老いた釣り人。この頃からしきりに画を描き、自作の題詩を賛し、楽しんだ。対岸に白く塗り残しになっているいくつかりの斑点は、どうやら鵞の群らしいと松岡譲は述べている。なお、四句目の「幾度鵞群」の下にある「知波頭」が,『漱石詩集』になく、削られている。七言絶句であるから、賛の字数はおかしいわけである。なお、印は朱文円印「漱石」 ≫(『俳人の書画美術8 漱石』所収「作品解説41(福田清人稿)」)
夏目漱石の生涯というのを、鳥瞰的・概括的に考察するときに、上記の「夏目漱石の漢詩(石川忠久稿))所収「漱石漢詩文年表(斎藤希文監修)」は、多くの示唆を投げ掛けてくれる。
以下(参考その一)に、その「抜粋」(第一期~第五期)に対応して、「俳句の時代」・「作家(小説家)の時代」・「漢詩(南画)の時代」などのネーミングを付すると、次のとおりとなる。
そして、上記の「崖臨碧水図自画賛(漱石)」と「山上有山路自画賛(漱石)」とは、≪第四期1912 年 5 月〜 1916(大正5)年春 →「漢詩(南画)の時代」≫の代表作ということになる。
【(参考その一) 「夏目漱石の漢詩(石川忠久稿))所収「漱石漢詩文年表(斎藤希文監修)」(抜粋)
第一期〜 1894(明治27)年3 月 → 「修養期」
《少年期から大学卒業まで》・〜満二七歳
おもに課題作文や友人との交流にともなう漢詩文が書かれていた。
第二期1895 年 5 月〜 1900(明治33)年 → 「俳句の時代」
《松山中学から第五高等学校を経て渡英まで》・満二八歳〜三三歳
第五高等学校在籍中は同僚の漢学者長尾雨山(ながおうざん)(一八六四〜一九四二)に詩の添削を受けていた。
空白期1900 〜 1910(明治 43)年 → 「作家(小説)の時代」
《英国留学から小説家となるまで》・満三三〜四三歳
一九〇〇年から一九〇三年までの英国留学(滞在中の一九〇二年九月に子規没)、第一高等学校講師着任の後、一九〇五年一月に「吾輩は猫である」を「ホトトギス」誌上に発表。
以降、漱石は小説家の道を歩み、一九〇七年四月には朝日新聞社に入社して長編小説の執筆を仕事とする。
第三期1910(明治43)年 7 〜10 月 → 「病臥・転換期」
《修禅寺大患前後》・満四三歳
胃潰瘍による入院を機に再び詩を作り始める。とくに修禅寺大患後の作が多い。
第四期1912 年 5 月〜 1916(大正5)年春 →「漢詩(南画)の時代」
《詩と画の世界》・満四五〜四九歳
この時期の漱石は好んで南画を描くようになり、しばしば自ら詩を題した。また、人に求められて書いた作も少なくない。
第五期1916(大正 5)年 8 月〜 11 月20 日 「最晩年期」
《『明暗』執筆期》・満四九歳
七言律詩を作ることを日課とし、生涯で最も集中して詩が作られた時期。 】
【(参考その二) 「第七講 漱石の美術批評」(抜粋)
https://www.iwanami.co.jp/files/tachiyomi/pdfs/0291360.pdf
晩年に描かれた南画山水を見ると、漱石がいかに描くという行為に没頭し、そこに自分の世界をかったかと思われてならない。それが、漱石の自己本位を基本とする作家のあるべき態度だったかいなかったはずである。私には、この場合の「人が見て」というのは「自分が見て」と同じではなだからといって、漱石はそのために何か具体的な努力をするとか技術的な工夫をしようとは思ってほぼ同様の文面が見られることからも、これが漱石の本心から出たものであることは疑いないが、りません」 ( 「津田青楓宛書簡」大正二年十二月八日付) という言葉がある。
同日、野上豊一郎宛にも気持のする奴をかいて死にたいと思ひます文展に出る日本画のやうなものはかけてもかきたくはあら人が見て難有い心持のする絵を描いて見たい山水でも動物でも花鳥でも構はない只崇高で難有い築き上げていったかが伝わってくる。しばしば引用される漱石の言葉に「私は生涯に一枚でいゝからである。そして、何よりも、漱石にとって絵を描くことは自己を映し出すことであり、自己を実以上を要すれば、漱石にとって美術とは、孤独を慰める話し相手、創作に刺激をもたらす良き友、自己を映し出し実現することのできる分身のような存在であったという言い方も可能であろう。 】
E383BBE983A8E58886E59BB3.jpg)
「崖臨碧水図自画賛(漱石)」(部分図)
E383BBE585A8E4BD93E59BB3.jpg)
「崖臨碧水図自画賛(漱石)」紙本着色/134.0×33.0㎝
https://nipponkanshi.hankeidou.jp/2016/08/2016080702-242dd1bf16a.html
≪厓臨碧水老松愚 (厓は碧水に臨んで 老松 愚なり)
路過危橋仄徑迂 (路は危橋を過ぎて 仄径 迂なり)
佇立筇頭雲起處 (佇立す 筇頭に雲起こる処)
半空遙見古浮圖 (半空 遥かに見る 古浮図) ≫
≪ 七言絶句は大正三年作。仄徑(そくけい)はかすかな小道。筇頭(きょうとう)は杖の頭。
古浮圖(こふと)は古い寺塔。印は白文方印で「漱石」とある。 ≫(『俳人の書画美術8 漱石』所収「作品解説38(福田清人稿)」)
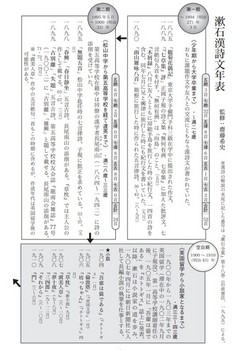
「夏目漱石の漢詩(石川忠久稿))所収「漱石漢詩文年表(斎藤希文監修)」)その一
https://www.taishukan.co.jp/files_upload/upload/owned_media_magazine/journalkanbun203.pdf

「夏目漱石の漢詩(石川忠久稿)」所収「漱石漢詩文年表(斎藤希文監修)」その二
https://www.taishukan.co.jp/files_upload/upload/owned_media_magazine/journalkanbun203.pdf
夏目漱石の「詩(漢詩)と画(南画)の世界」というのは、上記の「夏目漱石の漢詩(石川忠久稿)」所収「漱石漢詩文年表(斎藤希文監修)」の、その「第四期(1912年5月~1916(大正5年)春)・満四五~四九歳」の時代ということになる。
その中で、≪〔題自画〕「山上有山路不通」七言絶句。自らの画に題した最初の詩≫の、
その「山上有山路不通」(七言絶句)は次のものである。
.jpg)
「山上有山路自画賛(漱石)」紙本着色/66.5×45.0㎝
https://nipponkanshi.hankeidou.jp/2016/08/2016080701-6b734ac079c4.html
≪山上有山路不通 (山上に山有りて 路 通ぜず)
柳陰多柳水西東 (柳陰に柳多くして 水 西東)
扁舟盡日孤村岸 (扁舟 尽日 孤村の岸)
幾度鵞群訪釣翁 (幾度か鵞群 釣翁を訪ふ) ≫
≪大正元年十一月作。扁舟は小舟。盡日は終日。釣翁は年老いた釣り人。この頃からしきりに画を描き、自作の題詩を賛し、楽しんだ。対岸に白く塗り残しになっているいくつかりの斑点は、どうやら鵞の群らしいと松岡譲は述べている。なお、四句目の「幾度鵞群」の下にある「知波頭」が,『漱石詩集』になく、削られている。七言絶句であるから、賛の字数はおかしいわけである。なお、印は朱文円印「漱石」 ≫(『俳人の書画美術8 漱石』所収「作品解説41(福田清人稿)」)
夏目漱石の生涯というのを、鳥瞰的・概括的に考察するときに、上記の「夏目漱石の漢詩(石川忠久稿))所収「漱石漢詩文年表(斎藤希文監修)」は、多くの示唆を投げ掛けてくれる。
以下(参考その一)に、その「抜粋」(第一期~第五期)に対応して、「俳句の時代」・「作家(小説家)の時代」・「漢詩(南画)の時代」などのネーミングを付すると、次のとおりとなる。
そして、上記の「崖臨碧水図自画賛(漱石)」と「山上有山路自画賛(漱石)」とは、≪第四期1912 年 5 月〜 1916(大正5)年春 →「漢詩(南画)の時代」≫の代表作ということになる。
【(参考その一) 「夏目漱石の漢詩(石川忠久稿))所収「漱石漢詩文年表(斎藤希文監修)」(抜粋)
第一期〜 1894(明治27)年3 月 → 「修養期」
《少年期から大学卒業まで》・〜満二七歳
おもに課題作文や友人との交流にともなう漢詩文が書かれていた。
第二期1895 年 5 月〜 1900(明治33)年 → 「俳句の時代」
《松山中学から第五高等学校を経て渡英まで》・満二八歳〜三三歳
第五高等学校在籍中は同僚の漢学者長尾雨山(ながおうざん)(一八六四〜一九四二)に詩の添削を受けていた。
空白期1900 〜 1910(明治 43)年 → 「作家(小説)の時代」
《英国留学から小説家となるまで》・満三三〜四三歳
一九〇〇年から一九〇三年までの英国留学(滞在中の一九〇二年九月に子規没)、第一高等学校講師着任の後、一九〇五年一月に「吾輩は猫である」を「ホトトギス」誌上に発表。
以降、漱石は小説家の道を歩み、一九〇七年四月には朝日新聞社に入社して長編小説の執筆を仕事とする。
第三期1910(明治43)年 7 〜10 月 → 「病臥・転換期」
《修禅寺大患前後》・満四三歳
胃潰瘍による入院を機に再び詩を作り始める。とくに修禅寺大患後の作が多い。
第四期1912 年 5 月〜 1916(大正5)年春 →「漢詩(南画)の時代」
《詩と画の世界》・満四五〜四九歳
この時期の漱石は好んで南画を描くようになり、しばしば自ら詩を題した。また、人に求められて書いた作も少なくない。
第五期1916(大正 5)年 8 月〜 11 月20 日 「最晩年期」
《『明暗』執筆期》・満四九歳
七言律詩を作ることを日課とし、生涯で最も集中して詩が作られた時期。 】
【(参考その二) 「第七講 漱石の美術批評」(抜粋)
https://www.iwanami.co.jp/files/tachiyomi/pdfs/0291360.pdf
晩年に描かれた南画山水を見ると、漱石がいかに描くという行為に没頭し、そこに自分の世界をかったかと思われてならない。それが、漱石の自己本位を基本とする作家のあるべき態度だったかいなかったはずである。私には、この場合の「人が見て」というのは「自分が見て」と同じではなだからといって、漱石はそのために何か具体的な努力をするとか技術的な工夫をしようとは思ってほぼ同様の文面が見られることからも、これが漱石の本心から出たものであることは疑いないが、りません」 ( 「津田青楓宛書簡」大正二年十二月八日付) という言葉がある。
同日、野上豊一郎宛にも気持のする奴をかいて死にたいと思ひます文展に出る日本画のやうなものはかけてもかきたくはあら人が見て難有い心持のする絵を描いて見たい山水でも動物でも花鳥でも構はない只崇高で難有い築き上げていったかが伝わってくる。しばしば引用される漱石の言葉に「私は生涯に一枚でいゝからである。そして、何よりも、漱石にとって絵を描くことは自己を映し出すことであり、自己を実以上を要すれば、漱石にとって美術とは、孤独を慰める話し相手、創作に刺激をもたらす良き友、自己を映し出し実現することのできる分身のような存在であったという言い方も可能であろう。 】
夏目漱石の「俳句と書画」(その十三) [「子規と漱石」の世界]
その十三 漱石の「子規没後の俳句(その三)」(「明治四十五年/大正元年~」周辺)
「子規→虚子」の流れは、俳句結社(雑誌)の「ホトトギス」として、未だに、「俳句」界の、「定型俳句」(「自由律俳句」に対する「定型俳句)の牙城として君臨し続けている。
これに比して、「子規→碧悟桐」の流れ(「新傾向俳句」)を汲む、「自由律俳句」の「層雲」(荻原井泉水ら)や「海紅」(中塚一碧楼ら)は、多数派の「ホトトギス」に対して少数派ということになる。
もう一つ、「子規・漱石→東洋城」の、「俳諧=連句」と親近感を有する「定型俳句」(「俳諧の発句」的「伝統俳句」)を標榜する俳誌「渋柿」も、漱石門下の「小宮豊隆、寺田寅彦、安倍能成、鈴木三重吉」等々が参画して、さながら、「ホトトギス」の「虚子俳句」に対する、「渋柿」の「漱石俳句」という感すら抱かせるものがある。

「漱石山房と其弟子達」(津田清楓画)→A図
https://blog.goo.ne.jp/torahiko-natsume/e/6ad1c4767dddc3568e6b34e7d727b501
≪「上段の左から」→則天居士(夏目漱石)・寅彦(寺田寅彦)・能成(阿部能成)・式部官(松根東洋城)・野上(野上豊一郎)・三重吉(鈴木三重吉)・岩波(岩波茂雄)・桁平(赤木桁平)・百閒(内田百閒)
「下段の左から」→豊隆(小宮豊隆)・阿部次郎・森田草平/花瓶の傍の黒猫(『吾輩は猫である』の吾輩が、「苦沙弥」先生と「其門下生」を観察している。)
「則天居士」=「則天去私」の捩り=「〘連語〙 天にのっとって私心を捨てること。我執を捨てて自然に身をゆだねること。晩年の夏目漱石が理想とした心境で、「大正六年文章日記」の一月の扉に掲げてあることば。」(「精選版 日本国語大辞典」)
「天地人間」(屏風に書かれた文字)=「天地人」=「① 天と地と人。宇宙間の万物。三才。② 三つあるものの順位を表わすのに用いる語。天を最上とし、地・人がこれに次ぐ。
※落語・果報の遊客(1893)〈三代目三遊亭円遊〉「発句を〈略〉天地人を付ける様な訳で」(「精選版 日本国語大辞典」)→「2096 空に消ゆる鐸のひびきや春の塔(漱石・「前書」=「空間を研究せる天然居士の肖像に題す」)→「空間に生れ、空間を究(きわ)め、空間に死す。空たり間たり天然居士(てんねんこじ)噫(ああ)」(『吾輩は猫である』第三話)
↓
https://www.konekono-heya.com/books/wagahai3.html ≫
この「漱石山房と其弟子達」(津田清楓画)は、その姉妹画(『漱山と十大弟子(津田清楓著)』の挿絵)』関連のものがあって、それは下図のようなものがある。

津田青楓≪漱石と十弟子≫昭和51(1976)年/紙本著色/A4判用(縦30.9cm×横22.0cm×厚さ0.04cm)→B図
https://takadanobaba.keizai.biz/photoflash/2115/
https://soseki-museum.jp/user-guide/museum-shop/
≪ A図とB図とを比較すると、まず、A図(「則天居士」=漱石)B図(「漱石大明神」となり、A図(百閒)がB図(「筆者亀吉)」=「青楓」)となり、「弟子」(寅彦・能成・東洋城・豊一郎・三重吉・茂雄・桁平・豊隆・次郎・草平)も、そのネーミングを異にしている。
そして、屏風の文字も、A図「天地/人間」に比して、B図「地/非在天/人間」と様変わりをしている。≫
(追記) 夏目漱石俳句集(その九)<制作年順> 明45/大正元年(1912年)~大正5年(1916年)・年月不詳(2284~2527 )
明治45年/大正元年(1912年)
2284 雪の夜や佐野にて食ひし粟の飯
2285 壁隣り秋稍更けしよしみの灯
2286 懸物の軸だけ落ちて壁の秋
2287 行く春や壁にかたみの水彩画
2288 壁に達磨それも墨画の芒哉
2289 如意払子懸けてぞ冬を庵の壁
2290 錦画や壁に寂びたる江戸の春
2291 鼠もや出ると夜寒に壁の穴
2292 壁に脊を涼しからんの裸哉
2293 壁に映る芭蕉夢かや戦ぐ音
2294 壁一重隣に聴いて砧かな
2295 水盤に雲呼ぶ石の影すゞし
2296 湯壺から首丈出せば野菊哉
2297 五六本なれど靡けばすゝき哉
2298 蚊帳越しに見る山青し杉木立
2299 御かくれになつたあとから鶏頭かな
2300 厳かに松明振り行くや星月夜
2301 かりそめの病なれども朝寒み
2302 秋風や屠られに行く牛の尻
2303 橋なくて遂に渡れぬ枯野哉
2304 杉木立寺を蔵して時雨けり
2305 豆腐焼く串にはらはら時雨哉
2306 琴作る桐の香や春の雨
大正2年(1913年)
2307 人形も馬もうごかぬ長閑さよ
2308 菊一本画いて君の佳節哉
2309 四五本の竹をあつめて月夜哉
2310 萩の粥月待つ庵となりにけり
2311 葉鶏頭高さ五尺に育てけり
大正3年(1914年)
2312 播州へ短冊やるや今朝の春
2313 松立てゝ門鎖したる隠者哉
2314 春の発句よき短冊に書いてやりぬ
2315 冠を挂けて柳の緑哉
2316 鶯は隣へ逃げて藪つゞき
2317 つれづれを琴にわびしや春の雨
2318 欄干に倚れば下から乙鳥哉
2319 我一人行く野の末や秋の空
2320 内陣に仏の光る寒哉
2321 春水や草をひたして一二寸
2322 縄暖簾くゞりて出れば柳哉
2323 橋杭に小さき渦や春の川
2324 同じ橋三たび渡りぬ春の宵
2325 蘭の香や亜字欄渡る春の風
2326 老僧に香一しゅの日永哉
2327 竹藪の青きに梅の主人哉
2328 茶の木二三本閑庭にちよと春日哉
2329 日は永し一人居に静かなる思ひ
2330 世に遠き心ひまある日永哉
2331 線香のこぼれて白き日永哉
2332 留守居して目出度思ひ庫裏長閑
2333 我一人松下に寐たる日永哉
2334 引かゝる護謨風船や柳の木
2335 門前を彼岸参りや雪駄ばき
2336 そゞろ歩きもはなだの裾や春の宵
2337 春風に吹かれ心地や温泉の戻り
2338 仕立もの持て行く家や雛の宵
2339 長閑さや垣の外行く薬売
2340 竹の垣結んで春の庵哉
2341 玉碗に茗甘なうや梅の宿
2342 草双紙探す土蔵や春の雨
2343 桶の尻干したる垣に春日哉
2344 誰袖や待合らしき春の雨
2345 錦絵に此春雨や八代目
2346 京楽の水注買ふや春の町
2347 万歳も乗りたる春の渡し哉
2348 春の夜や妻に教はる荻江節
2349 木蓮に夢の様なる小雨哉
2350 降るとしも見えぬに花の雫哉
2351 春雨や京菜の尻の濡るゝほど
2352 落椿重なり合ひて涅槃哉
2353 木蓮と覚しき花に月朧
2354 永き日や頼まれて留守居してゐれば
2355 木瓜の実や寺は黄檗僧は唐
2356 春寒し未だ狐の裘
2357 寺町や垣の隙より桃の花
2358 見連に揃の簪土間の春
2359 染物も柳も吹かれ春の風
2360 連翹の奥や碁を打つ石の音
2361 春の顔真白に歌舞伎役者哉
2362 小座敷の一中は誰梅に月
2363 花曇り御八つに食ふは団子哉
2364 炉塞いで窓に一鳥の影を印す
2365 寺町や椿の花に春の雪
2366 売茶翁花に隠るゝ身なりけり
2367 高き花見上げて過ぎぬ角屋敷
2368 塗笠に遠き河内路霞みけり
2369 窓に入るは目白の八つか花曇
2370 静かなるは春の雨にて釜の音
2371 驢に騎して客来る門の柳哉
2372 見上ぐれば坂の上なる柳哉
2373 経政の琵琶に御室の朧かな
2374 楼門に上れば帽に春の風
2375 千社札貼る楼門の桜哉
2376 家形船着く桟橋の柳哉
2377 芝草や陽炎ふひまを犬の夢
2378 早蕨の拳伸び行く日永哉
2379 陽炎や百歩の園に我立てり
2380 ちらちらと陽炎立ちぬ猫の塚
2381 紙雛つるして枝垂桜哉
2382 行く春や披露待たるゝ歌の選
2383 眠る山眠たき窓の向ふ哉
2384 魚の影底にしばしば春の水
2385 四つ目垣茶室も見えて辛夷哉
2386 祥瑞を持てこさせ縁に辛夷哉
2387 如意の銘彫る僧に木瓜の盛哉
2388 馬を船に乗せて柳の渡哉
2389 田楽や花散る里に招かれて
2390 行春や僧都のかきし絵巻物
2391 行春や書は道風の綾地切
2392 藁打てば藁に落ちくる椿哉
2393 静坐聴くは虚堂に春の雨の音
2394 良寛にまりをつかせん日永哉
2395 一張の琴鳴らし見る落花哉
2396 春の夜や金の無心に小提灯
2397 局に閑あり静かに下す春の石
2398 春深き里にて隣り梭の音
2399 銀屏に墨もて梅の春寒し
2400 三味線に冴えたる撥の春浅し
2401 海見ゆる高どのにして春浅し
2402 白き皿に絵の具を溶けば春浅し
2403 筍は鑵詰ならん浅き春
2404 行く春のはたごに画師の夫婦哉
2405 行く春や経納めにと厳島
2406 行く春や知らざるひまに頬の髭
2407 鶯や髪剃あてゝ貰ひ居る
2408 活けて見る光琳の画の椿哉
2409 飯食へばまぶた重たき椿哉
2410 行春や里へ去なする妻の駕籠
2411 酒の燗此頃春の寒き哉
2412 晧き歯に酢貝の味や春寒し
2413 嫁の傘傾く土手や春の風
2414 春惜む日ありて尼の木魚哉
2415 業終へぬ写経の事や尽くる春
2416 春惜む茶に正客の和尚哉
2417 冠に花散り来る羯鼓哉
2418 門鎖ざす王維の庵や尽くる春
2419 春惜む句をめいめいに作りけり
2420 枳殻の芽を吹く垣や春惜む
2421 鎌倉へ下る日春の惜しき哉
2422 新坊主やそゞろ心に暮るゝ春
2423 桃の花隠れ家なるに吠ゆる犬
2424 草庵や蘆屋の釜に暮るゝ春
2425 牽船の縄のたるみや乙鳥
2426 三河屋へひらりと這入る乙鳥哉
2427 呑口に乙鳥の糞も酒屋哉
2428 鍋提げて若葉の谷へ下りけり
2429 料理屋の塀から垂れて柳かな
2430 酒少し徳利の底に夜寒哉
2431 酒少し参りて寐たる夜寒哉
2432 眠らざる夜半の灯や秋の雨
2433 電燈を二燭に易へる夜寒哉
2434 秋風の聞えぬ土に埋めてやりぬ
大正4年(1915年)
2435 春を待つ支那水仙や浅き鉢
2436 真向に坐りて見れど猫の恋
2437 柳芽を吹いて四条のはたごかな
2438 筋違に四条の橋や春の川
2439 紅梅や舞の地を弾く金之助
2440 春の川を隔てゝ男女かな
2441 萱草の一輪咲きぬ草の中
2442 牡丹剪つて一草亭を待つ日哉
2443 椿とも見えぬ花かな夕曇
2444 宝寺の隣に住んで桜哉
2445 白牡丹李白が顔に崩れけり
2446 木屋丁や三筋になつて春の川
2447 竹一本葉四五枚に冬近し
2448 女の子十になりけり梅の花
2449 水仙や早稲田の師走三十日
2450 水仙花蕉堅稿を照しけり
2451 菊の花硝子戸越に見ゆる哉
大正5年(1916年)
2452 春風や故人に贈る九花蘭
2453 白梅にしぶきかゝるや水車
2454 孟宗の根を行く春の筧哉
2455 梅早く咲いて温泉の出る小村哉
2456 いち早き梅を見付けぬ竹の間
2457 梅咲くや日の旗立つる草の戸に
2458 裏山に蜜柑みのるや長者振
2459 温泉に信濃の客や春を待つ
2460 橙も黄色になりぬ温泉の流
2461 鶯に聞き入る茶屋の床几哉
2462 鶯や草鞋を易ふる峠茶屋
2463 鶯や竹の根方に鍬の尻
2464 鶯や藪くゞり行く蓑一つ
2465 鶯を聴いてゐるなり縫箔屋
2466 鶯に餌をやる寮の妾かな
2467 温泉の里橙山の麓かな
2468 桃の花家に唐画を蔵しけり
2469 桃咲くやいまだに流行る漢方医
2470 輿に乗るは帰化の僧らし桃の花
2471 町儒者の玄関構や桃の花
2472 かりにする寺小屋なれど梅の花
2473 文も候稚子に持たせて桃の花
2474 琵琶法師召されて春の夜なりけり
2475 春雨や身をすり寄せて一つ傘
2476 鶯を飼ひて床屋の主人哉
2477 耳の穴掘つてもらひぬ春の風
2478 嫁の里向ふに見えて春の川
2479 岡持の傘にあまりて春の雨
2480 一燈の青幾更ぞ瓶の梅
2481 病める人枕に倚れば瓶の梅
2482 梅活けて聊かなれど手習す
2483 桃に琴弾くは心越禅師哉
2484 秋立つや一巻の書の読み残し
2485 蝸牛や五月をわたるふきの茎
2486 朝貌にまつはられてよ芒の穂
2487 萩と歯朶に賛書く月の団居哉
2488 棕櫚竹や月に背いて影二本
2489 秋立つ日猫の蚤取眼かな
2490 秋となれば竹もかくなり俳諧師
2491 風呂吹きや頭の丸き影二つ
2492 煮て食ふかはた焼いてくふか春の魚
2493 いたづらに書きたるものを梅とこそ
2494 まきを割るかはた祖を割るか秋の空
2495 饅頭に礼拝すれば晴れて秋
2496 饅頭は食つたと雁に言伝よ
2497 吾心点じ了りぬ正に秋
2498 僧のくれし此饅頭の丸きかな
2499 瓢箪は鳴るか鳴らぬか秋の風
年月不詳
2500 忠度を謡ふ隣や春の宵
2501 帰り路は鞭も鳴さぬ日永かな
2502 馬市の秣飛び散る春の風
2503 春雨や四国遍路の木賃宿
2504 野を焼た煙りの果は霞かな
2505 春の水馬の端綱をひたしけり
2506 鶯や障子あくれば東山
2507 鳴く蛙なかぬ蛙とならびけり
2508 大方はおなじ顔なる蛙かな
2509 遠雷や香の煙のゆらぐ程
2510 夏草の下を流るゝ清水かな
2511 蚊ばしらや断食堂の夕暮に
2512 蓮毎に来るべし新たなる夏
2513 そり橋の下より見ゆる蓮哉
2514 ひとむらの芒動いて立つ秋か
2515 びんに櫛そよと動きぬ今朝の秋
2516 うそ寒や綿入きたる小大名
2517 明けたかと思ふ夜長の月あかり
2518 吾猫も虎にやならん秋の風
2519 すゞなりの鈴ふきならす野分哉
2520 酔過ぎて新酒の色や虚子の顔
2521 長からぬ命をなくや秋の蝉
2522 いくさやんで菊さく里に帰りけり
2523 元禄の頃の白菊黄菊かな
2524 ふつゝかに生れて芋の親子かな
2525 行く年を隣の娘遂に嫁せず
2526 発句にもまとまらぬよな海鼠かな
2527 水仙や朝ぶろを出る妹が肌
(参考その一) 「夏目先生の俳句と漢詩(寺田寅彦)」周辺
https://www.aozora.gr.jp/cards/000042/files/43569_24585.html
夏目先生が未だ創作家としての先生自身を自覚しない前に、その先生の中の創作家は何処(どこ)かの隙間を求めてその創作に対する情熱の発露を求めていたもののように思われる。その発露の恰好(かっこう)な一つの創作形式として選ばれたのが漢詩と俳句であった。云わば遠からず爆発しようとする火山の活動のエネルギーがわずかに小噴気口の噴煙や微弱な局部地震となって現われていたようなものであった。それにしてもそのために俳句や漢詩の形式が選ばれたという事は勿論偶然ではなかったに相違ない。先生の自然観人世観が始めから多分に俳句漢詩のそれと共通なものを含んでいた事は明らかであるが、しかしまた先生が俳句漢詩をやった事が先生の自然観人世観にかなりの反作用を及ぼしたであろうという事も当然な事であろう。ともかくも先生の晩年の作品を見る場合にこの初期の俳句や詩を背景に置いて見なければ本当の事は分らないではないかと思う事がいろいろある。少なくも晩年の作品の中に現われている色々のものの胚子(はいし)がこの短い詩形の中に多分に含まれている事だけは確実である。
俳句とは如何なるものかという問に対して先生の云った言葉のうちに、俳句はレトリックのエッセンスであるという意味の事を云われた事がある。そういう意味での俳句で鍛え上げた先生の文章が元来力強く美しい上に更に力強く美しくなったのも当然であろう。また逆にあのような文章を作った人の俳句や詩が立派であるのは当然だとも云われよう。実際先生のような句を作り得る人でなければ先生のような作品は出来そうもないし、あれだけの作品を作り得る人でなければあのような句は作れそうもない。後に『草枕』のモニューメントを築き上げた巨匠の鑿(のみ)のすさびに彫(きざ)んだ小品をこの集に見る事が出来る。
先生の俳句を年代順に見て行くと、先生の心持といったようなものの推移して行った迹(あと)が最もよく追跡されるような気がする。人に読ませるための創作意識の最も稀薄な俳句において比較的自然な心持が反映しているのであろう。例えば修善寺における大患以前の句と以後の句との間に存する大きな距離が特別に目立つ、それだけでも覗(うかが)ってみる事は先生の読者にとってかなり重要な事であろうかと思われる。
色々の理由から私は先生の愛読者が必ず少なくもこの俳句集を十分に味わってみる事を望むものである。先生の俳句を味わう事なしに先生の作物の包有する世界の諸相を眺める事は不可能なように思われる。また先生の作品を分析的に研究しようと企てる人があらばその人はやはり充分綿密に先生の俳句を研究してかかる事が必要であろうと思う。
(昭和三年五月『漱石全集』第十三巻、月報第三号)
(参考その二) 「漱石の親友 天然居士・米山保三郎」周辺
https://rendezvou.exblog.jp/7067220/
学生時代の夏目金之助に作家になることを勧め漱石が彼の言葉に強く動かされた人物・米山保三郎のことはよく知られています。ただ、これまで研究者の中で誤解があり、漱石の語句の解釈に問題があるまま流布されてきたのが現状です。
「天然居士は空間を研究し、論語を読み、焼芋を食い、鼻汁を垂らす人である」
焼き芋と鼻汁を垂らす、これは禅の歴史に実在した中国の禅僧・懶さん(王ヘンに賛)和尚の故事から来る引用なのでした。漱石は畏敬する親友の米山保三郎へ深い愛情と禅に生きる彼を讃える意味で書いたものでしょう。しかし、世間一般ではなかなか通用しない事も充分知っていました。そうであるからこそ、『猫』のなかで次のように書いているのです。
「天然居士は空間を研究し、論語を読み、焼芋を食い、鼻汁を垂らす人である」
苦沙弥先生、一気呵成にこう書き流し、声を出してこれを読み、「ハハハ面白い」と笑うが、「うん。鼻汁を垂らすはさすがに酷だ、焼き芋も蛇足だ」と線を引き。結局「天然居士は空間を研究し論語を読む人である」だけにしたころで、これではあまりに簡単すぎると全部ボツにして、原稿用紙の裏に「空間に生れ、空間を究め、空間に死す。空たり間たり天然居士、噫」
実際、漱石はこの米山の兄、熊次郎から実弟の写真へ揮毫を懇望されて、漱石は俳句を書いています。その俳句とは、
空に消ゆる鐸のひびきや春の塔 という追悼の一句です。親友の死を悼む漱石の心情があふるるばかり、見事な名句と思います。写真は400X300mm、単身像の右側にこの句があり、左にこう記されています。
空間を研究する天然居士の肖像に題す 己酉 四月 漱石
己酉,となれば、1909年、明治四十二年です。漱石が朝日新聞社に入社して2年目の四月に詠んだものと明確に判るのが嬉しいところです。また、米山が鼻水を垂らすの表現がとかく世俗的に解釈され、漱石がいかにしてこの語句を入れたかということは研究者の間でないがしろにされて来ました。しかし、漱石がただ、ユーモラスにこんな語句を入れるはずはないのです。洟を垂らそうが自分は三昧になっているのだという仏道の修行による逸話なのです。
出典もありますから、その引用もしておきましょう。『碧巖録』第三十四則より。
「懶瓚和尚。隱居衡山石室中。唐德宗聞其名。遣使召之。使者至其室宣言。天子有詔。尊者當起謝恩。瓚方撥牛糞火。尋煨芋而食。寒涕垂頤未甞答。使者笑曰。且勸尊者拭涕。瓚曰。我豈有工夫為俗人拭涕耶。竟不起。使回奏。德宗甚欽嘆之。」
(懶瓚和尚、衡山石室の中に隱居す。唐の德、宗其の名を聞いて、使を遣して之を召す。使者、其の室に至つて宣言す。天子詔有り、尊者まさに起つて恩を謝すべし。瓚、まさに牛糞の火を撥つて、煨芋を尋ねて食す。寒涕、頤に垂れて未だ甞て答えず。使者笑つて曰く、且らく勸む、尊者、涕を拭え。瓚曰く、我れ豈に工夫の俗人の為に涕を拭くこと有らん耶といつて、竟に起たず。使、回つて奏す。德宗、甚だ之を欽嘆す。)
私は嘗て東慶寺の井上禅定和尚様から分かりやすいお話を聞いておりました。
昔、中国の偉い坊さんがあって皇帝が先生になってくれって勅使を迎えに遣るんだ。当時の中国では牛の糞の乾いたのを焚き付けにしてその牛糞の火の中へ芋をいれて焼いている処へ勅使が来た。らいさん和尚は牛糞の中から芋を掘り出して勅使に食えって云うんだ。勅使が見るとこの和尚、鼻水を垂らして下顎まで延びている。それを勅使は「まあ、洟を拭きなさいと云ったんだ。
なんだ、お前はそんな事で来たのか、勅使としておれを迎えに来たのではねえのか。おれが洟を垂らしていようがそんな事どうでもいい事だ、おれは三昧になっているんだ。っていう面白い問答があるんだよ。それを元にして漱石は「焼き芋を食らい、鼻汁を垂らす」てな、昔の懶瓚和尚がやったという事を思い出して書いているんだけれど、猫に笑われるから消しちゃうんだ。」(鎌倉漱石の会会報所載)
やはり禅定様の仰ることは納得のゆくものですね。
念のために付記しますと、漱石の友人で円覚寺・釈宗演の師である今北洪川について参禅をし、居士号を与えられた逸材が二人いました。無為という居士号は菅虎雄、天然の居士号は米山保三郎でした。米山は不運にも若くして病死したのでしたが、彼の伝記を漱石が書くという計画もあったと狩野亨吉は書いています。漱石がもう少し生きていたらなば実現したかも知れないのですが…。
「子規→虚子」の流れは、俳句結社(雑誌)の「ホトトギス」として、未だに、「俳句」界の、「定型俳句」(「自由律俳句」に対する「定型俳句)の牙城として君臨し続けている。
これに比して、「子規→碧悟桐」の流れ(「新傾向俳句」)を汲む、「自由律俳句」の「層雲」(荻原井泉水ら)や「海紅」(中塚一碧楼ら)は、多数派の「ホトトギス」に対して少数派ということになる。
もう一つ、「子規・漱石→東洋城」の、「俳諧=連句」と親近感を有する「定型俳句」(「俳諧の発句」的「伝統俳句」)を標榜する俳誌「渋柿」も、漱石門下の「小宮豊隆、寺田寅彦、安倍能成、鈴木三重吉」等々が参画して、さながら、「ホトトギス」の「虚子俳句」に対する、「渋柿」の「漱石俳句」という感すら抱かせるものがある。

「漱石山房と其弟子達」(津田清楓画)→A図
https://blog.goo.ne.jp/torahiko-natsume/e/6ad1c4767dddc3568e6b34e7d727b501
≪「上段の左から」→則天居士(夏目漱石)・寅彦(寺田寅彦)・能成(阿部能成)・式部官(松根東洋城)・野上(野上豊一郎)・三重吉(鈴木三重吉)・岩波(岩波茂雄)・桁平(赤木桁平)・百閒(内田百閒)
「下段の左から」→豊隆(小宮豊隆)・阿部次郎・森田草平/花瓶の傍の黒猫(『吾輩は猫である』の吾輩が、「苦沙弥」先生と「其門下生」を観察している。)
「則天居士」=「則天去私」の捩り=「〘連語〙 天にのっとって私心を捨てること。我執を捨てて自然に身をゆだねること。晩年の夏目漱石が理想とした心境で、「大正六年文章日記」の一月の扉に掲げてあることば。」(「精選版 日本国語大辞典」)
「天地人間」(屏風に書かれた文字)=「天地人」=「① 天と地と人。宇宙間の万物。三才。② 三つあるものの順位を表わすのに用いる語。天を最上とし、地・人がこれに次ぐ。
※落語・果報の遊客(1893)〈三代目三遊亭円遊〉「発句を〈略〉天地人を付ける様な訳で」(「精選版 日本国語大辞典」)→「2096 空に消ゆる鐸のひびきや春の塔(漱石・「前書」=「空間を研究せる天然居士の肖像に題す」)→「空間に生れ、空間を究(きわ)め、空間に死す。空たり間たり天然居士(てんねんこじ)噫(ああ)」(『吾輩は猫である』第三話)
↓
https://www.konekono-heya.com/books/wagahai3.html ≫
この「漱石山房と其弟子達」(津田清楓画)は、その姉妹画(『漱山と十大弟子(津田清楓著)』の挿絵)』関連のものがあって、それは下図のようなものがある。

津田青楓≪漱石と十弟子≫昭和51(1976)年/紙本著色/A4判用(縦30.9cm×横22.0cm×厚さ0.04cm)→B図
https://takadanobaba.keizai.biz/photoflash/2115/
https://soseki-museum.jp/user-guide/museum-shop/
≪ A図とB図とを比較すると、まず、A図(「則天居士」=漱石)B図(「漱石大明神」となり、A図(百閒)がB図(「筆者亀吉)」=「青楓」)となり、「弟子」(寅彦・能成・東洋城・豊一郎・三重吉・茂雄・桁平・豊隆・次郎・草平)も、そのネーミングを異にしている。
そして、屏風の文字も、A図「天地/人間」に比して、B図「地/非在天/人間」と様変わりをしている。≫
(追記) 夏目漱石俳句集(その九)<制作年順> 明45/大正元年(1912年)~大正5年(1916年)・年月不詳(2284~2527 )
明治45年/大正元年(1912年)
2284 雪の夜や佐野にて食ひし粟の飯
2285 壁隣り秋稍更けしよしみの灯
2286 懸物の軸だけ落ちて壁の秋
2287 行く春や壁にかたみの水彩画
2288 壁に達磨それも墨画の芒哉
2289 如意払子懸けてぞ冬を庵の壁
2290 錦画や壁に寂びたる江戸の春
2291 鼠もや出ると夜寒に壁の穴
2292 壁に脊を涼しからんの裸哉
2293 壁に映る芭蕉夢かや戦ぐ音
2294 壁一重隣に聴いて砧かな
2295 水盤に雲呼ぶ石の影すゞし
2296 湯壺から首丈出せば野菊哉
2297 五六本なれど靡けばすゝき哉
2298 蚊帳越しに見る山青し杉木立
2299 御かくれになつたあとから鶏頭かな
2300 厳かに松明振り行くや星月夜
2301 かりそめの病なれども朝寒み
2302 秋風や屠られに行く牛の尻
2303 橋なくて遂に渡れぬ枯野哉
2304 杉木立寺を蔵して時雨けり
2305 豆腐焼く串にはらはら時雨哉
2306 琴作る桐の香や春の雨
大正2年(1913年)
2307 人形も馬もうごかぬ長閑さよ
2308 菊一本画いて君の佳節哉
2309 四五本の竹をあつめて月夜哉
2310 萩の粥月待つ庵となりにけり
2311 葉鶏頭高さ五尺に育てけり
大正3年(1914年)
2312 播州へ短冊やるや今朝の春
2313 松立てゝ門鎖したる隠者哉
2314 春の発句よき短冊に書いてやりぬ
2315 冠を挂けて柳の緑哉
2316 鶯は隣へ逃げて藪つゞき
2317 つれづれを琴にわびしや春の雨
2318 欄干に倚れば下から乙鳥哉
2319 我一人行く野の末や秋の空
2320 内陣に仏の光る寒哉
2321 春水や草をひたして一二寸
2322 縄暖簾くゞりて出れば柳哉
2323 橋杭に小さき渦や春の川
2324 同じ橋三たび渡りぬ春の宵
2325 蘭の香や亜字欄渡る春の風
2326 老僧に香一しゅの日永哉
2327 竹藪の青きに梅の主人哉
2328 茶の木二三本閑庭にちよと春日哉
2329 日は永し一人居に静かなる思ひ
2330 世に遠き心ひまある日永哉
2331 線香のこぼれて白き日永哉
2332 留守居して目出度思ひ庫裏長閑
2333 我一人松下に寐たる日永哉
2334 引かゝる護謨風船や柳の木
2335 門前を彼岸参りや雪駄ばき
2336 そゞろ歩きもはなだの裾や春の宵
2337 春風に吹かれ心地や温泉の戻り
2338 仕立もの持て行く家や雛の宵
2339 長閑さや垣の外行く薬売
2340 竹の垣結んで春の庵哉
2341 玉碗に茗甘なうや梅の宿
2342 草双紙探す土蔵や春の雨
2343 桶の尻干したる垣に春日哉
2344 誰袖や待合らしき春の雨
2345 錦絵に此春雨や八代目
2346 京楽の水注買ふや春の町
2347 万歳も乗りたる春の渡し哉
2348 春の夜や妻に教はる荻江節
2349 木蓮に夢の様なる小雨哉
2350 降るとしも見えぬに花の雫哉
2351 春雨や京菜の尻の濡るゝほど
2352 落椿重なり合ひて涅槃哉
2353 木蓮と覚しき花に月朧
2354 永き日や頼まれて留守居してゐれば
2355 木瓜の実や寺は黄檗僧は唐
2356 春寒し未だ狐の裘
2357 寺町や垣の隙より桃の花
2358 見連に揃の簪土間の春
2359 染物も柳も吹かれ春の風
2360 連翹の奥や碁を打つ石の音
2361 春の顔真白に歌舞伎役者哉
2362 小座敷の一中は誰梅に月
2363 花曇り御八つに食ふは団子哉
2364 炉塞いで窓に一鳥の影を印す
2365 寺町や椿の花に春の雪
2366 売茶翁花に隠るゝ身なりけり
2367 高き花見上げて過ぎぬ角屋敷
2368 塗笠に遠き河内路霞みけり
2369 窓に入るは目白の八つか花曇
2370 静かなるは春の雨にて釜の音
2371 驢に騎して客来る門の柳哉
2372 見上ぐれば坂の上なる柳哉
2373 経政の琵琶に御室の朧かな
2374 楼門に上れば帽に春の風
2375 千社札貼る楼門の桜哉
2376 家形船着く桟橋の柳哉
2377 芝草や陽炎ふひまを犬の夢
2378 早蕨の拳伸び行く日永哉
2379 陽炎や百歩の園に我立てり
2380 ちらちらと陽炎立ちぬ猫の塚
2381 紙雛つるして枝垂桜哉
2382 行く春や披露待たるゝ歌の選
2383 眠る山眠たき窓の向ふ哉
2384 魚の影底にしばしば春の水
2385 四つ目垣茶室も見えて辛夷哉
2386 祥瑞を持てこさせ縁に辛夷哉
2387 如意の銘彫る僧に木瓜の盛哉
2388 馬を船に乗せて柳の渡哉
2389 田楽や花散る里に招かれて
2390 行春や僧都のかきし絵巻物
2391 行春や書は道風の綾地切
2392 藁打てば藁に落ちくる椿哉
2393 静坐聴くは虚堂に春の雨の音
2394 良寛にまりをつかせん日永哉
2395 一張の琴鳴らし見る落花哉
2396 春の夜や金の無心に小提灯
2397 局に閑あり静かに下す春の石
2398 春深き里にて隣り梭の音
2399 銀屏に墨もて梅の春寒し
2400 三味線に冴えたる撥の春浅し
2401 海見ゆる高どのにして春浅し
2402 白き皿に絵の具を溶けば春浅し
2403 筍は鑵詰ならん浅き春
2404 行く春のはたごに画師の夫婦哉
2405 行く春や経納めにと厳島
2406 行く春や知らざるひまに頬の髭
2407 鶯や髪剃あてゝ貰ひ居る
2408 活けて見る光琳の画の椿哉
2409 飯食へばまぶた重たき椿哉
2410 行春や里へ去なする妻の駕籠
2411 酒の燗此頃春の寒き哉
2412 晧き歯に酢貝の味や春寒し
2413 嫁の傘傾く土手や春の風
2414 春惜む日ありて尼の木魚哉
2415 業終へぬ写経の事や尽くる春
2416 春惜む茶に正客の和尚哉
2417 冠に花散り来る羯鼓哉
2418 門鎖ざす王維の庵や尽くる春
2419 春惜む句をめいめいに作りけり
2420 枳殻の芽を吹く垣や春惜む
2421 鎌倉へ下る日春の惜しき哉
2422 新坊主やそゞろ心に暮るゝ春
2423 桃の花隠れ家なるに吠ゆる犬
2424 草庵や蘆屋の釜に暮るゝ春
2425 牽船の縄のたるみや乙鳥
2426 三河屋へひらりと這入る乙鳥哉
2427 呑口に乙鳥の糞も酒屋哉
2428 鍋提げて若葉の谷へ下りけり
2429 料理屋の塀から垂れて柳かな
2430 酒少し徳利の底に夜寒哉
2431 酒少し参りて寐たる夜寒哉
2432 眠らざる夜半の灯や秋の雨
2433 電燈を二燭に易へる夜寒哉
2434 秋風の聞えぬ土に埋めてやりぬ
大正4年(1915年)
2435 春を待つ支那水仙や浅き鉢
2436 真向に坐りて見れど猫の恋
2437 柳芽を吹いて四条のはたごかな
2438 筋違に四条の橋や春の川
2439 紅梅や舞の地を弾く金之助
2440 春の川を隔てゝ男女かな
2441 萱草の一輪咲きぬ草の中
2442 牡丹剪つて一草亭を待つ日哉
2443 椿とも見えぬ花かな夕曇
2444 宝寺の隣に住んで桜哉
2445 白牡丹李白が顔に崩れけり
2446 木屋丁や三筋になつて春の川
2447 竹一本葉四五枚に冬近し
2448 女の子十になりけり梅の花
2449 水仙や早稲田の師走三十日
2450 水仙花蕉堅稿を照しけり
2451 菊の花硝子戸越に見ゆる哉
大正5年(1916年)
2452 春風や故人に贈る九花蘭
2453 白梅にしぶきかゝるや水車
2454 孟宗の根を行く春の筧哉
2455 梅早く咲いて温泉の出る小村哉
2456 いち早き梅を見付けぬ竹の間
2457 梅咲くや日の旗立つる草の戸に
2458 裏山に蜜柑みのるや長者振
2459 温泉に信濃の客や春を待つ
2460 橙も黄色になりぬ温泉の流
2461 鶯に聞き入る茶屋の床几哉
2462 鶯や草鞋を易ふる峠茶屋
2463 鶯や竹の根方に鍬の尻
2464 鶯や藪くゞり行く蓑一つ
2465 鶯を聴いてゐるなり縫箔屋
2466 鶯に餌をやる寮の妾かな
2467 温泉の里橙山の麓かな
2468 桃の花家に唐画を蔵しけり
2469 桃咲くやいまだに流行る漢方医
2470 輿に乗るは帰化の僧らし桃の花
2471 町儒者の玄関構や桃の花
2472 かりにする寺小屋なれど梅の花
2473 文も候稚子に持たせて桃の花
2474 琵琶法師召されて春の夜なりけり
2475 春雨や身をすり寄せて一つ傘
2476 鶯を飼ひて床屋の主人哉
2477 耳の穴掘つてもらひぬ春の風
2478 嫁の里向ふに見えて春の川
2479 岡持の傘にあまりて春の雨
2480 一燈の青幾更ぞ瓶の梅
2481 病める人枕に倚れば瓶の梅
2482 梅活けて聊かなれど手習す
2483 桃に琴弾くは心越禅師哉
2484 秋立つや一巻の書の読み残し
2485 蝸牛や五月をわたるふきの茎
2486 朝貌にまつはられてよ芒の穂
2487 萩と歯朶に賛書く月の団居哉
2488 棕櫚竹や月に背いて影二本
2489 秋立つ日猫の蚤取眼かな
2490 秋となれば竹もかくなり俳諧師
2491 風呂吹きや頭の丸き影二つ
2492 煮て食ふかはた焼いてくふか春の魚
2493 いたづらに書きたるものを梅とこそ
2494 まきを割るかはた祖を割るか秋の空
2495 饅頭に礼拝すれば晴れて秋
2496 饅頭は食つたと雁に言伝よ
2497 吾心点じ了りぬ正に秋
2498 僧のくれし此饅頭の丸きかな
2499 瓢箪は鳴るか鳴らぬか秋の風
年月不詳
2500 忠度を謡ふ隣や春の宵
2501 帰り路は鞭も鳴さぬ日永かな
2502 馬市の秣飛び散る春の風
2503 春雨や四国遍路の木賃宿
2504 野を焼た煙りの果は霞かな
2505 春の水馬の端綱をひたしけり
2506 鶯や障子あくれば東山
2507 鳴く蛙なかぬ蛙とならびけり
2508 大方はおなじ顔なる蛙かな
2509 遠雷や香の煙のゆらぐ程
2510 夏草の下を流るゝ清水かな
2511 蚊ばしらや断食堂の夕暮に
2512 蓮毎に来るべし新たなる夏
2513 そり橋の下より見ゆる蓮哉
2514 ひとむらの芒動いて立つ秋か
2515 びんに櫛そよと動きぬ今朝の秋
2516 うそ寒や綿入きたる小大名
2517 明けたかと思ふ夜長の月あかり
2518 吾猫も虎にやならん秋の風
2519 すゞなりの鈴ふきならす野分哉
2520 酔過ぎて新酒の色や虚子の顔
2521 長からぬ命をなくや秋の蝉
2522 いくさやんで菊さく里に帰りけり
2523 元禄の頃の白菊黄菊かな
2524 ふつゝかに生れて芋の親子かな
2525 行く年を隣の娘遂に嫁せず
2526 発句にもまとまらぬよな海鼠かな
2527 水仙や朝ぶろを出る妹が肌
(参考その一) 「夏目先生の俳句と漢詩(寺田寅彦)」周辺
https://www.aozora.gr.jp/cards/000042/files/43569_24585.html
夏目先生が未だ創作家としての先生自身を自覚しない前に、その先生の中の創作家は何処(どこ)かの隙間を求めてその創作に対する情熱の発露を求めていたもののように思われる。その発露の恰好(かっこう)な一つの創作形式として選ばれたのが漢詩と俳句であった。云わば遠からず爆発しようとする火山の活動のエネルギーがわずかに小噴気口の噴煙や微弱な局部地震となって現われていたようなものであった。それにしてもそのために俳句や漢詩の形式が選ばれたという事は勿論偶然ではなかったに相違ない。先生の自然観人世観が始めから多分に俳句漢詩のそれと共通なものを含んでいた事は明らかであるが、しかしまた先生が俳句漢詩をやった事が先生の自然観人世観にかなりの反作用を及ぼしたであろうという事も当然な事であろう。ともかくも先生の晩年の作品を見る場合にこの初期の俳句や詩を背景に置いて見なければ本当の事は分らないではないかと思う事がいろいろある。少なくも晩年の作品の中に現われている色々のものの胚子(はいし)がこの短い詩形の中に多分に含まれている事だけは確実である。
俳句とは如何なるものかという問に対して先生の云った言葉のうちに、俳句はレトリックのエッセンスであるという意味の事を云われた事がある。そういう意味での俳句で鍛え上げた先生の文章が元来力強く美しい上に更に力強く美しくなったのも当然であろう。また逆にあのような文章を作った人の俳句や詩が立派であるのは当然だとも云われよう。実際先生のような句を作り得る人でなければ先生のような作品は出来そうもないし、あれだけの作品を作り得る人でなければあのような句は作れそうもない。後に『草枕』のモニューメントを築き上げた巨匠の鑿(のみ)のすさびに彫(きざ)んだ小品をこの集に見る事が出来る。
先生の俳句を年代順に見て行くと、先生の心持といったようなものの推移して行った迹(あと)が最もよく追跡されるような気がする。人に読ませるための創作意識の最も稀薄な俳句において比較的自然な心持が反映しているのであろう。例えば修善寺における大患以前の句と以後の句との間に存する大きな距離が特別に目立つ、それだけでも覗(うかが)ってみる事は先生の読者にとってかなり重要な事であろうかと思われる。
色々の理由から私は先生の愛読者が必ず少なくもこの俳句集を十分に味わってみる事を望むものである。先生の俳句を味わう事なしに先生の作物の包有する世界の諸相を眺める事は不可能なように思われる。また先生の作品を分析的に研究しようと企てる人があらばその人はやはり充分綿密に先生の俳句を研究してかかる事が必要であろうと思う。
(昭和三年五月『漱石全集』第十三巻、月報第三号)
(参考その二) 「漱石の親友 天然居士・米山保三郎」周辺
https://rendezvou.exblog.jp/7067220/
学生時代の夏目金之助に作家になることを勧め漱石が彼の言葉に強く動かされた人物・米山保三郎のことはよく知られています。ただ、これまで研究者の中で誤解があり、漱石の語句の解釈に問題があるまま流布されてきたのが現状です。
「天然居士は空間を研究し、論語を読み、焼芋を食い、鼻汁を垂らす人である」
焼き芋と鼻汁を垂らす、これは禅の歴史に実在した中国の禅僧・懶さん(王ヘンに賛)和尚の故事から来る引用なのでした。漱石は畏敬する親友の米山保三郎へ深い愛情と禅に生きる彼を讃える意味で書いたものでしょう。しかし、世間一般ではなかなか通用しない事も充分知っていました。そうであるからこそ、『猫』のなかで次のように書いているのです。
「天然居士は空間を研究し、論語を読み、焼芋を食い、鼻汁を垂らす人である」
苦沙弥先生、一気呵成にこう書き流し、声を出してこれを読み、「ハハハ面白い」と笑うが、「うん。鼻汁を垂らすはさすがに酷だ、焼き芋も蛇足だ」と線を引き。結局「天然居士は空間を研究し論語を読む人である」だけにしたころで、これではあまりに簡単すぎると全部ボツにして、原稿用紙の裏に「空間に生れ、空間を究め、空間に死す。空たり間たり天然居士、噫」
実際、漱石はこの米山の兄、熊次郎から実弟の写真へ揮毫を懇望されて、漱石は俳句を書いています。その俳句とは、
空に消ゆる鐸のひびきや春の塔 という追悼の一句です。親友の死を悼む漱石の心情があふるるばかり、見事な名句と思います。写真は400X300mm、単身像の右側にこの句があり、左にこう記されています。
空間を研究する天然居士の肖像に題す 己酉 四月 漱石
己酉,となれば、1909年、明治四十二年です。漱石が朝日新聞社に入社して2年目の四月に詠んだものと明確に判るのが嬉しいところです。また、米山が鼻水を垂らすの表現がとかく世俗的に解釈され、漱石がいかにしてこの語句を入れたかということは研究者の間でないがしろにされて来ました。しかし、漱石がただ、ユーモラスにこんな語句を入れるはずはないのです。洟を垂らそうが自分は三昧になっているのだという仏道の修行による逸話なのです。
出典もありますから、その引用もしておきましょう。『碧巖録』第三十四則より。
「懶瓚和尚。隱居衡山石室中。唐德宗聞其名。遣使召之。使者至其室宣言。天子有詔。尊者當起謝恩。瓚方撥牛糞火。尋煨芋而食。寒涕垂頤未甞答。使者笑曰。且勸尊者拭涕。瓚曰。我豈有工夫為俗人拭涕耶。竟不起。使回奏。德宗甚欽嘆之。」
(懶瓚和尚、衡山石室の中に隱居す。唐の德、宗其の名を聞いて、使を遣して之を召す。使者、其の室に至つて宣言す。天子詔有り、尊者まさに起つて恩を謝すべし。瓚、まさに牛糞の火を撥つて、煨芋を尋ねて食す。寒涕、頤に垂れて未だ甞て答えず。使者笑つて曰く、且らく勸む、尊者、涕を拭え。瓚曰く、我れ豈に工夫の俗人の為に涕を拭くこと有らん耶といつて、竟に起たず。使、回つて奏す。德宗、甚だ之を欽嘆す。)
私は嘗て東慶寺の井上禅定和尚様から分かりやすいお話を聞いておりました。
昔、中国の偉い坊さんがあって皇帝が先生になってくれって勅使を迎えに遣るんだ。当時の中国では牛の糞の乾いたのを焚き付けにしてその牛糞の火の中へ芋をいれて焼いている処へ勅使が来た。らいさん和尚は牛糞の中から芋を掘り出して勅使に食えって云うんだ。勅使が見るとこの和尚、鼻水を垂らして下顎まで延びている。それを勅使は「まあ、洟を拭きなさいと云ったんだ。
なんだ、お前はそんな事で来たのか、勅使としておれを迎えに来たのではねえのか。おれが洟を垂らしていようがそんな事どうでもいい事だ、おれは三昧になっているんだ。っていう面白い問答があるんだよ。それを元にして漱石は「焼き芋を食らい、鼻汁を垂らす」てな、昔の懶瓚和尚がやったという事を思い出して書いているんだけれど、猫に笑われるから消しちゃうんだ。」(鎌倉漱石の会会報所載)
やはり禅定様の仰ることは納得のゆくものですね。
念のために付記しますと、漱石の友人で円覚寺・釈宗演の師である今北洪川について参禅をし、居士号を与えられた逸材が二人いました。無為という居士号は菅虎雄、天然の居士号は米山保三郎でした。米山は不運にも若くして病死したのでしたが、彼の伝記を漱石が書くという計画もあったと狩野亨吉は書いています。漱石がもう少し生きていたらなば実現したかも知れないのですが…。
夏目漱石の「俳句と書画」(その十二) [「子規と漱石」の世界]
その十二 漱石の「子規没後の俳句その二)」(「明治四十年~四十四年」周辺)

「吾輩は猫である」初出/俳句雑誌「ホトトギス」(第8巻4号・1905年・明治35年1月)
https://www.facebook.com/SosekiFan/photos/a.190617470970894/1350207411678555/?type=3
「ホトトギス((第8巻)」(目次集)
http://www.hototogisu.co.jp/
第4号/明治38年(1905)1月
第5号/明治38年(1905)2月
第6号/明治38年(1905)3月
第7号/明治38年(1905)4月
第8号/明治38年(1905)5月
第9号/明治38年(1905)6月
第10号/明治38年(1905)7月
第11号/明治38年(1905)7月
第12号/明治38年(1905)8月
第13号/明治38年(1905)9月
「吾輩は猫である」(「初出」と「単行本」)
https://www.library.tohoku.ac.jp/collection/collection/soseki/syuyo-neko.html

(初出)『ホトトギス』 明治38年1月~明治39年8月まで10回にわたり断続的に連載
(単行本)上編 明治38年10月 中編 明治39年11月 下編 明治40年5月 大倉書店・服部書店
≪(内 容)
猫を語り手として苦沙弥・迷亭ら太平の逸民たちに滑稽と諷刺を存分に演じさせ語らせたこの小説は「坊っちゃん」とあい通ずる特徴をもっている。それは溢れるような言語の湧出と歯切れのいい文体である。この豊かな小説言語の水脈を発見することで英文学者・漱石は小説家漱石(1867-1916)となった。(岩波文庫解説より)
(自作への言及)
東風君、苦沙弥君、皆勝手な事を申候。それ故に太平の逸民に候。現実世界にあの主義では如何と存候。御反対御尤に候。漱石先生も反対に候。
彼らのいふ所は皆真理に候。しかしただ一面の真理に候。決して作者の人生観の全部に無之故(これなきゆえ)その辺は御了知被下(くだされたく)候。あれは総体が諷刺に候。現代にあんな諷刺は尤も適切と存じ『猫』中に収め候。もし小生の個性論を論文としてかけば反対の方面と双方の働きかける所を議論致したくと存候。
(明治39年8月7日 畔柳芥舟あて書簡より)
『猫』ですか、あれは最初は何もあのように長く続けて書こうという考えもなし、腹案などもありませんでしたから無論一回だけでしまうつもり。またかくまで世間の評判を受けようとは少しも思っておりませんでした。最初虚子君から「何か書いてくれ」と頼まれまして、あれを一回書いてやりました。丁度その頃文章会というものがあって、『猫』の原稿をその会へ出しますと、それをその席で寒川鼠骨君が朗読したそうですが、多分朗読の仕方でも旨かったのでしょう、甚くその席で喝采を博したそうです。(中略)
妙なもので、書いてしまった当座は、全然胸中の文字を吐き出してしまって、もうこの次には何も書くようなことはないと思うほどですが、さて十日経ち廿日経って見ると日々の出来事を観察して、また新たに書きたいような感想も湧いて来る。材料も蒐められる。こんな風ですから『猫』などは書こうと思えば幾らでも長く続けられます。(「文学談」)≫(「東北大学附属図書館 夏目漱石ライブラリ」)
http://neko.koyama.mond.jp/?eid=209617
≪「俳句の五十年(高浜虚子著)」抜粋
ある時私は漱石が文章でも書いて見たならば気が紛れるだろうと思いまして、文章を書いて見ることを勧めました。私は別に気にも留めずにおったのでありまして、果して出来るか、出来んかも分らんと考えておったのでありました。ところが、その日になって立寄ってみますと、非常に長い文章が出来ておりまして、頗(すこぶ)る機嫌が良くって、ぜひこれを一つ自分の前で読んでみてくれろという話でありました。文章会は時間が定まっておりまして、その時間際に漱石の所に立寄ったのでありましたが、そういわれるものですから止むを得ず私はその文章を読んでみました。ところがなかなか面白い文章であって、私等仲間の文章とすると、分量も多くそれに頗る異色のある文章でありましたから、これは面白いから、早速今日の文章会に持出して読んでみるからといって、それを携えて文章会に臨みました。私がその漱石の家で読んだ時分に、題はまだ定めてありませんでして、「猫伝」としようかという話があったのでありますが、「猫伝」というよりも、文章の初めが「吾輩は猫である。名前はまだない」という書き出しでありますから、その「吾輩は猫である」という冒頭の一句をそのまま表題にして「吾輩は猫である」という事にしたらどうかというと、漱石は、それでも結構だ、名前はどうでもいいからして、私に勝手につけてくれろ、という話でありました。それでその原稿を持って帰って、「ホトトギス」に載せます時分に、「吾輩は猫である」という表題を私が自分で書き入れまして、それを活版所に廻したのでありました。
それからその時分は、誰の文章でも一応私が眼を通して、多少添削するという習慣でありましたからして、この『吾輩は猫である』という文章も更に読み返してみまして、無駄だと思われる箇所の文句はそれを削ったのでありました。そうしてそれを三十八年の一月号に発表しますというと、大変な反響を起しまして、非常な評判になりました。それというのも、大学の先生である夏目漱石なる者が小説を書いたという事で、その時分は大学の先生というものは、いわゆる象牙の塔に籠もっていて、なかなか小説などは書くものではないという考えがあったのでありますが、それが小説を書いたというので、著しく世人の眼を欹(そばだ)たしめたものでありました。そればかりではなく、大変世間にある文章とは類を異にしたところからして、非常な評判となったのでありました。
それで、漱石は、ただ私が初めて文章を書いてみてはどうかと勧めた為に書いたという事が、動機となりまして、それから漱石の生活が一転化し、気分も一転化するというような傾きになってきたのでありました。それと同時に『倫敦塔』という文章も書きまして「帝国文学」の誌上に発表しました。
それから『吾輩は猫である』が、大変好評を博したものですから、それは一年と八ヶ月続きまして、続々と続篇を書く、而(しか)もその続篇は、この第一篇よりも遙かに長いものを書いて、「ホトトギス」は殆(ほとん)どその『吾輩は猫である』の続篇で埋ってしまうというような勢いになりました。それが為に「ホトトギス」もぐんぐんと毎号部数が増して行くというような勢いでありました。≫
(追記) 夏目漱石俳句集(その八)<制作年順> 明40年(1907年)~明治44年(1911年)(1910~2283)
明治40年(1907年)
1910 御降になるらん旗の垂れ具合
1911 隠れ住んで此御降や世に遠し
1912 御降に閑なる床や古法眼
1913 打つ畠に小鳥の影の屡す
1914 物いはぬ人と生れて打つ畠か
1915 長短の風になびくや花芒
1916 月今宵もろもろの影動きけり
1917 里の灯を力によれば燈籠かな
1918 春寒の社頭に鶴を夢みけり
1919 布さらす磧わたるや春の風
1920 屑買の垣より呼べば蝶黄なり
1921 香焚けば焚かざれば又来る蝶
1922 旅に寒し春を時雨れの京にして
1923 永き日や動き已みたる整時板
1924 加茂にわたす橋の多さよ春の風
1925 雀巣くふ石の華表や春の風
1926 花食まば鶯の糞も赤からん
1927 姫百合に筒の古びやずんど切
1928 恋猫の眼ばかりに痩せにけり
1929 藤の花に古き四尺の風が吹く
1930 若葉して又新なる心かな
1931 髪に真珠肌あらはなる涼しさよ
1932 時鳥厠半ばに出かねたり
1933 のうぜんの花を数へて幾日影
1934 看経の下は蓮池の戦かな
1935 蓮剪りに行つたげな椽に僧を待つ
1936 蓮に添へてぬめの白さよ漾虚集
1937 白蓮に仏眠れり磬落ちて
1938 生死事大蓮は開いて仕舞けり
1939 ほのぼのと舟押し出すや蓮の中
1940 蓑の下に雨の蓮を蔵しけり
1941 田の中に一坪咲いて窓の蓮
1942 夕蓮に居士渡りけり石欄干
1943 明くる夜や蓮を放れて二三尺
1944 蓮の欄舟に鋏を渡しけり
1945 蓮の葉に麩はとゞまりぬ鯉の色
1946 石橋の穴や蓮ある向側
1947 一八の家根をまはれば清水かな
1948 したゝりは歯朶に飛び散る清水かな
1949 宝丹のふたのみ光る清水かな
1950 苔清水天下の胸を冷やしけり
1951 ところてんの叩かれてゐる清水かな
1952 底の石動いて見ゆる清水哉
1953 二人して片足宛の清水かな
1954 懸崖に立つ間したゝる清水哉
1955 したゝりは襟をすくます清水かな
1956 両掛や関のこなたの苔清水
1957 市に入る花売憩う清水かな
1958 樟の香や村のはづれの苔清水
1959 澄みかゝる清水や小き足の跡
1960 法印の法螺に蟹入る清水かな
1961 追付て吾まづ掬ぶ清水かな
1962 三どがさをまゝよとひたす清水かな
1963 汗を吹く風は歯朶より清水かな
1964 岩清水十戸の村の筧かな
1965 かち渡る鹿や半ばに返り見る
1966 二三人砧も打ちぬ鹿の声
1967 寄りくるや豆腐の糟に奈良の鹿
1968 橋立や松一筋に秋の空
1969 抽んでゝ富士こそ見ゆれ秋の空
1970 鱸釣つて舟を蘆間や秋の空
1971 春の水岩ヲ抱イテ流レケリ
1972 花落チテ砕ケシ影ト流レケリ
1973 朝貌や惚れた女も二三日
1974 垣間見る芙蓉に露の傾きぬ
1975 秋風や走狗を屠る市の中
1976 山の温泉や欄に向へる鹿の面
1977 灯火を挑げて鹿の夜は幾時
1978 芋の葉をごそつかせ去る鹿ならん
1979 厠より鹿と覚しや鼻の息
1980 山門や月に立たる鹿の角
1981 ひいと鳴て岩を下るや鹿の尻
1982 水浅く首を伏せけり月の鹿
1983 見下して尾上に鹿のひとり哉
1984 行燈に奈良の心地や鹿の声
1985 漫寒の温泉も三度目や鹿の声
1986 岩高く見たり牡鹿の角二尺
1987 蕎麦太きもてなし振や鹿の角
1988 郡長を泊めてたまたま鹿の声
1989 宵の鹿夜明の鹿や夢短か
1990 暁に消ぬ可き月に鹿あはれ
1991 秋の空幾日迎いで京に着きぬ
1992 雲少し榛名を出でぬ秋の空
1993 押分る芒の上や秋の空
1994 秋の空鳥海山を仰ぎけり
1995 朝顔の今や咲くらん空の色
1996 立秋の風に光るよ蜘蛛の糸
1997 恩給に事足る老の黄菊かな
1998 菊に結へる四っ目の垣もまだ青し
1999 端渓に菊一輪の机かな
2000 杉垣に昼をこぼれて百日紅
2001 酸多き胃を患ひてや秋の雨
2002 大鼓芙蓉の雨にくれ易し
2003 後仕手の撞木や秋の橋掛り
2004 朝日のつと千里の黍に上りけり
2005 露けさの庵を繞りて芙蓉かな
2006 露けさの中に帰るや小提灯
2007 かりがねの斜に渡る帆綱かな
2008 雁や渡る乳玻璃に細き灯を護る
2009 北窓は鎖さで居たり月の雁
2010 傾城に鳴くは故郷の雁ならん
2011 夕雁や物荷ひ行く肩の上
2012 灯を入るゝ軒行燈や雁低し
2013 帆柱をかすれて月の雁の影
2014 客となつて沢国に雁の鳴く事多し
2015 遠近の砧に雁の落るなり
2016 提灯に雁落つらしも闇の畔
2017 花びらの狂ひや菊の旗日和
2018 侘住居作らぬ菊を憐めり
2019 白菊や書院へ通る腰のもの
2020 草庵の垣にひまある黄菊かな
2021 旗一竿菊のなかなる主人かな
2022 草共に桔梗を垣に結ひ込みぬ
2023 白桔梗古き位牌にすがすがし
2024 草刈の籠の目を洩る桔梗かな
2025 桔梗活けて宝生流の指南かな
2026 扶け起す萩の下より鼬かな
2027 ふき易へて萱に聴けり秋の雨
2028 藁葺に移れば一夜秋の雨
2029 雷の図にのりすぎて落にけり
2030 秋の蚊の鳴かずなりたる書斎かな
2031 黒塀にあたるや妹が雪礫
2032 女の童に小冠者一人や雪礫
2033 茶の花や黄檗山を出でゝ里余
2034 丸髷に結ふや咲く梅紅に
2035 むら鴉何に集る枯野かな
2036 川ありて遂に渡れぬ枯野かな
2037 法螺の音の何処より来る枯野哉
2038 たゝむ傘に雪の重みや湯屋の門
2039 吾影の吹かれて長き枯野哉
2040 女うつ鼓なるらし春の宵
2041 白絹に梅紅ゐの女院かな
2042 酒買ひに里に下るや鹿も聞き
2043 文債に籠る冬の日短かゝり
明治41年(1908年)
2044 日毎踏む草芳しや二人連
2045 二人して雛にかしづく楽しさよ
2046 鼓打ちに参る早稲田や梅の宵
2047 青柳擬宝珠の上に垂るゝなり
2048 居士が家を柳此頃蔵したり
2049 門に立てば酒乞ふ人や帽に花
2050 鶯の日毎巧みに日は延びぬ
2051 吾に媚ぶる鶯の今日も高音かな
2052 勅額の霞みて松の間かな
2053 飯蛸の一かたまりや皿の藍
2054 飯蛸や膳の前なる三保の松
2055 飯蛸と侮りそ足は八つあると
2056 春の水たるむはづなを濡しけり
2057 連翹に小雨来るや八っ時分
2058 花曇り尾上の鐘の響かな
2059 籠の鳥に餌をやる頃や水温む
2060 山伏の関所へかゝる桜哉
2061 強力の笈に散る桜かな
2062 南天に寸の重みや春の雪
2063 真蒼な木賊の色や冴返る
2064 そゝのかす女の眉や春浅し
2065 塩辛を壺に探るや春浅し
2066 名物の椀の蜆や春浅し
2067 僧となつて鐘を撞いたら冴返る
2068 穴のある銭が袂に暮の春
2069 いつか溜る文殻結ふや暮の春
2070 逝く春や庵主の留守の懸瓢
2071 嫁がぬを日に白粉や春惜む
2072 垢つきし赤き手絡や春惜む
2073 春惜む人にしきりに訪はれけり
2074 おくれたる一本桜憐なり
2075 逝く春やそゞろに捨てし草の庵
2076 青柳の日に緑なり句を撰む
2077 短夜を交す言葉もなかりけり
2078 文を売りて薬にかふる蚊遣かな
2079 安産と涼しき風の音信哉
2080 二人寐の蚊帳も程なく狭からん
2081 青梅や空しき籠に雨の糸
2082 五月雨や主と云はれし御月並
2083 鮟鱇や小光が鍋にちんちろり
2084 まのあたり精霊来たり筆の先
2085 此の下に稲妻起る宵あらん
2086 朝寒や自ら炊ぐ飯二合
2087 公退や菊に閑ある雑司ケ谷
2088 大輪の菊を日に揺る車かな
2089 たゞ一つ湯婆残りぬ室の隅
2090 春色や暮れなんとして水深み
2091 一つ家を中に夜すがら五月雨るゝ
2092 垣老て虞美人草のあらはなる
明治42年(1909年)
2093 小袖着て思ひ思ひの春をせん
2094 初日の出しだいに見ゆる雲静か
2095 とかくして鶯藪に老いにけり
2096 空に消ゆる鐸のひゞきや春の塔
2097 俊寛と共に吹かるゝ千鳥かな
2098 五月雨やももだち高く来る人
2099 初秋の芭蕉動きぬ枕元
2100 春はものゝ句になり易し京の町
2101 手を分つ古き都や鶉鳴く
2102 黍遠し河原の風呂へ渡る人
2103 黍行けば黍の向ふに入る日かな
2104 草尽きて松に入りけり秋の風
2105 鞭鳴らす頭の上や星月夜
2106 なつかしき土の臭や松の秋
2107 負ふ草に夕立早く逼るなり
2108 高麗人の冠を吹くや秋の風
2109 秋の山に逢ふや白衣の人にのみ
2110 秋晴や山の上なる一つ松
2111 故郷を舞ひつゝ出づる霞かな
2112 動かざる一篁や秋の村
2113 帰り見れば蕎麦まだ白き稲みのる
2114 銅の牛の口より野分哉
明治43年(1910年)
2115 独居や思ふ事なき三ケ日
2116 御堂まで一里あまりの霞かな
2117 花びらに風薫りては散らんとす
2118 ふと揺るゝ蚊帳の釣手や今朝の秋
2119 秋の思ひ池を繞れば魚躍る
2120 宮様の御立のあとや温泉の秋
2121 尺八を秋のすさみや欄の人
2122 温泉の村に弘法様の花火かな
2123 別るゝや夢一筋の天の川
2124 秋の江に打ち込む杭の響かな
2125 秋風や唐紅の咽喉仏
2126 秋晴に病間あるや髭を剃る
2127 秋の空浅黄に澄めり杉に斧
2128 衰に夜寒逼るや雨の音
2129 旅にやむ夜寒心や世は情
2130 蕭々の雨と聞くらん宵の伽
2131 秋風やひゞの入りたる胃の袋
2132 風流の昔恋しき紙衣かな
2133 生残る吾恥かしや鬢の霜
2134 立秋の紺落ち付くや伊予絣
2135 骨立を吹けば疾む身に野分かな
2136 稍寒の鏡もなくに櫛る
2137 鯛切れば鱗眼を射る稍寒み
2138 病む日又簾の隙より秋の蝶
2139 病んでより白萩に露の繁く降る事よ
2140 蜻蛉の夢や幾度杭の先
2141 蜻蛉や留り損ねて羽の光
2142 取り留むる命も細き薄かな
2143 仏より痩せて哀れや曼珠沙華
2144 虫遠近病む夜ぞ静なる心
2145 余所心三味聞きゐればそゞろ寒
2146 月を亘るわがいたつきや旅に菊
2147 起きもならぬわが枕辺や菊を待つ
2148 生き返るわれ嬉しさよ菊の秋
2149 たそがれに参れと菊の御使ひ
2150 範頼の墓濡るゝらん秋の雨
2151 菊作り門札見れば左京かな
2152 洪水のあとに色なき茄子かな
2153 菜の花の中の小家や桃一木
2154 秋浅き楼に一人や小雨がち
2155 生きて仰ぐ空の高さよ赤蜻蛉
2156 鶴の影穂蓼に長き入日かな
2157 一山や秋色々の竹の色
2158 古里に帰るは嬉し菊の頃
2159 静なる病に秋の空晴れたり
2160 菊の宴に心利きたる下部かな
2161 大切に秋を守れと去りにけり
2162 竪に見て事珍らしや秋の山
2163 坐して見る天下の秋も二た月目
2164 ともし置いて室明き夜の長かな
2165 堂守に菊乞ひ得たる小銭かな
2166 力なや痩せたる吾に秋の粥
2167 佳き竹に吾名を刻む日長かな
2168 見もて行く蘇氏の印譜や竹の露
2169 秋草を仕立てつ墓を守る身かな
2170 秋の蚊や我を螫さんと夜明方
2171 頼家の昔も嘸栗の味
2172 鮎の丈日に延びつらん病んでより
2173 肌寒をかこつも君の情かな
2174 貧しからぬ秋の便りや枕元
2175 京に帰る日も近付いて黄菊哉
2176 稲の香や月改まる病心地
2177 天の河消ゆるか夢の覚束な
2178 裏座敷林に近き百舌の声
2179 帰るは嬉し梧桐の未だ青きうち
2180 帰るべくて帰らぬ吾に月今宵
2181 雲を洩る日ざしも薄き一葉哉
2182 甦へる我は夜長に少しづゝ
2183 骨の上に春滴るや粥の味
2184 鶺鴒や小松の枝に白き糞
2185 寐てゐれば粟に鶉の興もなく
2186 粟の如き肌を切に守る身かな
2187 冷やかな瓦を鳥の遠近す
2188 冷かや人寐静まり水の音
2189 的礫と壁に野菊を照し見る
2190 鳥つゝいて半うつろのあけび哉
2191 朝寒や太鼓に痛き五十棒
2192 先づ黄なる百日紅に小雨かな
2193 いたつきも久しくなりぬ柚は黄に
2194 足腰の立たぬ案山子を車かな
2195 骨許りになりて案山子の浮世かな
2196 病んで来り病んで去る吾に案山子哉
2197 濡るゝ松の間に蕎麦を見付たる
2198 藪陰や濡れて立つ鳥蕎麦の花
2199 稲熟し人癒えて去るや温泉の村
2200 柿紅葉せり纏はる蔦の青き哉
2201 就中竹緑也秋の村
2202 数ふべく大きな芋の葉なりけり
2203 新らしき命に秋の古きかな
2204 逝く人に留まる人に来る雁
2205 鶏頭に後れず或夜月の雁
2206 釣台に野菊も見えぬ桐油哉
2207 思ひけり既に幾夜の蟋蟀
2208 過ぎし秋を夢みよと打ち覚めよとうつ
2209 朝寒も夜寒も人の情かな
2210 顧みる我面影やすでに秋
2211 暁や夢のこなたに淡き月
2212 ぶら下る蜘蛛の糸こそ冷やかに
2213 嬉しく思ふ蹴鞠の如き菊の影
2214 肩に来て人懐かしや赤蜻蛉
2215 渋柿も熟れて王維の詩集哉
2216 つくづくと行燈の夜の長さかな
2217 小行燈夜半の秋こそ古めけり
2218 一叢の薄に風の強き哉
2219 雨多き今年と案山子聞くからに
2220 柿一つ枝に残りて烏哉
2221 君が琴塵を払へば鳴る秋か
2222 たゞ一羽来る夜ありけり月の雁
2223 明けの菊色未だしき枕元
2224 日盛りやしばらく菊を縁のうち
2225 縁に上す君が遺愛の白き菊
2226 井戸の水汲む白菊の晨哉
2227 蔓で堤げる目黒の菊を小鉢哉
2228 いたつきも怠る宵や秋の雨
2229 形ばかりの浴す菊の二日哉
2230 三日の菊雨と変るや昨夕より
2231 白菊と黄菊と咲いて日本かな
2232 菊の香や幾鉢置いて南縁
2233 生垣の隙より菊の渋谷かな
2234 暖簾に芸人の名を茶屋の菊
2235 青山に移りていつか菊の主
2236 搨置いて菊あるところどころかな
2237 燭し見るは白き菊なれば明らさま
2238 菊の雨われに閑ある病哉
2239 菊の色縁に未し此晨
2240 蔵沢の竹を得てより露の庵
2241 柩には菊抛げ入れよ有らん程
2242 有る程の菊抛げ入れよ棺の中
2243 ひたすらに石を除くれば春の水
2244 病んで夢む天の川より出水かな
2245 風に聞け何れか先に散る木の葉
2246 萩に置く露の重きに病む身かな
2247 冷やかな脈を護りぬ夜明方
2248 露けさの里にて静かなる病
2249 迎火を焚いて誰待つ絽の羽織
2250 朝寒や生きたる骨を動かさず
2251 無花果や竿に草紙を縁の先
2252 屠牛場の屋根なき門や夏木立
2253 勾欄の擬宝珠に一つ蜻蛉哉
2254 冷かな文箱差出す蒔絵かな
2255 冷かな足と思ひぬ病んでより
2256 冷ややかに觸れても見たる擬宝珠哉
2257 冷やかに抱いて琴の古きかな
2258 提灯を冷やかに提げ芒かな
2259 なに食はぬ和尚の顔や河豚汁
2260 浦の男に浅瀬問ひ居る朧哉
明治44年(1911年)
2261 腸に春滴るや粥の味
2262 蝶去つてまた蹲踞る小猫かな
2263 たく駝して石を除くれば春の水
2264 鶏の尾を午頃吹くや春の風
2265 冠せぬ男も船に春の風
2266 涼しさや蚊帳の中より和歌の浦
2267 四国路の方へなだれぬ雲の峰
2268 起きぬ間に露石去にけり今朝の秋
2269 蝙蝠の宵々毎や薄き粥
2270 稲妻に近くて眠り安からず
2271 灯を消せば涼しき星や窓に入る
2272 風折々萩先づ散つて芒哉
2273 耳の底の腫物を打つや秋の雨
2274 切口に冷やかな風の厠より
2275 たのまれて戒名選む鶏頭哉
2276 抱一の芒に月の円かなる
2277 稲妻に近き住居や病める宵
2278 石段の一筋長き茂りかな
2279 空に雲秋立つ台に上りけり
2280 広袖にそゞろ秋立つ旅籠哉
2281 鬢の影鏡にそよと今朝の秋
2282 朝貌や鳴海絞を朝のうち
2283 女して結はす水仙粽哉
(参考)「漱石氏と私(高浜虚子)」周辺(「抜粋」)
https://www.aozora.gr.jp/cards/001310/files/47741_37678.html
≪ 漱石氏が創作に筆を執りはじめるようになってから、氏と私との交渉も雑誌発行人と人気のある小説家との関係というようなものがだんだんと重きをなして来た。今までは漱石氏は英文学者として、私の尊敬する先輩として、また俳友として、利害関係の無い交際であったのであって、何か文章を書くように勧めて「猫」の第一回が出来たのも、それを以て『ホトトギス』の紙上を飾ろうとか、雑誌の売れ行きを増そうとか、そういうような考は少しもなく、尊敬する漱石氏が蘊蓄(うんちく)を傾けて文章を作ってみたらよかろうという位な軽い考であったのであるが、一度び「猫」が紙上に発表されて、それが読書界の人気を得て雑誌の売行(うりゆき)が増してみると、発行人としての私は勢い『ホトトギス』のために氏の寄稿を要望せねばならぬような破目になって来た。漱石氏もまたはじめの間はその要望を寧ろ幸いとして強いて創作の機会を見出すようにつとめつつあったらしかった。
そうこうしているうちに氏は一躍して文学界の大立物となってしまった。各種の雑誌は競うて君の作物を掲げ、その待遇も互に他におとらぬようにと競争するようになって来た。『ホトトギス』は従来原稿料というものを殆ど払ったことはなかったのであるが、「猫」には一頁一円の原稿料を払うことにした。そうしてこれはやがて他の作家にも及ぼしてすべての人の作物に同じような原稿料を仕払うことにした。しかしながら一頁一円の原稿料というものは、当時にあっても決して十分の待遇とはいえなかった。他の雑誌はもっと沢山の原稿料を支払って居るものであることが、後になって分った。今まで世間と殆んど没交渉であった『ホトトギス』は、原稿料の相場というようなものは皆目承知しなかった上に、四、五人の社員組織でやっていた窮屈な制度のもとにあっては、にわかに『ホトトギス』を世間体の雑誌に改革して競争場裡に打って出るというようなことは仲々難かしかった。漱石氏はそんなことには頓着なしに、『ホトトギス』は自分の生れ故郷としてこちらが要望するままに暇さえあれば筆を執ることをいつも快諾したのであったが、しかも他の雑誌社からの要求が烈しくなればなるほど自然『ホトトギス』のために筆を執る機会が少くなって来た。それと同時に氏はその門下生ともいうべき人々の作品を『ホトトギス』に紹介して、これを紙上に発表することを要求した。私は大概その要求に従った。中には止むを得ず載せたようなものもあったけれども、中にはまた沢山の傑作もあった。三重吉みえきち君をはじめとして今日文壇に名を成している漱石門下の多くの人が大概処女作を『ホトトギス』に発表するようになったのもそのためであった。
漱石氏はまた『ホトトギス』を今少し機関の備わった堂々とした雑誌にして発行したらよかろうという考を持もっていたのであった。私がその事を快諾さえすれば、氏は十分に力を尽してくれる考があったことと想像するがその頃の『ホトトギス』の事情はその要求を容いれることが出来なかった。これを詳しく書くのは面倒臭いが、要するに四方太君などは漱石氏の文芸に不服で、それよりも純正の写生文雑誌として世間の人気などに頓着なく押し進みたいという希望を持っていたし、発行人としての私はそんなことをして損ばかりしていてもやり切れないから、少しは世間に面(つら)を出して人気のあるものにしたいと、漱石氏の作品などを歓迎する傾きがあった。けれどもまた私としては、漱石氏のような考のもとに全然『ホトトギス』を改革してしまって、四方太君らを排斥してしまうことは出来ないし、また世間の雑誌の如く原稿料を潤沢にして漱石氏はじめ多くの新進作家諸君を優遇するとなると、ただ鳴るが面白いことになってしまって『ホトトギス』の世帯はとてもやり切れない、と考えたところから、いつも四方太君などに不平を抱かせながら、漱石氏らにもまた慊(あき)たらぬ思いをさせるような態度で、その日暮(ひぐらし)に雑誌を出していた。
明治三十九年以後の漱石氏と私との関係は、今言ったような有様で、ある時は漱石氏から私に対して雑誌編輯の上の督励となったり、後進の推薦となったり、また一般文壇に対する不平や懊悩(おうのう)を訴えて来るような場合も少くなかったが、今手紙を取り出してみても、最も多いのは私の原稿の依頼に対して何日までに書くとか、何枚書いたとかこう忙(せわし)くってはやり切れないとかいう用談の方が多くなって来て居る。今その手紙について一々当時の聯想を書いてみたら面白いのであるが、手紙だけの分量でもかなり多い上にその手紙だけでほぼ当時の状態も想像せられることと思うから左に明治三十九年の手紙で、手元に残って居るもの一切を掲載することにする。≫

「吾輩は猫である」初出/俳句雑誌「ホトトギス」(第8巻4号・1905年・明治35年1月)
https://www.facebook.com/SosekiFan/photos/a.190617470970894/1350207411678555/?type=3
「ホトトギス((第8巻)」(目次集)
http://www.hototogisu.co.jp/
第4号/明治38年(1905)1月
第5号/明治38年(1905)2月
第6号/明治38年(1905)3月
第7号/明治38年(1905)4月
第8号/明治38年(1905)5月
第9号/明治38年(1905)6月
第10号/明治38年(1905)7月
第11号/明治38年(1905)7月
第12号/明治38年(1905)8月
第13号/明治38年(1905)9月
「吾輩は猫である」(「初出」と「単行本」)
https://www.library.tohoku.ac.jp/collection/collection/soseki/syuyo-neko.html

(初出)『ホトトギス』 明治38年1月~明治39年8月まで10回にわたり断続的に連載
(単行本)上編 明治38年10月 中編 明治39年11月 下編 明治40年5月 大倉書店・服部書店
≪(内 容)
猫を語り手として苦沙弥・迷亭ら太平の逸民たちに滑稽と諷刺を存分に演じさせ語らせたこの小説は「坊っちゃん」とあい通ずる特徴をもっている。それは溢れるような言語の湧出と歯切れのいい文体である。この豊かな小説言語の水脈を発見することで英文学者・漱石は小説家漱石(1867-1916)となった。(岩波文庫解説より)
(自作への言及)
東風君、苦沙弥君、皆勝手な事を申候。それ故に太平の逸民に候。現実世界にあの主義では如何と存候。御反対御尤に候。漱石先生も反対に候。
彼らのいふ所は皆真理に候。しかしただ一面の真理に候。決して作者の人生観の全部に無之故(これなきゆえ)その辺は御了知被下(くだされたく)候。あれは総体が諷刺に候。現代にあんな諷刺は尤も適切と存じ『猫』中に収め候。もし小生の個性論を論文としてかけば反対の方面と双方の働きかける所を議論致したくと存候。
(明治39年8月7日 畔柳芥舟あて書簡より)
『猫』ですか、あれは最初は何もあのように長く続けて書こうという考えもなし、腹案などもありませんでしたから無論一回だけでしまうつもり。またかくまで世間の評判を受けようとは少しも思っておりませんでした。最初虚子君から「何か書いてくれ」と頼まれまして、あれを一回書いてやりました。丁度その頃文章会というものがあって、『猫』の原稿をその会へ出しますと、それをその席で寒川鼠骨君が朗読したそうですが、多分朗読の仕方でも旨かったのでしょう、甚くその席で喝采を博したそうです。(中略)
妙なもので、書いてしまった当座は、全然胸中の文字を吐き出してしまって、もうこの次には何も書くようなことはないと思うほどですが、さて十日経ち廿日経って見ると日々の出来事を観察して、また新たに書きたいような感想も湧いて来る。材料も蒐められる。こんな風ですから『猫』などは書こうと思えば幾らでも長く続けられます。(「文学談」)≫(「東北大学附属図書館 夏目漱石ライブラリ」)
http://neko.koyama.mond.jp/?eid=209617
≪「俳句の五十年(高浜虚子著)」抜粋
ある時私は漱石が文章でも書いて見たならば気が紛れるだろうと思いまして、文章を書いて見ることを勧めました。私は別に気にも留めずにおったのでありまして、果して出来るか、出来んかも分らんと考えておったのでありました。ところが、その日になって立寄ってみますと、非常に長い文章が出来ておりまして、頗(すこぶ)る機嫌が良くって、ぜひこれを一つ自分の前で読んでみてくれろという話でありました。文章会は時間が定まっておりまして、その時間際に漱石の所に立寄ったのでありましたが、そういわれるものですから止むを得ず私はその文章を読んでみました。ところがなかなか面白い文章であって、私等仲間の文章とすると、分量も多くそれに頗る異色のある文章でありましたから、これは面白いから、早速今日の文章会に持出して読んでみるからといって、それを携えて文章会に臨みました。私がその漱石の家で読んだ時分に、題はまだ定めてありませんでして、「猫伝」としようかという話があったのでありますが、「猫伝」というよりも、文章の初めが「吾輩は猫である。名前はまだない」という書き出しでありますから、その「吾輩は猫である」という冒頭の一句をそのまま表題にして「吾輩は猫である」という事にしたらどうかというと、漱石は、それでも結構だ、名前はどうでもいいからして、私に勝手につけてくれろ、という話でありました。それでその原稿を持って帰って、「ホトトギス」に載せます時分に、「吾輩は猫である」という表題を私が自分で書き入れまして、それを活版所に廻したのでありました。
それからその時分は、誰の文章でも一応私が眼を通して、多少添削するという習慣でありましたからして、この『吾輩は猫である』という文章も更に読み返してみまして、無駄だと思われる箇所の文句はそれを削ったのでありました。そうしてそれを三十八年の一月号に発表しますというと、大変な反響を起しまして、非常な評判になりました。それというのも、大学の先生である夏目漱石なる者が小説を書いたという事で、その時分は大学の先生というものは、いわゆる象牙の塔に籠もっていて、なかなか小説などは書くものではないという考えがあったのでありますが、それが小説を書いたというので、著しく世人の眼を欹(そばだ)たしめたものでありました。そればかりではなく、大変世間にある文章とは類を異にしたところからして、非常な評判となったのでありました。
それで、漱石は、ただ私が初めて文章を書いてみてはどうかと勧めた為に書いたという事が、動機となりまして、それから漱石の生活が一転化し、気分も一転化するというような傾きになってきたのでありました。それと同時に『倫敦塔』という文章も書きまして「帝国文学」の誌上に発表しました。
それから『吾輩は猫である』が、大変好評を博したものですから、それは一年と八ヶ月続きまして、続々と続篇を書く、而(しか)もその続篇は、この第一篇よりも遙かに長いものを書いて、「ホトトギス」は殆(ほとん)どその『吾輩は猫である』の続篇で埋ってしまうというような勢いになりました。それが為に「ホトトギス」もぐんぐんと毎号部数が増して行くというような勢いでありました。≫
(追記) 夏目漱石俳句集(その八)<制作年順> 明40年(1907年)~明治44年(1911年)(1910~2283)
明治40年(1907年)
1910 御降になるらん旗の垂れ具合
1911 隠れ住んで此御降や世に遠し
1912 御降に閑なる床や古法眼
1913 打つ畠に小鳥の影の屡す
1914 物いはぬ人と生れて打つ畠か
1915 長短の風になびくや花芒
1916 月今宵もろもろの影動きけり
1917 里の灯を力によれば燈籠かな
1918 春寒の社頭に鶴を夢みけり
1919 布さらす磧わたるや春の風
1920 屑買の垣より呼べば蝶黄なり
1921 香焚けば焚かざれば又来る蝶
1922 旅に寒し春を時雨れの京にして
1923 永き日や動き已みたる整時板
1924 加茂にわたす橋の多さよ春の風
1925 雀巣くふ石の華表や春の風
1926 花食まば鶯の糞も赤からん
1927 姫百合に筒の古びやずんど切
1928 恋猫の眼ばかりに痩せにけり
1929 藤の花に古き四尺の風が吹く
1930 若葉して又新なる心かな
1931 髪に真珠肌あらはなる涼しさよ
1932 時鳥厠半ばに出かねたり
1933 のうぜんの花を数へて幾日影
1934 看経の下は蓮池の戦かな
1935 蓮剪りに行つたげな椽に僧を待つ
1936 蓮に添へてぬめの白さよ漾虚集
1937 白蓮に仏眠れり磬落ちて
1938 生死事大蓮は開いて仕舞けり
1939 ほのぼのと舟押し出すや蓮の中
1940 蓑の下に雨の蓮を蔵しけり
1941 田の中に一坪咲いて窓の蓮
1942 夕蓮に居士渡りけり石欄干
1943 明くる夜や蓮を放れて二三尺
1944 蓮の欄舟に鋏を渡しけり
1945 蓮の葉に麩はとゞまりぬ鯉の色
1946 石橋の穴や蓮ある向側
1947 一八の家根をまはれば清水かな
1948 したゝりは歯朶に飛び散る清水かな
1949 宝丹のふたのみ光る清水かな
1950 苔清水天下の胸を冷やしけり
1951 ところてんの叩かれてゐる清水かな
1952 底の石動いて見ゆる清水哉
1953 二人して片足宛の清水かな
1954 懸崖に立つ間したゝる清水哉
1955 したゝりは襟をすくます清水かな
1956 両掛や関のこなたの苔清水
1957 市に入る花売憩う清水かな
1958 樟の香や村のはづれの苔清水
1959 澄みかゝる清水や小き足の跡
1960 法印の法螺に蟹入る清水かな
1961 追付て吾まづ掬ぶ清水かな
1962 三どがさをまゝよとひたす清水かな
1963 汗を吹く風は歯朶より清水かな
1964 岩清水十戸の村の筧かな
1965 かち渡る鹿や半ばに返り見る
1966 二三人砧も打ちぬ鹿の声
1967 寄りくるや豆腐の糟に奈良の鹿
1968 橋立や松一筋に秋の空
1969 抽んでゝ富士こそ見ゆれ秋の空
1970 鱸釣つて舟を蘆間や秋の空
1971 春の水岩ヲ抱イテ流レケリ
1972 花落チテ砕ケシ影ト流レケリ
1973 朝貌や惚れた女も二三日
1974 垣間見る芙蓉に露の傾きぬ
1975 秋風や走狗を屠る市の中
1976 山の温泉や欄に向へる鹿の面
1977 灯火を挑げて鹿の夜は幾時
1978 芋の葉をごそつかせ去る鹿ならん
1979 厠より鹿と覚しや鼻の息
1980 山門や月に立たる鹿の角
1981 ひいと鳴て岩を下るや鹿の尻
1982 水浅く首を伏せけり月の鹿
1983 見下して尾上に鹿のひとり哉
1984 行燈に奈良の心地や鹿の声
1985 漫寒の温泉も三度目や鹿の声
1986 岩高く見たり牡鹿の角二尺
1987 蕎麦太きもてなし振や鹿の角
1988 郡長を泊めてたまたま鹿の声
1989 宵の鹿夜明の鹿や夢短か
1990 暁に消ぬ可き月に鹿あはれ
1991 秋の空幾日迎いで京に着きぬ
1992 雲少し榛名を出でぬ秋の空
1993 押分る芒の上や秋の空
1994 秋の空鳥海山を仰ぎけり
1995 朝顔の今や咲くらん空の色
1996 立秋の風に光るよ蜘蛛の糸
1997 恩給に事足る老の黄菊かな
1998 菊に結へる四っ目の垣もまだ青し
1999 端渓に菊一輪の机かな
2000 杉垣に昼をこぼれて百日紅
2001 酸多き胃を患ひてや秋の雨
2002 大鼓芙蓉の雨にくれ易し
2003 後仕手の撞木や秋の橋掛り
2004 朝日のつと千里の黍に上りけり
2005 露けさの庵を繞りて芙蓉かな
2006 露けさの中に帰るや小提灯
2007 かりがねの斜に渡る帆綱かな
2008 雁や渡る乳玻璃に細き灯を護る
2009 北窓は鎖さで居たり月の雁
2010 傾城に鳴くは故郷の雁ならん
2011 夕雁や物荷ひ行く肩の上
2012 灯を入るゝ軒行燈や雁低し
2013 帆柱をかすれて月の雁の影
2014 客となつて沢国に雁の鳴く事多し
2015 遠近の砧に雁の落るなり
2016 提灯に雁落つらしも闇の畔
2017 花びらの狂ひや菊の旗日和
2018 侘住居作らぬ菊を憐めり
2019 白菊や書院へ通る腰のもの
2020 草庵の垣にひまある黄菊かな
2021 旗一竿菊のなかなる主人かな
2022 草共に桔梗を垣に結ひ込みぬ
2023 白桔梗古き位牌にすがすがし
2024 草刈の籠の目を洩る桔梗かな
2025 桔梗活けて宝生流の指南かな
2026 扶け起す萩の下より鼬かな
2027 ふき易へて萱に聴けり秋の雨
2028 藁葺に移れば一夜秋の雨
2029 雷の図にのりすぎて落にけり
2030 秋の蚊の鳴かずなりたる書斎かな
2031 黒塀にあたるや妹が雪礫
2032 女の童に小冠者一人や雪礫
2033 茶の花や黄檗山を出でゝ里余
2034 丸髷に結ふや咲く梅紅に
2035 むら鴉何に集る枯野かな
2036 川ありて遂に渡れぬ枯野かな
2037 法螺の音の何処より来る枯野哉
2038 たゝむ傘に雪の重みや湯屋の門
2039 吾影の吹かれて長き枯野哉
2040 女うつ鼓なるらし春の宵
2041 白絹に梅紅ゐの女院かな
2042 酒買ひに里に下るや鹿も聞き
2043 文債に籠る冬の日短かゝり
明治41年(1908年)
2044 日毎踏む草芳しや二人連
2045 二人して雛にかしづく楽しさよ
2046 鼓打ちに参る早稲田や梅の宵
2047 青柳擬宝珠の上に垂るゝなり
2048 居士が家を柳此頃蔵したり
2049 門に立てば酒乞ふ人や帽に花
2050 鶯の日毎巧みに日は延びぬ
2051 吾に媚ぶる鶯の今日も高音かな
2052 勅額の霞みて松の間かな
2053 飯蛸の一かたまりや皿の藍
2054 飯蛸や膳の前なる三保の松
2055 飯蛸と侮りそ足は八つあると
2056 春の水たるむはづなを濡しけり
2057 連翹に小雨来るや八っ時分
2058 花曇り尾上の鐘の響かな
2059 籠の鳥に餌をやる頃や水温む
2060 山伏の関所へかゝる桜哉
2061 強力の笈に散る桜かな
2062 南天に寸の重みや春の雪
2063 真蒼な木賊の色や冴返る
2064 そゝのかす女の眉や春浅し
2065 塩辛を壺に探るや春浅し
2066 名物の椀の蜆や春浅し
2067 僧となつて鐘を撞いたら冴返る
2068 穴のある銭が袂に暮の春
2069 いつか溜る文殻結ふや暮の春
2070 逝く春や庵主の留守の懸瓢
2071 嫁がぬを日に白粉や春惜む
2072 垢つきし赤き手絡や春惜む
2073 春惜む人にしきりに訪はれけり
2074 おくれたる一本桜憐なり
2075 逝く春やそゞろに捨てし草の庵
2076 青柳の日に緑なり句を撰む
2077 短夜を交す言葉もなかりけり
2078 文を売りて薬にかふる蚊遣かな
2079 安産と涼しき風の音信哉
2080 二人寐の蚊帳も程なく狭からん
2081 青梅や空しき籠に雨の糸
2082 五月雨や主と云はれし御月並
2083 鮟鱇や小光が鍋にちんちろり
2084 まのあたり精霊来たり筆の先
2085 此の下に稲妻起る宵あらん
2086 朝寒や自ら炊ぐ飯二合
2087 公退や菊に閑ある雑司ケ谷
2088 大輪の菊を日に揺る車かな
2089 たゞ一つ湯婆残りぬ室の隅
2090 春色や暮れなんとして水深み
2091 一つ家を中に夜すがら五月雨るゝ
2092 垣老て虞美人草のあらはなる
明治42年(1909年)
2093 小袖着て思ひ思ひの春をせん
2094 初日の出しだいに見ゆる雲静か
2095 とかくして鶯藪に老いにけり
2096 空に消ゆる鐸のひゞきや春の塔
2097 俊寛と共に吹かるゝ千鳥かな
2098 五月雨やももだち高く来る人
2099 初秋の芭蕉動きぬ枕元
2100 春はものゝ句になり易し京の町
2101 手を分つ古き都や鶉鳴く
2102 黍遠し河原の風呂へ渡る人
2103 黍行けば黍の向ふに入る日かな
2104 草尽きて松に入りけり秋の風
2105 鞭鳴らす頭の上や星月夜
2106 なつかしき土の臭や松の秋
2107 負ふ草に夕立早く逼るなり
2108 高麗人の冠を吹くや秋の風
2109 秋の山に逢ふや白衣の人にのみ
2110 秋晴や山の上なる一つ松
2111 故郷を舞ひつゝ出づる霞かな
2112 動かざる一篁や秋の村
2113 帰り見れば蕎麦まだ白き稲みのる
2114 銅の牛の口より野分哉
明治43年(1910年)
2115 独居や思ふ事なき三ケ日
2116 御堂まで一里あまりの霞かな
2117 花びらに風薫りては散らんとす
2118 ふと揺るゝ蚊帳の釣手や今朝の秋
2119 秋の思ひ池を繞れば魚躍る
2120 宮様の御立のあとや温泉の秋
2121 尺八を秋のすさみや欄の人
2122 温泉の村に弘法様の花火かな
2123 別るゝや夢一筋の天の川
2124 秋の江に打ち込む杭の響かな
2125 秋風や唐紅の咽喉仏
2126 秋晴に病間あるや髭を剃る
2127 秋の空浅黄に澄めり杉に斧
2128 衰に夜寒逼るや雨の音
2129 旅にやむ夜寒心や世は情
2130 蕭々の雨と聞くらん宵の伽
2131 秋風やひゞの入りたる胃の袋
2132 風流の昔恋しき紙衣かな
2133 生残る吾恥かしや鬢の霜
2134 立秋の紺落ち付くや伊予絣
2135 骨立を吹けば疾む身に野分かな
2136 稍寒の鏡もなくに櫛る
2137 鯛切れば鱗眼を射る稍寒み
2138 病む日又簾の隙より秋の蝶
2139 病んでより白萩に露の繁く降る事よ
2140 蜻蛉の夢や幾度杭の先
2141 蜻蛉や留り損ねて羽の光
2142 取り留むる命も細き薄かな
2143 仏より痩せて哀れや曼珠沙華
2144 虫遠近病む夜ぞ静なる心
2145 余所心三味聞きゐればそゞろ寒
2146 月を亘るわがいたつきや旅に菊
2147 起きもならぬわが枕辺や菊を待つ
2148 生き返るわれ嬉しさよ菊の秋
2149 たそがれに参れと菊の御使ひ
2150 範頼の墓濡るゝらん秋の雨
2151 菊作り門札見れば左京かな
2152 洪水のあとに色なき茄子かな
2153 菜の花の中の小家や桃一木
2154 秋浅き楼に一人や小雨がち
2155 生きて仰ぐ空の高さよ赤蜻蛉
2156 鶴の影穂蓼に長き入日かな
2157 一山や秋色々の竹の色
2158 古里に帰るは嬉し菊の頃
2159 静なる病に秋の空晴れたり
2160 菊の宴に心利きたる下部かな
2161 大切に秋を守れと去りにけり
2162 竪に見て事珍らしや秋の山
2163 坐して見る天下の秋も二た月目
2164 ともし置いて室明き夜の長かな
2165 堂守に菊乞ひ得たる小銭かな
2166 力なや痩せたる吾に秋の粥
2167 佳き竹に吾名を刻む日長かな
2168 見もて行く蘇氏の印譜や竹の露
2169 秋草を仕立てつ墓を守る身かな
2170 秋の蚊や我を螫さんと夜明方
2171 頼家の昔も嘸栗の味
2172 鮎の丈日に延びつらん病んでより
2173 肌寒をかこつも君の情かな
2174 貧しからぬ秋の便りや枕元
2175 京に帰る日も近付いて黄菊哉
2176 稲の香や月改まる病心地
2177 天の河消ゆるか夢の覚束な
2178 裏座敷林に近き百舌の声
2179 帰るは嬉し梧桐の未だ青きうち
2180 帰るべくて帰らぬ吾に月今宵
2181 雲を洩る日ざしも薄き一葉哉
2182 甦へる我は夜長に少しづゝ
2183 骨の上に春滴るや粥の味
2184 鶺鴒や小松の枝に白き糞
2185 寐てゐれば粟に鶉の興もなく
2186 粟の如き肌を切に守る身かな
2187 冷やかな瓦を鳥の遠近す
2188 冷かや人寐静まり水の音
2189 的礫と壁に野菊を照し見る
2190 鳥つゝいて半うつろのあけび哉
2191 朝寒や太鼓に痛き五十棒
2192 先づ黄なる百日紅に小雨かな
2193 いたつきも久しくなりぬ柚は黄に
2194 足腰の立たぬ案山子を車かな
2195 骨許りになりて案山子の浮世かな
2196 病んで来り病んで去る吾に案山子哉
2197 濡るゝ松の間に蕎麦を見付たる
2198 藪陰や濡れて立つ鳥蕎麦の花
2199 稲熟し人癒えて去るや温泉の村
2200 柿紅葉せり纏はる蔦の青き哉
2201 就中竹緑也秋の村
2202 数ふべく大きな芋の葉なりけり
2203 新らしき命に秋の古きかな
2204 逝く人に留まる人に来る雁
2205 鶏頭に後れず或夜月の雁
2206 釣台に野菊も見えぬ桐油哉
2207 思ひけり既に幾夜の蟋蟀
2208 過ぎし秋を夢みよと打ち覚めよとうつ
2209 朝寒も夜寒も人の情かな
2210 顧みる我面影やすでに秋
2211 暁や夢のこなたに淡き月
2212 ぶら下る蜘蛛の糸こそ冷やかに
2213 嬉しく思ふ蹴鞠の如き菊の影
2214 肩に来て人懐かしや赤蜻蛉
2215 渋柿も熟れて王維の詩集哉
2216 つくづくと行燈の夜の長さかな
2217 小行燈夜半の秋こそ古めけり
2218 一叢の薄に風の強き哉
2219 雨多き今年と案山子聞くからに
2220 柿一つ枝に残りて烏哉
2221 君が琴塵を払へば鳴る秋か
2222 たゞ一羽来る夜ありけり月の雁
2223 明けの菊色未だしき枕元
2224 日盛りやしばらく菊を縁のうち
2225 縁に上す君が遺愛の白き菊
2226 井戸の水汲む白菊の晨哉
2227 蔓で堤げる目黒の菊を小鉢哉
2228 いたつきも怠る宵や秋の雨
2229 形ばかりの浴す菊の二日哉
2230 三日の菊雨と変るや昨夕より
2231 白菊と黄菊と咲いて日本かな
2232 菊の香や幾鉢置いて南縁
2233 生垣の隙より菊の渋谷かな
2234 暖簾に芸人の名を茶屋の菊
2235 青山に移りていつか菊の主
2236 搨置いて菊あるところどころかな
2237 燭し見るは白き菊なれば明らさま
2238 菊の雨われに閑ある病哉
2239 菊の色縁に未し此晨
2240 蔵沢の竹を得てより露の庵
2241 柩には菊抛げ入れよ有らん程
2242 有る程の菊抛げ入れよ棺の中
2243 ひたすらに石を除くれば春の水
2244 病んで夢む天の川より出水かな
2245 風に聞け何れか先に散る木の葉
2246 萩に置く露の重きに病む身かな
2247 冷やかな脈を護りぬ夜明方
2248 露けさの里にて静かなる病
2249 迎火を焚いて誰待つ絽の羽織
2250 朝寒や生きたる骨を動かさず
2251 無花果や竿に草紙を縁の先
2252 屠牛場の屋根なき門や夏木立
2253 勾欄の擬宝珠に一つ蜻蛉哉
2254 冷かな文箱差出す蒔絵かな
2255 冷かな足と思ひぬ病んでより
2256 冷ややかに觸れても見たる擬宝珠哉
2257 冷やかに抱いて琴の古きかな
2258 提灯を冷やかに提げ芒かな
2259 なに食はぬ和尚の顔や河豚汁
2260 浦の男に浅瀬問ひ居る朧哉
明治44年(1911年)
2261 腸に春滴るや粥の味
2262 蝶去つてまた蹲踞る小猫かな
2263 たく駝して石を除くれば春の水
2264 鶏の尾を午頃吹くや春の風
2265 冠せぬ男も船に春の風
2266 涼しさや蚊帳の中より和歌の浦
2267 四国路の方へなだれぬ雲の峰
2268 起きぬ間に露石去にけり今朝の秋
2269 蝙蝠の宵々毎や薄き粥
2270 稲妻に近くて眠り安からず
2271 灯を消せば涼しき星や窓に入る
2272 風折々萩先づ散つて芒哉
2273 耳の底の腫物を打つや秋の雨
2274 切口に冷やかな風の厠より
2275 たのまれて戒名選む鶏頭哉
2276 抱一の芒に月の円かなる
2277 稲妻に近き住居や病める宵
2278 石段の一筋長き茂りかな
2279 空に雲秋立つ台に上りけり
2280 広袖にそゞろ秋立つ旅籠哉
2281 鬢の影鏡にそよと今朝の秋
2282 朝貌や鳴海絞を朝のうち
2283 女して結はす水仙粽哉
(参考)「漱石氏と私(高浜虚子)」周辺(「抜粋」)
https://www.aozora.gr.jp/cards/001310/files/47741_37678.html
≪ 漱石氏が創作に筆を執りはじめるようになってから、氏と私との交渉も雑誌発行人と人気のある小説家との関係というようなものがだんだんと重きをなして来た。今までは漱石氏は英文学者として、私の尊敬する先輩として、また俳友として、利害関係の無い交際であったのであって、何か文章を書くように勧めて「猫」の第一回が出来たのも、それを以て『ホトトギス』の紙上を飾ろうとか、雑誌の売れ行きを増そうとか、そういうような考は少しもなく、尊敬する漱石氏が蘊蓄(うんちく)を傾けて文章を作ってみたらよかろうという位な軽い考であったのであるが、一度び「猫」が紙上に発表されて、それが読書界の人気を得て雑誌の売行(うりゆき)が増してみると、発行人としての私は勢い『ホトトギス』のために氏の寄稿を要望せねばならぬような破目になって来た。漱石氏もまたはじめの間はその要望を寧ろ幸いとして強いて創作の機会を見出すようにつとめつつあったらしかった。
そうこうしているうちに氏は一躍して文学界の大立物となってしまった。各種の雑誌は競うて君の作物を掲げ、その待遇も互に他におとらぬようにと競争するようになって来た。『ホトトギス』は従来原稿料というものを殆ど払ったことはなかったのであるが、「猫」には一頁一円の原稿料を払うことにした。そうしてこれはやがて他の作家にも及ぼしてすべての人の作物に同じような原稿料を仕払うことにした。しかしながら一頁一円の原稿料というものは、当時にあっても決して十分の待遇とはいえなかった。他の雑誌はもっと沢山の原稿料を支払って居るものであることが、後になって分った。今まで世間と殆んど没交渉であった『ホトトギス』は、原稿料の相場というようなものは皆目承知しなかった上に、四、五人の社員組織でやっていた窮屈な制度のもとにあっては、にわかに『ホトトギス』を世間体の雑誌に改革して競争場裡に打って出るというようなことは仲々難かしかった。漱石氏はそんなことには頓着なしに、『ホトトギス』は自分の生れ故郷としてこちらが要望するままに暇さえあれば筆を執ることをいつも快諾したのであったが、しかも他の雑誌社からの要求が烈しくなればなるほど自然『ホトトギス』のために筆を執る機会が少くなって来た。それと同時に氏はその門下生ともいうべき人々の作品を『ホトトギス』に紹介して、これを紙上に発表することを要求した。私は大概その要求に従った。中には止むを得ず載せたようなものもあったけれども、中にはまた沢山の傑作もあった。三重吉みえきち君をはじめとして今日文壇に名を成している漱石門下の多くの人が大概処女作を『ホトトギス』に発表するようになったのもそのためであった。
漱石氏はまた『ホトトギス』を今少し機関の備わった堂々とした雑誌にして発行したらよかろうという考を持もっていたのであった。私がその事を快諾さえすれば、氏は十分に力を尽してくれる考があったことと想像するがその頃の『ホトトギス』の事情はその要求を容いれることが出来なかった。これを詳しく書くのは面倒臭いが、要するに四方太君などは漱石氏の文芸に不服で、それよりも純正の写生文雑誌として世間の人気などに頓着なく押し進みたいという希望を持っていたし、発行人としての私はそんなことをして損ばかりしていてもやり切れないから、少しは世間に面(つら)を出して人気のあるものにしたいと、漱石氏の作品などを歓迎する傾きがあった。けれどもまた私としては、漱石氏のような考のもとに全然『ホトトギス』を改革してしまって、四方太君らを排斥してしまうことは出来ないし、また世間の雑誌の如く原稿料を潤沢にして漱石氏はじめ多くの新進作家諸君を優遇するとなると、ただ鳴るが面白いことになってしまって『ホトトギス』の世帯はとてもやり切れない、と考えたところから、いつも四方太君などに不平を抱かせながら、漱石氏らにもまた慊(あき)たらぬ思いをさせるような態度で、その日暮(ひぐらし)に雑誌を出していた。
明治三十九年以後の漱石氏と私との関係は、今言ったような有様で、ある時は漱石氏から私に対して雑誌編輯の上の督励となったり、後進の推薦となったり、また一般文壇に対する不平や懊悩(おうのう)を訴えて来るような場合も少くなかったが、今手紙を取り出してみても、最も多いのは私の原稿の依頼に対して何日までに書くとか、何枚書いたとかこう忙(せわし)くってはやり切れないとかいう用談の方が多くなって来て居る。今その手紙について一々当時の聯想を書いてみたら面白いのであるが、手紙だけの分量でもかなり多い上にその手紙だけでほぼ当時の状態も想像せられることと思うから左に明治三十九年の手紙で、手元に残って居るもの一切を掲載することにする。≫
夏目漱石の「俳句と書画」(その十一) [「子規と漱石」の世界]
その十一 漱石の「子規没後の俳句その一)」(「明治三十七年~四十年」周辺)
https://www.ndl.go.jp/exhibit70/23.html
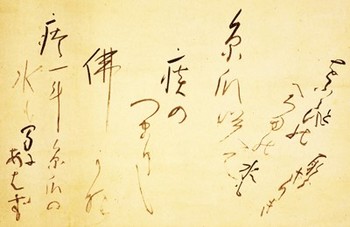
「絶筆三句 子規」(紙本墨書/31.0×44.3㎝/国立国会図書館蔵)
https://www.ndl.go.jp/exhibit70/23.html
≪〔正岡子規 著〕〔正岡子規 明治35(1902)年〕写【WB41-61】43 〔絶筆三句〕の画像(デジタルコレクション)
日本の近代文学に多大な影響を及ぼした俳人、歌人の正岡子規が臨終間際に書き残した三句。明治35(1902)年9月18日の午前11時頃、紙を貼りつけた画板を妹の律に持たせ、仰臥しながら記した。翌19日午前1時頃、子規の息は絶えた。満34歳の若さであった。病魔に苦しみながらも、死の直前まで俳人として生き抜いた壮絶な姿がうかがえる。
(書き起こし)
をととひのへちまの水も取らざりき/糸瓜咲て痰のつまりし佛かな/痰一斗糸瓜の水も間にあはず ≫
(漱石「略年譜」)「東北大学附属図書館 夏目漱石ライブラリ」
https://www.library.tohoku.ac.jp/collection/collection/soseki/nenpu.html
明治35(1902) 9月 子規死去
10月 スコットランド旅行
12月 帰国の途に着く
明治36(1903) 1月 帰国
4月 第一高等学校講師 東京帝国大学英文科講師
10月 三女・英子誕生 藤村操自殺
明治37(1904) 4月 明治大学講師
12月 「吾輩は猫である」を「山会」で朗読
明治38(1905) 1月 「吾輩は猫である」(『ホトトギス』)
1月 「倫敦塔」(『帝国文学』)
1月 「カーライル博物館」(『学燈』)
6月 「琴のそら音」(『七人』)
12月 四女・愛子誕生
明治39(1906) 4月 「坊っちやん」(『ホトトギス』)
9月 「草枕」(『新小説』)
10月 「二百十日」
10月11日 第1回「木曜会」 伊藤左千夫『野菊の墓』
明治40(1907) 1月 「野分」(『ホトトギス』)
3月末~4月初 京都 大阪に旅行
5月 『文学論』(大倉書店)
5月 入社の辞(『東京朝日新聞』)
6月 長男・純一誕生
6月~10月 「虞美人草」
6月 西園寺公望からの文士招聘会を断る
9月 牛込区早稲田南町7番地へ転居
(追記) 夏目漱石俳句集(その七)<制作年順> 明37年(1904年)~明治39年(1906年)
明治37年(1904年)
1851 人の上春を写すや絵そら言
1852 ともし寒く梅花書屋と題しけり
1853 鳩鳴いて烟の如き春に入る
1854 杳として桃花に入るや水の色
1855 雨ともならず唯凩の吹き募る
1856 見るからに涼しき島に住むからに
1857 骸骨を叩いて見たる菫かな
1858 罪もうれし二人にかゝる朧月
1859 小夜時雨眠るなかれと鐘を撞く
1860 伏す萩の風情にそれと覚りてよ
1861 白菊にしばし逡巡らふ鋏かな
1862 女郎花を男郎花とや思ひけん
1863 人形の独りと動く日永かな
1864 世を忍ぶ男姿や花吹雪
1865 野に下れば白髯を吹く風涼し
1866 夏の月眉を照して道遠し
1867 十銭で名画を得たり時鳥
1868 秋立や断りもなくかやの内
1869 ばつさりと後架の上の一葉かな
1870 秋風のしきりに吹くや古榎
1871 名月や杉に更けたる東大寺
明治38年(1905年)
1872 朝貌の葉影に猫の眼玉かな
1873 蓮の葉に蜘蛛下りけり香を焚く
1874 初時雨故人の像を拝しけり
1875 うそ寒み故人の像を拝しけり
1876 白菊の一本折れて庵淋し
1877 只寒し封を開けば影法師
1878 一人住んで聞けば雁なき渡る
明治39年(1906年)
1879 寄りそへばねむりておはす春の雨
1880 本来はちるべき芥子にまがきせり
1881 短冊に元禄の句や京の春
1882 春風や惟然が耳に馬の鈴 (『草枕』より十七句~)
1883 馬子唄や白髪も染めで暮るゝ春
1884 花の頃を越えてかしこし馬に嫁
1885 海棠の露をふるふや物狂ひ
1886 花の影、女の影の朧かな
1887 正一位、女に化けて朧月
1888 春の星を落して夜半のかざしかな
1889 春の夜の雲に濡らすや洗ひ髪
1890 春や今宵歌つかまつる御姿
1891 海棠の精が出てくる月夜かな
1892 うた折々月下の春ををちこちす
1893 思ひ切つて更け行く春の独りかな
1894 海棠の露をふるふや朝烏
1895 花の影女の影を重ねけり
1896 御曹司女に化けて朧月
1897 木蓮の花許りなる空を瞻る
1898 春風にそら解け襦子の銘は何(~『草枕』より十七句)
1899 釣鐘のうなる許りに野分かな
1900 祖師堂に昼の灯影や秋の雨
1901 かき殻を屋根にわびしや秋の雨
1902 青楼や欄のひまより春の海
1903 渡殿の白木めでたし秋の雨
1904 春雨や爪革濡るゝ湯屋迄
1905 暮れなんとしてほのかに蓼の花を踏む
1906 乱菊や土塀の窓の古簀垂
1907 冬籠り染井の墓地を控へけり
1908 鰒汁と知らで薦めし寐覚かな
1909 春を待つ下宿の人や書一巻
(参考その一)「絶筆三句 子規」周辺
http://www.sakanouenokumo.com/siki_zeppitu.htm
≪ 子規の辞世の句となった糸瓜の三句。その場に居合わせた河東碧梧桐は、当時の様子を次のように回顧している(出典「子規言行録(明治版)」)。
十八日の頃であったか、どうも様子が悪いという知らせに、胸を躍らせながら早速駆けつけた所、丁度枕辺には陸氏令閨と妹君が居られた。予は病人の左側近くへよって「どうかな」というと別に返辞もなく、左手を四五度動かした許りで静かにいつものまま仰向に寝て居る。余り騒々しくしてはわるいであろうと、予は口をつぐんで、そこに坐りながら妹君と、医者のこと薬のこと、今朝は痰が切れないでこまったこと、宮本へ痰の切れる薬をとりにやったこと、高浜を呼びにやったかどうかということなど話をして居た時に「高浜も呼びにおやりや」と病人が一言いうた。依って予は直ぐに陸氏の電話口へ往って、高浜に大急ぎで来いというて帰って見ると、妹君は病人の右側で墨を磨って居られる。軈《やがて》例の書板に唐紙の貼付けてあるのを妹君が取って病人に渡されるから、何かこの場合に書けるであろうと不審ながらも、予はいつも病人の使いなれた軸も穂も細長い筆に十分墨を含ませて右手へ渡すと、病人は左手で板の左下側を持ち添え、上は妹君に持たせて、いきなり中央へ
糸瓜咲て
とすらすらと書きつけた。併し「咲て」の二字はかすれて少し書きにくそうであったので、ここで墨をついでまた筆を渡すと、こんど糸瓜咲てより少し下げて
痰のつまりし
までまた一息に書けた。字がかすれたのでまた墨をつぎながら、次は何と出るかと、暗に好奇心に駆られて板面を注視して居ると、同じ位の高さに
佛かな
と書かれたので、予は覚えず胸を刺されるように感じた。書き終わって投げるように筆を捨てながら、横を向いて咳を二三度つづけざまにして痰が切れんので如何にも苦しそうに見えた。妹君は板を横へ片付けながら側に坐って居られたが、病人は何とも言わないで無言である。また咳が出る。今度は切れたらしく反故でその痰を拭きとりながら妹君に渡す。痰はこれまでどんなに苦痛の劇しい時でも必ず設けてある痰壺を自分で取って吐き込む例であったのに、きょうはもうその痰壺をとる勇気も無いと見える。その間四五分たったと思うと、無言に前の書板を取り寄せる。予も無言で墨をつける。今度は左手を書板に持ち添える元気もなかったのか、妹君に持たせたまま前句「佛かな」と書いたその横へ
痰一斗糸瓜の水も
と「水も」を別行に認めた。ここで墨ををつぐ。すぐ次へ
間に合わず
と書いて、矢張り投捨てるように筆を置いた。咳は二三度出る。如何にもせつなそうなので、予は以前にも増して動気が打って胸がわくわくして堪らぬ。また四五分も経てから、無言で板を持たせたので、予も無言で筆を渡す。今度は板の持ち方が少し具合が悪そうであったがそのまま少し筋違いに
をとひのへちまの
と「へちまの」は行をかえて書く。予は墨をここでつぎながら、「と」の字の上の方が「ふ」のように、その下の方が「ら」の字を略したもののように見えるので「をふらひのへちまの」とは何の事であろうと聊か怪しみながら見て居ると、次を書く前に自分で「ひ」の上へ「と」と書いて、それが「ひ」の上へはいるもののようなしるしをした。それで始めて「をとヽひの」であると合点した。そのあとはすぐに「へちまの」の下へ
水の
と書いて
取らざりき
はその右側へ書き流して、例の通り筆を投げすてたが、丁度穂が先に落ちたので、白い寝床の上は少し許り墨の痕をつけた。余は筆を片付ける。妹君は板を障子にもたせかけられる。しばらくは病人自身もその字を見て居る様子であったが、予はこの場合その句に向かって何と言うべき考えも浮かばなかった。がもうこれでお仕舞いであるか、紙には書く場所はないようであるけれども、また書かれはすまいかと少し心待ちにして硯の側を去ることが出来なかったが、その後再び筆を持とうともしなかった。 ≫
(参考その二) 「子規居士弄丹青図(浅井忠)」周辺

「子規居士弄丹青図」(「ホトトギス」正岡子規追悼号(明治35年12月)挿絵用画稿 浅井忠)
http://nobless.seesaa.net/article/483626589.html
≪浅井は子規没後、ホトトギスの子規追悼集に「子規居士弄丹青図」を描いて子規を哀悼している。サラサラと鉛筆で描いたような戯画風の絵で、縁側のほうにころがる3個の柿と鉢植えの花を写生しているのだろうか、無精ひげの子規が床に横になったまま絵を描いている。生前の子規の特徴をよくとらえた愛情あふれる絵だ。≫
https://www.ndl.go.jp/exhibit70/23.html
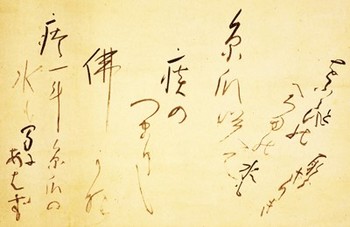
「絶筆三句 子規」(紙本墨書/31.0×44.3㎝/国立国会図書館蔵)
https://www.ndl.go.jp/exhibit70/23.html
≪〔正岡子規 著〕〔正岡子規 明治35(1902)年〕写【WB41-61】43 〔絶筆三句〕の画像(デジタルコレクション)
日本の近代文学に多大な影響を及ぼした俳人、歌人の正岡子規が臨終間際に書き残した三句。明治35(1902)年9月18日の午前11時頃、紙を貼りつけた画板を妹の律に持たせ、仰臥しながら記した。翌19日午前1時頃、子規の息は絶えた。満34歳の若さであった。病魔に苦しみながらも、死の直前まで俳人として生き抜いた壮絶な姿がうかがえる。
(書き起こし)
をととひのへちまの水も取らざりき/糸瓜咲て痰のつまりし佛かな/痰一斗糸瓜の水も間にあはず ≫
(漱石「略年譜」)「東北大学附属図書館 夏目漱石ライブラリ」
https://www.library.tohoku.ac.jp/collection/collection/soseki/nenpu.html
明治35(1902) 9月 子規死去
10月 スコットランド旅行
12月 帰国の途に着く
明治36(1903) 1月 帰国
4月 第一高等学校講師 東京帝国大学英文科講師
10月 三女・英子誕生 藤村操自殺
明治37(1904) 4月 明治大学講師
12月 「吾輩は猫である」を「山会」で朗読
明治38(1905) 1月 「吾輩は猫である」(『ホトトギス』)
1月 「倫敦塔」(『帝国文学』)
1月 「カーライル博物館」(『学燈』)
6月 「琴のそら音」(『七人』)
12月 四女・愛子誕生
明治39(1906) 4月 「坊っちやん」(『ホトトギス』)
9月 「草枕」(『新小説』)
10月 「二百十日」
10月11日 第1回「木曜会」 伊藤左千夫『野菊の墓』
明治40(1907) 1月 「野分」(『ホトトギス』)
3月末~4月初 京都 大阪に旅行
5月 『文学論』(大倉書店)
5月 入社の辞(『東京朝日新聞』)
6月 長男・純一誕生
6月~10月 「虞美人草」
6月 西園寺公望からの文士招聘会を断る
9月 牛込区早稲田南町7番地へ転居
(追記) 夏目漱石俳句集(その七)<制作年順> 明37年(1904年)~明治39年(1906年)
明治37年(1904年)
1851 人の上春を写すや絵そら言
1852 ともし寒く梅花書屋と題しけり
1853 鳩鳴いて烟の如き春に入る
1854 杳として桃花に入るや水の色
1855 雨ともならず唯凩の吹き募る
1856 見るからに涼しき島に住むからに
1857 骸骨を叩いて見たる菫かな
1858 罪もうれし二人にかゝる朧月
1859 小夜時雨眠るなかれと鐘を撞く
1860 伏す萩の風情にそれと覚りてよ
1861 白菊にしばし逡巡らふ鋏かな
1862 女郎花を男郎花とや思ひけん
1863 人形の独りと動く日永かな
1864 世を忍ぶ男姿や花吹雪
1865 野に下れば白髯を吹く風涼し
1866 夏の月眉を照して道遠し
1867 十銭で名画を得たり時鳥
1868 秋立や断りもなくかやの内
1869 ばつさりと後架の上の一葉かな
1870 秋風のしきりに吹くや古榎
1871 名月や杉に更けたる東大寺
明治38年(1905年)
1872 朝貌の葉影に猫の眼玉かな
1873 蓮の葉に蜘蛛下りけり香を焚く
1874 初時雨故人の像を拝しけり
1875 うそ寒み故人の像を拝しけり
1876 白菊の一本折れて庵淋し
1877 只寒し封を開けば影法師
1878 一人住んで聞けば雁なき渡る
明治39年(1906年)
1879 寄りそへばねむりておはす春の雨
1880 本来はちるべき芥子にまがきせり
1881 短冊に元禄の句や京の春
1882 春風や惟然が耳に馬の鈴 (『草枕』より十七句~)
1883 馬子唄や白髪も染めで暮るゝ春
1884 花の頃を越えてかしこし馬に嫁
1885 海棠の露をふるふや物狂ひ
1886 花の影、女の影の朧かな
1887 正一位、女に化けて朧月
1888 春の星を落して夜半のかざしかな
1889 春の夜の雲に濡らすや洗ひ髪
1890 春や今宵歌つかまつる御姿
1891 海棠の精が出てくる月夜かな
1892 うた折々月下の春ををちこちす
1893 思ひ切つて更け行く春の独りかな
1894 海棠の露をふるふや朝烏
1895 花の影女の影を重ねけり
1896 御曹司女に化けて朧月
1897 木蓮の花許りなる空を瞻る
1898 春風にそら解け襦子の銘は何(~『草枕』より十七句)
1899 釣鐘のうなる許りに野分かな
1900 祖師堂に昼の灯影や秋の雨
1901 かき殻を屋根にわびしや秋の雨
1902 青楼や欄のひまより春の海
1903 渡殿の白木めでたし秋の雨
1904 春雨や爪革濡るゝ湯屋迄
1905 暮れなんとしてほのかに蓼の花を踏む
1906 乱菊や土塀の窓の古簀垂
1907 冬籠り染井の墓地を控へけり
1908 鰒汁と知らで薦めし寐覚かな
1909 春を待つ下宿の人や書一巻
(参考その一)「絶筆三句 子規」周辺
http://www.sakanouenokumo.com/siki_zeppitu.htm
≪ 子規の辞世の句となった糸瓜の三句。その場に居合わせた河東碧梧桐は、当時の様子を次のように回顧している(出典「子規言行録(明治版)」)。
十八日の頃であったか、どうも様子が悪いという知らせに、胸を躍らせながら早速駆けつけた所、丁度枕辺には陸氏令閨と妹君が居られた。予は病人の左側近くへよって「どうかな」というと別に返辞もなく、左手を四五度動かした許りで静かにいつものまま仰向に寝て居る。余り騒々しくしてはわるいであろうと、予は口をつぐんで、そこに坐りながら妹君と、医者のこと薬のこと、今朝は痰が切れないでこまったこと、宮本へ痰の切れる薬をとりにやったこと、高浜を呼びにやったかどうかということなど話をして居た時に「高浜も呼びにおやりや」と病人が一言いうた。依って予は直ぐに陸氏の電話口へ往って、高浜に大急ぎで来いというて帰って見ると、妹君は病人の右側で墨を磨って居られる。軈《やがて》例の書板に唐紙の貼付けてあるのを妹君が取って病人に渡されるから、何かこの場合に書けるであろうと不審ながらも、予はいつも病人の使いなれた軸も穂も細長い筆に十分墨を含ませて右手へ渡すと、病人は左手で板の左下側を持ち添え、上は妹君に持たせて、いきなり中央へ
糸瓜咲て
とすらすらと書きつけた。併し「咲て」の二字はかすれて少し書きにくそうであったので、ここで墨をついでまた筆を渡すと、こんど糸瓜咲てより少し下げて
痰のつまりし
までまた一息に書けた。字がかすれたのでまた墨をつぎながら、次は何と出るかと、暗に好奇心に駆られて板面を注視して居ると、同じ位の高さに
佛かな
と書かれたので、予は覚えず胸を刺されるように感じた。書き終わって投げるように筆を捨てながら、横を向いて咳を二三度つづけざまにして痰が切れんので如何にも苦しそうに見えた。妹君は板を横へ片付けながら側に坐って居られたが、病人は何とも言わないで無言である。また咳が出る。今度は切れたらしく反故でその痰を拭きとりながら妹君に渡す。痰はこれまでどんなに苦痛の劇しい時でも必ず設けてある痰壺を自分で取って吐き込む例であったのに、きょうはもうその痰壺をとる勇気も無いと見える。その間四五分たったと思うと、無言に前の書板を取り寄せる。予も無言で墨をつける。今度は左手を書板に持ち添える元気もなかったのか、妹君に持たせたまま前句「佛かな」と書いたその横へ
痰一斗糸瓜の水も
と「水も」を別行に認めた。ここで墨ををつぐ。すぐ次へ
間に合わず
と書いて、矢張り投捨てるように筆を置いた。咳は二三度出る。如何にもせつなそうなので、予は以前にも増して動気が打って胸がわくわくして堪らぬ。また四五分も経てから、無言で板を持たせたので、予も無言で筆を渡す。今度は板の持ち方が少し具合が悪そうであったがそのまま少し筋違いに
をとひのへちまの
と「へちまの」は行をかえて書く。予は墨をここでつぎながら、「と」の字の上の方が「ふ」のように、その下の方が「ら」の字を略したもののように見えるので「をふらひのへちまの」とは何の事であろうと聊か怪しみながら見て居ると、次を書く前に自分で「ひ」の上へ「と」と書いて、それが「ひ」の上へはいるもののようなしるしをした。それで始めて「をとヽひの」であると合点した。そのあとはすぐに「へちまの」の下へ
水の
と書いて
取らざりき
はその右側へ書き流して、例の通り筆を投げすてたが、丁度穂が先に落ちたので、白い寝床の上は少し許り墨の痕をつけた。余は筆を片付ける。妹君は板を障子にもたせかけられる。しばらくは病人自身もその字を見て居る様子であったが、予はこの場合その句に向かって何と言うべき考えも浮かばなかった。がもうこれでお仕舞いであるか、紙には書く場所はないようであるけれども、また書かれはすまいかと少し心待ちにして硯の側を去ることが出来なかったが、その後再び筆を持とうともしなかった。 ≫
(参考その二) 「子規居士弄丹青図(浅井忠)」周辺

「子規居士弄丹青図」(「ホトトギス」正岡子規追悼号(明治35年12月)挿絵用画稿 浅井忠)
http://nobless.seesaa.net/article/483626589.html
≪浅井は子規没後、ホトトギスの子規追悼集に「子規居士弄丹青図」を描いて子規を哀悼している。サラサラと鉛筆で描いたような戯画風の絵で、縁側のほうにころがる3個の柿と鉢植えの花を写生しているのだろうか、無精ひげの子規が床に横になったまま絵を描いている。生前の子規の特徴をよくとらえた愛情あふれる絵だ。≫
夏目漱石の「俳句と書画」(その十) [「子規と漱石」の世界]
その十 漱石の「五高・英国留学・帰朝(子規没前後)」時代(「明治三十三・四・五・六年」周辺)

「浅井黙語(忠)のパリ留学を祝う送別会(浅井忠画) 「ホトトギス」明治33年(1900)1月号掲載」
https://www.culture.city.taito.lg.jp/bunkatanbou/topics/famous_persons/shiki/japanese/page_04.html
≪ 明治33年(1900)1月16日、万国博覧会視察と留学のためパリへ行く画家浅井忠の送別会が子規庵で開かれました。集まったのは、子規、浅井をはじめ、内藤鳴雪(ないとうめいせつ 俳人)陸羯南(くがかつなん)、下村為山(しもむらいざん 画家、俳人)、中村不折、五百木瓢亭(いおきひょうてい 日本新聞記者、俳人)、松瀬青々(まつせせいせい 俳人)、高浜虚子です。画家三人による合作の絵に皆で賛(さん 画の余白に句等を添える)を書き、洋食を食べ、さまざまに楽しんでいます。その様子を子規は短歌にしています。≫
(上記の「画家浅井忠の送別会」の人物群像)
(前列の「画筆中の「浅井忠」と、左=「下村為山(黒羽織)?」と右「中村不折?」)
≪※浅井 忠(あさい ちゅう) 1856年7月22日(安政3年6月21日) - 1907年(明治40年)12月16日)は、明治期の洋画家、教育者。号は黙語(もくご)。(中略)1895年、京都で開催された第4回内国勧業博覧会に出品して妙技二等賞受賞[2]。1898年に東京美術学校(現在の東京芸術大学)の教授となる。その後、1900年からフランスへ西洋画のために留学した。(中略)正岡子規にも西洋画を教えており、夏目漱石の小説『三四郎』の中に登場する深見画伯のモデルとも言われる。『吾輩ハ猫デアル』の単行本の挿画を他の2人とともに描いている。(「ウイキペディア」)
※下村為山(しもむらいざん)生年/慶応1年5月21日(1865年)・ 没年/昭和24(1949)年7月10日・出生地/伊予国松山(愛媛県)/本名下村 純孝/別名別号=百歩,牛伴。経歴/上京して洋画を小山正太郎に学び、不同舎塾の後輩に中村不折がいる。のち日本画を久保田米遷に学び、俳画に一家をなした。明治22年内国勧業博覧会で受賞。俳句は正岡子規に師事し、洋画写生の優越姓を不折に先立って子規に説いたと伝えられる。27年松山に日本派俳句会の松風会を興し、日本派の俳人として活躍、句風は子規に「精微」と評された。30年松山版「ホトトギス」創刊時に初号の題字を書いたといわれる。その後も東京発行の「ホトトギス」や「新俳句」に表紙・挿画などを寄せ、同派に貢献した。句は「俳句二葉集」「春夏秋冬」などに見られる。(「20世紀日本人名事典」)
※中村不折(なかむらふせつ)[生]慶応2(1866).7.10. 江戸[没]1943.6.6. 東京洋画家,書家。本名はさく太郎,号は環山。初め南画を学び,1887年小山正太郎,浅井忠に洋画を学んだ。 94年日本新聞社に入社し新聞挿絵を担当。 1901年渡仏,アカデミー・ジュリアンに学び J.P.ローランスに師事して官学派の画風を習得。 05年帰朝後は太平洋画会会員となる。文展審査員,19年帝国美術院会員,34年太平洋美術学校校長,39年帝国芸術院会員を歴任。重厚な画風の歴史画にすぐれ,また日本画も巧みで北画風の水墨画を得意とした。書の造詣も深く六朝風を学び,能書家としても著名。また東京根岸の自宅の邸内に書道博物館を創設して,書に関する文献,参考品1万点余を展示。主要作品『建国そう業 (そうぎょう) 』 (1907,焼失) ,『賺蘭亭図 (らんていをあざむくのず) 』 (20,東京国立近代美術館) 。
(後列の「病臥中の子規」の右側の「黒羽織」の三人)
※陸羯南(くがかつなん)/ 没年:明治40.9.2(1907)/生年:安政4.10.14(1857.11.30)/明治時代の新聞記者。陸奥国(青森県)弘前に津軽藩士中田謙斎の長男として生まれる。幼少時から漢学を学び,藩校の後身東奥義塾に入学,漢学,英学等を学ぶ。明治6(1873)年東奥義塾を中退し,仙台の宮城師範学校に入学したが,校長と衝突し退学となり,9年上京。同年7月,司法省法学校に入学した。同期生には,原敬,福本日南,国分青崖らがいた。12年寮の食事への不満が原因で起きた賄征伐事件で,原敬らと共に退学処分を受け,故郷青森に帰り『青森新聞』編集長となった。またこの年,親戚の陸家再興の名目で陸姓を名乗る。13年,讒謗律に触れ罰金刑を受ける。青森新聞社を退職し,種々の仕事を転々としたのち,16年に太政官御用掛となり,官僚の世界に入った。この間,フランスの政治,行政の調査に当たり,その書物を翻訳出版するなど後年の政論の基礎を培った。 18年内閣官報局が新設されるや,編集課長に就任したが,21年,在野の言論活動を志し退職,同年4月3日,谷干城,杉浦重剛らの支援を受けて新聞『東京電報』を創刊し,さらに発展させて翌22年2月11日新聞『日本』を発刊,新聞の党派性,営利性を否定し,自らの信ずる「道理」のみによって自立する「独立新聞」という峻厳な新聞理念を提示し新聞ジャーナリズムに大きな影響を与えた。同時に国民主義を標榜し,三宅雪嶺,志賀重昂らの政教社の発行する雑誌『日本人』と提携しながら,明治20年代,30年代を通じて,欧化主義を批判するナショナリズムを領導する言論活動を展開した。しかし明治末期には,新聞界の営業主義化の大勢のなかで新聞経営は苦境に陥り,39年『日本』を手放さざるをえなくなった。翌年病没。明治期の「独立新聞記者」の典型であった。<著作>『陸羯南全集』全10巻/(有山輝雄) (「朝日日本歴史人物事典:(株)朝日新聞出版朝日日本歴史人物事典について」)→(「子規」の右側の人物?)
※内藤鳴雪(ないとうめいせつ)/俳人。江戸に生まれる。本名素行。松山藩校明教館・昌平黌で漢学を学ぶ。明治に入り文部省に勤務。藩の常盤会寄宿舎の舎監となり正岡子規を知り句作、日本派の長老と仰がれた。句集に「鳴雪句集」「鳴雪俳句鈔」など。弘化四~大正一五年(一八四七‐一九二六)(「デジタル版 日本人名大辞典+Plus」)→(「不折?」の右後方の人物?)
※五百木瓢亭(いおきひょうてい) 1871-1937 明治-昭和時代前期のジャーナリスト,俳人。明治3年12月14日生まれ。22年上京し,同郷の正岡子規らと句作にはげむ。28年日本新聞社にはいり,34年「日本」編集長。昭和3年政教社にうつり,「日本及日本人」を主宰。大アジア主義をとなえた。昭和12年6月14日死去。68歳。伊予(いよ)(愛媛県)出身。俳号は飄亭(ひょうてい)。著作に「飄亭句日記」など。(「デジタル版 日本人名大辞典+Plus」)→(「鳴雪?」の後方の人物?)
(「羯南?」と「瓢亭?」の間の二人)
※松瀬 青々(まつせ せいせい) 明治2年(1869年)4月4日 - 昭和12年(1937年)1月9日)は、日本の俳人。「倦鳥」を創刊・主宰。関西俳壇で高濱虛子主宰の「ホトトギス」と一線を劃す俳人として重きをなした。本名・弥三郎[1]。大阪市出身。(「ウイキペディア」)
※阪本(坂本)四方太(さかもとしほうだ) 1873年〈明治6年〉2月4日 - 1917年〈大正6年〉5月16日)は、俳人。本名、よもた。鳥取県出身。正岡子規門下生。俳誌『ホトトギス』にて活躍。代表作は『夢の如し』。墓所は豊島区駒込の染井霊園。(「ウイキペディア」)
→(「ホトトギス」の記事中に「四方太」の名あり。)
(「子規」の左側の人物→虚子?)
※高浜虚子(たかはまきょし) 没年:昭和34.4.8(1959)/生年:明治7.2.22(1874)
明治から昭和の俳人,小説家。本名清。虚子号は本名をもじって正岡子規によりつけられた。伊予国(愛媛県)松山藩の元藩士池内家の4男として松山市に生まれ,祖母方の姓を継ぎ高浜姓となる。伊予中学時代に同級生の河東碧梧桐を介して郷里の先輩で帝国大学文科大学の学生であった子規と文通して文学を志し,やがて碧梧桐と共に仙台の二高を中退,子規による日本派俳句を推進する両輪となった。明治31(1898)年松山から発行されていた『ホトトギス』を引き継いで東京から編集発行し,俳句とともに写生文や小説を掲載,明治38年からは夏目漱石の『吾輩は猫である』『坊つちやん』などの掲載で誌名を高め,自らも『俳諧師』『風流懺法』などを発表。俳句は碧梧桐にまかせ小説に転じようとしたが,碧梧桐の客観写生俳句が新傾向へと進んで定型や季題を無視する形勢となった大正2(1913)年俳句に復活,以後多数の傑出した俳人を育てて,子規の抱いていた俳句の未来への疑問を吹き払い,庶民の詩,花鳥諷詠の詩として俳句を普及し繁栄させた。その指導方針は主観尊重の写生から客観写生へと変わったが,俳句は有季定型の伝統詩であるという守旧派の立場を貫いた。その人柄は洋行中も和服で通したこと,ファシズムも戦争も自然現象のごとく「何事も野分一過の心」で過ごしたこと,『ホトトギス』を家系相続とし家元化したことなどに顕著である。『進むべき俳句の道』『五百句』『句日記』『虚子俳話』『定本虚子全集』など著書多数。文化勲章受章。(矢島渚男) (「朝日日本歴史人物事典」)
(追記) 夏目漱石俳句集(その七)<制作年順> 明治33年(1900年)~明治36年(1903年)
明治33年(1900年)
1780 新しき願もありて今朝の春
1781 菜の花の隣もありて竹の垣
1782 鶯も柳も青き住居かな
1783 新しき畳に寐たり宵の春
1784 春の雨鍋と釜とを運びけり
1785 折釘に掛けし春著や五つ紋
1786 ひとり咲いて朝日に匂ふ葵哉
1787 京に行かば寺に宿かれ時鳥
1788 ふき通す涼しき風や腹の中
1789 秋風の一人をふくや海の上
1790 阿呆鳥熱き国にぞ参りける
1791 稲妻の砕けて青し海の上
1792 雲の峰風なき海を渡りけり
1793 赤き日の海に落込む暑かな
1794 日は落ちて海の底より暑かな
1795 空狭き都に住むや神無月
1796 柊を幸多かれと飾りけり
1797 屠蘇なくて酔はざる春や覚束な
1798 貧乏な進士ありけり時鳥
明治34年(1901年)
1799 絵所を栗焼く人に尋ねけり
1800 白金に黄金に柩寒からず
1801 凩の下にゐろとも吹かぬなり
1802 凩や吹き静まつて喪の車
1803 熊の皮の頭巾ゆゝしき警護かな
1804 吾妹子を夢みる春の夜となりぬ
1805 満堂の閻浮檀金や宵の春
1806 見付たる菫の花や夕明り
1807 病んで一日枕にきかん時鳥
1808 礎に砂吹きあつる野分かな
1809 角巾を吹き落し行く野分かな
1810 近けば庄屋殿なり霧のあさ
1811 後天後土菊匂はざる処なし
1812 栗を焼く伊太利人や道の傍
1813 栗はねて失せけるを灰に求め得ず
1814 渋柿やにくき庄屋の門構
1815 ほきとをる下駄の歯形や霜柱
1816 月にうつる擬宝珠の色やとくる霜
1817 茶の花や智識と見えて眉深し
1818 茶の花や読みさしてある楞伽経
明治35年(1902年)
1819 山賊の顔のみ明かき榾火かな
1820 花売に寒し真珠の耳飾
1821 なつかしの紙衣もあらず行李の底
1822 三階に独り寐に行く寒かな
1823 句あるべくも花なき国に客となり
1824 筒袖や秋の柩にしたがはず
1825 手向くべき線香もなくて暮の秋
1826 霧黄なる市に動くや影法師
1827 きりぎりすの昔を忍び帰るべし
1828 招かざる薄に帰り来る人ぞ
明治36年(1903年)
1829 落ちし雷を盥に伏せて鮓の石
1830 引窓をからりと空の明け易き
1831 ぬきんでゝ雑木の中や棕櫚の花
1832 愚かければ独りすゞしくおはします
1833 無人島の天子とならば涼しかろ
1834 短夜や夜討をかくるひまもなく
1835 更衣同心衆の十手かな
1836 ひとりきくや夏鶯の乱鳴
1837 蝙蝠や一筋町の旅芸者
1838 蝙蝠に近し小鍛冶が槌の音
1839 市の灯に美なる苺を見付たり
1840 玻璃盤に露のしたゝる苺かな
1841 能もなき教師とならんあら涼し
1842 蚊帳青く涼しき顔にふきつける
1843 更衣沂に浴すべき願あり
1844 薔薇ちるや天似孫の詩見厭たり
1845 楽寝昼寝われは物草太郎なり
1846 雪の峰雷を封じて聳えけり
1847 船此日運河に入るや雲の峰
1848 一大事も糸瓜も糞もあらばこそ
1849 座と襟を正して見たり更衣
1850 衣更て見たが家から出て見たが
(参考その一)「画家浅井忠の送別会」周辺
https://plaza.rakuten.co.jp/akiradoinaka/diary/202008010000/
≪ 忠は、明治33年2月16日に新橋から神戸に向かい、28日に神戸港から「神奈川丸」に乗り込んでパリを目指しました。4月15日にマルセイユについた忠は、マルセイユ観光ののち列車に乗って17日の夕方にパリに着きました。開催されていたパリ万国博覧会をしばしば訪れ、5月からはマラコフ58番地で池辺義象、福地復一らと共同生活を始めています。パリの生活にようやく慣れた5月20日に、忠は子規に宛てて手紙を送りました。その内容は、『巴里消息』として7月10日号の「ホトトギス」に掲載されています。博覧会の絵を見て不満が募ったこと、日本風の装飾(アールヌーボー風)がヨーロッパを席巻していることなどが伝わってきます。
拝啓、近頃御病気如何、好時節に向い御快方のことと奉存候。小生不相替健全、はばかりながら御安慮被下度候。博覧会この頃ようやくおおかた整頓仕候。美術館の絵画、仏国十年以来の名作を陳列して大に世界に驕らんとす、諸外国また競争日本の国画及び油画その間にはさまれ実に顔色なし。その前に立留るもうら恥しく候。もとより美術館に入りて恥かき候ことは予め期したることなれど、かくはかり萎れかえりたる有様を目の前に見るは情けなき次第に有之候。油画の画風、概していえば、前世紀のものは曇天に向い当世紀の画風は晴天に向いたる傾きありて、すべて明るく晴したる有様に有之候。画風の千差万別なる、あまり奇を好みて文人画的なるあり、また美術院的なるもありて、何が何やら画いた人も知らざるならんと思わるる物さえ有之候。彩色の研究は確に当世紀に大進歩をなしたる様相見え候。しかしてその弊のある所もまた相見え候。山水画の進歩は年々著しき様も相見え候。平易なる画題をとらえて洒落なる無邪気なる山水画も増加せし様見え候。英独諸国も大抵仏国風に化せられたる様相見え侯。仔細に熟視すれば、おのおの異りたる所は有之候得共、以前の如く特有を顕わし居らざる様に有之候。
独の着実なると英の色の濃きはよく見れば確に分別有之候。伊太利は退歩、露と米は中々強敵に有之候。甚だ不思議なるは油画の変化極りなきことにて、日本油画の皆同一流儀の如く見えて色の枯痩したるは先ずおくも、日本画の四條と狩野の絶対に反対なる画風もこの場内に入りては皆一流の如く無味淡泊にして白紙に少少形を止めたる様見え候もおかしく候。総じてたっぷりしたる墨画が一番目を引き、細かき彩色画の如きは少しも目に止らず、日本画には彩色なしというても宜敷候。日本の美術は、工芸家の通弊として、大体の組織に甚だ不注意にして、細かき筆遣い細かき仕事を自慢して、女の頭の髪の毛の線がきとか、象牙彫りの魚の鱗とかいうものに骨折りて四昼半の座敷で賞翫せんとするものを、五間や六間離れて見ては何が書きあるや更にわからず。少くとも十間以上離れざれば品物が分明ならざる様な大胆の仕事の数千もある中に入り込みせられたるその筈と申すべし。陶器、織物、室内装飾に至りてはただあっけに取られ申候。八九分は皆日本意匠を取りて日本品よりは遥に上手に仕事され、茶人の涎を流しそうなるもの、骨董屋の堀り出し相なるものより、埃及(エジプト)、支那、日本を加味して自由自在に応用変化したるもの、着眼の点可恐ことに候。ヲーストリー、ホンガリー、ノルウヱー、デンマークなどの東洋的室内装飾の渋くして凝りたるには宜に一驚を喫し候。仏国自慢の工芸列品は未だ整頓不致、アシバリード右方は諸外国の列品にして、左方は仏国の諸列館なり。整頓の上はまた肝玉をつぶすことと存居候。クシャクシャ的、金ピカ的のものは独逸、露西亜の列品の一部に在るのみにて、余は皆ノロリとしたる東洋的曲線の形式に法りて、模様に至りては純然たる日本画か亜細亜的装飾のみ競争して応用したる様見えたり。色彩は多くじみに傾き、鈍き鼠色か、鈍き緑か、鈍き紫か、シットリと
沈んだる色多し。噪々しく目を射るような派手なる時代は過ぎ去りたりと見え申候。織物の模様に至りては、中村不折をして泣かしむるやうなもの多く、ビカピカと絹の光りたるようなものでなく、木綿物ににぶ色を以て不器用に埃及的模様を施したる、いうに言われぬ味ありて、旅で買いたきものばかりたくさんにしてただ涎を流しおり候。五六尺の小さき織物でも百五十法以上のもの多く、手も出しかねおり候。
これに反し日本の出品には実に嘔吐を催し候。諸外国のスッカリ整頓したる真中に挟まれ、未だ荷ときもせず明箱ばかりにて、少しつら出しおるものは相も不替横浜仕入れの義経弁慶などの赤画をただ無暗矢鱈に透間なくかき散したるもの多く、蒔画に至りては勧工場的安物の仕入物の如く、形と模様とすべよくもよくも不揃にかつ厭味にかくも出来たものと思わるるもののみ少々面出しおり候。小生悪口をたたき候所、普き物は未だ箱内に仕舞ありと弁解致居候が、日本品はかなり手後れになりて閉場まで陳列に間に合わざる方仕合せかと存候。しかしその内どんなものが出るや不分候。見ぬ内の攻撃はこれ位に致置可申候。織物は先ず日本の出品の中にて比較的一番宜敷様見受候。しかし色の配合などいうことは知らぬと見え、折角の模様を地合でぶっこわしたるものや工手間を掛けてますますマズクしたるもの多し。今少し学問的に講究して、彩色の取り合せとか、線の一致とかいう位のことは知らぬ内は到底だめに有之候。日本の位置が余り欧洲と遠かり過ぎて世界の広きを不知、西洋人に世辞を言われて鼻を高くしておる間は何事もダメと存候。西洋人の日本意匠を取るは明治時代の小刀細工的のものなどは毫末も省みず、少なくも元緑以前の心持の大なる大マカなる処に着眼せるなり。故にある人はまたこれを弁解して古物崇拝となり、ただ先人の跡を学ばしめんとするに至る。この辺宜敷具合ものと存候。何に致せ日本の美術家工芸家が大本を睨めずしてただ枝葉ばかりに走り、田舎に引込みて井中の蛙たる中はイツもこんなものと存候。これまでとても外国博覧会に賛同して本国に報告することは手前味噌の偽りの報告のみにて出品者を誤らしめたる罪軽からずと存候。この度は岡目の人も大分見え候間幾分兵相を知ることも出来可くと存候。しかし熱心なる芸術家は少く、ツマリ運動者が運動の結果ごますりて保護金に有り附きたる人多き故、有益なる報告を費し帰る人は幾何ならんか、誠に思うままにならぬは世の常ながら、真実芸術に身を入れおる人はイツモ人後に立つは悲むべき至りに候。如何に従来の博覧会屋と唱えて再三再四宜務に当りたる人が無学なる職人を誤りたるかを宜見致候。兼てよりこれらのこと知らざるに非るも眼前に見ることの腹立たしさ御推察可被下候。その他面白からぬこと見聞、不平はますます嵩み申候。国に帰りてこんな悪口をきいたら、外国に行て年月も立たぬうち外国贔屓になりて本国をくさす不届物とて人は相手にせざるならん。本国の人に世辞を遣うて賞られたければ矢張り従来の老人連の太鼓事務官の亜流たらざるべからず。目あり耳あるもの見聞して黙してはおられず候。ついに報告やら不平やらごったになりて無益の寝言に流れ汗顔の至に御坐候。
この表紙はノルウエーの敷物に余程面白き鬼や不思議の動物のかたありて面白く感じ候間ふと浮び申候。可成鈍き色に上るよう印刷屋へ御命し被下度候。黄色は黄土色が宜敷かと存候。
陸翁へもこの寝言御咄し被下度、この次は全部整頓の上まじめの報告御送り可申上候。過日来サンクルー、ベルサイユ、サンゼルマンなどの二三里離れたる田舎へ遊び、巴里の盛界を脱して何ともいわれざる愉快を覚え候。巴里附近の田舎の景、実に美しくセーブル、ムードレなどセーヌ河の河蒸気に乗りて二錢を投ずれば三四十分にて逹し申候。この頃当地一年中の好時節、青葉茂りて百花開き、三河島、王子あたりの景色よりは田園の様清潔にして実に心地よく、その内このあたりに居を移して気楽に暮し度思いおり候。乍末御社中諸君へ宜敷御伝声奉願上候。 巴里にて。
五月廿日
子規 詞兄
表紙の下絵を御目に掛けんとて書き出し候所、ついに不平を洩して面白くも無きこと長々書き連ね候段御許し被下度候。(浅井忠 子規宛書簡)≫
(参考その二)「夏目漱石と浅井忠との交流」周辺
https://plaza.rakuten.co.jp/akiradoinaka/diary/202204250000/
≪ 漱石と忠の交流は、漱石のロンドン留学から始まりました。漱石は途中のパリで万博に夢中になり、この万国博に22日、25日、27日の3度、訪れています。明治33年10月22日の『漱石日記』には「十時頃より公使館に至り、安達氏を訪う。あらず。その寓居を尋ねしが、また遇わず。浅井忠氏を尋ねしも、また不在にて不得已帰宿。午後二時より渡邊氏の案内にて博覧会を観る。規模宏大にて二日や三日にて容易に観尽せるものにあらず。方角さえ分らぬ位なり。『エヘル』塔の上りて帰路。渡邊氏方にて晩餐を喫す。それよりGrand Voulevardに至りて繁華の様を目撃す。その状態は夏夜の銀座の景色を五十倍位立派にしたるものなり」、10月26日には「朝浅井忠氏を訪う。それより芳賀藤代二氏と同じく散歩す。雨を衝て還る。樋口氏来る」と書かれており、中を訪ねていたことがわかります。
明35(1902)年7月2日付の妻鏡子宛の手紙に、「只今巴理より浅井忠と申す人帰朝の序拙寓へ止宿是は画の先生にて色々画の話杯承り居候」と記し、この時から漱石と忠は一気に親しくなったと思われます。明治41年2月15日、神田美土代町で行われた第一回朝日講演会の記録『創作家の態度』には「その時、浅井先生はどの街へ出ても、どの建物を見ても、あれは好い色だ、これは好い色だと、とうとう家へ帰るまで色尽くしで御仕舞いなりましたーー先生は色で世界が出来上がってると考えてるんだなと大に悟りました」とあり、浅井とロンドン市内を歩いた漱石は、画家のものの見方を直に触れることができました。また、談話の『文士と酒、煙草』で「いつかロンドンにいる時分、浅井さんといっしょに、とある料理屋で、たったビール一杯飲んだのですが、たいへんまっかになって、顔がほてって町中を歩くことができず、ずいぶん困りました。日本では、酒を飲んでまっかになると、景気がつくとか、上きげんだとか言いますが、西洋ではまったく鼻つまみです
からね」と語っています。
浅井は佐倉藩士の長男として江戸に生まれ、1876年に工部美術学校に入学しフォンタネージの指導を受けます。そして明治美術会の結成に参加し、東京美術学校教授となって1900年からフランスヘ留学していました。1902年に掃国した忠は京都に移り、後進の指導にあたります。
忠は、漱石の依頼で処女作『吾輩は猫である』の中篇と下篇の挿画を頼みました。明治38年2月12日の橋口五葉への自筆絵はがきに「浅井の口絵画の百姓の足はうまいと思う。如何」と送っています。また、明治39年11月11日、橋口五葉宛に「浅井の画はどうですか。不折は無暗に法螺を吹くから近来絵をたのむのがいやになりました」とあり、上篇のみ中村不折が挿画を担当した理由がほの見えてきます。
また、漱石は『それから』にも、忠を登場させています。「直木は代助の顔を見てとうとう笑い出した。代助も笑って、座敷へ来た。そこには誰も居なかった。替え立ての畳の上に、丸い紫檀の刳抜盆が一つ出ていて、中に置いた湯呑には、京都の浅井黙語の模様画が染め付けてあった。からんとした広い座敷へ朝の緑が庭から射し込んで、すべてが静かに見えた。戸外の風は急に落ちたように思われた。(11)」とあります。浅井忠は「黙語」という画名を持っていたのです。
「三四郎」では三四郎と美彌子が深見という画家の遺作展を見る場面がありますが、これは第6回太平洋画会で行われた忠の遺作展を念頭に描いています。
「じゃ、こうなさい。この奥の別室にね。深見さんの遺画があるから、それだけ見て、帰りに精養軒へいらっしゃい。先へ行って待っていますから」
「ありがとう」
「深見さんの水彩は普通の水彩のつもりで見ちゃいけませんよ。どこまでも深見さんの水彩なんだから。実物を見る気にならないで、深見さんの気韻を見る気になっていると、なかなかおもしろいところが出てきます」と注意して、原口は野々宮と出て行った。美禰子は礼を言ってその後影を見送った。二人は振り返らなかった。
女は歩をめぐらして、別室へはいった。男は一足あとから続いた。光線の乏しい暗い部屋である。細長い壁に一列にかかっている深見先生の遺画を見ると、なるほど原口さんの注意したごとくほとんど水彩ばかりである。三四郎が著しく感じたのは、その水彩の色が、どれもこれも薄くて、数が少なくって、対照に乏しくって、日向へでも出さないと引き立たないと思うほど地味にかいてあるということである。その代り筆がちっとも滞っていない。ほとんど一気呵成に仕上げた趣がある。絵の具の下に鉛筆の輪郭が明らかに透いて見えるのでも、洒落な画風がわかる。人間などになると、細くて長くて、まるで殻竿のようである。(三四郎 8) ≫
(参考その三)「世紀転換期のヨーロッパ滞在 : 浅井忠と夏目金之助(伊藤徹稿)」(「関西大学学術リポジトリ」)
(参考その四)「浅井忠の明治」周辺
http://nobless.seesaa.net/article/483626589.html
≪ 明治3年に土佐藩が送り出した英国留学生5人の中に、のちの民権家馬場辰猪のほか明治洋画界の草分けとなる国沢新九郎(明治10年死去)がいた。国沢は法律の勉強を命じられていたが、画家に転向して明治7年に帰国、東京麹町平河町に洋画塾「彰技堂」を開いて人気を博すようになる。このあたらしい画塾に、佐倉藩出身の20歳の聡明な若者が入塾する。のちの洋画家浅井忠(ちゅう)(1856~1907)である。
夏目漱石の『三四郎』に、美禰子と三四郎が絵画の展覧会「丹青会」に行く有名なくだりがある。画家の原口が三四郎に「深見さんの水彩は普通の水彩の積りで見ちゃ不可ませんよ。何処までも深見さんの水彩なんだから。実物を見る気にならないで、深見さんの気韻を見る気になっていると、中々面白い所が出て来ます」と言い残して野々宮と出て行き、次のように続く。
<細長い壁に一列に懸っている深見先生の遺画を見ると、なるほど原口さんの注意した如く殆んど水彩ばかりである。三四郎が著るしく感じたのは、その水彩の色が、どれもこれも薄くて、数が少くって、対照に乏しくって、日向(ひなた)へでも出さないと引き立たないと思う程地味に描いてあるという事である。その代り筆が些(ちっ)とも滞っていない。殆んど一気呵(か)成(せい)に仕上げた趣がある。絵の具の下に鉛筆の輪郭(りんかく)が明かに透いて見えるのでも、洒落(しゃらく)な画風がわかる。>
丹青会とは、明治41年に上野で開催された太平洋画会第6回展のことで、ここで深見先生こと浅井忠の回顧展が開催されていた。浅井はこの展覧会の前年、明治40年に京都で51歳で亡くなっている。
夏目漱石はひと回り年配の洋画家浅井忠を畏敬してやまなかった。上の『三四郎』の文章からも、浅井の絵の質の高さを世に知らしめる意図が窺えるし、『それから』にも「湯呑には、京都の浅井黙語の模様画が染め付けてあった」と浅井を登場させているほどだ(「黙語」は浅井の号)。
漱石は明治33年10月に英国留学の途上パリに立ち寄り、ひと足先に同地に44歳という遅い留学をしていた浅井を訪ねている。浅井は明治29年に東京・上根岸に居を構えたことで近くに住むジャーナリストの陸羯南(くがかつ(なん)や正岡子規と交流を深め、子規庵にも出入りするようになっていた。漱石はその子規の紹介で、パリの浅井を訪ねたのである。このときの出会いがふたりの初対面らしく、よほど気が合ったのか2年後の明治35年には日本への帰国途上の浅井がロンドンの漱石を訪ね、下宿に4日間も滞在しているのである。
漱石は浅井没後、明治41年の講演で次のように回想している。
「私が先年倫敦に居った時、此間亡くなった浅井先生と市中を歩いたのであります。其時浅井先生はどこの町へ出てもどの建物を見てもあれは好い色だ、これは好い色だと、とうとう家へ帰る迄色尽しで御仕舞いになりました。流石画伯だけあって、違ったものだ、先生は色で世界が出来上がってると考えてるんだと大いに悟りました」
わかいころ建築家志望だった漱石は、留学時代から美術工芸誌「The Studio」を定期購読するほどの美術好きで、かれの芸術観の基層には当時欧州を席巻していたアーツ・アンド・クラフツ運動やアール・ヌーヴォーの影響、そして洋画家浅井忠の存在がどっしりと盤踞(ばんきょ)していたはずである。
また子規が「写生」に目覚めるのも浅井忠との出会いによる。浅井はわかい弟子の中村不折(ふせつ)(画家・書家)を子規に紹介し、その不折をして浅井が師フォンタネージから学んだ絵画技法である写生の本質を子規に伝授せしめ、子規はそれを俳句や短歌にも応用するようになる。漱石の『吾輩は猫である』初版本の上巻挿画を不折、中・下巻を浅井が描いていることからも漱石・子規と画家の浅井・不折の親密さが見てとれるだろう。
さて浅井の洋行が決まってのち、明治33年1月16日に陸、子規のほか画家や俳人など10人ほどが集まり子規庵で送別会が開かれた。長身で端正な風貌の浅井をいつも「先生」と呼び尊敬してやまなかった子規であったが、病の悪化で死を覚悟していたかれはそのとき「先生のお留守さむしや上根岸」の句を詠み、もう会えぬかもしれぬ浅井を哀惜したのである。しかしさいわいにも浅井は帰国後、開校予定の京都高等工芸学校(現京都工芸繊維大学)の教授として京都へ移住する前に子規を見舞うことができたのだ。このわずか3週間後に子規は亡くなる。
浅井は子規没後、ホトトギスの子規追悼集に「子規居士弄丹青図」を描いて子規を哀悼している。サラサラと鉛筆で描いたような戯画風の絵で、縁側のほうにころがる3個の柿と鉢植えの花を写生しているのだろうか、無精ひげの子規が床に横になったまま絵を描いている。生前の子規の特徴をよくとらえた愛情あふれる絵だ。
このように明治の文化人たちにおおきな影響を与えた“日本近代洋画の父”浅井忠はしかし没後、薩摩出身で11歳年少の黒田清輝(せいき)の陰に隠れてしまい、作品のレベルのみならずその先駆的業績すら過小評価されてきた感がある。浅井の生きた明治という時代は、社会のあらゆる分野が薩長土肥、なかんずく薩長二藩の下級武士たちによる「薩長に非ずんば人に非ず」と云われるほどに強力な藩閥政治の只中にあり、絵画芸術もむろんその埒外にはなかったのだ。
浅井忠は、江戸東方の要衝であった下総の佐倉藩(現千葉県佐倉市)出身である。同藩は幕末、英邁な藩主堀田正陸(まさよし)(のち幕府老中首座)が江戸の蘭方医佐藤泰然を招き、大坂の適塾と並び称される高名な蘭学塾「順天堂」(現順天堂大学の前身)を創設するなど学問分野におおくの俊才―思想家の西村茂樹、外交官の林董(ただす)、医者の松本良順、農学者の津田仙(せん)など―を輩出したことで知られるが、戊辰戦争で新政府軍の前にやむなく恭順、禄高三百石の藩士の長男であった浅井忠之丞(のちに忠と改名)は朝敵の子、負け組として冷や飯を食うことになるのだ。
一方、勝ち組である薩摩の子爵の養子として何不自由なく育った黒田清輝は、明治17年に弱冠18歳でフランスに留学する。もともとは政治家を目指し法律を学ぶ予定だったが、土佐の国沢新九郎同様に絵画に興味が移り転向する。この10年間にもわたる優雅な留学生活が、黒田におおきな僥倖をもたらすことになる。
黒田の洋行中、国内では岡倉天心とフェノロサによる洋画排斥運動が燃えさかり、洋画家たちは死に体も同然になっていたのだ。展覧会での洋画展示も禁止され、明治22年に開校された東京美術学校(学長は岡倉天心)にも西洋画科は設置されないという逆風下、洋画家のリーダー格であった浅井は日本初の美術団体「明治美術会」を創設して必死に踏ん張っていた。そんな矢先の明治26年7月、薩閥のプリンス黒田清輝が帰国する。
黒田の帰国は浅井ら洋画家に朗報と思われたが、黒田は帰国の3年後に明治美術会と袂を分かって新グループ「白馬会」を創設し、その翌月に天心は東京美術学校長を罷免され同校に西洋画科が設置されると同時に黒田が教授に就任、洋画界は政治に翻弄されつつ内部分裂してゆく。印象派風の明るい絵を描く白馬会の画家らは外光派・紫派と呼ばれてもてはやされ、浅井らは脂(やに)派・旧派と揶揄されるようになるのだ。日本の美術界はすでに黒田清輝を中心に回りはじめていたのである。
そんな流派同士の不毛な争いにほとほと嫌気がさしていた浅井に突然、文部省からパリ万博の監査官任命と2年間のフランス留学の命が下る。浅井は渡りに船とばかりに翌年の明治33年に渡欧、帰国後は東京美術学校教授を辞して京都に赴き、京都高等工芸学校開校と同時に教授として図案科で美術やデザインを教え、聖護院洋画研究所のちに関西美術院を創設して後進の指導を行うようになる。派閥争いにうつつをぬかす東京の美術界をよそに、浅井は京都で悠然と油絵、水彩画、陶芸のほか洒脱なデザイン画を描き、のちの日本画壇を代表する梅原龍三郎、安井曾太郎、津田青楓らを育ててゆくのである。
だが残念なことに、そんな生活も永くは続かなかった。
京都に移住してわずか5年後の明治40年暮れ、美術・工芸の革新を目指した天性の芸術家は、時代の波に翻弄されながら51年の生涯を古都の地で閉じるのである。死の間際まで関西美術院と京都高等工芸学校の学生らを気にかけ、「どうか美術院も学校も宜しく頼む」と言い遺したという。
実を云うと、わたしはその旧京都高等工芸学校、現在の京都工芸繊維大学の建築工芸学科卒である。同科は昔の図案科であるから、不肖ながらわたしは浅井忠の遥か遠い弟子ということになる。そう勝手に決めこんで、最近はヘタな素描や水彩画をはじめている。お手本は云うまでもなく、浅井黙語先生である。≫

「浅井黙語(忠)のパリ留学を祝う送別会(浅井忠画) 「ホトトギス」明治33年(1900)1月号掲載」
https://www.culture.city.taito.lg.jp/bunkatanbou/topics/famous_persons/shiki/japanese/page_04.html
≪ 明治33年(1900)1月16日、万国博覧会視察と留学のためパリへ行く画家浅井忠の送別会が子規庵で開かれました。集まったのは、子規、浅井をはじめ、内藤鳴雪(ないとうめいせつ 俳人)陸羯南(くがかつなん)、下村為山(しもむらいざん 画家、俳人)、中村不折、五百木瓢亭(いおきひょうてい 日本新聞記者、俳人)、松瀬青々(まつせせいせい 俳人)、高浜虚子です。画家三人による合作の絵に皆で賛(さん 画の余白に句等を添える)を書き、洋食を食べ、さまざまに楽しんでいます。その様子を子規は短歌にしています。≫
(上記の「画家浅井忠の送別会」の人物群像)
(前列の「画筆中の「浅井忠」と、左=「下村為山(黒羽織)?」と右「中村不折?」)
≪※浅井 忠(あさい ちゅう) 1856年7月22日(安政3年6月21日) - 1907年(明治40年)12月16日)は、明治期の洋画家、教育者。号は黙語(もくご)。(中略)1895年、京都で開催された第4回内国勧業博覧会に出品して妙技二等賞受賞[2]。1898年に東京美術学校(現在の東京芸術大学)の教授となる。その後、1900年からフランスへ西洋画のために留学した。(中略)正岡子規にも西洋画を教えており、夏目漱石の小説『三四郎』の中に登場する深見画伯のモデルとも言われる。『吾輩ハ猫デアル』の単行本の挿画を他の2人とともに描いている。(「ウイキペディア」)
※下村為山(しもむらいざん)生年/慶応1年5月21日(1865年)・ 没年/昭和24(1949)年7月10日・出生地/伊予国松山(愛媛県)/本名下村 純孝/別名別号=百歩,牛伴。経歴/上京して洋画を小山正太郎に学び、不同舎塾の後輩に中村不折がいる。のち日本画を久保田米遷に学び、俳画に一家をなした。明治22年内国勧業博覧会で受賞。俳句は正岡子規に師事し、洋画写生の優越姓を不折に先立って子規に説いたと伝えられる。27年松山に日本派俳句会の松風会を興し、日本派の俳人として活躍、句風は子規に「精微」と評された。30年松山版「ホトトギス」創刊時に初号の題字を書いたといわれる。その後も東京発行の「ホトトギス」や「新俳句」に表紙・挿画などを寄せ、同派に貢献した。句は「俳句二葉集」「春夏秋冬」などに見られる。(「20世紀日本人名事典」)
※中村不折(なかむらふせつ)[生]慶応2(1866).7.10. 江戸[没]1943.6.6. 東京洋画家,書家。本名はさく太郎,号は環山。初め南画を学び,1887年小山正太郎,浅井忠に洋画を学んだ。 94年日本新聞社に入社し新聞挿絵を担当。 1901年渡仏,アカデミー・ジュリアンに学び J.P.ローランスに師事して官学派の画風を習得。 05年帰朝後は太平洋画会会員となる。文展審査員,19年帝国美術院会員,34年太平洋美術学校校長,39年帝国芸術院会員を歴任。重厚な画風の歴史画にすぐれ,また日本画も巧みで北画風の水墨画を得意とした。書の造詣も深く六朝風を学び,能書家としても著名。また東京根岸の自宅の邸内に書道博物館を創設して,書に関する文献,参考品1万点余を展示。主要作品『建国そう業 (そうぎょう) 』 (1907,焼失) ,『賺蘭亭図 (らんていをあざむくのず) 』 (20,東京国立近代美術館) 。
(後列の「病臥中の子規」の右側の「黒羽織」の三人)
※陸羯南(くがかつなん)/ 没年:明治40.9.2(1907)/生年:安政4.10.14(1857.11.30)/明治時代の新聞記者。陸奥国(青森県)弘前に津軽藩士中田謙斎の長男として生まれる。幼少時から漢学を学び,藩校の後身東奥義塾に入学,漢学,英学等を学ぶ。明治6(1873)年東奥義塾を中退し,仙台の宮城師範学校に入学したが,校長と衝突し退学となり,9年上京。同年7月,司法省法学校に入学した。同期生には,原敬,福本日南,国分青崖らがいた。12年寮の食事への不満が原因で起きた賄征伐事件で,原敬らと共に退学処分を受け,故郷青森に帰り『青森新聞』編集長となった。またこの年,親戚の陸家再興の名目で陸姓を名乗る。13年,讒謗律に触れ罰金刑を受ける。青森新聞社を退職し,種々の仕事を転々としたのち,16年に太政官御用掛となり,官僚の世界に入った。この間,フランスの政治,行政の調査に当たり,その書物を翻訳出版するなど後年の政論の基礎を培った。 18年内閣官報局が新設されるや,編集課長に就任したが,21年,在野の言論活動を志し退職,同年4月3日,谷干城,杉浦重剛らの支援を受けて新聞『東京電報』を創刊し,さらに発展させて翌22年2月11日新聞『日本』を発刊,新聞の党派性,営利性を否定し,自らの信ずる「道理」のみによって自立する「独立新聞」という峻厳な新聞理念を提示し新聞ジャーナリズムに大きな影響を与えた。同時に国民主義を標榜し,三宅雪嶺,志賀重昂らの政教社の発行する雑誌『日本人』と提携しながら,明治20年代,30年代を通じて,欧化主義を批判するナショナリズムを領導する言論活動を展開した。しかし明治末期には,新聞界の営業主義化の大勢のなかで新聞経営は苦境に陥り,39年『日本』を手放さざるをえなくなった。翌年病没。明治期の「独立新聞記者」の典型であった。<著作>『陸羯南全集』全10巻/(有山輝雄) (「朝日日本歴史人物事典:(株)朝日新聞出版朝日日本歴史人物事典について」)→(「子規」の右側の人物?)
※内藤鳴雪(ないとうめいせつ)/俳人。江戸に生まれる。本名素行。松山藩校明教館・昌平黌で漢学を学ぶ。明治に入り文部省に勤務。藩の常盤会寄宿舎の舎監となり正岡子規を知り句作、日本派の長老と仰がれた。句集に「鳴雪句集」「鳴雪俳句鈔」など。弘化四~大正一五年(一八四七‐一九二六)(「デジタル版 日本人名大辞典+Plus」)→(「不折?」の右後方の人物?)
※五百木瓢亭(いおきひょうてい) 1871-1937 明治-昭和時代前期のジャーナリスト,俳人。明治3年12月14日生まれ。22年上京し,同郷の正岡子規らと句作にはげむ。28年日本新聞社にはいり,34年「日本」編集長。昭和3年政教社にうつり,「日本及日本人」を主宰。大アジア主義をとなえた。昭和12年6月14日死去。68歳。伊予(いよ)(愛媛県)出身。俳号は飄亭(ひょうてい)。著作に「飄亭句日記」など。(「デジタル版 日本人名大辞典+Plus」)→(「鳴雪?」の後方の人物?)
(「羯南?」と「瓢亭?」の間の二人)
※松瀬 青々(まつせ せいせい) 明治2年(1869年)4月4日 - 昭和12年(1937年)1月9日)は、日本の俳人。「倦鳥」を創刊・主宰。関西俳壇で高濱虛子主宰の「ホトトギス」と一線を劃す俳人として重きをなした。本名・弥三郎[1]。大阪市出身。(「ウイキペディア」)
※阪本(坂本)四方太(さかもとしほうだ) 1873年〈明治6年〉2月4日 - 1917年〈大正6年〉5月16日)は、俳人。本名、よもた。鳥取県出身。正岡子規門下生。俳誌『ホトトギス』にて活躍。代表作は『夢の如し』。墓所は豊島区駒込の染井霊園。(「ウイキペディア」)
→(「ホトトギス」の記事中に「四方太」の名あり。)
(「子規」の左側の人物→虚子?)
※高浜虚子(たかはまきょし) 没年:昭和34.4.8(1959)/生年:明治7.2.22(1874)
明治から昭和の俳人,小説家。本名清。虚子号は本名をもじって正岡子規によりつけられた。伊予国(愛媛県)松山藩の元藩士池内家の4男として松山市に生まれ,祖母方の姓を継ぎ高浜姓となる。伊予中学時代に同級生の河東碧梧桐を介して郷里の先輩で帝国大学文科大学の学生であった子規と文通して文学を志し,やがて碧梧桐と共に仙台の二高を中退,子規による日本派俳句を推進する両輪となった。明治31(1898)年松山から発行されていた『ホトトギス』を引き継いで東京から編集発行し,俳句とともに写生文や小説を掲載,明治38年からは夏目漱石の『吾輩は猫である』『坊つちやん』などの掲載で誌名を高め,自らも『俳諧師』『風流懺法』などを発表。俳句は碧梧桐にまかせ小説に転じようとしたが,碧梧桐の客観写生俳句が新傾向へと進んで定型や季題を無視する形勢となった大正2(1913)年俳句に復活,以後多数の傑出した俳人を育てて,子規の抱いていた俳句の未来への疑問を吹き払い,庶民の詩,花鳥諷詠の詩として俳句を普及し繁栄させた。その指導方針は主観尊重の写生から客観写生へと変わったが,俳句は有季定型の伝統詩であるという守旧派の立場を貫いた。その人柄は洋行中も和服で通したこと,ファシズムも戦争も自然現象のごとく「何事も野分一過の心」で過ごしたこと,『ホトトギス』を家系相続とし家元化したことなどに顕著である。『進むべき俳句の道』『五百句』『句日記』『虚子俳話』『定本虚子全集』など著書多数。文化勲章受章。(矢島渚男) (「朝日日本歴史人物事典」)
(追記) 夏目漱石俳句集(その七)<制作年順> 明治33年(1900年)~明治36年(1903年)
明治33年(1900年)
1780 新しき願もありて今朝の春
1781 菜の花の隣もありて竹の垣
1782 鶯も柳も青き住居かな
1783 新しき畳に寐たり宵の春
1784 春の雨鍋と釜とを運びけり
1785 折釘に掛けし春著や五つ紋
1786 ひとり咲いて朝日に匂ふ葵哉
1787 京に行かば寺に宿かれ時鳥
1788 ふき通す涼しき風や腹の中
1789 秋風の一人をふくや海の上
1790 阿呆鳥熱き国にぞ参りける
1791 稲妻の砕けて青し海の上
1792 雲の峰風なき海を渡りけり
1793 赤き日の海に落込む暑かな
1794 日は落ちて海の底より暑かな
1795 空狭き都に住むや神無月
1796 柊を幸多かれと飾りけり
1797 屠蘇なくて酔はざる春や覚束な
1798 貧乏な進士ありけり時鳥
明治34年(1901年)
1799 絵所を栗焼く人に尋ねけり
1800 白金に黄金に柩寒からず
1801 凩の下にゐろとも吹かぬなり
1802 凩や吹き静まつて喪の車
1803 熊の皮の頭巾ゆゝしき警護かな
1804 吾妹子を夢みる春の夜となりぬ
1805 満堂の閻浮檀金や宵の春
1806 見付たる菫の花や夕明り
1807 病んで一日枕にきかん時鳥
1808 礎に砂吹きあつる野分かな
1809 角巾を吹き落し行く野分かな
1810 近けば庄屋殿なり霧のあさ
1811 後天後土菊匂はざる処なし
1812 栗を焼く伊太利人や道の傍
1813 栗はねて失せけるを灰に求め得ず
1814 渋柿やにくき庄屋の門構
1815 ほきとをる下駄の歯形や霜柱
1816 月にうつる擬宝珠の色やとくる霜
1817 茶の花や智識と見えて眉深し
1818 茶の花や読みさしてある楞伽経
明治35年(1902年)
1819 山賊の顔のみ明かき榾火かな
1820 花売に寒し真珠の耳飾
1821 なつかしの紙衣もあらず行李の底
1822 三階に独り寐に行く寒かな
1823 句あるべくも花なき国に客となり
1824 筒袖や秋の柩にしたがはず
1825 手向くべき線香もなくて暮の秋
1826 霧黄なる市に動くや影法師
1827 きりぎりすの昔を忍び帰るべし
1828 招かざる薄に帰り来る人ぞ
明治36年(1903年)
1829 落ちし雷を盥に伏せて鮓の石
1830 引窓をからりと空の明け易き
1831 ぬきんでゝ雑木の中や棕櫚の花
1832 愚かければ独りすゞしくおはします
1833 無人島の天子とならば涼しかろ
1834 短夜や夜討をかくるひまもなく
1835 更衣同心衆の十手かな
1836 ひとりきくや夏鶯の乱鳴
1837 蝙蝠や一筋町の旅芸者
1838 蝙蝠に近し小鍛冶が槌の音
1839 市の灯に美なる苺を見付たり
1840 玻璃盤に露のしたゝる苺かな
1841 能もなき教師とならんあら涼し
1842 蚊帳青く涼しき顔にふきつける
1843 更衣沂に浴すべき願あり
1844 薔薇ちるや天似孫の詩見厭たり
1845 楽寝昼寝われは物草太郎なり
1846 雪の峰雷を封じて聳えけり
1847 船此日運河に入るや雲の峰
1848 一大事も糸瓜も糞もあらばこそ
1849 座と襟を正して見たり更衣
1850 衣更て見たが家から出て見たが
(参考その一)「画家浅井忠の送別会」周辺
https://plaza.rakuten.co.jp/akiradoinaka/diary/202008010000/
≪ 忠は、明治33年2月16日に新橋から神戸に向かい、28日に神戸港から「神奈川丸」に乗り込んでパリを目指しました。4月15日にマルセイユについた忠は、マルセイユ観光ののち列車に乗って17日の夕方にパリに着きました。開催されていたパリ万国博覧会をしばしば訪れ、5月からはマラコフ58番地で池辺義象、福地復一らと共同生活を始めています。パリの生活にようやく慣れた5月20日に、忠は子規に宛てて手紙を送りました。その内容は、『巴里消息』として7月10日号の「ホトトギス」に掲載されています。博覧会の絵を見て不満が募ったこと、日本風の装飾(アールヌーボー風)がヨーロッパを席巻していることなどが伝わってきます。
拝啓、近頃御病気如何、好時節に向い御快方のことと奉存候。小生不相替健全、はばかりながら御安慮被下度候。博覧会この頃ようやくおおかた整頓仕候。美術館の絵画、仏国十年以来の名作を陳列して大に世界に驕らんとす、諸外国また競争日本の国画及び油画その間にはさまれ実に顔色なし。その前に立留るもうら恥しく候。もとより美術館に入りて恥かき候ことは予め期したることなれど、かくはかり萎れかえりたる有様を目の前に見るは情けなき次第に有之候。油画の画風、概していえば、前世紀のものは曇天に向い当世紀の画風は晴天に向いたる傾きありて、すべて明るく晴したる有様に有之候。画風の千差万別なる、あまり奇を好みて文人画的なるあり、また美術院的なるもありて、何が何やら画いた人も知らざるならんと思わるる物さえ有之候。彩色の研究は確に当世紀に大進歩をなしたる様相見え候。しかしてその弊のある所もまた相見え候。山水画の進歩は年々著しき様も相見え候。平易なる画題をとらえて洒落なる無邪気なる山水画も増加せし様見え候。英独諸国も大抵仏国風に化せられたる様相見え侯。仔細に熟視すれば、おのおの異りたる所は有之候得共、以前の如く特有を顕わし居らざる様に有之候。
独の着実なると英の色の濃きはよく見れば確に分別有之候。伊太利は退歩、露と米は中々強敵に有之候。甚だ不思議なるは油画の変化極りなきことにて、日本油画の皆同一流儀の如く見えて色の枯痩したるは先ずおくも、日本画の四條と狩野の絶対に反対なる画風もこの場内に入りては皆一流の如く無味淡泊にして白紙に少少形を止めたる様見え候もおかしく候。総じてたっぷりしたる墨画が一番目を引き、細かき彩色画の如きは少しも目に止らず、日本画には彩色なしというても宜敷候。日本の美術は、工芸家の通弊として、大体の組織に甚だ不注意にして、細かき筆遣い細かき仕事を自慢して、女の頭の髪の毛の線がきとか、象牙彫りの魚の鱗とかいうものに骨折りて四昼半の座敷で賞翫せんとするものを、五間や六間離れて見ては何が書きあるや更にわからず。少くとも十間以上離れざれば品物が分明ならざる様な大胆の仕事の数千もある中に入り込みせられたるその筈と申すべし。陶器、織物、室内装飾に至りてはただあっけに取られ申候。八九分は皆日本意匠を取りて日本品よりは遥に上手に仕事され、茶人の涎を流しそうなるもの、骨董屋の堀り出し相なるものより、埃及(エジプト)、支那、日本を加味して自由自在に応用変化したるもの、着眼の点可恐ことに候。ヲーストリー、ホンガリー、ノルウヱー、デンマークなどの東洋的室内装飾の渋くして凝りたるには宜に一驚を喫し候。仏国自慢の工芸列品は未だ整頓不致、アシバリード右方は諸外国の列品にして、左方は仏国の諸列館なり。整頓の上はまた肝玉をつぶすことと存居候。クシャクシャ的、金ピカ的のものは独逸、露西亜の列品の一部に在るのみにて、余は皆ノロリとしたる東洋的曲線の形式に法りて、模様に至りては純然たる日本画か亜細亜的装飾のみ競争して応用したる様見えたり。色彩は多くじみに傾き、鈍き鼠色か、鈍き緑か、鈍き紫か、シットリと
沈んだる色多し。噪々しく目を射るような派手なる時代は過ぎ去りたりと見え申候。織物の模様に至りては、中村不折をして泣かしむるやうなもの多く、ビカピカと絹の光りたるようなものでなく、木綿物ににぶ色を以て不器用に埃及的模様を施したる、いうに言われぬ味ありて、旅で買いたきものばかりたくさんにしてただ涎を流しおり候。五六尺の小さき織物でも百五十法以上のもの多く、手も出しかねおり候。
これに反し日本の出品には実に嘔吐を催し候。諸外国のスッカリ整頓したる真中に挟まれ、未だ荷ときもせず明箱ばかりにて、少しつら出しおるものは相も不替横浜仕入れの義経弁慶などの赤画をただ無暗矢鱈に透間なくかき散したるもの多く、蒔画に至りては勧工場的安物の仕入物の如く、形と模様とすべよくもよくも不揃にかつ厭味にかくも出来たものと思わるるもののみ少々面出しおり候。小生悪口をたたき候所、普き物は未だ箱内に仕舞ありと弁解致居候が、日本品はかなり手後れになりて閉場まで陳列に間に合わざる方仕合せかと存候。しかしその内どんなものが出るや不分候。見ぬ内の攻撃はこれ位に致置可申候。織物は先ず日本の出品の中にて比較的一番宜敷様見受候。しかし色の配合などいうことは知らぬと見え、折角の模様を地合でぶっこわしたるものや工手間を掛けてますますマズクしたるもの多し。今少し学問的に講究して、彩色の取り合せとか、線の一致とかいう位のことは知らぬ内は到底だめに有之候。日本の位置が余り欧洲と遠かり過ぎて世界の広きを不知、西洋人に世辞を言われて鼻を高くしておる間は何事もダメと存候。西洋人の日本意匠を取るは明治時代の小刀細工的のものなどは毫末も省みず、少なくも元緑以前の心持の大なる大マカなる処に着眼せるなり。故にある人はまたこれを弁解して古物崇拝となり、ただ先人の跡を学ばしめんとするに至る。この辺宜敷具合ものと存候。何に致せ日本の美術家工芸家が大本を睨めずしてただ枝葉ばかりに走り、田舎に引込みて井中の蛙たる中はイツもこんなものと存候。これまでとても外国博覧会に賛同して本国に報告することは手前味噌の偽りの報告のみにて出品者を誤らしめたる罪軽からずと存候。この度は岡目の人も大分見え候間幾分兵相を知ることも出来可くと存候。しかし熱心なる芸術家は少く、ツマリ運動者が運動の結果ごますりて保護金に有り附きたる人多き故、有益なる報告を費し帰る人は幾何ならんか、誠に思うままにならぬは世の常ながら、真実芸術に身を入れおる人はイツモ人後に立つは悲むべき至りに候。如何に従来の博覧会屋と唱えて再三再四宜務に当りたる人が無学なる職人を誤りたるかを宜見致候。兼てよりこれらのこと知らざるに非るも眼前に見ることの腹立たしさ御推察可被下候。その他面白からぬこと見聞、不平はますます嵩み申候。国に帰りてこんな悪口をきいたら、外国に行て年月も立たぬうち外国贔屓になりて本国をくさす不届物とて人は相手にせざるならん。本国の人に世辞を遣うて賞られたければ矢張り従来の老人連の太鼓事務官の亜流たらざるべからず。目あり耳あるもの見聞して黙してはおられず候。ついに報告やら不平やらごったになりて無益の寝言に流れ汗顔の至に御坐候。
この表紙はノルウエーの敷物に余程面白き鬼や不思議の動物のかたありて面白く感じ候間ふと浮び申候。可成鈍き色に上るよう印刷屋へ御命し被下度候。黄色は黄土色が宜敷かと存候。
陸翁へもこの寝言御咄し被下度、この次は全部整頓の上まじめの報告御送り可申上候。過日来サンクルー、ベルサイユ、サンゼルマンなどの二三里離れたる田舎へ遊び、巴里の盛界を脱して何ともいわれざる愉快を覚え候。巴里附近の田舎の景、実に美しくセーブル、ムードレなどセーヌ河の河蒸気に乗りて二錢を投ずれば三四十分にて逹し申候。この頃当地一年中の好時節、青葉茂りて百花開き、三河島、王子あたりの景色よりは田園の様清潔にして実に心地よく、その内このあたりに居を移して気楽に暮し度思いおり候。乍末御社中諸君へ宜敷御伝声奉願上候。 巴里にて。
五月廿日
子規 詞兄
表紙の下絵を御目に掛けんとて書き出し候所、ついに不平を洩して面白くも無きこと長々書き連ね候段御許し被下度候。(浅井忠 子規宛書簡)≫
(参考その二)「夏目漱石と浅井忠との交流」周辺
https://plaza.rakuten.co.jp/akiradoinaka/diary/202204250000/
≪ 漱石と忠の交流は、漱石のロンドン留学から始まりました。漱石は途中のパリで万博に夢中になり、この万国博に22日、25日、27日の3度、訪れています。明治33年10月22日の『漱石日記』には「十時頃より公使館に至り、安達氏を訪う。あらず。その寓居を尋ねしが、また遇わず。浅井忠氏を尋ねしも、また不在にて不得已帰宿。午後二時より渡邊氏の案内にて博覧会を観る。規模宏大にて二日や三日にて容易に観尽せるものにあらず。方角さえ分らぬ位なり。『エヘル』塔の上りて帰路。渡邊氏方にて晩餐を喫す。それよりGrand Voulevardに至りて繁華の様を目撃す。その状態は夏夜の銀座の景色を五十倍位立派にしたるものなり」、10月26日には「朝浅井忠氏を訪う。それより芳賀藤代二氏と同じく散歩す。雨を衝て還る。樋口氏来る」と書かれており、中を訪ねていたことがわかります。
明35(1902)年7月2日付の妻鏡子宛の手紙に、「只今巴理より浅井忠と申す人帰朝の序拙寓へ止宿是は画の先生にて色々画の話杯承り居候」と記し、この時から漱石と忠は一気に親しくなったと思われます。明治41年2月15日、神田美土代町で行われた第一回朝日講演会の記録『創作家の態度』には「その時、浅井先生はどの街へ出ても、どの建物を見ても、あれは好い色だ、これは好い色だと、とうとう家へ帰るまで色尽くしで御仕舞いなりましたーー先生は色で世界が出来上がってると考えてるんだなと大に悟りました」とあり、浅井とロンドン市内を歩いた漱石は、画家のものの見方を直に触れることができました。また、談話の『文士と酒、煙草』で「いつかロンドンにいる時分、浅井さんといっしょに、とある料理屋で、たったビール一杯飲んだのですが、たいへんまっかになって、顔がほてって町中を歩くことができず、ずいぶん困りました。日本では、酒を飲んでまっかになると、景気がつくとか、上きげんだとか言いますが、西洋ではまったく鼻つまみです
からね」と語っています。
浅井は佐倉藩士の長男として江戸に生まれ、1876年に工部美術学校に入学しフォンタネージの指導を受けます。そして明治美術会の結成に参加し、東京美術学校教授となって1900年からフランスヘ留学していました。1902年に掃国した忠は京都に移り、後進の指導にあたります。
忠は、漱石の依頼で処女作『吾輩は猫である』の中篇と下篇の挿画を頼みました。明治38年2月12日の橋口五葉への自筆絵はがきに「浅井の口絵画の百姓の足はうまいと思う。如何」と送っています。また、明治39年11月11日、橋口五葉宛に「浅井の画はどうですか。不折は無暗に法螺を吹くから近来絵をたのむのがいやになりました」とあり、上篇のみ中村不折が挿画を担当した理由がほの見えてきます。
また、漱石は『それから』にも、忠を登場させています。「直木は代助の顔を見てとうとう笑い出した。代助も笑って、座敷へ来た。そこには誰も居なかった。替え立ての畳の上に、丸い紫檀の刳抜盆が一つ出ていて、中に置いた湯呑には、京都の浅井黙語の模様画が染め付けてあった。からんとした広い座敷へ朝の緑が庭から射し込んで、すべてが静かに見えた。戸外の風は急に落ちたように思われた。(11)」とあります。浅井忠は「黙語」という画名を持っていたのです。
「三四郎」では三四郎と美彌子が深見という画家の遺作展を見る場面がありますが、これは第6回太平洋画会で行われた忠の遺作展を念頭に描いています。
「じゃ、こうなさい。この奥の別室にね。深見さんの遺画があるから、それだけ見て、帰りに精養軒へいらっしゃい。先へ行って待っていますから」
「ありがとう」
「深見さんの水彩は普通の水彩のつもりで見ちゃいけませんよ。どこまでも深見さんの水彩なんだから。実物を見る気にならないで、深見さんの気韻を見る気になっていると、なかなかおもしろいところが出てきます」と注意して、原口は野々宮と出て行った。美禰子は礼を言ってその後影を見送った。二人は振り返らなかった。
女は歩をめぐらして、別室へはいった。男は一足あとから続いた。光線の乏しい暗い部屋である。細長い壁に一列にかかっている深見先生の遺画を見ると、なるほど原口さんの注意したごとくほとんど水彩ばかりである。三四郎が著しく感じたのは、その水彩の色が、どれもこれも薄くて、数が少なくって、対照に乏しくって、日向へでも出さないと引き立たないと思うほど地味にかいてあるということである。その代り筆がちっとも滞っていない。ほとんど一気呵成に仕上げた趣がある。絵の具の下に鉛筆の輪郭が明らかに透いて見えるのでも、洒落な画風がわかる。人間などになると、細くて長くて、まるで殻竿のようである。(三四郎 8) ≫
(参考その三)「世紀転換期のヨーロッパ滞在 : 浅井忠と夏目金之助(伊藤徹稿)」(「関西大学学術リポジトリ」)
(参考その四)「浅井忠の明治」周辺
http://nobless.seesaa.net/article/483626589.html
≪ 明治3年に土佐藩が送り出した英国留学生5人の中に、のちの民権家馬場辰猪のほか明治洋画界の草分けとなる国沢新九郎(明治10年死去)がいた。国沢は法律の勉強を命じられていたが、画家に転向して明治7年に帰国、東京麹町平河町に洋画塾「彰技堂」を開いて人気を博すようになる。このあたらしい画塾に、佐倉藩出身の20歳の聡明な若者が入塾する。のちの洋画家浅井忠(ちゅう)(1856~1907)である。
夏目漱石の『三四郎』に、美禰子と三四郎が絵画の展覧会「丹青会」に行く有名なくだりがある。画家の原口が三四郎に「深見さんの水彩は普通の水彩の積りで見ちゃ不可ませんよ。何処までも深見さんの水彩なんだから。実物を見る気にならないで、深見さんの気韻を見る気になっていると、中々面白い所が出て来ます」と言い残して野々宮と出て行き、次のように続く。
<細長い壁に一列に懸っている深見先生の遺画を見ると、なるほど原口さんの注意した如く殆んど水彩ばかりである。三四郎が著るしく感じたのは、その水彩の色が、どれもこれも薄くて、数が少くって、対照に乏しくって、日向(ひなた)へでも出さないと引き立たないと思う程地味に描いてあるという事である。その代り筆が些(ちっ)とも滞っていない。殆んど一気呵(か)成(せい)に仕上げた趣がある。絵の具の下に鉛筆の輪郭(りんかく)が明かに透いて見えるのでも、洒落(しゃらく)な画風がわかる。>
丹青会とは、明治41年に上野で開催された太平洋画会第6回展のことで、ここで深見先生こと浅井忠の回顧展が開催されていた。浅井はこの展覧会の前年、明治40年に京都で51歳で亡くなっている。
夏目漱石はひと回り年配の洋画家浅井忠を畏敬してやまなかった。上の『三四郎』の文章からも、浅井の絵の質の高さを世に知らしめる意図が窺えるし、『それから』にも「湯呑には、京都の浅井黙語の模様画が染め付けてあった」と浅井を登場させているほどだ(「黙語」は浅井の号)。
漱石は明治33年10月に英国留学の途上パリに立ち寄り、ひと足先に同地に44歳という遅い留学をしていた浅井を訪ねている。浅井は明治29年に東京・上根岸に居を構えたことで近くに住むジャーナリストの陸羯南(くがかつ(なん)や正岡子規と交流を深め、子規庵にも出入りするようになっていた。漱石はその子規の紹介で、パリの浅井を訪ねたのである。このときの出会いがふたりの初対面らしく、よほど気が合ったのか2年後の明治35年には日本への帰国途上の浅井がロンドンの漱石を訪ね、下宿に4日間も滞在しているのである。
漱石は浅井没後、明治41年の講演で次のように回想している。
「私が先年倫敦に居った時、此間亡くなった浅井先生と市中を歩いたのであります。其時浅井先生はどこの町へ出てもどの建物を見てもあれは好い色だ、これは好い色だと、とうとう家へ帰る迄色尽しで御仕舞いになりました。流石画伯だけあって、違ったものだ、先生は色で世界が出来上がってると考えてるんだと大いに悟りました」
わかいころ建築家志望だった漱石は、留学時代から美術工芸誌「The Studio」を定期購読するほどの美術好きで、かれの芸術観の基層には当時欧州を席巻していたアーツ・アンド・クラフツ運動やアール・ヌーヴォーの影響、そして洋画家浅井忠の存在がどっしりと盤踞(ばんきょ)していたはずである。
また子規が「写生」に目覚めるのも浅井忠との出会いによる。浅井はわかい弟子の中村不折(ふせつ)(画家・書家)を子規に紹介し、その不折をして浅井が師フォンタネージから学んだ絵画技法である写生の本質を子規に伝授せしめ、子規はそれを俳句や短歌にも応用するようになる。漱石の『吾輩は猫である』初版本の上巻挿画を不折、中・下巻を浅井が描いていることからも漱石・子規と画家の浅井・不折の親密さが見てとれるだろう。
さて浅井の洋行が決まってのち、明治33年1月16日に陸、子規のほか画家や俳人など10人ほどが集まり子規庵で送別会が開かれた。長身で端正な風貌の浅井をいつも「先生」と呼び尊敬してやまなかった子規であったが、病の悪化で死を覚悟していたかれはそのとき「先生のお留守さむしや上根岸」の句を詠み、もう会えぬかもしれぬ浅井を哀惜したのである。しかしさいわいにも浅井は帰国後、開校予定の京都高等工芸学校(現京都工芸繊維大学)の教授として京都へ移住する前に子規を見舞うことができたのだ。このわずか3週間後に子規は亡くなる。
浅井は子規没後、ホトトギスの子規追悼集に「子規居士弄丹青図」を描いて子規を哀悼している。サラサラと鉛筆で描いたような戯画風の絵で、縁側のほうにころがる3個の柿と鉢植えの花を写生しているのだろうか、無精ひげの子規が床に横になったまま絵を描いている。生前の子規の特徴をよくとらえた愛情あふれる絵だ。
このように明治の文化人たちにおおきな影響を与えた“日本近代洋画の父”浅井忠はしかし没後、薩摩出身で11歳年少の黒田清輝(せいき)の陰に隠れてしまい、作品のレベルのみならずその先駆的業績すら過小評価されてきた感がある。浅井の生きた明治という時代は、社会のあらゆる分野が薩長土肥、なかんずく薩長二藩の下級武士たちによる「薩長に非ずんば人に非ず」と云われるほどに強力な藩閥政治の只中にあり、絵画芸術もむろんその埒外にはなかったのだ。
浅井忠は、江戸東方の要衝であった下総の佐倉藩(現千葉県佐倉市)出身である。同藩は幕末、英邁な藩主堀田正陸(まさよし)(のち幕府老中首座)が江戸の蘭方医佐藤泰然を招き、大坂の適塾と並び称される高名な蘭学塾「順天堂」(現順天堂大学の前身)を創設するなど学問分野におおくの俊才―思想家の西村茂樹、外交官の林董(ただす)、医者の松本良順、農学者の津田仙(せん)など―を輩出したことで知られるが、戊辰戦争で新政府軍の前にやむなく恭順、禄高三百石の藩士の長男であった浅井忠之丞(のちに忠と改名)は朝敵の子、負け組として冷や飯を食うことになるのだ。
一方、勝ち組である薩摩の子爵の養子として何不自由なく育った黒田清輝は、明治17年に弱冠18歳でフランスに留学する。もともとは政治家を目指し法律を学ぶ予定だったが、土佐の国沢新九郎同様に絵画に興味が移り転向する。この10年間にもわたる優雅な留学生活が、黒田におおきな僥倖をもたらすことになる。
黒田の洋行中、国内では岡倉天心とフェノロサによる洋画排斥運動が燃えさかり、洋画家たちは死に体も同然になっていたのだ。展覧会での洋画展示も禁止され、明治22年に開校された東京美術学校(学長は岡倉天心)にも西洋画科は設置されないという逆風下、洋画家のリーダー格であった浅井は日本初の美術団体「明治美術会」を創設して必死に踏ん張っていた。そんな矢先の明治26年7月、薩閥のプリンス黒田清輝が帰国する。
黒田の帰国は浅井ら洋画家に朗報と思われたが、黒田は帰国の3年後に明治美術会と袂を分かって新グループ「白馬会」を創設し、その翌月に天心は東京美術学校長を罷免され同校に西洋画科が設置されると同時に黒田が教授に就任、洋画界は政治に翻弄されつつ内部分裂してゆく。印象派風の明るい絵を描く白馬会の画家らは外光派・紫派と呼ばれてもてはやされ、浅井らは脂(やに)派・旧派と揶揄されるようになるのだ。日本の美術界はすでに黒田清輝を中心に回りはじめていたのである。
そんな流派同士の不毛な争いにほとほと嫌気がさしていた浅井に突然、文部省からパリ万博の監査官任命と2年間のフランス留学の命が下る。浅井は渡りに船とばかりに翌年の明治33年に渡欧、帰国後は東京美術学校教授を辞して京都に赴き、京都高等工芸学校開校と同時に教授として図案科で美術やデザインを教え、聖護院洋画研究所のちに関西美術院を創設して後進の指導を行うようになる。派閥争いにうつつをぬかす東京の美術界をよそに、浅井は京都で悠然と油絵、水彩画、陶芸のほか洒脱なデザイン画を描き、のちの日本画壇を代表する梅原龍三郎、安井曾太郎、津田青楓らを育ててゆくのである。
だが残念なことに、そんな生活も永くは続かなかった。
京都に移住してわずか5年後の明治40年暮れ、美術・工芸の革新を目指した天性の芸術家は、時代の波に翻弄されながら51年の生涯を古都の地で閉じるのである。死の間際まで関西美術院と京都高等工芸学校の学生らを気にかけ、「どうか美術院も学校も宜しく頼む」と言い遺したという。
実を云うと、わたしはその旧京都高等工芸学校、現在の京都工芸繊維大学の建築工芸学科卒である。同科は昔の図案科であるから、不肖ながらわたしは浅井忠の遥か遠い弟子ということになる。そう勝手に決めこんで、最近はヘタな素描や水彩画をはじめている。お手本は云うまでもなく、浅井黙語先生である。≫
夏目漱石の「俳句と書画」(その九) [「子規と漱石」の世界]
その九 漱石の「第五高等学校」」時代(その四・明治三十二年周辺)

「蕪村忌(明治32年(1899)12月)」 (子規庵蔵)
https://www.culture.city.taito.lg.jp/bunkatanbou/topics/famous_persons/shiki/japanese/page_04.html
≪西側黒板塀前で撮影。子規は、中央で脇息(きょうそく、肘掛け)にもたれています。≫
http://chikata.net/?p=2883
(再掲)
明治32年(1899年)
1月、子規へ句稿を送る(75句)
1月、子規『俳諧大要』を発表。
2月、子規へ句稿を送る(105句)
5月、長女(筆子)誕生。
9月、子規へ句稿を送る(51句)
同月、阿蘇登山。
10月、子規へ句稿を送る(29句)
(追記) 夏目漱石俳句集(その六)<制作年順> 明治32年(1430~1540)
https://sosekihaikushu.seesaa.net/article/200912article_1.html
明治32年(1899年)
1430 我に許せ元日なれば朝寝坊(「虚子・碧悟桐」宛書簡)
1431 金泥の鶴や朱塗の屠蘇の盃 (子規へ送りたる句稿三十二・七十五句・一月)
1432 宇佐に行くや佳き日を選む初暦
1433 梅の神に如何なる恋や祈るらん
1434 うつくしき蜑の頭や春の鯛
1435 蕭条たる古駅に入るや春の夕
1436 兀として鳥居立ちけり冬木立
1437 神苑に鶴放ちけり梅の花
1438 ぬかづいて曰く正月二日なり
1439 松の苔鶴痩せながら神の春
1440 南無弓矢八幡殿に御慶かな
1441 神かけて祈る恋なし宇佐の春
1442 呉橋や若菜を洗ふ寄藻川
1443 灰色の空低れかゝる枯野哉
1444 無提灯で枯野を通る寒哉
1445 石標や残る一株の枯芒
1446 枯芒北に向つて靡きけり
1447 遠く見る枯野の中の烟かな
1448 暗がりに雑巾を踏む寒哉
1449 冬ざれや狢をつるす軒の下
1450 凩や岩に取りつく羅漢路
1451 巌窟の羅漢共こそ寒からめ
1452 釣鐘に雲氷るべく山高し
1453 凩の鐘楼危ふし巌の角
1454 梯して上る大盤石の氷かな
1455 巌頭に本堂くらき寒かな
1456 絶壁に木枯あたるひゞきかな
1457 雛僧の只風呂吹と答へけり
1458 かしこしや未来を霜の笹結び
1459 二世かけて結ぶちぎりや雪の笹
1460 短かくて毛布つぎ足す蒲団かな
1461 泊り合す旅商人の寒がるよ
1462 寐まらんとすれど衾の薄くして
1463 頭巾着たる猟師に逢ひぬ谷深み
1464 はたと逢ふ夜興引ならん岩の角
1465 谷深み杉を流すや冬の川
1466 冬木流す人は猿の如くなり
1467 帽頭や思ひがけなき岩の雪
1468 石の山凩に吹かれ裸なり
1469 凩のまがりくねつて響きけり
1470 凩の吹くべき松も生えざりき
1471 年々や凩吹て尖る山
1472 凩の峰は剣の如くなり
1473 恐ろしき岩の色なり玉霰
1474 只寒し天狭くして水青く
1475 目ともいはず口ともいはず吹雪哉
1476 ばりばりと氷踏みけり谷の道
1477 道端や氷りつきたる高箒
1478 たまさかに据風呂焚くや冬の雨
1479 せぐゝまる蒲団の中や夜もすがら
1480 薄蒲団なえし毛脛を擦りけり
1481 僧に似たるが宿り合せぬ雪今宵
1482 雪ちらちら峠にかかる合羽かな
1483 払へども払へどもわが袖の雪
1484 かたかりき鞋喰ひ込む足袋の股
1485 隧道の口に大なる氷柱かな
1486 吹きまくる雪の下なり日田の町
1487 炭を積む馬の脊に降る雪まだら
1488 漸くに又起きあがる吹雪かな
1489 詩僧死して只凩の里なりき
1490 蓆帆の早瀬を上る霰かな
1491 奔湍に霰ふり込む根笹かな
1492 つるぎ洗ふ武夫もなし玉霰
1493 新道は一直線の寒さかな
1494 棒鼻より三里と答ふ吹雪哉
1495 なつかしむ衾に聞くや馬の鈴
1496 親方と呼びかけられし毛布哉
1497 餅搗や明星光る杵の先
1498 行く年の左したる思慮もなかりけり
1499 染め直す古服もなし年の暮
1500 やかましき姑健なり年の暮
1501 ニッケルの時計とまりぬ寒き夜半
1502 元日の富士に逢ひけり馬の上
1503 蓬莱に初日さし込む書院哉
1504 光琳の屏風に咲くや福寿草
1505 眸に入る富士大いなり春の楼 (1431~「同上」)
1506 馬に蹴られ吹雪の中に倒れけり(「手帳」より 三十一句)
1507 雪の客僧に似たりや五七日
1508 沈まざる南瓜浮名を流しけり
1509 石打てばかららんと鳴る氷哉
1510 楽しんで蓋をあくれば干鱈哉
1511 乾鮭や薄く切れとの仰せなり
1512 妾と郎離別を語る柳哉
1513 春風に祖師西来の意あるべし
1514 禅僧に旛動きけり春の風
1515 郎を待つ待合茶屋の柳かな
1516 鞭つて牛動かざる日永かな
1517 わが歌の胡弓にのらぬ朧かな
1518 煩悩の朧に似たる夜もありき
1519 吾折々死なんと思ふ朧かな
1520 春此頃化石せんとの願あり
1521 招かれて隣に更けし歌留多哉
1522 追羽子や君稚児髷の黒眼勝
1523 耄碌と名のつく老の頭巾かな
1524 筋違に葱を切るなり都振
1525 玉葱の煮えざるを焦つ火鉢哉
1526 湯豆腐に霰飛び込む床几哉
1527 立ん坊の地団太を踏む寒かな
1528 べんべらを一枚着たる寒さかな
1529 ある時は鉢叩かうと思ひけり
1530 寄り添へば冷たき瀬戸の火鉢かな
1531 雪を煮て煮立つ音の涼しさよ
1532 挙して曰く可なく不可なし蕪汁
1533 善か悪か風呂吹を喰つて我点せよ
1534 何の故に恐縮したる生海鼠哉
1535 老たん(※耳偏に冉)のうとき耳ほる火燵かな
1536 仏画く殿司の窓や梅の花 (1506~「同上」)
1537 夫子貧に梅花書屋の粥薄し(子規へ送りたる句稿三十三・一〇五句・二月)
1538 手を入るゝ水餅白し納屋の梅
1539 馬の尻に尾して下るや岨の梅
1540 ある程の梅に名なきはなかり鳧
1541 奈良漬に梅に其香をなつかしむ
1542 相伝の金創膏や梅の花
1543 たのもしき梅の足利文庫かな
1544 抱一は発句も読んで梅の花
≪季=梅の花(春)。※抱一は江戸後期の画家、酒井抱一。諸芸に優れ、俳諧は江戸座に学んだ。自選発句集『屠龍之技』がある。≫
1545 明た口に団子賜る梅見かな
1546 いざ梅見合点と端折る衣の裾
1547 夜汽車より白きを梅と推しけり
1548 死して名なき人のみ住んで梅の花
1549 法橋を給はる梅の主人かな
1550 玉蘭と大雅と語る梅の花
1551 村長の上座につくや床の梅
1552 梅の小路練香ひさぐ翁かな
1553 寄合や少し後れて梅の掾
1554 裏門や酢蔵に近き梅赤し
1555 一つ紋の羽織はいやし梅の花
1556 白梅や易を講ずる蘇東坡服
1557 蒟蒻に梅を踏み込む男かな
1558 梅の花千家の会に参りけり
1559 碧玉の茶碗に梅の落花かな
1560 粗略ならぬ服紗さばきや梅の主
1561 日当りや刀を拭ふ梅の主
1562 祐筆の大師流なり梅の花
1563 日をうけぬ梅の景色や楞伽窟
1564 とく起て味噌する梅の隣かな
1565 梅の花貧乏神の祟りけり
1566 駒犬の怒つて居るや梅の花
1567 筮竹に梅ちりかゝる社頭哉
1568 一斎の小鼻動くよ梅花飯
1569 封切れば月が瀬の梅二三片
1570 ものいはず童子遠くの梅を指す
1571 寒徹骨梅を娶ると夢みけり
1572 驢に乗るは東坡にやあらん雪の梅
1573 梅の詩を得たりと叩く月の門
1574 黄昏の梅に立ちけり絵師の妻
1575 髣髴と日暮れて入りぬ梅の村
1576 梅散るや源太の箙はなやかに
1577 月に望む麓の村の梅白し
1578 瑠璃色の空を控へて岡の梅
1579 落梅花水車の門を流れけり
1580 梅の下に槙割る翁の面黄也
1581 妓を拉す二重廻しや梅屋敷
1582 暁の梅に下りて嗽ぐ
1583 梅の花琴を抱いてあちこちす
1584 さらさらと衣を鳴らして梅見哉
1585 佩環の鏘然として梅白し
1586 戛と鳴て鶴飛び去りぬ闇の梅
1587 眠らざる僧の嚏や夜半の梅
1588 尺八のはたとやみけり梅の門
1589 宣徳の香炉にちるや瓶の梅
1590 古銅瓶に疎らな梅を活けてけり
1591 鉄筆や水晶刻む窓の梅
1592 墨の香や奈良の都の古梅園
1593 梅の宿残月硯を蔵しけり
1594 畠打の梅を繞ぐつて動きけり
1595 縁日の梅窮屈に咲きにけり
1596 梅の香や茶畠つゞき爪上り
1597 灯もつけず雨戸も引かず梅の花
1598 梅林や角巾黄なる売茶翁
1599 上り汽車の箱根を出て梅白し
1600 佶倔な梅を画くや謝春星
1601 雪隠の壁に上るや梅の影
1602 道服と吾妻コートの梅見哉
1603 女倶して舟を上るや梅屋敷
1604 梅の寺麓の人語聞こゆなり
1605 梅の奥に誰やら住んで幽かな灯
1606 円遊の鼻ばかりなり梅屋敷
1607 梅の中に且たのもしや梭の音
1608 清げなる宮司の面や梅の花
1609 月升つて枕に落ちぬ梅の影
1610 相逢ふて語らで過ぎぬ梅の下
1611 昵懇な和尚訪ひよる梅の坊
1612 月の梅貴とき狐裘着たりけり
1613 京音の紅梅ありやと尋ねけり
1614 紅梅に艶なる女主人かな
1615 紅梅や物の化の住む古館
1616 梅紅ひめかけの歌に咏まれけり
1617 いち早く紅梅咲きぬ下屋敷
1618 紅梅や姉妹の振る采の筒
1619 長と張つて半と出でけり梅の宿
1620 俗俳や床屋の卓に奇なる梅
1621 徂来其角並んで住めり梅の花
1622 盆梅の一尺にして偃蹇す
1623 雲を呼ぶ座右の梅や列仙伝
1624 紅梅や文箱差出す高蒔絵
1625 藪の梅危く咲きぬ二三輪
1626 無作法にぬつと出けり崖の梅
1627 梅活けて古道顔色を照らす哉
1628 潺湲の水挟む古梅かな
1629 手桶さげて谷に下るや梅の花
1630 寒梅に磬を打つなり月桂寺
1631 梅遠近そぞろあるきす昨日今日
1632 月升つて再び梅に徘徊す
1633 糸印の読み難きを愛す梅の翁
1634 鉄幹や暁星を点ず居士の梅
1635 梅一株竹三竿の住居かな
1636 梅に対す和靖の髭の白きかな
1637 琴に打つ斧の響や梅の花
1638 槎牙として素琴を圧す梅の影
1639 朱を点ず三昧集や梅の花
1640 梅の精は美人にて松の精は翁也
1641 一輪を雪中梅と名けけり (1537~「同上」)
1642 靴足袋のあみかけてある火鉢哉 (「手帳」より 十六句 )
1643 ごんと鳴る鐘をつきけり春の暮
1644 炉塞いで山に入るべき日を思ふ
1645 白き蝶をふと見染めけり黄なる蝶
1646 小雀の餌や喰ふ黄なる口あけて
1647 梅の花青磁の瓶を乞ひ得たり
1648 郎去つて柳空しく緑なり
1649 行春や紅さめし衣の裏
1650 紫の幕をたゝむや花の山
1651 花の寺黒き仏の尊さよ
1652 僧か俗か庵を這入れば木瓜の花
1653 其愚には及ぶべからず木瓜の花
1654 寺町や土塀の隙の木瓜の花
1655 たく駝呼んで突ばい据ぬ木瓜の花
1656 木瓜の花の役にも立たぬ実となりぬ
1657 若葉して籠り勝なる書斎かな (1642~「同上」)
1658 暁や白蓮を剪る数奇心 (「村上霽月」宛書簡)
1659 馬渡す舟を呼びけり黍の間(子規へ送りたる句稿三十四・五十一句・九月)
1660 堅き梨に鈍き刃物を添てけり
1661 馬の子と牛の子と居る野菊かな
1662 温泉湧く谷の底より初嵐
1663 重ぬべき単衣も持たず肌寒し
1664 谷底の湯槽を出るやうそ寒み
1665 山里や今宵秋立つ水の音
1666 鶏頭の色づかであり温泉の流
1667 草山に馬放ちけり秋の空
1668 女郎花馬糞について上りけり
1669 女郎花土橋を二つ渡りけり
1670 囲ひあらで湯槽に逼る狭霧かな
1671 湯槽から四方を見るや稲の花
1672 鑓水の音たのもしや女郎花
1673 帰らんとして帰らぬ様や濡れ燕
1674 雪隠の窓から見るや秋の山
1675 北側は杉の木立や秋の山
1676 終日や尾の上離れぬ秋の雲
1677 蓼痩せて辛くもあらず温泉の流
1678 白萩の露をこぼすや温泉の流
1679 草刈の籃の中より野菊かな
1680 白露や研ぎすましたる鎌の色
1681 葉鶏頭団子の串を削りけり
1682 秋の川真白な石を拾ひけり
1683 秋雨や杉の枯葉をくべる音
1684 秋雨や蕎麦をゆでたる湯の臭ひ
1685 朝寒み白木の宮に詣でけり
1686 秋風や梵字を刻す五輪塔
1687 鳥も飛ばず二百十日の鳴子かな
1688 灰に濡れて立つや薄と萩の中
1689 行けど萩行けど薄の原広し
1690 語り出す祭文は何宵の秋
1691 野菊一輪手帳の中に挟みけり
1692 路岐して何れか是なるわれもかう
1693 七夕の女竹を伐るや裏の藪
1694 顔洗ふ盥に立つや秋の影
1695 柄杓もて水瓶洗ふ音や秋
1696 釣瓶きれて井戸を覗くや今朝の秋
1697 秋立つや眼鏡して見る三世相
1698 喪を秘して軍を返すや星月夜
1699 秋暑し癒なんとして胃の病
1700 聞かばやと思ふ砧を打ち出しぬ
1701 秋茄子髭ある人に嫁ぎけり
1702 湖を前に関所の秋早し
1703 初秋の隣に住むや池の坊
1704 荒壁に軸落ちつかず秋の風
1705 唐茄子の蔓の長さよ隣から
1706 端居して秋近き夜や空を見る
1707 顔にふるゝ芭蕉涼しや籐の寝椅子
1708 涼しさや石握り見る掌 (前書「寅彦桂浜の石数十顆を送る」)
1709 時くれば燕もやがて帰るなり
1710 秋立つや萩のうねりのやゝ長く (1659~「同上」)
1711 いかめしき門を這入れば蕎麦の花(子規へ送りたる句稿三十五・二十九句・十月)
1712 粟みのる畠を借して敷地なり
1713 松を出てまばゆくぞある露の原
1714 韋編断えて夜寒の倉に束ねたる
1715 秋はふみ吾に天下の志
1716 頓首して新酒門内に許されず
1717 肌寒と申し襦袢の贈物
1718 孔孟の道貧ならず稲の花
1719 古ぼけし油絵をかけ秋の蝶
1720 赤き物少しは参れ蕃椒
1721 かしこまる膝のあたりやそゞろ寒
1722 朝寒の顔を揃へし机かな
1723 先生の疎髯を吹くや秋の風
1724 本名は頓とわからず草の花
1725 苔青く末枯るゝべきものもなし
1726 南窓に写真を焼くや赤蜻蛉
1727 暗室や心得たりときりぎりす
1728 化学とは花火を造る術ならん
1729 玻璃瓶に糸瓜の水や二升程
1730 剥製の鵙鳴かなくに昼淋し
1731 魚も祭らず獺老いて秋の風
1732 樊かい(口偏に會)や闥を排して茸の飯
1733 大食を上座に粟の飯黄なり
1734 瓜西瓜富婁那ならぬはなかりけり
1735 就中うましと思ふ柿と栗
1736 稲妻の目にも留らぬ勝負哉
1737 容赦なく瓢を叩く糸瓜かな
1738 転けし芋の鳥渡起き直る健気さよ
1739 靡けども芒を倒し能はざる (1711~「同上」)
1740 重箱に笹を敷きけり握り鮓 (「手帳」より 十四句)
1741 見るからに涼しき宿や谷の底
1742 むつとして口を開かぬ桔梗かな
1743 さらさらと護謨の合羽に秋の雨
1744 渋柿や長者と見えて岡の家
1745 門前に琴弾く家や菊の寺
1746 時雨るゝや足場朽ちたる堂の漏
1747 釣鐘をすかして見るや秋の海
1748 菊に猫沈南蘋を招きけり
1749 部屋住の棒使ひ居る月夜かな
1750 蛤とならざるをいたみ菊の露
1751 神垣や紅葉を翳す巫女の袖
1752 火燵して得たる将棋の詰手哉
1753 自転車を輪に乗る馬場の柳かな (1740~「同上」)
1754 見るからに君痩せたりな露時雨(霽月の「九州めぐり句稿」より十三句)
1755 白菊に酌むべき酒も候はず
1756 抜けば崇る刀を得たり暮の秋
1757 白菊に黄菊に心定まらず
1758 ホーと吹て鏡拭ふや霜の朝
1759 時雨るや宿屋の下駄をはき卸す
1760 凩や斜に構へたる纏持
1761 旅の秋高きに上る日もあらん
1762 行秋を鍍金剥げたる指輪哉
1763 秋風や茶壺を直す袋棚
1764 醸し得たる一斗の酒や家二軒
1765 京の菓子は唐紅の紅葉哉
1766 長崎で唐の綿衣をとゝのへよ (1754~「同上」)
1767 横顔の歌舞伎に似たる火鉢哉(「虚子」宛書簡 四句)
1768 炭団いけて雪隠詰の工夫哉
1769 御家人の安火を抱くや後風土記
1770 追分で引き剥がれたる寒かな (1767~「同上」)
1771 決闘や町をはなれて星月夜 (『全集』収載)
1772 安々と海鼠の如き子を生めり
1773 時雨ては化る文福茶釜かな
1774 寒菊や京の茶を売る夫婦もの
1775 茶の会に客の揃はぬ時雨哉
1776 山茶花や亭をめぐりて小道あり
1777 茶の花や長屋も持ちて浄土寺
1778 小春日や茶室を開き南向
1779 水仙や髯たくはへて売茶翁 (1771~「同上」)
(参考) 「 根岸庵を訪う記(寺田寅彦)」周辺
https://www.aozora.gr.jp/cards/000042/files/24406_15380.html
九月五日動物園の大蛇を見に行くとて京橋の寓居(ぐうきょ)を出て通り合わせの鉄道馬車に乗り上野へ着いたのが二時頃。今日は曇天で暑さも薄く道も悪くないのでなかなか公園も賑(にぎ)おうている。西郷の銅像の後ろから黒門(くろもん)の前へぬけて動物園の方へ曲ると外国の水兵が人力(じんりき)と何か八釜(やかま)しく云って直(ねぶ)みをしていたが話が纏(まと)まらなかったと見えて間もなく商品陳列所の方へ行ってしまった。マニラの帰休兵とかで茶色の制服に中折帽を冠(かぶ)ったのがここばかりでない途中でも沢山(たくさん)見受けた。動物園は休みと見えて門が締まっているようであったから博物館の方へそれて杉林の中へ這入はいった。鞦韆(ぶらんこ)に四、五人子供が集まって騒いでいる。ふり返って見ると動物園の門に田舎者らしい老人と小僧と見えるのが立って掛札を見ている。
其処(そこ)へ美術学校の方から車が二台幌(ほろ)をかけたのが出て来たがこれもそこへ止って何か云うている様子であったがやがてまた勧工場(かんこうば)の方へ引いて行った。自分も陳列所前の砂道を横切って向いの杉林に這入るとパノラマ館の前でやっている楽隊が面白そうに聞えたからつい其方(そちら)へ足が向いたが丁度その前まで行くと一切(ひときり)済んだのであろうぴたりと止(やめ)てしまって楽手は煙草などふかしてじろ/\見物の顔を見ている。後ろへ廻って見ると小さな杉が十本くらいある下に石の観音がころがっている。何々大姉(だいし)と刻してある。真逆(まさか)に墓表(ぼひょう)とは見えずまた墓地でもないのを見るとなんでもこれは其処(そこ)で情夫に殺された女か何かの供養に立てたのではあるまいかなど凄涼(せいりょう)な感に打たれて其処を去り、館の裏手へ廻ると坂の上に三十くらいの女と十歳くらいの女の子とが枯枝を拾うていたからこれに上根岸(かみねぎし)までの道を聞いたら丁寧(ていねい)に教えてくれた。
不折(ふせつ)の油画(あぶらえ)にありそうな女だなど考えながら博物館の横手大猷院尊前(だいゆういんそんぜん)と刻した石燈籠の並んだ処を通って行くと下り坂になった。道端に乞食が一人しゃがんで頻(しきり)に叩頭(ぬか)ずいていたが誰れも慈善家でないと見えて鐚一文(びたいちもん)も奉捨にならなかったのは気の毒であった。これが柴とりの云うた新坂なるべし。つくつくほうし(※漢字)が八釜(やかま)しいまで鳴いているが車の音の聞えぬのは有難いと思うていると上野から出て来た列車が煤煙を吐いて通って行った。三番と掛札した踏切を越えると桜木町で辻に交番所がある。帽子を取って恭(うやうや)しく子規しきの家を尋ねたが知らぬとの答故(ゆえ)少々意外に思うて顔を見詰めた。するとこれが案外親切な巡査で戸籍簿のようなものを引っくり返して小首を傾けながら見ておったが後を見かえって内に昼ねしていた今一人のを呼び起した。
交代の時間が来たからと云うて序(つい)でにこの人にも尋ねてくれたがこれも知らぬ。この巡査の少々横柄顔おうへいがお)が癪(しゃく)にさわったれども前のが親切に対しまた恭しく礼を述べて左へ曲った。何でも上根岸八十二番とか思うていたが家々の門札に気を付けて見て行くうち前田の邸(やしき)と云うに行当(ゆきあた)ったので漱石師(そうせきし)に聞いた事を思い出して裏へ廻ると小さな小路(こうじ)で角に鶯横町(うぐいすよこちょう)と札が打ってある。これを這入って黒板塀と竹藪の狭い間を二十間(けん)ばかり行くと左側に正岡常規(つねのり)とかなり新しい門札がある。黒い冠木門(かぶきもん)の両開き戸をあけるとすぐ玄関で案内を乞うと右脇にある台所で何かしていた老母らしきが出て来た。姓名を告げて漱石師より予(かね)て紹介のあった筈(はず)である事など述べた。玄関にある下駄が皆女物で子規のらしいのが見えぬのが先ず胸にこたえた。外出と云う事は夢の外ないであろう。枕上(まくらがみ)のしきを隔てて座を与えられた。
初対面の挨拶もすんであたりを見廻した。四畳半と覚しき間(ま)の中央に床をのべて糸のように痩せ細った身体を横たえて時々咳(せき)が出ると枕上の白木の箱の蓋を取っては吐き込んでいる。蒼白くて頬の落ちた顔に力なけれど一片の烈火瞳底に燃えているように思われる。左側に机があって俳書らしいものが積んである。机に倚(よる)事さえ叶(かな)わぬのであろうか。右脇には句集など取散らして原稿紙に何か書きかけていた様子である。いちばん目に止るのは足の方の鴨居(かもい)に笠と簑とを吊して笠には「西方十万億土順礼 西子」と書いてある。右側の障子の外が『ホトトギス』へ掲げた小園で奥行四間もあろうか萩の本(もと)を束ねたのが数株心のままに茂っているが花はまだついておらぬ。
まいかいは花が落ちてうてながまだ残ったままである。白粉花(おしろいばな)ばかりは咲き残っていたが鶏頭(けいとう)は障子にかくれて丁度見えなかった。熊本の近況から漱石師の噂になって昔話も出た。師は学生の頃は至って寡言(かげん)な温順な人で学校なども至って欠席が少なかったが子規は俳句分類に取りかかってから欠席ばかりしていたそうだ。
師と子規と親密になったのは知り合ってから四年もたって後であったが懇意になるとずいぶん子供らしく議論なんかして時々喧嘩(けんか)などもする。そう云う風であるから自然細君(さいくん)といさかう事もあるそうだ。それを予(あらか)じめ知っておらぬと細君も驚く事があるかも知れぬが根が気安過ぎるからの事である故驚く事はない。いったい誰れに対してもあたりの良い人の不平の漏らし所は家庭だなど云う。
室(へや)の庭に向いた方の鴨居に水彩画が一葉隣室に油画が一枚掛っている。皆不折が書いたので水彩の方は富士の六合目で磊々(らいらい)たる赭土塊(あかつちくれ)を踏んで向うへ行く人物もある。油画は御茶の水の写生、あまり名画とは見えぬようである。不折ほど熱心な画家はない。もう今日の洋画家中唯一の浅井忠(ちゅう)氏を除けばいずれも根性の卑劣な媚嫉(ぼうしつ)の強い女のような奴ばかりで、浅井氏が今度洋行するとなると誰れもその後任を引受ける人がない。ないではないが浅井の洋行が厭(いや)であるから邪魔をしようとするのである。
驚いたものだ。不折の如きも近来評判がよいので彼等の妬(ねたみ)を買い既に今度仏国博覧会へ出品する積(つも)りの作も審査官の黒田等が仕様もあろうに零点をつけて不合格にしてしまったそうだ。こう云う風であるから真面目に熱心に斯道(しどう)の研究をしようと云う考えはなく少しく名が出れば肖像でも画いて黄白(こうはく)を貪(むさぼ)ろうと云うさもしい奴ばかりで、中にたまたま不折のような熱心家はあるが貧乏であるから思うように研究が出来ぬ。そこらの車夫でもモデルに雇うとなると一日五十銭も取る。少し若い女などになるとどうしても一円は取られる。それでなかなか時間もかかるから研究と一口に云うても容易な事ではない。
景色画でもそうだ。先頃上州(じょうしゅう)へ写生に行って二十日ほど雨のふる日も休まずに画いて帰って来ると浅井氏がもう一週間行って直して来いと云われたからまた行って来てようよう出来上がったと云っていたそうだ。それでもとにかく熱心がひどいからあまり器用なたちでもなくまだ未熟ではあるが成効するだろうよ。
やはり『ホトトギス』の裏絵をかく為山(いざん)と云う男があるがこの男は不折とまるで反対な性で趣味も新奇な洋風のを好む。いったい手先は不折なんかとちがってよほど器用だがどうも不勉強であるから近来は少々不折に先を越されそうな。それがちと近来不平のようであるがそれかと云うてやはり不精だから仕方がない。
あのくらいの天才を抱きながら終ついに不折の熱心に勝を譲るかも知れぬなど話しているうち上野からの汽車が隣の植込の向うをごん/\と通った。隣の庭の折戸の上に烏からすが三羽下りてガー/\となく。夕日が畳の半分ほど這入って来た。
不折の一番得意で他に及ぶ者のないのは『日本』に連載するような意匠画でこれこそ他に類がない。配合の巧みな事材料の豊富なのには驚いてしまう。例えば犬百題など云う難題でも何処どこかから材料を引っぱり出して来て苦もなく拵(こしら)える。
いったい無学と云ってよい男であるからこれはきっと僕等がいろんな入智恵をするのだと思う人があるようだが中々そんな事ではない。僕等が夢にも知らぬような事が沢山あって一々説明を聞いてようやく合点(がてん)が行くくらいである。どうも奇態な男だ。先達(せんだ)って『日本』新聞に掲げた古瓦の画などは最も得意でまた実際真似(まね)は出来ぬ。あの瓦の形を近頃秀真(ほずま)と云う美術学校の人が鋳物(いもの)にして茶托(ちゃたく)にこしらえた。そいつが出来損なったのを僕が貰うてあるから見せようとて見せてくれた。十五枚の内ようよう五枚出来たそうで、それも穴だらけに出来て中に破れて繕つくろったのもあるが、それが却(かえ)って一段の趣味を増しているようだと云うたら子規も同意した。
巧みに古色が付けてあるからどうしても数百年前のものとしか見えぬ。中に蝸牛(かたつむり)を這わして「角つのふりわけよ」の句が刻してあるのなどはずいぶん面白い。絵とちがって鋳物だから蝸牛が大変よく利いているとか云うて不折もよほど気に入った様子だった。羽織を質入れしてもぜひ拵えさせると云うていたそうだと。話し半(なかば)へ老母が珈琲(コーヒー)を酌んで来る。子規には牛乳を持って来た。汽車がまた通って「※つくほうし」(漢字)の声を打消していった。
初対面からちと厚顔(あつかま)しいようではあったが自分は生来絵が好きで予(かね)てよい不折の絵が別けても好きであったから序(つい)でがあったら何でもよいから一枚呉(くれ)まいかと頼んで下さいと云ったら快く引受けてくれたのは嬉しかった。子規も小さい時分から絵画は非常に好きだが自分は一向かけないのが残念でたまらぬと喞(かこ)っていた。
夕日はますます傾いた。隣の屋敷で琴が聞える。音楽は好きかと聞くと勿論きらいではないが悲しいかな音楽の事は少しも知らぬ。どうか調べてみたいと思うけれどもこれからでは到底駄目であろう。尤(もっと)もこの頃人の話で大凡(おおよそ)こんなものかくらいは解ったようだが元来西洋の音楽などは遠くの昔バイオリンを聞いたばかりでピアノなんか一度も聞いた事はないからなおさら駄目だ。どうかしてあんなものが聞けるようにも一度なりたいと思うけれどもそれも駄目だと云うて暫く黙した。自分は何と云うてよいか判らなかった。
黯然(あんぜん)として吾(われ)も黙した。また汽車が来た。色々議論もあるようであるが日本の音楽も今のままでは到底見込みこみがないそうだ。国が箱庭的であるからか音楽まで箱庭的である。一度音楽学校の音楽室で琴の弾奏を聞いたが遠くで琴が聞えるくらいの事で物にならぬ。やはり天井の低い狭い室でなければ引合わぬと見える。それに調子が単純で弾ずる人に熱情がないからなおさらいかん。自分は素人考(しろうとかんがえ)で何でも楽器は指の先で弾くものだから女に適したものとばかり思うていたが中々そんな浅いものではない。日本人が西洋の楽器を取ってならす事はならすが音楽にならぬと云うのはつまり弾手ひきての情が単調で狂すると云う事がないからで、西洋の名手とまで行かぬ人でも楽がくの大切な面白い所へくると一切夢中になってしまうそうだ。こればかりは日本人の真似の出来ぬ事で致し方がない。ことに婦人は駄目だ、冷淡で熱情がないから。露伴(ろはん)の妹などは一時評判であったがやはり駄目だと云う事だ。
空が曇ったのか日が上野の山へかくれたか畳の夕日が消えてしまいつくつくほうしの声が沈んだようになった。烏はいつの間にか飛んで行っていた。また出ますと云うたら宿は何処(どこか)と聞いたから一両日中に谷中(やなか)の禅寺へ籠る事を話して暇(いとま)を告げて門へ出た。隣の琴の音が急になって胸をかき乱さるるような気がする。不知不識(しらずしらず)其方へと路次を這入(はいる)と道はいよいよ狭くなって井戸が道をさえぎっている。その傍で若い女が米を磨といでいる。流しの板のすべりそうなのを踏んで向側へ越すと柵があってその上は鉄道線路、その向うは山の裾である。其処を右へ曲るとよう/\広い街に出たから浅草の方へと足を運んだ。琴の音はやはりついて来る。道がまた狭くなってもとの前田邸の裏へ出た。ここから元来た道を交番所の前まであるいてここから曲らずに真直ぐに行くとまた踏切を越えねばならぬ。琴の音はもうついて来ぬ。森の中でつくつくほうしがゆるやかに鳴いて、日陰だから人が蝙蝠傘(こうもりがさ)を阿弥陀にさしてゆる/\あるく。山の上には人が沢山たくさん停車場から凌雲閣ゅりょううんかく)の方を眺めている。左側の柵の中で子供が四、五人石炭車に乗ったり押したりしている。機関車がすさまじい音をして小家の向うを出て来た。浅草へ行く積りであったがせっかく根岸で味おうた清閑の情を軽業(かるわざ)の太鼓御賽銭(おさいせん)の音に汚(けが)すが厭になったから山下まで来ると急いで鉄道馬車に飛乗って京橋まで窮屈な目にあって、向うに坐った金縁眼鏡き(んぶちめがね)隣に坐った禿頭の行商と欠伸(あくび)の掛け合いで帰って来たら大通りの時計台が六時を打った。 (明治三十二年九月) ≫

「蕪村忌(明治32年(1899)12月)」 (子規庵蔵)
https://www.culture.city.taito.lg.jp/bunkatanbou/topics/famous_persons/shiki/japanese/page_04.html
≪西側黒板塀前で撮影。子規は、中央で脇息(きょうそく、肘掛け)にもたれています。≫
http://chikata.net/?p=2883
(再掲)
明治32年(1899年)
1月、子規へ句稿を送る(75句)
1月、子規『俳諧大要』を発表。
2月、子規へ句稿を送る(105句)
5月、長女(筆子)誕生。
9月、子規へ句稿を送る(51句)
同月、阿蘇登山。
10月、子規へ句稿を送る(29句)
(追記) 夏目漱石俳句集(その六)<制作年順> 明治32年(1430~1540)
https://sosekihaikushu.seesaa.net/article/200912article_1.html
明治32年(1899年)
1430 我に許せ元日なれば朝寝坊(「虚子・碧悟桐」宛書簡)
1431 金泥の鶴や朱塗の屠蘇の盃 (子規へ送りたる句稿三十二・七十五句・一月)
1432 宇佐に行くや佳き日を選む初暦
1433 梅の神に如何なる恋や祈るらん
1434 うつくしき蜑の頭や春の鯛
1435 蕭条たる古駅に入るや春の夕
1436 兀として鳥居立ちけり冬木立
1437 神苑に鶴放ちけり梅の花
1438 ぬかづいて曰く正月二日なり
1439 松の苔鶴痩せながら神の春
1440 南無弓矢八幡殿に御慶かな
1441 神かけて祈る恋なし宇佐の春
1442 呉橋や若菜を洗ふ寄藻川
1443 灰色の空低れかゝる枯野哉
1444 無提灯で枯野を通る寒哉
1445 石標や残る一株の枯芒
1446 枯芒北に向つて靡きけり
1447 遠く見る枯野の中の烟かな
1448 暗がりに雑巾を踏む寒哉
1449 冬ざれや狢をつるす軒の下
1450 凩や岩に取りつく羅漢路
1451 巌窟の羅漢共こそ寒からめ
1452 釣鐘に雲氷るべく山高し
1453 凩の鐘楼危ふし巌の角
1454 梯して上る大盤石の氷かな
1455 巌頭に本堂くらき寒かな
1456 絶壁に木枯あたるひゞきかな
1457 雛僧の只風呂吹と答へけり
1458 かしこしや未来を霜の笹結び
1459 二世かけて結ぶちぎりや雪の笹
1460 短かくて毛布つぎ足す蒲団かな
1461 泊り合す旅商人の寒がるよ
1462 寐まらんとすれど衾の薄くして
1463 頭巾着たる猟師に逢ひぬ谷深み
1464 はたと逢ふ夜興引ならん岩の角
1465 谷深み杉を流すや冬の川
1466 冬木流す人は猿の如くなり
1467 帽頭や思ひがけなき岩の雪
1468 石の山凩に吹かれ裸なり
1469 凩のまがりくねつて響きけり
1470 凩の吹くべき松も生えざりき
1471 年々や凩吹て尖る山
1472 凩の峰は剣の如くなり
1473 恐ろしき岩の色なり玉霰
1474 只寒し天狭くして水青く
1475 目ともいはず口ともいはず吹雪哉
1476 ばりばりと氷踏みけり谷の道
1477 道端や氷りつきたる高箒
1478 たまさかに据風呂焚くや冬の雨
1479 せぐゝまる蒲団の中や夜もすがら
1480 薄蒲団なえし毛脛を擦りけり
1481 僧に似たるが宿り合せぬ雪今宵
1482 雪ちらちら峠にかかる合羽かな
1483 払へども払へどもわが袖の雪
1484 かたかりき鞋喰ひ込む足袋の股
1485 隧道の口に大なる氷柱かな
1486 吹きまくる雪の下なり日田の町
1487 炭を積む馬の脊に降る雪まだら
1488 漸くに又起きあがる吹雪かな
1489 詩僧死して只凩の里なりき
1490 蓆帆の早瀬を上る霰かな
1491 奔湍に霰ふり込む根笹かな
1492 つるぎ洗ふ武夫もなし玉霰
1493 新道は一直線の寒さかな
1494 棒鼻より三里と答ふ吹雪哉
1495 なつかしむ衾に聞くや馬の鈴
1496 親方と呼びかけられし毛布哉
1497 餅搗や明星光る杵の先
1498 行く年の左したる思慮もなかりけり
1499 染め直す古服もなし年の暮
1500 やかましき姑健なり年の暮
1501 ニッケルの時計とまりぬ寒き夜半
1502 元日の富士に逢ひけり馬の上
1503 蓬莱に初日さし込む書院哉
1504 光琳の屏風に咲くや福寿草
1505 眸に入る富士大いなり春の楼 (1431~「同上」)
1506 馬に蹴られ吹雪の中に倒れけり(「手帳」より 三十一句)
1507 雪の客僧に似たりや五七日
1508 沈まざる南瓜浮名を流しけり
1509 石打てばかららんと鳴る氷哉
1510 楽しんで蓋をあくれば干鱈哉
1511 乾鮭や薄く切れとの仰せなり
1512 妾と郎離別を語る柳哉
1513 春風に祖師西来の意あるべし
1514 禅僧に旛動きけり春の風
1515 郎を待つ待合茶屋の柳かな
1516 鞭つて牛動かざる日永かな
1517 わが歌の胡弓にのらぬ朧かな
1518 煩悩の朧に似たる夜もありき
1519 吾折々死なんと思ふ朧かな
1520 春此頃化石せんとの願あり
1521 招かれて隣に更けし歌留多哉
1522 追羽子や君稚児髷の黒眼勝
1523 耄碌と名のつく老の頭巾かな
1524 筋違に葱を切るなり都振
1525 玉葱の煮えざるを焦つ火鉢哉
1526 湯豆腐に霰飛び込む床几哉
1527 立ん坊の地団太を踏む寒かな
1528 べんべらを一枚着たる寒さかな
1529 ある時は鉢叩かうと思ひけり
1530 寄り添へば冷たき瀬戸の火鉢かな
1531 雪を煮て煮立つ音の涼しさよ
1532 挙して曰く可なく不可なし蕪汁
1533 善か悪か風呂吹を喰つて我点せよ
1534 何の故に恐縮したる生海鼠哉
1535 老たん(※耳偏に冉)のうとき耳ほる火燵かな
1536 仏画く殿司の窓や梅の花 (1506~「同上」)
1537 夫子貧に梅花書屋の粥薄し(子規へ送りたる句稿三十三・一〇五句・二月)
1538 手を入るゝ水餅白し納屋の梅
1539 馬の尻に尾して下るや岨の梅
1540 ある程の梅に名なきはなかり鳧
1541 奈良漬に梅に其香をなつかしむ
1542 相伝の金創膏や梅の花
1543 たのもしき梅の足利文庫かな
1544 抱一は発句も読んで梅の花
≪季=梅の花(春)。※抱一は江戸後期の画家、酒井抱一。諸芸に優れ、俳諧は江戸座に学んだ。自選発句集『屠龍之技』がある。≫
1545 明た口に団子賜る梅見かな
1546 いざ梅見合点と端折る衣の裾
1547 夜汽車より白きを梅と推しけり
1548 死して名なき人のみ住んで梅の花
1549 法橋を給はる梅の主人かな
1550 玉蘭と大雅と語る梅の花
1551 村長の上座につくや床の梅
1552 梅の小路練香ひさぐ翁かな
1553 寄合や少し後れて梅の掾
1554 裏門や酢蔵に近き梅赤し
1555 一つ紋の羽織はいやし梅の花
1556 白梅や易を講ずる蘇東坡服
1557 蒟蒻に梅を踏み込む男かな
1558 梅の花千家の会に参りけり
1559 碧玉の茶碗に梅の落花かな
1560 粗略ならぬ服紗さばきや梅の主
1561 日当りや刀を拭ふ梅の主
1562 祐筆の大師流なり梅の花
1563 日をうけぬ梅の景色や楞伽窟
1564 とく起て味噌する梅の隣かな
1565 梅の花貧乏神の祟りけり
1566 駒犬の怒つて居るや梅の花
1567 筮竹に梅ちりかゝる社頭哉
1568 一斎の小鼻動くよ梅花飯
1569 封切れば月が瀬の梅二三片
1570 ものいはず童子遠くの梅を指す
1571 寒徹骨梅を娶ると夢みけり
1572 驢に乗るは東坡にやあらん雪の梅
1573 梅の詩を得たりと叩く月の門
1574 黄昏の梅に立ちけり絵師の妻
1575 髣髴と日暮れて入りぬ梅の村
1576 梅散るや源太の箙はなやかに
1577 月に望む麓の村の梅白し
1578 瑠璃色の空を控へて岡の梅
1579 落梅花水車の門を流れけり
1580 梅の下に槙割る翁の面黄也
1581 妓を拉す二重廻しや梅屋敷
1582 暁の梅に下りて嗽ぐ
1583 梅の花琴を抱いてあちこちす
1584 さらさらと衣を鳴らして梅見哉
1585 佩環の鏘然として梅白し
1586 戛と鳴て鶴飛び去りぬ闇の梅
1587 眠らざる僧の嚏や夜半の梅
1588 尺八のはたとやみけり梅の門
1589 宣徳の香炉にちるや瓶の梅
1590 古銅瓶に疎らな梅を活けてけり
1591 鉄筆や水晶刻む窓の梅
1592 墨の香や奈良の都の古梅園
1593 梅の宿残月硯を蔵しけり
1594 畠打の梅を繞ぐつて動きけり
1595 縁日の梅窮屈に咲きにけり
1596 梅の香や茶畠つゞき爪上り
1597 灯もつけず雨戸も引かず梅の花
1598 梅林や角巾黄なる売茶翁
1599 上り汽車の箱根を出て梅白し
1600 佶倔な梅を画くや謝春星
1601 雪隠の壁に上るや梅の影
1602 道服と吾妻コートの梅見哉
1603 女倶して舟を上るや梅屋敷
1604 梅の寺麓の人語聞こゆなり
1605 梅の奥に誰やら住んで幽かな灯
1606 円遊の鼻ばかりなり梅屋敷
1607 梅の中に且たのもしや梭の音
1608 清げなる宮司の面や梅の花
1609 月升つて枕に落ちぬ梅の影
1610 相逢ふて語らで過ぎぬ梅の下
1611 昵懇な和尚訪ひよる梅の坊
1612 月の梅貴とき狐裘着たりけり
1613 京音の紅梅ありやと尋ねけり
1614 紅梅に艶なる女主人かな
1615 紅梅や物の化の住む古館
1616 梅紅ひめかけの歌に咏まれけり
1617 いち早く紅梅咲きぬ下屋敷
1618 紅梅や姉妹の振る采の筒
1619 長と張つて半と出でけり梅の宿
1620 俗俳や床屋の卓に奇なる梅
1621 徂来其角並んで住めり梅の花
1622 盆梅の一尺にして偃蹇す
1623 雲を呼ぶ座右の梅や列仙伝
1624 紅梅や文箱差出す高蒔絵
1625 藪の梅危く咲きぬ二三輪
1626 無作法にぬつと出けり崖の梅
1627 梅活けて古道顔色を照らす哉
1628 潺湲の水挟む古梅かな
1629 手桶さげて谷に下るや梅の花
1630 寒梅に磬を打つなり月桂寺
1631 梅遠近そぞろあるきす昨日今日
1632 月升つて再び梅に徘徊す
1633 糸印の読み難きを愛す梅の翁
1634 鉄幹や暁星を点ず居士の梅
1635 梅一株竹三竿の住居かな
1636 梅に対す和靖の髭の白きかな
1637 琴に打つ斧の響や梅の花
1638 槎牙として素琴を圧す梅の影
1639 朱を点ず三昧集や梅の花
1640 梅の精は美人にて松の精は翁也
1641 一輪を雪中梅と名けけり (1537~「同上」)
1642 靴足袋のあみかけてある火鉢哉 (「手帳」より 十六句 )
1643 ごんと鳴る鐘をつきけり春の暮
1644 炉塞いで山に入るべき日を思ふ
1645 白き蝶をふと見染めけり黄なる蝶
1646 小雀の餌や喰ふ黄なる口あけて
1647 梅の花青磁の瓶を乞ひ得たり
1648 郎去つて柳空しく緑なり
1649 行春や紅さめし衣の裏
1650 紫の幕をたゝむや花の山
1651 花の寺黒き仏の尊さよ
1652 僧か俗か庵を這入れば木瓜の花
1653 其愚には及ぶべからず木瓜の花
1654 寺町や土塀の隙の木瓜の花
1655 たく駝呼んで突ばい据ぬ木瓜の花
1656 木瓜の花の役にも立たぬ実となりぬ
1657 若葉して籠り勝なる書斎かな (1642~「同上」)
1658 暁や白蓮を剪る数奇心 (「村上霽月」宛書簡)
1659 馬渡す舟を呼びけり黍の間(子規へ送りたる句稿三十四・五十一句・九月)
1660 堅き梨に鈍き刃物を添てけり
1661 馬の子と牛の子と居る野菊かな
1662 温泉湧く谷の底より初嵐
1663 重ぬべき単衣も持たず肌寒し
1664 谷底の湯槽を出るやうそ寒み
1665 山里や今宵秋立つ水の音
1666 鶏頭の色づかであり温泉の流
1667 草山に馬放ちけり秋の空
1668 女郎花馬糞について上りけり
1669 女郎花土橋を二つ渡りけり
1670 囲ひあらで湯槽に逼る狭霧かな
1671 湯槽から四方を見るや稲の花
1672 鑓水の音たのもしや女郎花
1673 帰らんとして帰らぬ様や濡れ燕
1674 雪隠の窓から見るや秋の山
1675 北側は杉の木立や秋の山
1676 終日や尾の上離れぬ秋の雲
1677 蓼痩せて辛くもあらず温泉の流
1678 白萩の露をこぼすや温泉の流
1679 草刈の籃の中より野菊かな
1680 白露や研ぎすましたる鎌の色
1681 葉鶏頭団子の串を削りけり
1682 秋の川真白な石を拾ひけり
1683 秋雨や杉の枯葉をくべる音
1684 秋雨や蕎麦をゆでたる湯の臭ひ
1685 朝寒み白木の宮に詣でけり
1686 秋風や梵字を刻す五輪塔
1687 鳥も飛ばず二百十日の鳴子かな
1688 灰に濡れて立つや薄と萩の中
1689 行けど萩行けど薄の原広し
1690 語り出す祭文は何宵の秋
1691 野菊一輪手帳の中に挟みけり
1692 路岐して何れか是なるわれもかう
1693 七夕の女竹を伐るや裏の藪
1694 顔洗ふ盥に立つや秋の影
1695 柄杓もて水瓶洗ふ音や秋
1696 釣瓶きれて井戸を覗くや今朝の秋
1697 秋立つや眼鏡して見る三世相
1698 喪を秘して軍を返すや星月夜
1699 秋暑し癒なんとして胃の病
1700 聞かばやと思ふ砧を打ち出しぬ
1701 秋茄子髭ある人に嫁ぎけり
1702 湖を前に関所の秋早し
1703 初秋の隣に住むや池の坊
1704 荒壁に軸落ちつかず秋の風
1705 唐茄子の蔓の長さよ隣から
1706 端居して秋近き夜や空を見る
1707 顔にふるゝ芭蕉涼しや籐の寝椅子
1708 涼しさや石握り見る掌 (前書「寅彦桂浜の石数十顆を送る」)
1709 時くれば燕もやがて帰るなり
1710 秋立つや萩のうねりのやゝ長く (1659~「同上」)
1711 いかめしき門を這入れば蕎麦の花(子規へ送りたる句稿三十五・二十九句・十月)
1712 粟みのる畠を借して敷地なり
1713 松を出てまばゆくぞある露の原
1714 韋編断えて夜寒の倉に束ねたる
1715 秋はふみ吾に天下の志
1716 頓首して新酒門内に許されず
1717 肌寒と申し襦袢の贈物
1718 孔孟の道貧ならず稲の花
1719 古ぼけし油絵をかけ秋の蝶
1720 赤き物少しは参れ蕃椒
1721 かしこまる膝のあたりやそゞろ寒
1722 朝寒の顔を揃へし机かな
1723 先生の疎髯を吹くや秋の風
1724 本名は頓とわからず草の花
1725 苔青く末枯るゝべきものもなし
1726 南窓に写真を焼くや赤蜻蛉
1727 暗室や心得たりときりぎりす
1728 化学とは花火を造る術ならん
1729 玻璃瓶に糸瓜の水や二升程
1730 剥製の鵙鳴かなくに昼淋し
1731 魚も祭らず獺老いて秋の風
1732 樊かい(口偏に會)や闥を排して茸の飯
1733 大食を上座に粟の飯黄なり
1734 瓜西瓜富婁那ならぬはなかりけり
1735 就中うましと思ふ柿と栗
1736 稲妻の目にも留らぬ勝負哉
1737 容赦なく瓢を叩く糸瓜かな
1738 転けし芋の鳥渡起き直る健気さよ
1739 靡けども芒を倒し能はざる (1711~「同上」)
1740 重箱に笹を敷きけり握り鮓 (「手帳」より 十四句)
1741 見るからに涼しき宿や谷の底
1742 むつとして口を開かぬ桔梗かな
1743 さらさらと護謨の合羽に秋の雨
1744 渋柿や長者と見えて岡の家
1745 門前に琴弾く家や菊の寺
1746 時雨るゝや足場朽ちたる堂の漏
1747 釣鐘をすかして見るや秋の海
1748 菊に猫沈南蘋を招きけり
1749 部屋住の棒使ひ居る月夜かな
1750 蛤とならざるをいたみ菊の露
1751 神垣や紅葉を翳す巫女の袖
1752 火燵して得たる将棋の詰手哉
1753 自転車を輪に乗る馬場の柳かな (1740~「同上」)
1754 見るからに君痩せたりな露時雨(霽月の「九州めぐり句稿」より十三句)
1755 白菊に酌むべき酒も候はず
1756 抜けば崇る刀を得たり暮の秋
1757 白菊に黄菊に心定まらず
1758 ホーと吹て鏡拭ふや霜の朝
1759 時雨るや宿屋の下駄をはき卸す
1760 凩や斜に構へたる纏持
1761 旅の秋高きに上る日もあらん
1762 行秋を鍍金剥げたる指輪哉
1763 秋風や茶壺を直す袋棚
1764 醸し得たる一斗の酒や家二軒
1765 京の菓子は唐紅の紅葉哉
1766 長崎で唐の綿衣をとゝのへよ (1754~「同上」)
1767 横顔の歌舞伎に似たる火鉢哉(「虚子」宛書簡 四句)
1768 炭団いけて雪隠詰の工夫哉
1769 御家人の安火を抱くや後風土記
1770 追分で引き剥がれたる寒かな (1767~「同上」)
1771 決闘や町をはなれて星月夜 (『全集』収載)
1772 安々と海鼠の如き子を生めり
1773 時雨ては化る文福茶釜かな
1774 寒菊や京の茶を売る夫婦もの
1775 茶の会に客の揃はぬ時雨哉
1776 山茶花や亭をめぐりて小道あり
1777 茶の花や長屋も持ちて浄土寺
1778 小春日や茶室を開き南向
1779 水仙や髯たくはへて売茶翁 (1771~「同上」)
(参考) 「 根岸庵を訪う記(寺田寅彦)」周辺
https://www.aozora.gr.jp/cards/000042/files/24406_15380.html
九月五日動物園の大蛇を見に行くとて京橋の寓居(ぐうきょ)を出て通り合わせの鉄道馬車に乗り上野へ着いたのが二時頃。今日は曇天で暑さも薄く道も悪くないのでなかなか公園も賑(にぎ)おうている。西郷の銅像の後ろから黒門(くろもん)の前へぬけて動物園の方へ曲ると外国の水兵が人力(じんりき)と何か八釜(やかま)しく云って直(ねぶ)みをしていたが話が纏(まと)まらなかったと見えて間もなく商品陳列所の方へ行ってしまった。マニラの帰休兵とかで茶色の制服に中折帽を冠(かぶ)ったのがここばかりでない途中でも沢山(たくさん)見受けた。動物園は休みと見えて門が締まっているようであったから博物館の方へそれて杉林の中へ這入はいった。鞦韆(ぶらんこ)に四、五人子供が集まって騒いでいる。ふり返って見ると動物園の門に田舎者らしい老人と小僧と見えるのが立って掛札を見ている。
其処(そこ)へ美術学校の方から車が二台幌(ほろ)をかけたのが出て来たがこれもそこへ止って何か云うている様子であったがやがてまた勧工場(かんこうば)の方へ引いて行った。自分も陳列所前の砂道を横切って向いの杉林に這入るとパノラマ館の前でやっている楽隊が面白そうに聞えたからつい其方(そちら)へ足が向いたが丁度その前まで行くと一切(ひときり)済んだのであろうぴたりと止(やめ)てしまって楽手は煙草などふかしてじろ/\見物の顔を見ている。後ろへ廻って見ると小さな杉が十本くらいある下に石の観音がころがっている。何々大姉(だいし)と刻してある。真逆(まさか)に墓表(ぼひょう)とは見えずまた墓地でもないのを見るとなんでもこれは其処(そこ)で情夫に殺された女か何かの供養に立てたのではあるまいかなど凄涼(せいりょう)な感に打たれて其処を去り、館の裏手へ廻ると坂の上に三十くらいの女と十歳くらいの女の子とが枯枝を拾うていたからこれに上根岸(かみねぎし)までの道を聞いたら丁寧(ていねい)に教えてくれた。
不折(ふせつ)の油画(あぶらえ)にありそうな女だなど考えながら博物館の横手大猷院尊前(だいゆういんそんぜん)と刻した石燈籠の並んだ処を通って行くと下り坂になった。道端に乞食が一人しゃがんで頻(しきり)に叩頭(ぬか)ずいていたが誰れも慈善家でないと見えて鐚一文(びたいちもん)も奉捨にならなかったのは気の毒であった。これが柴とりの云うた新坂なるべし。つくつくほうし(※漢字)が八釜(やかま)しいまで鳴いているが車の音の聞えぬのは有難いと思うていると上野から出て来た列車が煤煙を吐いて通って行った。三番と掛札した踏切を越えると桜木町で辻に交番所がある。帽子を取って恭(うやうや)しく子規しきの家を尋ねたが知らぬとの答故(ゆえ)少々意外に思うて顔を見詰めた。するとこれが案外親切な巡査で戸籍簿のようなものを引っくり返して小首を傾けながら見ておったが後を見かえって内に昼ねしていた今一人のを呼び起した。
交代の時間が来たからと云うて序(つい)でにこの人にも尋ねてくれたがこれも知らぬ。この巡査の少々横柄顔おうへいがお)が癪(しゃく)にさわったれども前のが親切に対しまた恭しく礼を述べて左へ曲った。何でも上根岸八十二番とか思うていたが家々の門札に気を付けて見て行くうち前田の邸(やしき)と云うに行当(ゆきあた)ったので漱石師(そうせきし)に聞いた事を思い出して裏へ廻ると小さな小路(こうじ)で角に鶯横町(うぐいすよこちょう)と札が打ってある。これを這入って黒板塀と竹藪の狭い間を二十間(けん)ばかり行くと左側に正岡常規(つねのり)とかなり新しい門札がある。黒い冠木門(かぶきもん)の両開き戸をあけるとすぐ玄関で案内を乞うと右脇にある台所で何かしていた老母らしきが出て来た。姓名を告げて漱石師より予(かね)て紹介のあった筈(はず)である事など述べた。玄関にある下駄が皆女物で子規のらしいのが見えぬのが先ず胸にこたえた。外出と云う事は夢の外ないであろう。枕上(まくらがみ)のしきを隔てて座を与えられた。
初対面の挨拶もすんであたりを見廻した。四畳半と覚しき間(ま)の中央に床をのべて糸のように痩せ細った身体を横たえて時々咳(せき)が出ると枕上の白木の箱の蓋を取っては吐き込んでいる。蒼白くて頬の落ちた顔に力なけれど一片の烈火瞳底に燃えているように思われる。左側に机があって俳書らしいものが積んである。机に倚(よる)事さえ叶(かな)わぬのであろうか。右脇には句集など取散らして原稿紙に何か書きかけていた様子である。いちばん目に止るのは足の方の鴨居(かもい)に笠と簑とを吊して笠には「西方十万億土順礼 西子」と書いてある。右側の障子の外が『ホトトギス』へ掲げた小園で奥行四間もあろうか萩の本(もと)を束ねたのが数株心のままに茂っているが花はまだついておらぬ。
まいかいは花が落ちてうてながまだ残ったままである。白粉花(おしろいばな)ばかりは咲き残っていたが鶏頭(けいとう)は障子にかくれて丁度見えなかった。熊本の近況から漱石師の噂になって昔話も出た。師は学生の頃は至って寡言(かげん)な温順な人で学校なども至って欠席が少なかったが子規は俳句分類に取りかかってから欠席ばかりしていたそうだ。
師と子規と親密になったのは知り合ってから四年もたって後であったが懇意になるとずいぶん子供らしく議論なんかして時々喧嘩(けんか)などもする。そう云う風であるから自然細君(さいくん)といさかう事もあるそうだ。それを予(あらか)じめ知っておらぬと細君も驚く事があるかも知れぬが根が気安過ぎるからの事である故驚く事はない。いったい誰れに対してもあたりの良い人の不平の漏らし所は家庭だなど云う。
室(へや)の庭に向いた方の鴨居に水彩画が一葉隣室に油画が一枚掛っている。皆不折が書いたので水彩の方は富士の六合目で磊々(らいらい)たる赭土塊(あかつちくれ)を踏んで向うへ行く人物もある。油画は御茶の水の写生、あまり名画とは見えぬようである。不折ほど熱心な画家はない。もう今日の洋画家中唯一の浅井忠(ちゅう)氏を除けばいずれも根性の卑劣な媚嫉(ぼうしつ)の強い女のような奴ばかりで、浅井氏が今度洋行するとなると誰れもその後任を引受ける人がない。ないではないが浅井の洋行が厭(いや)であるから邪魔をしようとするのである。
驚いたものだ。不折の如きも近来評判がよいので彼等の妬(ねたみ)を買い既に今度仏国博覧会へ出品する積(つも)りの作も審査官の黒田等が仕様もあろうに零点をつけて不合格にしてしまったそうだ。こう云う風であるから真面目に熱心に斯道(しどう)の研究をしようと云う考えはなく少しく名が出れば肖像でも画いて黄白(こうはく)を貪(むさぼ)ろうと云うさもしい奴ばかりで、中にたまたま不折のような熱心家はあるが貧乏であるから思うように研究が出来ぬ。そこらの車夫でもモデルに雇うとなると一日五十銭も取る。少し若い女などになるとどうしても一円は取られる。それでなかなか時間もかかるから研究と一口に云うても容易な事ではない。
景色画でもそうだ。先頃上州(じょうしゅう)へ写生に行って二十日ほど雨のふる日も休まずに画いて帰って来ると浅井氏がもう一週間行って直して来いと云われたからまた行って来てようよう出来上がったと云っていたそうだ。それでもとにかく熱心がひどいからあまり器用なたちでもなくまだ未熟ではあるが成効するだろうよ。
やはり『ホトトギス』の裏絵をかく為山(いざん)と云う男があるがこの男は不折とまるで反対な性で趣味も新奇な洋風のを好む。いったい手先は不折なんかとちがってよほど器用だがどうも不勉強であるから近来は少々不折に先を越されそうな。それがちと近来不平のようであるがそれかと云うてやはり不精だから仕方がない。
あのくらいの天才を抱きながら終ついに不折の熱心に勝を譲るかも知れぬなど話しているうち上野からの汽車が隣の植込の向うをごん/\と通った。隣の庭の折戸の上に烏からすが三羽下りてガー/\となく。夕日が畳の半分ほど這入って来た。
不折の一番得意で他に及ぶ者のないのは『日本』に連載するような意匠画でこれこそ他に類がない。配合の巧みな事材料の豊富なのには驚いてしまう。例えば犬百題など云う難題でも何処どこかから材料を引っぱり出して来て苦もなく拵(こしら)える。
いったい無学と云ってよい男であるからこれはきっと僕等がいろんな入智恵をするのだと思う人があるようだが中々そんな事ではない。僕等が夢にも知らぬような事が沢山あって一々説明を聞いてようやく合点(がてん)が行くくらいである。どうも奇態な男だ。先達(せんだ)って『日本』新聞に掲げた古瓦の画などは最も得意でまた実際真似(まね)は出来ぬ。あの瓦の形を近頃秀真(ほずま)と云う美術学校の人が鋳物(いもの)にして茶托(ちゃたく)にこしらえた。そいつが出来損なったのを僕が貰うてあるから見せようとて見せてくれた。十五枚の内ようよう五枚出来たそうで、それも穴だらけに出来て中に破れて繕つくろったのもあるが、それが却(かえ)って一段の趣味を増しているようだと云うたら子規も同意した。
巧みに古色が付けてあるからどうしても数百年前のものとしか見えぬ。中に蝸牛(かたつむり)を這わして「角つのふりわけよ」の句が刻してあるのなどはずいぶん面白い。絵とちがって鋳物だから蝸牛が大変よく利いているとか云うて不折もよほど気に入った様子だった。羽織を質入れしてもぜひ拵えさせると云うていたそうだと。話し半(なかば)へ老母が珈琲(コーヒー)を酌んで来る。子規には牛乳を持って来た。汽車がまた通って「※つくほうし」(漢字)の声を打消していった。
初対面からちと厚顔(あつかま)しいようではあったが自分は生来絵が好きで予(かね)てよい不折の絵が別けても好きであったから序(つい)でがあったら何でもよいから一枚呉(くれ)まいかと頼んで下さいと云ったら快く引受けてくれたのは嬉しかった。子規も小さい時分から絵画は非常に好きだが自分は一向かけないのが残念でたまらぬと喞(かこ)っていた。
夕日はますます傾いた。隣の屋敷で琴が聞える。音楽は好きかと聞くと勿論きらいではないが悲しいかな音楽の事は少しも知らぬ。どうか調べてみたいと思うけれどもこれからでは到底駄目であろう。尤(もっと)もこの頃人の話で大凡(おおよそ)こんなものかくらいは解ったようだが元来西洋の音楽などは遠くの昔バイオリンを聞いたばかりでピアノなんか一度も聞いた事はないからなおさら駄目だ。どうかしてあんなものが聞けるようにも一度なりたいと思うけれどもそれも駄目だと云うて暫く黙した。自分は何と云うてよいか判らなかった。
黯然(あんぜん)として吾(われ)も黙した。また汽車が来た。色々議論もあるようであるが日本の音楽も今のままでは到底見込みこみがないそうだ。国が箱庭的であるからか音楽まで箱庭的である。一度音楽学校の音楽室で琴の弾奏を聞いたが遠くで琴が聞えるくらいの事で物にならぬ。やはり天井の低い狭い室でなければ引合わぬと見える。それに調子が単純で弾ずる人に熱情がないからなおさらいかん。自分は素人考(しろうとかんがえ)で何でも楽器は指の先で弾くものだから女に適したものとばかり思うていたが中々そんな浅いものではない。日本人が西洋の楽器を取ってならす事はならすが音楽にならぬと云うのはつまり弾手ひきての情が単調で狂すると云う事がないからで、西洋の名手とまで行かぬ人でも楽がくの大切な面白い所へくると一切夢中になってしまうそうだ。こればかりは日本人の真似の出来ぬ事で致し方がない。ことに婦人は駄目だ、冷淡で熱情がないから。露伴(ろはん)の妹などは一時評判であったがやはり駄目だと云う事だ。
空が曇ったのか日が上野の山へかくれたか畳の夕日が消えてしまいつくつくほうしの声が沈んだようになった。烏はいつの間にか飛んで行っていた。また出ますと云うたら宿は何処(どこか)と聞いたから一両日中に谷中(やなか)の禅寺へ籠る事を話して暇(いとま)を告げて門へ出た。隣の琴の音が急になって胸をかき乱さるるような気がする。不知不識(しらずしらず)其方へと路次を這入(はいる)と道はいよいよ狭くなって井戸が道をさえぎっている。その傍で若い女が米を磨といでいる。流しの板のすべりそうなのを踏んで向側へ越すと柵があってその上は鉄道線路、その向うは山の裾である。其処を右へ曲るとよう/\広い街に出たから浅草の方へと足を運んだ。琴の音はやはりついて来る。道がまた狭くなってもとの前田邸の裏へ出た。ここから元来た道を交番所の前まであるいてここから曲らずに真直ぐに行くとまた踏切を越えねばならぬ。琴の音はもうついて来ぬ。森の中でつくつくほうしがゆるやかに鳴いて、日陰だから人が蝙蝠傘(こうもりがさ)を阿弥陀にさしてゆる/\あるく。山の上には人が沢山たくさん停車場から凌雲閣ゅりょううんかく)の方を眺めている。左側の柵の中で子供が四、五人石炭車に乗ったり押したりしている。機関車がすさまじい音をして小家の向うを出て来た。浅草へ行く積りであったがせっかく根岸で味おうた清閑の情を軽業(かるわざ)の太鼓御賽銭(おさいせん)の音に汚(けが)すが厭になったから山下まで来ると急いで鉄道馬車に飛乗って京橋まで窮屈な目にあって、向うに坐った金縁眼鏡き(んぶちめがね)隣に坐った禿頭の行商と欠伸(あくび)の掛け合いで帰って来たら大通りの時計台が六時を打った。 (明治三十二年九月) ≫
夏目漱石の「俳句と書画」(その八) [「子規と漱石」の世界]
その八 漱石の「第五高等学校」時代(その三「明治三十一年」)周辺
http://chikata.net/?p=2883
(再掲)
明治31年(1898年)
1月、子規へ句稿を送る(30句)
2月、子規『歌よみに与ふる書』を発表。
5月、子規へ句稿を送る(20句)
9月、子規へ句稿を送る(20句)
10月、子規へ句稿を送る(20句)
同月、熊本で漱石を主宰とした俳句結社「紫溟吟社」が興る。

(昭和9年の寅彦/『昭和文学全集3寺田寅彦集』から)「(熊本県立大学図書館オンライン展示))
https://soseki-kumamoto-anniversary.com/info/%e7%ac%ac%e4%ba%94%e9%ab%98%e7%ad%89%e5%ad%a6%e6%a0%a1%e3%81%ab%e5%85%a5%e5%ad%a6%e3%81%97%e3%81%9f%e5%af%85%e5%bd%a6/
≪ 第五高等学校に入学した寅彦は、「夏目漱石先生の追憶」(改造社『俳句講座 第八巻 地方結社編』昭和7年12月/昭和8年12月岩波書店発行『蒸発皿』に再録)に「学校ではオピアムイーターや、サイラス・マーナーを教はつた」と書いているように漱石の英語の授業を受け、明治31年(1898年)――「第二学年の学年試験の終つた頃」、「同県学生のうちで試験をしくじつた」「二三人の為に」「点を貰ひに」、「白川の河畔」の漱石の家を「初めて尋ね」たとき、俳句について話を聞き、以後、漱石の家に出入りして俳句の添削を受け、漱石が子規に送ってくれた寅彦の句が『ほとゝぎす』『国民新聞』や新聞『日本』等に掲載されるようになり、また、明治32年(1899年)7月に第五高等学校を卒業して9月に東京帝国大学理科大学入学することになった寅彦は、漱石の紹介で子規を訪ね、『ほとゝぎす』との縁がさらに深まった。
また、漱石が明治33年(1900年)9月に文部省の派遣でイギリス留学に出発したときには、在京の寅彦は、「先生が洋行するので横浜へ見送りに行つた。船はロイド社のプロイセン号であつた。(中略)「秋風の一人を吹くや海の上」といふ句を端書に書いて神戸からよこされた」(「夏目漱石先生の追憶」)と書いているように、横浜に見送りに行き、また漱石が2年間の留学を終えて明治36年(1903年)1月に帰朝したときにも、新橋停車場に出迎えに行っている。
帰朝後漱石は第五高等学校を辞職して第一高等学校・東京帝国大学の講師となり、明治40年(1900年)には教職を辞して東京朝日新聞社に入社して〝お抱え作家〟となったが、寅彦は、「帰朝当座の先生は矢来町の奥さんの実家中根氏邸に仮寓して居た。(中略)千駄木に居を定められてからは、又昔のやうに三日にあげず遊びに行つた」と書いているように、イギリスから帰ったばかりの漱石の仮寓を訪ね、その後、同年3月に転居した千駄木町の住まいを、日記に「夜夏目先生を千駄木町の新寓に訪ふ」(3月16日)、「午後夏目先生を訪ふ書斎にて種々の書籍を見せてもらふ」(同22日)、「夜夏目先生を訪ふ。宗教論。乱れ髪の歌の話」(同24日)とあるように、早速頻繁に訪れ、明治39年12月に転居した西片町の住まい、明治40年9月に転居した早稲田南町の漱石山房に出入りし、また漱石を誘って音楽会等にも出かけている。そのような二人の交流は大正5年(1916年)12月9日に漱石が亡くなるまで続いた。≫
(追記) 夏目漱石俳句集(その五)<制作年順> 明治31年(1327~1629)
https://sosekihaikushu.seesaa.net/article/200911article_16.html
明治31年(1898年)
1327 行く年や猫うづくまる膝の上(「子規へ送りたる句稿(二十八)三十句。一月)
(「夏目漱石デジタルコレクション」草稿)
https://www.kanabun.or.jp/souseki/list.html
1328 焚かんとす枯葉にまじる霰哉
1329 切口の白き芭蕉に氷りつく
1330 家を出て師走の雨に合羽哉
1331 何をつゝき鴉あつまる冬の畠
1332 降りやんで蜜柑まだらに雪の舟
1333 此炭の喞つべき世をいぶるかな
1334 かんてらや師走の宿に寐つかれず
1335 温泉の門に師走の熟柿かな
1336 温泉の山や蜜柑の山の南側
1337 海近し寐鴨をうちし筒の音
1338 天草の後ろに寒き入日かな
1339 日に映ずほうけし薄枯ながら
1340 旅にして申訳なく暮るゝ年
1341 凩の沖へとあるゝ筑紫潟
1342 うき除夜を壁に向へば影法師
1343 床の上に菊枯れながら明の春
1344 元日の山を後ろに清き温泉
1345 酒を呼んで酔はず明けたり今朝の春
1346 稍遅し山を背にして初日影
1347 駆け上る松の小山や初日の出
1348 甘からぬ屠蘇や旅なる酔心地
1349 温泉や水滑かに去年の垢
1350 此春を御慶もいはで雪多し
1351 正月の男といはれ拙に処す
1352 色々の雲の中より初日出
1353 初鴉東の方を新枕 (前書「賀虚子新婚 一句」)
≪季=初鴉(新)。※虚子宛書簡には「承はれば近頃御妻帯のよし何よりの吉報に接し候心地千秋万歳の寿をなさんがため一句呈上致候」とある。虚子は前年の六月に結婚した。 (後略)≫(『漱石全集第十七巻・坪内稔典注解』)
1354 僧帰る竹の裡こそ寒からめ
1355 桐かれて洩れ来る月の影多し
1356 一尺の梅を座右に置く机 (1327~「同上」)
1357 梅ちつてそゞろなつかしむ新俳句(「虚子」宛書簡)
≪季=梅(春)。※虚子から「新俳句」(明治三一・三)を送ってもらった令状に記した句。礼状で漱石は「小生爾来俳境日々退歩昨今は現に一句も無之候此分にてはやがて鳴雪老人の跡釜を引き受ける事ならんと少々寒心の体に有此候」と述べた。(後略) ≫(『漱石全集第十七巻・坪内稔典注解』)
1358 春雨の隣の琴は六段か(「子規へ送りたる句稿(二十九)二十句。五月)
1359 瓢かけてからからと鳴る春の風
1360 鳥籠を柳にかけて狭き庭
1361 来よといふに来らずやみし桜かな
1362 三条の上で逢ひけり朧月
1363 片寄する琴に落ちけり朧月
1364 こぬ殿に月朧也高き楼
1365 行き行きて朧に笙を吹く別れ
1366 搦手やはね橋下す朧月
1367 有耶無耶の柳近頃緑也
1368 颯と打つ夜網の音や春の川
1369 永き日を太鼓打つ手のゆるむ也
1370 湧くからに流るゝからに春の水
1371 禰宜の子の烏帽子つけたり藤の花
1372 春の夜のしば笛を吹く書生哉
1373 海を見て十歩に足らぬ畑を打つ
1374 花一木穴賢しと見上たる
1375 仏かく宅磨が家や梅の花
1376 鶴を切る板は五尺の春の椽
1377 思ひ切つて五分に刈りたる袷かな (1358~「同上」)
1378 となりから月曇らする蚊やり哉 (「九州新聞」)
1379 松風の絶へ間を蝉のしぐれかな (「同上」)
1380 小き馬車に積み込まれけり稲の花(「子規へ送りたる句稿(三十)二十句。九月)
1381 夕暮の秋海棠に蝶うとし
1382 離れては寄りては菊の蝶一つ
1383 枚をふくむ三百人や秋の霜
1384 胡児驕つて驚きやすし雁の声
1385 砧うつ真夜中頃に句を得たり
1386 踊りけり拍子をとりて月ながら
1387 茶布巾の黄はさめ易き秋となる
1388 長かれと夜すがら語る二人かな
1389 子は雀身は蛤のうきわかれ
1390 相撲取の屈託顔や午の雨
1391 ものいはぬ案山子に鳥の近寄らず
1392 病む頃を雁来紅に雨多し
1393 寺借りて二十日になりぬ鶏頭花
1394 恩給に事を欠かでや種瓢
1395 早稲晩稲花なら見せう萩紫苑
1396 生垣の丈かり揃へ晴るゝ秋
1397 秋寒し此頃あるゝ海の色
1398 夜相撲やかんてらの灯をふきつける
1399 菅公に梅さかざれば蘭の花 (1380~「同上」)
1400 朝顏や手拭懸に這ひ上る (「承露盤」)
1401 能もなき渋柿どもや門の内 (「承露盤」)
1402 立枯の唐黍鳴つて物憂かり(「子規へ送りたる句稿(三十一)二十句。十月)
1403 逢ふ恋の打たでやみけり小夜砧
1404 蝶来りしほらしき名の江戸菊に
1405 塩焼や鮎に渋びたる好みあり
1406 一株の芒動くや鉢の中
1407 乾鮭のからついてゐる柱かな
1408 病妻の閨に灯ともし暮るゝ秋
1409 かしこまりて憐れや秋の膝頭
1410 かしこみて易を読む儒の夜を長み
1411 長き夜や土瓶をしたむ台所
1412 張まぜの屏風になくや蟋蟀
1413 うそ寒み油ぎつたる枕紙
1414 病むからに行燈の華の夜を長み
1415 秋の暮野狐精来り見えて曰く
1416 白封に訃音と書いて漸寒し
1417 落ち合ひて新酒に名乗る医者易者
1418 憂あり新酒の酔に託すべく
1419 苫もりて夢こそ覚むれ荻の声
1420 秋の日のつれなく見えし別かな
1421 行く秋の関廟の香炉烟なし (1402~「同上」)
1422 朝寒の楊子使ふや流し元 (「反省雑誌」)
1423 駕舁の京へと急ぐ女郎花(「同上」)
1424 柳散り柳散りつゝ細る恋(「同上」
1425 病癒えず蹲る夜の野分かな(「同上」
1426 つるんだる蜻蛉飛ぶなり水の上(「同上」
1427 菊作る奴がわざの接木かな (「承露盤」)
1428 ゆゝしくも合羽に包むつぎ木かな (「承露盤」)
1429 風呂に入れば裏の山より初嵐 (『寺田寅彦全集』中の句)
(参考)「子規庵句会図(河東碧悟桐賛・下山為山画、明治三十・三十一年頃)周辺

≪「子規庵句会写生図」画・下村為山 賛・河東碧梧桐 」(昭和10年(1935)、子規庵寄託資料、紙本淡彩、48.0×52.3㎝)
https://www.culture.city.taito.lg.jp/bunkatanbou/topics/famous_persons/shiki/japanese/page_04.html
明治30、31年(1897-1898)頃の子規庵新年句会での盛会の様子を描いたこの図は、昭和10年に「中央美術協会」が、俳句革新記念として限定30部作成しました。掛軸として頒布されたその1幅が平成25年(2013)子規庵に寄贈されました。すべて肉筆のため、画も賛も少しずつ異なる箇所があります。子規を初めとして石井露月、佐藤肋骨、河東碧梧桐、坂本四方太、内藤鳴雪、佐藤紅緑、高浜虚子、大谷繞石、吉野左衛門、五百木飄亭、梅沢墨水、数藤五城、赤木格堂、諫早李坪、下村為山、折井愚哉、寒川鼠骨、福田把栗、山田三子、谷活東、岩田鳴球、松下紫人等(子規から左回り)が参加しています。≫
≪「碧悟桐賛」全文
明治三十年頃より子規居士/の傘下に集る同人一党日に/月に新人を迎へ例月根岸子規/庵の句会の意気常に沖天/の概を占めせり/
牛伴画伯(注・「為山」の俳号)の此写生図ハ恐らく/明治三十一・二年頃の新年/発会の光景なるべく鳴雪の/披講各自採点の状四十/年を隔てて当時を目賭せし/む画中の人既に故人となれる者/子規居士と共に十名曰く/
内藤鳴雪 坂本四芳太 / 石井露月 墨水 / 数藤五城 大谷繞石 / 吉野左衛門 諫早李坪 / 新井愚哉/
而して今日尚ほ健在なる者も/多く白頭霜鬢既に老境に入る/当時を追想して多少の感慨なめしとせんや / 碧悟桐識 ≫(『俳人の書画美術7 子規(集英社刊)』所収「図版解説125(和田茂樹)」)
http://chikata.net/?p=2883
(再掲)
明治31年(1898年)
1月、子規へ句稿を送る(30句)
2月、子規『歌よみに与ふる書』を発表。
5月、子規へ句稿を送る(20句)
9月、子規へ句稿を送る(20句)
10月、子規へ句稿を送る(20句)
同月、熊本で漱石を主宰とした俳句結社「紫溟吟社」が興る。

(昭和9年の寅彦/『昭和文学全集3寺田寅彦集』から)「(熊本県立大学図書館オンライン展示))
https://soseki-kumamoto-anniversary.com/info/%e7%ac%ac%e4%ba%94%e9%ab%98%e7%ad%89%e5%ad%a6%e6%a0%a1%e3%81%ab%e5%85%a5%e5%ad%a6%e3%81%97%e3%81%9f%e5%af%85%e5%bd%a6/
≪ 第五高等学校に入学した寅彦は、「夏目漱石先生の追憶」(改造社『俳句講座 第八巻 地方結社編』昭和7年12月/昭和8年12月岩波書店発行『蒸発皿』に再録)に「学校ではオピアムイーターや、サイラス・マーナーを教はつた」と書いているように漱石の英語の授業を受け、明治31年(1898年)――「第二学年の学年試験の終つた頃」、「同県学生のうちで試験をしくじつた」「二三人の為に」「点を貰ひに」、「白川の河畔」の漱石の家を「初めて尋ね」たとき、俳句について話を聞き、以後、漱石の家に出入りして俳句の添削を受け、漱石が子規に送ってくれた寅彦の句が『ほとゝぎす』『国民新聞』や新聞『日本』等に掲載されるようになり、また、明治32年(1899年)7月に第五高等学校を卒業して9月に東京帝国大学理科大学入学することになった寅彦は、漱石の紹介で子規を訪ね、『ほとゝぎす』との縁がさらに深まった。
また、漱石が明治33年(1900年)9月に文部省の派遣でイギリス留学に出発したときには、在京の寅彦は、「先生が洋行するので横浜へ見送りに行つた。船はロイド社のプロイセン号であつた。(中略)「秋風の一人を吹くや海の上」といふ句を端書に書いて神戸からよこされた」(「夏目漱石先生の追憶」)と書いているように、横浜に見送りに行き、また漱石が2年間の留学を終えて明治36年(1903年)1月に帰朝したときにも、新橋停車場に出迎えに行っている。
帰朝後漱石は第五高等学校を辞職して第一高等学校・東京帝国大学の講師となり、明治40年(1900年)には教職を辞して東京朝日新聞社に入社して〝お抱え作家〟となったが、寅彦は、「帰朝当座の先生は矢来町の奥さんの実家中根氏邸に仮寓して居た。(中略)千駄木に居を定められてからは、又昔のやうに三日にあげず遊びに行つた」と書いているように、イギリスから帰ったばかりの漱石の仮寓を訪ね、その後、同年3月に転居した千駄木町の住まいを、日記に「夜夏目先生を千駄木町の新寓に訪ふ」(3月16日)、「午後夏目先生を訪ふ書斎にて種々の書籍を見せてもらふ」(同22日)、「夜夏目先生を訪ふ。宗教論。乱れ髪の歌の話」(同24日)とあるように、早速頻繁に訪れ、明治39年12月に転居した西片町の住まい、明治40年9月に転居した早稲田南町の漱石山房に出入りし、また漱石を誘って音楽会等にも出かけている。そのような二人の交流は大正5年(1916年)12月9日に漱石が亡くなるまで続いた。≫
(追記) 夏目漱石俳句集(その五)<制作年順> 明治31年(1327~1629)
https://sosekihaikushu.seesaa.net/article/200911article_16.html
明治31年(1898年)
1327 行く年や猫うづくまる膝の上(「子規へ送りたる句稿(二十八)三十句。一月)
(「夏目漱石デジタルコレクション」草稿)
https://www.kanabun.or.jp/souseki/list.html
1328 焚かんとす枯葉にまじる霰哉
1329 切口の白き芭蕉に氷りつく
1330 家を出て師走の雨に合羽哉
1331 何をつゝき鴉あつまる冬の畠
1332 降りやんで蜜柑まだらに雪の舟
1333 此炭の喞つべき世をいぶるかな
1334 かんてらや師走の宿に寐つかれず
1335 温泉の門に師走の熟柿かな
1336 温泉の山や蜜柑の山の南側
1337 海近し寐鴨をうちし筒の音
1338 天草の後ろに寒き入日かな
1339 日に映ずほうけし薄枯ながら
1340 旅にして申訳なく暮るゝ年
1341 凩の沖へとあるゝ筑紫潟
1342 うき除夜を壁に向へば影法師
1343 床の上に菊枯れながら明の春
1344 元日の山を後ろに清き温泉
1345 酒を呼んで酔はず明けたり今朝の春
1346 稍遅し山を背にして初日影
1347 駆け上る松の小山や初日の出
1348 甘からぬ屠蘇や旅なる酔心地
1349 温泉や水滑かに去年の垢
1350 此春を御慶もいはで雪多し
1351 正月の男といはれ拙に処す
1352 色々の雲の中より初日出
1353 初鴉東の方を新枕 (前書「賀虚子新婚 一句」)
≪季=初鴉(新)。※虚子宛書簡には「承はれば近頃御妻帯のよし何よりの吉報に接し候心地千秋万歳の寿をなさんがため一句呈上致候」とある。虚子は前年の六月に結婚した。 (後略)≫(『漱石全集第十七巻・坪内稔典注解』)
1354 僧帰る竹の裡こそ寒からめ
1355 桐かれて洩れ来る月の影多し
1356 一尺の梅を座右に置く机 (1327~「同上」)
1357 梅ちつてそゞろなつかしむ新俳句(「虚子」宛書簡)
≪季=梅(春)。※虚子から「新俳句」(明治三一・三)を送ってもらった令状に記した句。礼状で漱石は「小生爾来俳境日々退歩昨今は現に一句も無之候此分にてはやがて鳴雪老人の跡釜を引き受ける事ならんと少々寒心の体に有此候」と述べた。(後略) ≫(『漱石全集第十七巻・坪内稔典注解』)
1358 春雨の隣の琴は六段か(「子規へ送りたる句稿(二十九)二十句。五月)
1359 瓢かけてからからと鳴る春の風
1360 鳥籠を柳にかけて狭き庭
1361 来よといふに来らずやみし桜かな
1362 三条の上で逢ひけり朧月
1363 片寄する琴に落ちけり朧月
1364 こぬ殿に月朧也高き楼
1365 行き行きて朧に笙を吹く別れ
1366 搦手やはね橋下す朧月
1367 有耶無耶の柳近頃緑也
1368 颯と打つ夜網の音や春の川
1369 永き日を太鼓打つ手のゆるむ也
1370 湧くからに流るゝからに春の水
1371 禰宜の子の烏帽子つけたり藤の花
1372 春の夜のしば笛を吹く書生哉
1373 海を見て十歩に足らぬ畑を打つ
1374 花一木穴賢しと見上たる
1375 仏かく宅磨が家や梅の花
1376 鶴を切る板は五尺の春の椽
1377 思ひ切つて五分に刈りたる袷かな (1358~「同上」)
1378 となりから月曇らする蚊やり哉 (「九州新聞」)
1379 松風の絶へ間を蝉のしぐれかな (「同上」)
1380 小き馬車に積み込まれけり稲の花(「子規へ送りたる句稿(三十)二十句。九月)
1381 夕暮の秋海棠に蝶うとし
1382 離れては寄りては菊の蝶一つ
1383 枚をふくむ三百人や秋の霜
1384 胡児驕つて驚きやすし雁の声
1385 砧うつ真夜中頃に句を得たり
1386 踊りけり拍子をとりて月ながら
1387 茶布巾の黄はさめ易き秋となる
1388 長かれと夜すがら語る二人かな
1389 子は雀身は蛤のうきわかれ
1390 相撲取の屈託顔や午の雨
1391 ものいはぬ案山子に鳥の近寄らず
1392 病む頃を雁来紅に雨多し
1393 寺借りて二十日になりぬ鶏頭花
1394 恩給に事を欠かでや種瓢
1395 早稲晩稲花なら見せう萩紫苑
1396 生垣の丈かり揃へ晴るゝ秋
1397 秋寒し此頃あるゝ海の色
1398 夜相撲やかんてらの灯をふきつける
1399 菅公に梅さかざれば蘭の花 (1380~「同上」)
1400 朝顏や手拭懸に這ひ上る (「承露盤」)
1401 能もなき渋柿どもや門の内 (「承露盤」)
1402 立枯の唐黍鳴つて物憂かり(「子規へ送りたる句稿(三十一)二十句。十月)
1403 逢ふ恋の打たでやみけり小夜砧
1404 蝶来りしほらしき名の江戸菊に
1405 塩焼や鮎に渋びたる好みあり
1406 一株の芒動くや鉢の中
1407 乾鮭のからついてゐる柱かな
1408 病妻の閨に灯ともし暮るゝ秋
1409 かしこまりて憐れや秋の膝頭
1410 かしこみて易を読む儒の夜を長み
1411 長き夜や土瓶をしたむ台所
1412 張まぜの屏風になくや蟋蟀
1413 うそ寒み油ぎつたる枕紙
1414 病むからに行燈の華の夜を長み
1415 秋の暮野狐精来り見えて曰く
1416 白封に訃音と書いて漸寒し
1417 落ち合ひて新酒に名乗る医者易者
1418 憂あり新酒の酔に託すべく
1419 苫もりて夢こそ覚むれ荻の声
1420 秋の日のつれなく見えし別かな
1421 行く秋の関廟の香炉烟なし (1402~「同上」)
1422 朝寒の楊子使ふや流し元 (「反省雑誌」)
1423 駕舁の京へと急ぐ女郎花(「同上」)
1424 柳散り柳散りつゝ細る恋(「同上」
1425 病癒えず蹲る夜の野分かな(「同上」
1426 つるんだる蜻蛉飛ぶなり水の上(「同上」
1427 菊作る奴がわざの接木かな (「承露盤」)
1428 ゆゝしくも合羽に包むつぎ木かな (「承露盤」)
1429 風呂に入れば裏の山より初嵐 (『寺田寅彦全集』中の句)
(参考)「子規庵句会図(河東碧悟桐賛・下山為山画、明治三十・三十一年頃)周辺

≪「子規庵句会写生図」画・下村為山 賛・河東碧梧桐 」(昭和10年(1935)、子規庵寄託資料、紙本淡彩、48.0×52.3㎝)
https://www.culture.city.taito.lg.jp/bunkatanbou/topics/famous_persons/shiki/japanese/page_04.html
明治30、31年(1897-1898)頃の子規庵新年句会での盛会の様子を描いたこの図は、昭和10年に「中央美術協会」が、俳句革新記念として限定30部作成しました。掛軸として頒布されたその1幅が平成25年(2013)子規庵に寄贈されました。すべて肉筆のため、画も賛も少しずつ異なる箇所があります。子規を初めとして石井露月、佐藤肋骨、河東碧梧桐、坂本四方太、内藤鳴雪、佐藤紅緑、高浜虚子、大谷繞石、吉野左衛門、五百木飄亭、梅沢墨水、数藤五城、赤木格堂、諫早李坪、下村為山、折井愚哉、寒川鼠骨、福田把栗、山田三子、谷活東、岩田鳴球、松下紫人等(子規から左回り)が参加しています。≫
≪「碧悟桐賛」全文
明治三十年頃より子規居士/の傘下に集る同人一党日に/月に新人を迎へ例月根岸子規/庵の句会の意気常に沖天/の概を占めせり/
牛伴画伯(注・「為山」の俳号)の此写生図ハ恐らく/明治三十一・二年頃の新年/発会の光景なるべく鳴雪の/披講各自採点の状四十/年を隔てて当時を目賭せし/む画中の人既に故人となれる者/子規居士と共に十名曰く/
内藤鳴雪 坂本四芳太 / 石井露月 墨水 / 数藤五城 大谷繞石 / 吉野左衛門 諫早李坪 / 新井愚哉/
而して今日尚ほ健在なる者も/多く白頭霜鬢既に老境に入る/当時を追想して多少の感慨なめしとせんや / 碧悟桐識 ≫(『俳人の書画美術7 子規(集英社刊)』所収「図版解説125(和田茂樹)」)



