「鹿下絵新古今和歌巻」逍遥(その十九) [光悦・宗達・素庵]
その十九 式子内親王
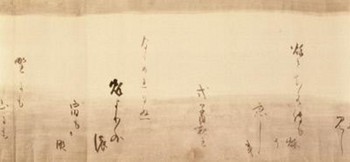
「鹿下絵新古今集和歌巻断簡(慈円その二・式子内親王その一)」(シアトル美術館蔵)

「鹿下絵新古今集和歌巻断簡(式子内親王その二)」(シアトル美術館蔵)

「鹿下絵新古今和歌巻(全体図の十「式子内親王その二・円融院その一」(『書道芸術第十八巻本阿弥光悦(中田勇次郎責任編集)』)
19 式子内親王:ながめわびぬ秋より外の宿もがな野にも山にも月やすむらむ
(釈文)な可め王日怒秋よ利外濃宿も可那野尓も山尓も月や須むら無
(「式子内親王」周辺メモ)
https://www.asahi-net.or.jp/~sg2h-ymst/yamatouta/sennin/syokusi.html#AT
百首歌たてまつりし時、月の歌
ながめわびぬ秋よりほかの宿もがな野にも山にも月やすむらん(新古380)
【通釈】つくづく眺め疲れてしまった。季節が秋でない宿はないものか。野にも山にも月は澄んでいて、どこへも遁れようはないのだろうか。
【語釈】◇ながめわびぬ 「ながむ」はじっとひとところを見たまま物思いに耽ること。「わぶ」は動詞に付いて「~するのに耐えられなくなる」「~する気力を失う」といった意味になる。◇月やすむらん 月は澄んでいるのだろうか。秋は月の光がことさら明澄になるとされた。「すむ」は「住む」と掛詞になり、「宿」の縁語。
式子内親王 久安五~建仁一(1149~1201)
後白河天皇の皇女。母は藤原季成のむすめ成子(しげこ)。亮子内親王(殷富門院)は同母姉、守覚法親王・以仁王は同母弟。高倉天皇は異母兄。生涯独身を通した。
平治元年(1159)、賀茂斎院に卜定され、賀茂神社に奉仕。嘉応元年(1169)、病のため退下(『兵範記』断簡によれば、この時二十一歳)。治承元年(1177)、母が死去。同四年には弟の以仁王が平氏打倒の兵を挙げて敗死した。元暦二年(1185)、准三后の宣下を受ける。建久元年(1190)頃、出家。法名は承如法。同三年(1192)、父後白河院崩御。この後、橘兼仲の妻の妖言事件に捲き込まれ、一時は洛外追放を受けるが、その後処分は沙汰やみになった。
建久七年(1196)、失脚した九条兼実より明け渡された大炊殿に移る。正治二年(1200)、春宮守成親王(のちの順徳天皇)を猶子に迎える話が持ち上がったが、この頃すでに病に冒されており、翌年正月二十五日、薨去した。五十三歳。
藤原俊成を和歌の師とし、俊成の歌論書『古来風躰抄』は内親王に捧げられたものという。その息子定家とも親しく、養和元年(1181)以後、たびたび御所に出入りさせている。正治二年(1200)の後鳥羽院主催初度百首の作者となったが、それ以外に歌会・歌合などの歌壇的活動は見られない。他撰の家集『式子内親王集』があり、三種の百首歌を伝える(日本古典文学大系八〇・私家集大成三・新編国歌大観四・和歌文学大系二三・私家集全釈叢書二八などに所収)。千載集初出。勅撰入集百五十七首
「鹿下絵新古今集和歌巻」逍遥ノート(その十七)
式子内親王 については、下記のアドレスなどでしばしば触れてきた。
狩野探幽筆「新三十六歌仙画帖」(その一)後鳥羽院と式子内親王
https://yahan.blog.ss-blog.jp/2019-11-23
狩野永納筆「新三十六人歌合画帖」その一 後鳥羽院と式子内親王
https://yahan.blog.ss-blog.jp/2020-01-09
「鹿下絵新古今和歌巻」逍遥(その七) 式子内親王
https://yahan.blog.ss-blog.jp/2020-05-14
ここで、前回の「慈円の年譜」(『岩波新書308源頼朝(永原慶二著)などを参考))に、上記の「周辺メモ」の「式子内親王」に関する事項を付記すると次のとおりである(以下の※印)。
この二人は、式子内親王が六歳程度年長であるが、同時代を生き、式子内親王は賀茂の斎院、慈円は天台座主と俗世と離れた環境を余儀なくされたということで、共通項を同じくする。
そして、何よりも、歌人として、後鳥羽院が実質的に編んだ『新古今和歌集』の入集数で、慈円は、西行(九十四首)に次いでの第二位(九十二首)、そして、式子内親王は、「西行(九十四首)→慈円(九十二首)→良経(九十二首)→俊成(七十二首)」に次いで第五位(四十九首)で、この二人が、当時の後鳥羽院歌壇の両翼ということになる。
因みに、その式子内親王に次いで、「定家(四十六首)→家隆(四十六首)→寂蓮(三十五首)→後鳥羽院(三十四首)→俊成女(二十九首)」で、『新古今和歌集』のベストテンの十人の歌人というのは、「西行→慈円→良経→俊成→式子内親王→定家→家隆→寂蓮→後鳥羽院→俊成女」ということになる。
(「慈円と式子内親王」関連年譜」)
久安五年(1149)※式子内親王誕生。後白河天皇の第三皇女。
久寿二年(1155)慈円誕生。摂政関白藤原忠通の子。兼実・兼房らの弟。良経らの叔父。
保元元年(1156)保元の乱(「崇徳上皇・藤原頼長」対「後白河天皇・藤原忠通」の争い)
平治元年(1159)平治の乱(「後白河院政派・源義朝」対「二条親政派・平清盛」の争い)
※ 式子内親王、内親王宣下を受け斎院に卜定、賀茂神社に奉仕。
永万元年 (1165) 慈円、覚快法親王(鳥羽天皇の皇子)に入門、道快を名のる。十歳。
仁安二年(1167)平清盛 太政大臣就任。武家政権成立。
嘉応元年 (1169) ※式子内親王、病のため斎院を退下。
治承四年(1180)源頼朝挙兵。※以仁王(式子内親王同母弟)敗死(平家追討)。
文治元年(1185)壇ノ浦合戦、平氏滅亡。慈円、三十歳。
建久三年(1192)頼朝、征夷大将軍。慈円、天台座主に就任する。三十七歳。
建久七年 (1196) 建久七年の政変(兼実の失脚。慈円天台座主などの職位を辞す。)
建仁元年 (1201) 慈円は再び天台座主に補せられる(後鳥羽院院政)。※式子内親王薨去。
元久二年(1205)『新古今和歌集』成る。慈円、五十歳(「和歌所」寄人)。
建暦二年(1212)鴨長明『方丈記』成る。慈円、三たび天台座主に就く。五十七歳。
承久二年(1220)慈円『愚管抄』成る。六十五歳。
承久三年(1221)承久の乱。後鳥羽上皇ら配流。六十六歳。
嘉禄元年 (1225) 慈円入寂。七十歳。
『小倉百人一首』(藤原定家撰)と『新々百人一首』(丸谷才一撰)の二首(式子内親王)
玉の緒よ絶えなば絶えねながらへば 忍ぶることのよわりもぞする(『小倉百人一首89』 『新古今集』恋一・1034)
https://www.asahi-net.or.jp/~sg2h-ymst/yamatouta/sennin/syokusi.html#LV
https://yahan.blog.ss-blog.jp/2020-05-14
百首歌の中に、忍恋を(三首)
玉の緒よ絶えなば絶えねながらへば忍ぶることのよわりもぞする(新古1034)
【通釈】私の玉の緒よ、切れてしまうなら切れてしまえ。もし持続すれば、堪え忍ぶ力が弱ってしまうのだ。
【語釈】◇玉の緒 魂と身体を結び付けていると考えられた緒。命そのものを指して言うこともある。◇絶えなば絶えね 絶えてしまうなら絶えてしまえ。「な」「ね」は、完了の助動詞「ぬ」のそれぞれ未然形・命令形。
【補記】『式子内親王集』には補遺の部(「雖入勅撰不見家集歌」)に載せ、元来式子の家集には無かった作。制作年、制作事情などは不詳である。
【他出】定家十体(有心様)、定家八代抄、別本八代集秀逸(家隆撰)、自讃歌、百人一首、新三十六人撰、歌林良材
【参考歌】作者未詳「万葉集」
息の緒に思へば苦し玉の緒の絶えて乱れな知らば知るとも
(『古今和歌六帖』には第四句「絶えて乱るな」として載る)
曾禰好忠『好忠集』
乱れつつ絶えなば悲し冬の夜をわがひとりぬる玉の緒よわみ
わが恋は知る人もなしせく床の泪もらすなつげの小枕(『新々百人一首72』『新古今集』恋一・1036)
https://www.asahi-net.or.jp/~sg2h-ymst/yamatouta/sennin/syokusi.html#LV
わが恋はしる人もなしせく床の涙もらすなつげのを枕(新古1036)
【通釈】私の恋心は知る人とてない。堰き止めている床の涙を洩らすな、黄楊(つげ)の枕よ。
【語釈】◇つげのを枕 黄楊で作った木枕。枕は人の心を知るものとされたが、黄楊の木で作ったものはことに霊力が強いとされたらしい。万葉集巻十一に「夕されば床の辺去らぬ黄楊枕なにしか汝が主待ちかたき」と、やはり黄楊の枕に対し呼びかけた歌がある。なお、「つげ」を「告げ」の掛詞と見れば、その名を忌んでいることになろう。
【他出】正治初度百首、定家八代抄、六華集
【本歌】平貞文「古今集」
枕よりまた知る人もなき恋を涙せきあへずもらしつるかな
式子内親王の『新古今和歌集』入集歌など
https://www.asahi-net.or.jp/~sg2h-ymst/yamatouta/sennin/syokusi.html
百首歌たてまつりし時、はるの歌
山ふかみ春ともしらぬ松の戸にたえだえかかる雪の玉水(新古3)
【通釈】山が深いので春が来たとも知らない我が庵の松の戸――その戸に、途絶えがちに滴りかかる雪の雫よ。
【語釈】◇松の戸 松の木で作った板戸、または松の枝を編んだ枝折戸。いずれにしても山家の粗末な戸である。「松」には「待つ」が掛かる。◇たえだえかかる 間隔を置いて掛かる。どこから落ちてくるとも言っていないが、それゆえにかえって「雪の玉水」のイメージは鮮烈である。◇雪の玉水 雪が融けてできた雫。掲出歌以前の用例は見えず、おそらく式子内親王創意の語であろう。
【補記】正治二年(1200)、すなわち内親王薨去前年、後鳥羽院に詠進した百首歌「正治初度百首歌」。
百首歌たてまつりしに、春歌
ながめつるけふは昔になりぬとも軒端の梅はわれを忘るな(新古52)
【通釈】眺め入った今日は過去になるとしても、軒端の梅は私を忘れずにいておくれ。
百首歌たてまつりしに
いま桜さきぬと見えてうすぐもり春にかすめる世のけしきかな(新古83)
【通釈】まさに今桜が咲いたと見えて、空はうっすらと曇り、春らしく霞んでいる世のありさまであるよ。
百首歌に
はかなくてすぎにし方をかぞふれば花に物おもふ春ぞへにける(新古101)
【通釈】とりとめもなく過ぎてしまった年月を数えれば、桜の花を眺めながら物思いに耽る春ばかりを送ってしまった。
家の八重桜を折らせて、惟明親王のもとにつかはしける
やへにほふ軒ばの桜うつろひぬ風よりさきにとふ人もがな(新古137)
【通釈】幾重にも美しく咲き匂っていた軒端の八重桜は、盛りの時を過ぎてしまった。風より先に訪れてくれる人がいてほしい。
【語釈】◇家の八重桜 この「家」は、式子内親王が晩年住んだ大炊御門(おおいみかど)の邸。
【補記】惟明親王は高倉天皇の皇子で式子の甥にあたる。親王の返歌は「つらきかなうつろふまでに八重桜とへともいはですぐる心は」。因みに続後撰集には同じく大炊殿の八重桜を巡って式子内親王と九条良経とが贈答した歌を載せる(「ふるさとの春を忘れぬ八重桜これや見し世にかはらざるらむ」「八重桜をりしる人のなかりせば見し世の春にいかで逢はまし」)。
花は散りてその色となくながむればむなしき空に春雨ぞふる〔新古149〕
【通釈】花は散り果てて、これというあてもなく眺めていると、空虚な空にただ春雨が降っている。
斎院に侍りける時、神館(かんだち)にて
忘れめや葵を草に引きむすびかりねの野べの露のあけぼの(新古182)
【通釈】忘れなどしようか。葵の葉を草枕として引き結び、旅寝した野辺の一夜が明けて、露の置いたあの曙の景色を。
百首歌たてまつりし時、夏歌
かへりこぬ昔を今と思ひ寝の夢の枕ににほふ橘(新古240)
【通釈】再び戻って来ない昔を、今のことのように思いながら寝入ると、うつらうつら夢見る枕もとに匂ってくる、橘の花の香よ。
百首歌たてまつりしに
声はして雲路にむせぶほととぎす涙やそそく宵のむら雨(新古215)
【通釈】声は聞こえるものの姿は見えず、雲の中でむせぶように泣く時鳥よ。その涙がそそぐのか、今宵の驟雨は。
百首歌の中に
夕立の雲もとまらぬ夏の日のかたぶく山にひぐらしの声(新古268)
【通釈】夕立を降らせた雲ももう留まっていないこの山――暑かった夏の日が傾いたこの山で、いま蜩の声が響く。
百首の歌たてまつりし時
窓ちかき竹の葉すさぶ風の音にいとどみじかきうたたねの夢(新古256)
【通釈】窓近くの竹の葉に吹きすさぶ風の音のために、ますます短く醒めてしまった転た寝の夢よ。
百首歌に
うたたねの朝けの袖にかはるなりならす扇の秋の初風(新古308)
【通釈】転た寝した明け方の袖に、変わったと感じる。なれ親しんだ扇の風が、今年最初の秋風に――。
百首歌の中に
ながむれば衣手すずしひさかたの天の河原の秋の夕暮(新古321)
【通釈】じっと眺めていると、自分の袖も涼しく感じられる。川風が吹く、天の川の川原の秋の夕暮よ。
それながら昔にもあらぬ月影にいとどながめをしづのをだまき〔新古367〕
【通釈】それはそれ、月は同じ月であるのに、やはり昔とは異なる月影――その光に、いよいよ物思いに耽って眺め入ってしまった、繰り返し飽きもせず。
百首歌たてまつりし時、月の歌
ながめわびぬ秋よりほかの宿もがな野にも山にも月やすむらん(新古380)
【通釈】つくづく眺め疲れてしまった。季節が秋でない宿はないものか。野にも山にも月は澄んでいて、どこへも遁れようはないのだろうか。
題しらず
更くるまで眺むればこそ悲しけれ思ひも入れじ秋の夜の月(新古417)
【通釈】夜が更けるまで眺めていたからこそ悲しいのだ。もう深く心にかけることはすまい、秋の夜の月よ。
百首歌たてまつりし秋歌に
秋の色は籬にうとくなりゆけど手枕なるる閨の月かげ(新古432)
【通釈】色々に咲いていた垣根の草花はうつろい、秋の趣は疎くなってゆくけれど、反対に、私の手枕に馴れてくる閨の月光よ。
百首歌の中に
跡もなき庭の浅茅にむすぼほれ露の底なる松虫のこゑ(新古474)
【通釈】人の通った跡もなく生い茂る庭の浅茅――その草葉にぎっしりと絡みつかれ、露の底から聞こえてくる、人を待つような松虫の声よ。
擣衣の心を
千たび擣(う)つきぬたの音に夢さめて物おもふ袖の露ぞくだくる(新古484)
【通釈】果てしなく擣つ砧の音に夢から醒めて、悲しい物思いに耽る私の涙が落ち、袖に砕け散る。
百首歌たてまつりし時
更けにけり山の端ちかく月さえて十市(とをち)の里に衣うつこゑ(新古485)
【通釈】夜は更けてしまった。山の稜線近くにある月の光は冴え冴えとして、十市の里に衣を打つ音が聞こえる。
百首歌たてまつりし秋歌
桐の葉もふみわけがたくなりにけり必ず人を待つとなけれど(新古534)
【通釈】桐の落葉も踏み分け難いほど積もってしまったなあ。必ずしも人を待つというわけではないけれど。
題しらず
風さむみ木の葉はれゆく夜な夜なにのこるくまなき庭の月かげ(新古605)
【通釈】風が寒々と吹き、そのたびに木の葉が散ってゆく夜々を経て、もはや残る隈(くま)無く照らす庭の月光よ。
百首歌の中に
見るままに冬は来にけり鴨のゐる入江のみぎはうす氷りつつ(新古638)
【通釈】見ている間に、もう冬は来ていたのだなあ。鴨の浮かんでいる入江の波打際が薄く氷りながら。
百首歌に
さむしろの夜半の衣手さえさえて初雪しろし岡の辺の松(新古662)
【通釈】寝床の上の夜の袖が冷え冷えとしていたが、今朝見れば初雪が白く積もっているよ、岡のほとりの松は。
百首歌たてまつりしに
日かずふる雪げにまさる炭竈の煙もさびし大原の里(新古690)
【通釈】何日も続く雪模様で炭竈の煙が多くなるのも寂しげである。大原の里よ。
(「賀歌・哀傷歌・離別歌・羇旅歌・雑歌・神祇歌・釈教歌」→省略 )
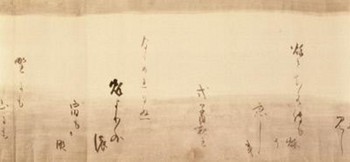
「鹿下絵新古今集和歌巻断簡(慈円その二・式子内親王その一)」(シアトル美術館蔵)

「鹿下絵新古今集和歌巻断簡(式子内親王その二)」(シアトル美術館蔵)
「鹿下絵新古今和歌巻(全体図の十「式子内親王その二・円融院その一」(『書道芸術第十八巻本阿弥光悦(中田勇次郎責任編集)』)
19 式子内親王:ながめわびぬ秋より外の宿もがな野にも山にも月やすむらむ
(釈文)な可め王日怒秋よ利外濃宿も可那野尓も山尓も月や須むら無
(「式子内親王」周辺メモ)
https://www.asahi-net.or.jp/~sg2h-ymst/yamatouta/sennin/syokusi.html#AT
百首歌たてまつりし時、月の歌
ながめわびぬ秋よりほかの宿もがな野にも山にも月やすむらん(新古380)
【通釈】つくづく眺め疲れてしまった。季節が秋でない宿はないものか。野にも山にも月は澄んでいて、どこへも遁れようはないのだろうか。
【語釈】◇ながめわびぬ 「ながむ」はじっとひとところを見たまま物思いに耽ること。「わぶ」は動詞に付いて「~するのに耐えられなくなる」「~する気力を失う」といった意味になる。◇月やすむらん 月は澄んでいるのだろうか。秋は月の光がことさら明澄になるとされた。「すむ」は「住む」と掛詞になり、「宿」の縁語。
式子内親王 久安五~建仁一(1149~1201)
後白河天皇の皇女。母は藤原季成のむすめ成子(しげこ)。亮子内親王(殷富門院)は同母姉、守覚法親王・以仁王は同母弟。高倉天皇は異母兄。生涯独身を通した。
平治元年(1159)、賀茂斎院に卜定され、賀茂神社に奉仕。嘉応元年(1169)、病のため退下(『兵範記』断簡によれば、この時二十一歳)。治承元年(1177)、母が死去。同四年には弟の以仁王が平氏打倒の兵を挙げて敗死した。元暦二年(1185)、准三后の宣下を受ける。建久元年(1190)頃、出家。法名は承如法。同三年(1192)、父後白河院崩御。この後、橘兼仲の妻の妖言事件に捲き込まれ、一時は洛外追放を受けるが、その後処分は沙汰やみになった。
建久七年(1196)、失脚した九条兼実より明け渡された大炊殿に移る。正治二年(1200)、春宮守成親王(のちの順徳天皇)を猶子に迎える話が持ち上がったが、この頃すでに病に冒されており、翌年正月二十五日、薨去した。五十三歳。
藤原俊成を和歌の師とし、俊成の歌論書『古来風躰抄』は内親王に捧げられたものという。その息子定家とも親しく、養和元年(1181)以後、たびたび御所に出入りさせている。正治二年(1200)の後鳥羽院主催初度百首の作者となったが、それ以外に歌会・歌合などの歌壇的活動は見られない。他撰の家集『式子内親王集』があり、三種の百首歌を伝える(日本古典文学大系八〇・私家集大成三・新編国歌大観四・和歌文学大系二三・私家集全釈叢書二八などに所収)。千載集初出。勅撰入集百五十七首
「鹿下絵新古今集和歌巻」逍遥ノート(その十七)
式子内親王 については、下記のアドレスなどでしばしば触れてきた。
狩野探幽筆「新三十六歌仙画帖」(その一)後鳥羽院と式子内親王
https://yahan.blog.ss-blog.jp/2019-11-23
狩野永納筆「新三十六人歌合画帖」その一 後鳥羽院と式子内親王
https://yahan.blog.ss-blog.jp/2020-01-09
「鹿下絵新古今和歌巻」逍遥(その七) 式子内親王
https://yahan.blog.ss-blog.jp/2020-05-14
ここで、前回の「慈円の年譜」(『岩波新書308源頼朝(永原慶二著)などを参考))に、上記の「周辺メモ」の「式子内親王」に関する事項を付記すると次のとおりである(以下の※印)。
この二人は、式子内親王が六歳程度年長であるが、同時代を生き、式子内親王は賀茂の斎院、慈円は天台座主と俗世と離れた環境を余儀なくされたということで、共通項を同じくする。
そして、何よりも、歌人として、後鳥羽院が実質的に編んだ『新古今和歌集』の入集数で、慈円は、西行(九十四首)に次いでの第二位(九十二首)、そして、式子内親王は、「西行(九十四首)→慈円(九十二首)→良経(九十二首)→俊成(七十二首)」に次いで第五位(四十九首)で、この二人が、当時の後鳥羽院歌壇の両翼ということになる。
因みに、その式子内親王に次いで、「定家(四十六首)→家隆(四十六首)→寂蓮(三十五首)→後鳥羽院(三十四首)→俊成女(二十九首)」で、『新古今和歌集』のベストテンの十人の歌人というのは、「西行→慈円→良経→俊成→式子内親王→定家→家隆→寂蓮→後鳥羽院→俊成女」ということになる。
(「慈円と式子内親王」関連年譜」)
久安五年(1149)※式子内親王誕生。後白河天皇の第三皇女。
久寿二年(1155)慈円誕生。摂政関白藤原忠通の子。兼実・兼房らの弟。良経らの叔父。
保元元年(1156)保元の乱(「崇徳上皇・藤原頼長」対「後白河天皇・藤原忠通」の争い)
平治元年(1159)平治の乱(「後白河院政派・源義朝」対「二条親政派・平清盛」の争い)
※ 式子内親王、内親王宣下を受け斎院に卜定、賀茂神社に奉仕。
永万元年 (1165) 慈円、覚快法親王(鳥羽天皇の皇子)に入門、道快を名のる。十歳。
仁安二年(1167)平清盛 太政大臣就任。武家政権成立。
嘉応元年 (1169) ※式子内親王、病のため斎院を退下。
治承四年(1180)源頼朝挙兵。※以仁王(式子内親王同母弟)敗死(平家追討)。
文治元年(1185)壇ノ浦合戦、平氏滅亡。慈円、三十歳。
建久三年(1192)頼朝、征夷大将軍。慈円、天台座主に就任する。三十七歳。
建久七年 (1196) 建久七年の政変(兼実の失脚。慈円天台座主などの職位を辞す。)
建仁元年 (1201) 慈円は再び天台座主に補せられる(後鳥羽院院政)。※式子内親王薨去。
元久二年(1205)『新古今和歌集』成る。慈円、五十歳(「和歌所」寄人)。
建暦二年(1212)鴨長明『方丈記』成る。慈円、三たび天台座主に就く。五十七歳。
承久二年(1220)慈円『愚管抄』成る。六十五歳。
承久三年(1221)承久の乱。後鳥羽上皇ら配流。六十六歳。
嘉禄元年 (1225) 慈円入寂。七十歳。
『小倉百人一首』(藤原定家撰)と『新々百人一首』(丸谷才一撰)の二首(式子内親王)
玉の緒よ絶えなば絶えねながらへば 忍ぶることのよわりもぞする(『小倉百人一首89』 『新古今集』恋一・1034)
https://www.asahi-net.or.jp/~sg2h-ymst/yamatouta/sennin/syokusi.html#LV
https://yahan.blog.ss-blog.jp/2020-05-14
百首歌の中に、忍恋を(三首)
玉の緒よ絶えなば絶えねながらへば忍ぶることのよわりもぞする(新古1034)
【通釈】私の玉の緒よ、切れてしまうなら切れてしまえ。もし持続すれば、堪え忍ぶ力が弱ってしまうのだ。
【語釈】◇玉の緒 魂と身体を結び付けていると考えられた緒。命そのものを指して言うこともある。◇絶えなば絶えね 絶えてしまうなら絶えてしまえ。「な」「ね」は、完了の助動詞「ぬ」のそれぞれ未然形・命令形。
【補記】『式子内親王集』には補遺の部(「雖入勅撰不見家集歌」)に載せ、元来式子の家集には無かった作。制作年、制作事情などは不詳である。
【他出】定家十体(有心様)、定家八代抄、別本八代集秀逸(家隆撰)、自讃歌、百人一首、新三十六人撰、歌林良材
【参考歌】作者未詳「万葉集」
息の緒に思へば苦し玉の緒の絶えて乱れな知らば知るとも
(『古今和歌六帖』には第四句「絶えて乱るな」として載る)
曾禰好忠『好忠集』
乱れつつ絶えなば悲し冬の夜をわがひとりぬる玉の緒よわみ
わが恋は知る人もなしせく床の泪もらすなつげの小枕(『新々百人一首72』『新古今集』恋一・1036)
https://www.asahi-net.or.jp/~sg2h-ymst/yamatouta/sennin/syokusi.html#LV
わが恋はしる人もなしせく床の涙もらすなつげのを枕(新古1036)
【通釈】私の恋心は知る人とてない。堰き止めている床の涙を洩らすな、黄楊(つげ)の枕よ。
【語釈】◇つげのを枕 黄楊で作った木枕。枕は人の心を知るものとされたが、黄楊の木で作ったものはことに霊力が強いとされたらしい。万葉集巻十一に「夕されば床の辺去らぬ黄楊枕なにしか汝が主待ちかたき」と、やはり黄楊の枕に対し呼びかけた歌がある。なお、「つげ」を「告げ」の掛詞と見れば、その名を忌んでいることになろう。
【他出】正治初度百首、定家八代抄、六華集
【本歌】平貞文「古今集」
枕よりまた知る人もなき恋を涙せきあへずもらしつるかな
式子内親王の『新古今和歌集』入集歌など
https://www.asahi-net.or.jp/~sg2h-ymst/yamatouta/sennin/syokusi.html
百首歌たてまつりし時、はるの歌
山ふかみ春ともしらぬ松の戸にたえだえかかる雪の玉水(新古3)
【通釈】山が深いので春が来たとも知らない我が庵の松の戸――その戸に、途絶えがちに滴りかかる雪の雫よ。
【語釈】◇松の戸 松の木で作った板戸、または松の枝を編んだ枝折戸。いずれにしても山家の粗末な戸である。「松」には「待つ」が掛かる。◇たえだえかかる 間隔を置いて掛かる。どこから落ちてくるとも言っていないが、それゆえにかえって「雪の玉水」のイメージは鮮烈である。◇雪の玉水 雪が融けてできた雫。掲出歌以前の用例は見えず、おそらく式子内親王創意の語であろう。
【補記】正治二年(1200)、すなわち内親王薨去前年、後鳥羽院に詠進した百首歌「正治初度百首歌」。
百首歌たてまつりしに、春歌
ながめつるけふは昔になりぬとも軒端の梅はわれを忘るな(新古52)
【通釈】眺め入った今日は過去になるとしても、軒端の梅は私を忘れずにいておくれ。
百首歌たてまつりしに
いま桜さきぬと見えてうすぐもり春にかすめる世のけしきかな(新古83)
【通釈】まさに今桜が咲いたと見えて、空はうっすらと曇り、春らしく霞んでいる世のありさまであるよ。
百首歌に
はかなくてすぎにし方をかぞふれば花に物おもふ春ぞへにける(新古101)
【通釈】とりとめもなく過ぎてしまった年月を数えれば、桜の花を眺めながら物思いに耽る春ばかりを送ってしまった。
家の八重桜を折らせて、惟明親王のもとにつかはしける
やへにほふ軒ばの桜うつろひぬ風よりさきにとふ人もがな(新古137)
【通釈】幾重にも美しく咲き匂っていた軒端の八重桜は、盛りの時を過ぎてしまった。風より先に訪れてくれる人がいてほしい。
【語釈】◇家の八重桜 この「家」は、式子内親王が晩年住んだ大炊御門(おおいみかど)の邸。
【補記】惟明親王は高倉天皇の皇子で式子の甥にあたる。親王の返歌は「つらきかなうつろふまでに八重桜とへともいはですぐる心は」。因みに続後撰集には同じく大炊殿の八重桜を巡って式子内親王と九条良経とが贈答した歌を載せる(「ふるさとの春を忘れぬ八重桜これや見し世にかはらざるらむ」「八重桜をりしる人のなかりせば見し世の春にいかで逢はまし」)。
花は散りてその色となくながむればむなしき空に春雨ぞふる〔新古149〕
【通釈】花は散り果てて、これというあてもなく眺めていると、空虚な空にただ春雨が降っている。
斎院に侍りける時、神館(かんだち)にて
忘れめや葵を草に引きむすびかりねの野べの露のあけぼの(新古182)
【通釈】忘れなどしようか。葵の葉を草枕として引き結び、旅寝した野辺の一夜が明けて、露の置いたあの曙の景色を。
百首歌たてまつりし時、夏歌
かへりこぬ昔を今と思ひ寝の夢の枕ににほふ橘(新古240)
【通釈】再び戻って来ない昔を、今のことのように思いながら寝入ると、うつらうつら夢見る枕もとに匂ってくる、橘の花の香よ。
百首歌たてまつりしに
声はして雲路にむせぶほととぎす涙やそそく宵のむら雨(新古215)
【通釈】声は聞こえるものの姿は見えず、雲の中でむせぶように泣く時鳥よ。その涙がそそぐのか、今宵の驟雨は。
百首歌の中に
夕立の雲もとまらぬ夏の日のかたぶく山にひぐらしの声(新古268)
【通釈】夕立を降らせた雲ももう留まっていないこの山――暑かった夏の日が傾いたこの山で、いま蜩の声が響く。
百首の歌たてまつりし時
窓ちかき竹の葉すさぶ風の音にいとどみじかきうたたねの夢(新古256)
【通釈】窓近くの竹の葉に吹きすさぶ風の音のために、ますます短く醒めてしまった転た寝の夢よ。
百首歌に
うたたねの朝けの袖にかはるなりならす扇の秋の初風(新古308)
【通釈】転た寝した明け方の袖に、変わったと感じる。なれ親しんだ扇の風が、今年最初の秋風に――。
百首歌の中に
ながむれば衣手すずしひさかたの天の河原の秋の夕暮(新古321)
【通釈】じっと眺めていると、自分の袖も涼しく感じられる。川風が吹く、天の川の川原の秋の夕暮よ。
それながら昔にもあらぬ月影にいとどながめをしづのをだまき〔新古367〕
【通釈】それはそれ、月は同じ月であるのに、やはり昔とは異なる月影――その光に、いよいよ物思いに耽って眺め入ってしまった、繰り返し飽きもせず。
百首歌たてまつりし時、月の歌
ながめわびぬ秋よりほかの宿もがな野にも山にも月やすむらん(新古380)
【通釈】つくづく眺め疲れてしまった。季節が秋でない宿はないものか。野にも山にも月は澄んでいて、どこへも遁れようはないのだろうか。
題しらず
更くるまで眺むればこそ悲しけれ思ひも入れじ秋の夜の月(新古417)
【通釈】夜が更けるまで眺めていたからこそ悲しいのだ。もう深く心にかけることはすまい、秋の夜の月よ。
百首歌たてまつりし秋歌に
秋の色は籬にうとくなりゆけど手枕なるる閨の月かげ(新古432)
【通釈】色々に咲いていた垣根の草花はうつろい、秋の趣は疎くなってゆくけれど、反対に、私の手枕に馴れてくる閨の月光よ。
百首歌の中に
跡もなき庭の浅茅にむすぼほれ露の底なる松虫のこゑ(新古474)
【通釈】人の通った跡もなく生い茂る庭の浅茅――その草葉にぎっしりと絡みつかれ、露の底から聞こえてくる、人を待つような松虫の声よ。
擣衣の心を
千たび擣(う)つきぬたの音に夢さめて物おもふ袖の露ぞくだくる(新古484)
【通釈】果てしなく擣つ砧の音に夢から醒めて、悲しい物思いに耽る私の涙が落ち、袖に砕け散る。
百首歌たてまつりし時
更けにけり山の端ちかく月さえて十市(とをち)の里に衣うつこゑ(新古485)
【通釈】夜は更けてしまった。山の稜線近くにある月の光は冴え冴えとして、十市の里に衣を打つ音が聞こえる。
百首歌たてまつりし秋歌
桐の葉もふみわけがたくなりにけり必ず人を待つとなけれど(新古534)
【通釈】桐の落葉も踏み分け難いほど積もってしまったなあ。必ずしも人を待つというわけではないけれど。
題しらず
風さむみ木の葉はれゆく夜な夜なにのこるくまなき庭の月かげ(新古605)
【通釈】風が寒々と吹き、そのたびに木の葉が散ってゆく夜々を経て、もはや残る隈(くま)無く照らす庭の月光よ。
百首歌の中に
見るままに冬は来にけり鴨のゐる入江のみぎはうす氷りつつ(新古638)
【通釈】見ている間に、もう冬は来ていたのだなあ。鴨の浮かんでいる入江の波打際が薄く氷りながら。
百首歌に
さむしろの夜半の衣手さえさえて初雪しろし岡の辺の松(新古662)
【通釈】寝床の上の夜の袖が冷え冷えとしていたが、今朝見れば初雪が白く積もっているよ、岡のほとりの松は。
百首歌たてまつりしに
日かずふる雪げにまさる炭竈の煙もさびし大原の里(新古690)
【通釈】何日も続く雪模様で炭竈の煙が多くなるのも寂しげである。大原の里よ。
(「賀歌・哀傷歌・離別歌・羇旅歌・雑歌・神祇歌・釈教歌」→省略 )



