東洋城の「俳誌・渋柿」(管見)その三 [東洋城・豊隆・青楓]
その三「俳誌・渋柿(417号/昭和24・1)・「漱石三十三回忌」など」
E3808DE8A1A8E7B499.jpg)
「俳誌・渋柿(417号/昭和24・1)」表紙
https://dl.ndl.go.jp/pid/6071548/1/1
E3808DE79BAEE6ACA1.jpg)
「俳誌・渋柿(417号/昭和24・1)」目次
https://dl.ndl.go.jp/pid/6071548/1/2
E3808DE5A5A5E4BB98.jpg)
俳誌・渋柿(417号/昭和24・1)」所収「漱石先生三十三回忌(東洋城)」・「奥付など」
https://dl.ndl.go.jp/pid/6071548/1/10
(目次)
[卷頭語 / 秋谷立石山人/p表一
中野から / 小宮蓬里野人/p表二
漱石忌/p1~1
漱石雜詠/p1~1
落木林森(15)夕ぐれ / 東洋城/p2~3
卷頭句 / 東洋城/p4~11
句作問答/p4~8
句作問答(第二部) 九月號、十月號、十一月號/p8~11
お年玉--「空谷無人」に付 / 東洋城/p12~13
下山轉住 / 城/p13~13
例會 松山十一月/p13~13
用語解 / 綠蔭/p13~13
題詠/p14~15
蓑虫 / 十四王/p14~14
冬隣 / 晨悟/p15~15
噫格堂 / 城/p15~15
漱石先生三十三回忌 / 東洋城/p16~16
曲謠 檜垣(上) / 東洋城/p表四
奧付/p表紙の三 ](「国立国会図書館デジタルコレクション」)
東洋城年譜)(『東洋城全句集(中巻)』所収)
昭和十九年(1944) 六十七歳
空襲激しくなり浅間山麓に籠山し、昭和二十四年に至る。『続山を喰ふ』『不衣の句を講ず』を連載。紙の配給減り十六頁の「渋柿」となる。
昭和二十年(1945) 六十八歳
宇和島の邸宅土蔵戦火に会ひ、始祖伝来の家宝を失ふ。信州より焦土の都往復、「渋柿」の刊行続く。『楽木林森』『八月十四日以降』連載。能成文部大臣に親任。
昭和二十一年(1946) 六十九歳
敗亡の後の困難と闘ひ、熱情と至誠を傾注して「渋柿」の毎月発行を指揮す。村上霽月没。
昭和二十二年(1947) 七十歳
「渋柿」四百号に達す。露伴没。
昭和二十三年(1948) 七十一歳
古稀を迎ふ。「古稀遺言」連載。伊予を遍歴。
昭和二十四年(1949) 七十二歳
浅間山麓より帰京。「山籠解脱記」「流浪記」連載。伊予を遍歴指導。伊予小野小学校に、句碑建つ。十二月、森田草平没。
(管見)
一、 「中野から / 小宮蓬里野人/p表二」の末尾に、「六十でも、七十でも、いい事を始めるのに遅いといふ事はない。今日の三十三回忌を機として、ひとつ大にやる事にしようぢやないか。(昭和二三・一二・九)」と記されている。
ちなみに、小宮豊隆は、『漱石二十三回忌』(昭和17年)に、『漱石全集(決定版)』の「小宮豊隆『解説』」一巻に収めた『漱石の芸術(著者/小宮豊隆 著/出版者 岩波書店/出版年月日 昭和17)を刊行している。
https://dl.ndl.go.jp/pid/1078598/1/3
[「漱石の芸術」
目次
『吾輩は猫である』/1
短篇上/26
短篇下/71
『虞美人草』/113
『坑夫』/130
『三四郎』/143
『それから』/161
『門』/178
『彼岸過迄』/195
『行人』/216
『心』/250
『道草』/267
『明暗』/284
小品/323
『文學論』/354
『文學評論』/384
「評論・雜篇」/408
「詩歌俳句及初期の文章」/441
「日記及斷片」/477
「書簡集」/507
「續書簡集」/544
「別冊」/574
談話筆記 本の書き入れ ](「国立国会図書館デジタルコレクション」)
二、「漱石忌/p1~1」「漱石雜詠/p1~1」中の「東洋城」の句は、次のとおりである。
「漱石忌/p1~1」中の「東洋城」の句は、次の二句である。
五(※いつ)とせや山住(※やまずみ)下りて漱石忌 (東洋城)
大(※おお)いなる冬大(※だい)なる詩(※し)や漱石忌 (同)
三、「落木林森(15)夕ぐれ / 東洋城/p2~3」「卷頭句 / 東洋城/p4~11」「句作問答/p4~8」「句作問答(第二部) 九月號、十月號、十一月號/p8~11」「お年玉--「空谷無人」に付 / 東洋城/p12~13」「下山轉住 / 城/p13~13」「例會 松山十一月/p13~13」「用語解 / 綠蔭/p13~13」のこれらは、全て、「東洋城(俳文)」「東洋城選句(選句)」「東洋城(句作問答)」「東洋城(関連句会・近況報告)」ということになる。
四、「下山轉住 / 城/p13~13」には、「下山準備の数十日、昼夜兼行。(中略) 七十老齢這箇患累顧みてよく身命を次ぐと思ふ。(後略)
餅を搗く隣や都第一夜 」と、浅間山麓より帰京しての、その第一夜の感慨を記している。
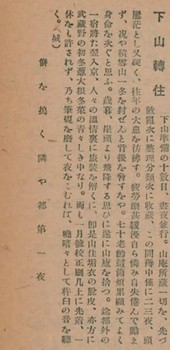
https://dl.ndl.go.jp/pid/6071548/1/8
五、「題詠/p14~15」「蓑虫 / 十四王/p14~14」「冬隣 / 晨悟/p15~15」は、「題詠(秋の空)/水莖春雨選、題詠(蓑虫)/西岡十四王選、題詠(冬隣/小林晨悟選)で、「渋柿」の主要同人が関与しているのは、この「雑詠(題詠)」のページ数にして二頁に満たないということになる。即ち、俳誌「渋柿」というのは、主宰者・松根東洋城が「隅から隅まで」手入れしている個人俳誌という印象すら拭えないというのが、素直な見方であろう。
六 「漱石忌/p1~1」「漱石雜詠/p1~1」そして「漱石先生三十三回忌 / 東洋城/p16~16」も、東洋城の選句、そして、東洋城の「漱石先生三十三回忌」の記述ということになろう。この「漱石先生三十三回忌」の、当日の出席者の名は「鏡子夫人」以外は記述されていない。
(追記その一) 『漱石と十弟子(津田青楓著)』周辺
https://yahan.blog.ss-blog.jp/2024-01-11
(再掲)
E4B880.jpg)
『漱石と十弟子(津田青楓著)』(右上から)「世界文庫・昭和24年版」/「朋文堂新社・昭和42年版」/(右下から)「芸艸堂・昭和49年版」/「芸艸堂(新装版)平成27年版)」
https://twitter.com/unsodo_hanga/status/1355015832892399617/photo/4
『漱石と十弟子(津田青楓著)』は、昭和二十四年(一九四九)一月に世界文庫より出版した。これは、津田青楓は、その前年(昭和二十三)十二月九日の「漱石三十三回忌」については触れていないが、「漱石三十三回忌」に因んでの出版と解しても差し支えなかろう。
この著書の、「漱石十弟子」は、年齢順にすると、次のとおりとなる。
松根東洋城(明治十一=一八七八・二月)・寺田寅彦(明治十一=一八七八・十一月)
森田草平(明治十四年=一八八一・三月)・岩波茂雄(明治十四年=一八八一・八月)
鈴木三重吉(明治十五年=一八八二)
阿部次郎(明治十六年=一八八三・八月)・野上臼川(明治十六年=一八八三・九月)・安倍能成(明治十六年=一八八三・十二月)
小宮豊隆(明治十七年=一八八四)
赤木桁平(明治二十四年=一八九一)
これに、この『漱石と十弟子(津田青楓著)』の折り込みの口絵写真(「漱石山房図/漱石と十弟子(津田青楓画)」には、受付のような人物(百鬼園=内田百閒)が描かれている。この受付のような人物(百鬼園=内田百閒)が、(筆者亀吉=津田青楓)というものもある。

「漱石と十弟子(津田青楓画)」昭和51(1976)年/紙本著色/A4判用(縦30.9cm×横22.0cm×厚さ0.04cm)→B図(「漱石山房記念館蔵」)
https://soseki-museum.jp/user-guide/museum-shop/
これらについては、下記のアドレスなどで先に紹介している。
https://yahan.blog.ss-blog.jp/2023-12-24
ここで、この(百鬼園=内田百閒)と(筆者亀吉=津田青楓)との二人も付け加えて置こう。
津田青楓(明治十三年=一八八〇)
内田百閒(明治二十二年=一八八九)
上記の「漱石十弟子(漱石十二弟子)」のうち、昭和二十三年(一九四八)十二月九日の「漱石三十三回忌」の年以前の物故者は、次のとおりとなる。
寺田寅彦(明治十一=一八七八・十一月~昭和十年=一九三五)
鈴木三重吉(明治十五年=一八八二~昭和十一年=一九三六)
岩波茂雄(明治十四年=一八八一・八月~昭和二十一年=一九四六)
赤木桁平(明治二十四年=一八九一~昭和二十四年=一九四九・十二月十日)

「岩波茂雄と赤木桁平(津田青楓「スケッチ画」)」(『漱石と十弟子(津田青楓著)』)
(再掲)
https://yahan.blog.ss-blog.jp/2024-01-11
[ 岩波氏(※岩波茂雄)の顔も、桁平氏(※赤木桁平)の顔も画家から言ふと捨てがたい珍品なのだ。岩波ときたら禅月大師十六羅漢像の、なかからぬけ出した一人の羅漢像のやうで、画中の白眉なんだ。線の太い大形な羅漢のとなりに、これは又貧弱な色の青白い、当時大学を出たてのほやほやの法学士、赤木桁平君は、そのころのインテリゲンチャの風采を代表してゐるかに見える。
それが隅っこの方で岩波が本を見てゐると桁平君が首をのばして、その本をのぞき込んでゐる。その顔の対照が面白いからこの二人はやめられないのだ。岩波はそのころ女学校の先生をやめて、神田にケチくさい古本屋の店を出してゐた。それが漱石のものを手はじめに出版をぽちぽちやり出し、仲間の学者連のものをちらほら出してゐるうちに、変り種の本屋として老舗となり、こつちの知らぬまに多額納税者とやら貴族院議員とやらになつてゐた。趣味のない男だから岩波本が世間に出るやうになつてから、本の装幀はカチカチになつてしまつた。
桁平は、近江秋江や徳田秋声や田山花袋なぞの自然主義文学が癪だといつて、「遊蕩文学撲滅論」を書いて、文壇をさはがせた。支那戦争が段々英米戦争に発展せんとする段階に突入するころから、どこで学んだのか一ぱしの海軍通になり、「日本の海軍は無敵だよ、イギリスとアメリカほむかうにまはしたつて毅然たるものだよ。」そんな元気で遂に「アメリカ恐るるに足らず」といふ一書を発表して軍国主義のおさき棒を勤めた。終戦後国会議員の責任が追及された時、真先きに辞任してひつ込んでしまつたのは賢明であつた。](『漱石と十弟子(津田青楓著)』)
※ 岩波茂雄の最期は、「1945年(昭和20年)3月27日:貴族院議員。/ 1946年2月11日:文化勲章を受章。/1946年4月25日:逝去。」(「ウィキペディア)と、出版界の雄として栄光の裡に没した。
それに対して、赤木桁平のそれは、「1945年(昭和20年)12月2日、連合国軍最高司令官総司令部は日本政府に対し赤木を逮捕するよう命令(第三次逮捕者59名中の1人)、A級戦犯の容疑で巣鴨拘置所に勾留される。同年12月6日に衆議院議員を辞職。後に病気のため釈放されるも、公職追放となり、そのまま不遇のうちに死去。」(「ウィキペディア」)と、岩波茂雄と好対照の不遇の裡に没している。
そして、その没した日が、「漱石三十三回忌」(「1949年(昭和24年)2月9日」)の翌日(2月10日」)というのは、赤木桁平(池崎忠孝)の最期のメッセージのようにも思われてくる。
(追記その二) 小宮豊隆の「東京音楽学校長就任・辞職」周辺
[昭和二十一年(一九四六) 六十二歳
東京音楽学校長を引き受ける。これは岩波茂雄の奔走によるものである。(以下略)
昭和二十四年(一九四九) 六十五歳
(前略) 六月 東京音楽学校長辞職。 ](『蓬里雨句集』所収「小宮豊隆年譜」)
[第二次世界大戦後の1946年、新校長小宮豊隆の主導で職員の大量罷免を伴う学内改革が行われた。その結果、高折宮次(ピアノ科主任)、遠藤宏(音楽史科主任)、木下保(声楽科主任)、橋本國彦(作曲科主任)、井上武雄(ヴァイオリン科主任)、平井保三(チェロ科主任)、井口基成(ピアノ科)、宇佐美ため(ピアノ科)、平井保喜(作曲科)、永田晴(管科)、細川碧(作曲科)、中村ハマ(ピアノ科)の11名の教授が罷免され、その独裁的なやりかたに抗議する校長不信任運動に加わった豊増昇、永井進の2名のピアノ科教授が退職した。
1949年5月31日、学制改革により新制東京芸術大学が発足すると、東京音楽学校はこれに包括されて音楽学部の前身となり、1952年3月に廃止された。本流の予科・甲種師範科が募集70人と超少数精鋭であったが、全入の選科も東京藝術大学音楽学部に統合したため、音楽学部の募集は172名(1951年以降)となった。なお東京美術学校には選科生はほとんど居なかったため、東京美術学校の予科・師範科の募集人数と東京藝術大学美術学部の募集人数はあまり変化しなかった。
1946年の募集人数 甲種師範科30名、本科40名(予科と統合)。本科内訳 声楽科8名、器楽科(ピアノ・オルガン8名、バイオリン・チェロ・ダブルベース6名、管楽器・打楽器5名)作曲科2名、邦楽科(能楽2名、箏曲4名、長唄4名) ](「ウィキペディア」)
[2.2 東京音楽学校校長の邦楽科廃止論
小宮は,1948 年 5 月 6 日と 7 日の『時事新報』において,東京芸術大学においては,邦楽科を置く代わりに,邦楽研究所を設ける計画であることを公表した。新しい大学では技術と理論が互いに支えあう教育が行われるべきであり,理論的研究や歴史的研究が遅れている邦楽を後進養成のためだけに大学で教育すべきではないというのが彼の考え方だった。そして,研究所の使命は,邦楽の中で真に民族的なものを明らかにし,将来に生かすべきものとそうでないものを明らかにすることであるとし,その研究のために,純粋な邦楽を純粋に保存する必要があるとした。その考え方の基礎には,邦楽は,洋楽に比べて,現在の日本人の心の一部しか動かすことのできない「過去の芸術」,「無縁の芸術」であるという見方があった(小宮 1948)。
さらに,この問題を取り上げた 6 月 29 日の『読売新聞』には,「邦楽は日本の封建時代に育てられ,完成した日本芸術であるから世界の芸術の仲間入りをするためには必ず洋楽の過程を経なければならぬというのが私の信念だ【中略】邦楽をやりたいものは学部を卒業してから研究所に入ればよい」という小宮の談話が掲載された(吉川 2002: 203)。
小宮は,新しい時代の日本音楽は,洋楽を基礎として生み出されるべきであり,邦楽はそこでは役割を果たしえないと考えていたようだ。小宮は,ちょうど邦楽科廃止論争に決着がついた 1949 年に初版が出版された『明治文化史』第 9 巻「音楽演芸」の第一章「明治の音楽・演芸」を執筆している。その中で,「和楽」について,「明治維新の変動からはたいした影響を受けることがなく」,「いわば『文明開化』の世界のものとは,全然趣の違った世界を表現しているのに過ぎない」(小宮 1980: 51)としている。
小宮が理想としたのは,日清・日露戦争を経て「名義上だけでも世界の一等国の仲間入りをし」た「新しい日本にふさわしい」「気宇の雄大な音楽」だった(小宮1980: 54)。東京音楽学校の前身である音楽取調掛は,1879 年,伊沢修二を掛長として発足し,「東西二洋ノ音楽ヲ折衷シテ新曲ヲ作ル事」を方針の 1 つとした。しかし,小宮は「日本の在来の音楽の方面」では,「そういうことが一向顕著でない」と断じ,それは「在来の日本の音楽に携わる人達が,ことごとく個人主義者であり,保守主義者であり,自分の籠っている硬い殻の中から首を出して,世間を眺めようとする意欲を奮い立たせることがなかったせいだったのではなかったか」(小宮 1980: 54–55)と国立民族学博物館研究報告 28巻 2 号268記している。さらに,西洋音楽についての節では,この「和洋折衷」の方針は「虻
蜂とらずのものになり易」く,「音楽取調掛が東京音楽学校となり,東京音楽学校があらゆる方面の外人教師を招聘し,次第に洋楽専門の音楽教育に発展して行ったことは,当然のことだった」(小宮 1980: 61)としている。
『明治文化史』中の文章は,明治時代の音楽について書かれたものだが,小宮は,基本的に邦楽科廃止論争当時の邦楽にも同様の見解をもっていた。東京芸術大学が発足する 1949 年 6 月を目前にして,小宮は 4 月 8 日と 5 月 11 日に衆議院文部委員会に呼び出されている。会議録に記された 5 月 11 日のやりとり(衆議院文部委員会1949)の中で,小宮は,邦楽を「大学の教育の本筋の中からは取除き」「別科としてこれを置きたい」と述べている。
別科とは「一般的な教養は十分ではないけれども技術がすばらしくできるというふうな人の技術を伸ばさせるために」置かれたもので,「今のところ邦楽は技術だけなの」で別科で十分としていた。彼は,研究が進んだ段階で正科に入れるかどうか考えるべきだとも述べているが,本気でそのようにするつもりはなかったようである。「邦楽を認めないとか,あるいは邦楽を低級だというふうに考えてない」とは述べているが,「これから先の音楽は洋楽が本流になるべきもの,また教育するとすればその本流に従って教育すべきであ」るとした。彼によれば,「邦楽の上に西洋音楽のようなものを継ぎ木をして,その継ぎ木をしたものから新しい日本の音楽をつくろうとするのは姑息な手段で」あり,家元制度を打破し新しい音楽をつくる邦楽の革新は,邦楽の制度の中で育ってきた者にはできない。さらに,彼は次のように自身の邦楽観を語っている。
「 実は私は邦楽には将来の発展性はないというふうにしか考えられないのです。その意味で邦楽の将来に対しては私はスケプチツクなんです。その理由は,邦楽は長い歴史を持つているには違いないけれども,しかし琴だの三味線だのというものは,徳川の時代になつてから発逹したものでありまして,また徳川の時代に完成したものでございますから,いわば徳川の町人の趣味あるいは感情,あるいは思想といえば言い渦ぎるかもしれませんが,そういうものを表現しているものではあるけれども,もつと古い時分からの,二千年なら二千年の歴史を貫いて日本に流れている日本の民族精神というふうなものを,十分に表現し得ておるものとは,私は考えられないのであります。ことに江戸時代には,音楽は遊里の生活と結びつき,あるいは芝居と結びついて,江戸の町人一般の好尚を代表し,また好尚をしつけて来ているような形になつております。その徳川の町人文化というものは,たいへんいいものもあるし,また一方からいえば,今日の時勢には非常に適しないものをたくさん持つておる。そういうふうな意味で,琴だとか長うただとかいうもののいいものと悪いものをよりわけて,今日の時勢に適するとか,あるいはこれから先文化国家としての日本人の栄養の源になつて,新しい力を奮い起して新しい仕事をしようという,その仕事の燃料を供給することができるような力は,持つていないと私は信じております(衆議院文部委員会 1949)。」 ] (「小泉文夫の日本伝統音楽研究―民族音楽学研究の出発点として―福岡正太稿」)
※ 『漱石と十弟子(津田青楓著)』では、小宮豊隆について、次のような夏目漱石評を紹介している。
「 豊隆は素裸体になれない男だから、知らぬ奴は反感を起すが悪気はないよ。」
E3808DE8A1A8E7B499.jpg)
「俳誌・渋柿(417号/昭和24・1)」表紙
https://dl.ndl.go.jp/pid/6071548/1/1
E3808DE79BAEE6ACA1.jpg)
「俳誌・渋柿(417号/昭和24・1)」目次
https://dl.ndl.go.jp/pid/6071548/1/2
E3808DE5A5A5E4BB98.jpg)
俳誌・渋柿(417号/昭和24・1)」所収「漱石先生三十三回忌(東洋城)」・「奥付など」
https://dl.ndl.go.jp/pid/6071548/1/10
(目次)
[卷頭語 / 秋谷立石山人/p表一
中野から / 小宮蓬里野人/p表二
漱石忌/p1~1
漱石雜詠/p1~1
落木林森(15)夕ぐれ / 東洋城/p2~3
卷頭句 / 東洋城/p4~11
句作問答/p4~8
句作問答(第二部) 九月號、十月號、十一月號/p8~11
お年玉--「空谷無人」に付 / 東洋城/p12~13
下山轉住 / 城/p13~13
例會 松山十一月/p13~13
用語解 / 綠蔭/p13~13
題詠/p14~15
蓑虫 / 十四王/p14~14
冬隣 / 晨悟/p15~15
噫格堂 / 城/p15~15
漱石先生三十三回忌 / 東洋城/p16~16
曲謠 檜垣(上) / 東洋城/p表四
奧付/p表紙の三 ](「国立国会図書館デジタルコレクション」)
東洋城年譜)(『東洋城全句集(中巻)』所収)
昭和十九年(1944) 六十七歳
空襲激しくなり浅間山麓に籠山し、昭和二十四年に至る。『続山を喰ふ』『不衣の句を講ず』を連載。紙の配給減り十六頁の「渋柿」となる。
昭和二十年(1945) 六十八歳
宇和島の邸宅土蔵戦火に会ひ、始祖伝来の家宝を失ふ。信州より焦土の都往復、「渋柿」の刊行続く。『楽木林森』『八月十四日以降』連載。能成文部大臣に親任。
昭和二十一年(1946) 六十九歳
敗亡の後の困難と闘ひ、熱情と至誠を傾注して「渋柿」の毎月発行を指揮す。村上霽月没。
昭和二十二年(1947) 七十歳
「渋柿」四百号に達す。露伴没。
昭和二十三年(1948) 七十一歳
古稀を迎ふ。「古稀遺言」連載。伊予を遍歴。
昭和二十四年(1949) 七十二歳
浅間山麓より帰京。「山籠解脱記」「流浪記」連載。伊予を遍歴指導。伊予小野小学校に、句碑建つ。十二月、森田草平没。
(管見)
一、 「中野から / 小宮蓬里野人/p表二」の末尾に、「六十でも、七十でも、いい事を始めるのに遅いといふ事はない。今日の三十三回忌を機として、ひとつ大にやる事にしようぢやないか。(昭和二三・一二・九)」と記されている。
ちなみに、小宮豊隆は、『漱石二十三回忌』(昭和17年)に、『漱石全集(決定版)』の「小宮豊隆『解説』」一巻に収めた『漱石の芸術(著者/小宮豊隆 著/出版者 岩波書店/出版年月日 昭和17)を刊行している。
https://dl.ndl.go.jp/pid/1078598/1/3
[「漱石の芸術」
目次
『吾輩は猫である』/1
短篇上/26
短篇下/71
『虞美人草』/113
『坑夫』/130
『三四郎』/143
『それから』/161
『門』/178
『彼岸過迄』/195
『行人』/216
『心』/250
『道草』/267
『明暗』/284
小品/323
『文學論』/354
『文學評論』/384
「評論・雜篇」/408
「詩歌俳句及初期の文章」/441
「日記及斷片」/477
「書簡集」/507
「續書簡集」/544
「別冊」/574
談話筆記 本の書き入れ ](「国立国会図書館デジタルコレクション」)
二、「漱石忌/p1~1」「漱石雜詠/p1~1」中の「東洋城」の句は、次のとおりである。
「漱石忌/p1~1」中の「東洋城」の句は、次の二句である。
五(※いつ)とせや山住(※やまずみ)下りて漱石忌 (東洋城)
大(※おお)いなる冬大(※だい)なる詩(※し)や漱石忌 (同)
三、「落木林森(15)夕ぐれ / 東洋城/p2~3」「卷頭句 / 東洋城/p4~11」「句作問答/p4~8」「句作問答(第二部) 九月號、十月號、十一月號/p8~11」「お年玉--「空谷無人」に付 / 東洋城/p12~13」「下山轉住 / 城/p13~13」「例會 松山十一月/p13~13」「用語解 / 綠蔭/p13~13」のこれらは、全て、「東洋城(俳文)」「東洋城選句(選句)」「東洋城(句作問答)」「東洋城(関連句会・近況報告)」ということになる。
四、「下山轉住 / 城/p13~13」には、「下山準備の数十日、昼夜兼行。(中略) 七十老齢這箇患累顧みてよく身命を次ぐと思ふ。(後略)
餅を搗く隣や都第一夜 」と、浅間山麓より帰京しての、その第一夜の感慨を記している。
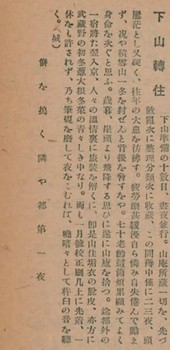
https://dl.ndl.go.jp/pid/6071548/1/8
五、「題詠/p14~15」「蓑虫 / 十四王/p14~14」「冬隣 / 晨悟/p15~15」は、「題詠(秋の空)/水莖春雨選、題詠(蓑虫)/西岡十四王選、題詠(冬隣/小林晨悟選)で、「渋柿」の主要同人が関与しているのは、この「雑詠(題詠)」のページ数にして二頁に満たないということになる。即ち、俳誌「渋柿」というのは、主宰者・松根東洋城が「隅から隅まで」手入れしている個人俳誌という印象すら拭えないというのが、素直な見方であろう。
六 「漱石忌/p1~1」「漱石雜詠/p1~1」そして「漱石先生三十三回忌 / 東洋城/p16~16」も、東洋城の選句、そして、東洋城の「漱石先生三十三回忌」の記述ということになろう。この「漱石先生三十三回忌」の、当日の出席者の名は「鏡子夫人」以外は記述されていない。
(追記その一) 『漱石と十弟子(津田青楓著)』周辺
https://yahan.blog.ss-blog.jp/2024-01-11
(再掲)
E4B880.jpg)
『漱石と十弟子(津田青楓著)』(右上から)「世界文庫・昭和24年版」/「朋文堂新社・昭和42年版」/(右下から)「芸艸堂・昭和49年版」/「芸艸堂(新装版)平成27年版)」
https://twitter.com/unsodo_hanga/status/1355015832892399617/photo/4
『漱石と十弟子(津田青楓著)』は、昭和二十四年(一九四九)一月に世界文庫より出版した。これは、津田青楓は、その前年(昭和二十三)十二月九日の「漱石三十三回忌」については触れていないが、「漱石三十三回忌」に因んでの出版と解しても差し支えなかろう。
この著書の、「漱石十弟子」は、年齢順にすると、次のとおりとなる。
松根東洋城(明治十一=一八七八・二月)・寺田寅彦(明治十一=一八七八・十一月)
森田草平(明治十四年=一八八一・三月)・岩波茂雄(明治十四年=一八八一・八月)
鈴木三重吉(明治十五年=一八八二)
阿部次郎(明治十六年=一八八三・八月)・野上臼川(明治十六年=一八八三・九月)・安倍能成(明治十六年=一八八三・十二月)
小宮豊隆(明治十七年=一八八四)
赤木桁平(明治二十四年=一八九一)
これに、この『漱石と十弟子(津田青楓著)』の折り込みの口絵写真(「漱石山房図/漱石と十弟子(津田青楓画)」には、受付のような人物(百鬼園=内田百閒)が描かれている。この受付のような人物(百鬼園=内田百閒)が、(筆者亀吉=津田青楓)というものもある。

「漱石と十弟子(津田青楓画)」昭和51(1976)年/紙本著色/A4判用(縦30.9cm×横22.0cm×厚さ0.04cm)→B図(「漱石山房記念館蔵」)
https://soseki-museum.jp/user-guide/museum-shop/
これらについては、下記のアドレスなどで先に紹介している。
https://yahan.blog.ss-blog.jp/2023-12-24
ここで、この(百鬼園=内田百閒)と(筆者亀吉=津田青楓)との二人も付け加えて置こう。
津田青楓(明治十三年=一八八〇)
内田百閒(明治二十二年=一八八九)
上記の「漱石十弟子(漱石十二弟子)」のうち、昭和二十三年(一九四八)十二月九日の「漱石三十三回忌」の年以前の物故者は、次のとおりとなる。
寺田寅彦(明治十一=一八七八・十一月~昭和十年=一九三五)
鈴木三重吉(明治十五年=一八八二~昭和十一年=一九三六)
岩波茂雄(明治十四年=一八八一・八月~昭和二十一年=一九四六)
赤木桁平(明治二十四年=一八九一~昭和二十四年=一九四九・十二月十日)

「岩波茂雄と赤木桁平(津田青楓「スケッチ画」)」(『漱石と十弟子(津田青楓著)』)
(再掲)
https://yahan.blog.ss-blog.jp/2024-01-11
[ 岩波氏(※岩波茂雄)の顔も、桁平氏(※赤木桁平)の顔も画家から言ふと捨てがたい珍品なのだ。岩波ときたら禅月大師十六羅漢像の、なかからぬけ出した一人の羅漢像のやうで、画中の白眉なんだ。線の太い大形な羅漢のとなりに、これは又貧弱な色の青白い、当時大学を出たてのほやほやの法学士、赤木桁平君は、そのころのインテリゲンチャの風采を代表してゐるかに見える。
それが隅っこの方で岩波が本を見てゐると桁平君が首をのばして、その本をのぞき込んでゐる。その顔の対照が面白いからこの二人はやめられないのだ。岩波はそのころ女学校の先生をやめて、神田にケチくさい古本屋の店を出してゐた。それが漱石のものを手はじめに出版をぽちぽちやり出し、仲間の学者連のものをちらほら出してゐるうちに、変り種の本屋として老舗となり、こつちの知らぬまに多額納税者とやら貴族院議員とやらになつてゐた。趣味のない男だから岩波本が世間に出るやうになつてから、本の装幀はカチカチになつてしまつた。
桁平は、近江秋江や徳田秋声や田山花袋なぞの自然主義文学が癪だといつて、「遊蕩文学撲滅論」を書いて、文壇をさはがせた。支那戦争が段々英米戦争に発展せんとする段階に突入するころから、どこで学んだのか一ぱしの海軍通になり、「日本の海軍は無敵だよ、イギリスとアメリカほむかうにまはしたつて毅然たるものだよ。」そんな元気で遂に「アメリカ恐るるに足らず」といふ一書を発表して軍国主義のおさき棒を勤めた。終戦後国会議員の責任が追及された時、真先きに辞任してひつ込んでしまつたのは賢明であつた。](『漱石と十弟子(津田青楓著)』)
※ 岩波茂雄の最期は、「1945年(昭和20年)3月27日:貴族院議員。/ 1946年2月11日:文化勲章を受章。/1946年4月25日:逝去。」(「ウィキペディア)と、出版界の雄として栄光の裡に没した。
それに対して、赤木桁平のそれは、「1945年(昭和20年)12月2日、連合国軍最高司令官総司令部は日本政府に対し赤木を逮捕するよう命令(第三次逮捕者59名中の1人)、A級戦犯の容疑で巣鴨拘置所に勾留される。同年12月6日に衆議院議員を辞職。後に病気のため釈放されるも、公職追放となり、そのまま不遇のうちに死去。」(「ウィキペディア」)と、岩波茂雄と好対照の不遇の裡に没している。
そして、その没した日が、「漱石三十三回忌」(「1949年(昭和24年)2月9日」)の翌日(2月10日」)というのは、赤木桁平(池崎忠孝)の最期のメッセージのようにも思われてくる。
(追記その二) 小宮豊隆の「東京音楽学校長就任・辞職」周辺
[昭和二十一年(一九四六) 六十二歳
東京音楽学校長を引き受ける。これは岩波茂雄の奔走によるものである。(以下略)
昭和二十四年(一九四九) 六十五歳
(前略) 六月 東京音楽学校長辞職。 ](『蓬里雨句集』所収「小宮豊隆年譜」)
[第二次世界大戦後の1946年、新校長小宮豊隆の主導で職員の大量罷免を伴う学内改革が行われた。その結果、高折宮次(ピアノ科主任)、遠藤宏(音楽史科主任)、木下保(声楽科主任)、橋本國彦(作曲科主任)、井上武雄(ヴァイオリン科主任)、平井保三(チェロ科主任)、井口基成(ピアノ科)、宇佐美ため(ピアノ科)、平井保喜(作曲科)、永田晴(管科)、細川碧(作曲科)、中村ハマ(ピアノ科)の11名の教授が罷免され、その独裁的なやりかたに抗議する校長不信任運動に加わった豊増昇、永井進の2名のピアノ科教授が退職した。
1949年5月31日、学制改革により新制東京芸術大学が発足すると、東京音楽学校はこれに包括されて音楽学部の前身となり、1952年3月に廃止された。本流の予科・甲種師範科が募集70人と超少数精鋭であったが、全入の選科も東京藝術大学音楽学部に統合したため、音楽学部の募集は172名(1951年以降)となった。なお東京美術学校には選科生はほとんど居なかったため、東京美術学校の予科・師範科の募集人数と東京藝術大学美術学部の募集人数はあまり変化しなかった。
1946年の募集人数 甲種師範科30名、本科40名(予科と統合)。本科内訳 声楽科8名、器楽科(ピアノ・オルガン8名、バイオリン・チェロ・ダブルベース6名、管楽器・打楽器5名)作曲科2名、邦楽科(能楽2名、箏曲4名、長唄4名) ](「ウィキペディア」)
[2.2 東京音楽学校校長の邦楽科廃止論
小宮は,1948 年 5 月 6 日と 7 日の『時事新報』において,東京芸術大学においては,邦楽科を置く代わりに,邦楽研究所を設ける計画であることを公表した。新しい大学では技術と理論が互いに支えあう教育が行われるべきであり,理論的研究や歴史的研究が遅れている邦楽を後進養成のためだけに大学で教育すべきではないというのが彼の考え方だった。そして,研究所の使命は,邦楽の中で真に民族的なものを明らかにし,将来に生かすべきものとそうでないものを明らかにすることであるとし,その研究のために,純粋な邦楽を純粋に保存する必要があるとした。その考え方の基礎には,邦楽は,洋楽に比べて,現在の日本人の心の一部しか動かすことのできない「過去の芸術」,「無縁の芸術」であるという見方があった(小宮 1948)。
さらに,この問題を取り上げた 6 月 29 日の『読売新聞』には,「邦楽は日本の封建時代に育てられ,完成した日本芸術であるから世界の芸術の仲間入りをするためには必ず洋楽の過程を経なければならぬというのが私の信念だ【中略】邦楽をやりたいものは学部を卒業してから研究所に入ればよい」という小宮の談話が掲載された(吉川 2002: 203)。
小宮は,新しい時代の日本音楽は,洋楽を基礎として生み出されるべきであり,邦楽はそこでは役割を果たしえないと考えていたようだ。小宮は,ちょうど邦楽科廃止論争に決着がついた 1949 年に初版が出版された『明治文化史』第 9 巻「音楽演芸」の第一章「明治の音楽・演芸」を執筆している。その中で,「和楽」について,「明治維新の変動からはたいした影響を受けることがなく」,「いわば『文明開化』の世界のものとは,全然趣の違った世界を表現しているのに過ぎない」(小宮 1980: 51)としている。
小宮が理想としたのは,日清・日露戦争を経て「名義上だけでも世界の一等国の仲間入りをし」た「新しい日本にふさわしい」「気宇の雄大な音楽」だった(小宮1980: 54)。東京音楽学校の前身である音楽取調掛は,1879 年,伊沢修二を掛長として発足し,「東西二洋ノ音楽ヲ折衷シテ新曲ヲ作ル事」を方針の 1 つとした。しかし,小宮は「日本の在来の音楽の方面」では,「そういうことが一向顕著でない」と断じ,それは「在来の日本の音楽に携わる人達が,ことごとく個人主義者であり,保守主義者であり,自分の籠っている硬い殻の中から首を出して,世間を眺めようとする意欲を奮い立たせることがなかったせいだったのではなかったか」(小宮 1980: 54–55)と国立民族学博物館研究報告 28巻 2 号268記している。さらに,西洋音楽についての節では,この「和洋折衷」の方針は「虻
蜂とらずのものになり易」く,「音楽取調掛が東京音楽学校となり,東京音楽学校があらゆる方面の外人教師を招聘し,次第に洋楽専門の音楽教育に発展して行ったことは,当然のことだった」(小宮 1980: 61)としている。
『明治文化史』中の文章は,明治時代の音楽について書かれたものだが,小宮は,基本的に邦楽科廃止論争当時の邦楽にも同様の見解をもっていた。東京芸術大学が発足する 1949 年 6 月を目前にして,小宮は 4 月 8 日と 5 月 11 日に衆議院文部委員会に呼び出されている。会議録に記された 5 月 11 日のやりとり(衆議院文部委員会1949)の中で,小宮は,邦楽を「大学の教育の本筋の中からは取除き」「別科としてこれを置きたい」と述べている。
別科とは「一般的な教養は十分ではないけれども技術がすばらしくできるというふうな人の技術を伸ばさせるために」置かれたもので,「今のところ邦楽は技術だけなの」で別科で十分としていた。彼は,研究が進んだ段階で正科に入れるかどうか考えるべきだとも述べているが,本気でそのようにするつもりはなかったようである。「邦楽を認めないとか,あるいは邦楽を低級だというふうに考えてない」とは述べているが,「これから先の音楽は洋楽が本流になるべきもの,また教育するとすればその本流に従って教育すべきであ」るとした。彼によれば,「邦楽の上に西洋音楽のようなものを継ぎ木をして,その継ぎ木をしたものから新しい日本の音楽をつくろうとするのは姑息な手段で」あり,家元制度を打破し新しい音楽をつくる邦楽の革新は,邦楽の制度の中で育ってきた者にはできない。さらに,彼は次のように自身の邦楽観を語っている。
「 実は私は邦楽には将来の発展性はないというふうにしか考えられないのです。その意味で邦楽の将来に対しては私はスケプチツクなんです。その理由は,邦楽は長い歴史を持つているには違いないけれども,しかし琴だの三味線だのというものは,徳川の時代になつてから発逹したものでありまして,また徳川の時代に完成したものでございますから,いわば徳川の町人の趣味あるいは感情,あるいは思想といえば言い渦ぎるかもしれませんが,そういうものを表現しているものではあるけれども,もつと古い時分からの,二千年なら二千年の歴史を貫いて日本に流れている日本の民族精神というふうなものを,十分に表現し得ておるものとは,私は考えられないのであります。ことに江戸時代には,音楽は遊里の生活と結びつき,あるいは芝居と結びついて,江戸の町人一般の好尚を代表し,また好尚をしつけて来ているような形になつております。その徳川の町人文化というものは,たいへんいいものもあるし,また一方からいえば,今日の時勢には非常に適しないものをたくさん持つておる。そういうふうな意味で,琴だとか長うただとかいうもののいいものと悪いものをよりわけて,今日の時勢に適するとか,あるいはこれから先文化国家としての日本人の栄養の源になつて,新しい力を奮い起して新しい仕事をしようという,その仕事の燃料を供給することができるような力は,持つていないと私は信じております(衆議院文部委員会 1949)。」 ] (「小泉文夫の日本伝統音楽研究―民族音楽学研究の出発点として―福岡正太稿」)
※ 『漱石と十弟子(津田青楓著)』では、小宮豊隆について、次のような夏目漱石評を紹介している。
「 豊隆は素裸体になれない男だから、知らぬ奴は反感を起すが悪気はないよ。」




コメント 0